| Tweet | پ@ |
“]چعپFhttp://exodus.exblog.jp/5986025/
پuژذ•غ’،‰ً‘جپv‚ھپuƒoƒ‰ƒoƒ‰ژEگlژ–Œڈپv‚إ‚ ‚é‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ح’P‚ب‚é”نڑg‚إ‚ح‚ب‚¢پD”N‹à‰ïŒv’ •ë‚جˆêچsˆêچs‚ھ”ق‚ç‚ھ‰ك‹ژ‚ة”ئ‚µ‚½”ئچك‚ج‹Lک^‚إ‚ ‚èپC”ئ‰ب’ ‚ئ‚إ‚àŒؤ‚ش‚ׂ«‚à‚ج‚إ‚ ‚éپD“ءژê–@گl‚ة’چ‚¬چ‚ـ‚ꂽچàگ“ٹ—Zژ‘‚جŒ´ژ‘‚ح‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا—Xگ‚ب‚¢‚µ”N‹àژ‘‹à‚إ‚ ‚èپC”ق‚ç‚ھگH‚¢ژU‚ç‚©‚µ‚½‰ƒ‚جŒمپCکA‘±پE‹“گپE‹ٹپEƒoƒ‰ƒoƒ‰ژEگlژ–Œڈ‚ج‹¥چsŒ»ڈê‚ئ‚µ‚ؤ‚جƒڈƒ“ƒrƒV‘qŒة‚ً••ˆَ‚·‚é‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ح‚ ‚éˆس–،‚إ“–‘R‚إ‚ ‚éپDچ،“ْ‰ن‚ھچ‘‰ï‚جژQ‹c‰@–{‰ï‹cڈê‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚±‚جڈWچ‡“I”ئچك‚ھٹ®‘S”ئچك‚ئ‚µ‚ؤ‰B•ءٹ®—¹‚µپC‚Q‚O‚O’›‰~”N‹àژ‘‹à‚حچ‘چغƒ}ƒtƒBƒA‚جٹاٹچ‚ةˆع‚éپ¦پD پ¦‚±‚ê‚ـ‚إ‚T”N‚ةˆê“xچ‘‰ï‚ة‚و‚錩’¼‚µ‚ًچs‚¤‚±‚ئ‚ھ–@“I‚ة‹`–±•t‚¯‚ç‚ê‚ؤ‚«‚½”N‹àگ§“x‚ح‚Q‚O‚O‚S”N‚جژ©ŒِگŒ ‚ة‚و‚é”N‹à‰üٹv‚إچ‘‰ï‚ج’èٹْ“I‚بƒ`ƒFƒbƒN‚ب‚µ‚ةچsگ‚جœ“ˆس‚إ‰^‰c‚إ‚«‚邱‚ئ‚ة‚ب‚ء‚½پD”ق‚ç‚ھپw‚P‚O‚O”NˆہگS”N‹àپx‚ئŒؤ‚ٌ‚إ‚¢‚é‚ج‚ح‚±‚ج‚±‚ئ‚ًˆس–،‚·‚éپDپiگفŒv‚إ‚ح‚P‚O‚O”NŒم‚ةگد—§‹à‚ھ‹َ‚ء‚غ‚ة‚ب‚邱‚ئ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éپ\‚P”N•ھ‚ج‹‹•t‹à‘ٹ“–ٹz‚ًژc‚µ‚ؤپjچإŒم‚جˆêچs‚حپu–¯‘°ƒ}ƒtƒBƒA‚©‚çچ‘چغƒ}ƒtƒBƒA‚جٹاٹچ‚ةˆع‚éپv‚ئŒ¾‚¦‚خ‚à‚¤ڈ‚µ‚ح‚ء‚«‚è‚·‚邾‚낤پD‚Q‚O‚O’›‰~‚ئ‚¢‚¤ژ‘‹à‹K–ح‚حپi—X’™ژ‘‹à‚ًڈœ‚¯‚خپjگ¢ٹE‚ة—ق‚ًŒ©‚ب‚¢‚à‚ج‚إ‚ ‚éپDˆ×‘ض‚ً‘€چى‚·‚邱‚ئ‚àپC‘¼چ‘Œoچد‚ة‰î“ü‚·‚邱‚ئ‚àپCگي‘ˆ‚ً‹N‚±‚·‚±‚ئ‚·‚ç‰آ”\‚¾پD‚»‚ê‚ً–¯‰c‰»‚·‚é‚ئ‚¢‚¤پI ‚Q‚W“ْ•t‚¯‚«‚ء‚±‚جƒuƒچƒO‚إ‚ح‹»–،گ[‚¢ژ–ژہ‚ھژw“E‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپD–ى“}‹cˆُ‚½‚؟‚ھژRگ[‚¢‰œ•گ‘ ‚جƒڈƒ“ƒrƒV‘qŒة‚ـ‚إژ‹ژ@’c‚ً‘g‚ٌ‚إ’n“¹‚ب’²چ¸ٹˆ“®‚ً‘±‚¯‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚«پCˆê•û‚جˆہ”{ژٌ‘ٹ‚ح•ھچڈ‚ف‚جƒ^ƒCƒ€ƒeپ[ƒuƒ‹‚ًٹ„‚¢‚ؤٹ¯“@‚ة“cŒ´‘چˆêکN‚ًŒؤ‚ر‚آ‚¯’‹گH‚ًژو‚ء‚ؤ‚¢‚½پI‚±‚ê‚©‚çˆہ”{ƒqƒbƒgƒ‰پ[‚جگé“`‘ٹƒQƒbƒyƒ‹ƒX‚ھ‘¼‚إ‚à‚ب‚¢“cŒ´‘چˆêکN‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ھ”»‚éپDˆہ”{“àٹt‚حچ‘Œ ‚جچإچ‚‹@ٹض‚إ‚ ‚éچ‘‰ï‚ة‚ج‚ف‹–‚³‚ꂽچ‘گ’²چ¸Œ ‚ةٹî‚أ‚«–¯ژه“}پEژذ–¯“}پE‹¤ژY“}‚جٹe“}‹cˆُ‚ç‚ھٹضŒWڈب’،‚ة‹پ‚ك‚ؤ‚¢‚é’²چ¸ژ‘—؟‚ج’ٌڈo‚ً‹‘‚ف‘±‚¯‚ؤ‚¢‚éپD‚±‚ê‚ھچ‘–¯‚ة–ع‰B‚µ‚µ‚ؤژ–ژہ‚ً••ˆَ‚µƒ}ƒXƒvƒچƒpƒKƒ“ƒ_‚إ‚»‚ê‚ة‘م‚¦‚é‚ئ‚¢‚¤ˆہ”{‘S‘جژه‹`گژ،‚جژè–@‚إ‚ ‚éپD Commented by exod-US at 2007-06-23 22:50 x چ‘–¯”N‹à‚ئŒْگ¶”N‹à‚ة‚حپu–@‚ج‰؛‚إ‚ج•½“™پv‚ً‚©‚¯—£‚ꂽژہ‘ش‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·‚ھپC‚³‚ç‚ة’´—D‹ِ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ھŒِ–±ˆُ‚ج“ü‚鋤چد”N‹à‚إ‚·پD‚ئ‚ç‚؟‚ل‚ٌ‚ح‚à‚؟‚ë‚ٌ‚²‘¶’m‚©‚ئژv‚¢‚ـ‚·‚ھپC‹¤چد”N‹à‰ء“üژز‚حپuٹm’è‹’ڈo”N‹àپv‚ة‰ء“ü‚·‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚¹‚ٌپD‚±‚ê‚حپuٹm’è‹’ڈo”N‹àپv‚ھٹ댯‚بƒCƒJƒTƒ}”ژ‘إ‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ًگ•{‚ھ’m‚ء‚ؤ‚¢‚ؤپCگ•{‚جڈ]‹ئˆُپi‚ج”N‹àگ§“xپj‚ً‚»‚جٹ댯‚ة‚³‚炳‚ب‚¢‚½‚ك‚ج–hŒى‘[’u‚إ‚·پDژذ•غ’،‰ً‘ج‚جگ^‚ج‘_‚¢پi‚جˆê‚آپj‚حŒِ“I”N‹àگ§“x‚ً’ׂµ‚ؤٹOژ‘‚ج‹پ‚ك‚éپuٹm’è‹’ڈo”N‹àپv‚ةژ‘‹à‚ًˆع“®‚·‚邱‚ئ‚إ‚·‚ثپD پ„”N‹à•s•¥‚¢‚ھ‚S‚Oپ“ˆبڈم‹ڈ‚ؤپA‚»‚ٌ‚بڈَ‹µ‚ج’†‚إ‚ـ‚ئ‚à‚ة”N‹à‚ھ‹@”\‚·‚é‚ئژv‚ي‚ê‚ـ‚·‚©پB گ§“x“I‚ة‚حٹ®‘S‚ة”j’]‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپCŒْگ¶”N‹àپi‹¤چد”N‹à‚ًٹـ‚قپj‚¾‚¯‚ب‚çپC‹‹•t‚ًˆّ‚«‰؛‚°‚邱‚ئ‚إ‚ـ‚¾‘خ‰‰آ”\‚إ‚·پDچ‘–¯”N‹àگ¢‘ر‚ھ“Œv“I‚ة‚ا‚ج‚‚ç‚¢‚©”cˆ¬‚µ‚ؤ‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپC‰¼‚ةچ‘–¯‚ج1/4‚¾‚ئ‚·‚é‚ئپCŒ»گ•{‚حٹ®‘S‚ة‚±‚ج1/4‚جچ‘–¯‚ًپuٹü–¯پv‚µ‚و‚¤‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پD‚»‚جژَ‚¯ژM‚ة‚ب‚é‚ج‚حپCپu–¯ژهŒىŒ›کA—§گ•{پv‚µ‚©‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپDپ¨Œ³‹Lژ–‚جƒRƒپƒ“ƒg—“ژQڈئ Commented by exod-US at 2007-06-28 05:03 x ‚Q‚O‚O‚S”N‚ةگ•{پE—^“}‚ح”N‹à‰üٹv‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ً‚â‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپC‚±‚جژ“_‚إ”N‹à‰ïŒv‚ح‚U‚O‚Oپ`‚V‚O‚O’›‰~‚ظ‚ا‚جپiڈ«—ˆپjچآ–±’´‰كپiŒِژ®گ”ژڑ‚إ‚ح‚S‚Q‚O’›‰~پj‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پD‚±‚ê‚ة‘خ‚µ‚ؤگ•{‚ح‡@ ‹‹•tگ…ڈ€‚جˆّ‚«‰؛‚°پC‡A”[•t‹àٹz‚جˆّ‚«ڈم‚°پC‡Bگإ•‰’S—¦‚ج‘‰ءپC‚ب‚ا‚إ‚ظ‚عچآ–±’´‰كƒ[ƒچ‚جگ…ڈ€‚ةڈCگ³‚µ‚ـ‚µ‚½پD‚µ‚©‚µپC‚±‚ê‚ة‚ح‘ه‚«‚ب—ژ‚ئ‚µŒٹ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پD ‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حپCگ”ژڑ‚إ‚حٹm‚©‚ةƒoƒ‰ƒ“ƒX‚ھژو‚ê‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½‚ج‚إ‚·‚ھپCژہچغ‚ح‚ ‚é”N‘م‚©‚ç‹‹•tٹz‚ئژَ‹‹ٹz‚ھ‹t“]‚·‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ھ‹N‚«‚é‚ئ‚¢‚¤ژdٹ|‚¯‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إ‚·پD‚±‚ê‚ة‚حگlŒû‘‰ء—¦‚ئ‚©‚¢‚ë‚¢‚ë‚بƒpƒ‰ƒپپ[ƒ^‚ھٹضŒW‚µ‚ـ‚·‚ھپCگ•{‚ج—\‘ھ‚ح‚آ‚ث‚ة‚à‚ء‚ئ‚àٹأ‚¢گ”ژڑ‚ًژg‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پD‚¢‚¸‚ê‚ة‚µ‚ؤ‚àپCŒ»چف‚جگفŒv‚إ‚ح’x‚‚ئ‚à‚P‚X‚U‚T”Nگ¶‚ـ‚ê‚جگ¢‘م‚©‚çŒم‚ح‚©‚¯‚½‹àٹz‚و‚èژَ‚¯ژو‚é‹àٹz‚ج•û‚ھڈ‚ب‚‚ب‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ھ”گ¶‚µ‚ـ‚·پD‚±‚ê‚ح‚à‚¤ƒ_ƒپ‚إ‚·‚ثپDٹm’è‚إ‚·پD ‚µ‚©‚à‚±‚ê‚حپC’Nˆêگl’E—ژ‚µ‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤‘z’èڈم‚ج‚±‚ئ‚إ‚·‚©‚çپCپiƒpپ[ƒgƒ^ƒCƒ}پE”ٌگ³‹KŒظ—p‚ھ‘‰ء‚µ‚ؤ‚¢‚錻ڈَ‚إ‚حپjژہچغ‚ة‚ح‚à‚ء‚ئ‚à‚ء‚ئڈًŒڈ‚حŒµ‚µ‚‚ب‚è‚ـ‚·پDŒْگ¶”N‹à‚ج“K—p”حˆحٹO‚جژ–‹ئڈٹ‚ ‚é‚¢‚حپC“K—p”حˆح“à‚إ‚ ‚é‚ج‚ة”N‹à‚ً‘g‚ك‚ب‚¢ژ–‹ئڈٹ‚ح‘‰ء‚·‚éˆê•û‚إ‚·پD‚±‚ٌ‚ب‚ج‚ة“ü‚éگl‚ھ‚¢‚é‚ي‚¯‚ھ‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپD‘چ’E—ژ‚µ‚ـ‚·پD‚±‚ٌ‚ب‚±‚ئ‚ح‚Q‚O‚O‚S”N‚ج”N‹à‰üٹvژ‚©‚ç’m‚ê“n‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إ‚·‚ھپCگ•{—^“}‚ح—ل‚ة‚و‚ء‚ؤ‹ˆّ‚ة‹چsچجŒˆ‚إ“ث”j‚µ‚½‚ئ‚¢‚¤‚ي‚¯‚إ‚·پD‚؟‚ب‚ف‚ةژ„ژ©گg‚ح‚±‚جژٹْ‚ح‚ـ‚ء‚½‚پuگژ،پv‚ًŒ©‚ؤ‚ـ‚¹‚ٌ‚إ‚µ‚½‚ج‚إ‰ل’ ‚جٹO‚إ‚·پDژ„‚ھگژ،‚ًƒ`ƒFƒbƒN‚µژn‚ك‚½‚ج‚ح‚Q‚O‚O‚T”N‚ج—Xگ‰ًژU‚©‚ç‚إ‚·‚©‚çپDپDپD ژ‘—؟پFŒْگ¶”N‹à‚ًƒoƒ‰ƒ“ƒXƒVپ[ƒg‚إژa‚éپiچ‚ژRŒ›”Vپj ‚¢‚âپC‚ظ‚ٌ‚ئ‚ةچ‘‰ئ‚ًٹغ‚²‚ئ–¯‰c‰»‚µ‚½•û‚ھ‚ـ‚µ‚ب‚ٌ‚¶‚ل‚ب‚¢‚©‚ئژv‚¦‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پDچcچ‘‰½گç”N‚©’m‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپC–¾ژ،ˆغگV‚ج‘O‚و‚è‚à‚ء‚ئˆ«‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پD چً“ْ‚ج‹Lژ–‚إڈ‘‚«‚ـ‚µ‚½‚ھپCƒچƒVƒAٹv–½Œمƒ\کA–M‚ھ‘S“y‹گ§ژû—eڈٹ‰»‚µ‚ؤ‚ن‚•ûŒü‚ةگi‚ٌ‚إ‚ن‚‚ج‚حپuگH—ئ“ئچظپپچ’•¨ٹ„“–’¥”پv‚ة‘خ‚·‚éƒTƒ{ƒ^پ[ƒWƒ…‚ئ‚»‚ê‚ة‘خ‚·‚é’eˆ³پEژو’÷‚è‚©‚çژn‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پDŒ»چف‚جگ•{‚جگچô‚ًŒ©‚é‚ئ‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‚»‚جچ⓹‚ً“]‚°—ژ‚؟‚ؤچs‚ء‚ؤ‚é‚و‚¤‚ةŒ©‚¦‚ـ‚·پD‰½‚ئ‚©‚µ‚ب‚¢‚ئ–{“–‚ةƒ_ƒپ‚إ‚·‚ثپD “c’†’¼‹B‚ئ‚¢‚¤گl‚ھ‚¢‚ـ‚·پDٹç‚حŒ©ٹo‚¦‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·‚ھپC•پ’i‚ا‚ٌ‚ب”Œ¾‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚©•ھ‚©‚è‚ـ‚¹‚ٌپD‚±‚جگl‚ھ—ژ–’·‚ً‚â‚ء‚ؤ‚¢‚é‚Q‚Pگ¢‹IگچôŒ¤‹†ڈٹ‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پDŒo’cکA‚ھگف—§‚µ‚½Œِ‹¤گچô‚جƒVƒ“ƒNƒ^ƒ“ƒN‚إ‚·پD‚±‚±‚ھ‚P‚X‚X‚X”N‚ةپuپ`“ْ–{Œoچدچؤگ¶‚جƒJپ[ƒh‚ئ‚µ‚ؤ‚ج”N‹à‰üٹvپ`پv‚ئ‚¢‚¤’ٌŒ¾‚ًڈ‘‚¢‚ؤ‚¢‚ـ‚·پDٹî–{“I‚ة‚حپuŒْگ¶”N‹à–¯‰c‰»پv‚ًژه’£‚·‚é‚à‚ج‚إ‘½•ھŒ»چف‚جژذ•غ’،‰ً‘ج‚ج“®‚«‚ب‚ا‚جƒxپ[ƒXƒ‰ƒCƒ“‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئژv‚¤‚ج‚إ‚·‚ھپC‚±‚ج’†‚إ”N‹à‰ïŒv‚ًˆê“xƒٹƒZƒbƒg‚·‚邽‚ك‚جژèڈ‡‚ً’ٌˆؤ‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پD‚ـ‚¾‚و‚“ا‚ٌ‚إ‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپC‚¢‚¸‚ê‚ة‚µ‚ؤ‚à”N‹à‰ïŒv‚ًˆê“xٹ®‘S‚ة”j’]ڈˆ—‚³‚¹‚ب‚¢‚ئƒ_ƒپ‚¾‚ئژv‚¢‚ـ‚·پD ‚±‚ج—¼ژزپiچ‚ژRŒ›”VپC‚Q‚Pگ¢‹IگچôŒ¤‹†ڈٹپj‚ة‹¤’ت‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚حپC”N‹à‰ïŒvچؤŒڑ‚جŒ´ژ‘‚ئ‚µ‚ؤ‰i‹vچ‘چآ‚ج”چsپi‚P‚O‚Oپ`‚Q‚O‚O’›‰~پj‚ً’ٌˆؤ‚µ‚ؤ‚¢‚é“_‚إ‚·پD‰i‹vچ‘چآ‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حڈٹزٹْŒہ‚ج‚ب‚¢چ‘چآ‚إ‚·‚©‚çپC–{ژ؟“I‚ةپuٹ”ژ®پv‚ئ“¯‚¶‚إ‚·پiٹ”ژ®‚حڈٹزٹْŒہ‚ج‚ب‚¢•د“®—ک‘§ژذچآپjپD‚آ‚ـ‚èپC‚±‚ꂱ‚»‹†‹ة‚جپuچ‘‰ئ‚ج–¯‰c‰»پv‚ئŒؤ‚ٌ‚إچ·‚µژx‚¦‚ج‚ب‚¢‚à‚ج‚إ‚·پD‚Q‚آڈم‚جƒpƒ‰ƒOƒ‰ƒt‚إ‚حڈç’k‚ةپuچ‘‰ئ‚ج–¯‰c‰»پv‚ئڈ‘‚¢‚½‚ج‚إ‚·‚ھپCکA’†‚ح‚·‚إ‚ةپu–{‹Cپv‚إ‚»‚جژ–‹ئ‚ةژو‚èٹ|‚©‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پD‹†‹ة‚جƒLƒƒƒsƒ^ƒٹƒYƒ€‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌپD ژ„‚ج‘خˆؤ‚حپuگ•{‰ف•¼‚ج”چsپv‚إ‚·پDŒ»چs–@گ§‚إ‚à‰آ”\‚¾‚ئ‚حژv‚¢‚ـ‚·‚ھپCژ„‚ح‚ق‚µ‚ë“ْ–{‹âچs‚ًچ‘‰c‰»‚µ‚½•û‚ھ‚و‚¢‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئچl‚¦‚ؤ‚¢‚ـ‚·پDژ„‚جƒCƒپپ[ƒW‚إ‚حگ•{‰ف•¼پiژ©—R‰ف•¼‚ئŒؤ‚ٌ‚إ‚¢‚ـ‚·‚ھپj‚حچ‘–¯Œoچد‹¤“¯‘ج‚ً’ت—p’nˆو‚ئ‚·‚é’nˆو’ت‰ف‚إ‚·پD ‚à‚¤ˆê‚آپCپuڈء”ïگإپv‚ة‘م‚ي‚é‘مˆؤ‚ئ‚µ‚ؤپuژوˆّگإ(transaction tax)پv‚ً’ٌˆؤ‚µ‚ـ‚·پDڈء”ïگإ‚حچإڈI“I‚ة‚حچإڈIڈء”ïژز‚ھ‘Sٹz•‰’S‚·‚é‰غگإ•ûژ®‚إ‚·‚ھپCژوˆّگإ‚ح‰ف•¼“Iژوˆّ‚ج‘S’iٹK‚ةپu’´’ل—¦‚©‚آ’è—¦پv‚ج•ٹ‰غ‚ً‰غ‚·‚é‚à‚ج‚إ‚·پD“––ت‚ح‚½‚ئ‚¦‚خپC‹âچsŒûچہٹش‚جژوˆّ‚ةŒہ’肵‚ؤ‚à‚و‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·‚ھپC—v‚ح‚¨‹à‚جˆع“®پiŒˆچدپj‚ة‘خ‚µ‚ؤ‰غگإ‚·‚é•ûژ®پC‚آ‚ـ‚èˆêژي‚ج‰ف•¼‚جژg—pژèگ”—؟‚ج‚و‚¤‚ب‚à‚ج‚إ‚·پD‘S‹âƒlƒbƒg‚ً’ت‰ك‚·‚éژ‘‹à‚ح‚P“ْ‚R‚O‚O’›‰~‚‚ç‚¢‚ح‚ ‚è‚ـ‚·‚©‚çپC‰c‹ئ“ْ‚ً”N‚Q‚O‚O“ْ‚ئ‚µ‚ؤ‚Pپ“‚ج‰غگإ‚إ‚U‚O‚O’›‰~‚à‚جگإژû‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پD‚Pپ“‚إ‚ح‘ه‚«‚·‚¬‚é‚ئ‚µ‚ؤ‚à‚OپD‚Pپ“‚إ‚à‚U‚O’›‰~‚إپC‚ظ‚عŒ»چف‚جچخ“ü‹K–ح‚ة•C“G‚µ‚ـ‚·پD‚±‚ج•ûژ®‚ب‚çˆê“xƒVƒXƒeƒ€‚ً—§‚؟ڈم‚°‚ؤ‚µ‚ـ‚¦‚خŒم‚حٹ®‘S‚ةƒIپ[ƒgƒپپ[ƒVƒ‡ƒ“‚إ“®‚«‚ـ‚·‚©‚çپCچ‘گإ’،‚ھ‚ـ‚邲‚ئ•s—v‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پIگ•{‰ف•¼پEژوˆّگإ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپC‚±‚؟‚ç‚ةژ„‚جڈ¬ک_•¶(2003”N)‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پD “àٹt‚ح–¯ژه“}‹cˆُ‚ھ—v‹پ‚·‚éگ”ژڑ‚ً‚·‚ׂؤ‰B‚µ‚±‚ٌ‚إƒ{پ[ƒiƒX•شڈم‚‚ç‚¢‚إ‚¨’ƒ‚ً‘÷‚»‚¤‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپC‚»‚ٌ‚بڈ¬چ×چH‚ھ’ت—p‚·‚éژٹْ‚ح‚ئ‚ء‚‚ة‰ك‚¬‚ـ‚µ‚½پD‚T‚O‚O‚O–œŒڈ‚ج•s–¾ƒfپ[ƒ^‚ب‚ا‚ج–â‘è‚ًƒNƒٹƒA‚·‚邱‚ئ‚ح”N‹à‰ïŒv‚ًگ´ژZ‚·‚é‘O’iٹK‚إ•ذ•t‚¯‚ب‚‚ؤ‚ح‚ب‚ç‚ب‚¢چى‹ئ‚إ‚·‚ھپC‚ـ‚¸‚»‚ê‚ة‘S—ح‚إژو‚è‘g‚ق•K—v‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پD‚ا‚ج‚‚ç‚¢‚جژٹش‚ھ‚©‚©‚é‚©•ھ‚©‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپC–{‹C‚إ‚â‚ê‚خ‚P”N‚إ‚ك‚ا‚ح•t‚‚ئژv‚¢‚ـ‚·پD‚µ‚©‚µپCچإڈI“I‚ة‚ح“چ‡‚إ‚«‚ب‚¢ƒfپ[ƒ^پC‚³‚ç‚ة‚»‚à‚»‚à–¢“ü—ح‚إ‘ن’ ‚·‚ç•´ژ¸‚µ‚ؤ‚¢‚éƒfپ[ƒ^‚ھژc‚è‚ـ‚·پDŒْگ¶”N‹à‚جڈêچ‡پC‚ ‚é‰ïژذ‚ة‚ ‚éژٹْ‹خ–±‚µ‚ؤ‚¢‚ê‚خŒ´‘¥‚ئ‚µ‚ؤ”[•t‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ئ‚ف‚ب‚·‚ئ‚¢‚¤ƒ‹پ[ƒ‹‚ًگف‚¯‚ê‚خ‚ ‚é’ِ“xƒJƒoپ[‚·‚邱‚ئ‚ح‚إ‚«‚é‚ئژv‚¢‚ـ‚·‚ھپC‚¢‚¸‚ê‚ة‚µ‚ؤ‚à‚ا‚±‚©‚ةڈء‚¦‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½ƒfپ[ƒ^‚ً‰ٌ•œ‚·‚邱‚ئ‚ح‚إ‚«‚ـ‚¹‚ٌپD‚µ‚©‚µپCڈ‚ب‚‚ئ‚à‚»‚ج‘چٹz‚جگ„Œv’l‚ًŒvژZ‚·‚邱‚ئ‚ح‚إ‚«‚ـ‚·پD ‚±‚جڈء‚¦‚½”N‹à‚ة‚ح‚Qژي—ق‚ ‚è‚ـ‚·پD‹àٹz‚حچ‘Œة‚ة“ü‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ھ”[•tژز‚ً“ء’è‚إ‚«‚ب‚¢‚à‚ج‚ئپC”[•t‚³‚ꂽ‚¨‹àژ©‘ج‚ھ‚ا‚±‚©‚ةڈء‚¦‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½‚à‚جپiƒlƒRƒoƒo‚³‚ꂽ‚à‚جپj‚إ‚·پD‚¢‚¸‚ê‚ة‚µ‚ؤ‚àپCپiچإڈI’iٹK‚ة‚ب‚è‚ـ‚·‚ھپj‚±‚ê‚ç‚جژ–Œج‹àٹz‚جگ„Œv’l‚ًٹm’è‚·‚é•K—v‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پD گس”C–â‘è‚ح‚»‚جژ“_‚إ”گ¶‚µ‚ـ‚·پD‹àٹz‚ةŒ©چ‡‚ء‚½‚¾‚¯‚جگس”C‚جژو‚è•û‚ًŒ©‚¹‚ؤ‚à‚炤‚µ‚©‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپDŒ»چف‚ج“àٹt‚ھ‚â‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚حپC‚»‚ج‘چٹz‚ةƒtƒ^‚ً‚µ‚ؤپi‰كڈ¬‚ةŒ©‚¹‚©‚¯‚ب‚ھ‚çپjپi”ق‚ç‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚حپjڈ¬ٹz‚جڈـ—^‚ًژ«‘ق‚·‚éƒtƒٹ‚إ‚²‚ـ‚©‚»‚¤‚ئ‚¢‚¤‚à‚ج‚إ‚·پD‚à‚؟‚ë‚ٌ‰آ”\‚ب‚ç‚خŒYژ–‘i’ا‚³‚ê‚ب‚‚ؤ‚ح‚ب‚ç‚ب‚¢‚µپC‚ـ‚½‚»‚ج‚و‚¤‚بƒPپ[ƒX‚àڈo‚ؤ‚‚é‚ئژv‚¢‚ـ‚·پD ژذ•غ’،‚ً‚U‚آ‚ةگط‚èچڈ‚ٌ‚إ‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ح‚ـ‚ء‚½‚ƒoƒ‰ƒoƒ‰ژEگlژ–Œڈ‚ج”ئگl‚ھچڈ‚ٌ‚¾ژ€‘ج‚ً‚ ‚؟‚±‚؟‚ة•ھژU‚µ‚ؤژج‚ؤ‚é‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ة‚»‚ء‚‚è‚إ‹¹•³ˆ«‚‚ب‚è‚ـ‚·‚ھپC–¯‰c‰»‚جٹل–ع‚حŒ‹‹ا‚ح‰½•S’›‰~‚ئ‚¢‚¤”N‹àژ‘‹à‚ج‰^—pŒ ‚ج–â‘èپi’N‚ھ‰^—p‚·‚é‚©پHپj‚إ‚·پDژ„‚ح‰؛ژè‚ة–¯‰c‰»‚·‚é‚و‚èپC‹¤چد”N‹à‘gچ‡‚ة‚»‚ء‚‚èˆعٹا‚·‚é‚ج‚ھˆê”شٹm‚©‚¾‚ئژv‚¢‚ـ‚·پD‚±‚±‚إ‚حپi‘¼‚ج‹@چ\‚إ‚ح‚ظ‚ئ‚ٌ‚اژ¸”s‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپj”N‹àگد—§‹à‚ًژہ‚ةŒ«–¾‚ةپi‰½ڈ\”N‚àپj‰^—p‚µ‚ؤ‚¨‹à‚ًپiŒv‰و’ت‚èپj‘‚₵‚ؤ‚¢‚éژہگر‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پD“أƒQƒ^ƒJ‚جƒGƒT‚ةŒà‚ê‚ؤ‚â‚é•K—v‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپD پuژذ•غ’،‰ً‘جپv‚حپuƒoƒ‰ƒoƒ‰ژEگlژ–Œڈپv‚إ‚ ‚é‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ح”نڑg‚ئ‚¢‚¤‚و‚èپC‚à‚ء‚ئگ^ژہ‚ة‹ك‚¢‚à‚ج‚إ‚·پD”N‹à‰ïŒv’ •ë‚جˆêچsˆêچs‚ھ”ق‚ç‚ھ‰ك‹ژ‚ة”ئ‚µ‚½”ئچك‚ج‹Lک^‚إ‚ ‚èپC”ئ‰ب’ ‚ئ‚إ‚àŒؤ‚ش‚ׂ«‚à‚ج‚إ‚·پD—Xگژ‘‹à‚جƒ}ƒlپ[ƒچƒ“ƒ_ƒٹƒ“ƒO‚حٹ®—¹‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپC“ءژê–@گl‚ة’چ‚¬چ‚ـ‚ꂽچàگ“ٹ—Zژ‘‚جŒ´ژ‘‚ح‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا—Xگ‚ب‚¢‚µ”N‹àژ‘‹à‚إ‚·پD”ق‚ç‚ھگH‚¢ژU‚ç‚©‚µ‚½‰ƒ‚جŒمپCکA‘±‹“گ‹ٹƒoƒ‰ƒoƒ‰ژEگlژ–Œڈ‚ج‹¥چsŒ»ڈê‚ئ‚µ‚ؤ‚جƒڈƒ“ƒrƒV‘qŒة‚ً••ˆَ‚·‚é‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ح‚ ‚éˆس–،‚إ“–‘R‚إ‚·پDژrٹپCگl“÷ڑnگH‚جگ¢ٹE‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚àŒ¾‚¢‰ك‚¬‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپD ‚آ‚¢‚ة‹چsچجŒˆپBŒْکJˆدگR‹c‚إŒ©‚¦‚éپu”N‹à‚جˆإپv پi•غچâ“Wگl‚ج‚ا‚±‚ا‚±“ْ‹LپC2007-06-28پj
‚ئ‚ç‚؟‚ل‚ٌپFژ‘—؟‚ ‚è‚ھ‚ئ‚¤‚²‚´‚¢‚ـ‚·پDژŒn—ٌ‚إ’²‚ׂ½‚¢‚ئ‚«ˆê”شٹmژہ‚ب‚ج‚حگ°“V‚ئ‚ç“ْکa‚ًƒ`ƒFƒbƒN‚·‚邱‚ئ‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ھ’è”ش‚ة‚ب‚ء‚½‚ف‚½‚¢‚إ‚·‚ثپD
‚ئ‚ç‚؟‚ل‚ٌپF‚¨‚ح‚و‚¤‚²‚´‚¢‚ـ‚·پD‘O‚ة‚ئ‚ç‚؟‚ل‚ٌ‚©‚çپCپu”N‹à•s•¥‚¢‚ھ‚S‚Oپ“ˆبڈم‹ڈ‚ؤپA‚»‚ٌ‚بڈَ‹µ‚ج’†‚إ‚ـ‚ئ‚à‚ة”N‹à‚ھ‹@”\‚·‚é‚ئژv‚ي‚ê‚ـ‚·‚©پBپv‚ئگq‚ث‚ç‚ê‚ؤپCپuگ§“x“I‚ة‚حٹ®‘S‚ة”j’]‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپCŒْگ¶”N‹àپi‹¤چد”N‹à‚ًٹـ‚قپj‚¾‚¯‚ب‚çپC‹‹•t‚ًˆّ‚«‰؛‚°‚邱‚ئ‚إ‚ـ‚¾‘خ‰‰آ”\‚إ‚·پDپv‚ئ“ڑ‚¦‚ؤ‚ـ‚·‚ھپC“P‰ٌ‚µ‚ـ‚·پDپuŒْگ¶”N‹à‚ح‹‹•t‚جˆّ‚«‰؛‚°‚إ‘خ‰‰آ”\پv‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حپCژ„‚ھچl‚¦‚½‚ج‚إ‚ح‚ب‚‚ؤ”نٹr“Iچإ‹ك‚جƒjƒ…پ[ƒX‚إ“ا‚ٌ‚¾‚à‚ج‚إ‚·پD‚؟‚ه‚ء‚ئƒ\پ[ƒX‚حچ،Œ©“–‚½‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپCگس”CپiŒ ˆذپj‚ ‚é‹ط‚©‚ç‚جڈî•ٌ‚إ‚·پDٹm‚©‚ة‚±‚ê‚ح‚ ‚éˆس–،‚إƒEƒ\‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپD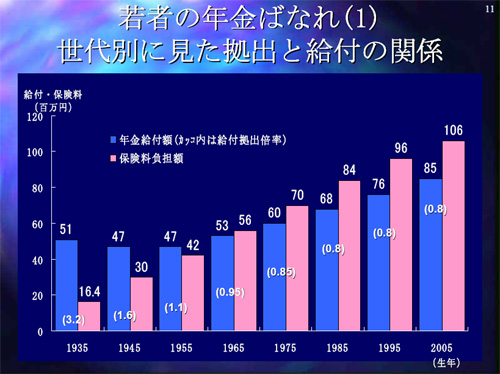
”N‹àƒfپ[ƒ^‚ًƒCƒ“ƒyƒC‚µ‘±‚¯‚éƒAƒx“àٹt پi‚«‚ء‚±‚جƒuƒچƒOپC2007-06-28پj
”N‹àڈî•ٌ‚ح–ِ‘ٍŒْکJ‘هگb‚ة‚و‚ء‚ؤ‰B•ء‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é پi‚ف‚©‚ٌ‚¤‚ـ‚¢پC2007-06-27پj
ˆہ”{‚ح‚¤‚»‚آ‚«پBژذ•غ’،‚ئŒ‹‘ُ‚µ‰B•ء‚ح‚©‚é پiYahoo!Œfژ¦”آپC2007-06-27پj
ژ©–¯“}‚حچ‘‰ئŒِ–±ˆُ–@‰üگ³ˆؤ‚ًژQ‰@“àٹtˆدˆُ‰ïپi“،Œ´گ³ژiˆدˆُ’·پپ–¯ژه“}پj‚إ‚جچجŒˆ‚ًڈب—ھپA‚Q‚X“ْ‚ج–{‰ï‹c‚إ’¼گعچجŒˆ‚ةژ‚؟چ‚قپu’†ٹش•ٌچگپv‚ة“¥‚فگط‚é•ûŒü‚炵‚¢پB پiگ°“V‚ئ‚ç“ْکaپC2007-06-27پj
پu‹Œ‘ن’ ”pٹüپv‚إژذ•غ’،’·ٹ¯‚ةچR‹c•¶‚ًژè“n‚· پi•غچâ“Wگl‚ج‚ا‚±‚ا‚±“ْ‹LپC2007-06-27پj
ژذ•غ’،’·ٹ¯پA–ى“}ژ‹ژ@’c‚ً‘qŒة‘O‚إ–ه‘O•¥‚¢ پi•غچâ“Wگl‚ج‚ا‚±‚ا‚±“ْ‹LپC2007-06-27پj
|
|
پ£‚±‚جƒyپ[ƒW‚ج‚s‚n‚o‚ضپ@پ@پ@پ@پ@ HOME > ژG’kگê—p24Œfژ¦”آ
ƒtƒHƒچپ[ƒAƒbƒv:پ@
|
|
“ٹچeƒRƒپƒ“ƒg‘SƒچƒO پ@ƒRƒپƒ“ƒg‘¦ژ”zگM پ@ƒXƒŒŒڑ‚ؤˆث—ٹ پ@چيڈœƒRƒپƒ“ƒgٹm”F•û–@
|
|
 پ@‘è–¼‚ة‚ح•K‚¸پuˆ¢ڈC—…‚³‚ٌ‚ضپv‚ئ‹Lڈq‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
پ@‘è–¼‚ة‚ح•K‚¸پuˆ¢ڈC—…‚³‚ٌ‚ضپv‚ئ‹Lڈq‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
Œfژ¦”آ,‚l‚k‚ًٹـ‚ق‚±‚جƒTƒCƒg‚·‚ׂؤ‚ج
ˆêگط‚جˆّ—pپA“]چعپAƒٹƒ“ƒN‚ً‹–‰آ‚¢‚½‚µ‚ـ‚·پBٹm”Fƒپپ[ƒ‹‚ح•s—v‚إ‚·پB
ˆّ—pŒ³ƒٹƒ“ƒN‚ً•\ژ¦‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
|
|
|
|
|
|
|
|