| Tweet |
(回答先: 日航ジャンボ機が墜落して16時間という殺人的時間を確保したのはそのアリを殺す為だったのではないかと疑われている 投稿者 そのまんま西 日時 2007 年 7 月 15 日 18:05:16)
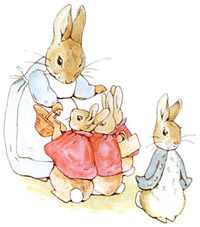

はじめに
このパンフレットを作成した目的は、悲惨な航空機事故の再発防止を目的とするもので、日航123便事故の真の原因を明らかにし、正しい再発防止のための対策がとられる事を求めて作成したものである。
日航123便事故は1985年8月12日18時25分頃、伊豆半島の東の海上を飛行中、異常事態が発生し、約30分飛行した後、18時56分頃、群馬県の上野村の山中に墜落した。
乗客509名乗務員15名、あわせて524名が搭乗していたが、重傷の乗客4名が生き残ったのみで、520名が死亡した。
これは1機の事故としては最大の死亡者数であった。
この事故については既に日本の事故調査委員会(以下 事故調と略)が1987年6月19日、事故調査報告書を発表して事故原因の調査は公式には終了したことになっている。
--------------------------------------------------------------------------------
報告書の結論は
原因
本事故は、事故機の後部圧力隔壁が損壊し、引き続いて尾部胴体・垂直尾翼・操縦系統の損壊が生じ、飛行性の低下と主操縦機能の喪失を来したために生じたものと推定される。飛行中に後部圧力隔壁が損壊したのは、同隔壁ウエブ接続部で進展していた疲労亀裂によって同隔壁の強度が低下し、飛行中の客室与圧に耐えられなくなったことによるものと推定される。
というものであり、尾翼を破壊し操縦に不可欠の油圧系統を破壊させたエネルギーを客室の与圧された空気の噴出に求めている。そのために客室の急減圧の存在が証明されなければならないが、急激な客室圧力の低下は、航空関係者の目には見いだせない。
事故調の報告書の中にも、急減圧を証明はしていない。減圧を証明するために事故調が行った実験の結果については報告書が事実に反する疑いが強い。
われわれは航空機の運航に直接携わっているものであり、航空の現場の状況には熟 知しているが、事故機のCVR、FDR、は極秘扱いにされており、その内容は事故調の発表したもの以外の情報はなく、直接CVRを聞く機会はなかった。残骸も一度見ることが出来ただけで、それ以降は見る機会はなかった。
このパンフレットは、報告書をもとに現段階での疑問点と、事故原因についての考察である。
遺族の方々については、その気持ちに時効があるはずもなく、航空関係に働くものにとって日航123便事故は忘れてはならない事故であり、経営者にとっても決して忘れることなく「絶対安全」の確保をめざして努力する義務がある。運輸省は航空の安全を国民に保証する立場にあり、日航123便事故からできる限りの改善点を引き出しその実現に努力しなければならない責任がある。
ところが運輸省の事故調が行った日航123便事故の事故原因の調査は疑問だらけである。この事故調査については多くの航空関係者、検察関係者などからその内容の基本的なところに疑問が出されている。事故調はこれを現在のところ全く無視している。
この事故については、世間では後部圧力隔壁の修理ミスによる急減圧が原因で垂直尾翼が破壊され、同時に油圧系統も破壊され操縦不能になり墜落したと思いこまされている。マスコミ関係でも「後部圧力隔壁の破壊」という言葉が123便の枕詞のように使われ続けてきた。その結果このような誤解を世間に植え付けてしまった。
ところが、この圧力隔壁を原因とする推定には、多くの疑問があり、真の事故原因ではあり得ない。
特に、事故調が隔壁説の核心部分であると考えた30万フィート/分(約9万1千メートル/分)程度の急減圧と、それに続く20分近くの2万フィート(約6千メートル)以上の高度を酸素マスクなしで、低酸素症にならずに、操縦可能か否かを明らかにするために、「ただならぬ意気込みで」行ったと言われる急減圧実験の結果について、報告書の記載は事実に反する事が明らかになっている。
これと併せて、CVRの解読に至っては、乗員らが理解できないような解読、急減圧を否定する部分は解読が曖昧で、次第に変化していることなど、意図的に解読が変更されたのではないかとの疑惑が強く持たれている。
急減圧が仮に存在したとすれば、何故乗員が急減圧に対する処置を全く行わず、操縦室と客室の間のドアーが設計強度以上の差圧が加わったと見られるにもかかわらず何故開かなかったのか、後部圧力隔壁より後方の(セクション48と呼ばれる部分)のプレッシャ・レリーフ・ドアが開いてたはずであると仮定しながらそのドアーは御巣鷹山まで機体から飛散せずに飛行できたのか、セクション48は設計強度としては差圧1.5psi(ポンド/平方インチ)とボーイング社の資料に明記されている。従ってそれよりもはるかに大きい圧力に耐える(事故調の推定では4psiの圧力に耐える)垂直尾翼のトルクボックスが破壊される前に、1.5psiでセクション48の部分が先に破壊され、空気は機外に放出され垂直尾翼は破壊されないのではないか?
事故調は毎分28万ftの急減圧があったとすれば、乗員らは減圧を直ちに感知せず、緊急降下もせず酸素マスクを着用しなかった事実は乗員らにとっては考えられないことである。この点については当時の事故調査委員長は「酸素マスクをつけるよりもっと重大なことがあったと考える」と述べ('94.2.6 日本テレビ放映)、「その理由を明らかに出来なかった」と究明を放棄していた報告書の内容を訂正した。
事故調の委員長が自ら70点のできの調査と採点していたが、これではとうてい「的確な事故調査」とはいえず、この事故を教訓としてなにを改善したのかも明確でない。この時期にもう一度123便事故を振り返ってみたい。
急減圧が事故の真の原因でないことは以下に示す事実から明白になっていると信じるが、では真の事故原因は何であったのか、という疑問が残る。
客室内の空気のために尾翼が破壊されたのでなければ尾翼を破壊したエネルギーは何処から供給されたものか、そこに真の事故原因がある。 300ノット(約550km/h)で飛行している機体が受ける空力的な力か、それとも他の飛行物体との接触によるものかどちらかにならざるを得ない。
123便事故からすでに8年以上の歳月がすぎ、航空労働者の中にも123便事故を知らない世代も増加してきている。また事故の概要を忘れてしまった人も少なくない。この時期に再び123便事故を振り返り、真の事故原因を考えることは極めて重要であると考える。
123便事故の経過を思い出していただくために、ここに事故調の作成した事故調査報告書の一部(飛行の経過の部分)を参考資料として添付した。
認定した事実
2.1 飛行の経過
日本航空株式会社(以下「日航」という。)所属ボーイング式747SR−100型JA8119は、事故が発生した昭和60年8月12日、同社定期503便、363便、366便として、航空機関士(363便及び366便に搭乗)を除き事故時とは別の運航乗務員により運航された。
同機は、366便(福岡ー東京)として17時12分に東京国際空港に着陸し17時17分に18番スポットに駐機して、その後123便(東京ー大阪)としての飛行準備のための点検等が行われた。
東京航空局東京空港事務所に提出された同機の飛行計画は、計器飛行方式、巡航速度467ノット(真対気速度)、巡航高度24,000フィート、目的地大阪空港への経路は三原、相良、シーパーチ、W27、串本VORTAC、V55、信太VOR/DME、大阪NDBまでの予定所要時間は54分、持久時間で表された燃料搭載料は3時間15分であった。
同機は、副操縦士の機長昇格訓練のため、機長が右操縦士席、副操縦士が左操縦士席に位置し18時04分に18番スポットから地上滑走を開始し、その後、18時12分滑走路15Lから離陸した(以下、付図ー1及び別添3、5、及び6参照)。
同機は、24,000フィートに上昇中に18時16分55秒東京管制区官制所(以下「東京コントロール」という。)に対し、現在位置からシーパーチ(非義務位置通報点・大島から253度、74海里)へ直行したい旨の要求を行い、同要求は18時18分33秒に承認された。
18時24分35秒、同機がシーパーチに向け巡航高度24,000フィートに到達する直前、伊豆半島南部の東岸上空に差し掛かるころ、「ドーン」というような音とともに飛行の継続に重大な影響を及ぼす異常事態が発生し、その直後に機長と副操縦士によるスコーク77(ATCトランスポンダの緊急コード番号7700の意味)との発声があり、次いで、18時25分21秒東京コントロールに対して異常事態が発生したため22,000フィートに降下し、同高度を維持すること及び羽田(東京国際空港)に引き返すとの要求が行われた。18時25分40秒同機から大島へのレーダ誘導の要請があり、これに対し東京コントロールは羽田への変針は右旋回か左旋回かとの問い合わせを行ったところ、同機から右旋回を行うとの回答があったので、東京コントロールは同機に対し大島へのレーダ誘導のため右旋回で進路90度で飛行せよとの指示を発出し、同機は18時25分52秒これを了承した。同機はその後、伊豆半島南部の中央付近で若干右へ変針し西北西に向かって伊豆半島を横切り駿河湾上へ出たが、このころから同機には顕著なフゴイド及びダッチロール運動が励起され、これら現象はその後強弱に変化しながらも墜落直前まで続いた。18時27分02秒東京コントロールは同機に対し緊急状態宣言の確認を行い、次いで「どのような緊急状態か。」との問い合わせを行ったが同機からの応答はなかった。18時28分31秒、東京コントロールは同機に対し、再度「大島へのレーダ誘導のため、針路90度で飛行せよ。」と指示したが、これに対し、18時28分35秒同機から「現在、操縦不能」との回答があった。
同機は、駿河湾を横切り18時30分頃静岡県焼津市の北付近の上空を通過した後、18時31分頃右へ変針して北上を始めた。このころ東京コントロールが、同機に対し「降下可能か。」と問い合わせを行ったところ18時31分07秒同機から「現在降下中」との回答があり、次いで、現在高度を問い合わせたところ現在高度は24,000フィートとの回答があった。18時31分14秒東京コントロールが「現在位置は、名古屋空港から72海里の地点、名古屋に着陸できるか。」との問い合わせを行ったところ同機からは、「羽田へ帰ることを要求する。」との回答があった。
18時31分26秒東京コントロールは同機に対し、今後は日本語で交信してもよい旨を伝え同機はこれを了承した。
18時35分ごろ、同機は富士山の西方約35キロメートルの地点付近の高度約23,000フィートで右へ変針して東へ向かい、その後18時38分ごろ、富士山の北北西約7キロメートル付近から左へ変針して北東に向かって飛行し、次いで18時41分ごろ山梨県大月付近の高度約21,000フィートから、約3分でほぼ360度右へ変針するとともに高度約17,000フィートまで降下した。その後の同機は東に向かって急速に降下をしながら飛行し、18時45分46秒「操縦不能」との返信を行い、次いで左へ変針して北東へ向かったが18時47分07秒同機から羽田へのレーダ誘導の要請があり、これに対し東京コントロールは「羽田の滑走路は22なので針路90度をキープして下さい。」との指示を行い、同機はこれを了承した。次いで18時47分17秒東京コントロールからの「操縦できるか。」との問い合わせに対し「操縦不能」の送信があった。18時48分ごろ、高度約7,000フィートで同機は東京都西多摩郡奥多摩町付近上空から左へ変針し西北西に向かって徐々に上昇しながら飛行し、18時53分ごろ高度約13,000フィートに達した後再び降下を始め18時53分31秒「操縦不能」を再度送信した。18時54分19秒同機は高度約11,000フィートで東京コントロールの指示により東京進入官制所(以下「東京アプローチ」という。)に交信を切り換えた後18時54分25秒同機から「現在位置を知らせ。」との要求があり、これに対し東京アプローチは羽田の北西55海里、熊谷の西25海里の地点を伝達したところ18時54分55秒同機はこれを了承した。次いで東京アプローチは18時55分05秒羽田も横田も受け入れ可能である旨を送信し同機はこれを了承した。その後は、東京アプローチ及び横田進入官制所からの呼び掛けに対する同機からの応答はなかった。墜落地点の南南西3〜4キロメートルの地点での目撃者(4名)によれば、「同機は東南東の奥多摩の方向からかなりの低高度、低速度で機首をやや上げて大きな爆音をたてながら飛んできた。飛行機は我々の頭上を通過したがその後北西にある扇平山(標高1,700メートル)の付近で急に右へ変針し東北東の三国山(標高1,828メートル)の方向へ飛行した。次いで三国山を越えたと思われるころ突然、左へ傾き北西へ急降下し、山の陰に見えなくなった。その後同機が隠れた山陰から白煙と閃光が見えた。」とのことであった。
同機は、三国山の北北西約1.4キロメートルの稜線(標高約1,530メートル、付図ー13の一本から松の地点)にある数本の樹木に接触し、次いで同地点の西北西約520メートルの稜線(標高約1,620メートル、付図ー13のU字溝の地点)に接触した後、同地点から更に北西約570メートルにある稜線に墜落した。墜落した地点は群馬、長野、埼玉の3県の県境に位置する三国山の北北西約2.5キロメートルにある尾根(標高約1,565メートル、北緯35度59分54秒、東経138度41分49秒)であった。
推定墜落時刻は、18時56分ごろであった。
付図ー1 JA8119飛行経路略図
第2章 報告書の疑問点
4名の生存者以外は即死であったのか?
報告書25頁には「4名を除いた他の者は即死若しくはそれに近い状況であった」との記載がある。
しかし、この事故の4名の生存者らは墜落後、しばらくの間は多くの人の息づかいや話し声を聞いている。生存者の一人、落合由美さんは
『墜落直後に、「はあはあ」という荒い息遣いが聞こえました。一人でなく、何人もの息遣いです。そこらじゅうから聞こえてきました。まわり全体からです。
「おかあさーん」と呼ぶ男の子の声もしました。
次に気がついたときは、あたりはもう暗くなっていました。どのくらい時間がたったのか、わかりません。』
(中略)
『どこからか、若い女の人の声で、「早くきて」と言っているのがはっきり聞こえました。あたりには荒い息遣いで「はあはあ」と言っているのがわかりました。まだ何人もの息遣いです。
それからまた、どれほどの時間が過ぎたかわかりません。意識がときどき薄れたようになるのです。』
(中略)
『突然、男の子の声がしました。「ようし、ぼくはがんばるぞ」と、男この子は言いました。学校へあがったかどうかの男の子の声で、それははっきり聞こえました。しかし、さっき「おかあさーん」と言ったこと同じ少年なのかどうかは、判断はつきません。』
(中略)
『やがて真暗ななかに、ヘリコプターの音が聞こえました。あかりは見えないのですが、音ははっきり聞こえていました。それもすぐ近くです。これで、助かる、と私は夢中で右手を伸ばし、振りました。けれど、ヘリコプターはだんだん遠くへ行ってしまうんです。
帰っちゃいやって、一生懸命振りました。「助けて」「だれか来て」と、声も出していたと思います。ああ、帰ってゆく・・・・・。
このときもまだ、何人もの荒い息遣いが聞こえていたのです。しかし、男の子や若い女の人の声は、もう聞こえてはいませんでした。』
(中略)
『涙はでません。全然流しませんでした。墜落のあのすごい感じは、もうだれにもさせたくないな。そんなことを考えていました。そして、また意識が薄れていきました。
気がつくと、あたりはあかるかった。物音は何も聞こえません。全く静かになっていました。生きているのは私だけかな、と思いました。でも、声を出してみたんです。「がんばりましょう」という言葉が自然に出てきました。返事はありません。「はあはあ」という荒い息遣いも、もう聞こえませんでした。』
落合さんは墜落後16時間以上たってから、救出された。この16時間の間に生存者はかなり多くいたことは明らかで、捜索救難がもっと速く行われていれば生存者はもっと多くなっていた可能性がある。
このことは「墜落の夏」(新潮社 吉岡 忍著)の中でも指摘されている。
’85年8月16日付け東京新聞の報道では、「墜落地わかっていたのに・・・」と地元民 県警など取り上げず との見出しで(資料 5)
「墜落現場が小倉山だの御座山だのと言っていたのは、機動隊や自衛隊の連中だけだ。オレたち地元の住民は12日の夜から、南のスゲノ沢の方だと確信していたんだよ。なのに、(警察などは)オレたちの声を無視してあさっての方向を捜索させた。4人以外にも生存者がいたのなら夜中でも十分救出に行けたんだ!」
と生存者ら4名を最初に発見した人は語っている。
地元の関係者は、県警側は「小倉山へ向かう」と主張。地元側は「絶対に違う」と反論したが、機動隊長がガンとしてゆずらず、結局間違った方面へ捜索隊を出発させてしまったと語っている。
朝日新聞社会部の作成した「日航ジャンボ機墜落」によると、墜落地点として多くの連絡者のはっきりしている情報の中で、何故か20時8分にあった長野県警への「氏名不詳」の110番の情報、「現場はぶどう峠の長野県側(北相木村)だ、とだれもが信じた。
何故このような「氏名不詳」の情報に踊らされたのか?
この捜索の誤りの責任を追及するのでなく、このようなばかげたミスはどうやれば再発を防げるか検討する必要が事故調にはあったのではないか。
事故調のように「4名以外は即死またはそれに近い状態であった」と事実を曲げてしまったのでは、捜索救難の改善は生まれてこない。「ようし、ぼくはがんばるぞ」と叫んだ子どもの死は無駄にされている。
事故調の判断を固めた重要な減圧実験結果に疑惑が
事故調が123便で発生したと推定している、毎分28万フィート(1分間で9万3千メーターの高度の気圧まで低下)の減圧は、「個人差はあるものの同機に発生したとみられる程度の減圧は人間に対して直ちに嫌悪感や苦痛を与えるものではないので、乗務員は酸素マスクの着用について心に留めつつも飛行の継続のために操縦操作を優先させたものと考えられる。」と述べている(報告書115頁)。
また、事故調は、減圧室を使用して、被験者1名で、650ftの高度から24000ftの高度まで約5秒間で減圧させた。被験者は試験開始から終了まで酸素マスクなしで課題作業に従事した。その結果、被験者には急減圧による格別の症状は認められなかったと報告書の付録176〜179ページに記載している。
しかし、この減圧テストの被験者本人が、日航の乗員らに対して「減圧試験は650ftから24000ftまで、計画では7秒であったが5.3秒で減圧させた、その結果は肺の空気が激しく吸い出され、すぐに視野が暗くなる等の酸欠症状が現れたため、直ちに酸素マスクを着用しなければならなかった。」と話しており、事故調の試験結果をはっきりと否定している。
’86年11月25日午後1時半より、日本航空機関士会の会員10名は航空自衛隊 航空医学実験隊(東京都立川市)をの見学した。
「緊急時における人間の行動について」講演を聴いた後、低酸素症実験と急減圧実験等を見学した(資料 6ー1,2)。
この見学について見学者の一人は、次のように同会の会報('87ー1ー15)に
「高度25000ftでの低酸素体験では被験者の顔色が、1分半位で土色になり、マスクを着け酸素を吸い出すと、見る間に顔色がバラ色に戻りました。(中略)最も印象に残ったことは、雑談の中で聞いた日航事故を想定して、客室高度650ftを7〜8秒かけて24200ftに急減圧した実験で、今まで経験した事がないほど肺から空気が吸い出され、すぐにまわりが暗くなり(低酸素症)思わず酸素を吸ったという話でした。」と感想を寄せている。
この実験について、「悲劇の真相」(鶴岡憲一・北村行孝著 読売新聞社)183頁に急減圧論争の項目の中で、この実験についての記載がある。
これによるとこの実験に対して「事故調の意気込みには、ただならぬものがあった。」そして、この実験の結果『「クルーが操縦不能にならなかったことは、急減圧が発生しなかったことの理由にはならない。急減圧が起きれば操縦できなくなるという説も成立しない」との事故調の判断は、このテストで固まったのだ。』と記載されている。そうであれば、この実験こそ事故調の急減圧を中心とするストーリーの決定的な要素となっていることになる。
この決定的な実験の被験者A氏が日航の乗員らに対して「すぐに酸欠症状が現れ、酸素マスクを着用した」と述べているのである。
これは極めて重要なことで、事故調の報告書の核心部分に疑惑がもたれていることになり、報告書が根底から信頼できないものとなっている。
この実験結果については、従来の航空界の常識をであった有効意識時間は、2万フィートで5〜10分という定説を覆すものでもあり、再度公開実験が不可欠である。
CVRの解読にも疑問、CVRは音の記録
CVRは操縦室内の会話や音を録音したテープである。従って操縦室の個人的な会話も録音される。また刑事責任の追及に利用されたならば乗務員らは自分を守る権利も奪われてしまう。そのためCVRは航空の安全の向上のためだけにしようする目的で装備されている。ところが中標津YS−11墜落事故(’83年3月11日)では乗務員の刑事責任を追及するために、検事がCVRを悪用しようとした。
さらに、日本航空のモスクワ事故(’72年11月28日)の時にはCVRに記録されていた「やっこらさ」というかけ声を悪用して、乗員の弛み事故などと事故原因を乗員の操作ミスであるかのような印象を世間に与えるために利用した。
日本航空のニューデリー事故では運輸省はCVRの声をテレビで公表している。ところが今回の日航123便事故ではCVRは全くの極秘扱いで、事故機の乗員の同僚や家族にさえも聴かせていない。
以下に述べるように事故調の解読は極めて曖昧である。かりに事故調の人ではわかりにくい発音でも、同僚や家族ならば正確に理解できる場合もあり得ると考えられるがそれすらもやっていない。よほど事故調にとってまずいことがCVRに記録されていたと疑われているのもやむを得ない。
解読の変化とその方向 事故調によるCVRの解読はこれまで3種類が公表されている。この三つの解読には微妙な変化が見られる。
(1)85年8月27日付 経過報告として発表された解読
(2)86年3月28日付 聴聞会のための事実調査に関する報告書の案に添付されたもの
(3) 87年6月19日付 事故調査報告書(単に報告書または最終報告と呼ばれることが多い)に添付されたもの
これら三つの解読で変化が見られる点を比較してみた。
太字部分は不確実な解読を示す
(1)'85.8.27 解読
(2)'86.3.28 解読
(3)'87.6.19 解読
30' 27" F/E
(インターフォン)
キャビンプレッシャーどうでしょうか。
キャビンマスクは落っこちてますか。
ああそうですか。じゃあキャビンプレッシャー・・・して下さい。 30' 29" F/E
オキシジェンプレッションどうですか
オキシジェンマスクおっこってますか
あーそうですかじゃーオキシジェンプレッシャー
あーその・・・つけてください
30' 28" F/E
オキシジェンプレッシャーどうですか?
オキシジェンマスク?おっこってますか?
あーそうですか
じこーオキシジェンプレッシャーあーその
PO2ボトルちゃんとつけてください
30' 52" F/E
キャビン マスクがドロップしているから
・・・・・
キャビンプレッシャはドロップしてます 30' 52" F/E
オキシジェンマスクがドロップしているから 30' 52" F/E
(左に同じ)
31' 35" ハイチャイム
はいなんですか。もっと後ろの方ですか。えーと、何がこわれているのですか。どこですか。
あーあーあーあー、荷物の収納室のところですね
後ろの方の一番後ろの方ですね。はいわかりました。
あのですね、荷物室に入れてある収納室の一般のですね。荷物の収納スペースのところが落っこちてますね。
これは降りたほうがいいと思いますね。
33' 12" ハイチャイムF/E
アール・・・
アールファイブの窓ですか。
はい了解しました。
はい了解しました。
はいわかりました。
33' 33"
F/E キャプテン
CAPT はい
F/E
アールファイブの窓が・・・
エマディセントやったほうがいいと思います。
CAPT はい
31' 36" ハイチャイム
31' 41" F/E
はいなんですか。・・・の後ろの方ですか。
えーと、なにがはがれてるんですか。どこですか。
31' 59" CAPT
あーあああ
32' 01" F/E
荷物を収納するところですね
後ろの方の一番後ろの方ですね。はいわかりました。
32' 11" F/E
あのですね
荷物室に入れてある
荷物のですねいちばんうしろのですね
荷物の収納スペースのところがおっこってますね。
これは降りたほうが
いいと思います
32' 32" F/E
マスクは一応みんな吸っておりますから
33' 13" ハイチャイム
33' 16" F/E
ライトオキシジェン調べてくれる
33' 23" F/E
アールファイブの・・・・・ですか。
はい了解しました。
はい了解しました。
はい了解しました。
・・・ちょっと
・・・キャプテン
33' 35"
F/E キャプテン
CAPT はい
F/E
アールファイブのマスクがストップですから ひとつ
これ
エマディセントやったほうがいいと思いますね。
CAPT はい
31' 36" ハイチャイム
31' 41" F/E
はいなんですか。後ろのほうですか。
えーと、なにがこわれているんですか。
どこですか。
31' 59" CAPT
あーあああ
32' 01" F/E
(左に同じ)
32' 11" F/E
(左に同じ)
32' 32" F/E
(左に同じ)
33' 13" ハイチャイム
33' 17" F/E
ちゃんとオキシジェン調べてくれる?
33' 23" F/E
アールファイブのはまだですか。
はい了解しました。
はい了解しました。
はい了解しました。
33' 35"
F/E キャプテン
CAPT はい
F/E
アールファイブのマスクがストップですから・・・・・
エマディセントやったほうがいいと思いますね。
CAPT はい
33' 55" F/E
マスクを我々もかけますか
CAPT はいかけた方がいいです
F/E・・・・・
緊急マスク出来たら吸った方がいいと思いますけど
CAPT はい
33' 46" F/E
マスクを我々もかけますか
CAPT はい
COP かけた方がいいです
33' 54" F/E
オキシジェンマスク出来たら吸った方がいいと思いますけど
33' 46" F/E
マスクを我々もかけますか
CAPT はい
COP かけた方がいいです
33' 54" CAPT
33' 54" F/E
オキシジェンマスク出来たら吸った方がいいと思いますけど
CAPT はい
35' 22" JL123
ええとですね。今あのー
R5のDOORがあのー
BROKENしました。
えーそれで 今DESCENTしております。
えー
35' 34" F/E
ええとですね
いま あのー アールファイブドアーがブロークンしました えーそれで
いまあー
デイセントしております
えー 35' 34" F/E
(左に同じ)
以上の解読を全般的に比較すると、事故直後の’85年8月27日の解読が乗員の目から見れば一番納得できるものである。
(1)の解読の30分27秒の「キャビンプレッシャどうでしょうか、 キャビン マスクはおっこってますか」という質問は減圧の疑いがあるときには極めて自然な質問である。
しかし、(2)の解読になると30分29秒「オキシジェンプレッションどうですか」「あーそうですか じゃーオキシジェンプレッシャー あーその・・・・つけてください」という解読は、プレッションという言葉も使うことはなく、客室には酸素圧力計もなく、客室乗務員に酸素の圧力を尋ねるこはあり得ない。
(1)で確定的な解読であった「キャビンプレッシャー」が(2)不確実な「オキシジェンプレッション」となり3の解読になると「オキシジェンプレッシャーどうですか」と確定的な解読に変わっている。
客室に乗客用の酸素の圧力を示す計器はない。この解読の変化は不自然であり、2の段階で何らかの意図を持って解読が修正されたものと見ざるを得ない。その意図は、「R5の窓ですか」を「まだ」に変更する布石であったと考えることもできる。
このように、事故原因に直接関わる部分でCVRの解読は不自然に変化しており、そこに意図的なものを感じる人は多い。CVRの解読についてのこの他の疑問点を以下に列挙してみた。
意味不明の解読「PO2」 CVRは音の記録
報告書では事故調の解釈によるCVRの解読のみを報告書に示している。しかし、CVRは音の記録であり、事故調の公表したものの中には聴聞会用の資料である事実調査報告書の案までにはなく、最終報告書で18時30分39秒につけ加えられた、「PO2」という言葉などは、どの様に発音していたのか全く不明の記述がある。
少なくとも「ピーオー・ツー」なのか「ピーオー・に」あるいは「ポータブル・オーツー」と聞こえたのか、事故調の希望する「解釈」でなく、音の記録である以上、せめて、どの様に聞こえたのか、「解読」の結果を示さなければ意味がない。また、PO2については乗員の中でも、単独では直ちに意味が理解できないものも見られるほど、一般的な呼び名ではなく、この解読には疑義を示すものが少なくない。
機関士は「R5ドア・ブロークン」の情報はどこから得たのか
さらに事故調の解釈に疑問が出されているのは、18時35分35秒頃機関士が社用無線で報告した「R5のドアが、ブロークンしました。えーそれで、いま・・いまディセントしております」という内容である。
この通信を傍受したものは少なくない、「事故直後報道されたのは、R5ドア(右最後部ドア)が破損し、墜落した。」であったことは多くの人が記憶している。
事故機の残骸からR5ドアは墜落地点で発見された。
そのため乗員の間で、R5ドア、ブロークンが何を意味するのかが話題になった。その結果は多くの乗員が、R5ドアが破壊飛散するとすれば胴体後部の大規模な破壊であり空中分解のような状態になる。したがってR5ドアの部分的な変形か破壊ではないか、窓が割れた可能性もあるのではないかと推定した。
事故から15日後の8月27日に事故調が解読したCVRの内容が公表された。その中で18時33分20秒過ぎ頃の記録として、機関士と客室乗務員の間のインターフォンの会話として「アール ファイブのまどですか、はい りょうかいしました」と確定的な聞き取りとして(不確実部分はアンダーラインがつけられていたがこの部分はなかった)記載され、続いて機関士はその内容を、33分33秒頃に 「キャプテン」と呼びかけた後、「アールファイブの窓が・・・エマディセントやったほうがいいとおもいます。」と機長にアドバイスしている。
これによって乗員らの疑問は解け、やはりR5の窓付近に異常があったのだ、それを機関士はR5ドアーブロークンと報告したのだと理解、納得できた。
ところが、事故調が聴聞会のために’86年3月28日付で作成した事実調査報告書の案では、確定的な読みとりであったはずの20秒過ぎの「アール ファイブのまどですか」が「アール ファイブの・・ですか」と解読不明に変えられ、続く機長へのアドバイスも「アールファイブのマスクがストップですから ひとつ これ エマディセントやったほうがいいとおもいますね」に変更された。
続いて、’87年6月19日に公表された最終報告書では、「アールファイブのはまだですか」(下線部分は不確実な解読)と確実から不確実に改められた。機長への報告は 「アールファイブのマスクがストップですから・・・エマージェンシーディセントやったほうがいいとおもいますね」
つまり、「まど」 「・・・」 「まだ」と確実から不確実へと変化し、機長への報告は
「まどが・・・」 「マスクがストップですから ひとつ これ エマージェンシーディセントやったほうがいいとおもいますね」 「マスクがストップですから・・・エマージェンシーディセントやったほうがいいとおもいますね」
と変化している。これについて乗員の中から、まどならば理解できたのが、R5のマスクではおかしい。機関士は何時・誰から「R5ドアブロークン」の情報を得たのか? 第一R5のマスク等という言葉は乗員は使わない。「R5のマスク」の意味を多くの客室乗務員に尋ねたところ、「R5ドアの客室乗務員席の頭上にある酸素マスクのことですか?」との質問が帰ってきている。「R5付近のマスクが不作動ならどの様に操縦室に報告するか?」との質問に対しては、「Eコン右側の酸素(マスク)が出ません」(Eコンとは、Eコンパートメント・・後部客室・・の略称)との答えが圧倒的に多かった。R5のマスクと答えた人は皆無であった。R5のマスクとはどの様に考えてもR5ドアの客室乗務員用のマスクのことでありそれ以外の意味はない。
マスクの不作動を理由に緊急降下をするのではない
「R5のドアがブロークンしました。それでいまディセントしております」との送信は、R5付近の機体に損傷があったことを短く述べたとすると、R5付近に損傷があったことを機関士が情報を得ていなければならない。CVRにはそのような記録はない。いったいどの様にして機体の損傷を確認したのか?
機体の損傷に関する会話は、18時31分36秒客室からの4度目のインターホンの呼び出しに答えて航空機関士が「後ろの方ですか? 何が壊れているんですか? どこですか?荷物を収納するところですね? 後ろの方の一番後ろの方ですね?はいわかりました。」と破損箇所を確認している。このやりとりの中にはR5という言葉は全くない。
それを機長、副操縦士らに伝えている。この破損個所をR5ドアブロークンと省略することはあり得ないと多くの乗員は答えている。
R5付近のマスクの故障を、R5ドアーブロークンと省略することはあり得るのであろうか? 運航乗員、客室乗務員の中では絶対にあり得ないという回答が100%であった。
28万フィート/分という激しい急減圧があればマスクがすべて作動していても緊急降下をするのが当然で、マスクの不作動を理由に緊急降下をするようにと機長にアドバイスすることはあり得ない。この解読の変更の説明はCVRへの疑問を疑惑へと発展させた。
「マスクはみんな吸ってます」50秒後に「R5のまだですか」?
さらに、機関士を始め操縦室の乗員らは酸素マスクを着けていない。客室の一部の酸素マスクが不作動であったとしても、事故調の主張するように 毎分30万フィート程度の減圧が、人間に不快感を与えないのであれば、それほど酸素の圧力などを気にする必要もないはずである。異常発生直後から操縦室の乗員らは急減圧に対する対応をしていない。「ディコンプレッション」のコールもなく、高度の降下の要求も24000ftから22000ftへの降下であり (急減圧ならば13000ftへの降下を要求する)、マスクも着けず急減圧と緊急降下への行動を一切とっていない。
運航乗務員らが減圧(急減圧でない)を確認したと見られるのはCVRの解読から見ると、30分28秒頃に機関士が客室乗務員にインターフォンで酸素マスクが落下していることを確認した時点である。異常発生から6分が経過している。
そのなかで、「マスクは一応みんな吸っておりますから」(32分32秒)と他の乗員に報告していた機関士が、1分もたたない 33分23秒に「R5のはまだですか?」と酸素マスクの具合はよくならないかと質問すると言うことも極めて不自然であり解読は誤っている。
「R5ドア ブロークン」はR5付近の酸素マスクのトラブル?
上記のように、機関士が社用無線で会社に送信した 「R5ドア ブロークン」の送信については、多くの人が疑問を待っていた。
これの対して、事故調の関係者が「悲劇の真相」(読売新聞社 鶴岡健一・北岡行高 著)の著者らに、解読の変更のいきさつを気軽に語っている(同書 150頁)。
それによると
この解読の変更の鍵になったのは、落合さんら生存者の証言だった。「(R5ドアの周辺を担当していた)スチュワーデスは、天井から下がった客席の酸素マスクを伝いながら吸い、乗客の安全指導に当たっていました」というのである。
急減圧が起きた場合、スチュワーデスは、乗客のように天井から下がる酸素マスクを着用していたのでは移動できないため、普通は各スチュワーデス席付近に保管してある携帯用小型酸素ボトルを(容器)を取り出して使う。ところが、R5ドア付近にいたスチュワーデスは、ボトルでなく落下型の客席マスクを使っていたという。
こうした証言とCVR記録の解読から浮かび上がったのは、異常事態の中でのスチュワーデスの活躍ぶりだった。「R5ドア近くの天井から下がった酸素マスクは、隔壁破壊の衝撃のためか、酸素の出がよくなかった。それでスチュワーデスは自分のボトルをその客に譲り、自分はいつか酸素の出がよくなるかもしれないと期待しながら、故障した客のマスクを着けて客を励まし、酸素マスクの着用方法などを指導していた可能性が強い。機関士の福田さんが『R5はまだですか』と尋ねたのは『まだ、酸素マスクの具合はよくならないか』という意味だったのです。さすがにスチュワーデスですね。よくがんばったと思いますよ。こうした経緯の後に福田さんは、日航とのカンパニー無線交信で、R5ドア付近の機体が損傷したらしいことを『R5ドア ブロークン』と、はしょって通報したのだと推測できます」と事故調関係者はナゾを解き明かしてくれた。
との記載がある。これによって乗員ら航空関係者は、この解読の変更に対して強い疑惑を持つとともに、これを苦しい言い訳と受け取り、報告書への不信感を決定的なものにした。
この説明に対する第一の疑問は、客席のマスクを適当に使いながら移動することを事故調が疑問視している事である。しかし、客室乗務員らから見れば疑問視するには当たらない。
ポータブル酸素ボトルをコートルームから取り出してマスクをアウトレットにさし込み、バルブを開いてからマスクを着用するのはかなり時間を要する(後述する123便とほぼ同高度で急減圧を経験したUAL811便の急減圧では酸素パイプが切れて酸素が流れず、当然酸素マスクが落下せず、ポータブル酸素ボトルを使用したが、着用にかなりの時間を要し、低酸素症によりめまいを経験している)。従って、酸素マスクが落下した直後に、急いで乗客の援助を必要とする場合などはこのように客席の予備マスクを利用することはあり得ることで、異常な行動ではない。後述するマンチェスター上空でのカナダ航空機の減圧事故では客室乗務員らは客席のマスクを使用して客室内を移動している。
この事故の場合にはポータブル酸素ボトルが収納されている後方のコートルーム付近が破壊されていたことが明らかになっており、激しく揺れる機内で、ポータブル酸素ボトルが、直ちに使用できる状態になかったことも考えなければならない。
客室乗務員自身が客席のマスクを利用しているのに、激しく揺れる機内で、乗客に一人だけしか利用できない重たいポータブル酸素ボトルを利用させたとするのは、他の乗客を差別することであり極めて不自然な想像でしかない。むしろこの想像の方が異常である。
客室乗務員らは「各座席列には予備のマスクがあり、もし一個のマスクが不良でも予備のマスクを利用させるのが普通である」と答えている。
減圧でマスクが落下したのならば酸素が出ないのは何故か
CVRの解読に関連した次の疑問は、酸素マスクの収納部のドアが開いているのにどうして酸素が出なかったのかと言うことである。
酸素マスクの収納部のドア(ふた)は酸素の供給パイプに酸素が流され、その圧力によってドアの止め金が外されマスクが落下する機構になっている(資料 7)。
しかし、この止め金は比較的はずれやすくやや衝撃のある着陸時にもマスクが落下することがある。
減圧によって酸素マスクの収納部が開き、マスクが落下したのであれば、収納部のラッチを外すための酸素は来ていたのであるから、酸素が出ない理由は個別の酸素マスクのトラブルが原因としか考えられない。
酸素マスクの収納部のドアは酸素ボンベから7〜15秒間送られてくる50〜100psiの比較的高い圧力の酸素でラッチを外すことによって開かれる。従って減圧によって酸素系統が作動したのであれば、ドアが開いたことは酸素が供給されていることになる。
酸素系統の配管が破壊されて酸素が供給されていなければ、酸素マスクの収納部のドアが開かない。後述するUAL811便の事例では酸素系統の配管が破壊されたため酸素マスクは落下しなかった。酸素マスクの収納部のドアが開いて、酸素が供給されないとすれば、ドアの開放が酸素圧で開かれたのでなく、衝撃など減圧以外の原因で開かれたものと推定も可能である。
酸素マスクを使用するにはマスクを十分に手前に引いてバルブ・アクチエイティング・ピンを引き抜いて酸素がマスクに流れるようにバルブを開かなくてはならない(資料8)。酸素が出ない理由の多くは、このピンが引き抜かれていないことによる。それを客室乗務員らは指導して回ったのではないかと推定している乗員が多い。
酸素が出ないことはすぐには気づかない
かりに酸素が出なくてもマスクについている吸気弁は吸うことによって客室内の空気を吸い込むことが出来るので、直ちに息が出来ない状態になるものではなく。酸素が流れているのかいないのかは、酸素を一時的にためておくリザーバーバッグの下についている緑色の部分(フローインディケイター)が膨らんでいるか否かで判断される(資料 9)。
この事故の場合のように、操縦席の乗員らが酸素マスクを着用しないでも特に急激に異常が発生していない状態では、多くの乗客らは酸素が流れているかどうか直ちに判断することは困難で判定するまでに時間を要するものと見られる。
生存者らが後部に限定されていたことから、前方客室での酸素の供給は不明であるが次の理由によりR5付近だけが酸素が十分供給されないことは考えにくい。
酸素系統の配管は、資料10の図に示すとおり、酸素マニホールドと呼ばれる主要な配管が客室の周囲に配管され、左右のマニホールドは最後部で左右が連結されている。従ってR5付近だけ酸素が出ない事は考えにくい。事故調はどの様にその事実と理由を確認したのか説明が必要である。
CVRの保存と関係者への公開を、減圧実験の公開を!
このように疑問だらけのCVRは日航に返還されているが日航はそれを秘密にし、毎日の運航で安全を直接支えている乗員らにも聞かせていない。CVRが企業側の手によって破棄される危険にさらされている。これを阻止するのが真の事故原因を解明する上で急務である。
これまで述べたことだけでこの報告書の信頼性は失われているが、事故調査委員会はまず航空関係の人々から理解信頼される報告書をつくらなければ意味がない。国民から信頼される機関となるために、再調査は不可欠である。日頃B−747型機に乗務している機長らが、大型機における急減圧について会社との公開調査を要求しているが、これら現場で乗務する乗員の疑問に対して事故調査委員会は回答を示さなければならない。
少なくとも、減圧室における28万フィート/分の減圧実験を公開で行うことが社会に対する責任である。
事故調の報告書作成までの経過についての疑問
事故発生直後には、事故調もこの事故原因がB−747型機の垂直尾翼の構造上の問題であるとの疑念を抱き、事故から3日後の8月15日に「B−747型機の垂直尾翼と方向舵について一斉点検」を命じている。
これと同時に配布された航空局が作成した資料によると「垂直尾翼の損傷が事故原因の端緒である疑いが強くなったと判断されるので、とりあえず下記のような検査を実施するよう指示することとした。なお、今後の事故調査の進展を踏まえ、また当該型式系列型機の製造国の当局である米国連邦航空局(FAA)とも密接な連絡を保ちつつ必要な措置をとる所存である。」
この措置に対して、整備関係者の一部から適切な措置だとの指摘があった。事実この点検の結果、多くの異常が発見された(資料11ー2)。
ボーイング747型機の垂直尾翼、方向舵については垂直尾翼と胴体を結合しているボルトにストレス・コロージョン(応力腐食)によるひびが入る例が報告されており、方向舵については方向舵を動かす油圧装置の方向舵への取り付け部に同じくストレス・コロージョンによるひび割れが報告されていたからである(資料12)。
ところが、8月15日ボーイング社は尾翼に欠陥はない。これまで一度も尾翼が原因の事故はないとこれに反発した(資料 13. 8月16日付新聞報道)。
この理屈は物事に始まりがないとするもので、技術者としての良心のかけらもない非科学的な態度と非難されるべきものである。
「悲劇の真相」によると8月22日アメリカの調査グループに所属していたNTSBの調査官の一人が、日本側の藤原事故調査官に「隔壁の中継ぎ板の一部が短い。リベット付近をよく調べたほうがいい」と耳打ちし、名刺の裏に図まで書いて教えたと言われている。
続いて8月29日アメリカFAAのスイフト氏らから、「日本航空123便は修理ミスから、2列にリベットが打たれるべきところが、一列しか効いていないそのため強度が低下し、14000回の飛行で圧力隔壁が破断する可能性がある」と日本の航空宇宙技術研究所で日本側技術者らに教えた。そのとき圧力隔壁の金属疲労は断面の電子顕微鏡写真まで提供されている。
この話を聞いた日本側の研究者らは、あっけにとられていたとされている。
アメリカ側はさらに日本の事故調の八田委員長(当時)にに直接話したいと要求している。事故調側ではアメリカの誘導に乗せられることを警戒しながらもこの要求に応じている。
日本側では調査によって確認されるまではアメリカ側の話を極秘扱いにしたとされている。
ところが9月6日にボーイング社がニューヨーク・タイムス紙を通じて、「日航123便事故は圧力隔壁の破壊が原因で、飛行中に減圧が起きた。墜落現場で調査した結果、修理ミスが見つかった。そのため圧力隔壁は強度が不足していた。」と突然発表した。
このようなアメリカの態度が世間に漏れると「事故調はアメリカ側の描いたストーリーを押し付けられている」と見られかねないと、事故調は秘密にしていたと言われている。
その後も、圧力隔壁の破壊が垂直尾翼を破壊したとする、破壊過程の筋書きもアメリカ側がコンピューターによる推定計算を主導的に発表し、それを日本側が裏付けるという経過をたどった(資料 14 昭和61年8月25日付日本経済新聞)。
航空機の製造国であるアメリカが関与していたとしても科学的で、真の事故原因が追究されるならば問題はないと言えるかもしれないが、この事故調査には疑問が多すぎる。
報告書の内容が疑問だらけの上に、この経過が示すように、事故機のメーカーや、製造国が事故調査に主導的に関与している事などから、航空関係者ばかりでなく経過を知る人々からは、日本の事故調の能力と独立性に強い疑問がもたれている。
第三章 事故調が主張する事故原因についての検討
事故調が事故発生の四日後に発表した、事故原因は 隔壁修理ミス→後部圧力隔壁にクラック→客室の与圧空気が漏れて尾部の非与圧部分の内部圧力を上昇→垂直安定板等を破壊→油圧4系統のパイプを破壊→操縦不能→墜落
このシナリオは、事故直後の8月16日に公表されている。この破壊過程では、垂直尾翼の破壊の原因となったエネルギーを客室内の与圧空気の噴出に求めている。この基本的な方向は報告書でも維持されている。
従って、客室内の空気の大量かつ高速の噴出がなければならない。つまり急減圧が尾翼破壊の前提となるが、急減圧の存在が証明されなければこのシナリオは崩壊する。
この筋書きがつくられた頃は、隔壁の復元もまだ行われていない段階で、もちろん海中の破片の回収も行われておらず、日本航空側から偽の「落合証言」が発表されていた状況にあった。
その後は事故調側から流される情報のすべては、このストーリーに沿ったものに限られ、調査もこのストーリーに沿ったものに限られた。相模湾の海底からの破片やAPU(補助動力装置・・機体最後部に装備され事故機では相模湾上空出で機体から脱落した)の回収に積極的でないことを指摘された事故調は、[APUは爆発の可能性がなく、あれ以上の捜査は必要性がなかっただけのことですよ」(悲劇の真相 109頁)と筋書き以外のものは調査の必要がないとの態度を明確にしている。
それとは逆に報告書では「方向舵の残骸は回収されたものが少なく、痕跡B及びCの発生の経緯を明らかにすることは出来なかった。」(報告書59頁)、「垂直尾翼の回収が部分的であるので、垂直尾翼の破壊順序を詳細に特定することは困難である」(報告書69頁)、などと相模湾での残骸回収が不十分であったことを口実に破壊過程の追求を怠っている。聴聞会でも多くの口述人らが相模湾の残骸回収の必要性を述べていたが、この事故調の態度はこの聴聞会を無視したものである。
これでは真の事故原因の究明は不可能である。このような態度は事故調査では許されないものである事は冒頭の山口氏の言葉にもあるとおりである。
このストーリーのキーワードとなっている急減圧の存在については、聴聞会でも日本の乗員組合の連絡会である日乗連をはじめ、航空安全会議、スチュワーデスの組合の連絡会議(客乗連)からも、日本航空の機長らからも疑問が出されていた。これに対して事故調の公表する情報はこれに対抗するかのように、特に急減圧の存在を印象づけるものに重点が置かれていた。
日乗連が指摘した、急減圧の存在を否定する事実については、「2万4千フィートの高度の気圧まで減圧しても、9分間程度は、わずかに機能低下するだけで操縦可能」と減圧の存在のみを強調し、どの程度の急減圧かには全くふれず、しかも事故機の乗員らは2万3千フィート以上を10分、その後2万2千フィート以上を7分間も、操縦かんを力を込めて操作し、速度と姿勢の変化を見ながらエンジンの推力を調節して機体を操作しようと試みていたのである。しかし、テストはわずか9分間だけ、それでも機能低下を認めている。何故事故機と同じ条件で20分程度のテストができないのか? 新聞では見出しだけに「急減圧」の文字を使わせ、急減圧の存在を印象づけようとした(資料15)。
(資料15 新聞記事 急減圧でも操縦可能)
他の急減圧事例に見る機内の状況急
急減圧の存在について事故調側の挙げる証拠を分析・検討し、さらに、急減圧の存在を否定するような事実と、その後発生した大型機の急減圧事故について123便と比較して急減圧の存在について検証する。
これまで急減圧を伴った大型機の事故事例は少なくない。
’72年6月12日 アメリカン航空 DC−10型機
11750ftを上昇中、後部貨物室のドアーが開き急減圧が発生、高度は低かったが爆発音と霧が発生し機内を風が吹き抜けた。
’75年1月15日 ナショナル航空 DC−10−10型機
39000ftの高度を飛行中、#3エンジンが分解し、その破片が客室の窓を破壊した。一名の乗客が窓からすい出され行方不明となった。減圧発生から約10秒後に操縦室内の酸素マスクから酸素が流出し、その音がCVRに記録されている。これは減圧を示す一つの証拠として注目された。
’86年10月26日 タイ航空 エアバスA300ー600型機
高度33000ftで土佐湾上空を飛行中、機内で手投げ弾が爆発し後部圧力隔壁を破壊、急減圧発生、9秒間で5600ftから20000ftまで減圧、減圧率は約96000ft/minであった。
機内では、操縦士は直ぐに急減圧の発生を認識し、緊急降下を試みている。与圧空気は機内を強い風となって通り抜け、最後部洗面所の化粧台を倒壊させ圧力隔壁後方へ抜けた。搭乗者247名中89名が航空性中耳炎になった。
’89年2月24日 ユナイテッド航空 ボーイング747−122型機
ホノルルを離陸して22000〜23000ftの間を上昇中異常音とともに、爆発的な急減圧が発生、運航乗務員らは直ちに酸素マスクを着用したが酸素は出てこなかった。直ちに緊急降下を開始しホノルルへ引き返した。原因は前方貨物ドアーが吹き飛び、約14平米の穴があき、それと同時に機内の酸素供給システムが破壊された。
客室内では減圧とともに強い風が客室内を吹き抜け客室乗務員らはものに掴まって吹き飛ばされるのを防いだ。風が治まった後も、機内の騒音が激しく、乗客への着水準備の指示に困難を来した。機内のアナウンス(PAシステム)は騒音のために全く役に立たなかった。減圧に伴って気温が急激に低下し凍えるように寒く感じた。客室の酸素マスクは作動しなかったため客室乗務員らは携帯用酸素ボトルを使用したが、その数が十分でなく、一部の乗員は、酸素不足によるめまいを経験している。
’90年12月11日 エア・カナダ L1011型機でマンチェスター上空
で発生した急減圧事故は、高度37000ftを飛行中後部圧力隔壁が破損し、急減圧が発生した。
乗員らは直ちに酸素マスクを着用し、緊急降下を開始するとともに、急減圧に関するチェックリストを行っている。
緊急降下後ロンドン、ヒースロー空港に無事着陸した。客室内では後部にいた客室乗務員は、鈍い「どーん」という音と同時に、左後部のトイレ付近から空気が流れる音が聞こえた。30〜40秒後に乗客用マスクが落下した。客室内の気圧はこの間に6300ftから最高20500ftまで減圧し、緊急降下によって再び気圧は上昇し、10000ftになっている。 結果的には20000ft以上に56秒間、18000ft以上に2分20秒間あったことが記録されていた。この減圧によって、3名の乗客が激しい頭痛と耳痛を訴え、数人がめまいを訴えた。
後部トイレのパネルが後部圧力隔壁に押し付けられパネルの縁がさけていた。グラスファイバーの断熱材が尾翼の下部の中央付近の点検孔から垂れ下がっているのが見られ、後部圧力隔壁の後方の胴体内部にも多量の断熱材が見られた。
圧力隔壁はその外周の8〜9時の位置の三角のパネルの外周部に2ftと1ft程度の長方形の部分が後方にめくれていた。
これら5件の事故を123便の例と比較すると、次の表のようになる。
日航123便事故
その他の大型機減圧事故
機内の音 特に感じられなかった
(生存者らの口述) 強い風が吹き抜けた、風のために飛ばされそうになったり、化粧台が破壊された
機内の騒音 特に感じられなかった
(生存者らの口述) 気流による騒音が激しく会話できない、PAも役にたたない例もある
減圧の認識 異常発生直後には減圧を認識した形跡はない
緊急降下を開始せず すぐに減圧を認識し緊急降下
耳への影響 エレベーターで経験するのと同じ程度に軽く詰まった感じ
(生存者らの口述) 航空性中耳炎多発
低酸素症 ほとんど見られず 23、000ft付近でも発生
酸素の噴出 全くなし 操縦室の酸素マスクから酸素が噴出し、その音がCVRに録音された例もある
(ナショナル航空DC−10)
気温の低下 その兆候なし 気温が急激に低下、凍えるような寒さを訴える
以上の例から見て、急減圧に伴う現象と見られている、風・騒音・気温の低 下などは123便では見られない。
日本航空では、客室乗務員に対して、急減圧発生に伴う現象として、衝撃音・急激な空気の流れ・霧の発生・ほこり・物体の飛散・そして、14000ft以上の高度の場合のマスクの自動落下の6項目を挙げている。しかし、123便では急激な空気の流れ、ほこり、物体の飛散は見られていない。
乗員らは急減圧を認識していない。異常発生後も 24000ftから2000ft降下を要求しただけで、酸素マスクもつけず緊急降下もしなかった。
霧の発生から見て、また生存者が耳が軽く詰まったと述べていることから見て減圧はあったと見られるが事故調が主張するような急減圧はなかったことは明らかである。
これらの減圧事故の中でも、日航123便と条件が類似しているものに’89年2月24日に発生したUAL811便 B−747ー122型機のハワイ沖の事故がある。減圧が発生した高度は約23000ft付近で、123便と近く、機材もおなじB−747であった。 この事故機の減圧発生時の機内の状況は搭乗していた客室乗務員らによって詳細に明らかにされている。
ここで注目すべきは、急減圧発生時に見られた現象について、チーフパーサーのLAURA BRENTLINGERをはじめ客室乗務員らはいずれも異口同音に
機内を強い突風が吹き抜け、紙屑や、雑誌が舞い上がった。客室乗務員も 飛ばされそうに感じた。
ギャレー(キッチン)のドアやカートを上げ下ろしするリフトのドアが差圧により開いた。
気温が急激に低下し、凍えるように寒くなった(FREEZING COLD)。事故調の推定ではー40度まで下がったことになっているがその事実は確認されていない。そんな兆候は全くない。
めまいを感じ、脳は十分働いていない感じだった。酸素マスクのプラグをボトルにつ差し込むことがスムーズにできなかった。この作業を見ていた他の乗員は、まるでスローモーションの画面を見ているようだったと語っている。
機内の騒音レベルは高く、力一杯叫んでも自分自身に聞こえないほどであった。乗客との会話もほとんどできなかった。
一方、123便の例では減圧時の騒音、機内の風、気温の低下は見られず、操縦室と客室の間のドアに強度以上の差圧が加わっていたとの事故調の試算にも関わらず、このドアは開いておらず、ギャレードアなどが吹きあけられたのとは全く異なっている。これらは減圧に伴う空気の流れによって生ずる物理的現象であり、811便にだけに発生するものではないし、個人差があると言うわけには行かない現象で、ドアに設計強度以上の差圧が加わったと推定されるのに、ドアが開かなかったのは、科学的に考えれば、ドアが偶然壊れなかったのでなく、推定に誤りがあり推定した差圧より低かったと考えるのが当然ではないだろうか。事故調の考え方は、非科学的である。
811便は減圧後直ちに緊急降下をしている。それでも酸素マスクなしでは酸欠症状が見られる。騒音で会話や叫び声も聞こえないような811便にたいして、123便ではアナウンスや会話も正常に行われ状況はあまりにも異なっている。
’75年1月15日に発生したナショナル航空のDC−10事故ではCVRの記録に特異な音が記録されていた。この音はダグラス社などで分析された結果この音は「操縦室内の酸素マスク(PRESSURE-DEMAND TYPEと呼ばれる形式の酸素マスクでマスクを着用して吸気するとマスクの内部が減圧する。それに応じて酸素が供給される)から機内の減圧に対応して、酸素が自動的に放出されたために生じた音である」と確認された(資料16)。
5. The cockpit flow noise, which gegan about 10 seconds after the start of the massive failure, is similar to the noise made by cockpit pressure-demand oxygen masks discharging automatically in the 100 percent oxygen mode, This is identification is substantiated with a cabin decompression calculation.
(資料16 DC−10 アルバカーキー事故報告書の一部)
日航で使用しているは操縦席の酸素マスクはPRESSURE-DEMAND TYPEであり、飛行前点検で酸素100%にセットするように定められている。従って、操縦席の気圧が低下した場合には、マスクを着用して吸気したのと同じ条件になり酸素が放出されるはずである。乗員が着用しない状態では酸素マスクから発する音は、マスクの位置等から見て操縦室内の音をCVRに記録するエリアマイクに収録されやすい状態にあるが123便ではその記録がない。
また、エア・カナダのL1011の例は後部圧力隔壁破壊による減圧であり後部にいた乗員が空気の流出音を聴いている。123便ではその記録はない。
以上の通りどこから見てもこれまでの急減圧事故と123便事故は機内の状況がかなり異なっている。事故調の急減圧説は再検討が必要となっている。
急減圧が存在した証拠はあるのか?
事故調が急減圧を推定した根拠
後部圧力隔壁の一部に疲労亀裂とみられる縞模様がみられたこと。
後部圧力隔壁に裂け目と後方への折れ曲がりがあったこと。
与圧室内側に使用されている断熱材が圧力隔壁後方と推定尾翼付近の内部から発見されたこと。
客室内の霧の発生(生存者の口述)。
客室減圧警報が作動していたこと。
プレレコーデッド・アナウンスがCVRに記録されていること。
客室内の酸素マスクが落下していたこと。
以上の7点を挙げている。
他方、急減圧を否定する証拠も少なくない。
異常発生時に乗員らは急減圧と認識していない。
機内を風が吹き抜けていない。
機内に騒音がない。
乗員らは2万フィート以上の高度を酸素マスクなしに18分以上も力を込めて操縦かんを操作していたが、低酸素症の明確な兆候がない。
操縦室と客室の間のドアーが開かれていない。事故調の計算でもこの扉の耐圧を越える差圧が加わったとされているが、CVRにも開いた記録がない。
後部圧力隔壁の破壊が少ない。
断熱材など圧力隔壁の後部に吹き出されたものが、垂直尾翼を破裂させるほどの大量の空気が、高速で流出したとするには少なすぎる(資 料17〜18)。
圧力隔壁に接している後部トイレの壁の破壊が少なすぎる。
酸素マスクの落下、プレレコーデッドアナウンスの作動が不自然。
123便では耳が軽く詰まった程度だが、30万フィート/分程度の急減圧ならば耳が痛くなり鼓膜が破れる例も生じると考えられる。
気温は6秒で65度も低下したと事故調は言うが、その事実がない。
客室の減圧警報と事故調が主張している18時24分37秒の警報音は1秒間しか作動しておらず、離陸警報の可能性が高い。
CVRに酸素マスクからの酸素放出の音が記録されていない。
このように急減圧を否定する事実も少なくない。
(資料 17)写真ー94 垂直尾翼取付部 胴体フレーム(BS2436〜2460)
胴体フレームの間の補強ビームに塊状の断熱材が認められる。と事故調は説明するが、断熱材の量は異常に少ない。
(資料 18)写真ー97 水平安定板センタ・セクションの中央区画
内部の操縦索に断熱材が付着しているのが認められる。
事故調は報告書のほかに、マスコミ関係者に急減圧があったとする「証拠」を挙げている。ここで示されている「証拠」は、次の2点が航空関係者の間で話題となった。
「悲劇の真相」187頁に、[ある事故調査官がこの本の著者に打ち明けて話として「私が急減圧が起きたことを確信したのは、乗客の一人が機内を写した写真を、事故から四日目に群馬県警から見せられた時です」その写真には、天井から客席ごとに酸素マスクが下りており、乗客たちがマスクを口に当てていたのである。]と述べられている。乗客がマスクを吸っているだけでどうして急激な減圧と判断したのであろうか?
急減圧でなくても酸素マスクの落下、乗客の酸素マスクの使用は発生する、どこで急激な減圧と区別し確信したのか誰もが疑問を持つところである。
しかも、この写真を見たのが事故の4日後でありそのとき「急減圧」を確信した事は、この写真が事故調の事故原因の推定に大きな役割を果たしたことになる。ところがこの写真は具体的に明らかにされておらず。報告書の中にも全く触れられていないのはどうしたことであろうか。
「悲劇の真相」187頁によると、河津駅前にいたタクシー乗務員が「ドカーン」という音を聞き、上空を飛ぶ飛行機の尾部から白い煙の固まりを吐き出すのを目撃した。
この煙についてベテラン調査官(名前は明らかにされていない)は「あれこそ、機内の暖かい空気が大量に流出したため発生した大量の霧だった。後部圧力隔壁が破れたため、機内で急減圧が起きた証拠ですよ」と説明したとの記載がある。
これについて、暖かい湿度の高い空気ならば、エンジンの排気ガスのほうが客室の空気よりも湿度も温度も高く、量も大きいのに、飛行雲を引いていたという目撃はなかったのかとの疑問が出され、機内で急減圧があったことの証拠がなく、客室の空気が流れていないことから見て、これは油圧パイプが破断したときに3000psiに加圧された作動油(スカイドロール)が霧となって噴出したと見られる。この点については、CVRの事故調の解読にも、乗員らが「ハイドロプレッシャがおっこちていますハイドロが(航空機関士18時26分00秒)」とあるところから見ても、残骸の油圧系統の損傷状況からも油圧の作動油であることは多くの航空関係者の一致した見方であり、客室の空気と見る根拠は見いだせない。しかも、報告書にはこの「証拠」もまた全く記載されていない。
報告書に記載されている急減圧を推定した根拠について検討を進める。
1.ないし2.の圧力隔壁の破壊などは、墜落時の破壊か、飛行中の破壊か区別できなければ減圧の原因と推定することはできないのは当然である。この破壊が飛行中に発生したか否かは、そのときの機内の状況から推定されなければならない。いかに隔壁に大きな穴があいていたとしても、機内に急減圧の兆候が見られなければそれは異常発生後の破壊とされなければならない。
ここで問題なのは、急減圧であって、単純な減圧ではない。急激な減圧でなければ垂直尾翼は破壊されない。
事故調はこの減圧の程度を約280000ft/min(1分間で28万フィート=約8万5千メーター、言い換えれば、6秒間で8500メーターの山の頂上に-----エベレストの頂上近くに6秒間で-----押し上げられたのと同じ程度の減圧)と推定している。
ここで示されている白い霧やプレレコーデッド・アナウンス、酸素マスクの落下、減圧警報の作動など4.から7.は減圧を推定させる事柄であっても、事故調の推定したような急激な減圧を推定させるものではない。
減圧が在ったことについては乗員も理解できる。これについては乗員もこの事故に関する聴聞会でも緩やかな減圧があったのではないかと口述している。
この点が航空関係者以外には理解しにくい点で、我々が疑問視しているのは単に減圧の存在でなく、急減圧がなかったのではないかとの疑問を呈しているのである。
ここで事故調が挙げている項目のうち急減圧に伴う機内の状況に関する部分についてまず検討してみる。
白い霧は9000ft/minでも発生、急激な減圧を推定させるものではない
霧の発生の条件は、気温がそのときの気圧の下での露点温度以下に気温が低下したときに発生する。霧の発生は事故当時の機内の湿度と、気温の低下が重要な要因となる。
’91年9月12日に、日航のボーイング747ー400型機が、試験飛行中に与圧調整装置の異常から、アウトフロー・バルブ(客室空気の排気口、これの開閉により機内の圧力を調整している)が突然開き、フライトレコーダーによると9000ft/minの程度の減圧が発生した。
機内にはこの時も白い霧が発生している。
この事例は、試験飛行中の出来事であり、機内には搭乗者も少なく、湿度は低く、満席で、真夏の積乱雲の多い気象条件の、日航123便に比べて、霧は発生しにくい条件にあったと推定される。
従って、123便における機内の霧の発生は減圧の証拠ではあっても、事故調の推定したような激しい急減圧の証拠ではあり得ない。事故調や一部の評論家は、減圧の証拠を急減圧とすり替えようとしているように見受けられる。
異常音の直後の警報音は客室減圧警報とは断定できない
事故調の解読によるとされているCVR記録によると(資料19)「どーん」という異常音の発生は18時24分35.5秒で、その1.5秒後に1秒間だけ警報音が記録されている。
(資料19 報告書CVR解読 18時24分の部分)
この警報音が何の警報音であるか疑問である。CVRが極秘扱いにされているため確認は出来ていない。異常音の発生直後の、18時24分38.9秒に、それまで使用されていた自動操縦装置がオフにされている。自動操縦が切られると必ず警報音が作動するようになっているが、このCVRに記録された警報音が客室の減圧警報であるとすれば、自動操縦の警報音が作動しなかったことになる。自動操縦の警報音は停止することは出来ず、それが作動しなかったとすれば何らかの機構上の不具合が生じていたと見られる。しかし、事故調はこの点について十分な検討を行っていない。
多くの乗員が現在もこの警報音は自動操縦の警報音であると考えている。しかしここでは、客室の減圧警報であると仮定して検討を進める。
客室減圧警報の警報音を発する装置は離陸警報と兼用で、地上では安全な離陸に必要な条件が整っていないときに警告する離陸警報に使用され、空中では客室の減圧警報として使用されている。地上と空中の区別をしているのが4本の主車輪の「ティルト」で、空中にあるときは車輪を4個取り付けた台車(トラック)は油圧によって、それぞれきまった角度に保持されるこれをティルト状態と呼んでいる。地上にあるときは機体の重量によって台車はティルトでなく接地面と平行になる。ティルトでないときは機体の種々の機能の状態は地上モードとなる。
問題なのは空中でティルト状態でなくなった場合で、その場合には離陸警報が作動する(資料20)。
(資料20 ティルト状態の車輪の写真)
離陸警報が作動する条件は、3番エンジン(右内側エンジン)の推力を離陸推量に近い状態にしたとき(事故機の異常発生時の推力設定では作動する状態にあった)、フラップ、スポイラー、水平尾翼の位置、車輪の走向装置等が安全に離陸できる状態にないときに作動する。異常発生時にはフラップは離陸位置になく、ティルトに異常があれば離陸警報が作動する条件にあった。
客室の減圧警報は客室内の気圧が高度1万フィートの高度の気圧より低くなると作動する。
この音がどちらか判断するためにはティルトの状態が鍵を握っている。
事故調でもこの音は、どちらかわからないことを前提に諸条件を解析しているが、その中でティルトの状態について、フライトレコーダーの解読に誤りがある。
問題のティルトの状態は、フライトレコーダーの中にサンプル・レート1(1秒間に1回の記録)で記録されており、事故調の報告書の中にも示されている(資料21 DFDRの一部)。
(報告書DFDRのティルトを含む部分とエラーマーク)
しかし、このディジタル式のフライトレコーダーには多くのエラー部分があった。その中で最後まで解読できなかった部分の一つとして、報告書の付録88頁には、「18時24分35秒ごろに連続3サブ・フレームのエラーマークが残った」と記載されている。
1個のサブフレームは1秒であり、3秒間のエラーつまり解読が不正確な部分が残ったことになる。この部分について事故調は、前後のデーターを挿入することによってその間のデーターを推定することができた (報告書 付録89頁)としている。しかし、ティルトの記録は量的なものでなく、ティルトか否かのみの記録であり、前後の記録から推定することは意味がない。
従って、18時24分35秒から3秒間のティルトの記録は解読不能と言うことにならざるを得ない。
その結果、18時24分37秒に頃CVRに記録されていると言われる「警報音」はフライト・レコーダー(DFDR)の記録だけでは、離陸警報か、客室減圧警報かは判定がつかない。
これをあえて客室減圧警報音とした事故調の推定には疑問が残る。
客室警報音か否かを決定するには、その他の条件も合わせて検証し判断しなければならない。そこで次に警報音が客室の減圧警報音であると仮定した場合の問題点を検証してみた。
1秒間だけの減圧警報ならば急減圧なし、日航社内でも調査中
事故調の推定通りに、この一秒の警報音が客室の減圧のものであったとすると何故一秒だけで停止したかが問題となる。
この最も重要と見られる点について報告書は、「その理由を明らかにすることはできなかった」と簡単に述べただけで、解析の努力を放棄している。
一度作動を始めた客室減圧警報を停止させる条件は2つある。一つは客室内の気圧が約一万フィート以下の高度の気圧に上昇すること。第二には航空機関士パネルにある「客室高度警報音停止スイッチ」を作動させることである。
第一の客室の気圧が一度下がって1秒間で再び上昇したとすれば、事故調の考えた急激な減圧は存在しないことになる。そのような減圧と昇圧が生じると、乗客、乗員らに強い鼓膜に異常を感じさせる。しかし、生存者らはいずれも、耳の苦痛は訴えておらず、異常直後の乗員らも通常通りに会話をしている事実から見て、この可能性はない。
第二の機関士が警報音を停止させたとすると、機関士は減圧が生じていることを認識していなければこの操作を行うことはできず、減圧の認識が在れば「ディコンプレッション!」と他の乗員に伝えたはずである。
さらにその後、再び25分04秒から同じ警報音が鳴っているにも関わらず、それを停止させた形跡はない。最初の警報音だけ停止させ、2度目は止めないことは考えられない。
シュミレーターの訓練などである程度減圧警報が作動することが予測されていても、警報を停止するまでには速くとも数秒の時間がかかっている。これは乗員らが訓練でしばしば経験しているところである。1秒間で警報を停止することは極めて困難であり、あり得ないともいえる。
以上の理由から、18時24分37秒から1秒間だけ作動した警報音は客室の減圧警報ではなく、離陸警報として作動したと推定する方が矛盾がない。
事故調は報告書の付録163頁に付図−3に 客室高度及び離陸警報の推定図を示しているが(資料22−1)、何故か異常発生時の記録だけ省略されている。これをFDRの記録に従って訂正すると 資料22−2 のようになる。従って18時24分37秒の警報音は客室高度警報か離陸警報かの区別が付かないとしなければならない。
(資料22−1、2)
車輪に異常 CVRと併せて検討すると離陸警報と推定される
この警報音が記録されている18時24分37秒頃の他の情報を点検すると、CVRに、車輪について乗員が注目している会話が記録されている( ( )内は説明)。
18時24分 38秒・・・(発言者不明)・・・内容不明 ('86年3月28日付け事故調の
作成した事実調査報告書の案では機関士とされていた) 39秒・・・(機長) 「なんか爆発したぞ」(報告書の案では「なんか・・・」
とされていた) ・ 42秒・・・(機長)「スコワーク77」(注 緊急信号)
43秒・・・(副操縦士)「ギアドア」 (車輪の収納部のドア) (機長)「ギアみて ギア」 (車輪みて 車輪)
{44秒・・(機関士)「えっ」(機長)「ギア」(報告書の案のみ記載)}
{45秒・・・(副操縦士)「ギア エンジン」(報告書の案のみ)} 46秒・・・(機長)「エンジン?」 (報告書の案では「オッケイ」)
47秒・・・(副操縦士)「スコワーク77」 48秒・・・(機関士)「オールエンジン・・・」
・ 51秒・・・(副操縦士)「これみてくださいよ」(報告書の案では機長 「・・・これみてみろ」であった)
{52秒・・(不明)えっ (報告書の案のみ)} 53秒・・・(機関士)えっ
・ 55秒・・・(機関士)オールエンジン・・・(不確実) ・ 57秒・・・(副操縦士)ハイドロプレッシャみませんか?
・ 59秒・・・(機長)なんか爆発したよ (最後の「よ」の部分は不確実)
・ 18時25分 04秒・・・(機関士)ギア ファイブオフ(車輪の警報灯は5個とも消えている
・・・車輪は収納されている状態を示す)
この会話から異常発生直後に、乗員らは車輪関係に注目している事がわかる。機長席にいた副操縦士が、車輪収納部のドアに注目しているのは、パイロット側の計器パネルにある「ドア・オープンライト」が一時的に点灯したことを推定する乗員が多い。ライトの点灯を見て、副操縦士が「ギアドア」と他の乗員に知らせようとしたと推定するのが自然であろう。
続いて機長が「ギア見て」と発言しているのは、機関士に対して機関士席の計器板にある車輪関係のアナウンシエーター・モジュウル(車輪関係の警報灯などが集められているパネル)を点検するように指示したものと乗員らには受け取られている(資料 23)。
(資料23 F/EパネルのL/Gアナウンシエーター・モジュウル)
これを受けて、機関士はシステムを点検するためのスイッチを操作して確認した後、25分4秒に「ギア ファイブオフ」と答えており、5本の脚(前車輪と主車輪4本)に関係する警報灯がこの時点で点灯していなかったことを示している。
これらの会話から、異常発生の直後、車輪関係に一時的に異常があった疑いが濃く、この異常発生直後に副操縦士が「ハイドロプレッシャみませんか」と油圧の異常を指摘していること、またDFDRのデータによれば(資料 24)、異常発生時に、上下方向の加速度が、一瞬 +0.75Gに下がり、次の瞬間には、機首が1秒間に4.5度(この時点の速度300ノット[時速約560km]から見ると、極めて急激な機首上げで
(資料 24 報告書DFDR VERGとPITCHの拡大図)
高速で走る車が、突然、道路の段差で飛び跳ねたような状態に類似)に跳ね上げられ、2秒後には元の位置に戻っている。その結果、機体には1秒間で約2Gの突き上げられるような加速度を受け、次の瞬間には+0.25Gまで下がっている。その差は−1.7Gに及んでいる。
このように上下方向に大きな加速度を加えると、車輪の位置に異常を来すことは良く知られており、それに加えて油圧(ハイドロ)系統に異常が重なると、ティルトに一時的な異常が生じた可能性は一層高くなる。
そうすれば、一時的に機体が地上にある状態に切り替わり、離陸警報が作動する。
飛行中ティルトの異常で減圧発生
空中でティルトに異常が発生すると、飛行機は空中にあるにも関わらず地上にある状態に切り替えられるため、操縦系統を始め作動条件が切り替えられる。ここで問題なのは、着陸後客室の圧力が外気と等しくなるようにするために(着陸後、機内と機外で圧力差があるとドアが開かなくなることがある、 ’91年9月19日に発生したノースウエスト航空のBー747ー400型機の成田空港における事故では着陸後も客室の与圧が残っていたためにドアの開放が遅れて緊急脱出に手間取った) 飛行機が接地時に、ティルトが外れ与圧装置の気圧調節をしているアウトフローバルブを自動的に開放し、機の内外の圧力差をなくする。空中でティルトに異常が発生すると、空中であるにもかかわらず、地上と同じ状態になるためアウトフローバルブが開放され、減圧が発生する。
これによる事例が実際に発生している。
ボーイング747ー400型機が、飛行中に車輪を降ろしたところ、ティルトが正常の位置からはずれ、機体が地上モードになったために、客室の与圧装置のバルブ(アウトフロー・バルブ)が開き、急減圧ではないが減圧が発生し、緊急降下を行った事例が発生している。この点については後で述べるが、123便事故でもティルトに異常があれば減圧を伴って、離陸警報が作動する。この事故の状況と一致している点が多い。
さらに、’93年8月23日付けで発行された、日本航空の B−747−400の航空機運用規程に関する Bulletin No,73 は「#1または#4油圧系統の圧力が失われた場合の地上モードの異常について」(Hydraulic System 1or4 Depressurization-Ground ModeAnomaly について)によれば「飛行中Hyd System 1または4(油圧系統1または4)の圧力がなくなると、機体が飛行状態(Flight Mode)から地上状態(Ground Mode)になる可能性があることが判明した。」(資料25)と記載されている。このBulletinは−400型機のものではあるが、車輪付近の構造は基本的には事故機でも変わりはない。事故機の場合は、すべての系統の油圧が失われ、作動油も失われている。その上約2GものプラスGと強い横揺れを受けた状態ではティルトに異常が生じ、空中で地上モードになった可能性は極めて高いと考えられる。
従って、この1秒間の警報音は離陸警報であり一時的にアウトフローバルブ(客室圧力を調整するバルブ)が開いて客室に一時的な減圧(減圧警報が鳴らない程度の、10000ftまで減圧しない程度の)が発生した蓋然性は高い。これは多くの航空関係者が持つ疑問で、この点について事故調や隔壁破壊急減圧説を主張する「学者」、「評論家」などが全く触れもせず検討しなかったのは不自然と見る者が少なくない。
(資料25 −400AOM)
プレレコーデッド・アナウンス(PRA)はいつから作動したのか
報告書では、CVRにPRAが録音されていたのは18時25分15秒、25分53秒、27分17秒と28分15秒から始まる4回だけであったと報告書には記載されている。
減圧時には何よりも先に酸素マスクの着用が必要である。酸素不足による機能低下とそれに続く意識の喪失は全く本人が予見できないため、まず酸素マスクを着用する。客室乗務員も減圧時には酸素マスクを着用する必要がある。そのためアナウンスが不可能であるため事前に緊急用PRAとして事前に録音されたテープを使用する。
緊急用PRAの作動開始は、二つの場合があり、第一には客室の気圧が約14000ftの高度の気圧に相当するまで低下すると、客室内の酸素マスクが使用可能な状態になると同時に、乗客への減圧時の指示を録音したテープが作動し始める。
第二には、左最前部ドア付近にあるPRE-RECORDED ANNOUNCEMENTS PANELを操作することによって開始される(資料26)。
(L−1のPRA操作パネル 客室乗務員訓練教材より抜粋)
事故調の推定では、24分38秒に客室の気圧の低下を検出して圧力スイッチが作動し、PRAが作動を開始したとされている。この123便事故の場合は、CVRの解読によれば、18時24分44秒からパーサーが「酸素マスクをつけてください・・・」とアナウンスをしている。
客室の酸素マスクを乗客が使用できるように、座席上部の酸素マスク収納部のドアを開かせマスクを落下させるのは、PRAを作動させる客室の圧力を検出したのと同じ圧力スイッチによって酸素のバルブが開かれ、はじめの7〜15秒間だけ比較的高い圧力の酸素が客室に配管されたパイプに流され、その圧力によって酸素マスクの収納部のふたの止め金がはずされて、酸素マスクが落下して使用状態になる。そのために、圧力スイッチが作動してから酸素マスクが落下するまでには、かなりの時間を要する。このことは機構的に7〜15秒間やや圧力の高い酸素を流すことから見ても推定される。
試験飛行などでの経験から、減圧状態が検知されてから、マスクの落下までに数秒以上の遅れがあると言われている。
18時24分38秒に減圧状態が検知され、圧力スイッチが作動したのであれば、マスクの落下が5秒遅れるとしても、マスクの落下は43秒頃になる。
従って、酸素マスクが落下するとほぼに同時にパーサーがアナウンスを開始したことになる。一般的には、酸素マスクの落下を見て、それでもPRAが開始されないのを認めてから、アナウンスを開始しようとするはずで、その間多少の時間が必要である。そのうえマスクが出たら直ちに着用するように訓練され、PRAがすぐに始まる事をよく知っているはずの、経験豊かなパーサーが、マスクが落下したと同時にマスクをつけずにアナウンスをするという推定は不自然さが残る。このようなパーサーの行動についてどう考えるか、数十人の客室乗務員に質問してみたところ、
「酸素マスクは落下してきたがしばらくしてもPRAが流れてこなかったのではないか、そこで乗客の安全を考えて、酸素マスクをはずして、自らマイクでアナウンスをしたと思う。」とほぼ全員が答えている。
そこで報告書に示された事故調の行ったPRA開始時刻の推定方法を検討してみた。
事故調のPRA開始時刻に関する推定は、報告書の付録158頁に記載されている。以下はその推定に関する部分をそのまま示す。
[報告書の抜粋]
PRA開始時刻の推定
CVR記録によれば、PRAによる緊急放送は、機長席のトラックに非常に小さな声で録音されていたが、その声は、優先順位の高い客室乗務員(パーサー)の放送によって打ち消された部分や、管制交信との重なりにより聞き取れない部分が多かった。そこで聞き取れた部分(18時25分15秒、25分53秒、27分17秒及び28分15秒から始まる4箇所)から、同緊急放送の開始時刻の推定を行ったところ次のとおりであった。
CVRに記録されたPRAのうち、日本語と英語での放送が完全に1回録音されていた18時27分17秒から始まる部分の録音時間を計測したところ約25.0秒から26.0秒であり、その平均時間は25.5秒で、これは、付録8の1の(1)に前述した録音時間とほぼ一致するものであった。この平均時間を基準にして27分17秒より以前のPRAの回数を算定したところ、付録8の付表ー 2のとおり、この27分17秒より以前のPRAの回数は6回であり、このことから、1回目のPRAの開始は、18時25分44秒頃であることがわかった。
付録8 付表−2 18時27分17秒を基準にしたときの緊急放送の繰り返し開始時刻
事故調の推定は以上の通りである。27分17秒からのアナウンスを何故6回目としたのかその根拠が示されていない。ただ単に、PRAの緊急降下のアナウンス一回に要する時間が約25、5秒であるとして、 27分17秒からのものを7回目と仮定すればPRAの開始時刻が事故調のシナリオに一致する、18時24分44秒になるから7回としたとしか考えられない。
28分15秒から始まるものが最後であるとする根拠もない、第一回目は録音が、パーサーのアナウンスも他機との交信もない間にも、全く録音されていないのに、事故調がその間もPRAが放送されていたと推定するのであれば、28分15秒以降にもPRAがあった可能性を否定できない。
また、報告書では「緊急用PRAは、通常自動的に作動する」として手動による操作を考慮していないが、客室乗務員がマスク着用のアナウンスをするのは、「通常」とは考えられず、客室乗務員がPRAパネルを操作して作動させたことも考慮しなければならない。PRAの終了についても手動による操作も考慮しなければならない。
報告書から見る限り、PRAがCVRに記録されているのは25分15秒が初めてであり、それ以前に、「ただいま緊急降下中、マスクをつけてください」の2つの指示が入っているため、実際にPRAが始まったのはその約5秒前と見られ、25分04秒からの警報音の記録を客室の気圧が10000ftまで減圧した警報音とすれば、それに続いて14000ftまで減圧し、PRAが作動し始めたと見ると時間的にも自然な推定であり、こじつけのような事故調の推定よりも理解しやすい。
酸素マスクの落下はハードランディング以上の+2Gによる可能性も
事故機は異常発生時に、300ktの対気速度で飛行していたが、突然、機首が1秒以下の間に5度も急激に跳ね上げられ、最大1.9G、最小0.25Gと上下方向の加速度の変化を受けている(資料26)。
着陸時にハードランディング(衝撃を感じる着陸)になることがあるが、その場合でも1.9Gもの衝撃を記録することはほとんどない(DC−9等一部の機種では2Gを越えやすいものがあるが、B747は少ない)。1.6G程度でも酸素マスクの収納部のラッチ(止め金)がはずれて、ふたが開きマスクが落下することがある。酸素マスク収納部のドアーのラッチがどの程度のGではずれるかデーターは明らかにできなかったが、乗員らの経験から同型機では2Gならばほとんどの酸素マスクが落下するものと理解されている。
’90年3月24日発生したキャセイ航空のロッキード1011型機の成田空港におけるハードランディング事故では、2.5Gの衝撃が記録された。その結果機内では「数個の酸素マスクが降り、多くのオーバーヘッド・ストウェッジ(天井収納棚)の蓋が開き、また破損した個所もあった。」と報告されている。日航123便で機内の天井付近で破壊が見られたのも、過大なGの結果である可能性が推定される。
酸素マスクの落下が、衝撃によるものであれば、圧力スイッチで作動するPRAが作動しないで、マスクだけ落下することもあり得る。衝撃による落下の場合には、24分35秒ごろ異常発生とほぼ同時にマスクが落下し、それを目撃したパーサーがPRAが作動しないために24分44秒頃にアナウンスを開始したとすれば時間的な経過には不自然さがない。
事故調が推定しているように、酸素マスクが出たが酸素が流れなかったとしたら(酸素が流れているか否かを短時間で判断することは困難、これについては後述)上下の加速度によってマスクが落下した可能性は高くなる。
事故機の1/2,1/3の時間でも機能低下
以上これまで点検してきたとおり機内の状況を見る限り、123便では減圧はあったと見られるものの事故調の推定した程度の急減圧が発生した形跡はない。事故機に急減圧があったとすれば、その機内の圧力は資料28−1に示すように意識を失う危険が高かったことになる。
資料 28−1 各高度における有効意識時間と意識消失時間
この事故に関する聴聞会で乗員らが指摘していたのは、事故機の乗員らが酸素マスクをつけずに20分近くも高度2万フィート以上を飛行し続けていた事実である。減圧があったとしたら乗員には低酸素症の兆候が見られたはずで、それが見られないのは減圧がなかったからではないかという、減圧への疑問であった。
これに対して、事故調は「隔壁主因」説を補強するために、航空自衛隊の航空医学実験隊の減圧室を使って、事故機と同じような形で減圧させその中で9分間は酸素マスクをつけなくてもわずかしか低酸素症による機能低下は見られないと公表した(資料16 読売新聞昭和61年8月7日付)。 事故調は報告書の中で急減圧と低酸素条件下での人間への影響を調査するために、二回の試験を行い、それに基づいて「事故機に生じたと見られる程度の減圧(注 約30万ft/min程度の減圧とそれに続く約20分間の2万ft以上の飛行)は人間に対して直ちに嫌悪感や苦痛を与えるものではない」(報告書115頁)と結論づけている。
事故調の行った試験は資料28のグラフに示したように、事故機の条件とは異なり時間的にも短いものである。
試験1として報告書に記載されているのは、被験者2名が酸素マスクをつけて、8分間をかけて24000ftまで気圧を下げ(事故調の推定は事故機では5〜6秒間で24000ftまで減圧)、その後二人の被験者が交代に、一人12分間だけマスクをはずしたとしている。事故機は20000ft以上の高度に18分以上あったのに比べると2/3だけの時間、しかも急減圧があれば低酸素症が早く現れる事が一般に知られている。このテストでは8分間でゆっくりと減圧させている。これでは事故機に急減圧があっても操縦が不可能となるような低酸素症が生じないとする根拠とは全くなっていない。
(資料28 報告書付録 10 付図2 試験2における減圧パターン)
被験者本人が否定する報告書の実験結果
試験2の急減圧実験は後述の通り疑問がある。この時同時に行われた実験では2名の同乗者が事故機の約半分の時間に当たる10分間だけ酸素マスクをとりはずして高度20000ft以上の中で作業をしたが多少の低酸素症と見られる兆候が見られた程度であったとされている。
その上、報告書では、この急減圧実験では事前に酸素吸入を行い、血液中の窒素を減少させてから実験を行っている。
低酸素症についての実験でも、事故機で発生していると事故調が推定した条件の2ないし3分の1の時間しかテストをしていない。
これだけの実験で、事故機で発生した減圧下でも酸素マスクなしでも意識を失わず操縦が可能であるとの結論を導くのは明らかな誤りである。
試験2の急減圧実験では、被験者1名は酸素マスクを終始着用せず、同乗者3名はマスクを着用し、事故機で発生したと事故調が推定しているのと同じような(約30万ft/min)程度の急減圧、650ftの高度に等しい気圧から約5秒間で24000ftまで減圧させ、20分間にわたり20000ft以上の高度を維持した。
その結果「被験者には急減圧による格別の症状は認められなかった。その後低酸素症と見られる軽度の変化が見られた」と報告書は記載している。
前述したように、この実験の唯一の被験者は、本人が直接日航の乗員らに対して、’86年11月25日、この実験結果について次のように語っている(資料7)。
「実験は650ftの高度に相当する気圧から、24000ftの気圧まで、7秒で減圧させる計画であったが、実際には5.3秒で減圧した。肺の空気が激しく吸い出され、すぐに視野が暗くなるなどの酸欠症状が現れたため、直ちに酸素マスクを着用しなければならなかった。」
この被験者の話は多くの乗員が知っている。
この部分の報告書の記載が事実でないと多くの人が受けとめ、事故調の報告書に強い疑念を抱いている。
航空局の監修のもと操縦士協会が作成したAIM JAPAN(AIRMAN'S INFORMATION MANUL JAPAN)9ー7頁 952[高高度の影響](資料 29)でも、
(資料29)
「20000ftの高度では5〜12分間で修正操作と回避操作を行う能力が失われてしまい、まもなく失神する。」
と明記されている。ところが123便では異常発生(事故調のいう急減圧発生)から10〜12分経過した35分から37分にかけて[EPR(エンジン推力)の操作によりフゴイド運動が若干減少した]と報告書に記載されており、機長らはこれまでに経験したことのないエンジン推力のみによる激しいフゴイド運動の修正操作を見事に行っている。このように修正操作の能力が失われないばかりか、経験したことのないエンジンだけによる修正操作を学習していた。その後も失神せず減圧の影響が見られない(資料30)。
(資料 30 報告書291頁 35分〜37分頃の部分 1/4頁)
公開減圧実験を
事故調は「報告書3.1.11の試験結果にも見られるように個人差はあるものの同機に発生した程度の減圧は人間に対して直ちに嫌悪感や苦痛を与えるものではないので、・・・・」と報告書115頁で述べている。このように事故調の行った実験は、結果に疑惑のもたれている急減圧実験を除いてはいずれも、事故機の条件とは異なって減圧としては軽度の実験であり、その結果をもって直ちに人間に嫌悪感や苦痛を与えないとの結論は出し得ない。明らかに誤りでありこの点は再調査しなければならない。事故調自身が事故機に発生した程度の減圧が人間に対して嫌悪感も苦痛もない程度の危険のないものであると確信しているのであれば、何故同じ条件で実験できないのか、同じ条件では被験者らに意識の喪失などの重大な低酸素症が現れることを承知していたものと見られているのもやむを得ない。
この点については、再度公開で実験することによって、容易にどちらが真実か確認できることであり、公開での実験が不可欠となっている。
日航の機長組合を始め、関係労組が大型機における急減圧について労使で再検討することを要求しているが、企業側は応じていない。
また事故調の所属する運輸省の労働組合も参加している航空関係の労働組合で結成している(1966年2月4日の全日空東京湾事故を契機に結成された)航空安全会議でも運輸省に公開実験を要求しているが拒否されている。
セクション48(圧力隔壁後部)の強度について
ボーイング747型機の胴体最後部の与圧されていない部分はSECTION48と呼ばれている。この部分には補助動力装置(APU)がその中に装備されている。ボーイング社のフェイルセーフに関する資料によれば、APU部分を含めてこの部分の設計最終強度は1.5psiとされている。APUから配管されている高圧空気(PNUEUMATIC AIR)の破損した場合にセクション48全体の破壊を防止するため、フェイルセイフ(破壊を限定させるための設計上の対策)としてプレッシャー・レリーフ・ドアが装備されており、1.0psiの差圧で開放され、セクション48の内圧が1.5psiを越えないように作られている。APUの高圧空気ダクトの破裂によって、1.4psiまで内圧が上昇すると計算され、それにダイナミックファクターとして15%増しの1.61psiの静的最終強度をフェイルセーフ強度としている。
事故調は垂直尾翼の損壊について報告書(107頁)では
[プレッシャーレリーフ・ドアが開口し,APU防火壁が破れて尾部胴体後部から外部へ空気が流出しても、なお尾部胴体前部及びこれと通じている垂直尾翼の内部の圧力は上昇し、圧力が4psi程度上昇した時に垂直尾翼の破壊がアフト・トルクボックスのストリンガーとリブコードの取付部において始まったと推定される。]としながらも[破壊過程の詳細を特定することは出来なかった。]と破壊過程は十分に検討されていない。
垂直尾翼の破壊が、静的内圧4psi程度に上昇した時に始まったとするのであれば、セクション48の強度が1.5psi程度であれば垂直尾翼の破壊以前にAPUを含む胴体最後部が大きく破壊され、垂直尾翼の内圧が4psiに上昇しないことが推定される。
この点についても再検討が必要である。
後部圧力隔壁については、空中で8.66psiの差圧で破壊したにしては開口部が小さすぎるとの指摘が整備関係者や他の急減圧事故例に比較して破壊が少ないと指摘するものが少なくなかった。特に、後部圧力隔壁の後方に噴出している断熱材などの量が、垂直尾翼を数秒で破壊したほどの大量の空気の流れがあったとするには、あまりにも少ない。事故調の試算でも胴体の断面積を19.6m2として胴体内の風速は10m/sとされている。従って圧力隔壁の開口部が1.8m2であれば開口部付近は100m/s程度の速度にならざるを得ない。それにしては報告書の写真94〜98に示されているように、隔壁後方で発見された断熱材は極めて微量でしかない。従って後部圧力隔壁の破壊は空中でなく、山に激突したときに、前部胴体内の空気が胴体の破壊に伴って後部客室内の圧力を高め、墜落の衝撃などにより生じた後部圧力隔壁の亀裂と変形した部分から後方に飛散したものと推定することも可能であり、これを否定できるものはない。
第四章 破壊過程についての考察
破壊の始まりは尾翼か後部圧力隔壁か
事故調の報告書は修理ミスから後部圧力隔壁の破壊、垂直尾翼の破壊、全油圧系統の喪失、操縦不能という筋書きになっている。
急減圧の存在は、改めて公開実験などでの裏付けが必要である。しかし、これを拒否している以上、急減圧はその存在が証明されていない。
後部圧力隔壁から噴出した客室内の空気による垂直尾翼の損壊でなければ、垂直尾翼を破壊した原因は何であったのか検討してみた。
我々はCVRも聞かされず、残骸も自由に見ることは出来ず、FDRのデータも事故調の提供する範囲でしか知り得ない。従って破壊過程を決定的に明らかにすることは出来ないが、乗員や整備士や客室乗務員ら日常運航に携わるものが理解でき納得できる破壊過程についての考察を試みた。事故調の報告書のように現場のものが理解、納得できない分析では安全性向上に何の役にも立たない。
異常発生とその後の経過を考える
異常発生時のFDRのデータをよく見ると、その直前の18時24分35秒の飛行状態は
CAS(補正計器速度)=300.5kt 緩やかに加速中 ALT(気圧高度) =23950ft
PCH(縦揺れ角) =2.5° HSTB(縦トリム) =4〜5UNIT EPR(=エンジン推力)=1.350付近で緩やかに減少中
自動操縦CMD1で飛行中であった。
乗員の目から見れば、この状態は巡航高度に達して水平飛行になったばかりの段階でエンジン推力を減少させつつあるように見える(資料31)。
(資料31 DFDRの拡大図を重ねたものに、CVRの音を重ねたもの)
この状態から異常発生時に一番最初に見られた変化は尾部での低周波振動とそれに続く前後方向の加速度の増加である(資料24)。
事故調ではFDR上で水平尾翼の角度を示すデータが35秒に100ユニットに振り切ったのが最初の変化であるといっていたが、このデータは1秒間に1回記録されているため、35秒から36秒の間に変化したもので、35秒には変化は生じていない(資料33)。
つづいて、操縦かんが中立位置から1秒間で1度機首上げ側に動き、次の2秒間で最大限に近い機首下げ7.5度まで下げられている。
続いて前後方向の加速度が1秒間に4回記録されるデータのうち1つだけが+0.5Gの前方への加速度を示している。 続いて横方向の加速度が最初ひとつのデータだけが(1秒に4個のデータのうち一個だけ)左に0.2Gに振れ、続いてこまかく振動している。この振動は、36秒から約1秒間は2ヘルツの振動数を示している。横方向加速度は1秒4回の割でデータが記録されているので、横方向に2の倍数・・・4、8、12、16・・・ヘルツの振動があった可能性を示している。
これはボイスレコーダーに記録されていた振動、8〜16ヘルツと一致し、この振動が横方向であったことを示している。これは上部方向舵のフラッター周期12〜13ヘルツと一致している。また方向舵の操作量はこの振動と全く対応していない。これらの事実から、上部方向舵のフラッターの発生が考えられる。
注目すべき変化として、続いて垂直方向のGの記録が1/2秒間マイナス側に0.25G程度加わって0.75Gになった後、1.9Gまで跳ね上がっている。その差1.15G程度の変化で、次の2秒間で0.25G近くまで低下し,1.6G以上のマイナスのGの変化を受けている。
異常事態の発生直後に機体が受けた加速度の特徴は、横方向の振動と上下方向の加速度の大きな変化である。
300ノットで飛行中に1秒間に約5°という極めて急激な機首上げが見られる。これが大きな垂直Gの原因になっていることは明らかであり、では何故このような機首上げが生じたかを検討しなければならない。
機首上げが生じるには、エレベーター(昇降舵)を機首上げ側に動かすか、水平尾翼全体(ピッチ・トリム)が機首上げに動く、舵以外に尾部を直接押し下げる力あるいは機首を直接押し上げる力が働くなどの原因が考えられる。異常発生時には自動操縦が使用されており、FDRのデータにはエレベーターが作動した形跡が見られない。水平尾翼のトリムは100ユニットに跳ね上がっているが、これはその速度から見て、実際にスタビライザーが動いたとは見られない。客室の空気が垂直尾翼の先端から噴出したために機首上げの力が加わったことは、客室の中で空気の流れがなかったことから否定されている。
横方向の振動に続いて機首を1秒間に数度も跳ね上げる、あるいは尾部を下に押し下げる大きな力は、300ノットで飛行中であることを考えると、上部方向舵が振動(フラッター)を起こし破壊し、その過程で大きな空気抵抗となればばこの程度の力は生じる可能性が十分に考えられる。
(資料32 下部方向舵上面の傷 1/3頁程度)
海上で揚収された下側方向舵の上面についていた、上側方向舵とのあたり傷(資料32)及び事故以前にも方向舵を動かす力が働くパワーコントロール・パッケイジの垂直尾翼への取り付け部分のストレス・コロージョンによるひび割れが報告されていたことなどから、上部方向舵のこの部分に破壊が起発生したことも推定され、あるいは垂直尾翼の機体への取付ボルトの異常、上部方向舵のフラッターを防止するための8個のマスバランス(バランスをとるための錘)の損傷・脱落、等も考えられる。その結果方向舵にフラッターが生じ、大きな抵抗を垂直尾翼上部に発生させ、垂直尾翼の上部を後方に引っ張る結果となり、機体に機首上げの力を加え、その後破壊・飛散したした。破壊の過程で上部方向舵が空気抵抗により垂直尾翼のトルクボックスを後方に引っ張り、それを倒壊させた事が推定される。
この時に機体に加えられた力は、機体の重心から見ると機首上げのモーメントとなり、FDR上では機首上げ角2.5゜から1秒間で7.2゜まで跳ね上がっている。それに伴って上下方向の加速度(垂直G)が約1.9Gに増加している。1.9Gはたまに発生するハートランディングでもほとんど見られないほど激しい突き上げるような加速度である。次の2秒間に0.26Gまで急激に下がっている。今度は浮き上がるようなGの変化である。後半のGの減少は、突然の機首上げに対して、オートパイロットが大きく機首下げの操舵をし、次の瞬間には、方向舵が飛散し機首上げモーメントがなくなり過剰修正となり機首が急激に押し下げられたものと見ることが出来る。
上部方向舵が破壊飛散する過程で、下部方向舵の上面に上部方向舵のゴムシールによる強い圧着痕を残したと見られる。この圧着痕については事故調は「その発生の経緯を明らかに出来なかった。」としている。
方向舵の破壊の過程で垂直尾翼のトルクボックスを破壊した。同時に4系統の油圧の配管を破壊した。垂直尾翼を支えていた胴体のフレームを破壊し、R5ドアの窓付近を破壊した。これが緩やかな減圧の原因の一つとなった。急激な機首上げに伴う2G程度の加速度と油圧の異常により車輪のティルトに異常を来たし、離陸警報を作動させた。同時に与圧装置のアウトフローバルブを開放する方向に、一時的に動かした。その結果一時的に減圧を生じさせる一因となった。
大きな上下方向のGの変化によって酸素マスクが落下し、減圧による酸素マスクの落下でないためにプレレコーデッド・アナウンスは作動しなかった。それを見たパーサーが自分でアナウンスを開始した。このような推定は合理的で矛盾がなく、乗員には理解しやすい。
CVRに記録されていた低周波振動とその始まった時刻
報告書の付録167頁に同付録の173頁の付図ー7のグラフの分析として、いわゆる「ドーン」という大きな音(18時24分35.5〜36.6秒)に先立って、「ある周波数帯においてこれより前の18時24分35.3〜35.4秒ごろ既に始まっている兆候が認められた。」と明記されている。明らかに、ドーンという音よりも0.1〜0.3秒前から、8ヘルツ〜32ヘルツの間の振動が発生していることになる(資料24、33)。
(資料33 報告書付録9 173頁 全帯域、8ヘルツ、16ヘルツ)
この振動について事故調はこの最初の部分の音は「本体の振動に起因すると思われる大きな周波数変動」と推定し、その原因を「CVRの本体の設置場所の近くで防振装置によって吸収できないほどの著しい機体の振動や激しい空気流が発生したことによるものと推定される」(報告書94頁)と推定している。
しかし、これまでに明らかなとおり、客室内に「激しい空気の流れ」は見られないので、「著しい機体の振動」しか残らない。もしも、振動の原因が空気の流れであれば、「ドーン」の後も空気の流れは存在したはずであり、振動も続いていなければならない。振動は、0.6秒間しか連続していない。空気の流れもその間しか存在しなかったことになる。この振動は、FDRに記録されていた、横方向の加速度の振動と一致する2の倍数の振動を記録している。したがって、この振動は機体の横ゆれによるもので、その原因は方向舵、垂直尾翼のフラッターが考えられる。
「CVRに記録されている大きな周波数変動と最初の音とが同一発生源によるものと仮定すると、両者の時間差と音速から勘案してその発生源はエリアマイクからおよそ数十メートル離れたところになるはずであり、これはCVR本体とエリアマイクの設置位置との距離54メートルに矛盾するものではない。」と事故調は説明している。しかし、「ドーン」という音も地上で聞かれたほどの大きな振動であり、地上の微気圧振動計にまで記録を残した音が音源の近くにあった、CVRに直接影響が出ていないことは考えられない。したがって低い周波数の振動が、「ドーン」に先だって発生していたと考える方が自然ではないだろうか?
エリアマイクの周波数特性は90ヘルツがほぼ下限であり、それ以下の振動数はマイクを通しては記録されないと見られている。従って32ヘルツ以下の振動はマイクから入力されたものでない。CVR本体に大きな振動を与えた場合に、テープに「飛び」が生じないで、その振動が音と同じように、テープに波形として記録されるメカニズムに疑問がないわけではないが、既に述べた通り、急減圧がなかったことは明白であり、この低い周波数の振動が空気の流れによるものでない。
この十数ヘルツという振動は方向舵のフラッター振動数に近い値であり、事故調の推定でも、震動源はCVR本体に近い部分であるとされており、方向舵のフラッターが「ドーン」に先だって生じその直後に垂直尾翼が倒壊したときに「ドーン」が記録されたことを強く推定させるものとなっている。
方向舵フラッターについての考察
方向舵などの舵面のフラッターは、「舵面の剛性や重量配分が原因となって起こる自励振動によるものと、主翼のねじれと補助翼、垂直尾翼のねじれと方向舵、水平尾翼と昇降舵等の間の連成(相互に関連しあう)によって発生する振動で、一度発生すると振幅が増大し構造破壊を招く危険性がある。」と一般に言われている。
この危険なフラッターを防止するために、
方向舵ならば垂直尾翼と方向舵の相対的な運動が生じないように両方の剛 性を高める。ヒンジなど操舵機構にガタが、緩みが生じないようにする。
舵面の重心をヒンジの軸よりも前方にする(そのためにヒンジの前方に錘 「マスバランス」をつける)。
操縦系統・機構の剛性を高めて遊びとゆるみをなくす。
フラッターを抑制する機構を装備する(油圧で操舵し、油圧が失われない ようにする)。
等の対策が行われている。
ボーイング社ではB−747の方向舵についてもちろんフラッターに関するテストを行っている。B−747のような油圧による操舵をしている場合には油圧が正常に作動している場合にはフラッターは発生しにくい。
ボーイング社でのテスト内容はテストは
通常の程度の柔軟性(フレキシビリティー)を持った胴体に約80%のペイロードを搭載した状態で、重心位置は27.8%平均翼弦(MAC)。
水平尾翼と主翼は固定しているもの(リジット)と想定。
翼内のタンクはすべて満タンとしセンタータンクは空の状態。
この状態で、方向舵の振動周波数、方向舵の重心位置とヒンジラインとの関係、空力的ヒンジラインまわりのモーメント、方向舵のねじれ振動周期、垂直尾翼の曲げと引っ張り剛性、胴体剛性等を、一系統の油圧喪失、両系統の油圧喪失、マスバランスの損傷、油圧作動部とその取付部の損傷の2種類の構造破壊と一系統の油圧喪失の4条件の下で調査するためにテストされている。
その結果、方向舵の振動周波数は12〜13ヘルツと算定されている。特に上部方向舵だけはマスバランスを使用してヒンジと重心位置の関係のバランスを維持している。
このテストの範囲では確かにフラッターは減衰することが確認されているかもしれないが、油圧作動部の破壊は他の部分の破壊、例えばヒンジ部分の破壊を誘発する可能性も低くない。また機体の老朽化によって胴体の剛性の低下や、垂直尾翼の胴体への取付ボルトの破損、ゆるみ、方向舵自体の剛性の低下、などと競合した場合のフラッターの発生については調査されていない。
この事故機の機体では、事故前に上下の方向舵のずれが指摘されており方向舵自体、ヒンジ、操舵系統等に剛性の低下が見られていた可能性が高い。
−400型機では上部方向舵を補強
B−747シリーズの最新型である−400シリーズでは、方向舵の舵角が6.5度大きくった(25度から31.5度に変更)ためもあるが油圧の作動筒(アクチエイティング・シリンダー)が1本独立して増加され3本になり、油圧による力を受ける部分のリブ(RIB)が補強され、さらに中央部に桁が一本追加されている。その上、上部方向舵のマスバランスが取り外されている。
下部方向舵については、アクチエイティング・シリンダーの増設はなされていない。舵角の増加が理由ならば下部方向舵にも補強が必要になるはずである。上部方向舵を補強する必要性があったものと見られる。この補強はかなり大きな設計変更であり、方向舵の剛性が高められ、油圧の作動筒の全体としての強度が高められ、一本の作動筒とその関連部分の破壊だけでは、致命的なフラッターの発生を押さえ、操舵不能に陥らないように変更されたと見られる。
この事実は多くの人から、123便事故に対する対策ではないかと見られている。 このような破壊過程に関する推定は、一つの推定ではあるが、多くの事実を矛盾なく説明でき、航空関係者には理解しやすく、納得出来るものである。
これはあくまでも事故調の報告書に示された「事実」とその他出版物に公表された情報、及び乗員らが持っている知識と経験、情報に基づいて推定したもので、乗員や航空関係の現場に携わる者らにとってはある程度理解し納得できるものとなっている。さらにCVRや残骸が公表され検証することが出来れば、より一層真実に近づくことが可能となるであろう。
おわりに
以上述べたように、日航123便事故に関する「事故調査報告書」は肝心なところはその理由を明らかにせず。事故調のシナリオにとって決定的な重要性を持つ急減圧実験については疑惑がもたれており、どこから見ても「急減圧」があったとする証拠はない。「急減圧」の存在を主張されている出版物もあるが、ここで指摘するように、急激でない減圧は認められるが、毎分 280000FTという激しい急減圧を裏付ける事実は今の所見あたらない。従って、当然再調査が必要である。
この報告書の中で、唯一航空関係者の評価を得ているのは、報告書5.2の所見の項に述べられているCVRの改善である。本件事故ではCVRの解読に多くの疑問が指摘されており、CVRの内容の解読がが事故原因の究明に重要であることは衆目の一致するところである。このCVRの改善を指摘したことは評価に値するものとして注目される。
CVRの改善についてはアメリカ・日本では行われていないが、イギリスではすでに改善されたシステムが使用されている。これは「ホット・マイク システム」と呼ばれているもので、各乗務員の席に装備されているマイクロホンの出力を常時CVRに入力されるように配線する事によって、各乗員の会話が明瞭に記録されるだけでなく同時に、操縦室内の音を記録するための、一種の集音マイクとしても利用するもので、多くの費用を要しないで大きな効果を上げている。
機体によっては、この方式と現在日本とアメリカで使用されている解読しにくい方式をスイッチで切り替えて使用できるものもあると言われ、乗員らの同意を得れば、すぐにも改善できる問題である。
真の事故原因を明らかにしなければ、再発防止はおぼつかない。真の事故原因を究明することは人類の利益につながることであり、ここでは誰の責任かは問題ではない。何故事故は発生したのかを科学的に追求し、このような悲惨な事故が再び起きないようにしなければならない。それが520人の命を無駄にしない道である。
http://araic.assistmicro.co.jp/araic/aircraft/download/bunkatsu.html#5
http://www.alpajapan.org/kannkoubutu/genatsu/PRE1.HTM
http://www.alpajapan.org/kannkoubutu/genatsu/PART11.HTM
http://www.alpajapan.org/kannkoubutu/genatsu/PART21.HTM
http://www.alpajapan.org/kannkoubutu/genatsu/PART31.HTM
http://www.alpajapan.org/kannkoubutu/genatsu/PART41.HTM
http://www.alpajapan.org/kannkoubutu/genatsu/END1.HTM
|
|
|
|
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
|
|
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。
|
|
|
|
|
|
|
|