http://www.asyura2.com/09/cult7/msg/607.html
| Tweet |
(回答先: 独占インタビュー 元弟子が語るイエス教団「治療」の実態!! 投稿者 中川隆 日時 2010 年 7 月 11 日 23:15:00)
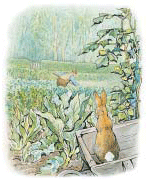
河合隼雄・京大名誉教授はドイツの哲学者オイゲン・ヘリゲルと日本の弓道師範とのエピソードを紹介している。
ヘリゲルは大正から昭和にかけて東北大学の講師として日本に滞在し、五年間、弓道を習う。その様子を書きとめたのが『弓と禅』(1981、福村出版)で、東西の文化の比較を語るとき、広く用いられる文献だ。
ヘリゲルは日本にきて、まず禅を学ぼうとしたが、ある人に止められた。論理的な思考に慣れた彼には禅はとっつきにくい。最初は具体的に手でつかむことのできる芸道のようなものがよかろう、それを通してつかむことのできないものに移っていけばよいから、という理由だった。
彼は弓道に入門するが、師範の指導についていけない。
師範は4つのことを教えた。
1「弓をひくのに、筋肉を使ってはならない」
2「肺で呼吸してはならない」
3「矢を放とうと意志してはならない」
4「的に当てようとしてはならない」
彼は腕を力いっぱい張らないと弓がひけない。見ると、たしかに師範は強い弓をひくときも腕はゆるんでいる。
「呼吸の仕方が悪いからだ」と師範は腹式呼吸を教えるが、「呼吸は肺でするものでないか」「これでも自分は一心に力を抜こうとしているのだ」と彼は反発する。
「いろいろ考えるのがいけない。何も考えずに呼吸だけに集中しなさい」と師範は諭す。
そのうち、やっと1と2はできるようになった。
しかし、3と4はどうしても納得できない。指の自然な放れを待つことができないのだ。
彼は合理的に主張する。
「私が弓を引き放つのは的にあてるため。引くのは目的に対する手段です。意志するな、といわれてもそれはむりです」。
これに対し、師範は
「正しい弓道には目的も意図もありませんぞ!あなたは意志の行わないものは何も起こらないと考えていられるのですね」
と反論する。
腹にすえかねたヘリゲルは
「それでは先生は目隠しをしてでもあてられるのでしょうね」
と言ってしまう。
______________
修行が始まり、ヘリゲルは矢を放つことになった。
しかし、彼は矢を放つ方法が分からない。
-------------------------------
ヘリ「先生、どのように矢を放てばよろしいのですか?」
-------------------------------
-------------------------------
師範「無になって、矢を放つのだ。」
-------------------------------
-------------------------------
ヘリ「えっ!? 無になると言いますが、それでは誰が矢を放つのですか?」
-------------------------------
-------------------------------
師範「あなたの代わりに誰が射るかが分かるようになったなら、一人前だ。」
-------------------------------
-------------------------------
ヘリ「どういうことか、分かりません。きちんと説明してもらえませんか?」
-------------------------------
-------------------------------
師範「経験してからでなければ理解できないことを、言葉でどう説明すれば
よかろう?
どんな知識や口真似も、何の役に立とう?
ただ、あなたは精神を集中し、まず意識を外から内へ向け、次に内にある
意識すらも無くしていくことを努力しなさい。」
-------------------------------
阿波師範の言葉、「無心になって、矢を放て!」。
しかし、ヘリゲルにはそのことが理解できなかった。
そして、西洋合理主義者である彼は、いろいろ考えた結果、「無心」になるため
の何らかのテクニックがあるに違いないと考えた。彼は、阿波師範の矢の放ち方
を徹底的に研究し、そのやり方を真似た。
-------------------------------
ヘリ「これで、師範と同じように射放てる! 恐らくこれが無心なんだ!」
-------------------------------
彼は得意げに師範の前で射放った。
非常によい出来ばえだったので、彼は師範からのお褒めの言葉を期待した。
しかし、師範はそっけなくいう。
-------------------------------
師範「どうかもう一度。」
-------------------------------
ヘリゲルはもう一度、射放った。今度の矢は、最初の矢より上手くいった。
ヘリゲルは嬉しくなって、師範の顔を見た。
すると師範は、一言もなく歩み寄り、ヘリゲルの手から静かに弓を取り、それを
片隅に置いた。そして、誰も居ないかのように、無言のまま座り続けた。
ヘリゲルはその意味を悟り、その場を立ち去った。
ヘリゲルが技術的に解決しようとしたため、師範は深く傷ついたのである。
後日、ヘリゲルは師範に平謝りをし、何とか許してもらった。
〆 〆 〆
それから何年かたって、ヘリゲルは「的」を射ることを許された。
それまでの4年間は、2メートル先の藁束に向かって、射放っていたのだった。
今度の「的」は60メートルも先にある。ヘリゲルは途方にくれた。
-------------------------------
ヘリ「矢を的に当てるためには、どうすれば良いのでしょうか?」
-------------------------------
-------------------------------
師範「的はどうでも良いから、今までと同じように射なさい。」
-------------------------------
-------------------------------
ヘリ「しかし、的に当てるならば、的を狙わないわけにはいきません。」
-------------------------------
-------------------------------
師範「いや、その狙うということがいけない。的のことも、当てることも、
他のどんなことも考えてはいけない。ただただ、無心になるのだ。」
-------------------------------
-------------------------------
ヘリ「無心ですか?」
-------------------------------
-------------------------------
師範「そう、無心だ。そうすれば的が自分の方に近づいてくるように思われる。
そうして、的は自分と一体になる。」
-------------------------------
-------------------------------
ヘリ「的と自分が一体に!? そんなことが、本当に可能なのですか?」
-------------------------------
-------------------------------
師範「うむ。的と自分が一体になれば、矢は自分の中心から放たれ、自分の中心
に当たるということになる。故に、あなたは的を狙わず、自分自身を狙い
なさい。それが出来れば、あなたは宇宙になれる。」
-------------------------------
-------------------------------
ヘリ「無理です。私には理解できません。」
-------------------------------
-------------------------------
師範「弓術は技術ではない。理屈や論理を超越したものなのだ。弓を引いている
自分は宇宙と一体となるべきであり、すなわち禅的生活なのである。」
-------------------------------
しかし、ヘリゲルには信じられない。
______________
何事も理屈で納得しようとする頑迷な弟子を持った師は、このうるさい質問者を満足させるものが見つかるかもしれないとの希望を持って、日本語で書かれた哲学の教科書を何冊か手に入れた(!)。
その後、しばらく経って、師は首を振りながらそれらの本を投げ出し、こんなものを職業として読まなければならない弟子から、精神的にはろくなことは期待できないわけがだいぶん分かってきた、と親しいものに漏らした。
「偶然」が起こるのは、その数年後である。
______________
的に当てることへの執着を、何度師に諭されてもぬぐい去ることのできないヘリゲルに、師がこう言って、
「あなたの悩みは不信のせいだ。的を狙わず射当てることができるということを、あなたは承服しようとしない。それならばあなたを助けて先へ進ませるには、最後の手段があるだけである。それはあまり使いたくない手であるが」、
夜もう一度、来るようにと告げる。
弟子は夜になって師を訪問する。師は無言で立ち上がり、弓と二本の矢をもって着いてくるようにと歩き出す。
針のように細い線香に火を灯させた師は、先ほどから一言も発せずに、やがて矢をつがう。
もとより、線香の火以外の光はない。闇に向かって第一の矢が射られる。
発止(はっし)という音で火が消え、弟子は矢が命中したことを知る。
そして漆黒の中、第二の矢が射られる。師は促して、二本の矢を弟子に改めさせる。
第一の矢はみごと的となった線香の真ん中をたち、そして第二の矢は、第一の矢に当たりそれを二つに割いていた。
「私はこの道場で30年も稽古をしていて暗い中でも的がどの辺りにあるかわかっているはずだから、一本目の矢が当たったのはさほど見事な出来映えでもない、とあなたは考えられるであろう。
それだけならばいかにももっともかも知れない。
しかし二本目の矢はどう見られるか。
これは私から出たものでもなければ、私があてたものでもない、この暗さで一体狙うことができるものか、よく考えてごらんなさい。
それでもまだあなたは、狙わずにはあてられぬと言い張られるか。まあ、私たちは、的の前ではブッダの前にあたまを下げるときと同じ気持ちになろうではありませんか」
この逸話は、のちにドイツに帰った弟子がこのことを『日本の弓術』という講演で語るまで、(師とこの弟子にしか)知られなかった。かつてドイツ人の弟子と、弓道の師との間を通訳した日本人は、講演の速記録を読み、さっそく師にこのことを尋ねた。
「不思議なことがあるものです。「偶然」にも、ああいうことが起こったのです」
師は笑って答えた。
http://readingmonkey.blog45.fc2.com/blog-entry-4.html
上記の対話の成立について、河合さんは非常に興味深いこととして、両者が「半歩ずつ」自分の領域を踏み出している点をあげている。
ヘリゲルは学者らしい慎みを破って「暗闇でもできるのか」と師範に挑戦している。
師範は「正しい弓道には目的も意図もない」と主張していたのに、挑戦に乗って弟子を導く「意図」のために矢を射ている。
両者が自分の土俵に固執していると対話は生まれない。
一歩はみ出すのはそれぞれのアイデンティティが壊れるが、半歩踏み出すのは可能だろう。むろん、対話が成立するまでにはそれぞれが悩み、工夫する時間の経過が必要だ。
事実、ヘリゲルの場合も、途中で、師範と対立し、一度破門にされている。それを乗り越えて対話の成果が生まれたのだ。
現象を虚心にみるというとき、意識のレベル、ということも考えねばならない。
宗教的な修行によって得る体験やビジョンによって、通常の意識より、レベルアップされた状態。これまでは「異常」とか「病的」とレッテルを張られていたものが「意識の拡大」とみられるようになった。
http://d.hatena.ne.jp/kanama/20091006
弓と禅 改版 (単行本)
オイゲン・ヘリゲル (著), 稲富 栄次郎 (翻訳), 上田 武 (翻訳)
http://www.amazon.co.jp/%E5%BC%93%E3%81%A8%E7%A6%85-%E6%94%B9%E7%89%88-%E3%82%AA%E3%82%A4%E3%82%B2%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%98%E3%83%AA%E3%82%B2%E3%83%AB/dp/4571300271
オイゲン・ヘリゲル(Eugen Herrigel、1884年3月20日 - 1955年4月18日)は、ドイツの哲学者。海外では日本文化の紹介者として知られている。
哲学者としてはヴィルヘルム・ヴィンデルバントやエミール・ラスクの下で学んでおり、いわゆる新カント派の系譜に属する。ラスクが第一次世界大戦で戦死した後、ハインリヒ・リュッケルトの依頼を受けたヘリゲルはラスク全集(全3巻)を編纂、刊行した。
大正13年(1924年)、東北帝国大学に招かれて哲学を教えるべく来日、昭和4年(1929年)まで講師を務める。
この間日本文化の真髄を理解することを欲し、妻に日本画と生け花を習わせて講義にやってきた先生の教えを横で聞き、大正14年には妻と共に弓術の大射道教を創始した阿波研造を師として弓の修行に勤しみ始める。
日本人と西洋人のものの考え方の違いや禅の精神の理解に戸惑うものの、ドイツに帰国する頃には阿波より五段の免状を受けた。
帰国後の1936年、その体験を元にDie ritterliche Kunst des Bogenschiessens(騎士的な弓術)と題して講演をする。1941年にはこの講演の原稿から柴田治三郎訳『日本の弓術』(岩波文庫)が、1948年には同じ内容をヘリゲル自身が書き改めたZen in der Kunst des Bogenschiessens(『弓術における禅』)が出版され、ここから更に『Zen in the Art of Archery|Zen in the Art of Archery Zen in the Art of Archery』(ランダムハウス)、稲富栄次郎訳『弓と禅』(福村出版)、藤原美子訳『無我と無私』(ランダムハウス講談社)など様々な訳本が出ている。
ドイツに帰国後、ナチス政権下でエアランゲン大学の教授となり、大学人として成功した[1]が、晩年は苦難の日々を過ごした。その中で彼を精神的に支えたのは、『葉隠』だったという。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%82%A4%E3%82%B2%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%98%E3%83%AA%E3%82%B2%E3%83%AB
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。