http://www.asyura2.com/09/reki02/msg/653.html
| Tweet |
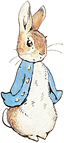
http://www.rekishi.info/library/yagiri/scrn2.cgi?n=1076
ヒミコは美女だったのか
「死せる子は眉目(みめ)よかりき」と古来からいわれるせいだろうか。ともそれば
過去の女性はみな美しかったようにされてしまう。
余りに事故で死ぬのが多いせいか、今でこそそうではなくなったが、かつては夏の
溺死ぐらいしか事故死はなかったので、
「水死美人」といった熟語があった程である。だから、そのせいでもあろう。一生に
一度は美人と呼ばれたいと思う悲しい娘心で、三原山へ行って死ぬようなのもいた。
さて、歴史という過去の具象の中にあっても、人々は細川ガラシャや於市の方を美
女にしてしまうごとく、「ヤバダイ国」のヒミコをも、近頃ではクレオパトラなみの
美女であったかのように、そう願望するがゆえにか決めてしまいたがる傾向がある。
というのもなにしろ男は、女といえば美女しか女性でないような考えをもっている
者が多く、それにヒミコのヤバダイ国には、
「トウマ」「フヤ」ら二十八国が従属していたといわれるから、さながら彼女の色香
にひかれ、それらの国々が従っていたような錯覚すらも持つのだろう。
しかし男王が、そのお妃さまを選ぶのなら、これは自分のために選りすぐりの美女
を探しもしようが、彼女は妃ではなく生涯独身の女王だったといわれる。となると、
「女王」といっても現代のようにコンテスト形式で詮衡されるところの、
「海の女王」や「下着の女王」といった興味本意なものではなかろう。もっと神聖視
され、恐らく神示によったものだから、美しかったかどうかは神のみが知り給うこと
だったろう‥‥
といって日本には外国のような「愛の女神」など存在せず、みな「山の神」とか、
「さわらぬ神に祟りなし」の方だから、本当は恐い顔をした女だったかも知れぬ。
それにどんな人種だったかも気に掛かる。
『日本書紀』にでているウケモチノカミ。そして、『古事記』のオオゲツヒメ、とい
った女神たちは、神殿の燃ゆる紅蓮の焔の中から、呪文を唱えつつ生まれでてきて、
やがて、
(一粒の麦、もし死なずば‥‥)といったように神殿の祠の窟内で惨殺されたその身
体を土壌とし、豊かな五穀の実りを産み出してゆくのである。
さて‥‥これが弥生式土器で知られる紀元一世紀前後の、わが日本列島における水
稲農耕開始時期の、女神のあり方だったとなると、
「ヒミコ」が女王として選ばれていたのも、何も美貌であったからというのが理由で
はなく、死んでからも肥やしがよくきくような、ヒップの大きな、そしてボインも豊
かな女人だったということになる。
なにしろ、縄文中期にかけての時代にあっては、
「より多くの土毛物(つちけもの‥‥土から生える植物)を、豊かに実らせる」
ために、産神としての女神は一定の年令になると殺され、土中に埋められて、そこ
で永遠に呪術をかけておらねばならぬ義務を課せられていたのだから、日本の民族学
では、
「地母神」の名をつけるが、ヒミコも今日考えるような、気楽な女王稼業ではなかっ
たろう。
『魏志倭人伝』には彼女の死後の有様を、
「直系百余歩(百四十メートル位か)の塚へ、おさめた」とある。
だから、ヒミコはヤバダイ国の岡の上に埋められてからも、四方八方に眼をくばり、
休むことなく豊作であれ、との呪文を唱えていた事になるのであろう。
さて、女王となるべき女神が、紅蓮の焔中から、両手を高くあげ、呪文を唱えつつ
生まれてくるというのは、拝火教信仰である。
しかし、そうした部族はツングースにもいるが、彼らは男尊女卑の習俗だったから、
女王を立てるような事はなかったろう。
すると女尊男卑の拝火教徒であったとすると、その種類も限定されてくる。
となると、これは南インドに住まっていて、インド・アーリア人やギリシャ民族の
進攻に追い散らされる迄は、栄えていたヤバンル族ではあるまいか。
二十世紀の今日になると、現地では弱小民族とされて、その後裔は、
「ペラマビグラン山脈」の中に匿れ住むプラヤン族と、南インドで貧民、賎民として
扱われているガダル族らに分かれている。
しかしカルカッタやボンベイでも、この部族の者は、盛り場の雑踏の中で見かけら
れる。私も初めてインドへ行った時は、
(インド人はグルカ兵みたいな巨漢ばかり)と思いこんでいたし、ホテルのボーイも
2メートル近い大男揃いだったので、カルカッタのグランドホテル前の賑やかな通り
で、いきなりズボンを引っ張られたとき、小さいから子供のつもりで振り向いた処、
鼻下に堂々たる八の字髭をつけているのには面喰わされた事がある。
さて、その小男に引っ張られ連れて行かれた処、これまた小柄な女性がいて、それ
が無言のままで捲くった個所には、身体つきには不似合いな立派な顎髭みたいなのが、
もじゃもじゃ生え茂っていて、さすがに無気味になってこそこそ退散してきた事があ
るが、そのとき、
「Kadar族か、Pulayan族なのか」
うっかりして聞き漏らしてきたが、そのどちらにしろ紀元一世紀前後は、南インド
から今のマレーシア、そしてベトナムにまで分布し、栄えていたヤバンル族の末裔に
相違ないのだから、異によると、「ヒミコ」というのは、彼女と同じような矮小民族
ということになり、それゆえ、魏国や漢国から、「倭小の国」つまり「倭国」といわ
れていたのではあるまいかとも想像される。それに、
「ギリシャ史」では、
「紀元前521年に生まれたペルシャのアケメネス王朝のダレイオス王が、インダス
河右岸を占領していた頃から、ギリシャとは交易があり、紀元前327年にアレクサ
ンドリア大王が、ギリシャ軍の精鋭を率いてインドへ攻めこんだとき、矮小民族は現
在のベトナムに当るチャムパー(ギリシャ名カテイガラ)へ送ったところ、東方海上
へ筏で逃亡した者が多かった」
となっていて、明治時代に故木村鷹太郎が、「日本の上代語にギリシャ語が多く混
じっている点、そして、ギリシャ人がヤバンルとよんでいたのが、現代のゲルマン民
族の日本への呼称のヤバンとなっている点‥‥この二つの理由から、日本人というの
は、ギリシャ民族を祖先にするものではあるまいか」
と発表して明治の学界を沸かせたが、どうもヒミコは、ギリシャ人に追われて日本
列島へ漂着した矮小民族‥‥女神崇拝族の中で、呪術つまりシャーマンにたけた女人
優位のヤバンル族ではなかったかとも、帰納できるようである。
さて従来の歴史の常識で、
「倭=やまと=大和朝廷」とみてゆくと、ヤバダイ国やヒミコの実像も判らなくなる
が、別個に分けてしまい、
「倭」は文字通り、アフリカのピグミーに比べれば大きいが、それでも平均身長以下
の矮小民族とみれば、後に天孫族と同化混血したとしても、その当初は、後のヤマト
民族とは異質のものと、はっきり区別がついてくる。
そうなると、私がカルカッタで連れこまれて逢ってきた女性に、かつてのヒミコ女
王も似ていることになるのであろう。
しかし伴っていった小男の八の字髭と、その女性の小学生のようなあどけない肢体
には、似つかわしくない茂みにばかり気をとられ、どうも肝心な顔の方の記憶が残念
ながらないのである。
とはいえ、もしもあまり容貌がひどかったら、拡げる前にさっさと退散してきた筈
だから、まあ十人並みというか、眼のぱっちりした、こじんまりとした美少女タイプ
だったような気もする。
インドのアッサム地方のナガ族の女は、それ程までには色も黒くなく、顔だちも日
本人とそっくりとよくいわれるが、私のみてきた小柄な女性も、そういえば日本人に
似ていた感じもする。だから、
「ヤバダイ国のヒミコ女王」というのは、今でいえば、
「トランジスター・グラマー」といった可愛いスタイルだったらしい。が、それがま
だ紀元の始まる前の未開発時代だったとはいえ、
「地母神」「産神」の名をつけられ、岩戸の中へ閉じこめられ、
「五穀豊穣」の祈願のためにそこで殺され、「呪詛の案山子」みたいに大地へ埋めら
れたのかと想うと、
(いつの時代でも女上位などというのは、うまく女を操り利用するための、男共の策
謀)といったような気がしてならない。
とはいえ、なんといってもヒミコが吾らにとって、母なる大地のような存在だった
のだから、いくら生涯独身であったと伝えられても、その子宮に吾らの内なるものの
繋がりを見るしかないと想われるのである。
日本人の原点は‥‥
日本列島とよばれる地帯に住む吾らは、日本人とよばれ、何処の土地へ行っても、
その日本人という肩書きからのがれられないのは、立場を置き換えれば、さながら猫
に生まれたのが、いくら顔を尖らせてみても、犬とは認められないように、ひとつの
定まった宿命的なものでもあるらしい。つまり、「脱・日本」はできえたにしても、
「脱・日本人」というわけにゆかぬのである。
そこで海外へ出ると、どうしても、日本人とは何かと考えさせられてしまう。
何故かといえばヨーロッパの国々は陸続きのせいか、スイスなんか国民の半分以上
がドイツ系で、別国人といってもそうはっきりした見分けはつけにくい。が日本人と
きたら中国人と間違えられはするが、吾ら自身においては、あくまでも日本人以外の
何物でもないでのである。
つまり時には同じような黄色人種だというので、同一視されることがあっても、
「ウイ」とか「ヤア」とそれに対し面倒くさいからと、答える日本人はいない。
行きずりの異邦人に間違えられたとて、格別どうという事はないのだが、誰もがむ
きになって日本人であることを主張したがる。
潔癖といってしまえばそれまでだし、日本人としての自負や誇りからだという人も
あるだろうが、どうもそうではないらしく、もっと内なるものの反撥によるのでは有
るまいか。
それは愛国心にも結びつくものだろうが、日本人は日本人であることに時には勇み
たち、また時には悲しがったりもする。
となると、その原点は何にもとづき、それは何に由来するのかといった疑念さえも
浮かぶ。
吾々はそうしたとき、それへの解明に、
『古事記』をひもといたりする。もちろん、それはいわゆる神話の世界である。
イザナギ、イザナミの男女二神が、
「この漂える国をおさめ作り固めをなせ」
と大詔を拝して天降ってきたという物語に対し、同じ神話でも、
(アダムが肋骨の一本をとってイブをこしらえた)とする、なんか不自然な人間第一
号よりも、同伴で空から舞いおりてこられた方に、身びいきであろうが親しみをもつ。
蛇に教わって林檎の実をかじってから、さながらプレイのように男女の営みを始め
るのよりも、そうした行為は、お国の為であり、「人的資源」を確保する報国作業で
あるのだと、きわめて愛国的に、かつて教え込まれた私どもには、
「わが身はなりなりて成りたらざる所が一処あり」と、受け入れ体勢をとられる女神
の方が遥かに日本的であり、そして、その意味をすばやく汲みとって共に協力して人
的資源の増産に励まんと、雄々しくも男神もそれにうなずかれたまいて、
「わが身はなりなりて成り余れる処、一所あり、その余れる処もて、その余りたらざ
る処をおぎない、埋め合せを致さん」
きわめて論理的に考えられ、人的資源開発よりも領土拡張と先に大八州(おおやし
ま)をその行為によって産み出されるのだが、これの方が情緒がある。さて、とはい
うものの、
「女人が先に口をきくは良からず」と男神が咎められ、その最中にできた第一子は葦
船へ入れ流してしまい、産児制限の皮切りになされたというのは、どうみても男尊女
卑思考である。
となるとヒミコが君臨していた頃の耶馬台国八幡国家群とは、まったく違った大陸
系の男権国家がそれにとって代わってから、これは作られた神話ということになるの
でもあろうか。
そして、それらの人々は何処から移住してきたか、北方説や南方説がいりまじって
いるが、そちらをとるべきであろうか迷わされる。
早大の水野裕教授は、栃木県葛生町で発見された葛生原人や、豊橋市牛川で見つか
った牛川原人、そして静岡三ヶ日町で発掘された三ヶ日原人らの骨にもとづく旧石器
時代人が、日本列島の地質学上では、洪積世の後期に当るから、それらの原人を、
「約十万年前か、もうしこし古いもの」とみなし、そこでこれを、
「ヨーロッパ旧石器時代人の一種ネアンダルタール人に、それら日本原人は類似して
いる」ととき、
「血液型でみると、南方民族系のO型が日本列島には一番多く、ツングース系のB型
が北海道から東北、特に裏日本から中部山岳地帯に多く、それに朝鮮型A型が中国や
四国、九州に分布しているから、日本人というのは、原(土着)日本人に、アイヌ、
ツングース、インド、インドネシア、苗族などが、新石器時代からの長い期間に、局
地的に断続的に混血をくり返しつつ合成されたものであろう」
と、日本人が混血人なのを明らかにしている。が、それに対して、
「日本人は純血な単一民族である」としたがる傾向が、戦争中などは露骨で、挙国一
致体制といった掛け声から、すべての日本人は、
「源平藤橘」の四姓によって構成され、根本においては、その発生源は唯一つである、
と歴史家もとき、そして、
「われら日本人はみな純粋に神の子である」と教えられていたものである。
しかるに敗戦となってGIが続々と入ってきて、各地の日本女性から、眼色毛色の
変わった赤ん坊が次々と生まれだすと、話はまた違ってきてしまい、
「混血こそ優良人種を生むのである。かつて明治の先覚者森有礼は、日本女性をヨー
ロッパへ送って種つけして貰い、日本民族の改良を計ろうとした程である」
とまでいわれるようになって、巷ではジュースまでが当時は、
「ミックス・ジュースもできます」と喫茶店の看板になった程である。しかし一般の
心情としては、
「うちの娘が混血児をうんでくれて、めでたい」という改良思想家ばかりではなく、
大磯の沢田美喜女史の手を煩わすようなものも多かった。
つまり一般の日本人は戦前のごとく、まだ、「まじりっけなしの大和民族」であり
たい願望からか、心情的に日本人単一民族説をとく者もいるようである。
もちろん、これは江戸時代からも、林羅山によって、
「中国の史書に、呉の太伯の後裔が日本人という説があるから、われらは南支那から
集団できたのである」といわれたり、
「秦の始皇帝のとき、不老長寿の妙薬を求めにきた除福の子孫が吾々なり」と云いふ
らす者もあり、「萩生徂来」の名を、あちら風に、「物徂来」とかえてしまう学者す
らもいた。また、明治になってからも、
「義経はジンギスカンなり」を発表して一世を風靡した有名な小谷部全一郎も、日本
人はユダヤ人なりと、東北八郎潟湖畔の遺跡をもってして、そこに残されている十字
架の墓碑や、ヤコブとかヨハネといったユダヤ系の名に、今も発音が似通っている人
名をもって、その裏書として発表した。
しかし、そうした用語の発音の類似という点で、大和民族が他から一括導入された
という説をたてた者には、明治時代に、
「ギリシャ語」の日本語の共通点の多さから、日本人はギリシャ民族が東行したもの
だと、木村鷹太郎が提出し、大正時代にはアナーキストの石川三四郎が、今のイラク
に当るメソポタミア人をもってする「シュメール起源説」をとなえた。
(これは今でも一部の研究者の手によって、菊の十六枚の花弁は、イラクにだけかつ
て有ったものであると、日本イラン文化研究会の手で、現地でいろいろ調査が続行さ
れている)
『万葉集の謎』という本をもって、昭和に入ると安田徳太郎が、
「ヒマラヤ奥地のレプチャ人こそ、古代日本人である」
と、『万葉集」に残された日本古語とレプチャ語の比較研究を発表して、おおいに
世評にのぼったのも、まだ記憶に新しい。
他に、目ぼしい説をピックアップすれば、
田口卯吉の「古代日本人匈奴起源説」堀岡文吉の「天孫族マライ渡来説」がある。
これは、日本人の常食の米は世界各地で産するが、その稲の品種がみな違い、日本
稲と交配し実を結ぶ稲の原産地は、南方シナからインドシナ半島方面、つまり現在の
マレーシアに限られている点からして考究されたもので、
(吾々の食する米の原産地がマライ半島なら、その稲を日本列島へもちこんで来た人
種も、またマライ系でなくてはならぬ)
とする説で、これに関しては、
「古代人種にとって、もちろん動物においてもそうであるが、塩は欠くことのできぬ
必需品であった、だから各々その伝えている製塩技術をみると、民族の根源が判る。
さて日本式と同じような製塩技術方法をとっている所は、世界中何処を探しても南シ
ナ海沿岸だけで他にはないのである」
と、海水学の権威、杉ニ郎は、この日本人マライ説に賛成し、言語学専門の大野晋
は、やはり日本人の原点に関し、
「指示代名詞コ・ソ・カ(またはア)が配列正しく順をおって応答される言語、つま
り日本語と同じ文法のもとにある言語は、インドシナのベトナムから、マレーへかけ
て住む人種のみ、限定され今なお使われている用語法なのである」
と、やはりこれを裏書きしている。そして彼は、
『日本語の起源』の著において、
「琉球の方言、なかんずく首都那覇の方言の母音たるや、これは本土の共通語母音と、
明白な対応関係をもっている。この点から考察すると、那覇語こそ日本語の母胎をな
すものともいえるのである」
といった意味のことをのべ、
「沖縄・高天原説」のような思考を展開させているが、学界からは黙殺の態度をとら
れているらしい。
しかし、これは別に飛躍した説でもなんでもない。妥当と考えられもする。
なにしろ、その那覇周辺には、
「久米部族」とよばれるのが明治までは住みつき親衛隊となり、
「鎖(さし)の側(かわ)」とよばれて、中山王宮を取り巻き、守護していたのであ
る。(サンケイ刊「サムライ無宿」に詳しく書いたが)彼らこそ、『古事記』や『日
本書紀』に多少の字句の相違はあるにせよ、はっきりと、
「みつみつし久米が子らが、根もとに植えしハジカミ口ひくく(辛く)吾は忘れじ、
撃ちてしやまむ」
とでてくる久米の子の末裔でないなどと、いいきれないからである。なにぶんにも
本土の方では、その久米の子らは、どうしたことかその後は何も現れてこず、ただ、
「そらを飛んでいた久米の仙人なるものが、たまたま川で洗濯中の女人の胯間が水面
に映るのを見かけ、それと女の脛の白さに眼がくらみ、あっという間もなく神通力を
失い落下してきた」
といった艶笑小噺の中でしか伝わっていないのである。が、
「唐栄」ともよばれた鎖の側の久米部三十六姓の者達は、
「尽忠」をその部族の掟としていた。だから、明治十年五月、当時病臥中の尚泰王が、
明治政府の手によって東京へ運び去られようとすると、
「尊王の大儀」に彼らは一斉に蹶起した。
これまでは王家の安泰のためには、薩人の横暴にも堪えていたが、もはや我慢はな
らないと、「勤王攘夷」のむしろ旗をたて、久米の者らは見を挺して王宮の周りに、
今でいうピケをはった。そして部落から荒れ狂う南支那海を山原(やんばる)船で、
当時の清国へ助けを求めに出かけた。
もちろん内海外海日本の警察隊が包囲していて、彼らは次々と沈められた。それで
も尊王の大儀に殉ぜんと久米の子らは死を覚悟で密航した。
彼らが清国へ救いを求めに、悲惨な脱出行をしたのには、それなり理由がある。
なにしろ彼らにしてみればクマソ同様にみていたハヤト族のサツマ人に慶長十四年
に攻撃され、そきの中山王尚寧が捕われたあと、島津家の占領下におかれ苦しめられ
たので、その後は、いわゆる、「やまとぶり(日本風)は一切せず、「唐栄」とよば
れていたごとく、中国語しかしゃべっていなかったからでもある。
ということはまた、取りも直さず後述する崇神朝の騎馬民族は、ツングース系で朝
鮮経由で馬をもってきたものならば、この久米の子の沖縄とは無関係になる。つまり、
「久米の子ら」が守り奉った天孫系の方たちは、陸路をあまり通らず東支那海を春か
ら夏に吹く風にのって、つまり貿易風の黒潮暖流にのって日本列島の九州へ渡られた
ことになる。そしてそこから内海を大和に向かい、熊野、伊勢へ御東征の軍を進めら
れたものである。となると騎馬民族でない唐ぶりの王朝系にとっては、やはり沖縄こ
そ、それら日本人の原点ということに間違いなくなる。
日本武尊妃は朝鮮美人
景行帝の第二皇子で西暦前八十二年に御誕生、十六歳で九州へ熊襲征伐に向かった
際、単身女装して敵の巣窟へのりこみ、
「オウスノミコト」という名前だったのを、そのとき仕止めた敵の首領が、苦しい断
末魔の息の下から、
「オウスとかチャウスというのは何ですから、これからは、どうか、ヤマトタケルと、
お名のりくださいますよう」
と頼まれて、その名にかえて大和へ戻った処、またしても、すぐ東征の命をうけた
ので伊勢へ途中立ち寄られて、伯母の、
「ヤマトヒメノミコト」から剣を貰った。
おかげで隠れていた敵に荒野で包囲され野火をつけられ、危うく焼死しかけた時も、
「おのれッ」と、その宝剣で草を薙ぐと、火勢はあべこべに敵の方へと向かってゆき、
これには向こうが逆に周章狼狽してしまい、
「あつい、あつい」と降参し、めでたく彼らをみな帰順させる事に成功したので、そ
の時よりこの宝剣に、「草薙剣」と命名したが、相模の国から海上へ東征の舟旅を進
めると、折りから一天俄かにかき曇り大暴風雨となった。そして、「もはや舟は沈ま
んとす」という有様に荒れ狂ってきた。
見かねた御妃の弟橘媛(おとたちばなひめ)が、夫のみことを救い奉らんとして、
「さねさし相模の、小野にもゆる火の、ほなかに立ちて呼びし君はも」
の詠草を残され、怒涛さかまく大海原へ身を挺し、
「海神の怒りをしずめん」と、飛びこまれ海の藻屑とならせられたもうた話は、
「日本女性婦徳の鑑(かがみ)」として今も広く知れ渡っている。なのに、その弟橘
媛が朝鮮の御方であったとか、また、
『フロイス日本史』によれば、安芸の宮島の祭神である女神三柱も朝鮮の御方だとい
われるのも、みな結びつきあって、どうもそこにはやはり繋りがあるのではなかろう
か。
『記紀』にみえる「日本武尊」は、今では歴史家も公然と、
「神話の中の架空の武人である」と定義している。
だから架空の方の御妃が、日本人でも朝鮮人でもまたはインド人でも差し支えない
ようなものだ。
が、そうした説が生まれてきたのは、なんといっても、
「さねさし」という相模にかけた御歌の枕詞が、はっきりした朝鮮語だったせいでは
あるまいかと想われる。
「さね」は「中心」の意の朝鮮語で、後には日本語の核という字にあてられ、女性自
身の中心部のことをいうようにもなるが、だからといって、
「さねを指し」という淫らな意味ではなく、この「さし」は「城」の意味である。
後には今の東京都と埼玉県を併せた地域を、「武蔵(むさし)」というようになっ
たが、初めは、そうよばれたのは『国造本紀』によれば、今の埼玉県であり、「胸刺
(むねさし)」と東京都の方は区別して呼ばれていた。
「むねさし」「むさし」共に「宗城」「主城」の意味だが、「むね」も後には日本語
となって、戦記物などにはよく、
「宗徒(むねと)の面々、集まり候え」などと出てくるものだし、また、
「徒然草」の中などでは、「家の作り方は夏むきを、むねとすべし」などと出ている。
が、朝鮮語でもなにしろそちらが原語ゆえ、宗(むね)であるのが正しかろう。
「む」一字きりの方も、三省堂『古語辞典』などでは、
「上代語・『み』が他の語と合して熟語を作る時の形」
となっているが、朝鮮語では、「正しい、正真正銘」の意である。
‥‥ということは、日本武尊や弟橘媛の話は、神話の中の架空のヒーローやヒロイ
ンであったにせよ、その当時の東国は、
さねさし(中心城)と称する神奈川県
むうさし(正真城)と名のる東京都
むねさし(主たる城)という埼玉県
の三つが並んでいたことになる。つまり三つの地域が、
(自分の所こそ、正真正銘の宗城である)と、いわば本家争いを、互いにしていたの
が証明される。
こういう例は、たとえば越(こし)の国が、
「越前、越中、越後」と三分されて併立したように、吉備の国が、
「備前、備中、備後」となり、他にも、「陸前、陸中、陸後」といった例も今に伝わ
っている。
では、なぜ三分されて名づけられているかを推理すると、これは、かつての朝鮮が、
「馬韓」「弁韓」「辰韓」と、三韓になっていたり、後にも、『新羅(しらぎ)』
『高句麗(こうくり)』『百済(くだら)』と三つになっていたから、その三方面よ
り渡航してきた者らが、「当方の出張所のある地域こそ、本当の正しい土地である」
と競合して、そうした呼称をしあっていたのではあるまいか。
というのは、わけがあるのである。
なにしろ、それまでの日本は倭国とよばれたごとく、女王をたてて小さく各地に群
居し、実際の戦いよりも悪霊を押しつけあう呪詛であけくれしていた。
だから騎馬民族が大挙して攻めこんでくると、彼らは驚き、
「大変だ。身体の大きなのが、四つ足に跨って攻めてきたぞ」
というだけで、すぐさま騎馬民族に対し、
「恐れ入りました」と帰順してしまったものらしい。しかし、その後か、はたまた、
その前に久米の子らを従えて、海路進攻してきた天孫族が既にいたものなら、
「おのれ、くるか、いざまいれ」と抗戦したものの、船できて馬のない彼らは戦い利
なく破れて、また船にのって沖縄の方へ戻ってしまったものなのか‥‥
もはや今となっては判りようもないが、西暦紀元前から一、二世紀の間に、船にの
って逃げもできず踏み止まった久米の子らの残党や、倭人たちは、一応はみな騎馬民
族によって征服されたのだろう。
処が、その混乱に乗じて、この時、海の彼方の三韓が、
「日本よい国」とばかりに兵をむけ、部分的に占領して、各自勝手にコロニーをひら
き、関東を例に引けば、
「むさし国」は大宮の氷川神社が、彼らの持ちこんできた祖神。
「むねさし国」は、多摩郡八王子日野の大国魂神社がそれで、
「さねさし国」は、後の箱根権現を、その祖神を祀る神廟として、勧請してきて祀り、
信仰していたのである。
「青丹よし奈良の都は咲く花の」とよばれる「ナラ」の言葉が、朝鮮語の「国」を意
味するという程だから、日本へ渡ってきて落着いてしまった朝鮮人の勢力は、侮り難
いものがあったのだろう。
「人皇五十代光仁天皇は、四十七代の女帝孝謙帝御妹君の井上内親王の御聟であらせ
られたが、当時河内の平野郷に住まっていた朝鮮系の高野新笠がうみ奉った桓武帝が、
その死後に代られると、未亡人の井上皇后は太子と共に吉野の山寺へ押しこめられ、
そこで食を絶たれたもうて餓死させられた」
と、久米邦武は、この時代のことをかいている。
そして桓武帝をかつぎあげた朝鮮系が、宮中をすっかり押さえてしまったので、帝
の後宮は、女御として、
「クダラ王教法媛」「クダラ王永継媛」
そして女官長に当る尚侍(ないしのかみ)に、「クダラ王の娘教信」、その次長に
「クダラ王明信の娘」「クダラ王教仁姫」「クダラ王貞香娘」
さながら今日のキイサンクラブのごとく、クダラの女官が御所の後宮を取りしきり、
この後の嵯峨天皇の御代も、
「女御はクダラ王媛貴命」「尚侍はクダラ王慶命媛」と変らず、人皇五十五代の仁明
帝の代でも、クダラ王永慶媛があがっていた。
帝の御側近が朝鮮の百済の姫たちばかりゆえ、御政務を補助する文武百官もこれみ
なクダラ人が、その重要なポストを占めていたことはいうまでもなく、桓武帝延暦十
年の、「官符」の冒頭に、
「正月十八日、百済王御哲、坂上田村麿をもって東海道に遣しぬ」
の個所さえみられる。坂上田村麿も、父は参議をつとめていた外来人の当麿の子で
あるというから、この部隊はクダラや東南アジア系の人たちの集りだったらしい。つ
まり、この時代は、
「朝鮮のクダラ人にあらざれば、人にあらず」
といった様相さえ示していたのだろう。そこで、
「彼奴はクダラでない」というのは、取るにたらない存在だったものらしい。これは
西暦八世紀の話だが、今でもよく、
「彼奴はクダラでねえ‥‥くだらねえ」と、吾々が人をこきおろす時に用いるのも、
その頃の名乗りの用語法なのであろう。えらいものである。
だから、よし架空のヒロインであれ、オトタチバナヒメも、クダラでなくては話に
ならぬし、クダラないから、朝鮮の女性として伝わってきたらしい。
http://www.rekishi.info/library/yagiri/scrn2.cgi?n=1077
高松塚古墳はカマクラ(住居)か
日本は万世一系の国だが、株主総会で役員が変るごとく、王朝も天(あま)の朝は
天照大神を最後に、崇神、仁徳、継体と変遷がある。
さて、高松塚古墳が作られたとみられる飛鳥朝の欽明、推古期は、六世紀の後半か
ら七世紀へかけてである。
その欽明朝は、継体帝第四子天国排開広尊だが、もちろん上にアマの字がついても、
これは『日本書紀』を作った藤原体制の都合での命名で、天の朝とは無関係である。
なにしろ日本列島は、この時代から、
「世の中が変わった」という現象を示し、仏教が入ってきたり、唐風にすべてが変り、
「弁髪」と称して男でも豪い人は三つ編みのお下げを、だらりと垂らしていたから、
「‥‥長い物には巻かれろ」とする日本人的精神が地下(ぢげ)人達の間にここに芽
生え、今でいえば英会話学校のようなのが出来て、そこで、会計や計算を、
「イ、アル、サン、スウ」とやったものらしい。
今日でも数の数え方を、「算数」とよんだり教科書のタイトルにするのも、その頃
の名残りである。もちろん若い人は物覚えが早かったが、中年以上の者はそうはゆか
ず、といってカンニング・ペーパーを作ろうにも紙があまりなかった時代なので、木
片を削って、
「何であるか‥‥シヨマ」「判りました‥‥ミンパイ」「早く‥‥カイカイジー」
などと、会話早判りを細かく書きつけたものを、みな持ち歩くようになった。
しかし、あんまり大きなのを担ぎ廻っては後の主婦連に間違えられるから、その範
囲を一坪つまり3.3平方メートルの百分の一以下に定めて勺(しゃく)とよんだ。
今では何坪何合何勺といった使い方をされ、木片の方は「笏(しゃく)」の字が当て
られている。イチイ、ヒイラギ、桜といった書き直しに便利な削りやすい物ばかりだ
けでなく、竹の太いのも使われていたのだろう。
しかし明治になると、この笏のすこしの大小でも問題になり、「爵位」となって、
お公卿さんは公、侯、伯、に分けられ、旧大名は子爵となった。
さて、高松塚古墳は、ちょうどその頃のものゆえ、壁画のカラフルな美人画が、カ
ラ風(ふう)な下ぶくれ型であっても別に可笑しくない。
しかし、藤原氏は天下を握りだすと、
「カラ=唐」という用語は禁じてしまい、
「韓=カラ」と呼ばせるようにしだした。
いわゆるカラ神と称されるのが、高句麗系だったり百済のであるのはこのせいであ
る。
そしてカラを韓にすり替えただけでなく、「漢」の字も、天の朝に似通ったアの発
音をつけてアヤと称せしめた。『延喜式』などの「今来漢人(いまきあやひと)」も、
漢つまり唐から来たばかりの新知識というのではなく、百済人をさして用いている。
つまり作成者の都合で、カラはすべて、みな唐ではないように書かれている。では、
日本史で彼ら自身のことは何と自称したかといえば、そこは漢字の国の出身ゆえ、
「トウはトウでも、藤」としたものらしい。
うがった見方をすれば、春夏秋冬季節の移り変りがはっきりしていて、当時はスモ
ック公害もない日本列島へやってきて、
「これ、桃源郷か」と、「トウゲン」とよび、それが藤原の名のりになったのかも知
れぬ。
なにしろ高松塚古墳の見つかったところも、「藤原京」というが音読では「トウゲ
ンキョウ」なのである。
なにしろ日本では明治中期までは、
「漢字は当て字、つまり発音さえそれで通れば差し支えない」とされていたので、新
選組が新撰組になったり、今の秋刀魚も昔の『浮き世風呂』や『吾が輩は猫である』
では、三馬と書かれているくらいのものである。
誤字とか当て字がうるさくなったのは、入社試験の問題にフルイとして意地悪く使
われ出した時からで、まるでそれが常識や教養を計るバロメーターなみになったのだ
が、昔は、当て字どころか当て絵で、暦さえ出来ていた程である。
さて、今ではあまり豪くはないらしいが、かつては家長として威張っていたのを、
「トウさん」とあがめて呼んだり、
「良家の子女」つまり京都大阪方面の、大きな商家の娘に対して、
「嬢さん」と文字はかくが、これを、「トウさん」「トウはん」とよぶのも、現代な
らば、やはり「唐さん」と書かねばならぬところなのだろう。なにしろ河竹黙阿弥の、
『白浪五人男』の浜松屋の店先の場でも、
「これは、トイチな御嬢さま」と、江戸でも判るような台辞になっているが、この場
合でも字を当てるなら、(唐でも一番の)といった最高級の賞め言葉であろう。
「といち、はいち」といった俗語もそれからでているし、『枕の草子』に、
「近衛の中将を、頭(とう)の中将と申しはべる」
とか、「蔵人の頭」というのもあって、
「頭はトウ、つまり唐」を意味するから、最高位をやはり公家ではそう発音し、適当
に当て字をして用いていたものだろう。
また、人形屋やデパートの宣伝で、
「ひな祭りは古くから宮中でまつられた由緒正しき奥ゆかしいもので‥‥」と勿体を
つけるけど、御所が平安京の京都にあった明治までは、絶対にそんなことはないので
ある。
『続日本紀』によれば、
「唐武た太后の故事をしのび神護景雲元年三月三日より、文士を西大寺法院に集め、
帝は曲水の賦をなさしめ、頭初(第一位)に賞扶を賜わる」とさえ明記される。
『事物起源』では、だからして、
「三月三日は曲水宴[きょくすいのえん]とよび、御所では流水に漢文の七言絶句の
色紙を浮かべ、文武百官酒盛りをなす。夷祭は明正帝の御代のみ、御生母中福門院
(徳川英忠の娘の和子)がなせしが、その後は忌み嫌われて、これは斥けられる」と
出ている。
つまり内裏さまや親王さまが並ぶお白神の元型で、今のこけしの原点であるお雛さ
まであっても、三月三日、御所で行われる唐武太后の曲水宴には、到底うち勝てなか
ったくらいである。
「トウ」と名のつくものは、つまりすべてにおいて立ち勝り豪かったのが、高松塚古
墳のできた頃から始まった日本風俗なのである、といっても決して過言ではなかろう。
さて、日本史の根本資料の『日本書紀』では、
「日本には確定した国家が既にあって、そこへ唐に滅ぼされた百済などの人間が、現
在の言葉でいえば逃亡奴隷のごとく、亡命してくるのを帰化人として受け入れ、それ
らへ保護を加えた」といったような書き方をしている。
しかし、これは藤原体制によって編さんされた歴史だから、彼らに百済人が降伏帰
化したのがそうなっているだけの話にすぎない。
なにしろ三韓時代から一衣帯水の距離にあった日本は、そのコロニーの状態だった。
つまり、弁韓、辰韓、馬韓の三つが、それぞれ日本へ植民地を持っていたらしい。そ
の名残りは、
「ムネサシ(胸刺)の国が、今の埼玉」
「ムウサシ(武蔵)の国が、今の東京」
「サネサシ(実刺)の国が、今の神奈川県」
の例は前にも述べたが、サネは、「首城、主城、中核城」をいうのだろう。
「むね」とか「むう」というのは、その後、
「仰せをむねとし」とか「むうと念じ」などと日本語に転化し、「さねさし」の方も、
「相模の枕言葉」とされていたが、やがて、
「女性自身の枕言葉」とされていたが、やがて、
「女性自身の中核」をさすようにもなる。
つまり日本中が、かつては、
「備前、備中、備後」「越前、越中、越後」「羽前、羽中、羽後」とよぶごとく、三
つに分かれていたのも、なんといっても三韓の頃の名残りであろう。ということは、
俗にいう、
「神功皇后の三韓征伐」などは、本当のところ三韓よりの征伐であったのが正しかろ
う。
しかし大陸の魏が乱れ五胡十六国に分かれるような世になると、朝鮮半島に鼎立し
ていた三韓も、次々と唐に滅ぼされた。
オランダがナポレオンに屈伏した際も、日本の長崎の出島だけには、オランダ国旗
が世界でただ一流はためいていたというが、普通は本国が滅ぼされると植民地も奪わ
れる。
それにフランスから長崎では速すぎるが、中国大陸から日本はきわめて近いのであ
る。
『日本書紀』の「天智紀」に出ている処の、
「白鳳二年八月二十七日、吾軍唐軍と白村江に戦って利あらず」とされる六六三年が、
どうも日本へ彼らの進駐の、きっかけを与えたものではあるまいかと想われる。
つまり、高句麗らの北鮮系を追い、南鮮系の百済人がもっとも勢力をえていて、
「百済にあらざれば人にあらず」とされ、
「百済ではない‥‥詰らぬやつ」というのが、「‥‥クダラないやつ」と今でも訛っ
て残っているくらいの権勢をもち、百済語で、
「国」を意味するところの、ナアラをもって、「奈良」の都まで建てていたのが、次
第にその勢力を増してきたトウ氏によって、
「本国の百済はすでに滅び亡国の民のくせに、汝らはよい加減にしたらどうや」と、
せっかくそれまで営々として築いてきた地盤を、百済人が奪われてしまうのが、ちょ
うど高松塚古墳が出来たと推理されている八世紀の初頭に当たる。
つまり紺屋の白袴というのか。これまでの文部省検定パスの自分の本が、教科書と
して売れなくなるのを怖れてか、歴史家の肩書きをつけられる人は、まだ、
「遺骨は帰化人貴族の百済人か?」などと、臆面もなくコメントを発表しているが、
その点はっきりと松本清張は、
「日本と朝鮮は、同一民族」の説をうち出している。つまり、その意見は、
「皆が思っているように吾々が朝鮮文化を吸収したのではなく、もともと同一民族で
極言すれば、日本は朝鮮から分かれた国で、対馬海峡があるので向こうが動乱のとき
日本は独立し、先住原住民の風習を融合しより日本的になった。つまりアメリカが英
国から独立したごとく‥‥」というのである。
凡俗の歴史家の述べるところよりは卓越なものである。
だが、竿頭一歩すすめれば、これでも違う。
つまり八世紀に大陸から独立をしたのは、なにも日本の国そのものではない。進駐
してきていた藤原勢力が、
「もはや、われらは唐ではなく藤である」
と、彼らは勝手に独立したのだろう。征圧されていた高句麗系の北鮮人や、土着の
天の朝系の西南種らの日本原住民を、奴隷化して、ここに独立したのである。
いうなれば、故マッカーサー将軍以下が、あのまま住みついて日本各地に、その後
も基地を置きっ放しで、新アメリカ日本州として独立させてしまったようなものであ
る。
これに関しては朝日新聞社刊の『日本原住民史』に、詳しく、その経緯がでている。
さて、日本古代史が専門という井上光貞説では、
「七世紀後半の物と高松塚古墳は推定できる。八世紀に入ってからとは考えられない。
文武天皇の時から火葬になっているのに、高松塚には骨が残っていない」と、きわめ
て明快だが、これではあまりに単純すぎる。東大で講座をもっている方の説だから傾
聴したいが、どうも感心しない。これは六国史の中の、
『日本文徳天皇実録』の中からの援用だろうが、高句麗人は西南系土着民と混じって
から、「拝火教」の宣撫をうけ彼らの火葬に同化するが、百済人は土葬であって、こ
れは858年の文徳帝の死後も、河内交野を初め百済系の多かった墳墓の発掘によっ
ても、明白にされていることである。
それでは、その首級のない高松塚古墳の遺骨が誰なのか?
つまり何族人なのか?というので、いろいろ談義されているが、草壁皇子にしろ高
市皇子であっても、百済人であるとみれば問題ない。
それを七世紀後半の日本列島に、ちゃんとした日本国が厳然としてあって、そこに、
「日本人」とよぶ民族が既に今のごとく、存在していたとするからすべてが可笑しく
なる。
つまり『日本文徳天皇実録』をも含む六国史が、渡来したトウの人の漢文によって
書かれたものと正確につかめず、それを、
(日本国なるものがイザナギ、イザナミの二神によって、天の浮橋より天の鉾にて創
られた時から、ある程度の国家形態をととのえ七世紀まで確固として存続。百済が滅
びた時も断固武力にて本土防衛をして、亡命した帰化人を保護し得るだけの実力があ
った)
とするような妄想に取りつかれるからして、ために種々の揣摩臆測が出るのだろう。
「皇子」なる文字からして、どうも誤まるのだろうが、
『日本書紀』の中でも堂々と、中大兄皇子が蘇我入鹿を大極殿で仆してしまう条を、
「韓人、鞍作りを殺す」と、中大兄皇子のことを頭ごなしにそう呼び、後に皮はぎし
て馬鞍や馬具作りとなる北鮮系の、騎馬民族の末裔の蘇我氏を侮るごとくに書いてい
る。
だから、その遺骸から首級がなくなっているのも、埋葬後何人かが入って荒らして
いる事実も、盗人の仕業ではなく、つまり、
「政争で世の中が変わり、敗者となり反体制となった被葬者への、制裁か報復での墓
あばきとみられる」と、奈良県種原考古学研究所でも、高松塚への意見を発表してい
る。
ということは、これも、
(クダラ系が押さえていた天下を、やがて藤原氏と自称する唐からの人たちに奪われ、
かつては吾らの事をさえ、クダラでないのはクダラねえと罵りおった不届き者め‥‥)
と、その墓を荒らされたのだとする裏書きともなるのだろう。
なにしろ高松塚古墳の場所が、
「藤原京」ともよばれた橿原の朱雀大路の下ってきたところ。大極殿の建物のあった
個所から真っすぐの地点にあるゆえ、そこの地元の研究所の意見は正しかろうと想え
る。
また、被埋葬者を、持統・天武の御子、とされる草壁皇子や高市皇子とする推測の
他に、
「天武帝の九番目の御子の刑部親王」
ではないかとする説も出ている。
しかし、後の戦国時代以降になっても、藤原体制の公家なるものは、七世紀から八
世紀へかけての彼らの建国の際に、あくまでも抗戦したゲリラの末裔。つまり捕らえ
た後、
「別所、散所、院地、院内」の名でよばれた捕虜隔離収容所へ抑留した俘囚の子孫の
武家に対しては、それが大名でも、
「清掃人夫取締役----掃部守(かもんのかみ)」
「配膳台所勝手役----内膳正(ないぜんのしょう)」
「水くみ運搬の役----主水正(もんどのしょう)」
「税金を徴収の役----主税(ちから)」
そして、現今と違って裁判官を、他から怨嗟の的となる嫌われ者の役としていたか
ら、
「弾正」の名称で、武家につけたが、
「刑部」も、おさかべとは読ませたが、今でいうなら捕物に向かう刑事のことで、こ
れも、やはり嫌われ役として武家に限った。
これは、千金の子は盗賊に死せず、とする中国の格言からきていて、
「トウとい藤原氏の子孫のする役ではない」
と定まっていたものである。なのに、その刑部をもって名とされているという事は、
いくら天武さまの御子でも、その御生母がぱっとしなかったせいではなかろうか。
また『日本書紀』の持統帝五年の記に、
「百済王義慈の伜にて持統帝より、百済王の名のりを許され公卿となって、飲食物や
衣裳などを拝受した」とでている善広が、その遺骨の主ではないかとする説もある。
だが、みなれっきとした百済系ゆえ、これなら火葬してないのも当然だし、壁画の
女人が、顔は唐風でも、チョコリ[チョゴリ]やチョマ[チマ]を身につけているの
もうなずける。
さて、木棺を布で巻き、漆をかけた棺として発見されたので、墳墓と扱われている。
しかし宮殿や公共の建物、社寺は別として、十一世紀頃になっても、日本人の一般
は堅穴を掘って生活していたのは事実である。
百済人もまた横穴を大きく掘り、石材で周りをかため、住居にしたのは、建築技術
の進まなかった当時、冷暖房上きわめて自然だった。
という事は、棺があっても墳墓でなく、マイホームだったかも知れぬ疑問である。
なにしろ、そのマイホームの事を古代朝鮮語では、「カマクラ」とよぶ。
のち騎馬民族の末裔で、自分らこそ、
「ミナモトの民なり」と自称した連中が、相州釜利谷(かまりや)別所の山にたてた
鎌倉幕府の、
「カマクラ」だが、今も東北で雪をかためて作る小さな氷室をよぶごとく、朝鮮系の
マイホームは小さな円形横穴だったのである。
さて、日本では、
「木が流れ、石が沈む」という譬がある。
というのは、遺骸の主かともされている高市皇子が、十市(といち)(唐一)皇女
の死をなげき、
(山吹の咲く泉への道を知らぬのは悲しい)
とうたっている挽歌について、
「これは、シルクロードを通って伝えられた生命の泉の絵があったのだと、K・Dさ
んがいっているのを、高松塚古墳の墳墓の絵をみて俄然私の中によみがえってきた」
と、四月十八日付のY紙の夕刊に、成城大の某さんという人が書いている。
さて、高松塚古墳の副葬品の中に白銅鏡が発見されている。「海獣葡萄鏡」とよば
れるもので、法隆寺五重塔の心礎から発見されている葡萄鏡と図柄が酷似している。
また同じく正倉院御物の、
「金銀鈿荘唐太刀(でんかざりからたち)」の刀の柄と同じ唐草形の透かし彫りが、
やはり副葬品の中にある。
これと壁画の「白虎」の後足にみられるなつめ椰子の葉をイラストしたとされる、
「パルメット模様」について、高名な歴史家達は同じように筆を揃えて、
「シルクロードを通ってペルシャあたりから唐へ入り、それが日本へ伝来してきたも
の」
と、まことあっさりとかたづけられている。
もちろん、なにもこれは今になって始まったことではなく、素戔嗚尊を祀る祇園祭
のときに、山車に吊り下げられる古代ペルシャの布も、正倉院御物に入っているペル
シャ布も、
「これらはシルクロードを通って、遥々と日本へ運ばれてきたものである」と注釈が
つけられ、それが今では定説になっている。
だから高名な歴史家達も成城大学の先生も、あっさりそのまま鵜呑みにしているら
しい。
しかしである。
「シルクロードが西暦何年頃に出来たのか?」
はたして調べてみたり、その研究書でも見たことが彼らにはあるのだろうか?
レニングラード大学モナザビスキー教授の1969年版の、
「シルクロード、その歴史」なる研究論文によれば、13世紀初頭の元の遠征のとき、
今日のハンガリヤへ進軍路をひらくため、トルキスタンの多くの捕虜を使役にして、
軍用道路として何万頭もの羊を通すため開発したものが、後には荒廃したが、14世
紀になって隊商によってまた踏み固められ、どうにか通れるようになったのだとある。
なにもロスキーの教授を信用して、日本の学者をとやかくいうのではない。
しかしソ連では、もし怠惰とか研究不熱心を学生から告発されたら、大学教授とい
えど罷免されて、地方のウチーチェリとよばれる公学校の教員へ飛ばされてしまう国
である。
日本のように十年一日のごとき講義をしたり、己れの本が多くの学校の教科書に採
用されて、隠れたベストセラーになることだけを生き甲斐にしているのとは違う。
私もN大やM大で講師をしてきているのであまり何もいえないが、シルクロードを
トラックで何度も往復している教授の研究論文では、これまでのように、なんでもシ
ルクロードを通して日本へ入ってきたのだと胡麻かしている学説は、みな消し飛んで
しまう。
日本のようにインフレ政策をとるため、産業道路をどんどん作るのは滅多にない例
で、普通、ロードと呼ばれるのは、昔の軍用道路があとで民間人に使われだした例が
多い。
やはりジンギスカンの羊の群れが踏み固め開発したとするのが、常識的にも正しい
ようだ。
もちろん日本列島は暖流寒流が交互に、突き当たるように流れてくるから、なにも
シルクロードがなかった頃でも、ペルシャ湾からでも、潮流とよぶ時速6ノットから
10ノットに及ぶ水中エスカレーターににのれば、筏でもこられないことはない。
「スメラミコト」の「スメラ山脈」や、「男山のスサノオ」「女山のオマン」が、そ
のペルシャ湾には今も面して聳えているのである。
そして十六枚の花弁をもつ菊も、原産地は朝鮮や中国ではなくて、ペルシャなので
ある。
だからして、ペルシャ独特の「パルメット図案」や、アラベスクの副葬品をみると、
遺骨の主はペルシャ人だったかも知れない。
壁画そっくりの下ぶくれの型が、今でも向こうではビューティとされているから、
姿や形はチョマリでも、ペルシャ女でなかったとする反証はないようである。
タイ民族の日本移住
今でも北海道のアイヌ系の人が、内地人のことを、
「シャモ(和人)」とよんだり、また今でも関西の河内あたりで、蹴合いに用いる闘
鶏を、やはり「シャモ」と称し、また吾々の御飯をもりつけする板片を、
「シャモジ」とよぶのは、何か関連があってなのか、どうも引っ掛かるものがあるよ
うである。
梵語の「シャモ」が、日本の仏教用語では、「沙門」となり、「桑門」同様に出家
の僧のことをさすから関係があるとする説もあるが、唯それだけの結びつきであろう
か。
「シャモ」というと、現代のタイ国の古名が、「シャム国」または「シャモロ国」と
いわれ、昔はカンボジアから今のベトナムまでの版図をもつ、広大な国だったが、そ
こと日本とは関り合いが有ったのだろうか。これまでの日本歴史では、
「山田長政がシャモロ国へ渡航し、のち六昆王となり、元和七年(大坂夏の陣六年後)
九月に、ときの老中筆頭土井利勝に、新煙硝二百斤と虎皮の進物を届く」
と江戸中期になって、国交が初めて開け、江戸誓願寺を宿所としたシャモロ人が、
山田長政の使者にきた旧九州浪人伊東久太夫を、通弁として貿易を始めたようにでて
いるが、その以前からも、交流はあったものだろうか。
「ベトナム戦記」のニュースなどを見ると、日本人そっくりの容貌をしたのが多いし、
また、キック・ボクシングの試合でも、よく日本人に似たタイ国の選手が出てきて、
びっくりさせられる。どうして東南アジア系は同じ有色人種とはいえ、ああまで日本
人の一部にそっくりなのだろうか。また日本人がベトナム戦にわが事にように心を痛
める関連はなんであろうかと疑いたくもなる。
というのも、実際の処では徳川時代は、すべてが各藩単位で日本全体の歴史などは
どうでもよく、「日本歴史」なるものは、明治二十年代の後半から四十年代までにか
けて纏めあげられたものなので、どうしても、日清、日露の二大戦争で、
(下関----関釜連絡セ船----釜山。そして京城から新義州。鴨緑江から南満州鉄道で
奉天)
といったコースが、強烈に植え付けられた歴史になっている。また、それが大衆に
もすっかり馴染みになってしまったせいか。
日本の対外相手は、これ朝鮮半島と中国に限定してしまった感がある。しかし釜山
浦まで出て、そこから朝鮮半島経由で大陸へというコースより、実際は海上を年に二
回交互に吹く季節風や貿易風によって、南支那海や東支那海を往復していた方が、遥
かに多かったのではあるまいか。織田信長の頃でさえ、香港に近いマカオと日本の泉
州堺の間には、定期航路があった程である。
そして、その頃のポルトガル人は、マカオと印度のゴア、そこからリスボンとやは
り潮流にのって航行していた位である。
だからタイ国、当時のシャモロ国から、日本へ吹いてくる風の季節には、彼らもま
た、やはり黒潮を利用して、日本列島へ渡ってきたのだろう。
なにしろ『古事記』にでてくる処の、「野見の宿禰と当麻(たいま)の蹴速(けは
や)の垂仁天皇天覧御前試合の情景」たるや、
「日本の国技相撲の始め」とされているが、「ハッケヨイ、ノコッタ」と、土俵で四
股を踏むといった相撲ではなかった。つまり双方ともに正面で取り組むような勝負で
はないのである。
野見の宿禰は西方に向かって三拝九拝。
当麻の蹴速は南方に膝まずいて叩頭。
「ゴーン・ゴン」とゴングがなると、
「やあやあ」向き合った両人は、まわしなど当時はしめていなかったせいか、手など
伸ばさず脚を高々とあげ、互いに相手の胸や腹にアタックを加えあい、
「ハオ、ハオ」と声援をうけ、軍鶏の蹴り合いのような試合を続け、とうとう最後に
は、
「KO」で宿禰が、蹴速をキック・ダウンさせてしまい、今でいえばタイトルマッチ
をとって、勝名乗りをうける事となったと出ているのである。
だから、キック・ボクシングの選手が、宿禰神社へお詣りするのなら話は判るがそ
うではない。
今では日本相撲協会の、役員が初場所をあける前に、横綱を従えて、
「どうぞ大入満員、札止めになりますよう」
と羽織袴で威儀を正して、恭しく参拝する慣わしになっている。すこし変てこであ
る。
しかしヤバダイ国の連合グループに、投馬国というのが入っているのは前述したが、
発音からすると、そのトウマと当麻は同じような感じもする。それゆえ、この勝負と
いうのは、
(旧インド系と推理される倭人の国が、東南アジアから転入してきた国家体制に打ち
破られた事実)を相撲に仮託して物語っている寓話かも知れないのである。
だが、とはいうものの、いくら野見の宿禰がタイトル防衛を続けて勝ったからとい
って、それで当時のシャモロ国の名が日本列島に響き渡り、色々の物にシャモの名が
付いたとは考えられもしない。
これはやはりある時点において、彼らが大量に集団移住してきたものと見るべきだ
ろう。
しかし、そんなに大勢の異邦人が、一度にどっと南の国から、
「今日は」とやってきたら、これはどうなったろうか。
現代の感覚なら、万博かオリンピック見物といった受け取り方もあろうが、昔そん
なものが有る筈もないから、とても歓迎されて、「ウエルカム」と招じ入れられるよ
うな事は、いくら古代でもまあなかったろう。となると友好的に入国できたという事
実は、観光目的でなければ、彼らが今日の国連軍のような恰好で堂々と進駐してきた
ものと、みなすことは飛躍であろうか。
また、それ程の大掛かりな進駐が有った裏には(何か突発事が有ったものと見なし
うる)といった事実を意味すると考えてはいけなかろうか。
これまでの日本歴史では、
「仏教伝来は宋の国から、唐の国から」と、中国からみな来たことになっている。
が、あれはどうも誤りではなかろうかという仮説のもとでのことだが、
「中国から印度まで」の間を現在旅行してみても判ることだが、もっとも仏教の盛ん
な国は、それは朝鮮でも中国でもなく、なんといってもカンボジアとかタイである。
なにしろ1970年9月5日の外電によれば、ベトナム解放軍の女兵が全裸体とな
って前線に現れたそうである。するとである。
(女人の裸体を己れの眼で見ると、戒律によって仏果がえられず、仏罰をうける)と
教育されているカンボジア兵は、そのため、みな狼狽して、
「眼の汚れになり、色慾を勃起させては、御仏の戒めにそむくことになる」と、みな
視ないように眼をとじてしまい、とてもこれでは迎撃にならず、次々と解放軍に攻め
落とされ弱らされているとのニュースが伝えられている。
日本では黄ばく宗[黄檗宗?]というのか、茶道具を包んだりする時に用いる、黄
赤色の布地の長いのを、肩から曳ずり気味の托鉢の群れが、バンコックの町へゆくと
集団で朝は町に溢れている。[『黄檗宗』とは、隠元を開祖とする江戸初期の禅宗の
一派。いわゆる『北方仏教』であり、ここで関連あるタイ国の『南方仏教』とは関係
ないようです]
男は成人式みたいに一度は仏門へ入って、こうした修行をして仏果をうるのだそう
だが、ぞろぞろ歩いているのは壮観である。
だからして陸路重点に考え、仏教伝来は中国からとみるより、釈尊の生まれたもう
た本場のインドや旧シャムロのタイから、船舶民族によって吾国へ直接導入されたと
いうような、発想はできぬものであろうか。
そうでないと足でキックするような相撲の原点は、やはり貿易風によって彼らに持
ちこまれた体技としか思えないからである。
そして、キックボクシングや、シャモとよばれる軍用鶏をもちこんだ民族によって、
それまでの騎馬民族系はとうとう征服されたか、または、
「仏の功徳」によって折伏してしまう世になったのだろう。このため対抗上、クダラ
系の人々は、「韓(から)神」さまを守って、仏派に対して各地に分散したらしく思
われる。もちろん既得権益を守るために、朝鮮半島からの人々は結集もしたのであろ
う。
そこでシャモロ側も、「護法」のために貿易風を利用して、大兵団を日本へ送りこ
み、彼らは、その当時クダラ系のコロニーであった河内から八尾方面を、まっ先に占
領したろうことも考えられる。
そうでなくては、今もその地方に、闘鶏として、南方系軍用鶏が飼われ、
「河内名物、軍鶏のかけ合わせ」となった由来が判らなくなるのである。
そしてバラバラのタイ国米になれていた彼らは、日本米のべたつくのに弱って、便
箋に用いていた木片の古いのを削って、これで飯盛りをしていたのだが、文字が残っ
ている物もあったからして、「文字のついたシャク」ゆえ「シャモジ」
と転化し、それゆえ海路安全の守護神である安芸の宮島の厳島神社が、現在に到る
も、日本全国のシャモジの75パーセントまでの製造販売を独占しているのかも知れ
ない。
そういえば厳島神社の赤塗りは、香港あたりの水上飯店の建物によく似通っている
し、「蛋民(たんみん)」とよばれる水上生活者が用いているサンパンと同じ物が、
社宝の、「平家御一門参拝之図」の供奉船には描かれている。
だから寿永三年の壇の浦海戦のときは、たまたま西南へ貿易風が吹きだす季節だっ
たから、平家の軍船の内で流されて行ってしまったものがあるのかとも想いたくなる。
「中国民族史」や「香港案内」にも、
「蛋民というのは氏族不明の漂流民である」などとでている。
もちろん逆に考察して、シャムかもっと西南から季節風が北東に吹く冬季に、向こ
うから流れてきて、それが戻ろうとした際、香港あたりに足止めになってしまって、
そこに定着したのがそのままになったか。
これは、大陸からの久米の子らが、そちらへ戻ろうとしてならず、中間の沖縄に辿
りついたきりになってしまったような見方もできるからして、それらと同じようなケ
ースでなかったとは、とてもいい切れないものがある。
http://www.rekishi.info/library/yagiri/scrn2.cgi?n=1078
「清和源氏」はありえない
「足柄山の山奥で‥‥」の童謡で名高い坂田の金時は、子供の頃に絵本で散々眺めさ
せられたが、マサカリ担いで本当に獣を集めて相撲をとらせたり、馬の代わりに熊に
のったりしていたものだろうか。また、五月五日の端午の節句には、
「金時」の人形が必ずといって良いほど飾られるのは、
(勇壮な男児に育ってほしい)といった親の願望だけでなく、金太郎系の原住民が今
もかなり多いせいではなかろうか、などとも想える。
また、坂田の金時のほかに、渡辺の綱、碓井(うすい)貞光、卜部季武(すえたけ)
という、源頼光の四天王の名が、治安元年(1021)に初めて現れてきて、いわゆ
る源氏の郎党団のはしりをなすのも、それ相応のいわれがあるのでは‥‥と考えられ
るものがある。
そして一般に、よく、
「清和源氏」といわれるが、戦後は、清和帝と源氏は無関係だったとか、誤りである
といいだされてきた。となると、
「清和帝----貞純親王----経基----満仲----頼光」といった従来の、
「その頼光の弟の頼信から、頼義。そして八幡太郎義家」とする源氏系図なるものは、
まるっきりの架空のフィクションと化してしまう事にもなる。それでは、
「足柄山」の山中で、わざわざマサカリ担いだ金太郎が、熊に跨ってハイシドウドウ、
ハイドウドウと馬乗りの稽古をつみ、
「坂田の金時」と改名し、頼光の四天王になったのも意味合いがなくなるような気が
してくる。
では、源氏とはいったい全体、何であったのか‥‥、彼らが自称していたらしい、
「みなもとの何某」という表現の仕方は、ミナモトの民、つまり原住民を意味するも
のとみるしかないから、彼らがそうであるなら絶対に天孫系の皇統であり得る筈では
ないのであるともみられる。つまり、
「清和源氏」というのは、系図歴史屋のフィクションではなかろうかという事になる。
昔は、「は=わ」ゆえ「姓わ源氏」といった歴史の嘘としかみる他はなくなる。
源頼光の弟頼信が、岩清水八幡へ捧げた告文に、
「吾は陽成帝の御子元平王の流れをくむ、経基の孫である」
とあるのが発見されたとして、戦後になってからというもの、
「これまで清和源氏といわれていたのは、陽成帝では御治世の功績もなく、それに早
く藤原氏によって廃帝された御方と伝わり、桓武平氏という称号に比べ、対照上劣る
ような感じがするからして、清和帝の子孫が『源』の姓を賜ったことにしたのだろう」
と、これまでの、
「清和源氏」という呼称は実存しない誤りであったとされるようになった。が、
「陽成帝よりの流れであるならば」というので、今では、木地師とよばれる山者の祖
先といわれる御方の祖先と、源氏の祖は同じこととされ、
「陽成源氏という呼称に変えるべきだ」
の説も強まっている。しかしである。
「誰が誰の末裔」といった系図的思考は、ひとまずこれを棚上げとして、
「源」という姓だけを考えると、なにも源姓は、清和帝や陽成帝の御子孫に初めて授
かったものでもなんでもないようである。もともと、
『日本三代実録』というのは、清和、陽成、光孝三朝の国史であるが、その貞観元年
(859)正月の条をみると、清和帝が御即位なさったばかりだというのに、もう、
「左大臣、従二位 源の朝臣真(あそんまこと)」
「縁葬諸司 正三位 源の朝臣定(あそんさだ)」
「参議中納言正三位 源の朝臣弘(あそんひろし)」
「参議左兵衛従四位 源の朝臣多(あそんただし)」
「兵部少輔従五位下 源の朝臣直(あそんすぐる)」
武官系の殿上人には源の姓をつけた者が、ずらりと並んでいる。
これでは清和帝の子孫の授姓でもなければ、その御子陽成帝の御子孫に、初めて賜
ったものでもない事が一目で判り得る。
貞観十八年[876]十一月二十九日に陽成帝が、御位を替わられ、年号が、
「元慶元年」と改まるが、源融以下左大臣、大納言、参議の源氏の者らの身分はその
儘である。
三年後の元慶三年[879]。この二月四日に十七歳の陽成帝は、藤原一門のため
に二条院へ移され給い、帝位は仁明帝の第三皇子であった五十五歳の時康親王へと譲
られ、この御方が光孝帝とならせられるのだが、正月の宴ではまだ、
「源 融はそのまま左大臣」「源 多が大納言から昇進して右大臣」
「源 能有が、参議から中納言に昇任」そして参議には新しく、
「源 冷」「源 光」「源 是忠」の三人が加わっている。
その後、間もなく藤原基経太政大臣の野望によって、藤原一門がこぞって、
「帝廃位」の不敬をあえてするようになるのだが、まだ正月には、
「源」の姓のつく一族一門は栄えていたのである。
となると、さて、これまでのごとく、
「清和源氏」といった名称を公然と用いていた歴史家は、
「清和帝のお生まれなされる以前から、源の朝臣某といった連中が、きら星のごとく
いたのでは、説明のつけようがない」
というのであろうか、それにこの時代は、
「応天門炎上の伴善男事件があったので、どうしても右大臣や左大臣といった官職を
もつ源朝臣の名も表向きになってしまう」
と気をつかってのせいか、これら源の姓をもつ人々を、
「王と運命を共にした」というこじつけであろうか、「王氏」とよび、王氏と藤原氏
の争いによって陽成帝の廃立を説明しているようである。
そして延喜十三年(913)まで右大臣をつとめた「源朝臣光」を最後にして、源
の姓を持つ者は御所から消え失せてゆくのである。
さて、それではこの源姓の者たちの発生はいつからかとなると、
「桓武帝」の次の「平城帝」そして、その後の「嵯峨帝」の御系図によれば、
嵯峨-----仁明帝-----文徳帝-----清和帝-----陽成帝
|___源 信 |__源 多 |__源能有
|___源 常 |__源 光
|___源 融
つまり清和帝の御誕生以前から、源の姓は皇室の御一門の賜姓として既にあった事
になっている。
そして、藤原氏の策謀によって、源姓系の天皇さまは追われ、そのクダラ系の御一
族も追手の眼をのがれ各地へ逃げられたから、今いう処の、白衣をきたり白旗をたて
るところの、
「近江源氏」「村上源氏」といった色々なグループが各地で生まれるようになるのら
しい。
しかし、いくら命からがら逃げ落ちられたにしても、そう簡単に何処へでも逃避行
できるというものではない。
そこで陽成帝側近の源姓の者らは、かつて嵯峨帝の祖父に当られる桓武帝の延暦の
御代に、百済王俊哲や坂上田村麿をして討伐させ、その捕虜を全国二千余ヵ所に分散
させた別所へと、その難をさけられた。そこの長吏は、桓武帝の時からの者だから、
「彼処へ入りこめば、われらは助かろう」
それぞれ各地の別所へと源氏は入りこんだのである。
この「別所」という地名は、今でも柳生但馬守の、柳生の庄にもその儘で残り、
「別所小学校」の名もあるが、鯛で名高い備後の鞆の浦へ行く道路の左側も、やはり
「別所」の地名で残っている。
名古屋から静岡にかけては「院内(いんだい)」、
京では「院地」「印地」、地方では「散所、山所、産所」ともよばれる。安寿と厨
子王の連れてゆかれた所の、
「山所太夫」というのが、そこの長吏のことで、そうした地域は、原住民捕虜収容所
だった関係上、山奥や辺ぴな地帯だったので、そこに住む奇怪な魚も、「山椒魚」な
どとよばれる。
さて山の中の別所へ入りこんだ源氏と原住民は、
「生きてゆくため」には、原生林を切りひらき、山中の獣を集めてこれを馴らしたり、
その肉を食し皮をはいで防寒具にした。
そして、いつの日にかまた再起する時のため、山中で武闘を旨として、その訓練に
あけくれていたのである。
だから○金の腹掛けをしていたかどうか判らぬが、金時がまさかりを肩に、熊にの
っていたのはその為であり、刀伊族が船団を連ねて来寇してきた国難の時がきて、徴
用令がでて、
「国土防衛の士は集まれ、憂国の者は来れ」
それまでは見むきもされなかった敵性の別所へも布令が廻ってきた。今でいえば、
さしずめ自衛隊の創設である。
そこで坂田の金時は足柄山別所から、渡辺の綱らは京の羅生門あたりの茅屋から、
源の頼光司令官の軍隊へ応募し、やがて、「四天王」とよばれるようになるのである。
そして今も源氏が好きな人が多いのは、金時らの子孫が、現代の吾々日本人の中に
は、かなり多いことを意味しているのだろう。
エビスとは何なのか
「征夷大将軍」という官名に対しての、これは疑惑であるが‥‥
永承六年(1051)、奥州平泉の東夷尊長安倍頼良(のち頼時)が反乱を起こし
た。そこで陸奥守藤原登任が討伐に向かったが、あべこべに撃破されてしまったため、
急遽京へ向け、
「乞う援軍、われらとても打ち勝こと能わず」
悲壮なSOSを発したので、時の関白藤原頼通(通長の長男で、一条中宮顕子の弟
にあたる)が、源頼信の伜の頼義をよび、
「汝を陸奥守に任ずるによって、征きて東夷を討つべし」と命令を下した。
そこで源頼義はその子の八幡太郎義家以下家の子郎党を従えて、
「勝ってくるぞと勇ましく」とばかり奥州へ向かっていった。
ところが延暦の昔。紀の古佐美が平泉へ討伐に行った時は、
「征東大将軍」の官名と節刀を奉じて行ったが、源頼義の場合は、
「陸奥守の後任」というだけで、御所へよばれて正式に辞令が出たわけでもなく、節
刀を拝受して行ったものでもない。ただ藤原頼通の代理の右大臣藤原教通から、
「確りやってくるがよいぞ」と激励され、送り出されたにすぎぬ。そこで史家の中に
はそれを証拠に、
「安倍一族はアイヌの東夷の酋長に当るから、その討伐位に、大げさに征夷(東)大
将軍の任命などしなかったのだろう」
との説もあるが、はたしてそうだったのだろうか‥‥と、これに引っ掛かる。
『東北史料』の<奥羽記要>には、
「頼義これ夷なり、そのため昇殿は許されず、もって節刀を賜ることなく東行す。よ
って土人らはその威に服さず」とあるからでもある。
さて、
「征東大将軍」の官名はその当時すでにあった、「征夷大将軍」の方は、この百三十
年後の寿永三年(1184)に、源義仲が初めて授けられる官名だからして、(まだ、
ないものが授与される訳とてなかろう)といってしまえばそれ迄の話だが、これには
別の理由があるらしい。
紀の古佐美の時には、東海道東山道各地から召集した壮丁五万をもって、進撃させ
たのだから、どうしても、いかめしい肩書きが統制上必要だったのだろうが、
「源の頼義の場合」は、奥州の平泉へ行くまでの間に、各地の別所に入れられている
原住民と、そこへ紛れこんでいる陽成帝の頃の、落武者みたいな源氏の末裔を、呼び
集め統合して行くだけのことだから、いわば一族一門のことであるとされていたらし
い。
つまり、なにもなんとか大将軍などという、肩書きを貰って行かなくても、統制上
支障を来さないと見られていたからなのであろうと考えられもする。
なにしろ、この時点から約三十年前に、刀伊(一)の来寇があった。それまで海外
から攻めこまれる事など、夢にも考えていなかった藤原氏が、これには周章てふため
き、
「これは、えらいこっちゃ、大変どっせ」
とばかり、かつての被占領民である俘囚の裔を狩り集めてきて、
「剣の鍛造が手間どるなら片刃だけでよいから、量産に励め」
当時のことゆえ、軍需工場は村の鍛冶屋だから、これを総動員して、
「その手ゆるめば、戦力にぶる」とか、
「産業戦士が国運をささえ握る」と、それまでの双方の剣に代わる、片一方だけが刃
のカタナ(片名)を、どんどん作らせ、これを俘囚の裔にみな持たせ、インスタント
武士団である国土防衛戦士を編成したことがある。
「刀伊の来寇」を「刀一」ともかくのは、この時、片刃刀が生まれたせいによるらし
い。つまり、源の頼光やその四天王の坂田の金時らも、そのときの一員だったのであ
るが、さて俄か作りとはいえ、日本が挙国一致体制をしき、
「片刃とはいえ刀まで量産して、迎え撃つ構えをしている」という情報が向こうに伝
わったせいなのか、
「では止めとこう」となった模様で、その後は進攻してこなくなった。だから藤原氏
は、やれやれとほっとしたものの、
「武器をもたせた俘囚の裔を、ぶらぶらさせておくのは危険だ」
クーデターでも起こされては大変と心配したあげく、
「夷をもって夷を征さすべし」となって、これが、「東北進攻」の命令となったので
ある。
さて、この、
「夷」というよび方であるが、これはもともと日本語ではなく、中国の呼称なのであ
る。つまり、話は横道にそれるが、
「倭」が紀元一、二世紀頃の名だったのに代わって、それを征服して建国した、崇神
朝以降の日本に対する中国(後漢から蜀、晋、宋)から見ての呼称であった。
だからインドの矮小民族が群居していたヤバダイや八(はち)ハタ国家群が、「倭」
ならば‥‥騎馬民族のたてた国が、
「夷」ということになるわけだが、これを「イ」と発音するか、「エビス」と読むか
で色々と違ってこようというものである。
昔のことだが、東京の山手線のエビス駅の近くに昭和の初めまで、
「エビスビール」の大きな煙突が今はまたリバイバルされたが、その頃は残骸をさら
していた。
もちろん今はないが、このビール会社没落の原因は、大正初年シベリヤ出兵の頃か、
その後は、北樺太より沿海州方面へ、ビールをどんどん輸出したのが一本も売れなく
て、破産したからである。
なぜ売れなかったかといえば、北樺太や沿海州のツングース系人の間では、「エビ
ス」というのは、日本語の「オ○○コ」と同じような、極めて一般的に普及している
女性自身の原語だったからして、向こうの男共に、
「そこは此方から入れる個所であって、此方の咽喉へ通すものではない」とか、
「おう不潔‥‥」といった具合に完全な不買同盟をつくられ、総スカンをくったから
である。
その内に冬季がくると、零下三十度の寒さに、瓶がみな割れてしまって返品も不能
になり、そのビール会社はついに倒産してしまったのである。
江上波夫氏の「騎馬民族説」つまりツングースが日本へ渡ってきたのではないか、
という発想も、案外このエビスビールがヒントであるのかも知れない。
さて、「夷」とよばれるのが、ツングース系だったとなると、彼らは、その渡来し
た当初こそ、矮小民族の国々を馬蹄に踏みにじって、日本列島を押えていたものの、
そのうち文化の進んだ三韓からやってきた軍勢に追われたのか、それともシャモロの
仏教勢力によって叩かれたのか、征服され、あくまでその新興勢力に帰順しなかった
者らは、
「敵性原住民」として別所へ収容されたり、さもなくば東北の寒い地帯へ追い詰めら
れていたものらしい。
つまり、エビスダイコクといった七福神というのは、
「蘇(素)民将来系」という原始宗教の祭神になっていて、特に、
(鯛を抱えたエビスと、米俵二つを踏まえたダイコク)の一対は、今でも縁起物とし
て売られたり飾られているが、双方とも男体というのは変である。あれの原型の、
「お白さま」というのが東北に残っていて、今では「こけし」にも転化し、「おひな
さま」にも変化しているが、米俵二つを踏んづけているのは、ホーデンを意味する男
性の象徴だからダイコクさまは男らしい。しかし、エビスの方は初めは女らしいので
ある。
七人の内で弁天さまだけが、唯一の女人で、後はみな男というのでは釣合がとれぬ
から、すくなくともエビスも、やはり女人の性器名ゆえそうであるらしい。
東海地区は別所をもって上にオをつけて呼ぶが、関西へゆくとエベスの転化をもっ
て呼称する地域もある。しかし仏家は、この原始宗教の七福神を忌み嫌っていたから、
余計にこんがらかせようと意図し「酒をハンニャ湯」といったように、寺の隠し女の
ことを故意に、
「ダイコク」などといわせている。
さて、当時の日本の生き残りの夷で、東北で一大勢力をしめしていた安倍一族は、
のち「藤原姓」を金で買った藤原三代の遺体が、ミイラとして残っているので骨格の
復元をしてみたところ、アイヌ系というよりは大頭のツングース系だったといわれて
いる。
こうなると安倍一族に従っていた軍勢の中には、北海道のアシュロ系のアイヌ人も
混じっていたかも知れぬが、平泉に城をかまえていた安倍の一党は、そうではなかっ
たらしい。
しかしアイヌでなくても、公家からみれば、夷と目されるツングース系の騎馬民族
であった事に間違いない。
だから、伊勢二見ガ浦と平泉の二ヵ所だけに、「松下社」とよ蘇民将来系の日本土
着系の神社がある。彼ら土着民を騎馬民族が押え服従させるために、その神を押えて
いたものと推理できるのではなかろうか。
源平合戦は奴隷の反乱
「おごる平家は久しからず」とはいうものの、1132年(長承元年)に、三十三間
堂建立の建築技術を認められ、内昇殿へ上ることを許された平忠盛の伜の高平太が、
その三十五年後(仁安二年)には、「太政大臣平相国清盛」となり、四年後(承安元
年)に、彼は十五歳の娘の徳子を、十一歳の高倉帝に押しつけ奉り、
「平家にあらざれば人に非ず」とばかり「お種頂戴」を強要するまでに専横をほしい
儘にし、そして十年後にその清盛入道が死ぬと、あとはバラバラになって転落の一途
を辿り、寿永四年(1185)の三月に平家の一門は、壇の浦の海底へみな沈んだこ
とになっている。
ただ清盛の弟経盛の末子敦盛だけが、一の谷の合戦で船へ逃げこもうとする寸前、
波打際で熊谷直実につかまってしまった。
ところが、見ればまだ稚(わか)く美しい身分ありげな公達なので、熊谷直実は、
「さあ早うに行きなされ」と見逃して助けようとした。なのに、
「これこれ熊谷どの、何をしておられる」
と源氏の兵が近くまで駈け寄ってきたので、敦盛も、もはやこれまで逃れえぬ土壇
場と観念してか、けなげにも首を直実の前にさし伸ばし、
「早うに、お討ちなされましょう」と口にした。
熊谷直実は不憫とは想ったが、味方の荒武者が集まってくるのでは、もはやなんと
もならず涙をのんで、
「では、お覚悟ッ」と、その細首を打ち落したが、敦盛の事を忘れかねて戦後は出家
し、二十三年後の承元二年(1208)九月十四日に京の黒谷で死去するまで、「あ
つもり」「あつもり」といっていたというが、そんなに美少年だったのだろうか。ど
うも話としては面白いが、あまりに話ができすぎていて、衆道の盛んな頃の作話らし
く、文政五年(1822)刊の黄表紙の。
「一谷双葉軍記」では、うつ伏せにねじ伏せた敦盛の鎧の下垂れをめくりあげ、直実
がなんしている挿絵まで入っている程である。
とはいえ、だからといって敦盛が絶世の美童だったかどうかは、想像画しか残って
いないから判らない。
しかし引っ掛かるのは安芸宮島の厳島神社で、拝観料を五十円とる宝物殿に飾って
ある陳列ケースの中の、
「平家公達の佩刀」と説明されている刀である。
平敦盛も平家の公達の一人だから、一の谷の戦でもこうした佩刀をおびていただろ
う。処が、これは日本刀ではない。
全然そりのない棒剣なのである。これはトルコの三日月刀(ヤガタン)と同じよう
な、サラセンの貴族が腰にささず、ぶら下げるものであって、イスタンブールや、ヨ
ルダンの空港では、同型のものを土産品として米貨15ドルぐらいから並べて売られ
ている。
さて、その宝物殿の入って右側の、採光の悪いガラスケースの上の方に、古い彩色
画とミニチュアの模型の船がおかれている。
これを見た時、はて何処かで同じ物にお目に掛ったことがあると考えたら、ポルト
ガルのリスボンの海岸べりにある海事博物館に、
「ムーアの王の船」として陳列されていたモデルシップと、そっくりそのものなので
ある。
ジェロニモ博物館に用事があって、この七月に行った時、隣り合っているから、ま
た、のぞきに寄ったが、やはり間違いなかった。
しかし、このモデルショップたるやガレー船なのである。奴隷が左右に三十人ずつ、
交互に漕ぐように櫂が並んでいる船である。
アラビア人とアフリカ人の混血したのがムーア人だが、こうした奴隷船はスペイン
やポルトガルの古書には、よく挿絵入りであるし、映画でも見られるものである。
しかし日本には、奴隷を鎖でつなぎ鉄笞でぶん殴って漕がせるガレー船は、なかっ
たことになっている。なのに厳島神社宝物殿には、
「平家御座船」の小さな木札とともに、模型が展示され、胡粉がとれ薄ぼんやりとし
てはいるが、船が海に浮かんでいる絵までが現存するのである。これは何を意味する
のだろう。
それに、もう一つ、
源氏の方は各地の別所へ押しこめられていた原住系の裔だから、近江から尾張から
と一斉に蜂起して、武士団を結成するのだが、平氏ときたら、何処彼処から挙兵して、
清盛の許へ駆けつけてきたという話は何もない。
対比してみると、源氏には、梶原源太景時とか和田義盛といった一騎当千の家臣団
の名が、きら星のごとくに並ぶが、平氏の方はこれといった名も伝わっていない。み
な、
「平家の公達」と御一門の名だけである。現代の株式会社には、
「同族会社」というのがあるが、武士団で同族きりというのは変である。
だから平家の武士団とは何処からかの、傭兵としか考えられないが、そのせいか壇
の浦合戦で、すうっとみな消えていってしまう。日本史では、海底の藻屑となってし
まったということになっているが、それならば、
(死体を確認し、その首をもいで)一般に公示しなければ、討ち取った事にはならな
い。ただ漠然と、見えなくなった海底へ沈んだらしいだけでは、今でいう、「行方不
明」にすぎなくなる。当時の源氏は平宗盛とその子清宗、平時忠だけを捕え、その首
を六条河原にさらしただけにすぎない。
謡曲では、平知盛が舟の碇を身体にまきつけ、海底に沈んだように作ってあるが、
碇は救命ブイと違って一人一個の割りにはなっていない。
舟一隻に一個しかついていない筈だから、完全に沈んだ者は一隻一人となる。では
平家一門がみな死んだのを証明したのは誰かというと、小泉八雲こと外人のラフカデ
ィオ・ハーンである。
彼は「耳なし抱一」をかいた時、幼い安徳帝初め平氏の一門の石塔がずらりと並ん
だ墓所で、抱一が琵琶を弾じたように描写したからして、それからというもの、
(平家の一門のお墓が揃って有ったという事は、皆水死をとげたという証拠であろう)
とされている。つまり小説で外人が証明した恰好になって、明治期に墓も揃い、それ
で日本史はできている。
しかし、この海戦で変なのは、平氏の船団が、小舟の類に到るまで鉄鎖で連絡され
ていたということである。当時の日本は、今もそうだが鉄の産出はすくなく、鉄鎖な
ど貴重品である。
それに、これから海戦をしようという船群が、そんなふうに行動の自由を自分から
束縛するような事をしたら、船合戦など出来よう筈がない。
だから「義経八艘飛び」などといったジャンプもされてしまうのだが、これは何故
だろうか‥‥となるのである。
しかし寿永四年三月二十八日というのは、今の太陽暦に直すと五月三日。つまり東
南へ季節風が吹きだす時期に当たっている。
平氏の船団は、その季節風に流され、内海から外洋の黒汐にのって、東南アジアへ
脱出するため、はぐれぬよう小舟まで繋いだのではあるまいかと考えられまいか。ま
た海戦の途中で平氏の船団は東南へと流されていってしまったから、平氏一門の大半
は取り逃してしまったものの、
(次に、東南の方角から逆の季節風が吹いてくるのは、冬である)
という知識は源氏の武者共にもあったから、すぐさま頼朝へ、
「平氏の大半を討ち洩らし逃がしましたが、もし取って返して攻めてきましても、そ
れは半年先のことにござそうろ」
と梶原源太らが、そのことを鎌倉へ注進をしたのだろうことは想像がつく。
『玉葉』や「吾妻鏡』をみても、本来なら平氏の残党狩りを徹底的にやるべきなのに、
頼朝は平氏と結託した公卿の追捕は命じているが、てんで平氏の残党狩りなどやって
いない。
それどころか頼朝は平氏の方は放ったらかしで、その翌月から義経や伯父の行家を、
反革命分子として追うのに憂身をやつしている。
----だがこれでは日本史は辻つまが合わなくなる。そこで、
「平家部落」とか「秘境部落」というのが各地に点在するのである。
「おまや平家の公達ながれヨーオーホイ、おどま追討の那須の末ヨー」といった「ひ
えつき節」が今も唄われているから、
(船にのり損ねたり、浮び上がって陸へはい上った平氏の残党が、源氏の追捕を逃れ
て山の中へ逃げこんで、そこに秘境部落を作った)
といった具合にされている。しかしガレー船を漕がせていた海洋民族の平氏が、ど
うして山の中などへ入りこんで生きてゆけようか。そんな事をしなくても、年に二回
交互に季節風が吹き、外洋の黒汐の潮流にのれば楽に南支やマレーへ行けるのが判っ
ていたのだから、とっくに彼らは洋上を逃げていた筈である。では、
「秘境部落」とか「平家部落」と今いわれている所へ、逃げこんでいたのは誰だった
かといえば、それこそ頼朝の死後北条氏に追われた源氏の残党たちである。彼らは前
にいた別所は、北条氏によく知られていたので、
「自発的により深い、より安全な山の中へと、それぞれ彼ら源氏の者らは逃げこんで
行った」とみるべきで、「歴史読本」(42年3月号)に、
「四国の険しい祖谷(いや)山脈の平家部落と称される所に、実は源氏の余類が秘か
に匿れすみ、その子孫が引き続き現存しているのはまことに面白い話である」
と紹介されているのもその例だが、そうした秘境部落には、
「白山神」が例外なしに祀られているのも、その特徴であるといえよう。
白山神とか白山権現は(所によっては白髯神)は、韓(から)神さまであって、か
つてツングース族が騎馬民族として、白衣を纏い白旗をたて日本列島へ渡来してきた
時に奉じてきた祖神である。彼らは平氏とは違い、「山の民」であるから、人跡まれ
な秘境へ入りこんでも、どうにか生きてゆけたものらしい。
これも----今まで誰も解明しなかった事実で、まさかと首を傾けるむきもあろうが、
今の神戸、その当時の福原を清盛が開港し、いった何処と貿易していたかを考えても、
この答えはでてくる。
これまでの史家は、朝鮮中国と交易していたものとしているが、
「対馬の国主宗親光」は、平氏を恐れ高麗(こま)に亡命していたが、壇の浦合戦が
すむと、高麗王より、「これを進物に」と舟三杯の貢物を頼朝宛にことずかって帰国
し、国交再開の書面を鎌倉に届けているし、南宋孝宗淳煕も、
「相国入道の時には国書を遣した者に非礼を加え、往復が絶えていたが今後は旧交を
温めん」と使者をよこしている事が、「宋国史」にも残っている。
そのせいか、頼朝の死後、源実朝は北条政子ら一族の圧迫に堪えかねて、1217
年(建保五年)に南宋亡命を企てねばならなかった事実もあるのである。
『吾妻鏡』や『玉葉』にも記載されている宗親光の、高麗よりの国交再開打診の話と
並べてみると、平氏が朝鮮中国とは交易通商どころか国交さえ絶っていた事実が、そ
れらでも立証され得る。
となると平氏は、福原港つまり現在の神戸港を作ったのは、いったい何処の国と交
易したり国交を結ぶ為だったろうかとなる。
しかしその頃は今のようにアメリカもまだなく、ソ連も有りえないのだから、朝鮮
中国と仲違いしていて、それ以外の国といえば、地図をあけるまでもなく、東南アジ
アとか西南アジアといわれる地域か、またはその先のインド、パキスタン方面という
事になるだろう。
そして日本からは西南方面に吹く貿易風の吹く季節に船出しても、途中で、風の切
れ目もたまにはあるだろうから、日本沿岸では珍しい奴隷に漕がせるガレー船も平氏
には必要だったのだろう。
そして奴隷といっても、まさか向こうの人間を使うわけはなかろうから、平清盛は、
山間に隠れ住んでいた原住系の男を捕えさせ、これを鉄鎖につないで船を漕がせたの
だろう。
だから、彼ら原住系の中には酷使に堪えかねて、寄港先のマレーシア方面で脱走を
計った者も多かったらしく、
「逃亡奴隷」として案外に早くから、向こうには日本人が潜りこんでいたらしく、そ
れぞれ日本人町といったタウンも、海岸べりに作っていたものと想像される。
また、福原から何を輸出していたかという問題も、ここに出てくる。
史家は、味噌、漬物、織物とか漆器、刀剣甲冑ととくが、それらは江戸初期に向こ
うに定着した日本人が多くなって、成功した彼らの需要によって、初めて輸出可能に
なったものであろう。
まだ命からがらに海を泳ぎ渡って陸に辿りつき、掘立て小屋で食うや食わずで乞食
みたいな有様だった逃亡奴隷に、そんな物を輸入させ購入するだけの余力があったと
は考えられぬ。
ではトランジスターテレビやラジオやカーもなかった時代に、何を船積みして送り
出していたかといえば、中世紀の交易品は世界中共通であるが、運搬が容易な商品で
ある。
つまりそれは人間である。平清盛は福原から奴隷輸出をして儲けていたとしか推理
できぬのである。そして、その人間資源たるや、原住系つまり源氏の者らである。
さて、日本史では源氏の面々が、
「平氏追討」の院宣を賜わって各地から、馬に跨って集まり、やがて平氏一門を倒し
てしまった‥‥という事になっている。
しかし、院宣という言葉に惑わされるが、ときの帝は、たとえ幼少であらせられて
も、清盛の孫に当たらせたもう安徳さまである。
だから体制は平氏の側にあり、源氏は反体制として決起し、いわば革命を起こした
のである。
さて今も昔も庶民は、体制には従順なものである。成田三里塚の農民たちが肥やし
を頭からかむって抵抗したのも、何処からの至上命令でもなく、あれは吾れと我身を
守る自衛でしかないのである。つまり、源氏が痩せ馬に鞭うち、ゲバ棒担いで集まっ
てきたのも、次々と捕えられ奴隷として積み出され、あの段階ではあれ以上は、もは
や堪えられぬ限度へきていたのである。
その当時としては、源(みなもと)と自称する民族は全滅寸前まで追いこまれてい
たと見るしかない。
という事は、山狩りをされ、身体強健な者はガレー船の漕手にされ、他は数珠つな
ぎにされ、その船で商品として向こうへ輸出されていたのに他なかろうから、やむを
得なかったのだろう。
つまり絵巻物での源平合戦は、美しくきらびやかであるが、あれは後世の絵空事と
しか想えぬ。まさかすぐ人目につく、あんなきらびやかな鎧をきていては、実際は、
矢を散々打ちかけられて狙われてしまうから、もっと地味な戦闘服だったろうし、そ
れになんといっても、実質的には源平合戦たるや「奴隷の反乱」だったのだから、も
っと、みじめったらしく寒々としたものだと想うべきで、それを否定したい方は、元
禄十五年(1702)十二月に、大石内蔵介以下が、あんな揃いのコスチュームで吉
良邸へ押しかけたとでも思っている、芝居と現実をごっちゃにしている人かも知れな
い。
http://www.rekishi.info/library/yagiri/scrn2.cgi?n=1079
軍用ジンギスカン義経
「源」と、「元」の音読みが、どちらも同じであり、それに源氏の笹竜胆の紋にそっ
くりなマークを、ジンギスカンが用いていたから、源義経は衣川の館で討死したので
はなく北海道へ渡り、そこから大陸へ入って、ジンギスカンになったのである。とい
う説が、大正時代に発表された。
丁度その頃、
「狭い日本にゃ住みあきた、シナにゃ四億の民がある」といった「馬賊の唄」が、こ
れまた大流行していたので、
「どうせ大陸へ渡って馬賊になるなら、ジンギスカン位の大物になろう」と、その本
は洛陽の紙価を高めた。だからそれを下敷きにしたものが、戦後にも出版されたが、
今や中国は、
『毛沢東語録』の世の中で、馬賊など時代錯誤のせいとなってしまった。
そこでオーストラリヤ輸入のマトンをさばく為に、
「ジンギスカン鍋」として、その方で彼の名前が宣伝されているようである。
それに大正時代の青少年の海外雄飛といえば、満蒙の天地と限定されていたものだ
が、今はエベレストまで出かけて行って滑降してきたり、ヒマラヤへ登って女性も遭
難して遺骸で戻ってくるような世の中だから、いくら、「ジンギスカンは源義経」と
いっても、ただ単に伝奇ものみたいに、興味本位に扱われるだけのことであるらしい
が、
「真相」というか、その真実はなんだったろうか。やはり気に掛かる一つの命題であ
る。というのは、火のない所に煙が立たぬ譬もあるように、それは、
(ジンギスカン=ツングース騎馬民族)
(源氏一族=やはりツングース系出身)
といった同族的な血の流れを同じくしているらしい点も推理されるからである。こ
じつけられるにはそれだけの、道具立もあろうというものである。
「ジンギスカン義経説」は、なにも大正時代の小谷部全一郎のベスト・セラーが皮
切りではない。
江戸時代文化年間頃の刊行物で小判十六枚とじの黄表紙もので、
「判官堀川逆夜討ち」なるものがある。これは京にいた九郎判官義経の堀川の館へ、
頼朝が差し向けた土佐坊らの追手が押し寄せてきた事への仕返しに、蒙古兵を率いて
京へ逆襲してきた判官が、
「おれが女を何処へやった」「かくなる上はせんもなし」
と被衣をかぶった身分のある女性や、牛車にのった高貴の女性を、手当たり次第に
引っぱり出してからが、それを押さえこみ、
「穴埋めに致すとは、ほんに、これがことをいうのかい」と、大見得をきっている絵
がでている。
はっきりとジンギスカンの名など何処にも出ていないが、蒙古兵を従え自分も同様
の衣裳をまとっている処をみると、江戸期にあっては、
「元寇」という十三世紀の出来事を、なぜ元軍十万が何度も懲りずに日本へ攻めこん
できたか?その理由が納得できず、
(源義経の亡霊が、仇討ちに殴りこみをかけてきたもの‥‥)
といった受け取り方を一般はしていたものらしい。それゆえ黄表紙本では、
「あらゆる恨みや憎しみは、みな食物と女のことが、その原因である」
といういい伝えにのっとって、さも女のことで妄執を残し、その未練から押し寄せ
てきたようになっている。しかし今日の史家は、頼朝の妻政子が北条氏なので、そこ
に重点をおき、
「源氏と北条氏とを一つ」にみているようだが、江戸期では、まさかそうした誤りは
作者もしていなかったという、これは裏書きでもあるらしいといえる。
つまり元が攻めこんだ頃の日本は、源氏を滅ぼして取って代わった北条政権の時代
なので、フビライ汗は同族のその仇討ちに乗りこんできたのだと、考えられていたよ
うである。
さて、高木彬光の『ジンギスカン義経』の種本は、小谷部全一郎の『成吉思汗は源
義経なり』だが、それにも種本がある。
福地桜痴居士の『義経仁義主汗』と、
(日本人はギリシャ民族の一部の東来説)をもって明治時代の洛陽の紙価を高らしめ
たことのある前述木村鷹太郎の『義経ジンギスカン』の二冊がそれである。
処が、それにも、また種本がある。『義経再興説』という明治十八年刊のものであ
る。
これは末松謙澄がロンドンで集めたものだそうで、内田弥八訳述という体裁になっ
ているが、今でいうリライトものらしい。
だが山岡鉄舟の題字が入っていたり、日清日露と大陸進出作戦を意企していた明治
軍部が、
(朝鮮征伐の豊臣秀吉)を国策に用いたと同様に、この義経大陸再興説も、
「国民精神作興用」にと、おおいにすすめて買わせたから明治三十年代の末には、三
十六版と重版し当時の一大ベスト・セラーになっていた。とはいえ時代が時代なので、
「たまたま友人一英書を恵む。繙(ひもと)きて之を見れば、即ち義経蝦夷より満州
へ渡り、元祖鉄木真(テムジン)と為るを記載するの書なり」
といった思わせぶりな序文から始まり、
「義経主従蝦夷ヨリ満州ニ渡航セシハ全ク事実ナリ、果シテ然ラバ斯ノ如キ文武両道
ノ才幹ヲ有スル人傑其名声ノ後世ニ伝ハルベキ大事業ヲ企図セズ、空シク日月ヲ徒費
スルナラント云フモ、吾人ハ之ヲ信ジ得ベキヤ、余ハ直チニ否ト云ハンノミ、謂フニ
義経ハ彼ノ豪傑成吉思汗其(ソノ)人ナラン」
といった大上段にふりかぶった内容で、
「義経の大陸に渡りし証左ハ、寛永年間越前ノ小港神保ノ船人満州ニ漂流セシニ恰
(アタカ)モ清朝北京遷都ノ時ニシテ、彼ノ船人モ共ニ北京ニ送ラレ道スガラ建夷奴
児(ケインイドル)地方家々ノ門戸ニ、義経及弁慶ノ画像ヲ貼付スルヲ見タリ、是レ
義経主従大陸ニ渡リシ顕然タル証左ナリト‥‥」
はっきり断言しきっていて、さも、
(青少年よ大志を抱け、諸君らは第二の義経となって、大陸に雄飛せよ。すすんで御
国のために御奉公せよ)
といわんばかりにアジっているような感じをうける。
これは前大戦中に、白虎隊の詩吟が流行したり、「二本松少年隊」といった本の広
告が大きく新聞に出たと思ったら、すぐ後ろから、「少年航空兵募集」や「少年戦車
兵志願受付」が開始されたのに、軌を同じゅうするような感じさえ連想させられる。
だから今日考えるような伝奇種ではなく、種本のそのまた元祖の、
『義経再興記』という本は、お国の為にと出された本であったことがよく判るのであ
る。
そして義経に国民の関心をひくため、
「義経千本桜」といった芝居や、「牛若丸」が、学童向きの絵本の主役になったし、
尋常小学校唱歌にまでうたわれ、
「京は五条の橋の上」とひろまったので、いわゆる「判官びいき」といった熟語さえ、
今では生まれたのであろうか。
さて話は戻るが、その源氏の世も一代限りで、意識的に義弟の義経を遠ざけさせて
しまったのも、北条氏の出身であるところの政子であったという事実。
そしてその源の頼朝の妻の政子が、いくら夫に先立たれた後とはいえ、その死ぬ時
に当たって、敵姓の氏名を、ことさらにつけ、
「源の政子」で最期をとげず、「平の政子」としてこの世を去ったことの奇怪さは、
難しすぎるのか、あまり問題にされていない。
だが、北条一門がそれを認めて葬っているのだから、これこそ源氏の謎を解く鍵だ
ろう。
北条氏の根拠地の鎌倉は、新田義貞によって滅ぼされ、殆んど史料がそのとき戦火
に焼かれてしまって、残されていないから、断定を下すのは難しいが、
「信州諏訪神社文書」に「伊豆伊藤(東)から廻されてきた別所者が、神領について
滞在し指図をしていった」旨の記載の個所がある。源頼朝在世中の古文書である。
となると、現在は温泉郷の伊豆伊東というのは、十二世紀末までは、原住民捕虜収
容地であったことになっている。
そうなれば、その伊東の長吏役をしていた北条時政が、
「よろしゅうござる、家の子郎党共をもってお味方しましょう」
と頼朝に肩入れして、ところの目付、つまり監視所の代官を討ち、石橋山で平家追
討旗上げをさせたのも、原住民と源氏との相互扶助的役割からみて納得できる。しか
し北条氏が、頼朝の死後、
「頼家」「実朝」といった血脈を殺してしまい、
「左大臣九条道家」の子の三寅丸(頼経)二歳を、政子の養子に迎え、形だけの征夷
大将軍となし、やがてそれも有名無実化していって、北条氏独裁制を確立する途上で、
邪魔者は消せとばかり、「梶原源太景時の一族」「比企能員一族」「畠山重忠一族」
「和田義盛一族」「三浦義村一族」と源氏家臣団の皆殺しを企てたのは、「出自」と
いう当時の出身部族が、もし源氏と、伊豆伊藤別所の北条と同じ種類のものなら、こ
れは可笑しなことになる。
だから後世の系図屋は、なんとかしてそれに辻つまを合わせようと、
「平貞盛----維時(これとき)----直方----維将(これまさ)」というのを作り、す
こしは良心が咎めるのか、「維将これまさに北条の祖なり」と、でっちあげて居る。
系図屋というのは、注文されれば何処からでも、もっともらしい名前をもってきて、
なんとか先祖にすえてしまい、それで依頼主の歓心をかう系図を作成していたリライ
ト業だったので、現代でも、注文通りの品物を巧く盗みだしてきて、それを捌く商売
人を、漢字では臓物商、故物買いとかくが、発音では『けいずや』と、まだいってい
るほどのものである。
さて歴史家の中には、政子が死ぬ時に、「平政子」を名のっている点からして、北
条氏は平家なりという系図を、その立場とご都合主義で信じている者もいるようだが、
常識的に考えて、
(平家の一族が頼朝に加担し、とうとう平家を没落させてしまう‥‥)
といった事が有り得るだろうか。また、いくらかでも平家の血筋を引くものなら、
その地位を利用して親しかった平家の一門を匿っておき、源氏全滅後にそれを表面に
出してもよいと思うが、てんでその形跡すらない。だから北条一族は、反源氏であっ
た事は確かだが、
「平氏の末裔」というのは単に名目上の恰好をつけたにすぎなかろう。
もちろん政子の場合は、泥臭い源氏よりも海外ムードの平氏の方に憧れていたから、
自分でペンネームのように気儘につけたものか、それとも北条一族が、
「打倒源氏」の正当性をPRするため、こじつけに政子の死後、そうした命名の仕方
をしたのか、今となってはそこまでは判らない。しかし延暦の昔、日本全国二千有余
に作られた捕虜収容所の別所とはいえ、そこに入れられた原住系は決して単一ではな
く、地域によって南方系北方系と雑多であったらしい事は判る。そして、
「義経が向こうへ行ってジンギスカンになったのではなく、ジンギスカンの先輩で日
本列島へ先にきていたのが、源氏になったらしい」
のは、騎馬民族説でも立証されるが、北条時宗の時代に元のフビライ汗が十万の兵
を向け、くり返し差し向け日本遠征を企てたのは、
「北条体制が反ツングース系だった」理由に、やはりよるものだろう。
イスラエルがアラブ諸国と戦をすると、世界各地のユダヤ人が援助し、アメリカの
ようにユダヤ人が体制を維持している国は、全面的にイスラエルを助けるごとく、民
族の血は濃いもので、山口の大内義隆のごときは南支那のニッポーに、祖先の地とし
て今でいう領事館さえ設置していた程である。
だから、もし北条氏が、
(ツングース系だったら)元とは友好関係を結んでいて、彼らから決して攻められる
ような事はなかったろうともいえる。
また人類学上では、鼻の根元から上顎の門歯へひく線と、耳孔と眼の窪みへひく線
との対角を、「全側面角」というが、石器時代人は80.8度、古墳時代人は81.
5度、鎌倉源氏は81.7度。ツングースは81.6度と、みな出っ歯型である。
「源義経は出っ歯の小男だった」といわれるのは、この骨格からの割り出しだが、ジ
ンギスカンやフビライ汗も、西瓜を食べるのに好適な顔をしていたことになる。
しかし北条政子が、反源氏反ツングースとなると、これは出っ歯型ではない。現代
日本人の「全側面角」は、平均85.1度だそうだが、政子もそれ位で口許の整った
顔ををしていた事になる。
俗に関東女は肌が浅黒いといわれるが、十二世紀から十三世紀頃のものと推定され
る人骨で、この角度に近いのは、ギリシャ人の進攻によって混血をよぎ[余儀?]な
くされたインドや、マレー人のものだけだからして、
「北条政子というのは、やや褐色の皮膚をして、口許尋常の女」
つまり当時としては、美人という事になるのである。
(江戸時代になっても、関東では「口許尋常」というのが美人の標準だったから、反
っ歯が割りと多かったらしい)
それゆえ頼朝もすっかり参ってしまったろうが、各地から集ってきた出っ歯の関東
武士も、この政子をしみじみ垣間見てからが、
「ええ女ごじゃのう」と、ぼおっとしてしまい、さて、それからというものは、(花
は霧島、煙草は国分)などというオハラ節はまだなかったが、彼女の名に敬語のオの
字をつけて、。
「女ごは、オ政子」といいふらすようになったらしい。
というのは、今では「マサコ」とよませるが、彼女がいた屋敷は、
「マンドコロ」と呼んでいたし、後の秀吉も、その母を「大政所」妻ねねを「北の政
所」といっていた。といってマンを致す所の意味ではなく、人間を意味するマンが、
マライ語では、施政官をさしていたから政務の意味だったろう。
つまりこうなると、南方系の平氏をツングース型北方人種の源氏が追っ払い、それ
を別所に分散されていた中の古代マレー系の北条氏が滅ぼしたのだから、北条時宗の
時代になって、
「おのれッ」と北方系の元が攻めてきたことも、ややこしいが人類学上では解明でき
るのである。
楠木正成悪党説の由来
長州人吉田松陰は、松下村塾を開くに先立って、安政三年(1856)四月十五日
に、「七生説」をまず書き、ついで嘉永四年(1851)に、
「楠公墓下ニ作ル」を詩作し、ときの光明天皇さまを後醍醐帝に、当時の大原重徳卿
を建武の中興の際の藤原卿になぞらえ、自分を楠木正成に擬した。そこで大原卿が、
「七生滅賊」の書を松陰に与えたが、これは今でも山口県萩町の松陰神社に蔵されて
いる。
さて松陰は、「七たびも生き返りて、夷敵をを打ちはらわん心、われ忘れやめ」
と刑死するに当たっても辞世の歌を残している位なので、彼によって教育された松
下村塾の教え子が、明治新政府の実力者になると、まず、
「正三位」が楠木正成に贈られ、やがて小学校令がでて、
『国定小学読本』が明治六年八月に初めて発刊されるや、楠木正成の話が文部省命令
で入れられ、ついで八年四月から全国の小学校で使わせることになった『日本略史』
にも、
「後醍醐天皇」の条に、(正成正行の桜井の駅の分れ)
が挿入され、義軍奉公の教育がそれで施されるようになった。
そして明治十三年七月の聖上西国巡幸の際、「正一位」が改めて正成へ追贈され、
「大楠公」として国民精神作興の一大柱石とされたのである。
なのに戦後の歴史家は、
「楠木正成は土豪だった」とか「悪党」だったと、まるで逆な評価をするのだが‥‥
どうして正反対に逆転してしまったのだろうか。
日本人として天皇さまにお尽し申し上げるのは、それは民族として至上命令ではな
かろうかと思うのに、時代によってはその価値観まで違ってくるということは、黙っ
ていられない義憤を感ずる。
「正一位」に勅旨策命されたとき、「橘朝臣正成」とされたことが、ややこしくなる
原因ではなかったろうか。とまず考えられる。なにしろ、
『尊卑分脈』とか『姓氏撰録』といった一方的なものでは、すべての日本人はこれこ
とごとく、「源平藤橘」の四つに包合されねばならぬ事になっている。そこで、「楠
木正成程の人の出自が、はっきりしなくては、いかぬではないか」というのだろうか。
歴史家は、まず『尊卑分脈』や『大系図』、そして『群書類従』中の橘氏系図に結び
つけてしまった。
この結果が『吾妻鑑』の元久二年(1205)七月の条に現れてくる「四国伊予の
家人の橘六公久(むつきみひさ)」とか、
『承久軍物語』巻四にでてくる「ならの橘四郎」そして、
『新撰玉藻集』の橘右馬太夫公成なども、順に結びつけ、
「橘氏の先祖」とされる敏達天皇を、楠木氏の遠祖とし、その十二代目の好古(また
は遠保)が、従三位大納言鎮守府将軍になったと、家格をもっともらしくして、これ
を正成まで系図で結びつけた。
だから戦前は、由緒正しき家柄に生れた正成なればこそ、
「楠の木の匂いがしてくる処に、忠勇の士がいる」と後醍醐帝の夢枕にまで現われ、
お召しをうけて御座所へ伺うや、両手をつき、
「臣正成ここに一人有る限りは、如何なる事がありましょうとも、大御心を安じ奉り
ます」と言い切ったものと思われていた。
処が戦後になると、
(いくら漢字の感じが、楠と橘で似てるとはいえ、同族扱いして、系図を結びつけて
しまうのは信頼がおけないことであるまいし)となって、
「橘一門であるなら、建武の中興の時に、もっと上位の段階に昇進できた筈である。
なのに従五位にしかなれなかったのは、地家だったからではあるまいか」といわれだ
した。
「地家」というのは「公家」に対する呼称である
つまり御所に仕えている公卿を、「公家」というのに、「地家」とは、俗に「地家
侍」といわれるごとく、かつて別所へ入れられていた俘囚の裔。刀伊の来寇のときに
急ぎ片刃の刀を持たされた俄か作りの武士団の子孫ということになるのである。
この時の武士団は、せっかくの軍備を遊ばせておくのは勿体ないと、東北遠征をい
いつけられ、これが俗にいう、
「前九年の役」「後三年の役」だが、戦後、生きて戻ってきた失業軍人の救済策にと、
ときの後鳥羽上皇の御仁慈により、今の皇宮警察官のような、「北面の武士」に彼ら
は援用された。
しかし全部を御所で、召し抱えられる筈はない。
そこで大半の武士は、それぞれの生まれ在所へと引きあげた。
「在郷侍」と地家武者のことをいうのは、この為である。
もちろん元寇の際に募集され、九州へ進発して、雄々しく戦ったのも彼らである。
しかし弘安の役が済んでしまうと、またお払い箱になった。台風のため思いがけぬ大
損害をうけたのは、元軍だけでなく彼らもまた同じ被害者だった。
それから四十三年。北条氏のあくなき専横に堪りかねた後醍醐帝は即位七年にして、
密かに討幕密勅を降された。それを奉じて各地の地家武者は、すぐさま御前に馳せ参
じようと立ち上がった。しかし、未だ時期尚早。
天皇さま側近の資朝や俊基らは捕らえられ、美濃の土岐頼兼や多治見国長らは、北
条高時の命令で、謀叛人、国賊として京六条河原で、首をはねられた。
「正中の変」といわれる1324年の王政復古未遂事件である。
挫折感に御宸禁(しんきん)を悩まし給うた帝は、その後ますます圧迫を強めてく
る北条体制に堪えかね、七年後の1331年(元弘元年)八月。
ついに京の御所を脱出され奈良の笠置山へと、決死の逃避行を遊ばされた。何故そ
こを選ばれたかといえば、笠置は柳生庄だったからである。
今では新蔭流柳生但馬守でしか知られていない土地だが、ここは伊賀の名張川と木
津川に挟まれた地域で、崇神天皇陵を初めずらりと天皇の御陵が並んでいる「守戸部
落」の地帯であった。
つまり別所地帯で、かつて北条政子やその父時政によって追われた源氏の残党が、
原住民と一つになって世をひそみ、匿れ住んでいた地帯ゆえ、北畠親房が、
「彼の地へお越しなされましたなら、土地者は反北条の者ゆえ、みな帝のおんため尽
忠のまことをお尽し致しましょう」
と帝におすすめ申しあげ遷幸を願ったのである。このとき、三河の足助次郎らは、
筒針別所の原住民の者百名を率いて来り投じ、
「楠木正成」もまた河内金剛山において、
「大君の御前に召され戦うは、生とし生ける者の勤めである」
すぐ赤坂山に土塁を築き、矢竹を集められるだけ運び上げ、別所の面々に檄をとば
して、
「われら地下の者が、おおみこころにそい奉れるは、この上もない男の栄(は)えぞ
‥‥われら菊の御紋章の下に、流水のごとくにも潔よく、この血を流し奉り御奉公の
誠をつくさん」
当時のことゆえ文字を読める者は少なかったから、
(菊を上下半分にし下へ水の流れを、判じ物のように書いた紙札)を配らせた。これ
が後に有名になる「菊水」の旗印である。
しかし、その頃、
「やぎゅう者」とよばれ人まじわり出来ぬような、扱いをうけていた大柳生、小柳生
の守戸の千二百の男女が、帝を守って力戦奮闘したが、六波羅の精鋭五千に包囲され
ては、月余の抗戦もむなしく、土地の百姓共が間道から敵を案内してきて、九月二十
八日には落城。謀叛人として柳生谷が赤く血の河になる程、ここの住民は斬り殺され、
帝はまた捕われの身となった。
翌月十五日。笠置を陥した六波羅勢五千は、楠木正成のたてこもる河内赤坂城を攻
めた。が、なにしろ僅か数百の別所者がたてこもっただけの、城とはよべぬ小屋同然
のものである。
「吹けばとぶような掘立小屋ではないか」
「鎧袖一触、叩きつぶしてしまえ」
と四方八方から力攻めに掛ってくるのを、弓矢はおろか槍や刀もろくにない別所者
は、巨岩を転がし大木を上から投げてくいとめた。
しかし血みどろの抵抗も六日にして、戦力のない赤坂城は六波羅方の占領する処と
なった。そこで翌年三月七日。
「もはや叛乱はすべて規制できた」とばかり北条高時は、
「帝を本土でなく隠岐の島へ流すべし」と、恐れ多くも日本人としては、とても考え
られぬような不敬をあえてした。
赤坂失墜後、地下へ潜行していた楠木正成は、十一月に千早城に拠り今度は河内の
別所者千を集め、菊水の旗を秋空にはためかせた。
今度は前の赤坂合戦で敵の武具を奪ったり、拾い集めていたから、装備も良くなっ
ていたので、翌月には奪取されていた赤坂城をも取り返し、気勢をあげることができ
た。
「昨冬討死」と伝わっていた楠木正成が生きていて、またしても旗上げした事に諸国
の勤皇の士は奮いたち、護良親王は吉野で旗上げ。
播磨では赤松則村の挙兵。関東では新田義貞が鎌倉へ攻め込み、足利尊氏が協力し
て、ここに「建武中興」は成ったのである。
だから、いくら楠木正成が、やぎゅう者同様な、守戸あがりの別所者であったにし
ろ、今になってその出身ゆえ差別観念から、
「悪党」よばわりはもっての他である。上海事変のときの、「爆弾三勇士」にしろ、
その二名までは楠公精神をうけつぐ地方の出身者で、それゆえ彼らは軍神にはなれず
勇士に止まったのだというが、われらの中なる誤った歴史学者の観念的差別でもって、
軽々しく論じたりするなどもってのほかでなかろうかと想う。
豪傑新田義貞の謎
青空高く舞い上がる凧の武者絵は、みなこれ「新田義貞」の髭もじゃの顔に統一さ
れていた。
私が子供の頃のメンコ遊びの、丸形のボール紙にはりついていた髭もじゃの武者の
顔にも、
「新田よしさだ」と書いてあった。
だから『三国志』の張飛やハンカイにも匹敵する吾国の大豪傑は、
「新田義貞そのひとなり」と思いこんでいたが、さて調べてみると、鎌倉攻めのとき
稲村が崎で、
「波が逆まき荒れ狂うは海神の祟りならん。わが宝剣をもって神慮を慰め奉らん。も
しこの剣を水中へ投じ、波が鎮まれば海神の御意に、この義貞がそうた事になるゆえ
‥‥一気に波打ち際まで突っ走り、鎌倉の北条御所へ討ちこまんず、如何」
と、海上を伏し拝み、おびたる佩刀を水中へ投じ、見る間に波のひくのを眺め、お
おいに勇みたつと、左右の者をかえりみて、
「神意は吾らにあり、今ぞ北条一族をば誅殺の時なり。われと共にいざ進み候え」と
ばかり馬に鞭打ち突入し、高時の首をとった。
だから、海神より見こまれた豪傑というので、新田義貞は英雄なのだろうか、どう
だろう‥‥彼に従ってきた上州新田別所の者達は、生れて初めてみる太平洋に、びっ
くりしてしまい、
「海は広いな、大きいな」と面喰ったかも知れぬが、
(潮の干満、その日は何時頃に引き潮になるか)位は、近くの猟師に聞いてもすぐ判
る事ではなかったろうか、と思えるのだが‥‥
つまり、それ位の知識で佩刀を投げこむトリック程度で、彼が幕末まで、
「豪傑」として特別扱いされていたのは、常識的には納得できぬし、明治になって俄
かに声価が、どすんとがた落ちしてしまったのも怪しい。
「雨あられと飛びくる矢は防ぎきれず、さながら全身針鼠のごとき有様となり、もは
やこれまでなりと、馬が深田にはまりこみ転げ落ちたるを潮に、潔くその身に刃を突
きさして、かねて覚悟の最期をばとげにけり」
といわれた新田義貞の霊を慰めんと、万治三年(1860)[1660の誤植?]
に福井藩主松平光通は、その討死したあたりに建碑したが、やがて明治三年になると
そこに小社が建立され九年には別格官弊社となる。明治十五年には正一位が贈られた
のであるが、地名をとって「藤島神社」と呼ばれて新田神社といわなくなる。しかし
それ以前の徳川時代にあっては、
(コレラやチフスといった伝染病や厄病よけの呪祷(まじない)絵にも画像が刷りこ
まれ、新田義貞の一と睨みで、いかなる悪鬼羅刹も退散するもの)
とされていたのだが、位階だけは正一位に昇進したものの、いつの間にか楠木正成
にその王座を奪われた形で、皇居前の銅像にも義貞は洩れ、しがないメンコ絵や凧の
武者絵にと転落してしまったのである。
もちろん新田義貞は豪傑といっても、それは容貌が、それらしいというだけであっ
て、確定史料には誰と組打ちしたとか、何某を押さえつけて首をとったとかいった話
は伝わっていない。
初めは元弘の役に際し、鎌倉幕府の命令で西上軍の中へ徴発編入され、河内へ進軍
していった。
そして、
「あれなる千早城を陥しそうらえ」と命ぜられ、
「かしこまって」と攻めてはいったが、新田義貞より楠木正成の方が強かったのかど
うかは判らぬが、何度も攻撃したが向こうがそれに応じてこないので一度も勝てずじ
まいだった。
もたもたしている内にそのうち嫌気がさしてきて、義貞は東国へ引きあげてしまっ
た。すると後醍醐帝よりの綸旨が、
「汝義貞も、北条高時の追討をなせ」と、秘かに届けられた。
天皇さまのご命令であるからには、日本人としてそれに否応のあるはずがない。そ
こで義貞も、
「はあッ」とばかり、昨日の友は今日の敵と北条高時の軍勢を討たんと進発しかけた
処、遥々陸奥の国から石川義光、武蔵からは熊谷直実の子孫の直経、遠江からは天野
経頭(つねず)。
そして、今は茶の産地で知られている狭山は、昔からの別所ゆえ、そこの武蔵七党
の連中が、常陸の塙政茂に従って参陣してきた。そして、
「北条というは、われら源氏の者共を殺掠したり、別所へ押しこめ差別待遇をなせし
不届きな輩‥‥いざこの時ぞ昔の仇討ちをなさん」
「さん候、今や復仇の時にてござそうろ」
「戦わんかな時きたる‥‥高鳴る胸の陣太鼓」
といった具合で新田義貞の軍勢は見る間に二千近くにふくれ上り、上州新田の庄か
ら世良田へでて、そこから利根川を渡り、やがて一行は、
「利根の川風」を背中の母衣に入れてふくらませ武蔵の比企郡高見から入間川を突破、
小手指原から府中へでた。
すると、鎌倉から廻されてきた北条泰家の軍勢が、
「来らば来れ、別所のやつばら」と待ち構えていたが、思いがけぬ新田義貞の軍勢の
多さに愕き、
「戦は兵の多寡によって決まる」とばかりに退却してしまい、
「それ追っかけろ」と分配河原から関戸河原へでた新田軍は、多摩川を渡って鶴間原
から世谷原へでて、そこから、
「本隊は片瀬腰越から極楽寺口の大手門へ」
「陸奥隊は村岡、州崎から鎌倉小袋坂口へ」
「武蔵隊は梶原の山越えに化粧(けはい)坂の裏手へ」
と三方から突入。このとき義貞が稲村が崎で潮の干満を計って、佩刀を投じたのだ
が、さて五月十八日から五日間にわたる大激戦で、とうとう北条高時以下の一族一門
を、葛西谷の東勝寺へ追い詰めてしまい、そこで彼らを全滅させてしまった。
しかし、これは義貞個人が強かったというより、つき従う武蔵狭山の別所の連中や
源氏崩れの連中にてれみれば、
「失地回復」の戦いだったから勇戦したのだろう。
というのも、カマクラというのは朝鮮語では、
「家居」の意味だが、古代ツングース語では、それは「首都」をさしているからであ
る。
さて義貞は船上山行在所におわした後醍醐帝のおん許へ、
「鎌倉占領、北条全滅」の報を急ぎお知らせ申しあげると、
「よくぞ致した」と御嘉賞を賜り、「左馬助(さまのすけ)」に任ぜられ、建武の中
興の論功行賞では「従四位ノ上、左兵衛督(さひょうのすけ)」として、越後守に任
官した。
やがて上野、播磨二ヵ国の介(すけ)も兼任したが、中興の政(まつり)が破れ足
利高(尊)氏と戦うことになって、箱根宮の下の戦で義貞は敗走した。
そして、翌延元元年(1336)、京に迫る足利軍を防いだ大渡合戦でまたしても
負けた。しかし源顕家の援軍でようやく京を回復したものの、またしても攻められ摂
津和田岬に陣をはったが、義貞は足利高氏に背後をつかれるのを恐れて退却し、この
ため湊川の楠木正成は放っておかれた格好となって、敵に包囲され、全滅してしまっ
た。
その後、義貞は北陸におもむき敦賀の金ガ崎城によったが、翌年ここも足利高経に
攻め落された。
その次の延元三年には平原寺の僧兵に包囲され、ついに藤島で最期をとげたのであ
る。
勤皇の至誠もよく判るし、転戦して苦労したのも充分に納得できる。
が、だからといって、大豪傑だったような面影はないのである。
なのに明治になってからは、すっかり影が薄くなったが、徳川三百年の間は、さも
豪傑中の豪傑といわんばかりに、もてはやされていたその謎たるや、何かというと、
平凡社版『大百科事典』第二十巻五十四頁の、新田氏系図を引用してみると、これは
一目瞭然たるものがある。
源義重___義兼___政兼___朝氏___(新田)義貞_____義顕
| |__義興
| |__義宗__岩松満次郎__新田男爵
|
|__義秀___(世良田)頼氏___教氏___満義___有親___親氏___徳川家康
俗に徳川家康は三河の松平元康が名を変えた同一[人]物で、先祖伝来の三河の地
を守ったとされている。が平凡社の事典では、
「家康は上州新田から出た世良田二郎三郎で、松平元康とは別人である」ことが、こ
れでもはっきり示されている。だから私は、
『徳川家康は二人だった』を書いているが、このため江戸時代においては今と違って
(権現さまは世良田)と知られていたからして、
「新田義貞は神君家康公の御先祖さまに当たる」
というのでハクがつき、代表的な豪傑と奉られたが、さて明治になると、今度は話
が変わってきて、明治新政府の連中に、
「新田義貞は徳川の祖ゆえ怪しからん」
とされて、楠木正成の方が株が上がったのである。
なお新田男爵となった本家の岩松の方は、
「御系図お貸し」の代償として、江戸時代は交代寄合組お旗本として百二十石の捨て
扶持を、代々徳川家から給されていたともいうが、何処の国にしろ決まったような運
命ではあるが、英雄は政権が交代すると、昨日までのヒーローが途端に卑怯者や悪党
にされてしまう。
しかし豪傑までが、歌は世につれ、世は歌につれといった具合に、その価値転換を
してしまう例は珍しい。ヨーロッパでも例がない。
恐らくこれは、絵草子屋ともよばれた江戸時代の出版業者が、命令もされないのに、
体制である徳川家へのおもねりに、
「武者絵は、権現さま御先祖の新田義貞」
と決めてしまって余りにも媚びすぎた結果、それが薩長の憎むところとなって、そ
の豪傑の地位から足を引っぱられ、今では忘れられてしまった存在になったのであろ
う。
が、彼も天子さまに命を賭してお尽し申し上げた一人である。
またいつの日にか見直され、豪傑でなくとも、かつてこの国にいた一人の忠臣とし
て再評価される時はきっとあるであろう。
http://www.rekishi.info/library/yagiri/scrn2.cgi?n=1080
足利氏と明国の秘密
足利義満は、「日本国王臣源道義」と書いた国書を送り、さながら明国に仕えるが
ごとき形だった。
その後の将軍義教の時においても、
『満済準后日記』という藤原師冬(もろふゆ)の子で、義満の猶子(ゆうし)として
三宝院二十五代目の座主となり、その当時、黒衣の宰相とよばれていた人の日記をみ
てみると、永享六年(1434)五月十二日の条には、
「唐朝書(明国書)を明人が捧げ持ってきたら、机の上において貰って、わが方は全
員礼服に身をかためその前に整列して、まず汚れを払うために御焼香をしてから三拝。
将軍は跪(ひざ)まずき膝行して、その書面を頂かせて貰うのが、応永九年九月に義
満公が、明国の勅使を迎えたときの作法であった」
とのべられてあり、翌六月三日の欄には、
「将軍義教公は明史を迎えられるのに、階(きざはし)の下までにじり降り、そこか
ら拝礼しつつ膝行するのはやめにしたいと仰せられたが、明国使は、それでは宣宗宣
徳帝に対して不敬であると、いくら頼んでも言下に斥け承知しなかった」旨の記載が
あり、「六月五日」の当日の条では、
「公卿は四足門に平伏、楽人は総門で演奏。明国使は中外門より殿上人に迎えられて
入り、将軍は曲録(椅子)をすすめ、己れはその前に座って焼香、つづけて二拝して
から明国書を頂けり」
と、その明使接待の情景がでているが、足利氏はなぜ明国への追従外交にあけくれ
していたのだろうか。散々に交渉したあげくが、三拝する処をニ拝にまけて貰ったき
りで、足利義教もいやいやながら膝で這って明の使者に近より、香をあげて拝むなど、
今では想像もつかぬ事だが本当らしい。
これでは史家のとく、
「足利義満は明国との通商の益を得るため、やむなく文字の上だけで臣下と名のった
にすぎぬ。つまり現代風に解釈するならば、名を棄て実を取ったのである」
といった説とは余りにも、裏肚に違いすぎるようである。
しかし、そうはいっても、足利時代に明国から攻めこまれかけたり、または、その
以前から日本が占領されていて属国扱いされていたという証拠もない。となるとこれ
は、足利氏だけにしぼってみて、何か明国と特殊関係があって、文字通り頭の上がら
ぬような義理があり、足利氏は代々そのために、天に陽があるごとく明国へは義理は
つくさねばならぬと、室町御所の主であり、そして、
「征夷大将軍」とよぶ当時の最高権力者の身が、いざりのように這って明国の使に拝
謁を賜っていたのではあるまいかとさえ、どうしても勘ぐりたくなるのを押さえよう
がない。
となると、この問題は足利義教の頃や、義満の代より遡って、どうしてもその始祖
まで考究してみなくてはならぬし、また足利氏というものを根本的に洗う必要もでて
くる。
さて、そこで妙なことは、足利氏たるや、「源」を名のって、代々等持院で火葬を
いとなんでいるが、どうもそれは治安上の政治的配慮からの処置ではないかとも思わ
れる点がある。
という理由は足利義兼が、その子義氏に三河吉良の庄を譲って、のちの吉良氏(吉
良上野介の先祖)を立てさせたとき、
「この笹竜胆の白旗は源家重代の旗というが‥‥足利家には不用の長物。しかし其方
は遠国へゆくのだから、もしもの用心に呉れてやる。万一の際にこの旗を立てれば、
思いがけず味方する者が現われ来って、危うき場合にても助かるであろう」と渡した
という話がある。
だから足利氏にしろ吉良氏にしろ、その分家の今川氏といえ、いくら表向きは「源
のなんとか」と取り繕っていても実際は違うようである。足利尊氏側近の武将の書い
たものといわれる『梅松論』の中でも、これはそれとなく、
「大友氏が足利氏に準じて『源姓』を称するのは、もともと中原在にて、藤原氏の大
友の荘を相続したる者なれば、これはその系図を故意に、源頼朝の落胤などと作りし
ゆえの牽強付会なり。○○同様に源にあらざればなり」となっている。但し○○の欠
字の一行は、群書類従本には入っていなく、慶長本のみである。
さてそういう眼でみると足利氏には変なところが多い。
足利高氏が摂津で敗北し、都落ちして西下するとき、
「忠節もっとも神妙なる相従い奉る船は三百余艘、播磨の灘に並びたり」と出ている
が、その数行前の『梅松論』の記述たるや、
「これまで供奉仕りてきし一方の大将の内、七、八人は引き返さんとす。この輩はみ
な関東の武将にて、これまで歴戦の功績をたてし者らなるが、しかりといえども御方
(高氏)敗北とあってはやむなく、いつしか旗をまき冑をぬき、笠印(足利方の)を
とり、みな部下を率いて、とぼとぼと戻りゆく有様。その心中こそ哀れなりけれ」
なのである。これをみると播磨灘には足利氏をエスコートする海軍が三百余艘きて
待っていたが、何故か上陸して戦わず‥‥そこまで足利氏の伴をしてついてきた、関
東を主な出身とする陸軍兵は、(乗船して西国へ行くのは困る)と、取って返して捕
虜になりに戻って行ったというのである。
「関東の将兵は船に馴れていないから、のったら船酔いして困るからだろう」
という味方もあろうが、これまでの戦功を無にして、それまでの足利方から離れて
いったのは、その海軍が、彼らにしてみると馴染めぬ軍勢で構成されていたのではあ
るまいか、といった疑問も生じてくるのは無理だろうか。
というのは、これより半世紀前の元寇はよく知られているものの、この南北朝時代
の日本へも、朝鮮半島から何度も兵船を連らねて来攻のあった事が、日本史で伏せら
れているせいではなかろうか。
『高麗紀』という朝鮮史料には、これは、はっきりと、
「慶尚道海師元帥朴蔵、水師営金宗衍、壱岐対馬を占領のため軍船三百差しむけ、歴
戦の末、わが国の勝利となる」とでている。
といって、これまでの日本史には足利高氏の時代に、朝鮮からの来攻が有った事は
勝った負けたは別にして何も出ていない。
が、もう一度、この間のことを振返ってみると、
「足利高氏西下、鎮西(九州)へおもむき、すぐ西国より攻め上る」
まるでシーソーゲームのように、足利氏というのは、負けるとさっさと艦隊に収容
されて西下し、すぐにまた勢いをもり返しては海路をとり、京へ攻めこむというのを
何度もくり返している。
だから西国から九州までは足利氏の地盤のような気もするが、すぐ兵を何千何万と
集めて短時日に戻ってくるというのはあまりに可笑しすぎる。
足利高氏が死んだのが1358年(正平十三年)で、その三十三年後の1392年
七月に、高麗王は李成桂に滅ぼされ、朝鮮国となるのだが‥‥もしも足利高氏をバッ
クアップしていた西南海上の幻の艦隊が高麗の慶尚道艦隊だったと仮定するのなら、
その七年後の、
「応永の乱」の勃発したすじも、成程と判り得る。勿論、日本史では、
「中国地方六州と防長ニ州の八ヵ国を領する大内義弘は、その前々年金閣寺造営を手
伝えと命令されてもきかず、前年八月に朝鮮より朴敦元が国史としてきたとき義弘の
挙動が、どうも怪しかったと管領畠山基国が云いふらしたのを憤って叛乱せしもの」
というが、大内氏は淋聖太子系といわれながら、漢族との繋がりがある。だから新
興朝鮮の使が、大内氏へ打診にきたのは、旧高麗国水軍が足利氏の庇護をうけ、瀬戸
内海に匿れているのをなんとか取り締まらせようと、この年に即位したばかりの明の
建文帝の意志を通しにきたものとみるべきであろう。『応永記』や『足利治乱記』に
よれば、その戦況は、
「堺の町の十六町四方に井楼四十八をたて、矢倉千七百二十五個所を急造し五千の兵
で守らしめた」
と伝わっているが、山口県の大内義弘が泉州堺にたてこもったというのも、当時こ
こが明国との港になっていて、向こうからすぐ応援にくるものと、それを計算に入れ
ての事だろう。
しかし、このとき援軍は来ず、当てがはずれて大内氏は敗死したが、応永二十六年
(1419)六月二十日には、北鮮韃靼(だったん)兵一万七千二百八十五人が、李
従茂の率いる二百二十七艘の艦隊に分乗して日本へ来襲した。
『看門御記(かんもんぎょき)』(伏見宮貞成(さだふさ)親王さま日記)によれば、
「唐人襲来、既に薩摩の地にとりつき国人と合戦を始めているが、唐人の中には鬼の
ごとき者も混じっていて、人力では攻め難いのに、次々と増えてきて八万艘にも及ぶ
由が御所へ注進されてきている」とでている。
かつて、源氏を倒した北条時代に元寇があって、その北条を倒した後の足利義持の
時代ですら、またも襲われたというのは、
「足利氏も北条氏同様に、非源氏系、つまりツングース北鮮系民族ではなかったこと」
を、これは意味するのではあるまいか。
なにしろ足利高氏の頃は、さも本当らしく、
「自分らは、源族だ」と高麗船団を利用し手伝わせていたが、その高麗が滅ぼされ新
興の朝鮮になると、時勢は一変して、
(どうも怪しい)と使節が調べにきたりしている内に、大内氏の叛乱がすべてを明ら
かにしてしまった。そこで、足利氏としては、もう明国へ頭が上がらなくなってしま
い、その討伐を恐れるの余り、臣従して、焼香をしたり三拝九拝して明使を迎えるよ
うな態度をとったのだろう。
「神軍奇瑞」といった願文をあげてはいたが、当時の足利体制は元寇の時のように、
また神風が吹くといた偶然性はあてにせず、ただもう堅実に、
「長い物にはまかれろ」と、いいなりになって向こうを刺戟しないように、懸命の努
力をしていたように思われる。追従外交どころの騒ぎではなかったらしい。
八幡(ばはん)船はでっちあげ
「応仁の乱」の終り頃に全国的に起きた土一揆、徳政一揆の暴動によって室町時代は
最後を遂げたものとされている。が、
『宣胤卿記』(中御門宣裔の文明十二年からの日記)に、
「当時政道これすべて、御台(みだい)の御沙汰なり」とでてくる日野富子夫人が、
内裏修繕を名目にして京へ入る七道に関所をもうけ、各地から京へ入ってくる物資に
税をかけ、人間にさえ通行税をかけたのが、「物価値上り」の元兇とみられている。
それゆえ、いわゆる打ちこわしに集まった生活難の暴徒が、文明十二年(1480)
九月に東寺へひとまず集まり、そこから北白川へ群がり出て、そこへバリケードを築
き今でいう解放区をもうけ、
「七道」の衆とよばれた関所番人と一つになり、牛車を仆して片っ端から火をつけて
廻って、掠奪をほしい儘にしたため、なんとも収拾がつかなくなり、
「戦国時代」にと、やがて移ってゆくとされているが、
「足白」または「足軽」といわれたり、一条兼良の日記には、「悪党」と書かれてい
たこれらの暴徒は、いったいどんな人間だったのだろうか‥‥
それに「徳政一揆」というのはモラトリアムだから、原則として、
「借金のある側が、その棒引きや延期を求める」ものなのである。
だが、よく考えてみると貧しい難民や百姓はいくら借りたくても貸してくれる所が
あるわけはない。つまり庶民が借金できたり、信用がないのに棒引きにする程、借財
できるなどとは常識的には考えられない。だから、これは年貢を先取りしてきた荘園
の支配人みたいなのが、
「先に何年分か取り上げたのは応仁の乱での物入りの為じゃった‥‥あの分は徳政と
して棒引きにし、今年からまた新規に納めろや」と布令したゆえ騒ぎになったのでは
なかろうか。徳政とは民に徳でなく、足利体制に得だったのと逆にも想える。
足利義昭まで十五代も続いた足利体制なのだが、それ迄なんとか支えてこられたの
が、実力というより、その実どうも明国の後楯だったらしい事に気づくと、これ迄は
なんでもなく見過ごされ教えられてきた事も怪しくなってくる。
『満済准后日記』の正長元年(1428)九月二十二日の条に、
「今川上総守(憲政)が駿河へ下り候うの用意をされているが、関東の大名の中には
<白旗一揆>の徒も混じっていることゆえ、お気をつけなされ、もし戦などに使う事
があっても、それらは使い棄てにて苦しくないものであるとの、注意を受けられた」
旨の記載がある。
この<白旗一揆の徒>という呼称は、足利体制下における、
「原住系の民の別所連中と、今ではそれに合流している源氏の末裔。そして、かつて
足利勢に逆らった楠木党や新田党の徒輩」をさす。
源平合戦の昔から、彼らは事あるごとに、
「白旗」をたてて、わいわいやっていたから、一揆とそれを軽くいなして呼んだので
あろう。
さて明国に臣従の形をとっていた足利氏は、仏教をもっての人心教化方策として、
片っ端から、ナミアミダとやらせていた。
処が白旗党余類の中でも騎馬民族系は、それに対抗して韓(から)神さまを信仰し、
白頭山でも偲ぶのか、加賀の白山さまを各地に勧請。それより古いヤバダイ系や八は
た系は、土俗八幡の祠を作り、その辺りに、シャクテイ女神に仕えるごとく、男性の
ものに似た陽石を並べ、これを「道祖神」としてまつった。
もちろん地域別に、ビシャモン、フクロクジュといった七福神を信仰の対象とする
部族もいた。
だから鎌倉中期に一遍上人がひらいた浄土宗の一派である時宗は、そうした異教徒
を有難い仏教へ転向させるため、室町時代になっても布教して廻り、これを当時の言
葉で、
「はちひらき」といった。土着の日本原住系の民に、当て字は色々とあるが、八、鉢、
蜂、羽地、といった蔑称があったからである。
もちろん、これに対する異説としては、松下見林の著などによれば、
「異民何も知らざるをもって、渡航の華人これに呆れて、ぱあなりと八の字を与う。
これ一ニ三四の八の音が、ぱあなればなり。しかるに負け惜しみなるか、八は末広が
りにて縁起よき文字なりなどという。しかれども<忘八>などというごとく華国にて
は、これ蔑みの語なるを知らぬもののいいなるべし」などというのもある。
山中にとじこめられていた別所者の彼らが、インディアンなみに山頂で煙の交信を
するのを、「蜂煙」、「蜂火」と書いて「のろし」、また彼らの決起を、これ「蜂起」
というのも、意味があるのである。
さて、『今昔物語』の中などには、
「いぶせき小屋に迷い来りつるものか。あな恐し餌取りの住み屋にや」などと出てく
るが、それまで山奥にいた「八」たちも、応仁の乱の人手不足から、人買いの手で集
められてきた。
山中を駆け廻って獣のごとく生きてきた者達ゆえ、足どりが軽いから「足軽」とか、
陽やけして黒いが足の裏だけは人間なみに白いから「足白」の蔑称がつけられた。つ
まり応仁の乱で集めてこられた中で、辛うじて生き残った者も、戦後になると簡単に
追い払われてしまったため、食ってゆけず、
「やってこまそ」と仕方なく、徒党をくんで始めた一揆が、京周辺から全国的に波及
したのである。
つまり、裸一貫の連中が借金できたり、信用貸しで物が買えるわけもないから、モ
ラトリアムの徳政一揆というのは間違いで、彼らは徳政反対の一揆に参加したのであ
る。
さて、それ迄にも、そうした原住系が足利体制側に仕えて、なんとか働かせて貰お
うとすると、今でいえば洗脳だが、当時のことゆえ、
(中味よりも人は見かけが肝心だ)と、まずその頭を坊さんなみに、くるくる坊主に
させてしまってから、その名も、「何々阿弥」と抹香臭く改名させたものである。
しかし、うっかり武器など携行させ、造反されては厄介だからと用心し、彼らには、
「生花」「茶湯」「謡曲」といった仕事を課した。今日いわゆる芸事の始祖の名がみ
な「本阿弥」とか「光阿弥」といったようになっているのはこの為なので、日本の文
化は原住民製である。
また足利時代の謎の一つは、なんといっても和寇である。
「南北朝争乱に志を得ない不逞の徒が一葦の軽舟に乗じ、北は朝鮮海峡から南はアモ
イ台湾の南支那海沿岸まで掠奪せり」
といった事になっていて、明国の『籌海図編』の永楽二年(1404)の条に、
「日本首(王)先に款を納め、わが国辺境を犯せし二十余人の擒を献ず」
つまり足利政権は明国の命令で、それらしい二十余の首を斬って直ちに献擒した、
という向こう側の記録である。だから日本の歴史家は、南支那沿岸まで、
「八幡大菩薩」の旗をたてた小舟が荒しに行ったものと考えて、これを昔から今日ま
で誰一人として疑う者すらいない。
しかし焼玉エンジンやモーターのなかった時代なのである。そこまで交替で漕いで
いったとでも考えているのだろうか。
いくら人力で漕いでも、南支那海と日本との間は、冬は向こうへ吹いてゆく季節風
があるから、その黒汐にのってゆけるが、これが逆の季節ではなんともなるものでは
ない。
だから常識的に十二月から二月まで吹く、その季節風に送られて南支那海へ行った
ものであるなら、彼らとて生身ゆえ、何か着ていないと風邪をひく。処が絵では、
「赤褌一本のみな裸体の儘である。
そこで、もし裸のままで行けたものとみるなら、それは風向きから考えても、逆の
方角、つまり南支那海に面したベトナムか、マレー半島を考えねばならない。また、
「八幡船」と書いて、「バハン船」と読ませるのも、呉音でも漢音でもない。これも
変である。
しかし、もし世界地図が手許にあれば、マレー半島つまり現在のマレーシア連邦を
みればよい。今でも南支那海に面している州の名は、
「バハン」なのである。そして四百年前の『バタビヤ日誌』の地図でみれば、マレー
シア連邦全部が、「バハン土候国」なのである。
命名の由来は、オランダが同地を占領するまで、つまり足利時代から徳川初期の頃
まで、そこはポルトガル人のバハン公爵家が、ベンハーの丘で統治をしていたという
のである。
だからポルトガル人が、バハンから南支那海を襲わせていたのが、
「バハン船」で、明国もそれをよく知っていたが、ポルトガルは恐いから、なんでも
いいなりになる日本へ文句をつけてきて、足利政権は白旗党を捕え、その首をとって
送っていたのだろう。
なにしろ、ああいう小舟は捕鯨船のキャッチャーボートみたいなもので、すぐ後方
に母艦がいて飲料水や食物をつみ、また収穫した掠奪船をすぐ積み取ってやらねば仕
事にならぬから、ポルトガルの軍艦もバハンからずっと同行していたのであろう。
とはいうものの、世界中どこへ行っても、己れの国が平気で泥棒をしたと認めてい
るような国は、まああるまい。しかも間違えて‥‥
まして「海国日本」などといわれながら、海流、潮流や貿易風、季節風を、もうす
こし小学校でも詳しく教えておけば、とうの昔に、八幡船の謎はとけていた筈である。
日本人の常識や判断が非科学的だと非難されるのも、こうした点からでもあろうか。
剣豪なのか塚原卜伝
「こしゃくなり爺ッ」と抜く手もみせずに、氷のような大刀を引き抜きざま振りかぶ
り、二つになれと斬って掛ってくるのを、その時すこしも周章(あわ)てず、
「何を致す‥‥」
ちょうど囲炉裏に向かって雑炊をつくっていた処ゆえ、咄嗟にその木蓋をとって、
頭上から電光のごとく見舞ってくる太刀先を、
「慮外致すな」と受けとめ、相手が思わず、つんのめる処を、すかさず、
「この未熟者めが‥‥」と白刃を押えていた木蓋で、今度は相手の頭をポカリと叩き
のめし、
「このわしを‥‥塚原卜伝と知ってか」
といえば相手は、土間にころげ落ち、
「命ばかりはお助けを‥‥」両手をついて三拝九拝。
「この不鍛練者めが‥‥」そのまま手にしていた蓋を鍋に戻し、やおら温顔をとり戻
し、
「もう直ぐ煮えるところ、雑炊じゃが一杯振舞おうかな」
にこにこと何もなかったように落着いたものであった。
----というのが知られた講談の中の一部分の抜粋である。
だが二キロもある日本刀の重みが、せいぜい二百グラムあるかなしかの木蓋に、加
速度をつけて激突した場合、いくら鈍刀でもスポンと蓋は切れるか飛ばされるのが道
理。
それを食い止めたばかりでなく、反って叩きのめして、相手をやっつけるというの
は、やはり世にいわれるごとく、塚原卜伝という人は、戦国時代の一大剣豪であった
のだろうか。
なにも講談をもって意地悪く追求するわけではないが、日本人は、単なる奉書紙を
巻いた五十グラムのもので相手の真剣も叩き落してしまう、きわめて非合理、非科学
的な荒木又右衛門の作り話さえ、「武術の極意」とか「至妙の業」といった神がかり
的なもののいい方で、さも当然らしく粉飾してしまって広めたり、
「剣禅一致」といった判ったような判らぬ説明で、アイマイモコたる発想をもって尊
しとするまやかし精神さえも堂々とまかり通るところの国民性をもつ。
しかし日本人が特別そうした方面に豪くて、ヨーロッパ人は愚かで精神面で劣って
いるのかも知れないが、ケンブリッジ出版社からでている向こう版の剣道極意書であ
るところの、
『フェンシング必携』には、はっきりと、
「剣技のすべては、その個人の運動神経の如何による。それは生まれつきのものであ
る」
とまで極言しているのである。もちろん突きだけのフェンシングと、大上段にふり
かぶり、
「やあッ」と叩っ斬る日本刀とでは違うかも知れないが、吾々としては、
「剣の途は至妙の一語につきる」とか、
「剣は人なり」など難かしい事をいわれるよりも、運動神経と、ずばりいわれる方が、
成程そうかと納得しやすい。
そして鍋の木蓋と刀で激突したら、蓋の方がバッサリ切れてくれない事には、どう
しても可笑しくなる。
もちろん日本紙がいくら丈夫であったとしても、またそれを荒木又右衛門が握って
いた処で、やはり真剣の方が当たったら紙を切ってくれねば、あまりにも不合理すぎ
て、漫画的な見方しかできない。
なのに、この日本という国では、
「石が流れて、木が沈む」という諺があるごとく、ムジュンというものが大手をふっ
て罷り通るような処もあるから、子供だましのような剣戟ごっこが、きわめて好戦的
ムード作りに役立つとでも、為政者に思われがちなのか、明治以降は日清日露そして
満州事変、大東亜戦前夜には、きまって、
「剣だ、剣だ」と叫ばれ、剣豪ものを流行させるような風潮があるようである。そし
て、そのたびに代表的スターのごとく、まっ先に担ぎ出されるのが、この、
「剣聖・塚原卜伝」なのである。だからして個人的に、卜伝に好き嫌いの感情などあ
るわけはないのだが、どうしても、その剣聖なるデフォルメに対し、槍先をつきつけ
るしかないようである。
山の中で仙人みたいに木の実を食して暮したら、そんなに野猿のごとくにも警戒本
能が発達し、運動神経は鋭敏になるものだろうか。
脂肪分がつかなくなって何キロかは減量し、そのため身軽になって敏捷になるだろ
う位は想像がつくが、だからといって反射神経や筋肉の活動がそんなに素早くなるも
のだろうか。
有名な歌手が海浜で声を鍛えたという話をきき、音楽女教師に好かれたい、認めら
れたいの一心で、小学五年生の時、息吹山のキャンプで一週間あまり山中でドレミフ
ァを我鳴(がな)った。
しかし直るどころか急性咽喉炎になって湿布をまかれ、酸素吸入器を毎日かけられ
涙をぽろぽろこぼした思い出がある。
これは芸大へ入って、いくら発声学をやっても音痴では駄目なのと同じことだろう。
幕末の文化年間(1804〜17)に美濃紙の本場武儀川べりの紙すきが、石臼で
こうぞを細かく潰してホモジナイズ化するという、日本では画期的な製紙法に成功し
た。このため従来の倍が量産されるようになり、従って紙価はこれまでの三分の二ま
でに下落した。そこで安い用紙を用いて、いわゆる文化文政の出版ブームが起きた。
さて、こうなると必要なのはライターである。
そこで出現したのが、若狭小浜の軽輩武士だが、本居宣長なき後の松坂の塾へ入門
し、古典をきわめたという伴信友がでてきた。
月産千枚、その生涯に三百余の著書をだしたというから、今ならさしずめ大流行作
家である。そして彼が書いたものも、
『春の秘めごと』といった初期のエロ本から、皇国史観の大家である故黒板勝美が、
その『六国史』の序文に、恭々しく、
「この三代実録の原本は、伴信友先生校訂の貴重なるものでありまして」と、あるご
とく、「清和・陽成・光孝」の日本三代実録の総漢文まで書いたかと思うと、天保時
代の撃剣流行に便乗しようとする書店の求めに応じ、「宮本武蔵」とか色々の剣豪を
こしらえた。
塚原卜伝も、また彼の三百余冊中の一冊で、その題名は、
『塚原卜伝の伝』とつけられている。
「幼名朝孝、新右衛門高幹、のち土佐守と名のり、全国修行三度に及ぶ」ともっとも
らしい書きぶりであるが、この種本は、
『甲陽軍鑑』である。しかし伴信友は、大衆作家には珍しい士分の出身で、ライター
になってからも大小をさし、いつも威儀を正していたから、近世における考証学派の
泰斗として寓されていたゆえ、
「伴先生のお書きになるものは間違いない」
という定評があったらしい。そこで塚原卜伝の話も、
『山鹿語類』『鹿島史』『関八州古戦録』『翁草』
といった享和以降(1801〜)版本になったものには、版行するときに書き加え
られたのか、みなそう入っているので、いつの間にか実在化され、かつては講談本の
花形であったのである。
というのも、他の武芸者は余りぱっとしないが、
「塚原卜伝は兵法修行にて廻国する際、大鷹三羽を据えさせて携行し、乗換え用の馬
も三頭ひかせ、いつも上下八十人ばかりの門弟を伴って旅行し、行く先々の尊敬をえ
ていた」とか、
「卜伝の一の太刀は、日本国中の大名たちへ相伝されているが、中でも公方の万松院
殿(十代将軍家・足利義晴)光源院殿(義晴の子の次の将軍の足利義輝)霊陽院殿
(信長に追われた足利義昭)にもみな伝授し、おおいに徳とされたものである」
といった記載から、足利将軍家の歴代が習うようでは、
「卜伝は超一流の剣豪だったのだろう」ということにされてしまったようである。
しかし、はたしてこれは文字通り信じてよいものだろうか。
この謎ときは、戦国時代における刀の在り方をまず考えればよい。
弓は「調度」槍は「道具」とよんでいたが、刀はただ、
「打ち刀」としかいわれていないのである。というのは、
(冑をかむり、鎧を身につけている場合‥‥)
それを刀で切りつけたら鉄と鉄の激突ゆえ、はね返ってくるだけでなく、刀が折れ
飛ぶか曲がるのが第一の難点。
鎧の脇の下とか背と首筋のあきとか、狙える個所は限定されていて、その間隙を仕
止めねばならないが、そこは突く位の間隔しか空いてなく、とても斬って掛れはしな
いことが第二の難点。
第三の難点は、二メートルまたは三メートルの槍先で突くのであるなら、相手を中
心においてその円周の距離間隔で自由がきくから、自分が誤って近づかない限り、向
こうから害はうけずに済む。
処が刀の場合は鍔元から切先までは六十センチか七十センチゆえ、相手に刃を当て
ようとすると、どうしてもその三分の二に当たる二十センチまでの至近距離に近よら
ねばならぬ。つまり相手を円の中心とみると二十センチの円周内が、己れの行動半径
になる。
これでは斬るつもりが逆に斬られる危険性がでて、巧くいっても相い討ちの恐れが
どうしてもある。きわめて効果率が悪いのである。
だからテレビや映画では剣その他の持ち道具が揃わぬ関係から、みんなに刀をもた
せて恰好をつけているのも見かけるが、実際には戦場で刀は用いない。
大道寺友山の『武道初心集』でも、できるだけ刀で戦ってはならぬが、人目をひく
ように刀で武者働きがしたいのなら、すぐ折れて使い物にならなくなるものだから、
予備の差料を持参して供侍の若党にささせ、馬の口取り仲間にもおびさせ、生きた刀
掛けのように家来に何本も携行させねば、わが身が危いと注意書を残している。
つまり武士は雑兵以外は、槍を戦場の表道具としたものゆえ、「槍一筋の家柄」と
これからいわれ、古来、
「刀一筋の家柄」とか「刀二本の家門」などといわぬのも、この為なのである。なの
に、戦場において、さも刀を振ったように誤られているのは、何故かというと理由は
芝居からである。
現代では小道具屋の都合で槍が揃わず、ジュラルミンの刀を俳優はもたされ、やあ
やあやっている。が、昔はそうした理由ではなく舞台の横巾が五メートル位しかなか
ったゆえである。つまり、そこで登場人物に槍をもたせては、一人で横が一杯になっ
て、二人のからみがさせられない。
刀なら、雪月花の型でチャンチャン振り付けができ、見得もきれて絵になるからで
ある。つまり刀が一般化されたのは、舞台の狭さのせいでデフォルメされたのである。
塚原卜伝を筆先で作り出した伴信友も、軽輩ではあるが士分の出ゆえ、そこはよく
心得て、戦場で刀を振り回すような荒唐無稽はさせていない。そこでその著では、
「塚原卜伝は合戦九度の槍合せに、高名なる首を二十一個とり、その内には、槍下の
首、場中の槍での首など七個を含む武辺なり」
とかく。つまり剣豪ではなく槍豪であって、相手を絡み倒し垂直に咽喉を突き下し
た勇敢な槍下の首や、乱戦になってわあわあ取り囲まれながらも、その場の中で狙っ
た相手を、
「やあッ」と天晴れ突き立てて取った場中の首すらもある武辺者であった、というよ
うに説明をしているのである。
さてこうなると、「打ち刀」ともよばれた刀の、戦場における効果はなにかとなる。
京城の韓国士官学校講堂に掲げられてあるところの、
「日軍来襲の図」は、悪鬼羅刹さながらの朝鮮征伐の際の日本兵を描いたものだが、
先頭の足軽はみな裸身で二刀を両手で手にもちあげ、飛来する矢をそれで叩き切って
進撃している。
日本は鉄の産出がすくなくヨーロッパや中国みたいな鉄の携行楯がなく、けやきや
樫の八分か一寸厚味の板楯しかなかったので、とても重く持って進めず刀は矢払いに
用いられていたものらしい。
(江戸初期の宮本武蔵を二刀流の元祖)とするものもあるが、それより一世紀前から、
雑兵とよばれる連中は二本刀だった。が、この事実はさておき、雑兵でない将校クラ
スが刀をおびていたのは、
「者ども進めッ」と指揮刀代わりに用いていたのと、槍で突き倒した相手の首を切断
する際の包丁代わりと、後は戦闘には使わなかったとすれば、何用だったのかという
問題になる。
それに、室町御所の歴代の将軍家が卜伝から、
「一の太刀」の伝授をうけていたとすれば、非戦闘的なものを何故わざわざ習ったか
という事になる。
いわゆる武芸の習得ならば、槍術をこそ学ぶべきなのに変ではないかとなるからで
ある。
しかし考えてみれば、将軍家みずからが先頭になって、
「それ突いてこまそ」と敵陣へ掛ってゆくわけなどはない。
もっとそれより必要なことは、不意を襲われて槍で突かれる暗殺を防ぐことである。
だから『甲陽軍鑑』という本は、あまり内容的には信用できない俗書にすぎないけれ
ど、それに出てくる塚原卜伝の原型を、もし実在の者とみるなら、それは今でいう、
「護身術コンサルタント」ではあるまいか。
と想う。つまり何時何処から不意に曲者に突いてこられても、これを素早く打ち払
うコツを教えていたものだと考えられる。なにしろ一の太刀で払いのけなくては生命
に係るから、えらい人も習ったのだろう。
つまり塚原卜伝は攻撃型の指南番でなく、防禦型の師匠であって、剣豪というより、
防豪とよぶのが正しかったのではあるまいか。
剣とはそういうもので、またそうした用途のために片刃だったのである。
テレビや映画で、剣豪が刀身を鞘に納めながら、にっこりと、
「今のは峯打ちじゃ」つまり刃でない背の方で切ったのだから、生命には関係ない心
配するなと、見世場を作る場面がある。
だが刀とは、なにも峯打ち用に片刃になっていて和戦両用に巧くできているのでは
ない。
片方にしか刃がついていないのは安全剃刀とは違い、
「打ち払い斥ける」のだけが使用目的だったからこそ、つまり被占領民の原住系に差
別して持たされていたがゆえに、ああなっていたのであることを考えて頂きたいもの
である。
http://www.rekishi.info/library/yagiri/scrn2.cgi?n=1081
ほら吹きは奴隷の叫び
「素波」「乱波」といった当て字をされているが、三田村鳶魚の考証では、このスッ
パやラッパというのは、多くは近江の甲賀の者か、さもなければ伊賀の者であると説
明をされ、何をするものかといえば、ラッパは使われている国の悪人を探して見つけ
たり、出先では、山賊、海賊なんでもやってのけた。すなわち敵国を荒らすので、こ
れはなかなか智慧がないと出来ない。謀略も巧みでなければ勤まらぬものである、と
いった具合になっていて、この、
『江戸の白浪』の中の一文が、ずっとその後も信用され今でも一般に引用されている。
つまり、それからというものは、彼らはさながら特殊な者の扱いで、
「スッパ」「ラッパ」といった類は、甲賀者、伊賀者と同義語に扱われだしている。
しかし、そうなると彼らは近江の甲賀、そして伊勢の両地方にだけ発生した存在だっ
たということになるけれど、そういう解釈で、はたしてよいものだろうか。
また「江戸の白浪」の中では、山鹿素行が松平定信の祖父定綱のために書いて提出
したと伝わる『武教全書』を引例してからが、三田村説は、
「忍びとは、海賊、山賊、強盗、窃盗の内の窃盗で、人知れず働く者ゆえ、気づかれ
ぬように適地へ忍びこみ、敵の物を奪ってくるのだから、偵察であると同時に窃盗な
のである」と、はっきりいいきってもいる。
「忍び」という言葉から、「忍びこむ」となり、そして、何かを持ち出してくるから
盗みであるという極めつけ方であるが、はたしてラッパやスッパは泥棒だったのだろ
うか。
また、せっかく乱波素波と区分しているのに、その違いも研究せずに一緒くたにし
ているけれど、似たようなもので名称だけの差であったと彼はいうつもりだったのか、
そこの処が他には何も書いてないから判らないのである。
しかし明治、大正、昭和にかけて、
「時代考証家」として令名のあった人ゆえ誰も疑わずみなそのまま鵜呑みにしている
が、こういう無茶な考証が荒唐無稽な「忍びの者」や「くの一」などを生みだしたも
とだろう。
もちろん彼は江戸物の考証にかけては、信頼のおける人である。しかし専門でない
戦国時代に関しては、どうだろうかといいたいだけである。
というのは、スッパ、ラッパと縮めてしまうから、それで判らなくなるが、これは
もともと、
「スッ八」「ラッ八」が正しいからである。
「八」というのは前にも書いたが、八世紀に山中や孤島へ追われた原住系の民のこと
で頼朝の死後、北条政権によってやはり終われ、それらと混じった源氏の者の集団。
つまり足利時代には前述してあるごとく、
「白旗党余類」とよばれていた連中がこれなのである。刀伊の来攻の時に山から狩り
出されてきた彼らは、その後、前九年、後三年の役をやらされ、生還した者の一部は、
ときの後鳥羽上皇の有難い思召しで、北面の武士に採用されたが、その他の者は、ま
た山奥へ戻った。
これらの者が応仁の乱の人手不足で、人買いの手をへて山から連れ出されてきた。
そして山名、細川の両陣営へ奴隷として生涯奉公で売り渡され、死ぬまでいわば矢よ
けの人間楯として使われていた足軽がそれである。
さて、それまで、平城(ひらじろ)とよばれる従来の物は、
(いつ何時ふいに敵に攻められるか)といった戦乱の時代になってくると、どうして
も、
「これでは用心が悪い」というのであろうか、それぞれ山城に変わってきた。
こうなると築くにしろ、また守るにしろ、山に馴れた八の者が使いやすいので、お
おいに需要がふえ、集団で山から買われてくるようになった。というのは、築くとか
守るといった他に、攻める側の方でも、攻撃用には山馴れした彼らを必要としたから
である。
さて、平城の場合は物見櫓に上って見渡せば、
「やや彼処に何十人、此方にはおよそ百」
と、いった具合に押寄せてくる人数をすぐ読みとれるが、これが山城となるとそう
はゆかぬ。
「はてあの杉木立辺りが怪しいし、櫟林の方にも敵が迫っているらしいが、てんで姿
が見あたらぬ。気配はすれども影なし、ほんにやつらは‥‥のような」ともなりかね
ない。
こうなると攻めるも守るも、平地の城合戦の時とは違って、一種の神経戦になって
くる。そして、この足利末期から戦国初期の戦争というのは、『加越闘諍記』の巻一
にも、
「それ仏法の大魔は、武士にとっては怨敵なれば、本願寺より上人が下りきて、吉崎
と申す所に道場をもうけ、御山と号し布教を始め、超越寺、勝厳寺など出来て繁昌す
るを、加州の守護富樫介は面白からず、よって種々の妨害を加えしかば、長享二年
[1488]九月九日門徒の面々、城を取り巻きて力攻めにし、ついに富樫介一党は
みな自尽しおえぬ」とあるような有様だった。
つまり白衣を纏い白紙の御幣をふる神主や行者、修験者を先頭にした武士団と、墨
染の僧衣をきた法師団との衝突である。中世期はヨーロッパでも日本でも宗教戦争だ
ったのだ。
さて、寺というのは昔から平地にあると、反仏的な連中の襲撃をうけていたので、
難をさけるため山の上に造営し、よって、
「本山」などと号していた。しかし当時のことゆえケーブルカーやロープウェイなど
はない。それに昔は空中から農薬散布などしなかったから、山には獣も多くいた。そ
こで、
『千手経』に、「諸元善神を招き呼ばんと欲する時は、まさに宝螺(ほら)を吹くべ
し」とあるホラ貝をば、
(天にまします神を迎えるためという‥‥インド教の伝え)
とは違って、狼や山犬を迎えぬために、つまり近よせず追っ払ってしまうために、
ヴォウヴォウと僧兵は吹きならして山から麓へおりていた。
さて、戦になるとこのホラ貝が、
(ホルンの角笛同様に極めて遠くまで達するこの貝の音は、高麗王朝恭悪愍王の時か
ら、軍楽器として重用され使用されていた故事)
にならってかどうか、まず仏教側が用いだした。加賀の守護富樫介の城が落ちたの
も、万雷の轟きわたるようなこだまする貝の音に、
「これは容易ならぬ大軍に囲まれたりとみゆ。もはや落城は火をみるより明らかなり、
いで潔よく早々に自害をこそ致すべけり」
すっかり度肝を抜かれた富樫介が、もはやこれまでと見切りをつけ、己が妻子に刃
をあて先に殺したゆえと伝わっている。
さて音響効果というものは、ハイファイのなかった頃でも充分に有ったのである。
山で吹きならすとコダマして轟き鳴り渡るホラ貝は、
「味方の志気を鼓舞するのに極めて宜しい」
「敵を攻める際にホラ貝を吹きたてると、味方の実勢が三、四倍にも聴こえて、向こ
うがひるむから、場合によっては戦わずして勝つ事もできる」
というように新兵器として、もてはやされるようになった。
つまり今でも、オーバーないい方をするのを、「ホラを吹く」と称するのはこれか
らであるが、さて仏徒側には山法師などという、
「ホラ吹き」が揃っていたが、白旗党の武士団には、そうした輸入楽器の奏者はいな
い。しかも、それら奏者は、まっ先駈けて突進して、最前線でブオウブオッと吹かな
い事には効果がない。
そこで眼をつけられたのが山者、つまり別所から買われてくる者達である。かつて
の軍隊経験者なら知っていようが、ラッパというのは肺活量の大きな者でないと、い
くら吹いても音が出ない。
ましてシンチュウ[真鍮]製のピカピカしたラッパより、遥かに原始的なホラ貝で
ある。そこで吹いて音が出るか出ないか、最初から口へ当てがわせて、ブオウとやら
せてみると、すぐ合格、不合格の判定がついた。だからして人買いブローカーは、そ
れでまず選び分け、
「ホラの音の出せるのは、らっ八」
「ホラ貝の吹けぬ連中は、素っ八」
といったふうに分類して、買ってきた男共をセールスしたものらしい。
「ラッパ」というのはポルトガル語で、天文年間(1532〜54)の輸入のように
思われているが、足利末期の『永亨記』にも、
「羅八の輩」の字もでてくるから、明国経由でもう伝わっていたのかも知れない。し
かし一般には、「貝」または「かい」で、ホラ貝のことは通っていた。
さて日本ではとれず、海外から輸入されていたホラ貝は、足利末期で米二十俵に一
個という位に、極めて高価なものだった。
武将や大名だからといって、誰もが皆そんな高値な物を簡単に揃えられるわけもな
く、そこで家来を出陣させる時でも、
「それ、ほら貝吹きの者らをつれてゆけ」
と片っ端から配属するといった事もなかった。
だが貝をもっていた部隊と、そうでない部隊とは士気が違う。
それゆえ負けて戻ってきた部隊は、敗因を貝にかこつけ、
「貝なければ」などといったし、それを持たない不甲斐ない大将を、
「かいなき大将」ともいう。ホラ貝が案外早く実戦に用いられたとみられるのは、
『源平盛衰記』や『吾妻鑑』の中にも現れてくるからである。
(どうも当時の平氏が福原の港から沢山輸入していたのではないかとも想える。これ
に関しては山中鹿之助が、布部合戦で毛利氏に負け尼子勝久を伴って海賊をしていた
とき、瀬戸内海の離島に匿してある昔のホラ貝の有り場所をみつけて歩き、それを売
って作った軍資金で天正四年(1576)に因幡の国で旗あげ、のち播磨の上月城に
たてこもった、という話もあるのである)
だから、ラッパの吹けるのがラッ八、吹けないのが、唯のスッ八といわれても、な
にも伊賀や甲賀の者と限ってはいなかった。
それを結びつけたのは、どうも後年のこじつけに他ならない。
というのは、足利後期には、ラッパ、スッパから「足白、足軽」と呼ばれていたに
せよ、彼らは打ち続く戦乱にかり出され命がけで揉まれている内に、戦場で落ちてい
る槍や刀を手に入れ、敵の鎧や冑を奪って己れの物となし、上から下まで見なり[身
なり?]の恰好を整え、
「寸法(ずんぽう)武者」とよばれる戦国武者になるが、やがて運の良い者は、戦国
大名にまでなり上がった。そこで、昔が昔ゆえに彼らには、
「切り取り強盗、武士の慣い」といった不文律さえ生れてくる。
徳川体制の最下級に組入れられ有名になった甲賀や伊賀者だけに、ラッパスッパは
しぼれない。彼らは東北から九州まで日本全国二千余の別所から出ていて、近江浅井
別所出身脇坂甚内のような大名さえもいる。つまり甲賀伊賀というのは、そこからの
出身大名がいなくて、施政上差し障りなかったせいではあるまいかと想う。また戦前
の修身教科書で、
「死ぬまで口からラッパを放しませんでした」で有名な主人公の名が、ある名前から
突然に、「木口小平」に変わったのも、その白神姓が別所特有の白山神の姓だったの
が判明した為といわれる。
つまり、かつての貝は貴重品だったゆえ、初期の奴隷ラッパである別所者は死んで
も大切にしていた名残りでもあろうか。いたましい話である。
忍びと忍術の差異
村山知義がアカハタの日曜版に『忍びの者』を書いてから、忍法ブームが復活した
が、かつての立川文庫の『猿飛佐助』『霧隠才蔵』たるや、
「おのれ狸親爺めッ、ひとつ眼にものみせてくれんと、佐助が九字をきりますれば、
家康の面前の朱盃が、満々と酒をたたえた侭で、ひらりひらりと、花に戯むれる蝶の
ごとくに舞いまする。そこで、おのれッと控えて居りまする豪傑共が、不敵なり曲者
ッと立ち上がらんとしますと、これへ拳固がポカリポカリと飛んできて、みなコブだ
らけの有様。そのとき怪しき影が障子に映り、それッと寄ってたかって取り押えます
と、なんとこれが庭前の石どうろう」
といった具合に、きわめて実害のない、おおらかな忍術だったのに、これが忍者に
なってしまってからは、まったく殺気をおびてしまい、
「ビシッ、ビシッと息をつく間もなく、角々に刃のついた忍者特有のまきびしが飛ん
できて、当たれば命も危うくなろうという有様ゆえ、そこで己れッと鉄砲隊で包囲を
すれば、水上下駄をつっかけ、濠をすいすい水すましのように駈けてゆき、それなり
葭の茂みへ‥‥」
といった具合に、一見科学的みたいな変貌をとげてしまったが、そうした忍びの者
と、かつての、のんびりムードの忍術使いと、同じ系譜とは認めがたいし、それにど
う考えても忍法が実存ならば、
「ぱあっと印を結んで、さあっと姿を消してしまえる」といった便利調法[重宝?]
なものが、どうして、なぜ無くなってしまったのだろうかと残念でならない。
これに関して、これまでの説は、
「江戸期に入って戦がなくなり天下泰平になった。それゆえもはや需要がなくなり、
それで消滅してしまったものらしい」ということになっている。
だが、在郷軍人の奉公袋ではあるまいし、戦時中だけ必要で、平和になったらもう
不用といったものではあるまいと想う。
現在だって、テレビのショウ番組などへ、
「何々流何十代目」と名のって、門下を従えて現われ立合いの真似事をしてみせる見
世物みたいなのもあって、評論家の中には、
「今も残っている忍術」などと臆面もなく書いている観察度の甘いひともあるけれど、
実際にそんなのが有ったとしたら、どういう事になるか、そりゃ迷惑する向きもある
だろうが、試験中に蝿ブンブンに化けて、ひとの答案をみて廻る事もできるし、憧れ
のタレント嬢の居室へ潜りこみ、ヌードポスターでなく被写体の実物の方をとっくり
眺められ、そのうえ相手を、
「不動金縛りの法」にかければなんでもできる。催眠術より確実だろうし、もし露見
しても、旧式忍術ならば、さあっと石地蔵に化けてしまえばよいし、新派の方なら、
さあっと黒装束のまま、逆回転してマンションの階上へ飛び上り、マキビシなるもの
をパッパと飛ばせ相手を煙にまいて逃げてしまえばよいのである。
まあ道義的にそれは悪い事だから見合わせるにしても、そういう技術があって習得
できれば、テレビのビックリショウにだって出られる。
たとえ私みたいな音痴でも、姿をパアッと消してから唄ってみせたら、
「姿なき歌手」ということになって、レコード歌唱特別賞位はとれるかも知れぬ。
そこまで派手にしなくとも、尾行専門の私立探偵でも始めれば、密室のモーテルへ
もはいって行けて、のぞき趣味も満足させられるかも知れぬなどと、愚劣なことまで
つい考えさせられてしまう程である。
つまり忍術にしろ、忍びの術にしろ、どっちにしても結構なものである。それを平
和になった位で消してしまうのは勿体ない話である。
とはいうものの、まったく多くの人が半信半疑で信じているだけに変てこな話であ
る。
前術した村山知義の『忍びの者』が大向こうの喝采を博しえたのは、百々地三太夫、
藤林某という二人の伊賀の頭目は同一人だったという設定が当たったのだが、これに
は実在のモデルがある。
新徴組へ入って有名な甲州の博徒祐天仙之助の親分三井楼宇吉というのが、別に、
「猿屋の勘助」という名で、甲府の内外を押えていたという話があったから、それか
ら得たヒントだろう。
さて、戦争にさえ鉄の楯はもってゆけず、木楯はとても両手でもきつく、やむなく
雑兵は両刀を振って、飛びくる矢を払いのけつつ、いわゆる「露払い」となって出陣
したような国で、
(今でも鉄の生産はすくなく、戦前は中国の大冶鉱山の鉄、今でも外国よりの輸入鉄
で賄っている)
「矢尻一ヶが米三升」とされていた国で、やはり本物ならば一個で米五升にも当たろ
うとする高値な鉄製のまきびしを、あんなに気前よく忍びの者が撒けただろうか。
もちろん今では観光ブームに便乗して、伊賀市の市役所では、吏員の一人が黒装束
に身をやつして実演してみせたり、名張では、
「忍術羊かん」なども売っているが、鋳物のまきびしも本物らしくやはり並べ陳列し
ている。
しかしガラスのケースに入っているそれを、
「ほおうッ」と覗きこむよりも、かつて百々地三太夫らのいたといわれる、その忍術
のメッカの入口の字名が、今の左右ともに、
「界外(かいげ)」と名が残っていることへ、眼をむけ留意したいものである。
そこを通らねば他の部落へ出られぬ地帯が、界外ならば、その鎖(とざ)された一
廓は、「外界」でなければならぬからである。そうなると、
「村里へでて百姓に見つかりそうになった時は、獣の皮をかぶりて化けて通り抜ける
べし」とか、
「もし見つかりかけたら、田の中へとびこみ足を揃えて垂直に立ち、かかりに化ける
べし」
といったユーモラスな化け方がでているのも、決して面白半分のものではなく、も
っと切実な現実の厳しさを感じさせまいか。というのは、
「忍者の里」といわれる地帯は、例外なく何処でも別所だからである。かつての刀伊
の来攻で狩り出された山者の中で、後鳥羽上皇さま御仁慈によって、皇居警察官に採
用されたのが一部だけであったごとく、足利時代の末からの動乱期に、運よく戦国武
者になり、戦国大名になれたのが、やはり限られた者のみで、大半は鎖[とざ]され
た橋板の掛っていない川向こうに追いやられていたのである。
今でも五月五日を、男の子の節句といって、鯉のぼりをたて、ちまきで祝う。が、
あれも起こりは、『右近記』によれば、
「国府宮祭の五月五日に限り、田夷(農耕奴隷となって年貢を納め、編戸の民となっ
たもの)に俘囚の囲地を襲うを許す古例あり、その囲地を院地、印地というゆえ、こ
れを因地打ちという。双方共に石を投げあい、終には河原で投げ合いをなすゆえ、地
方にては<河原石合戦>などともいう」
とでている。つまり早まって占領系の宣撫策にのって、年貢を納める編戸の民であ
る百姓になった連中を慰撫するため、年に一回、
(院地へ日頃の鬱憤ばらしに何をやっても可、大目にみてやる)といった政治的な配
慮がなされたのだろう。
足利期の『東夷詠集』などみると、当時のお公卿さんは、この流血沙汰の石投げに、
今の南米人がサッカー試合に賭けるみたいに、やはり財物をだしあっている。当日つ
まり五月五日が、雨天になっては石合戦がお流れになってしまうと心配した詠草も入
っている。
襲った側が勝つと、堀の中に飼ってある鯉など掻っ払ってきて青竹につきさし、己
れの戸口に立てたり、あやめの葉が硬いからこれを投げる石にまきつけたしょうぶ石
を「千巻(ちまき)」ともいって、これが形式的に今も伝わっている。だが、さて表
向きは一日きりとなっていても、それは彼らが囲地の中にひっそり暮していての話で、
もし外へ出てきたら百姓に叩き殺されても仕方がなかったものらしい。
となると別所の者たちに伝わってきた術、それを「忍びの術」というなら、界外か
ら安全に外部へ忍び出る術なのであって、それを、
「忍術」というならば、
「いくら苛められ迫害されても、それにじっと堪えて、長い物にはまかれろと、おか
みのいいなりになって、それで生きてゆくことを許されようと忍ぶことの術」とみる
他はなかろう。
さて話は戻って、『後鑑附録』というのがある。それに、
「足利九代将軍義尚が足利尊氏の作った鈎(まがり)御殿に陣取り、そこから佐々木
高頼を攻めたとき、伊賀の河合安芸ら一族家士、忍において大功あり、ここに伊賀者
の名は世に高くなりぬ」
とあって、これが日本における忍術の初の出現とされ、後にはもっともらしく、河
合安芸らの一族が佐々木陣所へ忍びこみ、おおいに荒し廻り、神妙奇異の働きをなし
たように作られている。
しかし徳川家康の天正十年のかぶと越えのとき、ガードマンとして採用され白子の
浦までついてきた甲賀三十六家の和田八郎の書き残したものという『和田伝書』には、
「ささき方に召され、こが(くこの実)叺(かます)に入れてまきしに将軍家足をや
まれ(踏みぬき)河合らに探しあてられ、のち吾らきわめて難儀す」
とでている。つまりカラタチとかクコといわれる、コガの実を叺に入れて持って行
き、陣所の廻りへ防禦用に撒いていたら将軍家が誤ってそれを踏んづけ、夏のことな
ので化膿した。
そこで掃部(かもん)係として供していた河合伊賀らが踏まぬように熊手で集めて
処分したゆえ、彼らは取りたてられたが、自分らはおかげでひどい目にあったという
のである。しかし、そういう河合らも、
『甲州軍学記書』によれば、
「沼地にある固き四つ目菱を敵の進路にまき、半長や裸足の尖兵共をくいとめるは甲
州流の軍学なるに、近頃、丹波や伊勢の者ら、固き山栗のいがを乾し固めて、甲州菱
の代用になし、いが者などと呼ばれ各所に傭われてゆく」とある。
つまり、「まきびし」というのは、武田信玄流に沼地の固い菱の実をまくのが正統
派だが、丹波や伊勢の連中は代用品に乾燥させた栗のいがを撒いたというのである。
つまり忍術博物館陳列の鋳物のまきびしは、大正時代に、伊藤銀月という忍術研究
家が、
「忍術巻物一揃いにつき、郵券一円送れ」と、「少年世界」に広告していた時、鋳物
では角がついていても、当たっても突き刺さりはしないからと、警察で許可になった
通信販売セット物の残品なのだろう。
では火遁水遁の面白い忍術はというと、これにもそれぞれの手品の種みたいなもの
は、あるのだろうが、現実は厳しいというのが、本当のことをいってしまっては、身
も蓋もないというのは、こういう事をさすのでもあろうか。「遁」の一字も忍と同じ
で逃げることを意味している。
それにしても、かつては苛められ差別され、それを堪え忍ぶ為に生まれた忍術が、
観光ブームにのって羊かんや饅頭の冠名になったり、またはエロを売る大衆小説のオ
ブラートという偽装にされているのは、かつてそれらの人々の匿された歴史を顧みた
とき、これが人間の歴史というものかと、そんな侘しさをひたひたと胸の裡にうず高
く波うたせ、かさを増せさせてしまうのである。
悪人毛利元就
最近つぶれた出版社から出た国定教科書の復刻版が、まだ出廻っているのを見かけ
る。
『尋常小学校修身書』も本屋の店先で売られているが、その巻三の、第二十三章をあ
けると、
「三つ矢の教え」というのが出てくる。原文は長くて廻りくどいから要約すると、毛
利元就が、その子の隆元、元春、隆景の三人を集めて矢を一本ずつ持たせ、
「折ってみよ」と次々に折らせてから、今度は三本かためて渡し、折れぬのをみすま
してから、
「一本の矢ならたやすく折れるが、三本一緒では折れまい。お前たち兄弟も一人ずつ
では敵に負けるかも知れないが、三人兄弟が一つになって仲良く手を握りあえば、決
して他から侮られたり、戦を仕掛けられて負けることもない」といってきかせれば、
「はい、われらはこの世で三人きりの兄弟、今の御教訓をよく守りますでございまし
ょう」と、幼い三人は手をつき、白髯をしごく元就に対して固く誓いました。
このため毛利家は、三人の兄弟が互いに力を合せて助け合いましたから、いつまで
も栄えました----という内容である。
「一本の矢は折れても三本かためてなら折れない」
というのは力学をもち出さなくとも、常識で考えて当然のことだが、昭和四十三年
五月から十一月までは読売新聞連載の、
『戦国意外史』では、「元就の子供は三人ではない、男女とも十二人いた。この話は
<鳩翁道話>という江戸末期に流行した心学ものといった説教話にすぎぬ」とは解明
しておいたが、かつての修身とは、そんな頼りない作り話で吾々を道徳教育してくれ
たのかと思うと、教えてくれた先生が怨めしくなるし、気の毒にもなる。
しかし、瞞(だま)されたと気がついた時から、
「真実とは何か、それは何処にあるのか」と、そんな怨念に私はとりつかれ、土地を
売り飛ばしあらゆる物を換金し、資料になる古文書を買い漁り、そして人並な生活も
投げ出してしまって、他から押しつけられたり教わったものでない私なりの常識をも
って、
「過去は固定している。こびりついている。だから岩肌に貼りついている貝殻をこじ
りあけるようにしてゆけば、なんとかそこに閉じこもっている真実も見つかろう」と、
ひっしもっしに十有六年かかって、やがて、八切史観とよばれるものへうちこんでし
まった。
だから私の史観は、怨念の産物かも知れない。そして、それへ導いたのが、この毛
利元就の三つ矢の嘘だったとしたら、これに引っ掛かったのが私という人間にとって
生涯の、とんでもない取り返しもつかぬ誤りだったか、はたまた、これまで誰も手の
つけられぬ解明をし得た事について、生けるあかしありと歓ぶべきか‥‥本当のとこ
ろ今の私は判らない。
その内に一人でのたれ死するのだと覚悟はしているものの、やはりもの侘しいから
だろう。
さて、三つ矢の話は、大正時代には、尋常小学校読本巻五。五年生のときに習う
『読み方』の本にものっていて、
「第三、父の教え」という題で、名前も毛利元就ではなく、
「ある侍」となっているが、内容は修身の本と同じである。
だから、大正、昭和を通じて、学校の教科書でこれを習った中年の日本人にはこの、
「毛利三つ矢」説は常識みたいなものに、なってしまっていて、それを、今さら、
「間違っている」などと指摘しようものなら、殆どの人が、
「何をっ、ばかばかしい」と不快な表情で顔を横にそ向けてしまうだろう。
しかしどうも本当の事よりも、広く弘まっていることの方が、ともすれば正しいよ
うな錯覚を与えてしまい、それを是とし別に考えもせず、といったおざなりな国民性
が出来上がったのは、後述する大岡越前守忠相の弾圧政策からのことであろう。
しかし真実はあくまでも、どこまでも真実であらねばならない。
別に毛利元就の作った子供が、三人でも十人でも差支えないようなものだが、それ
でも引っ掛かりがでてくるのは、
「隆元、元春、隆景の三人兄弟が仲良く力を合わせましたから、毛利家はさかえまし
た」
という結びの一章からだろう。
なにしろ関ヶ原の天下分け目の合戦のとき。
既に毛利元就は亡く、その長男の隆元も死に、伜輝元の代になっていたが、小早川
隆景の方も、おねねの方こと秀吉の未亡人北の政所の甥にあたる秀秋が養子に入って
いて、
「金吾中納言秀秋」を名のっていたが、その血筋から関ヶ原では西軍の大将のような
立場にあった。
なのに、この小早川が、東西両軍激突の最中に松尾山から、それまでの味方の大谷
方へ鉄砲を射ちかけ俄かに裏切った。このため、それまで勝っていた西軍も総崩れと
なり敗走といった結果になる。
毛利家三つ矢の教えからすれば、いくら秀秋が養子とはいえ、毛利本家や吉川家が、
彼のなす儘に勝手に寝返りさせたとは、とても思えない。どうもこれは一つ穴のムジ
ナだったのだろう。
となると、三つ矢の教訓とは、
「儲かる方へ寝返りをうて、裏切りをしろ」という教えで、それを承知で修身や国語
の時間に、「教科書」という絶対的権威のもとに、なにも知らぬ児童に教えていたこ
とになるのだろうか。
さて、その小早川秀秋は裏切りの褒美に、
「五万一千五百石」を新たに家康から加増され、それまでの筑前名島から、備前岡山
城へと移ったが、二年たった慶長七年(1602)十月十八日に二十一歳で死んだ。
すると家康は、
「跡目の相続人の届出がでていなかった」
と幼い男児がいたのにこれを無視して、先に渡した五万一千五百石はもとより、そ
れ以前から秀秋が領していた筑前筑後五十二万二千五百石までエビで鯛を釣ったみた
いに一切を没取してしまった。
秀秋に裏切りさせた吉川元春の子の吉川元家や、西軍大将として兵一万人で大坂城
の留守居をしていた毛利輝元は、もし、
「三つ矢の家訓があるならば」そういう時こそ一緒に掛け合って、小早川の存続に尽
力すべきだと思うが、てんで何もしていない。
それどころか『吉川家譜』では、
「御本家毛利輝元さまとて西軍大将だったゆえ、もし吉川元家のすすめで小早川が裏
切らなかったら百二十万五千石は全部没取、その御命もなかった処である。それを助
命され周防長門三十六万石にてあれ家名が残れたは、吉川家の策よろしきを得た為で
ある」
ぬけぬけと裏切りの正当性をといている。
しかし毛利百二十万五千石、小早川五十二万二千五百石、吉川十四万二千石、しめ
て百八十七万石が、裏切りなどせず、
「毛利輝元が西軍総大将ゆえ、みっともない真似はできぬ」
と三家が揃って西軍のままで戦っていたら、これは誰が考えても、東軍の負けで、
「毛利家百二十万五千石」を三分の一以下に滅ぼされることもなく、小早川家とて秀
秋が死んだにせよ五十二万石はそのままで家名は残ったろう。
この当時、毛利三家の裏切りで西軍に組した大名はみな取り潰され、浪人が天下に
溢れたので、彼らはみな口を揃え、
「毛利の三馬鹿大将」と罵ったものだという。
これでは三つ矢の教えたるや、どうも本当のところはインチキでしかなくなる。
しかし毛利の危機は、その前にもあったのである。
秀吉は備中高松を攻めている最中、本能寺の変を知り、すぐさま取って返すため、
毛利と和約を結んだが、これは仕方なくしたことで、本心からなにも仲直りがしたか
った訳ではない。
折あらば毛利を滅ぼそうとしている内に、朝鮮征伐となった。
そこで九州名護屋へ行っていた処、
「大政所さま御危篤」の知らせが入った。そこで取るものもとりあえず秀吉は引き返
したが、今の門司と下関間の柳浦のところで、乗っていた船が海中の岩に衝突し沈ん
でしまった。
幸い海面に突き出ている岩へ泳ぎついたが、折柄の満潮にどんどん海水が上がって
きて、今にも岩は呑まれかけんとする有様。
こうなっては秀吉とても、どうできるものでもない。すでに足の踝まで浸してくる
海水に、歯の根をがたがたさせている処へ、
「あいや難波なされてか‥‥」と、小舟を漕ぎよせてきた若者が、
「さあお年より、救って進ぜましょう」
まさか秀吉とは知らず裸ん坊の相手を、抱えるようにして救命した。死中に生をえ
てほっと人心地ついた秀吉が、くだんの若者に、
「これ其方は何者じゃ」と尋ねると、
「礼儀を知らぬ爺さまだ。年よりのことゆえ勘弁してとらせるが、こういう時には助
けて貰った礼の一言ぐらいはいい、それから自分の方から私は何のなにがしでござい
ますと、先に言うものだ」
と口ではきつくいったが、寒かろうと自分の木綿織りの厚司(あつし)を肩にはお
らせた。そこで秀吉も、
「成程、いわれてみればその通り、こりゃわしの粗忽であった」
すぐ大きなくさめをしつつうなずき、
「危うい処を助けてくれ済まなんだ、礼をいうぞ‥‥実は、わしは太閤秀吉であるぞ」
とうちあけた。これには若者も、
「うへッ」とびっくりして三拝九拝。
「てまえ、四郎元清の伜めにてござりますして、今は亡き毛利元就の四男にて安芸猿
掛五千貫を領する者の跡目‥‥今までの御無礼は存ぜぬことと云いながら、平に平に
御容赦を程を」と詫びながら、白布の巻いたのを持ち出してきて、
「これは、てまえの替えの下帯でございますが、よお洗ってございますれば‥‥」と、
しなびた一物を股ぐらに挟んで居る秀吉へ、
「‥‥御免」と近よって背後から、六尺褌を廻し締め、
「いくらか暖うなりましてござりまするか」
と、伺いをたてた。すると、
「元就が四男というと、吉川御前の死後、五十余歳の元就が迎えた来島海賊衆の、十
五歳の孫のような嫁女に生まれさせた子の伜なるか‥‥」
毛利とは信長在世中から戦っていた秀吉は、よく知っていた。
「はい、その奈々は、てまえのおばばにござりまする」
「左様か、怒涛を漕ぎ切る手つきの鮮やかさには見とれていたが、来島の河野通有の
血をひくとあれば、生まれながらにして海に馴れとるも道理というもの」
すっかり感心したように秀吉は唸り、
「おれが名を一字くれてやらす、今日より秀元と名のるがよい」
そのまま大坂城へつれ戻り、丁度、城へきていた毛利元就の孫の輝元をすぐさま呼
びよせ、
「わしは、いつか毛利を滅ぼす気でいたが、この秀元に助けられたゆえ放念する。し
かし其方は百二十万石の大身で、同じ元就の孫のこれが五千石とはなんじゃ、今すぐ
譲れとはいわんが養子にでもせいやい」といいつけたが、せっかちな秀吉は、取りあ
えず、
「領所長門周防山口城は秀元の分、何人もこれを奪うべからず」と三十六万石分だけ
別扱いするよう五大老徳川家康らの加判までとった。‥‥このため関ヶ原役後毛利家
を丸ごと取ってしまうつもりだった家康も、周防長門三十六万石だけは毛利輝元に認
めざるをえなかったのである。
つまり本当に毛利家を幕末まで残すことのできた功績は、己れの下帯まで差しだし
た四郎元清の伜秀元の働きであるゆえ、これが三つ矢に入っていないのは怪しからん
といいたいのである。
その当座は、恐らく徳川家の権勢を恐れた重臣共が、
「四郎元清さまは故太閤に目をかけられた御方ゆえ、今の世では反体制‥‥」という
ので名を削ったにしろ、明治になっては、もう徳川家に気兼ねすることもないから、
せめて
「毛利は四つ矢」にすべきなのにしなかったのは、横着というか。それとも、
「論語よみの論語知らず」といった具合に、なにも判らなかったのかどちらかであろ
う。
なにしろ己が家来のこととか、茶器を値良く売るためにしか、歴史は必要でないと
いった考え方が伝統的で、自分本位にしか視野を向けぬ傾向が多く、純粋の歴史のた
めの歴史をといった風潮は、かつては希薄だったようである。
しかし民族の歴史とか真実の歴史とかいうものは、欲得抜きで誰かが取り組むしか
ないものであると想う。だからこの話の詳しくは『新戦国意外史』に入れてある。
だからといって、私がそれをしているというのではない。ただ「意外史」「裏がえ
史」と嫌いな向きには蛇蝎のごとく忌まれても、莫迦を承知で私は突破口をぎりぎり
に切り開くため、金てこでこつんこつんとやっているだけである。
といっても、曳かれ者の小唄か、負け惜しみのように受けとられるかも知れぬと、
つい自嘲めいた感慨の裡に筆が滑ってしまい、余計なことをつけたしたようである。
http://www.rekishi.info/library/yagiri/scrn2.cgi?n=1082
切った首利用法
『戦国武家事典』という本によれば、「首実験」は、
「大将右の手に扇子を持ち床机に腰かけ、その背後に弓持ちやその他の役人が立った
り列座している。首を持参してきた奏者は、すこし離れて右の方に座す。その座り方
は両膝を伏せて前にて足を組み、(これすべて軍中にての坐りようなりの註がついて
いる)さて次に大将の着座定まりて、弓持ちの役人座を立ちて、弓を大将にまいらせ
る。(首実験するのに何故、弓が入用かの註はついていない)よって大将は持ちたる
扇を腰にさし(或いは鎧の引き合にさすの註がある。要するにジャマッケだから、落
さぬように何処かへ挟んでおけということだろう)左手に弓を受けとりて、直ちに弦
を内側へなし右の方へ曲げて向け突くべし。よって弓を進めたる人は左へ巡って戻っ
てきて、もとの座へ帰って座る」
というのが始まりで、
「首板にすえた首の元取りを右手で提げ、左手を首板の下にすえ、受け持つ格好でも
って出て、門外または幕を巻き上げた処で坐して待ち、さて大将の実験となると、首
の耳へ親指を入れ他の四本の指で顎をささえ、首を仰向けにしたまま、すこし左へひ
ねって持ってゆき、首の右側を見せるのが作法である」となっている。
しかし血なまぐさい食うか食われるかの戦国時代に、こんな舞台でカブキ役者が、
メリハリをつけるようなカッコウの首実験のため、わざわざ重い思いをして、首を斬
って持ち戻ってきたのだろうかと首を傾げたくなる。
もちろん立派な武将の首ならばそれだけの値打ちもあり、重い思いをして持ち運ん
でも酬れるだろうが、豪い武将は小数でその他大勢の雑兵ぐらいの方がなんといって
も多い。そういう首など担いで持ち帰ったところで、それではまるで徒労のようにも
想えるが、何故なのか判らない。
それに封建時代というのは身分制がはっきり決っていたのである。
講談や大衆よみものでは、下郎階級の足軽小者でも首をとってくれば、
「よくやった」と昇進し、やがて将校クラスに当たる武者にもなれたようになってい
るが、実際はああいうことはなく、非士分の者は手柄をよしたてたとしても、その頭
分か主人の功績ということにされてしまい、当人へは、
「褒美」という形で銭か米の一時賞与がでたにすぎないのである。
決して非士分の者が手柄によって取立てられるという事がなかったのは、現在のよ
うに個人のバイタリーで能率給や手当のつく自由競争の時代ではなかったからである。
「家名」「家門」といったものに重きをおかれた封建時代は、扶持とよばれた年俸も、
個人ではなくそれに与えられるの定めだったからである。
となると、いくらの儲けにもならぬのに、足軽小者までが重い思いで担ぎ帰ったの
は、「首は叩っ斬って持ち戻るもの」といった概念から離れて考えると、まことに奇
妙すぎて変である。
「切腹作法」といったものがあるが、それと同じことで、この首実験のやり方も、芝
居のト書きというよりも見にいった観客が、舞台の役者たちの動きを、持っていった
矢立で帖面へ写しとって、それを纏めて、版元が適当にもっともらしい題名をつけ、
文化文政時代に木版ですって売らんがために刊行したものなのであろう。
(白砂に裏返しの黄畳、それに赤い毛せん。水色の青い裃に白衣の主役が、飴色の三
宝へ一礼して、白紙をまいた短刀をきらりと抜いて、腹にあて、赤い血綿を引っぱり
出す)
といったそのままカラフルな絵になる切腹の舞台と、この首実験も同じであるらし
い。
しかし実際は、切腹も首実験も、それらは、
「死」という凄惨なものと生者との対面である。
そんな絵になったり、またはめりはりがつく演技であろう筈がなかろうと想う。も
ちろん負けていては、敵の首を並べて確認している暇もないから、これは勝利の祝典
もかねるからして、
「めでたやのう」「祝着至極」と景気は良かったらしいが、それだからといって大相
撲の結びの一番が終った後のように、大将自身が、
「ただ今より、弓とり」といった行事をおこなうのも可笑しい。それに敵の首級をと
るという事自体が、その死を確認させるための証拠物件ゆえ、実際は大将に見せる前
に、その下準備として、
「目明し」とよばれた死者を生前から見知りの者に、面通しをさせ、
「何某の首に相違ない」と決まってから、各札を元取にぶら下げたり、耳へ穴をあけ
イヤリングのようにして提出したものである。
もちろん怨めしそうな顔をした死首など、とても、
「これは、これは」と鑑賞するものではないから、大抵の場合は、
「何某、誰某の首級にて間違いなきものにござります」
と係りの者が言上すると、大将なる者はろくすっぽ見もせずに、
「あっ、そうか」「ふん」と、夏ならば鼻をふさいでいったろう。
(死者に礼をつくすため、恭々しく生首と対面した)などとは、余程のサディストで
なくてはしなかったろうと想える。
というのは、取った首を持ち戻るのが、なにも大将の検分にそなえるのが主要目的
でないなら、それは早く一般公開で提示し、
「敵の誰某をかくは討ち取ったるぞ」とPRし味方の士気を高揚させるか、または
「勝利」を現実的に誇示するために必要だった故、「‥‥早うに」と、おん大将には
ろくすっぽ見せもせず、青竹の先につき立て、高張り提灯のように飾ったものであろ
う。
さて、敵将クラスの首は、持ち戻れば大将に見てもらえ恩賞にあずかるか、または
一般に公開されて、己れの名を弘めることも出来るが、名もなき敵の首までどうして
重たいのに、持ち戻ったかという疑問が湧いてくる。
ふつうの生首で七キロはあるが、もし冑でも冠っていようものなら十五キロは越す。
これを鎧具足を見につけ槍を抱えこんだ者が、どうして、
「えんやこら」と抱えて持ち帰ったのかということである。
もちろん、首を持ち帰るのは、それだけ敢闘をした証拠であり、
士分には「昇進」という戦功報酬もあった。
しかし封建時代の戦国の世では、前述したごとく士分以下の者の取った首は、あっ
さり主人の手柄とされてしまい、その主人から当人へは、
「平首なら一個につき銭何文、冑をつけた『もつけ』の首ならば、その何倍」という
給与規定が、何処でも一律に定まっていた。
だから捲き上げる主人の側は、冑つきの首は、もっけの幸いであっても、運んでく
る側では倍の褒美を貰っても目方が、二つ分なら、とんとんであって、たいして果報
にはならない。
処が、この時代は初めに書いたように、みなせっせと足軽の首でも叩っ斬って、
「重い重い」と、ふうふういいながら抱え戻ってきたのは、なんのためだったかとな
るが、それを考える前に、現在の日本では、
「大衆保健薬は、はたして効き目があるのか」とか、
「不良薬品を摘発する家庭薬の取締官が、その発明者とは情けない‥‥」
などと騒がれつつも、国民一人平均年間七千円の薬代を払っている事実。つまり日
本人はきわめて薬を呑むのが好きな国民だということを、まず想起してみたい。
というのは今でこそ色々の名称で新薬が出るのに、戦国期というのは曲直瀬道三の
著をみても、いわゆる草根皮の煎じ薬のみである。
これでは薬好きの当時の人間が困ったろうことは、想像にかたくない気がする。
さて現在でも名称が残って通用しているが、漢方薬で、
「生薬(きぐすり)」というのがある。生きる薬というのではなく、生きていた物を
原料にしたという動物性蛋白質のもので、なんとかの黒焼といった物が売られている。
イモリの黒焼もこの分類である。
岡崎城の築山御前が武田方の減敬とよぶ唐人医と秘かに通じていたのが見つかって、
謀叛の疑いを掛けられ、家康に殺されたという話もあるが、甲斐の山中にまで入りこ
んでいた程に、この時代には、
「唐人(からうど)」と呼ばれる明国人や高麗人の、医者とか薬屋というのが多く、
それが中国地方から関東そして九州にまで沢山に日本へきていた。
何をしに来ていたかというと、徐福が東海の日本へ不老不死の妙薬を探しにきたと
いう伝説にのっとってか、彼らは仙薬を仕入れにきていたものという。かつて私が
『謀殺』をかいた時の種本に用いた、貝原益軒門下樫原重軒の『養生訓読解例集』に
は、
「戦国の頃、武者どもが持ち来たる生首はさながら西瓜のごとく十個ずつ竹篭に入れ
られ、これを唐人の手下が縄でひきずってゆき、人気なき所にて、たがねにて頭骨を
割り味噌をすくい出し、乾し固めて丸薬となし、これを唐(みん)国へ送りて、大い
なる利をあぐという。のち泰平の世となりて、打ち首なくなり彼らは帰国すといえど、
その神効は本朝にも伝えられ、富士吉田の番太郎長兵衛は死罪人の頭を割ってこれを
製す。富士の妙薬、浅間六神丸というはこれなり」とある。
輸出ばかりでなく、やはり薬好きの国民性はその頃からで、国内需要もずっと盛ん
だったらしい。
つまり鼻や耳でも切ってくればよいのに、重い思いをして首を運んできたのは、決
まった定額の恩賞の他に、生首一個につきいくらと、当時の六神丸本舗の出張人が買
取りに出張していたからで、
「ええコウラ、もう一つおまけにええコウラ」
昔の武者は汗をかきつつ、何個もひきずって持ってきたものらしい。
現代はすべて使い棄ての世の中だが、昔はそうではなくなんでも大切にし廃物利用
を心がけ、死人を埋めるのにも、こやし代りに蜜柑の木の根方などを選んでいたもの
である。
だからして人間とても同様。死んだからといって焼いて灰にするような勿体ないこ
とはせず、普段でも生血は竹筒に入れて、
「労咳」にきくと、今なら胸部疾患特効薬とされ、肛門のところは抉り取られ、
「黄花剤」の名でレプラとよばれた天刑病の薬とされていた位のものである。
「ど頭[たま]かちわって味噌ぬいたるで」という喧嘩言葉が河内あたりには今も残
っているように、頭蓋骨をかち割って味噌抜きする位は、当たり前のことで当時の常
識といえ、格別珍しい事でもなかったのだろう。
戦国ウーマン・リブ
「江戸時代の司法が女性を避けるような傾向があったのは、これは戦国時代に女武者
が陣頭に現れると、勇士とか大将といわれた者は、相手にするのを恥じたものである
から、その名残りで女子供が相手にせずといった心持ちが、江戸の法律にも有ったよ
うである」という説がある。
それからして戦国時代の女は哀れだったなどと、臆面もなく書く連中が多くて困っ
たものである。
元禄以降(1688)は儒教隆昌とあいまって女は哀れとなったが前はそうでもな
い。
なにしろ徳川四天王の一人で、天文十七年(1548)から慶長十五年(1610)
まで生きていた、その当時の人間である本多平八郎忠勝は、
「わしの若い頃は、まだ人手不足で共に戦にでていた戦国の名残りで、武家の女房は、
みな、いざという時に顔を強くみせるよう太い描き眉をつける関係上、眉はすり落し、
口中も敵を威嚇するため、人間をくらってきたようにおはぐろというもので歯を染め
ていた。もちろん今でも武家の女房は古式を守って眉を落し口を染めているが、近頃
は美布や化粧品などが弘まり軟弱化してきたから、昔程かどうか判らん‥‥しかし戦
国時代の女武者の働きというは、今どきの男共など足許へもよれぬ程のものがあった
のだ」
という回想談をかき残している。これが徳川中期に見つかり、原文は内閣総理府図
書館に保存されているが、明治時代には、
「稀有な戦国史料」として活字本にもなっている。非売品だったし数も僅かなので初
めにその説を引用させて貰った故三田村鳶魚は見ていなかったらしい模様だが、こん
なに両極端に意見が違うと、どちらが真実か迷わざるをえない。
しかし世のおおかたの女性は、
「強かった」といわれるよりは、「哀れであった」と伝えられる方が、被害者意識的
でお涙頂戴と思うのか、あまりこれに意見はのべず、今の時代の方が増しなんだろう
と満足しているのか、
「涙にあけくれした戦国女性」といったのが、どうもよく読まれているらしい。
もちろん男のひとも、女が強かったなどというのは聞く耳持たぬ、といった風潮が
残っているせいなのか、
「戦後の女性は強くなった。されど昔の女性は清く美しく、それなりに哀れでありし
か」
といった感慨のもとに、そうしたでたらめなものに眼をそむけようともしないので
ある。
とはいえアメリカ模倣のウーマン・リブの時代では、
「はたして昔は弱く悲しく哀れだったのか、どうか」を改めて解明する必要もあるの
ではなかろうか。
なにしろ真実というものは一つである。楯の両面みたいに極端に分かれていてはい
けないのである。
さて、「講釈師みてきたような嘘をいい」というが、明治大正の頃の人間の書いた
ものより、その当時の天文生まれの本多平八郎の方が正しいのではなかろうか。
三田村鳶魚は江戸の刑法が、女人を避けるような設定の仕方がされているからと、
その点から遡って、そうした舞文曲筆をしたものらしいが、江戸の法律の根本をなす
処の、
「武家法度」の改正から諸政令が一斉に発布されたのは、寛永六年(1629)から
十年の間で将軍家光の時に当たる。そして、その時代というのは、
「寛永通宝の鋳造を下命された鳴海屋平蔵が、ときの老中筆頭の大老職土井甚三郎利
勝をさして<春日御局(おんつぼね)ご家老土井大炊頭(おおいのかみ)>と、その
鋳銭受け書の公文書にかいているような世の中」なのである。
この春日局が何故それ程までに権勢をふるっていたかは、後述するが、寛永六年か
らは恐れ多くも主上も女帝の明正さまであらせられる。だから東西ともに女上位の時
代だったのだから、その間に制定公布された法律で女人を敬遠し、なるべく処罰の対
象から外したのは、これまた当然なことである。
なにしろ一口に、江戸時代といっても三百年にわたっているのである。
元禄期以降からの、「女は三界に家なし」とか「女三従の教え」といった、女権が
落ちてしまった男尊時代の考えで、戦国から江戸初期を判断するのは三田村鳶魚の誤
りであろう。
『フロイス日本史』をみても、
「城主の夫に金を貸し高利をつけ、支払い不能とみるや己れの家臣をもって、強制執
行してその城や領地をとりあげ女城主になる例」
も当時は珍しくなかったと、青い目の彼がもの珍しげに、日本における女上位を、
他にも例をあげ本国へ報告している程である。フロイスといえばイエズス派の彼の先
輩の修道士らが、
「上杉謙信」と今日、その死後の戒名で名を伝えられている政虎(まんとら)が、
「勇猛なる女城主であったこと」を報告しているのは、私の『魔女拷問』にも紹介し
ておいたが、それを裏書する当時の舟乗りの書簡も残されている。
それはスペインのトレドの司書館に1571〜80年の報告書として保管されてい
る。日本でも、
『豊薩軍記』にでてくる高尾城の十七歳の女城主の勇戦敢闘ぶり。
『当代記』にある、信州高遠城の祝女の大奮戦記。
『備中兵乱記』の、常山城主三村高徳の妻の激闘。
『今川家記』の、引馬城主飯尾豊前の妻が、米ぬかで血止めした大薙刀で敵二十余騎
を倒し、傷つきた夫を庇って死んで行った話。
数えだしたら切りがない位に、板額や巴御前以降でも、女武者の奮闘ぶりは残され
ている。
これは白人の女などは、すぐキャアッと叫んで失神するが、ヤマドナデシコは火事
などの際にも、男は周章狼狽しきっても、そこは落着き払って重たい物でも、
「よいこらしょ」と抱えだして持ち出してしまう例が多いから、かつての彼女らも、
夫のため吾が子のため勇ましく戦ったのだろう。
『アーニーパイル戦記』によれば、オキナワ戦では伊江島の比嘉姉妹は、十八歳と十
六歳の少女二人だが火薬箱を抱き、アメリカ軍戦車のキャタピラに飛びこんで玉砕し
ながら擱坐*(かくざ)させてしまい、
「日本の女性は強い」と彼に書かせている。にもかかわらず、
「女は哀れだった」というのは男の自己満足なのか、またはそういって欲しい女の甘
えなのか、そのどちらかだろう。
*かく‐ざ【擱坐・擱座】
船が浅瀬に乗りあげること。戦車などがこわれて動けなくなることにも
いう。(『EB広辞苑第四版』‥‥影丸)
しかし近頃のように女子中学生がしごきをしたり、女の暴力団さえ現れるような世
相では、とても格好がつかぬから、時代を逆行させてしまい、
「戦国時代の女性は哀れであった」といったいい方をして、
「戦の時に奥方や娘が人質にとられたり、磔にかけられて殺されなどして、いたまし
くも不憫であった」と説明されている。
もちろん人質にとられたり磔にされ、ブスッと槍で突かれること自体は気の毒であ
るが、考えてみれば、なにも女性だけがそうした目にあわされたわけではなく、男も
磔にされたり首をちょん斬られ、その頭をかち割られ脳味噌を抜かれていた時代であ
る。
それに今でも質屋へAB二つの物をもってゆけば、「此方のほうを預かります」と
値打ちのある方を取られる。
という事は、戦国時代にあっては、女性の方が野郎よりも値打ちがあったからこそ、
それで人質にとられたのではあるまいか。
それに現代のように、
「女性を庇ってやるのが民主主義だ、騎士道なんだ」
といった考え方をもってしては判りにくいが、もし敵も味方もフェミニスト揃いで
あったと仮定するならば、
「女を磔にかけて殺すとは残酷ではないか」
ということになって、そんな事をしたら向こうの敵愾心を煽ってしまい、味方から
も批難抗議を浴びせられる羽目になってしまう。
しかし戦争というものは、何をやるにしても味方の士気を高揚させ、敵の士気は沮
喪(そそう)させねばならぬものであるから、今と違って、恐らくその時代にあって
は、
「よくぞ女を磔にかけて、ブスッと殺してくれよった」
と、すっかり男はみな快哉を叫んで、味方は勇気百倍。敵の方も城主の妻や娘で、
自分のではないからして、
「口うるさく、威張りくさっとる女ごを、気持ちようやってくれ、これまでの溜飲が
下がったわい」と、すっかり歓び勇みたち、
「男心は男でなけりゃ判るものか」と手をふって、
「昨日の敵は今日の友」と城門を開いて、双方が仲よくバンザイをしあったものでは
あるまいか。
----と書くと、今の観念をもってして、まさかと苦笑するむきも有るだろうが、日
本の戦国時代から江戸初期にかけては、ちょうど海の彼方のヨーロッパでも、
「男につべこべ文句をつける女」
「意地悪で手におえぬような女」
「怠け者で食っちゃあ寝てる女」
といったのは、優先扱いで、「魔女」のレッテルをはられ、最低七十万人から最高
七百万人の間、数ははっきりしていないが、ジェームズ一世の英国でもイサベラ女王
のスペインでも、みな丸裸にむかれて丸焼きされていたのである。
バスク人の刑吏が馬車につんできた女達を、生きた儘でローストにしたり、馬に引
張らせて股裂きするのをみて、西半球の男共が、
「讃えんかな神の御名を、アーメン」と、ヤンヤと喜んで見物し、口笛を吹き手を叩
いていた時に、東半球の日本人の男だけが、
「女を殺すは勿体ない、使えるものを惜しい、可哀想ではないか」
唯たんに好色だけで、それにあくまで反対していたとは考えられない。
どうも悪いのは、中世紀の魔女狩りで子宮ごと焼かれ消滅しているから、現代の女
性は、みなセレクトされた残りの後裔ゆえ屑はいなくてみな素晴らしいのばかりだろ
う。
が、その当時の玉石混淆の女人は、ヨーロッパでも日本でも、男の立場からすれば
手のつけられぬような悪いのが多かったからなのだろう。
『加越闘諍記』という前述した天文元亀頃の古史料によれば、一向門徒が越中越後の
反仏的な城をみな押さえたとき、まずまっ先にしたことは、
「広大無辺の御仏の慈悲をもってしても、何々御前(ごぜ)さまとか、北の方とよば
れて、これまで城にふんぞり返って、男の武者どもを顎の先で使い威張りくさってい
た女ごだけは、衆生済度の枠には、なんとしても入れようがない」
と、みな縫針を束にしたので眼をつぶし、無明地獄におとしこれを放逐したという
のである。
だから彼女らのことを、
「盲女」とか「瞽女」とかいて、「ごぜ」とよむのは、御前さまとよばれていた名残
りから、反仏の者らが悼んでのせいである。
だから一向宗の顕如上人の妹を義妻にもち、権大僧正だった武田信玄に対し、敢然
と迎え討った上杉政虎(まんとら)をたたえる瞽女唄には、
「とら年とら月とらの日、生まれ給いしまんとらさまは、白山さまおん為に赤槍立て
ての御出陣、男もおよばぬ強力無双」があり、
『越後瞽女屋敷、世襲山本ごい名』の唄本の中に、総平仮名で入っていたのが今は点
字で伝わっているのである。つまり今は上杉謙信と男のごとく誤られている彼女も、
かつては、
「捕らえられて盲にされてはかなわん」と気張って、川中島で戦ったのだろう。しか
し、こうしたガムシャラ女武者が多くて、寺側は困ったらしく、高野山のごときは、
つい最近まで「女人禁制」を厳しく励行して、女性は絶対に山に入れぬよう、敬して
遠ざけていた。
という事は、戦国期のウーマン・リブたるや、現代のごとく延々七時間もパンや肉
まんをかじって大掛りな井戸端会議をしているようなものではなく、
「不言実行」というか、しきりに武闘をもって、「戦う女のぐるうぷ」の実存をしめ
していたことになる。
『本多平八郎遺文』に、女は優しくみえる眉毛をすり落し口中を染めて敵を脅したと
あるが、
「女は三界に家なし」といわれたように圧迫されていた江戸時代でも、武家の女房は、
眉を落し口をお歯黒で染めて、一旦緩急あれば夫と共に共闘する体勢をとっていた。
なのに当今の女性は、アメリカ兵にガムやチョコレートを貰った半世紀前の時点か
ら、すっかり堕落しきっている。
まだ終戦時の日本女性は、それでも精神的支柱があったからこそ、あの敗戦の苦し
みにも堪えてこられたのだろうが、今度もし、ああした時代がきた時、いまの若い女
の人たちはどうするのだろうか。
余計なことかも知れないが、まったく冷や汗ものである。
女も人間であるとばかみたいな事をいう暇に、その怒りを胸に自分自身を振返って
ほしいものである。でないと、せっかく戦国時代の女の勇猛ぶりを、四百年前に書き
残しておいてくれた本多平八郎忠勝に、申訳ないことになってしまう。
http://www.rekishi.info/library/yagiri/scrn2.cgi?n=1083
鉄砲軽視由来記
それは奇妙なことかも知れないが、昔からして、
「槍一筋の家柄」とはいうが「鉄砲一挺の家柄」とはいわない。
「街道一の弓取り」は、立派な武将のことをさすが、
「街道一の鉄砲打ち」となると、これは猟師の事となる。
それに『信長公記』などには、信長が鉄砲を習ったようにでているが、一般には、
「鉄砲」というと、「足軽鉄砲」とされている。
だからでもあろうか前大戦でも、アメリカ軍は、閣下とよばれる準将クラスでも肩
章をとって自動小銃を小脇にバリバリ撃ちまくって突撃してくるのに、これに対する
日本軍は、下士官の軍曹や伍長あたりでも、斬れもせぬ昭和刀をぶら下げて、
「日本刀は武士の魂だ」とばかり鉄砲は足軽なみで、えらいのは刀だとやっていた。
だから、つい弾薬の補給もおろそかになったのか、各地で弾丸がなくなってしまい、
「切り込み隊を組織する」と、兵隊はゴボウ剣をもたされて敵中へ突撃させられ、バ
リバリ敵の弾丸にうたれて死んでしまった。
またどうしても吾々の手で日本を守らねばならぬ時がくるかも知れないが、そのと
き、やはり銃をもたされ出征させられるかも知れないが、またも同じように、
「日本刀こそは日本武士道の精華」といった幻想にまきこまれ、一般大衆である兵が
銃をもたされているが故に、軽視され棄て殺しにされるようでは困るのである。
と書くと、まさかと首をひねり反撥されようとなさる向きもあろうが、日本におい
てはアメリカかぶれしたウエスタンクラブまであって、モデルガンが持てはやされる
ような今日でさえ、銃は鉄砲は心の底では伝統的に蔑まれているのではあるまいか。
なにしろテレビにしろ映画にしろ吾国のもので、鉄砲を持って姿を現すのは悪人に
決まっている。
そして銃口を主役に向け撃とうとするのだが、まず第一段階で間一髪を入れず弾丸
より早い主役の剣さばきで斬り倒されるか、遠隔な場合は手裏剣のような主動式飛び
道具の方が早くて、これを妨げてしまい、鉄砲を持った相手は、
「‥‥おのれ無念」といった表情で樹の枝などから、見苦しい格好で転げ落ちる。
たとえ、それより増しの場合でも、弾丸の速度よりも早く脇から咄嗟に、銃の前へ
主役の二枚目を好いている鳥追い女などが現れ出てきて身代わりといった具合に撃た
れてしまい、
「己れッ卑怯な」といった言葉をはきつつ、女の敵とばかり大刀をふるった主役が、
鉄砲を握っている相手に斬りつける。そして、
(鉄砲なる卑怯未練な武器を使用した悪い奴)は、醜くもがき苦しみ、さながら天罰
をうけたように悶絶して転がり、見る側は、それを因果応報といった具合にうけとめ
内心ザマみあみろと痛快がる。
このパターンが日本人の思考というか趣向に合ったものとして、定型化されているお
もむきがある。
それゆえ現代を扱ったものでも、やはり銃は冷遇されている。一般のアクションで
銃をもつ悪い奴を如何にして素手の主役が、不自然でなく叩きのめすかという擬闘が、
その見せ場にさえなっている。つまりチャンバラ物の無手勝流である。
しかし銃に向かって素手の人間が掛ってゆくというような事は、現実にあっては、
精神障害か異常者でない限り有り得る筈はない。
なのに日本では銃を軽視するがゆえに、そうした無理な設定がなされ、いかに精巧
な銃をもつ相手よりも、剣道の達人の方が互角に立ち合っても、必ず勝つという具合
に画面から視覚教育をしたり、剣豪作家も平気でそうした紙芝居のようなものをかく。
だからして、そうした弊害によって、
「銃はむなしく、剣こそわが命」といった観念が、常識的には妄想であったにしても、
確固たる信条として日本人に植え付けられてしまい、それゆえに、
「鉄砲より強い日本刀」といったイメージがひろく浸透し、さて実戦にぶつかって、
(日本刀は極めて至近距離まで相手に近づかねば、まったくなんの用もなさないのに、
火器である鉄砲は遥か彼方からでも、もし望遠レンズなどつけていれば、肉眼では視
えぬ距離からでも狙撃できるものだ)といった判りきった現実いぶつかって挫折させ
られる。やがて、
つまり観念の中の日本刀の優位さが、現実に火器の前で脆くもその幻想を崩されて
しまったとき。かつての日本の軍刀をぶら下げていた人たちは、そうかわれ誤てりと
落ちている銃を拾って、武器の交換をするだけの心理的転換もできず、やけっぱちに
なってその日本刀を振り廻し突入し、近づけぬまま倒されてしまうか、または、もは
やこれまでなりと、敵を切るつもりで吊さげてきたもので吾れと吾身を、刺し貫くと
いった自虐の悲劇を演じたものである。
こうした事態が過去に何千何万の有為な人たちによって、幾度となくくり返されて
きた悲劇たるや、日本武士道、日本精神をうたい文句にした刀剣商の商魂のせいだっ
たのかも知れない。値よく売れればそれでよいというので、鋳物同然の昭和刀まで、
もっともらしい銘を刻みこませ、それを堂々と、
(刀剣商の推奨する刀さえ求めて戦地へ行けば、それが護身の役割をはたす)といっ
たような煽り方までして売りまくられたせいなのであろうか。
まぁ戦争というのは何処でも誰かが儲けるために企画されるといった裏面がないで
もないから、道具屋もそれに便乗して儲けるのだろうが、踊らされ死なされる方は堪
ったものではない。
が、それにしても、こうした日本刀を扱う業者の剣豪作家まで使う派手な売りこみ
で、つい、そちらを過信しすぎてしまい、鉄砲が軽視されるような過ちはもうくり返
して貰いたくはない。
目には目、歯には歯をで銃で向かうように、神がかり的なものから常識的な観点に
戻って、何故にそれ程までに、この国では銃を卑しみ軽んずるの傾向があるかを探す
必要もでてこよう。
織田信長が設楽原で木柵を三段構えに結んで、武田勝頼の騎馬隊を近づけず、これ
を銃撃でほぼ全滅させたことは有名である。
だからして歴史書などでは、
「天文十二年(1543)に種が島へ鉄砲が伝来してから、この新しい武器は戦国時
代の日本各地に、瞬く間に広まった」といったように説明される。
しかし本当はどうだったろうか。たとえば徳川家康などは、鉄砲隊の入用のときは
信長から借りていた。上杉謙信や武田信玄は、ろくに備えていなかった。比較的利用
していたのは、太平洋沿岸に城をもつ中国、九州の大名に限られていただけではない
かといった疑いも持てる。
また旧日本陸軍が、銃を軽視して、それより斬れなくても昭和刀を愛好したのは、
「銃器を生産していか歩兵工廠や、その下請けの軍需産業は、なにも宣伝広告しなく
とも、軍需局が一括購入してくれ、日銀払出し小切手で支払いもまるまる貰えた」
のに対して、刀は、刀伊来攻の時のようにお上での買上げではなく、
「古美術商」などと看板を掲げた骨董屋であるからして、この際がぼっと儲けようと、
正札をどんどん吊り上げ、
「日本刀物語」とか『名刀名工談』といった類の、もっともらしいPR版を何千部か
買取り契約で書店から出させた。前述のごとくこれまでの歴史作家と称する者に、こ
の種の著書がかつてあるのはこの為のものとみてよかろう。
つまり世間知らずの一般の軍人は、単純というか純粋なので広告しない銃器よりも、
どうしても、「今宵の虎徹は血に飢えているぞ」といった刀や、いわゆる名刀と宣伝
されている方に、心が傾き、使ってみる迄は切れ味も判らぬから、大量生産の当時の
昭和刀でも、外見の拵えさえ一人前なら満足してぶら下げ、
「剣だ」「剣だ」と吉川英治の宮本武蔵でも読みつつハッスルしていたのだろう。と
なると、いわゆる剣豪作家なる者も、まんざらこれに対して責任がないとはいい切れ
ぬかも知れなかろう。
しかし日本において銃たるものが実際は初めからてんで重視されなかったことは、
江戸時代の初期に難破して千代田城へ招かれたフィリッピン長官ドン・ロドリゴの見
聞録にも、
「太子(徳川秀忠)の護衛隊は長槍、短槍を林のごとく立てた四百人。そして中近東
のアラバルダに似たナンキナ(薙刀)を抱えた三百人。そして半弓、大弓の射手五百
人が遠巻きにして、櫓の上に整列して守備していた」
鉄砲伝来六十六年たっている割りには、あまりにこの国では鉄砲が重要視されてお
らず、城の入口に立っていた銃隊だけしか見かけていないから、それは儀式的なもの
かも知れぬと書いている。
だから、
「へぼ将棋、王より飛車を大事がり」というが、まだ弓矢の方が大切にされていた日
本では、この慶長十四年(1609)頃でさえ、あまり鉄砲は重要視されていなかっ
たとみえる。
まさか、剣だ、剣だとはいっていないが、もっぱら当時は弓と槍に重点をおいてい
たようである。また、つまりこういう具合だったから、この二百五十九年後に、上海
帰りのリルならぬグラバーによって輸入されたアメリカ南部の廃銃に、鳥羽伏見でい
ともあっさり負けるのである。
さて、それでは前述したごとく、どうして、今ではガンブームといわれる位に銃は
好かれ、ウエスタンクラブなどという格好だけの同好クラブさえある程なのに、かつ
ての日本では銃がそんなに好かれなかったのか?当時は銃砲取締り法などもなかった
筈なのに‥‥と疑問がでてくるが、この答えは簡単である。それは、
「日本では女人がまっ先に用いたから」なのではあるまいか。つまり戦国期にあって
は、銃とは敵に至近距離まで近よってゆけぬ婦女子の武器だったことに起因するもの
であるらしい。
つまり話は‥‥
九州大友家の重臣立花道雪の一人娘おぎんによって、わが国最初の銃隊が作られた
から、ここに鉄砲の悲劇が持ち上がるのである。
道雪は雷にうたれ下半身不随ゆえ、ぎんの他に子供はなく、また当時は女領主も珍
しくなかったからして、彼女を女城主にした。
さてアマゾンの女は弓をひくのに邪魔だからと、乳房を切ったというが、立花城の
女中や腰元も、当今とは違い隆起の大きいのは「まあ百姓女のごと出張っとるじゃん
け」と蔑まれるから、布できりきり胸もとをまきつけて出陣していたらしい。
処が、ぎんには乳姉妹にあたる娘が生まれつき不幸にも、胸部が隆起し、いくら布
で縛ってもすくすく大きくなって、なんともならず、そこは強いようでも女は女、困
ってしまって泣き暮していた。
そこで見かねて、女城主のぎんが、
「これを用いてみてつかあせ」と、試しに鉄砲をもたせたところ、これなら胸がいく
ら出張っていても、正面に向け突き出して発射するのだから、きわめて巧くゆく。そ
こで、ぎん自身も、
「胸をきつく晒木綿でまきつけるは苦しやのう」
と今でいえばノーブラにしたい一心で、銃をもってみると弓よりは扱いやすい。よ
って大友家へ願いでて銃を多く廻して貰い、「女銃隊」をここに新しく編成すること
になった。
すると、先殿の道雪は下半身不随で、その御所望がなく、現在の殿は女ゆえ、これ
またその方で立身出世の夢のない城内の女共が、
「私も」「てまえも」と入隊志望してきて、ここに百人組の銃隊が生まれることとな
り、大友家が他と戦う時は、まずこの立花ぎんの銃隊が、まっ先にどんどんと一斉射
撃をした。
九州の方言で、「最初」のことを「はな」という。そこで、
「はなは立花、鉄砲女ご」と有名になった。
しかし、女でも鉄砲を持たせると、一人前の働きをするということが、今も昔も変
わらぬ男の自尊心を傷つけたのであろう。
『武具要説』などという木版本では、
「敵との距離が遠い時には鉄砲は有利な武器に違いないが、いやしくも武士たるもの
が、飛び道具で相手を討ちとるのは賞められた事ではない」などの説をかかげた。
だからでもあろうか、前にも述べたように、日本の映画やテレビでは、
「おのれッ卑怯なやつ‥‥」と、鉄砲をもち出してくるのは悪役に限られていて、必
ずヒーローの投げる手裏剣か何かにやられ、
「うぬ、残念至極ッ」と、見当違いに弾丸をとばして、もんどり打って転げ落ちたり
する。そこで旧軍部などは、この影響で、「鉄砲はあかん」と思いこんでしまったの
であろうか。
さて、ぎんの女銃砲隊が評判になりすぎ、加藤清正さえが逃げて廻ったので、年下
の夫の立花宗茂に嫌われ、ぎんは棄てられて一人淋しく死んでしまったが、それでも
世の男共はやっかみ精神で、
「鉄砲を用いるのなら足軽にもたせい、それでよいんじゃ」と軽蔑した扱い方を何処
もし、かつてのぎんの勇姿も今となっては、
「はなはたちばな、茶の香り、チャッキリチャッキリ、チャッキリナ」の茶つみ唄で
しか、この世には残されていない。
もちろん、この他の理由は、鉄砲は日本でも雑賀や国友で直ちに精巧な物が作られ
るようになったが、弾丸をとばせる火薬の主成分の硝石が日本では採掘する所がない。
苦しまぎれに歴史家は、厠の辺りの土を天日に乾してその中から硝石をとって精製
したなどと説明するが、便所の周辺の土をいくら水でこして血眼になって蒐集した処
で、猪口の底に沈む位しか取れる筈がない。だから臭い思いをしてそんな事をしても
なんともなるものでなく、今も昔も硝石鉱の輸入にすっかり依存しているのである。
処が、弓矢の方はこれは何処にでも材料がはえていて自給自足できるという強味が
ある。
そこで将軍家でも、火薬を輸入させねばならぬ鉄砲よりも、昔からの弓矢でと千代
田城を守らせていたのだろうし、一般の士分も自給するとなれば一発射つのにでも、
その分の為には向こう三軒両隣の便所さらいせねば、硝石は集まらぬと聞かされる鉄
砲は、鼻つまみものになり軽蔑されていたのだろう。
明治になっても、刀は鍛えれば国産できるが、硝石だけは日本中何処を探しても産
出する鉱山がなく、石油資源よりももっと始末が悪いからと、軍としても、
「弾丸はあまり使うな、それより刀を用いろ。兵はいくら死んでも葉書で召集できる
が、硝石はそうはゆかんのだ」と、幹部教育の方針をたてていたのではなかろうかと
も想像される。
哀れなり築山御前
‥‥徳川家康の正妻築山御前が、
「岡崎三郎信康は吾がうみし子なれば、わがいいつけ通り致すべく。よって事が成就
せし時には、家康の押さえている三河は、そっくり信康に戻してやって頂きたく。ま
た私には、そちらさま御家中の内にて、しかるべき人を世話して下さり、その御方の
妻にしてほしく。この条件さえ守って下さるものなら、これから信康にもきっと申し
つけお味方するよう手筈をととのえましょう」とだした手紙に、
「ご子息の三郎どのが当方の味方となり、家康を挟み討ちするものなら、三河だけで
なく別に一国をつけて参らせ候。そして築山御前には、幸い甲府郡内で五万石をはむ
小山田兵衛という侍が、去年妻を失ってやもめでござれば、打ってつけと存じ彼の妻
にお世話致し申し候。天正六年十一月十六日
武田勝頼」
といった手紙の往復があった由が、『三河後風土記』にある。
築山御前がいくら滅ぼされた今川義元一族瀬名氏の姫であったとしても、松平元康
との間に、お亀、おあい、三郎と三人も子がある。
「女は七人の子をなすも心を許すな」と、昔からいいはするが、なぜ武田方へ男の世
話など頼んだのだろうか。唐人医者減敬とも怪しかったというが、今でいう「よろめ
き夫人」だったのだろうか。「女は、それを我慢できない」とはいうが、いくら女盛
りの三十八歳の有夫の女性が、別の男の妻になりたいとは、今でいう重婚罪にあたる
が、築山御前はそんなにまでもの狂おしい女性だったのか‥‥どうも、これは首を傾
げたくもなる。
さて、それともう一つ関連して可笑しいことは、その夫とされる家康が彼女より遥
かに年下だった事である。なにしろ、もし二人でそれまでに子をなしたものなら、長
女お亀ごときは十三歳の子だから、受胎させたのは家康が十二歳という時点である。
戦国時代はなんといっても戦をするのに人手が入用だったから、女子のそのあかし
がみえると赤飯をたき、早速そこの組頭が、子をはらめるようになったものを、空
(あき)っ腹にしておく事やあると、女性を子作りの器械のごとくに扱ったから、十
四、五歳の幼な妻も当時は珍しくなかったが、だからといって形式的だけならいざ知
らず、実質的に男も幼な夫や幼い父になれたものかどうか疑問に想える。
現代と違って粗食だった頃の十二歳である。精神的に早熟であったとしても肉体的
にまで、一人前の生殖機能がもう働いていたなどとは、これは常識的にも考えられぬ
処である。
つまり築山御前がよろめいたとかよろめかぬといった詮索よりも、彼が彼女をどう
して小学校の五年生位の年頃で受胎させられたかといった不思議さの方に引っ掛かる
ものがある。
しかもお亀のみだけでなく翌年は年子で、おあい、その二年後に、のちの岡崎三郎
信康と、十五歳のときの徳川家康が既に三人の子持ちという方が変ではなかろうか。
これに対し、いくら今川一族の女であれ、夫が夫というには余りにも若すぎるから
とはいえ、一人のみならず連続三人も子を他から仕込み、それをもって----というの
は余りにも詭弁すぎなかろうか。
常識としてはやはり夫と築山御前の子、とみるが妥当であろう。
となると怪しむべきは彼女ではなくして、その夫の方になるのだが、なにしろ八代
将軍吉宗の時の大岡忠相によって徳川家のそうした事柄は一切秘密にされてしまって
いる。そこで、今でも松平蔵人元康と名のっていた彼女の夫が家康と改名し彼女を殺
したのだ、という男女の生理をまるで無視し切ったものが堂々と出版され読まれてい
るのである。
まず『三河後風土記』というのは、多くの歴史家が史料として扱い、文政、天保と、
読み本として何度も版行された物が多く出廻っているので、小説家まで種本にするが、
これは明治四十四年に非売品として出された『史籍雑纂』第三巻に収録されていると
ころの、
「大系図抄」に、はっきりと、
「江戸の元禄時代まで生きていた近江の百姓沢田源内、という贋系図屋が、その余暇
に書き上げた贋造史料本の一つで、内容が面白いのは、興味本位に書かれてあるせい
だ」と、すっぱぬかれているものだ。
だから、築山御前が、悶々の情に堪えかねているから、なんとか男を世話して頂戴。
そうすれば伜の三郎信康にいいつけ裏切らせまする、という手紙や、それに対し鹿爪
らしく、
「小山田備中守兵衛というのが妻を去年なくして空いている。穴埋めに用いられるの
に、それでは如何でござろうや」
まるで結婚相談所長のように、武田勝頼が返事をだしているのも、共に沢田源内の
フィクションという事になる。詰らないが事実ではないので、これはしようがない。
しかし天正七年八月二十九日夕、
「こないな所へまで連れてきやって‥‥なんと」
いぶかしそうに、輿から降ろされた築山御前が、浜名湖の水面を渡ってくる風にそ
よぐ葦草の茂みの中で振りむいたところ、
「主命なれば、御免なされましょう」
供してきた野中三五郎は、己が従者に持たせてきた槍の鞘を払いざま、しごくと見
せかけて、そのまま躍りこんでの一と突き。
「あッ」と乳房の下にくいこんだ槍の穂先を抜こうと身悶えし、築山御前は、苦しい
息の下から搾り出すようにして、
「‥‥主命といやるは家康どのがことか」
「はあッ、仰せの通り」と槍の穂先を抉るがごとく捻じあげれば、
「信康が成人するまで後見人をなし、自分は遠江だけでよいから浜松城を守り、岡崎
の城はそっくり戻すといいおったは嘘なりしか」
麻の葉打ち抜き柄の白地上布の胸許を、まるで山つつじのように、真紅に染めつつ
築山御前は、
「ひとに怨みつらみが有るものか、ないものか、よお覚えておきや‥‥」というも、
もはや喘ぎながらの有様、
それでも気強く、葦草の株を掴んで倒れまいとしつつ、
「この身をここまで誘き出して仕止めるからには‥‥気になるは伜三郎信康のこと‥
‥どないしやると‥‥いえ。さあぬかせ」
青白い月の光りに照らされ、もの凄い形相で、はったと睨みつけられては、野中三
五郎も膝頭にがくがく震えがきてしまい、
「早うに止めを‥‥」
「お、おん首討ち奉れや」と、己れは槍をつけたまま、まるで棒押しの格好で、従え
てきた野郎共に吃りながら命じた。という事になっている。
さて現在、浜松市広沢町にある西来院には、
「清池院殿潭月秋天(大禅尼法尼)淑霊」と彫られた石塔と、
「奉献、亨保八年八月二十九日、野中三五郎重政の曾孫、野中三五郎源友重同、敬白」
と文字の入っている古い石灯篭が二つある。
もし築山御前が、よろめいたり裏切って武田方に加担しようとして、殺されたもの
ならこれは仕方のないことで、なにも三五郎の曾孫が、お詫びに石灯篭を納めること
はない。
これは無実の者に濡衣をきせての殺害ゆえ、野中の家では代々、
「築山御前さまの祟りではないか」というようなことが相ついで起き、そこでやむな
く曾孫の代になってから、祥月命日(しょうつきめいにち)に無理して灯篭を寄進、
「これでひとつ、迷わず御成仏なされませ」
と三拝九拝して、泉下の霊を慰めたのだろう。
しかし戒名がついているだけでも、まだ築山御前は増しである。
『次郎長外伝』の「秋葉の火祭り」で名高い、山へ登る参拝道の入口になっている遠
州二股の、清竜寺にある、岡崎三郎信康廟はもっとひどい。
古びた扉に小さな葵紋がついているが、これは明治になって付けられた扉で、その
以前は土をかためた築地塀だけだったという。
そして、中央に石を五個、どうにか落ちないように、重ねて立てられているのが、
岡崎三郎の墓だというのだが、文字などは一つも彫られていない。
恐らく徳川十五代の間は、ここは、
「お止め墓」として、何人も参拝を許されなかったものではあるまいか。某作家の、
『徳川家康』の本の中では、
「なにッ信長公が、妻の築山と、吾が子の信康を成敗せいと仰せられるのか‥‥むご
やそないに酷い話があるものか‥‥」
「はあッ、御気持の程は、われら家人も、よおわきまえおりまするが、いま信長公の
御下知にそむくはかなわぬこと」
「そうか、この家康は、徳川の家のため、いとしき妻や、最愛の子まで、信長公の命
令とあれば、失わねばならぬのか‥‥」
と悲歎にくれる名場面として描かれているが、それにしては、戒名さえ刻むのを許
されなかった墓とは、くい違いがありすぎる。
さて、前に新田義貞の個所で、「世良田系として出ている家康の系図」を平凡社
『大百科事典』から引用して置いたが、
「世良田系の家康そのひと」と、「松平元康改姓名と伝わる家康」
とは、まったく別人らしい。これは尾張七代目当主の宗春が、その家康の玄孫に当
たる関係上、奥州梁川三万石の城主から兄継友の跡をついで尾張へ戻ってきて後、今
でいう郷土史家を動員し、尾張における家康の事跡を、六十二万石の力で調べ直して
みた。すると、
「松平元康の家康と、世良田の家康が、石が瀬と和田山で、二度までも正面衝突して
戦をした」という事実が見つけだされた。しかも、
「松平方の三河兵はプロの軍人なのに、東照権現さまの方は、伊勢の薬売り上りの榊
原小平太、遠州井伊谷の神官くずれの井伊党。渥美半島の木こり大久保党、駿府の修
験上りの酒井党といった寄せ集めのアマばかりゆえ、いつも戦ってはころ負けしてい
た」
というのである。これを発表したばかりに宗春は、
「不行届なり」と六十二万石をくびにされその後、尾張は御三家であるのに一人も将
軍になれず、それ処か田安家から養子を取らされた。その『草春院目録』によって、
『徳川家康は二人だった』を<八切日本史>にかいているが、築山御前は家康と枕は
共にさせられたかも知れないが、正式には松平元康未亡人であって、家康夫人ではな
い。
だから「後釜の男に小山田備中守はどうだろうか」などと贋作では書かれたりもす
るが、単身であるならば、それでもよろめきとはいえない。
天海僧正は、明智光秀か
上野公園にある寛永寺とか、埼玉県川越市の喜多院住持として、天海は有名であり、
『真宗伝記』の著作もよく知られている。
が、一般には1536年(天文五年)生まれで1643年(寛永二十年)に没、つ
まり百八歳までの長寿を保ったという点で、
「平均寿命が伸びた現在でさえ百歳以上は珍しい」のに、
「人間僅か五十年」が定年制だった時代に、そういう高年齢は信ぜられぬので、疑問
をもたれている。というのは昔から、
「めでたやな、めでたやな、三浦の大助百八ツ」
という長寿祝い唄があるごとく、百八という年齢は、実際年齢をさすのではなく、
長寿を象徴する熟語であるからである。
そして、この年齢不祥の僧正については多くの異説があるが、武田信玄をたよって、
延暦寺の僧徒と交流があり、七福神法の慧心流の幽旨をきわめ、天正五年上州世良田
の真言院長楽寺にて、豪春より密教の葉上流の奥義をうけたという。
だから徳川家康との結びつきは、世良田の在が家康の故郷なら、それでも判りうる
というものだが、天海が晩年に、
「一実神道」を説きだして、崇伝や本多正純と衝突したり、
「黒衣の宰相」とよばれた位に家康の生前は、宗教問題ばかりでなく政事や軍事にも、
相談役のように嘴を入れていたから、
「武将上りではないか」といわれ、そのため明智光秀その人ではなかったかとの説が
あるが、はたして同一人物だったのだろうか。
これは、源義経を衣川の館で死なせてしまうのを惜しみ、エゾ地へやったりジンギ
スカンに再生するのと同工異曲、つまりその亜流みたいな感じがどうもする。
という事は取りも直さず明智光秀に、義経なみの人気があるということの証左であ
ろう。
またそれは、これまでのような信長殺しの元凶みたいな感じであるならば、封建社
会にあっては、
(主殺し程大罪はなく、町屋の番頭手代が内儀と密通し心中し損なった節も、内儀は
主人筋ゆえその殺しを企てた廉(かど)によりと獄門にされた)ような江戸期にあっ
て、彼の死を惜しむ者が有ろう筈はなかろうと想われもする。
つまり明智光秀に冠せられたのが冤罪、無実の罪で濡衣であったという見方が一般
的だったからこそ、可哀そうにと同情する心がそうした生存説をも受け入れ広めたの
だろう。
また、家康が側近に彼を置いたという、うがった見方も、
(信長殺しを必要としたのは、家康だった‥‥それゆえ後の面倒をみるため、天海僧
正と名のりをかえさせ、汚名をきせたことへの償いをしていたのだ)といった処から
生じたものであろう。
つまり豊臣秀吉にとっては明智光秀は、倒さねば自分が天下がとれぬライバルだっ
たかも知れぬ。
が、徳川家にしてみれば、光秀と張り合うような要素はなく、
「秀吉は信長をだましこんだ大悪党」だが、
「光秀は信長には希代の大忠臣だった」といったような価値判断もされていたようで
ある。
だからこそ徳川家としては元禄時代までは、光秀に好意的だったともいえよう。
それが急転直下、悪者は光秀というような格好になったのは、大岡忠相のさしがね
や新井白石の筆によるとはいうものの、なんといってもそれは、
『日本政記』や『日本外史』をかいた通俗史家瀬山陽の、
「敵は本能寺にあり」の詩句に原因するのではなかろうか。
まだフォークも演歌もなかった頃なので、それを声高らかに放歌高吟し、廻るしか
なかった幕末の青年が、やがて反体制から体制側になって天下を掌握した時、権力の
坐についた彼らは、新しい明治史観を展開する代り、瀬山陽のデフォルメを一般に押
しつけてしまったようである。
すべてのこうした問題は、天正十年(1582)六月二日の本能寺の変に起因して
くる。というのは徳川家康が、三河刈屋城主水野信元の弟の子で、当時浪人していた
藤十郎勝成に、
「これは明智光秀遺愛の槍である。汝にやるから、光秀にあやかるがよい」と手渡し
たところ、勝成は有難くそれを拝受し、
「日向守光秀にあやかりまする」と誓った。
だから、信長殺しが明智光秀であるならば、あやかるといったからには、その槍で
家康をぐさりとやって、しかるべきである。
しかし、彼はそんな事はしていない。それ処か家康に対しては粉骨砕身の忠誠を尽
し、大坂合戦の時は、家康の孫の松平忠直ら大和軍全部を引率する責任者となって奮
戦。
死ぬ直前にも、島原の乱で幕府方が苦戦ときくや、備後福山から老躯をかって九州
の端へゆき、そこで、みずから槍を握って、
「これが今生の御奉公の仕納めである」と、家臣が諌めるのもきかずに本丸へ攻めこ
み、手傷をうけたがついに落城させてしまうと、
「明智光秀遺愛の槍を頂戴したが、これで、どうにかあやかることが出来たというも
の」と満足して引きあげ、やがて落命した。
これは故日本歴史学会会長高柳光寿氏も、
『信長殺し光秀でない』[当ボードにアップすみ]の裏付け史料として、発表されて
いるが、水野勝成の忠義ぶりは圧倒的だったらしく、その孫で旗本になっていた水野
十郎左衛門が、幡随院長兵衛の確執で長兵衛を殺した時にも、
「御家創業の功臣の血統を、やみくもに罰せられない」
老中評定で無罪になっている。
十郎左衛門が賜死となったのは、旗本白柄組の無法ぶりが、それからますます激し
く、とうとう放っておけなくなった、その八年後のことである。
[寺奴(『町奴』でなく)の幡随院長兵衛と水野十郎左衛門らの確執についての八切
作品は、#8425以降を御参照下さい]。
さて、水野藤十郎勝成の例をひくと、その手本であった明智光秀というのは、尽忠
無私の人だったことになる。それに家康が、「光秀を信長殺しとは、当時認めていな
かった点」と、
「家康は光秀に好意をもっていた」ことが、
「天海僧正というのは、家康が明智光秀を匿うため、僧体にして世間の眼をくらませ
ていたのではあるまいか、という憶測を、昔から一般に与えていたのではなかろうか」
となる。
----これは、家康の生存中から、彼が信長殺しに関連があったことを、一般の人が
知っていたこと。そして、もし明智光秀が生きていたら、彼を匿い庇わねばならぬ立
場にあったことを物語る。
通説俗説といわれる元禄から貞享年間に作られた家康伝説では、
「天正十年五月に三千両もって安土城へ行った家康は、そこで信長みずからに歓待さ
れ、やがて京見物するよう、案内役に長谷川秀一をつけられ上洛した。処が五月二十
九日に信長が小姓三十騎だけを伴って京へ入ってくると、御所の女御さまも周章てて
お逃げになったが、家康一行も船便を求めてか、堺へその日の内に移った」とされて
いるが、その後の有様となると、「処が六月二日早朝に本能寺爆発が起きると、家康
は船が見つからないから陸路甲賀から伊賀へでて、白子浦へと脱出し岡崎へ戻り、兵
を揃えて鳴海まで取って返した。しかしその時はもう六月の二十一日なので、一週間
前に秀吉が光秀を滅ぼした後だった」
「しかし家康は、秀吉から山崎円明寺川合戦が、とうに済みすべてが終ったと聞かさ
れても、先陣を津島に進めた儘で動かず、やっと二日目に退陣していった」という事
実すらある。
つまりそれ以降の徳川史観による家康神話では、本能寺の変が起き、家康も明智方
に狙われ追われ苦労して、神君として生涯における最大の苦難であったとするが、実
際は、どうも怪しいのである。
というのも、その六月二日。
本能寺から七十メートルの距離にあったイエズス派京布教所は、当時としては珍し
い三階建てで、そこのバルコニーから本能寺境内が眼下に見降ろせるので、夜明け前
より集ってきた兵や将校が、
「ちょっと入らせてくれ」とやってきたが、彼らの話では、
「三河の王イエヤスを討つよう命じられ、上洛してきたのに。イエヤスはサカイへ逃
げて此方にはいないから、そちらへ追いかけてゆくか、どうするか、テンカ(信長)
さまがお眼ざめになったら、御下知をうけるのだと話しあっていた」という内容の報
告書を、
『フロイス日本史』の中へ、当日、本能寺の爆発を見ていて、信長が髪一本残さず吹
っ飛ばされた事まで、カリオン修道士は詳しく書いているのも今では活字本になって
いる。
だからイエズス派の宣教師達は、
「信長に狙われた家康は、自分が百人位の家来しか伴ってきていなかたので、信長か
ら明智光秀に軍監つまり軍(いく)さ目付としてつけられた斉藤内蔵介が、光秀が自
分の建てた近江坂本城にいたので、代りに丹波亀山城にいたので、本能寺襲撃を依頼
した」と、まず考え、
「その六月二日という日は、内蔵介の妹が嫁いでいた四国の長曽我部を、信長が己が
子の三七信孝の領地にせんために、住吉浦から丹羽五郎左長秀が軍監となって、二万
の兵を進発させる船出の日にあたっていた。もちろん内蔵介は立場に困って、信長に
四国遠征中止方を願い出たが、聞き入れられず困っていた処、その美濃者の内蔵介へ、
やはり美濃者である奇蝶御前が、信長殺しを依頼しにきた。そこで内蔵介は、家康の
乞いもきき入れクーデターを敢行したのである」といった見方をして、印度のゴアへ
報告文をだしている。
それは、当時の権中納言山科言経卿の日記にも、
「斉藤内蔵介、謀叛随一なり」とでているのでも判る。
つまり公家側でも彼が発頭人であり首謀者だったことを裏書きしているのである。
しかし急ぎ岡山県の備中高松から引きあげてきた秀吉が、
「信長さまの仇討ち」と称して、これまでのライバルの明智光秀を討ちとってしまっ
た。つまり家康は急いで取って返して、京へ入り斉藤内蔵介を助けようとしたが、秀
吉の迅速ぶりにすっかり先を越されてしまい、内蔵介も殺されてしまったが、光秀も
秀吉の都合で、信長殺しにされる羽目となった。そこで、自責の念もあってか、彼と
しては光秀を悪しざまにはいわれず、よって、
「当代無比の忠義者であった」と、いいふらしていたため、水野勝成などは発奮して
忠勤を励んだのであろうし、また側近の天海も、
「事によったら、光秀ではないか」と、うがった見方をされ、勘ぐられたものでもあ
ろうか。
http://www.rekishi.info/library/yagiri/scrn2.cgi?n=1084
細川ガラシャ殺しの秘密
ガラシャことお玉は、当時、長岡与一郎といっていた、後の細川忠興の嫁となった
が、天性まるで玉をあざむくような麗質だったゆえ、忠興は二なき者として熱愛した、
といわれている。
それゆえ本能寺の変のあった時も、彼女に災いが及んではと三戸野(みとの)に秘
かに匿し、秀吉に対して命乞いをした。そこで、その情にほだされ、
「明智光秀の娘とはいえ、そこもとへ嫁入りしてござったからには、なんの係りもな
いことゆえ、心配などせんでよろしい」と、秀吉も彼女がそのまま忠興の妻であるこ
とを許した。
のち秀吉が亡くなって、関東関西お手切れとなったとき。
忠興が家康について東下りしていたのを、なんとか味方に引き入れんと西軍は、彼
女を大坂城へ人質に迎え入れんとした。しかし、己れの玉をあざむく美貌をよくわき
まえていたお玉は、
「私のような美しい女が大阪城へ連れてゆかれては、貞操を奪われるやも知れませぬ。
それでは愛してくれている夫に申しわけとてなし」
と留守居家老小笠原少斎をよびよせ、己れを槍で突き刺すように命じた。
少斎も、忠興の嫉妬が強いのはよく知っていたから、部屋へは入らず廊下から刺殺
し、自分も屠腹して、屋敷に火を放った。
そのため、戻ってきた忠興は、最愛の妻の死を悲しみ、少斎の黒焦げの屍を蹴飛ば
すと、涙をこぼし男泣きに喚きたて、
「よくも早まった事をしおった」と口惜しがって泣き喚き、足蹴にしたとまで伝わっ
ているが‥‥この話、はたして大衆作家が書くようなそんな愛妻物語だったのだろう
か。
長岡の姓を何故か改めてしまった細川忠興というのは、あの時代にあっては「きけ
もの」として知られた人物である。それが、そこまで取り乱すとはヒイキの引き倒し
で変ではないかといった気がする。
それにこういった話は実際に有ったにしても、今でいえばプライバシーにも当たる
事柄ゆえ、伏せられてしまうのが当然である。なのにどうして『細川家記』とよぶ家
伝史にまで、これが入れられているかという謎である。
普通なら匿し通すべきことが、事さらに記入されているのは、見せつけではないか
といった疑いなのである。
そこで、美人ではなく、この話を裏返しに組み立て直すと、
1.お玉はきわめてブスだった。が信長の命令ゆえやむなく嫁にした。
2.本能寺の変後、秀吉は何らかの必要上、お玉を殺し差し出すよう細川忠興に命
じた。しかし細川家では、幽斎が、何かの生き証人になるからと、出奔して行
方知れずと報告して、その実は三戸野へ、切り札として隠しておいた。
3.このため秀吉としては、お玉を殺させる時機を逸したが、その内に、関白とな
り、もはや天下に憚るものもなくなったので、その儘で放任しておいた。
4.処が慶長三年(1598)八月に秀吉が他界。一年おいて慶長五年。上杉景勝
がその有する黄金にものをいわせ、独力で天下を相手に謀叛せんとする企てに
徳川家康は討伐隊を率いて東上。これに細川忠興も従った。
5.さて小山まで兵を進めていた家康も、石田三成が旗上げしたとの報に接するや
江戸城まで引き返し善後策をねった。その時に、忠興が家康に命ぜられたのは
伏見長岡屋敷へ住まわせてあるお玉の口ふさぎであった。
6.お玉が何かを知っていて彼女の口からそれが洩れでもすると困ると、かつて秀
吉もおおいに案じたが、家康もこれからの合戦を前にして、これにはすこぶる
難色を示した。
7.しかし忠興は、長年の妻でござればとこれをまず拒んだ。すると家康は恩にき
るから大事の前ゆえ頼むとまでそれを求めた。よって忠興はそれではというの
で、安心して託せる小笠原少斎の許へすぐさま使いをだした。
8.もし、お玉が大坂城へつれてゆかれこの明智光秀の娘が、知っている事をもし
責められ口外したとしたら、家康の信用はがた落ちして、関ヶ原合戦に先立ち
東軍についた諸大名は、みな四散してしまう恐れがあったらしい‥‥ことにこ
れではなる。
つまり、逆にすると、こうした結果になる。
もちろん当て推量であって、唯まるっきり正反対にしてみた迄のことで、これには
なんら援用できる資料など有りようもない。
だが、こうした大胆な推理ができるのは、信長殺しの斉藤内蔵介の娘阿福が、
「春日局」の名で江戸の実権を握るや、後述のごとく、片っ端から外様大名の取潰し
をした家光の時代なのに、やはり取潰しにあっても仕方のない外様大名の細川忠興に
対し、十二万石から五十四万石へと常識では考えられぬような大巾の加増がなされる
という奇怪さからである。
とはいうものの、これまでの説を、まず順を追って当たって行かぬことには、話が
飛躍しすぎるからそれに戻ってみるが、どうも話しは、もちろんみな真赤な嘘である
らしい。いくらお玉が美人であったとしても、その夫を味方にする目的で、大阪城へ
連れてゆこうとした西軍が、彼女の操など奪う筈はなかろう。これは常識である。
それに、このとき彼女は既に三十八歳。長子の忠隆も二十歳になっていたのである。
いくら美人であったにしろ、ろくな化粧品もなかった時代の、しかも四十近い女にそ
んな心配があろうか。
また忠興は激怒して、少斎の遺骸を足蹴にしたというが、関ヶ原合戦の始まる前に
火をつけたのが、凱旋してきた数ヶ月後まで、そのままだったというのも変てこだが、
熊本市に残っている『小笠原家記』をみると、
「小笠原少斎の跡目長基に、細川忠興は姪のたね(後に千女)を己れの養女として一
緒にさせ、その間にできた長之という伜に、その二十三年後の話だが、忠興はやはり
弟の娘のこまんを己が養女として縁づけ」て居るのである。
これは『細川家記』の方にも、その裏付けが、「細川幽斎の孫娘にあたる千(せん)
女が、小笠原少斎の次男長基に嫁した」
と、はっきり記録されている。
さてこうなると、妬情けにかられ屍に鞭うつように蹴飛ばした男の跡目に、なぜ自
分の養女を縁づけたのか。そしてその生まれた子にまで、また養女を作って一緒にさ
せ、二重三重に縁結びして、少斎の遺族を雁字絡めにする必要が、どうしてあったの
かと怪しくなる。
さて寛永九年(1632)十月のことである。それまでも、それから先も徳川家と
いうのは諸大名の取潰しや、減封ばかりしていた筈なのが、
「恐れ多くも、上さまの思召しである」と、春日局は、将軍家光の台命として豊前小
倉十万石の細川をよびだし、
「其方は、わが亡父斉藤内蔵介とも入魂(じっこん)の者なれば‥‥」
つまり、斉藤内蔵介の遺児の阿福として、亡父と仲良しだったから取り計ってあげ
ましたのだと、先によく断ってから、
「肥後十二万石、豊後三郡しめて五十四万石」
と、これまでの十万石に比べると、5.4倍のベースアップをした。しかも肥後の国と
いうのは豪気な秀吉でさえ、
「彼地は収穫の多い美国である」と惜しがって、気に入りの加藤清正や小西行長にさ
え、吝って半国ずつしかやらなかった処である。
そうした屈指の最上等の国を、まるまる忠興に、格別これといった手柄もないのに、
急にやってしまったのは、何故だろうか‥‥
さて貰った忠興はどうしたかというと、お玉が産んだ長子忠隆は山城北野へ追放、
次男興秋は江戸へ送り(途中で脱走し山城東林院で、首つり自殺を遂ぐ)、お玉の死
後に別の女に産ませた三男忠利をもって、五十四万石の当主にたてた。これでは忠興
が、
(お玉を熱愛していた)という愛妻美談は、どう見てもまったくの嘘になる。
そして、お玉を殺し自分も死んだ小笠原少斎の遺族を、何重もの婚姻政策で縛った
のも、そこには秘密漏洩を気づかっての、糊塗策としかみられぬものがある。つまり
忠興にとって、お玉を大坂城へ入れずに少斎が殺したのは、非常な恩恵であり、その
ために五十四万石になれたような、何かがあったものらしい。
ということは初めに疑わしく書いておいたが明智光秀の娘であるお玉が、大坂城内
へ連れてゆかれ、そこで口を割って、もしも本当の処を、
「実は、信長殺しの真相は、かくかくでございました」
とでも真相を明らかにしていたら、東軍に加担していた大名の中でも、旧織田系は
いたから、それらが家康から離れて東軍は危うくなり、関ヶ原合戦で勝てなかったか
も知れぬ、というキーポイントがそこには秘められていたのだろうと推理される。だ
から、
「その口をふさぐ為に、お玉を殺し、自分も格好をつけるため死んでくれた少斎は、
細川家にとっては大忠臣」という事になって、代々殿様の御養女を下賜されるご一門
の扱いになったものらしい。
では、その秘密とはなにかというと、
「天正十年六月二日の夜明けに、信長のいた本能寺を包囲した軍勢は、丹波口から京
へ入ってきた」
という事実によるものである。
丹波は誰、丹後は誰と、国別に大名領の区画整理ができたのは、関ヶ原合戦から後
のことで、天正十年の頃はまだ入りまじっていて、丹後でも三戸野辺りは明智領だっ
たが、丹後も京への入口の船津、桑田の二郡は、これは当時長岡藤孝を名のっていた
細川家の領地である。
つまり、その昔、
「大江山」とよばれた老の坂から京の入口までは、
「長岡番所」とよばれる細川家の見張番小屋が何ヵ所も続いていて、京への出入りを
監視する役目をいいつかっていた。なのに、
「敵は本能寺にあり」と叫んだかどうかは判らぬが、斉藤内蔵介の率いる軍勢が、こ
の何ヵ所もの細川番所の関所を、六月一日夜から二日にかけて、堂々と通ってきたの
である。しかも僅かの人数が巧く身をひそめ、隙を窺って通り抜けてきたというので
はない。
一万三千の頭数が堂々と大手をふり、フリーパスで通行してきたのである。
こうなると、細川忠興やその父の幽斎は、斉藤内蔵介としめし合せていたか、前も
って徳川家康に頼まれてOKしていたか。
そうでなければ、一万三千の内の何パーセントかは、細川忠興または幽斎の率いて
いた丹波桑田か船津の兵ということにもなる。
つまり細川家こそ、巧く生き残った信長殺しの下手人の一人で、
「その汚名をかぶせられた明智光秀の三女であるお玉」
は、その真相を知っていたからこそ、もし大坂方に暴露されては、徳川家の不為と
考え、少斎がこれを刺殺したのだろうし、
「その時の借りを返すため」に徳川家は、斉藤内蔵介の遺児の春日局の手をへて、5.
4倍の増禄をあえてしたのだろう。なお、
『細川家記』には、明智光秀の手紙と称する物が入れられてある。
光秀自身が自分が謀叛をしたのは与一郎(忠興)の為であるといった内容のもので
ある。これは、文章が次々とおかしく、与一郎に敬語をつけている点などから、細川
家の家来の贋作ではなかろうかと、故高柳光寿氏も指摘しておられたが、細川家とい
えば名家という事にはなっているが、十二万石から明確でない理由で熊本一国の領主
になっただけあって、なんとか取りつくろおうと懸命になって、その係りの専属家臣
をも代々おいて、さも尤もらしい色々な話を創作したというか贋作させ、それをまと
めて、
「細川家記」として今に伝えているのだろう。もちろん後半はなんということはない
が、幽斎、忠興の二代の間の記録ときたらみな眉つばものであるといっては過言では
あるまいといえる。
なにしろ、イギリスの推理作家アガサ・クリステー[クリスティ]でさえ、
「アリバイが揃いすぎ、もっとも尤もらしいのこそ怪しい」といい切っているのが、
細川父子にも当てはまるのではなかろうか。
だが、それは信長や光秀、そして殺されたお玉お側からいうことであって、五十四
万石に所領を増やし家臣一同をうるおした忠興の存在は、細川の家来にとっては神様
みたいな存在だったから、肥後一国の全力を結集して色々と庇うように、手作りの史
料などを付け加えたのでもあろうか。
[八切止夫著『日本意外史』(番町書房刊)より]
**************************************************************************
なお、細川家と徳川家康、本能寺の変との関係については、同じく八切氏の労作
「信長殺し、光秀ではない」に詳しいです。このボードの#9644以降にアップし
てありますので、御参照下さいませ。
御先祖様の事はとにかく、細川の殿! アメリカで頑張ってね(^_^)
豊臣秀吉は猿でない
「うん、うぬは猿そっくりじゃな。まこと珍妙なつらじゃ。よし、今日よりは、猿め
とよんでつかわそうかい」
「はい、はい、召し使うてさえ頂けるものなら、てまえは猿でもなんでも、結構にご
ざります」と信長に奉公の初めから、いと気軽に、
「さるめ、さるめ」といわれた事に、あらゆる『太閤記』でされている。
しかし、
『両朝平壌録』という朝鮮の役のときに向こうから交渉にきた者の、帰国後の見聞録
ともいうべき報告書には、
「つらつら関白秀吉を、間近かに観察するに、左頬に黒あざのごとき汚点(しみ)が
数点浮きでており、口が尖っていて、その顔つきは一見、犬に相似していた」とでて
いる。
日本の講談では、猿だとか猿面冠者とあるが、実際に面会した人間は、はっきりと
秀吉を、
「犬に似ている」といい切っているのである。
はたして、どちらが本当だろうか?
また秀吉を、土百姓の子とか、鉄砲足軽の子であったなどというが、その頃、日本
へ宣教師としてきていたシュタインシェンの、
『キリシタン大名』には「樵夫」とあるし、
『日本西教史』にも「秀吉は若年の頃は木こり、たきつけ火付け用に柴の束を担ぎて、
売りひさぎ歩きし」とでている。また、
「講談」では「相当豪かった丹羽長秀や柴田勝家にあやかろうと、羽柴と姓をつけた」
というが、『古語辞典』では、
「はしば=枯柴の尖端で点火用にした端柴[はしば?]のこと。形状より羽柴ともい
う」とあるが、どちらが本当だろうか‥‥この方が論理的だと思われるが、これまで
そうした説は全然といってよい程とりあげられていない。まあ、講談とか、それに類
する読物ではそこまでの詮索は、煩わしくなるだけで必要がないのかも知れない。
しかし徳川の世が終って明治になった途端に持てはやされ、西郷隆盛ら征韓論者ら
によって、「豊太閤に続け」と叫ばれて以来、やがて日清日露と続く大陸進出作戦に
際しては、かつての先覚者、国民的大英雄として、小学校読本や絵本の主人公にされ、
しまいには一大人気者にさえのし上がってしまった彼には、
「これ藤吉、いやさ猿め」といったようなそんないわれ方でないと、一般の親しみが
得られなかったというのでもあろうか。
そうなると、秀吉という存在も、明治軍部が担ぎあげたジンギスカン義経と同じよ
うに、大陸開拓先進者という国民指導用の偶像だったにすぎない存在だったとも考え
られるのである。つまり明治以降、ある時代ごとに秀吉が、猿だ猿だと面白可笑しく
脚光を浴びさせられるのは、なにも木下藤吉郎の出世功名譚が世人から求められ、そ
れで引張り出されるのではなく、朝鮮とか中国を国民に身近かに感じさせねばならぬ
ような状態のときに、それはチンドンヤのごとく真先に、引張り出される道化ではな
かろうかと勘ぐりたくもなる。まったくそんな感じさえもするのである。
というのは徳川時代には秀吉の研究などされておらず幕末の、『真書太閤記』や
『絵本太閤記』ぐらいの、いわば講談本のはしりしか出ていない。だから乃木大将程
の人でさえ、
『真田十五代記』といった講談本の類しか読まなかったそうだから、それよりも年か
さの明治の元勲などが読んでいた本は、それ以下のものとしか考えられぬ。
だから秀吉を大陸進攻のパイオニアとして、小学校教科書などでおおいに取り上げ
たはよいが、朝鮮史料や当時のイエズス派の書簡などはみていなかったろう。だから
して、その内に、秀吉が正親町帝を追って自分が帝位につかんとしたとか、それに反
対した山科、四条卿らの大坂落ちといた新事態が明るみにでてくると、「勤皇精神」
を国民指導要領にしていた軍部も困ったのであろう。
そこで、秀吉の新事実は一切みな伏せてしまい江戸末期のままの秀吉像を凍結させ
たのである。
このため秀吉伝説は、文化文政の頃の版本から、すこしも解明されぬままに大手を
ふって今も、まかり通っているのだろう。
後述する大和興福寺多聞院英俊の当時の日記から、史家の中には、秀吉というのは
歴史知らずの明治政府が、正一位を贈りあがめ奉ってしまったが、実際は日本人にも
あるまじき思い上りの不届き者だった‥‥位は知っていた者もいたであろう。
だが、明治大正昭和の間ですっかり金字塔のように出来上がってしまった秀吉の虚
像に、正面から突き掛かるような勇気は誰も持ち合せていなかったのか、それとも、
もはや定説となってしまった伝説をぶち破っても、誰からも賞められはしなかろうと、
そんなばかげた徒労をあえて、強引にするような愚かしさはしないのであろう。
だが敢えてそれを改めて推理し直してみるとこうなるのである。
加藤清正を有名にしたのは、なんといっても日蓮宗である。
それと同様に、塚原卜伝を世にひろめたのも、常陸鹿島神社が幕末の剣術流行時代
に、当社こそ武の神と宣伝し、
「参篭した卜伝は、神のご庇護で剣の名人となった。剣を志す者は当社へ参詣すれば、
ご利益できっと上達すること間違いなし」
と弘めさせたせいだというが、秀吉もまた、「山王権現さま」とよばれる日吉神社
の信者獲得用にPRされていたものらしい。つまり日吉さまに願って生まれた子だか
ら、「日吉丸」であって、お稲荷さんの使いが狐なのに対し、
「日吉さまのつかわしめは、猿だったから日吉丸は猿とよばれた」
という論法なのである。もともと猿というのは、
「馬屋神」といわれ、信長や秀吉の頃は、馬が病気した時には、厩へ猿にきて貰って
小さな御幣を振らせれば直るとされていた。
つまり獣医というより、神聖な神の使いとみられ、猿飼部族は、
「神人」の扱いをされていた。という事は、今のようにモンキーセンターや、動物園、
それに家畜商もなかった時代では、
「猿は深山にすむ霊長類の動物」として、猟師でもなければ、実物は滅多に見られる
わけのものでもなく、一般の人間は薄気味悪がって、拝まんばかりにしていたのだろ
う。
処が天保の飢饉からの米価の値上がりで、非農耕の猿飼部族は食してゆけなくなり、
猿を伴って門付けして歩くようになったので、かつては恐れ敬われていた神人が、今
度はあべこべに、
「猿廻し」と軽蔑され、猿の方も、昔は、馬屋の神であったのが、多くの人目にさら
された結果が、価値を安っぽくさせ、
「テレツクテンのエテ公」となってしまったのである。
だからこそ『真書太閤記』や『絵本太閤記」の類も、初めは発禁版本没収の憂目を
秀吉ものを、そうした、「サルメ」「サル」の扱いにしたため、後には大目にみられ
て、どんどん売りまくられたのではなかろうか。
しかし異説もある。その頃、将軍家茂に、恐れ多くも京から和宮が御降嫁になって
いた。そこで一般庶民は蔭へ廻って、「将軍さまも天朝さまから嫁とりされては、頭
が上がるまい」
下世話にいうカカア天下を想像し愉しんでいた気味があるので、この「サルメ」と
いうのは広まったのだとする説である。これは、
『続日本紀』にある古い昔話だが、小野の姓を名のる一族の長(おさ)が、
「わが部族の男共が、前から住んでおりまする女尊系の部族の女に引っかけられ、次
々と連れ去られてしまい、今や小野族は滅びかけようとしています。どうか異種の民
でありまする猿女族を、この際討伐して下さって、わが氏族をお守り下さい」と願い
でたゆえ、
「よし、女ごに引っかけられ、しぼられ苛められておるとは不憫である」と、時の帝
は憐れみたまい、すぐ猿女部落を急襲させた。
処が猿女たちは「小野」の姓を自らにつけ、関所の眼をくらまし、もはや早いとこ
散らばって逃げてしまった。
そして旅にでた彼女らは、自分という一人称を、やがて、
「おの」といったいい廻しをなし、「おのが姿を影とみて‥‥」といったようなのを
唄って、旅芸人の元祖となり、「語り部」になったというが、追捕に後から行った男
たちも、ウスクダラではないが、逆に捕虜(とりこ)となって、「夫」という名の奴
隷にされた。
もちろん一部の女は捕らえられてきて、御所の中で、力仕事をする賎業につかされ、
これは「猿女」の名を伝え幕末まで続いているが、
「さるめ」というのは江戸時代にあっては、
「強い女」「かかあ天下」の意味だった。
そこで藤吉郎も、おねねに頭の上がらぬサルメだったろうという受け取り方で、将
軍家への当てこすりみたいに、「サルメ、サルメ」といったのが当たったものらしい。
処が明治になって、もう猿女の本当の意味が判らなくなり、「小男であった」といわ
れる秀吉に、その猿自体を押しつけ、
「猿面冠者」にしてしまったものと思われる。
そして、なにしろ明治新政府というのは、有能な士は幕末のテロで大かた倒され、
生き残れたのは、たいした事もない連中ばかりだったので、「王政復古」が成ると、
直ちに、
「豊国神社復興」の命令をだして勅使を派遣して正一位を贈った。
これは、織豊両氏の統一事業が、近代国家前期工作であったことが認められた結果
だと、故白柳秀湖はとくが、真相は、
(豊臣は徳川に滅ぼされているから、諸政一新のため)といった早とちりだったのだ
ろう。処が歴史家はそれを裏づけなければならぬから、故黒板勝美のごときは、その
『国史概観』『国史研究』といった旧制高校、専門学校の教科書用にかいたものでも、
「秀吉は京都内野の地を相して邸宅を造営。聚楽第と名づけ宏大壮麗目もさめるばか
りで、翌年四月に後陽成帝の行幸を仰ぎ、盛儀古今に比なしといわれる位に、勤王の
まことを示したものである」
と、なっているが、彼は歴史屋のくせしてその当時の、
『奈良興福寺多聞院英俊の日記』をみた事がなかったのだろうか。
その日記によると秀吉は、自分は先帝と持萩中納言の娘との間にできた子種である
からと、時の正親町帝を脅かし奉り、女御をみな裸にむいて磔にかけるとまで、紫宸
殿で喚きたて、あげくのはては皇太子誠仁(ことひと)親王のお命を縮めまいらせて
いる。
御所に向かいあった下立売通りから十町四方の民家を取払い、そこへ万博なみの規
模で造営したという聚楽第は、これは取りも直さず秀吉が自分が帝位につくための新
御所に他ならない。
そして、誠仁親王の亡霊にとり殺されると脅かされた結果が、親王の遺児をもって
帝となし、その御方を招いて聚楽第をおみせしたのが、
「秀吉の勤皇」とは、なんたる無智であろうか。その帝の謚号(おくりな)が、かつ
て廃帝の陽成さまの御名に「後」がつけてあるのをみても、歴史家なら判りそうなも
のを、教科書にまでするとは情けない。
さて、秀吉の幼児には、まだ鉄砲は尾張まで入っておらず、
「鉄砲足軽木下弥右衛門の子」となすのも間違いだが、
「太閤検地」によって、二公一民つまり六割六分まで年貢にとるという重税をかけ、
百姓に同情も理解もなく、ただ憎悪しか示さなかった秀吉は農耕階級出身者ではなく、
木こり、つまり山がつの子という素性の者だった方が正しかろう。
が、だからといって、それが秀吉の価値を損なう程のことでもない。
食うやくわずの木こりの伜が関白になれたという男のシンデレラ物語は、彼が野卑
であり傲慢であればある程、それは魅力的であり男性的でもあるのである。
つまり責められるのは、秀吉その人ではなく、彼を勝手に自分らに都合よくでっち
あげ、歴史というものをまったく歪めてしまう、利用者の側の方であるだろう。
釜ゆで石川五右衛門
前述したごとく『多聞院日記』に、
「一品(誠仁)親王さまが、急におかくれになった。はしかというが大人のかかる病
ではない。恐れ多い話ではあるが、殺害されたもうたか、御自害であろう。が、皇太
子さまが亡くなられたからには、次の帝の御位には、秀吉がつくのはもう確定したよ
うなものである」
とまで書かれている時代、今ではあまり知られていないが、山科言経、冷泉為満、
四条隆昌の三卿が、敢然として、
「秀吉ずれが帝位につくは絶対反対」と、正親町帝に申しあげた。処がこれが洩れ、
そこで、やむなく帝も勅勘(ちょくかん)という形で、三卿を追放処分となされた事
がある。
冷泉の姉が西本願寺門跡の裏方だったので、このとき都落ちした三卿は、西本願寺
敷地のいまの大阪中の島公演の処で逼塞していたが、この儘では大変なことになると
いうので、
「亡き一品親王さまの霊が天界で荒れ狂い、秀吉の命を縮めんと、あちこちの寺に落
雷させたり、火の雨を降らせ焼き尽している」
と門徒たちに流言蜚語をとばさせ、打倒秀吉のため活躍していた話は書いたことが
ある。
が、そうした折りに、
「おのれ秀吉め、命は貰った‥‥」と、忍びこんだ石川五右衛門というのは当時の秀
吉の実状からみれば、まこと惜しくも仙石権兵衛に捕らえられたとはいえ、
「尽忠勤王の士」として立派であると思うのだが、それよりも、秀吉伝説の方が強力
なので今では、
「浜の真砂はつきるとも、世に盗人の種はつきまじ」の歌だけが伝わり、あくまでも
泥棒としてのみ扱われているがそれでよいのだろうかと疑問が生ずる。
そして近頃は、泥棒から一歩進化したのが、「忍びの者」ということになってしま
った。
南禅寺山門の上で金ぴかのどてらみたいな打掛けをきて百日かつらの大きな頭をふ
りふり、「絶景かな」とやっている五右衛門と、黒装束で身軽にすいすい飛び廻るの
では、まったくイメージが違う。
しかし泥棒よりは忍術使いにされた方が彼にも名誉であろうというのか、近頃はそ
ちらが定説になりかけている。
だから今の内に疑義を差し挟んでおかないと、やがていつかは、泥棒の五右衛門は
消滅してしまい、忍術使いの方にだけ名が残り、それが一般的概念となって常識化し
てしまう惧れがある。
が、初めにことわっておくが、
「石川五右衛門」なる存在は、後述するごとく林羅山という江戸時代の公儀御用儒学
者が勝手にこしらえた架空の人物である。なにしろ日本人というのは思いやりがあっ
て心優しい民族なので、明治時代の尾崎紅葉が『金色夜叉』をかけば、熱海海岸に、
お宮の松をつくったり、すぐ物語中の人間をも実際にいたようにしたがり、一般もす
ぐ信じやすい人の良さがある。それが悪いというのではないが、鰯の頭も信心からと
称されるが、おかげで芝居講談までが歴史視されてしまう。
さて、前にもすこしだけふれておいたが、吾国の忍術なるものについては、
「藤林保武口述と伝わる、万川集海」
「服部半蔵口伝といわれる、忍秘伝」
「名取青竜軒の一子相伝の、正忍記」
というのが古典とされ、近世では、
「伊藤銀月利法公開、忍術極意皆伝」
「藤田西湖伝授秘技、忍術の実際」
といったのがある。銀月のは、昔の「少年世界」や「譚海」に一頁の広告が入って
いて、
「一円送れ切手可」とかいてあった。そこで取り寄せ、
「天狗飛び切りの術」というのを公開実演しようと思って、近くの寺の鐘楼から、や
あっと九字を切って飛んだら尾てい骨を打って気を失い、近所の悪童に担いでゆかれ
たのが、校医の処で、これが学校にばれてしまい、一年の初めから級長だったのが、
この時から落されてしまう羽目になった。通信教育では私も巧くできなかったのだろ
う。
藤田西湖は故江戸川乱歩に誘われて浅草の伝通院へ実演をみに行った。色々の道具
をもってきて、天井をコウモリのように逆さに歩くというのが呼び物だったが、剣道
の稽古着をきた肩巾の広いおっさんは、この本の中の写真にある通りですと、本を二
円で売りつけたきりだった。
そこで故乱歩氏は残念がって、
「伝通院で、天井板が痛むと急に休止をいってきたそうだ」
と誘った手前しきりに弁解しておられた。
が、さて、銀月や西湖の方は、忍術でなく銭儲けの算術に徹していたようだから、
古典の、『万川集海』から解明にかかりたいが、実はこれは、朝鮮の兵書の『間林精
要』と、中国明の軍書『武備志』の二つを糊と鋏でくっつけあった当時の海賊版でし
かない。
だが、『列子』や『史記』、『文選』にでてくるところの、
「奇幻たちまち起これば、万物その姿を異物に変え、大地を蹴ればドドンと姿が潜り
こんで消え、刀を口へ咥えて火を吐けば、カトンカトンと燃え広がって、あたりは紅
蓮の焔。スットンスットン呪文を唱えれば、雲霧たなびき辺り一面が暗くなって、天
より沛然たる雨となり、大地は割れて川となり水遁の術が行なえる魔可不思議さ」
といったような内容の、鬼神や方仙の行なったと称する、
「神仙術」が、忍術とされているから、これから児雷也のガマの妖術、天竺徳兵衛の
大蛇術。そして原田甲斐こと芝居の仁木弾正のチュウチュウ鼠術が、芝居から、目玉
の松ちゃんの忍術映画になり、これが後の円谷式特殊撮影技術の原点となったのであ
ろう。
「忍秘伝」の方は、伊賀流忍術虎の巻というので、これはややリアルで、
「軍法の忍は漢高相帝の時より窃盗をもって間(かん)とよび、間者とは忍び盗む者
をいう。つまり窃盗術こそ忍術の精華なりと伝わる」
まるで泥棒教科書のような事が、巻頭にかかれてある。
だから石川五右衛門が泥棒兼忍術使いであっても、それこそ精華であるといった書
き方であって、前述した、
「まき菱」「水中下駄」「結び梯子」の類が、もっともらしく羅列され、次になると、
「火器、火術こそ、忍術なり」と、今日のプラスチック爆弾のような「風爆火」の名
称もでて、これは『万川集海』の末尾にも、
「狼の糞の乾いたのに、もぐさ草をまぶして、それに硫黄と硝石をまぜたものが、の
ろし火薬」
「太い松の木の根株を細く裂いたのに、硝石をよくまぶして、これを闇夜に用いるの
が、卯花月夜」
とでている。つまり忍術というのは、大なり小なり、硝石を使わなくては、白い煙
ひとつ出せないものらしい。
処が、島原の乱以後、一般の硝石入手が困難になった。
厠の縁の下の土を掘って天日に何日もさらせば、小匙半分位は取れるというのは前
にも書いたが、塊っては今でも何処にも硝石の産出する鉱山などはない。
だから今でも日本ではすべて輸入依存だが、これが徳川家独占になって一般に出廻
らなくなっては、もはや忍術はやりたくても出来なくなり、それでドロンドロンと消
えて行ったのであろう。
さて石川五右衛門というのは、これは実在ではなく、十七世紀後半の、
『禁賊秘誠談』というのにでてくる泥棒で、のち『絵本太閤記』に登場させられるが、
作られた架空の人物であり、これが有名になったのは、やはり芝居の影響で、
「石川五右衛門一代記」から「釜が淵、二つ巴」といった浄瑠璃でまず操り人形芝居
として広まり、これが後になると、
「ああ絶景かな、春の眺めは価(あたい)千金」と南禅寺山門で、百日かつらで見得
をきる「金門五三桐」といった芝居で知れ渡った。
しかし芝居だと、のちに上演された「艶競べ石川染」でも、五右衛門は忍術など使
っていない。つまり彼を忍者にしてしまったのは、大正時代の玉田玉秀斎と、昭和に
入っての村山知義ということになる。さて前述した従二位権中納言山科言経の残した
日記の、
「文禄三年[1594]八月二十四日」の条に、
「京三条河原にて盗賊十名釜ゆでの刑にあう」という個所がある。
これは、林羅山が、その釜ゆでにされた者は石川五右衛門なりと、公儀儒官の権威
をもっていいきった。そこで、丁度その頃、美濃関で鋳造され売り出された一人用湯
釜に、その名が利用され、
「五右衛門風呂」という名称は今に到るも使用されている。
実在しなかった物語の主人公石川五右衛門を、なぜ林羅山が実在みたいに言明した
か、これは久しく謎とされていたが、真相は徳川家御為を計っての配慮によるものら
しい。
というのは、賎ヶ谷七本槍の一人で討死した石川一光の弟に、長松という者がいて、
これが代りに秀吉から千石を貰い、のち慶長三年[1598]六月二十二日付けで播
磨丹波で六千四百五十石にまで昇進したが、秀吉が死ぬと、彼は伏見城にいた徳川家
康を、
「あの狸親爺の息の根を止めない事には、豊家の運命が危ない」
と暗殺するために忍びこんだが、武運つたなく捕えられ、三条河原に梟首された。
これが、
『武家盛衰記』という題名で出された本に、はっきり、
「石川長松は忍びの名人にて」とあるのが当たって、その頃としては極めてよく売れ
たらしい。そこで林羅山としては、
「神君権現さまに刃を向けんとしたような不埒の輩が、もてはやされるとは何事か」
と町奉行に指示して発禁にした上で、反対に秀吉を狙ったという架空の石川五右衛門
を、それとすり変えるために、当時のおかみが後押しする形で公けに認めたのが、
「長松改め石川五右衛門」ということになるのであるらしい。どうも、[←なぜか、
ここで文章が切れております、誤植かな‥‥影丸]
さて、こういう具合に、おかみが泥棒行為は奨励しなくとも、
「泥棒五右衛門の肩をもつ」ような事をしたからして、やがて、
「白波五人男」といったような集団強盗が、芝居の当たり狂言の一つにもなり、
「盗みはすれども非道はせぬ、日本駄右衛門とは、俺がこったァ」と舞台で大見得を
きるのに観客が、
「そうだ、盗みは、非道ではない」と手を叩くようなことにもなったらしい。
http://www.rekishi.info/library/yagiri/scrn2.cgi?n=1085
島原の乱は切支丹か
「丑(寛永十四年[1637])十二月二十日ごろ、天草領内の者ども何事かは知ら
ず騒ぎたて候につき、二十二日より代官その他の村役の者々をつかわし取調べ居りし
処、二十四日に至りて男女三千人程、有馬村に集結の由。同心松田兵右衛門に侍八人
相そえ差し向けたが、二十五日に有馬村八郎尾と申す所にて、一揆のごとく騒ぎたて
るときき、代官林兵衛門はみな殺しにしてしまえと下知す」
というのが発端で、島原城の松倉勝家の家来と、鉄砲で装備された一揆が衝突し、
島原の一衣帯水の天草島では、益田四郎をもりたてた一隊が蜂起し、合計一万二千が
唐津の富岡城へ押し寄せた。そこで江戸表から板倉重昌に目付石谷十蔵をそえた征討
軍が送られてきた。
しかし一揆は、島原半島の端にある原城へたてこもってしまい、その数も二万を越
し、寛永十五年[1638]正月元旦の二度目の総攻撃で、板倉重昌は銃弾に当って
即死[というのは表向きの発表で、一揆側の落とした大石に潰されて即死という記録
も残っている]。当日だけでも討手の損害は、討死手負い四千余名、城の一揆方は九
十人と、『徳川実紀』にでている。
ニコラス・クーケルバッケルの指揮するライプ号は、その十五門の積載砲をもって、
一揆のこもる原城を正月十日より二十五日まで砲撃し、二十八日に弾丸を射ちはたし
て平戸へ戻り、翌二月二十七日に原城は陥落したというが、キリシタン一揆をキリス
ト教国の軍艦が砲撃という事があるだろうか。
もし、そんな事をしたら、ニコラスだけでなくライプ号の乗組員一同、みな故国へ
戻ればその教会から破門されてしまうは眼にみえている。
現在と違い宗門の権勢の強かった中世では、キングと名のつく人でさえ、破門とか
脅かされれば雪中で一晩中憐れみを乞うて侘立していなければならなかったというか
ら、ニコラス以下もし如何に利をもって誘われたにしろ、異邦人の国へきていて、徳
川家の為に、もし島原城に天帝の旗がはためいていたものなら、半月もの間に亘って
連日これを砲撃などするわけはなかろうと想われる。
しかし日本史では、益田四郎時貞が、天草四郎と名のって信徒を集め、賛美歌を高
らかに斉唱しつつ抗戦したというのだから、てんで辻つまが合わんのである。
それにいくら徹底抗戦といっても限度があるし、攻める側にしろ殺人鬼でもない限
り、同胞なのだから女子供まで殺掠すべき筈はなかろうと思うのだが、この島原の乱
にあっては前もって降参して裏切りをしていたとされる山田右衛作一人の他は、嬰児
まで皆殺しにしている。
もちろん日本史では、彼ら篭城者は自分から殉難の道を選び、一人と雖も降人する
者はなく、みなみずからの命を絶ったといわれている。
しかし百人や千人ではない三万人からの人間がいたのである。
人間は十人いれば十色という。どうして三万からの人間が各個撃破の落城時におい
て、みな同じように揃って自決という単一行動がとれたものか、疑わしいと思うのは、
それは僻みだろうか。
玉砕と伝えられた激戦地でも、サイパンや沖縄でも、死のうとして死ねずに助かっ
てしまい生き延びるのを余儀なくされた多くの人がいた。それを思うと手榴弾のよう
に叩きつけたら、即死できる可能性のものを渡されていなかった筈の何万かの老若男
女が、自分らから一人残らず潔く死についたという記録には信じがたいものがある。
つまりこれは、みな死んでいたとは、‥‥命令で皆殺しにされたものとして思えない。
本来ならばこうした叛乱事件は最終的には殺してしまうものでも、初めは生存者は
みな押さえ、背後関係とか色々よく調査をし、そしてそれから処分するのが常道であ
る。なのに何故か、初めから皆殺しというのは、一人でも生かしておいては、何かそ
れらの口から洩れては困ることが攻撃側の体制軍にあったのではあるまいか。
さて、事件勃発に遡って、この島原の乱で見逃され、そして誤られている点が二つ
ある。
最初に、一揆のたてこもった原城が、
「原城跡」とか「原の古城」とよばれ無人の廃城のような受け取り方をしている事で
ある。しかし実際は、そうではなかった。
信長の存世中はマカオ・堺間に年一回の定期航路があったが、彼の爆死後イエズス
派が追われる形で、フランシスコ派がそれに代りつつあったから、秀吉の代には口の
津がその港であった。これは『フロイス日本史』などにも、
「口の津発」とでてくる地名である。そして、そこの津にあったのが原の城で、そこ
は輸入硝石の集積所だったのである。
だからして其処を押さえた一揆方は、緒戦から火器を多く揃えて、現地の侍の討伐
隊を手もなく追い払い撃退していた。
つまり彼らが強かったのは、熱狂的な宗教心の為ではなく、火薬庫を押さえていた
せいなのである。
次に、口の津は、当時の外人の溜り場だったから、そこにはフランシスコ派にしろ
イエズス派にしろ、必ずや青い目の宣教師やその他の南蛮人がいた筈である。だった
ら彼らは、天草四郎時貞といった少年を担ぎ出すより、その異邦人達をこそ主将とし
て、
「キリシタン一揆」ならば立てるべきだったろう。その方が篭城している者の士気を
鼓舞したろうし、また、日本人より外人の方が、
「神の御名は讃えんかな」と扇動するにしても効果的だった筈である。なのに一揆は
それをしていない。何故だろうか。この戦いでの一揆方唯一の投降者である山田右衛
門作は、
「こういう旗をたてていた」と、キリシタン一揆であることを証明するように、デウ
スの旗をかいている。これは、証拠品とされて、
「天草四郎の旗」として今も残っている。
しかし、おかしなことにその絵旗は、イエズス派やフランシスコ派というったカト
リックの物ではなく、プロテスタントつまり新教の、
「カルヴィン派」の、それは旗なのである。
カトリックが種をまいた地方で、神の御教えを守って彼らが殉教のために、三万余
が玉砕したものなら話も通じるが、プロテスタントの旗をたてて戦ったというのでは
辻つまが合わない。例えていえば、
「南無妙法蓮華経」の日蓮宗の旗をたてて、本願寺派の門徒が戦をしたようなものだ
から、てんで変てこなのである。だからして日本の、
「長崎二十六聖人処刑」というのは有名で、海外でも取上げられているのに、その千
倍以上も殉死したことになっている島原一揆が、まったく無視されているというのも、
その理由はこれである。
もし伝えられているようなキリシタン一揆なら、せめて、
「十字架を首にかけ捧げもっていた事になっている天草四郎」一人だけにでも、ヴァ
チカン法王方より、
「聖人(セイント)」の称号ぐらいは出されてもよい筈なのに、放っておかれている
のは、やはり理屈に合わず殉教とは認め難いからであろう。
これは宗教問題であるから、日本史よりもローマ法王庁の見解に従えば、
「島原の乱はキリシタン一揆ではない事になる」のである。
だから、その当時も、キリスト教国オランダのニコラス・クーケバッケル艦長は、
ライプ号に砲弾をあるだけ積んで、平戸から島原を攻撃しにゆき、二週間にわたって
撃ちまくっている。
もしキリスト教徒が異教徒の迫害に対し、レジスタンスをしていたものなら、クー
ケルバッケル艦長は、一揆の応援をして徳川勢へ弾丸を飛ばさなければ、本国へ帰っ
てから教会より破門をうけて、
「悪魔に味方したサバトの一味」として処刑されたろうことは間違いない。
またライプ号の乗組員一同も、一揆の連中がデウスの御為に戦っているものなら、
それを半月も腰を落ち着けドカパン撃っていられたろうか。
つまりこの真相たるや、
「一揆側は、口の津へ乱入して、その当時は硝石の輸入業者をかねていた青い目の宣
教師を、みな殺しにして火薬庫を奪取した」
のに起因していまいか。だからこそ、その仇討ちに、ライプ号も攻撃側に協力した
のだろう。
しかしである。徳川方では、こうした騒動が各地に波及しては困るから、局地解決
をして他へ伝播しないように、後に切支丹くずれも加入しにいっているのに眼をつけ、
これを一緒くたにして、
「キリシタン一揆」としてしまい、その裏づけのため、クーケルバッケルから借りた
聖旗を、山田右衛門作に、模写させたのだろうが、その際、
「キリスト教に新教と旧教の別のあること」まで、さすがの智慧伊豆も気づかず、オ
ランダのカルヴィン派のものを今に残してしまったのだろう。
さて松平伊豆守が、なぜ、そのような窮余の手をうち、
『島原文書』として残されている当時の公文書に、みなキリスト教徒の叛乱のような
扱いをさせねばならなかったかというと、それにはそれなりの理由がある。
表面は紫下賜事件だが、その実は櫛笥(くしげ)中将の姫を寵愛なさり、御子を設
けられたのが、徳川秀忠の娘和子の悋気にふれ、退位を余儀なくされていた後水尾上
皇に、そのとき、
「討幕の院宣を出される」という動きがあったからである。
もちろん徳川家は素早く数万の兵を京へ送り込み、用心して御所を取り囲んだ。
この時、それら兵の慰安所として、それまで大角にあった廓が丹波口へ拡張されて
移転。奈良本辻や大坂ひょうたん町の遊里からも女をよびよせ、でき上がったのが、
今でも、
「島原」とよばれる廓のあった地である。
さて、伊豆守の手腕により、島原騒動は局地的解決でかたがつき、上皇の院宣はと
うとう出ずじまいで済んだ。
しかしそのうちに上皇と櫛笥中将の姫の間に誕生された良仁(よしひと)親王が、
やがて後西天皇さまになられた。
さて、その頃、中将の末姫(見[貝?]姫)が仙台へ売られてゆき、そこで生んだ
巳之助が成人し、
「伊達綱宗」となっていたので、伝奏園地中納言をもって、帝は討幕の策をめぐらさ
れた。しかしそれも事前に洩れてしまい、
「綱宗は二十二歳で若隠居を命ぜられ」やがて、帝も、そのとき十歳の霊元天皇さま
に御即位となるのである。
しかし綱宗の志をつぎ原田会らは討幕に志すが、伊達家の佐幕派伊達安芸に訴えら
れ、
「寛文十年事件となって、原田甲斐の伜や孫まで斬刑、母は餓死」
という悲惨な結末をみるが、俗に、
「伊達騒動は、島原一揆の後日譚」といわれる謎も、このことによるとみるのは誤り
であろうか。
が、そうなると徳川家の立場では、島原の古城へ立て篭った輩は反体制の暴徒にす
ぎなかろうが、日本全体からみれば、彼らはかつて金剛や千早の天嶮によって御醍醐
帝の御為に旗上げした楠木一族となんら変りがないことになる。
なのに皆殺しにされてしまって、もはや証拠がないからとはいえ、
「切支丹一揆」といった扱いだけで葬り去られてしまうのは、余りにも哀れではなか
ろうか。
歴史というものは、その時の権力者によって、如何ようにもなるものだとはいいな
がら、島原で殺された三万の同胞が、時の天朝さまの御為に散華していったものなら、
合掌してその冥福を心から祈らずにはいられないのである。
日本岩窟王・怨念の天皇
「樅の木は残った」のテレビは大原誠ディレクターらの努力で美しい画面が見られた
が、終ってしまうと伊達騒動も次第に人々から忘れ去られてゆく。
すると恐れ多いが、おいたわしい天皇さまの事を書く機会もやはり遠のくかも知れ
ない。
それでは、せっかく、
「天皇さまがいつの世も体制側にあったよう、誤り伝えられてきた歴史常識に対し、
そういう事はなく天皇さまといえど庶民同様、時には体制側に苛められ給い、よって
民草はお尽くし申し上げる事に意義を感じ、無宗教だといわれる吾々日本人は、勿体
ないが天皇教のような信仰を故に心に秘めているのだ」
という解明のため、今まで誰も判らずだったこの帝の御事績を明らかにする折りも、
やがて、これでは逸してしまう恐れすらあろう。
さて、私が初めて、この天皇さまに奇異を感じたのは、明治大正の国史教科書編纂
官であった重田定一が、大正五年刊の、『史説史話』[1981年10月『謎だらけ
の日本史』として、日本シェル出版より復刻。校閲・補注 八切止夫。その一部は#
9735にアップ済み]において、
「明治になってから歴代天皇に院号をつけるのは廃止になったのに、なぜか人皇百十
一代後西帝御一方だけに、後西院天皇と院号がつくのかと、宮内庁にも色々御伺いし
調べて貰ったが、一切不明である。まこと奇怪な謎だが判らない」とあるのに眼を止
めてからである。
が大正の末年からは、なんの説明もなく院号をとられ目立たなくなり、その後の八
代国治の国史大辞典では、「読書喫茶優遊戯を卒(お)えらる」とある。
これでは優雅な生涯をおえられた天皇さまのようだが、それでは何故、特殊な扱い
で、
「院」をつけ差別されたのか私は不思議でならなかった。
処が満州事変に突入した昭和六年、黒板勝美が編集した『国史大系』の各巻頭には、
それぞれ、
「京都御所東山御文庫の、日本書紀を始とする六国史は、後西天皇がおんみずから筆
をとって著作された尊いもので、この御本を拝観でき校訂できたのは、まこと無上の
光栄なり」
天皇さまの御直筆ゆえ、間違えのないものとうたってある。
『六国史』は、日本書記、続日本書紀、日本後紀、文徳実録、三代実録と、膨大なも
のである。
これをみずから書写されたとは、「優遊戯ばかりされていた御方」の出来る事では
なくなる。
そこで矛盾を感じている内に京都御苑拝観の機会をえた。
「桂宮邸趾」の史蹟の日蔭に、
「後西院天皇の仙洞凝華洞趾」
棒杭みたいな標識があった。
北向きの陰湿な地面にかつて存在した凝華洞とは何なのか?
歴代の帝は退位後は仙洞御所へ入らせ給う慣しなのに、この帝のみが畳十四、五枚
の狭隘な、「凝華洞」に入れられ給うた謎はなんであるのか。それに、ことさらに、
こうした標識が残されているのは、余程それが特殊な建物であったろうし、また一面
それは見せしめの為といった感じさえする。そこで管理の役人にきいたが判らなかっ
た。
処が、それから二年程して、『近世文芸叢書』の中の、
「京都叢書」に入っている、
「京羽二重」の底本が、寛文五年刊の著者不明の『京すずめ』と判って原本を探して
いると、その初版の写本が入手できた。
「御苑にて雀や鳥をかいたもうにや、あみ張りの小屋ありて」
の一節が、その冒頭にある。
「そうか‥‥」私は謎がとけた喜びよりも、おいたわしくて涙がこぼれた。
「凝華洞」とは、恐れ多くも京所司代牧野佐渡守が、二十七歳の帝を退位させ十歳の
霊元帝を御位につけた後、二十二年の長きに渡って幽屏(ゆうへい)し奉った獄舎だ
ったのである。
『京すずめ』が書かれた寛文五年は、御退位後三年目ゆえ、作者は、先帝救出の悲願
から。
「あみ張りの御小屋」と、竹矢来を張られた状況を、謎かけのように書いたものであ
ろう。
もちろん京所司代は躍気になって揉み消しを計ったらしい。
体制側の儒臣を動員し、これを叩いたらしく『古語辞典』では、
「京すずめ=口さがなき者の取るにたらぬ流言蜚語」とある。だから今でも、
「口さがなき京雀」といったような書き方をしたのをよく見かけるのは、この時のせ
いによるらしいのである。
では後西さまは何故に、そうした目にあわれたかとなるが、一言にしていえば、
「謀叛の帝」しかも史上ただ御一方の、挫折された例だからであろう。
天皇さまで時の体制を倒さんとされた方は、あえて後西さまだけではなく、清和帝
の御子陽成さまも旗上げなされかけたが、藤原氏に終われ山奥深く身を匿され木地師
の祖となり、「後醍醐帝」も、その当時、やぎゅう者と呼ばれていた大柳生小柳生俘
囚郷の者らをたよられ、笠置山に旗を立てられたが、やがて北条氏を打ち滅ぼされた。
が後西さまだけは不運にも失敗なされ、捕らえられ他への見せしめに竹矢来の中に
入れられ、「岩窟王」ともいうべき、
「凝華洞王」として幽屏され給うたのであろう。
しかも徳川体制は幕末まで、
「天皇さまと申せ公儀へ弓引かんとなさるにおいては、かくのごとき目にあいまする
ぞ」
恫喝のために、洞の跡を故意に残していたのは酷にすぎる。
明治維新となって体制が変わった時、本来ならば後西さまの事も明るみに出て、凝
華洞趾の棒杭も撤去せられるべきだった。
処が、講談で有名な大岡越前守忠相が、出版統制令と共に、「ご当家(徳川)に益
なきの書は一切無用のこと」を発令した為に、京所司代土岐丹後守が、恐れ多くも御
所内の後西さま一件書類をも没取焼却した。
よって、明治から大正に変わっても、何故、後西さまにだけ、「院」を徳川家の命
令で付け御所に伝わってきたか、皆目不明の儘うやむやになった。
だから後西さまの討幕の確定史料は、今となってはない。
が、推理してゆくとなると、
帝の御生母は、四条家より分かれた櫛笥家の一の姫である。
さて、彼女への後水尾帝の寵愛を憤った徳川秀忠の娘の中宮和子は、寛永六年[1
629]十一月八日に帝に退位を迫り、己れがうみ奉った七歳の女一宮に譲位を求め
明正帝として即位させた。
そして和子が宮中で権勢をますます振るったから、櫛笥家は生活に窮し末の娘を、
奥州へ身売り同然に銀子引換えで送っている。この貝姫のうんだ己之助が長兄次兄若
死のため、やがて伊達綱宗となるのである。
そして、その四年前には‥‥
先帝に御子がなかったため、高松宮家をつぎ、そこの明子姫と既に婚儀をあげられ
ていた良仁親王さまが帝位を継がれていた。
この親王が後西さまで、櫛笥左中将一の姫の御子なのである。
二十二歳の若き帝が、従弟にあたる十九歳の綱宗が仙台六十二万石の当主、となっ
たと聞こし召されたとき。後水尾帝のご無念を知り、徳川の圧政に立腹しておられた
だけに、共に、
「討幕」を志されたとしても、これは無理もない事だろう。
しかし京所司代の知る処となり、先に綱宗が二十二歳の若さをもって、小石川堀工
事中なるも隠退させられて処分。ついで後西さまも、十歳の霊元帝に譲位せられる結
果となった。
もし退位された後西さまが、仙洞御所へ入られ優遊戯にあけくれするような、優雅
な余生を送られたものなら、隠居させられた綱宗もその儘だったろう。
が、凝華洞に閉じこめられ給うというのを洩れ聞いては、
「恐れ多し、なんとか致さねば」
となったのであろう。テレビでは、伊達兵部が悪役で御家乗っ取りの騒動になって
いるが、実際は原田甲斐も兵部も日本人として勤皇の至誠を尽し、それを佐幕派とい
うか御家大事の伊達安芸が幕閣へ訴えたらしい。
なにも幕末になって初めて、勤皇の士が現れ討幕運動が起こったのではない。仙台
城には、「帝座の間」または「上々段間」とよばれた御座所さえ作られていた程であ
る。これは後西さまを凝華洞から救い奉って、お移し申し上げる為だったらしい。
しかし維新の頃になると、もうこれも判らなくなって、
「朝敵となり抗命した仙台城に菊花御紋の御座所はおかしい」
という事になってしまった。
『宮城県史』においても、
「聚楽第を模して作ったものか用途は不明」となっている。
が、歴代の藩主は、その帝座の間に必ず拝礼してから一段下った席についていたも
のだと、
『伊達史料』には出ている。
つまり公儀の眼目が取潰しならば、六十二万石没取も訳なかったものを、伊達騒動
の決着が泰山鳴動に終ったのは、その蔭に後西さまがもう処分済みになっていた故も
あるだろう。しかし原田甲斐の遺児は二十五歳の帯刀(たてわき)以下四名、その帯
刀の長男で五歳の采女(うぬめ)、当歳の伊織(いおり)までが、公儀目付佐藤作右
衛門立会の下に酷たらしく殺された。
しかし、これを耳に入れ給うた後西さまの御心境は如何であったろう。この年寛文
十一年[1671]より、不幸な生涯をおえられた貞享二年[1685]二月二十二
日まで、十五年間の歳月は、その怨念を、
「徳川体制は誤っているのだ」
と、これに抗議なされる為、かの『神皇正統記』にも比すべき天皇制の正しさを主
張なさるため、自ら書写されたのが『日本書紀』以下のご労作であった事を想うと、
民草の一人としてまこと恐れ多い極みである。
これを七百枚にわたって書き上げた、「真説・原田甲斐」を文芸春秋社から刊行し
たが、もし、おいたわしい後西帝のことをしのびたい方は一読してほしいし、なにも
幕末になって初めて討幕運動が起きたのではない事も判って頂けよう。「八切史」と
か「八切史観」というのは、
「何が真実なのか?」というテーゼの下に、「本当は何であったのか?」と取り組ん
でゆくものだからであることも理解してほしいものである。
大久保彦左と一心太助
----これは講談口演本より抜粋して、まず先に援用してみるとことにする。
「大変だ大変だァ、天下の一大事だァ」
「なんじゃ太助、騒々しいにも程がある。そうガアガア大声で怒鳴ってばかりおらん
と、もそっと落着いて話をしてみい、出来ぬか」
「てやあガンでえ‥‥おう親玉。おめえさんいくら天下の御意見番大久保彦左衛門だ
と、威張ってなすったって、年よりだから金つんぼは仕様もねえが‥‥目まで風穴同
然。なんにも見えなさらねえのか。情けねえったら有りゃしねえよ」
「なんじゃ、太助、うぬは泣いているのか。それでは腕に彫った一心鏡の如しの文句
の方が、泣くぞ、いうてみい、なんじゃ」
「てへッ、なんだもこうだも有りゃあしません。公害問題を放ったらかしにしようっ
て有様なんですぜ」
「えッ、そりゃまことか。それでは天下御政道が、めちゃらくちゃらではないか。こ
れ喜内ッ馬をひけッ、天下の一大事じゃ。さあ太助ついて参れ、何をもたもたいたし
おるか」
「へえ、合点承知の介で、そうこなくちゃ話にもならねえ、行きやしょう」
当今ならこういう事にもなろう彦左と太助の間柄を、かつて関西の作家は、
「大阪の人間には、太助みたいに体制べったりな、いやらしいのはいませんよと某さ
んからいわれまして、成程とがっくりしました」
といっていたが、一心太助とは、そんなべったりタイプのいやな奴だったのだろう
か。もちろん実在ではなく講談の張り扇から生まれ出た人物であるが‥‥すっかり考
えさせられてしまう。
なお、更に引掛るのは、何故そのフィクションの一心太助を、実在の大久保彦左と
組合わせたかという関連性である。
現在の吾々の眼からもってすれば、旗本一万騎と号した中には、あの時代のことゆ
え、水野十郎左衛門とか加賀爪甚十郎といった若くて、もっとばりばりした有名人が
沢山いた筈なのに、どうして選りも選ってあんな老人と勇み肌の太助を結びつけたの
か、まさか当時の講釈師がドン・キホーテとサンチョの組合わせを、転用の形で当て
はめたとも考えられぬし、奇妙に想う。
が、見台を張り扇で叩きながら、なまの聴衆を前にして口演した際には、一心太助
という人物をそれらしく浮び出される為には、水野十郎左では駄目で大久保に限った
必然性が何かしら有ったのではなかろうか。
今では、その講談は太助が大久保家へ奉公していた小者上りで、やはり女中だった
お仲と結びつき、邸を出て魚屋を開業したのだから、彦左衛門は里親みたいなもの‥
‥といった納得しやすいような設定に作り変えられているが‥‥まさか当初から、そ
こ迄は話が出来てはいなかったろう。
すると、「旗本と魚屋」といった取り合わせが、聴衆をして不自然さを感じさせな
かった裏には、職業も居住地も勝手に変えられなかった江戸時代にあっては、誰もが
旗本になろうとしてもなれなかったように、魚屋も限定されていて、今のように河岸
の魚市場へ仕入れに行って、荷さえ持ってきたら、それで始められるというわけのも
のではなかったらしい[現代においても、勝手に魚屋を始められるものではないが‥
‥]。
そして現代でこそ無神論者も多いが、江戸期では西方極楽浄土をとく宗旨が、だん
な寺として百姓町人の、人別帖とよばれる戸籍を握って、今の村役場や区役所をかね
ていたのだから、信仰というものが人間の差別や区別をもしていた。となると、身分
は旗本と魚屋とは違っていても、彦左と太助は同一信仰グループでないことには話に
ならない。
そして当時の寺のたてまえたるや、魚肉は生臭として拒んでいたのだから、それを
扱う魚屋が公然と寺の管轄に入っていたとは考えられもしない。
となると彦左の方も、決して西方極楽浄土を願いお寺の信者ではなかった事になる。
またそうした同類でなくては、この結びつきが江戸時代の聴衆の耳に入れられる筈も
ない。
だから、その関連性は何かと、それから先に解明して掛らねばならないようである。
さて彦左衛門という男。彼も実際は講談のごとく馬や駕篭で登城するのを差し止め
られれば、
「なら盥なら構わんじゃろ」と横紙破りするような、そうしたむちゃな人物でもない。
彼の本貫は、その著『三河物語』の冒頭に、
「ワレ老人ノ事ナレバ今日ノ夕方ニ死ンデシマウカモ知レヌ身デアル。ソレユエ唯今
コウシテ生キテ居ル内ニ、コレヲ書キ残シテオコウト思イツイタノダ。ト云フノハ御
主(将軍家)サマハ、譜代ノ家来ノコトヲ一向ニ御存ナク、マタ譜代の家来衆モ他ノ
譜代衆ノ筋目(家来)ヲ知ラナイユエ、予ガ知ッテ居ルコトダケヲ書キオクナリ、ガ
吾ガ子孫ニワレラガ筋目ヲ知ラセンタメニ残すモノユエ、カマエテ門外不出トイフナ
リ」といった文章に要約される。
一見なんでもないようだが、よく眼を通せば奇怪すぎる内容である。
この時代は三代将軍家光の頃だが、その家光が、新参の家来や外様大名の事ならい
ざ知らず、譜代の家来のこれまでの家系を一向に御存知ないというのである。世にこ
んな可笑しな、断絶した主従関係がはたして有るものだろうか。また、
「その譜代の家臣」も、譜代どうしであるなら親や祖父、先祖代々から知り合いでな
くてはならぬ筈なのに、彦左は、はっきりと、
「譜代ノ衆モ他ノ譜代ノ衆ノ筋目ヲ全然知ッテ居ラヌ」
と暴露するみたいなことまで、それには書いているのである。
常識で考えれば、譜代とは先祖から引き続き仕えている家臣団のことゆえ、こんな
バカげたことはなく、それに大久保彦左は、
「三河者ならば、かいえき(改易、頭ごなしにさっと)に御譜代の者と思食(思召)
されるやの間、そうした訳も子供らが、知っておらねば困るだろうから、書き残すな
り」とも、つけ加えているが、
「三河譜代」とはよく講談に使われる表現だが、これでは、
「三河の者となれば、どうしても頭ごなしに御譜代の者と思われ、間違われやすいか
らして、色々のことをこの際覚えておくよう、子供らに書いておくから、それを覚え
て信じこめ」
といった意味にしか取れず、何がなんだか判らなくなる。
といって三河とはいえ、大久保党の出身は、いわゆる松平家領国の地方ではない。
彼の在所は、灯台で名高い伊良湖岬の渥美半島の中心部あたりで、今も彦左衛門の幼
名をとった「兵助畑」の地名が残っていて、
「大久保」とよぶバス停留所の右手奥にある。
彦左の幼時は、この半島は田原の戸田家の領地であって、戸田党は信長の父の織田
信秀と結び、松平の三河党[三河の松平党?]とは戦いをしていた。
そうした間柄の戸田領の大久保党が、どうして、
「御譜代衆であるのか」と知らぬ者から間違われる事があるのだろう。そして、それ
に対し、
「はい、そうであります」と、ばつを合せて、自分の家系を先祖伝来の譜代に仕立て
たり、将軍家光の家系すらも、皆が知らぬからと作って覚えこませることの必要がど
うしてあったかと謎になる。
しかし、これは後述する御三家の尾張7代目徳川宗春の、
「徳川家康は二人だった」
という考証が判ればなんでもない。つまり大久保彦左は、
「家光さまの三代前の権現さまという御方は、三河松平の御出身のようになっている
が、実際はそうではないからして、家来の者もご素性をあまりよく知らぬ者が多い。
また将軍家におかせられても‥‥なにしろ、われら旗本は御譜代衆とはいわれている
が、わが大久保は渥美、水野十郎左は苅屋、加賀爪甚十郎らは遠江白須賀、榊原小平
太の身内共は伊勢白子浦、服部半蔵らは伊勢かぶと山と、口では三河譜代といっても、
みな非三河系ばかりゆえ、----これでは譜代の者の家筋など、とてもお判りになられ
よう筈はない」
という意味をのべているのであって、それゆえ、序文の末尾に、
「各々方にあっても、ご譜代はご譜代らしく筋目をつけた家系を、この際こしらえ子
孫に残されることが、御家(徳川家)に対する忠節というものでありましょう」と、
しめくくっているのである。
しかし内容は大久保党が木こりをしていて、初めて畑を貰ったときに感激したとい
ったような、楽屋落ちの話は一切かかず、
「徳川の出自」の第一章は、いざなぎいざなみの二神から始め、新田系をもって将軍
家の祖先とし、親氏から代々を次の章にかき、いわゆる徳川伝説を一人で書きこんで
いる。
もちろんこれは、『大久保忠敬日記』『彦左衛門筆記』『参河記大全』の名で類本
も多く、これが林大学頭の手によって、
『徳川史』の底本になったというから、後から色々と書きこみをされ、いま伝わって
いるようなものになり、それでは内容的に不自然だというので、彦左が、
「自分はこんなに御奉公しているのに、報われる処がすくない」といった愚痴めいた
個所も、そこは抜かりなく挿入されているのである。
しかし徳川家のために、こうしたもっともらしい史料めいたものを残したという事
は、まったく欠けがえのない大忠臣であった。
この余恵で大久保本家は、大久保長安事件に引っ掛かったがすぐ許され、小田原十
万石も春日局のためその子の稲葉正勝に奪われたが、貞享三年(1686)からは大
久保家へ戻されている。
また彼の書いた「徳川神話」を守ってゆくためには、
「彦左衛門とはなんだ。そんなのがいたのか」
では困るから、明治軍部推薦で桃中軒雲右衛門が、
「武士道鼓吹、赤穂義士伝」をやらされたごとく、江戸時代の講釈師は奉行所のお指
図で、辻々に小屋をもうけ、そこで、
「只今より、大久保彦左衛門のお話を一席‥‥」とやって、彦左の実在を一般に強調
している内、話を面白可笑しくするため、ドン・キホーテに対するサンチョパンサの
ごとく、一心太助も張り扇で叩き出されて生まれてしまったのである。
しかし江戸時代というのは、今の日本橋の橋の左右に、
「あまだな」とよぶ魚河岸の魚問屋四十軒があったが、
「生臭きもの」といわれた生魚乾魚一切の販売権は、エビス、ダイコクら七福神や白
山系統の信心衆、つまり昔は別所に入れられていた原住系の者らの限定職業で、
「千の利休」といわれる宗易も、堺で魚屋の元締めをしていたが、江戸でも魚河岸は
これは弾左衛門家取締りで、そのため、
「棒手ふり」とよばれる板台を天びんで担いで歩くような小前(こまえ)者でも、魚
を商う者は、同信仰でなくては許されなかった。
つまり今は八百屋をやろうが魚屋をやろうが勝手だが、昔は、八百屋は百姓系だが、
魚屋は製革業と同じ素性の者に限られていた。
だから一心太助も、ナムアミダの宗旨ではなかった。
やはり、ビシャモンか、エビスの神徒ということになる。
さて話は戻るが、大久保彦左衛門一党の出身地である渥美半島は、今は観光バスが
豊橋から一周しているが、雨天でなければ、半島を七つに分割しているビシャモン、
エビス、ダイコクの各社の、赤青黄だんだら染め幟旗(のぼり)がはためいているの
が見られる。
何も今急にそうなったのではなく、ここは半島全部が昔は別所だったし、権現さま
が危うくなったとき、此処へ逃げこんで隠れていた徳川家創業の由縁ある土地である。
だからでもあろうか、大久保彦左は、徳川家を守るために努力したのであるし、こ
れが講釈師の口から語られるとき。
江戸時代の常識では、
「魚屋というのは、表むきの身分の差は、旗本の大久保彦左との間にあったにせよ、
一心太助は同じ宗旨のひとつもんだ」
ということが周知であったから、心安げに、
「おう親分はいねえかッ、大変だァ、天下の一大事だ」
と、ねじり鉢巻のままの太助が、神田駿河台の大久保邸へ、無遠慮におしかけてく
る場面をのべても、講釈場の聴衆は、
「確りやれ」とやんやと手を叩き声援をし、彼らが決して違和感を覚えなかったのも
理由はそのせいだろう。
つまり徳川政権に大久保彦左という男は、べったりどころか自分が糊刷毛をもって、
せっせと徳川神話を作りあげた功労者なのである。
だからして、彦左を話の中心にもってきて、彼の奇骨ぶりをおおいに語らせるとい
う事は、
(そうした曲がった事の大嫌いな正直一途の、頑固者の彦左でさえ認め、ちゃんと書
き残している徳川家の歴史というは間違いないものだ)といった裏書き的効果が有っ
たからして、講釈師が公けに口にするのをおおいに、おかみから認められていたのだ
ろう。
http://www.rekishi.info/library/yagiri/scrn2.cgi?n=1086
水戸黄門の世界
元禄年間以降あらゆる出版物の統制をした徳川家のために、日本の歴史は、寄らし
むべし知らしむべからずといった具合になったから、庶民には芝居とか講釈、そして、
でろりん祭文の世界だけが覗き穴的に許されたに過ぎない。
それゆえ、まるでそうしたものが、つまり過去の時代を扱ったものすべてが、さな
がら歴史のごとくにも誤られたので、
「稗史、小説」といったいい方もされ、そして、それが、やがて活字によって表現さ
れる講談という形になったとき、今でいうサービス精神が庶民に迎えられるような語
り口となった。このため、大衆の代弁者としての一心太助を作り、体制のパイプ役に
大久保彦左が担ぎあげられたのであろう。つまり、
『水戸黄門漫遊記』といったものも、歴史なら事実ありの儘で良くても、銭をとって
読ませる為には面白可笑しくといった要素がいるので、痛快がるようにと加味された
ものなのである。
だから、かいつまんで紹介してみると‥‥
助さん格さんを伴にして田舎親爺然の、梅里先生が諸国を廻って歩き、権力を笠に
きて弱い者苛めしている連中を見つけると、
「ああ、これ、これ」すぐに声をかけ、
「助けてやりなされ」と腕っ節の強い二人をさしむけ、相手をこらしめる。もし向こ
うが代官とか領主の時には、体制には一応は逆らわずに、
「さあ縛りなされ、手向かいは致しませんぞ」
と連れられて行き、さて向こうの親玉が出てきた処で、
「やあやあ、ここに控えておられるを、誰方(どなた)かと心得おるか‥‥恐れ多く
も天下の副将軍水戸光圀公にあらせられるぞ」
助さん格さんが、びしっと一発かませる。すると向こうはびっくり仰天。真っ青に
なって平身低頭。そして、
「知らぬ事とはいいながら、平に、平に御容赦の程を‥‥」
泡をくって周章狼狽するまこと痛快な場面となるのである。
----しかし、この黄門漫遊記は全くの講談で、本当のところは侍臣を使いには出し
たが、ご老公は茨城の太田から何処へも行かなかったといわれる。
では、何故、そうした物語が、元禄時代を背景に生まれ出たのか。
今日、昭和元禄などと使われているように、元禄時代というのは泰平ムード溢れた
暢(のんび)りした世の中で、なにも御老公が嘘にしろ、てくてく諸国を見て廻る必
要も、なかったろうにと想われる。
が、こうしたいわゆる常識的な味方と、その時代の本当のところがまだ伝わってい
た頃の実際の見聞とでは、どれ位までくい違うものだろうかと気になる。
また元禄時代というのが表面は天下泰平であっても、一皮むけば、それは大変な世
だったこともまず判って頂きたいものである。それは今や、昭和元禄とまでよばれ平
和そのもののようにみえながら、故三島由紀夫氏らが、
「他からは狂気の沙汰にみられようとも、これぞ憂国の至情の致すところ」と割腹し
介錯をうけ胴と首を別個にして、自決している反面すらもあるのである。
さて、ターララ、タララララで始まる元禄花見踊という和洋大合奏が賑やかなので、
そんな世の中だったのかとも誤られやすいが、あれとても実際は元禄時代に出来たも
のではない。
「元禄小袖」とよばれる派手な衣裳も、勿論あの時代に関係はなく後世の産である。
では、どんな時代だったかというと、徳川時代をそのまま鵜呑みにしている歴史家が
説く元禄時代とその実際は、改めて考究してゆくとまるっきり違う。
「雪と炭」といった古い形容詞が当てはまる位に相違するのではなかろうか。
というのは徳川家というのは、もともと前述した平凡社『百科事典』の新田系図に
あるごとく、世良田系であり修験者畑である。
だから家康、秀忠の代には、
「柴衣事件」で知られるように、仏門への風当たりが極めて強く、坊主に対しては、
おもねってくるのには寛大でも、威張っている坊主には、くそみその扱いで遠島処分
にさえした。
しかしそれも、家光の代からおかしくなった。
秀忠は、「神君東照宮」として父家康を祀ったのに、
「仏式にやりかえい」と家光は、神君を権現さまに変えてしまった。だから家光の子
の家綱や、その弟の綱吉の時代になると、ますます仏教傾向がひどくなってきた。そ
して綱吉は、
「東光の者らをかたづけい」とまでいいだし始める。
東光とよばれるのは、西方極楽浄土を唱える一般の仏教に対し、
「東方瑠璃光如来」をもって、東方にこそ光ありとする宗派で、これは「医王仏」と
も、また、「薬師寺派」ともいうものである。
この信者は、かつて公家に対する地家、つまり原住系として捕虜収容所の、別所、
散所、院地へ入れられていたり、または、北条氏におわれて逃げこんできた源氏の残
党。つまり俘囚の裔なのである。
だから俗に武士は俘囚の末だからと、「地家侍」などといわれるのも、この為であ
るが、彼らは初めは、エビス、ダイコクの七福神や、白山神、土俗八幡の信仰だった。
しかし織田信長が天正十年六月に、本能寺で爆死をとげると世の中が一変し、今も
残されている、『天正十一年裁可状』の文面にもある通り、各地の拝み堂から、修験
や博士、太夫とよばれていたのがみな追われ、僧籍をもった者が代わりに入ってそれ
が寺と変わったとき。
いきなり頭ごなしに、西方極楽浄土も受けつけまいと、それらが、いわゆるお薬師
派になったので、それまでの原住系のあらかたは、東光の信者になったのである。
『天正日記』とよぶ徳川家康の臣が、刻明につけたものにも、小田原から江戸へ初め
て入ってきた家康が、まず東光の御堂を拝み、寄進をした旨をかいているが、この派
の信者は関東には多かった。
もちろん何時の時代、何処の場所でも、以前のオキナワにしてもアメリカ人より県
民の方が遥かに多いのは常識だが、徳川時代でも、西方極楽浄土の門徒より、東光信
者の方が数では圧倒的に多かった。
しかも彼らは、皮はぎという専売業をもっていた。
戦国時代は終り、冑鎧の需要はなくなったが、ビニールも[合成?]レザーもない
時代ゆえ、元禄期になっても皮革は高価に取引きされていた。
だから製皮業者を信者にもっている薬師寺派の方は、寄進喜捨が多く、掘立て小屋
みたいな拝み堂だったのが、次々と山門つきの立派な普請に変わっていった。昭和の
今日でも、
「お寺言葉」で、裕福な檀家のことを、
「肉の厚い」とか、「皮の良い」というのは、これから来ているのである。
さて、こうなると西方極楽浄土側の方では、
「面白くないこと、おびただしいものがある。怪しからん」
と将軍家の生母お玉の方をつつき、しきりと運動をした。
そして考え出された名案というのが、「皮をはいで儲けるな」とは法令が出せぬか
らして、
「生きものを憐れめ」という、生類憐れみの令である。
日本では獣といっても虎やバファローはいない。比較的捕えやすく皮を剥がしやす
いのは犬である。
そこで畜類を愛護する為ではなく、製革業者を弾圧する必要上、各地に犬小屋を作
って片っ端から収容した。しかし係りの役人の中には、その法令の真の目的までは判
っておらぬ者もいたからして、
「雀をとってはいかぬ。鳥類も生きとるから、生類の内に入るのである」と、畑で野
荒らしの雀をとった子供さえ牢に入れられた。
さて、これが地方へ行くと、ますます役人は融通がきかなくなるものだから、余計
に厳しくなってしまい、
「なに鼠を、猫が捕えて食したと申すか‥‥それなる猫を召捕って牢へ入れい‥‥う
ん、猫も生類の内か。それでは捕えた身共の手落ちとなり、責任問題になるやも知れ
んな。では猫の飼主をつかまえい。人間ならお叱りはあるまい」
といった事態が各地におきた。こうなっては野良へでも、吸いつくひるさえむしり
取れない。
そこで、誰か、役人や代官より豪い人が見廻りにきて、
「助けてくれぬものか」といった願望が、『水戸黄門漫遊記』となって現れ、庶民の
夢と憧れになったのだろう。もちろん講釈になった時期はずれるが、この元禄時代が
如何に大変であったかは、孫子の代まで語り伝えられていたので、
「そうか、黄門さんが廻って皆を助けて下されていたのか」
と一般大衆は涙を流して喜んで聞いていたのだろう。
だから『講談水戸黄門』の方も、そこは抜かりなく、
「ご老公におかせられては、犬より人間の方が粗末に扱われるとは何事かと、くだん
の死んだ犬の皮をはがさせ、血まみれなものを役人に渡してやり、わしは光圀なるぞ
と仰せられて‥‥」と、そういう挿話までが書き込まれている。
さて、俘囚の裔の原住系の中には武士となっている者が多いから、
「暴動、一揆、叛乱」という心配をしたのだろう。それまで知行所に住まうことも、
その行ききは自由だったのが、この元禄年間から禁止されてしまったのである。
やがて、この結果名主とか庄屋が、自分の宰領で年貢を出すようになったからして、
武士を軽視しだし、天誅組の吉村寅太郎のような庄屋の伜が、
「天皇さまの下に大百姓が揃って政務をとり、武士階級をなしにする時代」を夢みて
旗あげするようにもなるのだが、これは後の物語である。
虚像大岡越前
たしか『丹下左膳』にも、『大岡政談』というサブタイトルがついていた。そこで
大岡越前というのは、自分から聞きこみに、こつこつ歩き廻ったり、危うい目に逢い
ながらも庶民のために正義の味方となってくれた名奉行、というイメージを今も一般
に与えている。
処が、先年なくなった田村栄太郎の著では、
「すべての出版物に弾圧を加えたのは、講談で馴染みの大岡越前であって、一般庶民
の歴史常識、知識をまったくゼロにさせ、小説、演劇、講談といった出たらめな作り
ごとを、さながら史実のようにも誤認させた張本人は彼であって、そうした徳川時代
の愚民政策は、施政上都合がよいせいか今も続けられ、まったく噴飯ものである嘘八
百の芝居や講談に、歴史の方が折り曲げられ合せられている。バカバカしい話だが有
知識人と自負する人でも日本では講談常識の範囲でしかなく、それで頭がこりかたま
っている。これも大岡のせいだ」
と前置きがされてから、
「どんな書物であっても作者版元の住所実名を、奥書につけ奉行所へ差し出すこと。
これまで通りのことは良いが、新説異説を唱える者は厳罰に処せられること。権現さ
まや徳川家を扱った場合は、直ちに重き刑にあう。やむをえぬ場合は前もって奉行所
に伺い出てその差図を受くべく候」と、事前検閲制までとっていたと説明し、
「大岡越前を名奉行扱いしたのは、その後の出版業者が奉行所のミコをよくしようと、
中国ものの翻案で大岡政談を作ったせいだ」
としているが、さて、本当はどちらなのかということになってくる。
大岡越前守に対照されるごとく、やはり劇映画やテレビに引張り出される形の、遠
山桜の金四郎こと遠山左衛門尉景元とは、彼の有り方はまったく違うのである。
勘定方上りだった遠山は、経済取締りをかねたが、その方針は、やはり司法警察だ
ったろうが、大岡の方は徹底した行政警察なのである。
つまり彼は今でいう警察国家をまだ江戸時代なのに、世界に魁けて創造した卓越し
た頭脳と技倆の持主ということになる。
「武士は主があるを知って、主に主あるを知らず」とする封建時代にあっては、大岡
は徳川家の御為だけを考え治安維持に万全を尽せばそれで良かったのだろう。彼の施
政方針によって、日本の歴史が判らなくなったり、それが歪められてしまったとして
も、それは関知せざる所であったに違いない。
とはいうものの、町奉行という文字面の観念で、そうした行政方面の辣腕より、も
っと庶民的なものをと、今の人は感じたがるらしい。だからして、朱房の十手を腰に
さして歩くような大岡の虚像を瞼に描きたいもののようだが、町奉行という職は、町
のため住む人の為にと作られたものではなく、江戸時代にあってもそれは取締まるた
めに、おかみが作ったものである。
だから今日のように、
「税金で人件費を払っているから公僕」といった考えで、
「大岡さまは江戸の町の守り本尊」と、マンガ式にみてはならない。
彼が名奉行だった一つは、中国でも秦の始皇帝しかやれなかった焚書を、彼は日本
でも堂々とやっていること。
そして、まだ十八世紀の初頭の1717年(享保二年)に登用されると、すぐ今日
の警察国家の形態を考え出した点であろう。
次に二十世紀に入ってから、万国ジュネーブ協定によって、出版物は奥付に著者名
発行者名刊行月日をつけることが、赤化宣伝物横行防止のため、自由諸国間に取り決
められ、現に吾々のみる本はみな奥付がついているが、驚くなかれ大岡越前守は既に
1725年(享保十年)において、それを実施し法令化し、
「前もって奉行所へ訴え出て、その差図こを受け申すべく候」
事前検閲制度まで施行していたのだから、立派なものである。
「泥棒、人さらい、掻払い」といった町民のための司法警察は、
「主権在民」などといわなかった江戸時代の事ゆえ、放っておかれたので、日本駄右
衛門の白浪五人男の台辞のように、
「盗みはすれど、非道はせず」と、大岡越前は泥棒などは非道とはみず大目にみて、
行政警察にのみ専心。
やがて彼は、
「前の奥州梁川三万石城主にして、その兄継友の死後、尾張へ戻って御三家六十二万
石第七代目名古屋城主となり、それまでの通春」
の名を「徳川宗春」とかえた文学青年を、
「不都合のかどこれあり候」と閉門にしてしまうと、すぐさま、
室鳩巣序文、堀杏庵作となっている『石ガ瀬戦記』
の二冊に、尾張宗春自身の名で出された、『温故知要』まで一括没取し、これを江
戸表へ送らせ、ことごとく焼いてしまう弾圧ぶりを見事やってのけた。
何故かというと、これは、徳川の世も七代吉宗と、ようやくおさまり大磐石の安き
に落着いてきた処へもってきて、
「三河松平元康が家康さまというが、そちらは長顔で、尾張徳川家始祖義直公のため
名古屋城が築かれたとき、実地検分にこられた権現さまは丸顔であらせられた」とか、
「三河の家康さま[松平元康のこと]と浜松の家康さまが同一人のわけがない。何故
かなれば石ガ瀬と和田山で二度まで対戦しておられる」
「三河の方はプロの兵だから強かったが、権現さまの方は伊勢の薬売り榊原小平太と
か、遠州井伊谷の神官くずれや、渥美半島の木こりの大久保党、駿府の修験者酒井ら
の寄せ集めの者ゆえ、二度ともあっさり権現さま方は負けてしまわれたのである」
といった土地の故老たちの懐旧談を、いやしくも権現さまの玄孫にあたる御三家の
当主、宗春の手で版木にされ、
「徳川家康は二人だった」では、どうも公安上差支えたからであろう。
そこで御家御安泰のために、その版木は没取され、木はみな灰とし、宗春処分後も、
尾張へはそれから代々養子をもって継がせるという、抜本根源策を越前守はたてたの
である。
ついで大岡越前守が名奉行ぶりを発揮したのは、アメリカでFBIが創設されるよ
り、百年も前にそれを日本で始めたことによる。
大名領、天領と分かれていたその頃の日本は、法律も各国ごとに違っていた。
それを越前守は、街道という点と点をつなぐ線上において、全国を一つに結びつけ、
これに公儀直轄の探索逮捕の網をはることにした。
享保二十年(1735)十一月十六日付で、大岡越前守は、街道筋を遊芸物売りで
行商して歩く、昔の原住系で大道商いの、
「道の者」とよばれていた連中の主だった者を集め、彼らに、
「道中で怪しい者を見つけたら捕え、取調べ方を命ずる」
朱鞘の公刀に十手取縄を渡し、従来の地方警察制の上へ、新しく国家警察を設けた
のである。しかし当人らは、十手を腰にさして、
「ええ飴だ、飴だよ、金太郎さんの飴だよ」
と太鼓を叩いて廻っても売れはしない。
それに捕物をするのには人手がいるが、飴屋や薬売りでは、その人件費の捻出は不
可能である。
だから街道のやし[香具師]はいつしか縄張りをきめ合って定着し、現地の地方都
市が競輪競馬のギャンブルで資金を作り、それが地方警察の建物をたてたり給料を払
ったりするみたいに、賭場をひらく事にした。その方が儲かるし、子分を賭場では、
「ええ寄ってらっしゃい、お手なぐさみに如何さまで‥‥」
と客引きにつかい、御用の節には鉢巻をさせて、
「やいやい神妙にしろ」と、くり出すことができ、一石二鳥にうまくゆくからである。
つまり映画や三文小説では、
「二足草鞋の親分」という悪い奴の代名詞みたいにするが、あれは間違いで御用の十
手を握るやくざの親分の方こそ、大岡越前守から命ぜられた国家公務員のFBIの子
孫なので、いわば正統派なのである。
天保から幕末にかけて物価高と飢饉で浮浪人がふえ、もぐりのやくざが旅から旅へ
と渡り歩いたが、あれは半可打ちといわれた者で、「仁義」をきらせ、その生国や親
分の名を、まっ先にいわせるのも、筋目正しい大岡越前守さま御免許の渡世人の流れ
か、もぐりかの鑑別をする必要上、うまれたものなのである。
さて、幕末文久二年(1862)になって、それまで朱鞘をさし、御上御用をやり
ながら賭場をしていたやしの親分が、抜刀が横行しだしたのに手をやき、昔ながらの、
「神農さま」をまつる高市(たかまち)稼業一筋に戻ってしまうと、もう半可打ちも
本可打ちもなくなり、博徒らは血みどろになって縄張りを守り拡張しようと斬り合い
にあけくれするようになった。天保あたりまでまあ波静かにおさまっていたのは、大
岡越前守のFBI制で、博徒が御用聞を兼務していた賜物であったから、明治新政府
も、
「清水の次郎長に十手取縄」といったように初めはその真似をしたものである。
つまり俗に名奉行といわれる遠山桜の金四郎のごとき、町民に媚をうるようなげす
とは違い、なんでもかでも権力で押しきってしまい、後年の模範ともなっている彼こ
そ、
「能吏」中の能吏、徳川家にとっては他に比肩をみない名奉行であったといえよう。
うばは乳母でない話
箱根に姥子(うばご)の湯というのがある。
伝承では坂田山の金時が、眼の悪い姥を背負ってゆき、眼病にきくとされる明ばん
泉で治すため通ったとされている。また、「姥すて山」が信州の川中島の近くにある。
これは貧しい農民が食べさせてゆけなくなった姥を背負ってゆき、堪えてくれとや
むなく置いてくる山だったそうである。
だが、どちらも「ウバ」とあっても、もし乳を呑ませるだけの乳母であるなら、乳
離れした時に暇を出されてしまっている。
それでは年寄りになるまで同居して、眼が病むからと冷泉の出る所まで運んでゆく
事も事もなかろうと想われるのである。
しかし姥の字は女扁に老とかくから、老女と解釈したいらしく、翁と姥といった組
合わせもするが、女の古いのといってもやはり母親には違いなかろう。つまり「うん
だばば」がうばと想えるが、それでも現在では、「ウバ」といえば、乳母が常識であ
る。
漢音にしろ呉音にしろ、乳をウ、母をバとよぶ発音はないが、これが罷り通ってい
る。
もちろん戦国ものの確定史料には、そうした言葉はなく、乳人というしかない。
だから乳母も「ちちぼ」でなくては変だが、これの語源とされているものは、
橘成季(なりすえ)の『古今著聞集・十五』にあるところの、「幼き日に浅間しく
歎きて、うばにうれえ、たいじようしけれども」の一節からだという。
が、(うれえ=訴え)(たいじょう=両手をつき詫びる有様)だからして、うばが
奉公人の身分であるならば娘がそこまですることはなかろう。これは著聞集を解釈し
た人の誤りではなかろうか。
なにしろ「うば」を乳母にしてしまったが為に可笑しくなってしまったのは、なん
といっても春日局の存在である。
「竹千代御腹春日局、のち三代将軍家光 国松 御腹御台所 のち駿河大納言忠直」
と明記されているものが残っている。
これは幕末まで江戸城の紅葉山文庫に、極秘保管されていた『神君御遺文』の末尾
につけられていたもので、明治四十四年に非売品として千部だけ活字本になったもの
である。
原文は内閣総理府図書館に、今も歴然として残されている。
「御腹」とはいうまでもなく、生母のことである。つまり徳川家では、春日局は徳川
家光の母であったことが明白なのに、どうしてこれを匿していたのだろうか?
その謎ときは後に廻し、まず従来の乳母説をもう一度考えてみたい。俗説では、京
所司代板倉勝重が、徳川秀忠に長子が生まれたので、よき乳人をと公募して彼女を採
用し江戸へ送った、----という事になっている。
が、公募というからには、何人もの候補者が選ばれ江戸城へ集ってコンテストを受
けるべきである。なのに初めから彼女ひとりだけが東海道五十三次を遥々東下りして
江戸へ赴いている。
これでは肝心な秀忠夫妻に面接せぬ先から、もう決まっていた事になって変ではな
かろうか。
さて彼女はそのとき既に、正勝、正利の子があった。
つまり乳母として採用されるからには、末子の正利はまだ授乳中でなくては話が合
わぬ。処が正勝の子の稲葉正則が本郷湯島麟祥院へ、貞享三年九月十四日に奉納した
額によると、彼女が東下りした時、末子は既に三歳であったとある。
すると彼女の乳は止っていた筈である。ではドライミルク罐でも持って行ったのだ
ろうか?
家光の生母なら乳が出て呑ませられたろうが、でないと搾っても出ない事になる。
それに乳母なら、乳離れした時お暇が出るべきなのに、彼女はそのまま居座って家
光七歳の時には、死にかけの家康を駿河から引っ張り出してきている。
あれは乳母では強引すぎて、まるで男の責任を問う女のような、そんなやり口であ
る。
だから家光は秀忠の子ではなく家康が彼女に産ませ、母子こみで江戸へ送って置い
たもの、とも疑えるのである。
もし竹千代も国松も共に孫なら、わざわざ死ぬ前年の七十四歳の老人が、江戸まで
出てくる必要などなかったであろう。
また秀忠にしても吾子なら、家光が二十歳になったからといって、自分がぴんぴん
しているのに将軍職を譲ることもなかったろう。どうも変である。
春日局という名は彼女で打ち切りになってしまったが、それは、
「征夷大将軍側室にて小御所へ参内、天覧をうける女の官名」
と定まり、室町時代にも代々「春日局」は一人ずついて、『毛利家記』にも、足利
義昭の春日局の記事が書かれてある。
だから彼女がその名を用いたことは、家康の側室だった事に間違いなかろうと推理
される。
なにしろ彼女は前夫の子を十二万石の大名に、自分も神奈川三千石の所領の他に、
銀百貫匁ずつ毎年とっており、寛永二十年病気になると、代官町の屋敷へ家光は三度、
家綱も二度、御三家はもとより勅使までが詰めきる豪勢さで普通ではない。
なのに彼女が乳母と世間を偽ったのは、五代綱吉から徳川家では、彼女の父斉藤内
蔵介がなした信長殺しを、家康の使嗾とせず光秀にかぶせる為の工作で変えたものら
しい。なのに初めは、
「三代将軍家光公卿御はら」とあるのが、いつの間にか、乳母となってしまたったか
ら、戦前の修身の本などでは、
「春日局は幼い竹千代を大切にした。だから竹千代も成人してから、春日局を大事に
して仕えた。乳母とはいえ忠義を尽せば必ず報いがある。隠匿あれば陽報ありなので
ある」と、よく働け、主人を大切にしろ、といった教訓用にと教材用にされたもので
ある。
しかし、いくら忠義を尽した処で、相州東郡内用吉岡で三千石の領地と、毎年白銀
百貫匁ずつの手当となると、手取りだから一万石の大名なみで、他に春日局は江戸代
官町に三町四方の敷地を貰って、ここへ親類の蜷川喜左衛門の手で豪壮な邸を建てさ
せた。
そして寛永二十年九月に発病し、代官町の自邸へ下がると、千代田城から其処まで
家光は三回も行列を仕立てて見舞い、家光の子の家綱も二度にわたってその枕許に付
き添い、千代姫を始め家光の他の子女が詰めかけ、御三家の尾張、水戸、紀伊も何度
も伺っているが、恐れ多くも御所から勅使右衛門佐局までが下向している。これでは、
いくら忠義への報酬でもオーバーすぎる。家光の生母だからであり、家綱らには祖母
に当たるためだろう。
といっても、
「春日局は家光の乳母」と思いこまされている人が多いからして、
「そんな事はない」と否定したいだろうが、彼女を葬った前述の湯島天沢山麟祥院に、
追悼の額をあげた孫に当たる小田原城主稲葉美濃守正則や、江戸代官町の屋敷を建て
た蜷川(この曾祖父蜷川道斎の妹が斉藤内蔵介の母で、春日局の祖母)の自筆書付に
よれば、
「春日御局が京より東下されしは末子内記が産まれてより三年後の慶長九年なり」と
も明白にある。
つまり他人の乳母では、最後の子をうんでから三年もたっていてはとても乳など出
まい。
が、御腹ならば自分で家光を産んでいるのならば、これはいくらでも授乳できたと
いうものだろう。
さて、死せる子は眉目よかりき、などというが、どうも故人となった女は、死者へ
の礼でもあろうか誰もがみな美人扱いをされてしまう。
しかし本当の美女はそうざらにはいなかったらしい。が、誰もが依存なく指を屈す
るのは、やはり於市の方であろう。父の織田信秀は勝幡の小城から、尾張八郡を平定
するようになる迄、普通では兵も馬も集まらぬから、
「平手の庄の政秀には年頃の娘がいる」ときけば、その娘に後の三郎信長をうませ、
「阿古井の豪族土田久安に妙齢な女子」がと耳にすれば、それに後の四郎信行を作ら
せるように、一夫一婦の時代でなかったから、その生涯に男子は一郎信常から十一郎
長益(織田有楽)まで、女子も於市の他に八人をそれぞれ尾張の豪族の娘にうませて
いる。
そして、それらの親兄弟を味方にして、今でいえば同族会社のようなやり方で、尾
張一国を掌握し得たのである。
だから信長と於市は異母兄妹の間柄に当たる。
さて、信長は美少年万見仙千代を奪うため、摂津の荒木村重と戦ったようなホモ型
である。もちろん戦国時代ゆえ人的資源の必要上、生駒将監の後家娘に信忠、信雄を
うませたり、神戸の板御前とよぶ未亡人に信孝らを作らせているが、それはやむを得
ぬことで、きわめて女嫌いで女性にはむごかった。
それが於市御前だけは可愛がり、浅井長政へ嫁入りさせる時も、前にいた女はそっ
くり追放させ、信長は己れの長の名のりを与え、「長政」とした先方へ当人をとっく
り確かめてから縁づけている。
信長が他の異母妹には無頓着で、於市一人だけを溺愛したのは、やはり彼女が美少
年型の絶世の美女だったからによるのだろうといえよう。
この於市に三人の娘がうまれた。長女は、「やや」と初めよばれた茶々、後の淀君
である。この人を於市の娘ゆえ美女と誤る向きもあるが、秀吉が彼女を近づけたのは
二十二歳になったからの話しゆえ、それ迄、放って置かれたという事実は、あまり男
の気をそそる容貌ではなかった事になる。
『当代記』や、『大阪御陣記』によれば、「騎馬女三十人ばかりいつも引き連れ、緋
威しの大鎧をめされ七寸(ななき)の馬にめされ」と、出ているのをみると母親似で
はなく、父浅井長政生き写しの骨太な大女であったろうと、
『女人太閤記』に私は推理して書いた程だ。
次女の京極高次夫人になった常高院は、「細身ながら気性烈しく」と残っているが、
まあ十人並みであったろう。処が三女の、「ごう」とよばれたのは、これは於市をさ
え、しのぐ抜群の美人だったらしい。
「せんだんは双葉より芳し」というが、十二歳の時すでに母方の尾張大野の、佐治与
九郎に求められて人形のように嫁ぎ、翌年は連れ戻されて秀吉の養子だった信長の四
男於次丸秀勝にめあわされ十六歳になった時、秀吉がその秀勝を殺して、己れの甥の
秀次の弟小吉に同名を継がせた際、彼女は左大臣九条道房の許へやられ、やがて取り
戻されて徳川秀忠の許へ、「江戸へ与えるのだから、江与と改名せい」と嫁入りさせ
られる。
まあ、余程の絶世の美女でなくては、こうも、たらい廻しさせられるものではない。
さて、この絶世の美女のなれのはての江与と、春日局を対比させ、これをエリザベ
ス一世とメアリ・スチュワート女王との関係においてみたのが、「八切日本史」の中
の『謀殺』[既に当コーナーにアップ済み]なのである。
http://www.rekishi.info/library/yagiri/scrn2.cgi?n=1087
中元は民主主義精神
「百科事典」の類をみると、正月と暮の中間だから中元で明治以降贈物をする風習が
始まって、中元大売りだしなどというのが行われだした、となっているが、はたして
どうであろうか。
『唐六典』には、
「七月十五日、地官為中元、懺侃(ざんかん)言罪」となっている。つまり一月十五
日の上元は天帝に対し、供物をして寿ぐのだが、中元は地にある同じ人間どうしが、
平素の交際における不行届をわびて、物を贈ってその謝罪をするのだ、というのだか
ら明治時代というのは、とんだ間違いで、『唐六典』が輸入された平安朝以降が正し
かろうと想う。
もちろん、これが形式的になりだしたのは江戸時代からのことで、
『音物(いんもつ)問答』という文化年間の本では、
「武家屋敷入口に敷台があるは、玄関に立つ時の踏台の用の為ではない。もしその用
途なれば根太材を組み厳重にするべきだが、四方かまちのみで中央が空になっている
のはその上の音をよく反響させる為なのである」としてある。
つまり、これは挨拶のことを色代とかき、しきだいと訓するごとく、訪問客が手土
産持参の節、昔は銭束が多かったので、どさりと敷台に置くと、その目方でおよそど
れ位か音で判るゆえ、取次の申次衆は聞き耳をたて、
(まだ不足)と思えば知らん顔をしていて、追加して重くなった音がきこえてくると、
「‥‥どうれ」と初めて案内に出たもので、今の世に、よく銭を追加するのを、
「色をつける」などというのも、色代から始まった言葉なのである。
「音信不通」などと沙汰のないことを言うのも、その音は銭のことをさして、銭も送
ってこねば便りも来ぬというのである。
さて近頃流行の辻講釈まがいの歴史ものでは、
「武人不愛銭(ぜにをあいさず)」などというものがあるが、あれは見てきたような
嘘をついているので、江戸時代には七月の声をきくと日本橋本阿弥邸などに行列がで
きるのは、切紙を求めに諸家の用人などが集まってくる、と『江都歳時記』にも出て
くるぐらいである。
これだけでは今の人には判るまいが、江戸時代に本阿弥家の切紙が中元にもてはや
されたというのは、鰹節の切手やデパートの商品券が贈答用になったというのではな
い。
武士にとって、槍は攻撃用具だが、刀は「打ち刀」と古来よばれるように自己防衛
の用具だったから、この刀を贈答品にするというのが、好適のものとして喜ばれたら
しい。
が、刀には勝手に銘を切りこむ贋刀、つまり盗作も多いので、良いと思って贈って
も、それが不良品だったら反って逆効果になる。
だから本来は、本阿弥のような専門目ききの鑑定書をつけて贈るのが、心得という
ものだった。しかし、ここが難しい処で、とかく人間はそうした立場になると、悪い
ことをやりたがるもので、江戸中期の本阿弥の何代目かが、目ききの鑑定師の立場な
のに、目がくらんで盗作をやってのけたのがいた。
刀の銘を切り替えたか、贋と承知で証明書をだしたか判らないが、やってしまった
のである。こういう事は現代でも文学博士の肩書で、道具類に対してそういう事をし
て儲けているのもいるし、最近の某新聞の第一面に、八段抜きで、
「読者をなめた丸写し、堂々月刊誌に発表。形なしの某は、この盗作に関しては、非
常にはずかしい、この問題によって、どんな社会的制裁を受けようとも仕方がないこ
とだ、といっている」
と、それまで東京新聞の中間小説時評を担当していた、いわば目きき鑑定役でもあ
る批評家である男が、自分で盗作騒ぎを起こし問題になっているが、江戸時代は社会
的制裁を受けるどころか、そうした際は自分で制裁をしなければならなかった。
幸い刀の手持ちは沢山あったから、何代目の本阿弥さんは、一本を腹へ、一本を咽
喉へ、そしてもう一本を心の臓へつき刺し自決してしまったそうである。すると、こ
れが、
「一刀でも痛かるべきに三刀も刺すとは、さぞや苦痛であったろう」
と同情をひいた。なにしろ日本人は死にさえすれば、その罪を憎んでその人を憎ま
ずといったモラルがあるから、本阿弥家はその儘で続くこととなった。
しかし、そういう事があった後ゆえ、代は変っても、鑑定書を貰っても、どうして
も疑心暗鬼になり勝ちである。
そこで、本阿弥家では面倒ゆえ、証明書をつけるのは止めにして、
「一金五十両也、右金員引換えに何々銘の刀を引換えまする」といった切紙をだした。
もちろん、五両、十両の贈答用にもってこいのも、どんどん切紙を作製したから、
中元の季節になると門前に行列ができた。
というのは、なにしろ天下泰平の世では、
「貰うのはよいが、だからといってたえず手入れしたり、時々は研ぎに出さねばなら
ぬ実物は厄介千万である」
と、その切紙を持って交渉にゆくと、本阿弥家でもなにしろ実物でなくて紙切れに
すぎず、金準備高を無視して乱発している何処かの国の紙幣のようなものだから、
(本物と交換といって来られては困るが、金で引換えるのなら願ったり叶ったり)で
あるからして、
「これは十両の切紙でございますな。当方の手数料を一両二分引かせて頂き、はい八
両二分どうぞお納め下さい」と、すぐ現金払いに応じた。
こうなると刀剣鑑定は看板だけで、手形割引業のようなものだが、贈る方も貰う方
も、手数料はとられてもこんな重宝な事はない。
だから中元は本阿弥の切紙は便利がられたが、不思議に下元つまり暮の御歳暮には
用いられなかった。恐らく現金のやりとりゆえ年の暮は露骨すぎるので、贈るのをど
うも慎んだものらしい。
が、それにしても盗作批評家の本阿弥何代目かは、まこと都合のよい贈答システム
を残したものである。
というのは現在フィリッピンの学校用の歴史の本に、
「今日のわが国にワイロ、ゾウワイの悪習が、はびこっているのは、アメリカが占領
中に、これが民主主義であると教え、おしつけていったプレゼントの慣行から起きた
ものである」と明記されているけれど、そのワイロを贈るのが民主主義政治のあり方
の根元であるなら、これくらい体裁よく格好のよいワイロはないから結構なことであ
る。
平賀源内と人蔘
よくテレビや映画で、病人がでると町医が診察にきて、これは朝鮮人蔘を服用せね
ば助からぬといわれ、やむなく娘が身売りしたり、病人の夫の浪人者が殺し屋に傭わ
れてゆく‥‥といった設定が時々みうけられる。しかし、あれは嘘である。幕末の御
典医で、明治新政府の軍医総監となった松本良順の、『懐古録』の中にもはっきりと、
「府内(江戸市中)にて町医とし門戸をはる者は富士三哲を初め五指にたらず」とあ
る。
つまり当時人口が何百万もいた江戸でさえも、それ位のものだったから街道すじの
宿場になど、めったに町医がいるわけはない。
もしいるとすれば千葉周作の父のような馬医者が、博労の多い所に住みついていた
くらいのものである。ではいつ頃から町医が増えたかといえば、御一新後のことであ
る。明治六年から七年にかけ扶禄公債を当てがわれ放り出された侍は、士族の商法で
失敗したのが多かったが、中には文字が読めて、『傷寒論』一冊ぐらいをテキストに
開業した俄か医者もあった。まあこれなら威張って頭を下げなくとも出来るというの
で真似する者が激増し、雨後の筍のごとく輩出した。
それに武家屋敷は慎(たし)なみとして弓に用いる矢竹用の薮を必らずもっていた
ので、「筍医者」とか「薮医者」の呼称はそこから出たのだが、維新前は病気だとい
えば、「拝み屋」なる者が御幣を担いで飛んできてお祓いをし、ご加持祈祷とよんで
いた。
現在の常識からすると、それくらいのことではたして間に合ったものか、と首を傾
げたくなるが、そうした修験や行者は、野生の大麻草を乾燥させた粉末を常時携帯し
ていた。
そして病人に部屋を閉めきり、香炉で煙らせ嗅がせていたから、七転八倒して苦し
がっているのでも、今でいうマリファナ幻覚作用でモルヒネを注射したような鎮痛効
果が現れ、すこし暴れてもすぐ落着いたものらしい。
話は脱線するが、道中師とよばれた連中はその粉を煙草に混ぜて、金の有りそうな
のに吸わせ、暴れだしたりすると、
「狐つきだ」といって騒ぎたて、混乱にまぎれて胴巻きを掻払って逃げてしまうが、
後に残されるのは燃えかすの灰だけだから、「護摩の灰」とよぶのだと、二鐘亭半山
の旅日記にもでている。
さて、
話は戻るが、江戸時代にあっては、高麗人蔘とよばれたそれは大変貴重なもので、
江戸では吹上御苑内と小石川の御薬草園で栽培されていたが、町医の手に安易に入る
ような存在ではなかった。なにしろ御三家の水戸でさえ、光圀が特に乞うて将軍家よ
り苗木を分譲して貰ったが、それでも遠慮して、
「お花畑」と栽培地を称していた程である。ここは元治元年の戦で焼払われてしまっ
たが、今でも町名としては残っている。
さて水戸光圀は、その長男松平頼常が高松十二万石をつぐ時に、内密に朱色高麗人
蔘の根株を分け与えて持たせてやった。
もちろん水戸宗家でさえも将軍家へ気兼ねして、お花畑の名称で栽培しているくら
いゆえ、「御林(おはやし)」の名目で高松では植え付けをした。
これが今は栗林公園の名称で残っている。
さて、水戸藩祖頼房の曾孫にあたる奥州守山二万石松平頼貞の三男頼恭(よりたか)
が、元文四年九月に高松第五代の城主とし養子に入ってきた。
「光圀公の御計いで密(ひそか)に分苗して貰った紅人蔘なるものが、栽培されてい
るやにきくが、百聞は一見にしかず是非みたいものである」
二十九歳の頼恭は御林の中へ検分に行ったところ、水利の便がよくないのか気候の
関係のせいか、あまり芳しくなかったらしい。
「紅人蔘というは高麗にても珍しい品種ものといわれ、本邦にては一般には御止め薬
にて将軍家のみ用いられ、その効き目で男女合せて五十名余の子宝さえ、上さまは千
代田城でもうけていなさる。何もそれにあやかりたくて申すのではないが、枯死させ
るような事があっては大変であるぞよ‥‥」
頼恭は厳しく家臣共にいいつけた。この結果、御典医池田玄丈が、「御林掛り」を
兼務するよう命じられた。玄丈は四国では本草学の大家とされていた男だが、将軍家
しか口にできぬような高貴薬の栽培改良には手をやいてしまった。
すると、去度浦の海防用の番船などを蔵っておく倉番の者で、きわめて有能な若者
がいることを耳にした。そこで玄丈が引見すると、一人扶持つまり一日米三合だけの
給与しかない小者にしては、学もあり弁もたつ。
そこで玄丈は、殿に願い出て、「四人扶持、お薬坊主」と破格な四倍の立身をさせ
てから、己れの助手にして御林の高麗人蔘の栽培に当てさせた。これが、「非常の人」
とよばれた平賀源内である。
さて、これは天下の秘薬であって煎じて服用すれば、あの方も将軍さまのように強
くなるが、頭の方もよくなると聞かされて、
「そうか、馬鹿につける薬はない、とよくいうが、馬鹿でないのが呑めばもっと賢う
なるのかも知れん」と源内は、己れが服用したいばっかりに、御林の中の小屋へ詰め
きって、一心不乱に丹精こめ栽育をした。
テレビの「天下御免」ではザラメ砂糖を作りあげ、その褒美で長崎へゆくようにな
っているが、高松で精糖が成功するのはまだこれから一世紀も後の話で、ザラメのご
ときは明治の産物である。
では、何故に長崎へやって貰えたかといえば、高麗人蔘栽培成功のせいである。し
かし、藩主頼恭の思惑は長崎でより良質の人蔘をというのであったろうが、それは無
駄だったようである。その代り、源内は本草学の田村藍水の門に学ぶことができた。
当時は、支那本草学より脱却して、日本独特の本草学を開拓しようと、小野蘭山が、
『本草網目啓蒙』四十八巻及び『本草記聞』十五巻を刊行していた頃である。
高麗人蔘を栽培中密かに自分も服用し、もって頭脳明晰になったと自認する源内は、
「百嘗社」とよぶ山野の草木から鉱石まで研究する、尾張御典医水谷社中の荒井佐十
郎の力をかり、彼なりに高麗紅人蔘の分析や、その実験に出精をしたものらしい。
が封建時代にあっては、将軍家だけのものとされ御三家の水戸や親藩十二万石の高
松でさえ、内密にしていた紅人蔘を、源内ごとき民間人が研究するのは違法だったら
しい。
「門弟の一人と殺傷沙汰を起こした」といわれるが、判然としない理由で投獄され、
安永八年十二月十八日牢内で一服もられ殺されてしまった。杉田玄白はその死を、
「ああ非常の人非常の事を好む行いこれ非常なり、何ぞ非常に死せるや」と悲しみ、
彼の友荒井佐十郎は「人蔘のため延命する者はあるが彼のごとくその為に死すは珍事」
といっている。まあ、この源内の実像にふれたかったら『源内捕物帖』でも読むのが
手取り早いかも知れない。
ひな人形と黒駒の勝蔵
「祇園精舎の鐘の音」と、『平家物語』も始まるから、ともすると平家的なものを感
ずるが、祇園社の実体は反対の源氏的なものである。現在と違って、元禄時代までは
神仏は混合されず敵味方だった。
[八切氏は混同されているが、この場合の『祇園精舎』とは、古代インドのコー
サラ国の都シラーヴァスティーにあった精舎(僧房)のことで、祇園の八坂神
社の事ではない]
「犬神人[いぬじにん]」とよばれた祇園社の昔のガードマンは、社に仇なす寺と戦
うとき、いつも僧兵の群れと弓矢や薙刀をもって血を流していた。
[これも、事はそんなに単純ではなく、今日の京の八坂神社は、その創立からし
て僧円如により貞観十八年(876)に播磨広峰から山城八坂に遷され、はじ
めは興福寺、後には延暦寺別院と、既に『神仏混交』状態だった。また、その
下級神官ともいわれる犬神人も時折『山門』(延暦寺)に使役されて、山門の
ライバルである当時の新興宗教(一向宗、禅宗、法華宗など)の弾圧に狩り出
されていた。したがって八切氏の説くように『祇園社に仇なす寺と戦う』べく、
『僧兵の群れと戦っていた』という状況とは異なるようです]
処が徳川秀忠の娘の和子が後水尾帝の中宮として京上りしたとき、五月五日の白川
の院地打ちという京の石合戦をみて、えびすとよばれる源氏系の民が苛められるのに
立腹したのか、「お白神」とよばれる白山神社系統の木像を京へとりよせた。
これは今のこけしの元祖で白木一対の神体だが、彼女はこれに端布をまとわせて飾
り三月三日には白酒を供えた。やがて徳川家の圧迫で帝が退位され、和子のうみ奉っ
た女帝の明正帝の代になると、この人形まつりも一般に広まった。
しかし中宮に於ては三月三日というのは「曲水の宴」という明国の行事がそのまま
伝わって、公家は御所の中の小川に盃を浮かべ詩歌をつくって楽しむ日だった。
だから明正帝のあとは「夷まつり」として東京奠都まで公家はこれを忌み嫌ってい
た。五人ばやしや官女さまも並んでいるから、御所からのもののように誤られ勝ちだ
が、実際は無関係のものだった。では、どうして今の形式になったかというと、祇園
社の弦めそ達が、昔は、にかわで弓のつるを作っていたが、天下泰平で仕事がなくな
ったので、余ったにかわで獣毛をこけしの頭にはりつける人形細工のアルバイトをし
ている内に、
「京から出荷するんやったら御所スタイルが、ええやないか」
と白丁や三人官女までセットにし出荷してしまったのが、今日のひな人形のもとな
のである。
この祇園びなは、伏見人形の問屋で扱われたので、一般には「伏見びな」と呼ばれ
ていた。
さて、この伏見びなや鳩笛をこしらえていた木偶座(でくざ)というのは、代々御
所の白川卿がその管理というか座銭を取っていたものである。御所では忌み嫌った三
月のひなまつりの人形について、その落し前みたいな鐘だけを公卿さんが召し上げて
いたのは可笑しいが現実はそうだからちゃっかりしている。そして、この白川卿の家
来で、伏見へ人形の金を集金に行っていたのが、黒駒の勝蔵の従兄だったのも面白い。
さて、近頃、デパートで客よせに催す物産展で、「静岡県」というのには、必ずと
いって良い位に壁飾り式になったミニチュアの三度笠が売られていて、それには、
「清水二十八人集」と中央に大書きし、廻りにぐるりと傘文字でそれぞれの名がでて
いる。
円型に囲んで名前をかくという方式は、百姓一揆の訴えの時に誰が首謀者か判らぬ
ようにする為なのだが、これにはお馴染み、「森の石松」が目だつよう中央にきてい
る。
処でこの清水二十八人衆というのが、本当に実在していたかというと、伊勢の丹波
屋伝兵衛の甥の増川の仙右衛門ら数人は本当だが、後はまことに頼りなく幻想でしか
ない。
というのもこれは、次郎長の養子になった事もある天田五郎が、明治十七年四月に
出した『東海道遊侠伝』そして、その二年後に刊行された『明治水滸伝』『清水次郎
長伝』の二冊を種本にし、松廻家太琉というやくざ上がりの講談師が、日本橋茅場町
の寄席へかけたのを、
「どうでえ、そのネタを酒二升で譲らねえか‥‥なんなら三升」と持ちかけたのが三
代目神田伯山。
太琉も初めは惜しがったが、なにしろ呑みすけのこと。つい四升で手をうってしま
い、活字本の他に自分で色々かき止めた大福帖みたいなものまでそっくり伯山に譲渡
してしまった。
さて、この伯山というのは二代目伯山こと神田松鯉の門人で、初めは松山を名のり
明治三十七年に三代目を襲名した男だが、根っからの花札ずき。誰をつかまえてもサ
シでコイコイをして、これが下手の横好きで滅多に勝たない。
だから築地から新富町、人形町とその頃各所にあった席亭の下足番にも、高額では
ないが五銭十銭の借金が軒なみにあった。さて、今でもそうだが芸人の収入というの
は、
「割り」といってあがりの分配である。そこで何処の下足番も、伯山から貸しを取り
戻したい一心から、大声をはりあげて、
「いらっしゃい、えい神田伯山の始まり」
と、よびこんで客を入れる。そこで伯山たるもの義理に感じて、八丁堀の大増とい
う席亭の下足で目っかちの森野石松というのを、まず今日の森の石松といったスター
に仕立ててしまった。そして、
「江戸っ子だってねえ、すしくいねえ」
の一席を作りあげ、ついで、片っ端から借りのある連中の名を、次々と高座へかけて
しまった。そこで実在では五十五歳の吉五郎が、「神戸の長吉」という突ころばしの
二枚目になったり、実名関東だきの綱五郎が、「大瀬の半五郎」という寿司屋の親分
さんの名に変わってしまった。
だから森の石松にしても下足番で、故子母沢寛の研究でも、もちろん実際はいる筈
もないからして、
「漁師上りの乱暴者で豚松」というのがいたから、それがモデルではないかといって
いる。
そうなると問題は、大政小政の両名だが、この原型たるや意外にも黒駒勝蔵の身内
で、
「障子にうつるは大岩、小岩。鬼より恐いと誰がいうた」と今も甲府の盆唄に残って
いる成田村の岩五郎と、中川の岩吉の二人がいたからして、どうも伯山はそれを転用
したのではないかと思われる。
なにしろ、
「黒駒の勝蔵」にしても、伯山の講談では、次郎長一家に仇なすふとい悪玉だが、明
治二年に仙台藩の家老とし、王命抵抗のかどで自害を命じられた玉虫東海著の、
『官武通記』[これは八切氏により日本シェル出版から刊行されていたが、現在は絶
版]という幕末史料によると、
「元治元年甲府郡代加藤餘十郎沙汰書」なるものが採録されていて、それには、
「天誅組の那須信吾と交際のあった勝蔵は、長州の木梨精十郎の援助のもとに、甲府
城占領におしかけ、そのため叛徒として指名手配された」との模様が詳しく出ている。
どうも講談の世界は好い加減なのが多すぎるとはいえ、こうなると勝蔵の従兄も前
述のごとく白川卿随身の古川但馬守ゆえ、彼は単なる博徒ではなく、西国の日下燕石
(くさかえんせき)みたいな勤皇の志士ということになる。しかし、とはいえ伯山の
作った次郎長伝では極悪非道の無頼漢にされてしまった儘だ。
水戸天狗党は全学連
「人を斬るのが侍ならば、恋の未練がなぜ斬れぬ」と桜田門外で井伊大老を襲撃した
水戸の武士(後輩)たちが、元治元年(1864)筑波山に旗上げした水戸天狗党と
いうのは、藤田東湖の遺児小四郎を盟主にして集まった健児も二千とされる。
やがて彼らは江戸から差し向けられた公儀歩兵隊やフランス軍将校の指揮する砲兵
隊を向こうに廻して、那珂湊から大洗、そして今の日立市である当時の助川で田中源
蔵の隊はあくまでも抗戦。
やがて武田耕雲斉に率いられた本隊の方は、雪の加賀路へ落ちてゆき、そこで降参
すると、公儀討伐総督田沼意尊の苛酷な扱いで、畳十枚位の牢舎に三十人ずつが詰め
込まれ、横になれるどころかろくに坐りもできず、立ったままで排泄物もたれ流し、
さながらベトナムの虎の檻のような目にあわされた末、やがて一人ずつ引張り出され
て首を斬られた。
しかし武田や藤田に従って加賀へ行き、そこで殺された方は、
「勤皇尽忠の士」として明治になってから贈位、靖国神社へ合祀もさせられたが、田
中源蔵に率いられて助川を落ち八溝山へ向かった方は、全員贈位の沙汰もなく、十二、
三歳の少年が多かったから、坐らせて首を斬り落すのは厄介と、樹に吊して撲殺され
てしまっている。中には水戸支藩松平大炊頭の一子で十二歳の少年も混ざっていたと
いうのに、彼らはみなザンギリ髪に統一していたゆえ、それで見境なしに皆殺しの目
にあったのだろう。
しかし、彼ら少年までが決起したのが、勤皇精神によるものとするならば、なぜ今
日までそれは放りっぱなしになっているのだろう。といった疑惑もここに浮かんでく
る。
という事は、天狗党それ自体のあり方が、明治に入って水戸の生き残りの激党の連
中によって美化されてしまったのが、何かしら実際とは違っているのではないかとい
った感じすらする。
それに藤田小四郎や武田耕雲斉に率いられた方は有名なのに、田中源蔵が伴ってい
った部隊があまり知られていないのは、その幹部が他国者だったせいだろう。また彼
らの一人が残した辞世の句に、
「国のため想う心の晴れやかさ、死なむ今とて勇みたちいぬ」
というのがある。文字通りの感慨の歌だが、幕末の時代と現在とのくい違いは、こ
の、
「国」という言葉の概念であるらしい。「葉隠」の中でも、これはしきりと出てきて、
「国の歴史」とか「国のため」といった字句が多く、歴史家はなんの躊躇もなしに現
在的な解釈をして、「日本国の歴史」「日本国のため」いとも手軽にきめて掛って、
「葉隠れ武士道」とか「葉隠れ精神」といったものをもって、皇国史観にしてしまう
のだが、いったいそれでよいものだろうか。
なにしろ、葉隠の中にでてくる国というのは、佐賀一国のことであり、国史とは鍋
島家の藩史だけをさすものだからである。
わが国に、中央集権制の国家が出来たのは明治からであり、それまでは鍋島家中の
者に取っては佐賀が御国であり、水戸人にとっては常陸だけが国だったのである。だ
から、
「国のため想う心の」といっても、今日的な考え方での愛国心ではなく、当時として
は故郷を懐かしむ愛郷心。まあ、
「望郷の歌」といったくらいのところだったのであろう。なのに、それを愛国の至情
といったようにするから、ややこしくなるのであって、こうした歴史家のすりかえは
「君がため春の野にでて若菜つむ」といった古歌すらも、
「恐れ多くも一天万葉の御方のために」といった解釈さえ、かつてはされたもので、
今はリバイバルでまた復活されている「君恋し」の唄も、それが初めて流行した頃に
は、
「君恋し宵闇せまれば悩みははてなし、とは、かつて後醍醐帝の行在所へ忍び、孤忠
をいかに示さんかと、桜の樹に十字の詩、天勾銭(こうせん)をむなしゅうするなか
れの、児島高徳のことを唄ったものかと思っていたが、どうもそうではないらしいこ
とから児童が口にするのは止めるようにしたい‥‥」
といった朝会の訓辞を校長にされた日のことを思いだしても、どうも日本語には意
味が曖昧模糊としているのが多いようで困る。
だからでもあろうか、水戸天狗党の決起たるや明治に世が変る僅か四年前の、元治
元年の出来事なので、また一世紀ほどしかたっていないのに、すっかり評価も色々と
変っているようである。
というのは、旧幕時代は徳川体制からみれば、賊視されようとも、もはや明治にな
ればその価値観は一変されていようと想うのが、案外にそうでないことである。
水戸家菩提寺の納所日誌にも、
「乱賊」という文字で、天狗党は扱われているし、明治十年迄の茨城県下の公文書は、
これことごとく、「賊」の一語で片づけられてあって、徳川時代その儘の感がある。
だからして、彼らの郷里でさえ、そうした具合なら他はおして知るべしという事に
もなろう。
そして、そうした見方をするのは地方の無智な小役人共が、世が明治に変ったをの
弁ぜずに、旧幕時代の用語をその儘で踏襲しているのかと思うと、そうでもなく東京
に移った明治新政府も、
「水戸天狗党=賊軍」といった扱いを続けているのである。
明治十八年になって内閣官制ができ、伊藤博文が最初の内閣総理大臣となったが、
その閣僚もやはりそうした見方であったのである。
その裏付けとしては、
「元治元年十月二十五日、流賊あり、まさに本邑(ゆう)を掠めんとする。君(黒崎
友山)ここに郷人(ごうじん)を率いてこれを防ぐ。かたずして歿す。時に四十三歳
にて奸賊のため致命せるなり。
題額 大蔵大臣 公爵松方正義
撰文 帝国大学教授 博士内藤耻叟」
といった石碑が堂々と茨城県常陸太子(たご)町には、今もその儘で残っているの
をみても判り得る。
これは明治十八年に建てられたものだが、その六年後の明治二十四年に、藤田小四
郎らに従四位が贈られ、国家が改めて、
「勤皇の志士」と認めるまでは、日本全国において、水戸天狗党なるものは単に、
「賊徒」でしかなかったのである。つまりここに、
「維新史」のややこしさがあるのである。幕末になって各地から勤皇の志士が輩出し、
彼らがみな、「王政復古」を叫んで天朝さまの御為に尽したので、それまでの徳川体
制がくずれ、十五代将軍慶喜も慎んで大政奉還。めでたく明治の聖代になったという
プロセスに、突っこんで調べるとどうしても無理がでてくるからである。
これは余談になるが、私がかつて書いた『てんぱい騒動』のように、明治になって
も、薩人は薩摩が自分らの国、長州人にとっては長州だけが国だったからして、
「愛宕通旭(あたごみちあきら)卿」のように、
「まだ御年弱の帝を薩長の輩や岩倉具視らが、勝手気儘に動かし奉るは不敬不忠‥‥
天朝さま藩屏ともいうべき公家の者は、この際万難を排して、一死をもっても尊王の
大儀に殉じ、日本を一つの国にせばならぬ」
と、他の公卿にもふれ廻って、十津川郷士などを糾合し、
「赤誠勤皇隊」を作り、天朝さまをもって、新しい国の礎にしようと計った行為は、
(薩摩だけをまだ自分の国)と思いこんでいた大久保利通らの眼からすれば、
「過激思想である」と、明治四年の時点においては危険分子扱いだった。そこで通旭
は妻と共に、踏みこんできた薩人らに惨殺されてしまっている。
今考えれば、旧幕時代ならいざ知らず、明治四年にもなって、
「勤皇が叛逆罪」というのは解(げ)しがたいが、それが事実では仕方がない。
水戸天狗党にしろ、筑波山から栃木太平山に移って、そこに本営を置いていた時に
は堂々と、「水戸幕府」の大看板を掲げていたのである。これは、三光神社と名の改
まったそこの社務所に、明治中期までは残されていた。
つまり天朝さまの為に水戸人は決起したものではない、というと語弊があるかも知
れないが、彼らは、天朝さまの下の征夷大将軍に自分らの殿をたて、水戸の城下を江
戸にしたかっただけである。
これは、自分らの殿が将軍になれば、直参(じき)の身分になれたせいともみられ
る。現在の会社などでも、本社勤めと地方支社の者とでは、格段の差がつくが、昔は、
「直参(じき)と陪臣(また)」の違いは大変なもので、同じ武士でも月とすっぽん
ぐらいかけ離れていて、直参の仲間足軽は大名の家来より偉いとさえ、されていたせ
いだろう。
田中源蔵の隊三百の青少年は、それではなんの為に戦ったかというと、これは二年
半前に私が『元治元年の全学連』をかくため、調査をしに行ったとき、下妻のもとの
信福院で見せられた古い旗に、「全館連合」とあったので、それが、この謎をものが
たっている。
館といえば、映画館を今では考えるが、水戸の学校は、みな館をその下へつけてい
た。今となっては、水戸城三の丸にあった「弘道館」ぐらいしか知られていないが、
元治元年の頃には、私学二十三校といわれた程の数があった。これは前代の斉昭によ
って、「学芸新興」のため各地に郷校を設けられ、そこで士分以外でも有志の青少年
に進学の途をひらく目的で作られ、お手許金をもって教授方の手当も払い、月謝は殆
なきにひとしかった。
処が斉昭が死んで御代替りになると、私学補助金が打ち切られ、自費で賄ってゆけ
ない郷校はみな廃止のやむなきに到った。
そこで在学中の者が騒ぎ、行方(なめかた)郡小川館に籍のあった藤田小四郎が天
狗党の盟主におされるや、「われらも共に」と、小川館からは、学長にあたる元取の
竹内百太郎、それに岩谷敬一郎ら二十五人。
「行動を一緒に致そう」と南石川館から高橋友泰が十八人を率いて合流。ついで平磯
館、大宮館、久保館と各地の郷校から、お取潰しになりそうな学校の教授方が、教え
子を伴って参加してきた。
田中源蔵は若かったが野口の時雍(じよう)館の元取りをしていたので、その教え
子の十二、三の少年までが、ぶかぶかの竹胴をつけ背たけ程もある刀を杖について、
その周囲に集まってきた。彼が藤田小四郎や武田耕雲斉と離れ、別行動をとったのは、
「とても足弱な少年ばかりを伴って、雪の加賀へ入ってはゆけまい。無理であろう」
と考え、春になるまで冬篭りするつもりで、
「八溝山の頂上の、行者のおこもりする番小屋が広いから、そこへひとまず避難しよ
う」となったのだろう。
しかし武運つたなく、有り金をはたいて預けた八溝神社の祢宜(ねぎ)が、それで
食物を調えて頂上へ届けてくれるはずだったのに着服して逐電。
「口にする物がなくてはなんともならぬ。もはやこうなっては八溝山も今宵かぎり、
みんな気をつけ散り散りに落ちてゆけ」
とやむなく三日目に解散した処、麓で網をはっていた百姓や役人に捕えられ、みな
殺しにされた。
しかし、彼らの主張たるや、今でいう、
「私学振興、補助金要求」
「学内人事の干渉反対」といったものだったからして、明治二十四年になって辛うじ
て、武田耕雲斉や藤田小四郎は、追贈位をかたじけなくしても、田中源蔵の率いてい
た青少年三百の方は放りっぱなしにされ、今日に及んでいるのであろう。
とはいえ、よく考えれば武田や藤田の方にしても水戸城を攻撃しかけた時には、有
栖川宮家より御降嫁の夫人の掲げた菊の御紋章へ、彼らは銃撃を加えこれと戦ってい
る。
それに、もともとが水戸家の中の激党と鎮党のゲバであるから、なにも藤田東湖が
有名でその遺児だからと、小四郎らの方だけが叙勲され、町医者の伜上りが大将分だ
からと、田中隊は見棄てられた儘というのは、どうも片手落ちというか不合理にすぎ
る。
http://www.rekishi.info/library/yagiri/scrn2.cgi?n=1088
真相・鳥羽伏見戦争
「御用盗」の名で江戸八百八町を公然と荒し廻っている強盗団の巣窟が三田の薩摩屋
敷、と証拠をつかんだ江戸市中取締りの庄内藩は、慶応三年十二月二十三日夜、己が
屯所へまで鉄砲を打ちこまれたのには立腹した。そこで、
「下手人をすぐさまお引渡し願いたい」と交渉したが、三田の薩摩屋敷より、
「そげえなことは知り申っさん」とすげなく拒絶されてしまい、そこで、
「えい、もはや、これまで」堪忍袋の緒をきらし、翌二十四日夜。すぐさま支藩の兵
まで動員して、
「やってしまえ」と三田の薩摩屋敷を包囲するなり直ちに、これに火をかけて攻めた。
この知らせは、年の瀬も迫った二十九日夜。当時大坂城にいた徳川慶喜の許へも届
けられ、これに対し、同行していた老中永井尚志は、
「かくなる上は、すべてが薩摩の陰謀と判然しましたゆえ」と申しでて慶喜の許可を
貰い、総督に大河内正質をたて、すぐさま淀に本陣をもうけた。
そして「討薩の表」を掲げもった滝川播磨守の本隊は鳥羽街道を進み、竹中丹後守
の隊は伏見口から、一気に京へ入ろうとした。
しかし、そこには、薩長土三藩の兵がいたから、まず鳥羽口を守っていた薩州の中
村半次郎、野津七左衛門(のち鎮雄)が、滝川の部隊に放火を浴びせかけた。一月三
日の午後五時頃だというが、僅か二千たらずの軍勢に何故、このとき、精鋭であるべ
き幕軍二万近くがころ負けをしてしまったのか。
「錦旗が出てきたから、それで幕軍は退却したのだ」
というけれど単純すぎる。はたしてそんなことが有ったものなのか。
なにしろ錦旗の贋物を岩倉具視が呉服屋に調製させたのは、それより後だというの
だから、これではてんで話の辻つまが合わないことになる。
だからでもあろう。伏見奉行所にたてこもって戦い、逃げて船で江戸表へ戻った新
選組の土方歳三などに、
「もう、これからの戦争は鉄砲だ。いくら刀なんか振り廻したって歯が立たなかった」
などと語らせて、この経緯を説明しようとする小説もある。
しかし新選組には余り銃がそろっていなかったかも知れぬが、滝川播磨守や竹中丹
後守が率いて進撃したのは、なにも刀槍を振り廻した連中ではない。四年前の元治元
年に那珂湊で水戸天狗党をば散々に打ち破った光栄ある仏人軍事顧問が、調練して育
てあげた公儀歩兵隊なのである。
その歩兵隊が鉄砲をもっていない筈はないから、彼らはポンピドー銃を担ぎナポレ
オン砲を引張った砲兵隊と共に進軍したのである。
二万の内、新選組のようなのを除外しても、大半が歩兵隊だったのなら、まさか二
挺拳銃みたいな二挺鉄砲ということはなかろうから、二千たらずの向こうより幕軍の
方が遥かにその鉄砲の数も多いわけである。
だから、土方歳三にそんなことをいわせたように書いたとしても、こじつけでしか
ない事になる。
では個人的に薩摩っぽや長州人が滅法強すぎて、関東者はだらしなく鉄砲を放り出
して、みんな逃げてしまったのかともなる。
が、そんなに易々と幕軍とても退却はしていない。
徳川家伝習隊、会津藩兵も翌四日未明にかけ、一歩も退かずに、
「敵は僅少ぞ。頑張れや」と、土方歳三の率いる新選組と共に、伏見奉行所から反撃、
近藤勇の養子周平の他に新幕の隊士二十名近くを失いつつも、なお奮戦敢闘している。
しかし明るくなっては防ぎきれず、会津兵は淀まで下って散兵線をしいたが、新選
組はそれでも退却せず千本松に陣をしき、沼地を要害にして、ここで薩長軍をくいと
めた。
このため、新選組結成以来の仲間だった井上源三郎を初め、探偵諜報役だった山崎
烝以下二十余名を、改めてここで失ったのである。
そこで、息のある者もいたが、とても収容などできず、土方歳三は歩ける者だけ纏
めて辛うじて引きあげる羽目になった。
やがてこのため、富森、橋本、八幡まで進んできていた幕兵までが、まき添えのか
たちで敗走。雪崩をうって大坂城へと逃げこんだ。
元日は牡丹雪がふったが、二日、三日、そしてこの四日も、ひどい西北の烈風が吹
きまくっていた。だから風に叩きつけられて、京へ向かう行軍は阻まれたが、大坂へ
逃げ戻るとなると追風をうけるようなものだから、生き残った幕兵は夕方までにみな
立ち帰った。
「緒戦は不運にもしくじり申したが、この大坂城内には、まだ新しき兵が万余‥‥戻
ってきて編成し直した者を加えれば、二万いや三万にもなりましょう‥‥おんみずか
ら御出馬下されば、将兵は勇気百倍致しまして、関東武士の意気をあげましょう」
しきりと周囲の者は慶喜に出陣を求めた。
兵力が十倍近く多いのだから、誰がみても慶喜さえ陣頭に馬を進めれば、これは絶
対に勝利間違いなしの筈だからである。
処が慶喜は、
「この城がたとえ焼土となるとも、死をもって守るが徳川武士の本分というもの。も
し吾らが此処で討死したとしても、関東忠義の士がきっと遺志を継ぐであろう」
などと、今でいえばおおいにアジっておいて、そっと大坂城の後門(うしろもん)
から脱出。
「もしもし、どちらさまでござるか」
警護の兵たちが、ばらばらと駆け出してきて誰何(すいか)したが、
「これは、これは、てまえは上様のお小姓でござる」
山岡頭巾をかぶった慶喜は腰を屈めまでした。
さて、衛兵たちは、雲の上の慶喜の顔や姿など拝んだこともない。
それに、まさか前十五代将軍さまが、衛兵の御徒士あたりへ、形ばかりにせよ、頭
を下げる、とは思いもよらぬことだから、
「それは、それは‥‥」と通してしまった。
慶喜はそこですぐさま、天保山沖に碇泊させてあった軍艦開陽丸へのりこみ、八日
の夜に出帆し江戸へと帰ってしまった。
歴史家は、この間の事情を、
「慶喜は西軍が錦旗をあげれば官軍になるから、それと戦うと抗命朝敵となる。そこ
で恭順の意を表するため、騒ぐ家来達を放って戻ったのである」と説明する。
しかし、慶喜は三日の朝には、「討薩の表」を認め、進軍を命じているのである。
そしてこの慶喜は、御三家の名古屋城主徳川慶勝をして、
「なみの人にあらず、機をみるに敏、その頭脳の切れること、これは到底、世の凡俗
の及ぶところにあらず」
とまでいわせているが、その頭の廻転の早さには定評があった。
それ程までに頭のいい男が、三日の朝には、
「よし、薩摩を討て、京へ上れ」と命じておきながら、
「鳥羽伏見で僅か二千の敵に、向かい風に邪魔され二万近くの幕軍精鋭が敗走してき
た」と聞かされただけで、翌日の夕方には、
「恭順せねばならぬ」と途端に気が変ってしまい、己れの家臣を瞞(だま)してまで
逃げ出してしまえるものだろうか。女には、お天気屋というのがあって、くるくるっ
と気が変るそうだが、慶喜は男、しかも人一倍賢しい男なのである。
従来ここを解明できるものがいなかった。だからみな慶喜をかいても的を逸してい
るが、真相は、やはり彼の機をみるに敏な賢明さにあった。
問題は硝石である。徳川家では島原騒動以来、それを政治的配慮で切支丹一揆とい
いふらす事によって、「鎖国」政策をとった。
もちろんキリスト教ごときをそれ程までに、小児病的嫌悪をもって徳川家が恐れた
のではない。
便所の下を掘って天日に三日も乾してもやっと匙半分もとれるかどうか判らぬ硝石
たるや、1970年代の今日でも日本国中、何処にもその鉱山はない。だから慶喜は
その硝石の存在を恐れたのである。
なにしろ土民にすぎぬ連中でさえ、島原半島の口の津の硝石庫を押さえれば、徳川
家の歴戦の勇士が力攻めしても討伐に二年掛ったのである。そこで仰天し、
「これは大変である。硝石を大名共が勝手に入手し謀叛をなしたら、天下の一大事で
ある」と、ここに長崎に出島を築き、硝石の輸入は大公儀のみにと限定してきた。
「鎖国」の本当の理由たるや、つまりは実にこれである。
青い目の宣教師を迫害したのは、彼らがマカオやマニラからの、硝石のエージェン
トを兼ねていたからであり、キリシタン信者を殺させたのも、その手引きで硝石の密
輸があったせいで、九州の半島や島嶼(とうしょ)で虐殺が多かったのも、そのわけ
なのである。
江戸時代に「抜け荷」と称し密貿易取締りが厳しかったのも、なにも珊瑚やたいま
いが密輸入され女が着飾ったからといって、それくらいで公儀が大騒ぎする筈はない。
気づかわれたのは、日本にはなくすべて輸入に依存している硝石の密貿易だったの
である。そしてこの統制が幕末まで励行されていたので、このため、
「徳川三百年の泰平」は続けて来られたのである。
しかし馬関戦争の後、長州は井上聞多らを上海へ、薩州は鹿児島戦争のあと五代才
助らを海外へ出していた。硝石の買入れにである。
「徳川家は鎖国をして硝石の輸入を独占してきたはよいが、長年積みこんでおいた物
ゆえ、湿気をおび使い物にならなかったようだ。それに比して、薩長使用のものは上
海から輸入したての最新硝石と判明、とても‥‥これでは勝負にならぬ」と咄嗟に慶
喜は気がついたのである。
だから昔ながらの石頭の老中共が、
「わが方は薩長の十倍の兵がありまする。戦というは昔から、兵の多い方が勝つに決
まっております」
と口を酸っぱくして諌めても、
「鎖国までして、これまで押さえてきた硝石を、こう薩長土が自由にしだしたようで
は、もはや徳川の世もこれまでであろう」
と慶喜はあっさり見きりをつけ、さっさと江戸へ戻り、江戸城もやがてあけ渡し、
上野寛永寺へ、そして水戸へと引っこんだのである。
つまり慶喜が恭順の意を示さねばならなかったのは、
「硝石だった」ことが、これまで知られていないから、おおかたの歴史の知識を狂わ
せてしまっているようだ。もちろんその責任は、
「鉄砲の弾丸の原料が日本ではとれないことを国民に知らせては反戦的になる恐れが
あろう」と気づかって明治軍部へ忠義を尽すために、すべてを隠してきた歴史家や、
その忠実な後継者にある。
あとがき
私の歴史評論の代表作といえば、「日本原住民史」「新平家意外史」と前に出した
中央公論社版の「切腹論考」、それに八切裏がえ史改題の「日本裏がえ史」などであ
ろう。しかしヒミコや高松塚古墳から幕末までを一貫したものは、何といっても本書
が初めてである。
もともとこれは読者からの質疑応答用に書いたものを改めて統一し、初めから書下
しをしたものゆえ、この98パーセントまでは、誰にもまだ初見のものであろうだろ
う。
そして、これが他と相違している点は、「天の朝‥‥崇神騎馬王朝‥‥仁徳百済王
朝‥‥継体藤原王朝」の流れの中に、沖縄に戻り止った久米兵団の大陸的な王朝が挿
入されるではないかとする疑義。ついで島原一揆が俗にいう切支丹ではなかったこと
への解明。いろいろと新事実がこれにはもりこまれている。
最近ゼミナーや卒論に「八切日本史」を取り上げる若い人が多くなったので、これ
はそれに便利なように年代別に整えもしたが、まあそう肩をこらせずに、「真実の日
本歴史とは、そもそも‥‥いったい何だったのだろう?」と気やすく寝ころがっても
読めるようにといった配慮も加えたので、固いところより面白い個所の方が多いかも
知れない。しかし読んで可笑しかったり噴き出すような部分があっても、それが本書
の永遠の価値をそこなうものではないことを私は信じている。
----1972・5----躁と鬱の間にて‥‥八切止夫
[了]
|
|
|
|
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
|
|
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。