12. 2011年12月02日 11:00:01: gzi8V79XJU
>>11
>問題は福祉が厚いので、仕事に意欲的でなくなる、経済発展が遅れるということ。お言葉ですが、それは違うと思います。 北欧諸国は、経済成長と高福祉を両立させています。 「失われた20年」という長期経済停滞に苦しむ日本とは違う。 ■サヨクが発狂しちゃいそうな北欧の政策
サプライサイドにおいてはサヨクが大嫌いな「市場原理主義」的な政策が採られていることも知られていないようだ。
http://ameblo.jp/englandyy/entry-10703626875.html 北欧についてもっと深く知ろう
北欧は福祉が充実していてすばらしい国だ。
アメリカやイギリスのような「新自由主義」のような国とはまったく違う。
というような幻想を抱いている人は多い。
左派が福祉の充実の面だけを宣伝しているからだろう。
以前も書いた(サヨクが発狂しちゃいそうな北欧の政策)が、
その政策は多くの人が思っている以上にサプライサイドにおいては市場機能を重視したものになっている。
(サヨクが言うところの市場原理主義であり、新自由主義的なものだ)
各国の貿易・ビジネス・財政政策・金融政策・労働市場・投資に対する自由度ランキング
というものが発表されているので、今日はこれを見てみよう。
リンクを開いてもらえばわかるが、
日本は20位。
北欧のデンマークは8位、フィンランドは17位、スウェーデンは22位だ。
北欧のデンマーク・フィンランドは日本よりも上位。
スウェーデンも10項目のうち6項目で日本よりも自由度が高い。
財政の自由度と政府支出のGDPに占める割合が多い点が日本よりも大きく劣っており、
そのことが評価を下げているといえそうだ。
オーストラリア・カナダがそれぞれ3位、6位なのも興味深い。
資源があるから経済的にうまくいっているというような単純な説明も多いが、
しっかりと自由経済を取り入れていることが両国の経済の好調の要因といえるだろう。
北欧の福祉の充実面だけでなく、しっかりとサプライサイドに市場機能を取り入れてやっている
ということをもっと多くの人が知るべきだろうし、サヨクは隠すべきではないだろう。
http://news.livedoor.com/article/detail/5948590/
つまり、北欧は、市場原理主義+高福祉なのだ。
競争の敗者が自殺したり、ホームレスになったりしないよう手厚い社会保障があるのだ。
そこが日本と違うところ。 ■宮台真司氏
元々の新自由主義と、いわゆるネオリベとは区別しなければいけません。
ネオリベ=市場原理主義は、「小さな政府」&「小さな社会」の枠組みです。
新自由主義の「小さな政府」&「大きな社会」の枠組みとは全く違います。
でも、そうした初歩的な混同は日本に限ったことではありません。
ちなみにぼく(宮台)は、元々の意味での新自由主義者です。
「大きな社会」、すなわち、経済的につまづいたりちょっと法を犯した程度では路頭に迷わずに済む
「社会的包摂」を伴った社会を、グローバル化の流れの中で、どうやってつくり、維持するのか。
むろん道徳的伝統主義のような、かえって「社会的排除」を導く枠組を、頼るわけにはいきません。
だから、家族の包摂性、地域の包摂性、宗教の包摂性といっても、
かなり強い「社会的排除」を伴う旧来の家族や地域の宗教の、復活や維持を構想するわけにはいきません。
単なるノスタルジー(復古主義)では役立たないということです。
そこで、機能主義的な発想が要求されることになります。
http://blog.goo.ne.jp/mildwoods/e/4613e8b57dd63f84a6e608d5192c921d
北欧は、新自由主義型の高福祉社会といえるかもしれない。
竹中平蔵あたりとは大違い。 ■[経済] 小宮隆太郎の60年代後半スウェーデン経済論
http://d.hatena.ne.jp/tanakahidetomi/20070127#p2
■[経済] アメリカとは違う経済モデルは可能か?
著名な経済学者オリビィエ・ブランシャールがヨーロッパ型経済モデルについて簡潔な論説を書いていました。
ヨーロッパ型の経済モデルの特徴は、経済的効率性と寛容な社会保険制度を完備していることです。
いまある経済モデル(一番近いのはオランダ経済)の特徴を取り入れながらも、
ブランシャールの理想形態といえるものになっています。
その全体構想は、1)競争的な財市場、2)労働市場における保険制度、3)積極的なマクロ経済政策、から成立しています。
これらの特徴は今日の日本経済のあり方を考える上でも示唆に富むと僕は思います。…
ユーロという「足かせ」を否定しないかぎり、ここでのブランシャールが実現可能だと提起しているヨーロッパ型モデルの要は、
この第三の柱である積極的な財政政策とまた労使間の所得政策ということになるか、と思います。
もちろん日本では、共通通貨制度を採用していないですから、この足かせはフリーのはずですが
(実際には円の足かせがいまも効いています)、財政ならぬ積極的金融政策がキーになるのでしょう。
http://d.hatena.ne.jp/tanakahidetomi/20070801#p1 ■日本がスウェーデン経済モデルから本当に役立てる二,三のこと
ジェフリー・サックスの論文Revisiting the Nordic Model:. Evidence on Recent Macroeconomic Performanceより、
スウェーデン経済モデルから日本経済への含意。
1 小さな政府イデオロギー(社会福祉関係支出などの政府規模が大きいと経済をダメにしやすい)は、
必ずしも正しくはない(むしろサックス論文の範囲では、積極的な意味でこのイデオロギーは否定される)
2 ハイエク・フリードマン命題(福祉国家は隷従への道)は、北欧諸国の民主化レベルをみると完全に否定される。
3 エスニックな同質性が高ければ高いほど社会福祉は充実する傾向にある
(ひょっとしたら移民増加政策や出生率を増加させるための移民政策は社会福祉の維持よりもその縮小にこそ貢献してしまうかもしれない) 1,2は数値を以下一部列挙したけれども、よほど頑迷なイデオロギーをもたないかぎり、
小さな政府の方がいい、北欧諸国モデルはダメ、とはいいきれないと思う。…
▼社会福祉関連の支出水準
政府受取(税収+そのほか)・GDP比率は、北欧諸国は56%、EC諸国は47%、イギリスなどは38%。日本や米国は30%台前半。
政府支出・GDP比率は、北欧諸国は52%、EC諸国は49%、イギリスなどは38%、米国は30%台前半。
社会福祉関連の対GDP比率は、北欧諸国は20%後半、EC諸国は20%真ん中、イギリスなど10%後半。
北欧諸国は高税収+高社会福祉支出。イギリスなどは低税収+低社会福祉支出の国。
税収と社会福祉支出、それに政府支出の特質は相互に正の相関をもっていることが指摘されている。
▼社会福祉支出の特徴
公共部門の社会福祉支出は1)現金移転(年金など)2)、直接的な政府サービスの供給(育児、障害者へのサービスなど)、
3)積極的な労働市場政策(職業訓練、職業計画に沿った政府雇用)に区分されている。
北欧諸国はこの三点ともに高水準(対GDP比)。北欧諸国は過去20年間政府雇用を積極的に行ってきた。
米国との各項目の数字は、(北欧:米国 14.2:7.9、11.4:6.7、1.2:0.2)である。
米国は公的・私的社会福祉支出を合算しても北欧の水準よりも低い、ことが注目できる。
▼社会福祉関連支出と貧困
北欧の社会福祉制度は貧困を減少するのに貢献している。
貧困率、下位20%の人口が占める可処分所得の割合、ジニ係数を比較してみると、
北欧諸国とアメリカを対比すると、(5.6:17.1、9.7:6.2、24.7:35.7)である。
▼北欧諸国の福祉政策がもたらす労働市場の帰結
高い福祉政策はハイエクのいったように労働者のやる気を失わせるなど雇用に悪影響をもたらすか?
北欧諸国は高い就業率を維持している。これは過去10年あまりの積極的労働市場政策の成果、
さらに政府の公的雇用(高齢者、未熟練労働者、障害者らの雇用)の促進の成果、である。
これらは地方での社会福祉関連のサービスを行う人員として雇用されている。
http://d.hatena.ne.jp/tanakahidetomi/20070803#p1 ジェフリー・サックスの論説
グローバル化で政府の役割は教育、公平な税制などで必要性増す。
北欧モデルを勉強すべき。
僕のブログでもサックスの北欧モデルを前紹介した 日本だとなぜか北欧モデルは高福祉だけがクローズアップだが、
同時に昔から日本とは比較ならないほどの競争重視社会。
http://twitter.com/#!/hidetomitanaka/status/119888913291681792 月並みだが、結論は、ヨーロッパ型経済モデルとアメリカ型経済モデルのよいところを取り入れるべきということ。
しかし、その実現を阻んでいるのが、官僚、無能な政治家、大マスコミ、
そして特定の利益団体(経団連、連合、天下り法人、宗教団体、そして業界団体)ということか。 市場原理+高福祉(再分配強化)こそが正解か。 ■米、スウェーデン折衷型社会を=日本の将来で提言−内閣府の研究機構
日本は世代間や男女間の公平・平等によってリスクを分かち合う社会民主主義的なスウェーデン型と、
自己破産しても再出発しやすい仕組みのある自由主義的な米国型を折衷した社会を目指すべきだ−。
内閣府所管の財団法人、総合研究開発機構は10日、こうした提言を盛り込んだ報告書を発表した。
報告書によると、日本の現状は家族や企業を中心にした扶助を重視する点でフランス型、
生活保護などによる再分配機能が弱い点で米国型に近い。
しかし、仏に比べ現役・子ども世代への公的支出が著しく少ない一方、
米国より破産時に保有できる資産への制限が厳しいため、
「一部の人に過重なリスク負担を強いる」社会になっている。
今後の方向としては、家族手当や職業訓練、保育サービスなど現役世代への所得再分配を手厚く実施し、
女性労働力を活用しながら世代間の公平を実現しているスウェーデン型を目指すよう求めた。
また、グローバル化の中で規制緩和を進めた上で、
老後を支える多様な金融商品の開発や破産制度の改善などを通じて、
「リスクの社会化」を図るよう提言した。(2010/03/10-19:19)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_date1&k=2010031000864
http://jp.wsj.com/layout/set/print/Japan/Economy/node_40535 ■総合研 リスク分散の政策体系提言 米・スウェーデン折衷型を
内閣府所管の財団法人「総合研究開発機構(NIRA)」はこのほど、
日本の政策体系がどうあるべきかを提言した報告書「『市場か、福祉か』を問い直す」をまとめた。
同機構はこの中で、税制による分配を重視する社会民主主義的な「スウェーデン型」と、
市場のメカニズムによる分配を重視する自由主義的な「米国型」を折衷した社会を目指し、
リスクを分散するべきだとの提言を行っている。
報告書では、日本経済の長期停滞により、
(1)生活水準の低下(2)生活・雇用・老後などに対する不安、リスクの増大(3)所得格差の拡大−の
3点が家計に悪影響を及ぼしたと指摘した。
日本社会の現状については、家族や企業を中心にした扶助を重視する点で「フランス型」に、
生活保護などによる再分配機能が弱い点で「米国型」に近いと分析。
だが、フランスに比べ現役・子供世代への公的支出が著しく少なく、
米国のような寛容な破産制度もないため、「一部の人に過重なリスク負担を強いる」構造になっている。
解決策としては、日本はフランス型ではなく、家族手当や職業訓練、保育サービスなど現役世代への所得再分配を手厚く実施し、
世代間の公平を実現したスウェーデン型を目指すことを提言。
また、規制緩和や多様な金融商品の開発、破産制度の改善などを通じて、「リスクの社会化」を図ることも求めた。
http://www.sankeibiz.jp/macro/news/100326/mca1003260507008-n1.htm |
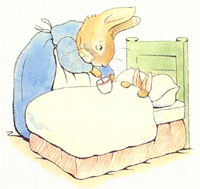
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。