http://www.asyura2.com/12/cult9/msg/226.html
| Tweet | پ@ |
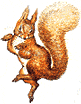
چ،‰ٌ‚ح“ْ•ؤگي‘ˆ‚جگ–گ¨‚ًˆê‹“‚ة‹t“]‚³‚¹‚½ƒ~ƒbƒhƒE´پ\ٹCگي‚ًŒںڈط‚·‚éپB
‚±‚ê‚ة‚و‚ء‚ؤ‘O‰ٌŒںڈط‚µ‚½‹Uڈطژز‚½‚؟‚جژہ‘ش‚ً‚³‚ç‚ة‹†–¾‚·‚éپB
ƒ~ƒbƒhƒE´پ[ٹCگي‚ة‚ـ‚آ‚ي‚éƒچƒpƒKƒ“ƒ_‚حپAگ^ژىکpٹïڈPچUŒ‚‚ظ‚ا‰ً–¾‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢پB–گS‚µ‚ؤ‚¢‚½“ْ–{ٹCŒRکAچ‡ٹح‘à‚ھپAچىگي’iٹK‚©‚ç“G‚ً•ژ‚èپAڈî•ٌگي‚ًŒyژ‹‚µپAŒ‹‰تƒAƒپƒٹƒJ‘¾•½—mٹح‘à‚ة‚و‚ء‚ؤٹ®•†‚ب‚«‚ـ‚إ‚ة’@‚«’ׂ³‚ꂽپA‚ئ‚¢‚¤Œأ‚¢ƒvƒچƒpƒKƒ“ƒ_‚©‚çپAچإ‹ك‚حژR–{Œـڈ\کZ‚ھگ^ژىکpٹïڈPچىگي‚ً‹ˆّ‚ةٹ¸چs‚³‚¹‚½ژ‚ئ“¯‚¶‹؛‚µ‚جژèŒû‚ًژg‚ء‚ؤپAƒ~ƒbƒhƒE´پ\چىگي‚ً‹چs‚³‚¹‚ي‚´‚ئ•‰‚¯‚³‚¹‚½پA‚ئ‚¢‚¤ƒvƒچƒpƒKƒ“ƒ_‚ة‚·‚è‘ض‚ي‚ء‚½’ِ“x‚إ‚ ‚éپB
گ^ژىکpچUŒ‚‚جژ蔲‚«‚àƒ~ƒbƒhƒE´پ[ٹCگي‚جژS”s‚àپA“ْ•ؤ‹¤“¯‰‰ڈo‚ة‚و‚é”ھ•S’·‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ةˆظک_‚ح‚ب‚¢پB’A‚µژ„‚ح‚»‚±‚©‚çژR–{Œـڈ\کZ‚ئ“ى‰_’‰ˆê‚ًڈœ‚پBƒ~ƒbƒhƒE´پ[ٹCگي‚ة‚آ‚¢‚ؤگو‚¸Œ‹ک_‚ًڈq‚ׂéپB
پ“ْ–{‚حƒ~ƒbƒhƒE´پ[ٹCگي‚ةٹ®ڈں‚µ‚ؤ‚¢‚éپB
پƒAƒپƒٹƒJ‚جپwٹïگص‚ج‹t“]ڈں—کپx‚حچ¼ڈp‚ة‚و‚é‚à‚ج‚إ‚ ‚éپB
ˆب‘OپA•S“c’¼ژ÷’کپw‰i‰“‚جƒ[ƒچپx‚ً“ا‚ٌ‚إٹ´“®‚µ‚½کb‚ًڈ‘‚¢‚½پB‚»‚جچغپA•S“cژپ‚ھƒ~ƒbƒhƒEƒGپ[ٹCگي‚إ‹}چ~‰؛”ڑŒ‚‚µ‚½ƒAƒپƒٹƒJ•؛‚ج—E‹C‚ً‚ظ‚ك‚ؤ‚¢‚½‚±‚ئ‚ةژ„‚à“¯’²‚µ‚½پB‚µ‚©‚µ‚±‚±‚إ‚»‚ê‚ً“P‰ٌ‚µ‚ؤپAژ©•ھ‚ج•s–¾‚ً‚¨کl‚ر‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢پB”ق‚ç‚ج—E‹C‚حƒ„ƒ‰ƒZ‚ة—ک—p‚³‚êپAژg‚¢ژج‚ؤ‚ة‚ة‚³‚ꂽ‚¾‚¯‚إ‚ ‚éپB
پƒ„ƒ‰ƒZ‚جژi—ك“ƒ‚ح‹g“c–خ‚ئڈ؛کa“Vچc‚إ‚ ‚éپB
پ“ْ–{‘¤‚جژه–ً‚حŒ¹“cژہ‚ئ•£“c”ü’أ—Y‚إ‚ ‚éپB
“ٌگl‚ئ‚à‰¼•a‚ًژg‚ء‚ؤ‚¢‚éپB
Œ¹“c‚ح”x‰ٹ‚ة‚©‚©‚ء‚½ƒtƒٹپA•£“c‚ح’ژگ‚‰ٹ‚جژèڈp‚ً‚µ‚½ƒtƒٹ‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚éپB
پ‹¤‰‰ژز‚حچ•“‡‹TگlپA“n•سˆہژںپA‰Fٹ_“ZپAژOکa‹`—EپA“،ˆن–خپB
’†‚إ‚àچ•“‡‹Tگl‚حپA‹g“c–خ‚ة’¼‚©‚ةŒq‚ھ‚éƒRƒlƒNƒVƒ‡ƒ“‚جˆêگl‚إ‚ ‚éپB
پƒAƒپƒٹƒJ‘¤‚جژه–ً‚حƒŒƒCƒ‚ƒ“ƒhپEƒXƒvƒ‹پ[ƒAƒ“ƒX‚إ‚ ‚éپB
ƒXƒvƒ‹پ[ƒAƒ“ƒX‚ح‘¾•½—mکAچ‡ٹح‘à‚إ‚ح‚ب‚’³•ٌ‘gگD‚ة‘®‚µ‚ؤ‚¢‚éپB
ƒXƒvƒ‹پ[ƒAƒ“ƒX‚ً‘—‚èچ‚ٌ‚¾‚ج‚حƒ”ƒBƒNƒ^پ[پEƒچƒXƒ`ƒƒƒCƒ‹ƒh‚¾‚ئچl‚¦‚ؤ‚¢‚éپB
پƒ~ƒbƒhƒE´پ\ٹCگي‚جگيژjژ‘—؟پEڈطŒ¾‚ح‰üâ‚پEs‘¢‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB
ƒ~ƒbƒhƒE´پ[چىگي‚جچ\‘z‚ھپAƒ~ƒbƒhƒE´پ\“‡چU—ھ‚ئƒAƒپƒٹƒJٹح‘àŒ‚–إ‚جپw“ٌ“e‚ً’ا‚ء‚½گظچôپx‚ئ”ل”»‚·‚é‚ج‚حƒvƒچƒpƒKƒ“ƒ_‚إ‚ ‚éپB‚±‚جپwگظچôپx‚ب‚‚µ‚ؤپAƒ„ƒ‰ƒZ‚حٹ®گ‹‚إ‚«‚ب‚¢پBکAچ‡ٹح‘àژi—ك•”‚ةƒ~ƒbƒhƒE´پ\“‡چU—ھ‚ًژهٹل‚ئ‚·‚éچىگي‚ً“WٹJ‚³‚¹پAƒ~ƒbƒhƒE´پ\“‡چU—ھ‚جچإ’†‚ة“G‹َ•ê‚ً”Œ©‚·‚éƒVƒiƒٹƒI‚إ‚ ‚éپBپw“ٌ“e‚ً’ا‚¤گظچôپx‚±‚»پA‚±‚جƒ„ƒ‰ƒZ‚ًٹ®گ‹‚³‚¹‚é—v’ْ‚إ‚ ‚éپB
پw“ٌ“e‚ً’ا‚¤گظچôپx‚ج‘وˆê‹`‚ئ‚³‚ꂽپAƒ~ƒbƒhƒE´پ\“‡چU—ھ‚جگي—ھ“Iˆس‹`‚ة‚آ‚¢‚ؤپA
ƒfپ[ƒ”ƒBƒbƒhپEƒoپ[ƒKƒ~ƒjپw“Vچc‚ج‰A–dپx‚¢‚¢‚¾‚à‚à–َپ@ڈo”؟ژذ‚و‚蔲گˆ‚·‚éپB
پw“ٌ•½•ûƒ}ƒCƒ‹‚ج•s–ر‚إ’ھ•—‚ةگپ‚«‚³‚炳‚ê‚ؤ‚¢‚é’ل’n‚ھ–â‘è‚ج“‡‚إ‚ ‚ء‚½پBƒ~ƒbƒhƒE´ƒC‚ج“ٌ‚آ‚ج“‡پAƒTƒ“ƒh‚ئƒCپ[ƒXƒ^ƒ“‚حپA•Sƒ}ƒCƒ‹گ¼‚ة‚ ‚é‚‚ê‚ئ‚¢‚¤–¼‚ج–¢ٹJ‚إ–³ڈZ‚جٹâڈت‚ئ‚ئ‚à‚ة‘¾•½—m–kگ¼ٹCˆو‚ة‰،‚½‚ي‚é—£“‡‚¾‚ء‚½پBƒ~ƒbƒhƒE´ƒC‚جژE•—Œi‚ب“y’n‚ًڈ„‚ء‚ؤچs‚ي‚ꂽگي“¬‚ة‚حپAƒ‹پ[ƒYƒ”ƒFƒ‹ƒg‘ه“—ج‚ئ‚»‚ج–‹—»–{•”‚ھ”F‚ك‚ؤ‚¢‚½ˆبڈم‚جˆس‹`‚ھ‚ ‚ء‚½‚ج‚إ‚ ‚éپBژہچغپAƒeƒ‹ƒ‚ƒsƒŒپ[ˆب—ˆپA‚±‚ê‚ظ‚اŒƒ‚µ‚پA‚ـ‚½ٹmŒإ‚ئ‚µ‚½——R‚ج‚½‚ك‚ةچs‚ي‚ꂽگي“¬‚حڈ‚ب‚©‚ء‚½پB
‚à‚µ“ْ–{‚ھ‚±‚جگي“¬‚ةڈں—ک‚ًژû‚ك‚ؤ‚¢‚ê‚خپA”ق‚ç‚حˆê‹مژl“ٌ”N”ھŒژ’†‚ةƒnƒڈƒC‚ًچU—ھ‚·‚é‚ئ‚¢‚¤چىگيŒv‰و‚ًژہچs‚µ‚½‚à‚ج‚ئژv‚ي‚ê‚éپB”ق‚ç‚ح‚³‚ç‚ةگi‚ٌ‚إپAƒpƒiƒ}‰^‰ح‚ًگè—ج‚µپAƒJƒٹƒtƒHƒ‹ƒjƒA‚ً‹؛‚©‚·‚±‚ئ‚إپAچ‡ڈOچ‘‚ةƒIپ[ƒXƒgƒ‰ƒٹƒA•ْٹü‚ً—]‹V‚ب‚‚³‚¹‚é‚ئ‚ئ‚à‚ةپAƒˆپ[ƒچƒbƒpگيگü‚ض‚ج”h•؛‚ً‘jژ~‚µپA‚»‚ج‚·‚ׂؤ‚جژ‘Œ¹‚ًƒAƒپƒٹƒJگ¼ٹCٹف–h‰q‚ةڈW’†‚³‚¹‚é‚ئ‚¢‚¤ˆسگ}‚ًژ‚ء‚ؤ‚¢‚½پB
ƒ~ƒbƒhƒE´ƒC‚ج•ؤŒR‚حچl‚¦‚ç‚ê‚ب‚¢‚ظ‚ا‚جچK‰^‚ةŒb‚ـ‚êپA‚»‚ê‚ًچإ‘هŒہ‚ة—ک—p‚µ‚½پBپx
ƒVƒiƒٹƒI‚ح‚±‚¤‚¢‚¤—¬‚ê‚إ‚ ‚éپB“ْ–{‚ھپw“ٌ“e‚ً’ا‚¤گظچôپx‚ً“WٹJ‚·‚éپ¨پwƒ~ƒbƒhƒE´ƒC‚ج•ؤŒR‚حچl‚¦‚ç‚ê‚ب‚¢‚ظ‚ا‚جچK‰^‚ةŒb‚ـ‚êپA‚»‚ê‚ًچإ‘هŒہ‚ة—ک—p‚µ‚½پBپx‚»‚ج‚½‚ك‚ةپAƒAƒپƒٹƒJ‘¤‚إ‚حپAپw”قژ©گg‚جگس”C‚إپAƒjƒ~ƒbƒc‚حƒ~ƒbƒhƒE´ƒCٹJگي‚جƒAƒپƒٹƒJ‘¤چىگيŒv‰و‚ً—§ˆؤ‚µپAچs“®‚ًٹJژn‚µ‚ؤ‚¢‚½پxپB‚آ‚ـ‚èƒjƒ~ƒbƒc‚ھپwچl‚¦‚ç‚ê‚ب‚¢‚ظ‚ا‚جچK‰^‚ةŒb‚ـ‚êپA‚»‚ê‚ًچإ‘هŒہ‚ة—ک—p‚µ‚½پx‚ئ‚¢‚¤ٹù’è‚ج‹طڈ‘‚«‚ة“Y‚¤‚ׂپAچs“®‚ً‹N‚±‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إ‚ ‚éپB
ƒoپ[ƒKƒ~ƒj‘±‚«پiگ^ژىکpٹïڈPچUŒ‚‚ج‰سڈٹ‚ج”²گˆ‚إ‚ ‚éپj
پw”ھŒژ‚ج‘و“ٌڈT‚ةپA—Tگm‚حٹCŒRŒv‰و‚جŒں“¢‚ة’…ژ肵‚½پBژR–{چ\‘z‚ح‚ـ‚¾—Tگm‚ئچ‚ڈ¼‹{‚ج‘¼‚ة‚حگ”گl‚جکAچ‡ٹح‘à–‹—»‚µ‚©’m‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½‚ج‚إپAژR–{‚حٹCŒRŒR—ك•”‚إ‚ح‚ب‚پAٹCŒR‘هٹwچZ‚إگà–¾‚ً“WٹJ‚µ‚½پBٹCŒR‘هٹwچZ‚ً‘I‚ٌ‚¾‚ي‚¯‚حپA‚»‚±‚ًٹاٹچ‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ھپA‚©‚آ‚ؤˆê‹م“ٌˆê”Nپi’چپ@‰¢ڈBٹO—V‚جگـپj‚ةٹّٹحچپژو‚جچb”آڈم‚إ—Tگm‚ج‘ج‘€‹³ˆç‚ة‚ ‚½‚ء‚½‚±‚ئ‚à‚ ‚é“Vچc‰ئ‚جˆêˆُپAٹCŒRڈڈ«پEڈ¬ڈ¼‹P‹vŒٍژف‚¾‚ء‚½‚©‚ç‚إ‚ ‚éپB
‹مŒژ“ٌ“ْپAژR–{ٹCŒR‘هڈ«‚ئ”z‰؛‚جڈ«چZ’B‚حچؤ‚رڈ¬ڈ¼چ‚Œٍ‚جٹاٹچ‚·‚éٹCŒR‘هٹwچZ‚ةڈW‚ـ‚ء‚½پBچc‹ڈ‚©‚ç–ٌŒـƒLƒچ—£‚ꂽ”’‹à‚جچcژ؛—ر‚ج‚ح‚¸‚ê‚ة‚ ‚éٹCŒR‘هٹwچZ‚حپAچ،“x‚ح—¤ŒR‘و”ھ“ٌŒR‚ج“ىگiŒv‰و‚ًژx‰‡‚·‚éٹCŒR‘¤‘Sچىگي‚ج—\چs‰‰ڈK‚ج•‘‘ن‚ئ‚ب‚ء‚½پBژR–{‚جŒv—ھ‚ح‚»‚±‚إ‚حپAٹJ–‹‚ج–é‚ةژg‚ي‚ê‚é‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢‚µژg‚ي‚ê‚ب‚¢‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢‚و‚¤‚ب’P‚ب‚é—]‹»‚ئ‚µ‚ؤˆµ‚ي‚ꂽ‚ة‚·‚¬‚ب‚©‚ء‚½پBژه—v‚بٹضگSژ–‚حپA“گ§‚³‚ꂽ•”‘à‚جƒ}ƒ‰ƒ„پEƒtƒBƒٹƒsƒ“پEƒE´پ[ƒNپEƒO±ƒ€پEƒ{ƒ‹ƒlƒIپEƒWƒƒƒڈ‚ض‚جڈم—¤‚ًژx‰‡‚·‚邽‚ك‚جٹCŒR‘¤‚جچىگيŒv‰و‚إ‚ ‚ء‚½پBپi’چپ@‹’DچàژYƒSپ[ƒ‹ƒfƒ“پEƒٹƒٹپ[‚ج•ڑگü‚إ‚ ‚éپj
ژR–{‚ھژ©•ھ‚جŒv‰و”âکI‚ج‹@‰ï‚ً’ح‚ٌ‚¾‚»‚ج‹مŒژ”ھ“ْ‚ج”سپAٹCŒR‘هٹwچZچZ’·‚جڈ¬ڈ¼Œٍژف‚حپA“Vچc‰ئˆê‘°پAگe‘°‚ًڈµ‘ز‚µ‚ؤڈj‰ê‚ج”سژ`‚ًٹJ‚¢‚½پB–طŒث“à‘هگb‚حپA‚©‚آ‚ؤ“àگe‰¤‚إ‚ ‚ء‚½ژµڈ\‰ك‚¬‚ج•ê“°‚ً”؛‚ء‚ؤ—ٌگب‚µ‚½پBپx
ƒ~ƒbƒhƒE´پ\چىگي‚إچإ‘ه‚جƒ„ƒ‰ƒZ‚جˆê‚آ‚ًگ؟‚¯•‰‚ء‚½‚ج‚ھپA‚±‚جڈ¬ڈ¼Œٍژف‚إ‚ ‚éپB
ƒoپ[ƒKƒ~ƒj‚ج‘±‚«
پwڈ„—mٹح‚ئ‹ى’€ٹح‚ةŒى‰q‚³‚ꂽƒAƒپƒٹƒJ‚ج‹َ•ê‚ًپAژR–{’ٌ“آ‚ح‘S‚•â‘«‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½پBچىگيŒv‰و‚ج‚ب‚©‚إپAگ^ژىکp‚ًٹؤژ‹‚·‚é”C–±‚حگوŒ‘à‚جگِگ…ٹح‘à‚ةٹ„‚è“–‚ؤ‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚½پBگِگ…ٹح‘à‚حپAچcچ@‚جڈ]’ي‚إˆê‹مژlˆê”N‚جگ^ژىکpŒv‰و“–ژ‚حٹCŒR‘هٹwچZچZ’·‚¾‚ء‚½ٹCŒR’†ڈ«‚جڈdگbڈ¬ڈ¼‹P‹vŒٍژف‚ھژi—كٹ¯‚ً–±‚ك‚ؤ‚¢‚½پB
ڈ¬ڈ¼Œٍ‚حƒ~ƒbƒhƒE´ƒCچىگي‚ة‘ه‚«‚بٹmگM‚ً•ّ‚¢‚ؤ‚¨‚èپA“ْ–{ٹCŒR‚جگâ‘خ“I‚ب—Dگ¨‚ھ‚»‚جڈں—ک‚ً•K‘R“I‚ب‚à‚ج‚ة‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚جگM”O‚ًژ‚ء‚ؤ‚¢‚½پB”ق‚جگِگ…ٹحŒQ‚حپAٹJگي‚ج”ھ“ْ‘O‚ةگ^ژىکpکpٹO‚ج‘Oڈ£’مژ@’è“_‚ئپAگ^ژىکp‚ئƒ~ƒbƒhƒE´ƒC‚ج’†ٹشٹCˆو‚ج“ٌ‚آ‚جŒx‰ْگü‚ة“WٹJ‚·‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ھپAŒ‹‰ت“I‚ة‚حƒ~ƒbƒhƒE´ƒCٹJگي‚جژl“ْ‘O‚ة‚â‚ء‚ئ‚±‚ê‚ç‚ج’è“_‚ض‚ج“WٹJ‚ھچs‚ي‚ꂽ‚ج‚إ‚ ‚éپB’x‰„‚µ‚½ژl“ْ‚جٹش‚ةپAƒGƒ“ƒ^پ[ƒvƒ‰ƒCƒYپAƒzپ[ƒlƒbƒgپA‚»‚µ‚ؤƒˆپ[ƒNƒ^ƒEƒ“‚àپA“ْ–{‘¤‚ج‘پٹْŒx‰ْگ…ˆو‚ً’ت‰ك‚µپAŒx‰ْ‚ج–ع‚ًگِ‚ء‚ؤƒ~ƒbƒhƒE´ƒC–k“ŒٹCˆو‚ضگع‹ك‚µ‚½پBپx
‚آ‚ـ‚èŒx‰ْگü‚ً’£‚é‚ج‚ًژl“ْ‚à’x‰„‚³‚¹‚ؤپA–³ژ–ƒAƒپƒٹƒJ‹َ•ê‚ً’ت‚µ‚ؤ‚ ‚°‚½‚ج‚إ‚ ‚éپB
پwکZŒژژO“ْچ پAڈ¬ڈ¼‚حژR–{’ٌ“آ‚ ‚ؤ‚ةƒAƒپƒٹƒJٹح‘à‚ھگ^ژىکp‚ة—¯‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚é‚©‚ا‚¤‚©‚ًٹm”F‚·‚é”C–±‚ةژ¸”s‚µ‚½ژ|‚ً’ت’m‚µ‚½پB‚µ‚©‚µڈ¬ڈ¼‚حپAڈ£‰ْگِگ…’ّ‚ھگ^ژىکp‚ئƒ~ƒbƒhƒE´ƒC‚جٹش‚جŒx‰ْگ…ˆو‚ة’x‚ê‚ؤ“’…‚µ‚½ژ–ژہ‚ة‚آ‚¢‚ؤپAژR–{‚ج’چˆس‚ًٹ«‹N‚µ‚و‚¤‚ئ‚ح‚µ‚ب‚©‚ء‚½پBپx
‚»‚è‚لژl“ْ‚à’x‰„‚µ‚½——R‚حŒ¾‚¦‚ب‚¢پB
پw‚±‚ê‚حڈd‘ه‚بژ¸چô‚¾‚ء‚½‚ج‚¾‚ھپAڈ¬ڈ¼‚ھچc‘°‚جˆêˆُ‚إ‚ ‚é‚ئ‚¢‚¤——R‚إپA‚ج‚؟‚ج“ْ–{‚ج—ًژj‰ئ‚½‚؟‚حٹشگع“I‚ة‚»‚ê‚ً‚ظ‚ج‚ك‚©‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ة‰ك‚¬‚¸پA‚ـ‚½ƒAƒپƒٹƒJ‚ج—ًژj‰ئ‚حپA‚»‚ج“O’ê“I‚بژ–Œم‚جŒ¤‹†‚ج‚ب‚©‚إ‚à“ْ–{‚ج—ًژj‰ئ‚جژه’£‚ة‚»‚ج‚ـ‚ـڈ]‚ء‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚ةژv‚ي‚ê‚éپBپx
’ا‹y‚·‚ê‚خپA“ْ•ؤ‹¤“¯ƒVƒiƒٹƒI‚ھکI’و‚·‚é‚©‚ç‚إ‚ ‚éپB
پwڈ¬ڈ¼Œٍ‚ھ–k‘¾•½—m‚ة“WٹJ‚µ‚½‚ئژR–{‚ھگM‚¶‚ؤ‚¢‚½چUŒ‚گِگ…ٹح‚جŒx‰ْگü‚ً“ث”j‚µ‚ب‚¯‚ê‚خپAƒAƒپƒٹƒJٹح‘à‚حژR–{‚جڈoŒ‚‚ة”½Œ‚‚ً‰ء‚¦‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ب‚¢”¤‚إ‚ ‚ء‚½پBƒjƒ~ƒbƒcں€‰؛‚ج‹َ•êژOگا‚حپA‚ـ‚¾ژ©–‚·‚é‚ة‘«‚éگيŒ÷‚ً‹“‚°‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½‚ھپAƒ~ƒbƒhƒE´ƒC–k“ŒٹCˆو‚ًƒXƒRپ[ƒ‹‚ة‚ـ‚¬‚ê‚ؤ‰B–§—،‚ةچqچs‚µ‚ب‚ھ‚ç‹@‰ï‚ً‚¤‚©‚ھ‚ء‚ؤ‚¢‚½پBپx
‚±‚جگو‚حژہچs”ئŒ¹“cژہپA•£“c”ü’أ—Y‚ج‚»‚ꂼ‚ê‚ج’کڈ‘‚ئپAƒvƒچƒpƒKƒ“ƒ_‚ًڈ‘‚‚½‚ك‚ة‚f‚Qگيژjژ؛’·‚ة‚³‚ꂽƒSپ[ƒhƒ“پEƒvƒ‰ƒ“ƒQ‚جپwƒ~ƒbƒhƒE´پ[‚جٹïگصپx‚ً‚½‚½‚«‘ن‚ة‚·‚éپB–َژز‚حژOڈ\—]”N‚ة‚ي‚½‚ء‚ؤƒvƒ‰ƒ“ƒQ‚ة‹¦—ح‚µ‚ؤ‚«‚½گç‘پگ³—²‚إ‚ ‚éپB–َژز‚ ‚ئ‚ھ‚«‚ة‚و‚é‚ئپAƒvƒ‰ƒ“ƒQ‚ح‚·‚إ‚ةˆê‹مژOژµ”NپAژلٹ±‚Q‚Vچخ‚ة‚µ‚ؤƒپƒٹپ[ƒ‰ƒ“ƒh‘هٹw‚ج—ًژjگ³‹³ژِ‚ئ‚ب‚èپAˆê‹م”ھپZ”N‚ةژ€‹ژ‚·‚é‚ـ‚إ‚»‚جگE‚ة‚ ‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤ڈrڈG‚إ‚ ‚éپB‘هگي’†‚حٹCŒRڈچ²‚ئ‚µ‚ؤپAگيŒم‚حگ؟‚ي‚ê‚ؤ‚f‚g‚pگيژjژ؛’·‚ئ‚ب‚èپAڈ؛کa“ٌپZ”N‚©‚ç“ٌکZ”N‚ـ‚إƒ}ƒbƒJپ[ƒTپ[گيژj‚ج•زڈW‚ة“–‚½‚ء‚½پBƒvƒ‰ƒ“ƒQŒآگl‚جƒ‰ƒCƒtƒڈپ[ƒN‚ئ‚µ‚ؤگ^ژىکpچUŒ‚‚ًژو‚èڈم‚°‚و‚¤‚ئŒˆگS‚µ‚½ژپA“¯گيژjژ؛‚ة‚حگç‘پگ³—²‚ًٹـ‚ك‚ؤژlگl‚ج‹ŒٹCŒRژmٹ¯‚ھ‹خ‚ك‚ؤ‚¢‚½‚ھپA‘Sˆُ‚ھ‹¦—ح‚µ‚½‚»‚¤‚¾پB
ƒvƒ‰ƒ“ƒQ‚جŒ¤‹†پE’²چ¸‚ة‘خ‚·‚éڈî”M‚حپwˆظڈي‚ئژv‚ي‚ê‚é‚ظ‚ا“O’ê“Iپx‚إپAپwچىگي‚ةڈ‚µ‚إ‚àٹضŒW‚ھ‚ ‚ء‚½گl‚ح•ذ‚ء‚د‚µ‚©‚çژ©‘î‚ةڈµ‚¢‚ؤƒCƒ“ƒ^ƒrƒ…پ[‚µپAچف“ْ’†‚ة‰ï‚ء‚½گl‚ح“ٌ•S–¼‚ً’´‚¦‚½پBپxپB‚»‚جŒمپAƒvƒ‰ƒ“ƒQ‚ح–ً“¾‚إژûڈW‚µ‚½ژ‘—؟‚àٹـ‚كپA™ث‘ه‚ب—ت‚ج‚»‚ê‚ًƒپƒٹپ[ƒ‰ƒ“ƒh‘هٹw‚ةژ‚؟‹A‚èپiƒvƒ‰ƒ“ƒQ‚جژ€Œم‚حƒvƒ‰ƒ“ƒQپEƒRƒŒƒNƒVƒ‡ƒ“‚ئ‚µ‚ؤ•غ‘¶پjپAڈ؛کaŒـڈ\ژO”N‚ةگ^ژىکpچUŒ‚‚ج‘Sٹھ‚ً’Eچe‚µ‚½پB–{ڈ‘‚جپwƒ~ƒbƒhƒE´°‚جٹïگصپx‚ًٹ®گ¬‚µ‚½‚ج‚حڈ؛کaŒـڈ\ژµ‚جڈH‚إ‚ ‚éپB‹أ‚èگ«‚إٹ®àّژه‹`‚جƒvƒ‰ƒ“ƒQ‚حپAƒ„ƒ‰ƒZ‚ًگ³“–‰»‚·‚éگيژj‚ًs‘¢‚³‚¹‚é‚ة‚ح•sŒü‚«‚بگlچق‚إ‚ ‚éپB
ƒSپ[ƒhƒ“پE‚vپEƒvƒ‰ƒ“ƒQپwƒ~ƒbƒhƒE´پ[‚جٹïگصپxگç‘پگ³—²–َپ@Œ´ڈ‘–[‚و‚è
پw•‰‚¯Œ¢‚ھڈں‚آکb‚ظ‚اƒAƒپƒٹƒJگl‚جگS‚ة‹‚‘i‚¦‚é‚à‚ج‚ح‚ب‚¢پBƒAƒپƒٹƒJ‚ح‚»‚جچ‘—حپA‚»‚جچL‘ه‚³‚¨‚و‚ر‚»‚ج’n—“I‚بٹضŒW‚©‚çپA‰ك‹ژˆêگ¢‹I‚جٹشپA‚»‚ج‚و‚¤‚ب—§ڈê‚ة—§‚ء‚½‚±‚ئ‚ھ‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‚ب‚©‚ء‚½پB‚ھپAƒ~ƒbƒhƒE´پ[‚جگي‚¢‚حپAƒAƒپƒٹƒJ‚ھ•‰‚¯Œ¢‚ج—§ڈê‚ة—§‚½‚³‚êپA‚»‚µ‚ؤڈں—ک‚ًٹl“¾‚µ‚½‚«‚ي‚ك‚ؤگ”ڈ‚ب‚¢ژ–—ل‚إ‚ ‚ء‚½پBپx
ڈک•¶‚ج‘è–¼‚ئ‚µ‚ؤپwگ^ژىکp‚ج— •ش‚µپx‚ئ‚ ‚é‚و‚¤‚ةپAƒ~ƒbƒhƒE´پ[ٹCگي‚àƒ„ƒ‰ƒZ‚إ‚ ‚éپB“¯چىگي‚ئگ^ژىکpٹïڈP‚حپA‚¢‚ي‚خ“¯‚¶ƒRƒCƒ“‚ج— •\‚إ‚ ‚éپBƒ„ƒ‰ƒZ‚ج“ء’¥‚جˆê‚آ‚حپA“¯‚¶–ًژز‚ًژg‚¢‰ٌ‚µ‚·‚邱‚ئ‚ة‚ ‚éپB’†‚إ‚àگ^ژىکpچUŒ‚‘à’·‚ج•£“c”ü’أ—Y‚ح“ءˆظ‚ب‘¶چف‚إ‚ ‚éپB”ق‚حگ^ژىکpچUŒ‚پEƒ~ƒbƒhƒE´پ[ٹCگيپEŒ´”ڑ“ٹ‰؛‚جƒ„ƒ‰ƒZ‚ة‰ء’S‚µپAگيŒم‚ح“`“¹ژt‚ة‚ب‚ء‚ؤƒrƒٹپ[پEƒOƒ‰ƒnƒ€‚ة‰ï‚ء‚ؤ‚¢‚éپB
ƒvƒ‰ƒ“ƒQ‘±‚«
پwƒ~ƒbƒhƒE´پ[‚ح“ْ–{‘¤‚ج‰كگMپA“mگï‚بŒv‰وپA•sڈ\•ھ‚بŒP—û‚¨‚و‚ر‰؛ژZ‚ج•¨Œê‚إ‚ ‚èپA‚»‚ê‚ح‚ـ‚½ƒAƒپƒٹƒJ‘¤‚ج—âگأپA‘nˆس‚¨‚و‚رڈî•ٌ‚ھ‚و‚’²کa‚³‚ꂽ•¨Œê‚إ‚ ‚ء‚½پBپx
‚±‚ê‚حژjژہ‚إ‚ح‚ب‚پAƒVƒiƒٹƒI‚جƒgڈ‘‚إ‚ ‚éپBƒ~ƒbƒhƒE´پ\‚ج•¨Œê‚حپA‚ ‚جژ肱‚جژè‚ًژg‚ء‚ؤپA‚»‚êˆبٹO‚ة‚حƒAƒپƒٹƒJ‚جڈں‹@‚ح‚ب‚¢پA‚ئ‚¢‚¤ڈَ‹µ‚إچs‚ي‚ꂽژcچ“‚ب”ئچك‚ج•¨Œê‚إ‚ ‚éپB
پwƒ~ƒbƒhƒE´پ[‚ج•¨Œê‚ة‚حپhƒcپ[پEƒŒپ[ƒgپi’x‚·‚¬‚½پjپh‚ھگ”‘½‚ژg‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ھپAپEپEپEژR–{‚حپAŒR—ك•”چىگي•”‚ئ‚ج‹¦—ح‚ج‰؛‚ةپA‘و“ٌ’iچىگيŒv‰و‚ج—§ˆؤ‚ً‚·‚إ‚ةٹ®—¹‚µپA“ى‰_•”‘à‚ھگ^ژىکp‚جچUŒ‚‚ًڈI‚ي‚ء‚ؤ‹Aچq‚ج“r‚ة‚آ‚‚â‚¢‚ب‚âپA‚»‚ê‚ً”“®‚·‚ׂ«‚إ‚ ‚ء‚½پBکAگي‚ج“ى‰_•”‘à‚ج”ٍچs‹@ڈو‚肽‚؟‚حپAچL“‡کp‚جŒj“‡”‘’n‚ة‹ڈگک‚ء‚½‚ـ‚ـ‚جگيٹح•”‘à‚ًپg’Œ“‡ٹح‘àپh‚ئŒؤ‚ٌ‚إ”ç“÷‚ء‚ؤ‚¢‚½پB‚ئ‚‚ةƒnƒڈƒCچUŒ‚‚ج‚ئ‚«‚ة”ٍچs‹@‘à‚ً—¦‚¢‚ؤˆجŒ÷‚ً‚ ‚°‚½•£“c”ü’أ—Y’†چ²‚حپAژR–{’·ٹ¯‚حƒAƒپƒٹƒJ‚ھƒnƒڈƒC‚إ”j‰َ‚³‚ꂽٹح‚ًڈC—‚·‚é‚ج‚ً‘ز‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©پA‚ئ‚ـ‚إژv‚ء‚ؤ‚¢‚½پBپx
•£“c”ü’أ—Y‚ئŒ¹“cژہ‚حƒSپ[ƒhƒ“پEƒvƒ‰ƒ“ƒQ‚جژ©‘î‚ةڈµ‚©‚ê‚ؤپA—[گH‚ً‚ح‚³‚ٌ‚إ‘OŒمژ€Œمژٹش‚ظ‚ا‚ج•·‚«ژو‚è‚ً‚V‚Oپ`‚W‚O‰ٌ‚®‚ç‚¢‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپB•£“c”ü’أ—Y‚ج‚±‚جٹ´‘z‚ح‚»‚ج‚ئ‚«‚ج‚à‚ج‚¾‚낤پB•£“c‚حƒVƒiƒٹƒI‰‰ڈo‚جˆêˆُ‚ئ‚µ‚ؤ‚ح‚µ‚ب‚‚àگ^‘ٹ‚ً–¾‚ç‚©‚ة‚µ‚ؤ‚¢‚éپBپwƒnƒڈƒC‚إ”j‰َ‚³‚ꂽٹح‚ًڈC—‚·‚é‚ج‚ً‘ز‚ء‚ؤ‚¢‚éپxپA‚ئ‚¢‚¤‹طڈ‘‚«‚¾‚ء‚½‚ج‚إ‚ ‚éپB
پwŒR—ك•”‘وˆê•”’·‚ج•ں—¯”ةڈڈ«پiٹC•½‚S‚Oٹْپj‚حƒ~ƒbƒhƒE´پ[چىگي‚ة•s“¯ˆس‚إ‚ ‚ء‚½‚ھپA‹‚¢”½‘خˆسŒ©‚ًڈq‚ׂب‚©‚ء‚½پB‚±‚ê‚ة”½‚µ‚ؤپA‘وˆê‰غ’·•x‰ھ’èڈr‘هچ²پiٹC•؛‚S‚Tٹْپj‚ح‹‚”½‘خ‚µ‚½پBچ•“‡‹Tگl‘هچ²پiگو”CژQ–dپ@ٹC•؛‚S‚Sٹْپj‚ئ“n•سˆہژں’†چ²پiگي–±ژQ–dپ@ٹC•؛‚T‚Pٹْپj‚ھƒ~ƒbƒhƒE´پ[‚حƒnƒڈƒCچU—ھ‚ج‘«ٹ|‚©‚è‚ئ‚ب‚肤‚é‚ئژه’£‚µ‚ؤ‚àپA•x‰ھ‚ئچq‹َچىگي’S“–‚جژO‘م’C‹gپi‚ف‚و‚½‚آ‚«‚؟پj’†چ²پiٹC•؛‚T‚Pٹْپj‚حژ¨‚ً‘ف‚»‚¤‚ئ‚à‚µ‚ب‚©‚ء‚½پBپx
پi’چپ@ژO‘م’C‹g‚حژO‘مˆêڈA‚جٹشˆل‚¢‚إ‚ ‚éپj
‚»‚±‚إ“n•س‚حپAŒj“‡”‘’n‚جٹّٹح‘هکa‚ة“dکb‚µ‚ؤڈ‚ً•ٌچگ‚µ‚½پB•ٌچگ‚ًڈI‚ي‚ء‚ؤ•x‰ھ‚جگب‚ة–ك‚ء‚½”ق‚حپAپuژR–{’·ٹ¯‚حƒ~ƒbƒhƒE´پ[چىگيˆؤ‚ھ”F‚ك‚ç‚ê‚ب‚¢‚ب‚ç‚خپA’·ٹ¯‚جگE‚ًژ«‚ك‚é‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚¨‚ç‚ê‚éپv‚ئ‚ج”ڑ’e”Œ¾‚ً“`‚¦‚½پBژR–{Œـڈ\کZ‘هڈ«‚ج’nˆت‚ئگ؛–]‚ة‰ں‚³‚ê‚ؤپAŒR—ك•”‚ح‚µ‚ش‚µ‚ش‚إ‚ ‚ء‚½‚ھپAƒ~ƒbƒhƒE´پ[چىگي‚ة‘خ‚·‚锽‘خ‚ً“P‰ٌ‚¹‚´‚é‚ً‚¦‚ب‚©‚ء‚½پB‚»‚ê‚حژR–{‚جگ^ژىکpچىگيŒv‰و‚ةŒR—ك•”‚ھ”½‘خ‚µ‚½‚ئ‚«‚ةپAژR–{‚ھچإŒم‚جژè’i‚ئ‚µ‚ؤژg‚ء‚½پh‹؛‚µپh‚جŒJ‚è•ش‚µ‚إ‚ ‚ء‚½پi–َ’چپپ‚»‚ج“–ژ‚ةکAچ‡ٹح‘àژQ–d‚إ‚ ‚ء‚½—L”n‚حپA‚»‚جژ‚ةژR–{‚ھ‰ت‚½‚µ‚ؤ“n•س‚ة‚»‚ج‚و‚¤‚ةژwژ¦‚µ‚½‚©‚ً‹^–âژ‹‚·‚éڈطŒ¾‚ًگيŒم‚ة‚µ‚ؤ‚¢‚éپ@پjپBپx
‘S•¶ƒKƒZ‚إ‚ ‚éپB“n•سˆہژںپA•x‰ھ’èڈrپAژO‘مˆêڈA‚ج‹Uڈط‚إ‚ ‚éپBˆب‘Oژ„‚حپAگ^ژىکpچUŒ‚‚جچ\‘z‚ح‘وˆêژںگ¢ٹE‘هگيڈI—¹’¼Œم‚ج‚P‚X‚P‚X”N‚©‚ç—pˆس‚³‚ê‚ؤ‚¨‚èپA‚P‚X‚R‚X”N‚WŒژ‚R‚P“ْ‚ةکAچ‡ٹح‘àژi—ك’·ٹ¯‚ة”C–½‚³‚ꂽژز‚حپAگ^ژىکpچUŒ‚‚ًگ‹چs‚·‚éڈh–½‚ً”w•‰‚ي‚³‚ê‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ًگà–¾‚·‚éچغ‚ةŒـڈ\کZ‚ج‹؛‚µ‚ة‚آ‚¢‚ؤŒ¾‹y‚µ‚½پB‚±‚ê‚ً“P‰ٌ‚µ‚ؤ‚¨کl‚ر‚µ‚½‚¢پB
ƒvƒ‰ƒ“ƒQ‘±‚«
پwژR–{‚جƒ~ƒbƒhƒE´پ\‚ًچU—ھ‚·‚ׂµ‚ئ‚جژه’£‚جگ³“–گ«‚ًڈط–¾‚·‚é‚©‚ج‚و‚¤‚ةپAژlŒژڈ\”ھ“ْƒWƒFپ[ƒ€ƒXپE‚gپEƒhƒٹƒbƒgƒ‹—¤ŒR’†چ²‚جژwٹِ‚·‚é‚aپ|‚Q‚T”ڑŒ‚‹@‚ھپA“Œ‹پA‰،•l‚ç‚ج“sژs‚ً’ت‚è–‚‚ج‚و‚¤‚ة”ڑŒ‚‚µ‚ؤ’ت‚蔲‚¯‚½پB“ْ–{ٹCŒR‚ج“–ژ–ژز‚حƒAƒپƒٹƒJ”ڑŒ‚‹@‚ة‚و‚é“ْ–{–{“y‚ة‘خ‚·‚éچUŒ‚‚ج‰آ”\گ«‚ة‚آ‚¢‚ؤپA‘ٹ“–‘O‚©‚ç—J—¶‚µ‚ؤ‚¢‚½پBپx
‚±‚ê‚ً—\چگ‚·‚é“ْ‹L‚ًژOکa‹`—E‚ھڈ‘‚¢‚ؤ‚¢‚éپB
پw“ٌŒژ”ھ“ْپAکAچ‡ٹح‘à‚جچىگيژQ–dژOکa‹`—Eپi‚ف‚ي‚و‚µ‚½‚¯پj’†چ²پiٹC•؛‚S‚Wٹْپj‚حپA‚»‚ج“ْ‚ج“ْ‹L‚ةژں‚ج‚و‚¤‚ةڈ‘‚¢‚½پBپu“G‚ھ“Œ‹‹َڈP‚ً‚·‚é‰آ”\گ«‚ھ‚ ‚é‚ھپA‘ه‚µ‚½–â‘è‚إ‚ح‚ب‚¢پB‚µ‚©‚µپA“Œ‹‚حژٌ“s‚إ‚ ‚èپA‰ن‚ھگ_چ‘‚ج’†گS‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ًچl‚¦‚ê‚خپA“G‚جژٌ“s‹َڈP‚ح‚¢‚©‚ب‚éڈَ‹µ‚إ‚à‹–‚·‚ׂ«‚إ‚ح‚ب‚¢پvژOکa‚ح•¨ژ–‚ً‘›‚¬—§‚ؤ‚é‚و‚¤‚بƒ^ƒCƒv‚ج’j‚إ‚ح‚ب‚©‚ء‚½پB‚»‚ج“–ژ‚ةژlڈ\ژOچخ‚إ‚ ‚ء‚½ژOکa‚ھŒR–±‹ا‹اˆُ‚©‚çژR–{‚ج–‹—»‚ئ‚ب‚ء‚½‚ج‚حپAٹJگي’¼‘O‚إ‚ ‚ء‚½پB”ق‚ج“ْ–{ٹCŒRچq‹َ‚ة‚¨‚¯‚éŒo—ً‚ئپA‚»‚جگ«ٹi‚©‚آگv‘¬‚ب”»’f—ح‚ً”ƒ‚ء‚ؤ‚¢‚½ژR–{‚ھپA‚ئ‚‚ة–]‚ٌ‚¾‚©‚ç‚إ‚ ‚ء‚½پBپx
ژOکa‚ح‚±‚ê‚©‚ç‚à–عŒ}ڈطŒ¾ژز‚ئ‚µ‚ؤچؤپX“oڈê‚·‚éپBژOکa‚ئچ•“‡‚ج‚¢‚³‚©‚¢‚ً’‡چظ‚µ‚½Œـڈ\کZ‚ھپA‚¹‚آ‚¹‚آ‚ئچ•“‡‚ة‘خ‚·‚éگ^ڈî‚ًڈq‚×پAٹ´Œƒ‚ة‘إ‚؟گk‚¦‚½چ•“‡‚ھ“ث‚ء•ڑ‚µ‚ؤ‹ƒ‚—L–¼‚بˆيکb‚ب‚اپAŒـڈ\کZ‚ةٹض‚·‚éڈd—v‚بƒvƒچƒpƒKƒ“ƒ_‚ًڈ‘‚«‚ ‚°‚½ŒمپAژOکa‚حƒeƒjƒAƒ“‚ة‘—‚èچ‚ـ‚êپwگيژ€پx‚·‚éپB—اگS‚ج™èگس‚ة‘د‚¦‚©‚ث‚ؤگ^‘ٹ‚ًکb‚·‰آ”\گ«‚ج‚ ‚éگlٹش‚حپAŒû••‚¶‚³‚ê‚é‚ج‚إ‚ ‚éپB
ƒvƒ‰ƒ“ƒQ‘±‚«
پw‚µ‚©‚àƒhƒٹƒbƒgƒ‹‘à‚ح—\‘z‚³‚ꂽ‚و‚è‚ح‚é‚©‚ة’ل‹َ‚ً”ٍ‚رپA—¤ŒR‚ج–hگيگي“¬‹@‚ًڈo‚µ‚ت‚¢‚½گي–@‚ًپA•£“c‚â‚»‚ج•”‰؛‚ج—ًگي‚ج“‹ڈوˆُ‚ح‘fگ°‚炵‚¢گي–@‚¾‚ئژv‚ي‚¸‚ة‚ح‚¢‚ç‚ê‚ب‚©‚ء‚½پB‚³‚ç‚ةپAƒhƒٹƒbƒgƒ‹‚جچUŒ‚‚ھ•êٹح‚ً”ٹح‚µ‚ؤ‚©‚ç’†چ‘‚ةŒü‚©‚¤•ذ“¹چUŒ‚‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ھ‚ي‚©‚é‚ئپA•£“c‚ح”ق‚ç‚ة‘خ‚µ‚ؤˆطŒh‚ج”O‚³‚¦ژ‚ء‚½پA‚ئ•£“c‚حƒCƒ“ƒ^ƒrƒ…پ[‚إڈq‚ׂؤ‚¢‚éپB
چ•“‡‚à‚»‚جƒCƒ“ƒ^ƒrƒ…پ[‚إپAƒhƒٹƒbƒgƒ‹‚ج‹َڈP‚ح‚»‚جگي‰ت‚±‚»ڈ‚ب‚©‚ء‚½‚ھپAپu“ْ–{‚ةگيœة‚ً‘–‚点‚½پv‚ئڈq‚ׂؤ‚¢‚éپB“ْ–{ٹCŒR‚ھƒAƒپƒٹƒJ‚جگ_چ‘‚ة‹كگع‚ً‹–‚µ‚½‚±‚ئ‚ة‚آ‚¢‚ؤپAڈ‚ب‚‚ب‚¢چ‘–¯‚ھŒ¶–إ‚ك‚¢‚½‚à‚ج‚ًٹ´‚¶پAژR–{’·ٹ¯‚ة”ٌ“ï‚جژèژ†‚ً‘—‚ء‚½پB‹َڈP‚ة‚و‚ء‚ؤ‚»‚جلàژ‚ًڈ‚آ‚¯‚ç‚ꂽژR–{‚حپA“Vچc‚¨‚و‚رچcژ؛‚جˆہ‘ׂً‚و‚èˆê‘w‹C‚ة‚·‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½پBپx
ژR–{Œـڈ\کZ‚حگ¬‚è‚·‚ـ‚µ“Vچc‰ئ‚ج‘fگ«‚ًڈ¼•½چP—Y‚©‚ç•·‚¢‚ؤ‚¢‚éپBŒـڈ\کZ‚ھپw“Vچc‚و‚رچcژ؛‚جˆہ‘ׂًˆê‘w‹C‚ة‚·‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½پx‚±‚ئ‚ح‚ب‚¢پB‚»‚¤‚¢‚¤‹طڈ‘‚«‚ة‚·‚邽‚ك‚ةپAƒhƒٹƒbƒgƒ‹‹َڈP‚ھٹ¸چs‚³‚ꂽ‚ج‚إ‚ ‚éپB
پwژOکa‚حژlŒژ“ٌڈ\“ْ‚ج“ْ‹L‚ةپAژR–{‚ج——R‚أ‚¯‚ة‚آ‚¢‚ؤژں‚ج‚و‚¤‚ةڈ‘‚¢‚ؤ‚¢‚éپBپu“ىڈ¹‚ة•sژ’…‚µ•ك—¸‚ئ‚µ‚½•ؤŒR‹@ڈوˆُ‚ج’آڈq‚ة‚و‚é‚ئپA”ق‚ç‚ح•êٹح‚©‚ç”ٹح‚µ‚½‚و‚¤‚إ‚ ‚éپB‚ئ‚·‚ê‚خپA“G‚ب‚ھ‚çپA“Vگ°‚ê‚ئŒ¾‚¤‚ׂ«‚¾پB‚±‚جژي‚جٹéگ}‚ً••‚¸‚邽‚ك‚ة‚حپAƒnƒڈƒC‚ًچU—ھ‚·‚éˆبٹO‚جچô‚ح‚ب‚¢پB‚»‚ج‚½‚ك‚ة‚حƒ~ƒbƒhƒE´پ\‚جچU—ھ‚ھ‘O’ٌ‚ئ‚ب‚éپBکAچ‡ٹح‘à‚ھƒ~ƒbƒhƒE´پ\‚ةچىگي‚ًژه’£‚·‚é——R‚àپA‚±‚±‚ة‚ ‚éپv‚»‚ê‚خ‚©‚è‚إ‚ب‚پA‚ح‚¶‚كƒ~ƒbƒhƒE´پ[چىگي‚ةژQ‰ء‚·‚邱‚ئ‚ً‹‘”غ‚µ‚ؤ‚¢‚½—¤ŒR‚àپAƒhƒٹƒbƒgƒ‹‚ج‹َڈPŒم‚ح“¯چىگي‚ةژQ‰ء‚·‚邱‚ئ‚ًژه’£‚·‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½پBˆê•ûپA—¤ŒR’·ٹ¯ƒXƒ`ƒ€ƒ\ƒ“‚حپA“ْ–{گl‚جژ©گ§گS‚ًژ¸‚ء‚½‚»‚ê‚ç‚ج“®‚«‚ًپA‹»–،گ[‚Œ©‚ؤ‚¢‚½پBپx
ˆê‹مژl“ٌ”NژlŒژڈ\”ھ“ْ‚ةٹ¸چs‚³‚ꂽƒh³پ[ƒٹƒbƒgƒ‹‘à‚ة‚و‚é‹َڈP‚ھŒ_‹@‚ئ‚ب‚ء‚ؤپA‹°œô‚µ‚½ژR–{Œـڈ\کZ‚ھƒ~ƒbƒhƒE´پ[ٹCگي‚ً‹چs‚µ‚½پA‚ئ‚¢‚¤‹طڈ‘‚«‚حژOکa“ْ‹L‚ًڈ‰‚ك‘½‚‚جگlٹش‚ھڈ‘‚¢‚ؤ‚¢‚éپBژ„‚à‚±‚ê‚ً‰L“غ‚ف‚ة‚µ‚ؤ‚¢‚½ژٹْ‚ھ‚ ‚ء‚½پB“P‰ٌ‚µ‚ؤ‚¨کl‚ر‚·‚éپBژR–{Œـڈ\کZ‚حˆê”NŒم‚ج“¯“ْپAڈˆŒY‚³‚ê‚éپBژlŒژڈ\”ھ“ْ‚ح“ْ•ؤ‹¤“¯‰‰ڈo‚ج‹L”O“ْ‚إ‚ ‚éپB
پw“ى‰_‚ج—L”\‚بچq‹َژQ–dŒ¹“cژہ’†چ²پiٹC•؛‚T‚Qٹْپj‚àپAƒ~ƒbƒhƒE´پ[چىگي‚ة‚حگ^ژىکp‚إ‚¤‚؟کR‚炵‚½•êٹحŒQ‚ًژd—¯‚ك‚éƒ`ƒƒƒ“ƒX‚ھ‚ ‚é‚ئچl‚¦‚ؤ‚¢‚½پBپuƒ~ƒbƒhƒE´پ[چىگي‚ًژہژ{‚·‚邱‚ئ‚إپAƒAƒپƒٹƒJژه—حٹح‘à‚ةŒˆگي‚ً‹—v‚·‚éƒ`ƒƒƒ“ƒX‚ھ‚ ‚é‚ئژv‚ء‚½‚ج‚إپAژ„‚حچىگي‚ةژ^گ¬‚µ‚½پv‚ئ”ق‚حڈq‚ׂؤ‚¢‚éپBکAچ‡ٹح‘à‚ھڈ«—ˆچىگي‚ئ‚µ‚ؤƒnƒڈƒCچU—ھ‚ًŒv‰و‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ً’m‚é‚ئپAŒ¹“c‚حƒ~ƒbƒhƒE´پ\‚ح‚»‚ج‘وˆê•à‚ئ‚µ‚ؤ‰؟’l‚ھ‚ ‚é‚ئژv‚ء‚½پB‚ھپA”ق‚حƒ~ƒbƒhƒE´پ[چىگي‚ة‚¨‚¯‚é—¤ڈمچىگي‚و‚è‚àٹCڈمچىگي‚ة‚و‚è‹‚¢ٹضگS‚ًژ‚ء‚ؤ‚¢‚½پBŒ¹“c‚جŒ©‚é‚ئ‚±‚ë‚ة‚و‚é‚ئپA“ى‰_‚ج‘ش“x‚ح‚ ‚ـ‚è‚ح‚ء‚«‚è‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½پB
“ى‰_‚جژQ–d’·‚ج‘گژ—²”V‰îپiٹC•؛‚S‚Pٹْپj‚ة‚و‚ê‚خ‘وˆêچq‹َٹح‘à–‹—»‚ج‘½‚‚حƒ~ƒhƒE´پ\چىگي‚ة”½‘خ‚إ‚ ‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤پB”قژ©گg‚»‚ج‹}گو–N‚إپAژں‚ج‚و‚¤‚ة’آڈq‚µ‚ؤ‚¢‚éپBپu‹@“®•”‘à‚حگ^ژىکpچىگي‚¢‚ç‚¢ٹe’n‚إٹqٹq‚½‚éگ¬Œ÷‚ًژû‚ك‚½‚ھپA“‹ڈوˆُ‚حŒ¸–ص‚µپAٹح‘DپAŒ}‚«‚حڈC—‚ً•K—v‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إپAژ„‚حƒ~ƒbƒhƒE´پ\چىگي‚ة”½‘خ‚إ‚ ‚ء‚½پBپEپEپE‚»‚ê‚خ‚©‚è‚إ‚ب‚پAƒ~ƒbƒhƒE´پ[“‡‚ًچU—ھ‚·‚邱‚ئ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‘½‘ه‚ج‹^–â‚ًژ‚ء‚ؤ‚¢‚½پBچىگيŒv‰و‚حکAچ‡ٹح‘àژi—ك•”‚إ‚·‚إ‚ةŒˆ’肳‚êپA‚ي‚ê‚ي‚ê‚ح‚»‚ê‚ً‚»‚ج‚ـ‚ـژَ‚¯“ü‚ê‚邱‚ئ‚ً‹—v‚³‚ꂽ‚ج‚إ‚ ‚ء‚½پv‚ئ‘گژ‚حڈq‚ׂؤ‚¢‚éپB“¯ژ‚ة”ق‚حپA‘وˆêچq‹َٹح‘à‘¤‚à‚ ‚ـ‚è’ïچR‚µ‚ب‚©‚½‚±‚ئ‚ً”F‚ك‚ؤ‚¢‚½پB”ق‚ح‚»‚ج’آڈq‚إپAپu‚ي‚ê‚ي‚ê‚حƒAƒپƒٹƒJ‚ً‰؛ژZ‚µپAڈڈگي‚جگ¬Œ÷‚إ–گS‚µ‚ؤ‚¢‚½پBٹ·Œ¾‚·‚ê‚خپA“G‚ھ‚½‚ئ‚¦ڈoŒ‚‚µ‚½‚ئ‚µ‚ؤ‚àپA—eˆص‚ةŒ‚–إ‚إ‚«‚é‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚½پBژ„‚ئ“¯‚¶ˆسŒ©‚إ‚ ‚ء‚½“ى‰_’·ٹ¯‚àپA”ق‚ج•”‘à‚ح‚¢‚©‚ب‚é”C–±‚ً‚à—§”h‚ةگ‹چs‚µ‚¤‚é‚ئگM‚¶‚ؤ‚¢‚½پv‚ئڈq‚ׂؤ‚¢‚éپBپx
‘گژ—²”V‰î‚ج•ƒگe‚حپAگ¬‚è‚·‚ـ‚µ“Vچc‰ئŒن—p’Bچà”´‚جڈZ—F–{ژذ—ژ–‚إ‚ ‚éپB‚¨–V‚؟‚ل‚ٌˆç‚؟‚ب‚ج‚©پA‘گژ‚ح‚©‚ب‚èچكˆ«ٹ´‚ة‹ى‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚إپAƒvƒ‰ƒ“ƒQ‚جƒCƒ“ƒ^ƒrƒ…پ[‚إ‚ح‚ذ‚½‚·‚çژ©Œبگ³“–‰»‚خ‚©‚肵‚ؤ‚¢‚éپB
پw“ى‰_‚جژQ–d’·‚ج‘گژ‚ج“ھ‚ة‚حپAپg“ٌ“e‚ً’ا‚¤‚à‚ج‚حˆê“e‚ً“¾‚¸پh‚ئ‚ج“ْ–{‚جŒ؟‚ھ‚±‚ر‚è‚آ‚¢‚ؤ‚¢‚½پB”ق‚ح‚±‚جŒ؟‚ھƒ~ƒbƒhƒE´پ\چىگي‚ج‘وˆêچq‹َٹح‘à‚ج”C–±‚ة“–‚ؤ‚ح‚ـ‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©پA‚ئگS”z‚µ‚ؤ‚¢‚½پBپuکAچ‡ٹح‘à–½—ك‚ة‚ح“ٌ‚آ‚ج–ع“I‚ھŒf‚°‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚½پBˆê‚آ‚حژه–ع“I‚إ‚ ‚éƒ~ƒbƒhƒE´پ\چU—ھ‚جگو–N‚ئ‚ب‚邱‚ئ‚إ‚ ‚èپA‚»‚ج‚ة‚ح“Gٹح‘à‚ھڈoŒ‚‚µ‚ؤ‚«‚½‚ب‚ç‚خپA“G‚ج‹@“®•”‘à‚ًŒ‚–إ‚·‚邱‚ئ‚إ‚ ‚ء‚½پB‚»‚ج’†‚إ‚àپA‘S”ت‚جچىگيŒv‰و‚©‚ç‚ف‚ؤپA‘وˆê‚ج–ع“I‚ةڈd“_‚ھ‚¨‚©‚ê‚ؤ‚¢‚½پB‚³‚ç‚ة“G‚جچq‹َٹî’n‚©‚ç‚جچUŒ‚‚àچl—¶‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚©‚ء‚½پBپEپEپEپE‚±‚ج“_‚ھژ„‚ھ‚à‚ء‚ئ‚àگS”z‚µ‚½‚ئ‚±‚ë‚إ‚ ‚ء‚½پB‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حپA‘وˆêچq‹َٹح‘à‚ح“ٌ“e‚ً’ا‚¤‚±‚ئ‚ً‹پ‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚½‚±‚ئ‚ة‚ب‚é‚©‚ç‚إ‚ ‚ء‚½پvپx
‘گژ—²”V‰î‚حژ©•ھ‚حˆ«‚‚ب‚¢پAکAچ‡ٹح‘àژi—ك•”‚جچىگي‚ھپg“ٌ“e‚ً’ا‚¤‚à‚ج‚حˆê“e‚ً“¾‚¸پh‚ئ‚¢‚¤’v–½“IŒ‡“_‚ًژ‚ء‚ؤ‚¢‚½‚©‚炾‚ئŒ¾‚¢‚½‚¢‚ج‚إ‚ ‚éپB‚µ‚©‚µ“ٌ“e‚ً’ا‚ء‚½‚±‚ئ‚حپA’v–½“IŒ‡“_‚إ‚ح‚ب‚¢پB‹َ•ê‚ً“ٌ‚آ‚ة•ھ‚¯‚ؤچى‹ئ‚·‚ê‚خچد‚قکb‚إ‚ ‚éپB’v–½“IŒ‡“_‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حپA‘S‚ؤ‚ج‹َ•ê‚إ“¯ژچى‹ئ‚إ•؛‘•‘•“]ٹ·‚³‚¹‚邱‚ئ‚إ‚ ‚éپB“]ٹ·‚µ‚½”ڑ’e‚ئ”ڑ‘•‚µ‚½”ٍچs‹@‚ً‚¸‚ç‚è‚ئ•ہ‚ׂؤپA‚³‚ ‚ا‚¤‚¼‚ئ”ڑŒ‚‚³‚¹‚邱‚ئ‚إ‚ ‚éپB
پwچىگيٹJژn‚ة“–‚½‚ء‚ؤ‚ح“ى‰_‚ج•âچ²‚ً‚à‚ء‚ئ‚à•K—v‚ئ‚·‚邱‚جٹْٹش‚ةپA‘گژ‚حڈم‹‚µ‚ؤپAگ^ژىکp‚إگيژ€‚µ‚½چq‹َ“‹ڈوˆُ‚ًپA“ءژêگِچq’ّ‚جڈوˆُ‚ئ“¯‚¶‚و‚¤‚ةپA“ٌ’iٹKگi‹‰‚³‚¹‚و‚ئڈم‘w•”‚ة‚¹‚ء‚آ‚¢‚ؤ‚¢‚½پBپx
’؛—ك‚ئ‚ح‚¢‚¦پA‘گژ‚حƒ„ƒ‰ƒZ‚ةŒ™‹C‚ھچ·‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ج‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢پB
پwژR–{‚حƒ~ƒbƒhƒE´پ\چىگي‚ة“ٌ•Sگاˆبڈم‚جٹس’è‚ً“®ˆُ‚·‚邱‚ئ‚ً—\’肵پA“¯“‡‚ة‘خ‚·‚éڈم—¤ٹJژn“ْپi‚m“ْپj‚ًکZŒژژµ“ْ‚ئŒˆ‚ك‚½پB‚m“ْ‚ح“ى‰_‚¨‚و‚ر‹ك“،‚ج•”‘à‚ھ•K—v‚ئ‚·‚éچىگيڈ€”ُٹْٹش‚ئپAڈم—¤چىگي‚ً—pˆس‚ة‚·‚éŒژ–¾‚جٹْٹش‚ًچl—¶‚µ‚ؤ’è‚ك‚ç‚ꂽپBچىگيŒv‰و‚ة‚و‚ê‚خپA‘وکZٹح‘àژi—ك’·ٹ¯ڈ¬ڈ¼‹P‹v’†ڈ«پiٹC•؛‚R‚Vٹْپj‚جگوŒ•”‘à‚جگِگ…ٹح‚ھپAکZ‚ھ‚”‚é“ٌ“ْ‚ـ‚إ‚ةƒ~ƒbƒhƒE´پ\‚ج“Œ•ûٹCˆو‚ةژOڈd‚جڈ£‰ْ–ش‚ً“WٹJ‚µپA“Gٹح‘à‚ج“®‚«‚ً’T‚邱‚ئ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½پBپx
پwژOڈd‚جڈ£‰ْ–شپx‚ًژl“ْ‚à’x‰„‚³‚¹‚ؤƒAƒپƒٹƒJٹح‘à‚ًƒXƒ‹پ[‚³‚¹‚ؤڈم‚°‚½ڈ¬ڈ¼‹P‹v‚حپAڈ؛کa“Vچc‚جچcچ@—اژq‚جڈ]’ي‚إ‚ ‚éپB
پ@
پwگي“¬‚ھژn‚ـ‚ء‚ؤ‚©‚ç“ى‰_‚ح‚·‚ׂؤ‚ًŒ¹“c‚ة‚ـ‚©‚¹‚ؤ‚¢‚½پB‚»‚ê‚ـ‚إ‚جگ¬Œ÷‚ح‚·‚ׂؤŒ¹“c‚ة‚و‚邱‚ئ‚ًٹmگM‚µ‚ؤ‚¢‚½“ى‰_‚ح‚ـ‚·‚ـ‚·‚»‚جژè’†‚جپgگآ‚¢’¹پh‚ةˆث‘¶‚µ‚ؤ‚¢‚½پBŒ¹“c‚ح‚ـ‚½‚ظ‚©‚ج–‹—»کA’†‚©‚ç‚ ‚éˆس–،‚إ‚حˆطŒh‚ج”O‚إ‘¸Œh‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½پBŒû‚ة‰“—¶‚ج‚ب‚¢ژز‚حŒِ‘R‚ئپA“ى‰_‚ج‹@“®•”‘à‚ًŒ¹“cٹح‘à‚ئŒؤ‚ٌ‚إ‚¢‚½‚ظ‚ا‚إ‚ ‚ء‚½پB‚ھپAŒ¹“c‚حŒ©‚ç‚ê‚邱‚ئ‚ًچD‚ـ‚ب‚©‚ء‚½‚µپAژ‚ة‚ح‹°‚낵‚¢‚±‚ئ‚¾‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚½پBپx
Œ¹“cژہ‚±‚»پA“ى‰_’‰ˆê‚ًک—گ‚³‚¹‚ؤ‚¢‚½گ^”ئگl‚إ‚ ‚éپB
پwƒ~ƒbƒhƒE´پ\چىگي‚ةٹض‚·‚éگ}ڈم‰‰ڈK‚ًڈI—¹‚·‚é‘O‚ةپAژR–{‚ح“ى‰_‚ة‘خ‚µ‚ؤپAƒAƒپƒٹƒJٹح‘à‚ئ‚‚ة‚»‚ج‹َ•ê‘à‚جچُ“G‚ة‚حچإ‘P‚ًگs‚‚·‚±‚ئپA‚»‚ê‚ة‘خ‚·‚锽Œ‚‚ج‚½‚ك“ى‰_‚جچUŒ‚‘à‚ج”¼گ”‚ح‹›—‹‘•”ُ‚ً‚·‚é‚و‚¤ژwژ¦‚µ‚½پB‚µ‚©‚µگو”CژQ–d‚جچ•“‡‚حچq‹َژQ–d‚جچ²پX–طڈ²’†چ²پiٹC•؛‚T‚ً‚Pٹْپj‚ةŒû“ھ‚إپAژR–{‚جژwژ¦‚ً–½—ك‚ةڈ‘‚«چ‚ق•K—v‚ح‚ب‚¢‚ئŒ¾‚ء‚½پBژQ–dٹش‚جˆسŒ©‚ج’²گ®پA‹Nˆؤ‚ج“_Œں‚حپAگي–±ژQ–d‚إ‚ ‚é“n•س‚جگE–±‚ج‚ذ‚ئ‚آ‚إ‚ ‚ء‚½‚ھپA”ق‚ح‚±‚ج‚±‚ئ‚ة‚آ‚¢‚ؤچ•“‡‚ـ‚½‚ح”قژ©گg‚ة‚آ‚¢‚ؤ•ظ–¾‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¢پB‚ھپAچ•“‡‚ج——R‚ح‚ح‚ء‚«‚肵‚ؤ‚¢‚éپB“ى‰_‚¨‚و‚ر‚»‚ج–‹—»‚حژR–{‚جژwژ¦‚ً’¼گع‚ة•·‚¢‚ؤ‚¢‚邵پA”ق‚ç‚ح‰ك‹ژ‚جٹJگي‚جŒoŒ±‚©‚çژR–{‚جˆسŒ©‚ھگ³“–‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ً’m‚ء‚ؤ‚¢‚é‚©‚çپAگيڈp“I‚بچו”‚ـ‚إچ،چX–½—ك‚ةڈ‘‚•K—v‚ح‚ب‚¢پA‚ئ‚¢‚¤‚ج‚إ‚ ‚ء‚½‚낤پBپx
‚±‚±‚ةƒSپ[ƒhƒ“پEƒvƒ‰ƒ“ƒQ‚جگ³‘ج‚ھ•‚‚«’¤‚è‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éپB‰½‚¹‘è–¼‚ھپwƒ~ƒbƒhƒE´پ\‚جٹïگصپx‚إ‚ ‚éپBƒvƒ‰ƒ“ƒQ‚حƒ„ƒ‰ƒZ‚ًپwٹïگصپx‚ةژd—§‚ؤڈم‚°‚éژg–½‚ً•‰‚ء‚ؤ‚¢‚éپB‚»‚ج‚½‚ك‚ةƒvƒ‰ƒ“ƒQ‚حپAŒـڈ\کZ‚ھ“G‹َ•ê‚جڈoŒ»‚ة”ُ‚¦‚ؤپwچUŒ‚‘¼‚ج”¼گ”‚ح‹›—‹‘•”ُ‚ً‚·‚é‚و‚¤ژwژ¦‚µ‚½پx‚±‚ئ‚ًپAپwگيڈp“I‚بچו”‚ـ‚إچ،چX–½—ك‚ةڈ‘‚•K—v‚ب‚ب‚¢پA‚ئ‚¢‚¤‚ج‚إ‚ ‚ء‚½‚낤پx‚ئ•د‚ب—‹ü‚ً‚±‚ث‚ؤپAچ•“‡‚ً•ظŒى‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚ ‚éپB‚f‚Q‚ج™ث‘ه‚بژj—؟‚âƒCƒ“ƒ^ƒrƒ…پ[‚ً‚à‚ئ‚ةوk•ظ‚ًکM‚·‚邱‚ئ‚حپAٹ®àّژه‹`ژزƒvƒ‰ƒ“ƒQ‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚³‚¼‚©‚µœxœ‚‚½‚éژv‚¢‚¾‚ء‚½‚±‚ئ‚¾‚낤پB
پwگ}ڈم‰‰ڈK‚ھڈI‚ي‚é‚ئپAچ•“‡‚ئ“n•س‚حکAچ‡ٹح‘à‚ج–½—ك‚ج‹NˆؤپA’²گ®‚ة‚©‚©‚ء‚½پB‚µ‚©‚µپA‚»‚ê‚ة‚ح“ى‰_•”‘à‚ج—‹Œ‚‘•”ُ‚¨‚و‚رگِگ…ٹح‚ھژUٹJگي‚جگ¼•û‚©‚ç‹Aچqچُ“G‚¹‚و‚ئ‚ج–¾ٹm‚بژwژ¦‚ھ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½پB‚±‚ê‚حڈd‘ه‚بŒë‚è‚إ‚ ‚ء‚½پA‚ئ“n•”‚ح”F‚ك‚ؤ‚éپB‚¾‚ھپAگِگ…ٹح‚ج–â‘è‚ح‚ق‚µ‚ëƒ^ƒCƒ~ƒ“ƒO‚جŒë‚è‚ئŒ¾‚¤‚ׂ«‚إ‚ ‚èپAŒ»’nژwٹِٹ¯‚ًچىگي‚جˆê‚©Œژ‚à‘O‚©‚ç‘©”›‚·‚é‚ج‚حپAگي‘ˆژw“±‚جŒœ–½‚بچô‚إ‚ح‚ب‚¢پA‚ئŒ¾‚¢“¾‚é‚إ‚ ‚낤پBپx
Œ¾‚¢“¾‚ب‚¢پBچُ“G‚حƒ~ƒbƒh´پ\چىگي‚ج–½‰^‚ً•ھ‚¯‚½ڈd‘ه‚بƒ|ƒCƒ“ƒg‚إ‚ ‚éپB–{ڈ‘‚جٹھ––‚إ‚حƒvƒ‰ƒ“ƒQژ©گg‚ھچُ“G‚ً‚¢‚¢‰ءŒ¸‚ة‚µ‚ؤ‚¢‚½‚±‚ئ‚ً”ٌ“پA‚»‚¤‚¢‚¤éپ‚è‚ھ”sˆِ‚¾‚ء‚½‚ئ‘چٹ‡‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚éپB‚²‚ـ‚©‚»‚¤‚²‚ـ‚©‚»‚¤‚ئ‚µ‚ؤژx—£–إ—ô‚بک_ژ|‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éƒvƒ‰ƒ“ƒQ‚حپA‚ظ‚ع•›“‡—²•Fڈَ‘ش‚ة‚ ‚é
پwپuچىگي‚جڈd“_‚ًƒAƒپƒٹƒJٹح‘à‚جŒ‚–إ‚ة‚¨‚‚ׂ«‚إ‚ ‚éپB‚»‚ج‚½‚ك‚ة‚حƒAƒٹƒ…پ[ƒVƒƒƒ“چUŒ‚•”‘à‚àƒ~ƒbƒhƒE´پ\‚ةŒü‚¯‚é‚ׂ«‚¾‚µپA‚ ‚ç‚ن‚éچىگي‰آ”\‚ب•؛—ح‚ًپA‚½‚ئ‚¦‘وŒـچ~چq‹َگي‘àپiگگ’كپ@مؤ’كپj‚ھژQ‰ء‚إ‚«‚é‚ج‚ً‘ز‚ء‚ؤ‚àپAƒ~ƒbƒhƒE´پ\‚ةڈW’†‚·‚ׂ«‚¾پv‚ئŒ¹“c‚حژه’£‚µ‚½پB‚»‚ê‚ة‘خ‚µ‚ؤچ•“‡‚حپAپuکAچ‡ٹح‘àژi—ك’·ٹ¯‚حˆê“xŒˆ‚ك‚½•ûگj‚ةژ×–‚‚ھ“ü‚邱‚ئ‚ً–]‚ـ‚ê‚ب‚¢پB‹@“®•”‘à‚جژه—v”C–±‚حƒ~ƒbƒhƒE´پ\چU—ھ‚جژx‰‡‚¾پv‚ئ“ڑ‚¦‚½پBپx
پwژ×–‚‚ھ“ü‚邱‚ئ‚ً–]‚ـ‚ê‚ب‚¢پx‚ج‚حپAŒـڈ\کZ‚إ‚ح‚ب‚چ•“‡‚إ‚ ‚éپBژل‚µ”ق‚ھ‚»‚جŒ¾—t’ت‚è‚ةکAچ‡ٹح‘àژi—ك’·ٹ¯‚جˆê“xŒˆ‚ك‚½•ûگj‚ً‹à‰ب‹تڈً‚ة‚µ‚ؤ‚¢‚½‚çپA‹›—‹‘•”ُ‚àچُ“G‚àˆêژڑˆê‹ه‚àکR‚炳‚¸–ء‹L‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ح‚¸‚¾پBپw‰^–½‚جŒـ•ھٹشپx‚ب‚ا‚ئ‚¢‚¤ƒ„ƒ‰ƒZ‚à‘¶چف‚¹‚¸پAکAچ‡ٹح‘à‚حٹyڈں‚µ‚ؤ‚¢‚éپBژ–ژہپAکAچ‡ٹح‘à‚حپw‰^–½‚جŒـ•ھٹشپxˆبٹO‚حٹ®ڈں‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إ‚ ‚éپB
پwˆê•ûپA‚»‚ج“–ژپAƒnƒڈƒC‚جƒjƒ~ƒbƒc‚ح‚ا‚¤‚µ‚½‚إ‚ ‚낤‚©پB”ق‚ح‚ا‚ج’ِ“x‚ة‚ـ‚إ‚±‚ê‚ç‚ج“ْ–{‚جٹéگ}‚ً’m‚ء‚ؤ‚¢‚½‚إ‚ ‚낤‚©پBڈ‰‚ك‚ج‚±‚ë”ق‚حڈî•ٌژQ–d‚جƒŒƒCƒgƒ“‚âگيڈpڈî•ٌژ؛’·‚جƒچƒ`ƒFƒtƒHپ[ƒg‚جڈَ‹µ”»’f‚ً‘S–ت“I‚ة‚حگM—p‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½پB“ْ–{‚جڈî•ٌ•”‚ھƒjƒZ‚جڈî•ٌ‚ً—¬‚µ‚ؤƒAƒپƒٹƒJ‚ً—ژ‚ئ‚µŒٹ‚ة“ü‚ê‚و‚¤‚ئ‚·‚éچô—ھ‰ئ‚à‚µ‚ê‚ب‚¢پA‚ئ”ق‚حژv‚ء‚ؤ‚¢‚½پB‚ھپA”ق‚حپAپuگ[‚چl‚¦‚½––پAژ„‚ح‚±‚ê‚ح–{“–‚¾‚ئژv‚¤‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½پv‚ئƒCƒ“ƒ^ƒrƒ…پ[‚إ“ڑ‚¦‚ؤ‚¢‚éپB‚»‚¤گS‚ةŒˆ‚ك‚é‚ئƒjƒ~ƒbƒc‚ح‹^‚ء‚½‚èپA–ہ‚ء‚½‚è‚·‚邱‚ئ‚ح‚ب‚©‚ء‚½پBپx
پu‚»‚¤‚¢‚¤ƒVƒiƒٹƒI‚ب‚ٌ‚¾‚وپv‚ئƒŒƒCƒgƒ“‚ة•·‚©‚³‚ê‚é‚ئپAƒjƒ~ƒbƒc‚ح‹^‚ء‚½‚è–ہ‚ء‚½‚è‚·‚邱‚ئ‚ح‚ب‚©‚ء‚½‚ج‚إ‚ ‚éپB‚±‚±‚©‚ç–{ٹi“I‚ب“ْ•ؤ‹¤“¯‰‰ڈo‚ھƒXƒ^پ[ƒg‚·‚éپB
پwŒـŒژ“ٌ“ْپi“ْ–{ژٹش‚إ‚حژO“ْپj‘هکa‚جٹحڈم‚إژR–{‚â‚»‚ج–‹—»‚ھگ}ڈم‰‰ڈK‚إچىگي‚ً—û‚ء‚ؤ‚¢‚邱‚ëپA”ق‚حƒ~ƒbƒhƒE´پ\‚ة”ٍ‚رپAˆê“ْ’†‚©‚©‚ء‚ؤƒ~ƒbƒhƒE´پ\ٹآڈت‚ًژ‹ژ@‚µ‚½پB‚آ‚¢‚إ“ْ–{‚ج‚ئ‚é‚إ‚ ‚낤چىگي‚¨‚و‚ر‚»‚ج•؛—ح‚جٹT—v‚ًڈq‚×پA‚إ‚«“¾‚éŒہ‚è‚ج‰‡ڈ•‚ً‚·‚邱‚ئ‚ً–ٌ‘©‚µ‚½پBپx
ƒjƒ~ƒbƒc‚حٹmگM”ئ‚ئ‚µ‚ؤچs“®‚ًٹJژn‚µ‚½‚ج‚إ‚ ‚éپB
پwŒـŒژŒـ“ْپAŒR—ك•”‘چ’·’·–ىڈCگg‚حژR–{‚ة‘خ‚µ‚ؤژں‚ج‚و‚¤‚ةژwژ¦‚µ‚½پBپuکAچ‡ٹح‘àژi—ك’·ٹ¯‚حپA—¤ŒR‚ئ‹¦—ح‚µپAگ¼•گƒAƒٹƒ…پ[ƒVƒƒƒ“—ٌ“‡‚ج—v’n‚¨‚و‚رƒ~ƒhƒE´پ\“‡‚ًچU—ھپAگè—ج‚·‚ׂµپvپx
‚±‚جچىگيژwژ¦‚ھپw‰^–½‚جŒـ•ھٹشپx‚جƒ„ƒ‰ƒZ‚ة•K—v•s‰آŒ‡‚¾‚ء‚½‚ج‚¾پBƒAƒٹƒ…پ[ƒVƒƒƒ“‚ة•گ—ح‚ً•ھژU‚µپAƒ~ƒbƒhƒE´پ\“‡‚جچU—ھ‚ة‘S”ڑŒ‚‹@‚ً“ٹ“ü‚³‚¹‚éپB‚³‚ç‚ةƒ~ƒbƒhƒE´پ\“‡‚ً“ٌژںچUŒ‚‚³‚¹پA‚»‚جچإ’†‚ة“G‹َ•ê‚ًڈoŒ»‚³‚¹‚éپB—F‰i‘هˆر‚ھپw‘و“ٌژںچUŒ‚‚ج•K—v‚ً”F‚قپx‚ئ‘—گM‚µ‚½‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حپA‚±‚ê‚حƒKƒZ‚إ‚ ‚éپBƒvƒ‰ƒ“ƒQژ©گg‚ھگ^‘ٹ‚ًڈ‘‚¢‚ؤ‚¢‚éپB‘و“ٌژںچUŒ‚‚ج‚½‚ك‚ة”ڑ’e‘•”ُ‚ً“]ٹ·‚³‚¹‚邽‚ك‚ةپA—F‰i‚ج‹ïگ\‚ً‘•‚ء‚½ƒ„ƒ‰ƒZ‚إ‚ ‚éپB‘و“ٌژںچUŒ‚—p‚ة‘•”ُ‚ً“]ٹ·‚³‚¹‚ؤ‚¢‚éچإ’†‚ة“G‹َ•ê‚ًڈoŒ»‚³‚¹پA‚³‚ç‚ة‚ـ‚½“]ٹ·‚³‚¹‚é‚ئ‚¢‚¤ڈَ‹µ‚ة‚·‚邽‚ك‚إ‚ ‚éپB‚±‚ê‚ة‹°چQ‚ً‚«‚½‚µ‚½“ى‰_‚ھ”ڑ’e‘•”ُ‚ً“ٌ“]ژO“]‚·‚é‚و‚¤‚ةپA–T‚إچ´‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ج‚ھ‘گژ—´”V‰î‚إ‚ ‚é‚ئژ„‚حٹmگM‚µ‚ؤ‚¢‚éپB‚±‚ê‚ة‚و‚ء‚ؤ‚ج‚فƒAƒپƒٹƒJ‚جٹïڈP‚حگ¬Œ÷‚µپAƒ‰ƒNƒ_‚ھƒnƒٹ‚جŒٹ‚ً’ت‚é‚و‚¤‚بپwڈں—کپx‚ً“¾‚½‚ج‚إ‚ ‚éپB
پw–{ڈ‘‚حژXŒèٹCٹCگي‚جڈعچׂًڈq‚ׂé‚à‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚çپA“¯ٹCگي‚ةٹض‚µ‹Lڈq‚·‚é‚ج‚حپA“¯ٹCگي‚ھƒ~ƒhƒE´پ\چىگي‚ة‚¢‚©‚ة‰e‹؟‚µ‚½‚©‚ةŒہ‚ç‚ê‚é‚ھپA‚»‚ج‰e‹؟‚ح‚«‚ي‚ك‚ؤڈd‚©‚آ‘ه‚إ‚ ‚ء‚½پBŒـŒژ”ھ“ْ‚ج’©پA‚ ‚ئ‚©‚çژXŒèٹCٹCگي‚ئŒؤڈج‚³‚ꂽ“ْ–{‚ئƒAƒپƒٹƒJ‚ج‹َ•êٹشƒ“‚¨ڈ‰‚جٹCگي‚ج–‹‚ھگط‚ء‚ؤ—ژ‚ئ‚³‚ꂽپB“ْ–{‚ھ’¾‚ك‚½‚ئ•ٌ‚¶‚½ƒTƒ‰ƒgƒK‚ح‚»‚جچ ƒVƒAƒgƒ‹‚ة‹ك‚¢ƒsƒ…پ[ƒ[ƒbƒgپEƒTƒEƒ“ƒh‚إڈC—’†‚إ‚ ‚ء‚½پB“ْ–{‚ھƒTƒ‰ƒgƒK‹‰‹َ•ê‚ًٹشˆل‚¦‚½‚ج‚حپA‚±‚ê‚إ“ٌ“x–ع‚إ‚ ‚ء‚½پB‚»‚ج”N‚جڈ‰‚ك“ْ–{‚جگِگ…ٹح‚ھƒŒƒLƒVƒ“ƒgƒ“‚ً’¾‚ك‚½‚ئ•ٌ‚¶‚½‚ھپA—‹Œ‚‚إ‘¹ڈ‚µ‚½‚ج‚حژہ‚حƒTƒ‰ƒgƒK‚¾‚ء‚½پB‚±‚جژ‚ج‘وŒـچq‹َگي‘à‚ج•ٌچگ‚حپA‚»‚جگي‰ت‚ً‰ك‘ه•]‰؟‚µ‚ؤ‚¢‚½پBˆê•ûپAƒŒƒLƒVƒ“ƒgƒ“‚ج”يٹQ‚à“ْ–{‚ھ•ٌ‚¶‚½‚و‚è‚à‚ح‚é‚©‚ةڈ‚ب‚©‚ء‚½پBگي‰ت‚ً‰ك‘ه•]‰؟‚µ‚½•ٌچگ‚ئٹَ–]“I‚بژvچl‚ةٹî‚أ‚¢‚ؤپA‘هکa‚جکAچ‡ٹح‘àژi—ك•”‚حپAŒـŒژŒـ“ْ‚©‚ç‚جˆêکA‚جگي“¬‚جگ¬‰ت‚ًژں‚ج‚و‚¤‚ةگ„’肵‚½پBپi—ھپjپi–َ’چپپژہچغ‚ة“G‚ة—^‚¦‚½‘¹ٹQ‚ئ‚جٹش‚ة‘هچ·‚ًگ¶‚¶‚½‚ج‚حپAژه‚ئ‚µ‚ؤƒ‰ƒoƒEƒ‹‚©‚çچىگي‚µ‚½ٹî’nچq‹َ•”‘à‚جگي‰ت•ٌچگ‚ھ‘S‚‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚و‚¢‚ظ‚اٹشˆل‚ء‚ؤ‚¢‚½‚©‚ç‚إ‚ ‚ء‚½پB‚ا‚¤‚µ‚ؤ‚»‚ٌ‚ب‚ة‘ه‚«‚‹¶‚ء‚½‚ج‚©پA‚¢‚ـ‚¾‚ة‚و‚‚ي‚©‚ç‚ب‚¢پjپx
گي‰ت•ٌچگ‚ھپw‘S‚‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚و‚¢‚ظ‚اٹشˆل‚ء‚ؤ‚¢‚½پx‚ج‚ةپAپw‚ا‚¤‚µ‚ؤ‚»‚ٌ‚ب‚ة‘ه‚«‚‹¶‚ء‚½‚ج‚©پA‚¢‚ـ‚¾‚ة‚و‚‚ي‚©‚ç‚ب‚¢پx‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حپAƒvƒچƒpƒKƒ“ƒ_ˆبٹO‚ة——R‚ب‚ا‚ب‚¢‚©‚炾پB—ل‚¦‚خ”’ڈFژںکY‚جŒأ‘ƒ‚إ‚ ‚éƒWƒƒƒpƒ“پEƒ^ƒCƒ€ƒYپEƒAƒ“ƒhپEƒAƒhƒ”ƒ@ƒ^ƒCƒUپ[‚حپAژ†ڈم‚إ‚³‚©‚ٌ‚ةŒض‘هگي‰ت•ٌچگ‚ًŒ–“`‚µ‚ؤگّ‚ء‚ؤڈ•’·‚³‚¹‚ؤ‚¢‚½پB‚±‚¤‚¢‚¤•—’ھ‚ً‰؛’n‚ةچى‚ء‚ؤ‚¨‚¢‚ؤپAŒم‚ةƒ~ƒbƒhƒE´پ\چىگي‚حٹCŒR‚جéپ‚èڈاŒَŒQ‚جژY•¨‚إ‚ ‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤ƒvƒچƒpƒKƒ“ƒ_‚ً—¬•z‚µ‚½‚ج‚إ‚ ‚éپB
پw“ى‰_‚ھƒAƒپƒٹƒJ‘¾•½—mٹح‘à‚جچىگيٹéگ}‚ً’m‚ç‚ب‚©‚ء‚½‚±‚ئ‚ًپA“ْ–{‚ح‚ ‚ـ‚è‹C‚ة‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½پB‚½‚ر‚½‚رˆّ—p‚·‚éƒWƒƒƒpƒ“پEƒ^ƒCƒ€ƒXپEƒAƒ“ƒhپEƒAƒhƒ”ƒ@ƒ^ƒCƒUپ[ژ†‚حŒـŒژ“ٌڈ\ژµ“ْ‚جژ†–ت‚ةپAژں‚ج‚و‚¤‚ةڈ‘‚¢‚ؤ‚¢‚éپBپu“G‚ھ–h‰q‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢چL‘ه‚ب‹وˆو‚ً’‚كپA‘¾•½—m‚ة–ع‚ً“]‚¶‚é‚ئپA“G‚ح‘¾•½—m‚ة‚ح‚²‚‹ح‚©‚ب•؛—ح‚µ‚©ڈ[“–‚إ‚«‚ب‚¢‚±‚ئ‚ة‹C•t‚‚ج‚إ‚ ‚éپB‘¾•½—m‚ة‚¢‚é“G‚جژc‘¶•؛—ح‚حپAگيٹحگ”گا‚¨‚و‚ر‹َ•êƒGƒ“ƒ^پ[ƒvƒ‰ƒCƒYپAƒzپ[ƒlƒbƒg‚ً’†گS‚ئ‚·‚é‚ة‚·‚¬‚ب‚¢‚إ‚ ‚낤پB‚»‚ج‹َ•ê•”‘à‚ھ‚¢‚©‚ب‚éچs“®‚ً‚·‚é‚©‚ھپAŒ»چف‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚à‚ء‚ئ‚à’چ–ع‚³‚ê‚é‚ئ‚±‚낾‚ھپA‚»‚ê‚ح‚ي‚ھ–³“Gٹح‘à‚ج“G‚إ‚ح‚ب‚¢پBژXŒèٹCٹCگي‚ً“]‹@‚ئ‚µ‚ؤ‘S‘¾•½—mٹCˆو‚ح‚ي‚ھ’éچ‘ٹCŒR‚ھژx”z‚·‚é‚ئ‚±‚ë‚ئ‚ب‚ء‚½‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚و‚¢پBپvپx
‚±‚¤‚¢‚¤ƒKƒZƒlƒ^‚ً’‡ٹش“à‚ةڈ‘‚©‚¹‚邱‚ئ‚ھپAژXŒèٹCٹCگي‚جپw‚ا‚¤‚µ‚ؤ‚»‚ٌ‚ب‚ة‘ه‚«‚‹¶‚ء‚½‚ج‚©پA‚¢‚ـ‚¾‚ة‚ي‚©‚ç‚ب‚¢پx‚‚ç‚¢‚ةپw‘S‚‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚و‚¢‚ظ‚اٹشˆل‚ء‚ؤ‚¢‚½پxŒض‘هگي‰ت•ٌچگ‚جŒّ—p‚جˆê‚آ‚إ‚ ‚éپB‚»‚ê‚ً‘گژژ©گg‚ھگّ‚ء‚ؤ‚¢‚½‚±‚ئ‚ح‘z‘œ‚ة“ï‚‚ب‚¢پB
پwژQ–d’·‚ج‘گژ‚ھپuŒـŒژ“ٌڈ\ژµ“ْ‚ة–LŒمگ…“¹‚ًڈoŒ‚‚µ‚½‚ئ‚«پA‚ي‚ھ‹@“®•”‘à‚ھگوگw‚ة—§‚ؤ‚خپAŒü‚©‚¤‚ئ‚±‚ë“G‚ب‚µ‚ئ‚جژ©گM‚ةˆى‚ê‚ؤ‚¢‚½پv‚ئŒ¾‚ء‚½‚ج‚حپA–³—‚ب‚©‚ء‚½پBپx
‘گژ‚حéپ‚èڈاŒَŒQ‚ًگپ’®‚·‚é–ً–ع‚¾‚©‚çپAپw–³—‚ب‚©‚ء‚½پxˆبٹO‚ة‰½‚ھ‚ ‚é‚ئ‚¢‚¤‚ج‚¾‚낤پB‚±‚±‚ةژٹ‚ء‚ؤ•£“c”ü’أ—Y‚ھ“ث”@پw‹}گ«’ژگ‚‰ٹپx‚ة‚©‚©‚éپB
پw‚»‚جچ پA”ٍچs‘à’·‚ج•£“c‚ح•aژ؛‚ة‰ç‚¹‚ء‚ؤ‚¢‚½پB‘½–Z‚ج“ْ‚ھ‘±‚¢‚½”ق‚حپA‚»‚ê‚و‚èڈ‚µ‘O‚ة‚³‚·‚و‚¤‚ب’ة‚ف‚ًٹ´‚¶پAٹî’n•t‹ك‚ج—¤ŒR•a‰@‚إگfژ@‚ًژَ‚¯‚½‚ئ‚±‚ëپA•ْڈc‚ة‚و‚é‚à‚ج‚ئگf’f‚³‚êپA•aژ؛‚ة“ü‚ê‚ç‚ꂽپB‚»‚ج–éپA•£“c‚حŒƒ’ة‚ةڈP‚ي‚ꂽپBڈ]•؛‚ھŒRˆم’·‚ًŒؤ‚ش‚ئپAŒRˆم’·‚حپu‚±‚ê‚ح‹}گ«–س’°‰ٹ‚¾پB‚·‚®ژèڈp‚ً‚·‚éپv‚ئ•£“c‚ةچگ‚°‚½پBپx
ژ„‚ح•£“c”ü’أ—Y‚ح‰¼•a‚ًژg‚ء‚ؤ‚¢‚ؤپA‹تˆنŒRˆم’·‚حƒOƒ‹‚إ‚ ‚é‚ئٹmگM‚µ‚ؤ‚¢‚éپBڈ¼–{ڈdژ،‚ھ’¥•؛ٹُ”ً‚ج‚½‚ك‚ة‰¼•a‚ة‚ب‚èپA•گŒ©‘¾کY‚ة‹U‚جگf’fڈ‘‚ًڈ‘‚¢‚ؤ‚à‚ç‚ء‚½‚ج‚ئ“¯‚¶ژèŒû‚إ‚ ‚éپB•£“c‚حژèڈp‚ب‚ا‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¢پB‚³‚ç‚ةŒ¹“cژہ‚àپw”x‰ٹپx‚ة‚©‚©‚éپBŒ¹“c‚ح‚¢‚©‚ة‚à‹ê‚µ‚°‚ةƒSƒzƒSƒz‚ئٹP‚ً‚·‚éƒ|پ[ƒY‚ج— ‚إپA“ى‰_‚ً‹؛‚µ‘±‚¯‚ؤ‚¢‚éپB‚»‚ê‚ھŒ¹“c‚ج”C–±‚إ‚ ‚éپB
پw•s‰^‚ً‰ءڈd‚·‚é‚©‚ج‚و‚¤‚ةپA•£“c‚ھژèڈp‚ًژَ‚¯‚ؤگ”“ْŒمپA‚±‚ٌ“x‚حŒ¹“c‚ھ”x‰ٹ‚ة‚©‚©‚èچ‚”M‚ًڈo‚µ‚ؤ•a‰ç‚µ‚½پB‚±‚ج“ٌڈd‚ج•s‰^‚حپA‚»‚ê‚ھگ^ژىکp‚ض‚ج“rڈم‚إ‚ ‚ء‚½‚ب‚ç‚خپA“ى‰_‚ًŒہ‚è‚ب‚”Y‚ـ‚µ‚½‚إ‚ ‚낤‚ھپA‚±‚ٌ‚ا‚ح”ق‚ح‚³‚ظ‚ا“®—h‚µ‚½‚و‚¤‚ة‚حŒ©‚¦‚ب‚©‚ء‚½پBˆê•ûپA‘T‚ة‹Aˆث‚µ‚ؤ‚¢‚½‘گژ‚ح‚¢‚آ‚à‚ج‚و‚¤‚ة•½گأ‚ً•غ‚ء‚ؤ‚¢‚½پBپx
•£“c‚ھپw‹}گ«–س’°‰ٹپx‚ة‚ب‚ء‚½‚ج‚àپAŒ¹“c‚ھپw”x‰ٹپx‚ة‚ب‚è‚©‚©‚ء‚½‚ج‚àپAƒ„ƒ‰ƒZ‚إ‚ ‚éپB•£“c”ü’أ—Y‚ھ‰¼•a‚ًژg‚ء‚ؤ—F‰iڈنژs‚ً‘م–ً‚ة—§‚ؤ‚½‚ج‚حپAƒ~ƒbƒhƒE´پ[ٹCگي‚إ”ٍچs‘à’·‚ً–±‚ك‚é‚à‚ج‚حژ€‚ت‰^–½‚ة‚ ‚é‚©‚ç‚إ‚ ‚éپB•£“c”ü’أ—Y‚ھ•aژ؛‚©‚甲‚¯ڈo‚µ‚ؤƒ„ƒ‰ƒZ‚ًٹدگي‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ج‚حپA•aژ؛‚ة‚¢‚½‚ç•آ‚¶چ‚ك‚ç‚ê‚ؤژ€‚ت‚©‚ç‚إ‚ ‚éپBŒ¹“c‚جپw”x‰ٹپx‚à“¯—l‚إ‚ ‚éپB“ى‰_•”‘à‚حپwŒ¹“cٹح‘àپx‚ئŒؤ‚خ‚ê‚é‚‚ç‚¢پAŒ¹“c‚ج‘¶چف‚ح‘ه‚«‚©‚ء‚½پBپw”x‰ٹپx‚ة‚ب‚ء‚ؤ‘وˆêگü‚جگي—ٌ‚©‚ç‘ق‚¢‚ؤپAگس”C‚جڈٹچف‚ً’ا‹y‚³‚ê‚ـ‚¢‚ئ‚·‚é•غگg‚جچô‚إ‚ ‚éپB
پwپuچ،‚â‚»‚جژ‚إ‚ ‚éپB–{“ْ‚جŒكŒمپA“ْ–{‚جٹح‘à‚ھچs“®‚ً‹N‚±‚µ‚½‚ئ‚جڈî•ٌ‚ھ‚ ‚ء‚½پB”ق‚ç‚ھ‚ي‚ê‚ي‚ê‚ج‚ا‚±‚ةچUŒ‚‚ً‚©‚¯‚ؤ‚‚é‚©‚ھپA‚ي‚ê‚ي‚ê‚ھژں‚ة’m‚é‚ׂ«‚±‚ئ‚¾پv‚ئ—¤ŒR’·ٹ¯ƒXƒ`ƒ€ƒ\ƒ“‚حŒـŒژ“ٌڈ\ژµ“ْ‚ج“ْ‹L‚ةڈ‘‚¢‚ؤ‚¢‚½پBپx
ƒXƒ`ƒ€ƒ\ƒ““ْ‹L‚ج–|–َپثپwچ،‚â‚»‚جژ‚إ‚ ‚éپB”ق‚ç‚ھ‚ي‚ê‚ي‚ê‚ج‚ا‚±‚ةچUŒ‚‚ً‚©‚¯‚ؤ‚‚é‚©‚ھپA‚ي‚ê‚ي‚ê‚ھژں‚ة’m‚é‚ׂ«‚±‚ئ‚¾‚©‚ç“–‘R’m‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚ ‚éپBپx
پw‘S‹@“®•”‘à‚¨‚و‚رٹeگي‘àژi—كٹ¯‚ة‘خ‚·‚éƒjƒ~ƒbƒc‚جچىگيŒv‰و‚حپA‚·‚إ‚ة—pˆس‚³‚ê‚ؤ‚¢‚جچُ“G‹@‚جŒ—ٹO‚ةˆت’u‚µپAˆê•ûپAƒ~ƒbƒhƒE´پ\‚©‚ç‚جچُ“G‹@‚حٹî’n‚©‚çژµ•Sٹ\‚ًچُ“G‚µ‚ؤپA“G‚و‚è‚àگو‚ة“ْ–{‚ج‹َ•ê•”‘à‚ً”Œ©‚·‚邱‚ئ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½پBپx
پwگو‚ة“ْ–{‚ج‹َ•ê•”‘à‚ً”Œ©‚·‚邱‚ئ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½پxƒVƒiƒٹƒI‚ة‚آ‚¢‚ؤپAگي‘ˆڈî•ٌ‹ا’·‚جƒŒƒCƒgƒ“‚حŒم‚ة’کڈ‘‚ج’†‚إڈd‘ه”Œ¾‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚éپB”ق‚ç“ْ–{‚جˆأچ†•¶‚ج‚`‚e‚ھ‰½‚ًژw‚·‚ج‚©’T‚낤‚ئ‚µ‚ؤپAپwƒ~ƒbƒhƒE´پ\‚ة‚حگ^گ…‚ھ•s‘«‚µ‚ؤ‚¢‚éپx‚ئ‚¢‚¤•½•¶‚ً‘إ“d‚µ‚ؤم©‚ًژdٹ|‚¯‚½ˆêŒڈ‚حپAچى‚èکb‚¾‚ئڈطŒ¾‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚ ‚éپB
http://homepage2.nifty.com/ijn-2600/samejima.htm—l‚و‚èˆب‰؛“]چعپB
پwپuƒ~ƒbƒhƒE´پ\“‡‚حگ…•s‘«پv‚ئˆà‚¤ƒjƒZ“d•ٌ‚ً•½•¶پi‚ذ‚ç‚ش‚فپj‚إ”گM‚µ‚ؤپu‚`‚eپv‚ھƒ~ƒbƒhƒE´پ\“‡‚ج’n“_•„ژڑ‚إ‚ ‚éژ–‚ًٹm”F‚µ‚½‚ئˆê”ت‚ةگM‚¶‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é—L–¼‚بکb‚ھ‚ ‚éپB“–ژ–ژز‚إ‚ ‚é•ؤ‘¾•½—mٹح‘àڈî•ٌژQ–d‚جƒŒƒCƒgƒ“’†چ²‚ح’کڈ‘‚ج’†‚إپuƒ~ƒbƒhƒE´پ\‚ة‚آ‚¢‚ؤڈ‘‚¢‚½‘S‚ؤ‚ج—ًژj‰ئ‚ھ‚±‚جŒڈ‚ةڈA‚¢‚ؤ‚ج‰ًژك‚ًژو‚èˆل‚ض‚ؤ‚¢‚éپv‚ئ’f’è“I‚ةڈq‚ׂؤ‚¢‚éپB‚µ‚©‚µ•ؤٹCŒR‚ھٹ‚‚àپu‚`‚eپv‚ًƒ~ƒbƒhƒE´پ\“‡‚ج’n“_•\ژ¦‚ةژg‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚ح‹ô‘R‚جˆê’v‚ئ‚ح‚ن‚ض‰½‚©‰^–½“Iˆأژ¦‚ًٹ´‚¶‚³‚¹‚éپBپx
‰^–½“Iˆأژ¦‚ًٹ´‚¶‚³‚¹‚éپ¨‹¤’ت‚جƒVƒiƒٹƒI‚ج‘¶چف‚ًٹ´‚¶‚³‚¹‚éپB
پu‚`‚eپv‚ً’n“_•„ژڑ‚ة‚µ‚ؤ‚¢‚é“ْ•ؤ‹¤’ت‚جƒVƒiƒٹƒI‚ھ‘¶چف‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إ‚ ‚éپB
پ@
ƒSپ[ƒhƒ“پEƒvƒ‰ƒ“ƒQ‘OŒfڈ‘‘±‚«
پwƒjƒ~ƒbƒc‚حƒŒƒCƒgƒ“‚ةŒü‚©‚ء‚ؤپAپu“G‚ئگعگG‚·‚é‚ج‚ح‚¢‚آپA‚ا‚±‚إ‚ئچl‚¦‚é‚©پv‚ئگu‚ث‚½پB‚»‚ê‚ة‘خ‚µ‚ؤƒŒƒCƒgƒ“‚حپAپu“G‚ئ‚جچإڈ‰‚جگعگG‚حپAکZŒژژl“ْŒك‘OکZژپiƒ~ƒbƒhƒE´پ\ژٹشپjپAƒ~ƒbƒhƒE´پ\‚©‚ç‚ج•ûˆتژO•S“ٌڈ\Œـ“xپi–kگ¼پjپA‹——£•Sژµڈ\Œـٹ\‚ج’n“_‚إپA‚ي‚ھƒ~ƒbƒhƒE´پ\‚©‚ç‚جچُ“G‹@‚ة‚و‚ء‚ؤ‚³‚ê‚é‚ئژv‚¢‚ـ‚·پv‚ئ“ڑ‚¦‚½پBپx
چו”‚ةژٹ‚é‚ـ‚إƒVƒiƒٹƒI‚حŒˆ‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚½پBƒAƒrپ[پEƒEµپ[ƒoپ[ƒO‚ج‹àŒ¾‚ج‚و‚¤‚ةپAگ_‚حچו”‚ةڈh‚é‚ج‚إ‚ ‚éپB
پw‰ï‹c‚ة—ٌگب‚µ‚½–تپX‚حپA‚»‚ج‰ï‹c‚ح—⌵‚بژ–ژہ‚ً—âگأ‚ةŒں“¢‚·‚ׂ«‚à‚ج‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ً’mژ»‚µ‚ؤ‚¢‚½پBƒ~ƒbƒhƒE´پ\‚ً“ْ–{‚ةگè—ج‚³‚ꂽ‚ب‚ç‚خپAƒnƒڈƒC‚ة‘خ‚µ‚ؤ“ْ–{‚ج“S‚ج–‚è‚ً‚آ‚¯‚½–î‚ھ‚آ‚«‚آ‚¯‚ç‚ꂽ‚à“¯‘R‚إ‚ ‚낤پA‚ئٹ´‚¶‚ؤ‚¢‚½پB‚»‚¤‚ب‚ê‚خپAƒnƒڈƒC‚ھچU—ھ‚³‚ê‚邱‚ئ‚ح’P‚ب‚éƒtƒچƒbƒN‚إ‚ح‚ب‚پA“ْ–{‚ھٹïڈP‚إ‚ح‚ب‚‹ڈP‚إƒAƒپƒٹƒJ–{“y‚ً‹َڈP‚µ‚ؤ‚àپAƒAƒپƒٹƒJ‚ح‚»‚ê‚ً‘jژ~‚إ‚«‚ب‚¢‚إ‚ ‚낤‚±‚ئ‚حپA’P‚ب‚錶‘z‚إ‚ح‚ب‚¢‚إ‚ ‚낤پB—ٌگب‚µ‚½’N‚à‚ھپA“ْ–{‚ح—\‘z‚à‚µ‚ب‚¢چUŒ‚‚ً‰¼ژط‚ب‚‚©‚¯‚ؤ‚‚éژè‹‚¢‹—ح‚ب“G‚¾‚ئپAگg‚ة‚µ‚ف‚ؤٹ´‚¶‚ؤ‚¢‚½پBپx
ƒAƒپƒٹƒJ‘¤‚حƒ~ƒbƒhƒE´پ\چىگي‚ًگ³“–‚ة•]‰؟‚µ‚ؤ‚¢‚éپBŒمگ¢“ْ–{گl‚ھ‚±‚ê‚ً‚ع‚땳‚ةŒ¾‚¤‚ج‚حپAƒvƒچƒpƒKƒ“ƒ_‚ة‚و‚éگô”]‚إ‚ ‚éپB
پwƒjƒ~ƒbƒc‚حژں‚ج‚و‚¤‚ة‹’²‚µ‚½پBپuڈî•ٌ‚ة‚و‚ê‚خپA“ْ–{‚ج‹َ•ê•”‘à‚حƒ~ƒbƒhƒE´پ\‚ج–kگ¼•û‚©‚点‚ـ‚ء‚ؤ—ˆ‚é‚ئژv‚ي‚ê‚éپBƒAƒپƒٹƒJ‚جژ·‚é‚ׂ«چô‚ح‚±‚ê‚ةٹïڈP‚ً‚©‚¯‚邱‚ئ‚¾پBƒAƒپƒٹƒJٹح‘à‚ح“G‚ئƒ~ƒbƒhƒE´پ\‚جٹش‚ة‹²‚ـ‚ê‚ؤ‚ح‚ب‚ç‚ب‚¢پB‘S—ح‚ًگs‚‚µ‚ؤپA“G‚ج—ƒ‘¤‚©‚çپA‚»‚ê‚àگوژè‚ً‚ئ‚ء‚ؤپAچUŒ‚‚ً‚©‚¯‚ب‚‚ؤ‚ح‚ب‚ç‚ب‚¢پvپB‚±‚جگي–@‚جƒJƒM‚حٹïڈP‚ھگ¬Œ÷‚·‚é‚©‚ا‚¤‚©‚ة‚©‚©‚ء‚ؤ‚¢‚½پB—ٍگ¨‚بƒtƒŒƒbƒ`ƒƒپ[‚¨‚و‚رƒXƒvƒ‹پ[ƒAƒ“ƒX‚ج•”‘à‚ھپAگqڈي‚بگv‘¬گ«‚ة–R‚µ‚¢چUŒ‚‚ةڈo‚½‚ب‚ç‚خپAژS”s‚ةڈI‚ي‚é‚إ‚ ‚낤پBپx
ƒvƒ‰ƒ“ƒQ‚ج•¶ڈح‚ً“Yچي‚µ‚ؤ‚¨‚±‚¤پB
پw‚±‚جگي–@‚جƒJƒM‚ح“G‹َ•ê‚ج‘S‚ؤ‚جچb”آڈم‚ة”ڑ‘•‚µ‚½”ٍچs‹@‚ھگ®—ٌ‚µ‚ؤ‚¢‚éڈَ‘ش‚ةٹïڈP‚ھگ¬Œ÷‚·‚é‚©‚ا‚¤‚©‚ة‚©‚©‚ء‚ؤ‚¢‚½پBگqڈي‚ب–d—ھگ«‚ة–R‚µ‚¢چUŒ‚‚ةڈo‚½‚ب‚ç‚خژS”s‚ةڈI‚ي‚é‚إ‚ ‚낤پxپB
ƒXƒvƒ‹پ[ƒAƒ“ƒXƒgƒtƒŒƒbƒ`ƒƒپ[‚ھچ‡—¬‚·‚é’n“_‚حƒjƒ~ƒbƒc‚ة‚و‚ء‚ؤپwƒ‰ƒbƒNپEƒ|ƒCƒ“ƒgپx‚ئ–¼•t‚¯‚ç‚ꂽپBپwچK‰^‚ج’n“_پx‚ئ‚¢‚¤ˆس–،‚ج–d—ھ’n“_‚إ‚ ‚éپB
ƒvƒ‰ƒ“ƒQ‘±‚«
پw“–‘R‚ج‚±‚ئ‚¾‚ھپAƒtƒŒƒbƒ`ƒƒپ[‚ئƒXƒvƒ‹پ[ƒAƒ“ƒX‚ھ‚à‚ء‚ئ‚à–]‚ٌ‚¾‚ج‚حپAگوگ§‚ً‚©‚¯‚ؤپA“ى‰_•”‘à‚ج”ٍچs‹@‚ھ•êٹح‚ج”ٍچsچb”آ‚ة•ہ‚ٌ‚إ‚¢‚é‚ئ‚«‚ةچUŒ‚‚ً‚©‚¯‚邱‚ئ‚إ‚ ‚ء‚½پBچq‹َڈoگg‚جژwٹِٹ¯‚إ‚ ‚ء‚ؤ‚àپA‚±‚ج‚و‚¤‚بڈuٹش“I‚بƒ^ƒCƒ~ƒ“ƒO‚ًŒˆ‚ك‚é‚ج‚حپAژٹ“ï‚ج‚±‚ئ‚إ‚ ‚ء‚½‚إ‚ ‚낤پBˆê‹مژl“ٌ”N‚ةڈo‚³‚ꂽƒٹƒ|پ[ƒg‚إپAƒjƒ~ƒbƒc‚حژں‚ج‚و‚¤‚ةڈq‚ׂؤ‚¢‚éپBپu‚ي‚ھ‹َ•ê‘à‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚±‚êˆبڈم‚ب‚¢”÷–‚بƒ^ƒCƒ~ƒ“ƒO‚ً•K—v‚ئ‚·‚é‚«‚ي‚ك‚ؤچ¢“ï‚بڈَ‹µ‚إ‚ ‚ء‚½پvپx
–{—ˆ‚ب‚ç‚خپwژٹ“ï‚ج‚±‚ئ‚إ‚ ‚ء‚½‚إ‚ ‚낤پxپwڈuٹش“I‚بƒ^ƒCƒ~ƒ“ƒOپxپw‚±‚êˆبڈم‚ب‚¢”÷–‚بƒ^ƒCƒ~ƒ“ƒOپx‚ً‘nڈo‚·‚邱‚ئ‚ھپAƒ~ƒbƒhƒE´پ\‚جƒ„ƒ‰ƒZ‚جٹل–ع‚إ‚ ‚éپBپwڈuٹش“Iپx‚ئŒ`—e‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپwƒ^ƒCƒ~ƒ“ƒOپx‚حپAژہچغ‚ة‚ح“ٌژٹش”¼‚ج•‚ھ‚ ‚ء‚½پBپw‚±‚êˆبڈم‚ب‚¢”÷–‚بƒ^ƒCƒ~ƒ“ƒOپxپA‚·‚ب‚ي‚؟‘S‚ؤ‚ج“G‹َ•ê‚جچb”آڈم‚إ•؛‘•“]ٹ·‚³‚¹‹}چ~‰؛”ڑŒ‚‚·‚é‚ـ‚إ”ٹح‚³‚¹‚ب‚¢پwƒ^ƒCƒ~ƒ“ƒOپx‚ًŒ»ڈo‚·‚é‚ـ‚إپA“ٌژٹش”¼‚©‚©‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚ ‚éپB
•؛‘•“]ٹ·‚ً‚·‚ׂؤ‚ج‹َ•ê‚إچs‚ب‚ي‚¹‚é‚ة‚حپAƒ~ƒbƒhƒE´پ\“‡چU—ھ‚©‚ç‹Aٹز‚µ‚½چUŒ‚‘à‚ً’…ٹح‚³‚¹‚ؤ‚¨‚•K—v‚ھ‚ ‚éپBچ¬—گڈَ‘ش‚ج’†پA“ٌژٹشˆبڈم‚à‚©‚¯‚ؤپwڈuٹش“I‚بƒ^ƒCƒ~ƒ“ƒOپx‚ھ—pˆس‚³‚ꂽ‚ج‚إ‚ ‚éپBŒہ‚è‚ب‚•‚ھ‚ ‚éپwڈuٹش“Iƒ^ƒCƒ~ƒ“ƒOپx‚ب‚ج‚إ‚ ‚éپB‚»‚جچإ‘ه‚جŒˆ‚كژè‚حƒ~ƒbƒhƒE´پ\“‡‚ج‘و“ٌژںچUŒ‚‚ً—F‰i‘هˆر‚ھ‹ïگ\‚µپA“ى‰_‚ھ‚»‚ê‚ًŒˆˆس‚µ‚½‚ئ‚¢‚¤ƒ|ƒCƒ“ƒg‚ة‚ ‚éپB‘Oڈq‚µ‚½‚ھ‚±‚جپw—F‰i‘هˆر‚ج‹ïگ\پx‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حگس”C“]‰إ‚جƒKƒZ‚ث‚½‚إ‚ ‚éپB
پw‘à’·‚ج—F‰i‚ھ”ي’e‚µ‚½‚»‚جڈو‹@‚ً‚ب‚¾‚ك‚ب‚ھ‚ç‹Aٹح‚ج“r‚ة‚آ‚¢‚½ژپA”ق‚جچUŒ‚‘à‚ھƒ~ƒbƒhƒE´پ\‚ة‚ا‚ꂾ‚¯‚ج‘¹ٹQ‚ً—^‚¦‚½‚©پAگ³ٹm‚ة‚ح’m‚ç‚ب‚©‚ء‚½پB”ق‚ح‚»‚جŒم‚جٹCگي‚إگيژ€‚µ‚½‚ج‚إپA”ق‚ھƒ~ƒbƒhƒE´پ\‚ج‘¹ٹQ‚ً‚ا‚¤Œ©‚½‚©پA’m‚邱‚ئ‚ح‚إ‚«‚ب‚¢پB‚ھپA—F‰i‚ح–¾‚ç‚©‚ة‚»‚جچUŒ‚‚جگ¬‰ت‚ة–‘«‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½پB”ق‚ج•”‘à‚ح‹—ح‚¾‚ئژv‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚½“G‚ج”ڑŒ‚‘à‚¨‚و‚رچُ“G‘à‚ةڈo‰ï‚ي‚ب‚©‚ء‚½‚µپAچq‹َٹî’n‚جٹٹ‘–کH‚ح‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا–³ڈ‚ج‚و‚¤‚إ‚ ‚ء‚½پB‚ـ‚½پA‚»‚ج‘خ‹َ‰خٹي‚ح‚ـ‚¾گ·‚ٌ‚ةŒ‚‚؟ڈم‚°‚ؤ‚¢‚½پB“ْ–{‚جڈم—¤•”‘à‚ھژèگô‚¢”½Œ‚‚ة‰ï‚¤‚ج‚حٹmژہ‚إ‚ ‚ء‚½پB—F‰i‚ح‚»‚¤Œ‹ک_‚µ‚½‚ةˆل‚¢‚ب‚©‚ء‚½پB”ي’e‚إ‘—گM‹@‚ًژg—p‚·‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ب‚‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إپA”ق‚حڈ¬‚³‚بچ•”آ‚ة’تگM•¶‚ًڈ‘‚«پA‚»‚ê‚ً“ٌ”ش‹@‚ج‹´–{•q’j‘هˆرپiٹC•؛‚U‚Uٹْپj‚ةچ·‚µڈo‚µپA”ق‚ج–¼‘O‚إ‘—گM‚·‚é‚و‚¤–½‚¶‚½پBژٹش‚حŒك‘Oژµژ‚إ‚ ‚ء‚½پBپu‘و“ٌژںچUŒ‚‚ج—v‚ ‚èپvپx
ڈطŒ¾‚µ‚½‚ج‚ھ—F‰iژ©گg‚إ‚ح‚ب‚پA‹´–{•q’j‘هˆر‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éپBژ„‚ح‚±‚êژ©‘ج‚ھs‘¢‚إ‚ ‚é‚ئچl‚¦‚ؤ‚¢‚éپB—F‰i‚حچ•”آ‚ةڈ‘‚¢‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚µپA‹´–{•q’j‘هˆر‚à‘إ“d‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¢پB
پw“ى‰_‚ھ—F‰i‚جپu‘و“ٌژںچUŒ‚‚ج—v‚ ‚èپv‚ج“d•ٌ‚ًژَگM‚µ‚½‚ج‚ئپAƒ~ƒbƒhƒE´پ\‚©‚ç‚ج‚s‚a‚e‚¨‚و‚ر‚aپ|‚Q‚U‘à‚ھ‹›—‹چUŒ‚‚ًٹJژn‚µ‚½‚ج‚حپA‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا“¯ژ‚إ‚ ‚ء‚½پB‚»‚ê‚حپA‚ ‚½‚©‚à—F‰i‚ج“d•ٌ‚جˆس–،‚·‚é‚ئ‚±‚ë‚ًژہڈط‚·‚é‚©‚ج‚و‚¤‚إ‚ ‚ء‚½پB‚±‚جژ“_‚إ‚حپAƒAƒپƒٹƒJ‚جٹCڈم•؛—ح‚ھ‹ك‚‚ة‚¢‚é‚ئ‚¢‚¤’›Œَ‚ًپA“ى‰_‚ح‘S‚“¾‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½پB‚»‚جژ‚ـ‚إ‚ة‚حپAچُ“G‹@‚ح—\’肳‚ꂽچُ“Gگü‚جگو’[‚ة“’B‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ح‚¸‚¾‚ھپA‚ـ‚¾‰½‚ج•ٌچگ‚à‚ب‚©‚ء‚½پB‚»‚±‚إ“ى‰_‚حپA—F‰i‚جˆسŒ©‹ïگ\‚ة‚»‚ء‚ؤپAƒ~ƒbƒhƒE´پ\‚ة‘خ‚µ‚ؤ‘و“ٌژں‚جچUŒ‚‚ً‰ء‚¦‚邱‚ئ‚ةŒˆ’肵‚½پBپx
‚±‚ê‚ھ‘هچ¬—گ‚جڈکڈح‚إ‚ ‚éپB
پw‚±‚ج“ى‰_‚جŒˆ’è‚حپA‘½‚‚ج‚±‚ئ‚ً‘هژٹ‹}‚ةٹ®گ¬‚·‚邱‚ئ‚ً—v‹پ‚·‚é‚à‚ج‚إ‚ ‚ء‚½پB“Gٹح‘à‚ً”Œ©‚µ‚½ژ‚ة”ُ‚¦‚ؤپAگشڈé‚ئ‰ء‰ê‚جچb”آڈم‚ةڈ€”ُ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é—‹Œ‚‹@‚ئپA”ٍ—´‚ئ‘“—´‚جچb”آڈم‚جٹح”ڑ‘à‚ج•؛‘•‚ًپAٹح‘DچUŒ‚—p‚©‚ç—¤ڈمچUŒ‚—p‚ة“]‘•‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢پB‚»‚ج‚½‚ك‚ة‚حپA”ٍچsچb”آڈم‚ةڈ€”ُ‚³‚ꂽ‘S‹@‚ًپAˆê’U‚»‚جٹi”[Œة‚ةچ~‚낵‚ؤپA—‹Œ‚‹@‚ح‹›—‹‚ً—¤—p”ڑ’e‚ةپAٹح”ڑ‹@‚ح‚»‚ج”ڑ’e‚ًٹح‘DچUŒ‚—p‚©‚ç—¤ڈمچUŒ‚—p‚ج‚à‚ج‚ةژو‚èٹ·‚¦‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢پB‚»‚ج“]ٹ·چى‹ئ‚ح‚ا‚ٌ‚ب‚ة‹}‚¢‚إ‚à“ٌژٹشˆبڈم‚ً—v‚·‚é‚ج‚إ‚ ‚éپB‚µ‚©‚àپA“G‹@‚ھƒ~ƒbƒhƒE´پ\‚ة‹A’…‚µ‚½‚ئ‚±‚ë‚ً‘_‚ء‚ؤچUŒ‚‚ً‚©‚¯‚邽‚ك‚ة‚حپAˆêچڈ‚ج—P—\‚à‹–‚³‚ê‚ب‚¢پBپx
ˆêچڈ‚ج—P—\‚à‹–‚³‚ê‚ب‚¢پA‚³‚à‚ب‚¢‚ئ‚ئ‚ٌ‚إ‚à‚ب‚¢‚±‚ئ‚ة‚ب‚éپA‚ئ“ى‰_‚ً‹؛‚µ‚½‚ج‚ح‘گژ—²”V‰î‚¾‚낤‚©Œ¹“cژہ‚¾‚낤‚©پB
پwŒ¹“c‚ح‹}‚¢‚إگMچ†•¶‚ً‹Nˆؤ‚µ‚½پBپu‘و“ٌژںچUŒ‚‘à‚ج•؛‘•‚ً—¤ڈمچUŒ‚—p‚ئ‚¹‚وپvپB“ى‰_‚ھ‚±‚ج–½—ك‚ً‚»‚ج‹َ•ê‚ة”گM‚µ‚½‚ج‚حŒك‘Oژµژڈ\Œـ•ھ‚إ‚ ‚ء‚½پB‚±‚جˆسژvŒˆ’肱‚»‚حپAڈيژ‚»‚ج“‹چع‹@‚ج”¼گ”‚ً—‹‘•‚ة‚·‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ھپA‹@“®•”‘à‚ج–½—ك‚ة–¾ژ¦‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚±‚ئ‚ً’m‚ء‚½چ•“‡‚ئ“n•س‚ھŒxچگ‚µ‚½‚ئ‚±‚ë‚ج‚à‚ج‚إ‚ ‚ء‚½‚ھپAŒ¹“c‚ح‚»‚ج‚و‚¤‚بچd’¼‚µ‚½چl‚¦•û‚ة”½ک_‚µ‚ؤپAژں‚ج‚و‚¤‚ةŒ¾‚ء‚ؤ‚¢‚éپBپu‚»‚ج‚و‚¤‚بچl‚¦•û‚ة‚±‚¾‚ي‚é‚ئپA“K“–‚ب“G‚ھ”Œ©‚³‚ê‚ب‚¢Œہ‚èپAچUŒ‚•؛—ح‚ج”¼گ”‚ھ—LŒّ‚ةژg‚ي‚ê‚ب‚¢‚±‚ئ‚ة‚ب‚éپBڈ‚ة‚و‚ء‚ؤپAŒˆ’è‚ح‚³‚ê‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢پvپx
پw‚ـ‚½پA‘وˆêچq‹َٹح‘àژQ–d‚ج‘گژ‚àژں‚ج‚و‚¤‚ةŒ¾‚ء‚ؤ‚¢‚éپBپuژR–{’·ٹ¯‚ھ‘وˆêچq‹َٹح‘à‚ج•؛—ح‚ج”¼گ”‚ًپA“G‚ج‹َ•ê‘à‚ة‘خ‚µ‚ؤ”ُ‚¦‚é‚و‚¤–]‚ٌ‚إ‚¨‚ç‚ê‚邱‚ئ‚حپA“ى‰_’·ٹ¯‚à‚»‚ج–‹—»‚à‚و‚ڈ³’m‚µ‚ؤ‚¢‚½پBژ–ژہپAڈ‚ج‹–‚·Œہ‚èپA‚»‚¤‚µ‚ؤ‚¢‚½پB‚ھپA“G‚جƒ~ƒbƒhƒE´پ\ٹî’n‚جچq‹َ•؛—ح‚ھ‚ي‚ê‚ي‚ê‚ة‘خ‚µ‚ؤچUŒ‚‚ًٹJژn‚µپA“G‚ج‹َ•ê•”‘à‚ھ‚ـ‚¾”Œ©‚³‚ê‚ب‚¢ڈ‚إ‚حپA‚¢‚é‚ج‚©‚¢‚ب‚¢‚ج‚©‚ي‚©‚ç‚ب‚¢“G‚ة‘خ‚µ‚ؤپA‚»‚ج•؛—ح‚ج”¼گ”‚ً–³ٹْŒہ‚ةچT’u‚µ‚ؤ‚¨‚‚ج‚حپA‘Oگü‚جژwٹِٹ¯‚ئ‚µ‚ؤپA‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‘د‚¦‚ç‚ê‚ب‚¢‚±‚ئ‚إ‚ ‚ء‚½پv‚½‚ئ‚¦پA‚»‚جŒˆ’è‚ھŒم‚إ–â‘è‚ة‚ب‚ء‚½‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢‚ھپAپu‚ ‚ج“–ژ‚جڈ‚إ‚حپA“ى‰_’·ٹ¯‚جŒˆ’è‚حگ³“–‚إ‚ ‚ء‚½پv‚ئ‘گژ‚ح’کژز‚ئ‚جƒCƒ“ƒ^ƒ†پ[‚إڈq‚ׂؤ‚¢‚éپBپx
‹ء‚‚ׂ«گ³“–‰»‚إ‚ ‚éپB“G‹َ•ê‚ھ”Œ©‚³‚ê‚é‰آ”\گ«‚ھژc‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éŒہ‚èپA—‹‘•‚ً”ُ‚¦‚ؤ‚¨‚‚±‚ئ‚ح•Kگ{‚إ‚ ‚éپBژv‚¦‚خ‚±‚¤‚¢‚¤››—‹ü‚ھ‚ـ‚©‚è’ت‚é‚و‚¤‚ةپAڈ¬ڈ¼‹P‹v‚ھڈ£‰ْ–ش‚ً’x‰„‚³‚¹“G‹َ•ê‚ًƒXƒ‹پ[‚³‚¹‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إ‚ ‚éپB
پw“ى‰_‚ج‚±‚جŒˆ’è‚ح‚»‚جŒم‚ةŒƒ‚µ‚¢”ل”»‚ج“I‚ئ‚ب‚ء‚½پBچ‚‚¢ٹO–ىگب‚©‚ç‚جŒ‹‰تک_‚©‚ç‚¢‚خپA“ى‰_‚ج‚±‚جŒˆ’è‚حڈd‘ه‚بƒ~ƒXƒeپ[ƒN‚إ‚ ‚ء‚½‚ئژv‚¤“اژز‚حپA‚«‚ي‚ك‚ؤ‘½‚¢‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢پB‚ھپA•Mژز‚حپA‘گژ‚⌹“c‚ئ“¯‚¶‚پA“–ژ‚جڈ‚©‚炵‚ؤپA“ى‰_‚جŒˆ’è‚ح‘أ“–‚ب‚à‚ج‚إ‚ ‚ء‚½‚ئگM‚¸‚é‚à‚ج‚إ‚ ‚éپBƒ~ƒbƒh´پ\‚ًچUŒ‚‚µ‚½—F‰i‚ھچؤچUŒ‚‚ج•K—v‚ھ‚ ‚é‚ئˆسŒ©‚ً‹ïگ\‚µ‚½‚±‚ئپAƒ~ƒbƒhƒE´پ\ٹî’n‚جچq‹َ•”‘à‚ھ‚ـ‚¾چUŒ‚‚ً‘±‚¯‚ؤ‚¢‚邱‚ئپA”ق‚ھ‚à‚ء‚ئ‚àگM—ٹ‚µ‚ؤ‚¢‚錹“c‚ھ“¯ˆس‚µ‚½‚±‚ئپA“ى‰_‚ح”قژ©گg‚جڈيژ¯‚ةٹî‚أ‚¢‚ؤŒˆ’è‚ً‰؛‚µ‚½‚©‚炦‚éپB‚µ‚©‚àپA‚»‚ج‘O“ْ‚ة“Œ‹‚©‚çپu‚ي‚ھٹéگ}‰و“I‚ةژ@’m‚³‚ꂽ’›Œَ‘S‚‚ب‚µپv‚ئ‚¢‚¤“d•ٌ‚ًژَگM‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إ‚ ‚éپBپx
ژ„‚ح“ى‰_‚جڈd‘ه‚بƒ~ƒXƒeپ[ƒN‚¾‚ئ‚حژv‚ي‚ب‚¢پB“ى‰_‚ة‘و“ٌژںچUŒ‚‚ًŒˆ’肳‚¹‚½‚ي‚¸‚©ڈ\ژO•ھŒم‚ةچُ“G‹@‚©‚ç“G‹َ•ê”Œ©‚ج•ٌچگ‚ھ“ü‚ء‚½‚ئŒ¾‚ء‚ؤچ¬—گ‚³‚¹پAŒ¹“c‚ھپw“¯ˆسپx‚µ‚½‚©‚炾‚ئژv‚¤پB“ى‰_‚ح”قژ©گg‚جڈيژ¯‚ةٹî‚أ‚¢‚ؤŒˆ’è‚ً‰؛‚µ‚½‚ئ‚حژv‚ي‚ب‚¢پBŒ¹“c‚ھ–T‚ç‚إ‹؛‚µ‚·‚©‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ئژv‚¤پBƒvƒ‰ƒ“ƒQ‚ھپw“ى‰_‚جŒˆ’èپx‚ًچm’è‚·‚é‚ج‚حƒ„ƒ‰ƒZ‚ًگ³“–‰»‚·‚邽‚ك‚إ‚ ‚éپBٹ®àّژه‹`ژز‚جƒvƒ‰ƒ“ƒQ‚ئ‚µ‚ؤ‚ح‚³‚¼‚©‚µ‹ê’ة‚¾‚ء‚½‚±‚ئ‚¾‚낤پB
پwپu’·ٹ¯‚à–‹—»‚à‘«‚ً‚·‚‚ي‚ꂽ‚و‚¤‚ةٹ´‚¶‚½پB“¯ژ‚ةپAڈ‚ً‚ا‚¤”»’f‚µ‚ؤ‚و‚¢‚©‚ي‚©‚ç‚ب‚©‚ء‚½پv‚ئŒ¹“c‚ح‰ٌ‘z‚µ‚ؤ‚¢‚éپBژQ–d’·‚ج‘گژ‚ح•ٌچگ‚³‚ꂽٹCˆو‚ة‹َ•ê‚ً”؛‚ي‚ب‚¢“G•”‘à‚ھ‚¢‚邱‚ئ‚ح‚ ‚蓾‚ب‚¢پA‹َ•ê‚ھ‚ا‚±‚©‚ة‚¢‚é‚ةˆل‚¢‚ب‚¢پA‚ئژv‚ء‚½پB‚ئ“¯ژ‚ةپA”ق‚حƒ~ƒbƒhƒE´پ\‚ة‘خ‚·‚é‘و“ٌژںچUŒ‚‚ً‚ا‚¤‚µ‚½‚çژو‚èڈء‚·‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚é‚©پAژv‚¢‚آ‚©‚ب‚©‚ء‚½پB‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حپAپg“G‚炵‚«‚à‚جŒ©‚نپh‚¾‚¯‚إ‚حپAƒ~ƒbƒhƒE´پ\‚ة‘و“ٌژںچUŒ‚‚ً‚©‚¯‚é‚ئ‚¢‚¤گو‚جŒˆ’è‚ً•دچX‚·‚é‚ة‚ح•sڈ\•ھ‚إ‚ ‚ء‚½‚©‚ç‚إ‚ ‚ء‚½پB‚ـ‚½پA‘گژ‚حڈoŒ‚‘O‚ةپg“ٌ“e‚ً’ا‚¤پh–â‘è‚إŒûک_‚µپAƒ~ƒbƒhƒE´پ\چUŒ‚‚ھ‘وˆê—Dگو‚ئŒ¾‚ي‚ꂽ‚±‚ئ‚ھپA‚»‚ج”O“ھ‚©‚ç‹ژ‚ç‚ب‚©‚ء‚½پBپx
–ع‘O‚ة”—‚ء‚½ٹë‹@‚و‚è‚àپA‚±‚ٌ‚ب‚±‚ئ‚ً”O“ھ‚ة’u‚¢‚ؤ››—‹ü‚ً‚±‚ث‚ؤ‚¢‚éƒ{ƒPژQ–d‚ھپAƒ„ƒ‰ƒZˆبٹO‚ة‚ا‚±‚ة‚¢‚é‚ج‚©پB‚±‚ٌ‚بŒ¾‚¢–َ‚ًڈ‘‚ƒvƒ‰ƒ“ƒQ‚àƒvƒ‰ƒ“ƒQ‚إ‚ ‚éپB‘گژ‚ئƒvƒ‰ƒ“ƒQ‚حƒCƒ“ƒ^ƒrƒ…پ[‚ئڈج‚µ‚ؤ‹¤–d‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚ ‚éپB
پw‚»‚µ‚ؤŒك‘Oژµژژlڈ\Œـ•ھپA“ى‰_‚ح‘S•”‘à‚ة‘خ‚µ‚ؤژں‚ج–½—ك‚ًڈo‚µ‚½پBپu“Gٹح‘à‚ة‘خ‚·‚éچUŒ‚‚ًڈ€”ُ‚·‚ׂµپB”ڑ‘•‚ة“]ٹ·‚ً‚¢‚ـ‚¾ڈI‚ي‚ç‚´‚é—‹Œ‚‹@‚ج•؛‘•‚ح‚»‚ج‚ـ‚ـ‚ئ‚¹‚وپv‚»‚جژ“_‚ـ‚إ‚ة‚حپAگشڈé‚ئ‰ء‰ê‚ج—‹Œ‚‘à‚ج‹›—‹‚©‚ç”ڑ’e‚ض‚ج•؛‘•“]ٹ·‚حپA‚ظ‚ع”¼•ھٹ®گ¬‚µ‚ؤ‚¢‚½پB•؛‘•‚ج“]ٹ·‚ًڈI‚ي‚ء‚½”ڑŒ‚‹@‚ح‚س‚½‚½‚رچb”آ‚ةŒf‚°‚ç‚êپA‚»‚جگ”‚ح—تٹ´‚ئ‚àڈ\‹@’ِ“x‚ة’B‚µ‚ؤ‚¢‚½پB‚à‚؟‚ë‚ٌپA‚»‚ج‚ـ‚ـ‚ج•؛‘•‚إ“Gٹح‘à‚ة‘خ‚µ‚ؤ”ڑŒ‚‚ً‰ء‚¦‚邱‚ئ‚ح‰آ”\‚إ‚ ‚ء‚½‚ھپA—‹Œ‚‚ج•û‚ھ‚ح‚é‚©‚ةگ³ٹm‚إ‚ ‚èپA‚»‚ج”j‰َŒّ‰ت‚à‘ه‚«‚©‚ء‚½پB‚»‚ج‚و‚¤‚بژٹش‚ئ‚جگي‚¢‚ج‚³’†‚ةپA•؛‘•‚ج“]ٹ·‚جژw—ك‚ھڈo‚³‚ꂽ‚ج‚إ‚ ‚ء‚½پB“ى‰_‚جڈ‘‚•êٹح‚ح‚»‚ج‚½‚ك‚ة‘هچ¬—گ‚ةٹׂء‚ؤ‚¢‚½پB‚»‚ج‘هچ¬—گ‚ً‘•‚·‚é‚©‚ج‚و‚¤‚ةپA“ى‰_•”‘à‚ة‘خ‚·‚éƒ~ƒbƒhƒE´پ\‚©‚ç‚جچؤ“x‚جچUŒ‚‚ھژn‚ـ‚ء‚½پBپx
”ڑŒ‚Œّ‰ت‚ج–â‘èˆب‘O‚ةپA‚±‚ج‚و‚¤‚ب‘هچ¬—گ‚ً‹N‚±‚³‚¹‚ب‚¢‚±‚ئ‚ج•û‚ھ‚و‚ظ‚اڈd‘ه‚إ‚ ‚éپB
‘هچ¬—گ‚جگي“¬–ح—l‚ًپw‘¾•½—mگي‘ˆپ@—¤ٹCŒRچq‹َ‘àپxگ¬”ü“°ڈo”إ‚و‚蔲گˆ‚·‚éپB
پw“G‚ح“ٌ”g‚ة•ھ‚©‚ê‚ؤ—ˆڈP‚µ‚½پB‘وˆê”g‚ھ‹ژ‚ء‚½’¼Œم‚ةپAڈم‹َŒx‰ْ‹@پi—ëگي‚R‚S‹@پj‚ج–ٌ”¼گ”‚ھ’…ٹح‚µ‚ؤ”R—؟‚ئ’e–ٍ‚ج•â‹‹‚ًچs‚ء‚ؤ‚¨‚èپA‘و“ٌ”g‚ج—ˆڈP‚ئ‚ئ‚à‚ةٹe•êٹح‚إژg—p‚إ‚«‚éگي“¬‹@‚ج‘S•”‚ھ”گi‚µ‚½‚ظ‚©پAƒ~ƒbƒhƒE´پ\“‡چUŒ‚‚ًڈI‚¦‚ؤ•êٹحڈم‹َ‚ة‹A‚ء‚ؤ‚«‚½—ëگي‚àگي“¬‚ة‰ء‚ي‚ء‚½پBپx
‘و“ٌ”g—ˆڈP‚ةƒ[ƒچگي‚ً‘S‚ؤ“ٹ“ü‚µ‚½‚ج‚إ‚ ‚é
پw‚±‚جٹشپAٹe•êٹح‚جٹi”[Œة“à‚إ‚حٹحچU‚ج•؛‘•‚ً—‹‘•‚©‚ç”ڑ‘•‚ضپA‚»‚µ‚ؤ‚س‚½‚½‚ر—‹‘•‚ض‚ئ•دچX‚·‚éچى‹ئ‚ھŒJ‚è•ش‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½پBپx
گي“¬‹@‚ً‘S‚ؤژg‚ء‚ؤ‰گي‚µ‚ؤ‚¢‚é‹ظ‹}ژ–‘ش‚ة‚¨‚¢‚ؤپA”ڑŒ‚‹@‚ح‚ئ‚¢‚¤‚ئٹi”[Œة‚إ•؛‘•“]ٹ·‚³‚¹‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إ‚ ‚éپBŒ©‚¦Œ©‚¦‚جƒVƒiƒٹƒI‚إ‚ ‚éپB
پw‚±‚ê‚ح“ى‰_‘وˆê‹@“®‘à’·ٹ¯‚ھپA“G‹@“®•”‘à‚جڈoŒ»‚ة”ُ‚¦‚ؤ‹›—‹‚ً“‹چع‚µ‚ؤ‚¢‚½‚à‚ج‚ًپAƒ~ƒbƒhƒE´پ\“‡‚ج‘و“ٌژںچUŒ‚‚ًچs‚¤‚½‚ك”ڑ’e‚ة•دچX‚µ‚½‚ھپA‚»‚ج“r’†‚إ“G‹@“®•”‘à”Œ©‚ج•ٌچگ‚ھ“ü‚ء‚½‚½‚كپAچؤ“xپA‹›—‹‚ةگد‚ف‘ض‚¦‚邱‚ئ‚ً–½‚¶‚½‚½‚ك‚إپA‹›—‹‚ئ”ڑ’e‚جگد‚ف‘ض‚¦‚ح•پ’ت‚إ‚àژٹش‚ھ‚©‚©‚邤‚¦‚ةڈم‹َŒx‰ْ‹@‚ج”’…‚ج‚½‚ك”ٍچsچb”آ‚حژg—p‚إ‚«‚¸ٹi”[Œة‚إچs‚ي‚ꂽ‚±‚ئ‚âپA“G‚ج‹َڈP‚ئ‚¢‚¤ˆ«ڈًŒڈ‚ھڈd‚ب‚ء‚½‚½‚كچى‹ئ‚حگi’»‚µ‚ب‚©‚ء‚½پB‚±‚ج•sژèچغ‚ھچُ“G‚جƒ~ƒX‚ب‚ا‚ئ‚ئ‚à‚ةƒ~ƒbƒhƒE´پ[ٹCگي‚ج”sˆِ‚ة‚آ‚ب‚ھ‚ء‚½‚±‚ئ‚حپA‚µ‚خ‚µ‚خژw“E‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚¨‚è‚إ‚ ‚éپBپx
پw‚±‚ج•sژèچغپx‚ج“à–َ‚ً‚à‚¤ˆê“xٹm”F‚µ‚ؤ‚ف‚و‚¤پB
‡@—F‰i‘هˆر‚ج‘و“ٌژںچUŒ‚‚جˆسŒ©‹ïگ\‚ًژَ‚¯‚ؤچؤ“xچUŒ‚‚ًŒˆ’è‚·‚éپB
‡Aچُ“G‹@‚©‚ç‚ج•ٌچگ‚ً‘ز‚½‚¸‚ة”ڑ‘•‚ً—¤ڈمچUŒ‚—p‚ة“]‘•‚³‚¹‚éپB
‡B‚»‚ج‚P‚R•ھŒم‚ةچُ“G‹@‚©‚ç•ٌچگ‚ھ‚ ‚èڈصŒ‚‚ًژَ‚¯‚éپB
‡C‚µ‚©‚µٹح‚جژي—ق‚ھ”»–¾‚µ‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤››—‹ü‚ً‚±‚ث‚ؤ“]‘•‚ً‘±چs‚³‚¹‚éپB
‡D‚آ‚¢‚ة“G‹َ•ê‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ھ”»–¾‚µ‚ؤ‘ه‹°چQ‚ً‚«‚½‚·پB
‡E‚µ‚©‚µ”ڑŒ‚‹@‚ً‘¦ژ”ٹح‚³‚¹‚¸“]‘•‚ً‘±‚¯‚³‚¹‚éپB
‡F“G‚ج‘وˆê”g‚ھ—ˆڈP‚·‚éپB
‡G“ْ–{‘¤‚ح‚·‚ׂؤ‚جƒ[ƒچگي‚ھ‰گي‚·‚éپB
‡G‚»‚جٹشŒ„‚ً“ث‚¢‚ؤ“G‚ج‘و“ٌ”g‚ھ—ˆڈP‚·‚éپB
‡H‚±‚ê‚ة‘خ‚·‚éŒ}Œ‚‚ح‰½‚à‚µ‚ب‚¢‚و‚¤‚ة‚·‚éپB
‡I‚½‚ء‚½“ٌ”‚ج–½’†‚إ‘S‚ؤ‚ج‚©‚½‚ھ‚آ‚‚ج‚ًŒ©ژç‚éپB
چؤ“xƒvƒ‰ƒ“ƒQ‚ج‘OŒfڈ‘”²گˆ‚ة–ك‚éپBƒvƒ‰ƒ“ƒQ‚جƒRƒWƒcƒP‚ئ‘گژ‚جèéٹA‚ة’چ–ع‚³‚ꂽ‚¢پB”ق‚ç‚ج–{گ«‚ھ剝‚«ڈo‚µ‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éپB
پwپu“G‚ح‚»‚جŒم•û‚ة‹َ•ê‚炵‚«‚à‚ج‚ً”؛‚¤پBپvŒك‘O”ھژ“ٌڈ\•ھ‚ة‘وژlچُ“Gگü‚ج—کچھ‹@‚ھ‘إ“d‚µ‚ؤ‚±‚جڈمچگ‚حپA‚»‚ج’©‚ة“ٹ‰؛‚³‚ꂽ‚¢‚©‚ب‚é”ڑ’e‚و‚è‚à‘ه‚«‚بڈصŒ‚‚ًپA“ْ–{‚جٹضŒWژز‚ة—^‚¦‚½پBپu‚»‚ج‚و‚¤‚ب‰آ”\گ«‚ًچl‚¦‚ب‚¢‚إ‚ح‚ب‚©‚ء‚½‚ھپAژ„‚حگS’êƒVƒ‡ƒbƒN‚ًژَ‚¯‚½پv‚ئ‘گژ‚ح‰ٌ‘z‚µ‚ؤ‚¢‚éپBپx
ژ„‚ح‘گژ—²”V‰î‚ةŒ¾‚¢‚½‚¢پB‚ ‚ب‚½‚ح“ى‰_’·ٹ¯‚جژQ–d’·‚ب‚ج‚¾پB‰½گçگl‚à‚ج•؛ژm‚ج–½‚ً—a‚©‚éگس”C‚ ‚é—§ڈê‚إ‚ ‚éپBگS’êƒVƒ‡ƒbƒN‚ًژَ‚¯‚½‚ب‚ا‚ئ•¶ٹw“IڈCژ«‚إچد‚ق‚و‚¤‚بڈê–ت‚إ‚ح‚ب‚¢پB‚ ‚ب‚½‚جŒû‚©‚ç‚حژ©Œبگ³“–‰»‚ج‚½‚ك‚جŒ¾‚¢–َ‚ئگس”C“]‰إ‚جŒ¾—t‚µ‚©ڈo‚ؤ‚±‚ب‚¢پB‚¹‚ك‚ؤŒû‚ً‚آ‚®‚ٌ‚إ‚¢‚ç‚ê‚ب‚¢‚ج‚©پB‚±‚ج‚و‚¤‚ب“ا‚ق‚ةٹ¬‚¦‚ب‚¢’p’m‚炸‚بƒCƒ“ƒ^ƒrƒ…پ[‚ً‚ا‚¤‚µ‚ؤ‚إ‚«‚é‚ج‚©پB
پwپuˆêڈu‚ح’·ٹ¯‚àƒVƒ‡ƒbƒN‚ًژَ‚¯‚ç‚ꂽ‚ةˆل‚¢‚ب‚¢‚ھپA’N‚إ‚à‚»‚ج‚و‚¤‚بژv‚¢‚ھ‚¯‚ب‚¢ڈê–ت‚ة’¼–ت‚·‚ê‚خپAˆêڈu‚حƒVƒ‡ƒbƒN‚ًژَ‚¯‚é‚إ‚ ‚낤پv‚ئ‘گژ‚حڈq‚ׂؤ‚¢‚éپB—کچھ‹@‚ة‚و‚é‹َ•ê‚炵‚«‚à‚ج”Œ©‚ج“d•ٌ‚جژَگM‚ئپA—F‰i‘à‚ھ“¯ژ‚ة‹Aٹز‚µ‚½‚±‚ئ‚حپA“ى‰_‚جˆسژvŒˆ’è‚ج‘I‘ً‚ً‚±‚êˆبڈم‚ب‚چ¢“ï‚ب‚à‚ج‚ة‚·‚邱‚ئ‚ة‚ب‚ء‚½پB“G‚ج‹َ•ê•”‘à‚ًچUŒ‚‚·‚邱‚ئ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپA‰½‚à–â‘è‚ح‚ب‚©‚ء‚½پB‚±‚ج“_‚ةٹض‚·‚éŒہ‚èپA“ى‰_‚ج‚ب‚·‚ׂ«‚±‚ئ‚ح–¾پX”’پX‚إ‚ ‚ء‚½‚ھپA–â‘è‚ح‚ا‚¤‚â‚ء‚ؤ‚â‚é‚©‚إ‚ ‚ء‚½پBپx
‰½‚à–â‘è‚ح‚ب‚©‚ء‚½پB‘گژژQ–d’·‚ھپAƒpƒjƒbƒN‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é“ى‰_‚ة‘خ‚µ‚ؤŒ»‘•”ُ‚ج‚ـ‚ـ‘¦ژچUŒ‚‚·‚é‚ׂ«‚±‚ئ‚ًگiŒ¾‚·‚ê‚خپB•؛‘•“]ٹ·‚ً–½—ك‚µ‚½‚P‚R•ھŒم‚ة“G‹َ•ê”Œ©‚جڈî•ٌ‚ً“ü‚ê‚ؤƒpƒjƒbƒN‚ة‚³‚¹‚½“ى‰_‚ًپAŒ¹“c‚ئƒOƒ‹‚ة‚ب‚ء‚ؤ‹؛‚µپA‚ك‚؟‚ل‚‚؟‚ل‚ب–½—كŒn“‚ًڈo‚³‚¹‚邱‚ئ‚ھ‘گژژQ–d’·‚ة—^‚¦‚ç‚ꂽ”C–±‚إ‚ ‚éپB
پw‚»‚جژپA‘و“ٌچq‹َگي‘àژi—كٹ¯‚جژRŒû‚حپA‹ى’€ٹح–ى•ھ‚ً’†Œp‚µ‚ؤپAپu‘¦چڈچUŒ‚‘à‚ً”ٹح‚¹‚µ‚ق‚é‚ً‰آ‚ئ”F‚قپv‚ئگشڈé‚ةگMچ†‚µ‚ؤ‚«‚½پB‚»‚ê‚ح—]Œv‚ب‚¨‚¹‚ء‚©‚¢‚ئŒ¾‚¤‚ׂ«‚إ‚ ‚ء‚½پB“ى‰_‚ھ”ق‚جˆسŒ©‚ً•K—v‚ئ‚·‚é‚ب‚çپA‚·‚إ‚ة‹پ‚ك‚ؤ‚¢‚½‚إ‚ ‚낤‚©‚ç‚إ‚ ‚ء‚½پBپx
ƒvƒ‰ƒ“ƒQ‚حƒ~ƒbƒhƒEƒGپ[ٹCگي‚جچ¼‹\”ئچك‚ً•²ڈü‚·‚邽‚ك‚ة–{ڈ‘‚ًڈ‘‚¢‚ؤ‚¢‚é‚ج‚¾‚©‚çپAژRŒû‚ج‹ïگ\‚ھژٹ“–‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ً”F‚ك‚é–َ‚ة‚ح‚¢‚©‚ب‚¢‚ج‚إ‚ ‚éپBژRŒû‚ح‚±‚جŒم‚àƒvƒ‰ƒ“ƒQ‚ج•s“–‚بچUŒ‚‚ًژَ‚¯‘±‚¯‚éپB
پwژRŒû‚ح‚ا‚؟‚ç‚©‚ئŒ¾‚¦‚خ‚¹‚ء‚©‚؟‚جگ«ٹi‚إپA‘پ‚“G‚ئˆêگي‚ًŒً‚¦‚½‚¢‚ئ”R‚¦ڈم‚ھ‚ء‚ؤ‚¢‚½پB‚³‚ç‚ة”ق‚ح“ى‰_‚ئ”§‚ھچ‡‚ي‚¸پAژR“à‚ج‹‰—F‚إ‚ ‚èکAچ‡ٹح‘àژQ–d’·‚إ‚ ‚ء‚½‰Fٹ_‚ھپAپu‘وˆêچq‹َٹح‘àژi—ك•”‚ح’N‚ھˆ¬‚è‚¢‚é‚âپv‚ئژRŒû‚ةژ؟–₵‚½‚ج‚ة‘خ‚µ‚ؤپAپu’·ٹ¯‚حˆêŒ¾‚àŒ¾‚ي‚تپAژQ–d’·پAگو”CژQ–d“™‚ا‚؟‚ç‚ھ‚ا‚؟‚ç‚©’m‚ç‚ت‚ھ‰°•aژز‘µ‚¢‚إ‚ ‚éپv‚ئ“ڑ‚¦‚½پA‚ئ‰Fٹ_‚ح‚»‚ج“ْ‹L‚ةڈ‘‚¢‚ؤ‚¢‚½‚ظ‚ا‚إ‚ ‚ء‚½پBپx
ƒvƒ‰ƒ“ƒQ‚ح‰Fٹ_“Z‚ج“ْ‹Lپwگي‘”ک^پx‚ة’N‚و‚è‚à‘پ‚’چ–ع‚µ‚ؤ–|–َŒ ‚ً“üژ肵پAگç‘پگ³—²‚ھ–|–َ‚µ‚ؤ‚¢‚éپB‘Oڈq‚µ‚½‚و‚¤‚ة‰Fٹ_‚à’؛—ك‚ًژَ‚¯‚½چHچىگl‚جˆêگl‚إ‚ ‚éپBکAچ‡ٹح‘àگو”CژQ–d‚جچ•“‡‹Tگl‚حپA‰Fٹ_‚جˆâ‘°‚©‚炱‚ج“ْ‹L‚ًژط‚è‚ؤپAژR–{Œـڈ\کZ‚ھˆأژE‚³‚ꂽ‘OŒم‚جژO‚©Œژ•ھ‚ظ‚ا‚ً”j‚èژج‚ؤ‚ؤ‚¢‚éپBپu‚ا‚±‚©‚ة‚¢‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½پv‚ئŒ¾‚ء‚ؤˆâ‘°‚ة“ْ‹L‚ً•ش‚µ‚ؤ‚«‚½‚»‚¤‚¾پB‚»‚¤‚¢‚¤چ•“‡‹Tگl‚ھ—Bˆê‰‚¶‚½‚ج‚ھپA‚±‚جƒvƒ‰ƒ“ƒQ‚جƒCƒ“ƒ^ƒrƒ…پ[‚إ‚ ‚éپBƒvƒ‰ƒ“ƒQ‚حچ•“‡‚©‚ç”j‚èژج‚ؤ‚½ƒyپ[ƒW‚ج“à—e‚ً•·‚«ژو‚ء‚ؤ‚¢‚邾‚낤پB
پw“ى‰_‚µ‚ؤ‚ح‚»‚ج‚و‚¤‚بˆسŒ©‹ïگ\‚ً•K—v‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½پBگ^ژىکp‚جڈں—کژز‚إ‚ ‚é”قˆبڈم‚ةچq‹َچUŒ‚‚جٹïڈPگ«‚ًگv‘¬گ«‚ج‰؟’l‚ً”Fژ¯‚µ‚ؤ‚¢‚éژز‚ح‚¢‚ب‚©‚ء‚½‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚و‚¢پBپx
ƒvƒ‰ƒ“ƒQ‚ح‰Fٹ_‚ج“ْ‹L‚ًڈdژ‹‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ة‚à‚©‚©‚ي‚炸پA‰Fٹ_‚ج‹Lڈq‚ئگ³”½‘خ‚جŒ©‰ً‚ًڈq‚ׂؤ‚¢‚éپBƒ„ƒ‰ƒZ‚جٹjگS‚ة‹ك‚أ‚‚ة‚آ‚êپAƒvƒ‰ƒ“ƒQ‚ج•¶ڈح‚ھ‚¾‚ٌ‚¾‚ٌ•›“‡—²•F‰»‚µ‚ؤ‚¢‚«‚آ‚آ‚ ‚é‚ج‚ھ‚¨•ھ‚©‚肾‚낤‚©پBگ°‚ê‚ئ‚«‚ا‚«“ـ‚èپA‚ج‚؟‰JپA‚ئ‚±‚ë‚ة‚و‚ء‚ؤ‚حèإپAè¹پA‚à‚µ‚©‚µ‚ؤƒuƒٹƒUپ[ƒh‚©—³ٹھ‚ة‚ب‚é‚إ‚µ‚ه‚¤پEپEپEپB‚©‚ب‚蜓ˆس“I‚ب•¶ڈح‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éپB
پw‚»‚جگي“¬‹@‚ج–â‘è‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپA‘گژ‚حژں‚ج‚و‚¤‚ةچl‚¦‚ؤ‚¢‚½پBپuژ„‚حچUŒ‚‘à‚ً‚·‚®”ٹح‚³‚¹‚و‚ئ‚جپiژRŒûپj‚جˆسŒ©‚ة‚حپA‘S–ت“I‚ة”½‘خ‚إ‚ح‚ب‚©‚ء‚½‚ھپAگي“¬‹@‚ج‰†Œى‚ب‚µ‚إ‚àچUŒ‚‚ةڈo‚¹‚ئ‚جˆسŒ©‚ة‚ح”½‘خ‚إ‚ ‚ء‚½پB‚ب‚؛‚ب‚çپAگي“¬‹@‚ً”؛‚ي‚ب‚¢چUŒ‚‘à‚ھ‚ي‚ھگي“¬‹@‚ة‚و‚ء‚ؤ‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‘S–إ‚³‚¹‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚½‚±‚ئ‚حپAŒ»‚ة–عŒ‚‚µ‚½’ت‚è‚إ‚ ‚ء‚½‚©‚çپAژ„‚حچUŒ‚‘à‚ة‚ح‚ا‚ٌ‚ب‚±‚ئ‚ً‚µ‚ؤ‚àپAگي“¬‹@‚ً‚آ‚¯‚½‚¢‚ئژv‚ء‚½پv‚ئ”ق‚حڈq‚ׂؤ‚¢‚éپBپx
ژ„‚ح‚±‚±‚ةپw‰^–½‚جŒـ•ھٹشپx‚ً‰‰ڈo‚µ‚½گ^”ئگl‚جˆêگl‚ھŒê‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ئژv‚¤پB“G‘¤‚ح‰†Œى‚ً‚آ‚¯‚ب‚¢‚ـ‚ـ‹}ڈP‚µ‚ؤ‚«‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚ ‚éپB‚»‚ê‚ة‘خ‚µ‚ؤ‘گژ—²”V‰î‚حپw‚ا‚ٌ‚ب‚±‚ئ‚ً‚µ‚ؤ‚àچUŒ‚‘à‚ة‚حپAگي“¬‹@‚ً‚آ‚¯‚½‚¢‚ئژv‚ء‚½پx‚ئ‚¢‚¤پB‚±‚ê‚ھ‘¦ژ”ٹح‚³‚¹‚ب‚©‚ء‚½——R‚¾‚ئ‚¢‚¤پB—ق‚ًŒ©‚ب‚¢‚ظ‚ا”nژ‚°‚½ƒRƒWƒcƒP‚إ‚ ‚éپBŒ‹‰تپA”ٹح‚ً‘ز‹@‚³‚¹‚ç‚ꂽچb”آڈم‚ج”ڑŒ‚‹@‚جŒQ‚ê‚ةپA‰†Œى‹@‚ً”؛‚ي‚ب‚¢“G”ڑŒ‚‹@‚ھ‹}چ~‰؛”ڑŒ‚‚ً‚µ‚ؤپAچb”آ‚حژè‚ھ•t‚¯‚ç‚ê‚ب‚¢‚ظ‚ا‰ٹڈم‚µپA‚©‚¯‚ھ‚¦‚ج‚ب‚¢ڈn—ûچq‹َ•؛‚ج”¼•ھ‚ئگ®”ُ•؛‚ج‘ه”¼پA‹y‚رگç–¼‹ك‚¢‹@ٹض‰ب•؛‚ھ’nچ–‚ج‹ئ‰خ‚ة•ï‚ـ‚êڈؤژ€‚µ‚½پB‘گژ—²”V‰î‚ح‘وˆêچq‹َٹح‘àژQ–d’·‚إ‚ ‚è‚ب‚ھ‚çپA“G‘¤‚ة–،•û‚ج•؛‚ًڈˆŒY‚³‚¹‚½‚ج‚إ‚ ‚éپB‚»‚ê‚ھ’؛—ك‚¾‚ء‚½‚©‚炾پB
پw‚»‚ê‚خ‚©‚è‚إ‚ب‚پAگي“¬‹@‚ً”؛‚ي‚ب‚¢چUŒ‚‚ح–³ˆس–،‚إ‚ ‚é‚ئ‚ج‘گژ‚جˆسŒ©‚ةپA“¯ٹ´‚إ‚ ‚ء‚½Œ¹“c‚حپA“ى‰_‚ئ‘گژ‚ة‘خ‚µ‚ؤپA‘وˆêژںچUŒ‚‚ًژû—e‚µ‚½Œم‚إپA“G‚ة‘خ‚·‚éچUŒ‚‘à‚ً”ٹح‚·‚é‚و‚¤گiŒ¾‚µ‚½پB”R—؟‚ھ‚ب‚‚ب‚è‚©‚¯‚ؤ‚¢‚½‘وˆêژںچUŒ‚‘à‚ج‹@‚ًژû—e‚·‚邽‚كپA‚·‚إ‚ة”ٍچsچb”آ‚ة•ہ‚ׂç‚ê‚ؤ‚¢‚½گ…•½”ڑŒ‚‹@‚ح‹}‚¢‚إٹi”[Œة‚ةچ~‚낳‚êپA‚»‚ج•؛‘•‚ً‚س‚½‚½‚ر‹›—‹‚ةژو‚èٹ·‚¦‚ç‚ꂽپBپx
‚±‚±‚ة“G‚ج‹}چ~‰؛”ڑŒ‚‚ًژَ‚¯‚é‚ـ‚إپA‰½‚ئ‚µ‚ؤ‚à–،•û”ڑŒ‚‹@‚ً”ٹح‚³‚¹‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤‘گژ‚ئŒ¹“cژہ‚جˆسژv‚ًٹ´‚¶‚éپB
پw‚±‚ê‚ç‚جگط”—‚µ‚½ڈَ‹µ‰؛‚إپA“ى‰_‚حپAƒVƒFپ[ƒNƒXƒsƒA‚جƒnƒ€ƒŒƒbƒg‚ج‚و‚¤‚ةپA‹´‚جڈم‚إ‰E‚·‚é‚©چ¶‚·‚é‚©چl‚¦‚é—]—T‚à‚ب‚©‚ء‚½پBŒ¹“c‚àپAپu“ى‰_’·ٹ¯‚ح‚·‚®Œˆ’f‚µ‚½پv‚ئڈq‚ׂؤ‚¢‚éپB—کچھ‹@‚ج“d•ٌ‚ًژَگM‚µ‚ؤ‚©‚çٹش”¯‚ً“ü‚ꂸپA“ى‰_‚حژں‚ج–½—ك‚ً‰؛‚µ‚½پBپuٹحڈم”ڑŒ‚‹@‚ح‘و“ٌژںچUŒ‚پi’چپ@ƒ~ƒbƒhƒE´پ\“‡چUŒ‚پj‚ة”ُ‚¦‚وپB“ٌ•SƒLƒچ”ڑ’e‚ً‘•”ُ‚ئ‚¹‚وپvپu‚ـ‚½•؛‘•“]ٹ·‚¾پv‚ئ•پ’i‚ح‚¨‚ئ‚ب‚µ‚¢گشڈé‚ج”ٍچs’·‚ج‰v“c’†چ²‚à‘هگ؛‚ًڈم‚°‚½پBپu‚±‚ê‚إ‚ح‚ـ‚é‚إ•؛‘•“]ٹ·‚ج‹£‹Z‚ً‚³‚¹‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚ب‚à‚ج‚¾پv‚ئپBپx
“ى‰_‚جŒ¾“®‚حپA‘گژ‚ئŒ¹“c‚ج’کڈ‘‚âƒCƒ“ƒ^ƒrƒ…پ[‚ة‚و‚é‚à‚ج‚إ‚ ‚éپBژ„‚ح”ق‚ç‚ھژ€گl‚ةŒû‚ب‚µ‚إ‘nچى‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئژv‚¤پB“ى‰_‚حƒTƒCƒpƒ“‚إ•،گ”‚جژmٹ¯‚ةژR‚ةکA‚ê‹ژ‚ç‚êپA”ق‚ç‚ج›ٌڈ•‚إپwژ©ٹQپx‚³‚¹‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚éپB“ى‰_‚ھگ¶‚«‚ؤڈطŒ¾‚µ‚ؤ‚¢‚½‚çپAƒ„ƒ‰ƒZ‚ھ”»–¾‚·‚é‚و‚¤‚ب‘گژ‚ئŒ¹“c‚جŒ¾“®‚ھ–¾‚ç‚©‚ة‚³‚ꂽ‚©‚ç‚إ‚ ‚éپB
پwˆê•ûپAٹe•êٹح‚جٹi”[Œة‚إ‚ح”¼‘³پA”¼ƒYƒ{ƒ“‚ج–hڈ‹•‚ً’…‚½گ®”ُˆُ‚ھپAٹ¾‚ـ‚ف‚ê‚ة‚ب‚ء‚ؤپA”ڑŒ‚‹@‚©‚ç”ھ•SƒLƒچ”ڑ’e‚ًچ~‚낵‚ؤ‚¢‚½پB‹@‚©‚çچ~‚낵‚½”ڑ’e‚حپA‚»‚ê‚ً‰؛‚ج’e–ٍŒة‚ةچ~‚ë‚·ژٹش‚ھ‚ب‚¢‚ج‚إپAٹi”[Œة‚ج‘¤–ت‚ة‰¼‚ةگد‚فڈم‚°‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚½پBپx
‚©‚‚µ‚ؤ‘هچ¬—گ‚ج’†پA–،•û‹َ•ê‚ًŒ‚’¾‚·‚é‚ةڈ\•ھ‚ب”ھ•SƒLƒچ”ڑ’e‚ھگد‚فڈم‚°‚ç‚ꂽ‚ج‚إ‚ ‚éپB
پw‘هکa‚جکAچ‡ٹح‘àژi—ك•”‚حپA‚±‚ê‚ç‚ج“d•ٌ‚ًژَگM‚µ‚ؤپAڈ‚جگ„ˆع‚ً‚©‚ب‚è‚و‚‚آ‚©‚ٌ‚إ‚¢‚½پB”ق‚ç‚حƒAƒپƒٹƒJ‚ج‹َ•ê‚ھ“ى‰_•”‘à‚جچUŒ‚Œ—“à‚ة‚¢‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ة‚آ‚¢‚ؤپAڈ‚µ‚àگS”z‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½پB‚»‚جڈuٹش‚ـ‚إژR–{‚¨‚و‚ر‚»‚جƒXƒ^ƒbƒt‚حپAƒAƒپƒٹƒJ‚ج‹َ•ê‚ھƒ~ƒbƒhƒE´پ\‚ج–k•û‚جٹCˆو‚ةچىگي‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚¢‚¤ڈî•ٌ‚ح‰½‚瓾‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½‚ج‚ة‚à‚©‚©‚ي‚炸پA‚±‚ج‚و‚¤‚ب–³گس”C‚ج”½‰‚حپA‚ق‚µ‚ëˆ ‘R‚ئ‚ب‚é‚خ‚©‚è‚إ‚ ‚éپB‚»‚ê‚خ‚©‚è‚إ‚ب‚پA‚»‚ê‚حپA”ق‚ç‚جچىگي‚ج‘هٹأ‚ج—\‘z‚ة”½‚µ‚ؤ“G‚ھڈoŒ»‚¢‚½‚ئ‚¢‚¤‹@”÷‚³—ا‚¢Œ»ژہ‚ةپA–ع‚ً•آ‚¶‚½‚±‚ئ‚ًژ¦‚·‚à‚ج‚إ‚ ‚ء‚½پBپx
‘هٹأ‚ج—\‘z‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚©‚炱‚»پA“Gٹح‘à‚ج“®Œü‚ً’ح‚ق‚½‚ك‚ةڈ¬ڈ¼‹P‹v‚ةژOڈd‚جڈ£‰ْ–ش‚ً“WٹJ‚³‚¹‚½‚ج‚إ‚ ‚éپB‚à‚؟‚ë‚ٌڈ¬ڈ¼‹P‹v‚حڈ£‰ْ‚ج—\’è“ْ‚ًژl“ْ‚à’x‰„‚³‚¹پA“Gٹح‘à‚ً–³ژ–‚ةƒXƒ‹پ[‚³‚¹‚ؤ‚ ‚°‚½‚±‚ئ‚ً•ٌچگ‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¢پBڈ¬ڈ¼‹P‹v‚ح“c•zژ{‘؛‰¤’©‚جچcچ@‚جڈ]’ي‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ح‘Oڈq‚µ‚½’ت‚è‚إ‚ ‚éپBƒvƒ‰ƒ“ƒQ‚ح‚³‚ç‚ةچ•“‡‚ئ‹¤–d‚µ‚ؤپAژR–{Œـڈ\کZ‚جŒ¾“®‚ًs‘¢‚µ‚ؤ‚¢‚éپB
پwپuƒAƒپƒٹƒJٹح‘à‚ً‘¬‚â‚©‚ةچUŒ‚‚¹‚و‚ئ“ى‰_‚ة–½—ك‚·‚ׂ«‚¾پA‚ئژv‚¤‚ھپAŒN‚ح‚ا‚¤ژv‚¤‚©پv‚ئژR–{‚حچ•“‡‚ةگu‚ث‚½پB‚»‚جژR–{‚ج–â‚¢‚ة‘خ‚µ‚ؤپAچ•“‡‚حپu“ى‰_’·ٹ¯‚ح‚»‚جچUŒ‚•؛—ح‚ج”¼گ”‚ًƒAƒپƒٹƒJ‹َ•ê•”‘à‚ة‘خ‚µ‚ؤڈ€”ُ‚µ‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚·‚©‚çپA‚·‚إ‚ةچUŒ‚‚ًڈ€”ُ’†‚¾‚ئژv‚¢‚ـ‚·پv‚ئ“ڑ‚¦‚½پB‚»‚±‚إژR–{‚ح‚»‚ج’ٌˆؤ‚ًˆّ‚ءچ‚ك‚½پBچ•“‡‚ح‚»‚جژ€‚ة‚¢‚½‚é‚ـ‚إ”ق‚جگس”C‚ً’ةٹ´‚µ‚ؤ‚¢‚½پBچ•“‡‚ھژR–{’·ٹ¯‚جˆسŒ©‚ة“¯ˆس‚µ‚ؤپAژR–{’·ٹ¯‚ج–¼‘O‚إڈo‚³‚ꂽ–½—ك‚حپA“ى‰_‚ة‚·‚®چUŒ‚‚ً‚³‚¹‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½‚©‚à‚µ‚ê‚ب‚¢پBپu“ى‰_’·ٹ¯‚ھپAکAچ‡ٹح‘àژi—ك•”‚ھ–]‚ٌ‚إ‚¢‚½‚و‚¤‚ة“®‚©‚ب‚©‚ء‚½‚ج‚حپAژ„‚جگس”C‚إ‚ ‚éپv‚ئچ•“‡‚ح’Q‚¢‚½پBپuƒ~ƒbƒhƒE´پ\چىگي‚ج‘وˆê–ع“I‚حپAƒAƒپƒٹƒJ‹َ•ê‘à‚ً’@‚‚±‚ئ‚إ‚ ‚éپv‚±‚ئ‚ًپA“ى‰_‚حڈ\•ھ‚ة—‰ً‚µپA‚»‚ê‚ة‘خ‚µ‚ؤڈ\•ھ‚ب‘خچRچô‚ًچu‚¶‚ؤ‚¢‚éپA‚ئچ•“‡‚حژv‚ء‚ؤ‚¢‚½پi–َژز’چپپˆبڈم‚ج‰ïکb‚âڈٹŒ©‚حپAچ•“‡‚ھˆê‹مکZژl”N‚ة’کژز‚ئ‚جƒCƒ“ƒ^ƒrƒ…پ[‚إڈq‚ׂ½‚à‚ج‚إ‚ ‚éپjپB‚ھپA‚»‚ê‚حچ•“‡‚جژv‚¢ˆل‚¢‚إ‚ ‚éپB‚Sڈح‚إŒ©‚½‚و‚¤‚ةپAچ•“‡‚حƒ~ƒbƒhƒE´پ\‚جچU—ھ‚ھچىگي‚ج‘وˆê–ع“I‚إ‚ ‚é‚ئ–¾‚ç‚©‚ة‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إ‚ ‚éپB“ى‰_‚ج‹@“®•”‘à‚ح‚»‚ê‚ة‚à‚ئ‚أ‚¢‚ؤ”»’f‚µ‚ؤچs“®‚µ‚ؤپAڈ‰‚ك—‹‘•‚©‚ç”ڑ‘•‚ةژو‚èٹ·‚¦‚錈’è‚ً‰؛‚µ‚½‚ج‚إ‚ ‚éپB“ى‰_‚جچUŒ‚‚ھ’x‚ꂽ‚ج‚حپAƒAƒپƒٹƒJ‹َ•ê•”‘à‚ًچUŒ‚‚·‚邱‚ئ‚ًڈa‚ء‚ؤ‚¢‚½‚©‚ç‚إ‚ح‚ب‚‚ؤپAڈ\•ھ‚ب•؛—ح‚إŒّ‰ت‚ ‚éچUŒ‚‚ً‚©‚¯‚و‚¤‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚½‚©‚ç‚إ‚ ‚ء‚½پBپx
چ•“‡‚ة‚و‚éژR–{Œـڈ\کZ‚ئ‚ج‚â‚èژو‚è‚جڈطŒ¾‚ح‹Uڈط‚إ‚ ‚éپBچ•“‡‚جژ©Œبگ\چگ‚حپA‚¢‚©‚ة‚àگMœكگ«‚ھ‚ ‚é‚و‚¤‚ةŒ©‚¹‚©‚¯‚邽‚ك‚ج‚à‚ج‚إ‚ ‚éپBˆؤ‚ج’èپAƒvƒ‰ƒ“ƒQ‚ح—D‚µ‚چ•“‡‚ً”ف‚ء‚ؤ‚ ‚°‚ؤپA“ى‰_‚حپi‚آ‚ـ‚è‘گژ‚⌹“c‚حپj“–‘R‚ج‚±‚ئ‚ً‚µ‚½‚ج‚¾‚ئ‚¢‚¤Œ‹ک_‚ة“±‚¢‚ؤ‚¢‚éپB“–‘R‚ج‚±‚ئ‚ً‚µ‚½Œ‹‰تپA‚ا‚ج‚و‚¤‚بژ–‘ش‚ھˆّ‚«‹N‚±‚³‚ꂽ‚©‚ًŒ©‚ؤ‚ف‚و‚¤پB
پw‚»‚جڈuٹش‚ة‰ء‰ê‚جŒ©’£‚è‚ھپu‹}چ~‰؛پv‚ئ‹©‚ٌ‚¾پB‚»‚ê‚ًŒ©‚½“¯ٹح‚ج”ٍچs’·“V’JچF‹v’†چ²پiٹC•؛‚T‚Pٹْپj‚ح‚»‚جƒvƒچ“I‚بٹ´ٹo‚©‚çپA‰_‚ً—ک—p‚µ‘¾—z‚ً”w‚ة‚µ‚ؤ“ث‚ءچ‚ٌ‚إ‚‚éپA‚±‚ê‚ح‘ٹ“–‚ب‚à‚ج‚¾‚ئٹ´‚¶‚½پBˆê•ûپAگشڈé‚جٹحڈم‚إ‚حڈ€”ُ‚جڈo—ˆڈم‚ھ‚ء‚½‘و“ٌژںچUŒ‚‘à‚ج”ٹح‚ھ‚ـ‚³‚ةژn‚ـ‚낤‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚½پB”ٍچs’·‚ج‘“c‚ح”’ٹّ‚ًگU‚èپAگي“¬‚جƒ[ƒچگي‚ح”ٍچsچb”آ‚ً‘–‚èژn‚ك‚½پB‚»‚جڈuٹش‚إ‚ ‚ء‚½پBŒ©’£‚è‚حپu‹}چ~‰؛پv‚ئ‹©‚ٌ‚¾پB‚»‚ê‚ً•·‚¢‚½•£“c‚ھŒ©ˆ¢ƒKƒGƒ‹‚ئپA“G‚جٹح”ڑژO‹@‚ھ–î‚ج‚و‚¤‚ةٹح‹´‚ةŒü‚©‚ء‚ؤ“ث‚ءچ‚ٌ‚إ‚‚é‚ج‚ھŒ©‚¦‚½پB”ق‚ح’eڈœ‚¯‚ة‘•”ُ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½ƒ}ƒ“ƒgƒŒƒbƒg‚ج‰A‚ةگg‚ً•ڑ‚¹‚½پBپx
‚»‚ê‚ـ‚إ‚حژg‚¢ژج‚ؤ‚جڑ™‚ئ‚µ‚ؤپAپwژwٹِٹ¯‚ح”ق‚ç‚ھٹٹ‘–کH‚ً—£‚ꂽڈuٹش‚ةژ€‚ٌ‚¾‚à‚ج‚ئژv‚¤‚ׂ«‚إ‚ ‚éپx‚ئ‚¢‚¤‚و‚¤‚ب“ءچU‚ً‚³‚¹‚ؤ‚¢‚½ƒAƒپƒٹƒJ‚حپAچ¼‹\”ئچك‚جƒNƒ‰ƒCƒ}ƒbƒNƒX‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚¨‚«‚جژè—û‚ê‚ً“ٹ“ü‚µ‚½‚ج‚إ‚ ‚éپB‹¤“¯‰‰ڈoژز‚ج•£“c‚حˆہ‘S‚ب”ً“ïڈêڈٹ‚©‚çˆê•”ژnڈI‚ً’‚ك‚ؤ‚¢‚½پBچL“‡Œ´”ڑ“ٹ‰؛‚جژ‚à“¯—l‚إ‚ ‚ء‚½پB
پwŒ¹“c‚ھ‚ـ‚¾ژ–‘ش‚ًٹyٹد‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ج‚حپA——R‚ج‚ب‚¢‚±‚ئ‚إ‚ح‚ب‚©‚ء‚½پB•پ’ت‚جڈَ‘ش‚ب‚ç‚خپA“ٌ”‚ج”ي’e‚ًژَ‚¯‚½‚¾‚¯‚إپA’v–½“I‚ب‘¹ٹQ‚ة‚ب‚é‚و‚¤‚ب‚±‚ئ‚ح‚ب‚©‚ء‚½‚¾‚낤‚©‚ç‚إ‚ ‚ء‚½پB‚ھپA‰ء‰ê‚ئگشڈé‚ھ”ي’e‚ًژَ‚¯‚½ژپA—¼ٹح‚جڈَ‘ش‚ح•پ’ت‚إ‚ح‚ب‚©‚ء‚½پB—¼ٹح‚ج”ٍچsچb”آ‚ة‚ح”R—؟‚ً–چع‚µپA‹›—‹‚ـ‚½‚ح”ڑ’e‚ً‘•”ُ‚µ‚½چq‹َ‹@‚ھ—ƒ‚ًکA‚ث‚ؤ•ہ‚رپA‚»‚ج‰؛‚جٹi”[Œة‚ة‚à“¯—l‚جڈَ‘ش‚ج‹@‚ھ”ٍچsچb”آ‚ة—g‚°‚ç‚ê‚é‚ج‚ً‘ز‚ء‚ؤ‚¢‚½پB‚ب‚¨ˆ«‚¢‚±‚ئ‚ة‚حپAگو‚ةچUŒ‚‹@‚©‚çژو‚è‚ح‚¸‚µ‚½”ڑ’e‚ھپA‚ـ‚¾ٹi”[Œة“à‚ة—‡‚ة‚ب‚ء‚ؤژc‚ء‚ؤ‚¢‚½پBچq‹َ‹@‚جƒKƒ\ƒٹƒ“‚ھ”R‚¦پA“‹چع‚µ‚½‹›—‹پA”ڑ’e‚ھ—U”ڑ‚µپA‚³‚ç‚ة‚»‚ê‚ھٹi”[Œة“à‚ج”ڑ’e‚ً—U”ڑ‚µپAگشڈé‚حٹش‚à‚ب‚پA‘گژ‚جŒ¾‚ة‚و‚ê‚خپAپg”R‚¦‚³‚©‚é’nچ–پh‚ئ‰»‚·‚邱‚ئ‚ة‚ب‚é‚ج‚إ‚ ‚ء‚½پBپx
“ى‰_‚ح‚©‚½‚‚ب‚ةگشڈé‚ً‘قٹح‚·‚邱‚ئ‚ً‹‘‚ٌ‚¾‚ھپA‘گژ‚ھپw”ٍ—´پx‚ةˆع‚ء‚ؤگي“¬ژwٹِ‚ً‘±چs‚·‚é‚ׂ«‚¾‚ئگà‚¢‚ؤ‹ى’€ٹح‚ة”ً“‚¹پA‚»‚ج‚ـ‚ـ‘هکa‚ةکAچs‚µ‚½پB“ى‰_‚ةژ€‚ب‚ê‚ؤ‚حژQ–d’·‚ج‘گژ‚àگ¶‚«’p‚ًژN‚·‚ي‚¯‚ة‚¢‚©‚ب‚¢پB‚à‚؟‚ë‚ٌ•£“c‚àŒ¹“c‚àˆêڈڈ‚ة”ً“‚½پB•£“c‚حپw“‹ڈوˆُ‚ھ‘Sˆُ‘قٹح‚·‚é‚ـ‚ـ‚إ‘قٹح‚·‚é—\’è‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½‚ھپA‚»‚ج‚و‚¤‚بڈَ‘ش‚إ‚ح‚ا‚¤‚µ‚و‚¤‚à‚ب‚©‚ء‚½پxپBپw“¯‚¶چ پAŒ¹“c‚جڈ]•؛‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚½گ…•؛‚ھ‹ى‚¯‚آ‚¯‚ؤ‚«‚ؤپA”ق‚ة”ق‚جˆَ”»‚ئ—a‹à’ت’ ‚ًژè“n‚µ‚½پB‰خچذ‚ً–`‚µ‚ؤŒ¹“c‚ج•”‰®‚©‚çژو‚èڈo‚µ‚ؤ‚«‚½‚à‚ج‚炵‚©‚ء‚½پxپB‚و‚‚àŒ¹“c‚ح‚±‚ê‚ًژَ‚¯ژو‚ء‚ؤ”ً“‚½‚ئژv‚¤پB
پw“ْ–{‘¤‚ج‹Lک^‚ة‚و‚ê‚خپA‘“—´‚حپAŒك‘Oڈ\ژ“ٌڈ\Œـ•ھ‚©‚çچ¶Œ½‘¤‚ةگ®‘R‚ئ•ہ‚ٌ‚¾”ٍچs‹@‚ج—ٌ‚ج’†‚ة’¼Œ‚’eژO”‚ج–½’†‚ًژَ‚¯پA‚»‚ج‚½‚ك”ٍچsچb”آ‚ح‰خ‚جٹC‚ئ‚ب‚èپAژں‚¢‚إ”ڑ’e‚¨‚و‚ر‹›—‹ٹi”[ŒةپA’e–ٍŒةپAƒKƒ\ƒٹƒ“’™‘ Œة‚ھ—U”ڑ‚µ‚½پA‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚éپB‘Sٹح‚ھ‚·‚®‰خ‚ة•ï‚ـ‚ꂽپB‘“—´‚جٹحڈم‚إ‚ح’N‚à‚à‚¤’·‚گ¶‚«‚ج‚ر‚ç‚ê‚ب‚¢‚ج‚حپA–¾‚ç‚©‚إ‚ ‚ء‚½پB‘وˆê’e‚ھ–½’†‚µ‚ؤ‚©‚çژOڈ\•ھŒم‚ةپA–ِ–{ٹح’·‚حپu‘چˆُ‘ق‹ژپv‚ً–½‚¶‚½پB‚©‚آ‚ؤƒXƒ}پ[ƒg‚إ‚»‚جˆذ—e‚ًŒض‚ء‚½‘“—´‚حپA‹ح‚©ژOڈ\•ھ‚إپAڈؤ‚¯—ژ‚؟‚½‰خ‘’ڈê‚ئ‰»‚µ‚ؤ‚¢‚½پBٹح’·‚ھŒ©“–‚½‚ç‚ب‚¢‚ج‚إپAڈوˆُ‚ھ’T‚µ‹پ‚ك‚é‚ئپA”ق‚ح‚ـ‚¾گMچ†‘ن‚ة—§‚ء‚ؤپA‰؛‚ة‚¢‚éگ¶‘¶ژز‚ً—م‚ـ‚µپAپuƒoƒ“ƒUƒCپv‚ً‹©‚ٌ‚إ‚¢‚½پBپx
پwƒAƒپƒٹƒJ‚ج‹}چ~‰؛”ڑŒ‚‘à‚حپA‚»‚ê‚و‚è‘O‚جگ””g‚ة‚ي‚½‚éچUŒ‚‚ھژOژٹش‚©‚©‚ء‚ؤ‚à‚إ‚«‚ب‚©‚ء‚½‚±‚ئ‚ًپA‚ي‚¸‚©ژO•ھ‚إ’Bگ¬‚µ‚½‚ج‚إ‚ ‚ء‚½پB‚±‚ج‹ء’Q‚·‚ׂ«‘هڈں—ک‚جŒ´ˆِ‚ئ‚µ‚ؤ‚حپAژں‚جژO‚آ‚ج‚±‚ئ‚ھچl‚¦‚ç‚ê‚é‚إ‚ ‚낤پB‚»‚جˆê‚آ‚حپAƒ}ƒbƒNƒNƒ‰ƒXƒLƒC‚ھ—ص‹@‰•د‚ة‚»‚جچُ“G‚ً‘±‚¯‚½‚±‚ئ‚إ‚ ‚èپA‚»‚ج“ٌ‚حپA‚½‚‚ـ‚´‚鋦“¯‚إƒGƒ“ƒ^پ[ƒvƒ‰ƒCƒY‚ئƒˆپ[ƒNƒ^ƒEƒ“‚جٹ؟ٹw‘à‚ھ‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا“¯ژ‚ة–ع•Wڈم‚ةژE“‚µ‚½‚±‚ئ‚إ‚ ‚ء‚½پB‘وژO‚حپA“ْ–{‚جƒ[ƒچگي‚ھگوچs‚µ‚½—‹Œ‚‘à‚ض‚ج‘خ‰‚ة’ا‚ي‚ê‚ؤ’ل‹َ‚ة‚¢‚½‚±‚ئ‚¾‚ء‚½پBپx
ٹ®àّژه‹`ژزƒvƒ‰ƒ“ƒQ‚وپAژ©•ھ‚إڈ‘‚¢‚ؤ‚¢‚ؤ‹َ‚µ‚‚ب‚¢‚ج‚©پBŒض‚炵‚°‚ةŒf‚°‚ؤŒ©‚¹‚éژO‚آ‚ج—v‘f‚ھپAƒAƒپƒٹƒJ‚جڈںˆِ‚إ‚ب‚¢‚±‚ئ‚ً•S‚àڈ³’m‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ح’N‚و‚è‚à‚ ‚ب‚½ژ©گg‚¾پB‚»‚ج‚و‚¤‚ب—vˆِ‚ھ‘S•”ٹ®گ‹‚³‚ê‚ؤ‚àپAˆث‘R‚ئ‚µ‚ؤکAچ‡ٹح‘à‚حڈں—ک‚µ‚ؤ‚¢‚½‚±‚ئ‚ح–¾‚ç‚©‚إ‚ ‚éپBƒAƒپƒٹƒJ‚ھڈں—ک‚µ‚½‚ج‚حپA‹َ•ê‚ھچُ“G‹@‚ة”Œ©‚³‚ꂽ‚ة‚àچS‚ي‚炸پA‚»‚جŒم“ٌژٹشˆبڈم‚ة‚ي‚½‚ء‚ؤ“ْ–{‘¤‚ج”ڑŒ‚‹@‚ھ•؛‘•“]ٹ·‚µپA‚³‚ ‚ا‚¤‚¼‚ئ‚خ‚©‚è‚ة‰خ–ٍŒة‚ج‚و‚¤‚بڈَ‘ش‚ة‚µ‚ؤ‚‚ꂽ‚ئ‚±‚ë‚ةپA‹}چ~‰؛”ڑŒ‚‚µ‚ؤگ””‚إ–½’†‚إ‘S‚ؤ‚ًگپ‚ء”ٍ‚خ‚·‚±‚ئ‚ھڈo—ˆ‚½‚±‚ئˆبٹO‚ة‚ب‚¢پB‚±‚جچ¼‹\”ئچك‚ة‘خ‚µ‚ؤگلگJگي‚ً‚½‚¾ˆêگl’§‚ٌ‚¾ژwٹِٹ¯ژRŒû‚ًپAƒvƒ‰ƒ“ƒQ‚ح“O’ê“I‚ةچUŒ‚‚·‚éپB
پwژRŒû‚ح‚·‚®پu‘S‹@چ،‚و‚è”گiپA“G‹َ•ê‚ًŒ‚–إ‚¹‚ٌ‚ئ‚·پv‚ئگMچ†‚إ•ش“ڑ‚µ‚½پBڈ‚حŒü‚±‚¤‹C‚ج‹‚¢ژRŒû‚ج•`‚¢‚½ƒVƒiƒٹƒI‚ة‚ز‚ء‚½‚è‚إ‚ ‚ء‚½پB‚»‚ê‚ح•s“G‚ة‚à‘وˆêچq‹َٹح‘à‚ةژè‚ً‚©‚¯‚ؤ‚«‚½ƒAƒپƒٹƒJ‹@“®•”‘à‚ة‘خ‚µ‚ؤ‹w“¢‚ج’ة‘إ‚ً‰ء‚¦‚ؤپA‹ا–ت‚ً‹t“]‚³‚¹پA“ئ—ح‚إƒ~ƒbƒhƒE´پ\چىگي‚ً•œٹˆ‚³‚¹‚ؤپA‚»‚ê‚ـ‚إ‚ج”sگي‚جگس”C‚ً•‰‚¤“ى‰_‚ةٹçگF‚ً‚ب‚‚³‚³‚¹‚و‚¤پA‚ئ‚¢‚¤‚ج‚إ‚ ‚ء‚½پB‚±‚جƒپƒچƒhƒ‰ƒ}“I‚بچ\‘z‚حپAژRŒû‚جگ«ٹi‚ة‚±‚êˆبڈم‚ب‚‚ز‚ء‚½‚è‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚½پBپx
ژRŒû‚حƒvƒ‰ƒ“ƒQ‚جƒqƒXƒeƒٹپ[‚ج”ھ‚آ“–‚½‚è‚ًژَ‚¯‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚ ‚éپBپwŒ»‘•”ُ‚ج‚ـ‚ـ‘¦ژچUŒ‚پx‚·‚邱‚ئ‚جگ³“–گ«‚ًژہڈط‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚ء‚½ژRŒû‚ھپA‚ ‚جژ肱‚جژè‚ًژg‚ء‚ؤچ¼‹\”ئچك‚ًگ³“–‰»‚µ‚و‚¤‚ئ‚µ‚½ƒvƒ‰ƒ“ƒQ‚ج“w—ح‚ًƒuƒ`‚±‚ي‚µ‚½‚©‚ç‚إ‚ ‚éپB
پwژRŒû‚ئٹح’·‚ج‰ء—ˆ‚حپAٹح‹´‚إڈoŒ‚‚·‚é“‹ڈوˆُ‚ج‚·‚ׂؤ‚ئˆ¬ژ肵پA’Z‚¢Œ¾—t‚ًڈq‚ׂؤ‚¢‚½پB‚»‚خ‚ة‚¢‚½‹@ٹضژQ–d‚ج‹v”n•گ—Eڈچ²پiٹC‹@‚R‚Wٹْپj‚ة‚و‚ê‚خپA‚»‚ê‚حپuŒN‚½‚؟‚¾‚¯‚ًژ€‚ب‚肽‚è‚ح‚µ‚ب‚¢پv‚ئ‚¢‚¤ˆس–،چ‡‚¢‚إ‚ ‚ء‚½پB‹v”n‚ھŒ©‚ؤ‚¢‚é‚ئپAڈoŒ‚‚·‚é‘à’·‚جڈ¬—ر“¹—Y‘هˆرپiٹC•؛‚U‚Rٹْپj‚ھژ•‚ًƒKƒ^ƒKƒ^–آ‚炵‚ؤ‚¢‚½پB‚»‚ê‚ح–¾‚ç‚©‚ةپAژ€‚ً“q‚µ‚ؤ‚à‚»‚ج”C–±‚ًگ‹چs‚·‚é‚ئ‚¢‚¤”ق‚جŒإ‚¢Œˆˆس‚ج•\‚ê‚إ‚ ‚ء‚½پBپuژ„‚ح‚»‚ج‚و‚¤‚بٹ´“®“I‚بƒVپ[ƒ“‚ًŒ©‚½‚±‚ئ‚ح‚©‚آ‚ؤ‚ب‚©‚ء‚½پv‚ئ”ق‚ح‰ٌ‘z‚µ‚ؤ‚¢‚éپBپx
‚¢‚ي‚ن‚é•گژزگk‚¢‚إ‚ ‚éپB–{“–‚ة‚»‚¤‚¢‚¤ڈَ‘ش‚ة‚ب‚é‚ئژ„‚à“ا‚ٌ‚¾‚±‚ئ‚ھ‚ ‚éپB
پ@
پwژRŒû‚ح—‹Œ‚‹@‚جڈ€”ُ‚ج‚إ‚«‚é‚ج‚ً‘ز‚ء‚ؤچUŒ‚‚ً’x‚ç‚·‚و‚èپAŒ»—L‚ج•؛—ح‚إ‚إ‚«‚邾‚¯‘پ‚چUŒ‚‚ً‚©‚¯‚é“r‚ً‘I‚ٌ‚¾‚ج‚إ‚ ‚ء‚½پB‚±‚جژRŒû‚جˆ¢•”پi’چپ@‘و”ھچq‹َٹح‘à‚جژwٹِ‚ًˆêژ“I‚ةˆّ‚«‚آ‚¢‚إ‚¢‚½پj‚ة‘خ‚·‚é—vگ؟‚ة‚حژں‚ج“ٌ‚آ‚ج“_‚إ‚«‚ي‚ك‚ؤ‹»–،‚ھ‚ ‚éپBپi“ٌ‚آ‚ئ‚à‚‚¾‚ç‚ب‚¢ƒCƒ`ƒƒƒ‚ƒ“‚ب‚ج‚إ‘وˆê‚ح—ھ‚µ‚ؤ‘و“ٌ‚¾‚¯ˆب‰؛‚ة”²گˆ‚·‚éپj‘و“ٌ‚حپAژRŒû‚جŒê’²‚ة‚حپAگو”Cڈک—ٌ‚ةٹضŒW‚ب‚پA–½—كŒû’²‚ج‰e‚ھŒ©‚ç‚ê‚邱‚ئ‚إ‚ ‚éپB‚»‚ج“–ژ‚ة”ق‚ھ‚¢‚©‚ة‚¢‚ç‚¢‚炵پA‚©‚آ–ىگS‚ة”R‚¦‚ؤ‚¢‚½‚©‚ًژ¦‚·‚à‚ج‚ئŒ¾‚¦‚و‚¤پBپx
ژRŒû‚ة‚ا‚ٌ‚ب–ىگS‚ًژ‚آ—]’n‚ھ‚ ‚é‚ئ‚¢‚¤‚ج‚¾پB”ق‚حژ€‚ً“q‚µ‚ؤ•”‰؛‚ة–½—ك‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚邾‚¯‚إ‚ح‚ب‚¢‚©پB‚»‚±‚ة‚ ‚é‚ج‚ح•”‰؛‚ئ‰^–½‚ً‹¤‚ة‚·‚é‚ج‚إ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ئ‚ؤ‚à–½—ك‚إ‚«‚ب‚¢پA•Kژ€‚ج‹tڈP‚ض‚ج‘sگâ‚بٹoŒه‚ھ‚ ‚邾‚¯‚إ‚ ‚éپB‚¾‚©‚ç•”‰؛‚½‚؟‚حژRŒû‚ج–½—ك‚ًژَ‚¯‚ؤ•گژزگk‚¢‚µپAگ¶ٹز‚ً‹A‚³‚¸‚ة“ث‚ءچ‚ٌ‚إ‚¢‚ء‚½‚ج‚¾پB
پw—F‰i‹@‚حƒ~ƒbƒhƒE´پ\چUŒ‚‚جژ‚ةپA‚»‚جچ¶—ƒ‚ج”R—؟ƒ^ƒ“ƒN‚ة”ي’e‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ھپA‚»‚جڈC—‚ح‚ـ‚¾ڈI‚ي‚ء‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½پB”¼•ھ‚ج”R—؟‚إ‚ح‹A‚é”R—؟‚ةژ–Œ‡‚‚إ‚ ‚낤‚±‚ئ‚ح–¾‚ç‚©‚إ‚ ‚ء‚½‚ھپA—F‰i‚حڈو‹@‚ًٹ·‚¦‚و‚¤‚ئ‚ج•”‰؛‚½‚؟‚جچؤژO‚ةگ\‚µڈo‚ً’f‚èپA”ي’e‹@‚إڈoŒ‚‚·‚錈گS‚ً•د‚¦‚ب‚©‚ء‚½پB—F‰i‚ح‚ا‚؟‚ç‚©‚ئŒ¾‚¦‚خŒاچ‚‚ج’j‚إ‚ ‚èپA‚»‚جچl‚¦‚ب‚èٹ´ڈî‚ً‘¼گl‚ة‘إ‚؟–¾‚¯‚é‚و‚¤‚ب‚±‚ئ‚ح‚µ‚ب‚©‚ء‚½پB‚ھپB—F‰i‚ً‚و‚—‰ً‚µپA‚©‚آ‘¸Œh‚µ‚ؤ‚â‚ـ‚ب‚¢‹´Œû‚حپA—F‰i‚جƒ~ƒbƒhƒE´پ\‚ة‘خ‚·‚éچؤچUŒ‚‚جگiŒ¾‚ھپAٹشگع“I‚ة‘هچذٹQ‚ًگ¶‚ٌ‚¾‚±‚ئ‚ة‘خ‚µ‚ؤپA”ق‚ھ‚»‚جگس”C‚ً’ةٹ´‚µ‚½‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئ‚¢‚¤‹‚¢ˆَڈغ‚ًژَ‚¯‚½‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚éپB‚ـ‚½پA‹´Œû‚ح‚»‚ج‚و‚¤‚بگس”C‚ًٹ´‚؛‚¸‚ةژ€’n‚ة•‹‚¢‚½—F‰i‚ج‘àˆُ‚جگSڈî‚ًژv‚¤‚ئپA‚»‚ج‹¹‚ة“ث‚«‚³‚³‚é‚à‚ج‚ًٹo‚¦‚½پBپx
—F‰i‚ة‚و‚é‘و“ٌژںچUŒ‚‚جگiŒ¾ژ©‘ج‚ھƒKƒZ‚إ‚ ‚éپB‚و‚ء‚ؤ‘و“ٌژںچUŒ‚‚جگiŒ¾‚ھ‘هچذٹQ‚ًٹشگع“I‚ةˆّ‚«‹N‚±‚µ‚½‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حپAگس”C“]‰إ‚à‚ح‚ب‚ح‚¾‚µ‚¢ƒvƒچƒpƒKƒ“ƒ_‚إ‚ ‚éپB‚±‚ê‚ح•XژR‚جˆêٹp‚ة‰ك‚¬‚ب‚¢پBƒvƒ‰ƒ“ƒQ‚ح™ث‘ه‚بژj—؟‚ًœ“ˆس“I‚ة—p‚¢‚邱‚ئ‚إپAچ¼‹\”ئچك‚ًپwƒ~ƒbƒhƒEƒG-‚جٹïگصپx‚ئŒ`—e‚·‚é‹\لش‚جڈ‘‚ًٹ®گ¬‚³‚¹‚½‚ج‚إ‚ ‚éپB
چ•“‡‹Tگl‚ج—صڈI‚جŒ¾—t‚حپu”ٍچs‹@‚ھ“ى‚ج‹َ‚ة”ٍ‚ٌ‚إچs‚پv‚¾‚ئ‚¢‚¤پB“ى‚ج‹َ‚ض”ٍ‚ٌ‚إچs‚Œـڈ\کZ‚ًڈو‚¹‚½”ٍچs‹@‚ھ‘ز‚؟•ڑ‚¹چUŒ‚‚ً‚³‚ꂽŒمپA‘¾•½—mگي‘ˆ‚ح—l‘ٹ‚ًˆê•د‚·‚éپB‘پٹْچuکa‚جƒVƒiƒٹƒI‚حٹ®‘S‚ةˆ¬‚è‚آ‚ش‚³‚êپAچ•“‡‚حٹw“kڈoگw‚µ‚½ژلژز‚ً‘_‚¢Œ‚‚؟‚ة‚·‚é“ءچU•؛ٹي‚ًژںپX‚ةچlˆؤ‚µ‚ؤ‚¢‚پB“Œ‹‘ه‹َڈP‚ً”çگط‚è‚ة”ٌگي“¬ˆُ‚جƒWƒFƒmƒTƒCƒh‚ھژn‚ـ‚èپAŒ´”ڑ“ٹ‰؛‚إ‘ه’c‰~‚ًŒ}‚¦‚éپB‚¾‚©‚炱‚»Œـڈ\کZˆأژE’¼Œم‚ةپA“ْ•ؤٹش‚جƒ„ƒ‰ƒZ‚جکA—چŒW‚è‚ً–±‚ك‚ؤ‚¢‚½”’ڈFکNژںکY‚حپA‰ئ‘°‚¾‚¯کA‚ê‚ؤ’كگى‘؛‚ة‘aٹJ‚µ‚½‚ج‚إ‚ ‚éپB پ@
|
|
|
|
‚±‚ج‹Lژ–‚ً“ا‚ٌ‚¾گl‚ح‚±‚ٌ‚ب‹Lژ–‚à“ا‚ٌ‚إ‚¢‚ـ‚·پi•\ژ¦‚ـ‚إ20•b’ِ“xژٹش‚ھ‚©‚©‚è‚ـ‚·پBپj
پ@
پ£‚±‚جƒyپ[ƒW‚ج‚s‚n‚o‚ضپ@پ@پ@پ@پ@ پڑˆ¢ڈC—…پô > ƒJƒ‹ƒg9Œfژ¦”آ
|
|
 ƒXƒpƒ€ƒپپ[ƒ‹‚ج’†‚©‚猩‚آ‚¯ڈo‚·‚½‚ك‚ةƒپپ[ƒ‹‚جƒ^ƒCƒgƒ‹‚ة‚ح•K‚¸پuˆ¢ڈC—…‚³‚ٌ‚ضپv‚ئ‹Lڈq‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
ƒXƒpƒ€ƒپپ[ƒ‹‚ج’†‚©‚猩‚آ‚¯ڈo‚·‚½‚ك‚ةƒپپ[ƒ‹‚جƒ^ƒCƒgƒ‹‚ة‚ح•K‚¸پuˆ¢ڈC—…‚³‚ٌ‚ضپv‚ئ‹Lڈq‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB‚·‚ׂؤ‚جƒyپ[ƒW‚جˆّ—pپA“]چعپAƒٹƒ“ƒN‚ً‹–‰آ‚µ‚ـ‚·پBٹm”Fƒپپ[ƒ‹‚ح•s—v‚إ‚·پBˆّ—pŒ³ƒٹƒ“ƒN‚ً•\ژ¦‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB