http://www.asyura2.com/12/hasan77/msg/624.html
| Tweet |
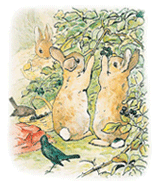
小笠原誠治の経済ニュースに異議あり! トップ |
QE3発表後の米経済の現実
2012/09/17 (月) 13:45
突然ですが、皆さんに質問したいと思います。
先日、米国のFRBがQE3を決定しましたよね。あれ、どう思います?
「どう思うかって、QE3の決定を好感して株価は上がり、そしてドル安の動きが出ていると思うけど‥」 「日本も、米国に倣って一層の金融緩和を実施すべきだという声が強くなっている‥」
多分、そう仰ると思っていました。
では、改めてお聞きしますが、では、何が功を奏しているのでしょう?
「何がって‥QE3の効果があったということだよ」
具体的に言いますと?
「だから、バーナンキ議長が言っていたように、QE3は株価に好影響を与え、また長期金利を引き下げる効果があるので、経済活動を刺激するだろうと」
確かにそんなことを言っていました。長期債の購入によって長期金利が低下し、従って、経済活動が刺激される効果が期待できる、と。
では、実際に長期金利はどうなっているのでしょう?
次のデータをご覧ください。
<米国債の利回りの推移>
10年物国債 10年物物価連動国債 差
2011年1月 3.39% 1.06% 2.33%
2011年2月 3.58% 1.24% 2.34%
2011年3月 3.41% 0.96% 2.45%
2011年4月 3.46% 0.86% 2.60%
2011年5月 3.17% 0.78% 2.39%
2011年6月 3.00% 0.76% 2.24%
2011年7月 3.00% 0.62% 2.38%
2011年8月 2.30% 0.14% 2.16%
2011年9月 1.98% 0.08% 1.90%
2011年10月 2.15% 0.19% 1.96%
2011年11月 2.01% 0.00% 2.01%
2011年12月 1.98% -0.03% 2.01%
2012年1月 1.97% -0.11% 2.08%
2012年2月 1.97% -0.25% 2.22%
2012年3月 2.17% -0.14% 2.31%
2012年4月 2.05% -0.21% 2.26%
2012年5月 1.80% -0.34% 2.14%
2012年6月 1.62% -0.50% 2.12%
2012年7月 1.53% -0.60% 2.13%
2012年8月 1.68% -0.59% 2.27%
9月4日 1.59% -0.68% 2.27%
9月5日 1.60% -0.69% 2.29%
9月6日 1.68% -0.63% 2.31%
9月7日 1.67% -0.68% 2.35%
9月10日 1.68% -0.68% 2.36%
9月11日 1.70% -0.68% 2.38%
9月12日 1.77% -0.61% 2.38%
9月13日 1.75% -0.72% 2.47%
9月14日 1.88% -0.78% 2.66%
(資料:FRB、Department of Treasury)
9月13日にQE3の決定が報じられたのですが、10年物国債の利回りは、バーナンキ議長の期待に反して、むしろ上昇しているのです。
この事実は、貴方はどう評価するでしょう?
「それは、米連銀が、住宅ローン担保証券や長期国債を大量に購入することによって紙幣を増刷することになれば、インフレになる可能性が大きくなり‥そして、インフレになるならば、長期金利はむしろ上がることもあり得ると」
私も、そう思うのです。ただ、いずれにしてもバーナンキ議長は、長期国債などの大量の購入は、長期金利の低下をもたらすメリットがあるとはっきりと述べていたにも拘わらず、実際にはこうして長期金利は上がっているのです。
では、市場は、本当にインフレになる可能性が大きくなっていると思っているのでしょうか?
そんなときには、何を見ればよいでしょうか?
「通常の長期国債の利回りと物価連動国債の利回りの差をみればいい」
そのとおり。
どういうことかと言えば、物価連動国債というのは、どんなにインフレになっても、そのインフレ分がカバーされて元本や金利が支払われるために、物価連動国債の利回りは実質金利のみしか反映せず、そしてその一方、通常の国債の利回りは、実質金利とインフレ率の双方を反映することになるのです。
つまり、
通常の国債の利回り=実質金利+予想インフレ率
物価連動国債の利回り=実質金利
従って、「通常の国債の利回り−物価連動国債の利回り=予想インフレ率」になるのです。
そして、その予想インフレ率が、上に示されたとおりQE3発表後に拡大している訳なのです。
ということで、米国の市場関係者は、今後インフレになる可能性が大きいと予想していることが分かる訳ですが‥しかし、幾ら超金融緩和策を採用しようと、否、超金融緩和策を採用するからこそ
予想インフレ率が上昇することになるのですが、そうして予想インフレ率が上がると、今度はそのことによって金利の上昇をもたらしてしまい、何のための超金融緩和策だったのかということになるのです。
だって、そうでしょ? 長期国債などを連銀が大量に購入すれば、そのことによって長期金利を引き下げ、そうなれば住宅投資や企業の設備投資などが刺激されると思ったのに、むしろインフレ懸念から金利の上昇をもたらしてしまうではないか、と。
まあ、でも、こうしたことが起きても別に不思議ではないのです。何故ならば、QE2を実施した今から2年ほど前にも似たようなことが起きた経験があるからです。
もちろん、バーナンキ議長はそのことについてはよく承知している訳で、だからこそ巷で言うQE3を実施することにも抵抗があったと思うのです。つまり、期待された効果があるかどうかは不確かだ、と。
ただ、それはそうとしても、市場がQE3を織り込み済みだと知り、そして、雇用の回復がイライラするほど遅いペースであるので、何もしないという訳にはいかなかったということなのでしょうか。
以上
http://www.gci-klug.jp/ogasawara/2012/09/17/017071.php
|
|
|
|
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
- ECBの果断、日銀の熟慮 ECBの新国債購入プログラムは張り子の虎か MR 2012/9/18 01:37:51
(0)
|
|
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。