16. 2013�N4��11�� 15:10:19
: rRzNJYtzaY
����_���B
https://www.jstage.jst.go.jp/article/pjab/89/4/89_PJA8904B-01/_pdf�_���ɂ���A���c�����a�@�́A��Ö@�l�����o�c����a�@�B ��Ö@�l�����́A���v���c�@�l�k�Е����x�����˔\������ݗ��B �������v���c�̃z�[���{�f�B�J�E���^
�L�����x���А��i�A�����J�j
FASTSCAN�@2251�^
���ʂ�2���ԑ���
���o���E�̓Z�V�E��134�A137����300Bq/bod
http://www.fukkousien-zaidan.net/body/index.html �Ƃ��낪�A�L�����x���Ђ̃z�[���y�[�W�ɂ͂e���������������@�Q�Q�T�P�Ȃ�v�a�b�́A������Ă��Ȃ��B
http://www.canberra.com/products/hp_radioprotection/fastscan.asp ���v���c�@�l�k�Е����x�����˔\�����̃z�[���y�[�W�ɂ���v�a�b�̎ʐ^������ƁA�L�����x���Ђ̂Q�Q�T�O�ɑ���������̂ł��邱�Ƃ�������B �L�����x���Ђ́A�Q�Q�T�O�̌��o���E�l�ɂ��āA�b���|�P�R�V�A�b���|�U�O�̓T�^�I�Ȍ��o�����l�́A�P���̌v���łP�W�O�x�N�����ȉ��ł���Ɛ������Ă���B
http://www.canberra.com/literature/invivo_counting/tech_papers/fastscan.pdf
http://www.asyura2.com/13/genpatu30/msg/540.html#c10 �L�����x���Ђ����\���Ă���P���v���P�W�O�x�N�������B���ł����ɁA�Q���v���R�O�O�x�N���������o�Ȃ��̂ł���i���ɓ쑊�n�s�������a�@�A���{���q�͌����J���@�\�ɂ���Q�Q�T�O���������o���E�l�j�A���́A���̂悤�Ȏ��Ԃ�������̂��A�ŏ��ɐ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �쑊�n�s�������a�@�̂v�a�b�����ł��������������A�o�b�N�O�����h�̐��ʂ������ꏊ�ōs���v�a�b�́A�o�b�N�O�����h�̐��ʂ���@���E���Ă��܂��A���m�ɑ���ł��Ȃ��\���������B������A�Q���v���R�O�O�x�N�����Ȃ̂��B �_���̐}�S�iThe ratio of 134Cs to 137Cs body concentrations�E�E�E�j���A������������Ă���B
�̓��ł́A�b���|�P�R�S���b���|�P�R�V�������I�������ɏ]���ׂ��Ȃ̂ɁA���̂������I�������ɏ]���Č����čs���X����������B
����́A�o�b�N�O�����h�̂b���|�P�R�S�̊�^�������������߂ɋN�������Ƃł͂Ȃ����낤���H
���Ȃ킿�A�v�a�b���o�b�N�O�����h�̐��ʂ��E���Ă����؋��ł͂Ȃ����낤���H �U�i�Q�P�D�S�����j�ƂP�T�i�T�S�D�Q�����j�̒j�q�̕��ϑ̏d���l����ƁA�U�Ύ��͂P�T�Ύ��̂Q�D�T�R�{�̓����픘�����Ă��Ȃ��ƁA���c�����a�@�̂v�a�b�����ł́A�s���o�ɂȂ�\���������Ȃ�B
���̖��́A���v���c�@�l�k�Е����x�����˔\�����̃z�[���y�[�W�ł́A�ȉ��̂悤�ɐ�������Ă��鎖�����B
���Ђ炽�����a�@�ł́A2012�N2��29���܂Ŋ�{�I�ɍX�߂Ȃ���WBC�������s���Ă��܂������A3��1�����X�߂�O�ꂵ�����ʁA�L�ӌ��o�҂̐������I�Ɍ����܂����B�܂�A�O����\���̗L�ӌ��o�҂̂����A�����̕��͈ߕ��ɔ��ʂɕt���������ː��Z�V�E�������o���Ă����\��������܂��B�O��̌��ʂɑ����܂܂�Ă����u�X�߂Ȃ��v�̕��̌��ʂƁA����̂悤�ɂ��ׂāu�X�߂���v�̕��̌��ʂ�P���ɔ�r����͓̂���A���̌��ʂ���A�@���N�x�ɓ����Ă���̕��ː��Z�V�E���̐ێ悪���������A�������͇A�̓�����̔r�����i�A�����A�c�O�Ȃ���ϋɓI�ɂ������Ƃł��܂���B
http://www.fukkousien-zaidan.net/research/index.html �_���ł͕\�Q�iResults of WBC�E�E�E�j�łQ�O�P�Q�N�Q���ƂR���̌��o�Ґ����ׂĂ݂�ƂP�P�R�l����X�l�}�����Ă���̂�������B �v�a�b�����̑O�ɁA�T�[�x�C���[�^�[�ňߕ�����������Ă��Ȃ����Ƃ��m�F���Ă����Ȃ���A���͈ߕ�����������Ă������ƂɂȂ�B ����ɂ��Ă̌������A����_���ɂ͂Ȃ��B
�Q�O�P�Q�N�R���ȍ~�̃f�[�^��s���悭���p���āA�����픘�͏��Ȃ������Ƃ̌��_���o���Ă��邾�����B ���Ɉ⊶�Ȃ��Ƃ́A����_�������v���c�@�l�k�Е����x�����˔\�������ߕ����A�ǂ̈ʂ̔Z�x�ʼn�������Ă����̂��������Ă��Ȃ����Ƃł���B �Ō�ɘ_���́A�v�a�b�����ɉ������q�ǂ������̉ƒ�́A���ː��h��ɊS�����������߂ɁA�������ʂ��s���o�ɂȂ�ƌ����o�C�A�X���Ȃ���Ƃ��ĎO�t���������邪�A�o�C�A�X�t���[�ƌ������߂ɂ́A�ʐڂɂ�長����蒲�����K�v�����A����͍s���Ă͂��Ȃ��B |
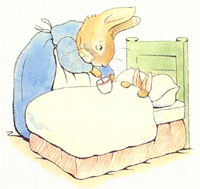
 �X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B