02. 2013年8月07日 17:55:45
: niiL5nr8dQ
ブログ:金融規制緩和と危機の芽
2013年 08月 6日 12:00 JST
2013年1月にバーゼル3の流動性規制緩和が発表されて以降、米MMFからの欧州銀のドル借入が顕著に増えている。写真は2011年2月、ポーランドのワルシャワで撮影(2013年 ロイター/Kacper Pempel) ブログ:消費増税慎重論と日銀総裁人事を結ぶ線
ブログ:意外と低い市場の参院選評価
ブログ:みずほ「1バンク」始動、残る課題は
ブログ:心静かな老後を迎えるために 森佳子 今年1月、G20諸国を中心に世界の中央銀行・金融監督当局で構成するバーゼル銀行監督委員会は、突如、バーゼル3の流動性規制の緩和を発表した。これをきっかけに、これまで規制によって割高になっていた金融機関の短期資金調達コストは低下し裁定取引が復活した。この面だけみれば、規制で低下した市場の効率性が回復したと言えるかもしれない。 今回の規制緩和の背景には、欧米金融機関による活発なロビー活動があった。金融界は、当初案どおりに規制が実施されれば、銀行間や企業・個人向けの融資が行いにくくなるとの予想をもとに、規制緩和を強く求めていた。 流動性規制の主軸であるリクイディティ・カバレッジ・レシオ(LCR)は市場から資金調達できない事態に備えて金融機関に流動性確保を促すもので、30日間の流動性枯渇期間に起こりうるキャッシュ流出額と同額またはそれ以上の流動性資産の保有を義務付ける。国際金融協会(IIF)の推計によれば、2010年末時点のLCRは日本が108%、スイスが87%、米国が86%、英国が81%、ユーロ圏が69%と、特にユーロ圏の金融機関がこの面で立ち遅れている。 世界金融危機を経て11年半ば頃まで、欧州銀は米国のMMF(マネー・マーケット・ファンド)経由で大量のドル資金を調達した。しかし、その後の欧州危機を受けて、米MMFは欧州銀から急激に資金を引き揚げた。深刻な資金調達難に直面した欧州銀は欧州中央銀行(ECB)による3年物流動性供給オペ(LTRO)の助けを借りつつ、短期のホールセールファンディングに頼り過ぎず、危機を繰り返さないバランスシートの構築へ向けて努力を続けていた。 ところが、LCR緩和を挟んで事態は一変した。 今年に入って欧州銀では米MMFからのドル借入が顕著に増えてきている。12年12月末比で、同借入はスイス銀や英銀で22%増、仏銀で21%増、オランダ銀で17%増、独銀で6%増となっている。 為替スワップ取引では、金融規制で調達コストが上昇したため裁定が効かない状況が続いていたが、LCR緩和によって「規制プレミアム」は消失し、裁定取引ができる環境になった。 MMFや為替スワップで調達された短期資金は、欧州銀において、投資ポジションに充てられるほか、不採算資産のファンディングにも充当される。 グローバルな金融危機の後処理が終わっていない中で、今回のLCR緩和で息を吹き返す金融機関の短期調達と高リスク投資。これらは今回もまた危機の温床となるだろうか。数年後に振り返って後悔の少ない金融行政のあり方について考えさせられる。 [東京 6日 ロイター]
|
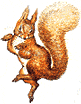
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。