http://www.asyura2.com/23/ban11/msg/744.html
| Tweet | �@ |
(��: �V�c�ꑰ�ɂ��l�g�����Ɠ��{�E�A�W�A�N���̗��j ���e�� ���엲 ���� 2024 �N 5 �� 16 �� 17:58:11)
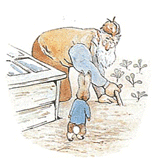
�_�������͎��ۂɂ������Ƃ���A����Q�T�O�N����R�O�O�N���̏o����
�V�Ƒ�_���_���V�c���퐶�l�ł͂Ȃ��������nchousen�l�ł��B
�Echousen �Œ��]�̈�얯�Ɛ��ɉ͗���̋o(�L�r)�_�k�����������Č�����{�l�ƑS��������`�q�̓��{���b�����y�핶���l(�`�l)�ɂȂ�
�Echousen �̖��y�핶���l(�`�l)���k��B�Ɉږ����Đ��c�_�k���n�߂�
�E�\�E���ɋ����������̓V�c�ꑰ���k��B�Ɉږ��A�A���s�s�̈ɓs�������A���{�l�z��(����)�����E�S�ƌ�������z��f�Ղʼn҂��ł����B�㊿�̌����邪����������(���ϓz������)�́u�ϓz�v�́u���Ɓv�ƓǂށB
�E�_�������E�`���嗐 �� �V�c�ꑰ�������E��a�E�O��ɓV���~�ՁA�ꕶ���͂��W�F�m�T�C�h�A�Ⴂ�ꕶ�����͎E���Ȃ��Ő��z��ɂ����B
�E���}�g�^�P���̓��� �� �֓��̓ꕶ���͂��W�F�m�T�C�h�A�Ⴂ�ꕶ�����͎E���Ȃ��Ő��z��ɂ����B
�E���c�����C�̉ڈΐ��� �� ���k�̓ꕶ���͂��W�F�m�T�C�h�A�Ⴂ�ꕶ�����͎E���Ȃ��Ő��z��ɂ����B
��������
���{�̎x�z�҂͍����̂� chousen �l�Ȃ̂Ŏc�s�Ŕ�l�ԓI�A�ǂ�ȍ������ł����R�Ǝ��s�ł���̂ł�
���̓��{�Ő����c���Ă���ꕶ�l�̓A�C�k�l�A�ꕶ�n�����l�A�퍷�ʓ��a�����������ł��B
�V�c�Ƃ͊������ŕS�ό��b���Ă����A
�퐶�l(chousen�̖��y�핶���l)�͓��{���b���Ă����A
�ꕶ�l�̓A�C�k���b���Ă����B
���}�g�̉p�Y�@���}�g�^�P���i=���`��x�j�@���c�����C�i=�S�Ϗo���̍݃R���j
���}�g�̉��@�����V�c�i=�ꂿ��S�ϐl�j
���}�g�̐M�@��א_�i=�n���n�̐`�����L�߂�j�@
���}�g�̍��j�@���{���I�i=�S�ϐl�̕Ҏ[�j
���}�g�̓V�@���V���i=chousen�����j
�����o�g�̃X�������̘a��拍��ɂ͂��Ȃ炸�u�V�v�����B���I�Łu�V�v�� chousen �������w���B
��������
�c���j�ς͐_�����ʂ��u�a�b660�N�v�Ƃ������A�߉ϒʐ��́u�`�c���N�v�A�v�ĖM���́u�`�c�U�N�v�A�Ƃ��A���؏C�O�́w�I�N����ǂ���x�i2000�N�j�ɂ����āu�a�b29�N�v�A���l�_���́w�Ñ���{�́u��v�̎���������������x�i2012�N�j�ɂ����āu�a�b70�N�v�Ƃ����B
�@�����ɑ��āA�L�I�̔N�㕪�͂ɂ����ď��߂ē��v�I�ɉȊw�I���͂��s�����̂́A���{���T���ł���i�}�Q�Ɓj�B���͌Ñ�̓V�c�A�����E�ߐ��̏��R�A�����E���m�̉��݈̍ʔN������A�Ñ�剤�̕��ύ݈ʔN�����10�N�Ƃ��A�_�����ʂ��u�`�c271�N���v�Ƃ��铝�v�I�Ȑ�����s�����B
http://hinakoku.blog100.fc2.com/blog-entry-70.html
�u���{���I�̐_���I�v������ƁA�ނ�́A���p�܂ł���Ă��āA�u�o���̃i�K�X�l�q�R�v�Ƃ̐퓬�̎��ɁA�M�œ��������Ái���݂̓����s�������t�߁j�܂Ői�o���ė��܂��A�����ł̐퓬�ŁA�Z�̌ܐ��������������̂ŁA����i���݂̑��s����搼��������t�߁j���M�Ōo�R���ēP�ނ������C�i���يC�A���p�j�ɏo���Ƃ̋L�q������܂��B
���݂̒n�`�ł́A�u���Â�����v�����n�ŁA�M�œ��B������ʉ߂����肷�邱�Ƃ��ł��܂���B
�ł��A�Q�T�O�N����R�O�O�N���̖퐶����̌㔼�ɂ́A���p�̉��ɉ͓��p�Ƃ����̂�����A���̓�̘p�f����悤�Ȕ�����̒n�`�i�В���n�j�̐�[�������J���Ă��āA�C�����͓��p�ɂ��������Ă����̂ł��B
���̌�A�͐ϕ��ɂ��ӂ������ĉ͓��ɂȂ�A�ӂ��������Ƃ��낪�u����v�ł��B
���̂悤�ɁA�u�_���v���������Ă������̏����A���ɓ`�����Ă��܂��̂ŁA�����Ƃ��ẮA�Q�T�O�N����R�O�O�N����̂��Ƃ��ƍl�����܂��B
���l�_���͐_���������͓����̎��ゾ�Ǝ咣���Ă��܂����A�͓��·T�̎��オ�������F
�E�Ñ�㕽��̎���F��2���N�O
�E�É͓�����̎���F��9000�N�O
�E�͓��pI�̎���F��7000�N�`6000�N�O
�E�͓��pII�̎���F��5000�N�`4000�N�O
�E�͓����̎���F��3000�N�`2000�N�O�iBC1050�N�`BC50�N�j
�E�͓���I�̎���F��1800�N�`1600�N�O�iAD150�N����350�N�j
�E�͓���II�̎���`��㕽��I�EII�̎���F��1600�N�O�ȍ~
http://altairposeidon.hatenablog.com/entry/2018/10/11/000000
���l�_���́A�_���������A�͓����̎��ゾ�Ǝ咣���Ă��܂����A���̂悤�ȗ��R����A�͓��·T�̎���ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�u���{���I�v�_�����ʂR�N�O�Q��11���ɁA�c�R���A��g��ɒ������Ƃ���Ƃ��A���������������đ�ϑ����������̂́ip.28�j�A���˓��C�ł͌��݂��A�����̕������A��U���Ԃ��ƂŁA�ۂ̉Y�t�߂𒆐S�ɁA�������ƊO�����ŁA���݂ɕω�����̂ŁA���̉e���Ɛ����ł��܂��B
�@����āA�͓�����͓��́A�o�����ł̗��o���Ƃ́A���W�Ƃ݂��A�R��10���ɁA���k���āA�͓����������̐_�̔����Âɒ������̂��ip.29�j�A�����́A�ύڂ��Ă��A���܂蒾�ݍ��܂Ȃ��A���\���D���ۖ؏M�Ȃ̂ŁA�����ĕ����鐅�ʂ̐��ۂȂ�A���ꂪ�������₩�Ȃ̂ŁA�t�炦��ł��傤�B
�@�]�k�ł����A�u���{���I�v�̖ɂ́A��ƋL�ڂ���Ă��܂����A�����ɂ́A��ƋL�ڂ���Ă��炸�A�u�����k�i�����̂ځj���āv�ƂȂ��Ă���A�������Γ��̐�́A���ł��B
�@���������A��g�̖x�]�̊J�킪���H�����T���I�ȑO�ɁA�D�Ő��˓��C�����a�ցA�l�E����A������ۂɂ́A��a�쐅�n��k�サ���Ƃ݂��A����Ȃ�͓����ł��͓��ł��A�i���ł����͂��ŁA�M�҂��R�D�Ƃ����Ă���̂́ip.34�j�A�����܂��Ȃ������A�\���D��z�肵������ł͂Ȃ��ł��傤���B
�ǂ����A���l�_�����A�_���V�c�̑��ʂ��A�I���O70�N�Ƃ����̂́A�V���̌������A�I���O57�N�A�����̌������A�I���O37�N�A�S�ς̌������A�I���O18�N�Ƃ���Ă���̂ŁA�����ɑR�E�D�z���悤�Ƃ��������ɂ����A�݂��Ȃ��̂́A�������ł��傤���B
��������
�r�_�J����o�y�������ʂ̓����̖��[�N��Ɩ��[���ꂽ���R
�r�_�J����358�{�̓������o�y���ċv�����̂ł����A�����̓����͂����떄�߂�ꂽ�̂�����������܂��B���ݍł��x������Ă��閄�[�N��Ɩ��[���ꂽ���R�������Ă��������B
�A���T�[
1�@���[�N��ɂ���
�@�@���@�����n�w�ɒY���������������ēy������A�Ӓ��A.D.250�} 80��A.D.1250�} 80�̔N�㑪�茋�ʂ��o�Ă��܂����A���q����͂��蓾�Ȃ��̂ŁA�O�҂ł���ƌ��_�t���Ă��܂��B
�@�@�R���I�ł��ˁB
�@�@�@���@�r�_�J��Ք��@�����T��3�i����������ψ���j�Q��
2�@���R�ɂ���
�@�@�i�炭�s���ł������A�卑�傪������̍ۂɋ����̋V���Ƃ��ĕ���[�����Ƃ̐V�����o�Ă��܂��B�i���k��w���_�����F�c���p�����j
�@�@���@���ꂽ�����̂قƂ�ǂ�✖�A�������ł͂Ȃ��A�ォ�獏��Ă���̂��A���������R�s���ł����B
�@�@������p�����Ďg�p���Ȃ��Ƃ̈Ӗ�������Ɛ������Ă��܂��B
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13278059.html
�@
|
|
������@�@�@�@�@ �����C���� > �ԊO�n11�f�����@���� �@�O��
|
|
�ŐV���e�E�R�����g�S�����X�g �@�R�����g���e�̓����}�K�ő����z�M �@�X�����Ĉ˗��X��
������@�@�@�@�@ �����C���� > �ԊO�n11�f�����@���� �@�O��
|
|
 �X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B���ׂẴy�[�W�����p�A�]�ځA�����N���������܂��B�m�F���[���͕s�v�ł��B���p�������N��\�����Ă��������B