http://www.asyura2.com/24/gaikokujin3/msg/372.html
| Tweet |
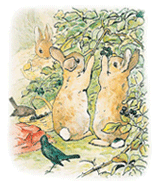
【学者が猛反対】菅政権の任命拒否から5年、今度は法人化ゴリ押し、国が「日本学術会議」を狙い撃ちする理由を探る/JBpress
須田 桃子
https://www.msn.com/ja-jp/news/national/%E5%AD%A6%E8%80%85%E3%81%8C%E7%8C%9B%E5%8F%8D%E5%AF%BE-%E8%8F%85%E6%94%BF%E6%A8%A9%E3%81%AE%E4%BB%BB%E5%91%BD%E6%8B%92%E5%90%A6%E3%81%8B%E3%82%895%E5%B9%B4-%E4%BB%8A%E5%BA%A6%E3%81%AF%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%8C%96%E3%82%B4%E3%83%AA%E6%8A%BC%E3%81%97-%E5%9B%BD%E3%81%8C-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%AD%A6%E8%A1%93%E4%BC%9A%E8%AD%B0-%E3%82%92%E7%8B%99%E3%81%84%E6%92%83%E3%81%A1%E3%81%99%E3%82%8B%E7%90%86%E7%94%B1%E3%82%92%E6%8E%A2%E3%82%8B/ar-AA1GirAl?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=a17b4f0223fe4192978d00b66b2868c6&ei=48
(須田桃子:科学ジャーナリスト)
日本の学術の“終わりの始まり”になるのでは――。
ノーベル物理学賞受賞者で日本学術会議の前会長、梶田隆章・東京大卓越教授が今年2月に記者会見で述べた懸念が、今、現実味を帯びつつある。
強行採決が目前
学術会議を国の特別機関から特殊法人へと改編する法案の審議が、参議院で大詰めを迎えた。
近日中にも所管の内閣委員会で強行採決されるかもしれないという緊迫した状況の中、国会前では連日のように、法案に反対する学者や市民による座り込みや集会が行われている。
梶田氏をはじめ学術会議の歴代の会長6人は国会に廃案を求める声明を出しており、学術会議も4月の総会で修正を求める決議をした。学会や学協会からは法案の廃案や修正を求める声明が続々と発表され、その数は5月末までに100を超えた。
市民からも約6万8000筆のオンライン署名が集まっている(しかし内閣府は3日、職員の多忙を理由に、最近集まった約4万2000筆の面会による受け取りを拒否した)。
法案の内容や提出までの経緯には、極めて深刻な、かつ多くの問題がある。会員選考や活動に政府がさまざまな形で関与できる仕組みを盛り込んだ現行の法案による法人化がなされれば、ナショナルアカデミーとしての機能は強まるどころか、むしろ弱体化していくに違いない。
日本の科学研究や科学技術政策を取材してきた1人として、強い危機感を抱いている。
法案の問題点
筆者がなぜそれほどの危機感を持っているのか、その理由を説明する前に、すでに指摘されている問題点を簡単に整理しておきたい。
ナショナルアカデミー、すなわち国の科学者コミュニティを代表して政策提言をする学術団体は主要各国にあり、日本でその役割を担っているのが学術会議だ。
自然科学から人文・社会科学まで幅広い分野から選出された会員210人が検討や議論を重ね、政府や社会に対する科学的助言として、年間数十件の提言や報告、勧告などをまとめている。40を超える国際学術団体に加入し、国際会議を共同主催するなど、海外の科学者コミュニティとの交流も盛んだ。
現在の学術会議は政府から独立した国の特別機関という位置付けだが、今回の法案では、国から独立させ、特殊法人として再編するとしている。
法案で最も問題視されているのは、会員の選考や日々の活動への政府の介入を可能にする、新たな仕組みが盛り込まれていることだ。
まず選考についてみてみよう。
現在は現会員が自分たちで次の会員候補者を推薦する方法(コ・オプテーション)で、これは各国の多くのナショナルアカデミーが採用する標準的な会員選考方式として知られる。
一方、2026年10月の新法人発足時とその3年後の会員選定では、特別に設置された選考委員会が候補者を選ぶ。この委員会のメンバーは、会長が首相の指定する学識経験者と協議して決めなければならない。
その後は会員で構成された委員会が候補者を選ぶが、その際、会員以外で構成される「選定助言委員会」に意見を聞くことが半ば義務付けられている。
活動に関しても外部から目を光らせる仕組みができる。いずれも会員以外で構成される「運営助言委員会」、「監事」、「評価委員会」が新たに設置されるのだ。監事と評価委員会のメンバーは首相が任命する。
幾重にも張り巡らされた管理システム。これでは新法人が現在のような独立性や自律性を保てなくなるのは必至だ。
財政基盤の脆弱性も心配される。現在の年間予算はおよそ9億~10億円。全額国費で賄われているが、これは米国や英国、ドイツのナショナルアカデミーが受けている公的資金とは比較にならないほど少ない額で、実質、手弁当の活動も多いと聞く。
法案では、政府が必要な金額を「補助することができる」としているが、2004年に法人化された国立大学が、翌年から運営費交付金を年1%ずつ減らされていった事実に照らしても、将来にわたり同規模の補助金が確保される保証はない。当然、外部の委員会の評価結果もその額に反映されていくだろう。
個々の会員の学問の自由や思想・信条の自由が直接、脅かされる危険性すらある。坂井学・内閣府特命担当大臣は5月9日の衆議院内閣委員会で「特定のイデオロギーや党派的主張を繰り返す会員は今度の法案で解任できる」と答弁した。かつての思想統制をほうふつとさせる発言だ。
「学術会議が政府従属的な疑似ナショナルアカデミー、似非(えせ)ナショナルアカデミーに変貌してしまう」
6月3日の参議院内閣委員会で、参考人の川嶋四郎・同志社大法学部教授がそう訴えたのも当然だろう。主要国のナショナルアカデミーでは、中国とロシアで会員選考に政府の介入の仕組みがあるが、英米仏には存在しないという。
経緯の問題
法案提出の経緯にまつわる問題にも触れておきたい。
そもそもの発端は、2020年10月に起きた、当時の菅義偉首相による新会員6人の任命拒否だった。
日本学術会議法では、首相による任命はあくまで形式的なものとされ、1983年の国会答弁で政府自身がそれを認めている。任命拒否の違法性が指摘され、批判が高まる中、菅氏は具体的な理由の説明を拒んだ。
問題を棚上げする一方で、政府は「活動が見えない」などとして学術会議への圧力を強め、与党の自民党は学術会議の「改革」に向けたプロジェクトチーム(PT)を設置した。今回の法案は、20年12月に自民党PTがまとめた提言に近い内容になっている。
任命拒否を巡っては、2018年に政府が法解釈を密かに変更していたことも明らかになっている。変更の経緯が分かる文書の全面的な開示を求めた裁判で、東京地裁は5月16日、「公益性が極めて大きい」として開示を命じる判決を出した。政府は控訴し、係争中を理由に開示を拒否している。
参議院内閣委員会では、委員から「法案ができてから公開されても遅い。法案審議をいったん止めて判決が出るまで待つべきだ」という意見も出ている。
政府の真の狙いは?
いわば究極の「論点ずらし」によって始まった学術会議の「改革」だが、政府の狙いは任命拒否問題をうやむやにし、会員選考への間接的介入を合法化することだけではないだろう。
それが透けて見えるのが、法案の中で現行法から消えた文言だ。「科学が文化国家の基礎」「わが国の平和的復興」といった従来の理念を示す前文が削除された一方で、「学術に関する知見が(中略)経済社会の健全な発展の基盤となる」が盛り込まれた。
「独立して職務を行う」という表現もなくなった。国が運営上の「自主性及び自立性」に「配慮」すべきとしているものの、独立性を担保する言葉は見られない。一方、「内閣総理大臣」が登場する箇所は、現行法の7回から44回に増えた。
「平和」が消えた背景には、おそらく「デュアルユース(軍民両用)研究」を推進したいという政府の思惑もあるだろう。
学術会議は、先の大戦で科学者が戦争に協力したことへの深い反省に基づき、1959年と1967年の2回にわたり軍事研究は行わないと宣言し、2017年の声明でも軍事的安全保障研究への懸念を表明したが、それらに対し、これまで複数の閣僚や自民党幹部が苛立ちや疑問を呈してきたからだ。
例えば下村博文・自民党政調会長(当時)は、任命拒否から間もない2020年11月の毎日新聞によるインタビューで「そこまでこだわるのであれば、行政機関から外れてやるべきではないか」と述べている。
内閣委員会で学術会議を批判した参考人
前述のような問題点から、筆者は現行の法案がもし通れば、学術会議が大きく変質し、弱体化することは避けられないと考えてきた。
しかし、6月3日の内閣委員会をインターネット中継で傍聴し、参考人の上山隆大・政策研究大学院大学客員教授が学術会議への批判をとうとうと述べるのを耳にしながら、ふと、想定される未来はそれより深刻かもしれない、という思いが浮かんだ。
その思いは、翌日の夕方に国会前で行われた座り込みで、任命拒否に遭った当事者の1人である加藤陽子・東京大教授が、「学術会議がなくなってもいいという覚悟で(法案を)書いているのではないか」と述べたときにより強まった。
上山氏は、「総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)」で2025年3月上旬までの9年間、3期にわたり常勤議員を務めた人物だ。CSTIは、内閣府に設置された「重要政策に関する会議」の一つで、首相が議長を務め、閣僚や有識者、学術会議会長の計14人で構成される。上山氏は有識者の中で唯一の常勤議員だった。
学術会議が政府とは独立の立場で科学者の意見を集約するボトムアップ型の政策提言をするのに対し、CSTIは政府とともにトップダウン型で科学技術政策の形成に携わる。
「学者の代表機関」である学術会議と、「科学技術の司令塔」であるCSTI。両機関はよく日本の科学技術政策にとっての「車の両輪」にたとえられてきた。
上山氏は、今回の法案提出に先立ち内閣府が設置し、学術会議の法人化について議論した有識者懇談会のメンバーでもある。
座り込みの際の演説で加藤氏は、「車の両輪」の片方の機関の中心メンバーが、役割の相反するもう片方の機関の再編に向けた議論に深く関わるいびつさを指摘したうえで、次のような見解を示した。
「有識者懇談会の最終報告書は、本来の学術会議が果たすべき役割についての過去の実績を評価するものではなく、(トップダウン型の組織に求める)全く別の尺度からの評価軸を当てはめて、問題が多い組織だと認定した。内閣府はトップダウン型のCSTIの一方的な評価によって、ボトムアップ型の学術会議の改革を目指している。トップダウン型とボトムアップ型の2つは不要だと考えたのではないか」
そのうえで、加藤氏はこうも述べた。
「本来トップダウンとボトムアップがあることによって正しい科学技術政策が導かれるが、CSTIは学術会議がボロボロになってなくなってもいいと思っているのだと、私は思います」
加藤氏の言葉通り、内閣委員会で上山氏は、「(各国のアカデミーのような助言活動が)今の学術会議にできるとは思わない。各国のアカデミーとの対話は真摯な形では成立しないであろうと思うほどの彼我の差がある」「諸外国のアカデミーと比較したときの最大の残念な点は、わが国のアカデミー(学術会議)にそこまでの権威がないこと」と、学術会議のこれまでの実績を根底から否定するような発言を繰り返した。
上山氏はさらに、それらの原因の一つとして学術会議の年間予算の少なさに言及し、その状況を改善するためにも法人化し、政府の助成金や民間からの寄付を自らの努力で募ることが必要だと力説した。
筆者自身、こうした見解を聞きながら大きな違和感を覚えずにはいられなかった。なぜならCSTI自身は、国が1950億円を投じて最長で10年間支援するムーンショット型研究開発制度などさまざまな大型研究開発事業を林立させ、国の潤沢な予算を使って運営しているからだ。
いずれの事業も「出口志向」と「選択と集中」という近年の日本の科学技術政策の特徴を象徴するようなプロジェクトだが、巨額の投資に見合った成果が得られたのか、各課題への資金配分や研究の進め方が適切だったかを検証し、公表する仕組みは十分とは言い難い。
例えば現在第3期目が進められている「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)」は、第1期の実績が全く検証されないまま第2期の実施が決まっていたことが、以前筆者も携わった毎日新聞の連載「幻の科学技術立国」取材班によって報じられている。
さらに言えば、CSTIの有識者議員の人選も不透明だ。内閣府設置法で有識者議員は「科学または技術に関して優れた識見を有する者」と定められているが、その具体的な選考方法は公表されていない。
任命拒否をした菅氏は2020年当時、学術会議について「閉鎖的で既得権益のようになっている」と繰り返したが、予算や人材などの資源配分に直接的な発言権を持つCSTIこそ、透明性を高めるべきだろう。
トップダウンだけではイノベーションは生まれない
日本の研究力は相対的に低下しつつあるが、私はこれまでの取材から、その大きな要因は、国立大学の運営費交付金の削減と、過度な選択と集中、さらにボトムアップ型の基礎研究の軽視だと考えている。
長期的な視野に立ってボトムアップ型で科学者の意見を集約し、時には政府やCSTIにとって耳の痛い内容も提言する学術会議の役割は大きい。学術会議が法人化によって弱体化し、仮にも「なくなって」しまったら、もはやCSTIの方針に口をはさむ機関はなくなる。科学技術政策における「出口志向」と「選択と集中」の傾向はますます強まり、研究力のさらなる低下を招くのではないだろうか。
それは、政府やCSTIが追い求めるイノベーションの芽も生まれてこなくなることを意味する。
車は片輪だけでは走れない。多くの反対や懸念の声を無視してこの法案を成立させることは、梶田氏が憂慮するように、まさに“終わりの始まり”になるだろう。日本の学術は今、大きな分岐点に立っている。
|
|
|
|
最新投稿・コメント全文リスト コメント投稿はメルマガで即時配信 スレ建て依頼スレ
|
|
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。