http://www.asyura2.com/24/health19/msg/141.html
| Tweet |
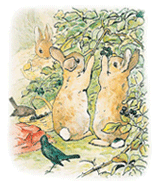
youtubeやSNSやニュースで、「今」のことが、自分にとって重要だ!と思い込んでしまうのは、どのような理由か?youtubeやSNSやニュースでやるようなことは、1日経過すれば忘れてしまうような、どうでもよい価値がないことだと思うのだが。
ChatGPT
とても良い問いですね。
「YouTubeやSNSやニュースで見聞きする“今”が、自分にとって重要だ!」と思い込んでしまうのには、人間の認知の仕組みや心理が深く関わっています。大きく分けると以下のような理由があります。
1. 新規性と脳の報酬系
脳は「新しい情報」に強く反応します。
新しい動画やニュースは、脳にとって「獲物」に近く、ドーパミンが分泌されて「重要だ」と感じやすい。
そのため、本当は大した内容でなくても「価値がある!」と錯覚しやすい。
2. 社会的比較と承認欲求
SNSやニュースは「他人が反応していること」を大量に見せます。
「みんなが話題にしている=自分も知らないと取り残されるかも」という**FOMO(Fear of Missing Out)**の心理が働く。
実際は1日経てば誰も気にしていない話題でも、リアルタイムでは「必須知識」のように感じてしまう。
3. 即時性と可視化の強化
SNSやニュースは「リアルタイム更新」が本質。
「今まさに起きていること」が目の前で可視化されると、過去や未来より“現在”が強調され、錯覚的に「重大事」に思える。
これは「利用者を画面に引き止める設計」の一部でもある。
4. 感情に訴える仕組み
怒り・驚き・不安といった強い感情を呼び起こすコンテンツほど拡散されやすい。
脳は感情をともなう情報を「重要だ」とマークしやすい。
結果的に、冷静に見れば取るに足らない話題でも、当事者にとっては「大事件」に感じる。
5. 短期的な記憶のトリック
脳は「目の前の刺激」を優先処理するため、短期的には「最重要!」と感じる。
でも時間が経てば定着しないので、翌日には忘れる。
つまり、「その時に強く大事に思ったこと」と「本当に人生に大事なこと」の間には、必ずギャップがある。
✅ まとめると
YouTube・SNS・ニュースは 「新しい × 社会的 × 感情的 × 即時性」 を最大限に利用して、脳に「これは重要!」と思わせる仕組みを持っています。
でも、それは「一時的にそう錯覚させられている」だけで、実際には人生に残るような価値を持たないことが多いのです。
では「YouTubeやSNSやニュースの錯覚(“今”が重要に思えてしまう感覚)」から距離をとるための 心構えや習慣 を詳しく整理しますね。
1. 心構え(マインドセット)
① 「一日後にはどうでもよくなる」前提で見る
目に入ったニュースやSNS投稿は「明日も価値があるか?」と自問する。
8割以上は「明日には忘れていいこと」と割り切る。
② 「情報は消費財」だと理解する
ネット情報の多くは“ファストフード”と同じ。
美味しくても栄養は薄い → 「ほどほどに」が正解。
③ 「自分が本当に大事にしたいテーマ」を決める
家族・健康・仕事・趣味など、自分にとっての“長期的に価値あること”を先に設定しておく。
それ以外の情報は「あくまで暇つぶし」と位置づけやすくなる。
2. 習慣(実践方法)
① 情報の「見る時間」を決める
例:朝30分だけニュース、SNSは夜寝る前に15分だけ。
これだけで「受け身」から「自分で選んで見る」に変わる。
② SNS・ニュースアプリの通知を切る
通知が来ると脳は「今すぐ大事」と錯覚する。
自分から取りに行く形にするだけで、急にどうでもよく見える。
③ 情報を「寝かせてから判断」する
面白いニュースや動画を見ても、すぐ反応せず「明日も気になるか」を確認する。
翌日もまだ関心があるものだけ深掘りする。
④ 「インプット:アウトプット比率」を意識する
見る時間と同じくらい、書く・話す・考える時間に使う。
ただ受け取るだけだと“錯覚”に飲まれやすい。
⑤ 情報より「経験」を優先する
1時間SNSを見る代わりに、散歩や読書や友人と会話する。
経験は長期的に記憶に残るが、情報はすぐ消える。
3. ミニ・テクニック
ホーム画面からSNSアプリを消す(検索して開く手間をあえて作る)
週に1日はデジタル断食(土曜はSNS・ニュース断ちなど)
「これは1年後も大事か?」フィルターを使う
✅ まとめると
「錯覚から距離をとる」には、
心の中で「明日も大事か?」と問い、
習慣として「通知を切り、時間を決め、寝かせて判断」し、
情報より経験や自分の価値観を優先すること。
Perplexity
なぜ「今」の情報を重要だと感じてしまうのか
結論(要約)
多くの人がYouTubeやSNS、ニュースで流れる最新情報を「重要だ」と感じるのは、脳の認知バイアスや報酬系メカニズム、社会的要因が組み合わさるためです。実際には多くの情報が一日で忘れ去られるような短命的・断片的なものであり、本来の価値は限定的ですが、「今」を追いかけ続けてしまうのは以下の理由によります。
1. 認知バイアスによる影響
1.1 新しさ効果(Recency Effect)
人は直近に得た情報を過度に重視する傾向がある。
SNSのフィードは新着順やアルゴリズムによって常に最新情報を提示し、このバイアスを強化する。
1.2 アベイラビリティ・ヒューリスティック(Availability Heuristic)
頻繁に目にする情報を実際よりも重要と判断しやすい。
通知やリマインダーが絶えず「話題」を思い起こさせ、忘れづらくなる。
2. 脳の報酬系とドーパミン
SNSの「いいね」や動画再生数などの即時フィードバックは、ドーパミンを分泌させる。
ドーパミンは「もっと見たい」「もっと知りたい」という欲求を強め、次々と最新情報を追わせる。
3. 社会的承認とFOMO(Fear Of Missing Out)
周囲が話題にしていると、「自分だけ知らないのでは」という不安が生じる。
情報をキャッチアップすることで所属感や承認欲求を満たそうとする。
4. アルゴリズムと注意の奪い合い
プラットフォーム側は注意時間の最大化を目的として設計されており、
ユーザーが長く滞在するように次々と新しい刺激を提供する。
5. 一過性コンテンツの特徴と問題点
特徴 効果 問題点
短時間で消費可能 手軽さゆえに頻繁にアクセスされる 実生活への応用・記憶定着が乏しい
感情的刺激が強い 注意を一瞬で引きつける 長期的には疲弊や情報過負荷を引き起こす
多様かつ断片的 常に新鮮な体験を提供する 実質的に重要度の低い情報に時間を浪費しがち
6. 対策・意識改善のヒント
情報ダイエット
閲覧時間を制限し、通知のオフやSNSアプリのアンインストールも検討する。
目的を持った情報収集
何のために情報を得るのかを明確にし、必要な情報源に絞る。
深く学ぶ
興味のあるテーマは書籍や専門記事などで深掘りし、短命的な情報から脱却する。
マインドフルネス
今この瞬間に意識を向ける瞑想や呼吸法で、情報への過度な依存を緩和する。
まとめ
「今」のニュースやSNSのトレンドは、脳の認知バイアスや報酬系、社会的承認欲求、アルゴリズム設計などが複合的に作用して重要視されやすいものの、多くは一過性で実生活には大きな影響をもたらしません。情報の消費量や質を自覚的にコントロールし、長期的に価値を生むコンテンツへの投資を意識することが大切です。
|
|
▲上へ ★阿修羅♪ > 不安と不健康19掲示板 次へ 前へ
|
|
最新投稿・コメント全文リスト コメント投稿はメルマガで即時配信 スレ建て依頼スレ
▲上へ ★阿修羅♪ > 不安と不健康19掲示板 次へ 前へ
|
|
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。