http://www.asyura2.com/25/senkyo297/msg/281.html
| Tweet | �@ |

��2025�N5��8���@�����Q���_�C1�ʁ@���ʃN���b�N�g��

�����ʔ���
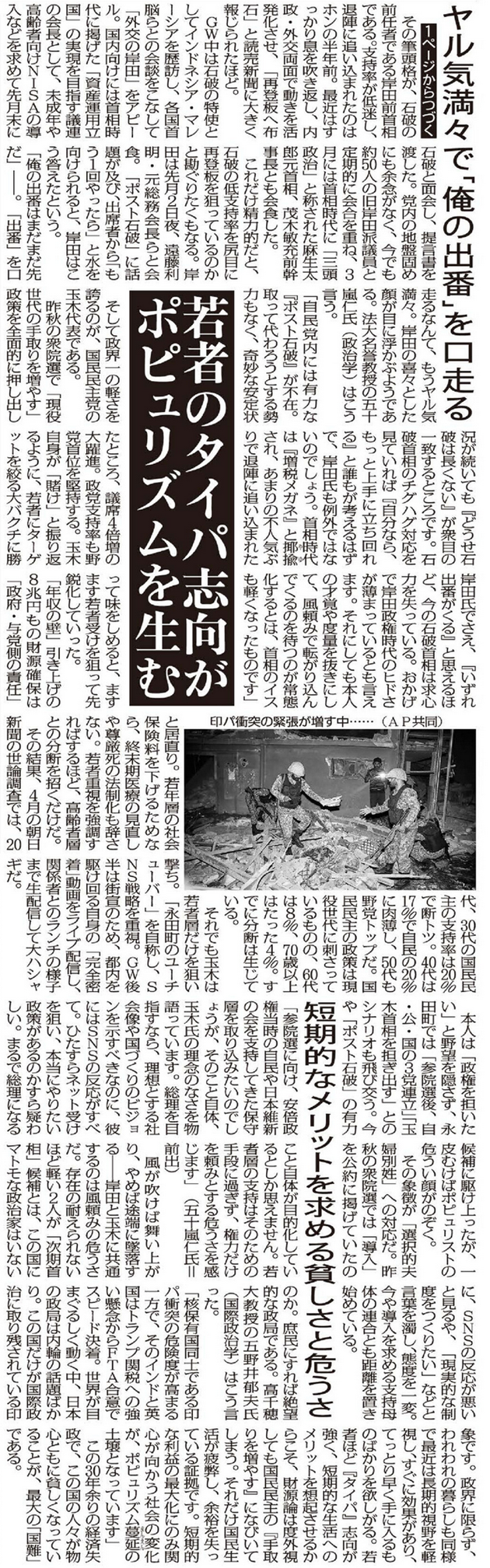
��2025�N5��8���@�����Q���_�C2��
�Δj���������A�ނ�����������c�ݓc�O����X�Ƃ������ʖ��n�V������]����
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/371510
2025/05/08�@�����Q���_�C�@����i�������z��

���ʓ_�́u�y���v�Ɓu�����v�^�i�b�j�����Q���_�C
�@�Δj���ŁA�R���������}�Ɏw�����Ă������A����������Ƌ�������B�o�ϑ���I���~�G�~�G�����A����Ȏ̎��ӂ�������悻�ɐg����Ŕڂ����A�����肾�B���̍��ɂ̓}�g���Ȑ����Ƃ͂��Ȃ��̂��A�Ə����̐�]�B
�@�@���@�@���@�@��
�@���_���~�G�~�G�ǂ��납�A���L�o�����B�����}�̐X�R�T�A�����}�̐��c���m����������7���A�s���ʼn�k���A�g�����v�Đ����Ƃ̊Ō������ɂ߂���ŐV���Ȍo�ϑ������������j�ň�v�����B���ł⋋�t������ɓ���A�Ă̎Q�@�I�O�̍����ڎw���B
�@7���͐Δj�������̏��쎛�ܓT������Ɗ��@�Ŗʉ�A�g�����v�����̎����ԕ��i�ւ̒lj��Ŕ����́u���{�ɂƂ��Ĕ��ɑ傫�Ȗ�肾�v�ƌ��A���S�̑�����悤�w���B����ɁA�R�����i�����̑��}�Ƃ��Ď��܂Ƃ߂�悤�n�b�p���������B
�@�Δj��������p�����Ɍo�ϑ��ł��o���̂́A�����炳�܂ȑI���B����1�J���]��œs�c�I�̍����i6��13���j���}���A�Q�@�I�ւƑ����A���̉Ă͑I���̋G�߁BGW���������r�[�A�������I�����[�h�ɓ˓����A�L���҂̊��S�����Ɩ�N�����A����������Ƌ�������B���傹��g����Ă��銴�h�ɉ߂��Ȃ��B
�@�Ƃ�킯�A������R��������Ƃ͎���x����͂Ȃ͂������B�ߘa�̃R�������̖u���͍�N�Ă���B���{�́u�H�ɐV�Ă��o��Η��������v�ƌ������������̂́A���i�̓O���O���㏸�B���~�ĕ��o�ɒǂ����܂��ƁA���x�́u3�����ɂ͓X���ɕ��сA���i�����������v�Ƃ������Ă����̂ɁA�t�Ɏ��Ԃ͈������Ă���B
�@�R��5�L��������̕��ω��i�͎���17�T�A���Œl�オ�肵�A�ߋ��ō��l���X�V�B�O�N��2�{���̍����������B
�@���~�Ă����Ғʂ�ɂ͓X���ɍs���n�炸�A�Ă�Œl������Ɍ��т��Ă��Ȃ��̂��B
�@�ꓖ�����̎��������ɂ͖j���ނ�B�R���������I���Ƀ}�C�i�X�ɍ�p����^�}�����Ƃ����{���������E���A�����܂ŏ����̖����d���B�R����������}���Ɠ}�ɐӔC����������Δj���q�h�C���̂����A����Ȏ̎��ӂ��g����Ŕڂ����A�����肾�B
�����C���X�Łu���̏o�ԁv��������
�@���̕M���i���A�Δj�̑O�C�҂ł���ݓc�O�ł���B�x������������A�ސw�ɒǂ����܂ꂽ�̂̓z���̔��N�O�B�ŋ߂͂������葧�𐁂��Ԃ��A�����E�O�𗼖ʂœ����������������A�u�ēo�֕z�v�Ɠǔ��V���ɑ傫����ꂽ�قǁB
�@GW���͐Δj�̓��g�Ƃ��ăC���h�l�V�A�E�}���[�V�A���K���A�e����]��Ƃ̉�k�����Ȃ��āu�O���̊ݓc�v���A�s�[���B���������ɂ͎���Ɍf�����u���Y�^�p�����v�̎�����ڎw���c�A�̉�Ƃ��āA�����N�⍂��Ҍ���NISA�̓����Ȃǂ����߂Đ挎���ɐΔj�Ɩʉ�A����n�����B�}���̒n�Ռł߂ɂ��]�O���Ȃ��A���ł���50�l�̋��ݓc�h�c���ƒ���I�ɉ���d�ˁA3���ɂ͎���Ɂu�O�������v�Ə̂��ꂽ�������Y���A�Ζؕq�[�O�������Ƃ���H�����B
�@���ꂾ�����͓I���ƁA�Δj�̒�x������K�ڂɍēo��_���Ă���̂��Ɗ����肽�����Ȃ�B�ݓc�͐挎2����A���������E���������Ɖ�H�B�u�|�X�g�Δj�v�ɘb�肪�y�сA�o�Ȏ҂���u����1��������v�Ɛ�����������ƁA�ݓc�͂����������Ƃ����B
�u���̏o�Ԃ͂܂��܂��悾�v�����B�u�o�ԁv��������Ȃ�āA���������C���X�B�ݓc�̊�X�Ƃ����炪�ڂɕ����Ԃ悤�ł���B�@�喼�_�����̌\���m���i�����w�j�͂��������B
�u�����}���ɂ͗L�͂ȁw�|�X�g�Δj�x���s�݁B����đ��낤�Ƃ��鐨�͂��Ȃ��A��Ȉ���������Ă��w�ǂ����Δj�͒����Ȃ��x���O�ڂ̈�v����Ƃ���ł��B�Δj�̃`�O�n�O�Ή������Ă���w�����Ȃ�A�����Ə��ɗ�������x�ƒN�����l����͂��ŁA�ݓc������O�ł͂Ȃ��̂ł��傤�B����́w���Ń��K�l�x�Ɲ�������A���܂�̕s�l�C�Ԃ�őސw�ɒǂ����܂ꂽ�ݓc���ł����A�w������o�Ԃ�����x�Ǝv����قǁA���̐Δj�͋��S�͂������Ă���B�������Ŋݓc��������̃q�h�������܂��Ă���Ƃ������܂��B����ɂ��Ă��{�l�̍ˊo��x�ʂ��ɂ��āA�����݂œ]���荞��ł���̂�҂̂���ԉ�����Ƃ́A�̃C�X���y���Ȃ������̂ł��v
��҂̃^�C�p�u�����|�s�����Y����

��p�Փ˂ْ̋����������c�i�b�jA�o ������
�@�����Đ��E��̌y�����ւ�̂��A��������}�̋ʖؑ�\�ł���B
�@���H�̏O�@�I�Łu���𐢑�̎���𑝂₷�v�����S�ʓI�ɉ����o�����Ƃ���A�c��4�{���̑���i�B���}�x��������}��ʂ���������B�ʖ؎��g���u�q���v�ƐU��Ԃ�悤�ɁA��҂Ƀ^�[�Q�b�g���i���o�N�`�ɏ����Ė������߂�ƁA�܂��܂���Ҏ�_���Đ�s�����Ă������B
�u�N���̕ǁv�����グ��8���~���̍����m�ۂ́u���{�E�^�}���̐ӔC�v�Ƌ�����B��N�w�̎Љ�ی����������邽�߂Ȃ�A�I������Â̌������⑸�����̖@�����������Ȃ��B��ҏd���������������قǁA����ґw�Ƃ̕��f�������������B
�@���̌��ʁA4���̒����V���̐��_�����ł́A20��A30��̍�������̎x������20���Œf�g�c�B40���17���Ŏ�����20���ɓ������A50�����}�g�b�v���B��������̐���͌��𐢑�Ɏh�����Ă�����̂́A60���8���A70�Έȏ�͂�����4���B���łɕ��f�͐����Ă���B
�@����ł��ʖ͎�ґw������_�������B�u�i�c���̃��[�`���[�o�[�v�����̂��ASNS�헪���d���BGW�㔼�͊X��̂��߁A�s�����삯��鎩�g�́u���S�����v��������C�u�z�M���A�W�҂Ƃ̃����`�̗l�q�܂Ő��z�M���đ�n�V���M���B
�@�{�l�́u������S�������v�Ɩ�]���B�����A�i�c���ł́u�Q�@�I��A���E���E����3�}�A���v�u�ʖ؎�S���o���v�Ƃ̃V�i���I����ь����B����u�|�X�g�Δj�v�̗L�͌��ɋ삯��������A���ނ��|�s�����X�g�̊낤���炪�̂����B
�@���̏ے����u�I��I�v�w�ʐ��v�ւ̑Ή����B���H�̏O�@�I�ł́u�����v������Ɍf���Ă����̂ɁASNS�̔����������ƌ����A�u�����I�Ȑ��x�����肽���v�Ȃǂƌ��t������A�ԓx����ρB���⓱�������߂�x����̘̂A���Ƃ�������u���n�߂Ă���B
�Z���I�ȃ����b�g�����߂�n�����Ɗ낤��
�u�Q�@�I�Ɍ����A���{���������̎�������{�ېV�̉���x�����Ă����ێ�w����荞�݂����̂ł��傤���A���̂��Ǝ��́A�ʖ؎��̗��O�̂Ȃ�����Ă��܂��B������ڎw���Ȃ�A���z�Ƃ���Љ�⍑�Â���̃r�W�����������ׂ��Ȃ̂ɁA�ނɂ�SNS�̔��������ׂāB�Ђ�����l�b�g��_���A�{���ɂ�肽��������̂�����^�킵���B�܂�ő����ɂȂ邱�Ǝ��̂��ړI�����Ă���Ƃ����v���܂���B��ґw�̎x���͂��̂��߂̎�i�ɉ߂����A���͂����𗊂݂Ƃ���낤���������܂��v�i�\���m��=�O�o�j
�@���������Ε����オ��A��߂Γr�[�ɒė����鄟���ݓc�Ƌʖɋ��ʂ���͕̂����݂̊낤�����B���݂̑ς����Ȃ��قnjy��2�l���u�����v���Ƃ́A���̍��Ƀ}�g���Ȑ����Ƃ͂��Ȃ��̂��B�����ɂ���ΐ�]�I�Ȑ��ǂł���B�����勳���̌ܖ���v���i���ې����w�j�͂����������B
�u�j�ۗL�����m�ł����p�Փ˂̊댯�x�����܂����ŁA���̃C���h�Ɖp���̓g�����v�łւ̋������O����FTA���ӂŃX�s�[�h�����B���E���ڂ܂��邵���������A���{�̐��ǂ͓��ւ̘b�����B���̍����������ې����Ɏ��c����Ă����ۂł��B���E�Ɍ��炸�A�����̕�炵�����l�ōŋ߂͒����I������y�����A�����Ɍ��ʂ�����A�Ă��Ƃ葁����ɓ�����̂����~������B��҂قǁw�^�C�p�x�u���������A�Z���I�Ȑ����ւ̃����b�g��z�N�����邩�炱���A�����_�͓x�O�����Ă���������́w����𑝂₷�x�ɂȂт��Ă��܂��B���ꂾ�������������敾���A�]�T�������Ă���؋��ł��B�Z���I�ȗ��v�̍ő剻�ɂ̂݊S���������Љ�̕ω����A�|�s�����Y�������̓y��ƂȂ��Ă��܂��v
�@����30�N�]��̌o�ώ����ŁA���̍��̐l�X�����S�Ƃ��ɕn�����Ȃ��Ă��邱�Ƃ��A�ő�́u����v�ł���B
�@
|
|
������@�@�@�@�@ �����C���� > �����E�I���E�m�g�j297�f�����@���� �@�O��
|
|
�ŐV���e�E�R�����g�S�����X�g �@�R�����g���e�̓����}�K�ő����z�M �@�X�����Ĉ˗��X��
������@�@�@�@�@ �����C���� > �����E�I���E�m�g�j297�f�����@���� �@�O��
|
|
 �X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B���ׂẴy�[�W�����p�A�]�ځA�����N���������܂��B�m�F���[���͕s�v�ł��B���p�������N��\�����Ă��������B