http://www.asyura2.com/09/hihyo10/msg/814.html
| Tweet |
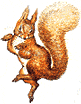
http://www.47news.jp/CN/201008/CN2010082801000428.html
--
共同通信社が27、28両日実施した9月1日告示の民主党代表選に関する全国緊急電話世論調査で、代表になってほしい候補者に菅直人首相(党代表)を挙げたのは69・9%で、15・6%の小沢一郎前幹事長を大きく上回った。民主支持層では菅氏支持は82・0%に上った。首相続投支持が世論、支持層の大勢であることが鮮明になり、党所属の国会議員や地方議員、党員・サポーター票の動向に影響を与えそうだ。
菅内閣の支持率は48・1%で、7、8両日調査の前回から9・4ポイント増。不支持率は8・6ポイント減の36・2%で、7月の参院選後、初めて支持が上回った。代表選の結果、首相が交代した場合、「衆院解散・総選挙を行うべきだ」とする回答は56・1%。「行わなくてもよい」は39・1%だった。「小沢首相」は世論の解散圧力にさらされることになりそうだ。
--
共同通信は調査人数を公開しろ。せいぜいどんなに多くても1000人程度だろう。
ニッポン放送でもこの調査結果を報道していて、菅直人が圧倒的支持で支持が不支持を上回ったと非常に強調して言っていた。
明らかなマスコミの願望報道だ。
以下のniftyの結果と真逆なのが、どれだけマスコミが偏向しているかよくわかる。
こちらは少なくとも5000人以上投票している
|
|
|
|
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
- Re: @nifty投票では圧倒的な小沢一郎支持 阿保の洞窟 2010/8/28 20:28:33
(0)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > マスコミ・電通批評10掲示板
|
|
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/
since 1995
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
▲このページのTOPへ
★阿修羅♪ > マスコミ・電通批評10掲示板
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。