|
<■68行くらい→右の▽クリックで次のコメントにジャンプ可> 鵜飼秀徳「仏教の戦争責任」より一部転載。(以下引用)
日本仏教界が一体となって戦争に協力したのだ。いや、「協力」などという間接的なものではない。各宗門の宗教的トップ(法主)自らが、天皇制の下での仏教ファシズム(皇道仏教)を先導する役割を担っていたのだ。
例えば、昭和天皇の従兄弟でもあった浄土真宗本願寺派二十三世門主大谷光照(勝如)は、歴代門主文書(1938年8月5日)の中で、こう語っている。 「国家の事変に際し進んで身命を鋒鏑(ほうてき)におとし一死(いつし)君国に殉ぜんは誠に義勇の極みと謂(いひ)つべし。一家同族の人々にはさこそ哀悼の悲しみ深かるべしと覚ゆれども畏くも上聞(じょうぶん)に達し代々に伝はる忠節の誉を喜びいやましに報国の務にいそしみ其の遺志を全うせらるべく候」 (国家の一大事に際して、すすんで命を戦地に投げ打ち、天皇のために死ねることができれば、義勇の極みといってもよいだろう。家族や親戚にとって悲しみは深いだろうが、それは畏れ多くも天皇に届き、末代まで伝わる忠節の誉として喜び、さらにお国の為に戦って、その遺志をまっとうしてほしい) 戦後は大谷光照らの戦争責任を追及する動きも起きた。法主による訓示は、末寺を通じてムラ社会のなかに浸透し、檀信徒の戦意を大いに発揚した。 日米開戦直後には、真宗大谷派では東本願寺大門楼上に3メートル四方に書かれた「皇威宣揚」の看板を、門の左右には「生死超脱」「挺身殉国」の立看板を設置するなどしている。 戦時下における戦争賛美の同調圧力と、熱狂の渦を作り上げた側面は否めない。 こうした大量殺人を伴う戦争に、仏教教団は直接的・間接的に関わった。そこで、殺生を戒める仏教がなぜ? という疑問が湧き上がる。この矛盾を正当化したのが、日清戦争以降に構築された「戦時教学」と呼ばれる論理だった。それは国家神道体制のなかで生き残りをかけた、仏教側の方便といえるものだった。 戦時教学に、僧侶は無批判に従った。なかには浄土教の「極楽往生」の考えをタテにして、戦地で死ぬことはむしろ歓喜すべきことと流布し、さらには「一殺多生(一人の敵を殺して、多くの日本人が生き残る)」を平然と唱える仏教者まで現れた。 日蓮宗僧侶で活動家の井上日召はその思想に染まり、テロ集団を率いて政財界の要人を暗殺した「血盟団事件」を引き起こしたことが知られている。 宗門の戦時協力の最たるものとして、軍用機の献納がある。日中戦争勃発以降、仏教団体は判明しているだけで零戦など50機以上の軍用機を軍部に献納している。 浄土宗は「明照(天皇から下賜された法然上人の大師号)号」、臨済宗は「花園妙心寺号」などと機体に銘打って献納した。真宗大谷派では、軍艦建造のための多額の資金を海軍に差し出している。 植民地支配に乗じてつくられた寺院
さらに、国の植民地政策に乗じて、各宗派は海外開教を推し進めた。わが国は日清戦争以降、中国、朝鮮、台湾といったアジア諸国へ侵出していく。そこに僧侶が従軍した。そして、最前線に多くの寺院を建立したのだ。 例えば、もっとも熱心に植民地布教をした教団のひとつ、浄土真宗本願寺派(西本願寺)では極東全体で400か寺近い寺院や布教所を開いている。 満州に開かれた曹洞宗寺院
戦線と教線(布教の前線)はぴたりと重なる。それは、国家と仏教とが共同で植民地化政策を推し進めた証といえる。 私は調べるほどに、目を背けたくなるような事実の数々を目の当たりにした。 宗教が国家権力と結びつき、暴走を始めるのは常。だが、そのメカニズムはどこにあるのか? 人民救済の目的を忘れた宗教はどうなっていくのか。いまこそ、私たちはそれを学ばなければならない。 実は近代における仏教と戦争の歴史の源流は、明治維新時の神仏分離令と、それに伴う廃仏毀釈で仏教教団が解体的出直しを迫られた時点にある。それまで混淆していた神と仏が切り離され、ドラスティックな「宗教改革」が実行された。そこで新たに「仏教と国家の関係」が構築された。 仏教界が生存をかけて、いかに国家に擦り寄り、植民地政策や戦争に加担し、自らを正当化していったのか。 私は金属供出や顕彰碑など戦争の痕跡が残る多くの寺院に足を運んで取材した。また、かつて軍隊に入隊した老僧へのインタビューも実施した。 こうした取材・調査の内容は拙著「仏教の大東亜戦争」(文春新書)に余すところなく記載した。その一部を本コラムで紹介してみたいと思う。 「仏教界と戦争との関わり」は紛れもなく、仏教界最大のタブーといえる。だが、宗教の本分から逸脱した残虐な過去を暴き、それを断罪するのが本書の目的ではない。国家神道体制によって変質せざるを得なかった日本仏教の運命を俯瞰し、国家と宗教の関係性を学び、真の宗教のあり方について、本書を通じて深めてもらえれば幸いだ。
|
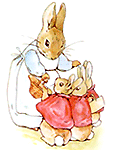
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。