|
����199�s���炢���E�́��N���b�N�Ŏ��̃R�����g�ɃW�����v�� ���C�E�_���I���A�������オ�����r�[�ɐ��{�����Ŕj�]���n�߂闝�R���������
2025�N6��22�� globalmacroresearch
https://www.globalmacroresearch.org/jp/archives/66836���E�ő�̃w�b�W�t�@���hBridgewater�n�Ǝ҂̃��C�E�_���I�����AMSNBC�̃C���^�r���[�ŐV�����o�ł��������wHow Countries Go Broke�x�i����F�Ȃ����Ƃ͔j�]����̂��j�̓��e���Љ�Ă���B �A�����J�̍�����@ �_���I���́A�O���w���E�����̕ω��ɑΏ����邽�߂̌����x�ł̓A�����J�̑O�ɔe�����Ƃ�������p�鍑��I�����_�C��鍑�Ȃǂɏœ_�āA�卑���ɉh���Ă��琊�ނ���܂ł̃v���Z�X�ƁA���̊Ԃɂ��̍��̍��̏��ǂ��Ȃ邩��������Ă����B ��������̐V���ł̓s���|�C���g�ō��Ƃ̔j�]���e�[�}�Ƃ��Ă���B�_���I���́A�A�����J�����̏ɋ߂Â��Ă���Ɨ\�z���Ă��邩��ł���B �d�v�Ȃ̂͐��{���ł���B���Ƃ́A�ŏ��͎����̌o�ϗ͂Ōo�ϐ��������Ă��邪�A�卑�ɂȂ�Ə��X�Ɍo�ϐ������؋��ɗ���悤�ɂȂ�B �_���I���͍���ʂɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ���B �M�p�����o�����Ƃōw���͂����܂��B����ɂ�蕉���ł���B �����A�����V���Ȏ����ݏo���Ȃ�A����͌��S���B �Ⴆ�ΐV���Ȏ��Ƃ̂��߂Ɏ؋������A���ꂪ�V���Ȏ����������炵�Ď؋���Ԃ���Ȃ�A�؋��͐��Y�I�ł���B �����A���قƂ�ǂ̐�i��������Ă���悤�ɁA�P�Ɏg�����߂����Ɏ؋��𑝂₹�A���{���͂ǂ�ǂ��Ă䂭�B ���{�������ɂȂ�Ƃ� �����O�܂ŁA��i���̐��{�͍����j�]���Ȃ��̂ŁA���{���͂����瑝�₵�Ă��ǂ��Ƃ������Ƃ��قƂ�Ǐ펯�ł��邩�̂悤�Ɍ����Ă����B �����A�������[���ł���Ԃ́A���{���͖��������N�����Ȃ������B�����A���ꂪ���̂��Ƃ������Ƃ�������ƍl���Ă݂����B �܂��A�������[���ł���ΐ��{�͍��̗�������Ȃ��ėǂ��B�P�ɍ��̎c�����ςݏオ���Ă��邾�����B ���������ɂȂ�Ύ؋���Ԃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���̂��ꂪ���ɂȂ�Ȃ��������H�@�V���ȍ��s���Ď芷����ꂽ����ł���B �����Œ��ӂ��Ă��炢�����̂́A���������ɂȂ�������V�K���s���Ă��A���̑��ʂ͕ς��Ȃ����Ƃł���B�����ɂȂ������͏��ł��A�������z�̐V���ȍ������s�����B �����疞���ɂȂ邱�Ǝ��̂����̑��ʂ�ω������邱�Ƃ͂Ȃ��A���̒��ɍ��������Ƃ������v���ς�炸���݂���̂ł���A�����̕����ς��Ȃ��̂ŁA���̏�Ԃ��������荑�̎��v�Ƌ����͕ς�炸�A���{���̋��z�����̎W��j�]�����邱�Ƃ͂Ȃ��B �������V���Ȏ؋���������̋����ʂ������邪�A�V���Ȏ؋������邩�ǂ����͐��{�������̈ӎv�Ō��߂邱�Ƃł���B�������v�����肸�A���̉��i�������������ɔ��s���o���Ȃ��̂ł���A�V���Ȏ؋������Ȃ���Ηǂ��B����Ōi�C��ނɂȂ邱�Ƃ����邾�낤���A�Ƃ������[�������̊Ԃ͍��̎W�͔j�]�����ɂ����܂ŗ����킯�ł���B ���̗������}�� �����R���i��̌������t�������������������悤�ɁA�C���t�����{���ɃC���t���������炵�Ă��܂��Θb�͈���Ă���B �_���I���͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B ���������ݏo���Ȃ����́A���̗������ƍ��̕ԍς�ςݏグ�A���ꂪ���̎x�o�������o���B �č����{�ɂ��ꂪ���N�����Ă���B �C���t���ɂȂ��ċ������オ��A���ɗ���������������B�������́A�؋��̌��{��Ԃ����ƂƂ͈Ⴄ�B���̗������͐��{�Ɏ؋��̑��z�𑝂₷���Ƃ����v����B���ꂪ�[�������̎���Ƃ͂܂������Ⴄ�_�ł���B �_���I���͎��̂悤�Ɏw�E���Ă���B ���N�A�č����{��7���h���x�o����B������5���h���Ȃ̂ŁA�Ԏ���2���h�����B �č��̗������͌���1���h�����B ����A�����J�̍����Ԏ��̔����͕č��̗������ƂȂ��Ă���B �����������������炷������ ���{�����������V���ȍ����s�Řd����_�ł͓��������A�������͍��̎c���𑝂₵�A���{�͎����̈ӎv�ł�����R���g���[�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B �V���ȍ����s�����s��Ɏ����ꂸ�A�\���Ȕ����肪�s�����Ă���ꍇ���A�Ƃ��������{�͗������̂��߂ɐV���ȍ��s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B �_���I���͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B ����A�����J�͎؋���Ԃ����߂Ɏ؋��𑝂₳�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B ������V���ȍ����s�����̎��v�Ƌ����̊W���A�����i������������Ƃ��Ă��A�Ƃ��������{�͍��s������Ȃ��B �ł͂ǂ����邩�B�[�������̊Ԃ͒�����s����������ō�������邱�Ƃ��ł������A�C���t���ɂȂ�����ł͎������������ƃC���t���ɂȂ�B �����炱���Ȃ������_�Ő��{�ɂ�3�����I�������Ȃ��Ȃ�B���̗������ȊO�̎x�o�����炵�č����Ԏ������炷���A���邢�͎x�o�����炳���ɍ��𑝂₵�����A�����i�����������邩�A������s�Ɏ�������ō��킹�ăC���t���ƒʉ݈��������N�������ł���B �_���I���͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B ������̎x�����͉u�a�̂悤�ɂ͂т���A���̎x�o�������o���Ă���B ���{��������������@ �x�o�����点�Όi�C��ނɁA�����s�𑱂�����������������㏸�ɁA�����������C���t���ɂȂ�B ���ꂪ�{���ɃC���t���ɂȂ��Ă��܂�����̃C���t������̖��H�ł���B ���̖������{�I�ɉ�������ɂ́A�[������������Ɩ����ɐςݏグ�Ă��܂������{�������Ƃ����邵���Ȃ��B�����_���I���͎��̂悤�Ɏw�E���Ă���B �A�����J�̍��̗ʂ́A1�l������Ō������悻23���h���i�F���悻3,000���~�j���B �������������Ȃ��ʼn�������Ƃ����̂́A�A�����J�l�͊F���̎؋���w�����Ƃ������Ƃł���B ���_ �Ƃ������ƂŁA�A�����J�o�ς͒����I�ɂ͖��炩�ɋl��ł���B���{�x�o�����炳�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�č����Ƀ}�C�i�X���Ƃ������Ƃł�����B ��������ɕč����̃p�t�H�[�}���X�����̍���舫���Ȃ��Ă���̂ł���B �K���h���b�N��: �č����̃o�u���͂����I����Ă���A�����ƃh���̒���œ�d�̔s�k��
�����Ė��炩�ɖ�������Ă���h���ƕč�����͎��������o���Ă���B�_���I���͎��̂悤�ɑ����Ă���B
�e���̒�����s��O���̓����Ƃ����͕č��ۗ̕L�����炵�ăS�[���h�Ɉڍs���Ă���B �A�����J�o�ςƃh���͂ǂ��Ȃ�̂��H�@�_���I���̐V���wHow Countries Go Broke�x�i����F�Ȃ����Ƃ͔j�]����̂��j�ɂ́A�C���t������̋A���Ƃ���1�͂��ׂĂ���{�o�ς̉���ɔ�₳�ꂽ����������B ���C�E�_���I���̐V���A���{�o�ς𐭕{���̑Ώ��Ɏ��s�����ꍇ�̎���Ƃ��Čf��
https://www.globalmacroresearch.org/jp/archives/66448 ���{�́A�A�x�m�~�N�X�Ȍ�̎�������ɂ��~���ɂ���āA�~���ĂŌ���������GDP���ꌩ�������������ɁA���{�o�ς̉��l�������I�ɂ́i�Ⴆ�h�����ĂŌ��āj�傫���ቺ�����A�h�C�c��C���h�ɔ�������������B �������Ƃ��A�����J�ɋN����Ƃ���A�h����č����͂ǂ��Ȃ邾�낤���H�@�_���I���̐V���͉p��ł����o�Ă��Ȃ����A�p���ǂ߂�l�͓ǂ�ł����ׂ��ł���B
https://www.globalmacroresearch.org/jp/archives/66836
��������
���C�E�_���I���̐V���A���{�o�ς𐭕{���̑Ώ��Ɏ��s�����ꍇ�̎���Ƃ��Čf��
2025�N6��10�� globalmacroresearch
https://www.globalmacroresearch.org/jp/archives/66448
���E�ő�̃w�b�W�t�@���hBridgewater�n�Ǝ҂̃��C�E�_���I�����A�A�����J�̍����j�]��\�z����V���wHow Countries Go Broke�x�i����F�Ȃ����Ƃ͔j�]����̂��j�̉p��ł����ɏo�ł����B �A�����J�Ɠ��{�̍����j�] 2018�N�ɏo�ł��������w�������@�𗝉�����x�ɂ����Č������t��\�z���A2020�N�ɏ����n�߂��w���E�����̕ω��ɑΏ����邽�߂̌����x�ɂ����Đ��E�I�ȕ���������\�z�����_���I�����A���ɐV���������B �ȉ��̋L���ŏЉ���ʂ�A�����ŗ\�z����Ă���͔̂e�����ƃA�����J�̍����j�]�ł���B ���C�E�_���I���̐V���������A�A�����J�͍����j�]����
���C�E�_���I���̐V���A�A�����J�������j�]����v���Z�X�����ׂ��ɗ\�z
�A�����J�̍�����@���������Ȃ����Ƃ́A�����̋L���ŏ\��������Ă���̂ł�����ɏ��肽���B
��������ŁA�_���I���̓A�����J��������������Ă���Ƃ͎v���Ă��Ȃ��B�Ⴆ�A�_���I���͐V�����Љ��u���O�L���Ŏ��̂悤�ɏ����Ă���B ���{�o�ς̎���͂킽�����V���ň����Ă�����̗ǂ��Ⴞ���A���ꂩ����������葱���邾�낤�B ���{�̍����̋A�� �u�V���ň����Ă�����v�Ƃ͂����������j�]�̂��Ƃł���B �Ȃ��_���I���͓��{�͗ǂ��Ⴞ�ƌ����Ă���̂��B���{�̐��{����GDP��2�{��傫�������Ă��邪�A���ꂪ�ǂ��������������N�����Ă���̂��B �_���I���͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B �����Əڂ��������A���{���{�̍��̐��������ɍ������߂ɁA���{���͍���������ƂȂ��Ă���B ���{�l�̑����͂�����āu���{���������Ă���l�̘b���v�Ǝv����������Ȃ����A�����I�ɓ��{���������Ă���̂͂��Ȃ������ł���B���̂Ȃ�A���{���̎�Ȕ�����͋�s�ł���A��s�͐l�X�̗a���ō����Ă���̂ŁA�����I�ɂ͗a���҂������Ă��邩��ł���B �����ƌ����Ɍ����A���̋������痈�闘�v�͋�s�ɍs���A���X�N�����͗a���҂֍s���B������a���҂̗���͍��ۗL�҂����������̂ł���B ���{�~�Ɠ��{���ۗ̕L���X�N �����u���ۗL�̃��X�N�v�Ƃ͉����낤���H�@���͖����X�N���Y�ł͂Ȃ������̂��H�@����������̘_�_�ł���B�_���I���̗\�z�ʂ荑�Ƃ��j�]����Ȃ�A�u�����X�N���Y�v�̍��͂ǂ��Ȃ�̂��H 2�����������Ƃ�����B�܂����́A�l�X���v���Ă���悤�Ȕj�]�̎d���͂��Ȃ��B�����ē��{���͊��ɔj�]���Ă���B 2�ڂ��|�C���g�ł���B������_���I���͓��{���̂��Ƃ��u����������v�ƌ����Ă���̂ł���B����͂����j�]���Ă��邵�A���ꂩ����j�]���Ă䂭�B ���ꂪ�_���I���̌����Ă��邱�Ƃł���B�_���I����2013�N�ȍ~�̃A�x�m�~�N�X�œ��₪��ʂ̎���������s���悤�ɂȂ��Ă���̓��{���̃p�t�H�[�}���X�ɂ��Ď��̂悤�Ɍ����Ă���B ���{�o�ς��x���邽�߂̒�����̂����Ŕ����Ȃ��Ȃ������{���̎��v�s����₤���߂ɁA����͑�ʂɎ�����������{�������ꂽ�B ���̌��ʁA���{���������Ă���l��2013�N�ȗ��A�č��������Ă���l�ɔ�ׂ�45%�̑���������Ă���B�܂��A�S�[���h�Ɣ�ׂ��60%�̑��������ƌ�����B ���{�l�̐�����N�H����~�� �_���I���̌����u���{���̃��X�N�v�Ƃ́A�בփ��X�N���܂�ł���B������O�ł���B�ʓI�ɘa�i������s����������ō�������邱�Ɓj�͎����̉��l���]���ɂ��āA���l��͍��̉�����h�����Ƃł���B ������ʓI�ɘa�œ��{�~���Z�ł͍����i�͏オ�邪�A�����I�ɂ͓��{���̉��l�͂ނ��뒾��ł䂭�B ���E���w�̃w�b�W�t�@���h�}�l�[�W���[�ł���_���I���͏�X�A�����ʉ݂���ɕ����⎑�Y���i���l���邱�Ƃ͋��Z�̔���Ƃł���l�X�̑傫�ȊԈႢ���Ǝ咣���Ă���B �ꕔ�̐l�X�́A���{�~�ʼn��l��������Ȃ���Γ��{�l�ɂ͖��Ȃ��ƌ����B�������������咣�ɂ͍��⌻�����P���������Ă���B�R���̒l�i���オ���Ă���1�̗��R�̓g���N�^�[�ȂǂɎg����R���オ�オ���Ă��邱�Ƃł���B �A�x�m�~�N�X�ȗ��A�h���~80�~����150�~�Ɏ���~���ŁA������哤�Ȃǂ̗A���i�̉��i���قƂ�ǔ{�ɂȂ����̂͂����̎��������A����G�l���M�[���i�̍����Ȃǂ�ʂ��č��Y�i�̉��i�܂ŏオ���Ă���B���ꂪ�����̉��l�������������Ƃ̌����ł���B�l�X�͂���ł��A�בւȂǓ��{�����Ƃ͊W�Ȃ��ƌ������낤���B ���_ ��������{�̖L������}��ꍇ�ɂ́A�Ӑ}�I�ɉ��l��������ꂽ���{�~�Ŏ��Y���i�⋋���Ȃǂ��l���Ă͂Ȃ�Ȃ��B�~���Ăʼn��i���オ���Ă��A����͉��i���オ�����̂ł͂Ȃ��~�̉��l���������������ł���B �_���I���͎��̂悤�Ɍ����Ă���B ���{�̘J���҂̕��ϓI�Ȓ�����2013�N�ȗ��A�A�����J�̘J���҂̒����ɔ�ׂ�58%���������B �����Ă��ꂪ�����ł���B���{�~�̉��l�������邱�ƂƂ́A�v����ɂ��Ȃ��̗a���⋋���̉��l�������邱�Ƃł���B �����瓯�������ł����̂������Ȃ��Ȃ�B���ꂪ�C���t���ł���B ������������̂ł͂Ȃ������̉��l��������ΐl�X�͋C�Â��Ȃ��Ƃ����̂��A�_���I���̐V���wHow Countries Go Broke�x�i����F�Ȃ����Ƃ͔j�]����̂��j�̘_�_�ł���B ����ǂ��납�A�A�_���E�X�~�X���ł����������Ƃ��w�E���Ă���g���Â��ꂽ���Ȃ̂ł���B �A�_���E�X�~�X���A�ʉ݂̉��l���������Ă���ʂ̐l�X���C�Â��Ȃ����R���������
�����č��Ƃ̍����j�]�͂���𗘗p���ċN����B�����獑�̔j�]�Ƃ͂܂��f�t�H���g���邱�Ƃł͂Ȃ��B�����̉��l�������邱�Ƃł���B
�_���I���͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B �V���ł͓��{�o�ς̎���ɂ��Ă܂�܂�1�͎g���ďڂ����������Ă���B �u���Ƃ̔j�]�̓f�t�H���g������Ɏ����̉��l�����ɂ���ċN����v�Ƃ����_���I���̗\�z�̐�D�̗Ⴞ���炾�낤�B �����č��Ƃ̔j�]�͎����̉��l���������ł͏I���Ȃ��B����͎n�܂�ɉ߂��Ȃ��B�ŋ߁A���Z�s��ł͓��{�̒��������̋����㏸���~�܂�Ȃ����Ƃ��b��ɂȂ��Ă���B �������l�����̎��̖�肪���{�o�ςɋ߂Â��Ă���B�M�҂̎茳�ɂ���p��łł́A�_���I���͓���̔j�]�\���ɂ܂Ō��y���Ă���B ���C�E�_���I�� : �ʉݖ\�����~�߂悤�Ƃ��钆����s�͂₪�Ē��߂�
�_���I���̑O���̏ꍇ�A���{��ł̏o�ł͉p��ł�2�N�ゾ�����B�����œǂ߂�l�͌����œǂ�ł����ׂ��ł���B
https://www.globalmacroresearch.org/jp/archives/66448
|
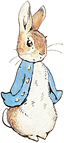
 �X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B �X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B