http://www.asyura2.com/18/social10/msg/473.html
| Tweet |
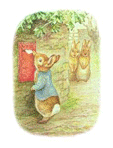
日本の少子化進行が止まらない「本当の原因」/東洋経済オンライン
荒川 和久 の意見
https://www.msn.com/ja-jp/news/opinion/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%B0%91%E5%AD%90%E5%8C%96%E9%80%B2%E8%A1%8C%E3%81%8C%E6%AD%A2%E3%81%BE%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84-%E6%9C%AC%E5%BD%93%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%9B%A0/ar-AA1M222I?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=68bdec3bafe6479c92dd2eed791c217c&ei=21
自由な恋愛――かつてそれが許されなかった時代を思えば、誰もが自由に恋愛ができる環境というのは素晴らしい世界のように見えますが、自由な恋愛はしばしばとても不平等な結果を生みます。
なぜなら、全員が恋愛力を持っているとは限らないからです。私は「恋愛強者3割の法則」と名付けていますが、恋愛力のある割合は今も昔もずっと3割程度しかいません。無論、3割しか恋愛できないとまでは言いませんが、「自由に恋愛していいよ」と言われても、必ずしも全員それが可能になるわけではありません。
さらに、恋愛が自由市場になったことで、恋愛力だけではなく、前提としての経済力が必要となってしまいました。いわば、自由な恋愛の世界の扉をあけるためには、まず「お金が必要」になっているのです。
結婚とお金の深い関係
当連載でもしばしば「結婚とはお金の問題である」と書いてきましたが、そのたびに「結婚できないのは金の問題ではない」と反論してくる人がいます。何も「結婚できるかどうかはすべてお金で決まる」とまでは申しませんが、結果として「その可否をお金が大きく左右している」こともまた事実です。しかも、それは直近10年で急激に顕在化しました。
国民生活基礎調査から、40代までの世帯主で児童のいる世帯(18歳未満の子のいる世帯)の世帯数を世帯年収別に2003年〜2013年〜2023年と10年おきに比較したものが以下のグラフです。
【画像】
https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1M1V2H.img?w=768&h=956&m=6
一目瞭然ですが、2003年から2013年にかけては、世帯年収別の分布はほぼ一緒で変化はありません。が、それが2023年になると、世帯年収300万円台から500万円台の中間層においてのみ世帯数が激減していることがわかります。
逆に、世帯年収700万円以上の経済的上位層では、これだけ婚姻減、出生減という中においてもその世帯数は全く減っていません。つまり、日本の婚姻減と出生減は中間層が結婚して子どもを持てなくなったということに尽きるわけです。
日本の場合は、出生数は完全に婚姻数と比例します。よって、これは年収中間層が結婚できなかったことが、今の少子化を作り出したと言っても過言ではありません。そして、ここで大事な点は、貧困層だけではなく、人口のもっとも多い中間層が結婚できなくなってしまったことこそが深刻な原因なのです。
男女の年齢別の初婚率(人口千対)もまったく同じ推移を辿っています。男女ともに25〜29歳の初婚率で比較すれば、2003年から2013年にかけての10年間では、男性▲2.6、女性▲1.4と減少幅は微々たるものだったのに対し、2013年から2023年にかけては、男性▲16.4、女性▲20.2と大幅な減少となっています。
中間層の婚姻が減っているとは、つまるところ、20〜30代の若い中間層が結婚できなくなっていることになるのです。
「お金がなければ恋愛さえもできない」
そうした現象の背景にはもっと深刻な事態が隠れています。もはや「お金がなければ結婚できない」だけではなく、「お金がなければ恋愛さえもできない」という事態に突入しているからです。
私のラボで調査した個人年収別の恋愛経験人数の推移(対象は20〜30代未既婚男女)を2016年と2024年とで比較したものが以下です。
まず、未婚男性を見ると、2016年時点ではまだ年収の多寡で恋愛人数の差はほとんどありませんでした。それが、2024年になると、きれいに年収が少なければ少ないほど恋愛人数も減ります。2016年比で恋愛人数が上回るのは年収600万円以上だけです。
これは、既婚男性でも同様の傾向で、2016年時点では年収300〜400万台の中間層がもっとも恋愛人数が多かったのに対し、2024年では600万円以上が最多となります。
結婚は経済生活ですから、特に男性の場合は結婚相手としての条件としてその年収が影響することはある意味当然ですが、結婚以前の恋愛の可否もまた年収次第となってしまっている現状があります。
一方、未婚女性も2016年はむしろ低年収の方が恋愛人数が多かったのに対し、2024年は男性と同じように高年収でないと恋愛ができなくなっている傾向が見てとれます。言い換えれば、男女とも高年収でなければ恋愛すらできなくなっているということです。
結婚と出産の意識のインフレ
ちなみに、結婚に至るまでの平均恋愛人数は約3.68人です。もちろん、それ以下では結婚に至らないということではありませんが、その平均値をひとつの基準としてとらえると、30代までに未婚男性は年収600万円以上、未婚女性も年収400万円以上でないとその恋愛人数に達しないということになります。それを満たす未婚男女は一体どれくらいいるでしょう。それぞれの年収中央値から考えれば、中央値年収ではとても恋愛をすることすらままならないということになります。
それを裏付けるように、現代では、結婚と出産の意識のインフレが起きています。
SMBCコンシューマーファイナンスによる「20代の金銭感覚についての意識調査」から、若者が考える「結婚が可能になる世帯年収」の中央値を独自に計算すると、2014年時点では379万円でした。その金額は、ちょうどその頃の、25〜29歳の男性の平均給料(個人年収)とほぼ一緒です。つまり、2014年までは20代後半の男性の一馬力の平均給料でも結婚できると若者自身が思っていたし、実際それで結婚できていたわけです。
ところが、2024年における「結婚可能年収」は544万円にまで高騰してしまいました。実に2014年対比で約1.4倍です。頑張れば手の届く範囲の稼ぎであればまだやりようもありますが、年収300万円台の中間層の若者にとって500万や600万円を稼げといわれても「とても無理なので諦めます」となってしまうでしょう。
このような結婚に対する意識のインフレが、実際の若者の年収とあまりに乖離しずぎていて、その基準を満たす大企業や公務員くらいしか結婚できない状態になっているのです。事実、大企業や公務員の未婚率は増えていません。
そうした現実を作りあげている背景には、中間層以下の若者が抱える経済的不安が大きいわけですが、よくよく考えれば当たり前で、恋愛という行動をするためにはお金も時間も必要です。日常生活で精一杯ならとてもそんな余裕はないでしょう。
親の経済状況が子の結婚にまでなぜ影響を及ぼすかというと、親が裕福であればあるほど子の環境が豊かなものになり、結果として子の学歴、就職先、年収が相対的に良いものになるからです。要するに、親が裕福なら子も裕福になり、結婚も子も持てますが(親にとっては孫)、親が貧乏なら子も貧乏になり、恋愛も結婚もできずに末代になるという経済的階級制が確立してしまったようなものです。
この状況は「失われた30年」という長期の経済停滞が中間層以下の親子にもっとも悪影響を及ぼした結果であるとも言えます。
政府はインフレ対策と言いますが、食品や電気代同様、近年謎に高騰してしまった「恋愛と結婚のインフレ」についても目を向けてほしいと思います。少子化対策において一番重要なのは、中間層の若者にとって、恋愛や結婚が手の届かない高級品と化してしまい、ままならない状態に陥っている現実を正しく認識することです。
少なくとも「自由な恋愛の扉を開けるためには、まず金を用意しろ」というゲームルールを見直さない限り、もう恋愛も結婚も子育ても経済上位3割層しか不可能になってしまうでしょう。
|
|
|
|
最新投稿・コメント全文リスト コメント投稿はメルマガで即時配信 スレ建て依頼スレ
|
|
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。