http://www.asyura2.com/23/jisin23/msg/145.html
| Tweet |
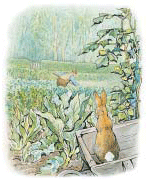
「南海トラフ巨大地震の確率見直し」 不確かさと誠実に向き合え 名古屋大教授 鷺谷威
2025年10月05日 07時00分 共同通信
https://www.47news.jp/13225604.html
政府の地震調査研究推進本部(地震本部)は「30年以内に80%程度」としてきた南海トラフ巨大地震の発生確率を改め、「60〜90%程度以上」「20〜50%」の2種類に変更した。妥当性に疑問が示されていた従来のモデル(計算手法)をやめ、別の二つのモデルで評価し直した結果だ。
同じデータを用いても、計算の仮定次第で確率は大きく変化する。これは科学の限界を端的に示しており、将来予測が大きな不確かさを持つことを意味する。災害に備える上では、確率の値に一喜一憂するのではなく、その値の不確かさと誠実に向き合う必要がある。
また、日本列島では、いつどこで大地震が起きても不思議ではない。南海トラフにだけ備えるのでは、地震防災としては著しく不十分であることも強調したい。
南海トラフ地震などの確率は定期的に見直されているが、今回の改定は戸惑う人も多いだろう。
背景には中日新聞記者が展開した調査報道がある。前回(2013年)の評価改定をきっかけに始まり、南海トラフ地震だけ他の地震とは異なるモデルが適用されて地震発生間隔が短く見積もられ、地震発生確率が高く評価されていることを指摘した。今回の改定は、これへの対応という意味合いが強い。
今回は、これまで南海トラフだけで用いてきたモデルによる評価の不確かさを考慮した新しいモデルと、南海トラフ以外の地震で通常使用されているモデルを用いた。30年以内の発生確率は、それぞれ大きく食い違う結果となった。
これについて、地震本部が公表した報告書は「疑わしいときは行動せよ」との行動原理に基づき、高い方の確率を使用するよう推奨している。科学的な評価と、それを政策において使用することを区別したと言える。本来は当然のこととはいえ、一歩前進だ。
従来の長期評価では、地震に関する純粋に科学的な評価と、防災に用いる際の政策的判断を含む内容をはっきりと区別せずに報告してきた。科学的評価の決定プロセスを後日、検証することが困難となり、将来に禍根を残す懸念があった。
1995年の兵庫県南部地震(阪神大震災)以降、地震に対する研究上の知見を社会に還元することを目的として、科学的、客観的な評価を行うことに専心してきた地震本部が、従来の枠を超えて情報発信を始めた点にも注目すべきだ。
最大90%程度以上という評価は、南海トラフ巨大地震が30年以内にほぼ確実に起きるというメッセージである。そうした心構えで地震や津波に備えることは無論重要だ。
一方、昨年の能登半島地震は、震源となった活断層についての最新の知見が反映されず、確率評価の対象にすらなっていなかった。
こうした大地震は恐らく、南海トラフ地震が起きる前に日本の各所で複数回起きて被害をもたらすことになるだろう。
われわれは大地震が繰り返す不安定な大地の上で暮らしている。このことを改めて肝に銘じて、将来の災害に備えてほしい。
―――――――――――
さぎや・たけし 1964年栃木県生まれ。東京大大学院中退。国土地理院を経て2008年から現職。日本測地学会会長。専門は固体地球物理学・地殻変動学。
―――――――――――
|
|
|
|
最新投稿・コメント全文リスト コメント投稿はメルマガで即時配信 スレ建て依頼スレ
|
|
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。