|
<■100行くらい→右の▽クリックで次のコメントにジャンプ可> 前に詳細に間違いを指摘しましたが、宇山卓栄さんのDNA解析の主張は完全なデマです。
アイヌ人の祖先が13世紀にカラフトから来たというのも間違いです。
北部東北・北海道の「ナイ」「ベツ」地名はすべてアイヌモシリ(アイヌ語地名)です。
それから、東北地方、北関東、甲信越地方のマタギの言葉もアイヌ語です。
マタギ(又鬼)は、日本の東北地方から北関東、甲信越地方にかけての山間部や山岳地帯で、伝統的な方法を用いて集団で狩猟を行う者を指します。
金田一京助 (アイヌ語研究の創始者)
「地名からみると北海道と東北は連続している。東北地方もかつてはアイヌ世界の一部であったと考えてよい」
菅江真澄 (江戸時代の博物学者)
「東北地方の地名はアイヌ語に由来する。東北地方から出土する土器はアイヌの作ったものである」 「ナイ」「ベツ」で終わる地名は北海道、樺太、東北などに多く見られ、アイヌ語で「川」や「沢」を意味する。
青森・秋田・岩手には、今日でも和井内、生保内、今別など、おびただしいアイヌ語地名がある。
中には奥戸(オコッペ=興部)、シレトコ、シラヌカなどよく知られた北海道の地名と同じものもある。 ■ 東北地方の「ナイ」「ベツ」地名の分布(=アイヌ語・夷語の話者)
https://livedoor.blogimg.jp/taptior/imgs/d/1/d128dbca.jpg 北海道の民族が東北に移住したのは続縄文時代ですから、続縄文人はアイヌ語を話していた事になります。 後北式土器文化
続縄文時代後半期には、その初めには道央に限られた後北式土器が、やがては全道一円に進出するとともに、東北地方南部まで分布域を拡大した。後北式土器とは後期北海道薄手縄文土器の略である。続縄文時代前半期には海岸線に沿って遺跡の分布がみられたが、後半期には河川沿いに遺跡が分布する傾向を見せることから、この時期になって海洋での漁労・狩猟活動から、河川での漁労活動に生産手段が変化したと考えられる。 藤本(1994)は、各地の河川中流域に多くの遺跡が分布し、拠点的な大遺跡と小規模な遺跡の組み合わせがみられること、川筋に沿ってみられることから、後の擦文文化、アイヌ文化に続く河川漁労を主とした生業体系がこの時期に成立したとしている。
https://adeac.jp/hakodate-city/text-list/d100050/ht002190
それから、アイヌ語地名は沖縄、九州、島根県でも沢山見つかっていますから、縄文語はアイヌ語だった可能性が高いです。
従って、アイヌ人は縄文人の直系の子孫です。
因みに、シベリアのニブフ語やツングース語はアイヌ語とは全く違う言語です。
それから日本語は縄文語ではなく、南満州の西遼河流域が起源だとされています: 日本語のルーツは9000年前の西遼河流域の黍(キビ)農耕民に!
https://a777777.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=14019324 弥生人のY-DNAは O1b2 ですが、O1b2は長江からは見つかっていません。 O1b2 が見つかっているのは日本と朝鮮と満州の西遼河だけです。 つまり、弥生人は満州の西遼河でキビ・アワを栽培していた農耕民で、朝鮮で長江人から水田稲作を学んでから、日本に移民してきたという事です: 日本語の原郷は「中国東北部の農耕民」 国際研究チームが発表
Yahoo news 2021/11/13(土) 毎日新聞 日本語の元となる言語を最初に話したのは、約9000年前に中国東北地方の西遼河(せいりょうが)流域に住んでいたキビ・アワ栽培の農耕民だったと、ドイツなどの国際研究チームが発表した。10日(日本時間11日)の英科学誌ネイチャーに掲載された。 日本語(琉球語を含む)、韓国語、モンゴル語、ツングース語、トルコ語などユーラシア大陸に広範に広がるトランスユーラシア語の起源と拡散はアジア先史学で大きな論争になっている。今回の発表は、その起源を解明するとともに、この言語の拡散を農耕が担っていたとする画期的新説として注目される。 研究チームはドイツのマックス・プランク人類史科学研究所を中心に、日本、中国、韓国、ロシア、米国などの言語学者、考古学者、人類学(遺伝学)者で構成。98言語の農業に関連した語彙(ごい)や古人骨のDNA解析、考古学のデータベースという各学問分野の膨大な資料を組み合わせることにより、従来なかった精度と信頼度でトランスユーラシア言語の共通の祖先の居住地や分散ルート、時期を分析した。 その結果、この共通の祖先は約9000年前(日本列島は縄文時代早期)、中国東北部、瀋陽の北方を流れる西遼河流域に住んでいたキビ・アワ農耕民と判明。その後、数千年かけて北方や東方のアムール地方や沿海州、南方の中国・遼東半島や朝鮮半島など周辺に移住し、農耕の普及とともに言語も拡散した。朝鮮半島では農作物にイネとムギも加わった。日本列島へは約3000年前、「日琉(にちりゅう)語族」として、水田稲作農耕を伴って朝鮮半島から九州北部に到達したと結論づけた。 研究チームの一人、同研究所のマーク・ハドソン博士(考古学)によると、日本列島では、新たに入ってきた言語が先住者である縄文人の言語に置き換わり、古い言語はアイヌ語となって孤立して残ったという。 一方、沖縄は本土とは異なるユニークな経緯をたどったようだ。沖縄県・宮古島の長墓遺跡から出土した人骨の分析などの結果、11世紀ごろに始まるグスク時代に九州から多くの本土日本人が農耕と琉球語を持って移住し、それ以前の言語と置き換わったと推定できるという。 このほか、縄文人と共通のDNAを持つ人骨が朝鮮半島で見つかるといった成果もあり、今回の研究は多方面から日本列島文化の成立史に影響を与えそうだ。 共著者の一人で、農耕の伝播(でんぱ)に詳しい高宮広土・鹿児島大教授(先史人類学)は「中国の東北地域からユーラシアの各地域に農耕が広がり、元々の日本語を話している人たちも農耕を伴って九州に入ってきたと、今回示された。国際的で学際的なメンバーがそろっている研究で、言語、考古、遺伝学ともに同じ方向を向く結果になった。かなりしっかりしたデータが得られていると思う」と話す。 研究チームのリーダーでマックス・プランク人類史科学研究所のマーティン・ロッベエツ教授(言語学)は「自分の言語や文化のルーツが現在の国境を越えていることを受け入れるには、ある種のアイデンティティーの方向転換が必要になるかもしれない。それは必ずしも簡単なステップではない」としながら、「人類史の科学は、すべての言語、文化、および人々の歴史に長期間の相互作用と混合があったことを示している」と、幅広い視野から研究の現代的意義を語っている。【伊藤和史】 韓国語の起源は9000年前、中国北東部・遼河の農耕民
Yahoo news 2021/11/13(土) 朝鮮日報日本語版
https://ameblo.jp/yuutunarutouha/image-12710029028-15031005547.html
|
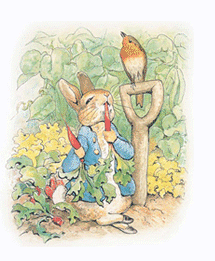
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。