|
<■98行くらい→右の▽クリックで次のコメントにジャンプ可> 日本神話は長江の稲作神話の物真似で日本の歴史を全く反映していない
ヤマタノオロチ退治
日本ではこのような大蛇はいない。日本の神話に語られるヤマタノオロチの人身供養の物語は雲南省などの長江流域の物語にその起源が求められる。浦島伝説の起源は中国の洞庭湖
浦島の話も洞庭湖には古くからありました。六朝時代の『拾遺記』(注10)に、洞庭山(洞庭湖の中にあるという説があります)の薬草を取りにいった男が洞窟に迷い込み、しばらく行くと別天地が開け、楽の響きや美女たちの歓待に酔いしれ、この世のものとも思われぬ夢のような暮らしをおくった話です。男は、やがてふと故郷が恋しくなり、帰郷を思いたつ。共に暮らした美女が別れを惜しみ、贈り物をくれる。洞窟の出口までおくられ、故郷に帰ってみると、知る人は一人もなく、家も何もない。村人にたずねると、三百年前に薬草を取りに行った男がそのまま帰ってこないという。男は行方不明となる。まさに山の浦島ですね。洞庭湖には、山にも湖にもこの話があるということです。 丹後地方には「不思議な時間」に関係する伝説として、「浦嶋伝説」の他に「八百比丘尼」の伝説と「羽衣伝説」があります。 「羽衣伝説」については、雲南省から東南アジアにかけての少数民族(苗(ミャオ)族や哈尼(ハニ)族、泰(タイ)族その他)の間に広く分布しているようですので、大林先生の言われるユーラシア大陸を西から東に流れる大きな文化の流れの1つの道(亀井貫一郎さんの言われる第1東胡のヒマラヤ迂回派のルート)があったことが窺われます。 春秋戦国時代の戦乱の時期から斉や呉や越が滅んだ時に、逝江省から山東半島にかけての地域から大勢の人達が日本列島に渡ってきたようです。 この時に既に不思議な時間の話が逝江省付近にあったかのかも知れませんが、アメリカ大陸や太平洋諸島域に不思議な時間の話が無いということは、不思議な時間の伝搬は紀元前1,000年(3千年前)より遅い時期と考えられますし、中国の話は西域との交流が確立した漢代の遅い時期から後に出来た話のようですので、もっと後の、大和国家成立過程の時期に大陸と往復した人達がもたらした(神仙思想と一緒にかどうかは判りませんが)ということにしておきましょう。
海幸山幸神話の一書(第1)や一書(第3)では山幸彦が海神の宮から戻るときに鰐に乗って戻ったとあり、また一書(第4)では海神の宮に行くときに鰐に乗っている。鰐は古事記の因幡の白兎にも登場する。この鰐は鮫であると言われているが、中国の揚子江流域には淡水性の鰐がおり、東南アジアのマレー鰐もかつては中国南部海岸にまで棲息していた可能性があるらしい。中国から鰐の知識が持ち込まれて鮫のイメージと融合して定着したという。
山幸彦は海神の娘の豊玉姫と結婚したが、この豊玉姫は鰐であった。このように人間と動物との結婚は異類婚と呼ばれる。ベトナム、ミャンマー、カンボジアなど東南アジアの王権起源の神話にはこの異類婚が多く、人間の男が動物の女と結婚して息子を作り、その子が新たな王国をつくるというストーリーが一般的だという。 学習院大学の名誉教授で芸能史学者の諏訪春雄によると、出雲の根の国神話についてもその由来を長江流域の少数民族の神話や伝説に求めることができるという。さらに諏訪氏は、東南アジアの兄妹始祖洪水伝説の系列に属するとされていた記紀の国生み神話が、実は長江流域に数多く発見される洪水神話に基づくことを論証し、東南アジアで発見される洪水神話もその分布状況から判断して中国から伝播したものである、つまり洪水神話はその源流は長江流域であるとしている。そしてこれと同じ理屈で、海幸山幸神話の原型も長江流域の伝承が取り込まれたのだと主張している。 ▲△▽▼ 天照大神は、日本の国号と記紀神話が成立したときに創作された新しい神です。より古い時代に「天照国なになに」という名で祀られた天照系の神々がいますが、そのなかに女神が単体で祀られたケースは見当たりません。信仰実績がないのですから、蘇我馬子達の暴挙が否定された後で、記紀神話が創作された時に、新しく設定された皇祖神と分かります。 記紀神話以前の古い国母神は、比売許曽(ひめこそ/姫の社という意味の古い高句麗語)に祀られていた明姫(アカルヒメ)でした。阿加流比売(アカルヒメ)という音写しか一般に知られてませんよね。天照大神・荒魂・瀬織津姫もまた記紀神話から除外されて、神社からもその名を消されていった女神です。隠蔽体質が顕著です。古い日女神達や建国にまつわる神話は、新たな日本国の神話と信仰を確立する妨げになるので、日本書紀に掲載されませんでした。本当の王統の誕生を祝うお祭りは、京都の葵祭です。建国神話はこのお祭りと一対一対応する桃太郎の昔話として知られています。 詳細を省きますが、アカルヒメが新羅から渡来した女神という神話は真に受けないでください。特有の仮託された表現で構成されているものを、矛盾に気付かずに、太陽神と巫女神が夫婦喧嘩したとか、元祖ストーカー王子と解釈するのは間違いです。書き手の地理的感覚や時間軸も混乱しています。阿加流比売を奉斎する巫女集団が大陸の高天原から渡来した時期は、黄巾の乱の後、卑弥呼登場の少し前です。 記紀神話成立以前の本来の太陽信仰を再生するうえで、国外の和人文化の記録が参考になります。
纏向型祭祀(土坑祭祀)と高句麗の東盟祭の類似性が指摘されています。中国大陸東岸の長江文明の稲作が日本まで伝わってきたことから分かるように、東夷とも倭(和)人とも呼ばれた人々の渡来によって、縄文時代は弥生時代に変わっていきました。黄巾の乱で発生した難民の渡来は、弥生時代を古墳時代に変えていきました。山東半島から纏向遺跡に至る東進ルート沿いに、和人文化圏が形成された時代がありました。高句麗地域(渤海湾岸文明)の朝日に対する信仰は東明信仰です。これを漢民族は扶桑信仰として書き残しています。高句麗では国母神とその息子の男王神の二霊廟を祀っているという記述も残ります。 明姫は「日が明ける」という意味を持つ日女神です。夜明けを神格化した女神です。夜明けから生まれてくるのは太陽です。太陽を神格化した男神が東明聖王です。夜明けが産む太陽。明姫が産む東明聖王。皇祖神・天照大神(女神)が産み出した皇統。高句麗の国母神とその息子の男王神に対する信仰とも対応します。 記紀神話は、イザナギとイザナミの男女一対の神による国産みから始まります。これは陰陽思想に基づきます。天照大神も陰陽思想の影響を受けて設定された太陽神です。天上に輝く陽の存在(太陽)は男神で、その光を受けて人の姿を取るとき、陰の存在の女神の姿を取るとされます。ですから、太陽神・天照大神の依り代となる巫(かんなぎ)は、生き神扱いの男装の巫女なのです。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1296497722
|
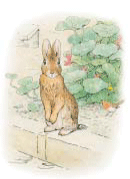
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。