http://www.asyura2.com/24/gaikokujin3/msg/606.html
| Tweet |
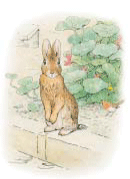
女性の働き方と年金 時代に即した抜本改革を/毎日新聞
2025/9/14
https://mainichi.jp/articles/20250914/ddm/005/070/076000c
公的年金のあり方は働き方や老後の生活設計と密接に関係している。社会の変化に応じて制度を見直すことが肝要だ。
先の通常国会で成立した改正年金法は、基礎年金の底上げ策やパート労働者らへの厚生年金の適用拡大といった低年金対策に一定の道筋を付けた。だが、女性の就労を制約している仕組みの抜本的な見直しは先送りされた。
厚生年金に加入している配偶者の扶養を受けていれば、保険料を納めることなく基礎年金を受給できる「第3号被保険者制度」である。対象者のほとんどが女性だ。
妻が専業主婦の世帯が多かった1985年に導入された。働いて収入を得ていない女性の年金権を確保する狙いだったが、就労を扶養の範囲に抑える「働き控え」と呼ばれる現象が生じた。
温存された低賃金構造
多様な人材を生かすためのコンサルティングを手がける「働きかた研究所」代表の平田未緒さん(57)は、パートの女性の中には、保険料負担が生じない範囲内で働くことを「当たり前」と考える人が少なくないと指摘する。
企業にとっても、厚生年金や健康保険の保険料を負担せずに人材を確保できるメリットがある。このため、女性の就労がパートに偏り、短時間労働で低賃金という構造が温存されることになった。
中高年の単身女性の交流団体「わくわくシニアシングルズ」代表の大矢さよ子さん(75)は40代で離婚して職探しをしたが、主婦向けのパートの求人しか見つからなかった。「厚生年金には入れず、低賃金のため国民年金の保険料負担も重かった」と振り返る。
90年代以降、共働き世帯が多数を占めるようになり、3号制度が導入された当時と状況は大きく変わった。
|
|
|
|
最新投稿・コメント全文リスト コメント投稿はメルマガで即時配信 スレ建て依頼スレ
|
|
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。