http://www.asyura2.com/24/health19/msg/123.html
| Tweet |
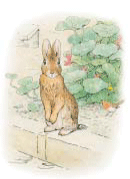
30代から始まる「免疫老化」防止に役立つ生活習慣/東洋経済オンライン
吉村 昭彦
https://www.msn.com/ja-jp/health/other/30%E4%BB%A3%E3%81%8B%E3%82%89%E5%A7%8B%E3%81%BE%E3%82%8B-%E5%85%8D%E7%96%AB%E8%80%81%E5%8C%96-%E9%98%B2%E6%AD%A2%E3%81%AB%E5%BD%B9%E7%AB%8B%E3%81%A4%E7%94%9F%E6%B4%BB%E7%BF%92%E6%85%A3/ar-AA1GohRd?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=bb13aae73c8046eeba55247ce261be42&ei=26
体内に侵入した病原体や異物から体を守る「免疫」の仕組み。人の健康になくてはなりませんが、加齢に伴い免疫機能も低下すると言われています。ここでは「免疫の老化」をテーマに、具体的に何が起きるのか、防止の手立てについて免疫研究の第一人者である吉村昭彦氏に聞きました。
免疫は2種類に大別される
免疫とは、体内に侵入したウイルスやバクテリアなどの病原体、あるいはがん細胞などの危険な「異物」から体を守る機能のことです。生まれつき備わっている「自然免疫」と、一度異物に接触することで獲得する「獲得免疫」の2種類に大別されます。
「自然免疫」は好中球やマクロファージ(体内に侵入した病原体・異物を貪食して排除する免疫細胞)などが病原体を攻撃する仕組みで、一方、「獲得免疫」は抗体や細胞傷害性のキラー細胞によって異物を排除するもので、一度接触した異物の情報を記憶して次回の感染などに備えるメモリー機能もあります。
体を病気から守るための免疫も誤作動や暴走で病気を引き起こすことがわかっています。本来、免疫は病原体やがんといった危険なものにだけ反応し、食物や花粉を攻撃することはありません。このような仕組みを「免疫寛容」と呼びます。
ところが異常調節や老化などが原因で働きが破綻すると、自己免疫疾患やアレルギーを発生します。例えば花粉症や食物アレルギー、1型糖尿病、関節リウマチなどは免疫寛容が破綻するために起きる症状です。
また免疫細胞が使用する「サイトカイン」と呼ばれる情報伝達物質の過剰な産生もアルツハイマー型認知症や糖尿病にも関係することが知られています。このように、免疫は体を守る働きがある一方、その弊害も明らかになってきました。
【画像】
https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1GoylU.img?w=768&h=455&m=6
体を守る免疫機能は30代ごろから老化が始まって加齢とともに徐々に進行します。そこには、個体の老化も深くかかわっています。
人間の体はおよそ60兆個(最近は37兆個と言われています)の細胞からできており、細胞の多くは分裂をしながら古い細胞と新しい細胞を入れ替えています。ところが細胞分裂の回数には限界があり、分裂しつくした細胞は二度と分裂・増殖できません。「細胞老化」と呼ばれる現象で、細胞老化に至った細胞は「老化細胞」と呼ばれます。
そして、老化細胞が増えると個体の老化も進み、蓄積した老化細胞はサイトカインを産生してがんや慢性炎症、臓器の機能不全など、多くの病気の原因となることがわかっています。マウスを用いた実験では、老化細胞を取り除くと動脈硬化や腎障害といった加齢に伴うさまざまな病気の発症が遅れました。
若い体では、老化細胞はがん細胞などと同様に、免疫により排除される仕組みになっています。これを免疫監視機能(異常細胞の除去)と呼びます。NK(ナチュラルキラー)細胞やキラーT細胞が老化細胞の表面に現れる老化抗原などを検知・破壊し、食細胞が処理するのです。
免疫システムが老化するとがんの発症リスクが高まる
ところが免疫システムが老化すると、がんの発症リスクが高まりますし、老化細胞も体内に蓄積しやすくなるのです。ワクチンの効果も若年層より弱まり感染症の重症化リスクも高まります。
加えて、免疫の老化は体内の炎症を増やし低レベルの炎症が持続する「炎症老化」の状態も招き、これにより動脈硬化や糖尿病などのリスクは上昇。アルツハイマー病、心血管疾患、骨粗鬆症との関連も指摘されています。
免疫が加齢により老化するのは、「胸腺」(胸骨の裏側に位置しT細胞を成熟させる器官)や「骨髄」といった、免疫細胞が作られる免疫工場の機能が低下するからです。結果、老化細胞の除去力は低下します。
特に胸腺は思春期以降に縮小し、60代以降では機能が大幅に低下します。これにより、新しく生まれるナイーブT細胞(まだ病原体に出会っていないまっさらなT細胞)が減少し、引き換えに病気との戦いの記録を持ち生き残った記憶T細胞(メモリーT細胞)が免疫の中心となります。しかし記憶T細胞もやがては細胞分裂が停止した「老化T細胞」もしくは機能が低下した「疲弊化T細胞」へと変化します。これらの細胞は免疫の活動を抑制するブレーキ因子が強く作用しており、老化を防ぐ免疫力は低下することになります。
胸腺だけではなく、骨髄も加齢に伴い免疫細胞の生産力が低下します。新しく生まれるB細胞(リンパ球の一種で抗体を作り出す)やNK細胞といったリンパ球は減り、その代わりにサイトカインを産生し炎症を起こすマクロファージが増え、掃除や修復にかかわるマクロファージは減少します。
これも加齢によって老化細胞の除去力が低下し炎症が慢性化する理由の1つです。慢性炎症は、臓器の老化を速め結果的に寿命を縮めることになります。
このように免疫系の老化は老化細胞の蓄積を促し、体の老化を加速させ、骨髄や胸腺の老化は免疫機能を低下させ、さらなる老化につながっていきます。個体の老化と免疫の老化はお互いに促進しあっているのです。
適切な栄養摂取のうえで行うカロリー制限に効果
そこで免疫老化を改善するために、疲弊化T細胞の機能回復や記憶T細胞の老化防止に関する研究も進められています。例えば、マウスを対象とした研究では、T細胞の遺伝子を操作したり、特殊な刺激を与えると機能を失わずに細胞を増やせることが証明されました。適切な方法が見つかれば人でも「若さ」を保ったT細胞を増やし続けられるかもしれません。
胸腺は強いストレスでも萎縮し、若いうちはストレスが排除されると再び大きくなりますが、加齢による萎縮を回復させるのは難しいとされています。わかっているのは、免疫の老化速度には個人差があり、遺伝的要因と生活習慣の両方が影響するということです。
例えば、100歳以上の家族がいるなど長寿家系は炎症反応が抑えられており、反対に関節リウマチといった自己免疫疾患や慢性炎症疾患の家族歴があると免疫系の消耗が早まる傾向が見られます。
老化を防ぐ研究で、人間に対して効果が報告されているのは、適切な栄養摂取のうえ行うカロリー制限です。カロリー制限は免疫系の老化も防止する可能性があります。2年間、カロリーを制限したら普通食の人に比べて胸腺が萎縮せず、ナイーブT細胞の数も多かったとの報告がありました。
ただし、カロリー制限は大きなストレスになる可能性もあり、どのような条件が最適なのか見つけるのは難しいとされています。
なお食事に関してはオリーブオイルや魚、ナッツといった地中海食、食物繊維、ポリフェノールを多く含むベリー類、DHAなどのオメガ脂肪酸、ヨーグルトをはじめとする発酵食品などは慢性炎症を抑制し、免疫系の老化を防止する効果が期待できます。これらは一般的に長生きや健康に資するとされているものです。
もっと手っ取り早く、薬で免疫老化を防止できないでしょうか? 実際に2型糖尿病の治療役に用いられ、一部ではやせ薬として知られる今話題の「GLP1受容体作動薬」にもカロリー制限に加えて、炎症を抑え老化を抑制する効果があると期待されていますが、副作用もあり研究段階です。
また、若いT細胞を増やし、免疫老化を抑制する作用が認められている免疫抑制剤の「ラパマイシン」も検討されたことがあります。264人の高齢者を対象に低用量のラパマイシンを6週間投与したところ、投与後にインフルエンザワクチン接種により抗体生産量が増え、さらに1年間は感染症の発生率が有意に減少しました。
ただし長期的な病気の罹患率の低下、健康寿命の改善については不明ですし、何よりも免疫抑制剤は量の加減が難しく、すぐに一般人が使用できるとは考えにくいです。
追い込まない程度の運動習慣がおすすめ
適度な運動も効果的だとわかっています。運動により筋肉から分泌されるホルモン物質の「イリシン」には、認知機能の改善やアルツハイマー病、心疾患系の予防に効果があり、ストレス軽減や健康寿命の延伸が期待できます。強いストレスと免疫老化は密接にかかわっているので、自身を追い込まない程度の運動習慣はおすすめです。
近年は、骨に免疫機能を若く保つ役割があることも明らかになりました。全身の骨は強度を保つため、古い骨と新しい骨を入れ替える「骨代謝」を行っています。骨代謝は「骨細胞」(破骨細胞と骨芽細胞を管理)、「破骨細胞」(古い骨を溶かして壊す)、「骨芽細胞」(新しい骨を作る)の3種類の細胞によって行われます。
ドイツの研究チームは、骨芽細胞が分泌する「オステオポンチン」というホルモンが赤血球や白血球の前駆体である「造血幹細胞」の機能を維持することを発表しました。 造血幹細胞が若さを維持することで全身の免疫機能が活性化するというのです。さらに骨芽細胞が分泌する「オステオカルシン」というホルモンも、さまざまな抗老化作用があるとわかっています。
骨に負荷がかかると骨代謝は促されるので、かかとを上げてから下ろす「かかと落とし運動」は効果的と言われています。併せてカルシウムやたんぱく質、ミネラル、ビタミンもバランスよく摂ると骨の強度は強くなり、骨が強くなると免疫力が上がるばかりか、オステオカルシンには記憶力の向上、肥満の防止といった効果もあります。
働き盛りのビジネスパーソンは運動不足で、ラーメンや揚げ物などカロリーの高い食事も好みがちです。まずは、ここで紹介した生活習慣を取り入れてはいかがでしょうか。
(構成:大正谷 成晴)
|
|
▲上へ ★阿修羅♪ > 不安と不健康19掲示板 次へ 前へ
|
|
最新投稿・コメント全文リスト コメント投稿はメルマガで即時配信 スレ建て依頼スレ
▲上へ ★阿修羅♪ > 不安と不健康19掲示板 次へ 前へ
|
|
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。