|
<■298行くらい→右の▽クリックで次のコメントにジャンプ可> <主張>学術会議法が成立 変われないなら再改革だ
社説
2025/6/20 5:00
https://www.sankei.com/article/20250620-5OKVA7Z7LRO3FE4R3XZSZBJ3XY/
日本学術会議を現在の
「国の特別機関」
から
「特殊法人」
に移行させる新たな学術会議法が成立した。
令和8年10月に新組織になる。
学術会議の光石衛会長は、独立性を損なう懸念が払拭されないまま法案が国会に提出され、修正されずに成立したとして、
「非常に残念だ」
とする談話を発表した。
歴代会長6人は声明を出し、石破茂首相に学術会議の独立性と自主性の尊重を約束するよう求めた。
令和2年に菅義偉首相(当時)が会員候補のうち6人を任命しなかったことについて
「会員選考の自主性、独立性、学問の自由の決定的侵害」
と改めて批判した。
国民を守るための軍事研究を忌避し続けてきたことへの反省はどこにもない。
国政選挙や首相指名選挙などの民主的な手続きを経て就任した首相による正当な人事に、今も尚反発している。
独善的な姿勢に呆れる他ない。
そもそも新法は独立性を損なう内容ではない。
学術会議の総会で会員を選任するとしている。
外部有識者による選定助言委員会を設けるが、この委員の選任も総会が行う。
運営の透明性を確保するため、首相任命の監事や評価委員を置き、業務や財務の監査や活動状況の評価を行う。
学術会議側は政府の介入を受ける恐れがあるとしているが、今後も税金が投入される以上、評価の仕組みを設けるのは当然だ。
政府に関わりたくないなら、自分たちだけで資金を集めればよい。
ただし、新法には抜本改革から程遠いという問題がある。
学術会議は例えば、新型コロナ禍の際、提言などで国民から評価されるような役割を果たさなかった。
学術会議の目的として条文に
「社会の課題の解決に寄与すること」
を新たに掲げたが、この程度で実効性が確保できるとは思えない。
学術会議が最も反省すべきなのは、昭和25年と42年に軍事目的の科学研究を拒否する声明を出し、平成29年にそれらの継承を宣言したことだ。
再出発には一連の声明の撤回が必要だ。
反省も撤回もしないのなら、政府は予算を執行の段階で大幅に絞り込むべきだ。
閉鎖的で反国民的な組織から、本当に国民のためになる組織に生まれ変われないのなら、再改革しなければならない。「右の人が入る法案許せるか」発言に坂井担当相「多様性確保の選考方法との評価」学術会議
2025/5/9 19:07
https://www.sankei.com/article/20250509-UBMKTBTAWRE6JOBJ3N67OOMDZI/
日本学術会議を国の特別機関から特殊法人に移行する法案を可決した2025年5月9日の衆院内閣委員会。
日本維新の会の三木圭恵氏は2025年4月の同会議総会で法案について
「これまでとは違う人が入ってくる」
「右に立っている人が入ってくる状態を許していいのか」
と述べた会員の発言に苦言を呈した。
「左派であろうと右派であろうと色々な人が入って学術を究明していくことが必要だ」
と強調した。
■「適切な選考方法とされた」
発言を巡っては2025年4月7日の同委で学術会議について
「一定の政治的考えを持つ人を排除していたとの疑念が生じる」
(自民党の平沼正二郎衆院議員)
などと疑問視する声が上がり、北海道大の宇山智彦教授が2025年4月8日、フェイスブック(FB)で自身の発言だと明らかにした。
宇山氏はFBで
「学術会議の法人化を中心的に唱えてきたのは、日本会議や統一教会と繋がりのある政治家たちであり、その人々が自分たちと同じ政治的立場を持つ人を学術会議の会員にしようと考えていても全くおかしくない」
などと主張した。
法案を所管する坂井学内閣府特命担当相は、宇山氏の発言について
「今までは右に立つ人が(学術会議の会員に)入っていなかったが、今後入ってくる認識を持っているからだと思う」
と指摘。
その上で
「法案で議論している選考方式が、この人がいうような右側に立つ人だけではなく幅広くダイバーシティーを確保するもので、色々な人が入ってくる」
「適切な選考方法だと評価されていることかと思う」
と語った。
■野党共闘の元会長連名の政治的中立は
また、法案を巡っては今年2025年2月に広渡清吾氏ら学術会議の歴代6会長が石破茂首相に撤回を求める共同声明を明らかにしている。
会長退任後の広渡氏は、平成29年の衆院選で共産党の機関紙やユーチューブチャンネルなどに登場し野党統一候補を応援した経緯があり、三木氏は
「声明に
『共産党と一緒に統一候補を掲げて戦う』
という人の名前を載せてしまうこと自体、学術会議の自浄能力の限界を感じる」
「(共同声明に)広渡氏の名前を消した方がいいと思う」
と指摘した。
坂井氏は、共同声明の政治的中立性を問われ、
「なかなか難しい」
「政治的勢力から独立して学術的な活動していただくのが望ましい」
と述べ、
「(法案が成立すれば)党派的な主張を繰り返す会員は、学術会議は解任できる」
「どのような場合が該当するかは学術会議で判断されるべき」
とメリットを挙げた。 日本学術会議の特殊法人化法案、可決 衆院内閣委 立民は独立性を懸念し、反対
2025/5/9 17:20
https://www.sankei.com/article/20250509-DTP7QRWKHZLKZPOL4AWKE5PIKU/
衆院内閣委員会は2025年5月9日、日本学術会議を現行の
「国の特別機関」
から
「特殊法人」
へと移行させる法案について、与党などの賛成多数で可決した。
近く開かれる本会議で衆院を通過、参院に送られる見通し。
立憲民主党など野党の一部は、政府介入が強まり独立性に懸念があるとして、法案に反対の姿勢を示している。
法案は学術会議を国から切り離した上で、首相任命の監事や評価委員を新設する内容。
学術会議は政府による監視が強まり自由な活動ができなくなる恐れがあるとし、法案の修正を求めている。
立民の山登志浩議員は、科学的な知見から政府と異なる意見が表明された場合に、人事や資金面での影響が出る可能性があるとして
「法案には政府が介入、関与する仕組みが残っている」
と批判した。
坂井学内閣府特命担当相は
「学術会議の独立性や自律性を抜本的に高めるための法案だ」
と強調した。 「右の人が入る法案許せるか」発言は北大教授 FBで「学術会議が右派にお墨付きは害」
2025/5/8 18:57
https://www.sankei.com/article/20250508-I3ZK2ZQPNNAFRAJZTJG7SDPFGU/
北海道大の宇山智彦教授(中央アジア近代史・現代政治)は2025年5月8日、フェイスブック(FB)で、日本学術会議を特殊法人化する政府提出法案を巡り2025年4月の同会議の総会で
「法律が通ることでこれまでとは違う人が入ってくる」
「文系には右に立っている人がいる」
「そういう人たちがここに入ってくる状態を許していいのか考える必要がある」
などと述べた人物は自身だと明らかにした。
発言した意図について
「(学術会議は)現在は政府と協力しつつ独立した立場を保てる研究者が会員になっているが、法人化後には右派が入って学術会議の活動を政治化する可能性があるのではないか」
と説明。
そう疑問視する理由として
「学術会議の法人化を中心的に唱えてきたのは、日本会議や(旧)統一教会(現・世界平和統一家庭連合)と繋がりのある政治家たちであり、その人々が自分たちと同じ政治的立場を持つ人を学術会議の会員にしようと考えていても全くおかしくないからである」
と主張した。
現在の学術会議に関しては
「共産党に連なるような左派の存在は全く感じられない」
「学術会議の外での法人化反対運動が軍学共同反対運動とかなり重なっていることもあり、学術会議もそのイメージで見られがちだ」
と指摘した。
一方、過去の学術会議では共産党系などの左派の会員が政治的な主張や活動をしていたとして
「決して好ましいことではなかった」
とした上で
「法人化後の学術会議に右派が入ることも同様に好ましくない」
とした。
宇山氏は
「右派の影響力の下で学術会議が、ジェンダーなど人権の問題や歴史観について、世論や学界の見方とは異なる抑圧的・国粋主義的な立場を取り、自民党右派や他の右派政党の政策にお墨付きを与えれば、大きな害があるだろう」
などと主張した。
問題の発言を巡って、法案を審議した2025年5月7日の衆院内閣委員会で発言者名を伏せたまま
「素直に解釈すると右の人に入ってほしくないと捉えられる」
「一定の政治的考えを持つ人を排除していたとの疑念が生じる」
(平沼正二郎氏)
など疑問視する声が自民党議員から上がっていた。 「右の人が入れる法案許せるか」学術会議会員の懸念に、自民・平沼氏「排除していたの?」
2025/5/7 17:45
https://www.sankei.com/article/20250507-HD6C5NFP5VGVDFYQZ642GHKCB4/
日本学術会議を特殊法人化する政府提出法案を審議した2025年5月7日の衆院内閣委員会では、東京都内で2025年4月14〜16日に開かれた学術会議総会で
「この法律が通ることで、これまでとは違う人が入ってくる」
と懸念を示した一部会員の発言が問題視された。
■学術会議は「特定思想で固めるか」
自民党の平沼正二郎衆院議員らによれば、この会員は総会で
「文系には政府にすり寄る、かなり右に立っている人が確実にいる」
「そういう人たちがここに入ってくる」
「そういう状態を許していいのか考える必要がある」
と述べたという。
平沼氏は
「素直に解釈すると右の人に入ってほしくないと捉えられる」
と述べ、会員が推薦した候補者を首相が形式的に任命する方式で行われる従来の会員選考について
「一定の政治的考えを持つ人を排除し、特定の思想で会員を固めていたとの疑念が生じる」
と指摘した。
その上で今回の法案に基づく会員選考について、
「異なる考えを持つ者を排除する選考を行えず、幅広い形で平等な選考が行われるのか」
と政府側に尋ねた。
■政府担当者も発言に「えっ」
内閣府の笹川武官房審議官は
「そういうことに資するための法案だ」
と述べた上で、会員選考について
「実質的な絞り込みを2回行い、過程を公開する」
「専門グループが選んだ候補がそのままスルーして会員になるわけではない」
「委員会や総会で実質的に絞り込まれる」
と強調した。
笹川氏も問題の発言をオンライン中継で聞いていたといい、
「『えっ』と思った」
「ただ実際はどうか分からない」
と述べた。
政治的な考えに応じて会員候補が排除されていたかどうかは不明だとした。
問題の発言については、自民の黄川田仁志衆院議員も2025年5月7日午前の同委で質した。
参考人の梶田隆章前学術会議会長は
「政治的な傾向がどうこうということについて、全く議論したことがない」
と述べるにとどめた。 <主張>学術会議の法案 反省ないのに税金投入か
社説
2025/3/19 5:00
https://www.sankei.com/article/20250319-IYNQVK6VS5KJNK75ZXMKUZVPYI/
政府は日本学術会議を現在の
「国の特別機関」
から特殊法人に移行させる学術会議法案を閣議決定し、国会に提出した。
首相が任命する監事や評価委員を置き、業務や財務の監査や活動状況の評価を行う。
透明性を高めるのが狙いだが、会員の選任では、首相任命をやめ、学術会議が総会で決める。
外部有識者による選定助言委員会も設けるが、同委員を選任するのも総会だ。
これで一体、何が改まるというのか。
法案は学術の知見を活用し、社会の課題解決に寄与することを目的としているが、期待できず、改革に値しない。
学術会議の光石衛会長は自主性、独立性の観点から懸念が払拭されていないとして、
「閣議決定は遺憾だ」
とする談話を発表した。
閣議決定に先立ち、歴代会長6人は
「責務を果たすことができない」
と法案撤回を求める声明を出した。
梶田隆章前会長は
「監視を強めるなど政府の思いのままにコントロールしようとしている」
と訴えた。
だが、これまで日本のために十分な責務を果たしてきたとはとても言えない。
中国が
「核汚染水」
とレッテルを貼った東京電力福島第1原発の処理水の海洋放出では、科学的知見に基づく反論をしてこなかった。
会見で大西隆・元会長は
「科学的な観点から議論する余地はあったかもしれない」
と述べたが、今更何を言っているのか。
新型コロナウイルス禍でもろくな役割を果たしてこなかった。
最大の問題は、防衛力の充実に関する研究を妨害する要因となってきたことだ。
昭和25年と昭和42年に軍事目的の科学研究を拒否する声明を出し、それらの継承を平成29年に宣言した。
学術会議は一連の声明を撤回していない。
侵略者から国民を守れなくてもよいということか。
政府は、このような反国民的行動をとってきた反省のない学術会議に対し、年間10億円前後の財政支援を継続する方針だ。
これは許し難い。
体制が改まるまでの間も、税金投入は最小限にしなければならない。
学術会議は政府の関与に反対するのなら、国費に頼らず自分たちで資金を集めればよい。
政府は改革効果が疑われる同法案を取り下げ、抜本的に改めて、出し直すべきだ。 学術会議への補助金投入は安保研究規制声明の破棄を条件に 保守党・島田氏が質問主意書で
2025/3/17 17:35
https://www.sankei.com/article/20250317-47G3XR7XXZFRNHOKA5NLKWVGSY/
日本保守党の島田洋一衆院議員は2025年3月17日、
「軍事的安全保障研究と見なされる可能性のある研究」
を声明で規制対象としている日本学術会議に対する国の補助金について、
「声明の破棄を条件とすべきではないか」
との質問主意書を提出した。
学術会議を巡っては、2026年10月に現在の
「国の特別機関」
から特殊法人へ移行させる日本学術会議法案が今国会に提出されており、国が新法人を財政支援することになっている。
島田氏は主意書で、将来的に軍事技術へ応用可能な基礎研究を助成する防衛装備庁の
「安全保障技術研究推進制度」
について、
「日本学術会議が、軍事研究を禁止した過去の同会議声明を踏まえて、安保研究制度は
『問題が多い』
とする批判声明を出し、同制度に対する大学からの応募が急減した」
と指摘した。
その結果、
「関連分野における研究の停滞や共同研究中止、海外研究者に論文発表の先行を許すといった事態を招いてきたと考える」
とし、
「政府はこの声明の破棄を補助金供与の条件とすべきではないか」
と石破茂首相に質した。
島田氏は産経新聞の取材に対し、
「提出された法案の第48条には政府が
『必要と認める金額を補助することができる』
と書かれている」
「ということは、税金を投入しなくてもいいというようにも読める」
「自衛隊の能力向上や自衛官の命を守ることを阻害している団体に税金を出すのはとんでもない」
「自衛隊に対する裏切りだ」
と話した。 学術会議、税金投入額2割増の12億円 与党「見合った活動なければ、さらなる改革も」
2025/3/7 20:02
https://www.sankei.com/article/20250307-FJEGWRE2DBIA5LFIO3YHXIHWRU/
2025年3月7日に閣議決定された日本学術会議法案で、学術会議は法人化される方向となった一方、国による年間10億円程度の財政支援は継続される。
学術会議側が国から完全に切り離されることに反発したためだ。
抜本改革とは言い難く、国益に適う組織に生まれ変わるかどうかも見通せない。
「戦後から続く法人化への議論に区切りをつけた」。
内閣府幹部は今回の改革の意義をこう強調した。
法人化の必要性は学術会議設立当初から指摘されてきた。
政府方針に反する見解を示す場合もある組織が国の機関であるのは不適切との考えからだ。
昭和28年には吉田茂首相(当時)も民間移管を検討した。
近年は自民党や保守層を中心に学術会議の法人化を求める声は更に強まっていた。
国民の税金で運営される組織であるにもかかわらず、大学などによる軍事研究を妨害する学術会議への不満が募っていた。
学術会議は昭和25年に軍事研究を忌避する声明を出し、平成29年にその継承を表明した。
科学技術の発展で軍事と民生の線引きが難しい中、声明は
「時代錯誤」
との批判が根強い。
新型コロナウイルス禍や東京電力福島第1原発処理水の海洋放出といった国民生活に関わる重要テーマでも、学術会議は科学的知見に基づく発信が不十分だった。
菅義偉政権の会員候補の任命拒否をきっかけに組織の在り方を巡る議論は大きく進んだ。
だが、国からの出資がない民間法人化には学術会議が抵抗し、内閣府所管の特殊法人への移行にとどまった。
この結果、税金の投入は継続され、令和7年度予算案では例年より2割程度多い約12億円が盛り込まれている。
法案では国益にかなう組織への変革を促すため
「社会課題の解決に寄与」
との基本理念を明記した。
政府関係者は
「デュアルユース(軍民両用)の先端技術研究も含まれると解釈できる」
と解説する。
ただ、拘束力はなく、確実に履行されるかは不透明だ。
自民中堅は
「予算に見合った活動ができないなら、更なる改革も必要だ」
と牽制した。 学術会議法案を閣議決定 国の特別機関から特殊法人へ移行も10億円の国費支援は継続
2025/3/7 16:04
https://www.sankei.com/article/20250307-H5BUXOK4M5IIRG2MMKEC6KZ43U/
政府は2025年3月7日、日本学術会議を来年2025年10月に現在の
「国の特別機関」
から特殊法人へ移行させる日本学術会議法案を閣議決定した。
首相が任命する
「監事」
や評価委員を置き、業務や財務の監査を行うことが盛り込まれたものの、意見に法的拘束力はない。
年間約10億円という国費による財政支援は継続される。
林芳正官房長官は同日の記者会見で
「日本学術会議の機能が強化され、国民の期待にしっかりと応えていくことを期待する」
と述べた。
法案では、学術会議を
「科学者の代表機関」
と位置づける。
社会課題の解決への寄与や人類社会の持続的な発展、国民の福祉向上に貢献するといった理念も明記した。
国は運営の自主性、自律性に配慮しなければならないとした。
また、これまでの首相による会員任命はなくし、学術会議総会が任命。
外部有識者からなる
「助言委員会」
が意見を述べる。
学術会議の組織の在り方見直しは、令和2年の菅義偉元首相による会員候補6人の任命拒否が発端。
現行制度では現会員が推薦した候補を首相が形式的に新会員として任命しており、国費を投じながら実質的に身内の推薦で会員が決まる不透明さに菅氏が懸念を示した。
令和5年には岸田文雄前首相が、第三者機関を会員選考に関与させる改正案の提出を試みたが、学術会議側の反発で断念している。 日本学術会議、令和8年に特殊法人へ移行 首相任命の「監事」が監査 閣議決定
2025/3/7 9:14
https://www.sankei.com/article/20250307-523GVOEY6BMDXOI2CP53QFYPNQ/
政府は2025年3月7日、日本学術会議を令和8年10月に現在の
「国の特別機関」
から、特殊法人へ移行させる日本学術会議法案を閣議決定した。
新法人を国が財政支援し首相による会員任命をやめる一方、首相任命の役員
「監事」
や評価委員を置き、業務や財務の監査などをする。
政府は会員選考や活動の透明性を高めるとしているが、運営に一定程度関与する仕組みを残す。
現在の選考では、現会員が学術的な業績などから会員候補者を選んで推薦し、首相が推薦に基づき新会員を任命している。
法案は、学術会議を
「科学者の代表機関」
とし、人類社会の持続的な発展、国民の福祉向上に貢献することを基本理念に明記した。
国は運営の自主性、自律性に配慮しなければならないとした。
新法人では、学術会議総会が会員を任命するが、外部有識者からなる
「助言委員会」
が意見を述べる。
定員は現在の210人から250人に増やし、政府への勧告権限は維持する。
[18初期非表示理由]:担当:スレと関係が薄い長文多数のため全部処理。自分でスレを建てて好きな事を投稿してください
|
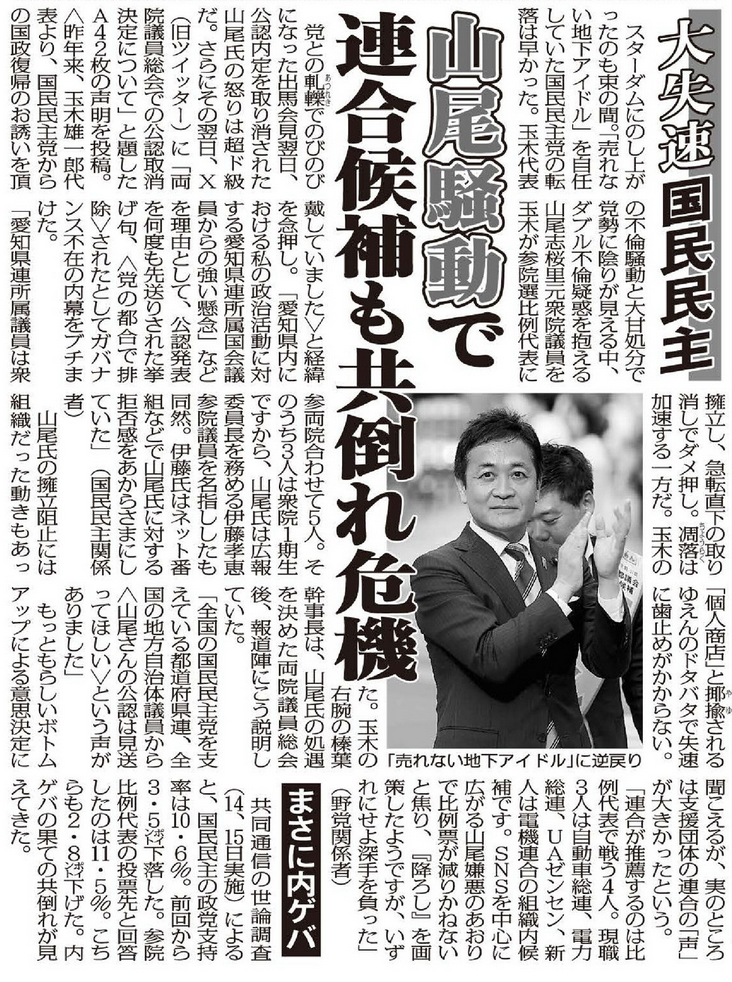

 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。