|
�ް�ެ݂͉��̃��[���b�p���̂Ăă^�q�`��I�̂��H �w�y���ւ̓��x �@�@�u�����͊y���ł����v�u���������̊p�ł���v�B�q���������W�܂��Ă̋S�������B��l�����t�����X�ƃy���[�ƃ|���l�V�A�Ō��������q�������̗V�с\�����ɂ́u�y���ɒH��������v�Ƃ������E���ʂ̊肢�����߂��Ă��܂��B�y���[���܂�̍�ƃo���K�X�E�����T���w�y���ւ̓��x �i�͏o���[�V�� 08.1���A�r�V�Ď��Ґ��E���w�S�W��Q���j�́A�����̐l���������[�g�s�A��ǂ����߂��P�X���I�ɐ������A����̔��t�҂ɂ��Đ��҂ł�������l�̐��U��ǂ������j�����ł��B �u�X�J�[�g���͂�����ҁv�Ƃ���ꂽ�t���[���E�g���X�^���i1803-1844�j�Ɓu�|�p�̏}���ҁv�|�[���E�S�[�M����(1848�]1903�j�B��l�̖O�����Ƃ̂Ȃ����܂�������́u�y���v�Nj��Ɉ��|����܂��B��l�́A�c��Ƒ��̊ԕ��ł����B �S�P�ŖS���Ȃ����t���[���̒Z���l�����ے�����̂́A�ޏ���₦���P���N���Ǝq�{�̒ɂ݁A�����ĐS���̋߂��ɐH�����e�e�ł����B�����́A�v�ł������ʼn�Ƃ̃A���h���E�V���U���B�y���[�l�̕��e�̎���A�n���Ȑ����̒��ŕ�e���疳���������ꂽ�����B�u�v�ƕ�炵�����̂����Ƃ���S�N�ԂɁA��x�Ƃ��Ĉ��̉c�݂��������Ƃ��Ȃ������B���ӁA��������B����A���������ꂽ�̂��v�B���̉������̒ɂ݂́A�����ȗ������Ă��܂��B���̏e�e�́A�t���[�����T���ȏf���̂���y���[�i�v����̓��S��j����t�����X�ɖ߂�A����̔��������������`�Ő��������߂��Ƃ��V���U���Ɍ�����A��p��S���߂��Ɏc�������̂ł��B �@�A���[�k�́A�V���U���Ƃ̊Ԃ̃t���[���̂R�Ԗڂ̎q���B�A���[�k�́A�V���U���ɂR�x�U������A��������܂��B�t���[���̓V���U�������i���A���̑����̒��ŁA�V���U���Ɍ����ꂽ�̂ł��B�s�K�Ȗ��A���[�k�́A�W���[�i���X�g�̃N�����B�X�E�S�[�M�����ƌ������A�|�[���݂܂��B�P�W�S�W�N�̊v����A�N�����B�X�͉Ƒ����āA�V�V�n�����߂ăy���[�Ɍ������܂��B���������̓r���ŕa�����A�A���[�k�͓�l�̎q���ƂƂ��Ƀy���[�ցB�y���[�ł́A�T���ȑc���̒�Ɋ��}����A�A���[�k���q���������A���܂�ď��߂čK���ȓ��X�𑗂�܂��B�|�[���E�S�[�M�������A��̒n�Ɂu�y���v���C���[�W����̂́A���̂Ƃ��̑̌��ɂ����̂ł��B �@�|�[���E�S�[�M�����͂P�W�X�P�N�U���A�^�q�`�ɓ������܂��B�S�R�̂Ƃ��ł��B�X�R�N�Ɉ�x�t�����X�A��܂����A�X�T�N�Ăу^�q�`�ւƖ߂�܂��B�P�X�O�P�N�X���Ƀ^�q�`����X�Ɂu���J�v�̒n�}���L�[�Y�����Ɉڂ�A�O�R�N�ɂT�T�ŖS���Ȃ�܂ł��̒n�ɏZ�ݑ����܂����B �@�^�q�`�ł̍ŏ��̍ȃe�n�b�A�}�i�����f���ɕ`�����̂��w�}�i�I�E�g�D�p�p�E(���삪�݂Ă���j�x�B���ł������ɂȂ����n�b�A�}�i���g�D�p�p�E(����j�ɋ����Ă���B���[���b�p���Ȃ����Ă��܂������z�I�Ȍo���ɁA�S�[�M�����͋����ɐk���܂��B �@�w�p�y�E���G�i�_��̐��j�x�B���̏��N�ƒ����̑f�ނ�T���ɁA�R�ɓ����Ă����܂��B�₽�����̒��ɓ���A���N���g�̂��Ă��܂��B�u�ɐF�̋�ԁA���̂���������Ȃ��A��������̂͊�ɓ����邹���炬�̉������ŁA�Î�ƈ��炩���A��������A�����͂܂������n��̊y���ɂ������Ȃ��ƃ|�[���Ɏv�킹���B�܂�����y�j�X���d���Ȃ��āA���ĂȂ��قǂ̗~�]�ɋC�������Ȃ肻���������v�B�S�[�M�����́A�}�t�[�i������L�ҁj�ɁA�̑�Ȉً������Ȃ�ł͂̎��R���������܂��B���҃o���K�X�E�����T�̃z���E�Z�N�V�����ȃV�[���́A�����ł��������B �S�[�M�����͎咣���܂��B�u���p�́A���̔����ϐ��̎�ꂽ�j���Ƃ����M���V���l�ɂ���č��o���ꂽ���m�̔��̌��^����A�s�ύt�Ŕ�Ώ́A���n�����̑�_�Ȕ��ӎ��̉��l�ςɎ���đ�����ׂ��ŁA���[���b�p�ɔ�ׂ�ƌ��n���������̔��̌��^�́A���Ƒn�I�ő��l���ɕx��ł����ΎG�ł���B�E�E�E ���n�|�p�ł́A���p�͏@���Ƃ͐藣�����Ƃ͂ł����A�H�ׂ邱�Ƃ���邱�ƁA�̂����ƁA�Z�b�N�X�����邱�ƂƓ��l�ɁA���퐶���̈ꕔ���`�����Ă���v�ƁB
�@�Ӗڂ̘V�k�̃G�s�\�[�h�́A�S�[�M�����̗������ꏊ���������āA�����[���B�S�[�M�������g���A�ɓx�Ɏ��͂𐊂������Ă��܂��B�{����g�ɂ܂Ƃ����V�k���A�ǂ�����Ƃ��Ȃ������܂��B��ō��E�����킵���@���Ȃ���A�S�[�M�����̂��Ƃɂ��܂����B
�u�|�[���������J���O�ɘV�k�͔ނ̋C�z�������Ď���グ�A�|�[���̗��̋��ɂ�������B�V�k�͂������Ɨ��r�A�����A�`�ւƎ�ł������Ă������B���ꂩ��|�[���̃p���I���J���āA�����ȂŁA�Ίۂƃy�j�X�����B���������Ă��邩�̂悤�ɁA�ޏ��͂��܂܍l���Ă����B ���ꂩ��\���܂点��ƁA�ޏ��͋������������ɋ��B�u�|�p�A���v�E�E�E
�}�I���̐l�X�̓��[���b�p�l�̒j�������ĂԂ̂������B�v �|���l�V�A�Ɂu�y���v���Ă����S�[�M�����́A���܂̏�ʂł��B�Z�b�N�X�ɂ���Č��n�ɃA�v���[�`���A�����ăZ�b�N�X�ɂ���Č��n������܂���S�[�M�����B�P�X�O�R�N�A�Ђǂ����L��Y�킹�Ȃ���A����ł����܂����B �����āA�ł����������R���������J�g���b�N�i���̌��߂��ꏊ�ɖ�������܂����B �����Ƃ��Ă̎i���̎莆�ɂ́A���̂悤�ɏ�����Ă��܂����B �u���̓��ɂ����čŋ߁A�L���ɑ��邱�Ƃ͂ЂƂA�|�[���E�S�[�M�����Ƃ����j�̓ˑR�̎������A�ނ͕]�������|�p�Ƃł��������_�̓G�ł���A�����Ă��̒n�ɂ�����i�ʂ�����̂��Ƃ��Ƃ��̓G�ł������v
http://minoma.moe-nifty.com/hope/2008/01/post_937b.html
�S�[�M�����W�@���������ߑ���p�فB
�@�W���͉���Ղ��N�㏇�ɁA�t�s�T�����܂߂���۔h�̉e���������ɂ����������̐��_����n�܂�B1886�N�̃u���^�[�j���؍݈ȍ~�A����Ɂu�S�[�M�����炵���v�G�ɂȂ��Ă����A������91�N�̃^�q�`�s���ƂȂ�B
�@�����āA�A��ʼn�u�m�A�m�A�v�i1893�|94�j�B�A����A�^�q�`�̊G�̕]���������������߁A�܂��^�q�`�̐�`�����悤�Ɣ��\�������̂ł���B�Ō�̓^�q�`�ڏZ�i1895�j����}���L�[�Y�����ł̎��i1903�j�܂ŁA�u��X�͂ǂ����炫���̂��@��X�͉��҂��@��X�͂ǂ��֍s���̂��v�܂ł��܂�7�_�B �ȉ��Ɍf�ڂ����摜�̂����A�S�[�M�����̍�i�͂��ׂĂ��̓W����œW�����ꂽ���́B �w�j�̋��\���͂ǂ����痈�����x(���`���[�h�E�����K���^�f�C���E�s�[�^�[�\���A�O�c�o�ʼn�)�ł́A�u���z�̊y���v�Ƒ肷���͂ŁA��m�����ɓs���̂����u�y���v�����悤�Ƃ����l���Ƃ��ăS�[�M�����������Ă���B �@����ɂ��ƁA�S�[�M����(1848�|1903)�̓^�q�`���A�ق��̒j�Ɏז�����Ȃ��v���C�x�[�g�E�N���u�ł���A���^�ł���Ȃ�������������ɗ����鏭���⏗�����ň�ꂽ�u�y���v�Ƃ��ĕ`�����B���̊y���ɂ͒j�͈�l�������Ȃ������B ���̒j�͊y���̑n�ݎ҂ł���Ɠ����ɔ`����������҂ł�����A���I�Ȗ��͂̂���Ⴂ�������̎p�ɖ���ǂ��Ȃ���A���R�̒��̕��a�Ƃ����f�p�ȊϔO�������Ă����̂ł���B �@�����������̎~�ߏ����Ȃ��u�������v���Ă������ł̐����ɉ����ẮA��l�⓯���l�Ɛ₦���g���u�����N�����A���̑���ɂ͕s���R���Ȃ��������̂́A���a�������Ŏ���ɂ�����܂܂Ȃ�Ȃ��Ȃ��Ă����B
�@
�@�܁A�ǂ�Ȃ��̂ɂ���A���l�̌����͉L�ۂ݂ɂ��ׂ��ł͂Ȃ��A���Ȃ��Ƃ��S�[�M�����́u�����v�ɂ��ẮA�����K���ƃs�[�^�[�\���������قǒP���ł͂Ȃ��������낤�A�ƃS�[�M�����̊G�̎�����ڂ̓�����ɂ��Ďv���܂�����B �u��Ɓ��j�v�̎����ɂ��ẮA���傤�Ǎ������I��������̍u�`�Ńh���N����(�u�T���_�i�p�[���̎��v)�ƃA���O��(�u�g���R���C�v)�̂�����r���Ă���ꂽ�B �@�h���N�����̓T���_�i�p�[���Ɏ��ȓ��e����Ɠ����ɁA����Ȏ����ɑ��铩�����Ă���B �@����A�A���O���̎����͊G�̊O�ɂ���B�~���t���[���͔`�����ł���A�������͌����Ă��邱�ƂɋC�Â��Ă��Ȃ��B���̎��_�̈Ⴂ�́A���ꂼ��̐��i�̍��ɂ����邪�A�������`�������̔N��ɋ���Ƃ��낪�傫�����낤�B�h���N������29�A�A���O���́A�Ȃ��82�ł���B
1894�N�u�p���b�g�������摜�v�B
�@��������A�S�[�M�������ǂ�Ȋ�����Ă��̂�����m��Ȃ������̂ł������B�w���̐l�S�b�z�x�ł̓S�b�z�ɕ������J�[�N�E�_�O���X���A�悭���Ă邾���ɁA�Ȃ�[���R�X�v���݂������������A�S�[�M�������̃A���\�j�[�E�N�C�����A���\�����Ɠ����n��̊炾�����̂ˁB �@���摜����́A�������ӎ�����������B�S�[�M�����̋����͖��_�A�Ȃ̊�̑��`�₻����ǂ��`�����ł͂Ȃ��A���̓��ʂ�\�����邱�Ƃł���B
1892�N�u�����킵����n�v�B
�@�S�[�M�����̎��_�͉�ʂ̊O�ɂ���B���̓S�[�M�����ɁA��ʂ̊O�̒j�Ɏ����������Ă���B�ޏ��̓��ʂ͉M���Ȃ��B�����A�����̐�̒j�ɑ��ċ���������Ă���͖̂��炩���B�����܂ł��Ȃ��j�ɂƂ��ẮA���ꂾ���ŏ[���ł���B . 1890�|91�N�u�����̑r���v�B
�@���f���́A���j�q�ŃS�[�M�����̈��l�A�W�����G�b�g���Ƃ����B�D�P�������ޏ����̂ĂāA�S�[�M�����̓^�q�`�ւƔ��B�@���̃W�����G�b�g�̎��̂̂悤�ɑ���߂����̂ɔ�ׂ�A�u�����킵����n�v�̏��̂���́A�܂��ɉ����̂��Ƃ��P���B�����ȓ��̂̕\���ɁA�u���ʁv�͔����Ă��Ȃ��B�K�v�Ȃ��̂��B
1897�|98�N�A�gD'où venons-nous? Que Sommes-nous? Où allons-nous?�h
�@�����ꂽ��ʂ̉E���A�w����������l�̏��́A�A���O�����D��ŕ`���|�[�Y���v�킹��B���Y���č���A��ʂ̊O�̒j���M�������l�̏��̂�����O�̃|�[�Y�́A�}�l�́u����̒��H�v�Ɠ����ł���B���R�ł͂���܂��B �����āA��ʂ̊O���M������u�ٍ��̏������v�Ƃ������́A�h���N�����́u�A���W�F�̏������v�Ƌ��ʂł���B������͎Q�l�ɂ����Ƃ������A�������������Ύ����Ǝ��Ă���̂ł��낤�B �@���̂Ȃ��A��Ɛg�̂����̑��݁B���_�A�u�����鏗�v�̓��ʂ����Ƃ���Ȃ��̂́A�ނ��듖�R�ł���B���������l���Ă��悤�ƁA�u����j�v�ɂ͂ǂ��ł������B���������A�ނɑ��ċ���������Ă��邩�ۂ��A���炢�Ȃ��̂��B���L������̂����Ȃ��u�ٍ��̏��v�ł���Ȃ�A�Ȃ�����ł���B �@�Ƃ����A�킩��₷�����߂Ɏ��܂肫��Ȃ��̂��A�������̑��݂��B
1892�N�u�G�E�n���E�I�G�E�C�E�q�A(�ǂ��֍s���́H)�v
�@����������̃^�q�`�̕��i�̑����ɁA���̍������͓��荞��ł���B�S�[�M�����̕��g�ł���̂͊ԈႢ�Ȃ��B�@��ʂ̊O���珗�����߂�Ɠ����ɁA��ʂ̒��ɂ�����B�n�����̉��Ȃǂł͂Ȃ��A�������Ɛ����ł��Ȃ����肩�A�����̏ꍇ�A�ڂ݂�ꂳ�����Ȃ����݂Ƃ��Ăł���B �@�������Ȃ���̌����̒��A�`���������̂͊y���̖��������B�����̂��̂́A�s���̂����A���傤���Ȃ��ϑz���ƒf���Ă��܂����Ƃ��ł��邾�낤�B����ł����̍�i�́A������Ȃ��͋����B http://niqui.cocolog-nifty.com/blog/2009/07/index.html
�@���S�[�M�����͉��̃^�q�`���������̂��H�^���ۍD�ǁi���R���M�Ɓj��
�u�l�́A�S�[�M�����ŏ��߂ă^�q�`��m������ł��B�����ŁA�S�[�M�������A�����ɃC�J�����|�p�Ƃ������̂���b�������Ǝv���܂��B�͂����茾���Ă��̐l���o�C�I�t�����X����^�q�`�܂łȂ�āA�ނ��Ⴍ���ቓ����ł��B������10�T�ԁB70���ł���B����Ȃɉ����̂ɉ��̍s�����̂��H�@���́A�o���ɊW�������ł��B �S�[�M�����́A1�˂���7�˂܂Ńy���[�ɏZ�ނ��ƂɂȂ�A���l�̏��g��������{���{�������B�F�B�́A�����l�̏��̎q�B������J�M�����1�ł��B�q���̍��̌o���́A�̂��̐l�Ԍ`���ɉe������ƌ����܂�����B�ނ̃^�q�`�̌��̊�b�͓�Ẵy���[�ɂ���̂ł��B�������|�C���g�I �t�����X�ɖ߂�Ƌ������̂Ȃ����Q�Ȃ̂��邿����ƕς�����q���ŁA����߂Ȃ������B�`�����炪�I���ƁA�S�[�M�����͌��K�����v�ɁB�C�ւ̓��ꂪ����������ł��ˁB�ނ͉������߂Ă����̂��H�w�y���i�p���_�C�X�j�x�ł��B�ނɂƂ��āA�c������̃y���[�̐������܂��Ɋy����������ł��B�S�[�M�����́A�ꐶ���́w�y���x��T��������̂ł��c�v
http://www.peaceboat.org/cruise/report/32nd/apr/0420/index.shtml �킪���ł����Ƃ��L���ǂ܂�Ă���S�[�M�����̒���́A�^�q�`�I�s�u�m�A�E�m�A�v�ł��낤�B�������A����܂ł̗��z�{�́A�F�l�̏ے��h���l�V�������E���[���X���啝�Ɏ�����������̂��{�ɂ��Ă���A�I���W�i���ɂ���ׂ�Ɓq�͂邩�ɐ^�����̔����A�֒����ꂽ�r���̂ł������B �S�[�M�������M�̌��e���͂��߂Ė|���{���͏]���ʼn߂���Ă����^�̈Ӑ}�𖾂炩�ɂ��A�ނ̑f��������Ă����ł��낤�B�܂��A�����u�����g�A�h�K�A�Z�U���k�A�S�b�z�A���h���A�}�������A�����{�[���Ɋւ���v���o��G�b�Z�C�͂��̑n���I�Ȍ|�p�ƁE�v�z�Ƃ̓��ʂ����Ɠ����ɁA���͓I�ȍ�Ƙ_�Ƃ��Ȃ��Ă���B �q���͒P���ȁA�����P���Ȍ|�p������肽���Ȃ���ł��B���̂��߂ɂ́A����Ȃ����R�̒��Ŏ������������Ȃ�����ؐl�ɂ�����킸�A�ޓ��Ɠ����悤�ɐ����A�q��������悤�Ɍ��n�|�p�̏���i������āA���̒��ɂ���ϔO��\�����邱�Ƃ����ɂƂ߂Ȃ���Ȃ�܂���B����������i�������A�����ꂽ���̂ł���A�^���̂��̂Ȃ̂ł��r�i�^�q�`�ɔ��O�A1891�j �q���͖�ؐl�����A�������ؐl�̂܂܂ł�����肾�r�i���̒��O�j
http://www.msz.co.jp/book/detail/01521.html �w�S�[�M���� �I���B���x
���ؐl�̋L�^�@�_�j�G���E�Q�����ҁ^���J����� �m�����n �I���B���Ƃ́A�^�q�`��Łu��ؐl�v���Ӗ�����B�|�[���E�S�[�M������1895�N�̃T�����E�h�E���E�\�V�G�e�E�i�V���i���E�f�E�{�[�U�[���i�������p����W�j�ɏo�i���ċ��ۂ��ꂽ�A�ٗl�ȁA������L�̓��������̑薼�ł���B�{���̃J�o�[�ɗp�����Ă���̂́u�I���B���v�Ƒ肳�ꂽ���ʉ�ŁA���̂ق��{���̕\���ɂ́u�I���B���v�̖ؔʼn�̕����A���ɂ́u�I���B���v�̃u�����Y���̎ʐ^�����荞�܂�Ă���B �j�_�ɂ��ď��_�ł����邱�̖�Ȑ_�I���B���ɁA�S�[�M�����͎������Ȃ��炦�Ă����B�S�[�M�����̒���ɂ́A��ؐl�ɂȂ肽���Ƃ������C�g�E���e�B�[�t���A�����������߂��Ă���B �S�[�M�����́u�e��Ȑ��v�v�Ƃ��Đl�����n�߂��Ǝ����Ō����Ă���悤�ɁA���Ə��D�̑D���ł���C�R�̌R�͂̏�g���ŁA���������l�̐E���̂ĂĊG��ɖv�������B���������n�ŁA�������肵����������������=���M�ƃS�[�M�����ɂ́A�Ɗw�ҕ��ȂƂ���͏������Ȃ������B �����Ƃ��������ꂽ�����̔�������F�߂�A�D��ĕ��������ꂽ��ؐl�Ƃ����{���I��d���B�����Ĉ���A�I�Z�A�j�A�ւ̎��ȒǕ��̒��ɂ���A�P�ɕ�������̒E���ł͂Ȃ��A���J��ȊG��̎������߂čŌ�ɂ͕�����L���ɂ���Ƃ����|�p�ƂƂ��Ă̌v�Z�B�V�������z�����߂Ēn���̔��Α��ւƕ��������Ƃ́A�ނ����I�Ȗ����̒��ɂƂ����߂����A���̂悤�ȋ������Ƃ������Ƃ��Aꡂ��ޕ��̉ߋ��E���݂̕����𖾝��ɐ[�����f���邱�Ƃ̂ł��闧���ނɗ^�����B �S�[�M�����̎c�����ˑ�ȕ��͂̏W�����A���̂��ǂ낭�ׂ����҂́A���ƌ|�p���Ƃ炵�o���B ���͏\�Ɏ��ʂ��肾�����B�ŁA���ʑO�ɁA�������O���ɂ���������`�����Ǝv�����B�܂�Ђƌ��̊ԁA��������A���͂���܂łɂȂ���M�����߂Ďd���������B�����Ƃ��A����́A�s�����B�E�h�E�V�����@���k�̂悤�ɁA�����ʐ������A���ꂩ�牺�G�����A�Ƃ������ɂ��ĕ`�����G����Ȃ��B����f���Ȃ��ŁA���іڂ��炯�̂��炴�炵�������܂̃L�����o�X���g���āA��C�ɕ`�����B������A�������͂ƂĂ��e���ۂ��B�i�c�c�j ����́A�����ꃁ�[�g�����\�A���l���[�g���\�̊G���B�㕔�̗������N���[���E�C�G���[�œh��A���F�̎��ɕ`���ċ������܂����t���X�R��̂悤�ɁA����ɑ薼�A�E��ɏ��������Ă���B�E��̉��ɁA�����Ă���c���ƁA�������܂��Ă���O�l�̏��B��F�̒�����������l�̐l�Ԃ��A���ꂼ��̎v������荇���Ă���B���́A���������̉^���Ɏv�����������Ă����l���A�������ɂ������܂����l���\�\���ߖ@�����āA�킴�Ƒ傫���`���Ă���\�\���A�r�������A�������l�q�Œ��߂Ă���B �����̐l���́A�ʕ�����ł���A��l�̎q���̂������ɓ�C�̔L������B����ɔ������R�r�B�����́A�_��I�ɁA�����I�ɘr�������A�ފ݂����������Ă���悤�Ɍ�����B�������܂����l���́A�����̌��t�Ɏ���݂��Ă���炵���B�Ō�ɁA���ɋ߂���l�̘V�k���A�^��������A���߂Ă���悤�ɂ݂���B�c�c�ޏ��̑����ƂɁA�����łƂ���������H�̔����ٗl�Ȓ������邪�A����́A���t�̋�������킵�Ă���B�i�c�c�j ���[�}�܂̎���������p�w�Z�̊w���ɁA�u����͂ǂ����痈���̂��H�@����͉��҂Ȃ̂��H�@����͂ǂ��ւ䂭�̂��H�v�Ƃ�����ŊG��`���ƌ�������A�z��͂ǂ����邾�낤�H�@�������ɔ䂷�ׂ����̃e�[�}�������āA���͓N�w�I��i��`�����B�������̂��A�Ǝv���Ă���B�i�c�c�j
�i�F�l�̉�ƁE�D��胂���t���G���A1898�N2���A�^�q�`�A�{��200-201�y�[�W�j �����ɏ�����Ă���u���v�Ƃ͂ނ��A���̏t������{�����J�̎n�܂����s��X�͂ǂ����痈���̂��@��X�͉��҂��@��X�͂ǂ��֍s���̂��t�i�{�X�g�����p�ّ��j�̂��Ƃ��B�S�[�M�����̎���ɂ܂ł킽���Ă����Ƃ������ȗF�l�������_�j�G���E�h�E�����t���G�ֈ��Ăď����ꂽ�莆�̈�߂ł���B
http://www.msz.co.jp/news/topics/01521.html
�s�g�P�A�����̏o����
�@����P�V�W�X�N�A�t�����X�v�����u�������̂Ɠ����N�A�쑾���m��ɂ����Đ����̔������N�������B����ƂȂ����̂́A�C�M���X�C�R�̌R�́A�o�E���e�B���ł���B �@���q�C���t���b�`���[�E�N���X�`�����Ɏw�����ꂽ�������v�����͊͒��̃u���C���S���A�u���C�͊͒��h�Ɩڂ��ꂽ��g���ƂƂ��ɏ��^�̃{�[�g�ɏ悹����䩗m���鑾���m�ɕ���o���ꂽ�B�����҂����́A�u���C�����͎����낤�Ǝv�������낤���A�͒������͊�ՓI�ɏ��^�{�[�g�ł͂邩�R�V�O�O�}�C�����ꂽ�I�����_�̂̃C���h�l�V�A�܂ōq�C���邱�Ƃɐ��������B�������ꂽ�쑾���m��̂��ƂƂ͂����A�C�M���X�C�R�������҂��������̂܂܂ɂ��Ă����킯���Ȃ��B�ǎ肪�����������A�N���X�`�����ꖡ�̑{�����s��ꂽ�B�ǐՕ����̓o�E���e�B���̍q�C�̖ړI�n�ł������^�q�`���Ɏc���Ă�����g���������S�����邱�Ƃɂ͐����������i�����A�R�����i��Y�ƂȂ����j�A�o�E���e�B���ƂƂ��ɑ����m�ɏ������c��̎҂����̍s���͝��Ƃ��Ēm��Ȃ������B �@�o�E���e�B���Ɣ����҂̈�}�̍s�����킩�����̂́A���ꂩ���Q�O�N��̎��ł���B�A�����J�̕ߌ~�D���A���O�͕t���Ă��邪�㗤���ꂽ���Ƃ̂Ȃ����A�s�g�P�A�����ɗ���������Ƃ���A�o�E���e�B���̏�g���Ƃ��̎q�������������̂ł���B�N���X�`���������́A�^�q�`�̏����ƒj����A��Ĕ�������ɂ����s�g�P�A�����ɓ�������ł����B �@�������A�����҂����́A�����Ǝ��������œ��m�����������A�A�����J�̕ߌ~�D�ɔ������ꂽ���ɔ����̃����o�[�Ő����c���Ă����̂͐����̃W�����E�A�_���X��l�����ł������B�W�����E�A�_���X�͌h�i�ȃL���X�g���k�ƂȂ��Ă���A�s�g�P�A�����͔��l�ƃ^�q�`�����̍�������Ȃ���̃L���X�g���̓������ƂȂ��Ă����B �@���̌R�̓o�E���e�B���̔����͓��{�ł͂���قǒm���Ă��Ȃ����A���m�ł͂��Ȃ胁�W���[�Ȏ����ŁA�C�m�̎����Ƃ��Ă̓^�C�^�j�b�N���̑���ɕC�G����قǂ̒m���x���ւ�Ƃ����A���Ăł͑����̌����⏬��������A��O���牽�x���f�扻������Ă���B�܂��A�o�E���e�B���̕����D������Ă���Ƃ����B �@���āA���̃o�E���e�B���̎q�������͍��ł��s�g�P�A�����ɏZ��ł���̂����A�ߔN�A�Ăђ��ڂ��W�߂��B���܂薼�_�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B�s�g�P�A�����̒j���������A�P�Q����P�T�܂ł̏��������Ƃ̐��������I�ɍs���Ă������Ƃ��\�I���ꂽ�̂ł���B����͖q�̓I�ŁA�h�i�ȃL���X�g���k�����̏Z�ޓ��ł���A�Ƃ����s�g�P�A�����̃C���[�W�������Ȃ����̂ł���A�Y�������ɂ����W�����B���̌o�܂́A�C���^�[�l�b�g�̃t���[�S�Ȏ��T�́u�E�B�L�y�f�B�A�v�ɂ��ڂ����L�q����Ă���B �u�E�B�L�y�f�B�A�E�s�g�P�A�����̎����v(�p��j
�u�E�B�L�y�f�B�A�E�s�g�P�A�����̎����v(���{��j �@�s�g�P�A�����̒j�������̗i��Ƃ��āA�s�g�P�A�����Ɉڂ�Z�����҂����̓^�q�`�̏������ȂƂ��Ă���A���������̃^�q�`�̏K���͂��Ȃ萫�I�Ɏ��R�Ȃ��̂ł���������A���������̊�ōق��͍̂��ł͂Ȃ����A�Ƃ������̂�����B
�@�������ɁA�^�q�`�����[���b�p�l�ɔ������ꂽ�����̋L�^�ɂ��ƁA���Ȃ萫�I�Ɋ��e���������Ƃ����Ď���B �@�܂��t�����X�l�̋L�^�ɂ��ƁA
�@
�@�u�J�k�[�͏������ň�t�ł��������A�炩�����̖��͂ł́A���[���b�p�����̑命���ɂЂ�����炸�A�g�̂̔������ł́A�ޏ��炷�ׂĂɒ��荇���ď����Ƃ��ł���ł��낤�Ǝv��ꂽ�B�����̐��̐��̑啔���͗��������B�Ƃ����̂́A�ޏ���ɓ������Ă���j��V���������A�ޏ��炪�����͐g�ɂ܂Ƃ��Ă��鍘�z��E�����Ă��܂��Ă�������ł���B �ޏ���́A�͂��߁A�J�k�[�̒������X�ɛZ�Ԃ����������A�����ɂ́A�ޏ���̑f�p���ɂ�������炸�A���������̒p���炢�����Ď�ꂽ�B���邢�́A���R���A�ǂ��ł��A���̐��܂�Ȃ���̉��a���ł����������Ă���̂ł��낤���B���邢�͂܂��A�Ȃ���������̏��p�����x�z���Ă���n���ɂ����Ă��A�����͂����Ƃ��]��ł��邱�Ƃ�]�܂ʂ悤�Ɍ�������̂��낤���B �j�����́A�����ƒP���A���邢�͂���_�ŁA�₪�āA�͂�����ƌ��ɏo�����B�ނ�́A��X�ɁA��l�̏�����I�сA�ޏ��ɂ��ė��ɍs���悤�ɔ������B�����āA�ނ�̌���̗]�n�̂Ȃ��g�Ԃ�́A�ޏ���Ƃǂ̂悤�ɕt�����������̂��͂����莦���Ă����B�i�R�{�E�����w�u�[�J�����B���@���E���V�L�x�i��g���X�@�P�X�X�O�N�j�P�X�Q�|�R�Łj�v
�@
�@�܂��A�L���ȃC�M���X�l�̃L���v�e���E�N�b�N�́A�^�q�`�̎Ⴂ�����������ȃ_���X��x��i�N�b�N�͖������Ă��Ȃ����A�I���ɃZ�b�N�X���������̂������炵���j�A�j�����@���W�c�̂悤�Ȃ��̂��`�����āA�������J��Ԃ�������A�q�������܂��ƎE���K���̂��邱�Ƃ������ꂽ���ɋL�^���Ă���i�����̃C�M���X�����Ď̂Ďq�̏K���͉��s���Ă����̂�����A���܂�傫�Ȃ��Ƃ͌����Ȃ��悤�Ɏv�����j�B �@���̂悤�ȃ��[���b�p�l�̋L�^���������̃^�q�`�̐��K���ɂ��āA����̒�������^�q�`�̃z�X�s�^���e�B�̏K��������������̂ł͂Ȃ����Ƃ��錤���҂����邪�A�^�q�`�͂��̌ト�[���b�p�Ɏx�z����A�L���X�g���̊������A���[���b�p�̏K���̉e�����ɂ������̂�����A���ォ��ސ�����̂͑Ó��ł͂Ȃ��B �@���āA�����̃^�q�`�����I�ɕ��c�Ȗʂ��������Ƃ��āA���ꂪ�����炢�̏�������ΏۂɂȂ����̂��낤���B �@�N�b�N�ɂ��ƁA�^�q�`�ɂ͎q�����ߕ����قƂ�ǐg�ɕt���Ȃ��K�������邪�A���q�̏ꍇ�͂R�A�S�܂ł��Ƃ������Ƃł���B����ɂ��ƁA���̎q�͂��Ȃ葁���i�K�Łu�q���v�łȂ��Ȃ�悤�ł���B����ɁA�x�z�҂̗�ł��邪�A�X�Ō��������Ƃ������Ƃ�����B��Ƃ̃S�[�M�������^�q�`�ɂ���Ă��āA���n�ʼn��l���̈��l������A�q���܂ō�������Ƃ͗L���ł��邪�A����ƂȂ����^�q�`�l�̏����݂͂�ȂP�R����P�S�ł���B������A�����̃^�q�`�ł́A���Ȃ�Ⴂ�N��ŏ����͑�l�Ƃ݂Ȃ���Ă������Ƃ��킩��B �@�ƁA�����܂ł͊����ɒm��ꂽ�^�q�`�̐��K���ł���B�ł́A��������̓����ҁA�P�W���I���̃C�M���X�͂ǂ��������̂��낤�B �@�P�W���I�̃C�M���X�́A�����Ƃ��Ă͒������A�Ӎ��̐��E�ł��������Ƃ��m���Ă���B�j�q�̏ꍇ�͓�\��㔼�A���q�̏ꍇ�ł���\�܍Έȏ�Ō����A�Ƃ����̂����ʂł������炵���B�قƂ�nj���ƕς��Ȃ����炢�̌����N��ł���B�����A�Ӎ��ł��鎖��͌���Ƃ͂����Ԃ�Ⴄ�B�����̕���l���x��A�����������ێ����邽�߂̌o�ϗ͂����邱�Ƃ�������߂ɁA��ނ��������x��Ă����Ƃ����̂�����炵���B�M����W�F���g���}���ɐ��܂�Ă��A���j�łȂ��Ɠ����悤�ȋ����ł������B �@���ʁA���C����Ȏ�҂������v�t������P�O�N�ȏ�Ɛg������]�V�Ȃ��������邱�ƂɂȂ�B�ߑ�̃C�M���X�̐��͂̊g��́A����烊�r�h�[�����ė]�����N�����̃G�l���M�[�ɂ���Ă����炳�ꂽ�Ƃ��錩��������قǂ��B �@���ϓI�Ȍ����N��͂Ƃ������Ƃ��āA���ۂɂ͂ǂ̂��炢�̔N��̏����Ȃ�Γ����̃C�M���X�l�j���͐��̑ΏۂƂ��Ă݂Ă����̂ł��낤���B �@����͂��Ȃ�Ⴉ�����A�Ɛ��肷�邱�Ƃ��ł���B�܂��A���͑����Ȃ����A�\��O���̏����ƌ������Ă���Ⴊ��������B���ɁA�����̒j�����Ȃ��Ȃ������ł��Ȃ������̂�����A���~�̂͂����Ƃ��Ĕ��t�w�̏������ɐ����邱�ƂɂȂ�̂����A���t�w�����͂��Ȃ�Ⴂ�N���q������Ă������Ƃ��킩���Ă���B �@�u��ɂ��q�ׂ��Ƃ���A���t�w�̒��ɂ͔N�[�������ʎႢ�q�����邱�Ƃ���������A�\�ɂ������Ȃ��q�����邱�Ƃ����������B�y�i���g�́A�u���C�g���F���č��Ō��������Ƃ��������������t�w�̈�c�ɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ���B �@�@�u�i�����j��\�l�قǂ̎Ⴂ���������A�ŔN���ł��\�Z�����A�����͓V�g�̂悤�Ȕ�������������Ȃ���A�V�g�̂悤�ȕ\��͂��ׂĎ����A�����܂����A������ȕ����̊�������Ă����̂��B�i�㗪�j�v�i���`���[�h�E�q�E�V���E�H�[�c���@�ʈ�E�]����w�\�����I�@�����h���̓��퐶���x�i�����Џo�Ł@�P�X�X�O�N�j�P�P�Q�|�R�Łj�v �@�܂�A�^�q�`�����łȂ��C�M���X�ł��A�����͂��Ȃ�c����������l�⌋������ɂȂ肦���킯�ł���B �@�����̐����Ƃ����͎̂Љ�I�Ȑg�����Ⴍ�A�č��ɍs�����͑D�ɏ��A�Ƃ����荇���܂ł����Ƃ����B�ނ�́A���Ƃ��C�M���X�ɖ߂����Ƃ��Ă����������邱�Ƃ͗e�Ղł͂Ȃ��A���ɂł����Ƃ��Ă��ɕn�̂Ȃ��Ő������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ͖ڂɌ����Ă����B �@���ꂪ�A�^�q�`�ɗ��Č���ƁA�{���͌�������ɂ������\��̏��������āA���������y�ł���B���̂܂܂����Ɏc�肽���A�Ǝv���Ă��s�v�c�͂Ȃ��B���ہA�^�q�`�ւ̍q�C�ł́A�����̒E���Ƃ����̂͂悭�������B����Ő��������ɓ���I�Ȋ�����������A�����ɂȂ�̂͂���Ӗ��ł͕K�R�ł������B �@�͒��̃u���C�͔����̌����ɂ��āA �u�킽���͂����A�����҂ǂ����^�q�`�l�̂Ƃ���ŃC�M���X����������炵���ł��邾�낤�Ɗm�M���A���ꂪ���������Ƃ̊W�ɂނ��т��āA�S�̂̍s���̊�{�I�ȓ��@�ƂȂ����ɂ������Ȃ��Ɛ�������݂̂ł���B �iI can only conjecture that the mutineers had assured themselves of a more happy life among the Otaheiteans , than they could possibly have in England; which, joined to some female connections, have most probably been the principle cause of the whole transaction.�j(William Bligh & Edward Christian The Bounty Mutiny�i�Q�O�O�P�j11.)�v�Ə����Ă���B �@�s�g�P�A�����ɂ́A�P�W���I�̃^�q�`�����łȂ��A������̃C�M���X�̃����^���e�B�[���ۑ�����Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B�������Ƃ���A����̎����̓^�C���}�V���ʼnߋ��֍s���āA��c���ق����悤�Ȃ��̂ł���B
http://www006.upp.so-net.ne.jp/handa-m/tosho/arekore/50.htm �^�q�`�����[���b�p�l�ɔ������ꂽ�����̋L�^�ɂ��ƁA���Ȃ萫�I�Ɋ��e���������Ƃ����Ď���B �@�܂��t�����X�l�̋L�^�ɂ��ƁA
�@
�@�u�J�k�[�͏������ň�t�ł��������A�炩�����̖��͂ł́A���[���b�p�����̑命���ɂЂ�����炸�A�g�̂̔������ł́A�ޏ��炷�ׂĂɒ��荇���ď����Ƃ��ł���ł��낤�Ǝv��ꂽ�B�����̐��̐��̑啔���͗��������B�Ƃ����̂́A�ޏ���ɓ������Ă���j��V���������A�ޏ��炪�����͐g�ɂ܂Ƃ��Ă��鍘�z��E�����Ă��܂��Ă�������ł���B �ޏ���́A�͂��߁A�J�k�[�̒������X�ɛZ�Ԃ����������A�����ɂ́A�ޏ���̑f�p���ɂ�������炸�A���������̒p���炢�����Ď�ꂽ�B���邢�́A���R���A�ǂ��ł��A���̐��܂�Ȃ���̉��a���ł����������Ă���̂ł��낤���B���邢�͂܂��A�Ȃ���������̏��p�����x�z���Ă���n���ɂ����Ă��A�����͂����Ƃ��]��ł��邱�Ƃ�]�܂ʂ悤�Ɍ�������̂��낤���B�j�����́A�����ƒP���A���邢�͂���_�ŁA�₪�āA�͂�����ƌ��ɏo�����B�ނ�́A��X�ɁA��l�̏�����I�сA�ޏ��ɂ��ė��ɍs���悤�ɔ������B�����āA�ނ�̌���̗]�n�̂Ȃ��g�Ԃ�́A�ޏ���Ƃǂ̂悤�ɕt�����������̂��͂����莦���Ă����B
�i�R�{�E�����w�u�[�J�����B���@���E���V�L�x�i��g���X�@�P�X�X�O�N�j�P�X�Q�|�R�Łj�v
�@
�@�L���v�e���E�N�b�N�́A�^�q�`�̎Ⴂ�����������ȃ_���X��x��i�N�b�N�͖������Ă��Ȃ����A�I���ɃZ�b�N�X���������̂������炵���j�A�j�����@���W�c�̂悤�Ȃ��̂��`�����āA�������J��Ԃ�������A�q�������܂��ƎE���K���̂��邱�Ƃ������ꂽ���ɋL�^���Ă���i�����̃C�M���X�����Ď̂Ďq�̏K���͉��s���Ă����̂�����A���܂�傫�Ȃ��Ƃ͌����Ȃ��悤�Ɏv�����j�B
�@���̂悤�ȃ��[���b�p�l�̋L�^���������̃^�q�`�̐��K���ɂ��āA����̒�������^�q�`�̃z�X�s�^���e�B�̏K��������������̂ł͂Ȃ����Ƃ��錤���҂����邪�A�^�q�`�͂��̌ト�[���b�p�Ɏx�z����A�L���X�g���̊������A���[���b�p�̏K���̉e�����ɂ������̂�����A���ォ��ސ�����̂͑Ó��ł͂Ȃ��B �@���āA�����̃^�q�`�����I�ɕ��c�Ȗʂ��������Ƃ��āA���ꂪ�����炢�̏�������ΏۂɂȂ����̂��낤���B �@�N�b�N�ɂ��ƁA�^�q�`�ɂ͎q�����ߕ����قƂ�ǐg�ɕt���Ȃ��K�������邪�A���q�̏ꍇ�͂R�A�S�܂ł��Ƃ������Ƃł���B����ɂ��ƁA���̎q�͂��Ȃ葁���i�K�Łu�q���v�łȂ��Ȃ�悤�ł���B����ɁA�x�z�҂̗�ł��邪�A�X�Ō��������Ƃ������Ƃ�����B��Ƃ̃S�[�M�������^�q�`�ɂ���Ă��āA���n�ʼn��l���̈��l������A�q���܂ō�������Ƃ͗L���ł��邪�A����ƂȂ����^�q�`�l�̏����݂͂�ȂP�R����P�S�ł���B������A�����̃^�q�`�ł́A���Ȃ�Ⴂ�N��ŏ����͑�l�Ƃ݂Ȃ���Ă������Ƃ��킩��B
http://www006.upp.so-net.ne.jp/handa-m/tosho/arekore/50.htm
���ɂ�SEX�@�|���l�V�A���@�Z�b�N�X
�|���l�V�A���@�Z�b�N�X�Ƃ͓쑾���m�����ɕ�炷�|���l�V�A�̐l�X�̊Ԃɓ`���Z�b�N�X�̉��`���w���B �|���l�V�A�^�M���V����u�����̓��X�v�ƌ����Ӗ��̃|���l�V�A�̓n���C�����A�j���[�W�[�����h�A�C�[�X�^�[�������ԂP�ӂ���8000�L���̎O�p�̓����̓��X�A�C�[�X�^�[���������B�~�N���l�V�A�͑����m�������̏����Q�ŁA�J�����������A�}�[�V���������Ȃǂ�����
�u�G���X�Ɛ��C�v
����͒j����ʂ̗͂��֎�����悤�ȃA�N���o�b�g�Ȑ��Z�ł͂Ȃ��A�������Ƃ������Ԃ̒��ł��݂��̖��̐����Ȃ���s���Â��Ȉ��̌`�ł��B ���ۂɌ�������Z�b�N�X�͕��ʁA�T����1�x�A���S���͂�������ƕ��������āA���𖧒������Ė���A����̐ڐG�͂��Ȃ��B�Z�b�N�X�����鎞�́A�O�Y����i�∤���ɍŒ�1���Ԃ�������B�݂��̐S�Ƒ̂��Ȃ����ɏ����̒��ɑ}��������́A�Œ�30���͓������ɂ����ƕ��������Ă���B��������Ƃ��́A�O�Y�ƈ��������Ȃ��Ƃ��P���ԍs���A�ڕ������i����������B�}�������̂��́A�j���͍Œ�R�O���͐g�����������������āA���ꂩ��O��^�����n�߂�B �I���K�X�����������̂����A�����Ԑ���������������܂ܕ��������Ă���B�R�T���قǂ��̕��i�𑱂��Ă���ƁA�S�g�ɂ����ăI���K�X���̉����̔g�����X�Ɖ�����Ă���̂��������߂邱�Ƃ��낤�B���Ȃ����j���ł���A�ː������Ȃ��܂ܑ���ƈ�̂ɂȂ��đS�g���ˑR�����g�̂悤�ɐk���邾�낤�B�����Ȃ�A�̂𗣂����ɐk���v�����A�k�����̂��̂ɂȂ�ׂ����B���̎��A2�l�̑̂̃G�l���M�[�����S�ɗZ�����Ă�����������ł��낤�B �j���ɖu�N�͂��Ȃ��Ȃ�悤�Ȋ����ɂȂ������A�����ɐ������Ȃ��Ȃ�Ƃ��A���̂Ƃ������������K�v�ɂȂ�B���̏ꍇ�ł��A�����̔g�͔��ɍ������ɂ����u���Ă����A�������A���_�܂ŏ��点�ăI���K�X���Ƃ��Ĕ���������̂ł͂Ȃ��A�S�������₩�ɂ��ăG�l���M�[�̂Ȃ��ɐg���܂�����̂ł���B�܂�A�}����Ɉނ��Ă��܂������ɂȂ������A�����h���ׂ̂݁A���������Ă������Ƃ������Ƃ��B�������A���̂܂ܓ����ɖv������̂ł͂Ȃ��A�ː��ɒB����O�ɍĂѓ������~�߂āA���i�𑱂�B �j���̓x�b�g�ɂ��ꂼ��y�Ȋ����ɐQ��B�Q�l�̏㔼�g�͗����Ă����A���Ղ̕����͂����������B�����͋����ɂȂ�A�j���͑̂̉E�����x�b�g�ɂ��Đg���N�����B���͂��݂̑̂ɂ���܂���B�j���͍����͏����̑��̊ԂɊ����ē���A�����̍����͒j���̍��̍��ɏ悹��B�݂��ɑ���̕��S�������邱�ƂȂ��A���낰��p���ł���Ƃ����d�v���ƌ����B�������āA�g���������ɂR�O���ԉ��ɂȂ��Ă���ƁA2�l�̊ԂɃG�l���M�[�������̂�������悤�ɂȂ�ƌ����B
http://rena-i.jp/porisex.htm �u�S�[�M�����v
�쑾���m�A�t�����X�̃|���l�V�A�B �^�q�`�B �Ƃ���z�e���̂T�̊ȒP�Ȍ��܂莖�B �P�A������蓮���Ȃ����B
�Q�A�C�����������b�N�X�����Ȃ����B
�R�A�Ƃɒu���Ă����y�b�g�̂��Ƃ͖Y��Ȃ����B
�S�A�������b���Y��Ȃ����B
�T�A�o�^�[�̒l�i���l����Ȃ�Ă����Ă̂ق��B ���̓��ł́A������������N���A
��������������H�ׁA
�����Ȃ����疰��̂ł��B �������Ȃ��ŁA�����{�[�b�ƊC�߂ĉ߂����B
���ꂪ�A��Ԃ��ґ�B �����̈ꖇ�́A����ȃ^�q�`�ŕ`����܂����B
�Ƃ����Ă��A������̂̓A�����J�ł����E�E�E�B �ꏊ�͐�̃j���[���[�N�B�A
�I���u���C�h�E�m�b�N�X�E�A�[�g�M�������[�B ��l�̎��P�Ƃɂ���ďW�߂�ꂽ����̐��X�E�E�E�B
�ł��A���ړ��Ă͂��̐�B�}���ł͂����܂���A�������ƁB
�����A���̊G���u�����̈ꖇ�v�ł��B �u�}�i�I�E�g�D�p�p�E�v �|�[���E�S�[�M�����̍�i�B ���̃|�[���E�S�[�M�����́A
�^�q�`�Ƃ����Ζ��O������������۔h�̋����B �Z�U���k���w�сA�W���|�j�Y���ɑ����������j��ƁB �S�b�z�Ƃ̋��������ł��A����̋������猖�ܕʂ�B
�����Ƃ킪�܂܂��|�p�̗ƂƂ����|�[���E�S�[�M�����B
�p���Ɏ��]���A����Ă����̂��^�q�`�B
���߂����͉̂���̂Ȃ����n�B �����āA�^�q�`�̏��������`�[�t�Ƃ���
�������̊G�̂ł��B
����ȐF�ʂƑ�_�ȍ\�}�B
�S�[�M�����̃^�q�`�B ����ȍ�i�̂Ȃ��ŁA�ٍʂ�����Ă���̂��A
���́u�}�i�I�E�g�D�p�p�E�v�ł��B �傫�����J���ꂽ�����̖ځB
����t���������B
�w��ɂ������܂�s�C���ȉe�́H �S�[�M��������C�̊y���Ō��������n�Ƃ́A�����������������̂��B ���17�x�A���o149�x�B
1�N�Ԃ̕��ϋC����25�x�O��B
�^�q�`�͍��ł��悭�A��C�̊y���ƌĂ�Ă��܂��B �p�y�[�e�̓^�q�`��K�ꂽ�l���K���������t�����X�̃|���l�V�A�B��̓s��B �S�[�M�������A���n�̃^�q�`��K�ꂽ�̂�1891�N�A43�˂̂Ƃ��B
�t�����X�̍`���o�Ă������2�����̑D���ł����B
�����A�p�y�[�e�̐l���͂��悻3000�l�B
���̈ꊄ�ɂ������Ȃ��t�����X�l���A�^�q�`�̐����A�o�ς��d���Ă��܂����B
���̒��_�ɌN�Ղ���̂��A�t�����X�{������C�����ꂽ���ł��B
�����̓J���u�C�o�g�̃��J�X�J�[�h�Ƃ����j�B ���� �u�^�q�`�ɂ����S�[�M���������ɉ�ɗ����B
���͉����ނ��}�����B �悤�����S�[�M�����N�A���̃��J�X�J�[�h���B���肽�܂��B
���̃p�y�[�e�ɂ͋����a�@�A�J�t�F�[�܂ő����Ă���B
���̎����̒����B
�p�����痈���N�ł����邱�Ƃ͂Ȃ���B
���������A�|�p���g�̌N�ɂ��ЁA�ё����`���Ă��炢�����Ƃ������̂����邻�����B
�܂��͂����G��`���Ă��ꂽ�܂��B ����A�����s���ł�����̂��ˁH�v �S�[�M�����́A�b�̓r���ŐȂ𗧂��Ă��܂����B ���������A�����C�ɂ���Ȃ��Ƃ����̂��B �p�y�[�e�̊X�p�ŁA�S�[�M�������������́B
����̓p���Ɠ��������A�����č����̓����B
���������߂����n�̊y���́A�����ɂ͂Ȃ������̂ł��B
���]�A�����Ă��ݏグ��{��Ɏ�������B ���������̔��[��2�N�O�B
�p���ł̓G�b�t�F�����������B
����������J����܂����B �S���x�z����V���������̖��J���B
�������A�S�[�M�������䂩�ꂽ�̂́A�����ɊJ�݂���Ă����A���n�p�r���I���ł����B
���m�̐_��A�|���l�V�A�̌��n�I�ȍr�X���������B
�p���̕����Љ�ŕ�炷�S�[�M�����B
�ނ̖ڂɁA����͒n��̊y���Ɍ����܂����B �����ŃS�[�M�����͍l���܂����B
�u�Ȃ�Ƃ��Ă��^�q�`�֍s�����v�ƁB
������R�l�𗘗p���A�C���킽�낤�Ƃ��܂��B
���������炸�A�G�����R�ɕ`����n�ʁE�E�E
���ꂪ�|�p���g�Ƃ����t�����X�{�������������������B
�S�[�M�������p���Ŏv���`�����n��̊y���A�^�q�`�B
�����ł͐̂���̐l�X�͌��n�̐_�X�𐒂߁A�Ƃ��ɕ�炵�Ă��܂����B
���ׂĂ̕��A���ׂĂ̌��ۂɐ_���h��A�����l�����Ă����̂ł��B
�_�b�Ɠ`���̍��A�|���l�V�A�E�E�E�B
�������A�S�[�M�������K�ꂽ���͂��͂�ߋ��̘b�B
�����ɂ���ČÂ��M�͎̂Ă��A�_���J��Ւd�����łɔp�ЂƉ����Ă����̂ł��B �|���l�V�A�E�_���X�B
�̂ŕ\�����錴�n�̌��t�B
���낤���Đl�X�̐S�Ɏp����Ă����^�q�`�̐_��B ����́A�L���Ȏ�����肢�A�_�ɋF��_���X�B
�킢�̑O�ɗx��A�_�ւ̐��������Ă�_���X�B
�����Ɏx�z���ꂽ�^�q�`�A�����Ɏc���ꂽ���n�̑����B ����
�u���̂��A�S�[�M���������A�ɂ�����B �Ђǂ��ł��̂߂���Ă���悤���������A�p�y�[�e���o��Ƃ����B ���[���b�p���牓�����肽���Ƃ��A���n�I�ʼn���̂Ȃ����Z���ƈꏏ�ɕ�炷�Ƃ������Ă��B �ق�Ƃ��ɁA�p�y�[�e���o�Č|�p�������ł���ƍl���Ă���̂��H �܂������B�����ɋA���Ă��邳�B�v
http://www.geocities.jp/mooncalfss/manao/manao1.htm �����n�̃C���� �p�y�[�e��A�S�[�M������������������̓}�^�C�G�A�B
���̔��Α��A���40�L���قǍs�����C�ӂ̑��B �����Ŕނ��������̂́E�E�E �f�p�Ō��n�I�ȕ�炵�B
�����ŗ͋����l�X�B
�z���ɐ����鏗�����B ���[���b�p�I���̊�ɂ͓��Ă͂܂�Ȃ����̂����B
�������A�S�[�M�����͂����Ɍ��n�̔��������̂ł��B
�p�y�[�e�ł͌����Č����Ȃ������A������̔������B �C�A�E�I���i�E�}���A�B �^�q�`�̐���q���B ���Ă�����͖̂����ߑ��̃p���I�B
�������肵���^�q�`�̐���}���A�B
�����Ċ��F�̃C�G�X�E�L���X�g�B ����q���̉��ɕ`���ꂽ�͕̂����k�̃|�[�Y�������^�q�`�̏��ƁA �Ɖ��F�̗����������V�g�B �C�A�E�I���i�E�E�E����̓^�q�`�̏o��̈��A�B ���ْ�
�u�S�[�M�����̐F�g���͂ƂĂ��N�₩�ŁA�قƂ�nj��F���������������F�� �ŕ`����Ă��܂��B
�����āA�^�q�`�̌����ӂ�Ɏ�����܂����B
���̌��̓|���l�V�A�̐l�X�ɑ��鈤��ƁA���h�̋C��������`���ꂽ��ł��B�v ���n�̊y���A�}�^�C�G�A�B �l�X�͐_����A���R�ƂƂ��ɐ�����B
�������Ȃ��Ă����A�����l���Ȃ��Ă����A�S�[�M�����A�����̂ЂƎ��B �}�^�C�G�A�̐l�X�ɂӂ�A�S�[�M�������������̂́A���������߂Â��Ă������n�̃^�q�`�B �n��ӗ~���������Ă���S�[�M�����A�ڎw�����̂̓V���v���Ȍ|�p�B �ׂ����Z�@���̂āA���������������Ƃ����������炩�ɕ`���B ���̂��߂ɂ́A���Z���Ƃ����t�������A���n�̐S�Ō��邱�ƁB
���ꂪ�^�̌|�p�ւ��ǂ蒅�����A�����l���Ă��܂����B �������A���̊G�͂قƂ�ǔ���܂���B
����
�u�Ԃ�����物�F�����B�Ђǂ��F�g���� ���ꂶ�ᔄ��Ȃ��ē��R���B �������A���̊G�͂ǂ����Ⴄ�ȁE�E�E�B�v
���n�̑��}�^�C�G�A�ł��A�������瓦��邱�Ƃ͂ł��܂���ł����B
�D�݂̐H���i��G�̋����̂̓p�y�[�e�����B
���E�E�E�����l�̃S�[�M�����ɕK�v�Ȃ̂͌o�ϓI�ȗ��Â��������̂ł��B
�G���Ă����l�����Ȃ��^�q�`�E�E�E
�҂��Ă����͕̂n���B �����ŁA�S�[�M�����͑��̂��ƂցB
�����Ə����ȓ��̖�l�ɂ��Ă��炨���B
��������A���ƐV�����G�̃��`�[�t�A��������ɓ���ƍl�����̂ł��B ����
�u����Ȃ킪�܂܂�b�A�ʗp����킯���Ȃ��B �t���A�����~�����H ���̖�l�ɍ̗p���낾�ƁH
��k����Ȃ��A�������炯����Ȃ���
�S�[�M�����̋��߂Ă���̂́A���n�̐����ł͂Ȃ������̂��I
�Ȃ�Ę����ŁA�g����Ȃ���I�v ���ɗ₽�����ꂽ�S�[�M�����́A�����̐g�����I�ɏグ�A�q�����݂����R�ɂł܂��B ��������Ƃ́A���h��B
�������Ɍ����āA�ɗ�ɂ��炩�����̂ł��B ����͌��n�ɖ|�M����镶���l�̈���ł�����܂����B �n���̂��߁A�G��`���ӗ~���������S�[�M�����́A�C���]�������˂āA�T�����s�ɏo�����܂��B �s����͓��̓����A��������ł������y�n�B
�₪�ăS�[�M�����̍s����Ɍ��ꂽ�̂́A�R�����̏����ȑ��ł����B
���̈ꌬ�Ő����������܂��B ���l�͐_�̎g���A�����M���鑺�l�͎����̖����ȂɂƊ��߂�̂ł��B
�����āA�^���̏o��B �u�}�i�I�E�g�D�p�p�E�v�ɕ`���ꂽ�����B �����̖��̓e�n�A�}�i�B���̃e�t���A13�B
�^�q�`�łł��������n�̃C���B �e�t���Ɉ�ڂō��ꂽ�S�[�M�����B
�ނ͂��̏�Ńe�t���ƌ������A�ꏏ�ɕ�炵�n�߂܂��B
���̌��𗁂тāA�����F�ɋP���e�t���̔��B
���ɏo��������n�̃C���A�e�t���Ƃ̐������S�[�M�����̌�����ς��܂����B
�����ɓł��ꂽ�^�q�`�͍��A�T�����߂����n�̊y���ɐ��܂�ς�����̂ł��B �S�[�M�����ɂ���Ďc���ꂽ���n�̃C���̏ё��E�E�E �S�[�M�����̖��A ��Ƃ������Ă�܂Ȃ����������E�E�E�B
����
�u���n�̃C�������āH�Ȃɂ�傰���ȁB
�����̓��̖�����Ȃ����B
����ɂ��Ă��A���̊G�̖��͉����ɋ����Ă���̂��ˁH
�������A���ɂ������܂��Ă��邠�̕s�C���Ȃ��͉̂����B
�A�b�A����́I�v
���C�ƎX��ʁB
�����Č��������т���R�X�B
���܂��܂Ȋ�����^�q�`�B ������֓���ƁA�����͂��łɓ`���Ɛ_�b�̐��E�ł��B http://www.geocities.jp/mooncalfss/manao/manao2.htm ���^�u�[��
�^�q�`�ɂ̓^�u�[������B
���҂𑒂����ꏊ�͔�����悤�ɁB
����Ȗ̉A�ɉ������Ȃ��悤�ɁB
�����^�u�[��j�邱�Ƃ�����A�������邾�낤�B ��͐Q�Ă�����̂ɔ�т��āA����i�߁A���ɂ͔������������A���Ɏ��炵�߂邱�Ƃ�����B���̖��������Č��ɂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B ���܂��^�q�`�ɓ`���Ƃ����A�^�u�[�̐��̂Ƃ͉����B
��1
�u�������˂��A���̓y�n�̃^�u�[�Ƃ�������H��̂��Ƃ���B�v
��2
�u�q���̂���Ɍ������Ƃ������B
����`���āA�������݂����Ȏp�����Ă���̂�B
�{���ɋ���������B�v �j
�u�g�D�p�p�E���ėH�삳�A����Ȋ����̂�E�E�E
�ЂƂɎ��t���Ɩڂ��傫���Ȃ��āA��������Ȃɒ����Ȃ�B�v �}�i�I�Ƃ́u�v���v�u�l����v�Ƃ����Ӗ��̃^�q�`��B
�}�i�I�E�g�D�p�p�E�Ƃ����^�C�g���ɂ́A�g�D�p�p�E�A�܂莀�삪���Ă���A�Ƃ����Ӗ������߂��Ă����̂ł��B
����
�u�g�D�p�p�E�ɂ��ẮA������������h�������B
�ɂ��ƁA�g�D�p�p�E�̓s�͐X�̈łɕ�܂ꂽ�R���̉��ɂ��邻���ȂB
�����Ńg�D�p�p�E�͐��𑝂₵�A���l�Ԃ̍���H�炤�Ƃ����B
�t���A��������20���I���Ƃ����̂ɁA�^�q�`�ɂ͂܂��������M���c���Ă���̂��B�v
�w�|��
�u�m���Ƀg�D�p�p�E�̓`���͎c���Ă���悤�ł��B
�g�D�p�p�E�Ƃ͎��l�̗�̂��ƂŁA��̈ł����܂悢�����ƍl�����Ă��܂����B
���̂��߁A�^�q�`�̐l�����͈ł�|�����āA�Q�Ă���Ƃ�����������₵�܂���B
���������̖�����������Ă��܂��ƁA�g�D�p�p�E���Ƃ̒��ɓ����Ă��āA
�Q�Ă���ԂɈ���������ƐM�����Ă�������ł��B�v
������A�S�[�M�����͋A�蓹���}���ł��܂����B
�ꂩ�����������֔��o���ɍs�����A��ł��B
�钆��1���A������͊��S�ȈŁB
���̌����_�ɉB��Ă����܂��B �e�t���̑҂����͈łɕ�܂�Ă��܂����B
����ȗ\���������S�[�M�����͋}���ŕ����̒��ցB
����ƁE�E�E�����͌��n�̈ŁB �v�킸�}�b�`���������S�[�M�����B
�����Ĕނ̖ڂɉf�������̂́E�E�E
�x�b�h�ɉ�����蓀��t�����悤�ȃe�t���B
����Ɍ��J���ꂽ�e�t���̖ځB �^�q�`�̐l�ɂƂ��āA�ł̓g�D�p�p�E�̂��݂��B
�e�t���ɂ͖�̈ł͋��|���̂��̂ł����B
�����āA���|�Ɏ˔����ꂽ�悤�ɐg���ł�����e�t���̔w��ɁA�S�[�M�����͂͂����茩���̂ł��B �w����������̂́A�������|�����ł����B
����͐₦�ԂȂ����|�ł���B
���̃g�D�p�p�E�����āA���͊��S�ɐS�Ђ���A ������G�̃��`�[�t�ɂ����x �S�[�M�����̓e�t����ʂ��āA�͂��߂Ė{���̌��n�𗝉������̂ł��B �e�t���A���n�ɏZ�ރC���B �^�q�`�ɂ��ĎO�x�ڂ̉āE�E�E�B
����
�u�����B���߂łƂ��A�S�[�M�����N�B
�N�ɂ����ɂ������m�点���B
�{������N�𑗂�Ԃ��悤�Ɍ����Ă����B
�����������܂��A���Y��Ԃ��z���ɒl���鍢���̉�Ƃ𑗊҂��邱�ƁB�t�����X�̑D�ŁB
�������A��Ԉ����D�ɁA�悹��悤�ɂƏ����Ă���B
�Ƃ�����A����ʼn�炪�|�p���g���܂̔C���������Ƃ����킯���B
��������悤�A�S�[�M�����N�B�v 1893�N7���B
�S�[�M�����͖{���t�����X�ւ̋A�H�ɂ��܂��B
�e�t���Əo���������A�S�[�M�����̐����͌����ė��z�̂��̂ł͂���܂���ł����B
�ɓx�̕n���A�����ďd�Ȃ��J�B
������Ȃ������̉e�B
���ǁA�ނ͓����o���悤�Ƀ^�q�`����ɂ��邵���Ȃ������̂ł��B �p���ɋA�����S�[�M�����́A���̃}�i�I�E�g�D�p�p�E�ɑ��̊G�̔{�ȏ�̒l�i�������Ƃ����܂��B �^�q�`�ɂ�����������Ɠ������ƁB
���X�̕�炵�͖Y��A�����b�N�X���܂��傤�B �ł��A��͖�������₳�Ȃ��悤�ɁB
�����Â�������A�ł̒����炠�Ȃ����݂߂鎀��Əo����ƂɂȂ邩������܂���E�E�E http://www.geocities.jp/mooncalfss/manao/manao4.htm
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@,�-'''`'�L�P �M�t�- �
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@,. �]�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �R
�@�@�@�@�@�@�@�@ ,.�]�L�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�_
�@�@�@�@�@�@�@ /�@�@�@�@�@ ,l�@�@�@�@�@�@�@�_�@�@�@�@ �R
�@�@�@�@�@�@�@/�@�@�@�@�@�@�@l|,�@��@ � |i�R, �R �_.�@�@�@�R
�@�@�@�@�@�@ /�@�@�@�@�@l�@�@i ! | i�@ | |l'�ā@�R i�R�@�R�@ ',
�@�@�@�@�@�@ !�@�@�@�@�@|�@ / | |. i�@ |.|| i.|�R |� | ', �@ i�@ i
�@�@�@�@�@�@!�@�@�@�@�@ !�@/�@|,��ҁ@|i ď\i�]�gi�! l�@ .i|�@ i
�@�@�@�@�@�@!�@i�@�@�@,.|!,.+�]'"| |�@| |i}�@�@' �ɪ|i,`i�@�@l.|�@i
�@�@�@�@�@�@l i�@l�@�@�@l |/;:=�j|i�@ l |�@�@ /rj:�R�_ i�@�@l i�@l
�@�@�@�@�@�@| |�@|�@�@ � '/ i�)�R,�R |!. �@�@' {::::::;�! �ri�[ | |�@|
�@�@�@�@�@�@| |i.�@|�@ !; �q�@!:::::::c!�@�@�@�@�@'�''(�� }i |�@i.|�@|
�@�@�@�@�@�@|�@! | |�@ ;:�@(��`''"�@�@�@�@��@�@//// /;:i |�@| !. |
�@�@�@�@�@�@ | i,�@�@i.�@�////�@�@�@�@�@ '�@�@�@�@�@/,�mi,�@�@ i. |
�@�@�@�@�@�@ ! .|�@ | i �,�T�A�@�@�@�@ ���,�@�@�@�@/�@�@ i |�@ |. i
�@�@�@�@�@�@ .! |�@ i�@|. | l�R�A �@�@�@ �P�@�@�@�^�@�@l�@ | i�@ |�@!
�@�@�@�@�@�@�@! |�@ i�@|i |l l|�@|`''�] ��@�@�@, �C�@ |i |�@|i�@| i�@ |. !
�@�@�@�@�@�@�@| |�@ i�@|i |i .| � �@�@�@` ''"�@�@�R/l| l__,.�-|l l�@ ! i�
�@�@�@�@�@,. -'"ށP�'' �Ri |!l '�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ ,.--�]'�@|.i |i�@| |i �R
�@ �@ �@ /�@�@�@�@�@�@�@! l l�P �M�@�@�@�@ �_ �@ �@ �@�@�@| /�i�@i.!�@ |
�@�@ �@ ,'�@�@�@�@�@ �@ �@ ! |�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@,|/�@|/i'�@�@ |
�@�@ �@i�@�@�@�@�@�@�@�@�@` l�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@.�m�@ � '�@�R� |
�@�@�@ | �@�@�@�@�@�@ Ɂ@�@�@�@�@,...�@�@�@�@�@�@�R�;�@�@�@ �@ �@ �@�@�R-,
�@�@�@ .!�@�@ �@ �@ �@ |::�@�@�@�@�@:..�..::�@�@�@�@�@�@ i:�@�@�@�@�@�@�@�@��''i
�@�@ �@ | �@�@�@�@�@�@l:: �@�@ �@ �@ ��"�@�@�@�@�@�@�@|:�@�@�@�@�@�@ �@�@ |
�@�@�@@�! �@ �@ �@ �@ |::�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@!::�@�@�@�@�@�@�@�@�
Teha'amana (�}�i��^����҂̈�)
�ް�ެ݂��^�q�`�Ō��o�������͉̂��ł������̂��H
�w�m�A�m�A�x�A��ʼn�
�^�q�`����t�����X�A�������S�[�M�����́A�ꍑ�̃^�q�`�ւ̗����̖R�����ɁA��]���܂��B����ȕꍑ�t�����X�ցA�^�q�`�̐����̂��炵����`���邽�߂ɐ��삵���t�@���^�W�[�����A�w�m�A�m�A�x�̑}���G�Ɏg�p����Ă�����i�̂��������A�Љ�����Ǝv���܂��B
�i���F�E�i���F�E�t�F�k�A�i�����킵����n�j ���ȏ��Ȃǂł��L���ȍ�i�A�w�����킵����n�x�����E���]��������i�ł��B�ʼn�ɂȂ�A�����͂����肳�������̂ɂȂ������ƂŁA��l���ł���G���@�̕\��̔Z�W���A��肭������Ƃ��Ă��邱�Ƃ���ۓI�ł��B�B �܂��A�G���@�������̂����g�J�Q���A������傫���A���̔ʼn�̒��S�ɕ`����Ă��邱�Ƃ��A�C�ɂȂ�܂��ˁB
�e�E�A�g�D�A�i�_�X�j
�}�I�����i�j���[�W�[�����h�̃|���l�V�A�n��Z���j�̌Ñ�_�b���B
�����ɒ�������̂́A��_�^�A�A���A�B�E���ɂ͍Đ��̗͂������̏��_�q�i�B�����ɂ́A��n�̒j�_�ł��莀�̏ے��ł���e�t�@�g�D�ƃq�i�̑Θb�̏�ʂ��`����Ă��܂��B
�����̐_�X�́A�S�[�M�����̍�i�̒��ł͂�������o�ꂷ��A�d�v�Ȗ������ʂ����Ă�����̂ł��B �Đ��̐_�ƁA���̐_���A�ӂ��蓯���ɉ���b���Ă���̂��A�i�������A�l���������ӂ���́A�ƂĂ����\�I�ɘb�����Ă���悤�Ɋ����܂��B�B�j�C�ɂȂ�Ƃ���ł��ˁB�B �}�i�I�E�g�D�p�p�E�i���삪���Ă���j �e�E�|�i��)
���̂ӂ��̍�i�̂́A�u����ɋ����鏗���v�Ƃ�������̎���`���o���Ă��܂��B
�w�}�i�I�E�g�D�p�p�E�x�̏����̎p���́A�y���[�̃~�C���̑̐�������Ɏ����Ă��܂��B�܂�A�l�Ԃ̎���̑��݂ł���~�C���ƁA�����̐�������Ă���A�Ƃ������Ƃł��B
�������A���̏ے��Ƃ��v���邱�̍�i�́A���悤�ɂ���Ăَ͑��̂悤�ɂ������܂��B ��������ӂ��̂��́A�܂�A���Ǝ�����̉������ӂ��̋��E�����h�炮�A�^�q�`�̖�̐_���`���o���Ă���悤�ł��B�ӂ��̑���������̂��A�ЂƂ̂��̂̒��ɗZ��������A�Ƃ������Ƃ́A�l�ނ̑傫�ȃe�[�}�ł���Ɗ����܂����B �܂��A�w�e�E�|�x�̕��́A�S�[�M�������^�q�`�łł������l�A�e�n�A�}�i���A��A������̏����������ŁA����ɋ����Ă���p��`������i�ł��B �^�q�`�̐l�X�ɂƂ��Ė�́A�썰����������A���Ɨׂ荇�킹�̐��E�ɂق��Ȃ�܂���ł����B�^�ɉ�����鏗���̌��ɂ́A�l�X�Ȏ��삽����������ɖڂ������Ă��܂��B�B ���̂��Ƃ���l����ƁA�S�[�M�����̕`���[���̐��E�́A����̉�X���l����悤�ȁA�P�Ȃ�������[�Ă��ł͂Ȃ��A���ꂩ��}����遁����̐��E���v�킹��悤�ȁA�����A�ł����E���̔��ꂽ���E���ނɂ��Ă����i�ł��邱�Ƃ�������܂��B�B http://nuartmasuken.jugem.jp/?eid=83
�w��X�͂ǂ����痈���̂��@��X�͉��҂��@��X�͂ǂ��֍s���̂��x��A���E�������o�ăS�[�M�������`������i�̂����A�C�ɂȂ�����i���������B�B
�e�E�n�y�E�i���F�E�i���F�i�����������j
1898�N�@���ʁE�L�����p�X�@���V���g���A�i�V���i���E�M�������[
http://www.abcgallery.com/G/gauguin/gauguin128.html
�w��X�́`�x�̊֘A��i�ł��B
�@
�����͗[���A���삪舕�����邪�A�������܂Ŕ����Ă��Ă��܂��B ��O�̂S�l�̏����̕\��́A�t���ł͂�����Ƃ킩��܂���B�����ׂĂ���悤�ɂ������邵�A�w�ォ�甗�肭���ɁA�����Ă���悤�ɂ������܂��B�B ��������ɂ́A�q���Ǝ���Ȃ����i�H�@�Â��̂ŁA�͂����肻���Ƃ͌�����܂�����j���Ђ���A���𒅂������ƁA�Đ��̏��_�q�i���`����Ă��܂��B���̑����Ƃɂ́A�S�[�M�����m���g�ł��鍕�����炵���e���A�łɕ����悤�ɂЂ�����Ƃ��܂��B ������ɁA���Ǝ����ΏƓI�ɕ`����Ă���悤�ł��B��x�������ӂ��A�Ȃ��������炦����Ƃ̐S���́A�ǂ����������̂������̂ł��傤������H �S�[�M�����̍�i�ɂ͂߂��炵���A���s��������A���Ă���Ƃ��炾���A�G��̒��Ɉ������荞�܂ꂻ���ɂȂ��i�ł��B
http://nuartmasuken.jugem.jp/?eid=89
��X�͂ǂ����痈���̂�,��X�͉��҂�,��X�͂ǂ��֍s���̂�
�iD'ou venons-nous? Que Sommes-nous? Ou allons-nous?�j
1897�N | 139�~374.5cm | ���ʁE�� | �{�X�g�����p��
http://www.salvastyle.com/menu_impressionism/gauguin_nous.html
������
http://www.meiga-koubou.com/item/%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%82%AE%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%80%8E%E6%88%91%E3%80%85%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%93%E3%81%8B%E3%82%89%E6%9D%A5%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%8B%E6%88%91%E3%80%85%E3%81%AF%E4%BD%95%E8%80%85/
�u��X�͂ǂ����痈���̂��A��X�͉��҂��A��X�͂ǂ��֍s���̂��v�Ƃ̓N�w�I�v�҂𔗂�A������139�~375cm�Ƃ����lj�̂悤�ȑ���ڂ̑O�ɂ��܂��ƁA���炭�߂܂��̂悤�Ȋ��o�ɏP���܂��B�S���ƍ��z�����̏��������A�n�ʂ̏�ɍ����āA����������Ă��܂��B
��ʉE���ɂ́A��̏�ɐԂ�V���Q�Ă���A�t�̍��[�ɂ́A���̂悤�ɍ����V�k���A��͂肱������Î����Ă��܂��B��ʒ����ł͒j���ʕ��������ł���A���̑����ŁA�������ʕ���H�ׂĂ��܂��B�l�тƂ̋߂��ɂ́A���ƔL�ƎR�r�ƒ��Ƃ��A�l�Ԃ����Ɠ��l�ɁA���\��ɒn�ʂɕ����Ă��܂��B��ʌ���ɂ́A�܂�������L�������_��������A�����đ̑S�̂��悤�Ȓ��߂𒅂����������A�E���Ɍ������ĕ����Ă��܂��B�w�i�ł́A���z�I�Ȏ����A����Ȏ}���L���Ă��܂��B
�@���̊G����A�A�_���ƃC���̋֒f�̎��Ɗy���Ǖ��̋����̕����A�z���邱�Ƃ́A���قǓ�����Ƃł͂���܂���B�������A���̋֒f�̉ʎ����̂����̂́A�C���ł͂Ȃ��������B�S�[�M�����̃C���́A�ǂ��݂Ă����ł͂Ȃ��B�}���I�E�o���K�X�E�����T�́A�w�y���̓��x�ŁA�ʕ����̂�l���̍��z�̂ӂ���݂��u���h���Ίۂƌł��Ȃ����y�j�X�v�̂悤���Ƃ���\�����Ă��܂��B�y���Ǖ����Î�����Ԃ����߂𒅂��ӂ���́A�A�_���ƃC���̂悤�ɒj�E���ł͂Ȃ����E���ł���A�܂��L���X�g���G��ɂ���ߒQ�ɂ����ӂ���ł͂Ȃ��A�����^���Ɍ�荇���Ă��܂��B�L���X�g���̐��E�����ނ���Ȃ�����A���e�͕ʂ̐��E��\�����Ă��܂��B �@���[�̘V�k�́A�ώ҂��Î����Ȃ���A����i���Ă���̂ł��傤���B�S�[�M�����́A�t�����X�̔����قŌ����y���[�̃~�C������A���̐l������n�삵���Ƃ������Ƃł��B�y���[�́A�S�[�M�������c�������߂������Ƃ���B���ɂ����V�k�͍ő��A�����邱�Ƃ�������߁A��n�ɕԂ��Ă������Ƃ��A��X�ɍ����Ă���̂�������܂���B �@���p�ّ؍ݒ��̑唼���A���̑��̑O�ɂ�������ʼn߂������̂ł����A���Ԃ��o�ɂ�Ă��̎��ɂ����V�k�̎������A�C�ɂȂ��Ďd��������܂���ł����B�u��X�͂ǂ��֍s���̂��H�v�B�V�k�̒��ق́A���̓����̂Ȃ��₢�|���Ȃ̂�������܂���B
http://minoma.moe-nifty.com/hope/2009/07/post.html
�g��X�͂ǂ����痈���̂�,��X�͉��҂�,��X�͂ǂ��֍s���̂��h �̓C�G�X����������t
���n�l�B������ ��8��
8:1�C�G�X�A�I���u�R�ɂ䂫���ӁB
8:2�閾����A�܂��{�ɓ��肵�ɁA���݂Ȍ䋖�ɘ҂肽��A�����ċ����ӁB 8:3�����ɛ{�ҁE�p���T�C�l��A�����̂Ƃ��߂ւ�ꂽ�鏗��A�ꂫ����A�����ɗ��ĂăC�G�X�Ɍ��ӁA 8:4�w�t��A���̏��͊����̂���A���̂܂ܕ߂ւ�ꂽ��Ȃ�B 8:5���[�Z�͗��@�ɁA�z����҂�ɂČ��ׂ��������ɖ������邪�A���͔@���Ɍ��ӂ��x 8:6�����]�ւ�́A�C�G�X�����݂āA�i�ӂ���ƂĂȂ�B�C�G�X�g�����߁A�w�ɂĒn�ɕ��������ӁB 8:7������ЂĎ~�܂���A�C�G�X�g���N���āw�Ȃ����̒��A�߂Ȃ��҂܂Ðāx�ƌ��ЁA 8:8�܂��g�����߂Ēn�ɕ��������܂ӁB 8:9�ޓ�������ėǐS�ɐӂ߂��A�V�l���͂��ߎႫ�҂܂ň�l��l���ł䂫�A�B�C�G�X�ƒ��ɗ��Ă鏗�Ƃ݈̂���B 8:10�C�G�X�g���N���āA���̂ق��ɒN������ʂ����Č��Ћ��Ӂw����Ȃ�A����i�ւ���҂ǂ��͉��|�ɂ��邼�A�����߂���҂Ȃ����x 8:11�����Ӂw���A�N���Ȃ��x�C�G�X���Ћ��Ӂw���������߂����A�����A���̌�ӂ����э߂�Ƃ��ȁx�n 8:12�����ăC�G�X�܂��l�X�Ɍ��Č��Ћ��Ӂw���͐��̌��Ȃ�A��ɜn�ӎ҂͈Â�������܂��A�����̌��ׂ��x 8:13�p���T�C�l�猾�Ӂw�Ȃ���͌Ȃɂ���暂��A�Ȃ����暂����Ȃ炸�x 8:14�C�G�X���ւČ��Ћ��Ӂw��ꎩ��Ȃɂ���暂��Ƃ��A�䂪暂����Ȃ�A
��͉��|���҂艽�|�ɉ�����m��̂Ȃ�B
����͉䂪���|���҂�A���|�ɉ�����m�炸�A
8:15�Ȃ����͓��ɂ��ĐR���A��͒N�����R�����B
http://bible.salterrae.net/taisho/xml/john.xml
�S�[�M���������グ�� �g��͉��|���҂艽�|�ɉ�����m��̂Ȃ�B����͉䂪���|���҂�A���|�ɉ�����m�炸�h�Ƃ����͍̂߂̏��̘b�̑����Ƃ��ăC�G�X����������t�Ȃ̂ł��B�����A ���_�����A�L���X�g���A�C�X���������̍����̗V�q�E�q�{���̕����ł͏���������E���s����G�����A �������I�i�j�[���� �� �I�i�j�[�ł��Ȃ��l�ɏ����̉A�j��؏����� �������������ꂽ �� �j�ӎ��ɗU�f���Ȃ��l�ɏ�����Αł̌Y�ɂ��� �Ȃ��v�ɔ��t���������ꂽ �� �v�ɓ����߂����J��Ԃ����Ȃ��l�ɍȂ�Αł̌Y�ɂ��� �����������E�s�ς��� �� �j��f�킹�Ȃ��l�ɏ�����Αł̌Y����t��ɂ���
�ɂ���đΏ�����`���������̂ł��B �C�G�X���ے肵�悤�Ƃ����̂͂����������_�����̓`���������̂ł����A�L���X�g���ł̓C�G�X�̋��������S�ɖ������A���_�����̈������`�����������肻�̂܂܋��`�Ƃ��Ďc�����̂ł��ˁB
�܂��A�p���X�`�i�̗l�ȍ����n�тł͐l����������� �݂�ȐH�ׂĂ����Ȃ��Ȃ�̂Ŏd�������̂ł����B _____________ �S�[�M������11����16�܂ŃI�����A���x�O�̃��E�V���y�����T�������X�}���_�w�Z�̊w���ŁA���̊w�Z�ɂ̓I�����A���勳�t�F���b�N�X�E�f���p�����[�����t�Ƃ���J�\���b�N�̓T��̎��Ƃ��������B �f���p�����[�͐_�w�Z�̐��k�����̐S�ɃL���X�g���̋����ⓚ��A���t���A���̌�̐l���ɐ������L���X�g���`�̗�I�ȉe����^���悤�Ǝ��݂��B ���̋����ɂ�����3�̊�{�I�Ȗⓚ��
�u�l�Ԃ͂ǂ����痈���̂� (Where does humanity come from?)�A
�u�ǂ��֍s�����Ƃ���̂� (Where is it going to?)�v�A �u�l�Ԃ͂ǂ�����Đi�����Ă����̂� (How does humanity proceed?)�v�ł������B
�S�[�M�����͌㔼���ɃL���X�g�����ɑ��ĖҔ�������悤�ɂȂ邪�A�f���p�����[�������������̃L���X�g�������ⓚ�̓S�[�M�������痣��邱�Ƃ͂Ȃ������B
http://www.asahi-net.or.jp/~VB7Y-TD/L1/210819.htm �_�j�G���E�h�E�����t���G���āi�P�W�X�W�N�Q���C�^�q�`�j �u�c���Ȃ��Ɍ����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����C���͂P�Q���Ɏ��ʂ��肾�����B����ŁC���ʑO�ɁC��ɓ��ɂ���������`�����Ǝv�����B�P�����̊Ԃ����ƒ���ʂ��ēr�����Ȃ���M�ŕ`���������B�c����́C�����P.�V���[�g���C���S.�T���[�g���̊G���B�c �E���ɁC�����Ă���Ԃ�V�ƁC�������܂�R�l�̏����B���F�̕��𒅂��Q�l�̐l�Ԃ����݂��̍l����ł������Ă���B �킴�Ƒ傫�����ĉ��ߖ@�����ĕ`�����l���́C�������܂�C�r����ɂ����C���������̉^�����l���Ă���Q�l�߂ċ����Ă���B �����̐l���́C�ʕ���E��ł���B��l�̎q�ǂ��̖T�ɂ́C�Q�C�̔L������B�����Ĕ��������M�B �����́C�_��I�ɗ����I�ɗ��r�������C�ފ݂��w���������̂悤���B�������܂����l���́C�����Ɏ����X���Ă���悤�Ɍ�����B
�Ō�ɁC���ɋ߂��V�k�́C����̉^�����Î�����߂Ă��邩�̂悤���B�c���̑����ɁC���łƂ��������ނP�H�̔������m�̒������邪�C��a�Ȍ��t�̖��p������Ă���B�c�v http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/ss/sansharonshu/444pdf/02-06.pdf �S�[�M�������g���F�l�����t���G���Ă̎莆�S�R�j�̒��ŋL���Ă���悤�ɁC�ʉE�[�ƍ��[�ɂ͐l�Ԃ̐��Ǝ���\�����̂悤�ɐԂ�V�ƘV�k���`����Ă���B��ʒ����ɂ́C�ʎ���������낤�Ƃ���N�̎p������C�T��ɂ͒n�ʂɍ��荞��ʼnʎ���H�ׂ�q��������B���̑��^�q�`�������z�u����C���M�⌢�C���Ƃ����������C�����ČÑ�̐_�Ƃ����������`����Ă���B�S�[�M�������l�́C���ł���������牷�߂Ă�����ނƂ��Ȃ�����C��i�̈Ӑ}��`���ꂽ�X�̑Ώۂ̈Ӗ��ɂ��ď\���Ȑ��������Ă��Ȃ��B ��s�����ł́C�܂���i�^�C�g���s��X�́c�t�̏o�T���̊m�F�����݂��Ă���B ���[�N���[�J�[�́C�S�[�M�����̃u���^�[�j������̏ё���Ɍ��o�����g�}�X�E�J�[���C�����́w�ߑ��N�w�x�ɁC
O Whence�� OhHeaven, Whither?�i�����ł�Maisd�foùvenouns nous? O Dieu,oùallonsnous?�j�Ƃ����薼�ƑΉ�����ꕶ��������Ǝw�E���Ă���B�܂��C�t�B�[���h���J�g���b�N�̔�V���������������ɁC��i�^�C�g���ƈ�v���镶�ʂ�����Ƃ��Ă���B��i���ɂ����郂�e�B�[�t�ƓT�����̊W�ɂ����ẮC�^�q�`����̎��g�̍�i����̓]�p�����łȂ��C�u���^�[�j������̍�i�ɂ��̎n�܂�����o������̂�����B ���̉E������ĉ����肷�鏗���̃|�[�Y�́C�P�W�W�X�N�́s�C�����W�߂�҂����t�̏����̃|�[�Y�]���������̂ł���B�܂��C���[�̊����ʼn������Ă������܂�V�k�̎p���C�u���^�[�j�����ォ��S�[�M��������i�Ɏg�p���Ă����|�[�Y�ł���C�y���[�̃~�C�����ɂ��̍��������o����B�^�q�`����̍�i������p���ꂽ�������ɂ����Ă��C�W�������̃{���u�h�D�[�����@�̃����[�t��G�W�v�g�̕lj�ɂ��̌��^������B �ȏォ��l�����邱�Ƃ́C�^�C�g������z�N�����L���X�g���I���_�ƁC���ۂ̃��e�B�[�t���猻��鐼�m�C�m���z�����L�����_�Ƃ̊Ԃɋ�����������Ƃ������Ƃł���B�����ō�i�����߂čl�@����ƁC�s��X�́c�t�ɂ́C��X�����͍����Ȃ�������B�����Ȃ��l�ԑ��݂��`����Ă���ƌ����Ȃ����낤���B�u���^�[�j���C�^�q�`�C���邢�̓W��������G�W�v�g�Ƃ���������̏ꏊ��l�X�ł͂Ȃ��C�l�Ԃ��̂��̂ւ̋������ۂ������ɂ͑��݂���B���ꂼ��̃��e�B�[�t�́C�f�ГI�\�ۂɂ��ւ�炸��i�S�̂ɂ����Ē��a���Ȃ��Ă���B�����āC�����������e�B�[�t�̔w�i�ɑ��݂���L���X�g����^�q�`�ɂ�����M�Ȃǂ̖����M�́C�l�Ԃ̋F��Ƃ������x���ɂ����ē����̂��̂Ƃ݂Ȃ����B ��i�^�C�g���s��X�͂ǂ����痈���̂��H��X�͉��҂��H��X�͂ǂ��֍s���̂��H�t�́C�l�ԂɂƂ��Ă̎��㖽��ł���B��
�܂肱�̊G��ɂ́C�S�[�M�������u���^�[�j���ɂ����Ċ�����nostalgia�̂̐l�ԑ��݂��̂��̂ւ̊�������̂ł���B
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/ss/sansharonshu/444pdf/02-06.pdf
�����۔h�̑�\���鋐���ɂ��đ�����`�̑n�n�҃|�[���E�S�[�M�����̉�Ƃɂ�����W�听�I�Ȍ���w��X�͂ǂ����痈���̂��A��X�͉����A��X�͂ǂ��֍s���̂��x�B
1895�N9������1903�N5���܂ő؍݂����A�����A��2���^�q�`�؍݊��ɐ��삳�ꂽ��i�̒��ōō�����̂ЂƂƂ��čL���F�߂���{��ɕ`�����̂́A�S�[�M�������l�ލŌ�̊y���ƐM���Ă����^�q�`�ɏZ�ތ��n���̐����₻�̎p�ŁA�{��ɂ̓S�[�M����������܂ł̉�ƂŔ|���Ă����G��\���͂��Ƃ��A��Ǝ��g�������Ă����l���ς⎀���ρA�Ǝ��̐��E�ςȂǂ������Ɏ�����Ă���B������A1898�N7���Ƀp���ւƑ����A���K�I�Ȑ����i���l�Ŕ��p�j�ɂ͎���Ȃ��������̂́A�����̏ے���`�҂��]�Ƃ炩�獂���]�������{��̉��߂ɂ��Ă͏����������Ă��邪�A ��ʉE�����ɂ͑�n�ɐ��܂�o�ł��Ԏq���A�����ɂ͉ʎ������Ⴂ�l���i�����ɋL�����ŏ��̏����G���@���֒f�̉ʎ������p��͂����Ƃ��l�����Ă���j���A�����č������ɂ͘V�����V�k���`����Ă��邱�Ƃ���A��ʓI�ɂ�(�l�Ԃ̐����玀)�̌o�߂�\�������Ƃ�������̗p����Ă���B �܂��V�k�̐�ɕ`����锒�����̉��߂ɂ��Ă��A���t�ł͗�������Ȃ��i���͌��t�����A���t�̋������j���Ӗ�����(�_��̏ے�)�Ƃ�����Ȃǔ�]�Ƃ⌤���҂�������l�X�Ȑ����������Ă���B ��ʍ������ɔz�����_���B���̐_���͍Ւd�}���G�ɍՂ���n���_�^�A���A�i�^�q�`�_�b�ɂ����鎊�����݁j�Ɖ��߂���A�������g�̎p�Ɏ����Đl�Ԃ������A���̉e�̓N�W�����邢�̓z�I�W���U���ł���Ɖ]���Ă���B�܂����̏��_�q�i�Ɖ��߂�������������Ă���B ����ɖ{����肪���钼�O�ɍň��̖��A���[�k�̎��̒m�点�������Ƃ�����A������A�S�[�M�����̓q�f�i��f�j�������E��}�������Ƃ��m���A����́A�{��͉�Ƃ̈⏑�Ƃ����߂���Ă���B�{��Ɏ������A����Ȍ��F�I�F�ʂƒP�����E���ʉ������l�̕\���A���ƈł���������Ɠ��̐��E�ς̓S�[�M�����̊G�搢�E���̂��̂ł���A���̓N�w�I�ȗl���Ƌ��ɁA��Ƃ̕����v�z��S���I���_�����ς�҂����i���A�₢������悤�ł���B
http://www.salvastyle.com/menu_impressionism/gauguin_nous.html
�u�M�т̃C�u�v�Ƃ��ĉ������̍�i�ɓo�ꂷ�鏗���̃|�[�Y�́A�W�������̃{���u�h�[����Ղ̃����[�t�����f���ɂ������̂ŁA�^�q�`�Ƃ͖��W�ł���B���Ȃ݂ɃC�u��U�f����ւ́A�S�[�M�����̊G�ł̓g�J�Q�Ƃ��ĕ\������Ă���B
����҂��������𗼎�ŕ������ރ|�[�Y�́A�y���[�̃~�C������v���������̂ŁA������^�q�`�Ƃ͖����ł���B �s��X�͂ǂ����痈���̂��@��X�͉��҂��@��X�͂ǂ��֍s���̂��t�̒��S�ɂ�������͕����ł͂Ȃ��A�^�q�`�̓y���̐_�l�A�Đ����i�ǂ錎�̏��_�ł���B
��ԋ������̂́A�G�̒��ɕ`����錢�́A�����Ă��̏ꍇ�S�[�M������\���Ƃ������Ƃł���B
http://nodahiroo.air-nifty.com/sizukanahi/2009/07/post-8a2a.html
���̊G�ŃS�[�M�����͐l�̈ꐶ�����ʂɕ\�����悤�Ƃ��Ă��܂��B�u���܂�āA�����āA���ʁv�������Ȃ瓖����O�Ȃ��Ƃ�`���Ă���̂ł��B �����Ă��̊G�ɂ͊C����̕��ɏ����`����Ă��܂��B
�E��ɂ͒��̊C���`����A�n���̒a�����Ӗ����A���̊C�ɂ͖�̊C���`����A�n���̏I�����Ӗ����Ă���̂ł��傤���B ���̊G�ɕ`����Ă���l���͂قƂ�ǂ������ł��B����L�A���Ȃǂ��`����Ă��܂��B���ꂼ��ɈӖ��Â������Ă��܂����ǂ��Ȃ�ł��傤���H �E�̎q�ǂ��͒a���ł��傤���A�����̃����S����낤�Ƃ��Ă��鏗���̓C�u�i�G�o�j���Ӗ������y�Ƌ�ɂ�\�����A���̓�������Ă��鏗���͎����Ӗ����Ă��܂��B ��ʑS�͈̂Â��̂ł����A�E���̏����ɂ͌����������Ă��āA�����͈Â��B �w�i�͉E�������Â��`����A�S�[�M�����ɂƂ��Ắu���̐��͐^���Èł��v�܂ł͂������A�u�ÈŁv�����炢�Ȃ̂ł��傤���B http://blogs.yahoo.co.jp/haru21012000/60035012.html 19���I�ȍ~�A�|���l�V�A�l�̓L���X�g���ɉ��@���Ă��܂����A�u���^�[�j���n���̃L���X�g���̏ꍇ�ƑS�������ŁA�O�ς̓L���X�g���̈ߑ���Z���Ă��Ă��A���̒��g�͌×��̃A�j�~�Y�����̂��̂������̂ł��ˁB �S�[�M�������`���A�_���ƃC�u��}���A�����������ނ�I��ł��܂����A���̈Ӗ����鎖�̓L���X�g���̋����Ƃ͑S���قȂ镨�Ȃ̂ł��B �g��X�͂ǂ����痈���̂�,��X�͉��҂�,��X�͂ǂ��֍s���̂��h�Œm�b�̖̎����̂�̂͒j�ł����A �G�f���̉�����̒Ǖ��Ƃ����͎̂��y���ł͂Ȃ��A�S������̉���Ƃ����Ӗ������̂ł��B�F
�V�����[���_�b�ɂ��A�_�l���܂��A�S�y�����˂Đl�Ԃ�n�����B
�u�Ȃ��A�_�l�͐l�Ԃ�n�������́H�v �Ƃ����̂��A�L���X�g���k��C�X�������k�̐e���A�q���Ɏ��₳��ĕԓ��ɋ�����f�p�ȋ^��B ����ɑ��āA���E�ŌÂ̏@���E�V�����[���_�b�́A�����ȉ�^���Ă���B �u�_�X�������Ȃ��Ă��悢�悤�ɁA�J���҂Ƃ��Đl�Ԃ͑n�����ꂽ�v �ƁA�V�����[���_�b�̔S�y�ɂ͖��L����Ă���̂��B ���킭�A�炢�_��Ƃ�A�������Ƃɏ]�����Ă����_�X����́A�s���s�����₦�Ȃ������B �u����Ȃɉ����������₪���āA�ǂ��������肾�A�R���`�N�V���[�v �Ɠ{���Ă����B �����̕�Ȃ鏗�_�E�i�����́A���̎��Ԃ�[���J�����Ă������A�u�_�X�̒��ł��A���ЂƂ������m�b�ҁv�ƕ]���̃G���L�_�́A�����Ƃ����炸�ɖ��肱���Ă����B
����Ƃ��A�i�������_�́A�G���L�_���������N�����Č������B �u���q��A�N���Ȃ����B���Ȃ��̒m�b���g���āA�_�X���炢�d�������������悤�ɁA�g���������Ȃ����v�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
��̌��t�ɂ���Ă��G���L�_�́A�S�y�����˂Đl�Ԃ�n�����B
�������ŁA�_�X�ɑ����Đl�Ԃ������悤�ɂȂ�A�_�X�͂߂ł����J�����������ꂽ�B�V�����[���_�b�̍ō��_�ł���V��̐_�A���i�G���L�̕��j��A��C�̐_�G�������i�G���L�̌Z�j���A����ɂ͑��сB�_�X�͏j�����J���A���������Ƀr�[����Ɉ����Đl�ޑn�����j�����i�V�����[���́A�r�[���̔��˒n�ł�����j�B ���̂Ƃ��A�r�[��������Ő����ς�����l�ނ̎n�c�G���L�́A�n��_�E�j���t���T�O�i�G��������G���L�ٕ̈ꖅ�j�ƂƂ��ɁA�l�ԂÂ���̋����������B
�u�L��������Ȃ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��l�ԁv��A
�u�r�A���K�}���ł��Ȃ��l�ԁv�A �u����������Ȃ��l�ԁv�A �u����낵�ė����オ�邱�Ƃ��ł��Ȃ��l�ԁv
�ȂǁA�����Ȑl�Ԃ��n��ꂽ�Ƃ���
�i�l���i��c�̂���������A���{�������ȃG�s�\�[�h�ł��ȁE�E�E�j�B
http://blog.goo.ne.jp/konsaruseijin/e/20278c1470953be34e1163edce926967
|
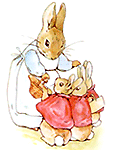
 �X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B