http://www.asyura2.com/18/reki3/msg/774.html
| Tweet |
(回答先: 雑記帳 古人類学の記事のまとめ 投稿者 中川隆 日時 2019 年 9 月 01 日 07:02:26)
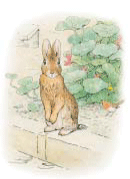
ネット上でよく見かける人類進化に関する誤解
2018年09月29日
人類進化に関する誤解のまとめ
https://sicambre.at.webry.info/201809/article_49.html
ネット上でよく見かける(と私が判断している)人類進化に関する誤解をいくつかまとめてみました。おもに現生人類(Homo sapiens)とネアンデルタール人(Homo neanderthalensis)関連となりますが、今後、他にも気づけば、取り上げていく予定です。
●現生人類の起源は遺伝学的に20万年前頃
現生人類出現の年代は遺伝学的に20万年前頃と推定されている、との認識を以前よく見かけたように思いますが、これは現代人のミトコンドリアDNA(mtDNA)における合着年代を現生人類出現の年代と同一視しているためで、誤解だと思います(関連記事)。そもそも、進化は連続的なものであり、どの時点で種(もしくは分類群)の起源と認定できるのか、難しい問題だと思います。現生人類の起源に関しては、現代人に共通する派生的な形態学的特徴がアフリカ各地で異なる年代・場所・集団に出現し、比較的孤立していた複数集団間の交雑も含まれる複雑な移住・交流により現生人類が形成された、との見解が有力になりつつあると私は考えており(関連記事)、そうだとすると、どの時点を現生人類の起源と考えるのか、ますます難しくなってきたように思います。
●出アフリカ現生人類集団は黒人だった
そもそも、更新世の人類史に「黒人」なる概念を用いることに大きな問題があると思いますが、ここでは、肌の色が濃い人々と読み替えて話を進めていきます。日本人も含めて非アフリカ系現代人の共通祖先集団の肌の色は濃かった、というわけです。ただ、そうである可能性は無視してよいほど低いわけではないとしても、そうではないというか、肌の色は多様だった可能性が高いと思います。(サハラ砂漠以南の)アフリカ人の肌の色は濃いと一般的には考えられているかもしれませんが、現代人の各地域集団間の比較で、アフリカは最も遺伝的多様性が高く、肌の色も多様です。現代人の多様な肌の色の遺伝的基盤もまた多様なのですが、薄い肌の色の遺伝的基盤の多くはアフリカ起源であり、非アフリカ系現代人の主要な遺伝子源となった共通祖先集団の出アフリカの前に、すでにアフリカにおいて肌の色は多様だったと考えられます(関連記事)。
●白人の肌の色はネアンデルタール人に由来する
人類進化史において「白人」なる概念を用いることに大きな問題があると思いますが、ここでは、おもにヨーロッパの肌の色が比較的薄い人々と読み替えて話を進めていきます。上述した出アフリカ現生人類集団の肌の色の問題とも関連しますが、肌の色の濃かった現生人類が、ネアンデルタール人との交雑により肌の色が薄くなった、との認識はそれなりに定着しているように思います。これは完全な間違いとまでは言えず、じっさい、異なる遺伝子座の複数のネアンデルタール人の対立遺伝子がヨーロッパ系現代人の肌と髪の色に影響を及ぼしているわけですが、それは色合いを濃くする方にも薄くする方にも作用しており、ネアンデルタール人の肌と髪の色も、現代人と同じく多様だったのではないか、と推測されています(関連記事)。少なくとも、肌の色の濃かった現生人類が、ネアンデルタール人との交雑により肌の色が薄くなった、と単純化できるわけではないと思います。じっさい、ネアンデルタール人と交雑した非アフリカ系現代人集団でも、更新世〜完新世初期にかけてのヨーロッパには肌の色の濃い集団が存在しており、現代人における薄い肌の色の定着に関しては、複雑な経緯があったと推測されます(関連記事)。また、色素形成機能を減少させるような遺伝的多様体の中には、現生人類とネアンデルタール人とで塩基配列が異なるものもある、と指摘されています(関連記事)。
●交雑の組み合わせはネアンデルタール人男性と現生人類女性のみ
ネアンデルタール人と現生人類との交雑はすでに広く知られていると思いますが、その組み合わせは現生人類女性とネアンデルタール人男性のみだった、との認識はよく見られます。しかし、現時点ではそうだと断定できるわけではなく、今後の研究の進展を俟つしかないと思います(関連記事)。
●世界で最もネアンデルタール人に近いのは日本人
これは、Toll様受容体関連遺伝子のハプロタイプのうち、ネアンデルタール人由来と推測されるものを有する割合が、調査した民族では日本人が最高というだけで、世界で日本人が最もネアンデルタール人と遺伝的に近縁であることを意味しません(関連記事)。たとえば、脂質異化作用関連遺伝子では、ヨーロッパ人の方が日本人よりもネアンデルタール人の影響は強いと推定されています(関連記事)。ゲノム規模でも、日本人よりも韓国人の方がわずかにネアンデルタール人の影響は強いと推定されています(関連記事)。
●純粋なサピエンスはアフリカ人のみ
非アフリカ系現代人は全員、ネアンデルタール人の遺伝的影響を受けています。一方、サハラ砂漠以南のアフリカ人には、ネアンデルタール人の遺伝的影響はほとんど見られません。もっとも、更新世に出アフリカ現生人類集団がアフリカに「戻った」と推定されており(関連記事)、それは完新世にも起きていたと推測されますし(関連記事)、イスラム教勢力や帝国主義の時代のヨーロッパ勢力のアフリカへの侵出もあるので、多くのアフリカ系現代人は、わずかながらネアンデルタール人の遺伝的影響を受けていると思われます。とはいえ、アフリカ人がネアンデルタール人の遺伝的影響をほとんど受けていないことは否定できません。しかし、それはアフリカ人が「純粋なサピエンス」であることを証明するわけではありません。古代DNAとの直接の比較ではないので確定的とは言えませんが、一部のアフリカ人の系統と遺伝学的に未知の人類系統との交雑の可能性が指摘されており、じっさいアフリカでは、現生人類にとってネアンデルタール人よりも遠い関係にあると思われる人類系統の中期更新世後期までの存在が確認されていて、それ以降も存在していた可能性が想定されます(関連記事)。
●貝などの海産物を食べていた人類は現生人類のみ
これは、貝などの海産物も食べるような柔軟な行動が可能だった人類は現生人類のみで、それ故に世界中に拡散してネアンデルタール人など先住人類を置換した、という文脈で語られることがあります。確かに、人類が貝を恒常的に食していたと推定される現時点で最古の事例は、アフリカ南部のピナクルポイント(Pinnacle Point)遺跡で確認されており、その年代は164000年前頃までさかのぼります(関連記事)。しかし、ネアンデルタール人も同じ頃に貝を食べていたと推測されており(関連記事)、人類は20万年以上前より貝も食べていて、それが恒常的だった集団もいる、と考える方が妥当だと思います。
https://sicambre.at.webry.info/201809/article_49.html
|
|
|
|
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
|
|
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。