http://www.asyura2.com/24/gaikokujin3/msg/524.html
| Tweet |
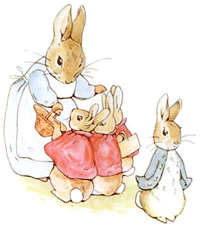
日本の魚が減ったのは「外国漁船が原因」説の真実/東洋経済オンライン
片野 歩 の意見
https://www.msn.com/ja-jp/news/opinion/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E9%AD%9A%E3%81%8C%E6%B8%9B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%AE%E3%81%AF-%E5%A4%96%E5%9B%BD%E6%BC%81%E8%88%B9%E3%81%8C%E5%8E%9F%E5%9B%A0-%E8%AA%AC%E3%81%AE%E7%9C%9F%E5%AE%9F/ar-AA1JKGCw?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=b573723233e04f9696d33c03ca5f3a9a&ei=38
7月の参議院選挙では外国人問題が争点となりました。意見や立場が異なるのは当然ですが、そこで前提となる情報が誤っていれば、議論そのものが土台から揺らいでしまいます。
スルメイカやサンマなど日本の漁獲量の減少についても同じで、「外国漁船が悪い」といった前提が正確でないため、多くの国民が理由を誤解しています。漁業も政治と同じく、国民が関心を持たなければ、その代償を払うのは私たち一人ひとりです。
漁業者が悪いわけではない
政府は「国際的に遜色のない資源管理システムの導入」を掲げています。しかし誤情報が蔓延する中で、実際には魚の取りすぎが止まらず、資源の持続性に逆行しているのが現状です。この流れを断ち切れなければ、日本の食卓と漁村はさらに厳しい状況に追い込まれます。
なお、漁獲量が減っているからといって漁業者が悪いわけではありません。最大の問題は「資源管理制度の不備」です。そのことが社会的に正しく認識されていないため、漁業者が非難されたり、自分で自分の首を絞めたりしています。その結果、消費者には価値の低い魚が高値で供給され、安くておいしい魚がますます手に入りにくくなるのです。
筆者は北欧を中心に世界各地の水産業の現場を回ってきました。ここでは現地で見聞きしたこととデータを組み合わせて発信しており、毎回多くの方に読んでいただき、好意的なメッセージや質問を頂戴しています。
ただ残念ながら、Yahoo!ニュースなどのコメント欄には少数の方々から誤解を広げかねない投稿が出てきます。そこで「う~ん」という評価が多かったコメントを拾ってみました。裏を返せば、ほとんどの読者が記事を正しく理解してくださっているということであり、うれしい限りです。
「海水温上昇のせい」「クジラが魚を食べ尽くす」「黒潮大蛇行のせい」など、科学的に矛盾を含むコメントは多数ありますが、まずは事象が正しく理解されていない「魚が獲れなくなったのは外国のせいなのか?」について考えます。
なお、これらの要因にまったく問題がないと言っているわけではありません。筆者が強調したいのは、本質的な問題が資源管理制度の不備にあるという点です。
なぜ外国漁船を悪く言わないのか?
そもそも魚が減っているのは、科学的根拠に基づく資源管理が行われていないことが根本的な原因です。根拠がない外国漁船への批判は、日本が「公海自由の原則を主張」してきた漁業の歴史などをたどられたりすると、批判どころか「巨大なブーメラン」がかえってくるでしょう。
歴史は繰り返します。必要なのは科学的根拠に基づく国別漁獲枠の設定です。もちろん EEZ(排他的経済水域)内への侵入など密漁は別問題ですが、日本は他国を非難できる立場にありません。魚が消えていく深刻な問題は、日本を下げるか上げるかという次元の話ではありません。
ちなみに筆者は日本人であり、外国から報酬を得て記事を書いているわけではありません。以下、よく見かけるコメントについて解説します。
よくあるコメントその1
「日本が取りすぎというのは誤り。日本が減らした分を他国が取っている」「公海での中国・韓国・ロシアの大型漁船による乱獲が原因」
もっともらしい主張ですが、瀬戸内海(愛媛県)の漁獲量推移と全国の漁獲量推移を比較すると、どちらもほぼ同じカーブで減少しています。瀬戸内海では中国・韓国・ロシアなど外国漁船は操業していません。もし外国漁船が主因であれば、瀬戸内海の漁獲量はこれほど減少しないはずです。サンマのように外国漁船が関係する魚種でも、俯瞰的に見ると問題の本質は外国船ではありません。
【画像】
https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/AA1JKGCc.img?w=768&h=754&m=6
ある全国紙にイカナゴ(コウナゴ)が瀬戸内海(大阪湾・播磨灘)で不漁なのは、温暖化でイカナゴを捕食する魚種が増加したためと出ていました。ところがそのイカナゴを捕食する魚種も含めて瀬戸内海の漁獲量は減っています。実際には資源管理の不備で生態系ごと破壊が進んでいるのです。こういった矛盾した報道が少なくないので社会の誤解が進んでしまいます。
「中国の数字は信用できない」?
よくあるコメントその2
「日本が漁獲量を守っても他国が取ってしまう」
一見その通りに思えますが、国際資源であるサンマの場合、実際の漁獲量を超える大きな漁獲枠が設定されています。昨年(2024年)、日本のサンマ漁獲枠は9万トンで、実漁獲量3万9千トンを大幅に上回りました。枠があっても、そもそもサンマがいないため獲り切れないというのが実態です。
一方、中国・台湾などは漁獲枠13万5千トンに対し14万5千トンで漁獲を切り上げています(1割弱の超過)。ノルウェーサバの枠消化は10%の凸凹は認めています。日本の漁獲枠は資源を守る仕組みとして機能しているのでしょうか。
「中国の数字は信用できない」
そう思う方もいるでしょう。しかしながら日本と資源を共有しているマサバ、マイワシ、スルメイカなどで少ない数量を申告する可能性は低いです。なぜなら、これから過去の漁獲実績に基づき国別の漁獲枠配分交渉がはじまることが予想されます。その際に実績を過少申告すれば、交渉が不利になるからです。
もっとも、漁獲量が漁獲枠に達するような状況では、ごまかしが起きる可能性があります。厳格なペナルティの設定が必要です。歴史は繰り返します。昨年(2024年)の公海上でのサンマ漁は中国・台湾などが枠に達しました。こういう時は注意が必要です。
ちなみに日本は、1977年に各国が200海里漁業専管水域(EEZ)を設定した際、アメリカなどの漁場から締め出されました。当時、日本の数字がまさに漁獲枠を誤魔化して過少申告していると取られていたのです。
漁獲枠が科学的根拠に基づく国別の漁獲枠が設定された際には、各国の漁獲量は資源の持続性のため厳格に管理されなければなりません。
漁獲量減少が韓国のせいではなかった例
北海道日本海側のスケトウダラ漁獲量推移を見てみましょう。当時、資源の減少は韓国漁船の漁獲が原因といわれていました。韓国漁船の漁獲量は赤丸期間の「オレンジ色」の部分です。確かに韓国漁船は一定量を取っていましたが、漁獲量の大半は日本漁船でした。
「中国の数字は信用できない」
そう思う方もいるでしょう。しかしながら日本と資源を共有しているマサバ、マイワシ、スルメイカなどで少ない数量を申告する可能性は低いです。なぜなら、これから過去の漁獲実績に基づき国別の漁獲枠配分交渉がはじまることが予想されます。その際に実績を過少申告すれば、交渉が不利になるからです。
もっとも、漁獲量が漁獲枠に達するような状況では、ごまかしが起きる可能性があります。厳格なペナルティの設定が必要です。歴史は繰り返します。昨年(2024年)の公海上でのサンマ漁は中国・台湾などが枠に達しました。こういう時は注意が必要です。
ちなみに日本は、1977年に各国が200海里漁業専管水域(EEZ)を設定した際、アメリカなどの漁場から締め出されました。当時、日本の数字がまさに漁獲枠を誤魔化して過少申告していると取られていたのです。
漁獲枠が科学的根拠に基づく国別の漁獲枠が設定された際には、各国の漁獲量は資源の持続性のため厳格に管理されなければなりません。
漁獲量減少が韓国のせいではなかった例
北海道日本海側のスケトウダラ漁獲量推移を見てみましょう。当時、資源の減少は韓国漁船の漁獲が原因といわれていました。韓国漁船の漁獲量は赤丸期間の「オレンジ色」の部分です。確かに韓国漁船は一定量を取っていましたが、漁獲量の大半は日本漁船でした。
よくあるコメントその3
「中国の数字は信用できない」
そう思う方もいるでしょう。しかしながら日本と資源を共有しているマサバ、マイワシ、スルメイカなどで少ない数量を申告する可能性は低いです。なぜなら、これから過去の漁獲実績に基づき国別の漁獲枠配分交渉がはじまることが予想されます。その際に実績を過少申告すれば、交渉が不利になるからです。
もっとも、漁獲量が漁獲枠に達するような状況では、ごまかしが起きる可能性があります。厳格なペナルティの設定が必要です。歴史は繰り返します。昨年(2024年)の公海上でのサンマ漁は中国・台湾などが枠に達しました。こういう時は注意が必要です。
ちなみに日本は、1977年に各国が200海里漁業専管水域(EEZ)を設定した際、アメリカなどの漁場から締め出されました。当時、日本の数字がまさに漁獲枠を誤魔化して過少申告していると取られていたのです。
漁獲枠が科学的根拠に基づく国別の漁獲枠が設定された際には、各国の漁獲量は資源の持続性のため厳格に管理されなければなりません。
漁獲量減少が韓国のせいではなかった例
北海道日本海側のスケトウダラ漁獲量推移を見てみましょう。当時、資源の減少は韓国漁船の漁獲が原因といわれていました。韓国漁船の漁獲量は赤丸期間の「オレンジ色」の部分です。確かに韓国漁船は一定量を取っていましたが、漁獲量の大半は日本漁船でした。
韓国漁船の排斥が求められ、ようやく1999年に出て行くことになりました。漁獲量の減少は、韓国漁船が原因とされていたので、当然1999年以降は、漁獲量が回復するはずでした。ところが、1999年以降の漁獲量推移は、期待されていた回復どころか激減。原因は韓国漁船ではなく、日本漁船の獲り過ぎだったのです。
スルメイカの漁獲量の落ち込みは深刻です。そこで減った理由に出てくるのが中国や韓国漁船の乱獲です。スルメイカは漁獲枠が大きすぎて全く機能していません。ところで悪いのはすべて外国漁船なのでしょうか?
ある国のイカ漁の記事があります。「地元に脅威〇〇イカ船団」「略奪に渦巻く非難」「根こそぎ包囲網に不安」「反感抑え紳士的警告」「ナイター並みの照明」「乱獲の反省と節度」「進出2年でもう不漁」「獲り過ぎかなと漁労長」
◯◯はどこの国と想像されますか?
実は〇〇は「日本」なのです。出所はニュージーランド沖での日本漁船のイカ漁に関する1974年の朝日新聞でした。当時は1977年の200海里漁業専管海域設定の前でした。それで日本漁船が12マイルもしくはそれ以内の好漁場に入って漁ができたのです。同国にとって日本漁船は脅威でした。また米国や他の国々の沖合においても漁獲能力が極めて高い日本漁船は脅威でした。それが、今では中国船に切り替わっているのです。
なお本文の主旨はどこの国が悪いというということではありません。国際的な視点で漁業を見ると、国が変わるだけで、まさに「歴史は繰り返す」なのです。漁業の歴史に関する基本的なことを知らないで他の国を批判ばかりしてしまうと、事実を知ると唖然としてしまうことになるでしょう。
こういった歴史的な背景が一般に紹介されるケースが少ないために、なぜ外国漁船のことを書かないのか?という単純な疑問につながってしまうのです。
なお筆者の目的は日本の水産資源を持続的にすることです。外国漁船を批判する内容を書いていない理由は、自国の資源管理制度を改善せずに他国に責任転嫁しても何も解決しないからなのです。
|
|
|
|
最新投稿・コメント全文リスト コメント投稿はメルマガで即時配信 スレ建て依頼スレ
|
|
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。