|
<■151行くらい→右の▽クリックで次のコメントにジャンプ可> 今読んだばかりの「戦闘教師ケン」氏のブログ記事が面白かったので転載する。
つまり、我々は自分自身の経験すら覚えておらず、自分の同時代の社会的実情を回想の中で美化する傾向があり、それが一部の「保守」や「愛国思想」を僭称する政党や論客に利用されがちだということだ。
念のために言えば、私は「三丁目の夕日」や司馬遼太郎の著作群自体には罪はないと思っており、それらは優れた作品だと思っている。また、政治的には基本的に保守主義である。(以下引用)「若苦しさ」というのは誤記だろうが、何の誤記だろうか。 2012年07月13日
『三丁目の夕日』はプロパガンダか幻想か?
とある議員がまたぞろ『三丁目の夕日』を持ち出して、「今の日本もあの頃のように皆が希望を持つ国に……」云々と言い出したものだから、思わずキレそうになってしまった。
こんな年になっても若苦しさが抜けず、我ながら困ったものだが、どうにも性分らしい。
自民党も民主党も同じだが、どうも最近の国会議員は歴史的経緯や成立のプロセスをきちんと検証しないで、思い込みだけで論じる傾向が強すぎる。ハッキリ言えば、国会議員としての識見もなければ、それを補うべく勉強する姿勢すら見せないのである。
こうした思い込みが、著作権法の改悪や児ポ法、あるいは生活保護法における扶養義務の強化や地方における青少年外出禁止条例となって現れているわけだが、そのどれもが結局のところ自由や表現手段を奪っていることに議員は自覚的でなく、官僚ばかりがほくそ笑んでいる始末になっている。
『竜馬がゆく』『坂の上の雲』『三丁目の夕日』は昭和の三大プロパガンダと呼んでも良い作品だと考えている。
『竜馬がゆく』は日本版『鋼鉄はいかにして鍛えられたか』であり、『坂の上の雲』は『中国の赤い星』に対応している。
ただ『三丁目の夕日』に対応するような、「共産主義時代は良かった」式の小説や映画はすぐに思い浮かばないが、これは単純に私の教養不足であろう。だが、現代ロシアでは帝政時代を美化し懐かしむような時代小説が一部の人気を博しているとも聞く。 『三丁目の夕日』は私も一時期連載を読んでいたことがあるし、映画はテレビで部分的に見た。すぐにチャンネルを変えてしまったが。
この作品については、かなり多くの批判的レビューが出ているので、今更私ごときが何か言うのも遅すぎかもしれないが、具体的な数字や事例を挙げながら、私なりの解釈を示しておきたい。
「昭和」に郷愁を覚える層に共通するのは、 ・治安が良く、誰もが安心して暮らせた。
・自然が豊かで、空がまぶしかった。
・家族が仲良く暮らし、子どもの虐待など無かった。 といったものだが、全部大ウソ!!
治安・犯罪から行こう。
『三丁目の夕日』の舞台は1955年から64年くらいまで、昭和30年代である。
1960年と2005年の暴力犯罪数(認知件数)を比較してみよう。 殺人:2650件 → 1350件
強姦:6350件 → 2080件
傷害:6万8300件 → 3万4500件 となっている。強盗や放火についてはほぼ同水準を維持している。
ただし、総人口は60年には9430万人だったものが、05年には1億2780万人に増えている。
人口が3割も増えた一方で、主要暴力事件は半分以下になっているのである。
1970年くらいまでの日本は、今からは想像も付かないほど危険な社会だった。
暴力性に限って言えば、『仁義なき戦い』に描かれたものの方が、よほど社会の実情に即していたと言えよう。
女性や子どもが夜に外を歩くなど、もっての外だったことは、すっかり忘れ去られている。 「自然が豊か」など、どこから来たイメージなのだろうか?
第二次世界大戦における物資不足で、日本政府は燃料を確保するために、際限なく木を切り倒し、根こそぎ動員していったため、山という山は禿げ山になってしまった。そのせいで、戦後しばらくは水害が起きると大災害となり、何千人という死者を出していた。
例えば、1959年に上陸した伊勢湾台風による死者は4700人で、阪神淡路大震災にも匹敵する被害を出しており、台風ごとに何百人もの死者が出るような始末だった。
今日では、死者が二桁に上ると、政府や自治体が批判にさらされることを思えば、隔世の観がある。
政府が災害の原因を認識し、植林政策を進めるのは60年代半ばのことであるが、今度は無原則的に「産業に役立つ」という理由で杉ばかりを植え、その管理には手を抜いたため、90年代以降、花粉によるアレルギーが国民に拡大していった。
伐採による災害も、植林による病害も、元凶は人災だったのである。 もう一つ指摘されるべきは公害問題だ。
水俣病が認知されるようになったのは、ちょうど50年代半ばのことであり、胎児性水俣病患者が初めて認知されたのは1961年のことだった。
だが、日本政府がチッソ工場から出た廃液と病気の因果関係を認めたのは1968年のことであり、その年まで廃液は垂れ流されていた。
水俣病患者に対して保証金が支払われ始めたのは1973年のことで、住民はそれまで20年以上に渡って一方的な公害被害にさらされ続けた。
さらに言えば、日本政府が水俣病発生について責任を認めたのは1995年の村山内閣のことだった。 「空が美しかった」などというのも大ウソで、大都市近郊や工場地帯では、工場からの煤煙や自動車の排気ガスで空が真っ黒になり、大気汚染によるぜんそく被害が急速に拡大していった時期でもあった。特に川崎、四日市、尼崎などはぜんそく被害が深刻で、あの自民党が環境庁の設置を認めざるを得なくなったきっかけになった。
団塊ジュニアに相当する私くらいの世代でも、子どもの頃は夏になると「光化学スモッグ注意報」が出て、休み時間などに外に出ることを禁じられたものだった。 川なども生活排水や工場排水が入り乱れ、何の規制もないために、酷い有様だった。
都市部を通る大きな川は、皆どす黒い水が流れ、周辺は異臭が漂っていた。
私が子どもの頃でも、多摩川で採ったり釣ったりした魚には奇形が多かった。多摩川がきれいになり、鮎などが戻ってきたのは、ここほんの10年程度の話に過ぎない。 道路は幹線道路を除いて舗装されておらず、雨が降ればぬかるみとなって、足をドロドロにして歩かされたし、車が通れば真っ黒な排気ガスが大量に吐き出されて咳き込まざるを得なかった。
電車は電車で東京などは殺人的な混み様の上、ノロノロ運転で、ラッシュ時の新宿では山手線や中央線などは何本も待たないとならない有様だった。 「家族が助け合って」とか「親子の情愛が深かった」などというのもウソである。
嬰児殺(赤ちゃん殺し)の被害者を見ると、最も多かったのは1950年の321人で、60年代は150〜200人で推移している。が、最近は年20人前後で落ち着いている。
親殺しについては、1956年が134件で、60年代は70〜90件の間で推移している。この数字は90年代以降また増えて、最近は120件前後で推移しているが、これは高齢化に伴う介護疲れによる老々殺人が増えているという特殊性がある。
検察庁に送検された売春従事者の数は、1959年には1万8600人を記録しているが、2007年にはわずか1060人でしかない。
50年代や60年代は、明治や戦中のマチスモが濃厚に残っており、配偶者に対する暴力などそもそも犯罪として認められなかったため、統計にすら上っていない。
大家族の中で「嫁いびり」のような陰湿な虐待が普通に存在した一方で、近代的な教育が普及して、都心部に労働需要が生じたために、多数の女性が喜び勇んで田舎を捨てて都会に出て行ったのである。しかし、都会に出てはみても、その労働環境は劣悪で低賃金による長時間労働を強いられたが、田舎に帰りたくない一念で女性は耐え続けていた。
東北などからは貧しい家の子どもは、中学を卒業すると臨時夜行列車に乗せられて都市部の工場へと送られ、劣悪な環境と低賃金の下で労働に従事させられた。俗に言う集団就職である。中には中学校の教員が引率していた例もあり、半ば国策的な労働力動員であったことが伺われる。 さて、もう十分だろう。
日本の50〜60年代というのは、米帝の指導を受けた霞ヶ関の主導の下で、第二次世界大戦の総括をせぬまま、国民を犠牲にして経済成長を実現させていった時代だった。
程度の差は大きいが、数千万の農民を犠牲にして工業化を実現した30年代のソ連にも似ている。
大企業を優遇して生産を拡張しつつ、災害や公害は放置し、他方、政治的には60年安保を見れば分かるとおり、右翼や暴力団を武装動員してデモ隊を攻撃させ、横道に逸れたデモ隊員は次々と警官に逮捕され、留置所に送られていったのである。
日本のこの時代は、むしろ『日本の夜と霧』や『仁義なき戦い』にこそ象徴されるべき暗黒の時代だった。 にもかかわらず、郷愁を覚える高齢者が多いことも確かである。
これは、暗黒の時代を生き延びた高齢者たちが、経済成長の果実を得られたものたちだったことは一因であろう。
また、人間にはそもそも都合の悪いことを忘れる機能が付いている。ショックを受けた時に気絶して、しかも記憶を失ってしまうことがあるのも、そういう機能の一つだ。
これが機能しないものは、早めに命を落としてしまいがちだ。
私のように暗黒面から目を離せない人間は長生きできないようになっているのである。
つまり、暗黒時代を生き延びたものたちは、都合の良い記憶だけが残り、暗黒面は記憶から欠落している可能性も十分にある。
ただ、犯罪について言えば、かつては治安の良い場所と悪い場所の境界がハッキリしており、いわゆる「悪所」では今日では想像も付かないほどの劣悪な治安環境にあったことはあるかもしれない。 「当時は希望に満ちあふれていた」という回顧は良く聞くが、当時の総合雑誌や新聞の社説を見る限り、 「激化するインフレ」「激増する犯罪」「再軍備に向かう日本」「共産主義の脅威」「台風犠牲者4千人超」「米ソが核実験」「第三次世界大戦はいつ勃発するか」 など暗いテーマばかりが並んでおり、およそ老人たちの回顧と違う。
この点では、ソ連の雑誌の方がよほど楽観的だ。 そして、私が「ロシアの高齢者の多くは、ソ連時代を懐かしがっていますよ」と言うと、「ウソだ〜」「あり得ない」などといった反応が普通に返ってくるくせに、自分たちの国については恐ろしく幻想的な過去を平気で信じていることは、まったくもって理解しがたいことである。
色々考えるのだが、『三丁目の夕日』は単なるプロパガンダなのか、日本のプチブルのノスタルジーなのか、にわかには判別しがたいものがある。
読者諸兄の御意見を伺いたいところだ。
|
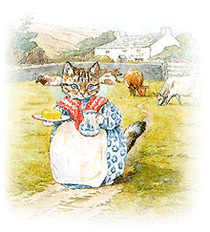
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。