<Vol.347:新年号2弾:Q&Aで解く、
マネタイゼーションの正と負の効果(2)> テーマ:財政ファイナンスとマネタイゼーション
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・
HP: http://www.cool-knowledge.com/
無料版の登録/解除: http://www.mag2.com/m/0000048497.html
有料版の登録/解除: http://www.mag2.com/m/P0000018.html
感想/連絡:yoshida@cool-knowledge.com
Systems Research Ltd. 吉田繁治
42791部 おはようございます。新年の2号目です。1号(1月2日送信)では、
Q&Aの形式で、2つのことを述べました。 最初に、それを振り返って、次の質問と回答に移っていきます。 本稿では、半ば以降で、マクロ経済の基本的な、GDPの三面等価と、
ISバランスの原理を使います。少し難しいところがありますが、論
理をたどれば、理解は進むでしょう。わが国のこれからの経済で、
もっとも重要なことに思えます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <Vol.347:新年号2弾:Q&Aで解く、
マネタイゼーションの正と負の効果(2)> 2016年1月10日:無料版 【目次】 1.前号の、2つの質問と回答を振り返ると
2.Question 2:
日銀が国債を買い切れば、政府の債務はなくなるという説
3.Question 3:
日銀はいつまでも、国債の買いを行うことができるのか
4.日銀の国債購入とインフレの関係
5.問題は、高齢化により家計貯蓄が減少していること
6.2020年の想定
7.2020年以降はどうなるか 【後記:負債性のマネー】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■1.前号の、2つの質問と回答を振り返ると ▼Question 1:
政府の債務超過(476兆円:14年3月)への回答 【過去の債務超過は問題ではない】
政府の貸借対照表(B/S)の債務超過で問題になることは、現在の
負債に対する資産不足である476兆円ではありません。 476兆円の債務超過になっていること自体が、大きな債務超過であ
っても、低利の国債の買い手があって、乗り越えられてきたことを
示すからです。(2014年3月末)。 資産の引き当てのない累積赤字が、売上(国ではGDP:500兆円)に
匹敵するくらい大きいのに、銀行団が融資を続けてきた企業と同じ
です。
https://www.mof.go.jp/budget/report/
public_finance_fact_sheet/fy2013/national/hy2013_gassan.pdf 【問題は、これからの財政支出の赤字】
この債務超過は、ほぼ30年間、政府の税収より財政支出が大きかっ
たことから来たものです。赤字額は、年平均で31兆円です。これを
基礎的財政収支、またはプライマリーバランスの赤字と言っていま
す。 財政支出が同じなら、税収が31兆円(GDPの約6%)増えない限り、
債務超過は増え続けます。31兆円は、消費税の純収入(輸出の消費
税還付を控除)に換算すると、ほぼ15%分です。 傾向では、476兆円が1年にほぼ31兆円ずつ増え続けます。問題にな
るのは、この債務超過がどこまで可能かということです。 これは、金融機関と日銀が、低い金利の国債をどこまで買い続ける
かにかかっています。国債の金利は、2016年1月では以下です。
(財務省) ・3年債 -0.014%
・5年債 0.016%
・10年債 0.245%
・20年債 0.958% 4年債以下は、日本でもマイナスの金利です。日銀が発行額面を超
える価格で買ったことを示すものです。100万円の1年債を100万
1000円で買えば、金利は100万1000円に対してほぼ−0.1%になりま
す。 10年債はプラス0.245%、20年債でも0.958%という低い金利です。
これは、80兆円/年の国債を買う異次元緩和によって、人為的に作
られている超低金利です。 国債の残高が1024兆円(15年12月)と多いことが理由で、10年債の
国債の金利が、ほぼ3%に上がると、国債の発行が困難になって行
きます。 金利が上がることは、国債が売れにくいことを示します。買い渋っ
ている市場に、新規国債の投入を増やせば、一層売れにくくなって、
金利が高騰するからです。 【分岐点は、財政赤字の方向】
10年債の金利で言うと、3%付近が、わが国の財政が、破産に向か
う分岐点になるでしょう。 ・5兆円/年(GDP比1%)くらいずつ、基礎的財政収支を減少させる
傾向なら、金利は上がらず、大丈夫でしょう。 ・年31兆円の財政収支の赤字が増えるか、減らない傾向なら、
2018年から2020年に、金利が上がる時期が来るでしょう。 金利が上がる理由は、増え続ける債務超過に、国債を買う金融機関
がリスクを感じるからです。 リスク率は、回収を保証する保険であるCDS(クレジット・デフォ
ルト・スワップ)の保険料率と等しい。CDSの証券は、金融機関の
間で売買されています。2016年1月では50ベーシス・ポイント、つ
まり0.5%です。
http://www.bloomberg.co.jp/apps/cbuilder?T=jp09_&ticker1=
Cjgb1u5%3AIND FRBが利上げをほぼ決めた2015年11月から、円国債のCDSが上がり始
めました。CDSの料率(販売されるときの価格)が2%くらいに上が
ると危険になります。その時は、国債の金利が、低くても3%に上
がるからです。 ■2.Question 2:日銀が国債を買い切れば、政府の債務はなくなる
という説 前号の2番目の質問について:政府の債務は日銀の買いによってな
くすことができるというリフレ派のT氏やH氏などのエコノミストが
いますが、これは本当のことかというものでした。 【回答】
政府と日銀のB/Sを連結した「統合政府」で見た場合、国債は消え
ても政府の債務が消えるのものではありません。日銀が買った国債
は、「日銀当座預金」という負債に振り替わっているからです。つ
まり政府の負債が、日銀の負債に振り替わっています。 日銀当座預金は、金融機関が、日銀内にもつ準備預金の口座です。
われわれの預金が、金融機関にとって負債であるように、日銀当座
預金は、統合政府(借り手)の金融機関(貸し手)からの負債です。 政府と日銀を内部取引と見れば国債は減ります。しかし日銀の当座
預金という債務が同じ額増えていますから、政府の債務が減ったわ
けではない。 現在10年債の金利が0.3%で、日銀当座預金の金利は0.1%です。日
銀が国債を買って、それを日銀当座預金に振り替えることにより、
政府は0.2%分の金利支払いを節約することはできます。 現在実行されている「異次元緩和」が、将来にわたって可能かどう
かは、次の質問と関連します。その回答の中で考えましょう。 ■3. Question 3:日銀はいつまでも、国債の買いを行うことがで
きるのか これが、今回のテーマです。相当に難しいことを考えねばなりませ
ん。 ▼質問3:日銀は、異次元緩和として、1年に80兆円の国債を買い増
して、ほぼ80兆円の当座預金を増やしています。 英国の経済学者、ディール・ターナー氏も、「日本は、紙幣増刷
(実際は日銀当座預金の増加)を恐れる必要はない」という論評を
寄せています(日経新聞 経済教室)。 インフレ目標2%を達成したあと、出口政策、つまり日銀が買って
きた国債を売ってマネーを吸収しようとすると、それは金融の引き
締めになるので、債券市場の金利が高騰し、国債価格が暴落する恐
れがあります。 (注)債券市場は、国債が売買されている市場です。1か月で約
756兆円の売買があります(2015年11月:日本証券業協会)。平均
すればほぼ全部の国債が、1.2か月1回は売買されている(年間10回
転)という大きさです。国債は長期保有されてはいない。このため、
国債のリスク率上昇から金利が上がるときは、数か月の短期間でも
大きく上がります。 国債価格が暴落すれば、債券市場の金利を一層上げる新規発行が困
難になって、資金不足の政府が、デフォルトや市払いを遅延させる
という「財政破産」に向かうでしょう。 このため日銀は、インフレ目標(2%)を達成したあとも、国債の
買いを止めることはできないという「出口政策不可能論」もありま
す。 日銀が、インフレ目標達成のあとも量的緩和をずっと続ければ、大
きなインフレにはならないでしょうか。可能性は否定できないよう
に思えるのですが・・・ 【回答】
この問題については、まだ、明確には答えられてはいません。起こ
っていないことについて述べるのは、想像力を要するからでしょう。
微力をかえりみず答えようと思います。 インフレになって期待金利が上がらないなら、確かに、紙幣増刷を
恐れる必要はない。しかし、以下で書くメカニズムでインフレンに
なり、それとともに、期待金利が上がって行くでしょう。 ■4.日銀の国債購入とインフレの関係 【いつからインフレになるのか】
まず、「日銀が国債を買い続け、国債を当座預金に振り替え続けた
場合、インフレになるのは、どういった原理で、いつからか」を考
えます。インフレは債券市場の期待金利を上げて、国債価格を大き
く下げるからです。 ▼原理:GDPの三面等価 → 生産=所得=需要(消費)から 国債の発行額が、企業と世帯の預金の増加(貯蓄の増加額)と見合
っている間は、インフレは起こりません。 マクロ経済には、「GDPの3面等価」という基本的な原理があります。
生産と所得、そして需要は一致します。つまり〔生産=所得=需要
〕です。需要は消費でもあるので、〔生産=所得=消費〕です。 【貯蓄は消費の先延ばしであり、貯蓄分の消費が減る】
しかし、所得のすべてが消費されているわけでない。所得を使わな
い貯蓄があるからです。
この貯蓄を入れれば、〔所得=消費+貯蓄〕です。 経済の全体(マクロ経済という)では、貯蓄された分、消費が減り
ます。つまり貯蓄の分、生産された商品が売れ残るという事態が起
こります。100の生産と所得のとき20が貯蓄されると、20の商品が
残ります。売れ残れば、次の生産や仕入れが減ります。これが不況
です。 不況とは、その国の生産力以下の消費しかないことを言います。
260万社の企業で言えば、それが生産した商品、仕入れた商品が売
れ残るということです。住宅建設も、住宅という商品の販売です。
工作機械も同じです。 では経済は、ここで、どうやって均衡しているのか。均衡とは、生
産=所得=需要(消費)になることです。 【生産と需要(消費)の均衡】
貯蓄を預かった銀行が貸付をし、その貸付によって、設備投資や住
宅購入が起こることによってです。つまり、貯蓄は何らかで使われ
ます。国内で貯蓄の余剰があるときは、その分が海外に資本流出し
ます。貯蓄増加=借入増加+海外流出、です。 借り入れをして使われる対象は、多くの場合、1年以内で消費する
商品ではなく設備、建築、機械なので、投資ということにします。
以下のとき、経済は均衡します。 生産=所得=消費+貯蓄
=消費+貯蓄の借り入れによる投資(国内+海外) 増加する貯蓄が、企業や世帯または政府によって借り入れられて、
借り入れで投資または消費がされるとき、経済は均衡します。上記
の式のときは、好況でも不況でもない。つまり、「GDPの自然成長
率」の状態です。以上が、概念です。以降では、数字で言います。 ▼具体的な数値で言えば・・・ 【企業と世帯の貯蓄(=資金余剰)】 (1)企業部門:
日銀の資金循環表で見ると、企業の貯蓄の増加(つまり資金余剰)
は2014年度で約110兆円です。2000年代は、企業部門は、〔税引き
後純益+減価償費=営業キャッシュフロー〕を下回る投資しかせず、
資金余剰部門になっているのです。
(注)図表2-2の民間非金融法人と家計の資金過不足の、長期傾向
を見てください。
http://www.boj.or.jp/statistics/sj/sjexp.pdf 260万社の合計では、借り入れの増加による設備投資はないという
ことです。これが、ここ20年、わが国の経済が成長していない、根
本の理由です。 年間では、260万社の企業部門の、貯蓄の増加(資金余剰)が、ほ
ぼ10〜20兆円あります。年間の営業キャッシュフローが留保され、
使われていない分がこれです。 (2)5300万世帯の家計部門:
家計の貯蓄の増加は、
・1990年代には、30兆円から40兆円はありましたが、
・2000年代からは、高齢化と定年退職の増加のため、年20兆円レベ
ルに減っています。 (1)と(2)から、260万社の企業部門と5300万世帯の合計で、1年
間に、30兆円〜40兆円の貯蓄(資金余剰)が生じています。 この30兆円から40兆円が、金融機関が国債を買っている資金になっ
ているのです。 【現在の均衡】
貯蓄(=資金余剰)と投資のバランスを、ISバランスと言っていま
すが、具体的な数値では以下です。 わが国の資金余剰(30〜40兆円)
=国債増加(35兆円)+海外への資本流出(10兆円) 文章で言えば、
・企業部門と世帯の資金余剰の増加(30〜40兆円)は、
・政府の国債の増加(35兆円)と、海外への資本流出(10兆円:経
常収支の黒字=資本収支の赤字)で、均衡しているということです。
これがISバランスです。 年間35兆円の新規国債は、元々のところでは、企業と世帯の資金余
剰(つまり消費不足)によってファイナンスされてきたのです。こ
のため政府が国債を原資に公共事業を行っても、インフレの要因で
はなかったのです。 (注)国債を直接に買っているのは金融機関です。国債を買う原資
になっているのは、金融機関が預かった、企業と世帯の資金余剰
(貯蓄の増加)です。 〔不況:物価は下がる〕
貯蓄の増加分が、借り入れられて使われないときは、生産物が売れ
残る不況になり、物価は下がる傾向になります。国全体では、「生
産>需要」になるからです。 これが、「生産=需要」になるには、商品価格が上がらねばならな
い。 〔好況:物価は上がる〕
逆に、貯蓄の増加分以上が、借り入れられて使われるときは、生産
物が足りない好況になり、物価は上がる傾向になります。国全体で
は、「生産<需要」になるからです。 これが「生産=需要」になるには、商品価格が下がらねばならない。 ここでやっと、インフレとの関係に至りました。 ■5.問題は、高齢化により家計貯蓄が減少していること わが国の問題は、高齢化のため、家計の貯蓄率が低下していること
です。世帯の貯蓄率(=貯蓄/所得)の低下は、国債をファイナン
スしてきた原資が減ることを意味します。 ・2015年現在は、1990年代の40兆円から減ったとはいえ、20兆円レ
ベルである家計の貯蓄が、
・2020年ころには、ほぼゼロに向かいます。 65歳以上の年金世帯は、平均して月6万円(年間72万円)の預金を
取り崩して消費しているからです。 世帯の年金は平均で20万円です(夫婦2人分)。年金では生活費に
足りず、現役の時に貯めてきた預金の取り崩しを月6万円行って、
1か月に使うのは26万円です。 1世帯平均で約20万円の年金(国民年金、厚生年金)を受給してい
る人は、3950万人に増えています。働く現役世代の50%に相当しま
す。 年金世帯の預金取り崩しが、合計では1年に12〜14兆円もあるため、
5300万の世帯の合計貯蓄が減ってしまうのです。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/h25_5.pdf 【2018年と2020年の想定】
2018年頃は、
・世帯部門の貯蓄の増加は、年10兆円以下に減るでしょう。
・企業部門の資金余剰も10兆円に減っていると想定できます。 2020年には、20兆円の家計の貯蓄の増加が、ゼロになる可能性が高
い。企業の貯蓄のみになれば、国全体の貯蓄は10兆円程度に減って
しまうのです。(注)企業は、借り入れで投資すするので普通は資
金不足部門になります。ところが1995年以降は、借り入れと投資を
減らしたため、資金余剰部門になっています。 【2018年頃から、インフレになっていく】
3年後の2018年に向かい、政府が35兆円の新規国債を発行して公共
事業を行い続けると、〔生産力<消費+国債による借り入れでの政
府投資・消費〕になるため、物価が上がるようになって行きます。
現在は上がっていない物価が、2017年、2018年ころから、上がるよ
うに変わるのです。 赤字の公共事業のため、国の生産力を上回る需要になると、物価が
上がることで調整されるからです。10兆円の需要超過があると物価
は2%上がり(GDPの2%)、15兆円なら3%、20兆円なら4%は上が
ります。 (注)国の総貯蓄が10兆円のとき、政府が35兆円の国債で財政支出
を行うと、25兆円の需要超過になって、結果は4%のインフレが想
定されます。 【インフレになると、金利が上がる】
理論的な金利は、〔期待金利率=実質GDPの期待成長率+物価上昇
率〕、です。 実質GDPの期待成長は、例えば0.5%でしかなくても、人々の期待物
価上昇率が3%に上がると、債券市場(金融市場)の期待金利は3.
5%に向かって上がります。 (注)期待金利が2%に上がるのが2018年、3.5%が2020年と想定し
ています。 【期待金利が上がると国債価格は下がる】
これは以下のように、既発国債の暴落を生みます。 金利0.3%の10年債で、残存期間(デュレーション)が7年のとしま
す。(注)わが国の、長短全部の国債の、満期までの平均期間は7
年です。 国債は、前述のように、1年に10回転するくらい激しく、売買され
ています。じっと持たれてはいない。平均保有期間は1.2ヵ月でし
かありません。 ▼物価上昇と期待金利 期待金利は、物価の上昇傾向を予想した上で、金融機関が要求する
金利です。国債をいくらで買うかで、期待金利が決まります。 金利は、日銀や政府ではなく、国債を買う金融機関が決めているの
です。〔期待金利=GDPの実質成長率+予想物価上昇率〕です。 物価が2%上がる傾向なら(予想物価上昇率が2%のとき)、国債を
買う金融機関は、国債に2%の利回りを要求します。
このため、既発国債は2%の利回りになるように、流通価格が下が
るのです。新発国債は、額面に対し2%の金利になります。 【期待金利と、発行済み国債の流通価格】
(1)期待金利が2%に上がったときの下落は、10.4% 国債価格=(1+表面金利0.3%×残存期間7年)÷(1+期待金利2.
0%×7年)=1.021÷1.14=89.6 → 10.4%下落 利回りが0.3%で額面100万円の国債は、価格が10.4%下がって89.
6万円になると、金利が2%に上がったことになります。
確かめます。 89.6万円で買った国債には0.3%(年間3000円)の金利がつき、7年
後に額面100万円の償還があります。
7年後の利回りは以下になります。 〔3000円×7年+差額10.4万円=12.5万円〕
〔12.5万円÷買った価格89.6万円=14%〕
〔14%÷7年=2%・・・年2%の利回り〕 89.6万円で買うと、額面に対して0.3%の金利でしかなかった国債
が、2%の利回りに変身します。国債を買う金融機関は、物価上昇
が2%になると、国債に2%の利回りを要求します。このため、2%
の利回りになるように、価格が下がるのです。 (2)期待金利が3.5%に上がったときの下落は、18.0% 国債価格=(1+表面金利0.3%×残存期間7年)÷(1+期待金利3.
5%×7年)=1.021÷1.245=82.0・・・18.0%下落 2015年末時点の、長短の国債の合計残は、1024兆円です(日銀資金
循環表)。
http://www.boj.or.jp/statistics/sj/sjexp.pdf 3年後の2018年には、期待金利2%が想定される中で、国債残は
1129兆円が想定されます。 国債の流通価格下落は、〔1129兆円×10.4%=117兆円〕にはなる
でしょう。 ■6.2020年の想定 5年後の2020年には、期待金利3%が想定され、国債残は1199兆円が
想定されます。国債の流通価格の下落は、〔1199兆円×18.0%に
216兆円〕なるでしょう。 重大なことを言えば、2019年には、BIS(国際決済銀行)の規制に
より、国際業務を行う銀行は、国債をリスク資産として時価計上し
なければならなくなることが想定されます(バーゼル4)。国債を
もっている金融機関にとっては、衝撃です。 ▼2018年ころから危険になる わが国では、政府が現在の財政赤字を続けると、日銀が国債を買い
続けるかどうかにかかわらず、2018年からは国債リスクの増加から、
期待金利が上がり、既発国債の価格が大きく下がって、金融機関と
日銀の、自己資本を消してしまう損害になります。 この時点では、日銀と金融機関は下がる国債を買い続けることはで
きなくなり、政府の国債が売れ残って、更に下がるという事態が予
想できるのです。 ▼日銀が国債を買うことのできる臨界点が来る つまり日銀がインフレになった後、いつまでも、国債を買い続ける
ものは、できないことです。もし行い続ければ、インフレ率はどん
どん高くなって、国債価格は一層大きく暴落するからです。 ■7.2020年以降はどうなるか 2020年以降になっても、日銀が異次元緩和の買い(年間80兆円)を
続けている場合、円の下落によって輸入物価(エネルギー、資源、
コモディティ)が上がり、物価上昇は二桁になる可能性があります。 そうなると、期待金利も10%を超え、既発国債(1199兆円)は、
40%も下がるでしょう。これは、財政の完全破産を意味します。 【ハイパー・インフレにはならない】
ただし一部で言われている物価が数百倍になるハイパー・インフレ
は、グローバル経済で輸出入が多い現在は起こりません。 ハイパー・インフレは、戦争や広範囲な疫病などで国内の生産力が
破壊され、通貨の増発が重なったとき、起こるものです。 なおそのときの通貨の増発も、1万円札の枚数を増やすのではない。
0を1個増やした10万円札なら、同じ枚数で10倍の金額が発行できる
からです。日銀が発行する紙幣の金額が10倍、100倍になるのがハ
イパー・インフレです。 論理的に、しかも数値を入れて実証的に述べたので、必要最小限の
ことを言っただけですが、回答が長くなりました。 結論を短くまとめれば以下です。 ・・・T氏及びリフレ派のエコノミストが言う「日銀はいくらでも
国債を買うことができる。財政破産も大きなインフレも起こらな
い」というのは、あからさまな偽説です。断言します。 ▼後記:負債性の通貨 日銀が、2013年4月以降行い続けている「異次元緩和」は、1年に
80兆円分の国債を、日銀の金融機関に対する負債である「当座預
金」に振り替える行為です。 このため、金融機関がもつ国債が減った分、日銀内の当座預金が増
えています(残高247兆円:15.12.22) 日銀当座預金は、現金と同等のものですから、国債が247兆円分日
銀によって買われ、この当座現金に振り替わっています(2015年
12月時点)。 拙著『膨張する金融資産のバラドックス』では、これを「負債性の
通貨」と定義しています。不換紙幣(法定通貨、管理通貨ともい
う)は、政府の財政信用をバックにし、政府の代理機関(通貨の
エージェント)である中央銀行が発行している負債性の通貨です。
本格的な論は、本書で読むことができます。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/482841858X/ref=s9_simh_gw_p14_d0_i2pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_s=desktop-1&pf_rd_r=1J1JEERAW29AJ4QMVCF5&pf_rd_t=36701&pf_rd_p=263612849&pf_rd_i=desktop 負債性通貨の信用の根源は、政府の財政の信用です。
(注)負債性ではない通貨は、金(ゴールド)です。
|
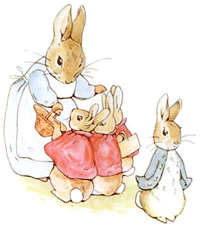
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。