内田樹 「英語教育について」2019-05-31
http://blog.tatsuru.com/2019/05/31_0824.html昨年の6月12日に東京の私学の文系教科研究会(外国語)」で行った講演録が出版された。「東京私学教育研究所所報」84号に掲載されているが、ふつうのひとはあまり手に取る機会がない媒体なので、ここに採録する。 ○司会者 今回は、ここ最近の外国語の文系教科研究会では例をみないほど多くの先生方にお集まりいただきました。6月の今ごろは、夏休みがそろそろ見えてきて、でもまだまだ遠くて、体力的にも精神的にもだいぶ苦しいころ合いだと思います。にも関わらず、これだけ多くの先生方が今回は集まってくださり、おかげさまで満員札どめとなりました。理由はたった1つです。今回、当研究会では、内田樹先生をお招きして講演会を開催できる運びとなりました。忙しくても体力的にきつくても、この方の話ならば何としても聞きたい、それが内田樹先生ではないでしょうか。 内田先生は、現在は神戸女学院大学名誉教授であるとともに、神戸市で武道と哲学研究のための学塾「凱風館」を主宰していらっしゃいます。もともとのご専門はフランス現代思想ですが、武道論、教育論、映画論、文学論、漫画論などなど、実に多くの専門領域をおもちで、あらゆる領域について、あらゆる人に、万人に届く言葉を発信していらっしゃいます。 内田先生の言葉の特徴は「届く」ということだと思っております。一見複雑で込み入った情況であっても、それについて内田先生が書かれた文章を読むと、目の前の混沌にさっとマップがかかり、そこにおいて自分がどのように歩みを進めていけばいいのかがすっと理解される。内田先生のご著書を読んで、そのような経験された先生方も多いのではないでしょうか。 内田先生の文章を読むと、そこに書かれた内田先生の言葉が、もともと自分のいいたかったことを言ってくれた、と思える経験がよくあります。実際はそんなことは考えたこともなかったことなのに。そんな風に、言葉が、読んでいる自分の内側にまで届いて、響くのです。また、言葉というもの、読書というものは、本来そのようなメカニズムやダイナミズムをもっているのだ、ということも、実は、内田先生から私は学ばせていただきました。 フランス現代思想がご専門ということもあり、言語というものに実に造詣の深い内田先生に、本日は「英語教育の危機」という演題のもと、激動期、大変革期といってもいい現在の英語教育界について、それから、英語に限らず、言葉を学ぶ、教えるとはどういうことかについて、存分に語っていただこうと思います。 それでは、内田先生、よろしくお願いいたします。
○内田 過分のご紹介にあずかりました。内田でございます。
一日の仕事が終わった後の、お疲れのところお集まり頂きまして、まことにありがとうございます。今、私が登壇する前に(公益財団法人東京都私学財団より外部検定試験料に関する)助成金の話がありましたけれども、実は今日もこちらに来る新幹線の車内で、「検証 迷走する英語入試」という、これは岩波のブックレットですが、これを読んでおりました。帯には、「緊急出版、混乱は必至」と書いてありますけれども、多分今の日本の教員の中で本当に最も困惑しているのは中高の英語の先生だろうと思います。本当にお気の毒だと思います。 本当にどうしてこんなことになってしまったのか、僕にはよくわからないのです。みなさんにもよくわからないのではないかと思います。これから民間試験が入試に導入され、センター試験の英語がいずれなくなるという流れになっていますけれども、どうしてこんなことが現場の英語教員たちの意向を無視して行われていくのか。誰に訊いても、よくわからないと言う。いったい、誰にとって、どんな利益があって、こんな制度改革を行うのか。 教育の目標は、子どもたちの市民的成熟を支援することに尽くされるわけですけれど、こんな制度改革で、子どもたちがどういう利益を得ることになるのか。子どもたちの知性的な成熟にこの改革がどう資するという見通しがあって、こんな改革を進めているのか、全くわからない。 今回のことに限らず、日本の外国語教育は迷走し続けています。そもそも何のために外国語を学ぶのかという根本のところについての熟慮が不足しているからです。もちろんここにいる先生たちこそ、まずそれについて考えなければいけない立場ですけれども、日々の業務から、このような猫の眼のようにくるくる変わる制度改革にキャッチアップすることに手いっぱいで、「子どもたちはどうして外国語を学ばなければいけないのか」という最も根源的な問いを深めていく余裕がない、そんな状況ではないかと思います。 英語の先生たちは、余りそういう話は聞きたくないかも知れませんけれど、自動機械翻訳が今すごい勢いで進化しています。文科省は、オーラル・コミュニケーションが必要だ、とにかく英語で話せなければダメだとさかんに言い立てていますけれど、そんな教育政策とは無関係に翻訳テクノロジーの方はどんどん進化している。 去年の「中央公論」で自動機械翻訳の専門家と英語の専門家の対談がありました。今の機械翻訳はこれまでとシステムが違って、ただ用例を溜め込むだけでなく、「ディープ・ラーニング」ができるようになって、これまでとはまったく別物になったらしい。 英語だと、今の自動機械翻訳が大体TOEIC600点ぐらいまでだけれども、数年のうちに800点になるそうです。対談の中で、自動機械翻訳の専門家が、だから、もう学校で英語を教える必要はなくなると言っていました。外交官とか通訳、翻訳とか、英語のニュアンスを精密に吟味する必要のある仕事では英語についての深い理解が必要だけれど、日常的なコミュニケーションについてはそんなものはもう要らない。だって、人間より機械の方が速く、正確になるから。英語の専門家は1%くらいいれば済む。後は機械に任せておけばいい、と。エンジニアらしい、いささか乱暴な議論でしたけれど、英語の先生たちはこの挑発的な発言に異論を立てる義務があると思います。小学生から英語を教える必要なんかないし、中学でも高校でも、特殊な職業をめざすもの以外には英語を教える必要がないと言い切ってるんですから。 僕は毎年野沢温泉にスキーに行くのですけれど、今年も3月に野沢に行ったら、もう外国人ばかりなのですね。僕らが泊まった旅館は七、八割が外国の方でした。食堂に案内された時に、座席表が外国名ばかりだったので、仲居さんに「大変ですね、英語で接客するんですか?」と訊いたら、「いいえ。私ら英語できませんから、全部Google翻訳です」とこともなげに答えられました。 僕はある禊の会に入っておりまして、ときどき禊の行に行くのですけれど、四月に行った時は、ロシア人が団体で来ておりました。聞くと驚く方が多いと思いますけれど、ロシア人も神道の禊をやる人たちがいるんですよ。モスクワにも道場があるんですが、やっぱり本場の日本で本格的に修行したいという人たちが来ているのです。この時はロシアの人とベネズエラの人が来ておりました。道場は祝詞を唱えたり、座禅を組んだりという行をしているところですから、もともと外国人の参加なんか予測していないし、もちろん外国語が堪能な人が揃っているわけではない。
来たロシア人たちは英語もあまりわからないということで、どうやって意思疎通するんだろうと心配しておりましたら、道場長が、「これがあるから大丈夫」と言って、小さな機械を見せてくれました。Pocketalk という手のひらサイズの自動翻訳機械でした。まさに『ドラえもん』の「ほんやくコンニャク」でした。そこには60ヵ国語が入っていて、ボタンを押して、日本語を言うと、外国語になって音声が出てくる。外国語音声を入力してもらうと、日本語の音声に訳される。さっそくロシア人たちとその機械で会話をしてみました。 僕はそういうガジェットに目がないので、家に帰ってすぐにAmazonで検索して、購入しました。SIMカードを入れると世界中どこでも使える。それが3万円台。仰天しました。いつの間にこんなものが・・・と思いました。われわれの知らないうちに、テクノロジーはどんどんと進化しているわけです。AIの「シンギュラリティー」が来ると産業構造が変わり、雇用環境が激変するとさかんに報道されていますけれど、そんな先の話ではなくて、自動化・機械化はあちこちでもう起きているわけです。 これまで英語をいやいや勉強してきた「のび太」君のような子どもたちにとって「ほんやくコンニャク」はまさに夢の機械だったわけですけれど、それが今やSIMカード付きで、3万円台で手に入る。いずれ価格競争が起きて、「ほんやくコンニャク」がコンビニで電卓程度の価格で売られる時代も来るかも知れない。電卓が普及したせいで筆算や珠算の能力に対するニーズが失われたように、機械翻訳が日常的なものになってきたら、オーラル・コミュニケーション能力を身に付ける必要もなくなります。よく「町で外国人にいきなり道を尋ねられたときに英語ができないと困る」というようなことを英語学習の動機づけとして語る人がいますけれど、これからはポケットから出せば済むわけですね。 今の「ほんやくコンニャク」は、まだ一度に聴き取れるセンテンスが短いですけれども、技術的な改良はこれからもどんどん進み、いずれどこでどんな外国語で話しかけられても、日本語でスムーズに対話できるようになる。『スターウォーズ』にすべての宇宙の言語が話せる通訳ロボットC−3POというのが出てきますけれど、個人用のC−3POをみんなが連れて歩けるようになるようなものです。 こういうところで僕がしゃべっている音声を、すぐに文字起こしして後ろのスクリーンに投影するというテクノロジーはすでに開発されています。もともとは聴覚障害者用に開発されたものです。手話通訳者がいなくても話を理解できるようにということで開発された。話し始めのうちは、技術者が文章に手を入れます。日本語は同音異義語が多いですし、人によってかなり特殊な言葉づかいをしますから、技術者がいったん文字起こしされたものを、意味が通るように修正する。でも、時間が経つと、機械が話し手の語彙や「話し癖」に慣れて、技術者が介入しなくても、機械が講演をタイムラグなしにスクリーンに映し出すようになる。僕がそのシステムを使って講演したのはもう1年半ぐらい前です。恐らく今はもっと技術が進化していると思います。 外国語教育はどうすれば効率的であるのかという話をわれわれは教育者という立場で必死にしているわけですけれど、そういうわれわれの側の努力とはまったく無関係に、科学技術は進化して、場合によっては英語教育についての根幹部分についてのこれまでの工夫や議論を無効化してしまうような変化が起きている。そのことをまずみなさんにはご理解頂きたいと思います。 自動機械翻訳がオーラル・コミュニケーションにおける障害の多くを除去してくれるということになったら、一体何のために外国語を学ぶのか? 日本の小・中・高の英語の先生方は、「何のために英語を学ぶのか?」ということについて、今や根源的な省察を要求されています。これまではそんなことを考える必要がなかった。英語を学ぶことの必然性・有用性は自明のものだと思われていた。でも、それが揺らいできた。 僕自身は長くフランス語を勉強してきて、大学では語学の教師をしていたわけですから、「なぜ外国語を学ぶ必要があるのか」に関してはずっと考え続けてきました。特に、フランス語やドイツ語のような第二外国語については、「そんなものを学生に履修させる必要がない、そんな時間があったらもっと英語をやらせろ」というタイプの議論に何度も巻き込まれましたから、「なぜとりあえず不要不急のものであるフランス語を学ぶ必要があるのか?」という問いについてはかなり真剣に考えて来ました。 僕の結論は「どんなものであれ、外国語を学ぶことは子どもたちの知的成熟にとって必要である」ということでした。これが僕の基本的な立場です。こればかりは譲れません。「ほんやくコンニャク」ができようと、ポケットマネーで通訳が雇えようと、そんなことは全く別のレベルで、人は外国語を学ぶ必要がある。でもそれは、文科省が言っているような「英語ができる日本人をつくる」といった功利的な目的とは無関係な話です。 今日、この中に文科省の方はいらしていますか。いらしたら、自動機械翻訳がどのように日本の外国語教育を変えていくのかについて、これまで省内ではどういう話し合いをされてきたのかお訊ねしたいです。調査はされていますか? 実際に機械をお使いになってみたことがありますか? 今、自動機械翻訳がどうなっているかを知っていれば、「英語ができる日本人」養成プログラムのような、ビジネスの場面でオーラル・コミュニケーションがうまくないと、侮られる、損をする、というようなことを英語習得の主目的を掲げているプログラムは存在そのものが無意味になるかも知れないということにもっとショックを受けていいはずなんです。でも、その気配もない。ということは、文科省の方々は自動機械翻訳については何もご存じないということだと思います。教育プログラムの根幹を揺るがすようなテクノロジーの進化について「何もご存じない」のだとしたら、それは教育行政を司る省庁として「あまりに不勉強」とのそしりを免れないのではないかと思います。
外国語学習について語るときに、「目標言語」と「目標文化」という言葉があります。「目標言語」というのは、今の場合なら、例えば英語です。なぜ英語を学ぶのか。それは「目標文化」にアクセスするためです。英語の場合であれば、ふつうは英語圏の文化が「目標文化」と呼ばれます。 僕らの世代において英語の目標文化ははっきりしていました。それは端的にアメリカ文化でした。アメリカ文化にアクセスすること、それが英語学習の最も強い動機でした。われわれの世代は、子どものときからアメリカ文化の洪水の中で育っているわけですから、当然です。FENでロックンロールを聴き、ハリウッド映画を観て、アメリカのテレビドラマを観て育ったわけですから、僕らの世代においては「英語を学ぶ」というのは端的にアメリカのことをもっと知りたいということに尽くされました。 僕も中学や高校で「英語好き」の人にたくさん会いましたけれど、多くはロックの歌詞や映画の台詞を聴き取りたい、アメリカの小説を原語で読みたい、そういう動機で英語を勉強していました。 僕もそうでした。英語の成績は中学生からずっとよかったのですが、僕の場合、一番役に立ったのはビートルズの歌詞の暗記でした。ビートルズのヒット曲の歌詞に含まれる単語とイディオムを片っ端から覚えたのですから、英語の点はいいはずです。 つまり、英語そのものというよりも、「英語の向こう側」にあるもの、英米の文化に対する素朴な憧れがあって、それに触れるために英語を勉強した。英米のポップ・カルチャーという「目標文化」があって、それにアクセスするための回路として英語という「目標言語」を学んだわけです。 その後、1960年代から僕はフランス語の勉強を始めるわけですけれども、この時もフランス語そのものに興味があったわけではありません。フランス語でコミュニケーションしたいフランス人が身近にいたわけではないし、フランス語ができると就職に有利というようなこともなかった。そういう功利的な動機がないところで学び始めたのです。フランス文化にアクセスしたかったから。 僕が高校生から大学生の頃は、人文科学・社会科学分野での新しい学術的知見はほとんどすべてがフランスから発信された時代でした。40年代、50年代のサルトル、カミュ、メルロー=ポンティから始まって、レヴィ=ストロース、バルト、フーコー、アルチュセール、ラカン、デリダ、レヴィナス・・・と文系の新しい学術的知見はほとんどフランス語で発信されたのです。 フランス語ができないとこの知的領域にはアクセスできない。当時の日本でも、『パイデイア』とか『現代思想』とか『エピステーメー』とかいう雑誌が毎月のようにフランスの最新学術についての特集を組むのですけれど、「すごいものが出て来た」と言うだけで、そこで言及されている思想家や学者たちの肝心の主著がまだ翻訳されていない。フランス語ができる学者たちだけがそれにアクセスできて、その新しい知についての「概説書」や「入門書」や「論文」を独占的に書いている。とにかくフランスではすごいことになっていて、それにキャッチアップできないともう知の世界標準に追いついてゆけないという話になっていた。でも、その「すごいこと」の中身がさっぱりわからない。フランス語が読めないと話にならない。ですから、60年代―70年代の「ウッドビー・インテリゲンチャ」の少年たちは雪崩打つようにフランス語を学んだわけです。それが目標文化だったのです。 のちに大学の教師になってから、フランス語の語学研修の付き添いで夏休みにフランスに行くことになった時、ある年、僕も学生にまじって、研修に参加したことがありました。振り分け試験で上級クラスに入れられたのですけれど、そのクラスで、ある日テレビの「お笑い番組」のビデオを見せて、これを聴き取れという課題が出ました。僕はその課題を拒否しました。悪いけど、僕はそういうことには全然興味がない。僕は学術的なものを読むためにフランス語を勉強してきたのであって、テレビのお笑い番組の早口のギャグを聴き取るために労力を使う気はないと申し上げた。その時の先生は真っ赤になって怒って、「庶民の使う言葉を理解する気がないというのなら、あなたは永遠にフランス語ができるようにならないだろう」という呪いのような言葉を投げかけたのでした。結局、その呪いの通りになってしまったのですけれど、僕にとっての「目標文化」は1940年から80年代にかけてのフランスの知的黄金時代のゴージャスな饗宴の末席に連なることであって、現代のフランスのテレビ・カルチャーになんか、何の興味もなかった。ただ、フランス語がぺらぺら話せるようになりたかったのなら、それも必要でしょうけれど、僕はフランスの哲学者の本を読みたくてフランス語を勉強し始めたわけですから、その目標を変えるわけにゆかない。フランス語という「目標言語」は同じでも、それを習得することを通じてどのような「目標文化」にたどりつこうとしているのかは人によって違う。そのことをその時に思い知りました。 ロシア語もそうです。今、大学でロシア語を第二外国語で履修する学生はほとんどいません。でも、若い方はもうご存じないと思いますけれど、1970年に僕が大学入学したとき、理系の学生の第二外国語で一番履修者が多かったのはロシア語でした。「スプートニク・ショック」と言われたように、60年代まではソ連が科学技術のいくつかの分野でアメリカより先を進んでいたからです。科学の最先端の情報にアクセスするためには英語よりもロシア語が必要だった。でも、ソ連が没落して、科学技術におけるアドバンテージが失われると、ロシア語を履修する理系の学生はぱたりといなくなりました。もちろんドストエフスキーを読みたい、チェーホフを読みたいというような動機でロシア語を履修する学生の数はいつの時代もいます。目標文化が「ロシア文学」である履修者の数はいつの時代もそれほど変化しない。けれども、目標文化が「ソ連の科学の先進性」である履修者は、その目標文化が求心力を失うと、たちまち潮が引くようにいなくなる。 僕の学生時代はフランス語履修者がたくさんおりました。でも、その後、フランス語履修者は急減しました。ある時点で中国語に抜かれて、今はもう見る影もありません。理由の一つは、日本のフランス語教員たちが学生たちの知的好奇心を掻き立てることができなかったせいなのですけれど、それ以上に本国のフランスの文化的な発信力が低下したことがあります。フランス文化そのものに日本の若者たちを「目標」として惹きつける魅力がなくなってしまった。 フランス語やロシア語の例から知れる通り、われわれが外国語を学ぶのは目標文化に近づくためなのです。目標文化にアクセスするための手段として目標言語を学ぶ。 しかし、まことに不思議なことに、今の英語教育には目標文化が存在しません。英語という目標言語だけはあるけれども、その言語を経由して、いったいどこに向かおうとしているのか。向かう先はアメリカでもイギリスでもない。カナダでもオーストラリアでもない。どこでもないのです。 何年か前に、推薦入試の入試本部で学長と並んで出願書類をチェックしていたことがありました。学長は英文科の方だったのですけれど、出願書類の束を読み終えた後に嘆息をついて、「内田さん、今日の受験者150人の中に『英文科志望理由』に『英米文学を学びたいから』と書いた人が何人いると思う?」と訊いてきました。「何人でした?」と僕が問い返すと「2人だけ」というお答えでした「後は、『英語を生かした職業に就きたいから』」だそうでした。 僕の知る限りでも、英語を学んで、カタールの航空会社に入った、香港のスーパーマーケットに就職した、シンガポールの銀行に入ったという話はよく聞きます。別にカタール文化や香港文化やシンガポール文化をぜひ知りたい、その本質に触れたいと思ってそういう仕事を選んだわけではないでしょう。彼らにとって、英語はたしかに目標言語なのですけれど、めざす目標文化はどこかの特定の文化圏のものではなく、グローバルな「社会的な格付け」なのです。高い年収と地位が得られるなら、どの外国でも暮らすし、どの外国でも働く、だから英語を勉強するという人の場合、これまでの外国語教育における目標文化に当たるものが存在しない。 これについては平田オリザさんが辛辣なことを言っています。彼に言わせると、日本の今の英語教育の目標は「ユニクロのシンガポール支店長を育てる教育」だそうです。「ユニクロのシンガポール支店長」はもちろん有用な仕事であり、しかるべき能力を要するし、それにふさわしい待遇を要求できるポストですけれど、それは一人いれば足りる。何百万単位で「シンガポール支店長」を「人形焼き」を叩き出すように作り出す必要はない。でも、現在の日本の英語教育がめざしているのはそういう定型です。 僕は大学の現場を離れて7年になりますので、今の大学生の学力を知るには情報が足りないのですけれども、それでも、文科省が「英語ができる日本人」ということを言い出してから、大学に入学してくる学生たちの英語力がどんどん低下してきたことは知っています。それも当然だと思います。英語を勉強することの目標が、同学齢集団内部での格付けのためなんですから。低く査定されて資源分配において不利になることに対する恐怖をインセンティヴにして英語学習に子どもたちを向けようとしている。そんなことが成功するはずがない。恐怖や不安を動機にして、知性が活性化するなんてことはありえないからです。 僕は中学校に入って初めて英語に触れました。それまではまったく英語を習ったことがなかった。1960年頃の小学生だと、学習塾に通っているのがクラスに二三人、あとは算盤塾くらいで、小学生から英語の勉強している子どもなんか全然いません。ですから、FENでロックンロールは聴いていましたけれど、DJのしゃべりも、曲の歌詞も、ぜんぶ「サウンド」に過ぎず、意味としては分節されていなかった。それが中学生になるといよいよ分かるようになる。入学式の前に教科書が配られます。英語の教科書を手にした時は、これからいよいよ英語を習うのだと思って本当にわくわくしました。これまで自分にとってまったく理解不能だった言語がこれから理解可能になってゆくんですから。自分が生まれてから一度も発したことのない音韻を発声し、日本語に存在しない単語を学んで、それが使えるようになる。その期待に胸が膨らんだ。 今はどうでしょう。中学校一年生が四月に、最初の英語の授業を受ける時に、胸がわくわくどきどきして、期待で胸をはじけそうになる・・・というようなことはまずないんじゃないでしょうか。ほかの教科とも同じでしょうけれど、英語を通じて獲得するものが「文化」ではないことは中学生にもわかるからです。わかっているのは、英語の出来不出来で、自分たちは格付けされて、英語ができないと受験にも、就職にも不利である、就職しても出世できないということだけです。そういう世俗的で功利的な理由で英語学習を動機づけようとしている。でも、そんなもので子どもたちの学習意欲が高まるはずがない。 格付けを上げるために英語を勉強しろというのは、たしかにリアルではあります。リアルだけれども、全然わくわくしない。外国語の習得というのは、本来はおのれの母語的な枠組みを抜け出して、未知のもの、新しいものを習得ゆくプロセスのはずです。だからこそ、知性の高いパフォーマンスを要求する。自分の知的な枠組みを超え出てゆくわけですから、本当なら「清水の舞台から飛び降りる」ような覚悟が要る。そのためには、外国語を学ぶことへ期待とか向上心とか、明るくて、風通しのよい、胸がわくわくするような感じが絶対に必要なんですよ。恐怖や不安で、人間はおのれの知的な限界を超えて踏み出すことなんかできません。 でも、文科省の『「英語ができる日本人」の育成のための行動計画の策定について』にはこう書いてある。 「今日においては、経済、社会の様々な面でグローバル化が急速に進展し、人の流れ、物の流れのみならず、情報、資本などの国境を超えた移動が活発となり、国際的な相互依存関係が深まっています。それとともに、国際的な経済競争は激化し、メガコンペティションと呼ばれる状態が到来する中、これに対する果敢な挑戦が求められています。」 冒頭がこれです。まず「経済」の話から始まる。「経済競争」「メガコンペティション」というラットレース的な状況が設定されて、そこでの「果敢な挑戦」が求められている。英語教育についての基本政策が「金の話」と「競争の話」から始まる。始まるどころか全篇それしか書かれていない。 「このような状況の中、英語は、母語の異なる人々をつなぐ国際的共通語として最も中心的な役割を果たしており、子どもたちが21世紀を生き抜くためには、国際的共通語としての英語のコミュニケーション能力を身に付けることが不可欠です」という書いた後にこう続きます。 「現状では、日本人の多くが、英語力が十分でないために、外国人との交流において制限を受けたり、適切な評価が得られないといった事態も起きています。」
「金」と「競争」の話の次は「格付け」の話です。ここには異文化に対する好奇心も、自分たちの価値観とは異なる価値観を具えた文化に対する敬意も、何もありません。人間たちは金を求めて競争しており、その競争では英語ができることが死活的に重要で、英語学力が不足していると「制限を受けたり」「適切な評価が得られない」という脅しがなされているだけです。そんなのは日本人なら誰でもすでに知っていることです。でも、「英語ができる日本人」に求められているのは「日本人なら誰でもすでに知っていること」なのです。 外国語を学ぶことの本義は、一言で言えば、「日本人なら誰でもすでに知っていること」の外部について学ぶことです。母語的な価値観の「外部」が存在するということを知ることです。自分たちの母語では記述できない、母語にはその語彙さえ存在しない思念や感情や論理が存在すると知ることです。 でも、この文科省の作文には、外国語を学ぶのは「日本人なら誰でもすでに知っていること」の檻から逃れ出るためだという発想がみじんもない。自分たちの狭隘な、ローカルな価値観の「外側」について学ぶことは「国際的な相互依存関係」のうちで適切なふるまいをするために必須であるという見識さえ見られない。僕は外国語学習の動機づけとして、かつてこれほど貧しく、知性を欠いた文章を読んだことがありません。 たしかに、子どもたちを追い込んで、不安にさせて、処罰への恐怖を動機にして何か子どもたちが「やりたくないこと」を無理強いすることは可能でしょう。軍隊における新兵の訓練というのはそういうものでしたから。処罰されることへの恐怖をばねにすれば、自分の心身の限界を超えて、爆発的な力を発動させることは可能です。スパルタ的な部活の指導者は今でもそういうやり方を好んでいます。でも、それは「やりたくないこと」を無理強いさせるために開発された政治技術です。
ということは、この文科省の作文は子どもたちは英語を学習したがっていないという前提を採用しているということです。その上で、「いやなこと」を強制するために、「経済競争」だの「メガコンペティション」だの「適切な評価」だのという言葉で脅しをかけている。 ここには学校教育とは、一人一人の子どもたちがもっている個性的で豊かな資質が開花するのを支援するプロセスであるという発想が決定的に欠落しています。子どもたちの知性的・感性的な成熟を支援するのが学校教育でしょう。自然に個性や才能が開花してゆくことを支援する作業に、どうして恐怖や不安や脅迫が必要なんです。勉強しないと「ひどい目に遭うぞ」というようなことを教師は決して口にしてはならないと僕は思います。学ぶことは子どもたちにとって「喜び」でなければならない。学校というのは、自分の知的な限界を踏み出してゆくことは「気分のいいこと」だということを発見するための場でなければならない。 この文章を読んでわかるのは、今の日本の英語教育において、目標言語は英語だけれど、目標文化は日本だということです。今よりもっと日本的になり、日本的価値観にがんじがらめになるために英語を勉強しなさい、と。ここにはそう書いてある。 目標文化が日本文化であるような学習を「外国語学習」と呼ぶことに僕は賛成できません。 僕自身はこれまでさまざまな外国語を学んできました。最初に漢文と英語を学び、それからフランス語、ヘブライ語、韓国語といろいろな外国語に手を出しました。新しい外国語を学ぶ前の高揚感が好きだからです。日本語にはない音韻を発音すること、日本語にはない単語を知ること、日本語とは違う統辞法や論理があることを知ること、それが外国語を学ぶ「甲斐」だと僕は思っています。習った外国語を使って、「メガコンペティションに果敢に挑戦」する気なんか、さらさらありません。 外国語を学ぶ目的は、われわれとは違うしかたで世界を分節し、われわれとは違う景色を見ている人たちに想像的に共感することです。われわれとはコスモロジーが違う、価値観、美意識が違う、死生観が違う、何もかも違うような人たちがいて、その人たちから見た世界の風景がそこにある。外国語を学ぶというのは、その世界に接近してゆくことです。 フランス語でしか表現できない哲学的概念とか、ヘブライ語でしか表現できない宗教的概念とか、英語でしか表現できない感情とか、そういうものがあるんです。それを学ぶことを通じて、それと日本語との隔絶やずれをどうやって調整しようか努力することを通じて、人間は「母語の檻」から抜け出すことができる。
外国語を学ぶことの最大の目標はそれでしょう。母語的な現実、母語的な物の見方から離脱すること。母語的分節とは違う仕方で世界を見ること、母語とは違う言語で自分自身を語ること。それを経験することが外国語を学ぶことの「甲斐」だと思うのです。 でも、今の日本の英語教育は「母語の檻」からの離脱など眼中にない。それが「目標言語は英語だが、目標文化は日本だ」ということの意味です。外国語なんか別に学ぶ必要はないのだが、英語ができないとビジネスができないから、バカにされるから、だから英語をやるんだ、と。言っている本人はそれなりにリアリズムを語っているつもりでいるんでしょう。でも、現実にその結果として、日本の子どもたちの英語力は劇的に低下してきている。そりゃそうです。「ユニクロのシンガポール支店長」が「上がり」であるような英語教育を受けていたら、そもそもそんな仕事に何の興味もない子どもたちは英語をやる理由がない。 達成目標があらかじめ開示された場合に、子どもたちの学習努力は大きく殺がれます。教育のプロセスをまじめに観察したことがある人間なら、誰でもわかることです。「勉強するとこんないいことがある」とか「勉強しないとこんなひどい目に遭う」というようなことをあらかじめ子どもに開示すると、子どもたちの学習意欲はあきらかに減退する。というのは、努力した先に得られるものが決まっていたら、子どもたちは最少の学習努力でそれを獲得しようとするに決まっているからです。 学習の場では決して利益誘導してはならないということを理解していない人があまりに多い。でも、長く教員をやってきてこれは経験的にはっきりと申し上げられます。賞品で子どもを釣ったり、恐怖で子どもを脅したりしても子どもたちの知的な能力は絶対に向上しません。彼らはどうやったら最少の学習努力で目的のものを手に入れるか、そこに全力を集中するようになるだけです。 大学で最初の授業のときにオリエンテーションをやると、必ず「先生、単位をもらえる最低点は何点ですか」と「この授業は何回まで休めますか」という質問が出ます。単位をとるための最低点と最少出席回数をまず確認する。「ミニマム」を知ろうとするわけです。これは消費者マインドを持って教室に登場した学生にとっては当然の質問です。「これいくらですか?」と訊いているわけですから。 彼らにとって単位や学位や免状や資格は「商品」なんです。そして、学習努力は「貨幣」です。だから、買い物客が「この商品の価格はいくらですか?」と訊くように、「この授業で求められる最少学習努力はどの程度ですか?」を訊いてくる。
求める商品にそれなりの価値があることは彼らだってわかっているのです。でも、どんな価値のある商品であっても、一番安い価格で買うというのは消費者の権利であり義務であるわけです。特売コーナーで同じ商品が安く売っていたら、カートに入れた商品を元の棚に戻して、特売コーナーの同一商品をカートに入れる。それは買い物をする人間としては当たり前のことです。「元の棚」がかなり遠いところであっても、ごろごろカートを押して、そこまで戻しにゆく。その手間を別に惜しいとは思わない。それが消費者です。 ですから、消費者としてふるまう学生たちの目には、出席をとらない科目、毎年同じ試験問題を出す科目、丸写しレポートでも単位をくれる科目は「特売コーナー」に置かれている商品のようなものとして映る。「特売商品」で同じ単位がもらえるなら、そういう「楽勝科目」だけを集めて卒業単位を稼ぐのが最もクレバーな学生生活であることになる。消費者マインドが骨までしみついた学生たちは、大学に来てまで「どうすれば最も少なく学べるか」をめざして努力するようになる。
もし書店に「3ヵ月でTOEICスコアが100点上がる」という参考書があったとします。それを買おうと思って、横を見たら「1ヵ月で100点上がる」という本があった。当然、そちらを買う。でも、その隣に、「1週間で100点上がる」という本があった。これはもうこちらを買うしかない。でも、そのさらに横には「何もしなくても100点上がる」という本があった。もう迷わずこれを買う。 そういうものですね。学習の達成目標が決まっていれば、あとはいかに少ない学習努力でそれを達成するかというところに知恵を使う。それが最も合理的であるということは子どもにだってわかります。ですから、学校で「勉強すると、こんないいことがある」という仕方で功利的に誘導するのは自分で足元を掘り崩しているようなものなのです。 車を買うときだって、ふつうの人は何軒もディーラーを回って、だいたい車格が同じくらいの車を値踏みして、「おたくはいくら引くの?」と訊いて回りますよね。そして、一番値引き率の高いディーラーで買う。子どもたちだって、そういう親たちのふるまいを見て育っています。だから、一番安いところで買うためには、一日かけて何軒もディーラーを回るくらいの苦労はしても当然だということを学ぶ。だから、学校でも「最少の学習努力で教育商品を手に入れるために最大限の努力を惜しまない」という非合理な行動をするようになる。 僕が教務部長をしている時に、単位をよこせとどなり込んできた学生がいました。事情を聴くと、レポートの期限に遅れたので、担当の教師が受理してくれなかった、それで単位を落としたというのです。期限に遅れたのは、提出期限が一日前倒しになったのを知らなかったからです。先生はうっかりして、入試があって学生入構禁止の日をレポートの提出期限として指定したしまったのです。大学の事務からそれを指摘されて、締め切り日を一日繰り上げて、学生たちには教室でそのことを告知したのですが、その学生はその日授業に出ていなかったのでそれを知らなかった。そして、大学構内に入れない日にレポートを持ってきて、ガードマンに追い返されてしまった。その学生と親たちが教務課の窓口に来て抗議しているわけです。「レポート提出期限の変更は授業を休んだ学生全員に周知徹底するのは大学の義務だ」と言う。「ちゃんと掲示板に告知してありました」と言ったのですが「中には掲示板を見ない学生だっている。教師は欠席した学生全員にひとりひとり電話をかけて知らせるべきだった」とごねる。ついに「弁護士を立てて大学を訴える」と言い出した。 この一家のご努力にはほんとうに感動しました。どうして教務課で騒ぎ立てることについてはこれほど努力を惜しまないのに、授業に出ることや掲示板を見ることにはこれほど努力を惜しむか。担任の先生に出席簿を出してもらって調べたら、その学生は15週のうち6回しか出席しておりませんでした。それを知らせたら、さすがに親も引き下がりました。その学生は親には「ほとんど全部出席していた」と嘘をついていたのでした。 この親子は消費者マインドで学校に来る人間の典型だと思います。「最低価格で商品を手に入れる」ためにはいかなる努力も惜しまない。それが倒錯的なふるまいだということが本人にはわからないのです。教務課相手に何日もかけてタフな交渉をするより、ふつうに授業に出ていた方がずいぶん楽だし、知識も身に着くので「一挙両得」ではないかと思うのですけれど、そういう計算が立たない。
親や学生だけではありません。学校にもいます。市場原理で教育を語る人間が。「学校は店舗だ。われわれが売っているのは教育サービスだ。保護者と子どもたちはクライアントだ。消費者に選好される教育商品を売るのが教育活動なのだ。だから、市場のニーズを見きわめ、ターゲットを絞って、マネジメントをしなければいけない」というようなことを言う人間が。本人はビジネスマインドで教育を語って、わかった気になっているようですけれど、本当に頭が悪い。そんなことをしたら、学力はどんどん下がるに決まっているではないですか。 だって、彼の言う「クライアント」が求めるのは「最低の学習努力で手に入る、価値のある教育商品」なわけですから、最終的には「勉強しなくても、学校に来なくても、試験を受けなくても、レポートを書かなくても、学習努力ゼロでも学位を差し上げます」というところを選ぶようになるに決まっている。 最近よく「在学中に1年留学」ということを謳っている大学がありますね。大学は学生から授業料を徴収して、留学先の大学に研修費を払って、差額を手に入れる。教育活動ゼロでそれなりの授業料が入るわけですから笑いが止まらない。学生の25%が大学に来ないんですから教育コストは大幅に軽減できる。人件費も光熱費も25%節約できるし、トイレットペーパーも減らないし、校舎の床も階段も損耗しない。そのうち「だったら留学期間2年にしたらどうか」と言い出すやつがきっと出てきます。それなら教員を50%減らすことができる。「それならいっそ留学3年必須にしたらどうか」と誰かが言い出し、ついには「いやそれより4年間留学必須にしたどうか」と言い出すやつが出て来る。そうすれば大学は何も授業せず、集めた授業料を留学先の研修費に払った差額はまるごとポケットに入る。もう教職員を雇う必要もないし、キャンパスさえ要らない。教育活動を一切しないでも金が入ってくる。 そうなんです。市場原理に従うなら、大学はできるだけ教育活動にコストをかけない方が儲かる。ですから、論理的には「大学がない」ときに利益率は最大化する。 実際に21世紀はじめに林立した株式会社大学の中には、貸しビルに部屋を借りただけでキャンパスを持たず、専任教員を雇わずに職員に講義させ、ビデオを見せて授業に代えたりして、最少の教育コストで「大儲け」を狙ったところがありました。もちろん、すぐに潰れました。でも、経営者は「どうして市場原理に従って経営したのに失敗したのか」最後まで理解できなかったのではないかと思います。 教育に市場原理を持ち込んだら、学生たちは「最少の学習努力」をめざし、学校経営者たちは「最少の教育コスト」をめざすようになる。それが当然なのです。でも、そんなものは教育ではない。そんな簡単なことさえわからない人間たちが、教育がどうあるべきかについて論じ、政策を決定して、現場にあれこれとお門違いな命令を下して、ひどい場合は大学を経営している。それが今の日本です。学校教育が劣化するのも当たり前です。 もう一つ、申し上げておきたいことがあります。それは学校に競争原理を持ち込んではならないということです。このエピソードも何度も本に書いたことですけれど、印象的な事例なので繰り返します。 僕のゼミの学生で、学習塾でバイトをしていたものがいました。そこは学習習慣のない子どもたちのための塾で、マンツーマンで勉強を教えていた。一生懸命教えた甲斐があって、その学生が担当していた子どもがようやく学習習慣が身についてきて、教室でも長い時間机に座っていられるようになった。そして、ある日ついに塾の学習進度が学校を超えた。学校でまだ習っていない単元に進んだのです。そうしたら、その子は、学校で自分が知っていることを先生が教え始めたら、立ち上がって歌を歌い出したというのです。 学校の先生から親に相談が行って、親から塾で担当していた学生に相談が行って、学生から僕が相談を受けて、「先生、一体この子は何のためにそんなことをしたのでしょう?」と訊かれたので、彼は彼なりに合理的な行動をとったのだと思うと答えました。 この子はずっと学校の勉強に遅れていた。それがようやくわずかながらも級友よりも先に進んだ。このアドバンテージを維持するためには、周りの級友たちの学習を妨害するのが最も効果的である。そう考えたわけです。 実際に、子どもたちは実に小まめに級友たちの学習妨害をしています。「学級崩壊」ということがある時点から言われ始めましたけれど、それは子どもたちが急激に反社会的になったからではなく、むしろ過度に社会化されたからではないかと僕は思っています。子どもたちは実際に合理的に行動しているのです。自分の学力を上げるための努力は自分ひとりにしかかかわらないけれど、学級崩壊はクラスメート全員の学習を妨害できる。同学齢集団内部での相対的な優劣を競うという観点から言うと、自分の学力を上げる努力よりも、周囲の学力を引き下げる努力の方が費用対効果が高い。 昔からそういうのはありましたね。進学校だと、試験前でも「全然勉強やってないよ」と言って級友を油断させたり、試験の前日に麻雀に誘って勉強の邪魔をしたりとか、そういう「せこい」ことをやっていた。でも、今はもっとそれを組織的かつ無意識的にやっている。競争原理的には合理的なふるまいなので誰も止めることができない。 偏差値というのがまさに競争原理がもたらした倒錯の典型です。偏差値は学力とは無関係です。あれは、同学齢集団のどの辺にいるのかという「格付け指標」です。今、偏差値70の子は、僕が中学生だった頃に連れ来たら、とてもそんな偏差値はとれないでしょう。競争相手の同学齢集団の規模が二倍以上だし、学力そのものも年ごとに低下していますから。でも、偏差値というのは集団そのものの学力が低下しても、格付け機能だけは変わらない。そういう競争に子どもたちを追い込んだら、当然子どもたちは「最少の学習努力で高い偏差値をとる方法」を工夫するようになります。そして、そのためには「集団全体の学力を下げる」のが最も効率的であるということは誰にでもわかる。 僕は神戸の住吉というところに住んでいます。近くには灘高とか六甲学院といった中高一貫の進学校があります。電車に乗ると、よくそういう学校の生徒たちに会います。ついにじり寄っていって、どんな話をしているのか立ち聞きしてしまう。みごとなほど知的な会話をしていない。直接教科の内容にかかわることでなくてもいいのです。今だったら、「米朝会談どうなると思う」というような話をしてもいいじゃないですか「金正恩はこれからどう出るか」とか「南北は裏で話がついていたのか」とか「CIAが絡んでいるのかね」とか、高校生だって、そういう話をしてもいいじゃないですか。「これから日本の政治はどうなるのか」とか「東京オリンピックはほんとうに開催できるのか」とか。自分たちのこれからにかかわることなんですから。でも、そういう話をまったくしていない。 例えば、生徒たちがそれぞれ手分けして海外のネットニュースを読んだり、本を読んだりして情報を集めて、それを共有すればいいと思うんですよね。頭のいい子たちなんだから。でも、そうやってお互いの知的リソースを富裕化するという作業はみごとなほどまったくしていない。おしゃべりの内容は、「そんなことを知っていても、試験の点数が一点も上がることのない話題、話し相手の知性が少しも活性化しない話題」に限定されています。もう、みごとなほど。無意識にやっているんですよ、そういうことを。同学齢集団の競争相手たちの知性が活性化することを本能的に回避しようとしている。そういうことを社会全体でやっている。学力が低下し、大学の学術的発信力が先進国最低にまで下落するのも当然なんです。 いったいどうすればいいのか。僕からの提案はシンプルなんです。でも、これは無理だと皆さんは言うと思います。それは「成績をつけない」ということです。成績をつけない。生徒たちを格付けをしない。教えたいことがあるので教える。聞きたい人は聞いてくれ。そういう授業をする。そんなことをしたら管理職からも、親からも、生徒たち自身からも「止めてくれ」と言われると思いますけれど、日本の学校教育を蘇生させる道はそれしかないです。点数をつけない。成績をつけるのを止めれば、格付けによって資源を傾斜配分するというルールを止めれば、日本の子どもたちの学力は一気にV字回復します。それは断言してもいい。 成績をつけ、格付をして、得点の高いものに報奨を与え、得点の低いものは処罰するというのは「微量の毒」のようなものなんです。毒もうまく使えば薬になるけれど、所詮は毒です。短期的に、一気に限界を超えさせるためには、格付けによる差別は有効です。でも、そういう無理は長続きするものじゃない。どこかで子どもたちの心身が壊れ始める。ほんとうに自己の知的限界を超えるためには、時間がかかるんです。教師は生徒たちの学びへの意欲が起動するまで、長い時間待たなければいけない。学びに促成栽培はあり得ないんです。 同学齢集団の中で相対的な優劣を競わせるのは「促成栽培」です。農作物を育てる時に、農薬や肥料を大量に投与したり、人工的な環境で育てるのと同じです。すぐに効果は出るけれど、それはほんとうに力がついたわけじゃない。 学校で子どもたちが身に付けるべき能力は、学校を出てから役立つものでなければ意味がありません。学校を出た後はすぐに年齢も違う、性別も違う、専門も違う人たちと共同的にかかわることになります。自分とものの考え方が違う人たちとのコラボレーションができなければ仕事になりません。同学齢集団内で相対的な優劣を競ってきた能力なんか、そういう場面では何の役にも立ちません。コラボレーションで必要なのは、汎用性の高い知的能力です。交渉力、調停力、胆力、共感力、想像力...そういうものです。だから、学校教育の本旨はそういう汎用性の高い知的能力を育ててゆくことでなければならない。それが子どもたちに本当に必要な、生きる知恵と力なんです。そういう力を高めてゆくことが、子どもたちの市民的な成熟を支援するということです。同学齢集団内の相対的な優劣を競わせて、お互いの知性が活発化するのを邪魔し合ってゆけば、子どもたちの生きる知恵と力はどんどん減退してゆく。それは今の日本の現実を見ればわかるはずです。 僕は、神戸の道場で合気道という武道を教えています。門人は今300人ぐらいです。僕のところでも段位や級は出しています。そういうものがある方が励みになるらしいから。ですから、門人たちは昇段級審査の前になると集中的に稽古をします。なんとか時間をやりくりして道場に来て、自主的に稽古をしている。そういうふうに集中的に稽古することで、ある「壁」を超えるということも現にあります。ですから、僕は段位や級を出すことの効用は認めてます。でも、それは「そういうもの」がある方が一人一人の力が伸びる確率が高いという経験知に基づいてのことです。段位の上下を比べたり、誰が早く昇段したのか、誰が遅いかというようなことは一切口にしない。別に抑制しているわけではなく、僕はそんなこと考えたこともないから。門人同士を比べて、この人の方がこの人より巧い、この人の方が強い、というようなことは考えたことがない。門人同士の相対的な優劣を比較することなんか、修業上何の意味もありません。優劣を比較する対象があるとしたら、それは「昨日の自分」だけです。「昨日の自分」と比べて「今日の自分」がどう変化したのか、それは精密に観察しなければなりません。昨日まで気づかなかったどういう感覚が芽生えたか。昨日までできなかったどういう動きができるようになったか。そこには注意を向けなければいけない。でも、同門の他人と自分を比べて、その強弱や巧拙などを論じても何の意味もない。ほんとうに何の意味もないのです。修業の妨げにしかならない。 僕の師匠は多田宏先生という方です。以前先生から「他人の技を批判してはいけない」と教えられました。僕はその時はまだ若くて、先生の意図よくわからなかった。口には出しませんでしたけれど、「他人の技の欠点に注目するのは有用なのではないか」と内心では思いました。先輩の技を注視して、あの人はここがよくない、あの人はここが優れている、この道場では誰それさんがやっぱり一番うまい、あの人は段位は高いが技術は劣るとか、そういうことを同門同士で論じ合ってもいいんじゃないかと思っていたからです。それが修業の役に立つと思っていた。 たぶん僕が得心のゆかない顔をしていたからでしょう、先生は僕の方を見て、「他人の技を批判してうまくなるのなら、俺も朝から晩まで他人の技を批判しているよ」と言って笑って去っていかれた。その時の先生の言葉が今でも心に残っています。他人と自分の間の技術の相対的な優劣など論じても、そんなことは自分の修業に何の役にも立たない。それを骨身にしみるような言葉で教えられました。 それはまさに武道修業者の基本として、澤庵禅師の『太阿記』の冒頭に掲げられている言葉です。 「蓋(けだ)し兵法者は、勝負を争わず、強弱に拘(こだわ)らず、一歩を出でず、一歩を退かず、敵、我を見ず、我、敵を見ず、天地(てんち)未分(みぶん)陰陽(いんよう)不到(ふとう)の処に徹して直ちに功を得べし」。 兵法者の心得として、まず勝負を争わないこと、強弱にこだわらないことと書いてあります。修業の第一原則がこれなんです。相対的な優劣にこだわってはならない。それは自分の力を高めていく上で必ず邪魔になる。勝てば慢心するし、負けたら落ち込む。そんなことは修業にとって何の意味もありません。修業というのは、毎日淡々と、呼吸をするように、食事をしたり、眠ったりするのと同じように、自然に、エンドレスに行うことが肝要なのです。だから、修業には目標というものがありません。 スポーツの場合だと、試合というものがあります。ある場所、ある時点に能力のピークが来るように設定して、それが終わったら、しばらく使い物にならないというようなことが許される。それは試合がいつどこでどういう形態で行われるか事前に開示されているからです。でも、武道が涵養している能力はそういうものではない。どんな危機的局面に際会しても、適切にふるまって、生き延びる力です。その語義からして、「危機」とは、それが何であって、いつどこで遭遇するかわからないものです。天変地異でも、テロでも、パンデミックでも、ゴジラ来襲でも、どんな状況でも適切に対応できる力を「兵法者」は修業する。それは試合に合わせて「ピーク」を設定するとか、ライバルとの相対的な優劣について査定したり、成績をつけたり、それに基づいて資源分配するということとはまったく別の活動です。
われわれは子どもたちを格付けして資源分配をするために教育をしているのか、それとも子どもたち一人一人のうちの生きる知恵と力を育てるために教育しているのか、そんなことは考えるまでもないことです。そして、一人一人の生きる知恵と力を高めるためには他人と比べて優劣を論じることには何の意味もありません。まったく、何の意味もないのです。有害なだけです。でも、現在の学校教育ではそれができない。全級一斉で授業をするという縛りがありますから、一人一人をそれほど丹念に観察できないというのはわかります。でも、授業を子どもたちの査定や格付けのために行うことについてはもっと痛みを感じて欲しいと思います。それはほんとうは学校でやってはいけないことなんです。 「日本の学校教育をよくする方法がありますか」とよく聞かれます。ですから、僕の答えはいつも同じです。「成績をつけないこと」です。でも、それを言うと、教員たちはみんな困った顔をするか、あるいは失笑します。「それができたら苦労はないですよ」とおっしゃる。でも、ほんとうにそれほど「それができたら苦労はない」ことなんでしょうか。 僕は現に武道の道場という教育機関を主宰していて、そこでは「成績をつけない。門人たちの相対的な優劣に決して言及しない」ということをルールにしていますが、実に効率的に門人たちは力をつけて、ぐいぐいと伸びています。道場では査定ということをしない。寺子屋ゼミという教育活動も並行して行っていますけれど、ここでも研究の個別的な出来不出来についてはかなりきびしいコメントをすることもありますけれど、ゼミ生同士の優劣について論じることは絶対にしません。
どうして教育の場で、教わる者たちは、指導者によって査定され、格付けされ、それに基づいて処遇の良否が決まるということが教育にとって「当然」だと信じられるのか、僕にはそれがわかりません。明らかにそれは教育にとって有害無益なことです。それは40年近く教育という事業に携わってきた者として確信を以て断言できます。 僕は、一昨日に千葉の保険医たちの集会に呼ばれてお話をしてきました。懇親会で隣にいた保険医の方から「医療と市場原理はどうしてもなじまないのですけれども、どうしたらいいでしょう」と訊かれました。その質問には「苦しんでください」と答えました。にべもない答えだったとは思いますけれど、仕方がないのです。医療と市場原理は並立しないからです。並立しないものを並立させてようとしているのだから、苦しむ以外にない。 医療というのは、医療を求める全ての人に、分け隔てなく、最高の質の医療を、ごくリーズナブルな代価で、できれば無償で提供することを理想としてます。そういう仕組みを作ることが医療の理想なわけですけれども、市場原理の中では、そうはゆかない。市場原理に即して考えると、医療は医師の技術・医療機器・医薬品・看護介護のサービスという「商品」として仮象する。だから、需給関係に従って、その「商品」に一番高い値を付ける人が所有することができる。アメリカはもうそうなっています。医療は市場で貨幣で買うものだと思われている。だから、お金をもっている人は最高の医療技術を享受できるけれど、貧困層は最低レベルの医療しか受けられない。富裕層は金に糸目をつけずに最高の医療スタッフを「侍医」として雇用することができるけれど、保険医療しか受けられない患者は、最低の医師、最低の看護師、最低の医療設備の病院にしか行けない。そのような最低の治療さえ受けられない人もいる。 でも、本来、医療というのはそういうものであっていいはずがない。「ヒポクラテスの誓い」というのは古代ギリシャの医療人の誓いで、いまでもアメリカの医学部卒業式ではこの誓言をするはずですけれども、そこには「患者が自由人であろうと奴隷であろうと医療内容を変えてはならない」と謳ってあります。最古の医療倫理が「医療は患者の個人的属性に従って変えてはならない」ということなのですが、そのヒポクラテスの倫理がもう守られていない。これはヒポクラテスの誓いの方が正しくて、市場原理の方が間違っているのです。だから、「どうしたらいいでしょうか」と訊かれても「苦しんでください」としか言いようがない。医療の理想は実現することが難しい。かといって市場原理に従ってゆけば、超富裕層が医療資源を独占して、貧しい者は医療の恩恵を受けられないという古代ギリシャ時代以前の未開社会にまで退化してしまう。市場原理に委ねるとある種の領域では制度は限りなく劣化するという平明な事実を直視すべきなんです。それを直視したくないというのなら、苦しむしかない。 それは、教育も同じです。われわれの共同体を担っていく次世代の若者たちの知性的な、感性的な、そして、霊性的な成熟を支援することが教育本来の目的です。ヒポクラテスの誓いと同じく、本来であれば全ての集団の、すべての子どもたちに同じ質の教育機会が与えられるべきなんです。だから「義務教育」なんです。集団には次世代を教育する義務が課されている。 何万年も前の小さな集団で暮らしている太古の時代から、子どもたちがある年齢に達したら、年長者たちが子どもたちを集めて、「生きる技術」を教えました。狩猟の仕方とか、農耕の仕方とか、魚の獲り方とかを教えた。そういう技術を学ばないと子どもたちは生き延びることができず、集団が消滅してしまうからです。集団を存続させるためには、子どもたちに、ある年齢に達したら「生き延びるための知識と技術」を教え込む。それが教育です。 教育する主体は集団なのです。そして、教育の受益者も集団なのです。集団が存続していくというしかたで集団が受益する。でも、今の教育では、子どもたちは消費者として「教育商品」を購入している気でいます。高い学歴を持ち、ハイエンドな資格とか免状を持っていたら、社会的地位が上がり、年収も上がり、威信も享受できる。だから、教育は商品だ、と。よい教育を受けたいというのは、よい洋服が欲しい、よい時計が欲しい、よい車が欲しいというのと同じだ、と。そういうものは自分の身を飾るものなのだから、自分の財布から金を出して買え、と。どうして税金を投じて、すべての子どもたち公教育を施さなければいけないのか、意味がわからないという人が現にいくらでもいます。 でも、何度でも申し上げます。教育は買い物とは違います。教育は集団の義務なんです。教育の受益者は子どもたち個人ではなく、共同体そのものです。共同体がこれから継続し、そこで人々が健康で文化的な生活ができるように、われわれは子どもを教育する。 でも、市場原理を持ち込んでくると、この筋目がまったく見えなくなってしまう。市場原理では、教育する主体は先生たち個人だとみなされる。集団ではないのです。教員個人の「教育力」なるものが数値的に表示されて、それに対して報奨や処罰が用意される。高い教育力を持つ教員個人が高い格付けを受けて、高い給与や地位を約束される。教育力の低い教員は低い格付けを受けて、冷遇される。それと同じように、教育を受けたことの利益は個人にのみ帰属する。知識も技術も、自分がその後他の同胞たちよりも高い地位に就き、高い年収を得るために、排他的に利用される。それがフェアネスだと信じている人が現代日本ではマジョリティを占めている。 教育するものからも、教育を受けるものからも、「共同的」という本来の契機がまったく脱落したのが、現在の教育です。教育活動は個人のではなく、集団の営みであるということを理解していない教員さえたくさんいます。 大事なことなので、何度でも申し上げますけれど、教育の主体は集団です。教育は集団で行うものであり、教育を受けるのは個人ですけれど、その個人の活動から受益するのは集団です。「ファカルティー(faculty)」というのは「教師団」という意味です。教育活動を行うのは「ファカルティ―」であって、教員個人ではありません。「ファカルティ―」というのは、同じ学校で、同じ学期に、職員室で机を並べて仕事している同僚たちだけのことではありません。今教えている子どもたちがこれまで就いて学んできたすべての教師たち、子どもたちの周りにいたすべての年長者たちと共に、われわれは「ファカルティー」を形成している。僕たちは、僕たちに先行する教師たち・年長者たちからいわば送り出され、手渡された子どもたちを受け取り、自分たちに教えられることを教え、それを次の教師たちに「パス」してゆく。そのすべての大人たちが「ファカルティ―」を形成している。 僕が神戸女学院大学に在職していた頃の話です。あの学校は同窓会の結束が固くて、卒業生がしばしば遺産を学校に贈与してくれます。部長会の席で、亡くなった卒業生から遺言で学校宛てに何千万円のご寄贈がありましたということを経理部長がしばしば報告してくれました。それを聞く度に、「ありがたいことだ」と思いながら、微妙に気持ちが片づかなかった。 85歳ぐらいで亡くなった卒業生からの遺産贈与だとすると、その人が神戸女学院に通っていたのは、今からもう70年ぐらい前なわけです。70年前ぐらいに受けた教育に対する感謝の気持ちを遺産として遺してくださったわけですけれど、僕たちはもうその人を教えた先生たちの顔も名前も知らない。みなさん、とっくにお亡くなりになっている。その人たちが行ったすばらしい教育への感謝の気持として遺産贈与があるのだけれど、今この学校で働いている教員たちに、果たしてそれを受け取る資格はあるのか、そう考えてしまったのです。だから、片付かない気持ちがした。 でも、しばらく考えて、これはやっぱり受け取っていいのだと思うようになりました。というのは、僕が今ここで必死に教育を行って、そのおかげでそれから後の人生が豊かなものになったと思ってくれた卒業生が、仮に今から70年後に神戸女学院に対して遺産を寄贈してくれたとします。その場合、遺産を受け取ることになった教員たちは、僕たちのことなんかもう覚えていないわけです。名前も知らないし、何を教えたのかも知らない。でも、もしそういうことがあったら、70年後の教師たちにはその遺産を喜んで受け取って欲しいと思います。というのは、教育活動というのは、「ファカルティー」が行うものだからです。70年前にここで教えた人たち、70年後にここで教える人たち、もう死んでしまった教師たち、まだ生まれてもいない教師たち、彼らを僕たちは一つの「ファカルティ―」を形成している。150年にわたってこの学校で教えた、これから教えることになるすべての教師たちと共に僕は「ファカルティ―」を形成している。卒業生の感謝の気持はたまたまその事案が発生した時に在職していた教職員が受け取るのではなくて、「ファカルティー」が受け取るのです。 教育の主体は集団である、教育は集団的な事業であるというのはそのことです。「教師団」には、今この学校で一緒に働いている人びとだけではなく、過去の教師たちも未来の教師たちも含まれている。そういう広々とした時間と空間の中で、教育活動は行われている。そして、そういうような時代を超えた集団的活動が可能なのは、教育事業の究極の目的が「われわれの共同体の存続」をめざすものだからです。 だから、教育政策の適否を計る基準は一つしかないと僕は思っています。それはその政策を実行することが子どもたちの市民的成熟に資するかどうか、それだけです。市民的成熟に資することであればよい。市民的成熟に関係のないこと、それを阻むものは教育の場に入り込ませてはいけない。それだけです。そういう基準で教育政策の適否を判定したら、今の文科省が主導している教育政策のほとんどは、子どもたちの市民的成熟にまったく何の関係もない、むしろそれを阻害するものだということがわかると思います。でも、そういうまっとうな基準で教育政策の適否を判定する習慣をわれわれは失って久しい。それが現在の日本の教育の混乱と退廃をもたらしている。 では、どうしたらいいのかと。まだもう少し話す時間が残っているようですから、ちょっとだけ話します。大した知恵がなくて、できないことばかり言って本当に申しわけないのですが、一つは、保険医の方に言ったのと同じで、「とにかく苦しんでください」ということです。そして、先ほども言ったように、できることなら成績をつけないでもらいたい。成績をつけてもそれほど教育活動が阻害されない教科もあるかも知れませんが、できればどの教科でも何とか成績をつけないで進めて頂きたい。カリキュラムのどこかに、子どもたちが誰とも競争しないで済む時間帯を設けて欲しい。昨日の自分と今日の自分の変化を自分ひとりで観察する。そのような学びの場を何とか立ち上げて頂きたいと思います。 もう一つ、今は英語教育にとりわけ中等教育では教育資源が偏ってきています。他の教科はいいから、とにかく英語をやれという圧力が強まっています。別にそれは英語の教員たちが望んだことではないのだけれど、教育資源が英語に偏っている。特に、オーラル・コミュニケーション能力の開発に偏っている。何でこんなに急激にオーラルに偏ってきたかというと、やはりこれは日本がアメリカの属国だということを抜きには説明がつかない。 「グローバル・コミュニケーション」と言っても、オーラルだけが重視されて、読む力、特に複雑なテクストを読む能力はないがしろにされている。これは植民地の言語教育の基本です。 植民地では、子どもたちに読む力、書く力などは要求されません。オーラルだけできればいい。読み書きはいい。文法も要らない。古典を読む必要もない。要するに、植民地宗主国民の命令を聴いて、それを理解できればそれで十分である、と。それ以上の言語運用能力は不要である。理由は簡単です。オーラル・コミュニケーションの場においては、ネイティヴ・スピーカーがつねに圧倒的なアドバンテージを有するからです。100%ネイティヴが勝つ。「勝つ」というのは変な言い方ですけれども、オーラル・コミュニケーションの場では、ネイティヴにはノン・ネイティヴの話を遮断し、その発言をリジェクトする権利が与えられています。ノン・ネイティヴがどれほど真剣に、情理を尽くして話していても、ネイティヴはその話の腰を折って「その単語はそんなふうには発音しない」「われわれはそういう言い方をしない」と言って、話し相手の知的劣位性を思い知らせることができる。 逆に、植民地原住民にはテクストを読む力はできるだけ付けさせないようにする。うっかり読む力が身に着くと、植民地の賢い子どもたちは、宗主国の植民地官僚が読まないような古典を読み、彼らが理解できないような知識や教養を身に付ける「リスク」があるからです。植民地の子どもが無教養な宗主国の大人に向かってすらすらとシェークスピアを引用したりして、宗主国民の知的優越性を脅かすということは何があっても避けなければならない。だから、読む力はつねに話す力よりも劣位に置かれる。「難しい英語の本なんか読めても仕方がない。それより日常会話だ」というようなことを平然と言い放つ人がいますけれど、これは骨の髄まで「植民地人根性」がしみこんだ人間の言い草です。「本を読む」というのはその国の文化的な本質を理解する上では最も効率的で確実な方法です。でも、植民地支配者たちは自分たちの文化的な本質を植民地原住民に理解されたくなんかない。だから、原住民には、法律文書や契約書を読む以上の読解力は求めない。 今の日本の英語教育がオーラルに偏って、英語の古典、哲学や文学や歴史の書物を読む力を全く求めなくなった理由の一つは「アメリカという宗主国」の知的アドバンテージを恒久化するためです。だから、アメリカ人は日本人が英語がぺらぺら話せるようになることは強く求めていますけれど、日本の子どもたちがアメリカの歴史を学んだり、アメリカの政治構造を理解したり、アメリカの文学に精通したりすること、それによってアメリカ人が何を考えているのか、何を欲望し、何を恐れているのかを知ることはまったく望んでいません。 言語は政治的なものです。オーラル・コミュニケーションはとりわけ政治的な力の差が際立つところです。一方が母語で話し、一方が後天的に学習した外国語で話して、そこで議論する、対話する、合意形成するということがどれほどアンフェアで、不合理なことか。英語が国際的共通語であるのは、英米が二世紀にわたって世界の覇権国家であったからです。それだけの理由です。だから、英語圏の人々は母語を話せば国際会議で議論でき、国際学会で発表できる。われわれ非英語圏の人間は、英語学習のために膨大な時間と手間をかけなければならない。それは計り知れないハンディキャップを課されているということです。超大国の覇権が恒久化されるように、言語状況そのものが設計されている。それは冷厳な歴史的事実なわけですから仕方がないことです。でも、「アンフェアだ」ということは言い続ける必要がある。 もう一つオーラル・コミュニケーションが重要視されるのは、オーラルだと、その出自が一瞬で判定できるからです。ネイティヴ・スピーカーなのか、長くその英語圏の国で暮らして身に付けた英語なのか、日本の学校で日本人に習った英語なのか、一瞬でわかる。これをverbal distinctionと言います。「言語による差別化」です。映画『マイ・フェア・レディ』の原作はバーナード・ショーの『ピグマリオン』という戯曲ですが、映画でも戯曲でも、テーマはこの「言語による差別化」でした。 映画の冒頭に、ヘンリー・ヒギンズ教授が、オペラハウスの前で、見知らぬ人に向かって、「あなたはどこの出身だ、職業は何だ」と次々と言い当てて気味悪がられるという場面がありますね。ヒギンズ教授は音声学の専門家ですから、一言聞いただけで、その人の出身地も階層も職業も学歴もことごとく言い当てることができる。でも、ヒギンズ教授はその能力を誇ってそうしているわけではないのです。イギリスでは、誰もが口を開いた瞬間に所属階級がわかってしまう。そういうかたちで「差別」が自動的に行われている。教授はそれはよくないことだと考えているのです。そして、自分はこのような「言語による差別化」を廃絶して、すべての人間が「美しい英語」を話す社会を実現するために研究をしているのだ、と語るのです。そこに花売り娘のイライザがあらわれて、すさまじいコックニーで話し始める。そこからご存じの物語が始まる。 でも、今日本で行われているオーラル中心の英語教育は、この時のヒギンズ教授の悲願とは、まったく逆方向を目指しています。一言しゃべった瞬間に、オーラル・コミュニケーション能力が格付できるシステムを構築しようとしている。これはまさに植民地の言語政策以外の何物でもない。 植民地英語を教えようとしている人たちの言うことはよく似ています。文法を教えるな、古典を読ませるな、そんなのは時間の無駄だ。それよりビジネスにすぐ使えるオーラルを教えろ、法律文書と契約書が読める読解力以上のものは要らない。そう言い立てる。それが植民地の言語政策そのままだということ、自分たちの知的劣位性を固定化することだということに気が付いていない。 植民地的な言語教育の帰結は、母語によっては自分の言いたいことを十分に表現できなくなるということです。フィリピンは現地語のタガログ語がありますけれども、旧植民地ですから、宗主国の言語である英語ができないと、官僚にもビジネスマンにも教師にもなれない。それは、生活言語であるタガログ語では、ビジネストークもできないし、政治・経済についても、学術についても語れないからです。母語にはそのための語彙がない。ある程度知的な情報を含む会話をするためには、英語を使うしかない。「フィリピンの人は英語がうまくて羨ましい」というようなことを無反省に言う人がいますけれど、フィリピン人が英語に堪能なのは、アメリカの植民地であり、母語を豊かなものにする機会を制度的に奪われていたからです。その歴史も知らないで、「なぜフィリピンの人はあんなに英語がうまいのに、日本人はダメなんだ」というようなことを言っている。そして、「そうだ。日本をアメリカの植民地にしてしまえば、日本人は英語が堪能になるに違いない」と本気で思っている。 母語を豊かなものにするというのは、あらゆる言語集団にとっての悲願です。というのは、すべての知的イノベーションは母語で行われるからです。先ほどは「母語の檻」からどうやって離脱するかというようなことを言っていたのに、話が違うではないかと思われる方もおられるでしょうけれど、そういうものなのです。全てのものには裏表がある。いいところもあれば、悪いところもある。外国語を習得するというのは「母語の檻」から出て知的なブレークスルーを遂げる貴重な機会なのですけれど、私たちは他の誰にもできないような種類の知的なイノベーションを果たすためには、それと同時に母語のうちに深く深く分け入ってゆくことが必要なのです。ほんとうに前代未聞のアイディアというのは母語によってしか着想されないからです。 僕はおととし池澤夏樹さん個人編集の「日本文学全集」で、『徒然草』の現代語訳をやりました。高橋源一郎さんが『方丈記』、酒井順子さんが『枕草子』を訳して、僕が『徒然草』というラインナップの巻です。池澤さんから依頼があった時に、『徒然草』なんて大学入試の時から読んでないので、できるかなと思ったのですが、とにかく引き受けて、古語辞典を片手に一年かけて訳しました。 やってみたら、結構訳せました。『徒然草』は800年前の古典なんですけれど、なんとか訳せた。そして、こういう言語的状況というのは、他の東アジアの諸国にはちょっと見られないんじゃないかなと思いました。古典を専門にしているわけでもない現代人が辞書一冊片手に古典を読んで、訳せるというようなことは中国でも、韓国でも、ベトナムでも、インドネシアでも、まず見ることのできない景色だと思います。 どうしてそんなことが可能なのか。それは日本語が大きな変化をこうむっていないからです。明治維新後に、欧米から最新の学術的な概念とか政治や経済の概念が輸入されましうたけれど、テクニカルタームを加藤弘之、西周、中江兆民、福沢諭吉といった人たちが片っ端から全部漢字二語に訳してしまった。natureを「自然」と訳し、societyを「社会」と訳し、individualを「個人」と訳し、philosophy を「哲学」と訳し...というふうにすべて漢字二字熟語に置き換えた。これはたいした力業だったと思います。 こういうことができたのも、日本列島の土着語に中国から漢字が入って来た時も、現地語を廃して、外来語を採用するということをせず、土着語の上に外来語を「トッピング」して、ハイブリッド言語を作ることで解決した経験があったからです。昔は「やまとことば」の上に中国語をトッピングして日本語を作った。ひらかなもカタカナも漢字から作った。明治になったら、今度は英米由来の概念を漢訳して、それを在来の母語の上にトッピングして新しい日本語を作った。日本語はこういうことができる言語なんです。そのおかげで、日本は短期間に近代化を遂げることができた。 中国の近代化が遅れた理由の一つは、欧米の言語を音訳したからです。中国語そのものを変えることを望まなかった。欧米の単語を漢訳して、新しい語を作るということは、中国語には存在しない概念が中国の外には存在することを認めるということです。これは世界の中心は中国であり、すべての文化的価値は中国を源泉として、四囲に流出しているのだという「中華思想」になじまない。だから翻訳しないで、そのまま音訳して中国語の言語体系に「トランジット」での滞在を認めただけで、言語そのものの改定を忌避した。 孫文はルソーの『民約論』を参考にして辛亥革命の革命綱領を起案したそうですけれど、孫文が用いたのは中江兆民の漢訳でした。兆民はルソーをフランス語から和訳と漢訳を同時に行ったのです。そういうことができた。土着語に漢語を載せるのも、土着語に欧米語を載せるのも、プロセスとしては同じことだったからです。 漱石も鷗外も荷風も、明治の知識人は漢籍に造詣が深かった。漱石は二松学舎で漢学を学んだあと英語に転じます。漱石がイギリス文学と出会っても、それに呑み込まれることがなかったのは、英文学のカウンターパートに相当する深みのある文学的なアーカイブが自分の中にすでに存在していたからです。すでに豊かな言語的資源を自分の中に持っていたからこそ、自在に新しい外国語に接することができた。だから、外国語を学ぶことと並行して、母語を深く学ぶ必要がある。そうしないと外国語に呑み込まれてしまう。知的なイノベーションで大きなハンディを背負うことになります。 というのは、ネオロジスム(新語)を作ることができるのは母語においてだけだからです。後天的に習得した外国語では新語や新しい概念を作ることはできません。僕が英語やフランス語で、勝手に新しい言葉を作っても、相手には全然通じない。I went というのは不規則変化で面倒だから、これからはI goed にしようと提案しても、英語話者は誰も相手にしてくれない。言っても鼻先で笑われるだけです。 でも、母語の場合だったら、「そんな言葉はない」「そんな意味はない」というかたちで新語が否定されることはない。だって、通じてしまうから。誰かが言い出した新語の意味がわかると、次は自分がそれを使い始める。ある人が、ふっとネオロジスムを思いついた時点で、それは潜在的には日本語のボキャブラリーにすでに登録されているのです。 前に温泉に行ったときに、露天風呂に入っていたら、あとから若い学生が二人入って来て、湯に浸かると同時に「やべ〜」と呟いたことがありました。もう10年近く前でしょうか。その時に「ああ、そうか。『やばい』というのは、『大変気持ちがいい』という新しい語義を加えたのだな」とわかりました。実際に今出ている国語辞典には「最高である、すごくいい」という新しい語義がすでに加筆されております。 「やばい」はもとからある語に新しい語義が加わった事例ですけれど、「真逆」というのは新語です。最初に聴いたのは高橋源一郎さんとしゃべっている時でした。「まぎゃく」という音を聞いただけで「真逆」という文字が自動的に脳裏に浮かびましたし、「正反対」の強い表現だということもわかりました。説明されなくても、わかる。 よく考えたら、これはすごいことですよね。新語や、新概念は発語された瞬間に、母語話者にはそれが何を意味するかがわかるのです。それは新語、新概念というのが、個人の思い付きではなくて、母語の深いアーカイブの底から泡のように浮かび上がってきたものだからです。最初にそれを口にした人はその「泡」をすくい上げて言葉にしたのです。創造したわけじゃない。だから、母語話者にはその意味がすぐわかる。 イノベーションというのは新語、新概念を創造することです。新しい言葉が、誰も聴いたことのない新しい言葉であるにもかかわらず、発語された時点ですでに母語において「受肉」している。だから、「あ、そういうことね」だと理解される。「それって、これまで誰も言ったことがないことだね」と理解される。変な話ですよね。新しい言葉が「これまで誰も言ったことのない言葉」として、その意味も用法もセットで受け容れられるんですから。母語ならそれができる。そして、外国語では、できない。 だから、本当に新しいものを発明しようと思ったら、われわれが作り出したものが世界標準になるとしたら、それは母語における新語というかたちで潜在的にはすでに語彙に登録されたかたちで登場してくるのです。 母語のアーカイブはそれだけ豊かだということです。日本の古語はある種の外国語なわけですけれど、少し読み慣れると、すぐにニュアンスがわかるようになる。古典を読んでゆくと、1000年前、500年前の日本人に世界がどう見えていたのか、彼らがどのようなコスモロジーのうちで生きていたのかが追体験される。これもやはり「母語的現実」からの離脱の経験であるわけです。 ただ、古典を学ぶというのと、英語を学ぶというのはぜんぜん異質の経験です。古典といっても日本語です。僕たちが今使っている現代日本語は、この古語から生まれて来た無数の「新語」の蓄積で出来ている。もとはと言えば、すべての日本語はこの古語のアーカイブのうちに起源を持っている。そこから浮かんできた「泡」の集大成が現代日本語なんです。吉田兼好を800年前からタイムマシンに乗せて現代に連れてきても、たぶん一月くらいで現代日本語をだいたい理解できるようになると思います。同じ生地で出来ているんですからわからないはずがない。 古典はある種の外国語であるにもかかわらず、その習得が異常に簡単です。なぜなら、知らないはずの単語や言い回しの意味が「なぜかわかる」から。『徒然草』で面白かったのは、『徒然草』の専門家の方からメールを頂いて、「訳文が正確だ」とほめて頂いたことです。特に係り結びの訳し分けがよかったと書いてありました。僕は係り結びにいくつもの意味の違いがあって、それは厳密には訳し分けないといけないということを知らなかったので、びっくりしました。文法規則を知らなかったのに、正しく訳せてしまった。そういうことが起きるのは、それが日本語で書かれていたからですね。 自国語の古典をまず学ぶこと。アクセスしやすい外国語をまず学んで、異なる言語形式で世界を分節する人たちの思念や感情を想像的に追体験すること。これはそれから後に外国語を学ぶ基礎としてとても有用な経験になるだろうと思います。 1960年代はじめに、江藤淳がプリンストン大学に留学したことがあります。江藤はプリンストンで日本文学を講じていました。英語で授業をやり、英語で論文を書いて、途中から夢も英語でみるようになったそうです。けれども、帰ってきた後に、新しいものを作ろうと思ったら、日本語で考えるしかないと思うようになった。思考がかたちをなす前の星雲状態にまで遡ることができるのは母語においてだけだからというのです。 「思考が形をなす前の淵に澱むものは、私の場合あくまでも日本語でしかない。語学力は習慣と努力によってより完全なものに近づけられるかも知れない。(...)しかし、言葉は、いったんこの『沈黙』から切りはなされてしまえば、厳密には文学の用をなさない。なぜなら、この『沈黙』とは結局、私がそれを通じて現に共生している死者たちの世界−日本語がつくりあげて来た文化の堆積につながる回路だからである。」(『近代以前』) われわれが使っている日本語のアーカイブのうちには、これまで日本列島に住み、言語を語ってきたすべての人々の記憶と経験が蓄積されていて、「淵」のようなものをかたちづくっている。この「淵」からしか、新しい言語的な創造を汲み出すことはできない。 江藤はこの母語のアーカイブのことを「沈黙の言語」と呼びます。かつて同じ言語を語ったすべての死者たちから遺贈された言語経験の総体、その「淵」に立つことによって初めて文学的な創造ができるのだ、と。 これとほとんど同じことを村上春樹も書いています。村上春樹はアメリカやイギリスやイタリアやギリシャや、世界中で暮らしていて、最後にボストンで河合隼雄さんと出会い、それが一つのきっかけになって日本に帰ってくるのですけれども、江藤淳と非常に似たことを言っています。 「どうしてだかわからないけれど、『そろそろ日本に帰らなくちゃなあ』と思ったんです。最後はほんとうに帰りたくなりました。とくに何が懐かしいというのでもないし、文化的な日本回帰というのでもないのですが、やっぱり小説家としての自分のあるべき場所は日本なんだな、と思った。というのは、日本語でものを書くというのは、結局思考システムとしては日本語なんです日本語自体は日本で生み出されたものだから、日本というものと分離不可能なんですね。そして、どう転んでも、やはり僕は英語では小説は、物語は書けない。それが実感としてひしひしとわかってきた、ということですね。」(『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』) 村上さんはデビュー作『風の歌を聴け』を最初は英語で書いて、それを自分で日本語に訳すというかたちで書き出したそうです。それがあの独特の文体の原型になった。でも、村上春樹さんも最終的には世界文学になるためには日本語の「淵」に立ち戻ってきた。その消息は河合隼雄さんとの次のやりとりから伺えます。
「村上 あの源氏物語の中にある超自然性というのは、現実の一部として存在したものなんでしょうかね。
河合 どういう超自然性ですか 村上 つまり怨霊とか... 河合 あんなのはまったく現実だとはいます。 村上 物語の装置としてではなく、もう完全に現実の一部としてあった? 河合 ええ、もう全部あったことだと思いますね。だから、装置として書いたのではないと思います。」(『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』)
河合隼雄さんはこの時に『源氏物語』に出て来る六条御息所の生霊は文学的虚構ではなくて、平安時代の人たちにとってはありありとした現実だったと断定するわけです。そのような物語的現実の中で人間は生き死にしているのだ、と。それを聞いて村上さんはそれ以外の外国語では文学的虚構でしかないものが、日本語のうちでは現実としてありありと顕現することがあり得るということに深く納得する。現実を創り出すのは、それを語る言語である。だから、本当に「世界のここにしかないもの」を創造しようと望むなら、自分の母語のうちに立ち返るしかない、村上春樹はそう考えた。江藤淳が日本語の「淵」に立ち返ろうと思って日本語に帰ったのと、これは同型的なふるまいだろうと僕は思います。
本当に創造的なもの、本当に「ここにしかないもの」は、母語のアーカイブから汲み出すしかない。ですから、どれだけ深く母語のうちに沈み込んでゆくかということと、母語をどうやってより豊かなものにするかということが、同時に文学者の課題になるわけです。それこそがそれぞれの国や地域の文化の質を高めるためにまずなすべきことなのです。 でも、今の日本では、母語に深く沈潜することも、母語を豊饒化することも、教育的課題としてはまず語られることがありません。日本人が日本語によってしか表現できないような新しい概念なり理説なりをどのように提示して、それを世界標準たらしめるのか。それを人類全体の知的資源に登録して、人間の文明をより多様なもの、より豊かなものにしてゆくことにどうやって貢献できるのか。そういう議論を教育論の中で聴くことはまったくありません。 母語の過去に遡ること、母語の深みに沈み込んでゆくこと、これが創造において決定的に重要なことなのです。これもまた僕たちが日常的に囚われている「現代日本語の檻」から離脱するための重要な手立てであるのです。 村上春樹の話ばかりになりますけれど、村上さんはエッセイの中で、はっきりと自分は上田秋成の後継者をめざすと書いています。「雨月物語」と村上文学は直接に繋がっている、と。明治時代の自然主義文学があるけれど、自分は近代文学の文学史的系譜とは無関係であって、上田秋成からダイレクトに繋がっている、と。 まことに奇妙な符合なのですが、上田秋成と現代文学を繋がなければならないということを江藤淳も書いているのです。半世紀以上の隔たりがありながら、江藤淳と村上春樹がともにアメリカから帰ってきたあとに、ほとんど同じことを書いている。それは日本語という回路を通じて、作家はかつて日本語を語ったすべての死者たちと共生しているということです。日本語は「日本語がつくりあげて来た文化の堆積につながる回路」だということです。二人ともに自国文化の「近代以前」の深い闇の中に降りてゆくことが新しいものを創造するためには必要なのだと書いている。そういう言語的な覚醒の経験をこの二人は共有している。 外国語を学ぶことも、母語の「淵」深く沈潜してゆくことも、ともに「母語の檻」から抜け出ることをめざすという点では少しも矛盾していません。言葉を学ぶということは、この二つのいずれをも欠かしてはならない、僕はそう思います。 学校教育の場で子どもたちに教えるべきことは、「君たちは君たちの言語の虜囚である」ということです。君たちは自由に思考し、自由に感じ、自由に言葉を操っているつもりでいるかも知れないけれど、君たちは実は君たちが閉じ込められている集団的な「言葉の檻」から出ることができないでいるのだ。君たちの語彙も、音韻も、ストックフレーズも、君たちが使うメタファーもレトリックも、すべて「既製品」なのだ。君たちは与えられた言語の中で感じ、考え、語ることを強いられている。でも、君たちの中には自分が「檻」の中にいることを薄々感づいていて、もっと清涼な空気を吸いたい、もっと自由に語りたい、もっと自由に考えたいという願いを抱いている人がいると思う。その人たちに教えたい。「母語の檻」から出るには二つの方法があるよ。一つは外国語を学ぶこと、一つは母語を共にする死者たちへの回路をみつけること。これはとても大切な教えだと思います。 僕は武道を教えていますけれども、それは今の子どもたちに「君たちが自然だと思っている身体運用以外の仕方がある」ということを教えるためです。身体の使いかは言語と同じように構造化されています。子どもたちが現代的な言語運用のルールに繋縛されているように、現代的な身体運用のルールに繋縛されて、それが自然だと思って暮らしている。すべての人間は自分と同じように身体を使って外界を感じ、身体を動かしている、そう素朴に信じ切っているわけです。人間の身体は太古から現代まで、世界中どこでも「同じようなもの」だと信じ切っている。でも、彼らの身体運用はまさに2018年の現代の都市で暮らしている子どもたちに選択的に強制された「奇妙な」身体の使い方なのです。一つの民族誌的奇習なのです。歩き方も、座り方も、表情の作り方も、声の出し方も、すべて集団的に規制されている。
それとは違う身体の使い方があることを、例えば中世や戦国時代の日本人の身体の使い方があることを僕は武道を通じて教えているわけです。子どもたちをその文化的閉域から解放するために武道を教えているわけです。君たちは学べば、ふだんの身体の使い方とは違う身体の使い方ができるようになる。その「別の身体」から見える世界の風景は彼らがふだん見慣れたものとは全く違ったものになる。それは外国語を学んで、外国語で世界を分節し、外国語で自分の感情や思念を語る経験と深く通じています。自分にはさまざまな世界をさまざまな仕方で経験する自由があること、それを子どもたちは知るべきなのです。 結局、教育に携わる人たちは、どんな教科を教える場合でも、恐らく無意識的にはそういう作業をしていると思うのです。子どもたちが閉じ込められている狭苦しい「檻」、彼らが「これが全世界だ」と思い込んでいる閉所から、彼らを外に連れ出し、「世界はもっと広く、多様だ」ということを教えること、これが教育において最も大切なことだと僕は思います。
最初のトピックに戻りますけれども、今行われている英語教育改革なるものは、子どもたちをさらに狭い母語的現実の中に封じ込めようとしています。彼らに現代日本固有の民族誌的奇習を刷り込んで、「これが全世界だ」と錯覚させようとしている点で、ほとんど犯罪的なことだと思います。
いささか過激な言葉を使いましたけれども、おそらく多くの先生方は、実感としては僕に同意してくださると思います。すべての教育実践は子どもの知性的な、感性的な成熟を支援するためにある、それに資するかどうかだけを基準にして教育実践の適否は判断されるべきである。これは教育者として絶対に譲れない、どんなことがあっても譲れない一線です。僕と同じように感じてくださる先生方が一人でも増えて下さることを願っています。それを今の日本の学校の中で、やり遂げるのはたいへんなことだと思います。さぞやご苦労されることと思います。 でも、一昨日の保険医さんに言ったように、教育というのは苦しむ仕事なのです。人類が始まった時から存在する太古的な仕事ですから、市場経済や国民国家ができるよりはるか前から存在した職能ですから、市場経済や国民国家となじみがよくないのは当たり前なのです。でも、われわれはすでに市場経済の世界に暮らしており、国民国家の枠内で学校教育をする以外に手立てを持たない。だから、葛藤するのは当たり前なんです。学校教育がらくらくとできて笑いが止まらないというようなことは、現代社会では絶対にあり得ないのです。それは学校教育のやり方が間違っているからではなくて、学校教育は市場経済とも国民国家とも食い合わせが悪いからです。それについては諦めるしかない。むしろ自分たちのほうがずっと前から、数万年前からこの商売をやっているのだからと言って、無茶な要請は押し返す。Noと言うべきことについてはNoと言う。とにかく子どもたちを守り、彼らの成熟を支援する。彼らが生き延びることができるように生きる知恵と力を高める。それがみなさんのお仕事だと思います。 何だか、応援しているのか呪っているのかわからないような講演でしたけれども、とにかくつらい現実をまずみつめて、それから希望を語るということでよろしいのではないかと思います。ご清聴ありがとうございました。
http://blog.tatsuru.com/2019/05/31_0824.html [18初期非表示理由]:担当:混乱したコメント多数により全部処理
192. 中川隆[-9912] koaQ7Jey 2019年5月31日 15:12:32: b5JdkWvGxs : dGhQLjRSQk5RSlE=[2443] 報告
▲△▽▼
2019年05月31日
アメリカ大卒者の半数が、店員など高卒と同じ職業に就いている 学生ローンの負担を含めると生涯収入が高卒を下回る人が増えている
画像引用:https://finance-gfp.com/wp-content/uploads/2018/01/student_loan_entai201801.png
大卒の生涯収入が高卒を下回る 生涯収入を増やすのに最も有効なのは学歴を増やすことで、大卒者の収入は高卒者より多かった。 だがこれはもうアメリカでは過去の話になりつつあり、高卒の生涯収入が大卒を上回る事態になっている。 原因その一は大学卒業に4年かかり、生涯の就労年数も高卒者より4年間短くなるが、従来は年収の多さでカバーしていた。 原因その2は大学卒業までに必要とする費用で、小学校から高校まで良い学校に通う必要がある。 めでたく大学受験に合格してもアメリカの学費は非常に高額なので、学生ローンを借りる事になる。 大学を卒業した時点で多額の教育費を親が負担しているうえに、子供は500万円以上の学生ローンを背負って社会に出る。
加えて高卒者より4年遅く最初の給料をもらい、マイナス500万円から社会人生活をスタートします。
もっとも大学卒業までの教育費や学生ローンを負債として差し引かないなら、大卒の収入は高卒者より多い。 アメリカの学費ローンの残高総額は1.5兆ドル(約164兆円)、平均的なアメリカの大学生は卒業時に400万円の借金がある。
アイビーリーグと呼ばれる有名大学だと、年間費用(学費、寮、その他)は5万3千ドルなので4年間で21万2千ドル(約2300万円)にもなります。
親が金持ちなら自分で払わなくて良いが、そうでなければバイトと学生ローンで払わなくてはならない。 この金額は日本の都内有名大学の4倍以上に達している。(学費は2011年時点なので、現在はもっと高くなっている)
大卒の半数は運転手や店員をやっている
日本でも学生ローンが卒業に重い負担になる奨学金問題が指摘され、破産する人もいるようです。 日本とアメリカの学生ローンには決定的な違いがあり、アメリカのは国がお金を貸しているので自己破産できません。 どれだけ貧困で返済困難であっても破産できないので、破産できるだけ日本の奨学金は良心的と言えます。
アメリカの大学進学率は88%に達していて、もはや高収入を得られる学歴ではなく、最低限必要な学歴になっている。
昔は大学を出れば高収入を得られたが、今は大学を出ても他の人と同じ学歴でしかなくなっている。 そこで学歴で高収入を得ようとする人は、アイビーリーグのようなよりお金がかかる大学を目指している。
こうした高学歴競争が「学歴インフレ」を加速させ、際限のない学費上昇と学生ローンの負担になっている。
調査によると大学卒業者の半数は大卒資格が必要ない職業に就いていて、事実上大学に掛けた時間とお金は無駄になった。 大学で学んだ内容が就職して役立っているなどはあるが、大卒だから高収入とは結びついていない。
大卒で運転手、消防士、店員、サービス業などについている人が半数で、これは社会のメカニズムから考えて止むを得ない。
例え大学進学率が100%になっても運転手やウエイターや店員は必要なので、全員が高収入管理職になることはない。 日本の大学進学率は57%でアメリカより30%も低いので、まだ大卒のメリットが残っている。
だが日本でも大学進学率が8割になったら、半数が高卒と同じ職に就くようになり、大卒だから高収入という事はなくなるでしょう。
http://www.thutmosev.com/archives/79958540.html#more
|
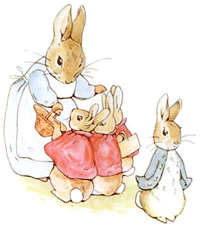
 スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。