|
�u�A���ԌR�v�Ƃ����Ł@�\�@�����A��蔲�����u����̋��|�v�P�X�X�T�N�S�� �@ �� �@ �@�P�X�V�P�N������V�Q�N�ɂ����āA���̍���k���������厖�����N�������B�u�A���ԌR�����v������ł���B �@�A���ԌR�Ƃ́A�����ł��ɍ��I�������u�ԌR�h�v�ƁA�u���{���Y�}�v�����h�_�ސ쌧�ψ���v�i���{���Y�}���珜�����ꂽ�ё�`�҂��O���ɍ�����g�D�j�����̂����R���g�D�ł���A�u���l���ۋ����v���R���I�ɓ��������g�D�ŁA���̍ō��w���҂ɑI�o���ꂽ�̂́A�ԌR�h�̃��[�_�[�ł���X�P�v�B�X�ɑg�D�̃i���o�[�Q�́A���l���ۋ����̃��[�_�[�ł���i�c�m�q�B �@�ނ�͌Q�n���ƒ��쌧�ɂ����āA�u�Y���R�x�x�[�X�����v�Ɓu��ԎR�������v�i��1�j���䂫�N�������B�Ƃ�킯�O�҂̎����́A�g�D���̓��u�𢑍����̖��ɂ����āA���X�ɐ��S�ȃ����`�������A�P�Q�����E�Q�A������������Ƃ��āA���̍��̍����^���j��Ɍ���I�ȃ_���[�W��^�����B �@�Ȃ��A�u��ԎR�������v�͑O�҂̎����Ő����c��A�ߕ߂�Ƃꂽ�����o�[�T�l���A���̌x�@���ǂƂ̏e����Ƃ��ăe���r�Ŏ������p����A�����̍����ɑN��Ȉ�ۂ�^�������A����͂����܂ŁA�u�Y���R�x�x�[�X�����v�i�u�����v�̎��҂̑������u�Y���R�x�x�[�X�v�ɂ����Č��o�������Ƃ���A�ȍ~�A�M�҂͂��̖��̂��g�p�j�̈�A�̗���̒��œˏo���������ł������B�]���āA�u�A���ԌR�����v�́A���́u�Y���R�x�x�[�X�����v���Ȃ��䂫�N�����ꂽ���Ƃ����A���̍\�������𖾂��邱�Ƃ����A���͋ٗv�ł���ƍl����B �@�{�e�́A�����̓����҂̓�����̎҂Ƃ��Ă̖��ӎ�����A�ʼn߂�����̐k�����ׂ��������A��ɐS���w�I�A�v���[�`�ɂ���Č��y�������̂ł���B �i��1�j1972�N�i���a47�j2���A�A���ԌR�̃����o�[5�l���A�y��ɂ���u��ԎR���v�i�͍��y��ۗ̕{���j�ɁA�R���̊Ǘ��l�v�l��l���ɗ��Ă�����A�x�����Əe�����W�J���A3���̋]���҂��o�������ɑS�����ߕ߂��ꂽ�����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@ �@�A���ԌR�����́A���̍��̊v���^���Ƃ������̂��A�����u�₳�����̒B�l��ވꌇ�Ђ̗]�n���Ȃ����Ƃ�I�悵���ɂ߂��̎����ł������B �@�����Ɋ֗^������҂����̉ߏ�ȕ�����x�����v�����z�́A�ނ�̖����ӎ�����Ȃ܂łɋ�藧�ĂāA�����ɑ��˂�ꂽ�Ⴂ�U���I�ȏ�O�̈���A�u�r�Ő�v�Ƃ����ߏ�ȕ���̂����Ɏ��ʂ���Ă����B�������ނ�̕���́A�����Ƃ̉���̐ړ_�����ĂȂ��n���ʼn��\����A���̒n�������̈��|�I�ȕǐ��͎�҂����̎�����A�k�i��������j�ɖ��Ղ����Ă������肾�����B �@�����ɁA���̎��������m�g�[���̉A�S�ȉf���œˏo��������l�́A�ۗ����ĊϔO�I�Ȏw���҂���݂���B�����A��s���鎖�����i�u���F�������v�A�u��Ǎ��n�C�W���b�N�����v�j�ŁA�w�lj�œI�ȏ�Ԃɒu����Ă����ԌR�h�̍��O�����o�[�̎w���I����ɂ����āA�������D�����i�l���j���w���������ɁA�A���ԌR�̍ō��w���҂ƂȂ����X�P�v�i��2�j���̐l�ł���B
�@
�@���̎������A�u��ΓI�Ȏv�z�Ȃ���̂�M����A��҂����ɂ��ЁX�����܂ł̕s�K�Ȃ鎖���v�ƌĂԂȂ�A���̎����̍���ɂ͎O�̗v�������݂���ƁA���͍l����B
�@
�@���̈�B�L�\�Ȃ�w���҂Ɍb�܂�Ȃ��������ƁB �@���̓�B�̒�m��ʕ����B �@���̎O�B�u���Y��`���_�v�ɏے������v�z�Ɛl�Ԋς̌����Ȗ��n���ƕΐ����B
�@
�@�\�\�@�ȏ�̖������y���邱�ƂŁA���͂��̎����̍\�������c���ł���Ǝv���̂��B
�@ �i��2�j1944�N�A���Ő��܂��B���s����w�݊w���ɓc�{�����Əo����đ傫�ȉe�����A�Њw���̊����ƂƂȂ�ԌR�h�ɎQ���B�����A�����̔h���̊������������ꂽ���Ɓi�u���F�������v�j�ŁA�h���̃��[�_�[�i�I���݂ƂȂ�A���Z�@�ւ��P�����A���z�̎�������ɓ���Ă����B�������ɁA�e�C�X���P���ĕ���B���Ă������l���ۋ����Ƃ̘A�g��}�邱�ƂŁA�u�A���ԌR�v����������Ɏ���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�\�\�@�ȉ��A�����̖��ɂ��āA�ڍׂɌ��y���Ă������B �P�D�ō��w���� �@ �@�X�P�v�͂��āA�ԌR�h�̓��Q�o�̋��|����G�O���S��}��A�g�D���痣�E�����Ƃ����ߋ������B�����A�ԌR�h�̑n���҂ł����������F��̈ӌ��ɂ��g�D�ւ̕��A���ʂ������A���́A���̏����������u���_�v���A��̘A���ԌR�����̉A�S���ݏo���S���I�����ɖ�������e����^����g���ƂȂ��Ă��āA�����Γ}���̉ߏ�ȃ��W�J���Y���̖z�����A��l�́u���_�v�̉ߋ��̕⏞�s���ł������ƐS����͂ł���悤�ȑ��ʂ����A�����͏h���I�ɕ�������ł����悤�Ɏv����̂ł���B �@�A���ԌR�����́A�����̕����Ŗ{���I�ɁA���̐X�P�v�Ƃ����j�̎����Ȃ̂ł���B �@���ƌ��͂Ɖ�ȁu�r�Ő�v��킢�����Ƃ����A�ɂ߂��̕���ɐ�����Ⴂ�U���I�ȏ�O�𑩂˂�g�D�̍ō��w���҂Ƃ��ẮA���̒j�͂��܂�ɑ��������Ȃ��߂����B����͂����~�X�}�b�`�ōς܂��ɂ́A�Ƃ��Ă���������Ȃ��قǂ̔���ȑ㏞���߂��Ă���B �@��ɑI��Ă͂����Ȃ��j���ō��w���҂ɌN�Ղ��A��ɉ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������̎w���҂ɂ���ĊJ����Ă��܂����Ƃ��A�Ɋg�U����l�X�Ȑl�ԓI�Ȏv�����s���ɍ킬���Ƃ��Ă����Â�������ٓ������Ȃ���A�����͑����ɏ�B�̌��~���삯�����Ă������̂��B �@�ō��w���҂ɂȂ����X�P�v�Ƃ����l�i�ɂ́A�ō��w���҂ɑ����������x�ŁA�s���Ȏw���҂������邱�Ƃ���ΓI�ɗv������Ă����B�ނ̎���́A�ނ̓�������̂��̗v���ɉ����Ă����Ƃ��������ɂ����A���̈���̍��������o���Ȃ��Ȃ鐢�E�����ɊJ���Ă��܂��Ă���B �@�X�P�v�̎���̒���̂����ɁA���͎����̍ł��[�����ɐ��ށA�����h���h���Ɖt�����b�݂̂悤�ȕ��i���_�Ԍ��Ă��܂��̂ł���B
�@
�@�X�P�v�̒���́A���炭�A�ނ̔\�͂̔��e��y���ɒ������n�����J�����Ă��܂����̂��B �@�����̃R�A�Ƃ�������A�u���Y��`���_�v�i�����ȋ��Y��`�I�l�Ԃ�ڎw�����߂̓}���������A���H�I�ɑI�����Ă������ƂŁA����ׂ��r�Ő�ɔ�����Ƃ������́j�̓o��́A�ނ̎���̒����������W���I�\���ł����āA���̌���ɂ����āA����̎��Ԃ��̂��̂ł������Ɣc���ł��邾�낤�B �@�g�D�I�w���҂Ƃ��Ă̔ނ̕n��Ȕ\�͂́A�����ɁA�l�Ԉ�ʂɑ��鐸�k�Ȋώ@���A�X�̃P�[�X�ɂ�����S���w�I���@�����@�������Ƃ���ɏW���I�Ɍ���Ă��āA�u���Y��`���_�v�̐g�̉��Ƃ������̂������Ă��܂��ł��낤�̕����ߒ��ւ̓��@�ƁA���̉ߒ��䂷��헪���\�z�ł��Ȃ��\�͓I�͔ے肵����̂�����̂��B �@�X�P�v�́A���Ȃ̗���̗D�z�����m�ۂ��邱�ƂɕK�v�ȏ�ɔz�������Ƒz���ł���B �@�R�x�x�[�X�ł̔ނ̎��Ȕᔻ�́A����́u���_�v���w���Ҏ��g���N�����Ƃɂ���Ă��Ȃ��A����̓}���|�W�V��������ɕς��Ȃ��Ƃ����m�M��O��ɂ��邱�ƂŐ������A���̂��Ƃɂ���āA�J��A���̉��ʓ��u����̐S���I�����ƐM�]����ɓ������肩�A�p���č���̎��Ȃ̃C�j�V���e�B�u�̏�����e�Ղɂ���Ƃ����R�X�g�v�Z���A�ނ̓����ɖ��ł��Ă����悤�ɐ��������B����́A���̒j���h���h�������l�ԓI����̑̌��҂ł��邱�Ƃ��v���m�炳��鉼���ł���B �@���̐����ɂ��ƁA�X�P�v�Ƃ����j�́A�������ʂ̊��A�F�m�́A���@�́A�w���́A���A�l���݂̗����I�\�͂������A����������ȏ�ł͂Ȃ������B�����āA���ɕ������ӎ���������ƐM������܂Ŏ��Ԃ�����I�ɏ����ł��Ȃ�����A�e�Ղɏ[���ł��Ȃ�������A�����ǂ����ň��������Ă���悤�ȃ^�C�v�̐l���ł���Ƃ��l������B���ɂ́A�ނ̍U������c�s�����a���I�l���������ɑ���قǂ̂��̂ł���Ƃ͓���v���Ȃ��̂ł���B �@�ԌR�h���ォ��̖��F�A�Ⓦ���v�i��3�j�́u�i�c����ւ̎莆�v�i�ʗ��Њ��j�̒��ŁA�X�P�v�̐l�����𐳊m�ɓ`���Ă���B �@�u�w���҂Ƃ��Ĉ��������Ȃ��Ŋ撣�낤�Ƃ��Ă��邱�ƁA�l�ɂ₳�������ƂŎ��͐M�����Ă��܂����B�����������ɐl�ɑ��Č}���A�Ë�������A�������h����M�O�̂Ȃ����A���x�������Ƃ��ꂫ������o���Ă��邱�Ƃ�m���Ă��܂����v �@���̎w�E�͏d�v�ł���B �@���̂Ȃ�A���̕����̒��ɂ����A�X�P�v�Ƃ������䂪�ʂ������댯�Ȓ���̐S���I�w�i������Ǝv���邩�炾�B �@�X�P�v�Ƃ�������́A���炭�A�����̗��ǂ��ɂ��邩�ɂ��Đ��m�Ɍ������Ă����B���m�Ɍ������Ă������̂ɁA�ނ̎���͂���𑼂̓��u�Ɍ���������邱�Ƃ�����Ă����̂ł͂Ȃ����B�A���A�}�h�Ƃ��Ă̗͊W����Ɉӎ����A�����������Ă������l���ۋ����̔N���̓��m�����ɁA�u�X�P�v�Ƃ����w���҂͑債�����ƂȂ��ȁv�ƕ����邱�Ƃ��ł�����Ă����Ǝv����̂ł���B �i��3�j���呲�B���������A25�B�ԌR�h�o�g�̃����o�[�Ƃ��āA�u��ԎR�������v�ɂ����ă��[�_�[�i�I������S���A�ߕߌ�3�N�ځA���a50�N�A�u�N�A�������v�[���đ�g�ِ苒�����v�ɂ�����u���@�K�I�[�u�v�ɂ���āA�ߕ������Ɏ���B �@���݂ɁA���h�S�Ƃ́A���̒�`�ɂ��A�u����������邱�Ƃւ̋��|���v�ł���B �@����́A����������邱�Ƃ�����鎩�䂪�A���������ꂽ�獢������̉������B�����Ƃ����S��ł���A������Ȃ��A�����ɁA�u�B���˂Ȃ�Ȃ������v������Ă���Ƃ����S���I����������B�u�B���˂Ȃ�Ȃ������v������鎩��́A���ł��W�̓����ɁA������ْ̋����^��ł���̂��B �@�l�Ԃ̎���͐����̗��j�Ղł���Ɠ����ɁA�Љ�I�W�t���̗��j�ՂȂ̂ł���B���������҂̗�ʂɗ��Ƃ��́A��ʂɗ����Ƃ̕����K���ɗL���ł���ƍl���邩�炾�B��ʂɗ��������肪�������U�����ė��Ȃ��Ƃ����m�M���Ȃ���A�l�͌����āA���犸���ė�ʂɗ����Ƃ�I�Ȃ��B�u�N�q�낤���ɋߊ�炸�v�̔@���A���肩��̗L���U����������̂�����X�^���X�̕ӂ�ɂ܂Ō�ނ��邱�ƂŁA��ɓ�ɑ����m����ጸ����w�͂�����̂��܂��A�l�Ԃ̎���̐��v�ȋ@�\�ł���B����͖{�\�ł͂Ȃ��B�S�ẮA�l�Ԃ̓I�w�K�̎Y���ł���B
�@
�@�X�ɕt������A�S���w�ł́A�u�z�E�������͑̂ɗǂ�����H�ׂ�v�Ƃ����̂��ꎞ�I�w�K�ƌĂсA�u�z�E�������͑̂ɗǂ�����H�ׂȂ����v�ƌ����������̋C���������߂ɁA�z�E��������H�ׂ�Ƃ���������I�w�K�ƌĂԂ��A���̐S���͊K�w�I�����𐬂��Ă���B�u���ꂪ�l�Ԃ̐��i���`�����Ă����v�A�ƍ��������a�@�̍���p�q�́A�u����̕�e���v�Ƃ����_���̒��ɏ����Ă���B�i�u�v�t���Ɖƒ�v��菊���@���M���[���j �@����͌��X�A�_�u���o�C���h�����ŗL���ȃA�����J�̎Љ�w�ҁA�O���S���[�E�x�C�g�\������N�����T�O�Ƃ��ėL�������A�l�Ԃ̎���́u�I�w�K�v�̒��ŎЉ���ʂ����A���̒��ōI�݂ɓG������k�������A�D��W�G�ɝn�i������j���グ�Ă����B �@�������A�����������čU�����ė��Ȃ��u�ǂ������ҁv�̑O�ł́A���i�ɋ��h�S�̔�����K�v�Ƃ��Ȃ�����A�l�Ԃ̎���͌���Ȃ����ɂȂ��̂ł���B����ɂ́A����𗇂ɂ���x���̎��Ԃ���ɕK�v�Ȃ̂��B�l�Ԃ����������Đ������m�ۂł���ꏊ�������A����̃��X�g�X�e�[�V�����ł���B���̂Ȃ�A�����́u�N�����Ȃ��P��Ȃ��ꏊ�v�ł��邩�炾�B �@�ȏ�̐��_����A���͐X�P�v�Ƃ����j�̎���ɒ���t���A���h�S�Ƃ������́A�u����������邱�Ƃւ̋��|����v������ƍl�����̂ł���B �Q�D����̒鉤 �@ �@�X�P�v�Ɖi�c�m�q����B�̎R���ɍ\�z�����ꏊ�́A���悻�l�Ԃ̎����K�x�ɋx�܂���ꏊ����ł��u�����Ă����B
�@
�@�l�Ԃ̎���ɍP��I�ɋْ��������߂�ꏊ�ɂ����āA�X�P�v�̎���͏�ɗ��ɂ���邱�Ƃ�����A�K�v�ȏ�̈ߏւ������ɔ킹�Ă����Ǝv����B�ނ̋��h�S�̑Ώۂ͋��l���ۋ����ɏW���I�Ɍ������Ă�������A��O�I�ɗ��̎��䂪�k��o�����Ƃ�����B �@�����ڌ�����@��ł����������̂��A���F�ł������Ⓦ���j�ł���B�Ⓦ�̓`����X�P�v���̐��m���������������Ȃł���B �@���l���ۋ������R�x�x�[�X�ɓ���ۂɁA���ɁA��l�̏l���]���҂��o�����Ƃ������Ⓦ������Ƃ��̐X�P�v�̓��h�́A���̒j�̕��ϓI�Ȑl�Ԑ����A�J��]���Ƃ���Ȃ��`���Ă���ƌ����邾�낤�B �@�X�͂��̂Ƃ��A�u�܂���������B������͂��͂�v���Ƃ���Ȃ���v�ƌ�������A�ßT�ȕ\��Ŏb�������𗎂Ƃ��Ă����ƌ����B�i�ȏ�̃G�s�\�[�h�́A�A�_�N�����u���m�����̘A���ԌR�v�ʗ��Њ��Q�Ɓj �@�X�P�v���Ⓦ����̕����Ƃ��̃C���p�N�g�́A�z������ɗ]�肠��B �@�X�͂��̂Ƃ��A�����������̊o��������đΛ����Ă����Ȃ��ƁA������̐Ǝコ���X���܂łɎN�����˂Ȃ����|��������������Ǝv����B �@�u�o��v�Ɓu�_�́v�\�\�@����I�ȏ��ŁA���̏������S���Ă���҂ɏ�ɖ����̂́A���̓�̃����^���e�B�ȊO�ł͂Ȃ����낤�B�u�o��v�Ƃ́A�u��������v�ł���A�u�_�́v�Ƃ́A�u���|�x�z�́v�ł���B���̒�`�ł���B�܂��ɂ��̂Ƃ��A�X�P�v�Ƃ����j�ɂ́A���̂悤�ȋ��x�Ȑ��_�������߂��Ă����̂ł���B�@ �@�K���ɂ��āA����͘A���ԌR�̍ō��w���҂̒n�ʂɂ��邩��A����̒���ɂ���āu����̒鉤�v���ѓO���邱�Ƃ��\�ł���A�����ł́u����ׂ��v���Ƒ��v�̉��\�ɂ���Ď��Ȏj���~�g������Ɠ���ł����̂��낤���B������ɂ���A�R�x�x�[�X�ɓ����Ă���̐X�P�v�̕ϐg�́A�ԌR�h���̓��u�����ɋߊ����ۂ��c�����悤���B
�@
�@���l���ۋ�������̉��R���}�q�ᔻ�ɒ[����A�u���Ȃ�u���W���A���v�Ƃ̐킢�́A�₪�āu�����v����퉻����Ɏ���A�����ɁA�u���Y��`���_�v���`�����Ƃ����l���̗����O�ځi�ق��͂��j���Ă����̂ł���B���`�Ɋ����鏊�́A�u�A���ԌR�����v�ł���B �@���A���̎��������߂Đ������Ă݂�B �@���̎������l����Ƃ��A�A���ԌR�́u�r�Ő�v�̎v�z������Ēʂ邱�Ƃ��ł��Ȃ����낤�B�u�r�Ő�v�̎v�z�����A���̎����̕�̂ƂȂ����v�z�ł���B���̎����ɂ܂�邠����s�K�́A�S�āu�r�Ő�v�̐��s�Ƃ�����{���肩��o�����Ă���Ƃ�������̂��B �@�u�r�Ő�v�Ƃ́A�G�i���ƌ��́j��|�����A�G�ɓ|����邩�Ƃ�����Ώ����o�����Ƃł���B�ނ�̈ӎ��ɂ����āA����͊v���푈�ȊO�ł͂Ȃ������B���̎v�z�͋��l���ۋ����̍����𐬂��}�I�C�Y���i�ё�`�E��4�j�̉e���������āA�R�x�x�[�X�̍\�z�ɋA�����Ă������ƂɂȂ邪�A�����ɂ͊��ɁA�s�K�Ȏ��Ԃ̉ߔ��̗v�����o�����Ă����B �@�R�x�x�[�X�Ƃ������I��Ԃ̑I�����A�u�r�Ő�v�̎v�z�̗��_�I�A���ƌ����Ă������ǂ��������ɋ^�₪�c�鏊�����A�Ⴂ�U���I�ȏ�O�͎���̎v�z�Ɠ��̂̏������A���炩�ɁA�s�s�Ɗu�₵���u���Ȃ��ԁv�ɋ��߂��̂ł���B �i��4�j�_�����s�s����ㅂ��A�s�s�u���W���A�W�[��œ|���邱�ƂŒB�������ƍl������J�_��̂̊v�����_�����A�_�����ǂ��܂ł����S�I��̂ƊŘƂ��낪����A�K���������Ύ�����B���̃��W�J���Ȏv�z���A��́u����i�v��u������v���v�Ƃ��������I�卬�����䂫�N�������ƌ����Ă����B���̉e���͂́A�J���{�W�A�́u�L�����O��t�B�[���h�v���N�������|����|�g�v�z��A�l�p�[���̃}�I�C�X�g��̍s���ɑ���ȉe����^�����B �@���̕������猾���A�u�r�Ő�v��킢�����s���Ȉӎu�Ƌ��x�ȓ��̂ɂ���ĕ��������ꂽ�X�[�p�[�}���i�u���Y��`�����ꂽ�l�i�v�j�ɕϐg����i�u���ȕϊv�v�j�܂ł͌����ĉ��R���Ȃ��Ƃ������H�I�e�[�[�i�u���Y��`���_�v�j�̓o��́A�ނ炪�R�x�x�[�X��I���������_�ŁA���ΊJ���ꂽ�s���ł������ƌ����邾�낤�B �@�ō��w���҂ɂ���Ē�N���ꂽ�u���Y��`���_�v�́A���ꂪ�ǂ̂悤�ȗ��_�I�g�g�݂������Ă����ɂ���A�{���I�ɂ́A�ō��w���҂̌��Ђƌ��͂��������Ă��������ɂ��������Ȃ��͎̂����ł���B���̂Ȃ�A�u���Y��`�I�l�ԁv�̃C���[�W�́A�������̌l�̊ϔO�̜��Ӑ��Ɉˋ����Ȃ���A�����ɓ���I�Ȕc��������Ȃقǂɔ��R�Ƃ������̂ł��邩�炾�B �@�u�r�Ő�v�̎v�z�́A���R�A�u�R�v�̑n�݂�K�R�����A�u�R�v�̑n�݂͋��͂ȏ�Ӊ��B�̗Ր�I�ȑg�D��v������B�R�x�x�[�X�́A���̗v���ɉ�����`�ō\�z���ꂽ�̂��B���̏��Œ�N���ꂽ���H�I�e�[�[�́A������N�����ō��w���҂̊ϔO�̜��Ӑ��ɑS�ʈˑ�����ȊO�ɂȂ��̂ł���B �@�L�̂Ɍ����A�ō��w���҂����ƌ����Δ��ɂȂ�A���ƌ������ɂȂ��Ă��܂��̂��B�ō��w���҂̐��`�����g�D�̐��`�ł���A�u�R�v�̐��`�Ȃ̂ł���B �@�u���Y��`���_�v�̓o��́A�{�l��������ǂ��܂Ŏ��o���Ă������ɍS�炸�A�ō��w���҂�_�i������ŋ��̃J�[�h�ł������̂��B�ō��w���҂Ƃ��Ă̐X�P�v�̕ϐg�́A���炪�o�����J�[�h�̌��p�̉������ƋO����ɂ��Đ��������̂ƌ��Ă����̂ł���B �@�����ɁA����ȏ��ɂ����āA�X�P�v�ɓ��[�����߂��Ă����ł��낤�A�u�o��v�Ɓu�_�́v�Ƃ������x�ȃ����^���e�B�ɂ�镐���́A�ō��w���҂�_�i��������u���Y��`���_�v�̒ɂ���āA�����ɍ\�z���ꂽ�W�����͐��̔Z�x�̐[���l�Ԃɕϗe�����߂�v���Z�X�̓��Ɏ��ʂ���A���̉ߏ�ȊϔO�n�����\����Ă����Ɏ������Ǝv����B �@�Ⓦ���j��A�_�N���ɁA�u�y�����v���v�킹��܂łɕϖe�����A����̕��e������ݏo�鉟���o���̋����ƈЌ����B�������ŁA�����Ό����锗�͂���ِ�ɂ���ĔN���̓��u���������Ɋ����A�ڂɂ́A�u�͗ʂ̈Ⴂ����v��遂��Č�����ԓx�Ȃǂ����S�͂ƂȂ��āA�u���Ȃ��ԁv�ɂ����āA�X�P�v�̐_�i�������ۗ������Ă����B �@�X�͋��炭�A����̃q���C�b�N�Ȏ��ȑ������܂߂���ۓI�ȃp�t�H�[�}���X�ɂ���āA�N���̓��u�����̎v���𑩂˂邱�Ƃ��ł����Ƃ��������ɁA�ꎞ�i�����Ƃ��j�Ђ����Ă����͂����B���̎����͑��h����ł���ƌ����Ă��� �@���h����Ƃ́A�W�ɂ�����\�̗͂����ɉ��l�ς�}�����邱�ƂŁA���̊W���u�D�v�ɂ���čۗ������Ă�������X���ł���B�����헁���邱�Ƃ́A�l���l�����Ƃ��ɖ�������͂̌���ɂ��Ȃ�B���h����𗁂т邱�Ƃ́A�S�Ă̌��͎҂��ς����M�]������̂ł���A�������ɓ���邽�߂ɁA�ނ炪�ǂ�قǏX�Ԃ������Č����Ă������ɂ��ẮA�������̒m�鏊�ł�����B �@�����āA���̗ނ̑��h����A�����Έ،h����Ɍq���蓾��S���I�����ɂ��Ă͖w�ǎ����ł��邾�낤�B�،h����̖{���́A����̊���ł���B����̊����̐l�i�ɕ������Ă��܂����Ɓ\�\�@���ꂪ���͎҂̍ł��ȕւȎx�z�̗l�Ԃł���Ƃ������Ƃ��B
�@
�@�X�P�v�́A����Ɉؕ|����^������̐l�i�\���ɂ���āA�u�R�v�Ɓu�}�v�̔e�����������A������Ќ��I�ȑԓx��I��I�ɉ����o���Ă����B�A�_�N���͐X�̕ϖe�ɋ����A�����ɉz������������o�������Ƃ������ɋL���Ă����B �@�z��������ɂ���҂ɑ��镁�ʂ̐l�X�̊�{�I�Ή��́A�O�����Ȃ����낤�B �@�u���ہv�A�u�����v�A�u�����v�ł���B �@����̌��Ђ��ɔF�߂��A���Ђ����ȂɐN�����Ă��邱�Ƃ��B�R�Ƌ��ނ��A����Ƃ��A�u�����Ƃ͖����ł���v�ƌ����āA�W��̐ړ_�������Ȃ����A�����́A����̌��Ђɓ������Ă������̂����ꂩ�̑Ή��ł���B �@�����Ŗ��ƂȂ�Ή��́A�����Ƃ����ԓx�ł���B �@�l�X���Ɍ��ɂł��u����Ȃ�����A�����͈ՁX�ƁA���҂̑O�Ŕڋ��Ȏ�����N����ɂ͂����Ȃ��B�����ő��̐l�Ԃ́A���肪�_�Ԍ�����u�コ�v��u���傳�v���A�����i�܂��͎��������j�����ɓ��ʂɓ͂����\���ł���Ǝv�����ނ��ƂŁA�����ɓs���̂��������n�삵�Ă����B �@�H���A�u�V�c�͎������̋��ɐS��ɂ߂Ă���B�V�c������ȏ�ꂵ�߂Ă͂Ȃ�Ȃ��v �@�H���A�u�ё�Ȃ͎������̐S���Ă���B��Ȃ̎w���Ɍ�肪����͂����Ȃ��B�����̂͑S�āA�����h�i��5�j�̃u�^�������B�v����i�߂Ă��������Ȃ��v�i�u�l�l�g�v�Ƃ̓����̏�����ɒ�N���ꂽ�A�u�ё�Ȃ̌�������A���̎w���ɏ]���v�Ƃ����A�؍��N�́u��̂��ׂāv�_���A���̃C�f�I���M�[�̊�ɂ́A���̕��ꂪ���炷��j �@�X�ɞH���A�u���������R�́A�{���͎����̓����Ȃ�肽���Ȃ��̂��B���������������n�����爫���B�F�ŏ��R������Ă��������Ȃ��v���X�B
�@
�@���̂悤�ȁu�m�o�C�A�X�v�i�������s���̗ǂ����ɂ���āA���Ԃ�c�����邱�Ɓj����l�������Ă��܂�����A���Ђւ̓����͂قڊ��������ƌ��Ă����B�������Đl�X�͔ڋ��Ȏ����E�F���A�S�n�ǂ��Ô��ȕ���ɓ������Ă������ƂɂȂ�̂��B �i��5�j������E�������ɑ�\���������h�̂��ƁB����������v���ŁA���{��`�ւ̕�����ڎw���}�������Ƃ��đœ|�̑Ώۂɂ��ꂽ�B �@
�@�X�P�v�����ȑ����̏�ŁA�����̢���_������������Ƃ����s�ׂ́A�܂������u�V�c�̗܁v�ł���A�u�ё̙��v�ł���A�u�������̋�a�v�ł���B
�@
�@�X�P�v�͂��̖�A�u����̒鉤�v�ɂȂ����B
�@
�@�ނ̏d�ꂵ�������́A���̌�̊��܂킵�������̕�����������t�����̂ł���B �@���ꂪ��̌_�@�ƂȂ��āA���Ȃ̉ߋ��ƌ��݂�e�͂Ȃ��\���A�P��o���A瞁i�قƂ��j�錌�̊C�̒������֓I�Ȓ�����ʂ����Ă��������������v�����Ƃ����A���́u����v�̐��E�ł̑����̃X�^�C�����蒅����̂ł���B �@���̖�A�ō��w���҂̈ꐢ���̑�ŋ����҂̉��l���́A�������ɂ͔�J�Ŗ���ɓ����Ă��܂������A����܂ł́A���ɂ܂��ĚT�苃���҂������ƌ����B �@���̂悤�ȃG�s�\�[�h�ɂ́A���~�̎��R�ɕ�����āA������q�����v���̃��}�������Ⴂ��O�̔M�C��f�i��������̂�����A���コ���ԈႦ�Ȃ���A���p����銴��杂̒�ԂƂȂ�Q�A�R�̗v�f�������Ă����Ƃ������悤���B �@������ɂ���A���̃G�s�\�[�h�́A�X�P�v�̌��͐����R�x�x�[�X�ɂ����Č`������Ă��������Ƃ�Y�قɌ���Ă���B �@�܂�X�́A�R�x�x�[�X�\�z�̓������瓯�u�����̓��̂Ɛ��_����ɊǗ����Ă�������ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��B�ނ́u���Y��`���v�_�̒��A���l���ۋ����̉i�c�m�q��̉��R���}�q�ᔻ�i��c���ɔ��𞀂�������A���ς������蓙�̍s�ׂɂ���āA�u���W���A�I�Ƃ��ꂽ�j�ւ̐����Ȕ����Ɨ����E�c�����ꂽ�̂ł���B �@���������ꂪ�A���Ɏ��͂Ŋo���Ɉ��������Ȃ������S�Ă̈����̎n�܂肾�����B�Y���R�x�x�[�X�ł́A�u���̑����v�̎n�܂�ł���B
�@
�@���𞀁i�Ɓj�������Ƃɏے������A�j���̃G���X�������u���W���A�v�z�Ƃ��ĝ��ˁi�Ђ��j�����̂��B����͒j�̒��̒j�����ƁA���̒��̏������̔ے�ł���B �@���̋ɂ߂��̂悤�ȁA�X�̕\��������B �@�u���͉��ŁA�u���W���[��K�[�h����������B����Ȃ���A�K�v�Ȃ��v �@�X�͂����������̂��B �@�ނ͏����̐����p�i�̎g�p����ے肵�A�V�����ŏ�������Ɨv�������̂ł���B���������X�̔ᔻ�́A�����Ɂu���v�ł��邱�Ƃ��̂ĂāA�u��m�v�Ƃ��Ă̂ݐ����邱�Ƃ����߂����̂ŁA�����A���̒��̏�������ے肵�Ă����͂��̉i�c�m�q�́A�����ŋL�����u�\�Z�̕�W�v�i�ʗ��Њ��j�̒��ŁA������u���l�ԓI�s�ׁv�ł���Ɣᔻ���Ă���B �@�X�P�v�̃G���X�����ے�̎v�l�́A�R�x�x�[�X�ɏW�������҂����𖼏�����Ɋׂꂽ�ł��낤�B �@��ΐߎq�i���l���ۋ����j�ɗ����������A�_�N���i�ԌR�h�j���A����ߋ��̗��������𗝗R�ɁA�u���̑����v���Ă���Ƃ��A�����Ƃ̊W���艻����A�u�����v�����߂��邱�Ƃ̋��|���ɋ����Ă������X���A�ނ́u���m�����̘A���ԌR�v�i�ʗ��Њ��j�̒��ŗ����Ɍ���Ă���B �@���I���F���̒��ŁA�X�́u���Y��`�I�l�ԁv�ς́A�j���̊������N������u���v�̔ے�ɂ܂ōs���������̂��B
�@
�@���l�ɁA�������u�ւ̗�����肪���R�i��ɁA�R�l�ڂ̋]���҂ƂȂ鏬���a�q�Ɨ����W�ɂ������j�ŁA�ŏ��ɑ��������߂�ꂽ��ɁA�S�l�ڂ̑������Ɏ�������\�h�i���l���ۋ����j�́A����̐��~����������Ƒ���������A�X�Ɂu���~���N��������A�ǂ�����̂��H�v�Ɩ₢�l�߂�ꂽ�B �@���̖₢�ɑ��āA�����͉��Ɠ��������B �@�u�F�ɑ��k���܂��v �@�����܂ŗ���ƁA�w�NJ쌀�̐��E�ł���B �@�������A���̏��F���̊�{�I�����͈���̊쌀��f�i�����邪�A���̓����́A��т��Ĕߌ��A������h���h���ɉt�����ɂ߂��̔ߌ��ł���B���̏��F�����쌀�Ȃ�A�����̂��̔��������̓��u�����̔����A�u���́A�h�A�z�I�v�Ɠ����y���@����āA����Ŋ������邾�낤�B �@�Ƃ��낪�A�����̂��̔����͐X�̋t�ɐG��āA�����̂�蒼�������߂��邱�ƂɂȂ�A���Ɏ��̊K������l�߂Ă����Ă��܂��̂ł���B �@���̏��F���ɂ͂����A�������邽�߂̐l�Ԃ̋����ȗ����U�镑�����t�H���[���Ă������[���A�́A�����̗]�T�������c����Ă��Ȃ������B �@���݂ɁA���̔c���ɂ��A���[���A�Ƃ́u�m��I�Ȃ�ᔻ���_�̏_�a�Ȃ�\���v�ł���B����Ȑ��_�Ɩ����Ȑ��ԁ@�\�\�@���ꂪ�v�����č������҂������\�z�����R�x�x�[�X�������B���̎R�x�x�[�X���̈ł̏L�C�̔Z�x�����Ȑ��Y�I�ɐ[�܂�ɂ�A��҂����̎���͋ɓx�ɖ��茸���āA�A�E�g��I�u��R���g���[���̗l����悵�Ă����B �@�ǂ��l�߂�҂��A�ǂ��l�߂���҂��A�����o�ɂ����鎞�Ԃ�ߑ����邱�Ƃ����ׂ������A�u�������邱�Ɓv�ƁA�u���������邱�Ɓv�̌����Ȃ����q�ϓI�ɔF�m���A���̍s�����O���C�����邱�Ƃ�������Ȃ����̘A���ɁA�R�x�x�[�X��喏W�i�����イ�j����S�Ă̎�҂����͝��i����j�ߕ߂��Ă����̂ł���B �@����ȉߏ�ȏ������Ȑ��E�ɕ��n�����ԂƂ��A�����ɕs�K�v�Ȃ܂łɉߏ�ȁu����̒鉤�v�����o���A�����Ō��o�������E�����A�u����̋��|�v�ƌĂԂׂ����E�ȊO�̉����̂ł��Ȃ��ł��낤�B �R�D����̋��|�@ �@ �@����l�Ԃ��A����Ɏ����̍s���ɋ��������o�����Ƃ���B
�@
�@�ނ���{�I�Ɏ��R�ł������Ȃ�A�s����������Ȃ��܂ł��A���̍s���̗L������_�����邽�߂ɍs����������������A�ꎞ�I�ɒ��f�����肷�邾�낤�B �@�Ƃ��낪�A�s���̗L�����̓_���Ƃ����I�������ŏ�����^�����Ă��Ȃ����ɂ����ẮA�s���̗L�������^���A�����ɋ��������o���Ă��A�s���F�������䂪�ċz���q�����Ƃ��~�߂Ȃ�����A�ނɂ͍s���̋ȍĐ��Y�Ƃ����I���������c����Ă��Ȃ��̂ł���B �@���̂Ƃ�����́A����̎����I�Ȉ��J���������邽�߂̋}�n�i���イ������j���̕�������o���B�����A�u���������o���鎩�������n�Ȃ̂��B������˔j���Ȃ��Ǝ��͕ς��Ȃ��v�ȂǂƂ�������ɃM���M���Ɏx�����āA�ނ͎�����K�肷����v����ȊO�ɂȂ��̂ł���B �@�ނɂ́A�s���̋����݂̂��~�ςɂȂ�̂��B �@�����ɂ����A�ނ̎���̈���̋��菊��������Ȃ�����ł���B�s���̋����͎�����v�X�C�茸�炵�A�敾�����Ă����B���̘A�����G���h���X�̗l�����N���Ă����̂ł���B �@���a�̏ے��ł��锵�ł��������ɓ�H�����߂���ƁA�����ɐ��S�ȓ˂����������N����A�����ꂩ�����ʃP�[�X�������ƌ����B �@����́A�R�����[�g�E���[�����c���u�\�������̎w�ց@�����s���w����v�i���쏑�[���j�ŏЉ���L���Ȏ���ł���B �@�S�Ă̐����ɂ́A���̐���������������œK���x�Ƃ������̂�����B�l�Ԃ̍œK���x�́A���䂪���҂Ƃ́A�����́A���҂���́u�L���U�������v��������A�K���ȃX�^���X���m�ۂ��邱�Ƃɂ���ĕۏႳ��邾�낤�B
�@
�@�œK���x�����ꂽ���F���Ɍ��͊W���������܂�A�����āA�u�r�Ő�v�̏����̂��߂̒��l���̒B������ΓI�ɗv������Ă���Ƃ��A���͕̏K���ߏ�ɂȂ�B���̏͂��ł��������Ă��āA�������I�[�o�|�t���[���A�W�͏�ɗL���U�������̘g���ɂ����āA���ْ̋�������ԉ����Ă��܂��Ă���B�l�Ԃ��ł��l�ԓI�ł��邱�Ƃ��m�F����葱���A�Ⴆ�A�G���X�����̍s�g���ߏ�ȗ}������Ɏ����āA��҂����̎���͉���ւ̋�襂ȏo��������������B���̉ߏ�ȏ̒��ŁA��҂����̃G���X�͑��݊Ď��̃V�X�e���Ɍq����āA�����₷��NJ��ɝ��i����j�ߕ߂��Ă��܂����̂ł���B �@�~�]�̔ے�́A�l�Ԃ̔ے�ɍs�������B �@�l�ԂƂ͗~�]�ł��邩�炾�B �@�l�Ԃ̍s�ׂ̐�����A���̍s�ׂݏo���~�]�̐���Ƃ������̂��܂��A�ʂ̗~�]�Ɉˋ���������A���̂��߂̎i�ߓ��Ƃ������̂��������̎���ł��邱�Ƃ�F�m�ł��Ȃ��܂ł��A���Ȃ��Ƃ��A���ꂪ�l�ԂɊւ���{�I�o�����ł��邱�Ƃ��A�������͋��炭�m���Ă���B�������̗~�]�́A���̗~�]�𐧌䂷�邱�Ƃ̕K�v����F�����鎩��̎w�߂ɂ���āA���̗~�]�𐧌䂵����ʂ̗~�]��}��ɂ��āA���Ƃ����䂳��Ă���Ƃ����̂������ɋ߂����낤�B �@�Ⴆ�A��̑O�ɔ����������y�������ׂ��Ă���Ƃ���B �@���������A�����H�ׂ��ɂ͂����Ȃ����R�������̓����ɂ���Ƃ��A�����H�ׂȂ��ōς܂�����̐�p���A�u���������䖝����ΕK���H�ׂ��邩��A���͎~�߂Ă����v�Ƃ����ނ̒P���ȍ����ɋ����Ă����Ƃ��悤�B �@���̂Ƃ��A�u���������y�����H�ׂ����v�Ƃ����~�]�𐧌䂵���̂́A����ɂ���Ĉ�������o����Ă����A�u���������䖝������ŁA���y�����H�ׂ����v�Ƃ����ʂ̗~�]�ł���B��҂̗~�]�́A����ɂ���ĉ��H����������̗~�]�Ȃ̂ł���B �@���̂悤�ɁA�l�Ԃ̗~�]�́A���ł������o���ɂȂ������̎p�Őg�̉�����邱�Ƃ͂Ȃ��B���������ł������Ȃ�A�����a���ƌĂ�ł������x���Ȃ����낤�B�~�]�����H�ł��Ȃ�����̕a���ł���B�~�]�̐���Ƃ́A����ɂ��~�]�̉��H�ł�����B���ꂪ�A�������\�ɂ܂鎄�́u�~�]�v�ɂ��Ẳ����ł���B �@������A������o�����B �@������l�Ɏv����ł��������Ȃ��ŔY�ނƂ��A���̍����ɂ���ĊJ�����Ɨ\�z�����A�f���炵���o���F�̐��E����ɂ������Ƃ����~�]�𐧌䂷����͎̂��ɗl�X���B �@�u���A�ł���������S�Ă�������������Ȃ����B���������A�w�����x�Ƃ����Q�[���ɐg���ς˂Ă��Ă���������Ȃ����v �@����Ȏ���̋}�n���̕������Ĉ�������o����Ă����ʂ̗~�]�A�܂�A�u�����ƃQ�[�����y�������v�Ƃ����~�]���A���̗~�]�𐧌䂷��P�[�X�����X���邾�낤�B�����ł��A�~�]������̉��H���Ă���̂ł���B �@�����́A�u���߂�B���O�͗����ɂ������Ă���ꍇ�ł͂Ȃ��B���O�ɂ͎i�@�����̂��߂̕������邾�낤�v�ȂǂƂ������ꂪ����ɂ���č��o����āA�u���̍����v�ɂ��G���X���E�ւ̗~�]�����䂳��邪�A���̂Ƃ��A����́u�i�@�����˔j�ɂ���ē�������y�v�Ɍ������~�]���A�����ɐ[�X�Ɣ}����Ă���̂����m��Ȃ��B�~�]���ʂ̗~�]�ɂ���Đ��䂳��Ă���̂ł���B �@�܂��A�X�g�C�b�N�ȑT�m�Ȃ�A�u�ς��邱�Ƃɂ���ē�������y�v�Ɍ������~�]�A�Ⴆ�A���h���ꂽ���Ƃ����~���Ƃ��A���Ȏ����~�������A����̐g�̂���������ɑ������鐫�~�𐧌䂷��̂����m��Ȃ��̂ł���B �@���̂悤�ɁA�~�]�����H������A�����́A�S���َ��̗~�]�������肷�邱�ƂŁA�������̎���͌��̗~�]�𐧌䂷��̂ł���B�~�]�̐���́A�{���I�ɂ͎���̎d���Ȃ̂��B�������̎���́A�u�`�P�O�_�o�v���痬������h�[�p�~���ɂ����y�̃V�����[�𗁂тāA�������������ɂȂ邱�Ƃ����邪�A�~�]�𐧌䂷�邽�߂ɂ�������H������A�S���َ��̗~�]�����o�����肱�Ƃ��炠�邾�낤�B �@�l�ԂƂ͗~�]�ł���Ƃ�������́A�]���āA�l�ԂƂ͗~�]�����H�I�ɐ��䂷��A����ɂ���Ă̂ݐ������Ȃ����݂ł���Ƃ�������Ƃ��A�S���������Ȃ��̂ł���B���������ł���͖̂{���I�ɗ~�]�̐���ł����āA�~�]���g�̔ے�Ȃǂł͂Ȃ��B�~�]��ے肷�邱�Ƃ́A���������������������ŁA�u�G��Ă݂����v�Ƃ����w�ǎ��R�Ȋ����F�m���A��������ɉ��H���镨������o�������ے肷�邱�ƂɂȂ�A����͐l�Ԃ̔ے�Ɍq���邾�낤�B �@�X�P�v�ɏے������A�A���ԌR���m�������Ƃ��Ă��܂������v�́A���O�n�̊ϔO�I�����A�y�ьP�����ꂽ���x�Ȑg�̂̑����͂ɂ���āA�l�Ԃ̃h���h�������~�]�����S�Ɏ�菜����邱�Ƃ��ł���ƍl����A�����̐l�Ԃ̎���ɋ����I�ɐA���t����ꂽ�A������܂����ȊϔO�̖����ł���B �@�܂������A���ꂱ�����B���_�I�ȊϔO�_�̋ɒv�Ȃ̂��B���̐l�Ԋς̓x����y�V��`�ƌ`����`�ɁA���͖w�nj��ׂ����t�������Ȃ��B �@�ނ炪�v������u�����v�Ƃ������̂��A�{���A�ɂ߂č��x�ȋq�ϓI�A���͓I�A���m�I�ȍ�Ƃł���ɂ��S�炸�A�ނ�̛Ƃ������v�͂���ȃn�[�h�ȃv���Z�X�Ƃ͑S�������ȁA�ߕ��Ɏ�ϓI�ŁA���o�I�ȕ��̘A���̉ߒ��ł������B �@��������点�A�����A�u�����̂悤�Ɏ��ɂ����Ȃ��B�ǂ����������炢��������Ȃ��v�Ƒi���鉓�R���}�q�ɁA�i�c�m�q������������́A�u�˂��A�����������Ă�v�Ƃ����ނ́A����Ƃ����s�n�D�Ƃ��Ř���s�тȔ����̂݁B������ࣁi�����j�ꂽ���͊W�̂����ɘI�悳�ꂽ���|�I�ȔY���ɁA�g�̓���v����������肾�B �@�����A���S�Ƃ����A����̍����Ɋւ�����̏���������Ă���҂́A�ʏ킻�̕�����C�����āA���ΓI������m�ۂ��悤�Ɠ������̂ł���B����̊�{�I�Ȉ��肪�A�����I�F�����x����̂ł���B���̋��|������I�ɖ������Ă���Ɍ����ŁA�ł������I�Ȕc�����\�ł���ƍl���邱�Ǝ��́A���͋ɂ߂Ĕ��I�Ȃ̂����A���X�A�R�x�x�[�X��I���������߂��ނ�́u�r�Ő�v�̎v�z���������I�ł���A�������I�A���A���ϔO�I�ȕ����ȊO�ł͂Ȃ��̂��B �@�X��i�c�́A������v�����ꂽ�҂��A�u���̋��|�v�����z���āA���ȕϊv��B�����铯�u�������A�u���Y��`�I�l�ԁv�ł���ƌ��ߕt�������A�ł́A�u���̋��|�v����̏��z�����ǂ̂悤�Ɍ�����̂��B�܂��A���̂Ƃ��o������ł��낤�A�u���Y��`�I�l�ԁv�Ƃ́A��̂ǂ̂悤�ȋ�ې����������l�ԂȂ̂��B �@�u�����v�̏�ɋ����킹�����̓��u�����̍U�����𒆘a���A�ނ�̐S��ɉ��^���̐e�a����A�����邱�Ƃɐ��A�����S������̒B�l�����A�܂��Ɂu���Y��`�I�l�ԁv�ł����āA����͋ɂ߂Ĝ��ӓI�A�l�H�I�A��I�A���ΓI�ȊW�̗͊w�̂����ɐ������Ă��܂����x���̌��Ȃ̂ł���B �@�v����ɁA�w�����ɏ�肭���������l�Ԃ݂̂��u�����v�̏����҂ɂȂ�Ƃ������Ƃ��B����������́A�{���̐l���̗ǂ�����A�X�Ɖi�c�ɓK���ȃX�^���X���L�[�v�������A�_�N���݂̂���O�ł����āi������̕ω����o�����Ȃ�������A�A�_�����o�̗��ɕ�����Ă������낤�j�A�u�����v��v�����ꂽ���̎�҂����́A���̃_�u���o�C���h�̎��������l�Ƃ��Đ��҂ł��Ȃ������̂ł���B �@�u�P�Q�l�̔���ꂵ��҂����v�����������u�_�u���o�C���h�v�Ƃ́A�����������Ƃ��B
�@
�@���R�̂悤�ɁA�m�I�Ɂu�����v����ΊϔO�_�Ƃ��ĝ��ˁi�Ђ��j����A�����̂悤�ɁA����̓����𒌂ɑł�����Ƃ������s�I�ȁu�����v�������A�v�z�Ȃ�����I�����Ƃ��ċ��܂��Ƃ����A�܂��ɏo���Ȃ��̏������ɂ������B���̂��Ƃ��A�ނ�̋ɓx�ɔ敾�������䂪���m�Ɋ��m���������炱���A�ނ�́A�u���҂̂��߂̑����v�̕������Ɍ����Ŗ͍������̂ł���B �@���ɋM�����A�������E���ɈႢ�Ȃ��Ǝ�������Ɛl���瓁��˂������āA�u�����肽���Ȃ�A���̌������Ƃ��v�Ɩ��߂��ꂽ��A�ǂ����邾�낤���B �@�ߋ��̂��������ʂ薂�I�Ȏ����ł́A��́A�F�Ɛl�̖��߂ǂ���ɓ����Ă��邪�A����͐����̈��S����`�I�ɍl���鎩��̐���ȋ@�\�̔����ł���B �@�R��ɁA�X�Ɖi�c�́A�u�����v�����߂�ꂽ�҂����������̖��ߒʂ�ɓ������Ƃ́A�u�����肽���v�Ƃ������a�ȃu���W���A�v�z�̕\��ł���ƌ��߂�������A�ނ�Ɂu�����v�̂�蒼���𔗂��Ă����B�w�����̖��߂�ϋɓI�Ɏ�e���Ȃ������痘�G�s�ׂƂ���A���Y�ɏ�������̂ł���B �@�u�P�Q�l�̔���ꂵ��҂����v�������Ă����̂́A�ނ�̐g�̂���łȂ��A�ނ�̎��䂻�̂��̂ł������̂��B �@���̐�Ώ��ł́A��҂����̎���̕���͑����B
�@
�@������I������D��ꂽ�Ǝ������鎩��ɁA�����悤�̂Ȃ��������P���Ă���B�����̗��j�Ղł��鎩�䂪���X�ɋ@�\�s�S���N�����A�łɓۂ܂�Ă����̂��B�u�ǂ�Ȃ��Ƃ������Ă����������v�Ƃ������ӂ��킪��A��a�Ȍ����������łɕ����̂ł���B �@�A���ԌR�����̎����P��́A���Y�Ɏ��鎞�ԂɎU��߂�ꂽ�A�S�ȃV�[���́A����̏o�������ĂȂ����䂪�ǂ̂悤�ɕ���Ă����̂��Ƃ����A���̈�̋Ɍ��̂��܂��A�������Ɍ����Ă����B���m�����ւ̉����ȑԓx��A�v�����h�i���l���ۋ����j����̓��a���I�s������莋����āA�u�����v�̑ΏۂƂȂ����������A�Ⓦ�Ɠ�l�œ������ʂɒT���s���ɏo���ۂɁA�����悤�Ǝv���Ί��ł��\�ł������̂ɁA�ނ͂������Ȃ������B �@���̎������A�u�����v�̏�ʼn����������̂��B �@�u�Ⓦ���E���āA����������@����M���Ă����v �@�����������̂��B �@�₩�ɐM������t���A���̒j�͓f�����̂ł���B �@���̎����̔������ł��^�����̂́A�����ɖ���_���Ă����Ƃ����Ⓦ���j���̐l�ł���B�Ȃ��Ȃ�Ⓦ�́A���̓����ւ̎R�x�����s�̖�A�������g����A�ނ̂قږ{���ɋ߂��Y�݂�ł��������Ă��邩��ł���B�Ⓦ�͎�������A�m���ɂ����������̂��B �@�u�Ⓦ����A���ɂ́w�����x�̎d��������Ȃ��̂ł���v �@�Y�݂�ł�������ꂽ�Ⓦ�͓��R�������A�������ނɂ͗L���ȃt�H���[���ł��Ȃ��B�������Ⓦ���A���ȉ����\�͂̔��e�����n���ɗ���␂�ł����̂ł���B�Ⓦ�ɂ́A���̂悤�ȔY�݂𑼂̓��u�ɑł�������Ƃ����s���́A���ɔs�k�ł���A�Ƃ��Ă����e�������̂ł͂Ȃ��Ɗ��邵���p���Ȃ��̂��B�������E���āA�E����}�낤�Ƃ���҂��A����Ȋ댯�ȍ���������Ȃ��A�ƍⓌ�́u�����v�̏�ōl�����炷���A�������ނ͍Ō�܂Ŏ������A�V�X�g���Ȃ������̂ł���B �@�����悤�Ǝv�����ł������邱�Ƃ��ł�����x�̎��R���m�ۂ��Ă��������P��́A���ɂ��̎��R���s�g�����A���낤���Ƃ��A�ނ��Ō�܂ŌŎ����Ă����l�����Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�ނ��Ō�܂ŋ���ł����u�K���G�v�Ƃ��čق���A�A�C�X�s�b�N�ɂ��S���炵�����Y�����}�����̂ł���B �@�����P��́A�u��������A����������藧�����v�Ƃ����_�u���o�C���h�̐�Ώ��ŁA�����ւ̌Ŏ��̋�ɂ��������͂܂��ł��낤�Ǝv���鎀�̑I���ɁA�}���ɌX���Ă������B �@�ނ̐������A�ނ̓����Ō��łɃK�[�h���鎩�䂪�A�ނ̑��݂��ΓI�ɋK�肷��A�w�nj��E�I�ȏɌq����āA�ɓx�̔敾����Q���A�@�\�s�S��悷��Ɏ���B�����ɁA�l�Ԃɑ���A�l�Ԃɂ��ł��c���Ȏd�ł����قڊ�������̂��B �@�l�Ԃ͂����܂Ŏc���ɂȂ��̂ł���A�c���ɂȂ�\�͂����̂ł���B �@�l�Ԃɑ���ł��c���Ȏd�ł��Ƃ́A�P�ɑ���̐�����D�����Ƃł͂Ȃ��B����̎�������X�ɐr�U�i�����ԁj��A���ɂ��̋@�\����̂����Ă��܂����Ƃł���B�l�ԂɂƂ��āA�����ė������̎i�ߓ��ł��鎩���j��s�ׂ����A�l�Ԃ̍ł��c���Ȃ�d�ł��Ȃ̂ł���B �@�u����E���v�i���̎E�Q�j�̍߂́A����ɂ���Ă����������Ȃ��ł����{�I�ȍ݂菈��ے肷��߂Ƃ��āA�����́A����ȏ�Ȃ��ň��̍߂ł���ƌ�����̂����m��Ȃ��B �@�u�P�Q�l�̔���ꂵ�҂����v�͎��������̖�����Ă����ł��낤�A���̗B��̋��菊�ł������������d�ɂ������āA����̏o��������������ł̈�̉^�����A���i���Ƃ��Ɓj���k�J�ɋA����Ƃ����w�K�����͊��i���̏ꍇ�A�E�o�s�\�̏��ɂ����āA���̏���E�o���悤�Ƃ���w�͂���s��Ȃ��Ȃ�Ƃ����Ӗ��j�̂����ɗ���␂݁A����҂͙�A����҂͔l��A����҂͋�������邪�A�������Ō�ɂȂ�ƁA�w�ǂ̎҂́A�܂�ł����ɉ����Ȃ��������̂悤�ɂ��ĐÂ��ɑ��₦�Ă������B �@�����āu�P�Q�l�̔���ꂵ�҂����v����������A�ނ���Ă����͂��̑S�Ă̍U���҂����̓����ɁA�u�ł�����ꂵ�҂����Ƃ́A���������ł͂Ȃ��̂��v�Ƃ����A�����Č���Ɍ���ł͂Ȃ�Ȃ���ɂ��������Ƃ��A�������́u���Ȃ��ԁv�́A�u�����ĒN�����Ȃ��Ȃ����v�Ƃ����ɂ܂ōŐڋ߂��Ă����A�Ǝ��͍l�@����B���̔c���͌���I�ɏd�v�ł���B���̂Ȃ�A���̔c���Ȃ����āu��ԎR�������v�̂��̐�]�I�ȏ�O�̟��i�����j���������邱�Ƃ��������ł���B �@�u��ԎR�������v�̔�Q�҂̕��ɂ́A�s�����ȕ\���ɕ������邩���m��Ȃ����A�u��ԎR���v�́A������Ȃ��A�R�x�x�[�X�ł́A�u�����ĒN�����Ȃ��Ȃ�v�Ƃ����Ɍ�����̏�������̉�����ƁA�����Ă���ȏ�ɁA���u�E���̐�]�I�y�V�~�Y���ɝ��ߕ߂��Ă��܂�������ɁA�g�̒���ɂ���C�̔�����⏞����i�D�̃X�e�[�W�ł������ƌ����悤���B �@���̊ԁA�e�ۂŐg���ł߂��҂����̎�����܂��A�R�x�x�[�X�̈łɔ����Ă����̂ł���B����҂����̎���́A����̓��u�邱�ƂŁA����̎����������グ�Ă����B�����͉䂪�g�Ƃ������|���A�c���ꂵ�҂����̎���ɍR���悤���Ȃ�����t���Ă����x�ɁA����҂̎���͊m���ɍ�����Ă����B���������͎̂v�z�ł���A�����ł���A����ł���A�z���͂ł���A�l�i���ꎩ�g�ł���B �@�������Ĉł͉v�X�[���Ȃ�A���̓����A�u�����ĒN�����Ȃ��Ȃ�v�Ƃ����~�X�e���[���Ȃ����Ă������̂悤�ɁA��a�Ȃ鎞�ԂɘM�i���Ă����j���̂ł���B �@�c���ꂵ�҂����́A���̎���̕�������������B �@���䂪���菊�ɂ���v�z������ŁA����͋���Ɉ���ϔO�̗����ƂȂ��āA������x����͂��̗͂����������Ȃ��Ȃ�B�R�x�x�[�X�Ŕ�ь������d�v�ȊT�O�A�Ⴆ�A�u���Y��`���v�Ƃ��A�u�s�k���v�Ƃ��������t�̒�`���B���ŁA���ہA�����̓��u�����͂��̔c���ɋꗶ���Ă����B
�@
�@�u���ۂ̂Ƃ���A���Y��`���Ƃ����T�O�͂��ɞB���ŁA�A���ԌR�̐����҂����͈�l�ɁA�܂����������ł��Ȃ������Əq�ׂĂ���B�ނ�́A�����鎩�ȕϊv���l�����悤�Ƃ����S��I�Ăт����͂悭�����ł����B���́A�ϊv���l��������ԂƂ͂ǂ��������̂Ȃ̂��A�l������ϊv�Ƃ͂��������Ȃ�Ȃ̂��A�����`���o����Ă��Ȃ����Ƃ������v �@����́A�p�g���V�A��X�^�C���z�t���j�i��6�j�́u���{�ԌR�h�v�i�͏o���[�V�Њ��j�̒��̋��������߂ł��邪�A�u���Y��`���v�Ƃ����ł��d�v�ȊT�O���c���ł��Ȃ��̂�����A�u����������Ȃ��v�Ƒi����̂����R�ł��낤�B
�@ �i��6�j1941�N���܂�D�~�V�K���B�f�g���C�g�o�g�D�~�V�K����w���{��E���{���w�����ƌ�C�n�[�o�[�h��w�ɂĎЉ�w���m�����擾�D���݁C�n���C��w�Љ�w�������D��O�����{�̓]�������͂��߁C�V�����^���̌����Œ����B�i�u��g�u�b�N�T�[�`���[�E���ҏЉ�v���j �@�u���́A�R�莁�Ɠy�Ԃɂ��Ⴊ��Œ��̈ꕞ�����Ȃ���b�����Ă������A���炭���āA������������ł���̂ɋC�������B �@�w��ς��I����ł��邼�I�x
�@�Ƌ��ԂƁA�w�����̑S�����y�Ԃɂ������ł����B�F�́A�������̎����m�F����ƁA�w�������܂Ō��C�������̂Ɂx�Ƃ��������A�������̓ˑR�̎��ɋ����Ă����B���ɉ������̒킽���̋����͑傫���A�i�c����͓�l�������������悤�ɂ��ĂȂ����߂Ă����B �@�w�ǂ����ċ}�Ɏ���ł��܂����낤�x�Ƃ����Ȃ���b�������Ă������A�b���������I����ƁA�i�c���A�w�����̌������A�w�����͓����悤�Ƃ������Ƃ��o���Ď��B�����͂���܂œ����邱�Ƃ�������x���ɂȂ��Ă����B���ꂪ�w�E����ăo���Ă��܂��A��]���Ĕs�k�����Ă��܂����x�Ǝ������ɓ`�����B �@�N���A�T�ȗl�q�ʼn�������Ȃ��������A���͉������̋}�Ȏ����M�����Ȃ��v���ł������߁A�i�c����̐����ɁA�Ȃ�قǂƎv�����B �@�����ĉ������̎������]�������Ƃɂ�鐸�_�I�ȃV���b�N���Ɖ��߂��A���̒i�K�ŁA���߂āw�s�k���x�Ƃ����K�肪�������̂��Ɗm�M�����B����܂ł̎��́A�w�s�k���x�Ƃ����K�肪�悭�킩�炸�A�����ł����ɎE���ꂽ�Ǝv���Ă����̂ł���v�i�M�Ғi���\���j
�@
�@����́A�A�_�N���́u���m�����̘A���ԌR�v����̔����ł��邪�A���u�����̎��ɒ��ʂ����ꕺ�m���R�x�x�[�X�̈ł̉��ŁA�ǂ̂悤�ɂ��Ď�����x���Ă����̂��Ƃ������Ƃ������[�I�ȗ�ł���B �@�u�v���v��ڎw���l�Ԃ��A���u�E�������������Đ����Ă����̂͗e�Ղł͂Ȃ��B���ʂ̐_�o�̎�����Ȃ�A��O�Ȃ�����̔j�]�̊�@�ɏP���邾�낤�B����̔j�]�̊�@�ɗ���������Ƃ��A���̊�@���������Ă����̂����䂻�ꎩ�g�ł���B �@���̎���́A����̊�@���ǂ̂悤�ɍ������Ă����̂��B �@���u�E����ʂ̕���ɒu�������Ă��܂����B�����́A����𐳓��������Ȃ��܂ł��A�S�̂ǂ����ł���ݏo�������̂́u�̐��v���ꎩ�g�ł���Ƃ��āA�����������̐��̓��m�𑱂��邩�Ȃǂ̕������l������B
�@
�@��҂̓T�^���A��ɒ����ɒE�o�����Ⓦ���j��A�����Ŏ��Y���x�Ɠ����ƈӋC���މi�c�m�q���낤���B�R��ɁA�R�x�x�[�X�̑����ňł̗�C���ċz����Ⴂ���䂪�A�Ȃ��u�v���Ɓv�Ƃ��Đ����Ă����ɂ͑O�҂̑I���������c����Ă��Ȃ��B�ނ�́A�u���u�E���v���u�s�k���v�̕���ɒu��������ȊO�ɂȂ������̂��B �@�A�_�N���̎���́A�u�����v�Ŏ���ł������҂́u��������ʊ��Ȏ��ȕϊv�̓����ɍ��܂��A�s�k�������v�Ƃ����c���ɗ��ꍞ�ނ��Ƃɂ���ċ~�ς��ꂽ�̂ł���B�����炱���A�����P��̎w���Ŏ��̂����ꂽ�̂ł���A���̎����̋����A�C�X�s�b�N�œ˂��h�����Ƃ��ł����̂ł���B �@�������A�A�_�N���̎���̐U���͑傫���A�x�X�댯�ȍj�n���Ƃ��Ă���B �@�w�����ɓ��邱�ƂŐl�i���ϖe�����悤�Ɏv�����Ⓦ���j�Ɍ������āA�ނ́u����Ȃ��Ƃ���Ă����̂��H�v�Ɩ₢�������E�C�������Ă����B �@�u�}���݂̂��߂����炵�����Ȃ����낤�v �@���ꂪ�A�Ⓦ�̂Ԃ�����ڂ��ȉ������B �@�A���ԌR���m�̒��ŁA���ΓI�Ɍ����ł������������L���Ă���Ǝv����A�_�́A���ǁA�u�s�k���v�Ƃ�������ɋ~�������߂�O�͂Ȃ������悤���B �@����ɗ����ꂽ���R���}�q�́A�g���M�i��7�j��̎w���ŗ��ɂ������u�̎��̂ɔn���ɂȂ�A�������̂��B �@�u���͑����������Ċv����m�ɂȂ�v �@�ޏ��͋��тȂ���A���̂̊�ʂ����葱�����B���̉��R������A���̂ƂȂ��Ĉłɑ�����^�����瓦����Ȃ������̂ł���B�ނ�̎���͎��̂�ːJ���錃��ł������Ȃ�����A���Ȃ̑��̂��������s������߂��Ȃ������̂��B �i��7�j��������23�B���l������w���ށB���l���ۋ����o�g�B�e�X�P��������u��������v�i�g�D������l�̓��m���i�c�̖��߂ɂ���ĎE�Q���������j�Ɋ֗^������A�R�x�x�[�X������́u��ԎR�������v�ɎQ�����A�ߕ߁B1983�N�A�������قŖ��������̔������A�㍐�����A�Y�͊m�肵���B�Ȃ��A11�Ԗڂ̋]���҂ƂȂ������q�݂���̎�����̕v�ł��������B �@
�@���������Ԃ́A�����̈�r��H��B �@��������J���ꂽ���̘A���͎���Ɏ��~�߂������Ȃ��Ȃ�A�u�����v�ɑ���\�͓I�w���̘g�g�݂���A���Y�ɂ�鐧�قƂ����Ɍ��I�Ȍ`�Ԃ��o�ꂷ��ɋy��ŁA���̎c���x�����悢��G�X�J���[�g���Ă����̂��B �@�X�Ɖi�c���A���q�݂���i���l���ۋ����j�̕�̂���َ������o�����@��^���ɘb���������Ƃ����G�s�\�[�h�́A�ō��w�����Ƃ��Ă̔ނ�̎���̕����`������̂Ȃ̂��B���̂Ȃ�A�u�����v�i�s���̋��q����َ������o�����Ƃ́A���q�́u�����v�𒆒f��������ŁA�ޏ����E�Q���邱�Ƃ��Ӗ����邩��ł���A����͎w�����́u�s�k���v�_�̎��Ȕے�ɒ�������̂ł���B �@�X�Ɖi�c�̗����̕���́A�ނ炪���q�̕�����؊J���đَ������o���Ȃ��������f�̖������A�������낤�ɁA�ނ玩�g�����Ȕᔻ���Ă��邱�Ƃ��疾�炩�ł���ƌ����悤���B �@����Ƃ��u�����v�ɂ�錃��������ŁA���͂�Y�I���͂����҂��ׂ����Ȃ����̂Ɛ��_�𑁂߂ɓj���āA�����̊v���Ƃ�g�D�̎q�Ƃ��Ĉ�Ă�������萶�Y�I�ł���Ƃ����v�z���A�����ɘI���ɔ����o���ɂ���Ă���ƌ���ׂ��Ȃ̂��B �@������ɂ���A�������ď������A���ɂ͉����I�ɁA�l�Ԃ́A�l�ԂƂ��Ă̎��䂪�m���ɍ�����Ă����̂ł��낤�B
�@
�@�����ꂽ����͎c���̓��퐫�ɓ��Ă����A���̏�O���킵���U�������قړ��퉻����Ă���ƁA���u�����̊�ƂȂ�ނ�̓ƑP�I�ȕ��@�̗ՊE�����A�O���Ɍ������Ċg�[���ʂ����Ă����B �@����́A�ǂ̂悤�ȑΏۂ́A�ǂ̂悤�ȍs�ׂ����u�����v�̑ΏۂɂȂ蓾��Ƃ������Ƃł���A�����āA��x���̖��H�ɛƂ�����E�o�s�\�Ƃ������Ƃ��Ӗ�����̂��B���̉ߒ��̒��ŕ��ꂩ�����Ă����������C�ɉ�̂ɒǂ����݁A�����čŌ�ɁA�g�̋@�\�E����Ƃ������ɂ����ǂ남�ǂ낵���u����̋��|�v���A�����Ɋ�������̂ł���B
�@
�@�A���ԌR�̃i���o�[�R�ł���������O�́A���R�̎���A�u�s�k���v�_�ɂ���Ă������[���ł��Ȃ���������������āA���ɒ����ψ�����̗��E��\�����邪�A�������ނ̒�R�͂����܂ł������B �@�p�g���V�A��X�^�C���z�t�̌��t�����A����̂��̃p�t�H�[�}���X�͈ꎞ�I���ʂ������炵�������ŁA�̈����̎��~�߂ɂȂ���������������Ȃ������B �@�ޏ��͏����Ă���B �@�u���ۂɂ͉���������Ă͂��Ȃ������B�l���ւ̐S���I�_�C�i�~�Y���͑��ς�炸�ŁA������������Ă��������Ȃ̂��B���������̉�����Ԃ��s���S�Ȃ��̂������B���łɋ]���҂ƂȂ����l�A��_���x�����ꂽ�l�A�܂��^�[�Q�b�g�ɂȂ��Ă��Ȃ��l�A���̎O�҂̂������ɖ��m�ȋ�ʂ͉����Ȃ������v�i�O�f�����j �@����A�u����v�̋�C�͖����ٔ��̗l����悵�āA�d���b��ł����̂ł���B �@�P�U���I����P�V���I�ɂ����ă��[���b�p�ɖ҈Ђ�U����������ٔ��̔�Q�҂́A�g���Ȃ��A�n�����A�����{�ʼnA���ȃ^�C�v�̏����ɏW�����Ă����Ƃ��������邪�A�₪�Ă��̊_������蕥���āA�u���ł�����v�̗l����悷��Ɏ���̂́A�}�~�̃��J�j�Y���������Ȃ��ߒ��ɐl�Ԃ��Ƃ��Ă��܂��ƁA�K���ߏ�ɐ��ڂ��Ă��܂�����ł���B
�@
�@�l�Ԃ̎���́A�}�~�̃��J�j�Y�����\�S�ɍ쓮���Ȃ����ł́A���܂�ɐƎ�߂���̂��B����͐l�Ԃ̖{���I���ׂł���B �@��������~�]���J�����ƁA�����ɎЉ�I�}�����\�S�ɋ@�\���Ă��Ȃ�����A�������������Ȃ��Ȃ�P�[�X�����X�o������B��q�����e�[�}���獱����E���邪�A�M�����u���ő叟���邱�Ƃ͖����̑�s����邱�ƂƖw�Ǔ��`�ł���A�Ƃ����ڋ߂̗��z�N���ė~�����B �@����͔]�Ȋw�I�Ɍ����A�X�g���X�z�������Ƃ��ẴR���`�]�[���̕��傪�}���͂������āA�]�ɋL�����ꂽ�������̖\���𐧎~�ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����ʁA�\�ꂽ��s�̃Q�[���ɗ��ꍞ��ł��܂��Ƃ��������ŏ[�����낤�B�u�������Ɉ�҂��炸�v�Ƃ����i�������H����̂͗e�Ղł͂Ȃ��̂ł���B�܂��Ă�Z�������̏����Ŕ[�����邱�ƂȂǁA���ւȃA�C�e���Ɉ��錻�㕶���Љ�̒��ł͐q��Ȏ����ł͂Ȃ��ƌ����Ă����B �@���݂ɁA�퍑�����Ƃ��Ė��������c�M���́A�u�b�z�R�Ӂv�i���c�Ƃ̌R�w���j�̒��ŁA�u�Z�������̏��͏\���̏��Ȃ�B�����̏��͂��₤���B�㕪�\���̏��͖����啉�̉����v�ƌ����Ă��邪�A�W�i�����j�������ł���B�������̗����̋����ȂǍ����m��Ă���̂��B �@�Y���R�̎R���ɍ��ꂽ�v���̂��߂́u����v�ɂ́A�K�x�ȑ��ݐ���̖���I�ȃ��[���̒蒅���S���Ȃ��A���߂���ߏ�ɗ���郊�X�N�ׂ��Ă����̂ł��낤�B �@��l�̏��Y�҂��o�������_�ŁA���́u����v�͊��S�ɗ}�~�͂������Ă��āA�u�����ĒN�����Ȃ��Ȃ�v�Ƃ�����ɂ��ׂ��̑O��ɂ������Ƃ�������̂��B �@�A���ԌR�̒����ψ��ł������R�c�F�́u�����v�̌_�@�ƂȂ����̂́A���ƍ���ŕ��C�ɓ������Ƃ����ȍs�ׂł������B �@������A�y�Ԃɂ��镺�m�����ɕ����͉̂i�c�m�q�ł���B
�@
�@�u�R�c�́A����N�ƒ��֍s�������A�Ԃ̏C�����ɕ��C�ɓ��������Ƃ���Ȃ��������肩�A����ɑ��āA����N�ƈꏏ�ɕ��C�ɓ������͎̂w���Ƃ����ϓ_����͂܂��������Ƃ͎v�����A��l�Ȃ�Εʂɂ܂����Ƃ͎v��Ȃ��Ƃ������B����͉���N�͂܂��v�z���ł܂��Ă��Ȃ�����A�����������ɕ��C�ɓ���u���W���A�I�ȌX���ɗ���邪�A�R�c�̗l�Ȏv�z�̌ł܂����l�ԂȂ�A���ɏo�ĕ��C�ɂ͓����Ă��悢�Ƃ������ƂŁA������`�ł���A�R�̓������y��������̂��B�R�c�́A���H���y�����Ă���̂ŁA���H�ɂ����݂����Ƃ�v�����邱�Ƃɂ����v�i�u���m�����̘A���ԌR�v���j
�@
�@�v����ɁA��l�Œ��̕��C�ɓ������s����ᔻ���ꂽ�R�c���A�u��l�ŕ��C�ɓ���Ζ��Ȃ������v�Ɠ������_�ɑ��āA���ꂱ���A�u������`�̘������̕\��v���Ƒ������d��ꂽ�̂ł���B �@�ߕߌ�A�܂��ɂ��̊�����`�����Ȕᔻ�������l�ł���i�c�̂��̕������m�������A�ٌ������ɁA�u�ًc�Ȃ��I�v�Ɣ����������Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B �@�����ĐX���A�R�c�̖��_���������Ă����A�����I�ɔ����Ă����B
�@
�@�u���O�ɗv������Ă��鑍���͎��H�ɂ����݂����Ƃ��v �@���̜����ɁA�R�c�̓����͈�����Ȃ��B �@�u�͂��A���̒ʂ�ł��v �@�X�ɐX�́A�⍓�Ɍ����n���B �@�u���O�ɂO�D�P�p�[�Z���g�̋@���^����B�������琅��t�ł܂��E��������v
�@
�@���ꂪ�A�Ō�́u�����v�ҁA�R�c�F�l���̃v�����[�O�ł���B
�@
�@�X�P�v�́A�����́u�e����Əl���v�i�V��Њ��j�̒��ŁA�R�c�F�̖��_���ȉ��̂悤�ɋL���Ă���B �@�@ ����A�i���A�����A��������̈�̂߂ɍs���ہA�ނ����h�����l�q�ŁA�l�����Ȃ��̂ɋ���Ƃ������肵�����B�@
�@�A �V�O�N�̐�����E�̍�����A���N�͊Q���Ă������A�����������Ȃ��ߓx�ɖh�q���悤�Ƃ����X�������鎖�B
�@�B ��ɏ������ׂ�����Ƃ��Ẵi�C�t���A����Ƃ��͉H�ڔ��Ŏh�����肵�Ȃ���A�u���Y�ꂽ�肷�鎖�B
�@�C �����ƌR���P���x�[�X�̒������������s���A���R���̌������̂��߂ɂ͉Ȋw�I�Ώ����K�v���Ə̂��āA�����̕i���������A���X�B
�@ �@�ȏ�̎R�c�̖��́A�K�������ւ̊ւ����̖��ł���A��ɏ��L�ǓI�A�鏑�I�Ȋ����ɏI�n�������ł���A�X�ɂ��āA�u���̑����v��ᔻ���Ȃ���A�u����͊v����m�ɂƂ��Ĕ����Ēʂ�Ȃ����Y��`���̊ł���v�A�Ƃ����X��̌����ɂ����ɓ�������コ�Ȃǂ��w�E�����B �@���̍Ō�́u�����ɓ�������v�Ƃ����w�E�́A�����̐X�P�v�ɂ�镺�m�����ւ̃_�u���o�C���h���ؖ�����M�d�Ȏ����ƂȂ���̂����i�ᔻ���������A���A�������������Ƃ�����d�S���j�A����ɂ��Ă��A�@�`�C�ɖԗ�����Ă��邱�Ƃ̉��Ƃ�����{�����A�������A��ϐ��A�����B �@�܂��ɏd���̋���˂����ϔO�l���ł���B����Ȃ��ƂɎ��Ԃ������ĘJ�͂��₷�Ȃ�A�����ɟr�Ő������ł������Ƃ������ƂɃG�l���M�[���X��������ǂ������Ȃ̂ɁA�Ƃ��]�v�Ȃ��Ƃ�Q���Ă��܂��قǂ��B �@���������ꂪ�A�}���n�̂����Ȃ��ߒ����J���Ă��܂����҂́A���̉ߏ�̗l�ԂȂ̂ł���B�ʂ����āA�N�����̖��Łi�߂�����j�̑��H����E�p�ł��邾�낤���B �@�Ƃ���ʼni�c�m�q�́A�J�ԂŎ�荹������Ă���悤�Ɉُ�ȃT�f�B�X�g�ł͂Ȃ��A�Ǝ��͍l���Ă���B �@�Ⴆ�A��R�Œ���ٔ����́A�i�c�m�q�̐l�i�I�C���[�W���A�u���Ȍ����~�������ŁA����I�A�U���I�Ȑ��i�Ƌ��ɁA�����ȋ^�S�A���i�S��L���A����ɏ������L�̎��X���A��Ӓn�̈����A�⍓�ȉ��s��������A���̎����Ɋ����̖��𑠂��Ă���v�ƌ��ߕt�������A���̍J�Ԃɗ��z���ꂽ�u�����v�`���ɂ́A�u����ȉЁX�i�܂��܂��j�����������N���������v�Ƃ�������ςɂ���āA���Ȃ胉�x�����O���ꂽ�C���[�W���F�Z�����f����Ă���B �@���ɂ́A�i�c�̎�L�A���Ȃ⑼�̎҂����̎�L�����ޏ��̃C���[�W�́A�R�x�x�[�X���ʼn��ʂ̓��u�����ɁA�u�S�o�o�A�v�Ƃ�����ۂ�^���Ă��������Ɍ�����悤�ɁA�m���ɁA�ȏ�ɗ�L��������X������݂����Ă��Ȃ������Ƃ͎v��Ȃ����A����ł��A�u�ɂ߂��̈����v�Ƃ͉������Ƃ�����ۂ������̂��B�J��A�O���l�̃p�g���V�A��X�^�C���z�t������i�c�]�̕��������͂����Ǝv����B �@�ޏ��͏����Ă���B
�@
�@�u���Ƃ�����ȓI�Ȑl�Ԃł����͓I�Ȑl�Ԃł��Ȃ����A���ׂĂ��܂������ƐM���āA��̍s�����j�Ɋ�łɂ����݂����Δ������\�͂������Ă���v�i�O�f���j
�@
�@���̎w�E�ɂ́A�ƂĂ��s���Ȃ��̂�����B
�@�ޏ��̔Ƃ������̉��ɂ��鉽�����_�Ԍ����邩��ł���B �@���ꂾ���͂قڊm�M�I�Ɍ����邱�Ƃ����A�X��i�c�̎��X�ȒNjy�́A�����A�u�i���o�[�Q�������v�Ƃ����悤�ȐS���I�����Ƃ͖w�ǖ����ł���A�܂��Ă�A�u�C�ɓ���Ȃ��ҁv��r������Ƃ����ړI�̂��߂����ɁA�����ɍl����꓾��S�Ă̍ߏ����ї��ĂĂ����Ƃ����悤�ȕ����Ƃ��قȂ��Ă���Ƃ������Ƃ��B �@�ނ�́A�u�r���̂��߂̔r���v�Ƃ����_�@�ɁA���C�̔@���߂��ꂽ���͎҂Ȃǂł͂Ȃ��B��������ꂸ�Ɍ����A�ނ�͖{�C�Łu�v����m�v�ł��낤�Ƃ����̂ł���B�{�C�ŁA���{�����͂Ƃ̟r�Ő������ł������Ƃ����̂��B �@�m���ɁA�X�P�v�ɂ͌��͂ɌŎ�����ԓx�������邪�A������Ƃ����āA����̌��͂��ێ����邽�߂����Ɂu�����v��s���i�˂����j����Ƃ�����������x���N���Ă��Ȃ��B �@�X�͎����P����ق��Ƃ��A�u���O�̓X�^�[�����Ɠ������v�ƌ������������A�ɂ߂ăX�^�[�����I�s���ɏI�n�����X�P�v���A���������u�l�����v�̃X�^�[�����ƕʂ�鏊�́A�L�[���t�����i��l���̔��[�ƂȂ����A�}�����ւ̈ÎE�����j�Ɍ�����A�u�ז��҂͎E���v�Ƃ����̎��̗L���ł���B �@�X�P�v�Ɖi�c�m�q�́A�P�Ɂu�v����m�v�Ƃ��Ă���܂����l�ԓI�������䖝�ł��Ȃ������̂ł���B�܂��Ă�A�X�͎����̉ߋ��Ɂu���_�v��������A���ꂪ���҂̒��Ɋ_�Ԍ����Ă��܂����Ƃ��䖝�Ȃ�Ȃ������̂��B�����v����̂ł���B �@���݂ɁA�l�Ԃ͂Ȃ����҂�����I�Ɍ����A���ނ̂��B �@���҂̒��ɁA�����ɓ��݂���ے�I���l�����Ă��܂����A�����́A�����ɓ��݂���ƐM����m��I���l�����o���Ȃ����A�����ꂩ�ł��邾�낤�B �@����́A�����̉��l�ɃZ���V�u���ɔ������鎩��قǍ������X���ł���Ǝv����B�^�ʖڂȐl�ԂقǁA���̌X���������̂��B���Ȃł��邱�Ƃ́A�����߈��ł��炠��B�A���ԌR�̕��m�������܂��A���܂�Ɍ��Ȃ����m���낤�Ƃ����̂ł���B
�@
�@�X�P�v�̈�e��ǂ�ł����ƁA���̒j���������ێq��K�I�ɔc�����鐫���̎�����ł��邱�Ƃ��ǂ�����B�������A�����������I�ɉ��߂���l�Ԃ��A���I�Ȕ��z�Ƃ��ł������ł���Ƃ͌���Ȃ��B��̐l�i�̓����ɁA�ۗ�����������`�Ƌɒ[�Ȕ���`����������P�[�X�������Ă��A�ʂɕs�v�c�ł͂Ȃ��̂ł���B�X�P�v�̃��W�b�N�́A�����ΐM����قǂ̐��_��`�ɂ���ĕ⊮����Ă������A�ނ̃p�g�X�̓��S�X��u������ɂ��āA�\������댯����₦������Ă����B �@�����́u�v���h�N�v�̑����������ł������悤�ɁA�j�I�B���_�҂ł��邪�̂ƌ����ׂ����A�X�P�v�̋ɂ߂ĊϔO�I�ȌX���́A���炭�A���l�̊ϔO�X���������ʂ̓��u�����́A���̎v�z����킹���U�����̃X�^�C���̕����t���ɂƂ��Ė��炩�ȏ�ǂɂȂ������A���ꂪ�u�����v��v�����ꂽ�҂̓����Ɍy�����������^�������Ƃ͎����ł��낤�B �@�X�Ɖi�c�́A�A���ԌR�Ƃ����u�v�z�Ƒ��v�̎q�������ɂƂ��ĈЌ��ɖ��������ł���A�܂������̑ӑĂ����������Ă���Ȃ����ŁA���i�[����ł��������B�ނ�͉䂪�q���x�z�����ɂ͍ς܂Ȃ�����玩�R�łȂ��������肩�A�q�������̉B��V�т̉��������c�����Ȃ��ł͂����Ȃ��n���ɂ܂ŁA���炭�A�m�炸�̂����ɓ��ݍ���ł��܂��Ă����̂��B����ƌ����̂��A�ނ�̂��������t���C���O��}�~������K�v�Ȏ葱�����A�u����v�̏��F���̓����ɔނ玩�g�����グ�Ă��Ȃ���������ł���B �@��́A�u�v����m�v�ւ̕ϊv�Ƃ�����Ζ���̎Y���ł��������B �@�ނ�͍D��ŁA����̎q�������ւ̃_�u���o�C���h��M�i���Ă����j��ł͂���܂��B�v���C�o�V�[�̊_������蕥���A�N���N�ɑ��Ăǂ�قǂ̈��~�ɔϖサ�����Ƃ����A���ꎩ�́A���ɐl�ԓI�Ȃ�U�������A�R�x�x�[�X�ɐN������܂ł͂����Ė��ɂ���Ȃ����������ɋy�Ԃ܂ŁA�ނ�͎����v���v�z�̐�ΐ��̖��ɂ���čق��Ă��܂����E�������ɊJ�����Ă��܂����̂��B
�@
�@�����̎̂ē�~�]���ʂ̖��Ȃ�~�]�ɂ���čْf���������Ƃ����A���ݍ���ł͂Ȃ�Ȃ��֒f�̐��E���J�����s�ׂ̃c�P���A�����̌p���͂�����Ȍ����̏�B�̓~�ɁA�W���I�ɁA�������I�ɕ\�����ꂽ�̂ł���B �@�v���C�o�V�[�̃{�[�_�[���B���ɂȂ邱�ƂŁA���݂̐l�i�̓K���ȃX�^���X���m�ۂ��邱�Ƃ�����ɂȂ�A�u�L���U�������v�̗ՊE���C�����e�Ղɒ������Ă����B�W�̒��ɏ��������܂�Ă��邩��A����̗D�ʎ҂���ʎ҂̓����ɓ��ݍ���ł����Ƃ����\�}���ʉ������B �@����̗D�ʎ҂ɂ���ĉߏ�ɔc�����ꂽ���ʎ҂̃v���C�o�V�[�́A�s�f�Ɂu�v����m�v�Ƃ����ɂ߂Ĝ��ӓI�ȉ��l��ɂ���ē���I�Ɍ�����邩��A�ɓx�ȋْ���Ԃ̉��ɒu����邱�ƂɂȂ�̂��B���R�̔@���A���x�ȋْ�����ƃ~�X�Ȃǂ�ł������낤�B�����āA���̃~�X��K���ɉB�����Ƃ��邩��A�ْ���Ԃ͖O�a�_�ɒB����B�܂��₦���A��ʂ̎҂̊፷����ߑ����āA�����ւ̏\�S�ȓK������{�헪�ɂ��邩��A�����̈ӌ���ԓx�Ȃǂ̕\�o���ɗ͉�����Ă��܂��̂ł���B �@����͎���̐헪�Ȃ̂��B �@����̔敾�����������邩��A���ꂪ���ꂽ�Ƃ��̃��o�E���h���A���܂�ɕ��C�Ȃ��قǂ̎��Ƃ����C���p�N�g�������炷�P�[�X���N���蓾��B���ꂪ�u�s�k���v�̐S�����J�j�Y���ł���B �@�Ƃ�����A�p�[�\�i���X�y�[�X�̓K���ȃX�^���X�̉�̂��A�u�L���U�������v�����I�ɐݒ肵�Ă��܂��Ƃ����ؕ|���ׂ���ł��܂��̂��B����̗D�ʎ҂���̉��ʎ҂ɑ���_�u���o�C���h���A�����ɒa������̂ł���B �@�u�L���U�������v�̓���I�ݒ肪�A����̗D�ʎ҂̎x�z�~���v�X���������A����̉��ʎ҂̎�����v�X�ڋ��ɂ����Ă����B����̉��ʎ҂̓|�W�V�����ɑΉ������L���ȓK�������l���Ȃ�����A���̔ڋ��������������D�ʎ҂ɂ���āA����ȃe�[�}���A���I�ɕ�����邱�ƂɂȂ�B���ꂪ�A�_�u���o�C���h�̃��J�j�Y���ł���B �@�`�Ƃ��������������蓾�Ȃ��̒��ŁA�`�Ƃ���������\�o���邱�Ƃ��g�̊댯�����߂邱�Ƃ�\��������Ƃ��A�l�͈�́A���Ɠ������炢���̂ł��낤���B�����ɂ́A�l�Ԃ̎����ɓ����ł��m�x�̍����댯�����ށB�l�͂�������A�ǂ̂悤�ɒE�o������̂��B �@�l�Ԃ͂��������Ƃ��ɁA�����́A�ł��c���ȑ��݂ɕϖe����B �@�����ȊO�Ɏ����̍s�ׂ�}�~�����鉽���̂Ȃ��A����̑O�ɁA�����ɑ��Ĕڋ��ɐU�������ʎ҂̎��䂪�f��Ƃ��A�`�Ƃ��������������蓾�Ȃ��̂ɁA�`�Ƃ����������ɕ\�o�����Ȃ��T�ⓚ�̖��H�ɒǂ��l�߂���A�`�ł��a�ł��b�ł��\�ȓ����̒��ŁA�������I�����Ă��A�K���s���𐏔��������ɂ͂����Ȃ��łɕ����߂��Ă��܂�����Ƃ����S���\�����_�u���o�C���h�ƌĂԂȂ�A���ꂱ���A�l�Ԃ̐l�Ԃɑ���c���̋ɂ݂ƌ����Ă����B �@���̂Ȃ�A����̎�����A��������ɓ����s�ȏ�̎c�����́A����ɂ���Đ�����l�Ԑ��E�ɂ͗e�ՂɌ�������Ȃ����炾�B
�@
�@�����ɁA�R�x�x�[�X�̋��|�̖{��������B
�@
�@�R�x�x�[�X�ŋN���������Ƃ́A������喏W�i�����イ�j����G�l���M�b�V���Ȏ�����Y�^�Y�^�ɐ�A���Ɉł̉��ɓj���Ă��܂����Ƃ������ƈȊO�ł͂Ȃ��B����E���i���̎E�Q�j�̍߂����A���肵�҂������ꐶ�w�����Ă����˂Ȃ�ʏ\���˂Ȃ̂ł���B �@�����ŁA�ȏ�̉��������Ă����B �@�肵�āA�u�����Ƃ������̎���E���̍\���v�ł���B�i����ɂ��ẮA�{�͂̍Ō�Ɉ�̕\�ɂ܂Ƃ߂��̂ŁA�Q�l�ɂ��ꂽ���j �@����́A�u�Y���x�[�X�̈Łv�̐S����͂ł���B
�@
�@�A���ԌR�́A�ŋ��̃_�u���o�C���h�𐬗������Ă��܂����̂��B�����Ɂu����̋��|�v���o�����A��ԉ����Ă��܂����̂ł���B �@�u����̋��|�v�̃R�A�́A�u����v��喏W�i�����イ�j��������̕���i�v�����z�j�������M����A�u�D�����̒B�l�v�̎u��҂����̎�����Y�^�Y�^�ɐ�āA�łɓj�i�قӁj���Ă��܂������Ƃɂ���B�u�l���@��v�̌������ɂ���҂�������ɂ���҂��A�������ׂāA���_�Ɉُ�𗈂��Ă�����ł͂Ȃ��B�ނ�͈�l�ɁA�u�v���̎̐v�ɂȂ낤�ƍl���Ă����̂ł���A����Ȏ��{�����͂Ɵr�Ő������ŁA���h�ɏ}���悤�Ɗ���Ă����̂ł���B �@���Ȃ��Ƃ��A�ނ�̎�ϓI�S��͂����ł������B �@����Ȕނ�́u�s���A�v�Ȏv�����ꂪ�A�u�Y���x�[�X�̈Łv�ɂ����Ƃ����Ԃɓۂݍ��܂�Ă����B�u����v�Ɓu����̒鉤�v�̏o����ڍ������̂��A�u�鉤�v���ǂ��̐l���ɂ��u���Y��`���_�v�̓��˂Ȃ�ł������B���ꂪ�A�̈ł�����Â��Ă��܂����̂ł���B�����\�h�ւ̑����ߒ��̏����ɂ́A�����𗧔h�Ȋv����m�Ɉ�Ă悤�Ƃ����v�����܂����Â��Ă��āA�������g�����̂��Ƃ����m���Ă�������A��̋P���������Ă��Ȃ������B �@�Y���x�[�X�ɒx��ĎQ�������A�_�N���́A���̕ӂ̎���ɂ��āu���m�����̘A���ԌR�v�̒��ŏ����Ă���B
�@
�@�u�������ɂ͒���l�߂����͋C���݂Ȃ���A�����ɂ������R���P���̂悤�Ȃ͂�Ƃ��������������Ȃ������B�y�Ԃ̒��̏��ɂ͈�l�̒j�������Ă����B�����\�h���������B�����͜ܜ�������ŐÂ��ɍ����Ă������A��ɂ͋P�����������B���́A�ނ������v������Ă���j���ȂƎv���A�����v���̂��т��������������A���̒���l�߂����͋C�ɕ����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝv�����v
�@
�@���͂��̎��_�ŁA���ɉ����ւ́u�\�͓I�w���v���J����Ă����̂����A���������łƂ����d��Ȑ��ق�������ƒ�`���邽�߂̊m�F���A�܂������ł͍s���Ă��āA�����ւ̍ŏ��̉��ł��A�P�Ɋ���I�\���̎Y���ł͂Ȃ��������Ƃ�����̂ł���B�@ �@�ڍׂɌ��y���Ȃ����A�u�v�����h�v�����������̗l�X�Ȗ��_�����h�̑�������ꂽ��A�X�P�v�͈ȉ��̂��Ƃ������������̂��B
�@
�@�u�v����m�Ƃ��Ă̒v���I�Ȏコ��������������w�����邽�߂ɉ���B���邱�Ƃ͎w���Ȃ̂��B�����ċC�₳���A�C�₩�炳�߂����ɋ��Y��`���̂��Ƃ�b���B�C�₩�炳�߂����ɋ��Y��`���̂��Ƃ�����邱�Ƃ��ł���͂���v
�@
�@�X�͂�����N���āA������w���������ꂽ�̂ł���B�i���̕ӂɂ��ẮA����O�́u�����R���P�X�V�Q�E���v��A�i�c�m�q�́u���\�Z�̕�W�v�ɏڂ����B���ɍʗ��Њ��j �@���̂Ƃ��i�c�m�q�́A���炪�u�����牣�낤�v�ƒ�Ă����A�S���͉��₩�ł͂Ȃ������B �@�ޏ��͏����Ă���B
�@
�@�u���͂����̂Ȃ��ɓ���Ă����肪�u���u���k���Ă����B���邱�Ƃɒ�R�������������A�w���Ƃ��ĉ��邱�Ƃ̎E�����ɑς����Ȃ��v������������ł���B���������͂��̐k�����B���A�w���Ƃ��ĉ���Ȃ�Ας��˂Ȃ�Ȃ��v
�@
�@���ꂪ�A�u�����v�Ɣl��ꂽ��퍐�́A�\�͓I�����ւ̐S���̃u���̒f�ʂł���B �@�������A�S�Ă͂�������J����Ă����B �@�C�₳����܂ŏW�c�\�s��������Ƃ����s�ׂ��A�u�v����m�v�Ƃ��Ĕ������Ȃ��s���ł���ƈʒu�Â����邱�ƂŁA����͋r�F����A��l�������Ă����B�u�C��ɂ�鋤�Y��`���v�Ƃ����A�X�̐M����l�ԗ����̒�m��ʓ݊����́A���炭�A�ނ̌ŗL�̌��ׂł������B�X�͉������E�Q����ӎu�Ȃǖѓ��Ȃ������̂��B����́A�ԌR�h���ォ��g�ɕt���Ă��܂����A�����̖\�͐M�̈������Y���ł��������ƌ�����B �@�������A�����͓s�s�ł͂Ȃ������B �@���т��グ��҂��ً}����͂��̃X�y�[�X�������ɂ͂Ȃ��A���̎���������I�ɎN����āA���͂�B�����Ƃ��Ă��B����Ȃ��ڋ������A���̗͂⌵�Ȋ፷���̒��Ɉ�������o����Ă���B�����ɁA�u����̋��|�v���o������̂ł���B �@�܂��Ȃ��A�\�͂̉��S�҂̎���ɂ��A����̔ڋ����ɓ{����o���銴��܂Ƃ��Ă��āA�p���čU�������������邱�ƂɂȂ�B�u�����͊v����m�ł��낤�Ƃ��Ă��Ȃ��v�Ɗ��Ă��܂����ƂŁA�v�X���肪������Ȃ��Ă��܂��̂��B����̖��ĂȊW���u����v�����A��������E�o����Ȏ��Ԃɒ��ʂ�����A�ߏ�ȕ���ɂ���ĕ⋭����Ă��܂����肷��ƁA�ɂ߂Ċ댯�ȓW�J���J����Ă��܂����Ƃ�����B�l�����@�����i��8�j��u�����`�E�_�r�f�B�A�������i��9�j��z�N���ė~�����B�u�Y���x�[�X�̈Łv�����A�܂��ɂ��̓T�^�I�ȓˏo�������B �@�N���A�����Ŕƍߎ҂ɂȂ낤�Ƃ����̂ł͂Ȃ��B�N���A�����Łu�s�k���v�ɂ�鎀�̂ł��낤�Ƃ����̂ł͂Ȃ��B�l�X�ɈقȂ������q�����G�ɏd�Ȃ荇���Ĉłɗn����Ƃ��A�����ɒʏ�̊ϔO�ł͂��悻�M����ߒ����˔@�J����Ă��܂��A�u����͕ς��ȁv�Ǝv�����A�N��������O���C�����邱�Ƃ��ł����A�B�A��������Ɏ��Ԃ���������Ă����B �@�l�Ԃ͉ߋ��ɁA���������ł̋L�������Ƃ����قǕ�������ł��Ă���̂ɁA�L���̐��m�ȓ`�B�������I�ɍs���Ă��Ȃ��������߂ɁA���ł������悤�Ȍ����d�˂Ă��Ă��܂��̂��B�l�Ԃ͂Ȃ��Ȃ�����Ȃ����݂Ȃ̂ł���B �i��8�j1978�N�ɁA�W���E�W���[���Y�Ƃ����j��������č��L���X�g���n�J���g�@���c�́i�u�l�����@�v�j���A��ẴK�C�A�i�ŏW�c���E���s�������ƂŒm���鎖���B �i��9�j1993�N�A�A�����J�E�e�L�T�X�B�ŋN���������B�f�r�b�h�E�R���V��������u�u�����`�E�_�r�f�B�A���v�Ƃ����J���g�I�@���c�̂��A�������ĘU�邵������A�W�c���E�������������A���E���ɂ͍����^�₪�c����Ă���B�����x�����̓˓��̍ہA���̉f�����S�ĂŒ��p����Ռ���^�����B �@
�@�����ɁA���܂�ɗL���ȐS������������B �@�P�X�U�O�N��ɍs��ꂽ�A�G�[����w�̃X�^�����[��~���O�����Ƃ����S���w�҂ɂ�����������ł���B�p�g���V�A��X�^�C���z�t���j���A�u���{�ԌR�h�v�̒��ŏЉ�Ă������A�����܂��A���̎����Ɍ��y���Ȃ���ɂ͂����Ȃ��B�A���ԌR�����̐S�����J�j�Y���ɂ��܂�ɍ������Ă��邩��ł���B �@�����͂܂��A�S���e�X�g�ɎQ�����邲�����ʂ̎s���������W���邱�Ƃ���n�߂��B���債���s�������Ƀ{�^�����������A�}�W�b�N�~���[�̌��������ɍ�������Ώۂ̐l�����̃~�X�ɓd�C�V���b�N��^����d���̃A�V�X�g�����߂�B �@�������Ď����̓X�^�[�g���邪�A���O�Ɏ����҂�������A���郌�x���ȏ�̓d������������팱�҂͎��S���邩���m��Ȃ��Ƃ������ӂ��������B����ɂ��S�炸�A�U�O�p�[�Z���g�ɂ��y�Ԏ����Q���҂́A�팱�҂̎������f�̃A�s�[����m��Ȃ���A���X�Ƃ��ăX�C�b�`�������������̂ł���B����́A�w�������Ԑl���ς��͂Ȃ������B �@�ܘ_�A�����̓����Z�ł���B�d�C�͍ŏ����痬��Ă��炸�A�팱�҂̋��т����Z�ł������B�������A���ꂪ�����Z�ł���ƒm�炸�A�����Q���҂̓{�^�����������̂ł���B���̃����Z�����̖ړI�́A���́A�u�l�Ԃ��ǂ��܂Ŏc���ɂȂ�邩�v�Ƃ����_�����邱�Ƃɂ������B
�@
�@�����āA���̎����̌��ʁA�l�Ԃ̎c�������ؖ����ꂽ�̂ł���B �@���������́A���̎����͂���ŏI���ɂȂ�Ȃ��B���̎����ɂ͑���������̂��B�����A�팱�҂��~�X���Ă��A���x�͂ǂ̂悤�ȃ{�^���������Ă��n�j�Ƃ����t���[�n���h����������A���Ɩw�ǂ̎s���́A�ł��y���d���̃{�^�����������̂ł���B �@���̎����ł́A�l�Ԃ̎c�������ے肳�ꂽ�̂ł���B �@�����̎����́A��̉������̂��B �@�l�Ԃ̎c�������A����Ƃ���c�������B���̗����Ȃ̂ł���B�l�Ԃ͎c���ɂ��Ȃ蓾�邵�A�[���ɗD�������Ȃ蓾��̂ł���B �@���҂���͉̂����B �@������͂����茾���邱�Ƃ́A���ߌn���̋��͂ȉ�݂̗L�����A�l�Ԃ̐S���ɏd�v�ȉe����^���Ă��܂��Ƃ������Ƃł���B�܂�l�Ԃ́A���鋭�͂Ȗ��ߌn���̉e�����ɒu����Ă��܂��ƁA�����ɋt�炢��s�ׂ̑������������A���ꂪ��`�����ɐ[�X�ƃ����N�����Ƃ��A����ׂ����s�̃V�X�e����n�����Ă��܂��̂ł���B �@�A���A�����u���������A���A�u�����̐S���w�v�ɐU��₷�����������{�l�́A�����̏ꍇ�A������̌����œ����Ă��܂��X�������邩��A�ׂ̐l�̃X�C�b�`�E�I����ڌ����Ă��܂��ƁA�s�ׂ̎������������������Ă��܂��悤�ȂƂ��낪����B �@�������A�����Ɂu�T�ώҌ��ʁv�̍\�����q�̈�ł���A�u�ӔC���U�̐S���w�v�i���������������̂ł͂Ȃ��ƍl���邱�Ɓj���}���ƁA���s�̃��J�j�Y���͍\�������邾�낤�B �@����͋^�������̒��S�l���ɁA�u�������������Ȃ��v�ƌ��킵�߂�\�����Ɠ����ł���A���̍��̖����A�W�A�e�n�ŖT�ᖳ�l�̐U���������Ă����Ȃ���A�u�����x���ꂽ�v�ƌ����Ă̂���X�����Ƃ��債�ĕς��Ȃ����낤�B
�@
�@�l�ފw�҂̍]�����P���͎����̒��ŁA�l�Ԃ̓����ɐ��ށu�E�C�}���v�ɂ��Č��y���Ă��邪�A����́A���̂悤�ȏX���ɂ܂鎄�����l�Ԃ��~���肪����ƌ����邩���m��Ȃ��B �@�]�����́A�u�\�㐢�I�̒����ɂ͕ߗ����ˎE���邱�Ƃ𖽂���ꂽ�\�̕��m�̏e�̂����A�\�꒚�ɂ͎��e���A�꒚�ɂ͋�C�����߂Ă����̂��ӂ��������v�Ƃ����N���|�g�L���̌��t���Љ�����ƁA�܂�ǂ̕��m���A�����͎E�Q�҂ł͂Ȃ��ƍl���Ď���̗ǐS���Ԃ߂����Ƃ��w�E���A�����ɐl�Ԃ́u�E�C�}���v�����悤�Ƃ���̂ł���B �@���͐l�Ԃ́u�E�C�}���v�Ƃ������̂ɂ��āA�ے���m������Ȃ��B�l�Ԃɂ́u���ł�����v�ƍl���Ă��邩��A���P���Ƃ��������Ƃ��̖��̐�����ɂǂ����Ă�����܂Ȃ��̂ł���B �@���݂ɁA���Y���x���ێ�����킪���̏��Y��i���A�Y�@�P�P���P���ɂ���či��Y�ł���ƒ�߂��Ă��鎖����m��l�͑������낤���A���ۂɏ��Y�̃{�^���������l���������݂��A���̒��̈���A���Y�𐬌����ɐ��s����{���̃{�^���ł���Ƃ���������m���Ă���l�͏��Ȃ��ɈႢ�Ȃ��B���̍����܂��A�Y�����̐S�̕��S���y�����邽�߂̃V�X�e�����ێ����Ă���̂ł���B �@�����A���ꂾ���͌�����B �@�l�Ԃ͊���W�̂Ȃ�������ȒP�ɎE���Ȃ��A�Ƃ������Ƃł���B �@�l�Ԃ��l�Ԃ��E�����Ƃ��ł���̂́A�ʏ킻���ɉ��O�Ƃ��A�v�z�Ƃ��A�g�����Ƃ��A�g�D�̘_���Ƃ����}���Ă��邩��ł���A��E�Ƃ͂����A�@����b�ɂ������āA����̍ݔC���ɂȂ��Ȃ����Y���s�̋���^���ɂ����̂ł���B���Ɏ��Y���s�̐ԉ��M�����������@����b���A�Y��������O�Ɋm�F����s�ׂ��������Ƃ����b���悭�������ł���B�i�@�s���̍ō��ӔC�҂��܂��A�l�X�Ȋ������������l�̐l�Ԃł���Ƃ������Ƃ��B �@�|���āA�A���ԌR�̎��́u�����v�́A����W���h���h���ɉt�����b�݂̂悤�ȗ���ŕ����オ���Ă��āA�ۗ����Đl�ԓI�����A�������A���܂�ɉߏ�ȋ����ɗ�����߂��Ă��܂����ƌ����邾�낤���B �@�c���ꂵ�҂����̎����������ʂ������ɁA�N�I�ɂ�����̊�@�ɗ�������āA���킶��Ǝ���̋��|�ɓۂݍ��܂�������B�r�Ő�Ƃ����{�Ԃɔ������͂��̃g���[�j���O�̉Ս����̒��ŁA���̂Ǝ���̂���������u���[�N�_�E���i���̏ꍇ�A���̋@�\�̐���j���N�����Ă��܂��āA�{�Ԃ������ɋ����Ă��܂����˂Ȃ������̂ł���B �@�u����̋��|�v�͍ł��댯�ȐS�������̋�C�̑O���ƂȂ�A�S�Ă̎҂��d�C�X�C�b�`���������A�N�Ƃ͌��킸�ɔ팱�̏�Ɉ�������o�����Q�[���̉Q���ɂ����āA�Ђ�����u�v�����z�v�̕�����v������͂Ȃ��B���������ɂ����A�����ė������̂����݂����Ȃ��̂ł���B�l�Ԃ͂������ď������A�����Ċm���ɑʖڂɂȂ��Ă����B �@�c���ꂵ�҂����̉��l�������͂ɕߔ�����A���l�������͂Ƃ̏e����ɉ^�����J���Ă������ƂɂȂ����Ƃ��A�c���ꂵ�҂����̑S�Ă̕\��̒��ɁA�����̉�������t��o����Ă����̂́A���܂�Ɉ������p���h�b�N�X�ł������B �@�u����܂ł̋��Y��`���̓����̒��ŁA�����Ȃ��G�Ƃ킯�̂���Ȃ��������������A�������d���ɂ���ď��Ղ������Ă����Ƃ���ɁA����Ɗ�Ɍ�����G������A���Y��`���̏d���A�Ƃ�킯�����̓��u�̎��ɑς��Ă�����ɂ���������A�G�Ƃ̑S�͂̓����ɂ���āA�����̓��u�����ɒǂ�������ӔC�����Ȃ���Ǝv��������ł���B���́A�{���ɋC���������ꐰ��Ƃ��Ă����B�F���A���l�炵���A���C�ɂ��ӂ�Ă����B�������A���������C���Ƃ͂���͂�ɁA�����Ƒ��̒ɂ݁A�̂̔�J����i�ƂЂǂ��Ȃ��Ă���A�͂����Ă��̎R�z���Ɏ��̑̂������낤���Ƃ����s�������������A�̂���������撣�邵���Ȃ������v�i�u���m�����̘A���ԌR�v���j �@����͖{�e�œx�X���p����A�A�Ԃ̈ꕺ�m�ł������A�_�N���̎�L�̒��́A���Ɉ�ۓI�Ȉ�߂ł���B �@�u�����v��v�����ꑱ���Ă����A�_�̉^�������I�ɕς����R�x�ړ��̐h�����A�u����v�Ɠǂ݉����S����Ύނ���͖̂��ł���B���m������ǂ��l�߂��u����̋��|�v���������Ƃ��A�ނ�̕��ꂩ����������͐M����قǂ̕����͂������Č������B�����ł̔����ɂ͖ܘ_�A���ꂼ��̒u���ꂽ�◧��ɂ��l�������邾�낤���A���Ȃ��Ƃ��A�A�_�̂悤�Ȉꕺ�m�ɂƂ��āA����͖�����������j�ȕǂ̕������������قǂ̉����������̂��B �@���̎R�z���̐�ɑ҂��Ă����̂����͂ɂ��ߔ��ł������ɂ���A�R�z���͕��m�����ɂƂ��ẮA�u����̋��|�v��˂������Ă����s�ׂł������B �@�R���z���邱�Ƃ͋��|���z���邱�Ƃł���A���|���z���邱�Ƃɂ���āA���ꂩ����������C�����邱�Ƃł������B �@����́A��������ȏ�͂Ȃ��Ƃ�����ɂ���̉���ł���B���̉���̉ʂĂɑ҂��̂����ł������ɂ��Ă��A���m�����ɂ͓�Ȃ��ς������ɂł���Ǝv�����ɈႢ�Ȃ��B�u�Y���x�[�X�̈Łv�ɔ�r����A����͋ς����t���b�g�ȋ�ɂł����Ȃ������̂��B �@�A���ԌR�̕��m��������B�̎R���ɉ��\�������E�́A�l�X�̎��䂪�����ɃA�N�Z�X���Ă��܂����Ƃ̊댯���w�K���邽�߂̋�ԈȊO�ł͂Ȃ������B �@�����ĕ��m�����́A�Ō�܂ł��̏��F������̒E�o������̈ӎu�ɂ���ĉʂ����Ȃ������B���F���̊O���ŋN�������̕ω���ǂ݉������Ƃɂ���Ă����A���m�����͎���̎���葱�������F������̒E�o���ʂ����Ȃ������̂ł���B �@�܂�ŁA����̕挊��فX�ƌ@�葱�����Ŏ��e���̎��l�̂悤�ɁA�����ē����������́A��������Ɏ��ԂɘM�i���Ă����j��Ă��������������B�l�X�̎���͌���Ȃ���]�̋ɂ݂ɏ��ߐs������Ă��܂��Ƃ��A�����グ���A�̂��N�������A�v�����\�����A�Ђ�����ċz���q���ł�������ƂȂ�B�����̓����ƊO������_���������ɂȂ��A�G�߂̕����A������Ղ�͂��Ȃ�������ї����A���Ă��~�������ɒu������ɂ��Ă����̂��B
�@
�@���m�����́A�����ʼn���҂��Ă����̂��B �@�����҂��Ă��Ȃ��̂��B�@�ނ�̎���͒����ԁA�҂��Ƃ�����Y��Ă����̂ł���B �@�҂��Ƃ���Y��Ă�������ɁA��w�̓˕����������Ă����B�˕��́A���䂪����ł��邱�Ƃ���܂��ɑ���ł��h���I�ȉ������^��ł����B �@���m�����̎���͓˂���������A�ʑ��̐��E�ɉ����o����Ă����B �@���̂Ƃ��A�u����̋��|�v�̊O���ɁA������̕ʂ̐��E�����݂��邱�Ƃ�m�����B���m�����́A���̐��E���������������A���������̐M���鋳�`�ɂ���Ĕj��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ɗo�債�Ă������E�ł��邱�Ƃ��A�����Ɋm�F����B �@���ꂩ�����Ă������m�����̎���́A���̐��E��O�ɂ��Č������S�����̂��B���������̂���܂ł̉Ս��́A���̐��E��|�����߂ɑ��݂��A���̉Ս��̕⏞�����̐��E�ɕԍς��Ă��炤���ƂȂ��A���������̖����������đ�Ȃ��ł��낤���Ƃ��A���m�����̎��䂪�c�������̂ł���B
�@
�@���m�����͎R���z���邱�ƂŁA�Ս��̉ߋ����z���Ă����B���|���z���Ă����B�����グ�Ă����ł𖾂邭���Ă����B �@���Ԃ�D�҂��镺�m�����́A���c�Ȃ܂łɓƂ�悪��̗����A�������ĊJ�n���ꂽ�̂��B �@ �k�����Ƃ������̎���E���̍\���l�i�A���ԌR�Ƃ����_�u���o�C���h�j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�D�̒a���Ɵr�Ő�̎v�z�̑I��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i����̗D�ʎ҂Ɖ��ʎ҂ւ̕����j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�u����̏o���v���@�R�x�x�[�X�̊m�ۂƊv����m�̗v��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�u���Y��`���_�v�̉��B�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�u����̒鉤�̏o���v���u���Y��`���_�v�ɂ��u�����v�ߒ��̓W�J
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�����v�ߒ��̓W�J�ɂ��v���C�o�V�[�̞B����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�ƌ̓K���X�^���X�̉�́j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�u����̋��|�̐����v���L���U�������̓���I�ݒ�ɂ��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\�͓I�w���̏o��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�u����̋��|�̓��퉻�v������̗D�ʎ҂Ɖ��ʎҊԂْ̋��̍��܂�ƁA
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����敾�ɂ��A�E�g��I�u��R���g���[���̓��퉻
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�ڋ����̏o���i���ʎҁ��D�ʎҁj�Ǝx�z�͂̑����i�D�ʎҁ����ʎҁj
�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ŋ��̃_�u���o�C���h�̐���
�@�@�@�@�@�@�i�`�����I���ł��Ȃ��̂ɁA�`��I�������Ȃ����ƁA�����́A
�@�@�@�@�@�@�@�@������I�����̒����炢��������I�������Ȃ����Ɓj �S�D���|�z���̐�ɑ҂��E �@ �@���������m�����̎R�z���́A���m�����̉^�����Ă����B �@���Ԃ�D�҂ł����ɕߔ������҂ƁA�e����Ƃ�����]�I�����A���߂Ă��ꂪ���邱�Ƃɂ���āA�����������u�v����m�v�̕����D�҂ł���]�݂�����҂Ƃ̍��́A�P�ɉ^���̍��ł����Ȃ��B���̉^���̍��́A�����ɁA�}���t���Ă�����O����C�萬�i�������j�ɕ��o������F��i���傤�����j����ɓ������̂��ł����҂ƁA�������ɓ�����Ȃ������҂Ƃ̍��ł������B �@�����Ƃ�����O�̂悤�ȁA���u�E���̏\���˂̏d�݂ŕ������̋ɂ݂ɂ������u�v����m�v���������Ƃ������ł������B�������{�l�̎v���̔@���ɍS�炸�A�e����Ƃ������I�ȏW�J�̃��A���e�B���A�u�Y���̈Łv�ŏW���I�ɗ��ߍ��X�g���X���A���̊ԁA�f�������������ʂ��������Ƃ͔ے�ł��Ȃ��ł��낤�B �@�e����ɎQ��������m�����͈�C�ɒʑ��̐��E�̎N���҂ɂȂ邪�A�T�l�̓����şr�Ő�Ƃ����ɏ�̊ϔO���e�ۂ�����G�̒��ɁA���^���̐g�̉����l������悤�ȓk�i�����j�Ȃ�ʉ������ǂꂾ���x�炳��Ă������A���͒m��R���Ȃ��B �@������ɂ���A�ނ炪�R���̊Ǘ��l�̕v�l�ɑ��Ĝ���i����j�ɑΉ����A����͊����A�u�l������͐j��{�����Ȃ��v�Ƃ�����������H����A�ނ�̌ŗL�̃X�g�C�V�Y�������Ă��Ȃ��������Ƃ��v���A�u�v����m�v�Ƃ�������ւ̃M���M���̌Ŏ��������Ɍ��邱�Ƃ��ł���B �@�ނ�͊Ǘ��l�̕v�l��l���ɂ����Ƃ��������A�l���̐����ƌ�������邽�߂̎��������̐푈�ɁA�l�������S����̂͗��j�̋`���ł���Ƃ����v��������A���̂��Ƃ��[�ւ���Ƃ����g���������ĕv�l�ɐڋ߂����悤�ɂ��v��ꂽ�B �@�ނ�̓����ł́A���������̍s�ׂ͂����܂ł��v���̐���ł���A���̂��߂̖I�N�ł���A�s�s�����Ɉ�������N���I�Ȍ��N�ł������ƍl�����̂ł��낤�B �@��������́A�ǂ��܂ł��ނ�̕����t���ł���A���ꂪ�Ȃ��Ă͎x����Ȃ��Ս��̉ߋ�����̊�Ɍ����Ȃ������ɁA�ނ�̎��䂪�₦���N����Ă������Ƃ��A�������͍��ǂ݉������Ƃ��ł���B���m�����͂����ł��A���������葱�����ߋ��Ɛ푈���Ă����̂ł���B
�@
�@���̐푈�ɂ��ẮA����ȏ㏑���Ȃ��B �@���R�A�u��ԎR���v�Ƃ����㗝�푈�ɂ����y���Ȃ��B���y���邱�Ƃœ����鋳�P�́A�{�e�̃e�[�}�ɑ����Č����A�w�NJF��������ł���B �@��́A�u�Y���x�[�X�̈Łv�̉��ɏo�����A�����ɖ߂��Ă����B���肵�҂����̎��䂪�A���邽�тɎ����グ�Ă����n���̘A���ɑ����Ď��������Ă������܂́A�������̓��퐢�E�ł������Ό����镗�i�ł���B �@�u��������v�Ɛ����𐂂ꂽ��l���A���̐��������肷��ʕ�������Ă����A�q���̎����ւ̋ꓬ��ڂ̓�����ɂ��āA�u�������I�v�Ƃ��A�u�������ɑ���I�v�Ƃ�����ʼnߏ�ɉ�����Ă��܂��t���C���O����A�������͉ʂ����Ăǂ��܂Ŏ��R�ł��蓾��̂��B�q���̎���邽�тɁA�������͎������̎�������������A�������m���ɔ���グ�Ă���Ƃ͌����Ȃ����B �A���ԌR�̈ł́A���͎������̈łł͂Ȃ��������B�A���ԌR�̕��m�������������������̑���Ƃ́A���ƌ��͂ł����ł��Ȃ��A����̍s��������߂��Ȃ��������̋ߑ�̍r���Ƃ������䂻�ꎩ�g�ł������̂����m��Ȃ��B �@���m�����͎c�炸�ߔ����ꂽ�B
�@
�@�����āA�����ɏ\�́A����ꂵ�҂����̎��̂��c���ꂽ�B�����ɍX�ɁA�̎��̂����������Ɏ������B���Ă����R�[�ɜԚL���ؗ�i�����܁j�������A�s�s�ł́A�����Ԃɋy�A�N�V�����f��̉��y�������Ȏ��Ȋ����������B �@����́A�s�s�Z���ɂƂ��ẮA�ȒP�Ɍ��ɂ͏o���Ȃ����A�������������i�D�̐����܂ł������B���̃A�N�V�����f�悩��A�l�X�͐�ɋ��P�������o�����Ƃ����Ȃ����낤�B�u�A���ԌR�̈Łv���A�w�ǎ������̒n�����̈łɌq�����Ă��邱�Ɓi��10�j���A���R�̔@���A�������͔F�m����Ȃ��B���l�ɂ���Ď䂫�N�����ꂽ���C�̉��Ƃ͑S�������̐��E�ɁA���������̓��퐫�����݂��邱�Ƃ𑽂��̐l�X�͔F�m���Ă���ɈႢ�Ȃ��B �@����ŗǂ��̂����m��Ȃ��B �@������A�������̎����̋ߑオ�ۏႳ��Ă���̂��낤�B����́A�X�P�v�Ƃ����T�f�B�X�g�ƁA�i�c�m�q�Ƃ����A�H�Ɍ��鈫���ɂ���Ď䂫�N�����ꂽ�A�w�Ǘ���s�\�Ȏ����ł���Ƃ����t���b�g�Ȕc���ȊO�ɂ́A�����Ȃ�[�ǂ݂������Ƃ������������O�ɂ͕K�v�������̂��B �@�������̑�O�Љ�́A�������̗ނ́u�l�������Ȏ����v���A��т̓ǂݐ�R�~�b�N�Ƃ��Ă��������ł��Ȃ����������ł��܂��Ă���悤�Ɏv����B���m�������ǂ�قNj��ڂ��ƁA�ǂ�قNj������Č����悤�ƁA�������̑�O�Љ�́A�������̗ނ́u�ُ�҂����̎����v�ɋ�������Ȃ����i�������j������g�ɂ��Ă��܂����̂��B �@�A���ԌR�����́A�ŏI�I�Ɏ������́A���̗~�]���R��`�ɋ����ė���O�Љ�ɂ���ēj��ꂽ�̂ł���B�������̑�O�Љ�́A���̂Ƃ��A���x�����̃Z�J���h�X�e�[�W���J���Ă��āA���L���Ȑ��������߂�l�X�̍K���������܂��A���̈����_�ɏ��l�߂Ă����B�l�X�͂��낻��A�u��ɍ������������v��͍�����Ƃ����v���𐏔������������̂��B �@����Ȏ���̋�C���A����Ȗ�Ȏ�������e����ꌇ�Ђ̑z���͂ݏo���Ȃ��͓̂��R�������B��O�ƕ��m�����̋����́A�����S���A�N�Z�X�����Ȃ����ɂ܂ŗ���Ă��܂��Ă����̂ł���B �@����́A�{���I�ɂ͒����̕s���ȏ�ǂ�P�i���j���J����Ƃ������x�̎���̉���^���ł������Ƃ�������A�P�X�U�O�N�㖖�̔M�����A�w�������̓ƑP�I�Ȏv�����݂̒����炵���������Ȃ��������Ƃ����o�ł��Ȃ��A���́u�v�z�v�̖��n�����Y���Y���ƈ��������Ă����c�P�ł��������B�ނ�̐l�ԊρA��O�ρA�ς̐M����ƑP���Ǝ�ϐ��ɁA���͌��t�������قǂ��B�ނ�ɂ͐l�Ԃ��A��O���A���̑�O������ƂȂ����Љ�̗~�]�̐����Ƃ������̂��A�S�������Ă��Ȃ������̂ł���B
�@
�@�l�ԂɑP�l���ƈ��l�����A�w�Ǔ�������悤�Ɉ�̐l�i�̓��ɑ��݂��A�̐����ɂ��q���[�}�j�X�g�����āA���̐����ɂ��ɂ߂��̑��������݂��Ă��܂��Ƃ������Ƃ��A���̐l�Ԋς̖{���I�Ȕc���ɂ����āA�ނ�ɂ͕����Ă��Ȃ������B���̔c���̈��|�I�ȕn�コ���A�ނ�̑������A���͍X�ɉA���Ȃ��̂ɂ��Ă��܂����̂ł���B �i��10�j�u����̋��|�v���l�Ԃ̐��ސ��E�ɂ����āA�ǂ��ɂł��`������Ă��܂����Ƃ��A�������͔F�m���˂Ȃ�Ȃ����낤�B �@�����A�ȉ��̏��������Ȃ�A��Ɂu����̋��|�v�̌`���͂��\�ł���Ƃ������Ƃ��B
�@
�@����͑��ɕ��I��Ԃ����݂��A���ɁA���̋�ԓ��Ɍ��͊W���`������Ă��āA��O�ɁA�ȏ�̏��������Ȋ����I�ȃ��J�j�Y���������Ă��܂��Ă��邱�ƁA���ł���B�����ɁA���^���̑�`������v�z�I�������}����A�u����̋��|�v�̌`���͌����č���ł͂Ȃ��B�Ⴆ�A���I�ȃJ���g�W�c��A�ƑP�I�ȉ^���c�́A�s�҉ƒ�A���X�B �@�����\�h�̎���𗇂ɂ��āA���̐��~��忓��i�����ǂ��j����������o���Ă����Ƃ��́A�X��i�c�̓��f�̂��܂́A�l�̐S�̗l�Ԃ𐢑��̐����œ��@�ł��Ȃ����_���m�́A�����̔\�͂̒������������N�����̂ł������B�@ �@�ނ�ɂ́A�u���~�̏����ŔY�ފv����m�v�͐�ɑ��݂��Ă͂Ȃ�Ȃ������ł������̂��B���R�̔@���A�~�]�͐��ݏo����Ă��܂����̂ŁA���ݏo����Ă��܂����~�]�́A�~�]�ݏo�����A�ɂ߂Đl�ԓI�Ȋw�K�ߒ��̕s���ȎY���ł���A��������䂪�\�S�ɓ��䂵���Ȃ���������A���Ȃ��Ƃ��A����o������ׂ��ł͂Ȃ����ŃM���M���ɐ��䂷��d�|�����A�����ɝn�i������j���グ�Ă����悤�ɓw�߂�Ƃ����悤�ȕ����̒��ł��������ł��Ȃ��̂ł���B
�@
�@�u���Y��`���������Ƃ�A�{���ɐl�Ԃ�m��A�l�Ԃ��D���ɂȂ邱�Ƃ��ł���v
�@
�@����́A�X�P�v�̏퓅��B �@�����ł����炭�A�[���l�@���Ȃ������ł��낤�A���́u�l�ԉ��s�v�̖���̒ꗬ�ɖ��ł��Ă��闝���ւ̉ߏ�ȐM�́A���́A�����������ė����˂Ȃ�Ȃ��ƍl���Ă���ɉ߂��Ȃ������̎��ԏ����V�X�e���ł����āA�X�P�v�Ƃ������䎩�g�ɂ���āA�[���Ɍ��������̂ł͂Ȃ����Ƃ����������B�����œǂތ���A�X�P�v�Ƃ����l�Ԃقǔ��I�ŁA���I�Ȑl�Ԃ͂��Ȃ�����ł���B
�@
�@�Ⴆ�A�R�菇�i�ԌR�h�j�̏��Y�̍ہA�R�肪��悤�ɂ������u�����E���Ă���v�Ƃ��������A�X�́A�u�v����m�̎��ȋ]���I�������v�Ƃ������ɋK�肵�Ă��܂��̂ł���B �@����́A�R�x�x�[�X�ɂ����Ăł͂Ȃ��A�ߕߌ�̍����ł̔�r�I��ÂȁA�ނ́u�����v�̎��Ԃ̑����ɂ����Ăł���B�R�x�x�[�X�ł̌����Ȃ����A�Ђ��Ђ��Ɠ`����Ă���悤���B �@�������������Ȃ����A�ł��A�S�ȕ��i�̒��Ō���Ă��܂��̂́A������l�̏��Y�ҁA�����P��̃P�[�X�ł���B �@�����͒ǂ��l�߂�ꂽ�Ƃ��A�u��s�����������肾�����v�Ƃ��A�u�{�a�������āA������������ׂ͂点�悤�Ǝv�����v�Ƃ��A�u�������u�ƐQ�邱�Ƃ�N�����z����v�ȂǂƂ����Y����f�����̂ł���B �@�Ō�̍����́A�����̖{�������m��Ȃ����A�O��҂̍����͖��炩�ɁA�ǂ��������������Ă������҂�[���������Ȃ��Ƃ����A���\�����I�ȃ_�u���o�C���h�����Y���ȊO�ł͂Ȃ��B�����ɁA�����P��̐��Y���̂Ȃ�����́A��Ȃ��̖��Łi�߂�����j������v��������B �@�Ƃ��낪�A�����ԍ����҂����̎�������Ă��邩��A���̎����̍��������Y�����ł���Ƃ������߂ɒ������A�����ɍł��A�S�ȓ��u�s�E���o�����Ă��܂��̂ł���B�����̎���͉s�\�Ȃ܂łɗ�A�j��Ă��܂����̂��B
�@
�@�����Ŏ����̃T�u����[�_�[�ł������A�i�c�m�q�̎�L�����p���Ă݂�B�����ɁA�i�c�m�q�̐Ȑl�Ԋς�`���Ă�����ۓI�ȋL�q�����邩�炾�B
�@
�@�u�Ⓦ����A�o���Ă��܂����B �@�w���Y��`���x�̂��߂̖\�͓I�����v�����ł̂��Ƃł������A�X���A�w���Y��`���������Ƃ�A�{���ɐl�Ԃ�m��A�l�Ԃ��D���ɂȂ邱�Ƃ��ł���x�Əq�ׂĂ������Ƃ��B����́A���Y��`�̗��O�Ɋ�Â������̂ł������A���u�E�Q���������S���Ă������́A�s�k������̗��O�͊Ԉ���Ă��Ȃ��Ǝv���̂ł����B �@�������āA�����ł̊Ŏ�Ƃ̐ڐG�ɐV�N���������܂����B�₳�����Ŏ炪���邱�Ƃɂ͋����A�Ȃ��Ȃ�����܂���ł����B �@�ܘ_�₳�����Ŏ���A���Ǔ��S�i���F�����S�u���̂��Ɓj�̎w���ɏ]�������Ҏx�z�̈ꗃ��S���Ă���̂ł����A���̂₳���������̐S���͂��܂��A�y���������A���̐���S�y�������̂ɂ��Ă���邱�Ƃ�������̂ł����B�����҂ƊŎ�̊W�ł�����傫�Ȍ��E������킯�ł����A���̂��ߊy�����͑傫���Ȃ�̂ł����v�i�u��������̎莆�v�ʗ��Њ����^�M�Ғi���\���j
�@
�@���̉i�c�m�q�̐l�Ԋς̍��q�ɂ́A�u�Ŏ灁���͂̔Ԑl���l����}������̐��̒��ړI�Ȗ\�̓}�V�[�����ڗ�ȗ⌌���v�Ƃ����A�ɂ߂ċ@�B�I�Ȕc���̍\��������B �@�����Ă���Ȕc�������l�i���u�S�₳�����Ŏ�v�̏o���ɓ��f���A���������Ă��܂��̂��B���R�Ƃ������ł���B�M����悤�Ȃ��̋�襂Ȑl�ԊςɁA�J��A�������̕������������B �@���̐l�Ԋς���́A�u�e�Ȃ����肳��v�Ƃ��A�u�Ј��̂��߂ɍ��g������ē����o�c�ҁv�Ƃ������ݗl���͌����ē����o����邱�Ƃ͂Ȃ��A�u�o�c�ҁv�Ƃ́A�u�ڂ������ĘJ���҂����g����A�t���^�o�R����i����j�����u�^�̂悤�ɑ������y�v�Ƃ����ɒ[�Ƀf�t�H�������ꂽ�C���[�W���A�ǂ����ŕ��ȍ����̐l�Ԋςɉe�𗎂Ƃ��Ă��āA����͋t�Ɍ����A�u���Y��`�҂͊��S�Ȃ�҂����ł���v�Ƃ����M��蒅�����邱�Ƃɑ傢�ɗ^���Ă���Ƃ������Ƃ��B �@�u���S�̎w���ɏ]���A�����x�z�̈ꗃ��S�v���A�u�₳�����Ŏ�v�̂��́u�₳�����v�ɁA�u�S���͂��܂��v�銴�������i�c�m�q�́A����ł��A�u�����҂ƊŎ�̊W�v�Ɂu���E�v�������A�u�y�����v���u�傫���v���镝�������Ă���B �@���������̂��Ƃ��A���疵���ɂȂ�Ȃ����Ƃ�F�m�ł��Ȃ��Ƃ����A�܂��ɂ��̈�_�ɂ����Ĕޏ��́u���E�v������̂��B �@�u�Ŏ�̂₳�����v���u�Ŏ�v�Ƃ����L���I�Ȗ����A�����A�u�̐��̒����ێ��v�Ƃ����{���I��������K��������������Ƃ͌���Ȃ����ɁA�܂��ɐl�Ԃ̎��R������A���̎��R���l�Ԃɂ����ΐS�n�ǂ�������^���邱�Ƃ��A�������͒m���Ă���B �@�������l�Ԃ��K�肷�邱�Ƃ�ے肵�Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�l�Ԃ͖����ɂ���Č��肳���Ƃ���������m�肷�邱�ƂƓ��`�ł͂Ȃ��B�����ɐl�Ԃ́A�l�ԂƂ��Ă̎��R�̕�������B���̎��R�̕����l�Ԃ��T�C�{�[�O�ɂ����Ȃ��̂ł���B �@���݂ɁA���̈��D����f��̈�ɁA���h���[��X�R�b�g�ḗu�u���[�h������i�[�v�����邪�A�����ɓo�ꂷ�郌�v���J���g�i�n����h�q����L�������̃��{�b�g�l�ԁj�̓��{�b�g�ł���Ȃ���A�ނ�ɂ͎���̐����𑀍삷�鎩�R���^�����Ă��Ȃ��B�����A�u���v���J���g�̈����݁v�ł���B���̈����݂͐[���A���̌����̎c�����͔�ނ��Ȃ������B������A�R���s���[�^�[�Љ�ɂ�����ßT�Ȗ������C���[�W������A�u�T�C�o�[�p���N�v�̐��I��i�Ƃ��āA����͉������d�����ɂȂ����̂��B �@���킸�����ȁA�S�u���̊Ŏ�͒f���ă��v���J���g�Ȃǂł͂Ȃ��B �@�u�����x�z�̈ꗃ��S���v�ȂǂƂ����A�j���[���t�g���L�̕\���͎v�z�I�K�萫�������̂�����A���������A�ًc�\�����Ă�����ׂ��؍����̂��̂ł͂Ȃ����A�������A���̂悤�Ȗ��ȋK�萫���A�r�Ő���͂��̌R���g�D�𗦂����u�����v���Ɓv�́A���̔�����o�ĕ��Ȑl�Ԋς̃x�[�X�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ͔ے肷�ׂ����Ȃ��B�l�Ԃ̍s�g�����鎩�R�̕��܂ł��������ɂ���Č��肳��Ă��܂��Ȃ�A�l�Ԃ̖����ɂ́A�u�������I�u���W���v�i�i��11�j��A�W���[�W��I�[�E�F���i��12�j�̕��w���E�����ҋ@���Ă��Ȃ����ƂɂȂ邾�낤�B �@�R��ɁA����͐l�Ԃ̔\�͂��ߑ�]�����߂��Ă���̂ł���B �@�l�Ԃɂ́A�����ɂ���đS�Ă����肳��Ă��܂��ɑ��銮�S�Ȕ\�͐��ȂǑS���������킹�Ă��Ȃ��̂��B����ɐl�Ԃ́A�l�Ԃ��x�z����\�͂������Ă��܂��قNJ��S�ȑ��݂ł͂Ȃ��B�����ǂ����ŁA�l�Ԃ͐l�Ԃ��x�z���ꂸ�ɑӑĂ��N���̂ł���B �@����́A�l�Ԃ̎x�z�~�������̍ی��̂Ȃ��Ƃ��������Ȃ��B�ǂ�قǐl�Ԃ��x�z���悤�Ƃ��A�x�z����ʂ��ǂ������������c����āA���Ɏx�z�̐�����痣�E���Ă��܂��s�O�ꂳ������������قǁA�������̎���͌��łł͂Ȃ��B �@�l�Ԃ̎���\�͂ȂǁA���X���̃��x���Ȃ̂��B�������͑���̐S�܂ł�����������Ȃ�����ł���B�����ɐl�Ԃ̎��R�̕������܂��̂ł���B���̕����l�Ԃ����A�V����̂��B �@�l�ԂƂ́A�{���I�Ɏ��R�ł���Ƃ������݂̎d�����A���Ƃ����������Đ����Ă��������Ȃ��A����ȑ��ݑ̂ł���B �@�l�Ԃ́A���̎��R�̊C�̒��łЂ����玩��Ɉˋ����Đ����Ă����Ƃ����A����ȊO�ɂȂ����݂̎d����������̂��B�@����͂Ђ�����A�\�S�ɓK�����悤�Ɠ����Ă����̂ł���B�ǂ̂悤�ȃV�t�g���\�����A��̍s�������Ԃ̌����Ă����B�K���̐����Ǝ��s�Ɋւ��F�m���A����ɂ���ĉʂ�����Ă����B�������P��̍s���̎Y���łȂ��悤�ɁA���s���܂��A����ȊO�ɂȂ��s���̎Y���ł���Ƃ͌�����Ȃ��̂��B �@�������A���ł����ʂ͈�ł����Ȃ��B���̌��ʂ��A���̍s�����J���Ă����B���䂪�܂��A�쓮����̂��B����̂����ɁA�����I�ɔ�J���ݐς���Ă����̂ł���B �@�V�r�A�ȏ��ł́A����̓t����]��]�V�Ȃ�����邾�낤�B �@�m���ɐl�X�ɂ́A����ލs���鎩�R������B����������͒��X�����F�߂Ȃ��B�ލs�̓��X�N�𐏔����邩�炾�B�ލs�̃R�X�g�͌����Ĉ����Ȃ��B����͑ލs���鎩�R���s�g���Ȃ��Ƃ��A�����Ɏ��������m����B���̎����̒��ł��A����͓������Ƃ��~�߂悤�Ƃ��Ȃ��B�~�߂��Ȃ��̂��B����͂����ɏo�����������Ȃ��ł���ƁA��]�������ƂȂ邾�낤�B �@�l�Ԃ͎��R�ł���O�͂Ȃ��Ƃ������݂ł���Ȃ���A�����A���R�ł��邱�Ƃ̏d���ɉ����f�i�Ђ��j����Ă����B�l�Ԃ͓����ɁA�ߏ�Ȃ܂łɕs���R�ȑ��݂ł�����̂��B���̂��Ƃ����䂪�F�m���Ă��܂��Ƃ��A�l�Ԃ͈�́A�ł��Ս��ȑ��ݗl���Ɖ����ł��낤�B �@��ΓI�Ȏ��R�́A��ΓI�ȕs���R�Ɠ��`�ƂȂ�B �@���ǁA�l�Ԃ͒��X�̎��R�ƁA���X�̕s���R�̒��ő��͐����Ă����B�l�Ԃ̎��R�x�Ȃ�č����m��Ă��邵�A�܂��A�l�Ԃ̕s���R�x�������m��Ă���B���̔F�m�̒��őS��������u���v�́A�K���Ȃ�u���v�ƌ����邾�낤���B �@�Ƃ�����A�i�c�m�q���u�₳�����Ŏ�v�̒��Ɍ����̂́A���X�̎��R�ƒ��X�̕s���R�̒��ɐ����镽�ϓI���{�l�́A���̑f�p�Ȑl�Ԑ��ł���B�i�c�ɂƂ��āu�₳�����Ŏ�v�̔����Ƃ́A�ǂ̂悤�ȑ̐��̉��ł��ς��Ȃ��A�l�Ԃ̎������́u�P���v���u�����I���̍����v�̔����ł���ƌ����Ă����B �@�R��ɁA���̂悤�Ȕ����������Ɍ��o�����ɂȂ��t�����A��l�̏������m�̂��̕����́A�w�Lj��|�I�ł���B�ޏ��͉ߋ��ɉ������A���������Ă����̂��ɂ��āA���̕����ɂ���ĉʂ����Č���邩�A���ɂ͕���Ȃ��B �@�ޏ��̂��̔������A�����ɁA�u�⍓�Ȃ鋤�Y��`�ҁv�̔����Ɍq�������̂��ǂ����ɂ��Ă��A���ɂ͕���Ȃ��B�������ޏ��̒��ŁA�u���Y��`�҂͂₳�����v�Ƃ������肪�A�u�₳�����l�Ԃ������Y��`�҂ł���v�Ƃ�������ɝz�i���j��ւ����Ƃ��Ă��A�����猾�킹��A�����ɂǂꂾ���́u�w�K�v�̔}����������m��Ă���A�Ƃ������ɓ˂��������Ȃ������́u�w�K�v�̂悤�ɂ����v���Ȃ��̂��B �i��11�j1985�N�ĉp����B�e���[��M���A���ēɂ��A�ߖ����̊Ǘ��Љ�h�����u���b�N��R���f�B�B �i��12�j20���I�O���Ɋ����C�M���X�̍�ƁB�u�����_��v�A�u�P�X�W�S�v�Ƃ�����\��ŁA�Љ��`�I�t�@�V�Y���̊댯�����s�����h���A�����Љ�̗\���I���w�Ƃ��ꂽ�B �@����O�ɂ���A�A�_�N���ɂ���A��ΐߎq�i���l���ۋ����j�ɂ���A�ނ�̎�L��ǂތ���A�ނ炪���Ȃ��Ƃ��A��ϓI�ɂ́A�u�₳�����̒B�l�v��ڎw���Ă����炵���Ƃ������Ƃ��`����Ă���͎̂����ł���B���ɁA���̕ӂ�����y���Ă݂悤�B �@�����ɁA��ΐߎq�̓��L����A���̈ꕔ�����p����B �@�f�ГI�Ȕ��������A�ޏ��̐S��E���_�C���N�g�ɓ`����Ă���̂ŎQ�l�ɂȂ邾�낤�B�ނ炪�u�����Ȃ�E�l�ҏW�c�v�ł���ƌ��ߕt���邱�Ƃ̓��������Ɠ����ɁA���f�B�A����^����ꂽ�A�ʂ��Ղ́u������v�ɂ���Ċ����Ă��܂����Ƃ̕|����Ɋ�����ɈႢ�Ȃ��B �@�u���ɂ͂ǂ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��A�����ł��悤�Ƃ����̂��A���̌��R�Ƃ����u�⊴�̒��ŁA�Ȃ����͌����Ă��܂��A���̒��ɉf�������A�Ó]����B��̎��ɏł����簐i���鋶�C������O�ƁA����Ɋ��Y�����̉ԥ���v �@�u�e�����A���C�����M�����A����̂��߂̐��A�����Ă悢�̂��H�����\�Ƃ�ł��Ȃ��A����Ȍ��t���ǂ����ēf����悤�Ƃ����̂��A�������ւ���������Ȃ��A���R�Ƃ��Ă����ɍ݂�̂����祥��v �@�u�����đł��Ђ����ꂽ�A���̈���ŁA�R�b�P�C�Ȏp�Ԃƈʒu����N�オ���ė��邪�����B���O�ɂ͎��ʂ��Ƃ���ӂ��킵���Ȃ��B�A���R���̕����͕@�����Ȃ�Ȃ��B�g���h�Ɨ����ꂽ�N���������ȁA�����Ă����ȁA���̎O�����ŁI�v �@�u���������ׂ��O�����ҁ\���肢������B���̎��A���͉��������Ƃ˂ɂ��Ȃ�邾�낤�ɥ��.�����g�̏��Ղ��ʂ��������邾�낤�ɥ���v �@�u�킩���ė~�����A�킩���ĉ������B�ǓƂȉ��Z�҂�A�ǓƂȖ��z�҂�B�����E���Ȃ��ŗ~�����A���c�ɑł��̂߂��Ȃ��ŗ~�����B������������ꂽ��������������ȏ�L���Ȃ��ŗ~�����B�����ė~������ł��B�����ǂ����悤���Ȃ��v �@�u�D�������N�_�T�C�B�W�������������F���̗D�������N�_�T�C�v �@�u���ɒD��ꂽ�����Ɨ����ꂽ�����A���߂ĉ����܂��A�����Ă͂Ȃ�Ȃ��v �@�u�ۂ����ł��A������͗���B���ꂪ�K���ƂȂ邩�A�߂��݂��ĂԂ��A��w�̐؎�����^���邩�A�S�Ă𗬂������ƂȂ邩�A����͍��A���͒m��Ȃ��B�����A�f���ł��肽���A���R�ł��肽���v �@
�@�ȏ�̑�ΐߎq�̓��L�̃^�C�g���́A�u�D���������������v�B �@���݂ɁA�ʗ��Њ��̂��̒����̃T�u�^�C�g���́A�u�A���ԌR�������m�̓��L�v�B
�@��L�Ɉ��p�������͂́A�P�X�U�W�N�P�Q���P�R������V�P�N�S���S���ɂ����đ�ΐߎq���������A���̓��L�̓����̒f�Ђł���B �@���������āA�ɂ߂Ēt�قȕ\���̃I���p���[�h�����A����������̂ɂƌ����ׂ����A�Z�I�ɂ���͂����Ȃ����̓�������A�ޏ��̎��䂪�̌������ω��ɕK���ɑΉ����Ă������Ƃ��������܂��A���ړI�ɓ`����Ă��āA�ƂĂ��ɁX��������ł���B �@�ޏ��ɂƂ��Ċv���Ƃł��葱���邱�Ƃ́A���`�̊ѓO�̂��߂̊m�M�I�e�����X������e���邱�Ƃ��Ӗ����Ă������A����ł��Ȃ��A�������e����Ȃ����ǂ�������F�m���Ă��܂��Ƃ��A�p���āA�s�K�v�Ȃ܂ł̎��s�ӎ�������ʼn��������Ă��܂��̂��낤�B �@���X�Ǝς����i�����j�������ŁA�ǂ����Ă����i�Ђ�j��ł��܂�����ɉ��Ƃ������̈߂�킹�āA�̐�w�����삷�邪�A��������ɎN����A�T���i���낽�j���āA����␂ނ̂��B �@�ޏ����܂��A�u���Y��`�҂͂₳�����v�Ƃ�������ɜ߂���Ă��邪�A���ꂪ�e������������������ւɈ����Ɏg���邱�Ƃ������Ȃ������ƁA�����ė��v�z�Ƃ̋ύt�ɏ��Ȃ���ʔg���������Ă��āA�ޏ��̎���͂�����[���ɏ�������Ă��Ȃ��̂ł���B �@���炭�A���䂪����������Ȃ��܂܁A��ΐߎq�͒�����ʂ����Ă����B
�@
�@��ɂ͏����̂��߂̏[���Ȏ��Ԃ��^�����邱�ƂȂ��A�M���M���̏��Łu����v������鈳�|���Ɉ��������Ă������B�������A���̓����̕n���𒇊ԂɌ���������Ă͂Ȃ�Ȃ��B���g��̐��E���猈�ʂ���ɂ́A����Ȃ�̊o�傪����Ƃ����܂݂�����ɐg�̉����Ă����ߒ�����Ƃ��A�����ɒN�����Ă���������A�u�C��Ŋ撣�艮�v�́u�����v���Ɓv���a������̂ł���B �@��ΐߎq�Ƃ�������́A���ꂪ�����ǂ����Ŋ�������Ă����ł��낤�A�����₷�鍢��Ȗ����ɂ₪�ěj�i�Ȃԁj���A���ݍӂ���Ă����B�ޏ����~�����u�D�����v�́A�u���Y��`���v�Ƃ����Ս��ȕ��ꂪ�J�����ł̐��E�̒��Œ��݂�ɂ���A��̂���Ă����̂��B �@�ޏ��́A�u���Y���v�Ƃ��Ă̎����P��̊�ʂ�����A�M�S�ȏl���҂������Č������B���̉ʂĂɁA�ޏ����g�̔ϖ�̉ߋ����u�l���@��v�̑O�Ɉ�������o���ꂽ����A�����I�ȍ����̘A�˂����X�ɗ��тāA���������ꂵ�҂ƂȂ��Ă����̂ł���B �@��ΐߎq�̎��́A��̐l�ԓI��������҂݂̂Ȃ炸�A��̐l�ԓI������ߋ��Ɏ������҂����ق����^���ɂ��邱�Ƃ������Č������B �@�u���Y��`���v�Ƃ����Ս��ȕ���́A�u�v�`��u�����v�Ƃ������ɂ����āA�l�X�̈ӎ��⊴�����̂��̉ߋ��ƌ��݂̈���A���X�ɍق��Ă������߂̋т̌���ł������̂��B �@�l���Ă��݂悤�B �@���̂悤�ȍق��ɂ��Ώۂ���A�ʂ����Ď��R�ł��蓾��҂��A��̂ǂ��ɂ���Ƃ����̂��B���̍ق��ɂ���Đ��҂��ʂ����҂ȂǁA���_�I�ɂ͂ǂ��ɂ����Ȃ��B��������āA�����F�߂�Ȃ�A�ق��ꂵ�҂̕M���ɂ́A�u�G�O���S�v�̉ߋ������X�P�v���w������đR��ׂ��Ȃ̂ł���B �@��ΐߎq�̎��́A���|�I�Ȃ܂łɗ��s�s�Ȏ��ł������B
�@
�@�ޏ��͂��̗��s�s���ɍR�c���邪�A���ꂪ����ɎU���Ă������Ƃ�m�����Ƃ��A��]�I�ȋ��̒��ɒ���ł����B�M���M���܂łɎ������i�����j�����ޏ��̎���́A���ɕ��ꋎ���Ă������̂��B �@����́A��̐t�̎��ł͂Ȃ��B�l�Ԃ́A�l�ԂƂ��Ă̊�{���x����A����Ȃ����Ă͐������Ȃ��A�݊����������Ȃ������̑S�������̎��Ȃ̂ł���B �@�ޏ��̎���͐��Ƀe�����̉�H�ɝ��ߕ߂��Ă��܂������A���̑z���͂̎˒��ɂ͂Ȃ��A�u�n���ƈ����ɚb�����O�̈������v���ߑ�����Ă����B�u�S�l�ނ̉���v�Ƃ����Ô��ȕ��ꂪ�a���ɏ�̉��y�̂����ɁA�u�₳�����̒B�l�v�ւ̒��������ꂽ�ɈႢ�Ȃ��B �@����������n�߁A���Ȃ��Ȃ���҂����𑨂����啨��̑厞�㐫�́A���ɋ����ė���Ղ����������Ă����B���Ȃ��Ƃ��A��������ċz���q���ł����Љ�ɂ́A�ނ�̏}���I�ȃe�����ɂ���ċ~�ς����ׂ��u���O�̈������v�ȂǁA�����w�ǐ����c����Ă��Ȃ������̂��B �@���x�ɐ��n����������O����Љ�̏o���́A�����̈ӌ���\�͂ɂ���ċ�����̎v�z���A���炩�ɒe���o�����_�������������ł����̂ł���B�A���ԌR�����̔ߌ��̍��q�ɂ���̂́A���̂悤�ȑ�O�����̋��x�Ȑ������ł���B���̎Љ�ł́A�ނ�͍ŏ����狥���ȃe�����X�g�ȊO�ł͂Ȃ������̂��B �@��ΐߎq���ǂ�قǂ̒�����ʂ������ƁA�ޏ��̓��F�[����U�X�g���b�`�i�P�X���I����Q�O���I�ɂ����Ċ������V�A�̏����v���Ɓj�ɂ͂Ȃ�Ȃ����A���[�U����N�Z���u���N�i��13�j�ɂ��������Ȃ��̂ł���B���[�U�����̙ˑ�ȏ��Ȃ̒��ŕ\�o�����q���[�}�j�Y�����A��ΐߎq�͂��͂�ړ����邱�Ƃ����ł��Ȃ��̂��B �@�ނ炪�ǂ���ϓI�Ɍ��߂��悤�ƁA�������̎Љ�ł́A�u�₳�����̒B�l�v��K�v�Ƃ��Ȃ��悤�Ȓ������`������Ă���B���̑�����b�����i���j�����낵�A���ꂪ�s���ƂȂ�A�o���҂�ߕ߂���܂łɔ��B���������`�������A�A���P�[���Ƃ�A����N�܂ŁA�X���ȏ�̐l���u�����v�����F����悤�ȑ�O�Љ�ɂ����āA�l���E���Ă܂ŒB�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������I�e�[�}�̑��݉��l�Ȃǂ́A�S�����e���ׂ����Ȃ������̂ł���B �@�u�₳�����̒B�l�v��ڎw���Ȃ�A�ǂ������O�ɒE�o������A�v����������Ă���B���̑���A���̖̑ʂ����͏����Ă����ȁA�ȂǂƂ��������̃��b�Z�[�W�����̍��̕����ɂ����Ղ�ƒ���t���Ă��āA��O�̎����ɂ͂U�O�N���ۂ̂悤�ȁA�u�J���̐t�v�ւ̃V���p�V�[�������c����Ă��Ȃ������̂��B �@���x�����Ƃ������퐫�̃J�[�j�o���́A���̍��̕��y��ς��A���̍��̐l�X�̐�����ς��A���̍��̐l�X�������ė����Ă����f�p�Ȓ�����ς��Ă������B����͐l�X�̊�����ς��A������ς��A������a����̃V�X�e����ς��Ă������̂ł���B �@�啨��̑厞�㐫���v��t���e�����X�g�������A���̂��Ƃ�m��Ȃ��B �@�ނ�͎���ɒu������ɂ��ꂽ���Ƃ�m��Ȃ��B�l�X�̌��݂�m��Ȃ�����A�l�X�̖�����m��Ȃ��B�l�X�̐S��m��Ȃ�����A�l�X�̗~�]��m��Ȃ����A���̗~�]�̍��܂̂��܂�m��Ȃ��B���z���́u�P���Ȃ��v�i��14�j�̃C���p�N�g��m��Ȃ����A�n�C�Z�C�R�[�i��15�j�ւ̔M����m��Ȃ��B �@�l�X�̐S��m��Ȃ��e�����X�g�́A�Ƃ��Ƃ����Ԃ̐S�܂ł������Ȃ��Ȃ��Ă����̂ł���B�ނ�͂����A�u�₳�����e�����X�g�v�ł���Ȃ��Ȃ����B�l�X��ے肵�A���Ԃ�ے肵���e�����X�g�́A�Ō�ɂ͎�������ے肵�Ă����̂��B���ꂪ�A�X�P�v�̎��E�ł������B �@�ނ�͐���s���A�u�\�Ԃɖ���������v���ӂ����Ƃ��āA����I���������߂鎞��̒ҕ��ɓj��ꂽ�̂��B������������������܂�Ȃ��B���ꂾ���Ȃ̂ł���B �@���݂ɁA������������i��16�j�ɂ��e�����̊g�U�́A�A���ԌR�����Ŕے肳�ꂽ���̂ɌŎ����邵�������Ă����Ȃ���O���A�X���ɂ������Č������Ō�̒���̃|�[�Y�ł���B �@�ނ�́u�����v�ł��邱�Ƃ���������ł��̂ĂāA�w�ǁA��`���������œ��������̂悤�ȓm��i������j�����N���Č������B��O�Љ�̔����́A���t�̒ʂ��ʔƐl��菓��i����ɂイ�j�ɂ���Ĕ�����A���s�s�ɂ܂����f�ȊO�̉����̂ł��Ȃ������B�]���āA����͒ʂ薂�I�Ȏ�������������镶���̂����ɏI�������̂ł���B
�@
�@���̒��́A��������ς���Ă��܂����̂��B �@����́A�X�P�v��i�c�m�q�͂��납�A���͂�A��l�̑�ΐߎq��������߂邱�Ƃ͂Ȃ��B�����ɑ���S�Ȃǂ́A�A�N�V�����f��̉��y�����\�������������Ŋ����������ƂɂȂ�A������C������߂���v���ȂǍX�X�Ȃ��B�܂��čٔ����t�H���[���闝�R�Ȃǂ͑S���Ȃ��A�i�c�����̎��Y�����̕�ɐڂ��A���ʼn��낷�Ƃ������x�̔����ŎC�߂��Ă��܂��ł��낤�B �@�A���ԌR�����́A�ŏ�����ߋ��̎����Ƃ��ď�������Ă��܂����̂ł���B �@����͎����̊J�n�Ƌ��Ɋ��ɉߋ��̎����ł���A�����łǂ̂悤�ȉA�S�Ȋ������W�J���ꂽ�ɂ���A�ǂ��܂ł�����́A���݂ɋ��P�������o���ɑ���ނ̎����Ƃ͖����́A�����܂����ߋ��̎����̈�ł����Ȃ������̂��B �@�A���ԌR�����́A�������čŏ�����A�����Ƃ��v�z�Ƃ����������̎����Ƃ͖����̉����Ƃ��āA���x��O����Љ��i�v�ɓj���Ă��܂����̂ł���B�@
�@ �i��13�j�h�C�c�v���̏ے��I���݁B�|�[�����h���܂�̃��_���l�ŁA�h�C�c�ڏZ��́u�X�p���^�N�X�c�v�������A�₪�đg�D�̓h�C�c���Y�}�ɔ��W�I�����B1919�N�ɕ����I�N���w�����邪�A�J�[������[�v�N�l�q�g�Ƌ��ɋs�E�����B �i��14�j�g�s��ł͎��E�����҂������Ă���@���������V���̕Ћ��ɏ����Ă����@�����ǂ����͍����̉J�@�@�P���Ȃ��@�s���Ȃ�����@�@�N�Ɉ����ɍs���Ȃ�����@�@�N�̊X�ɍs���Ȃ�����@�J�ɂʂꥥ��h�Ƃ����̎��ŗL���ȃt�H�[�N�\���O�B�����Љ�����A�l�̖���D�悷��v�����̂��Ă���B �i��15�j1970�N�㔼�Ɋ����A�A�C�h���I�ȋ����n�B�������ɂ��u����n�C�Z�C�R�[�v�Ƃ����q�b�g�Ȃł��L���B �i��16�j�����ɂ́A�u���A�W�A������������v�B1970�N�㔼�ɁA�O�H�d�H�r�����j������Ƃ���A�����A�u�A����Ɣ��j�����v���N�����A���{�Љ��k���������B �T�D�����ɝ��ߕ߂�ꂽ�j�́u���ȑ����v �@ �@�e�̍Ō�ɁA�u�A���ԌR�v�Ƃ����ł����グ���j�ɂ��ẴG�s�\�[�h���A���łɋL���Ă����B�i�c�m�q�Ƌ��ɁA���Ԃ��W�����Ă��邾�낤���`�R���̓��A�ɓ��ݓ����čs�����X�P�v�́A�����ɎU�������A�W�g�̌�����ē��h����B���F�Ζ��g�����V�[�o�[�Ȃǂ�����o����Ă��āA�R�c���̎��̂��������ߗނ��A���̂܂܊�A�ɂ܂Ƃ߂Ēu����Ă����B�i���݂ɁA���̈ߗނ����S�ȓ��u�l���̑S�e���𖾂���茜��ƂȂ�j �@���̂Ƃ��A�X�͏��Ƀw���R�v�^�[�̉����A���̎R���Ɍx�������̓��Â��@�m���āA�ނ̓��h�̓s�[�N�ɒB����B�ނ͖T��̉i�c�ɐ�]�I�Ȓ�Ă�����B
�@
�@�u�ʖڂ��B�r�Ő��키�����Ȃ��v
�@
�@�i�c�͂��������āA�i�C�t����Ɏ������B��l�͊�A�ɐ���ŁA�ނ炪������������ׂ������҂��Ă���B �@���������́A�i�c�{�l�Ɍ���Ă��炨���B
�@
�@�u���̓R�[�g���ʂ��i�C�t����Ɏ����A���A����o�ĐX���ƈꏏ�Ɋ�A�ɂ��Ⴊ�B���̟r�Ő�͂܂��ɖ��d�ȓˌ��ł��薳�Ӗ��Ȃ��̂ł������B�������A�������邱�Ƃ��X�����������Ă����\�����A�U�����������̂ł���B �@���͂����œ������Ƃ��e�ɂ��r�Ő�Ɍ��������ƂɂȂ�A����������������ł������ɓ��������ƂɂȂ�Ǝv�����B������A�ߑs�ȋC�����������������Ȃ������B���͂��̕�͂�˔j���邱�Ƃ�ڎw���A�Ƃ������S�͂şr�Ő�����Ƃ����C���������ɂȂ����B �@���̎��A�X�����A�w���������Ă݂�Ȃɉ�Ȃ��ȁx�Ƃ������B �@���́A�w�������Ă�̂�B�Ƃɂ����r�Ő��S�͂œ��������Ȃ��ł���x�Ƃ������B �@�X���͂��Ȃ��������A���̎��A���͈�̐X���͋��Y��`�����ǂ��v���Ă����̂��낤���Ǝv�����B�w���������Ă݂�Ȃɉ�Ȃ��ȁx�Ƃ��������́A�s�k��`�ȊO�̂Ȃɂ��̂ł��Ȃ���������ł���B �@���炭����ƁA�X���́A�w�ǂ��炪��ɏo�čs�����x�Ƃ������B �@���͐X���ɁA�w��ɏo�čs���āx�Ƃ������B �@�X���͈�u�Ƃ܂ǂ����\����������A���̂��Ƃ��Ȃ������B �@���������X���̎�C�̔�������ɓI�ȑԓx�ɒ��ʂ��āA���͖\�͓I�����v���̐擪�ɗ����Ă�������܂ł̐X���Ƃ͕ʐl�̂悤�Ɏv�����v�i�i�c�m�q���E�u�\�Z�̕�W�E���v�ʗ��Њ��^�M�Ғi���\���j
�@
�@
�@���̒���ɓ�l�͌x�@�ɕߔ�����A�l�������Ȃǂ̍ō��ӔC�҂Ƃ��āu�ق��ꂵ�ҁv�ƂȂ邪�A���m�̂悤�ɁA�X�P�v�͐V�N���}�������̓��ɍ������E�𐋂����̂ł���B�@�Ƃ�����A�ȏ�̉i�c�̃��A���ȕ`�ʂ̒��ɁA�������́A�X�P�v�Ƃ����j�̐��g�̐l�Ԑ��̈�[���_�Ԍ��邱�Ƃ��ł��邾�낤�B �@�����̖��߈ꉺ�œ������Ƃ��ł��钇�Ԃ����ƕʂ�A�T��ɂ́A���R�ȗ��s�������ɂ��Ă����C��ȁu�����v���Ɓv�������Ȃ��B�R���ł́A�ޏ����܂߂��w�ǑS�Ă̓��u�����̑O�ŁA�u�|�S�̔@�����Y��`�ҁv�Ƃ����X�[�p�[�}���������Ă��āA����͊T�ː������Ă������Ɍ������B �@���������Ԃ́A���u�E���̘A���Ƃ����A���炭�A�{�l���z�����ɂ��Ȃ������͂��̏ݏo���Ă��܂����B �@���炪�ϋɓI�Ɋ֗^�������̕����̒��ɂ����āA�ނ͂܂��܂��u�|�S�̔@�����Y��`�ҁv�Ƃ����A���g���y���ɉz������������������Č������B���̐S���I�����̐�����W�J���A���܂킵���l���̘A���Ɍ����Ȃ܂łɃI�[�o�[����b�v�����̂��B �@�ނ̐l�i���A�u���Y��`�ҁv�́u�|�S���v�i�⍓���j�̔Z�x�𑝂��Ă����x�ɁA���u�̒�����l�g�䋟�i�ЂƂ݂������j�ƂȂ�҂�������Ă����̂ł���B���̂悤�Ȏ�������݂������l�i�����܂�ɊϔO�I�Ȏv�z��ˏo�����������W�c�̍ō��w���҂ɂȂ�A���炭�A�s���ł������ɈႢ�Ȃ��Ǝv�킹��قǂ́A�w�Ǘ\�ꂽ�ߌ��I���A�����̏�B�̓~�̕��n�̋�Ԃ̑����ɕ�����Ă��܂����̂��B �@��̓��g����z���������������Ƃ������Ƃ́A�����l���̒��ł����N���蓾��Ƃ������Ƃł���B�������A��������������邱�Ƃ͖ő��ɂȂ��B�l�Ԃ̔\�͂́A���g��ȏ�̖�����������������قǁA���X���̌p���͂��������Ȃ��̂��B���g��ȏ�̖���������������Ƃ������Ƃ́A����̃��X�N�����߂邾���ŁA�����K�v�ȏ�ɋْ������邱�ƂɂȂ�B�ْ��̓X�g���X�����߂邾�����B �@�Z���G�i�J�i�_�̐����w�ҁj�̃X�g���X�w���ɂ��ƁA�X�g���X�Ƃ́A�u�����w�I�̌n���ɔ����I�ɂ����炳�ꂽ�A�S�Ă̕ω��Ɋ�Â�����nj�̌��݉���ԁv�ł���A����ɂ́A���[�X�g���X�i�ǂ��X�g���X�j�ƃf�B�X�g���X�i�����X�g���X�j������B �@�l�Ԃ����ɕ��ʂɓK�����ʂ����Ă���Ƃ��A���R�A�����ɂ̓��[�X�g���X�������Ă���B�K�x�ȃX�g���X�͓K���ɕs���Ȃ̂��B �@�f�B�X�g���X�́A�A���f�X�R���ɑ���i�u�A���f�X�̐��`�v�^��17�j���Ă��܂��Ƃ��A��_��k�Ђɑ����Ƃ��A�E�l�S�Ƀi�C�t��˂�������Ƃ��A�A�E�V�����B�b�c�Ɏ�����Ƃ������悤�ȃP�[�X�Ő�����X�g���X�ŁA�����A������@�\�s�S�����Ă��܂��B������̃X�g���X������̗ՊE�_���z������A�{���̎���̐���ȋ@�\�Ɏx��𗈂����̂ɕς��Ȃ��̂ł���B �@�l�Ԃ����g��ȏ�̖��������������邱�Ƃɖ�����������̂́A����ɗՊE�_���z����قǂ̃X�g���X���ݐς���邱�Ƃɂ���āA��������̖����A�����A���g��ȏ�̐l�Ԃ������邱�Ƃ������鎩��ƁA���̂��Ƃɂ���Đ�����X�g���X�𒆘a�����邽�߂ɁA���g��̐l�Ԃ������邱�Ƃ�v�����鎩��Ƃ̖����𑣐i���A���̖�����������Ԃɂ����Ă��܂����炾�B�l�Ԃ́A������������������Đ����Ă�����قnj��łł͂Ȃ��̂ł���B
�@ �i��17�j1972�N�A���O�r�[�I�肽�����悹���`���s�����q�@���A���f�X�̎R���ő���A�����c�邽�߂ɂ�ނȂ��l���H����]�V�Ȃ����ꂽ�Ռ��I�Ȏ�����`�����A�u���W���̃h�L�������^���[�f��B�w�����Ă����x�i�t�����N�E�}�[�V�����ēj�Ƃ����A�����J�f����b��ɂȂ����B �@
�@�X�P�v�������������u�|�S�̋��Y��`�ҁv�́A�����܂ł��ނ��A�u�����ł���ׂ��͂��̃X�[�p�[�}���v���Ȃ����Č��������\�̃q�[���[�ł������B �@�R��ɁA���̃q�[���[�ɂ�鋕�\�̕\�o���A�ނ����āA�u����̒鉤�v�̉��y�����������߂�قǂ̂��̂ł��������A�����^�킵�������ł���B�X�P�v�̎���ɁA�u����̒鉤�v�̉��y���ׂ�����ƒ���t���Ă��Ȃ������Ƃ͓���v���Ȃ����A���ɂ́A�ނ̎��䂪���т�����y�̃V�����[�ł�������A�����A���g��ȏ�̐l�Ԃ����������˂Ȃ�Ȃ������ӎ������ݏo�����A�ˑ�ȃX�g���X�V�����[�ł���悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��̂��B �@���䂪�������߂Ȃ��قǂ̃X�g���X�̓I�[�o�[�t���[������Ȃ��B�u�|�S�Ȃ鋤�Y��`�ҁv��������ɂ́A�l���������̃p�t�H�[�}���X�̘A�˂��v�������ɈႢ�Ȃ��B�u�s�k���v�����z���Ă����ӎu���O�������邱�ƂŁA����́u�|�S���v��������B�u�|�S���v�̔Z�x���A�u�⍓���v�ɂ���đ�ق���Ă��܂��̂ł���B���́u�⍓���v�����A���́A�I�[�o�[�t���[���ꂽ�X�g���X�̓f�b���Ȃ̂ł���B �@�]���āA�X�P�v�����g��ȏ�̐l�Ԃ������낤�Ƃ������قǁA�I�[�o�[�t���[�����X�g���X���u�⍓���v�Ƃ��Đg�̉�����邱�ƂɂȂ�B�u�|�S�Ȃ鋤�Y��`�ҁv�ւ̓��Ƃ������g��ȏ�̕���̉��\���A���̕��ꂪ�������{���I�ȋ��\���̌̂ɁA�X�ɂ��̋��\�����ϔO�̔��e�ɗ��߂��ɁA�u����ׂ��g�́v�Ƃ��ĉ����o���Ă���Ƃ��A�����ɋɂ߂Ċ댯�ȓ|������������̂��B
�@
�@�����A�u����ׂ��g�́v�ł��炸�A�u����ׂ��g�́v�ł��낤�Ƃ��Ȃ��ƈ�ەt����ꂽ�S�Ă̐g�́A�A���A�u����ׂ��g�́v�łȂ����߂ɁA�u����ׂ��g�́v��~����g�̂𐬌����ɉ����������p���������Ȃ��A�^�ɓ��ʓI�Ȑg�́A�Ⴆ�A��ΐߎq�̂悤�Ȑg�̂��A�u�����v�̖��ɂ���ė��ے肳��Ă��܂��Ƃ����ݏo���̂ł���B �@�u����ׂ��g�́v�̉��\���A�u����ׂ��g�́v�ł���Ȃ��g�̂����ނƂ��A�����ŋ��܂�邱�Ƃ̂Ȃ��g�̂Ƃ́A�u����ׂ��g�́v�ȊO�ł͂Ȃ��B�����ł́u����ׂ��g�́v�̌�������g�̂��܂��A�u����ׂ��g�́v�łȂ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B�����A�u�����v���u�_�v���ق��Ȃ��̂��B �@�ł́A�u����ׂ��g�́v�Ƃ��Ắu�_�v�̑��݂�O��ɂ��邱�ƂŐ��������邱�̏��ɂ����āA���́u�_�v��S���g�̂́A��̂ǂ̂悤�Ȑg�̂Ȃ̂��B �@���ꂪ�A�u�|�S�Ȃ鋤�Y��`�ҁv�������邱�Ƃ�v�����ꂽ�A�X�P�v�Ƃ����ŗL�Ȃ�g�̂ł���B�X�P�v�Ƃ����g�̂́A�u����ׂ��g�́v�Ƃ��āA���̑S�Ắu����ׂ��g�́v��ڎw���A�u����ׂ��g�́v�ł͂Ȃ��g�̂𑊑Ή�����A�B��̐�ΓI�Ȑg�̂ƂȂ�B���Ȃ��Ƃ��A����ȊO�ɂ͏l�������������郍�S�X�͂Ȃ��̂ł���B�u����ׂ��g�́v�ł͂Ȃ��g�̂��A���́u����ׂ��g�́v�ł͂Ȃ��g�̂�ے肷�邱�Ƃ͗��_�I�ɍ���ł��邩�炾�B
�@
�@�������āA�X�P�v�Ƃ����g�̂́A�u����ׂ��g�́v�̑̌��҂�������˂Ȃ�Ȃ��Ƃ����\���˂��Ă����B
�@
�@���ꂪ�������āA�u����̒鉤�v���u�X�P�v�̉��y�v�Ƃ������ɁA�����Ɍ��ߕt���邱�Ƃ�����ɂ����鍪��������B���͂���قǒP���Ȃ��̂ł͂Ȃ��̂ł���B �@�X�P�v�̒���́A�܂��u����ׂ��g�́v�����\����Ƃ�������̒��ɒ[���A�����ɖ��v���ĉʂĂ��ƌ����ׂ����B�ǂ����A���̒��̂ɖ�肪�������̂��B�u�o��v�Ɓu�_�́v��s���������j�̎���́A���̉ߌ��ȁA���܂�ɉߌ��Ȓ��A���̉A���ɂ܂鎖���̍��q�ɂ������Ƃ͌����Ȃ����낤���B
�@
�@���x��O����Љ�̂ƂΌ��ŁA�R�x�x�[�X�Ɉˋ����ğr�Ő�����ԂƂ����A���悻�M����|���i���̏ꍇ�A�Љ�I�K�͂���O�ꂽ�s�����������Ɓj����ɂ́A���������Ŏx����ɑ�������M�I�ȕ���ƁA���̕���ɏ}�������鎝���I�ȃp�g�X���s���ł������B �@�X�P�v�Ƃ����g�̂̓����ɁA�����̋��x�Ȕ\�͂�������Ă������ǂ����̌����A���Ȃ��Ƃ��A�R�x�x�[�X�ł̓M���M���̏��ʼn������Ă����B�X�P�v�Ƃ����\�͂̌���������ꂽ���Ƃ́A�X�P�v�Ƃ����g�̂��A�R�x�x�[�X�ŁA�u����ׂ��g�́v�����\�����Ă������Ƃ��Ӗ����邾�낤�B �@�ނ̔\�͂̌��̉���́A�����ɁA�u����̋��|�v���u�Y���x�[�X�̈Łv����̉���̉\�����J����Ȃ����Ƃ��Ӗ����Ă����̂ł���B���}�Ȕ\�͂����������Ȃ���l�̒j�́A���̉ߌ��Ȓ��A�P�Ȃ���s�����܂킵���S���ɓh��ւ��Ă��܂����̂��B �@�������A���̃h���}�]���́A���炭�A�j�̖{�ӂł͂Ȃ������悤�Ɏv����B�j�͂����A�����邱�Ƃ��w�Ǎ���Ȗ������A�ꕪ�̗V�ѐS�������Ȃ��ŁA�j�Ȃ�ɐ^���ɁA���A�O��I�ɉ����낤�Ɗo�債�������Ȃ̂������B �@�j�̂��̉ߌ��Ȓ����ۏ����R�x�x�[�X�Ƃ́A�j�ɂƂ��Ė����ł������̂��B �@�j�͂��̖����ɏ��ߐs������A�|�M���ꂽ�B���̖����́A���}�Ȕ\�͂��������Ȃ��j�ɐ��䂳��A�x�z�����悤�ȉF���ł͂Ȃ������̂ł���B�j���x�z�����̂́A�j�ɂ���Ĕ���ꂵ�҂����̓��݂̂̂ł����āA����ȊO�ł͂Ȃ��B�j���܂��A���̊��܂킵���F���ɔ����Ă����Ƃ����������悤���Ȃ��̂��B �@�j�͋��炭�A���̖����ɓ���Ȃ���Ό��͂ɂ������d�u��������A�u���̐t�͉₩���������v�Ɛ����ɉ�ڂ���A�������ۂ����N�e���ɓ]�g�𐋂����̂ł͂Ȃ����B �@�j��i�삷�����ȂǍX�X�Ȃ����A���ɂ͂��̒j���A���̂悤�Ȓ����j��̖\�����ѓO����\�͂ɂ����čۗ����ċł��邱�Ƃ�F�m���Ă��A���̐l�i���̂����l�ł���Ƃ����c�����Ƃ��Ă���e�ł����A��������ꂸ�Ɍ����A�j�̖\���̓��R�̋A���Ƃ͌����A�j��������Ă��܂������̉^���̉Ս����Ɍ��t�������݂̂ł���B �@�Ƃ�����A�ō��w���҂Ƃ��Ă̎����̔\�͂́u���v���z�����j�̏��Ƃ̌��ʐӔC�́A���܂�ɐr��ł���߂����B���ݍ���ł͂Ȃ�Ȃ������ɐN�����A�����ō��グ���A�u����̋��|�v�́u�鉤�v�Ƃ��ČN�Ղ������Ԃ̒��ŁA���̍ō��w���҂́u���u�v�ƌĂԂׂ����Ԃ̎����A��蔲���Ă��܂����̂��B �@�l�܂鏊�A�u����̋��|�v�̐��S���́A�ō��w���҂Ƃ��Ă̒j�̎���̐��S�������A�����ɔ����o���Ă��܂����̂ł���B �@�\�\�\�@�j���������͎������̓��퐢�E�ɂ����݂��Ă��āA���ꂪ���ł��������̎�X���������f�v����ƁA�Ô��ȖF����Y�킹�āA�،˂��J���đ҂��Ă���B���ꂪ�|���̂ł���B���̕|���́A�����́A�ߑ㕶���̏��n�̌��ł��邾�낤�B �@�ߑ㕶���̉��y�́A���ł����y�Ɍ��������s�𗝂����[����܂����Ă���̂��B�G�[����w�ł̐S���������t��o���������I���́A�܂��Ɏ������̎���̐Ǝコ���A���̉h���̉A�ɂ܂Ƃ��Ă��邱�Ƃ̔F�m���������ɔ�����̂������B���̂��Ƃ������ł��F�m�ł��邩��A���͋ߑ㕶���ւ̈����Ȕᔻ�҂ɂȂ낤�Ƃ͂�߂�ߎv��Ȃ��̂ł���B �@�������ɁA�������̕����́A�������̋\�ԓI�Ȕᔻ�ɂ���Ă͉����̂����ς����Ȃ��悤�Ȓn�����J���Ă��܂����̂ł���B�Â����������Ղ��r�i�ȁj�ߐs������A�����ɂȂ�������ƌ����āA�M���[�M���[���������̂̓t�F�A�ł͂Ȃ����A�������ɂ�������B�N�̂����ł��Ȃ��B�����g�̉������������Ă����̂ł���B�����̖��́A�L��i�Ђ����傤�j�A�����g�̖��ł���Ƃ����O�͂Ȃ��B �@�����I�ȕ������͎~�߂āA�j�ɂ��Ă̎��̍Ō�̊������L���Ă����B �@�j�͖����̒��ŁA���ɗ��ɂȂ�Ȃ������B �@�j���Ō�܂ŗ��ɂȂ�Ȃ������Ȃ�A���炭�A���͖{�e���������Ƃ͎v��Ȃ������ł��낤�B�I�n�A�j�Ƌ��ɖ����ɂ����������A�u�\�Z�̕�W�v�Ƃ����{���㈲���Ȃ�������A���́u�A���ԌR�̈Łv�ɂ��āA�v�l�����炷���Ƃ����Ȃ����������m��Ȃ��B �@���͂��̖{��ǂݐi�߂Ă��������ɁA����ɋ����l�܂��Ă��āA�j�̓����̌����Ȃ����i�̒��ɁA���Ƃ�����ϖ�̂悤�Ȃ��̂�忁i�����߁j���Ă���̂�������ꂽ�̂ł���B���̒j�́A�����̔\�͂ł͂ǂ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��悤�Ȗ����̎���Ɉ��������ē����Ă���A�Ƃ����v�����ɐɓ`����Ă��āA���ꂪ�ߕߌ��̏X�Ԃ�ǂ݉��������ɂȂ��Ă����B �@���ɂ́A���̒j�́u��C�Ȕ�������ɓI�ȑԓx�v�ɁA���̈�a�����o���Ȃ��B�j�͑ߕ߂Ɏ��鍓�i�ނ��j�����I�ȏ��ŁA��u�A���ʂ�E���̂ĂāA�u�ō��w���ҁv�Ƃ��Ă̌���I�Ȗ���������i�ق��Ă��j���悤�Ƃ����̂ł���B�j�͊v�����̍Ō�̃V�[���ŁA���̎�������S�ɔ����Č������̂��B�����Ă��ꂪ�A�ߌ��Ȓ�����ʂ������j�́A�ŏ��ɂ��čŌ�́A�ԗ��X�Ȏ���̕\�o�ƂȂ����ƌ����邩�A���ɂ͕���Ȃ��B �@�����́A�j������������Ƃ��A���̊�͒j�����X�ɋ��ߑ������u����ׂ��g�́v�́A�Ќ��ɖ������A��������ɖR�����\��ɖ߂��Ă����ƌ�����̂��낤���B �@�j�͍Ō�܂ŁA�u�|�S�̔@�����Y��`�ҁv�Ƃ���������̂Ă��Ȃ������̂��B���ꂪ���߂Ă��́A�j�̎��o�̗��̋��菊�ł������̂��B���ɂ͉�������Ȃ��B�����A�l�Ԃ͎���ł����ɂ��A���^���̕����K�v�Ƃ��Ă��܂����҂��ł��邱�Ƃ����͕����Ă�����肾�B �@�j�́u�����v�Ƃ������܂�Ɍ����₷���g�̕\���ɂ���āA�u���ȑ����v���ʂ������̂��A����Ƃ��A���ꂪ�j�́u�G�O���S�v�̎��Ȋ����_�������̂��A���ƂȂ��ẮA��͑z���̌���ł����Ȃ��B���Ȃ��Ƃ��A�����ɝ��ߕ߂�ꂽ�j�́u���ȑ����v���A�u�����v�Ƃ��������₷���g�̕\���ɂ���Ċ����_�����Ɗ���ɂ́A�j�������œf�b������n�̖\���͓˂������ĉߏ肾�����ƌ����邾�낤�B
�@
�@���̉ߏ�Ȃ�\���ɑ��āA�����j�͑S�l�i�������Ĉ����鉽���̂����������Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B���̂Ƃ��j�́A���炪�|���ׂ��W�I���������͋@�ւ̈��ɕߑ�����āA����ƑS�l�i�I�ɓ������鍇���I�����̌��Ђ������L���邱�ƂȂ��A���̐�]���̋ɂ݂��A���̂悤�Ȍ����₷���g�̕\���̂����ɁA�h�����āA���āu�ō��w���ҁv�ł������҂̃M���M���������i���傤���j���Z���i�邱���j�����̂ł��낤���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �i�P�X�X�T�N�P���E�e�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �k���A�{�e�̒��ł̑S�Ă̒��߁A�{�e�̈ꕔ�ɂ��ẮA�{�e���uWord�v�ɓ]�L���Ă����ۂɁA��̕�M�������Ȃ���A�Q�O�O�V�N�P���ɋL�q�������̂ł���l �@
�y�]�e�z
�@
�@�{�e�𝦕M�i�����Ђj��A�Q�����o�����R���Q�O���ɁA�u�n���S�T���������v�����������B�����A��A�́u�I�E���^���������v�Ƃ��Đ���k�������鎖�������݉�����_�@�ƂȂ��������ƍ߂ł���B �@�����̐^�������炩�ɂ����ɂ�A�u�T�e�B�A���v�ƌĂ������Ԃ̒��ŁA�������w����ł��镨�������A���낤���Ƃ��A��������Ɏg�p�����Ƃ����������A���̍��̐l�X�͖ڂ̓�����ɂ��邱�ƂɂȂ����̂ł���B
�@
�@�����Ӗڂ����̂́A�����̋��������ꎩ�g�����A�J��u�T�e�B�A���v�Ƃ������́A����I�Ȍ��͊W�̖\�����������F�����A�x�m�R�[�̕������Z�ȍ��y�̈�p���L���Ă����Ƃ��������������B �@�������������n�Ɏ��Ȋ�������A�����܂�����Ԃ����ݏo�������͊W�̓����́A�܂������u����̋��|�v�̗l����悷����̂������̂��B���R�̔@���A�����ɂ́u����̒鉤�v���N�Ղ��A���́u�鉤�v�ɂ���Ďx�z�����ΐ��i�ւ�ρj�ȊK���\���̉��\�ɂ���āA���̏��F���̌��͊W�́A������Ȃ��A���C���R�Ƃ���\�͋@�\�̋@�\�����Ă����̂ł���B �@���̎����́A�u����̋��|�v�̍ł������܂����l�Ԃ��N���Ă��āA�K�������s���Ȍ��o�������鎖�Ԃł���Ƃ͌����Ȃ����낤�B �@����ɂ��S�炸�A�ߑ㕶���Љ�̑����ɕ��������̎��R�Ȋw�̏��݂̂��z�������A���_�����̈ٗl�Ȑ������������E���A���������͕ΐ��i�ւ�ρj�ȗl�Ԃ����݉������āA�����ɓn���Čp���͂������Ă��܂����Ƃ��������ɒ��ڂ������A��Ɏ������̂��̒����������Љ�̋��ɁA�������������ė���ʓI�ȋK�͂���E���鎖�Ԃ̏o�������悤�ɂ��āA��̉ЁX�i�܂��܂��j�����u���v������ł��܂����|���@�\�\�\�܂��ɂ����ɂ����A���̎����̖{���̕|�������݂��Ă����ƍl����̂ł���B
�@ �@�u�A���ԌR�̈Łv�Ƃ����{�e�̖`���ɁA�u�Y���x�[�X�̈Łv���`���������q�Ƃ��āA���͎O�̓_�ɒ��ڂ����B�������A�����ʼn��߂Ċm�F����B �@���̈�B�L�\�Ȃ�w���҂Ɍb�܂�Ȃ��������ƁB
�@
�@���̓�B�̒�m��ʕ����B �@���̎O�B�u���Y��`���_�v�ɏے������v�z�Ɛl�Ԋς̌����Ȗ��n���ƕΐ����B
�@
�@���̎O�̗v�����g�D�I�ɁA�\���I�ɋ�����ꂽ���E�̒��ŁA���́u����̋��|�v�̏o���̉\������葝�������ƍl���Ă���B �@�܂��Ɂu�I�E���^���������v�́u�T�e�B�A���v�����A�u����̋��|�v�ȊO�̉����̂ł��Ȃ������̂ł���B�����āA�u�T�e�B�A���v�Ƃ����J���g���c�����o�����u����̋��|�v�́A�ȏ�O�̌`�����q�����łɃ����N���邱�Ƃŗ����グ���Ă����Ƃ������Ƃ��B �@�u�T�e�B�A���v�Ƃ������̏��F���̈ł̖{���́A�x�z���ߌn���̐�Ή��ƁA�E�o�s�\�̕��n�̎��Ԃ���퉻�����Ă������ɂ���B�A���A�����ł̌��͊W�̑g�D�͊w�́A���悻��O�I�ȏ@���c�̂̏_�a���ƗZ�ʐ��Ƃ͊��S�ɐ�Ă��āA�u�n���}�Q�h���v�z�v�Ƃ�����@�ȕ���̋��L���ɂ���āA���ɍ��W�c�̍d�����ƍ��������������̂ł������B �@�܂��Ɂu���͊W�̊��v�v�𑶕����t�i���ԁj��o���A���̑g�D�̍d�������\���������A���̃J���g���c�̈ł��ї�����A���̖{���I�Ȗ\�͐���K�R�����錈��I�Ȉ��q�ł���ƌ����Ă����B
�@
�@���̂悤�Ȗ��ӎ��ɂ���āA���͎�������ɁA�u���͊W�̊��v�v�Ƒ肷�鏬�_�������グ���B����́A�u���͊W�̊��v�v�Ƃ������̂��A������̏������������Ă��܂��A�������̓��퐫�̒��ɗe�Ղɏo�����Ă��܂��Ƃ����c�������ꉻ�������̂ł���B
�@
�@�ȉ��A�{�e���t�H���[����u��_�v�Ƃ��āA������L�q���Ă��������B �i�Q�O�O�V�N�P���L�j �@ ��_�@�u���͊W�̊��v�v �@ �@�l�Ԃ̖��ōł����Ȗ��̈�́A���͊W�̖��ł���B���͊W�͂ǂ��ɂł��������A�����Ȃ����Ől�X�����Ă��邩����Ȃ̂ł���B�@���͊W�Ƃ́A�ɂ߂Ď��������������x�z�E���]�̐S���I�W�ł�����B���̊W�́A�J��Z���Ȋ���W�̒��ɂ����ē���I�ɐ�������ƌ����Ă����B
�@
�@�Ⴆ�A�ɓ��̐��E�Ő��܂ꂽ�K���W�Ɋ���̔Z�x�������Ղ�n�Z������A�^�������̂Ɏ������W��f�v���Č����ĕ������Ƃ͂Ȃ����낤�B �@�����́A�ł���I�Ȍ��͊W�ƌ����₷���R���̒��ł����A���͔Z���Ȋ���W���`�����꓾�邱�Ƃ́A��D��Z�����̈����P�O���i������R�A���j������悭����B���N�ɎQ���������m���╺�m�̒��ɂ́A�������̂��̂ɂł͂Ȃ��A�����̏�i��������P�O��тɏ}�����Ƃ�����ۂ��c�����̂����������B
�@
�@�S�����w�҂̊ݓc�G���܂�ɐG��Č��y���Ă���悤�ɁA���{�R���m�͉_�̏�̓V�c�̂��߂Ƃ������A�����A�ނ�̒����̏�i���鉺�m������t���Z�̂��߂ɓ������B�܂����m���炪�A�O���ŋ����ׂ��E�m��������ꂽ�̂��A���i����̂����Ȃ��Ƃ����������Ă������m��̕��������̑O�ŁA�X�Ԃ��������ɂ͂����Ȃ���������ł���B�܂��ɌR���̒��ɂ����h���h���̊���W���b��ł��āA�����ł̌��͊W�̔Ȏx�����A�����ɐ�����l�X���ŋ��̐�m�Ɉ�ďグ�Ă������̂ł���B
�@
�@���݂ɁA�u�����̗͊w�v�́A���̍��̃p���[�̌���̈�ł������B �@���̗͊w���W�c���ł�����A�����̕������瓊�~�̋@���D���Ă������͎̂����ł��낤�B���{�R�����͒P�R�̂Ƃ��ɂ͈ՁX�ƓG�ɕ��������Ƃ��ł����̂ɁA�u�����̗͊w�v�ɓۂ܂�Ă��܂��ƁA���̉e���͂���������邱�Ƃ͋ɂ߂č���ł������B���̗͊w�̋��S�͂̋����́A�s��ɂ���ĕ����������ꂽ�l�X�̂����Ɉ��������ێ�����A�[�X�Ɖ�������Ă��邱�Ƃ͌o���I�����ł���ƌ����Ă����B �@���������u�����̗͊w�v�̔w��Ɋ���W�ƃ����N�������͊W�����݂���Ƃ��A�����Ɋւ��l�X�̎���͈��|�I�Ɏ�������A���̏W�����̃p���[���ɐ���ꍞ��ŁA���������܂�����������N�����B���̓T�^�Ⴊ�A�u�A���ԌR�����v�Ɓu�I�E���^���������v�ł������B �@�����ł́A�l�̎���̎��ݐ����w�Ǎς������ɂ���Ă��āA�łɈ�ㅂ��ꂽ�u����̋��|�v�̒��ɁA���̊W�����Ȃ������狰�|�̑����̘A�������͖Ƃ�Ă����ł��낤�A�l�X�ɃN���X���Čq�������n���G�}���A���X�Ȃ܂łɕ`�����܂�Ă��܂����̂ł���B �@���͊W�͓���I�Ȋ���W�̒��ɂ����������₷���Ə����Ă������A���R�̔@���A���ꂪ�S�Ă̊���W�̒��ɕ��ʂɐ��܂���ł͂Ȃ��B
�@
�@�\�\�@�Ꭶ���Ă������B
�@
�@�����ɁA�͂��Ȋ���̌덷�ł��ْ������܂�A���ꂪ���܂�₷���W������Ƃ���B �@���ׂȂ��Ƃŗ��ҊԂɃg���u�����������A������������������B������ꂽ�҂��A�Ԃ����Ŋ���I�ɔ������Ă������B���݂Ɍ��ꂵ�����V����p�葱���A�����ɋC�܂������ق����ꂽ�B�悭���邱�Ƃł���B�����������Ɋ���̈���I��崁i�킾���܁j�肪�����Ȃ���A���͊���E�������āA���̂悤�Ɉ�ߓI�ȃo�g�������a�����ׂ��A���قƂ����ɏՃ]�[���ɗ��ꍞ��ł����ł��낤�B �@�����ł̋C�܂������ق́A���݂Ɋ���̑��E�����m�F�ł��āA�����ɁA����ȏ㕬���グ�Ă��������̂��Ȃ��Ƃ������o�������܂ꂽ�Ƃ��ɁA�w�ǎ��R��������Ă����ɈႢ�Ȃ��B���ق͎�ł��̋V���ƂȂ��āA��͎��Ԃ̏͂Ɉς˂���B���̂悤�ȃ��C���̗����ۏႷ��̂́A�����ɐe�a�͂��L���ɓ����Ă��邩��ɑ��Ȃ�Ȃ��̂ł���B �@���̂悤�ɁA�����������Ƃ�S�ēf���o�����犮��������Ƃ����W�ɂ́A���͊W�̌����͋H���ł���ƌ����Ă����B�n�܂肪�����ďI��肪����Ƃ����o�g���́A�����[���ɃQ�[���̐��E�Ȃ̂��B �@�R��ɁA���͊W�ɂ͂���������A�Ȃ�̎��Ȋ��������Ȃ��A����̌ݏV�����Ȃ�����A�����ɑ��E���o�����܂�悤���Ȃ��̂ł���B�W������I������A�U��̖����]�����S�������Ȃ��B�U�ߗ��Ă�҂̜��Ӑ��������\�����A�W�������I�ɊJ���������I�Ȏ��Ԃ��_�@�ɁA�W�̓G���h���X�ȑ��H�ɛƁi�͂܁j��₷���Ȃ��Ă����B �@���Ԃ̓W�J���G���h���X�ł��邱�Ƃ��~�߂邽�߂ɂ́A�W�̗D���ۗ�������悤�Ȋm�F�̎葱�������߂��悤�B�u���͂��Ȃ��ɕ����i�Ђ�Ӂj���܂��v�Ƃ����V�O�i���̑��g�����A���̎葱���ɂȂ�B��҂���̂��̃V�O�i������e���邱�ƂŁA�W�ْ̋����ꉞ�̎��E�Ɏ���Ƃ��A���͂�����u���̎��Ȋ����v�ƌĂ�ł���B���͊W�́A�������́u���̎��Ȋ����v���O��������Ȃ��̂ł���B �@�R��ɁA�u���̎��Ȋ����v�́A��̎n�܂�̏I���ł��邪�A���Ȃ�n�܂�̐V�����s�����J�����ɉ߂��Ȃ���������B���͊W�́A�ǂ��܂ł����Ă��G���h���X�̖��ς�˂��������Ȃ��̂ł���B �@�\�\�@���̗�ŁA��̓I�Ɍ��Ă������B
�@
�@������ˑR�A���q�̖\�͂��J���ꂽ�B �@�\�����Ă����Ƃ͌����A���̓��˂ȓW�J�́A��e���[���ɋ�����������̂������B��e�͓��h���A�g�k���������ł���B������\�����Ă������ƂƂ͌����A��e�����ׂ��͂��̕��e���A���e�Ƃ��Ă̖������[���ɉʂ����Ă��Ȃ����ƂɁA��e�͓�d�̏Ռ������̂��B �@���e�͌���ł͕������̗ǂ����Ƃ������A������݂��Ă���Ă���B�����������͎��i���Ƃ��Ɓj���q�ϓI�߂��āA���Ԃ̊j�S�ɔ��邱�Ƃ���A��������������悤�Ȃ̂��B���e�͑��q�̖\�͂����]���āA�����Ɍ������ė���̂��ǂ����ŋ���Ă���悤�Ȃ̂ł���B �@��e�͋}���ɌǗ�����[�߂Ă������B���e�Ɠ��l�ɁA���q�̖\�͂�{�C�ŋ���Ă���B�ŏ��͂����ł��Ȃ������B�����ނ����A�R����ɋy��ŁA������ŝ��i���傤���Ⴍ�j����g�̂��A���������ēM��������l���q�̃C���[�W�Ǝ���ɏd�Ȃ�Ȃ��Ȃ��Ă��āA������́A�����̈ӎu�ɂ���Ă͐��䂵���Ȃ��\�̓}�V�[���ȊO�ł͂Ȃ��Ȃ����B
�@
�@���́A�����Ȃ��Ă��܂����̂��ɂ��āA��e�͂��������I�ɉ��߂���]�T�����ĂȂ��Ȃ��Ă��܂��Ă���B����ł��A�����̑��q�ւ̓M���ƁA���q�̑Θb�̌���I�Ȍ��@�́A���q�̖��s���ɖ������Ă���Ƃ��������͗e�Ղɂł����B �@���������ƂȂ��Ă͂����x���B�������ߓ�ߌ낪�����ɂ���B�ł��A�����x���B���q�̖\�͂́A�������ɏd�ʊ������߂Ă����B�����ɁA�̂��ė����������ė��Ȃ����e�ɂ܂ŁA���q�̖\�͂��g�債�Ă����͎̂��Ԃ̖��ɂȂ����B
�@
�@�ȏ�A���̈ؕ|���ׂ����z��@�̃C���[�W�������ł͐[���A��]�I�Ȃ܂łɈÂ��B
�@
�@��Ƒ��q�̓M����������͏��Ȃ��Ȃ����A�K�������A���̑S�Ă���g�̓I�\�͂����܂���ł͂Ȃ��B�������h���X�e�B�b�N�E�o�C�I�����X�i�c�u���ƒ���\�́j�̎���̑����ɁA�M���Ƃ�������Ƃ��������Q��������͔̂ۂ߂Ȃ��ł��낤�B �@���̔w�i�͂����ł͖��Ȃ����A�d�v�Ȃ̂́A���q�̖\�͂̏o�����A���炩�Ȍ��͊W�̔����Ƃ������ɔc�����ׂ��ł���Ƃ������Ƃ��B��q�̓M���̍\�}�����͊W�ƊŘ�i�݂ȁj���ׂ����ۂ��ɂ��Ă͕���鏊�����A�������̂悤�ɔc�������Ȃ�A�����ł̂c�u�͌��͊W�̋t�]�Ƃ������ƂɂȂ�B
�@
�@���j�̋����鏊�ł́A���͊W�̋t�]�Ƃ̓N�[�f�^�[��v���ɂ�鐭�����ȊO�ł͂Ȃ��A���̌��I�ȃC���[�W�ɂ��̖\�͂��Ȃ����Ă݂�ƁA�ɂ߂ċ����[���l�@���\�ƂȂ邾�낤�B �@���ɁA�������i�e���j�̑S�ے�ł���A���ɁA�V�����i�q���̌����j�̎���������B�����đ�O�ɁA�V�������ێ����邽�߂̌��́i�\�́j�̐������̍s�g�ł���B �@�A���A�u�ْ����\�́��n�l���[���v�Ƃ����T�C�N�������ƌ�����c�u�́A�v���̖\�͂ɔ�ׂĈ��|�I�ɖ����o�ł���A���I�ł���A���ӓI�ł���A�ς������I�ł���B �@���͂��̊m�M���̎コ�������A�c�u�̍ی��̂Ȃ�������t���Ă���B�\�͎�́i���q�j�́A���̊m�M�̂Ȃ������Ԃ���w�P���i�������Ⴍ�j�����A�������Ȃ��̂ɂ�����̂��B���͂�D���Ă��A�����ɐ��������o���Ȃ��B���������o���Ȃ��̂́A�����̗v������߂��Ȃ����炾�B�v�����߂��Ȃ��܂܁A���͂����������Ă����B�\�͂�������C�𐧔e����̂��B �@���̊m�M�̂Ȃ����ӓI�Ȗ\�͂̕����ɁA���q�̐e�����͎�X�����\�͉���̔����������N���Ă����B���ꂪ���q�ɂ́A������ڋ����ɉf��̂��B�u�ڋ��Ȃ�e�̎q�v�Ƃ����F�m�𔗂�ꂽ�Ƃ��A���̕�������̂��邽�߂ɁA���q�͖\�͂��p��������O�ɂȂ������̂��B�������p���������\�͂ɓ����f���e���������āA���q�̖\�͂͂܂��܂��G�X�J���[�g���Ă������B�u���̎��Ȗ������v�̈ł��A�������u����v���͂��Ă��܂����̂ł���B
�@
�@��e�̋��]�ƁA���e�̒��فB �@���̐�ɕ��e�ւ̖\�͂��҂Ƃ��A���̕��e�͈�́A���q�̖\�͂ɂǂ��Λ�����̂��낤���B
�@
�@�ߔN�A���̂悤�Ȏ��ԂɔY�ޕ��e���A���I�ȃJ�E���Z�����O����P�[�X�������Ă���B���̎��_�ŁA���ɕ��e�͔s�k���������Ă���̂����A���āA����Ȕs�k���������e�ɁA�u���q����̍D���Ȃ悤�ɂ����Ȃ����v�ƃA�h�o�C�X���������Ƃ����āA��p��b��ɂȂ����B�}�X�R�~�̘_���͎�Ƃ��āA�����ȃJ�E���Z�����O�����d�h���̕����ɗ���Ă������B �@���̌������}�X�R�~�ɋ߂��������A�����Ŋ����Ė^�J�E���Z���[����i�삷��Ɓ\�\�@���q�̖\�͂ɋB�R�ƑΏ��ł��Ȃ����̕��e���ώ@�����Ƃ��A�^�J�E���Z���[������ߓI�ȕ֖@�Ƃ��āA����i���q�j�̊����K�v�ȏ�Ɏh�����Ȃ��Ώ��@�����߂���Ȃ������A�Ɖ��߂ł��Ȃ����Ȃ��B �@�^�J�E���Z���[���͏�ɁA�s�k�������e�̋��Ɏ����X���郌�x���ɗ��܂�Ȃ��A�E����z�����L���ȃA�h�o�C�U�[�Ƃ��ẮA�ɂ߂ăn�[�h�Ȗ�����S�킳��Ă��܂��Ă���B������A�ނ炪�s�k�������e�ɁA�u���q�Ɠ����v�Ƃ������|�˓��I�ȃ��b�Z�[�W�𑗔g�ł������Ȃ��̂��B����ɂ��S�炸�A�ނ炪���e�ɁA�u�ŝ��ɑς��镃�e�v�̖����݂̂����߂��̂͌�肾�����B���̏ꍇ�A�u�����Ă͂����܂���v�Ƃ������b�Z�[�W�����Ȃ������̂ł���B �@�s�k�������e�ɁA�u�����v�Ƃ������b�Z�[�W�𑗂��Ă��A���炭��ɏI���ł��낤�B���̂Ƃ��A�u�䖝���Ȃ����v�Ƃ������b�Z�[�W���������e�ɋ��U�����͂��Ȃ̂��B �@���e�͂��̃��b�Z�[�W�����炤���߂ɁA�J�E���Z�����O�ɏo�������̂ł͂Ȃ����B���l�����̉Ս��ȏɃA�N�Z�X�����āA�����̔ڋ����𑊑Ή��������������B���҂̐��I�Ȕ��f�ɂ���āA���q�Ƃ̉ߔM�����s���̒��Ŏ��炪�I�������ڋ��ȍs�����~�ނȂ��������̂ł��邱�Ƃ��A�M���M���̏��Ŋm�F�����������̂ł͂Ȃ����B����ȓǂݕ����܂��\�ł������B �@���ǁA���e����e�����q�̖\�͂̑O��␁i�����j��ł��܂����̂��B�ނ�͒P�ɖ\�͂ɋ��i���сj�����̂ł͂Ȃ��B���͂Ƃ��Ă̖\�͂�␂̂ł���B�c�u�Ƃ������̂����͊W�Ƃ����X�L�[���̒��œǂ�ł����Ȃ�����A���̈ł̉��ɔ���Ȃ��ł��낤�B
�@
�@���q�̖\�͂̐S���I�w�i�Ɍ��y���Ă݂悤�B �@�ȏ�̃P�[�X�ł̕��q�W�ɁA��肪�Ȃ��Ȃ����炾�B
�@
�@���̃P�[�X�̏ꍇ�A�������Ƃ������ɑ��q�ɗ����������Ȃ��������e�̕s���f�̒��ɁA���f���s�݂ŗ���Ă������q�̐����̕ݐ������邱�Ƃ��ł���B�����������ė~�����Ƃ��ɗ����������ׂ����݂̃��A���e�B���H���ł���Ȃ�A���̂悤�ȕ��e�����������q�́A�ł͉��ɂ���āA��l�̒��N�j�̂����ɁA�������I�ȕ��e�����m�F����̂��낤���B �@���̂Ƃ����q�́A�����������Ă������N�j���A�ǂ̂悤�Ȏ��ԂɊׂ����玩���ɗ����������ė���̂��A�Ƃ��������̌��ɓ��ݏo���Ă��܂��̂��낤���B���ꂪ���q�̖\�͂������Ƃ����̂��B�c�u�Ƃ������̌��͂̋t�]�Ƃ����\�}�́A����ȋ��܂����S�ۂ�����̂��B �@������ɂ���A����ȏ�͂Ȃ��Ƃ����ň��̎��Ԃɒu����Ă��A���Ɏ����ɗ����������Ȃ��������e�̒��ɁA�Ō�܂Ń��f�������o���Ȃ��������O�����u������ɂ���āA�y���B���q�Ɍ�����܂܂ɔ������ɕ������e�̎p�����āA�S�����ԑ��q���ǂ��ɂ���Ƃ����̂��낤���B
�@
�@�u���A���ꂪ���e�̋����Ȃ̂��B��͂肱�̒j�́A���̕��e�������v
�@
�@���̃C���[�W��ǂ��삯�Ă��������m��Ȃ����q�́A���܂�ɗ��s�s�Ȃ�\�͂̑O�ɁA�C���[�W�𗠐镃�e�̔ڋ������N���ꂽ�B �@�ڋ��Ȃ���̂̓`���B �@���q�́A������R������������̂��B �@�{���͕\�������v���ȂǂȂ����q���A�ǂ�قǕ��e�����ɍs�����悤�Ƃ��A����Ŏ�ɓ������y�ȂǍ����m��Ă���B�����ɂ͐������Ȃ����A�헪����p�������Ȃ��B����̂́A�w�Lj�����Ȃ����͂Ƃ����Ȃ閂���B���ꂾ�����B �@�ƒ�Ƃ����u����v�����S���e�������q�̓����ɁA�}���ɋ����L�����Ă����B���̂��Ƃ́A���q�̒B���ڕW�_���A�P�ɓ��Ȃ�G�S�̏\�S�ȕ⏞�ɂȂ����Ƃ������Ă���B�ނ͎x�z�~�������߂ɁA���͂�D�悵���������̂ł͂Ȃ��B�܂��Ă�A�e���c�[���Ɏd���Ă邱�ƂŁA�����~�������������̂ł͂Ȃ��B �@���������ނ́A��~�̕⏞�����߂Ă��Ȃ��̂��B �@�ނ����߂Ă���͎̂���g��̕����ł͂Ȃ��A���̊Ԃɂ���������������̌��R���̏[���ɂ�������ƌ����悤���B�����Ŏ������ꂽ���R���̌̂ɁA����̈�A�Ȃ�̎��݊�������ꂸ�A���̂��߂̎Љ�ւ̃A�N�Z�X�ɕs��������Ă��܂��̂��B �@���R���̓����Ƃ́A���䂪�Љ�ł��Ă��Ȃ����Ƃւ̕s�����ł���A�����ł̖Ɖu�͂̕s�S���ł���A�����Ď��ȓ�������K�͊��o�̐Ǝ㊴�Ȃǂł���B �@���q���J�������͊W�́A���_�A���R���̕�U�ړI�ɋ��߂����̂ł͂Ȃ��B���Ƃ�茇�R���̔c�����獢��ł��邾�낤�B�����A�Љ�Ɏ��������Ă����Ȃ��NJ���A�Љ�I�h���ɑ����R�͂̎コ�Ȃǂ��痈�闎���̊��o���A�����ɉ������v�[�������Ă��܂��Ă���̂ł���B
�@
�@������������Ȃ��B����I�Ȃ��̂�����I�ɑ���Ȃ��̂��B �@���̐ӔC�͐e�����ɂ���B�v�t�����o�R���čU�����������Ă������䂪�A���₻�̔c���ɒH�蒅���āA�������u���Ă����҂����ɏP���������ė����̂ł���B �@���R�̂悤�ɁA�\�͂ɂ���Č��R���̕�U�������Ȃ������B �@�����ɋ��������L�������B���͂⌠�͊W����̂��铖���Ҕ\�͂������āA���ĉƑ��ƌĂꂽ�W���̂͋����̋ɂ݂ɂ������B�����ɂ́A�����������Ȃ������L�����������c����Ă��Ȃ������̂ł���B �@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�� �@�����ŁA���͊W�Ɗ���W�ɂ��Đ������Ă݂悤�B������܂Ƃ߂��̂��ȉ��̕]�ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ ����W�@�@�@��W
�@�@�@�@�@�֎�
�@�@�@�@�@�W�R�@�@ ���͊W�@�@ �@ �@ �@ �@�@�@�@�@�@�A
�@�@�@�@�@�̓x�@�@�͊W�@�@�@�@ �B �@�@�@�@�@�@�C
�@�@�@�@�@�@ ��@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@ ���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�W�̔Z���x���� �@�@
�@
�@�@�ɂ́A�\�͒c�A�@���c�́A�ƒ���\�͂̉ƒ�Ƃ��A�s�Ґe�Ƃ��̎q���A�܂���w�^�����̐�y��y�A�����Ƃ̔ԓ��ƒ��t�A�v���싅�̊ēƑI���A���[���c��Ƃ̂n�i�s�Ȃǂ��܂܂�悤���B �@�A�́A�p�u���b�N�X�N�[���̋��t�Ɨ����Ƃ̊W�ł���A�x�@�g�D�⎩�q���̏㉺�W�ł���A���_�a�@�̓��ǂƊ��҂̊W�A�Ƃ������Ƃ��납�B �@�܂��A�B�ɂ͕��ʂ̐e�q�A�e�F�A�Z��o���A���l���A���̊W���܂܂��B �@�ł��@�\�I�ȊW�ł��邪�̂ɁA������ۂC�ɂ́A�K�����ɂ�����X�I�Ȏt��W�A�ߗW�A���������Ă̊W��A�����e�ʊW�Ƃ������Ƃ��낪���邾�낤���B
�@
�@���͊W�̋��x�͂��̎��R�x�����肵�A����W�̋��x�͂��̊W�̔Z���x�����肷��B �@�����ŏd�v�Ȃ̂́A���͊W�̋��x�������A���A����W���Z���ł���W�i�@�j�ł���B�W�̎��R�x���Ⴍ�A����Z���Ɍ�������W�̕|���͕M�サ����̂�����B �@���̊W�����I�ȋ�ԂŐ������Ă��܂����Ƃ��̋��|�́A�A���ԌR�̐Y���R�x�[�X�ł̓��u�E����A�I�E���^�����{�݂ł̈�A�̃����`�E�l��z�N����ΗđR�Ƃ���B������������邱�ƂŁu����v�����A�����ɂ����܂����܂ł́u����̋��|�v�����܂�A���̌��͂̒��S�ɁA���͂Ƃ��Ắu����̒鉤�v�����o����̂ł���B �@�u����v�̒��ł͊�@�͊O���̐��E�ɂȂ��A��ɓ����ō��o����Ă��܂��̂��B���Ō��͊W�����܂��ƁA����W���H���ł����Ă��A�����L�̊���E�������o������A���݂ɗL���ȃp�[�\�i���E�X�y�[�X��ݒ�ł��Ȃ��قǂ̉ߏ�ȋߐڊ������͊W���X�ɉ������āA�����Ƀh���h���̊���W���`������Ă��܂��̂ł���B�����ɂ͗�������݂���]�n���Ȃ��A���ӓI�Ȍ��̖͂\���ƁA���̉ЊQ��h�����Ƃ����X���X���鎩�䂵�����݂��Ȃ��Ȃ�B�����悤�Ȓn�����A�����Ɍ��o������̂��B �@�\�\�@���̌��̖͂\���̊i�D�̗�Ƃ��āA���̋L���ɑN���Ȃ̂́A�A���ԌR�����ł̎����P��̏��Y�ɂ܂���ɂ��ׂ��G�s�\�[�h�ł���B �@���悻���Y�ɒl���Ȃ��悤���ȗ��R�ŁA�ނ̔��}�s�ׂ����e���A�A�C�X�s�b�N�Ŕ��ɂ���悤�ɂ��ē��u���E�Q�������̍s�ׂ́A�\�����錠�͂́A���̎~�ߏ����Ȃ��l�Ԃ𔘂��Č������B���̂悤�ȏ��ł́A�N�����l���⏈�Y�̑ΏۂɂȂ蓾�邵�A���̊�́A�u����̒鉤�v��ᒂɏ�邩�ۂ��Ƃ������ɂ������݂��Ȃ��̂��B �@���ہA�Ō�ɏl�����ꂽ�ÎQ�����̎R�c�F�́A����őK���ɓ������s�ׂ��u���W���A�I�Ƃ���A���ꂪ�_�@�ƂȂ��āA�ߋ����ȗ������U�镑�����f�߂����ɋy�B�R�c�Ɋւ��u�鉤�v�̋L�����w�ǜ��ӓI�ɍĕ҂���Ă��܂�����A�����ɉ����A�u�鉤�v��ᒁi����j�ɏ�i����j��s�ׂ������邾���ŁA���}������������Ă��܂��̂ł���B �@�����Ă����A�����ɂ͒N�����Ȃ��Ȃ�B �@���̂悤�Ȍ��͊W�̉�͎̂����҂��A�O���̐��E����̕ʂ̌��͂̓������������̂����ꂩ�����Ȃ��B��������n�����������邱�Ƃɂ͕ς�肪�Ȃ��̂��B �@����x��[���������͊W�̖�肱�����A���������茋�ԊW�̋Ɍ��I�l�Ԃ��������̂ł������B�]���Ď������́A�W�̉���x���Ⴍ�Ȃ�قǓK���Ȏ���͂������Ă������ɂ��ẮA�[���߂���قǔc�����Ă����ׂ��Ȃ̂ł���B �@�\�\�@���ɁA���ɂ���Ĕ������錠�͊W�ɂ��Č��y���Ă݂�B �@������ˑR�A�V�e���|�ꂽ�B�K���A���ɕʏȂ������B���������ǂ��c�����B���g�s���ƂȂ�A���������ɂȂ����B �@�|�ꂽ�e�ւ̈���[���A���ӂ̔O��������A�V�e�̎q�͌��g�I�ɊŌ삵�A���`��ԕ�ł����тɐZ��邩���m��Ȃ��B���̋C�����̌p���͂�⏞����悤�Ȉ��≷��̃p���[���Ή��������͂Ȃ��B���������̃p���[���Ǝ�Ȃ�A�V�e�̎q�́A�Ō�̌p���͂�ʂ̗v�f�ŕ�U���Ă����K�v�����邱�Ƃ����͊m���ł���B �@�ł́A�Ō�̌p���͂�����ȊO�̗v�f�ŕ�U����҂́A�����ɉ��������o���Ă��邩�B�����Ȃ��̂ł���B����̑�ւɂȂ�p���[�ȂǁA�ǂ��ɂ����݂��Ȃ��̂ł���B�����Ă�����A�u���̎q�͐e�̖ʓ|���łȂ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����ނ̓�����������B���������ꂪ�Ӗ������̂́A����̎�̕s��������ɂ���ĕ⊮���������ɂ����Ăł����āA���̕⊮�̗L�����E����E����قǂ̈�����������Ɍ�����A�������̎������ȂǕ��C�Ȃ���Ă��܂��̂ł���B �@�u������ׂ��v�Ƃ����S���I�����͂��L���ł����������̎Љ�A���͂Ȃ��B �@���������肵���p���͂����ɂ́A���肵������W�������҂Ƃ̊Ԃɓ����I���H���v�������悤�Ȕw�i�����ꍇ�ł���B�e�q�Ɉ��肵������W���Ȃ��A��I�����͂��ォ������A�a�ɓ|�ꂽ�e����삳����͂́A�ЂƂ蓹�����ɋ��邵���Ȃ��B���������̓��������������������Ă��܂�����A���ӁA���ډ��͔j�]���邱�ƂɂȂ�̂��B �@���ډ�삪�j�]���Ă���̂ɁA�Ȃ��������̎������W�����R�ɂ����Ȃ��ł���ƁA�����Ɍ��͊W�����܂�₷���Ȃ�A���̊W�����悢�戫�������Ă��܂����Ƃɂ��Ȃ邾�낤�B �@���̑̍ق��`���I�ɐ����Ă��Ă��A���҂̓����Ńv�[�����ꂽ�X�g���X���A����҂ɕ����i�ق��Ă��j�����s�����J���Ă��܂��ƁA���͂Ȑe�͏������ڋ����𔘂��o���Ă����B�e�̔ڋ����ɐڂ������҂́A�ߋ��̓˂������ꂽ�e�q�̊W�����̒��şT�ς�������X�g���X���A�V�e�Ɍ������ĕԕĂ����Ƃ��A����͊��ɕ��Q���ƌ����ׂ������ɂȂ��Ă���B �@����قǍd���������e���A���̂���Ȃɔڋ��ɂȂ��̂��B �@���̐e�ɑ��ĕK���ɑΛ����Ă��������̔����́A��̉��������̂��B�����ɉ��̉��l������̂��B �@����������吋ǁi�Ƃ���j�������āA���E�ɒ���t���Ǝ�ȗ����̂Ɍ������Ċ��ݕt���Ă����B���������̂Ă��Ȃ���������Ɋ܂܂�Ă��邩��A�����̖������p���čU�������������Ă��܂��̂��B���̊W�ɑ�O�҂̈ӎu���N���ł��Ȃ��Ȃ�ƁA�����Ő��܂ꂽ���͊W�́A�����Ŏ��ȑ��B���ʂ����Ă����Ă��܂��̂ł���B �@���ډ��������������ŋ����Ă����s�����_�Ԍ�����ł́A�[���Â��ɐ��s���A���̌ǓƂȉf����s�s�̌����̌��Ԃ��t��o���B�I��肪�����Ȃ��W�̓b�݂��A���킶��Ƃ��̐[�݂𑝂��Ă������̂悤���B �@�\�\�@�����́A��������I�ȃV�[���Ŕ���������A����ȃV�~�����[�V�����͂ǂ����낤���B �@��̑O�ɁA�����̌������Ƃɋɂ߂ď]���ɔ�������䂪�q������B
�@���̎q�͎����Ɏ��āA�ƂĂ����a���B�C���ア�B���̎q�����Ă���ƁA���������̎������v���o���B���ꂪ���ɂ͂ƂĂ��s���Ȃ̂ł���B �@�l�͂ǂ����A�����̒��ɂ����āA������������������X���𑼎҂̒��Ɍ��Ă��܂��ƁA���̑��҂��A�������������̕������͊m���Ɍ����Ă��܂��悤���B�܂��A�����̒��ɂ����āA�������D�ފ���X���𑼎҂̒��Ɍ��ĂƂ�Ȃ��ƁA���̑��҂ۂ̊���̂����ɑa�܂����v���Ă��܂��̂��낤�B�����̏ꍇ�A�����̒��ɂ��銴��X������ɂȂ��Ă��܂��̂ł���B �@�䂪�q�̔ڋ��ȑԓx�����Ă���ƁA�����̔ڋ������f���o���Ă��܂��Ă��āA���ꂪ���܂�Ȃ��s�����Ȃ̂��B���̎q�́A�l�̊�F���M�i�������j���Ȃ���C�����Ă���B���ꂪ���������Ă���̂��B���̎҂ɂ͌���t���邩���m��Ȃ����̎q�́u�ǂ��q�헪�v�́A���ɂ͋p���ĕ����������̂ł���B���ꂪ���̎q�ɂ͕���Ȃ��B������܂������������̂ł���B �@���̎q�ɑ��鈫����́A�ƒ�Ƃ����u����v�̒��œ������ɑ�������Ă����B������ӎ����鎩�����a�܂����A�s���ł��炠��B�����̒��ʼn����������Ă���B�r�C�����ǂ��ꂽ��C���]���Ȃ��̂ƍ������āA������Ă���B �@����Ȓ��ŁA���̎q�����������Č������B �@�����Ȃ����Ƃ����A����ᒂɏ��A�v�킸�{�C���R�ꂽ�B�ڋ��Ɏ������䂪�q�̑ԓx���A�]�v������������B����ɔC���āA���͏������k���邻�̉����ʂ��v�킸�����Ă��܂����B���ꂪ�A���̌�ɑ����s�K�ȏo�����̎n�܂�ƂȂ����̂��B �@�ȗ��A�䂪�q�́A�������邽�߂����̈ꋓ�����̑�����ᒂɏ��A����ɑŝ��i���傤���Ⴍ�j�������ĉ�����ȊO�ɏp���Ȃ��W�𐋂ɊJ���Ă��܂��āA���ɂ��[���ɐ���ł��Ȃ��ł���̂ł���B �@����̔Z�x�̐[���W�Ɍ��͊W���������A���ꂪ���̒��ɒu���ꂽ��A��́u���̎��Ȋ����v���u���̎��Ȗ������v���J���Ă����悤�ȁA�������ׂȌ_�@������Ώ[���ł��낤�B �@�����ŃC���[�W���ꂽ�ꖺ�̏ꍇ���A���̕s�݂Ɛ�Ǝ�w�Ƃ�����������������Ă��܂��āA�����Ɉ�C�Ɍ��͊W������������悤�Ȗ\�͂��p���������Ɏ�������A�w�Njs�߂̐��E���J�����B �@�s�߂Ƃ́A�g�̖\�͂Ƃ����\���l�Ԃ���̉\���Ƃ��Ċ܂A�ӎu�I�A�p���I�ȑΎ���\�͂ł���Ɣc�����Ă����B����́A�����ɂ͓��R�R�X�������͊W�̗͊w���������Ă���B �@�ꖺ���܂��A���̌��͊W�̗͊w�ɓ˂����������悤�ɂ��āA��C�ɂ��̕����̍s�����삯�Ă����B �@�Ⴆ�A���̖\�͂͐H�������Ƃ��A�����̋��v�Ƃ��̒��ړI�x�z�̗l�Ԃ����I�Ɋ܂ނ��ƂŁA�W�̌ݏV�������ȉ�̂��Ă������A���ꂪ���͊W�̗͊w�̕����W�J�𑁂߁A���̗����𐧌�ł��Ȃ��悤�Ȗ������������ɎN�����B���������ɂ́A�ʂ̈ӎu�̋����I�N���ɂ���Ă�������ł��Ȃ��������A�₦�₦�ɂȂ��ăt���[���Ă���B�e���̃x�[���������A�̔햌���Ă���悤�ł���B �@�\�\�@�s�߂̖������͊W�Ƃ��đ����Ԃ����ƂŁA���̍e���܂Ƃ߂Ă������B �@���������A�s�߂���҂ɓ��L�Ȑ��i�C���[�W�Ƃ͉����낤���B �@���ǁA�s�߂��₷���҂Ƃ́A�h�q���C�������łłȂ��A������O���Ńv���e�N�g���郉�C�����s�����Łi��q�ƒ�Ƃ��A�Ǘ��ƒ�Ƃ��j�A���̂��ߐl���r�߂��₷���҂Ƃ������ƂɂȂ낤���B �@�����������ɁA���Ȃ���ʌo���I�������܂܂�邱�Ƃ�F�߂邱�Ƃ́A�s�߂��^���_�ŏ������Ă������Ƃ�F�߂邱�ƂƓ��`�ł͂Ȃ��B �@�s�߂Ƃ́A�ӎu�I�A�p���I�ȑΎ���\�͂ł����āA�����ɂ͌��͊W�̉��^���̌`�����ǂݎ���̂ł���B���̗����̃��C�����O���A�s�߂̉^���_�͍J�Ԃ�Ȋ�����ɈႢ�Ȃ��B �@�s�߂̑��́A�����ɉϐ���F�߂����͊W�ł��邱�ƁB���́A�Ύ���\�͂ł��邱�ƁB��O�́A����̂ɔ�r�I�A�p�����������₷�����Ɓ\�\�@���̊�{���C���̗������A�����ł͏d�v�Ȃ̂��B �@�s�߂ɂ��\�̖͂{���́A����̎���ւ̖\�͂ł����āA���ꂪ���݂̋��v�⏬�Ԏg���Ƃ��A�l�X�Ȑg�̓I�\�͂��܂ޒ��ځA�Ԑڂ̖\�͂ł������Ƃ��Ă��A�����̖\�͂̃^�[�Q�b�g�́A�����Δڋ��Ȃ鑊��̔ڋ��Ȃ鎩��ł���B������ŝ��i���傤���Ⴍ�j���A�����邱�Ƃ����A�s�߂ɋ����҂����̔ڋ��Ȃ�_���ł���B �@�ڋ����W�����A�N���X����B �@�ނ�͑���̐g�̂������Ă��A���̎���������Ȃ���A�I�قǂ̒B�����������Ȃ��B���肪���E���l����قǂɏ����Ă���Ȃ���A�s�߂ɂ����y����ɓ�����Ȃ��̂��B�Ύ���\�͂�����A���̎���̋��̐g�̕\���������āA�����ɏ��߂ĉ��y�����܂�A���̉��y���S�Ă̌��͊W�ɒʂ�����y�ƂȂ邩��A�K�����傫�ȉ��y��ڎw���ăG���h���X�Ɏ��ȑ��B���d�˂Ă����B �@�����āA���̎�̖\�͂͊m���ɁA�����ĉʂĂ��Ȃ���������A�G�X�J���[�g���Ă����B���肪����������ƂŁA��U�͖\�͂����É����邱�Ƃ͂����Ă��i�u���̎��Ȋ����v�j�A�p���āA���̔ڋ����ւ̌y�̊��Ɛ������̒B���ɂ����y�̋L�����A���ӁA���̂�葝�����ꂽ�\�͂̕z�ƂȂ邩��A���̍ߐ[���W�ɂ��܂ł��I��肪���Ȃ��̂��B �@�s�߂Ƃ������̂��A���͊W���x�[�X�ɂ����p���I�ȑΎ���\�͂Ƃ����\���������Ƃ������Ɓ\�\�@���̂��Ƃ����ǁA����̐g�̂����̂ɂ���܂ŃG�X�J���[�g������Ȃ��A���̖\�͂̕|���̖{�������������̂ɂȂ��Ă��āA���̐��E�̍ی��̂Ȃ��ɐg�k���������ł���B �@�u�s�߁v�̖������͊W�Ƃ��đ����Ԃ����ƂŁA�������͂��̐��ɁA�u���͊W�̊��v�v�������Ȃ��L����̒��ŏ�ɕ��݂��Ă��錻�����A���ł��A�ǂ��ł��A�ڂ̓�����ɂ���ł��낤�B���ꂪ�l�Ԃł���A�l�ԎЉ�̌����ł���A���̏h�}�i���キ���j�Ƃ��ĂԂׂ��a���ƌ����邩���m��Ȃ��B �@���_���猾���A�������l�Ԃ̖{���I�ȋ���F�m������Ȃ��Ƃ������Ƃ��B�l�Ԃ��W�c�����A���ꂪ����̕����I���������Ƃ��A�����ɁA�������x�̊m���Ō��͊W�̌��o���Ă��܂������m��Ȃ��̂ł���B �@�J��Ԃ����A�l�Ԃ̎��䓝��\�͂ȂǍ����m��Ă���̂��B�����玄�����̎Љ��A�u�s�߁v��u�ƒ���\�́v�����₷�邱�Ƃ́A�w�Ǖs�\�ƌ����Ă����B�܂��Ă�A���͊W�̔������A�S�āu���v�̖��ʼn����ł���ȂǂƂ������z�́A���O�n�̖\���ł��炠��ƒf�����Ă����B �@�������A�ȏ�̕�����F�߂Ă��Ȃ��A�u�s�߁v���^���_�̖��ɊҌ�����̂́A�Ƃ��Ă��N���o�[�Ȕc���ł���Ƃ͎v���Ȃ��̂��B�u�s�߁v������̖��ł��邪�̂ɁA���̎������苭�����鋳�炪���߂��邩��ł���B �@�l�Ԃ͋��������A���̋��������ߏ�Ɍ��݉������Ȃ��X�L�����炢�͊w�K�ł��邵�A���̎�i���܂��A��ɂ����P�I�w�K�̒��ŁA��炩�͐i�������邱�Ƃ��\�ł��邾�낤�B���Ȃ��Ƃ��A���̂悤�ɔc�����邱�ƂŁA�������̓��Ȃ���Ə�ɑΛ����A�������瓦�S���Ȃ��m�b�̍H�v���炢�͍��o����ƐM����ȊO�ɂȂ��Ƃ������Ƃ��B �@�l�͏��F�A�����̃T�C�Y�ɂ����������������ł��Ȃ����A�]�ނׂ��łȂ����낤�B �@�����̔\�͂������ɒ������l���͌p���͂������Ȃ�����A�j�]�͕K���ł���B�܂��āA����𑼎҂ɗv�����邱�ƂȂǕs���߂���B�ߏ�ɑ���A�W�̗L�@���͏�������̂��B�����������āA�b�݂͑�������ƂȂ�B�W���ߑ㉻����Ƃ����c�ׂ́A�v���̊O�A�S�J�̔������̂ł���A�����̔E�ς�v������̂ł��邩�炾�B �@�l�͊F�A��������ɂ��đ��҂𑪂��Ă��܂�����A�����ɉ\�ȍs�ׂ肪�������ԓx�����Ă��܂��ƁA�ʏ�A�����ł̗����ɐl�͎��]����B�ǂ����Ă�����̗���ɗ����āA���̐��i��\�͂�Ύށi���Ⴍ�j���āA�q�ϓI�ɕ]������Ƃ������Ƃ͍���ɂȂ��Ă���B�����ɁA�s�K�v�Ȃ܂ł̊���[���N�����Ă��Ă��܂��̂ł���B �@�܂��t�ɁA�����̔\�͂ŏ����ł��Ȃ��������A���肪��ϓI�ɍ����o���A�u��e�́v����m��I�X�g���[�N�ɑ��āA�����Ɉϑ������Ă��܂������̎葱���ɂ͑����̗p�S���K�v�ł���B�����ɕK�v�ȏ�̌��z���������܂Ȃ����������̂��B�����ȊO�̎҂ɂ����ꂩ�������������g�傳��������̖\���́A�ł��X���Ȃ��̂̈�ł���ƌ����Ă����B���̂��Ƃ̔F�m�͊W�i�����j���d�v�ł���B �@�������͂�߂�߁A�u�ߑ�I�W�̎��H�I�n���v�Ƃ����e�[�}��e���Ɉ����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ��B����ȊO�ł͂Ȃ��B
http://zilx2g.net/index.php?%A1%D6%CF%A2%B9%E7%C0%D6%B7%B3%A1%D7%A4%C8%A4%A4%A4%A6%B0%C7
|
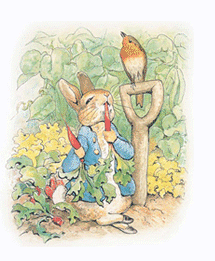
 �X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B