2021�N06��22��
�A�W�A�����ɂ����鏉�������l�ނ̊g�U�ƒn��I�A����
https://sicambre.at.webry.info/202106/article_22.html
�@�ŋ߁A�l�ޏW�c�̒n��I�A�����Ɍ��y���܂������i�֘A�L���j�A���̋L���ŗ\�������悤�ɁA�ߔN�傫���������i�W�����A�W�A�����Ɋւ��Ă��̖������܂��B�Ȃ��A����͂����ނ˃A���[���여��ȓ��ΏۂƂ��A�V�x���A��V�A�ɓ��k�����͌���I�ɂ������y���܂���B���������l�ށiHomo sapiens�j�̊g�U�Ɋւ��錤���͋ߔN����I�ɐi�W���Ă���A���̊T�v��c������ɂ́A�����l�ނ̋N���Ɋւ��鑍���iBergström et al., 2021�A�֘A�L���j��A�����l�ނɌ��炸�A�W�A�����̃z�������T�ς��������i�V����., 2021�A�֘A�L���j��A�㕔���Ί펞��̃��[���V�A�k���̐l�X�̌Ñ�Q�m�������Ɋւ���T���i����., 2021�A�֘A�L���j���L�v�ł��B�ŋ߂̑����I�_������́A�A�t���J���烆�[���V�A�ւƊg�U�������������l�ނ��A�g�U��Ŏq�����c�����ɐ�ł�������͒������Ȃ������A�Ǝ�������܂��iVallini et al., 2021�A�֘A�L���j�B�����̑����܂��A�A�W�A�����ɂ�����l�ޏW�c�A�Ƃ��ɏ��������l�ނ̊g�U�ƒn��I�A�����̖��������Ȃ�ɐ������܂��B
���l�ޏW�c�̋N���Ɗg�U����ь���l�Ƃ̘A�����Ɋւ�����
�@�l�ޏW�c�̋N���Ɗg�U�́A����l�̊e�n��W�c�̈�����`�▯����`�ƌ��т����Ƃ��������Ȃ��A���Ȗ��ł��B����n��̌Ñ�̐l�ވ�[���A�����n��̌���l�̑c��W�c��\���Ă���A�Ƃ̔F���͎��o�I�ɂ��斳���o�I�ɂ���A���������̂�����悤�ł��B�`�F�R�ł�20���I�㔼�̎��_�łقڔ����I�ɂ킽���āA��̊w���ł͂Ȃ������Ƃ��āA�l�A���f���^�[���l�iHomo neanderthalensis�j������`�F�R�l�̑c��Ƌ������Ă��܂����iShreeve.,1996,P205�j�B����́A�����l�ނɋ��ʂ̔F�m�I�X���Ȃ̂ł��傤���A�Љ��`�C�f�I���M�[�̉e�������邩������܂���B�`�F�R�Ƃ������`�F�R�X���o�L�A�Ɠ������Љ��`���̒����ƃx�g�i���Ɩk���N�̍l�Êw�́u�y�����W�iThe indigenous development model�j�v�^�X���������A�Ǝw�E����Ă��܂��i�g�c.,2017�A�֘A�L���j�B���̌X���́A�����n��̒����ɂ킽��l�ޏW�c�̈�`�I�A�����ƌ��т��₷���A�����O��Ƃ��錻���l�ޑ��n��i�����ƂЂ��傤�ɐ����I�ł��B�����ł͌��݁i���Ȃ��Ƃ�2008�N���܂Łj�ł��A���㒆���l�́u�k�����l�v�Ȃǒ����Ŕ������ꂽ�z���E�G���N�g�X�iHomo erectus�j�̒��n�q���ł���A�Ƃ̌����������̐l�Ɏx������Ă��܂��iRobert.,2013,P267-278�A�֘A�L���j�B�����A�����l�����҂��ւ�����ŋ߂̌��������Ă����ƁA�ߔN�̑����̒����l�����҂ɂ́A�l�ރA�t���J�N������O��Ƃ��Ă���l�������悤�ɂ��v���܂��B �@20���I���ȍ~�Ɍ����l�ރA�t���J�P��N�������嗬�ƂȂ��Ă���́A2010�N��Ƀl�A���f���^�[���l���敪����̃z�����ł���f�j�\���l�iDenisovan�j�Ȃǐ�Ńz�����i�Ñ�^�z�����j�ƌ����l�ނƂ̍������L���F�߂���悤�ɂȂ������̂́iGokcumen., 2020�A�֘A�L���j�A�z���E�G���N�g�X��l�A���f���^�[���l��f�j�\���l�Ȃǐ�Ńz�������猻��l�Ɏ��铯�n��̐l�ޏW�c�����̈�`�I�A�����́A���Ȃ��Ƃ��A�t���J�O�Ɋւ��Ă͊w�p�I�ɂقڔے肳�ꂽ�A�ƌ�����ł��傤�B��������ƁA����n��ɂ�����l�ޏW�c�̘A�����Ƃ̎咣�́A�ŏ��̌����l�ނ̓����ȍ~�ƍl������悤�ɂȂ�܂��B �@�I�[�X�g�����A�̃����\���iScott John Morrison�j�́A��Z���ւ̎Ӎ߂ɂ����āA�I�[�X�g�����A�ɂ������Z����65000�N�ɂ킽��A�����Ɍ��y���Ă��܂��B���̍����ƂȂ�̂́A�I�[�X�g�����A�k���̃}�W�F�h�x�x�iMadjedbebe�j��A��ՂŔ������ꂽ�����̐l�H���ł��iClarkson et al., 2017�A�֘A�L���j�B���̐l�H���ɂ͐l�ވ�[���������Ă��܂��A�����l�ނł���\��������߂č����ł��傤�B1���̎��l�Êw�I�������ʂ������ɁA��Z���̒����ɂ킽��I�[�X�g�����A�ł̘A�����������ɔF�߂Ă���킯�ł��B�������A�}�W�F�h�x�x��A��Ղ̔N��Ɋւ��ẮA���ۂɂ͂����ƐV�����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ̋����^�₪�悳��Ă��܂��iO�fConnell et al., 2018�A�֘A�L���j�B�����A�}�W�F�h�x�x��A��Ղ̔N�オ���������ɂ�65000�N�O����肸���ƐV�����Ƃ��Ă��A���Ȃ��Ƃ������N�O�ɂ͂����̂ڂ�ł��傤���A20���I�̃I�[�X�g�����A��Z���̃~�g�R���h���ADNA�imtDNA�j�̕��͂���́A���̑c��W�c�̓I�[�X�g�����A�k���ɏ㗤������A���ꂼ����̊C�݉����ɋ}���Ɋg�U���A49000�`45000�N�O�܂łɓ�I�[�X�g�����A�ɓ��B���đ��������A�Ɛ�������Ă��܂�����iTobler et al., 2017�A�֘A�L���j�A�����ɂ킽��I�[�X�g�����A�̐l�ޏW�c�̈�`�I�A�����ɕς��͂Ȃ��A�Ƃ��l�����܂��B �@�����Ŗ��ƂȂ�̂́A�ߌ���l��mtDNA�n�v���O���[�v�imtHg�j���炻�̑c��W�c�̊g�U�o�H�⎞���𐄑����邱�Ƃł��B���N�i2019�N�j�̌����ł́A����l��mtDNA�̕��͂Ɋ�Â��Č����l�ނ̋N���n�͌��݂̃{�c���i�k���������A�Ǝ咣����܂������iChan et al., 2019�A�֘A�L���j�A���̌����͌������ᔻ����Ă��܂��iSchlebusch et al., 2021�A�֘A�L���j�BSchlebusch et al., 2021�́AmtDNA�n�������l���W�c��\���Ă���킯�ł͂Ȃ��A�ƒ��ӂ����N���܂��B�n������N��͒ʏ�A�l���W�c�̕���ɐ�s���A�����̏ꍇ�A����̍��̐l���K�͂₻�̌�̈ړ����ɂ��`������邩�Ȃ�̎��ԍ�������A�Ƃ����킯�ł��B�܂�Schlebusch et al., 2021�́A����̈�`�I�f�[�^����n���I�N���𐄑����邳���̏d�v�Ȗ��Ƃ��āA�l���j�ɂ�����N�����猻��܂ł̏d�˂�ꂽ�l�����v�I�ߒ��i�ڏZ�╪���Z����K�͂̕ω��j�́u�㏑���v���x���w�E���܂��BmtDNA��Y���F�̂ƂƂ��ɕАe����`�W���Ƃ�������Ȉ�`�p����\���A����l��mtHg��Y���F�̃n�v���O���[�v�iYHg�j����ߋ��̊g�U�o�H�⎞���𐄑����邱�Ƃɂ͐T�d�ł���ׂ��ł��傤�B�܂��AmtDNA��Y���F��DNA���S�̓I�Ȉ�`�I�߉��W�f���Ă��Ȃ��ꍇ������A���Ƃ��Ό���l�A���f���^�[���l�́A�j�Q�m���ł͖��炩�Ɍ����l�ނ����f�j�\���l�̕��Ƌ߉��ł����AmtDNA�ł�Y���F��DNA�ł��f�j�\���l���������l�ނ̕��Ƌ߉��ł��iPetr et al., 2020�A�֘A�L���j�B �@�n�����́AmtDNA��Y���F�̂̂悤�ȕАe����`�W�������ł͂Ȃ��A�jDNA�̂悤�ɗ��e����p��������`���Ɋ�Â��Ă��쐬�ł��܂����A�Аe����`�W���̂悤�ɖ��m�ł͂���܂���B����ł��A�A�W�A������I�Z�A�j�A��[���b�p�Ȃnj���l�̊e�n��W�c���n�����ł��̈�`�I�W��������킯�ŁA����l�����ǂ̂悤�Ɍ��݂̋��Z�͈͂Ɋg�U���Ă����̂��A��������肪����ɂȂ�킯�ł����A�����Ŗ��ƂȂ�̂́A�n�����͉�����`�I�W�̕��ތQ���m�̊W��}������̂ɂ͓K���Ă�����̂́A�߂���`�I�W�̕��ތQ���m�ł͕��G�ȊW��K�ɕ\����Ƃ͌���Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B���Ƃ��Ό���l�ƍŋ߉��̌������ތQ�ł���`���p���W�[���ł́A�{�m�{�iPan paniscus�j�ƃ`���p���W�[�iPan troglodytes�j�Ƃ̍����iManuel et al., 2016�A�֘A�L���j��A�{�m�{�ƈ�`�w�I�ɖ��m�̗ސl���Ƃ̍����iKuhlwilm et al., 2019�A�֘A�L���j�̉\�����w�E����Ă��܂��B�܂��A�ȉ��̌����l�ނ̋N���Ɋւ��鑍���iBergström et al., 2021�j�̐}3c�Ŏ�����Ă���悤�ɁA�z�����̕��ތQ�Ԃ̍��������G�������A�Ɛ�������Ă��܂��B
�摜 �@�����������G�ȍ�������������镪�ތQ�Ԃ̊W�́A�ȉ��Ɍf�ڂ����q��Vallini et al., 2021�̐}1�̂悤�ɁA�����}�Ƃ��Ď����Ύ��ۂ̐l���j�ɂ��߂��Ȃ�܂����A����ł����Ȃ�P�����������̂ɂȂ炴��Ȃ��킯�Łi���������A���ۂ̐l���j���u���m�Ɂv���f�����}�͂قƂ�ǂ̏ꍇ�ƂĂ����p�I�ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��傤�j�A����l�̒n��W�c�ɂ��Ă��A�ߋ��̂��鎞�_�̏W�c�������͌̂ɂ��Ă��A���̋N����`���ߒ��Ɋւ��ẮA�����܂ł���܂��Ȃ��́i��𑜓x�j�ƂȂ�܂��B�l�A���f���^�[���l��f�j�\���l�ƌ����l�ނƂ̊W�ł������G�Ȃ��̂Ɛ�������Ă��܂�����A����l�̊e�n��W�c�̊W�͂���ȏ�ɕ��G�ƍl�����܂��B�N����`���ߒ���g�U�o�H�⌻��l�Ƃ̘A�����ȂǁA�����������G�ȊW����萳�m�ɔc������ɂ́A�Аe����`�W���ł��jDNA�ł��A����l�����ł͂Ȃ��Ñ�l��DNA�f�[�^���K�v�ƂȂ�A����l��DNA�f�[�^�����Ɋ�Â����n�����ɉߓx�Ɉˋ����邱�Ƃ͊댯�ł��B
�摜 �@����̒n��ɂ�����ߋ��ƌ���̐l�ޏW�c�̘A�����Ɋւ��ẮA��q�̂悤�ɍŋ߂̑����I�_������A�A�t���J���烆�[���V�A�ւƊg�U�������������l�ނ��A�g�U��Ŏq�����c�����ɐ�ł�������͒������Ȃ������A�Ǝ�������܂��iVallini et al., 2021�j�B��̓I�ɂ́A�`�F�R�̃R�j�F�v���V�iKoněprusy�j���A�Q�Ŕ������ꂽ�A���A�Q�̒���̋u�ɂ��Ȃ�ŃY���e�B�N���iZlatý kůň�j�ƌĂ�鐬�l����1�̂́A���[���b�p�ŌË��i45000�N�ȏ�O�j�̌����l�ޏW�c��\���܂����A����l�̒��ړI�c��ł͂Ȃ��A�Ɛ�������Ă��܂��iPrüfer et al., 2021�A�֘A�L���j�B�Y���e�B�N���́A�o�A�t���J�n����l�̊e�n��W�c����`�I�ɕ�������O�ɂ��̋��ʑc��ƕ����A�Ɛ�������Ă��܂��B�o�A�t���J�n����l�̑c��W�c�͈�`�I�ɁA�傫�����[���V�A�����n���Ɛ����n���ɋ敪����܂��B �@���̑��ɂ́A�`�F�R�̃o�`���L�����A�iBacho Kiro Cave�j�Ŕ������ꂽ�����l�ތ̌Q�i44640�`42700�N�O���j�́A����l�Ƃ̔�r�ł̓��[���b�p�����A�W�A�����ɋ߂��A���[���b�p����l�ւ̈�`�I�e���͏����������A�Ɛ�������Ă��܂��iHajdinjak et al., 2021�A�֘A�L���j�B�V�x���A�����̃E�X�`�C�V���iUst'-Ishim�j�ߍx�̃C���e�B�V��iIrtysh River�j�̓y��Ŕ������ꂽ44380�N�O���ƂȂ錻���l�ޒj����[�iFu et al., 2014�A�֘A�L���j��A���[�}�j�A�쐼���́u���̓��A�iPeştera cu Oase�j�v�Ŕ������ꂽ39980�N�O���́uOase 1�v�́iFu et al., 2015�A�֘A�L���j���A��̃��[���b�p�l���W�c�Ɉ�`�I�e�����c���Ă��Ȃ��A�Ɛ�������Ă��܂��BVallini et al., 2021�ł́A�E�X�`�C�V���̂�Oase 1�̓��[���V�A�����n���Ɉʒu�Â����AOase 1�̓o�`���L�����A�̌����l�ތ̌Q�i44640�`42700�N�O���j�Ƌ߉��ȏW�c����v�Ȓ��ړI�c�悾�����A�Ɛ�������Ă��܂��B�܂��A�u�����̓��A�iPeştera Muierii�A�ȉ�PM�j�v��34000�N�O���ƂȂ�́iPM1�j�́A���[���V�A�����n���Ɉʒu�Â����A�������̃��[���b�p��̏W���̕ψٓ��Ɏ��܂�܂����A���[���b�p����l�̑c��ł͂Ȃ��A�Ɛ�������Ă��܂��iSvensson et al., 2021�A�֘A�L���j�B
���A�W�A�����ɂ�����l�ޏW�c�̈�`�I�A����
�@���̂悤�Ƀ��[���b�p�ɂ����ẮA���������l�ނ�����l�ƈ�`�I�ɂȂ����Ă��Ȃ�����͒���������܂���B�A�W�A�����ɂ����Ă��A�ŋ߂ł͓��l�̎��Ⴊ���炩�ɂȂ����܂��B�A�W�A������DNA����͂���Ă���ŌÂ̌̂́A�k���̓쐼56km �ɂ���c园�i�c���j���A�iTianyuan Cave�j�Ŕ������ꂽ4���N�O���̒j���iYang et al., 2017�A�֘A�L���j�ŁA���̎��ɌÂ��̂������S���k�����̃T���L�[�g�k�J�iSalkhit Valley�j�Ŕ������ꂽ34950�`33900�N�O���ƂȂ鏗���iMassilani et al., 2021�A�֘A�L���j�ł��B�ŋ߂ɂȂ��āA���̃T���L�[�g�̂Ɏ����ŌÂ��A34324�`32360�N�O���ƂȂ�A���[���여��̏����iAR33K�j�̃Q�m���f�[�^������܂����iMao et al., 2021�A�֘A�L���j�B �@Mao et al., 2021�́A4���N�O���̖k���ߍx�̓c���̂�34000�N�O���̃����S���k�����̃T���L�[�g�̂�33000�N�O���̃A���[���여���AR33K���A��`�I�ɗގ����Ă��邱�Ƃ������܂��B�A�W�A��������l�̊e�n��W�c�̌`���j�Ɋւ���ŋ߂̕�I�����iWang et al., 2021�A�֘A�L���j�ɏ]���ƁA�o�A�t���J�����l�ނ̂�����A�t���J�n����l�ɒ��ړI�ɂȂ���c��n���i�c��n���Aancestry�j�́A�܂����[���V�A�����Ɛ����ɕ��܂��B���̌�A���[���V�A�����n���͉��ݕ��Ɠ������ɕ��܂��B���[���V�A�������ݕ��iEEC�j�c��n���ł����ɍ\�������̂́A����l�ł̓A���_�}�������l�A�Ñ�l�ł̓A�W�A�쓌���̌���X�V���`���V���ɂ����Ă̎�̏W���ł���z�A�r�������iHòabìnhian�j�W�c�ł��B�A�W�A��������l�̃Q�m���́A�����Ƀ��[���V�A�����������iEEI�j�c��n���ō\������܂��B���̃��[���V�A�����������c��n���͓�k�ɕ��A���͗���V�Ί펞��W�c�͂����ɖk���iEEIN�j�c��n���A���]����V�Ί펞��W�c�͂����ɓ���iEEIS�j�c��n���ō\�������A�Ɛ�������Ă��܂��B�����̌���l�͂��̓�k�̑c��n���̂��܂��܂Ȋ����̍����Ƃ��ă��f�����ł��A����̃I�[�X�g���l�V�A�ꑰ�W�c�̓��[���V�A��������������c��n������v�ȍ\���v�f�ł��iYang et al., 2020�A�֘A�L���j�B�ȉ��A���̌n���W��������Wang et al., 2021�̐}2�ł��B
�摜 �@�c���̂ƃT���L�[�g�̂�AR33K�͂����ɁA��k�ɕ���O��EEI�c��n���ō\������܂����A�T���L�[�g�̂ɂ́A�ʂ̑c��n�����d�v�ȍ\���v�f�i25%�j�ƂȂ��Ă��܂��iMao et al., 2021�j�B����́A�V�x���A�k�����̃��iRHS�iYana Rhinoceros Horn Site�j�Ŕ������ꂽ31600�N�O����2�̂ɑ�\�����c��n���ł��iSikora et al., 2019�A�֘A�L���j�B���̑c��n���́A24500�`24100�N�O���ƂȂ�V�x���A�암�����̃}���^�iMal'ta�j��Ղ̏��N�́iMA-1�j�ɑ�\�����Ñ�k���[���V�A�l�iANE�j�̑c��Ƃ���ASikora et al., 2019�ł͌Ñ�k�V�x���A�l�iANS�j�ƕ��ނ���Ă��܂��BMA-1�̓A�����J�嗤��Z���Ƃ̋�����`�I�ގ������w�E����Ă���iRaghavan et al., 2014�A�֘A�L���j�AMA-1�ɑ�\�����ANE�́A�����Ƀ��[���V�A�����c��n���ō\���������̂́AEEI�c��n���̉e�������ȏ�i27%�j�Ă���A�Ɛ�������܂��iMao et al., 2021�j�B����́AANS��ANE�ɋ敪���܂��BANE�֘A�c��n���́A����̃A�����J�嗤��Z����V�x���A�l��[���b�p�l�ȂǂɈ�`�I�e�����c���Ă��܂��B �@�d�v�Ȃ̂́A�c���̂ƃT���L�[�g�̂�AR33K�̔N�オ��������A26500�`19000�N�O���ƂȂ�ŏI�X���ɑ���iLast Glacial Maximum�A������LGM�j�����O�ŁA����l�ɂ͈�`�I�e�����c���Ă��Ȃ��A�Ɛ�������Ă��邱�Ƃł��iMao et al., 2021�j�B��k�ɕ���O��EEI�֘A�c��n���ł����ɍ\������邱���̌̂ɑ�\�����W�c�́A�A���[���여�悩�烂���S���k�����܂ŁALGM�O�ɂ̓A�W�A�����k���ɂ����čL�͂ɑ��݂����A�Ɛ�������܂��B�܂�A�A�W�A��������l�̎�v�Ȓ��ړI�c��W�c�́ALGM�O�ɂ͑��n��ɑ��݂����\���������A�A�W�A�����ł����[���b�p�Ɠ��l�ɏ��������l�ޏW�c�̍L�͂Ȑ�ŁE�u�����N�����\���͍����A�Ƃ����킯�ł��B�������A�Ñ�Q�m�������ł͕W�{��������߂Č���I�Ȃ̂ŁA�c���̂Ȃǂɑ�\������ŏW�c�ƃA�W�A��������l�̎�v�Ȓ��ړI�c��W�c���אڂ��ċ������Ă����A�Ƃ��z��ł���킯�ł����A���̉\���͒Ⴂ�ł��傤�B �@�A�W�A�����̌Ñ�Q�m�������̓��[���V�A�����A�Ƃ��Ƀ��[���b�p�Ɣ�r���Ēx��Ă���̂ŁA�A�W�A��������l�̎�v�Ȓ��ړI�c��W�c�����A�W�A�����ɓ��������̂��A�قƂ�ǖ��炩�ɂȂ��Ă��܂���B�A���[���여��͂��̉𖾂���r�I�i��ł���n��ƌ��������ŁALGM������19000�N�O���ɂ́AAR33K�����A�W�A��������l�ƈ�`�I�ɂ����Ƌ߂��́iAR19K�j�����݂��A14000�N�O���ɂ͂�蒼�ړI�Ɍ���l�ƈ�`�I�Ɋ֘A����W�c�iAR14K�j�����݂������Ƃ���A�A���[���여��ł͌���ɂ܂Ŏ���14000�N�ȏ�̐l�ޏW�c�̈�`�I�A�������w�E����Ă��܂��iMao et al., 2021�j�BAR19K��EEI�ł�����n�iEEIS�j�����k���n�iEEIN�j�ɋ߉��ŁA19000�N�O���܂łɂ�EEI�̓�k�̕��N���Ă����A�ƍl�����܂��B�ȉ��A�����̌n���W��������Mao et al., 2021�̐}3�ł��B
�摜
���A�W�A��������l�̌`���ߒ�
�@���ăA�W�A�����k���ɁA4���N�O���̓c���̂Ɨގ�������`�I�\���̏W�c���L�͂ɑ��݂��A����l�ɂ͈�`�I�e�����i�S���Ⴕ���͖w�ǁj�c���Ă��Ȃ��A�܂��ł����ƂȂ�ƁA��q�̂悤�ɁA�A�W�A��������l�̎�v�Ȓ��ړI�c��W�c�́ALGM�O�ɂ͑��n��ɑ��݂����\���������Ȃ�܂��B�ł́A�����̏W�c�����ǂ̂悤�Ȍo�H�ŃA�W�A�����Ɋg�U���Ă����̂��A�Ƃ�����肪�����܂��B���������l�ނ̃Q�m���f�[�^�ƍl�Êw�����ď��������l�ނ̊g�U��������Vallini et al., 2021�́A�E�X�`�C�V���̂�c���̂�o�`���L�����A��4���N�ȏ�O�̌̌Q�ɑ�\����鏉����EEI�W�c���A�����㕔���Ί�iInitial Upper Paleolithic�A�ȉ�IUP�j�̒S���肾�����\�����w�E���܂��BIUP�́A�����@�����iLevallois�j��@���p����ΐn����Ƃ��čL�͂ɒ�`����i���c., 2019�A�֘A�L���j�A�����@���g���N�_�Ƃ��āA���[���b�p�����E�A�W�A�������E�A���^�C�n��E�����k���ɓ_�݂��܂��B�i���c., 2020�A�֘A�L���j�B �@Vallini et al., 2021�́A���̌�A���[���V�A�����̂ǂ����ɑ��݂����o�A�t���J��̐l���W�c�́u�ڑ��n�v����A�ΐn����я��^�ΐn�ibladelet�j�̐���ɂ������Â����A�����i�⍜����悭�����㕔���Ί�iUP�j�̒S����ł��郆�[���V�A�����c��n���ł����ɍ\�������W�c�����[���V�A�K�͂Ŋg�債�A���[���V�A�����ł́A�ݗ���EEI�֘A�c��n������̂Ƃ���W�c�Ƃ̍����ɂ��A31600�N�O���ƂȂ郄�iRHS��2�̂ɑ�\�����ANE�i��������ANS�j�W�c���`�����ꂽ�A�Ɛ�������܂��B��q�̂悤�ɁA34000�N�O���ƂȂ郂���S���k�����̃T���L�[�g�̂�ANE�W�c������ȏ�̈�`�I�e�����Ă��܂��B�������A�A�W�A�����ł����l�̎�v�Ȓn��i�ߌ�����{�Љ�ň�ʓI�Ɂu�����v�ƔF�������悤�Ȓn��j�⒩�N��������т��̎��ӂ̃��[���V�A�������ݒn�����{�ł́A�Ñ�l�ł�����l�ł����[���V�A�����֘A�c��n���̌����ȉe���͌��o����Ă��܂���BVallini et al., 2021�́A�����̒n��ɂ����āA�N�����Ă���UP�l���W�c�̈ړ��ɑ���IUP�̒S���肾����EEI�W�c�̒�R�A��������EEI�W�c�̍Ċg�傪�N�����\�����w�E���܂��B �@EEI�W�c���ǂ̂悤�ɃA�W�A�����Ɋg�U���Ă����̂��s���ł����A�����ʂł�IUP�Ɗ֘A���Ă���Ƃ�����A���[���V�A���ܓx�n�т𓌐i���Ă����\�����������Łi���[���V�A��݂𓌐i���ăA�W�A�암���쓌���Ŗk�サ���\�����l�����܂����j�A���̓��i�̉ߒ��ň�`�I�ɕ������āA�c���̂�AR33K�ɑ�\�����W�c�ƁA�A�W�A��������l�̎�v�Ȓ��ړI�c��W�c�Ƃɕ����̂ł��傤�B�������A���ۂ̐l���j�͂��̂悤�Ɍn�����ŒP���ɕ\���Ȃ��ł��傤����A�����܂ł���܂��Ɂi��𑜓x�Łj�����������ɂ����܂��B�A�W�A��������l�̎�v�Ȓ��ړI�c��W�c��LGM�̑O��ɂǂ��ɂ����̂��A�����_�ł͒��ړI�Ȉ�`�I�肪����͂Ȃ��A�A�W�A�����ł͍X�V���̌����l�ވ�[�����Ȃ��̂ŁA�ŋߋ}���ɔ��W���Ă��铴�A�̓y��DNA��́i�V����., 2021�j�Ɉˋ����邵���Ȃ������ł��B �@�����AEEI�̓�k�̕���iEEIS��EEIN�j��19000�N�O���܂łɋN�������ƂƁA�V���x���^�؎��̕p�x����A������x�̐����͉\��������܂���B�V���x���^�؎��́A�A�����J�嗤��Z������{�l���܂߂ăA�W�A��������l�ł͍��p�x�Ō����A�k���̊��l�iCHB�j�ł͕p�x��93.7%�ɒB���܂����A�A�W�A�쓌����I�Z�A�j�A�ł͒�p�x�ł��B�V���x���^�؎��̓G�N�g�W�X�v���V��A��e�́iEDAR�j��`�q�̈ꉖ��^rs3827760��V370A�ψقƂ̊֘A�����炩�ɂȂ��Ă���iKataoka et al., 2021�A�֘A�L���j�A���̕ψق͔h���I�ŁA�o����3���N�O���Ɛ�������Ă��܂��iHarris.,2016,P242�A�֘A�L���j�BMao et al., 2021�́A���̔h���I�ψق��A�W�A�����k���ł́ALGM�O�̓c���̂�AR33K�ɂ͌����Ȃ����̂́A19000�N�O���ƂȂ�AR19K���܂ނ���ȍ~�̃A�W�A�����k���̌̂Ō����邱�Ƃ���ALGM�̒ᎇ�O�����ɂ��������̃r�^�~��D�����ւ̑I���������A�Ƃ̌����iHlusko et al., 2018�A�֘A�L���j���x�����Ă��܂��B �@�����̒m������A����̃A�W�A�����l��A�����J�嗤��Z���ɂ����č��p�x�Ō�����V���x���^�؎��́AEEIN�W�c�ɂ�����EEIS�W�c�Ƃ̕����ɏo�������A�Ɛ�������܂��B��q�̂悤�ɁAEEIS��EEIN�̕����19000�N�O���������̂ڂ�܂�����A�V���x���^�؎��̏o���N��̉�����2���N�O���ƂȂ肻���ł��B����ɁA��f��Mao et al., 2021�̐}3�Ŏ������悤�ɁA�A�����J�嗤��Z���ƈ�`�I�ɂ���߂ċ߉��ȁA�A���X�J�̃A�b�v�E�H�[�h�T����iUpward Sun River�j�Ŕ������ꂽ1�́iUSR1�j�͌Ñ�x�[�����W�A�i�x�[�����O�����j�l��\���AANE�֘A�c��n���i42%�j��EEIN�֘A�c��n���i58%�j�̍����Ƃ��ă��f�����ł��܂��B�Ñ�x�[�����W�A�l�̈���̎�v�ȑc��ł���EEIN�֘A�W�c�͑���EEIN�W�c��36000�}15000�N�O���ɕ������̂́A25000�}1100�N�O���܂ŗ��҂̊Ԃɂ͈�`�q�������������A�Ɛ�������Ă��܂��iMoreno-Mayar et al., 2018�A�֘A�L���j�B �@��������ƁA25000�N�O���܂łɂ̓V���x���^�؎����o�����Ă������ƂɂȂ肻���ł��BEEIN��EEIS��4���N�O���܂łɂ͕��A�V���x���^�؎��������炷�ψق�EEIN�ɂ�����3���N�O���܂łɂ͏o�����ALGM�ɂ����đI������A�A�W�A��������l�ƃA�����J�嗤��Z���̑c��W�c�ɂ����č��p�x�Œ蒅�����A�ƍl�����܂��B���̐������Ó��Ȃ�AEEIN�W�c�́AEEIS�W�c�ƈ�`�I�ɕ���������A�A���[���여�����S�������k���ɕ��z���A2���N�O���܂łɂ̓A���[���여��ɓ쉺���Ă����A�ƍl�����܂��B����AEEIS�W�c�́A���]����Ȃnj��݂̒����암��LGM�O�ɓ��B���Ă����̂�������܂���B���̒m���ł́A���̐������l�Êw�Ƒg�ݍ��킹�Ę_���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ŁA����̉ۑ�ƂȂ�܂��B�܂��V���x���^�؎��Ɋւ��邱���ߔN�̒m������A�V���x���^�؎����u�k�����l�v����A�W�A��������l�̘A���I�Ȑi���̍����Ƃ���悤�Ȍ����i�֘A�L���j�͂قڊ��S�ɔے肳�ꂽ�A�ƌ�����ł��傤�B
�����{�̐l���j
�@���{�ł�4���N���ȍ~�Ɉ�Ղ��}�����܂��i����., 2013�A�֘A�L���j�B4���N�ȏ�O�ƂȂ���{�ɂ�����l�ނ̍��ՂƂ��ẮA���Ƃ���12���N�O���Ƃ���铇�����o�_�s�̍�����Ղ̐Ί킪����܂����A���ꂪ�{���ɐΊ�Ȃ̂��A�����^�₪�悳��Ă��܂��i�֘A�L���j�B�����炭���E�ł��L���̍X�V����Ղ̔��@���x���ւ邾�낤���{�ɂ����āA4���N�ȏ�O�ƂȂ�l�ނ̍��Ղ�����߂ď��Ȃ��A�܂�������Ղ̂悤�ɋ����^�₪�悳��Ă��鎖������邱�Ƃ́A���ɂ���炪�{���ɐl�ނ̍��Ղ������Ƃ��Ă��A4���N�O�ȍ~�̓��{�̐l�ނƂ͈�`�I�ɂ������I�ɂ��֘A���Ȃ����Ƃ������������܂��B������{�l�̌`���Ƃ����ϓ_����́A���{�ł�4���N�O�ȍ~�̈�Ղ݂̂��ΏۂƂȂ�ł��傤�B �@���{�̍X�V���l�ވ�[��DNA��͂́A�ŋߕ��ꂽ2���N�O���̍`��l��mtDNA���ŏ��̎���ƂȂ�iMizuno et al., 2021�A�֘A�L���j�A�قƂ�lj𖾂���Ă��܂���B���{�ŌÑ�Q�m���f�[�^�������Ă���l�ވ�[�͊��V���Ɍ��肳��Ă���A�ꕶ����ȍ~�ƂȂ�܂��B���m���c���s�ɐ�Ò��̊L�˂Ŕ������ꂽ2500�N�O���ƂȂ�ꕶ����̂̊j�Q�m����͌��ʂ���������ł́A�u�ꕶ�l�i�ꕶ�����֘A�́j�v��38000�N�O���ɓ��{�ɓ����������Ί펞��W�c�̒��ړI�q���ł���A�Ƃ����������x������Ă��܂��iGakuhari et al., 2020�A�֘A�L���j�B�������A�`��l��mtDNA�́A���Ȃ��Ƃ������_�ł͌���l�Ō������Ă��炸�A���[���b�p��A�W�A�����嗤���Ɠ��l�ɁA���{�ł��X�V���ɓ����������������l�ނ̒��ɐ�ł����W�c�����݂����\���͍����悤�Ɏv���܂��B���̖��̉𖾂ɂ́A�ŋߋ}���ɔ��W���Ă��铴�A�̓y��DNA��͂��傫���v���ł��邩������܂���B �@�u�ꕶ�l�v�̃Q�m���f�[�^�́A��q�̈��m���Ŕ������ꂽ��[�݂̂Ȃ炸�A�k�C���iKanzawa-Kiriyama et al., 2019�A�֘A�L���j���t���iWang et al., 2021�j�⍲�ꌧ�iAdachi et al., 2021�A�֘A�L���j�̈�[�ł������Ă��܂��B�����ꕶ����̌���k�C���̌̂��瑁����B�̌̂܂ŁA����܂łɃQ�m���f�[�^�������Ă���ꕶ�l�̈�`�I�\���͂Ђ��傤�ɗގ����Ă���A�ꕶ�l�������I�ɂ͂Ƃ�������`�I�ɂ͒����ɂ킽���Ă���߂ċώ����������Ƃ��������܂��B�������A������{�l�̌`���ɂ����ďd�v�ƂȂ邾�낤�����{�̓ꕶ�������`�ӊ��̌̂̃Q�m���f�[�^���~�ς���Ȃ������́A�ꕶ�l�������ɂ킽���Ĉ�`�I�ɋώ��������Ƃ́A�ƂĂ��f��ł��܂���B �@�ꕶ�l��EEIS�֘A�c��n���i56%�j��EEC�֘A�c��n���i44%�j�̍����Ƃ��āA������{�́u�i�{�B�E�l���E��B�𒆐S�Ƃ���j�{�y�v�W�c�͓ꕶ�l�i8%�j�Ɛ��펞�㐼�ɉ͏W�c�i92%�j�̍����Ƃ��ă��f�����ł��A���͗���V�Ί펞��_�k���W�c�̒��ړI�Ȉ�`�I�e���͖����ł���قǒႢ�A�Ɛ�������Ă��܂��iWang et al., 2021�j�B�ꕶ�l�̃V���x���^�؎��̒��x�͂킸���Ȃ̂ŁiKanzawa-Kiriyama et al., 2019�j�A���̓_������A�ꕶ�l��EEIN�֘A�c��n������{�I�ɂ͗L���Ȃ��A�Ƃ̐���͑Ó��Ǝv���܂��B����ŁAEEIN�֘A�c��n���ł����ɍ\���������펞�㐼�ɉ͏W�c����v�ȑc��W�c�Ƃ��錻����{�l�i�u�{�y�v�W�c�j�ɂ����ẮA�V���x���^�؎������p�x�ł��B�����́A�V���x���^�؎��Ɋւ����q�̐����Ɛ����I�ł��B �@�ꕶ�l��YHg�ł����ڂ���Ă��܂��B������{�l�i�u�{�y�v�W�c�j�ł�YHg-D1a2a��35.34%�Ƒ傫�Ȋ������߂Ă���A�iWatanabe et al., 2021�A�֘A�L���j�k�C���ȂǏ�q�̓ꕶ�l�ł�YHg���m�F����Ă���̂͑S��D1a2a�ŁA���{�O�ł͒�p�x�ł��邱�Ƃ���AYHg-D1a2a�͓��{�ŗL�Ƃ̔F������ʓI�Ȃ悤�ł��B�������A�J�U�t�X�^���암�Ŕ������ꂽ�I����236�`331�N����1�́iKNT004�j��YHg-D1a2a2a�iZ17175�ACTS220�j�ł��iGnecchi-Ruscone et al., 2021�A�֘A�L���j�BKNT004��ADMIXTURE���͂ł́A���N�����ɋ߂����V�A�̉��ݒn��̈����̖��Ղ�7700�N�O���̌̌Q�iSiska et al., 2017�A�֘A�L���j�ɑ�\�����n���\���v�f�i�A�W�A�k�����l�c��n���j�̊����������A�����̖��Ռ̌Q��AR14K�ƈ�`�I�ɂ���߂Ė��ڂł��B�܂��A�A���[���여���11601�`11176�N�O����1�́iAR11K�j�́AYHg-DE�ł��B�A���[���여���YHg-E�����݂����Ƃ͍l���ɂ����̂ŁAYHg-D�ł���\��������߂č������ł��B �@YHg-D�̓A�W�A�쓌���̌Ñ�l�ł��m�F����Ă���A�z�A�r�������iHòabìnhian�j�w�Ō��������A�r���N���4415�`4160�N�O����1�́iMa911�j��YHg-D1�iM174�j�ł��iMcColl et al., 2018�A�֘A�L���j�B�ق�EEC�֘A�c��n���ō\�������A���_�}����������l��YHg���ق�D1�ŁAYHg-D1�̊�������������`�x�b�g�l��EEC�֘A�c��n���̊�����20%�߂��Ɛ��肳��܂��iWang et al., 2021�j�B�܂��A�ꕶ�l�ƈ����̖��Ռ̌Q�ȂǃA�W�A�������ݕ��W�c�Ƃ̈�`�I�ގ������w�E����Ă��܂��iGakuhari et al., 2020�j�BEEC�֘A�c��n����L����W�c���A�W�A�������ݕ������Ȃ�̒��x�k�サ�����Ƃ́A�ꕔ�̃A�����J�嗤��Z���W�c�ŃA���_�}�������l�ȂǂƂ̈�`�I�ގ������w�E����Ă��邱�ƁiCastro e Silva et al., 2021�A�֘A�L���j��������炩�ł��傤�B �@�����̒m������́AYHg-D1�͂�����EEC�֘A�c��n���ō\������錻���l�ޏW�c�ɗR�����A���[���V�A��݂𓌐i���ăA�W�A�쓌������I�Z�A�j�A�ւƊg�U���āA�A�W�A�쓌������k�サ�ăA�W�A�����ւƊg�U�������Ƃ��M���܂��B�J�U�t�X�^���̋I����3�`4���I�̌́iKNT004�j��YHg-D1a2a2a�ŁA�����̖��Ղ�7700�N�O���̌̌Q�ɑ�\�����n���\���v�f�i�A�W�A�k�����l�c��n���j�̊������������Ƃ�����AYHg-D1a2a�͓��{�ŗL�ł͂Ȃ��A�A�W�A�������ݕ��𒆐S�ɂ��Ă͍L�͂ɃA�W�A�����ɑ��݂��A�ꕶ����̎n�܂�O�ɓ��{�ɓ��������A�Ɛ�������܂��B������{�l�Ō�����YHg-D1a2a1��D1a2a2�̕�����A���{�ł͂Ȃ��A�W�A�����嗤���ŋN���Ă�����������܂���B��������ƁA4���N�O���܂ł����̂ڂ���{�̍ŏ��������l�ނ�YHg��D1a2a�ł͂Ȃ�������������܂���B�܂��AKNT004�̎��Ⴉ��́A������{�l��YHg-D1a2a2a�̒��ɂ́A�퐶����ȍ~�ɓ����������̂���������������Ȃ��A�ƍl�����܂��B �@���{�̍ŏ��������l�ނ��ꕶ�l�̒��ړI�c��Ȃ̂��ۂ��A�ꕶ�l���ǂ̂悤�ȉߒ��Ō`�����ꂽ�̂��A�����_�ł͕s���ł����A���{���܂߂ă��[���V�A�����̓��A�̓y��DNA��͂ɂ��A���̖��̉𖾂��i�ނƊ��҂���܂��B����A������EEI�֘A�c��n���ō\�������W�c��YHg�Ɋւ��ẮA�c���̂��i����., 2021�jK2b�ŁA�A���[���여���19000�N�O���ȍ~�̌̂�������C��������C2�ł��邱�Ƃ���AC��K2�̍��݂�������������܂���BYHg-K2������{�l���܂߂ăA�W�A��������l�ő����h��O���h������̂ŁA���̓_���j�Q�m���ł̓A�W�A��������l��������EEI�֘A�c��n���ō\������邱�ƂƐ����I�ł��B ���܂Ƃ� �@�l�ޏW�c�̒n��I�A�����Ƃ̊ϔO�ɂ͍��������̂����肻���ŁA���ꂪ������`�▯����`�Ƃ����т��₷�������ɁA�x�����K�v���Ƃ͎v���܂��B�ߔN�̌Ñ�Q�m�������̐i�W����́A�l�A���f���^�[���l�Ȃǐ�Ńz�����i�Ñ�^�z�����j�ƌ���l�Ƃ̓���n��ɂ������`�I�s�A�����͂������A�����l�ނɌ��肵�Ă��A�X�V���Ɗ��V���ɂ����ďW�c�̐�ŁE�u���͒������Ȃ��������Ƃ���������܂��B����ɁA���l�ރz�����ɂ����Ă��A������������n��ɂ�����l�ޏW�c�̐�ŁE�u���͒������Ȃ��������Ƃ���������Ă��܂��B �@��̓I�ɂ́A�A���^�C�R���̃l�A���f���^�[���l�́A�����̌̂Ƃ���ȍ~�̌̌Q�ň�`�I�n�����قȂ�A�u�����������A�Ɛ�������Ă��܂��iMafessoni et al., 2020�A�֘A�L���j�B�܂��A�C�x���A�����k���ɂ����Ă��A���A�͐ϕ���DNA��͂���l�A���f���^�[���l�W�c�ԂŒu�����������A�Ɛ�������Ă��܂��iVernot et al., 2021�A�֘A�L���j�B���݂̃h�C�c�Ŕ������ꂽ�l�A���f���^�[���l�Ɗ֘A�Â���ꂻ���Ȉ�Ղ̔�r����́A�l�A���f���^�[���l�W�c���ڏZ�E�P�ނ������͐�ŁE�i�Ǘ������W�c�̑ޔ�n����́j�ĈڏZ�Ƃ������ߒ����J��Ԃ��Ă������Ƃ��M���܂��iRichter et al., 2016�A�֘A�L���j�B �@�����������[���b�p�ɂ����镡�G�ȉߒ��̌J��Ԃ��ɂ�����l�A���f���^�[���l�͌`�����ꂽ�̂ł��傤���A����̓A�t���J�ɂ����錻���l�ނ����l�������A�ƍl�����܂��iScerri et al., 2018�A�֘A�L���j�B����ɂ����A�z�����i�֘A�L���j�⑼�̑����̐l�ތn���̕��ތQ�̏o���ߒ������l�ŁA����̒n��ɂ�����P���Ȓ����I�i���Ŕc�����邱�Ƃ͊댯�ł��傤�B���̈Ӗ��ŁA���Ƃ��Β��ؐl�����a��蟐��Ȃ̈�ՂɊւ��ẮA210���`130���N�O���ɂ����Đl�ނ��J��Ԃ����p������������Ȃ��A�Ǝw�E����Ă��܂����iZhu et al., 2018�A�֘A�L���j�A�����̏W�c���S�đc��E�q���W�ɂ������Ƃ͌���܂���B �@���̈Ӗ��ŁA�O���X�V������̃A�t���J�ƃ��[���V�A�̍L�͂Ȓn��ɂ�����l�ނ̘A����������ɂ��錻���l�ރA�t���J���n��i�����͍��{�I�ɊԈ���Ă���A�ƕ]�����ׂ��Ȃ̂ł��傤�iScerri et al., 2019�A�֘A�L���j�B����̓��[���V�A�����������Ɋւ��ĂقƂ�nj��y�ł��܂���ł������A�o�C�J���Βn��ł͍X�V�����犮�V���ɂ����Č����l�ޏW�c�̑傫�Ȉ�`�I�ϗe��u�����������A�Ɛ�������Ă��܂��iYu et al., 2020�A�֘A�L���j�B�܂������S���Ɋւ��ẮA���V���ɂ����čŏ��ɖq�{�����������炵���W�c�̈�`�I�\���͔�r�I�Z���ԂŎ���ꂽ�A�Ɛ�������Ă��܂��iJeong et al., 2020�A�֘A�L���j�B �@�����͏�q�����I�[�X�g�����A�̎���ł����Ă͂܂邩�����ꂸ�A65000�N�O���̐l�ނ̍��Ղ��{�����Ƃ��Ă��A���ꂪ����̃I�[�X�g�����A��Z���ƘA�����Ă��邩�ǂ����͕s���ŁAmtDNA�Ő��������5���N�߂��ɂ킽��I�[�X�g�����A�̐l�ނ̘A�����Ƃ̌������A�Ñ�DNA�f�[�^�������Ȃ���Ίm��͓���ł��傤�i�I�[�X�g�����A�ōX�V���̐l�ވ�[��͐ϕ�����DNA����͂���͓̂�����ł����j�B���{�����l�ŁA4���N�ȏ�O�Ƃ����s�m���Ȉ�Ղ͂������A4���N�O�ȍ~�̐l�ށA�Ƃ��ɍŏ����̐l�ނɊւ��ẮA�ꕶ�l�Ȃǂ��̌�̓��{�̐l�ނƈ�`�I�ɂȂ����Ă���̂��A�܂����f������Ƃ���ł��B���{�̐l���j�Ɋւ��ẮA�l�ވ�[�����DNA��͂ƂƂ��ɁA�X�V���͐ϕ���DNA��͂�����I�Ɍ�����i�W������̂ł͂Ȃ����A�Ɗ��҂��Ă��܂��B �@�������A��L�̎����͂����܂ł������_�ł̃f�[�^�Ɋ�Â����f�����Ɉˋ����Ă���̂ŁA����̌����̐i�W�ɂ��傫���ς�����Ȃ��Ƃ�����o�Ă���\���͒Ⴍ����܂���B�܂��A����͓���̒n��ɂ�����l�ޏW�c�̒����̘A�����Ƃ��������ɑ���^����������܂������A�t�ɁA���Ղɓ���̒n��ɂ�����l�ޏW�c�̒f���f�肷�邱�Ƃ����ł��傤�B���Ƃ��A������{�Љ�ɂ����āu�����I�ȁv�l�X�̊ԂōD�܂�Ă���炵���A�O������̑O��ɂ����āu�����l�v�������́u�������v�͐�ł����A�Ƃ����������ł��B�Ñ�Q�m���f�[�^���p���������ł́A����V�Ί펞�ォ�猻��̒����i�����ނˌ��݂͓̉�ȁE�R���ȁE�R���ȁj�ɂ����钷���̈�`�I�ގ����E���萫�̉\�����w�E����Ă��܂��iWang et al., 2020�A�֘A�L���j�B�������A��`�I�\���Ɩ����A����ɕ����́A���ւ���ꍇ�������Ƃ͂����A���ՂɌ��т��Ă͂Ȃ�܂��A�u�����v�ɂ�����l�ޏW�c�̘A������_����ꍇ�ɂ́A���������Q�m���������ł��Ȃ��A�Ƃ��l���Ă��܂��B �Q�l�����F Adachi N. et al.(2021): Ancient genomes from the initial Jomon period: new insights into the genetic history of the Japanese archipelago. Anthropological Science, 129, 1, 13–22.
https://doi.org/10.1537/ase.2012132
Bergström A. et al.(2021): Origins of modern human ancestry. Nature, 590, 7845, 229–237.
https://doi.org/10.1038/s41586-021-03244-5
Castro e Silva MA. et al.(2021): Deep genetic affinity between coastal Pacific and Amazonian natives evidenced by Australasian ancestry. PNAS, 118, 14, e2025739118.
https://doi.org/10.1073/pnas.2025739118
Chan EKF. et al.(2019): Human origins in a southern African palaeo-wetland and first migrations. Nature, 575, 7781, 185–189.
https://doi.org/10.1038/s41586-019-1714-1
Clarkson C. et al.(2017): Human occupation of northern Australia by 65,000 years ago. Nature, 547, 7663, 306–310.
https://doi.org/10.1038/nature22968
Fu Q. et al.(2014): Genome sequence of a 45,000-year-old modern human from western Siberia. Nature, 514, 7523, 445–449.
https://doi.org/10.1038/nature13810
Fu Q. et al.(2015): An early modern human from Romania with a recent Neanderthal ancestor. Nature, 524, 7564, 216–219.
https://doi.org/10.1038/nature14558
Gakuhari T. et al.(2020): Ancient Jomon genome sequence analysis sheds light on migration patterns of early East Asian populations. Communications Biology, 3, 437.
https://doi.org/10.1038/s42003-020-01162-2
Gnecchi-Ruscone GA. et al.(2021): Ancient genomic time transect from the Central Asian Steppe unravels the history of the Scythians. Science Advances, 7, 13, eabe4414.
https://doi.org/10.1126/sciadv.abe4414
Gokcumen O.(2020): Archaic hominin introgression into modern human genomes. American Journal of Physical Anthropology, 171, S70, 60–73.
https://doi.org/10.1002/ajpa.23951
Hajdinjak M. et al.(2021): Initial Upper Palaeolithic humans in Europe had recent Neanderthal ancestry. Nature, 592, 7853, 253–257.
https://doi.org/10.1038/s41586-021-03335-3
Harris EE.��(2016)�A���J�~��w�Q�m���v���@�q�g�N���̐^���x�i���쏑�[�A�����̊��s��2015�N�j
Hlusko LJ. et al.(2018): Environmental selection during the last ice age on the mother-to-infant transmission of vitamin D and fatty acids through breast milk. PNAS, 115, 19, E4426–E4432.
https://doi.org/10.1073/pnas.1711788115
Jeong C. et al.(2020): A Dynamic 6,000-Year Genetic History of Eurasia�fs Eastern Steppe. Cell, 183, 4, 890–904.E29.
https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.10.015
Kanzawa-Kiriyama H. et al.(2019): Late Jomon male and female genome sequences from the Funadomari site in Hokkaido, Japan. Anthropological Science, 127, 2, 83–108.
https://doi.org/10.1537/ase.190415
Kataoka K. et al.(2021): The human EDAR 370V/A polymorphism affects tooth root morphology potentially through the modification of a reaction–diffusion system. Scientific Reports, 11, 5143.
https://doi.org/10.1038/s41598-021-84653-4
Kuhlwilm M. et al.(2019): Ancient admixture from an extinct ape lineage into bonobos. Nature Ecology & Evolution, 3, 6, 957–965.
https://doi.org/10.1038/s41559-019-0881-7
Manuel M. et al.(2016): Chimpanzee genomic diversity reveals ancient admixture with bonobos. Science, 354, 6311, 477-481.
https://doi.org/10.1126/science.aag2602
Mao X. et al.(2021): The deep population history of northern East Asia from the Late Pleistocene to the Holocene. Cell, 184, 12, 3256–3266.E13.
https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.04.040
Massilani D. et al.(2020): Denisovan ancestry and population history of early East Asians. Science, 370, 6516, 579–583.
https://doi.org/10.1126/science.abc1166
McColl H. et al.(2018): The prehistoric peopling of Southeast Asia. Science, 361, 6397, 88–92.
https://doi.org/10.1126/science.aat3628
Mizuno F. et al.(2021): Population dynamics in the Japanese Archipelago since the Pleistocene revealed by the complete mitochondrial genome sequences. Scientific Reports, 11, 12018.
https://doi.org/10.1038/s41598-021-91357-2
Moreno-Mayar JV. et al.(2018): Terminal Pleistocene Alaskan genome reveals first founding population of Native Americans. Nature, 553, 7687, 203–207.
https://doi.org/10.1038/nature25173
O�fConnell JF. et al.(2018): When did Homo sapiens first reach Southeast Asia and Sahul? PNAS, 115, 34, 8482–8490.
https://doi.org/10.1073/pnas.1808385115
Petr M. et al.(2020): The evolutionary history of Neanderthal and Denisovan Y chromosomes. Science, 369, 6511, 1653–1656.
https://doi.org/10.1126/science.abb6460
Prüfer K. et al.(2021): A genome sequence from a modern human skull over 45,000 years old from Zlatý kůň in Czechia. Nature Ecology & Evolution, 5, 6, 820–825.
https://doi.org/10.1038/s41559-021-01443-x
Raghavan M. et al.(2014): Upper Palaeolithic Siberian genome reveals dual ancestry of Native Americans. Nature, 505, 7481, 87–91.
https://doi.org/10.1038/nature12736
Robert A.��(2013)�A�쒆�����q��w�l��20���N�y���Ȃ闷�H�x�i���Y�t�H�ЁA�����̊��s��2009�N�j
Scerri EML, Chikhi L, and Thomas MG.(2019): Beyond multiregional and simple out-of-Africa models of human evolution. Nature Ecology & Evolution, 3, 10, 1370–1372.
https://doi.org/10.1038/s41559-019-0992-1
Schlebusch CM. et al.(2021): Human origins in Southern African palaeo-wetlands? Strong claims from weak evidence. Journal of Archaeological Science, 130, 105374.
https://doi.org/10.1016/j.jas.2021.105374
Shreeve J.��(1996)�A���J��Y��w�l�A���f���^�[���̓�x�i�p�쏑�X�A�����̊��s��1995�N�j
Sikora M. et al.(2019): The population history of northeastern Siberia since the Pleistocene. Nature, 570, 7760, 182–188.
https://doi.org/10.1038/s41586-019-1279-z
Siska V. et al.(2017): Genome-wide data from two early Neolithic East Asian individuals dating to 7700 years ago. Science Advances, 3, 2, e1601877.
https://doi.org/10.1126/sciadv.1601877
Svensson E. et al.(2021): Genome of Peştera Muierii skull shows high diversity and low mutational load in pre-glacial Europe. Current Biology.
https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.04.045
Tobler R et al.(2017): Aboriginal mitogenomes reveal 50,000 years of regionalism in Australia. Nature, 544, 7649, 180–184.
https://doi.org/10.1038/nature21416
Vallini L. et al.(2021): Genetics and material culture support repeated expansions into Paleolithic Eurasia from a population hub out of Africa. bioRxiv.
https://doi.org/10.1101/2021.05.18.444621
Wang CC. et al.(2021): Genomic insights into the formation of human populations in East Asia. Nature, 591, 7850, 413–419.
https://doi.org/10.1038/s41586-021-03336-2
Watanabe Y et al.(2019): Analysis of whole Y-chromosome sequences reveals the Japanese population history in the Jomon period. Scientific Reports, 9, 8556.
https://doi.org/10.1038/s41598-019-44473-z
Yang MA. et al.(2017): 40,000-Year-Old Individual from Asia Provides Insight into Early Population Structure in Eurasia. Current Biology, 27, 20, 3202–3208.
https://doi.org/10.1016/j.cub.2017.09.030
Yang MA. et al.(2020): Ancient DNA indicates human population shifts and admixture in northern and southern China. Science, 369, 6501, 282–288.
https://doi.org/10.1126/science.aba0909
Yu H. et al.(2020): Paleolithic to Bronze Age Siberians Reveal Connections with First Americans and across Eurasia. Cell, 181, 6, 1232–1245.E20.
https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.04.037
�����G�V(2013)�u���{�̐����Ǝ�̏W�̎Љ�v�w��g�u���@���{���j�@ ��1���@���n�E�Ñ�1�xP27-62
�V���肩���A�ӒJ���A�Γc��(2021)�u�A�W�A�����̃z�����Ɋւ��郌�r���[�v�w�p���I�A�W�A�����j�w�F�A�W�A�ɂ�����z���E�T�s�G���X�蒅�v���Z�X�̒n���I�ҔN�I�g�g�݂̍\�z2020�N�x�������iPaleoAsia Project Series 32�j�xP101-112
�������V(2021)�u�㕔���Ί펞��̖k���[���V�A�̐l�X�Ɋւ���Q�m�������v�w�p���I�A�W�A�����j�w�F�A�W�A�V�l�����`���v���Z�X�̑����I����2020�N�x�������iPaleoAsia Project Series 36�j�xP27-44
���c��l(2019)�uIUP�i����������Ί�Ί�Q�j���߂��錤���̌���v�w�p���I�A�W�A�����j�w�F�A�W�A�ɂ�����z���E�T�s�G���X�蒅�v���Z�X�̒n���I�ҔN�I�g�g�݂̍\�z2018�N�x�������iPaleoAsia Project Series 18�j�xP125-132
���c��l(2020)�u���{�ւ̐l�ވړ����l���邽�߂̊o�������v�w�p���I�A�W�A�����j�w�F�A�W�A�ɂ�����z���E�T�s�G���X�蒅�v���Z�X�̒n���I�ҔN�I�g�g�݂̍\�z2019�N�x�������iPaleoAsia Project Series 25�j�xP84-91
�g�c�K(2017)�u�ꕶ�ƌ�����{�̃C�f�I���M�[�v�w���������w�Z�~�i�[�u�l�Êw�ƌ���Љ�v2013-2016�xP264-270
https://doi.org/10.24517/00049063
https://sicambre.at.webry.info/202106/article_22.html
|
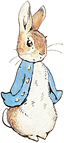
 �X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B