�������ȃ��J�[�h�̔�r�D�ʘ_2017�N05��09��
����̍��c���ق��A�W�A�J����s(ADB)�̔N������ŁA���Z����ɂ��āu(�o�ς�)���ȏ����ʂ�K�p�ł��Ȃ��v�ƁA���ڂ���ʂ�����܂����B �������c�O�Ȃ���A���c�����ǂ�ł��鋳�ȏ��͎Z���ł����A���̌o�ς͐��w�œ����Ă���̂ł���A�Ή������Ȃ��ē��R�ł��B �}�l�^���[�x�[�X���g�傷��C���t���A�Z���ł͂��������Ă���܂����A���w�ł͋��Z����̕������A�����̗��o���ʁA�l�����Ԃ���̏�����ȂǁA�l�X�Ȃ��̂���������܂��B ���{�ł͂�����}�l�^���[�x�[�X�𑝂₵�Ă��A����ア�̂ŕ������オ��Ȃ��B����Ȃ����烂�m�̉��l���オ��Ȃ��̂ł��B 3���̖����ΘJ���v�́A�����������O�N�������0.8%���B����ŏ������オ��킯������܂���B�������[���Ȃ̂́A�p�[�g�J���҂̎��ԓ����������2.1%���Ȃ̂ɁA����������2.2%���B�܂�P���͏オ��������ǘJ�����Ԃ����������߂ɁA���肪�������B ��Ƃ��J���͂��m�ۂ��悤�A�Ƃ��邽�߂ɔ����L���W�߂����ʁA��l��l�ɂ͉��b���s���킽��ɂ����B�����ċ��炭�A�����������͔N�������炳��鍂��҂̕�U�ɉ���Ă���̂ł���A����ł͌o�ς����܂����͂�������܂���B
����̂��銲�����A���Z�ɘa���~�߂ăC���t���ڕW�����B�ƂȂ����Ƃ��A�x�����R�X�g���c��A�Ƃ��ċ��Z������Â���A�Əq�ׂ܂����B�ȒP�Ɍ����A�����Ŏ~�߂�ƌi�C�����Ă��Ȃ�����A���₪���������Y�̃l�K�e�B�u�ȕ����ɂ�����R�X�g������̌o�c���������邩��A�Â��邵���Ȃ��B�Ƃ����_���o�c�҂̓T�^�̂悤�Ȃ��Ƃ������o�����̂ł��B
�c�O�Ȃ���A���₪���łƏd�Ȃ��Ă݂��܂��B���s������������������ł����A�D���ɛƂ܂��Ă����B���C�Ő����̂����������{�����Ƃ����A�������琳�����ǂ݉����Ȃ�����Ƃ����A���̍��ł͐��������łɂ��������Ȃ�n�߂Ă���̂ł��傤�B �u�o�ϊw�҂�9�������{�m�~�N�X�͊댯�v�Ƃ������ł́A��������s�ꂪ���������A����M���邩�A�������̍��ł͂��������Ȃ�n�߂Ă��܂��Ă���̂ł��傤�ˁB
http://blog.livedoor.jp/analyst_zaiya777/
�A���n�C���h�̌㊘�ɂ��ꂽ���{
�@���̓A�����J�̂��́u���܂��b�v�́A�P�X���I�ɔɉh������p�鍑���܂˂Ă��邾�����B��p�鍑�̏ꍇ�́A���̔ɉh�̓���Ƃ����̓C���h���͂��߂Ƃ���A���n�������Ă����B���Ƃ��Γ����C�M���X�̐A���n�ł������C���h�́A���h���Ȃǂ̌��ޗ���A�o���ăC�M���X��ɑ��z�̍������v�サ�Ă����B�Ƃ��낪�����̓��s�[�ł͂Ȃ��A�|���h���g���Č��ς���A���̂܂܃C�M���X�̋�s�ɗa�����Ă����B
�@������C�M���X�͂�����A���n��ɐԎ����o���Ă����C�������B�C�M���X�̋�s�ɗa����ꂽ�|���h���A�C�M���X�����Ŏg���������炾�B�C���h�͖��ڏ�͍��������A���������ɂȂ������A���̂������C�M���X�̋�s���玩�R�Ɉ����o���A�����̍��ł͎g���Ȃ������B�����̎g�����͗a���҂ł͂Ȃ��A�C�M���X�̋�s�����߂Ă������炾�B�����Ă������A�C�M���X�̋�s�͍����̐l�X�ɑ݂��o�����B �@�C�M���X�����͐A���n����A�������i���Ő��������̂��݁A���������͂�����|���h���C�M���X�̋�s�ɋz������A�C�M���X�̂��߂Ɏg����킯���B�������ăC�M���X�͂ǂ�ǂW�����B �@����A���n�͂ǂ��Ȃ������B���Ƃ��C���h�͏��i��A�o���Ă��A���̌��Ԃ�̑���̓|���h�ŃC�M���X�ɒ~�ς���邾��������A�����ɂ������܂��Ȃ��Ȃ�B�ǂ�ǂ�f�t���ɂȂ�A�s�i�C�ɂȂ����B
�d���������Ȃ�A������������A�܂��܂��K���œ����ėA�o����B�Ƃ��낪�������̑���́A�|���h�̂܂ܖ��`��̏��L�Ƃ��Ă�͂�C�M���X�����Ŏg����B�������Ă����獕�����o���Ă��C���h�͖L���ɂȂ�Ȃ������B�����āA�Ԏ����o���������C�M���X�́A�����K�ڂɔɉh��搉̂ł����B
�@���̃C�M���X�ƃC���h�̊W�́A�������茻�݂̃A�����J�Ɠ��{�̊W���ƌ����Ă��悢�B�o�ϓ��F�����\�����̎O���z�v����́A�u�����S���v�i���t�V���j�ɂ��������Ă���:
�A�o�g��ɂ���Ă�������{��������~�ς��Ă��A����̓A�����J�����ɂ���A�����J�̋�s�Ƀh���ŗa������A�A�����J�����ɑ݂��u�����B���{����̗a���́A�A�����J�ɂ��Ă݂�Ύ������B�ł���B�݂��o���ȂǂɎ��R�Ɏg�����Ƃ��ł���B
�@���{�͉҂��������ɂӂ��킵�����b�ɗ^��Ȃ��ǂ��납�A�A�o�֘A�Y�Ƃ������č�������͖����I�Ȓ�ɚb���ł���B��̌����ł���f�t���͂Ȃ��Ȃ��o���������Ȃ��B �@���{�̍������h���Ƃ��ė��������A�����J�͂ǂ��Ȃ̂��B�h���̓A�����J�̋�s������Z�s����o�R���čL���s���n��A�A�����J�o�ς̊g��̂��߂ɓ�������Ă���B���{�̍����͌��ǁA�A�����J�����ꗬ���Ԏ��̌����߂����A�������A�����J�̌i�C�̒�グ�ɍv�����Ă���̂ł���B�E�E�E �@�A�o�ʼn҂�����������{���h���ŃA�����J�ɗa���A���{�̗��v�ł͂Ȃ��A�A�����J�̗��v�ɍv�����Ă������A�~�����͂��f�t�����͂���܂邱�ƂȂ��A���{�E���₪����������x�o����Z�ɘa�Ƃ����f�t����������u���Ă��A����Ɏ�����������ʂ͌���Ȃ��̂ł���.
http://www.asyura2.com/0601/hasan45/msg/253.html
�C���h�C���{�����Ă��̎��́H �@
�A�����J���{���厑�{�����{�̃}�l�[���z������Ă���̂ł��B�A�����J�̓��{�o�ό����҂̊Ԃɂ͎��̂悤�Ȍ��������������ł��B
�\�w2015�N���炢�܂ŁA���{�̋����g���ăA�����J�̔ɉh���x����B2015�N�ɂȂ�Γ��{�̋��͐s���Ă��܂��B���̎��͒����ƃC���h���A�����J�����̕⋋���ɂ���x �u2020�N�̐��E�v�Ƃ���2004�N�H�ɍ��ꂽ�A�����J���{�����̃��|�[�g�ɂ́A�u2020�N�ɂ̓A�����J�̃p�[�g�i�[�͒����ƃC���h���v�Ə�����Ă��܂��B ������A�A�����J�̒����ȑ�w������NHK�EBS�Łu�����ƃC���h���A�����J�̃p�[�g�i�[���v�Ɩ��������Ƃ������Ƃł��B�A�����J�̗L�͂Ȍo�ϐl������|�̔��������Ă��܂��B �A�����J�͓��{�̕x���k���Ɍv�Z���āu2015�N���E���v���q�ׂĂ���̂ł��傤�B���{�̓A�����J�ɂ���Ďg���̂Ăɂ���悤�Ƃ��Ă���̂ł��B
http://wanderer.exblog.jp/4632381/ 2016�N 04�� 20���F�g�����v���͐������A���R�f�Ղ͕č������E�� Robert�@L.�@Borosage
�m�P�S���@���C�^�[�n - �Q�O�P�U�N�̕đ哝�̑I�Ɍ����������_���̂Ȃ��ŁA�ʏ����œ_�ƂȂ��Ă���B���a�}�w�������Ńg�b�v�𑖂�s���Y���h�i���h�E�g�����v���͒�������̗A���i�ɂS�T���̊ł��咣���Ă���B
�܂��A����}�w����ڎw���o�[�j�[�E�T���_�[�X��@�c������̃v���b�V���[���A�q�����[�E�N�����g���O���������܂ŁA�I�o�}�đ哝�̂��i�߂�����m�p�[�g�i�[�V�b�v����i�s�o�o�j�ɔ����Ă���B�����͈ȑO�A�f�Ջ���́u�͔́v�Ƃ܂ŏ̎^���Ă����ɂ�������炸���B ���ܖ��炩�ɂȂ����̂́A�č��̃O���[�o���ʏ�����E�Ő������ɔj��I�Ȃ��̂��������Ƃ����_���B�m���ɁA�A���i�̉��i�ቺ�Ƃ��̑��l���́A�č����ɉ��b��^�����B�����A���̈���ŕč��͉ߋ��ɗނ����Ȃ��قǂ̖f�ՐԎ�������Ă���A���̊z�͌��݁A�N�Ԗ�T�O�O�O���h���i��T�S�D�T���~�j�A���Ȃ킿�f�c�o�i���������Y�j�̖�R���ɑ�������B �����Ƃ̖f�ՂɌ����Ă��A�č��͂P�X�X�O�N����Q�O�P�O�N�܂łɁA����Q�S�O���l�̌ٗp�������Ă���B�Β��f�Վ��x���A�L�^���J�n���Ĉȗ��ƂȂ�ߋ��ő�̐Ԏ��ł���B��Ƃ͐l����������ی�E����ҕی�̋K�����قƂ�ǂȂ������̂悤�ȍ��X�֗ǎ��Ȍٗp���ړ]�����Ă��܂��A�č��ɂ͒n��Љ�ۂ��ƍr�p���Ă��܂����Ⴊ����������B �G�R�m�~�X�g�̎��Z�ɂ��A�l����̈������X�Ƃ̖f�Ղɔ����A�č��̃u���[�J���[�J���҂̒����͔N�Ԗ�P�W�O�O�h���ቺ���Ă��܂����Ƃ����B���ق��ꂽ�J���҂͏������Ƃ������A�������ł����A��]�������Ă���B���̐E�������邽�߂ɋ����قǒ����ɂ킽���ċ�J�����������ɁA�����͈ȑO�����Ⴂ�����̐E�ɏA������Ȃ��B �f�Ջ���ɂ�鉶�b�̑啔���́A��Ƃ̃o�����X�V�[�g�����P���A�����ƁA�o�c��w�������킹��B����ŘJ���҂́A�������A�ٗp�̈�����A�͂������Ă���B �ł́A�č��̐V���Ȓʏ�����Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��낤���B ��P�ɁA��y�҂��̏�ԂɂȂ��Ă���s�o�o��������A���ݐi�s���̊吼�m�f�Փ����p�[�g�i�[�V�b�v�i�s�s�h�o�j�̌��𒆒f���邱�Ƃɂ��A�ŋ߂̖f�Ջ���̃e���v���[�g�i�ЂȌ`�j�Ƃ͉���邱�Ƃ��B �V���Ȓʏ�����́A���܂łƂ͈قȂ錴���Ɋ�Â����̂ɂȂ�B�n�[�o�[�h��w�P�l�f�B�X�N�[���ō��ې����o�ϊw����������_�j�E���h���b�N�������咣����悤�ɁA�f�Ղ́A���ꎩ�̂��ړI�ł͂Ȃ��A��i�Ƃ��Č��Ȃ����ׂ����B�A�M���{�́A�č����A�����đ������A���g�̉��l�ς�Nj��ł���悤�Ȗf�ՃV�X�e����͍����ׂ��Ȃ̂ł���B �ǎ�����V�X�e���̉��ł́A�e���͘J���҂̌����ی����֘A�@���ȂǁA�����̎Љ�I�Ȏ�茈�߂�����Ă����邾�낤�B�c��́A�f�Ջ���ɂ��Ė��m�ȖڕW���߁A�������̑ΏۂƂ��邩�����肷�錠�������߂��A�i�s���̌����e��m�邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�B�哝�̂ɔ閧����F�߁A�c��͍��ӓ��e���C���ł����Ɏ^�ۂ�����\��������Ȃ��Ȃ�t�@�X�g�g���b�N�����͓P��邾�낤�B �܂��A�f�Ջ��c�̎������傫���ς�邾�낤�B���Ƃ��A�����Ђ̓������̎��s�Ɋւ���ڍׂȌ��̑���ɁA�J���҂ɉe����^���鍷����������肪�V���ɒ��ڂ��W�߂邱�ƂɂȂ�B�u�p�i�}�����v���\�I�����d�ʼn���X�L�����_�������t���Ă���悤�ɁA�O���[�o����Ƃɑ���ېł̋����ƒ��a�A�^�b�N�X�w�C�u���i�d�ʼn��n�j�̕��Ƌ����I�ȐŖ����s�����̒��S�ɂȂ邾�낤�B�C��ϓ���Ƃ��ăO���[�o���ȒY�f�r�o���i�̐ݒ萄�i���D��ۑ�ɂȂ�B�e�����ʉݑ���ɑ��ĕ��錠����^���邱�Ƃ��d�v���B �o�ϐ����Z���^�[�̃f�B�[���E�x�C�J�[������������Ă�����g�݂Ƃ��āA��t�A���Ȉ�t�A�ٌ�m�̉ߏ�ȏ���������Ă����ǂ̔r��������B�C�O�ŌP��������t�⎕�Ȉ�t���č��ŊJ�Ƃł���悤�ɂȂ�A�N�ԂX�O�O���h���A�P�l�������R�O�O�h���̈�Ô�ߖ�ł���ƃx�C�J�[���͎��Z���Ă���B �܂����ۓI�Ȍ��ɂ���āA��Ì����ɑ�����I�Ȓ��ڗZ�����s���O���[�o��������a������\��������B�����̐��ʂ̓p�u���b�N�h���C���̂܂܂ƂȂ�B�x�C�J�[���̎��Z�ł́A�č��ɂ����āA���i�̃R�X�g��������A�N�ԂR�U�O�O���h���A�f�c�o��łQ���A�P�l�������P�P�O�O�h���̐ߖ�ɂȂ�Ƃ����B����͂s�o�o���i�h�������肩�瓾����Ƃ��鉶�b�����͂邩�ɑ傫���B ���@�ő�̋c���A���Ƃ��ĂV�O���ȏオ�Q������u�i���I�c���A���v�́A�v���ɕx�ޑ�֓I�ȕ�ʏ��������Ă���B���̌v��ł͖f�Ղ̊g��A�������o�����X�̗ǂ��f�Ղ�ڕW�Ƃ��Čf���Ă���B�đ哝�̗̂��ꂩ��A�č����T�N�ԂŖf�Վ��x���قڋύt��Ԃɂ܂Ŏ����Ă������Ƃ��v�悵�Ă���Ɣ��\���邱�Ƃ��ł���B��������Ζf�Ս���������鏔���́A�������v�𑝂₵�A�A�o�哱�̐����ւ̈ˑ���ቺ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƋC�Â����낤�B�܂��O���[�o����Ƃ��A�����č��s��ɃA�N�Z�X��������A�č����ł����Ɠ������������������ƂɋC�����͂����B ���ύt�̂Ƃꂽ�f�Ղ����߂鐺�́A�Q�O�O�X�N�̋��Z��@������ɊJ�Â��ꂽ��v�Q�O�J���E�n��i�f�Q�O�j��ł��x������Ă����B�����h�C�c�ƒ�������@��E���邽�߂ɗA�o�ɗ͂���ꂽ���ƂŁA���̍��ӂ͒��������Ȃ������B �f�Վ��x�ύt�́A���Ē��������ƃE�H�[�����E�o�t�F�b�g���������悤�ɁA�g���[�h�o�E�`���[���x�ɂ���Ď������邱�Ƃ��\���B���̊z�̍���A�����錠������Ƃɗ^���A���N���̊z��\�z�A�o�z�ɋ߂Â��Ă����d�g�݂��B�܂��́A�č��̎�v�f�Ց��荑�ɂ��āA�č������炷�ׂ��f�ՐԎ��̏�������ꂼ���߂Ă������B��������Ζf�Ց��荑�ɂ́A�A�������ƗA�o�팸�𔗂�v���b�V���[��������A�����Ȃ���Ύ�����̊łƂ��č�p����ے������x�������ƂɂȂ�B ��Q�ɁA�c�A����Ă���v��ɂ́A�J���҂̌����A�l���A����ҕی�A���ی�����������i���ڏq���Ă���B�����̉ۑ�ɂ��Ċe�������̊�]�ɉ����Ă�茵�����@�����߂錠�����ی삳���B�f�Ջ���ɂ���ĕK�{���i�ɑ���Ó��ȉ��i�ł̃A�N�Z�X���m�ۂ���邱�Ƃ��K�v�Ƃ����B�����Ȃ�A�����ɂ��ی���g�債�悤�Ƃ��鐻���Ђ̊�Ă��}������邾�낤�B ��R�ɁA�c�A�̌v��ł́A�f�Ջ��肪�u���ƂƂ��Ă̌����v�d���邱�Ƃ����߂Ă���B������������邽�߂ɁA�����Ƒ��ƊԂ̕����������x�i�h�r�c���x�j�͓P�p����A�O���[�o�������Ƃ͊e���̖@���x�Ɉˋ�����������Ȃ��Ȃ�B�O���[�o����Ƃ����s�����������x�Ɍ��O�����̂ł���A���ƕی��������邩�A�ʂ̍��ɓ�����������B �܂��v��́A���{���B�Ɋւ���u�č����i�D��w���i�o�C�E�A�����J���j�v������g�債�A�i�삷�邱�ƂɂȂ�B�������[�߂��ŋ����A���E���̌ٗp���x���邽�߂ł͂Ȃ��A�����̌ٗp���x���邽�߂Ɏg���邱�Ƃ�v���ł���悤�ɂ��ׂ��Ȃ̂��B ��S�ɁA���͂��̌v��́A���R�f�Վ�`�҂������̂����Ŏx�����Ă��邱�Ƃ����܂��B�����邱�ƂɂȂ�B�܂�A�O���[�o���f�Ղ̏��҂��s�҂ɕ⏞��^����Ƃ������Ƃ��B ���Ƃ����č��̘J���҂́A�g��f�Ւ����x���@�Ɋ�Â��x������B�ȑO�������̒Ⴂ�d���ɏA������Ȃ���A�g�傳�ꂽ���Ƌ��t�E�����ی�������B�V���ȃC�j�V�A�`�u�ł́A�H����ɂ���đŌ��������n��Љ�ɑ���I�m�Ȏx��������邾�낤�B�č������J���҂̒����������f���}�[�N�ƃh�C�c�ł́A�J���҂��f�ՃV�X�e���̋]���ɂȂ�Ȃ��悤�A�č����͂邩�ɑ����̃��\�[�X�����x�Ȍ��C�E�A�E�����v���O�����ɓ����Ă���B �����ȎY�Ɛ헪���A���ύt�̂Ƃꂽ�f�Ղ̂��߂Ƀv���X�ɂȂ�B���Ȃ킿�A���łɐ��E��Ȋ�������u�O���[���Y�Ɗv���v�Ɍ������Ȃ����i�̔����A�����A�̔��ɂ�����D�ʂ������Ƃɓ��������헪�ł���B �Đ��{�̌��݂̃V�X�e���̎x���҂́A���R�f�Ղ��ی��`���Ƃ����I�����Ă���B�����A���݂̂悤�Ȗf�Ջ���͎��R�f�Ղݏo�����̂ł͂Ȃ��B����̗����̂��߂̑I��I�ȕی���s���Ă��邾�����B�č��̔j�œI�Ȗf�ՐԎ��́A�O���[�o���[�[�V�����̔����������A���ł͂Ȃ��A�ʏ��E�Ő���̈Ӑ}�������ʂȂ̂ł���B
�T���_�[�X�A�g�����v�����́A�č��̌��݂̐j�H�̋���������\���̂ɍv�������B
�䂪���̒ʏ�����́A�����̗��v�ɗL���ȃ��[���̓T�^�I�ȗ�ł���B�J���҂��s���ɂȂ�A�b�d�n�������܂��܂����z�̏�����Ȃ��ŁA�G�R�m�~�X�g�������A�č��ُ̈�Ȃ܂ł̊i���g��ɔނ炪���ڍv�����Ă��邱�Ƃ�F�߂�悤�ɂȂ��Ă���B�i���I�c���A���̒�ẮA���ɂ��Ȃ�����ֈĂ��\�ł��邱�Ƃ������Ă���B�č��̌��݂̋���́A�����ƌ��̖͂��ł���A�^���ł͂Ȃ��̂��B
���M�҂͐i����`�I�ȕăV���N�^���N�uInstitute for America�fs Future�v�̐ݗ��ҁB�o���c�́uCampaign for America�fs Future�v�̋����f�B���N�^�[�����߂�B
http://jp.reuters.com/article/borosage-trade-idJPKCN0XH05T?sp=true
�O�����̃T�}�[�Y�_�̉�� 14�^7�^28�i807���j
•�T�}�[�Y�ƃg�}�E�s�P�e�B�ւ̑傫�Ȕ���
�{��14�^6�^30�i��803���j�u�T�}�[�Y�ƃg�}�E�s�P�e�B�v
http://www.adpweb.com/eco/eco803.html
�Ŏ�グ���A�č��o�ς̒�����ؘ_�����{�ł����ڂ���n�߂��B�T�}�[�Y�����������͏���Ⓤ���̌����ȂǂŁA�č��o�ς�������Ɋׂ�ƌx�����Ă���B���̘b�́A�M�҂��{���ɂ���܂ŏq�ׂĂ������Ƃɍ��v����Ƃ��낪�����i�M�҂͒�����ؘ_�Ɋւ��Ă��̑��ɂ������̌����������Ƃ��Ē��Ă���j�B
�T�}�[�Y���́A���̑�Ƃ��ĕč��̃C���t���̑���C����Y�Ƃւ̓������i�����Ă���B�܂��t�����X�̌o�ϊw�҂̃g�}�E�s�P�e�B�͏����i���̊g�傪�S�̂̏����}�����v�s���ނƎw�E���Ă���i���̓_�ɂ��ăT�}�[�Y���������Ƃ������Ă���j�B���҂̎咣�͉��ĂŔ������Ă�ł���B������ؘ_�ɐl�X�����ƂȂ��������o���邩��ł��낤�B���[�}���V���b�N��̗����݂�����E�āE���̌o�ς́A���x�̍��͂��邪��ɂ���B���������҂����قǂ̗͋����ł͂Ȃ��Ɛl�X�͊����Ă���B
��i���ɂ����Ă���܂ł̌o�Ϙ_�d�̎嗬�h�i�܂�ÓT�h�A�V�ÓT�h�o�ϊw�j�̋c�_�́A�����ς狟���T�C�h���d��������̂ł������B�Ⴆ�ΐE�ƌP���ɂ���ĘJ���s��̃~�X�}�b�`���Ȃ����Ƃ��������̂ł���B�܂��ޓ��A�嗬�h�͋����T�C�h�d���̊ϓ_����A���ݐ����������߂邱�Ƃ��咣���Ă����B���̂��߂ɂ͋K���ɘa�ɂ��\�����v���K�v�ƌ��������Ă���B
����A�T�}�[�Y�ƃg�}�E�s�P�e�B�͏���Ɠ����̕s�U�ɂ����v�s������ɂ��Ă���B�����e�����{���S�����v�T�C�h�����Ă����킯�ł͂Ȃ��B���ہA���[�}���V���b�N��̋}���Ȍo�ς̗����݂ɑ��āA�����o���Ȃǂɂ����v�n�o��������{�����B�������M���V���̍�����@���N��A�e���͈�]���ċُk�����ɓ]�����B�p���͕t�����l�ŁA�����ē��{�͏���łł��A�܂��č��͌R����Ȃǂ̍����x�o���팸���Ă���B
�Ƃ����IMF��14�N�̐�i���̎����i�f�t���j�M���b�v��110���~�iGDP��2.2���ɑ����j�Ɛ��v���Ă���i�������M�҂͂���������߂���Ǝw�E�����j�B�T�}�[�Y�͕č���GDP�͐���GDP��10����������Ă���Ǝ咣���Ă���B�Ƃ��낪���{�ł͓��t�{���f�t���M���v��0.2���A����͂Ȃ�ƃf�t���M���c�v���������A�t�ɃC���t���M���b�v��0.6�������Ă���Ǝ��ɂ��������Ƃ������Ă���B������嗬�h�i�����T�C�h�d���h�j�̉e���ł��낤�B
���ہA����������Ή��B�͎�҂̎��Ɨ���10�����z���Ă���A�ݔ����������オ��Ɍ����Ă���B�č������Ɨ��͒ቺ���Ă��邪�A�K�ٗp�������Ă��邾���ł���B�e�����{�́A���̏����ċꗶ���Ă���B�������������N�����Ă���Ǝv������ł���̂ŁA��������͑łĂ��A�����ς���Z�ɘa�ɗ����Ă���̂�����ł���B�Ƃ��낪�g�}�E�s�P�e�B�́A�����̏ɂ����Ă̋��Z�ɘa�͂���ɏ����i�����g�傷��Ɣᔻ���Ă���B �M�҂́A�o�Ϙ_�d�̎嗬�h�����Ԃ��瑊��ɂ���Ȃ��Ȃ鎞�����ߕt���Ă���ƌ��Ă���B�T�}�[�Y��g�}�E�s�P�e�B�̐����S�Đ��������ǂ����͕ʂɂ��āA���v�T�C�h�d���Ƃ����l�����A���Ԃɉ����V�N�Ȃ��̂Ǝ����Ă���B����������̌o�Ϙ_�d�̎嗬�h���{���{���ɂȂ��Ă��邩��ł��낤�B
�T�}�[�Y��g�}�E�s�P�e�B�̎咣�́A������O�̂��ƂƕM�҂͍l����B���v������Όo�ς͐������A���v���s������Όo�ς͒����B���������Đ�T���Ŏ�グ���悤�Ɏ��v�������ȐV������r�㍑�́A�����������������o�ϐ������\�ł���B
�t�ɋ����T�C�h���l�b�N�ɂȂ��Čo�ϐ������o���Ȃ��Ȃ�āA��O�I�ȃP�[�X�ł���B�ߓx�Ɉꎟ�Y�i�Ɉˑ��������Ƃ��n��ȁA�u���W����A���[���`���Ȃǂ̓�ď�����V�A�A�����ċߑ�Y�Ƃ̂قƂ�ǂȂ��r�㍑�̈ꕔ�ȂǂɌ�����i����A�����O�̒����Ȃ�Ĉ�T�Ԃɓd�C���R���Ԃ�����������Ȃ��ō����o�ϐ����𑱂��Ă����j�B���̌���ꂽ���X�ɂ����K�p�ł��Ȃ��嗬�h�o�ϊw�̃|���R�c���_�ŁA���n�������E�āE���̌o�ς͂��o�ϐ����i�߂悤�Ƃ��Ă������Ƃ����������̊ԈႢ�������̂ł���B
•���o�V���̃T�}�[�Y���_�̉��
��N11���T�}�[�Y��IMF�̉�c�Œ�����ؘ_�����߂Ę_�����ڂ��ꂽ�BIMF�͌��X�o�Ϙ_�d�̎嗬�h�F�i�܂�ÓT�h�A�V�ÓT�h�o�ϊw�j�������@�ւł���B����IMF�ł�����i���S�̂Ńf�t���M���b�v��O�q�̒ʂ�110���~�Ɛ��v���Ă���B�������ɂ��̐����ُ͈�ɏ��������i�T�}�[�Y�͕č��̃f�t���M���b�v��GDP��10���Ƃ��Ă���̂ŁA�č�������110���~�Ȃ�Čy���z����j�AIMF�ł����f�t���M���v�̑��݂�F�ߖ��ɂ������ƂɈӖ�������B���Ȃ݂Ƀf�t�����ǂ����́A���̃f�t���M���b�v�Ō���ׂ��Ȃ̂ɁA�|���R�c�G�R�m�~�X�g�B�͂��܂��ɕ����̏オ�艺����Ō��悤�Ƃ���B �{���A������ؘ_�͓��{�Ō����o���ׂ����̂ł���B�Ƃ��낪�o�u�������A�������Ⴂ�����̂����{�ł͋����T�C�h�d���̘_������Ă��r���A�����ł����̘H���������Ă���B�t�ɓ��{�ł́A�T�}�[�Y���̂悤�Ȏ��v�T�C�h�d����ϋɍ�����������o�ϊw�҂�G�R�m�~�X�g���قƂ�ǔr�˂���čs�����B �Ƃ��낪���Čo�ς����{�o�ς�ǂ��|����悤�Ƀf�t�����[���ɂȂ����̂ł���B�悤�₭���Ă��f�t���ɐ^�ʖڂɎ�g�����Ƃ������͋C���o�Ă����̂ł���B���̐�삯�ƂȂ��Ă���̂��T�}�[�Y�ƃg�}�E�s�P�e�B�ƕM�҂͑����Ă���B
��Ȃ��̂����{�̌o�Ϙ_�d�ł���A�����č��̌o�ϊw�̗��s���ǂ��|���邵���\���Ȃ��̂ł���i�l�ޕs�����[���j�B�����炭�č��̌o�Ϙ_�d�Ŏ��v�T�C�h�d���̗��ꂪ�蒅����A���{���ǐ�����\��������B�����Ă��̒����ɏo�Ă���ƌ�����B
7��26�����s�̏T�����m�o�ς́A�g�}�E�s�P�e�B�̓��W��g��ł���B�܂����o�V����7��14������R���Ԃɓn��A�T�}�[�Y�̒�����ؐ����o�ϊw�����Ŏ�グ�Ă���B�o�Ϙ_�d�̎嗬�h�i�ÓT�h�A�V�ÓT�h�o�ϊw�j�F���ɂ߂ċ����A�܂苟���T�C�h�d����ӓ|�̓��o���T�}�[�Y�̒�����ؘ_����グ���̂ɂ͕M�҂��������B
�R���Ԃ̎��M�҂́A���c�T��勳���A�r���a�l�c�������A�����ĉ���N�勳���ł���B3���Ƃ��T�}�[�Y�������v�s���������ɒ�����ؘ_��W�J���Ă��邱�Ƃ��Љ�Ă���B�������莁�����́A�č��̓������iGDP�䗦�j�͂܂�15�����x�Ƃ܂���r�I���������Ǝ��������̊W�ł͕č��̒�ؐ��͑��v�ƌ��Ȃ��Ă���B
�����O���Ƃ�������Ƃ����_�ł͓��{�̕������Ԃ͐[���Ƃ������͂����Ă���B����Ȃ�A���́A����܂œ��{�Ŏ��v�s���ɋN�����钷������x�����鐺���o�Ȃ������̂��Ƃ����b�ɂȂ�B��͂肱����č��������Ȃ���Γ��{�͓����Ȃ��Ƃ�����Ȃ��}���Ȃ̂ł��낤�B
�������O���Ƃ��T�}�[�Y���̑����v����ɂ͕K�������^�����Ă��Ȃ��B�����̂悤�ȉߓx�̋��Z�ɘa��Ԃł̎��v����́A�o�u����������ƎO���͎咣���Ă���B�M�҂͌���ł͊ȒP�Ƀo�u�����N��Ƃ͍l���Ȃ����A���ɂ͐摖�肵�ăo�u������̎S�������Ă���҂܂ł���i���c�����j�B
�O�����́A�T�}�[�Y���̒�����ؘ_����������ꂼ����Ă���B���q����ƍ������S���ɐ��ʂ�����������Čo�ς̍\�������v���邱�Ƃ��}���i���c�����j�B�T�}�[�Y���͐����헪�ɏ��ɓI�ł��邪�A�����I�E�ϗ͂������Đ����헪�����s�i�r�������j�B����Љ�ɓK������o�ύ\���ւ̈ڍs�i���苳���j�B����ɂ��Ă��u�����͈�̉����v�Ƃ������S�߂Ȑ���̃I���p���[�h�ł���i����v�����Ȃ��̂Ȃ�u�Ȃ��v�ƌ����Ηǂ��j�B�O�����̑������ƁA��͂荡���̓��{�̌o�ϊw�҂ɃT�}�[�Y�_�̉���͖����������悤�ł���B ���o�V�����T�}�[�Y���̒�����ؘ_����グ���̂ŕM�҂����o�������͕ς�����̂��Ǝv�����B������23���́u�G�R�m�~�N�X�E�g�����h�v�ł́A���쓌�勳�����u�����\�͂̓V��@�������v�Ƃ܂��ɋ����T�C�h�d����ӓ|�̕��͂������Ă���B���쎁�̓T�}�[�Y���̒�����ؘ_�����p���Ȃ��炱��������Ă���̂���������B�܂�24���ɂ́u��@���@���v�ɋ��c�쎁�����l�̘_���ŊԔ����ȃR�����������Ă���B �����������{�o�ς͎��v�̓V��ɂԂ����Ă��A�����̓V��ɂԂ��邱�Ƃ͕S�p�[�Z���g�Ȃ��i�O�����ł������{�̃f�t������Ԑ[���ƌ����Ă���ł͂Ȃ����j�B�����̌o�ς̎��Ԃ�m�炸�Ɍo�ς�_����l�X�͍K���ł���B�ǂ������o�V���́A���n�r�����x�ł͎���Ȃ��قǂ̏d�a�ł���B
http://www.adpweb.com/eco/
�o�σR�����}�K�W�� 16�^10�^24�i913���j
�����̍\�����v�h
•�X�b�|�������Ă������
���{�o�ς͒ᐬ���������Ă���B�M�ҒB�͂��̌��������v�s���ƕ��͂��Ă���B���̎�ȗv���́A���{��30�ˑ�A40�ˑ�́u����N���v�̐l�����������Ă��邱�Ƃł���i���v�s���Ȃ̂�����u���Y�N���v�̐l���̌����͎�Ȗ��ł͂Ȃ��j�B�܂������i���������j���L�тȂ����Ƃ����̈�̗v���ɂȂ��Ă���B����ɑ��ɂ����v�s���̗v���͐F�X�ƍl�����邪�A�����ł͂���ȏ�̌��y�͏ȗ�����B ����ɑ��āA�ᐬ���̌����͎��v�T�C�h�ł͂Ȃ��A���{�̋����T�C�h�ɖ�肪���邩��Ǝ咣����҂����ɑ����B���̍l�����瓱���o������͓��{�̍\�����v�Ƃ������ƂɂȂ�B��T���ŏq�ׂ��悤�ɁA���̍\�����v�h�ɂ�Ƃ��āA�M�ҒB���咣��������x�o�ɂ����v�n�o����́A�ނ�����{�̍\�����v�ɂƂ��Ďז��ł����Q�ɂȂ�炵���B
�\�����v�h�̔��z�͌ÓT�h�o�ϊw���_�i�V�ÓT�h�o�ϊw���܂ށj�ɍ������Ă���B������u�Z�C�̖@���v�A�܂��������̂͑S�Ĕ����Ƃ����@�����������E�ł���B���������Ă�������c��⎸�Ƃ�������Ȃ狟���T�C�h�ɖ�肪����Ƃ������ƂɂȂ�B��̓I�ɂ͐��Y�ݔ����������Ă��Đ��i������ɍ���Ȃ��Ƃ��A�J���҂̎��ɖ�肪����Ƃ������ƂɂȂ�B
�\�����v�h�̑�́A�܂��K���ɘa�Ȃǂɂ�鋣������̋����Ƃ������ƂɂȂ�B����ɂ���ė������Y�ݔ���]���r��Ƃ̑ޏo�𑣂����ƂɂȂ�B�܂��Z�p�I�ɗ��J���҂ɂ͋���E�P�����{���Ƃ������ƂɂȂ�B�����̘b�́A�\�����v�h�ɐ��܂��Ă�����o�V���Ȃǂ̃��f�B�A�ł��悭��������B
�\�����v�h�̌o�ϐ������_�̎x���ƂȂ��Ă���莮������B����ɂ���
08�^9�^15�i��541���j�u�o�ϐ����̒莮�i���f���j�v
http://www.adpweb.com/eco/eco541.html �� 14�^7�^7�i��804���j�u�o�ϐ����̎O�̃p�^�[���v
http://www.adpweb.com/eco/eco804.html
�ȂǂŐ��������B
����͌o�ϊw�̋��ȏ��ɍڂ��Ă��� g�i�o�ϐ������j��s�i���~���j�^v�i���{�W���j�{ n�i�J���l���������j �ł��� �i����ɋZ�p�i������������� g�i�o�ϐ������j��s�i���~���j�^v�i���{�W���j�{n�i�J���l���������j�{t�i�Z�p�i���j �ɂȂ�j�B ����������s�i���~���j�����Ȃ�A�o�ϐ�������傫������ɂ͍������Ȃǂɂ���Ď��{�W�������������A�J���҂ɋ���E�P�����{���J�������ʂ𑝂₹�Όo�ς͐������邱�ƂɂȂ�B ��L�̌o�ϐ������_�̒莮�́A�ꌩ������������O�̂悤�Ɋ�����B�Ƃ��낪����ɂ́u�X�b�|�������Ă�����́v������B����́u���v�v�ł���B�������v�s������ԉ����Ă���Ȃ�A��L�̒莮�͉��̈Ӗ����Ȃ��B�܂�\�����v�h�́A���v�T�C�h��S�����Ă��Ȃ��̂ł���B�܂��Ɂu��������̂͑S�Ĕ����v�Ƃ����u�Z�C�̖@���v�̐��E�ɂ���B���̂悤�ɍ\�����v�h�̌o�ϗ��_�͒������������ꂵ�Ă���B
�Ƃ��낪���{�����̓o��ŏ͈�ς����B���{�����͑��̐�����f�t���o�ς���̒E�p�Ƃ����B�܂�f�t���M���b�v�̑��݂������ɔF�߁A���̉�������̐����ڕW�ɒu�����̂ł���B���{�@�ւ��a�X�ƃf�t���M���b�v�̑��݂�F�߂�悤�ɂȂ����B
�Ƃ��낪���{�@�ւ̌��\����f�t���M���b�v�͂���1�`2���ƈُ�ɏ������B����� 16�^8�^1�i��902���j�u�傫�ȎԂ͂��������v
http://www.adpweb.com/eco/eco902.html
�ŏq�ׂ��悤�ɁA�f�t���M���b�v�̎Z�o�Ɂu�ςm�`�h�q�t�A�v���[�`�v�Ƃ������������ꂵ����@���̂��Ă��邩��ł���B�܂��f�t���M���b�v�ُ킪���������߁A���ݐ��������ُ�ɏ������Z�o����Ă���B
�M�ҒB�́A�w���R�v�^�[�E�}�l�[�ɂ����v�n�o����������Ă���B�������\�����v�h�ɐ��܂������{�̌o�ς̘_�q�́A�f�t���M���b�v���������̂����炽���܂����{�o�ςɃC���t�����N�蕨������������Ƌ������̂ł���B������w���R�v�^�[�E�}�l�[����ւ̈�̎G���ł���B
•�L�蓾�Ȃ��f�t���M���b�v��1�`2��
���{�o�ς̐����������߂�ɂ́A���Y���̌��サ���Ȃ��Ƃ����b���悭�����B���̍����͐��ݐ����������ꂾ���������Ȃ��Ă���̂�����A���Y�����グ�鑼�͂Ȃ��Ƃ����̂ł���B��̓I�ɂ͋K���ɘa�ɂ���ċ����������ɂ��邱�Ƃ�Y�H���ւ̐V�@���̓����A�����ĘJ���҂̋���E�P���Ȃǂł���B���Ȃ݂ɖ{���ł͉ߋ� 01�^9�^10�i��221���j�u�u���Y���v�Ɓu�Z�C�T���Z�C�v�̘b�v
http://www.adpweb.com/eco/eco221.html
�ŁA���̘b����グ�����Ƃ�����B
�����������̑S�Ă��O�i�ŏЉ���\�����v�h�̃Z���t�ƈ�v����B�܂萶�Y�����グ��Ƃ������Ƃ͍\�����v�����{���邱�ƂƓ����Ӗ��ł���B��������ς���ƍ\�����v���s�����Ƃɂ���Đ��Y�����オ��Ƃ����b�ł���B �������ɍ��S�̂ł͂Ȃ���̊�Ƃōl����ƁA�������E�������Y���Ԃɍ���Ȃ��ꍇ�͐��Y�H���̉��P�i�V�@���̓����Ȃǂ��܂߁j��]�ƈ��̋���E�P�����K�v�ɂȂ��Ă���B�܂肱�̐��Y���̌���ɂ���Ē������ɑΉ�����Ƃ������Ƃ͗L�肤��B���������ɒ��������Ȃ��Ȃ�P�[�X���L�肤��B���̎��ɂ̓��X�g���ɂ�鐶�Y���̌���Ƃ������@���l������B�܂��ꍇ�ɂ���Ă͕s�̎Z����̐����Ƃ����������Ƃ��K�v�ɂȂ�B
�������ꍑ�̌o�ς��l����ꍇ�ƈ��Ƃ�Ώۂɂ���ꍇ�ł͎���قȂ邱�Ƃ�����B�������ɍ��S�̂̎��v���L�тĂ��鎞��Ȃ�A������Ƃ����ׂ����Ƃ͎��Ă���B�����Ă���悤�ɐ��Y���̌���Ƃ������ƂɂȂ�B��Ƃ͂���ɂ���Č���ꂽ���Y�����i���Y�ݔ��ƘJ���ҁj���������I�Ɏg���čő���̐��Y���s���̂ł���B���͂��̓�����Ő��ȂǂŎx�����邱�ƂɂȂ�B
�Ƃ��낪�����̂悤�ȃf�t���o�ςŎ��v�s������ԉ����Ă��錻��ł́A���Ɗ�Ƃł͗��Q���قȂ�Ƃ��������Ԃ��N��B�Ⴆ�Ί�Ƃ͔��オ������A���R�A�O�q�̂悤�Ȑ��Y���̌���̂��߃��X�g�����l����B���������ɂƂ��Ċ�Ƃ̃��X�g���ɂ�鎸�Ǝ҂̑����͗R�X�������ƂȂ�B
���̂悤�ɍ\�����v�h�̘_�q�́A�o�ς̍��x�������̂悤�Ɏ��v���ǂ�ǂ��鎞�ɓK��������������Ȃ��t�قȌo�ϗ��_�i�����T�C�h�̏d���j���A�����I�Ȏ��v�s�������������̓��{�ɂ��K�p���悤�Ƃ��Ă���̂ł���B�M�҂͂��̂��Ƃ��Ԉ���Ă���Ƃ����ƌ����ė����B
����t�D���������A�\�����v�h�̖ʁX�͌����̌o�ςɑa���u���o�J�v�̏W��Ƃ������ƂɂȂ�B�����ł������̌o�ς�m���Ă���Ȃ�A1�`2���̃f�t���M���b�v�Ƃ��قƂ�ǃ[���̐��ݐ������Ƃ������������ꂵ�����Ƃ͌����Č���Ȃ��B�{���Ƀf�t���M���b�v��1�`2���Ȃ�A�i�C�͒��ߔM��Ԃł��邱�Ƃ��Ӗ�����B���̂悤�ȏȂ�قƂ�ǂ̐��Y�ݔ��̉ғ�����100���ł���A���X��f�p�[�g�̓X��ɂ͔������q���E���������s�������Ă���͂��ł���i�I�풼��̓��{�⋌�\�A����̓X���Ɠ����悤�Ɂj�B �܂��{���Ƀf�t���M���b�v��1�`2���Ȃ�A�ǂ̊�Ƃ⏤�X�ł͂���ȏ㔄�邱�Ƃ̂ł��鐻�i�⏤�i�̍ɂ��Ȃ��Ȃ��Ă��āA�c�ƒS���҂̂قƂ�ǂ̎d���͒�����f�邱�ƂɂȂ��Ă���͂��ł���B���������Ĕ̔����i�̂��߂̍L���E��`�Ȃ�ĂƂ�ł��Ȃ����Ƃł���B���̂悤�Ɂu�ςm�`�h�q�t�A�v���[�`�v�ɂ���ē����o�����f�t���M���b�v�̐����͂��������L�蓾�Ȃ����̂ł���B
�������ɍ\�����v�h�̒��ɂ��A�i�X�Ɩ��͋����T�C�h�����łȂ��A���v�T�C�h�ɂ�����̂ł͂Ȃ����ƍl����҂������悤�ɂȂ����i���{�̋����T�C�h�͓��ɑ傫�Ȗ�肪�Ȃ��ƕM�҂͌��Ă���j�B���炩�ɍ\�����v�h�͗������}���Ă���B�����������Ȃ�����x�o�ɂ����v�n�o�Ƃ����킯�ɂ͍s���Ȃ��B�M�҂̋L���ł́A�ŏ��Ɏ��v�T�C�h�ɒ��ڂ����\�����v�h�́u�����֖������v����ɂ����l�X�ł���i���������g���Ă̎��v�n�o������Ǝ咣�j�B
���̎��͊O���l�ό��q�̗U�v��������l�X�ł���B����͊O���l�ό��q�̔������ɂ����v����_���Ă���B�����čŋ߂ł�TPP���������ڂ���Ă���B�Ƃ���ŃA�x�m�~�N�X�̑�O�̖�ł���u�����헪�v�̒��͋K���ɘa�Ȃǂɂ��\�����v�������͂��ł���B�Ƃ��낪��Ȃ��Ƃɍŋ߂ɂȂ��āu�����헪�v�̑���TPP�Ƃ����b���o��悤�ɂȂ��Ă���B����� TPP �ɂ��A�o�����_���ł���B ���̂悤�ɊO���l�ό��q�̗U�v��TPP�̖ړI�͎��v���Ƃ����Ă��O���̑����Ƃ������ƂɂȂ�B�������ɍ\�����v��鋟���T�C�h�̋����Ƃ������������ꂵ���l������́A�����͂����炩�i�����Ă���ƌ�����B����������ɑ��ĕM�ҒB�́A����ȏ�O���ˑ������߂�̂ł͂Ȃ��i�O���ˑ��͂�����~���ŋꂵ�ނ��ƂɂȂ�j�A��������i�w���R�v�^�[�E�}�l�[�Ȃǂɂ��j�ɂ������g�吭����咣���Ă���̂ł���
http://www.adpweb.com/eco/
���~�ƕn���@�Ę_�i�Z�C�̖@�����߂����āj
http://www.asyura2.com/11/hasan72/msg/908.html
�o�ϊw�ɂ́A������o�ϊw�ƁA���肫��Ȃ��o�ϊw������B �i���̐��������Ȃ��ĉ��̂��Ƃ������Ă���̂��킩��Ȃ��Ƃ����������������邩������Ȃ��̂ŁA ���������w���{��`�̂��߂̃C�m�x�[�V����(�v�V�j�x
http://www.amazon.co.jp/%E5%B0%8F%E5%AE%A4%E7%9B%B4%E6%A8%B9-%E7%B5%8C%E6%B8%88%E3%82%BC%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%AB-%E8%B3%87%E6%9C%AC%E4%B8%BB%E7%BE%A9%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E9%9D%A9%E6%96%B0-%E5%B0%8F%E5%AE%A4-%E7%9B%B4%E6%A8%B9/dp/4822229025
����A
��S�́@�C�m�x�[�V����(�v�V)�����̂��߂̌o�ό��_�@�̖`�����@
�|�u�L�����v�̌����v�Ɓu�Z�C�̖@���v����������A���Ȃ������h�Ȍo�ϊw�ҁ|�@
�𐔃y�[�W������Ɉ��p���@�i�w��ցcshn�x19.1���������j���Ă����܂��B �u�o�ϊw�́A�A�_���E�X�~�X����n�܂荡���ɂ�����ÓT�h�ƃP�C���Y�h�Ƃ���Ȃ�B�ÓT�h�͎��R���C�������s�ꖜ�\�_�҂ł���B�P�C���Y�͌ÓT�h��ᔻ�����B�{�͂͒��w1�N���x�̐��w�ŗ����ł���B�v�������ł��B�j
������o�ϊw�Ƃ͌ÓT�h�ŁA�Z�C�̖@������������Ƃ��܂��B
�Z�C�̖@�������������͏��������������Ă��܂����A�����̓ǂƂ��ɂ͂����ƒP���Ȑ����ł������Ǝv���܂��B "supply creates its own demand"�A�����͎������g�ɑ�����v�ݏo���B ��ԒP���ȗ���l����ƁA��������̏��i�͎U�����邱�ƂŁA�U��������2500�~�Ȃ�A��l�U���������2500�~�̎�������������B�s��Ɉ��鏤�i�����ƁA���z�̎����������炳���B�������G�ȏꍇ���l����ƁA120���~�̃g���^�J���[������䔄����120���~�̎����������炳���B120���~�͓y�n�i���R�j�A�J���A���{�Ƃ������Y�̎O�v�f�ɂ��ꂼ��n��A�����A�����Ƃ��Ďx�����A�����͒n��A�J���ҁA���{�Ƃ̎����ɂȂ�B���i�̑��z�Ǝ����̑��z�͓������B �����܂ł͓�����O�ŁA�P�C���Y�h���}���N�X�h������������Ȃ��B
��������悪�Ⴄ�B �ÓT�h�́A�l�͏��i���Ď����Ă���ʼn������i����j�A�c��͕K���������邾�낤�A�ƍl����B�����œ������Ȃ��Ƃ��͐l�ɑ݂��A�肽�l�͂������q���̂ł͂Ȃ��K����������B500���~�̏��i���s��ɂ����炳���Ƃ���500���~�̎������������A����͕K��500���~�̎��v�ɂȂ�B�����͕K���x�o�����B���ߍ��܂�Ă��܂����Ƃ͂Ȃ��B�����炽�Ƃ��s��̈ꕔ�Ŕ���c�肪�������Ă�����Ɠ��z�̍w���͂������Ɏc���Ă���̂�����A�s��ɔC���Ă����ΕK��������悤�Ɏs�ꎩ�g����������B�c �}���N�X�́A���{��`�ɂ����Ắu����v�͋�������邪�u�����v�͋�������Ȃ��A������K���u�����v���s������A�Ɣᔻ���܂����B����グ�����肵�߂Ė͗l���߂����邱�Ƃ����Ăł���킯�ł��B �P�C���Y�͗������I�D�Ƃ������t�Ő������Ă��܂��B ���Ƃ��u���@�v�ړI�̂��߂ɂ͎����̎������Ȃ�ׂ������ɋ߂��`�Łi�������̍����`�Łj�����Ă���K�v������B����ƁA�����������Ŏ�����Ă��镪�������i������c��A���Ƃ���������B ���������~����A���~���������ꂸ�ɗ��ߍ��܂��Ǝ��ƁA�n������������B �����܂Ő�������ƕK���ƌ����Ă����ق� ����A�u�O�ʓ����̖@���v�������āA�K�������邱�ƂɂȂ��Ă���̂��A�Ƃ����R�����g������̂ł����A�u�O�ʓ����̖@���v�Ƃ������̂͂Ȃ��A����̂́u�O�ʓ����̌����v�Ȃ̂������ł��B ����I�I�Y���������r�f�I�j���[�X�h�b�g�R���Łu���~�����Ƃ̌������Ƃ����l�������邪�v�ƈӌ������߂��āu�O�ʓ����̖@���������āA������̂ł��v�Ɠ����Ă��܂����B �O�ʓ����̌����Ɋւ��Ă͂����炪�킩��₷���܂Ƃ߂��Ă��܂��B
���@�@�@http://free-learning.org/?page_id=390#05 ��������ꍇ�́A�t���[���[�j���O�����K�}�N���o�ϊw��part2�����o�όv�Z�|���{�o�ς��ǂ�����H����T��@�O�ʓ����̌����@�ł��B
�e�L�X�g�ł�
�u�O�ʓ����̌����͓��v��̑�����s�����Ƃɂ���ď�ɐ������铝�v��̌����ɂ����܂���B�������A���̌������A�����o�ς̎��v�Ƌ������������Ɗ�����������l�������̂ŋC��t���܂��傤�B�v �ƒ����Œ��ӂ��Ăт������Ă��܂��B�i�ΐ�G���@�u���K�I�}�N���o�ϊw�v65�y�[�W�j ���́u�O�ʓ����̌����v�Ƃ����̂� �@�i���Y�ʂ���݂�Ɓj���������Y�E500���~
���i���z�ʂ���݂�Ɓj�����������E500���~
���i�x�o�ʂ���݂�Ɓj�������x�o�E500���~ �ł��� �u���������Y���A�������x�o���������ꍇ�A���Y���������x�o�����Ȃ��̂ŁA���̂�����c��A�q�ɂɔ���c��i�������܂��B�Ƃ��낪���v��́A���̔���c�������́A���̍������Ƃ��x�o�����ƍl���A�ɕi�����Ƃ������ڂɂ��č������x�o�ɉ�����̂ł��B�i�����j �@���̂悤�ɍl����A���v��́A�x�o�ʂ̍��������i�������x�o�j�Ɛ��Y�ʂ̍��������i���������Y�j�Ƃ͏�ɓ������Ȃ�܂��B�v �u�������A����́A���v��́A����c�������͍������Ƃ��x�o���Ĕ��������Ƃɂ��Ă��܂��̂ŁA�������Ȃ�Ƃ��������ŁA�����̐��Y�ʂƎ��v�ʁi�x�o�z�j������������c�肪�Ȃ��Ƃ������Ƃł͂���܂���B�v�i��67�y�[�W�j �X���̐��Y�z�̐������W�v����ƁA�X���̎����z�̍��v�Ƃ͌덷��R�ꂪ�����ĕK��������v����Ƃ͌���Ȃ�����A���v��͂��̐��������낦��A�Ƃ����̂͂킩��B���������x�o�z�����삵�đ����Ă��܂��Ƃ����͈̂��̃g���b�N�A�C���`�L�ŁA�u������������E������v�̌��ɂȂ�̂ł͂Ȃ����B ���~�̈ꕔ����������Ȃ��ł��ߍ��܂��Ə��i������c�莸�Ƃ��������邩�炻�̕����i���{���j�V���ɓ������Ȃ�������Ȃ��A�Ƙb��i�߂�� �u����c��ɂ͍ɓ����Ƃ�������������A�������Ă���̂��v �Ƃ������_����ꂽ���Ƃ��������̂ł����A���ꂪ�u���������v�Ȃ̂ł��傤�B �ŁA����I�I�Y�����̊������������Ă����l�Ȃ̂ł��傤���B �Ⴆ�Δ��^�e���r�ƊE�ɎQ�����邽�߂�1000���~�������čH������Ă��A�J���҂��ق����A���i���d���ꂽ�A���ꂪ1000���~�̓������B����A�����͂��̌����݂��O���10���~�̃e���r100���䂪����c���Ă��܂����A���ꂪ1000���~�̍ɂ��B���̓���������A�������A�Ƃ����l�ɂ܂Ƃ��Ȍo�ω^�c�͉\�Ȃ̂ł��傤���B ���Ǐ��������̌��_���ꏏ�ŁA���~���������ꂸ�ɗ��ߍ��܂��Ǝ��Ƃ���������B �����璙�~���z�������邾���̍��s���Č������Ƃ�����Ȃ�A�u���Ƃ��蓖�v�Ƃ�������������Ă������g�������Ƃ����l�ɂ�܂��Δ���c�肪��|����Ďs��̋@�\������B�s���ے肷��̂ł͂Ȃ��āA�s��̋@�\�������邽�߂ɁA���~�����v���X�}�C�i�X�Ń[���ɂ��邾���̃o���}�L�����Ȃ�������Ȃ��B �܂��́A���߂���A�������g���K�v�̂Ȃ��l�ɂ͂��������Ȃ������̌n�ɂ��Ȃ�������Ȃ��B �@�܂��A��������c��E���Ƃ���������ƁA����̎ア���i���瓊�����肪�n�܂�B ��ӂ́u�J���́v�͈�ԗ���̎ア���i������A�����l���ꂪ�N����B�܂蒙�~�ɂ���ĕs���������������邱�ƂɂȂ�B����ƁA�s���Ɉ��l��t����ꂽ�J���̔�����͂��̕��s���ȗ��v�邱�ƂɂȂ�B
������A�A�����J�哝�̑I�Ō��ꂽ�Ƃ����u�^�ʖځv�ɓ����Ď����̐����𐬂藧�����Ă����l�ԁi53���̔[�Ŏҁj�A�A�u�ŋ��ŐH�킵�Ă�����Ă���l�ԁv�i47����[�Ŏҁj�Ƃ����Δ䂻�̂��̂��s���Ȃ��̂��Ƃ�����B �J���͂̋����Ɋւ���ÓT�h�E�V�ÓT�h�̗��_�ł͘J���҂͘J�����邩���Ȃ��������őI�ׂ邱�ƂɂȂ��Ă���B���鎞�ԓ����ē���������ƁA���̂��߂Ɏ�����]�ɂƂ��͂���ɂ����Ă����ق���I�Ԃ̂��Ƃ����B����ȘJ���҂��������Ƃ����邩�B����͂܂�ŐH�ׂ�ɂ͎������Ȃ��e������̊w���A���o�C�g���B �@�Ȃ������l������100���~�̃x�[�V�b�N�C���J����ۏ��ē����������Ȃ������R�ɑI�ׂ�Ƃ������������o���ΌÓT�h�E�V�ÓT�h�̎s��̗��_����������Ƃ�����B �i�u�Z�[�̖@���v�߂Ă����炱��Ȃ��Ƃ�������̂ł͂Ȃ����B ���{�͘J���������������獑�ۋ����͂�������B�c �@����ƊE�Œ��グ���s���A�v10���~�������オ��A���ꂪ���ׂĉ��i�ɓ]�ł���āA�����̑S���i�̒l�i���v10���~�オ�����Ƃ���B����ǂ��̎��A���̏��i�������̑�������10���~�����Ă���̂�����A�����S�̂���������킯�ł͂Ȃ��B��������̂͗A�o�ƊE���낤�B�A�o�̂��߂ɘJ���҂̒�����n���������݂Ɉ���������Ƃ����̂́A�{���]�|�ł͂Ȃ����B �@���ɔ_�Ɩ��ł��������B �@���{�̔_�Ƃ��S�̂�10���~�̔_�Y���Y���Ă����Ƃ���B�������O���ł͓������̂�8���~�ō���Ă���B�Ȃ�Ƃ����ē��{�̔_�Ƃ��l��������8���~�ō�邱�Ƃɂ�����A�����̑�������2���~�����Ă��܂��B�����̗��v���S�̂Ƃ��đ�����킯�ł͂Ȃ��B �@����8���~�̔_�Y����A�����Ă��܂�����A�����̑�������8���~�����A8���~�̏��i������c��A8���~���̎��Ƃ���������B�c�j
http://www.asyura2.com/11/hasan72/msg/908.html �킽�������͈ȑO����u�O���[�o���Y���v�i�����ɂ́u���{������n��������O���[�o���Y���v�j��ᔻ���Ă����̂ł����A�A�����J�ł������悤�ȋc�_���N���Ă��܂��F
�R�����F�s�o�o�ŕč����������R�f�Ղւ̑㏞ 2015�N 04�� 13��
�m�P�O���@���C�^�[�n - ���R�f�Ղ͕č����{�̍����t���B�I�o�}�����������m�A�g����i�s�o�o�j�Ì��Ɍ����A���{�ɖf�Ռ��������ς˂�u�t�@�X�g�g���b�N�v�ƌĂ��f�Ց��i�����i�s�o�`�j�̎擾�Ɉӗ~�������̂́A���{�̓`���̈ꕔ�ł�����B�������A��A�̏؋��������Ƃ���ɂ��ƁA���W�r��̒Ꮚ�����ɒʏ���̊��S�ȍŌb���ҋ���F�߂�A���X�ɂ��ĕč��̃R�X�g���S�ɂȂ�B
�G�R�m�~�X�g�����͎��R�f�Ղ������炷�傫�ȗ��v�Ɋւ��āA�ÓT�h�o�ϊw�̊�{�����ł����r�D�ʐ������������ɏo���B�����f�Ց��荑�E�n�悪�݂��ɍł����ӂȕ���ɏW������A�ŏI�I�ɑo�����L���ɂȂ�Ǝ咣����̂��B �č��͂P�X���I�A���̗��_�����ł��邱�Ƃ��ؖ������B���B�����ɓS��ȉԂ�A�o�������ŁA�u�����B�ȁv�����̎Y�Ƃ�ی삷�邽�߂ɍ����ł�݂����B�P�W�X�O�N��܂łɕč��͂قƂ�ǂ̐�i�Y�ƕ���ɂ����ĉp���𗽉킵���B�č��ɂƂ��Ă��ꂪ�e�ՂɒB���ł���ڕW�ł������̂́A�����̉p���������Ȏ��R�f�Ղ̎�������Ȃɖڎw���Ă������߂��B �ŐV�̌����́A���݂ɉ��b���y�ڂ��f�Ղ���уI�t�V���A�����O�i�O���ւ̋Ɩ��ڊǁE�Ɩ��ϑ��j�̑��荑�ƁA�����ł͂Ȃ����荑���čl����ꏕ�ɂȂ�B�f�Ղ������̓I�t�V���A�����O�̑��荑����i���������ꍇ�A�č��̒����͏㏸����X���ɂ���B�������A�r�㍑�����肾�����ꍇ�A�Ƃ�킯�n���x���Ⴂ�J���҂⒆���x�̘J���҂̒����͒ቺ����B ���̂悤�Ȓ����̉������ʂ͐����ƂɌ��������Ƃł͂Ȃ��A���̋ƊE�̓����悤�ȐE�ɂ��y�ԁB��ʂɐ����Ƃ̒����̓T�[�r�X�Ƃ�荂���B�������A�A����Y�̊C�O�ړ]��������ƁA�����Ƃ̌ٗp�팸���͈͂�i�Ƌ��܂�A�E���������J���҂��]���������̒Ⴂ�T�[�r�X�ƂɈڍs����h�~�m���ʂ�������B�������Ē����̏k���͑S�̂ɋy�Ԃ̂ł���B �����̒ቺ���͂́A���Y�̊C�O�ړ]�����r�㍑����̗A���ɂ������炳���ꍇ�̕����͂邩�ɉe�����傫���B����͒������f�Ց��荑�ł���ꍇ�ɍł������ɕ\���B��������A�����P�O�����������ۂɁA�č��̊֘A����E��̒����͑S�̂łU�D�U���ቺ�����B����ɁA�قڑS�ẴP�[�X�ɂ����Ē����̒ቺ�́A�Ƃ�킯���������̊w�������Ȃ��Ꮚ���J���҂ɍł��������Ō���^����B �č��̐����Ƃ̌ٗp�Ґ��͂P�X�V�O�N�㔼�Ƀs�[�N���}���A���̌�S�ʓI�Ɍ����X���ɂ���B�������A���������E�f�Ջ@�ցi�v�s�n�j�ɉ��������Q�O�O�O�N�����炩�ɕ���_�ƂȂ����B�������璆������̏W���I����œI�ȕč��s��ւ̐��i�������n�܂����̂��B �Q�O�O�O���Q�O�O�X�N�̊Ԃɕč��͖�U�O�O���l���̌ٗp���������B����͂Q�O�O�O�N�̌ٗp�҂̖�R���̂P�ɑ�������B�ŋ߂͊ɂ₩�Ȍٗp���݂��A�����ƂłQ�O�P�O�N�ȍ~�ɂW�T���l�̐E���n�o���ꂽ���A�������ߍ��킹��ɂ͏��Ȃ�����B ���ł��j��I�ȃu�����h�Ƃ��Ă̒����̋����͂��a瀂�ł���B���E�ōł��������̍������S��Ђ̂P�ł���ăj���[�R�A�̗���l����Ε�����B�_���E�f�B�~�b�R���ō��o�c�ӔC�ҁi�b�d�n�j�ɂ��ƁA�j���[�R�A���P�g���̑e�|���Y�ɗv����J�����Ԃ͂킸���O�D�S���ԁA�����ɂ��Ė�W���P�O�h���ɂ����Ȃ��B�����̑唼�̓X�N���b�v���B����A�����ł͊����ȓS�z���g�p���Ă��邤���A�č��ւ̏o�׃R�X�g�͂P�g���������S�O�h�����B �f�B�~�b�R���͋ߒ��u�A�����J���E���[�h�v�̒��ŁA���ɒ����̘J���R�X�g���[���������ꍇ�ł��A�����̐��S�Ǝ҂������s��Ńj���[�R�A�����l�Ŕ̔����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ǝ咣����B�������A�ߋ��P�N�Ԃ̂����唼�ŁA�����̒ቿ�i�̓S�|���i�͕č��s��ɂȂ����ł��ė������Ă���A�f�B�~�b�R���͈�@�ȁu�s�������i�_���s���O�j�v�̖��炩�ȏ؋����Ǝw�E����B����ɑ��Ē������{�͓��R�̂悤�ɁA���ׂĂ͌����Ȗf�Ճ��[���ɂ̂��Ƃ����s�ׂ��Ǝ咣���Ă���B �������A�����͂����ƈقȂ郋�[���Ɋ�Â��ē����Ă���B�L�͂Ȑ����Ɗ�Ƃ͑唼�����L��Ƃł���A�������B����p�n�̃��[�X�A�Ő���R����܂ŋ��Y�}�����肷��R�X�g�Œ���Ă���A������`�Ő��{�̕⏕���Ă��邩�炾�B ����Ɉ������Ƃɒ������{�͋ߔN�A���B��č���Ƃɑ��A��^�_��̎̏����Ƃ��ē����Z�p���ړ]����悤���͂��|���Ă���B �����ȗ�͍��L��Ƃ̒������p��@�i�b�`�b�b�j�ƕčq��E�F���֘A��ƂV�Ђ̊Ԃ̒�g���B�č����ł͍q��@���{�[�C���O�ƃ[�l�����E�G���N�g���b�N�i�f�d�j���哱�����B�Q�������Ċ�Ƃ͂��ׂĒ����ɑ��Ă��Ȃ�̓����Z�p����Ă���B�f�d�̏d�v���Y�ł���q��d�q�H�w�Z�p�͌_��̎�v�������߂�B��i�̍q��H�w�Z�p�͒��������R���ʂŋ����S�����������삾�B�f�d�͋Z�p���R������ɘR�������邱�Ƃ͂Ȃ��Ǝ咣���A����ɔ�����؋������������ꍇ�̓v���W�F�N�g���ׂĂ��I������Ɩ��Ă���B���R�̂��Ƃ��B �����̂���܂ł̎��т�����Ɗy�ϓI�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�����͌��݁A���E�ő�̍����S���Y�Ƃ�L���A�L�^�I�ȃX�s�[�h�œS�������𐄐i����B�ƃV�[�����X�A���d�H�ƂȂǐ�i����Ƃ���ԗ����w�����A�����̋Z�p�����А��i�ɉ��p���郊�o�[�X�E�G���W�j�A�����O��i�߂Ă���B����炪�W���I�Ȏ�i�ƂȂ����̂��B�����ɑ���R���s���[�^�[�����_��̑唼�́A�x���_�[�����\�t�g�E�G�A�̐v�}�ɓ�����\�[�X�R�[�h�̃R�s�[�𒆍����{�ɒ��邱�Ƃ��`���t���Ă���B�ǂ�ȃn�C�e�N��Ƃł������̃J�M������̂̓\�[�X�R�[�h���B �����͈̑�ȍ��Ƃł���A��}�ȍ˔\�ƋΕׂȐl���������B�������A���{�̊����@�\�ɂ͐[���ȕ��s���I�悵�Ă���A���������̓��[�����Č��悾���̖����邱�Ƃ��������B���\�N�O�ɕč��̓S�|��Ђ��O����Ƃ̃_���s���O�ɕs���\�����Ă��s�������A�����̕Ċ�Ƃ͂���ɐi�������������肩��̕ی�[�u�����߂Ă���Ǝ~�߂��l�����邩������Ȃ��B�����A���Ƀj���[�R�A�̂悤�Ȋ�Ƃɂ́A�������������͂��Ă͂܂�Ȃ��B �����������̂悤�Ȏ��D�I�ȋ�������ɑ��āA�@�Ɋ�Â�������𓊗^���ׂ������B�����͂s�o�o���ɎQ�����Ă��Ȃ����A���̋}���Ȍo�ϔ��W�͓r�㍑���ׂĂ̖ڎw���ڕW�ƂȂ����B�č����{�́A������Ƃɑ�������ȏ������m�ۂ���������ł��ď��߂āA�V�����Ƃ̎��R�f�Ջ���̌������n�߂�ׂ����B
http://jp.reuters.com/article/jp_column/idJPKBN0N40JS20150413?sp=true �@�O���[�o���Y���Ɋ�Â����R�f�Ձ|�����ł́u���m�E�T�[�r�X�v�Ɍ��炸�A�u�J�l�i���{�j�v�����āu�q�g�i�J���ҁj�v�̈ړ��̎��R�����܂݂܂����|�ɂ���i���̍����͕n�������Ă����܂��B���ɁA�O���[�o���X�^���_�[�h���m���������E�ł́A���i���T�[�r�X���A �u�ǂ��̍��ō���Ă��A�����悤�ȕi���v �@�ɂȂ��Ă��܂��̂ł��B
�@�悭�A�_�Ɓu���v�v�����Ԑl���u�t�����l�����߂ā`�A���E�Ő키�`�v�ȂǂƎ咣���Ă��܂����A�����ɂ͍���ł��B�O���[�o���Y���ɂ����āA�ł��d�v�Ȃ̂́u���i�v�Ȃ̂ł��B
�@�Ƃ������A�t�����l�A�t�����l�����Ȃ�A�܂��͂�������Ă݂Ȃ����B�t�����l�����߂āA���i���P�O�{���Ђ�����Ԃ��Ă��猾���Ă���A�ĂȂ���ł��B
�@�O���[�o���Y�����i�W�������ʁA��i������ٗp�������邩�A�������͍����̌ٗp���u�����l����v����̊O���ږ��ɒD���Ă����܂��B���{�A�����A�k�Ă̍����̎���������������A�n�������A���E�́u�t���b�g������v���ƂɂȂ�킯�ł��B
���������A��i���̊�Ƃ̌o�c�҂��H����O���Ɉړ]����̂́A������̕����u�ׂ���v���߂ł��B��i�����̘J���҂̌ٗp�������A�ނ炪�҂��ł�����������ƌo�c�ҁA�����ƁA�H�ꂪ�ړ]���ꂽ��̘J���ҁA�����ď���҂Ɉړ]����܂��B���Ȃ킿�A�����Ƃ��炵�Ă݂�u���{���v���v���ő剻�����̂ł��B
�@�{���A���{���v���̍ő剻�́A�u�Z�p�J�������v�u�l�ޓ����v�����āu�ݔ������v�Ƃ����A�����ɂ����铊�������Ŏ��������ׂ����̂ł��B�Ƃ͂����A�����g��͔�p���ł������܂��̂ŁA
�u����Ȗ��ʂȂ��ƂɃJ�l���g���Ȃ�A�O���ɍH����ړ]���Ď��{���v�����ő剻����v �@���ꂪ�A�O���[�o�����厑�{��`�̌���I���ő�́u�댯�v�Ȃ̂ł������܂��B
�@���_�A���{���O���Ɉړ]����A�Z���I�ɂ͗��v�������܂��B�Ƃ͂����A�����̓�������ׂ�ɂȂ邽�߁A�������I�ɂ͋Z�p�͂������A����ɍ������n�������Ă����܂��B
�@��i���́A����ɔ��W�r�㍑�����Ă����܂��B�t�ɁA�H���Z�p���ړ]����Ă��锭�W�r�㍑�́A����ɐ�i���̕����ɋ߂Â��܂��B
�@�ŏI�I�ɂ́A���E���t���b�g������A�߂ł����A�߂ł����Ƃ����b�ł��B
�@���ق��Ă��������E�E�E�B
�@�\����Ȃ��ł����A�킽�����͐��E�̑��̑S�Ă̍��X���n�����܂܂������Ƃ��Ă��A���{�����ɉh���A�������L���ɂȂ邱�Ƃ�]�݂܂��B�Ȃ��Ȃ�A�킽�����͓��{�����ł���A�O���̍����ł͂Ȃ����߂ł��B�����������Ƃł�����܂���̂ŁA�Y�킲�Ƃ������K�v���Ȃ��킯�ł��B
�@�܂��A���݂̐�i�����O���[�o���Y���́u�i�W�x���������������v�i�O���[�o���Y����ᔻ����ƁA�����u��������Ƃ����̂��I�v�Ƃ������Ă���P�����o�J������̂ŁA���������Ă����܂��j�A�����̍������L���ɂȂ�u�����̎l�����I�v�Ɠ����H���ɖ߂�A��i���̍����݂̂Ȃ炸�A�r�㍑�̍������������ƂɂȂ�ł��傤�B���R�́A����Ŗc�������i���̎��v�ɑ��A�r�㍑�����u�����Ŕ��W�������Z�p�A�m�E�n�E�Ɋ�Â����Y�������i�A�T�[�r�X�v��A�o���Ă������Ƃ��ł��邽�߂ł��B
�@�O�����{���r�㍑�ɂ���Ă��āA�H������݂��A�����J���҂������g���Ȃ����i���ɗA�o���郂�f���ł́A�r�㍑���ɐ^�̈Ӗ��Łu�����\�́v�͂��܂���B�܂�͐������Ӗ��́u�o�ϐ����v�͕s�\�Ȃ̂ł��B
�@�����́A����𗝉����Ă��܂��B�����炱���A�O�����{�������Ƃ��́A�u���т���v�������A�劽�}���A�����ɋZ�p���ړ]��������A�u���S�̊�v�ƂȂ�A�e�͂Ȃ��ǂ��o�����Ƃ���킯�ł��B�i�t�ɁA������̎��Ȃ������́A�ǂ��o���܂��j
�@�Z���̗��v��Nj�������i���i���ɍ��������̂����{�j�̊�ƌo�c�҂����́A�����́u�����v�ɂ��������x����A���⎩���̈��S�ۏ����@�Ɋׂ�Ă��܂����킯�ł������܂��B
�@������ɂ���A���R�f�Ո�Ƃ��Ă��A�b�̓V���v���ł͂Ȃ��̂ł��B�{�G���g���[�ɏ�����Ă���u���v�ɃC���v�b�g���邾���ŁA
�u�s�o�o�͎��R�f�Ղł��B���R���������ł��i�|�������������ۂɂ킽�����Ɍ������Z���t���̂܂܂ł��j�v �@���邢�́A �u��r�D�ʘ_�����邩��A���R�f�Ղ͏�ɑP�v �@�ȂǂƎq�����݂����Ƃ��咣���A�O���[�o���Y����s�o�o�𐄐i���Ă���A�����A�����Ɂu�댯���v��������ł��傤�H
http://ameblo.jp/takaakimitsuhashi/ �Z�C�̉����̎��� 2015-06-04
�@���̌o�ς��������钆�A�����݂̂��㏸����B������s�̋��Z�ɘa�ɂ��ւ�炸�A���̌o�ςɂ����铊�����������A�s��������������J�l���،��s��ɗ��ꍞ�ށB���{�Ȃǂ̎�v���Ɠ������ۂ��A�����ł��N���Ă��܂��B
�@�����Ƃ��A�����̊����㏸�y�[�X�́u�ɒ[�ɑ����v���߁A�߁X�A�Q�O�O�W�N���l�ɏ�C�����s�ꂪ�\������\���͌����ĒႭ�Ȃ��Ǝv���܂��B��C�����w���̎������z�́A�U���P�����_�őΑO�N��Q�D�R�V�{�ɖc�����܂����B
�@��L�́u���̌o�ς��U���Ȃ����A�����݂̂��㏸���錻�ہv�A���Ȃ킿�����Ǝ��Y���l�̘����ɂ��āA��ꐶ���o�ό������̌F��p���������낵���K�ȃR�����������Ă������������̂ŁA���Љ�B
�w�R�����F�J�l�]���A�����㏸�̔w�i���F��p����
http://jp.reuters.com/article/jp_forum/idJPKBN0OI15Z20150602
�F��p�� ��ꐶ���o�ό������@��ȃG�R�m�~�X�g
�m�����@�Q���n - �Q���~��˔j�������o���ϊ������A�ڐ�ǂ�ǂ����㏸���Ă����������Ƃ����X�g�[���[�������I�ɐ������邱�Ƃ́A�G�R�m�~�X�g�ɂ͂炢�Ƃ��낾�B �@������A�ŋ߂̓��{�̌o�ώw�W�͈������̂��ڗ��B�����̃t�@���_�����^���Y�����ł͐������Â炢�B�S���̏���x�o���傫���������A���Y���v���S�\�U���ɂ����Ēᒲ���B�T����{�ɔ��\���ꂽ���Z�͗ǂ��������A����͉ߋ��̋Ɛъg��ł���B���{�̌i�C�́A�u�����ڂł݂ėǂ��Ȃ��Ă����v�ƛU�Șb�@��p���Đ���������Ȃ��B �����Ŕ��z���t�]�����āA�u�i�C�������݂��邩��]��}�l�[�������������グ�Ă���v�Ɛ������Ă݂悤�B����ƁA��������Ɛ����ł���B����͓��{�݂̂Ȃ炸�A�č��⒆���ɂ����ʂ��邱�Ƃ��B �@���Z�ɘa�̌��ʂ������Ă��邩��A��s���̋��C�\�z�Ɋ�Â��A���Y���i�̏㏸���㉟�������Ƃ��������ł���B�����㏸�́A�}�l�^���[�ȗv���Ȃ̂��B�i�㗪�j�x �@���Ƃ́u�o�ϊw�v�̑匳�Ɋւ��܂��B
�@���̌o�ςɂ����āA�o�ϊw�̑O��ł���A
�u���������v��n�o����A�Z�C�̖@���v �@�Ȃ�ʁA �u�Z�C�̉����v �@���������Ă���Ȃ�A���Z�ɘa�ɂ����̌o�ςœ������g�傷��͂��ł��B���Ȃ킿�A��Ƃ���s�Z�����A�������g�傷��킯�ł��B
�@�Ƃ��낪�A���݂̐��E�i���{�A�ł͂���܂���j�ł͎��v���s�����A�Z�C�̉������S���������Ă��܂���B���ʓI�ɁA���Z�ɘa�ŋ�s�Ɂu���J�l��݂��₷������v�����{���Ă��A���J�l�͎��̌o�ςɂ͌������܂���B�����s��i���邢�͓y�n�j�Ɍ������A���Y���i�������グ�܂��B
�@���Α��ŁA���̌o�ς̓����͊����������A�܂�́u���v�v�������Ȃ����߁A�f�c�o���}�C�i�X�����ɂȂ�i�P�|�R�����̃A�����J�j�A��p�Ԑ��Y���������i�����j�A��������������𑱂���i���{�j�Ƃ����킯�ł������܂��B
�@��L�́u�Z�C�̉����̌��v�ɐ����S���҂��C���t���A���v�n�o��Ƃ����K�Ȑ����ł��Ă��悳�����Ȃ��̂ł����A�����̏㏸���u���̌o�ς̕s�U���B���Ă��܂��Ă���v�Ƃ����̂�����Ȃ̂ł������܂��B
�@���[�}���V���b�N�O���A�قړ������ۂ��������A�������͂��߂Ƃ��鎑�Y���i����\�����A���̌o�ς���C�ɒɂ߂��܂����B�������Ƃ��N����̂ł��傤���B
�@���邢�́A���̂܂��Y���i�Ə����̘������g�債�Ă����̂��B�܂��ɁA�s�P�e�B�̂����u�������v���p������킯�ł����A�����Ȃ�Ɓu�����s�\�Ȋi���v���g�債�A�Љ�͕s���艻���Ă�������Ȃ��ł��傤�B
�@������ɂ���A�嗬�h�o�ϊw�̊�ՂƂȂ��Ă���u�Z�C�̉����v�́A�܂��ɎƂ��ċ@�\���Ă��܂��Ă��܂��B�e���́A���}�ɂ��́u�Z�C�̉����̎����v��ł������K�v������̂ł��B
http://ameblo.jp/takaakimitsuhashi/entry-12034756797.html
�o�ϐ����̎O�̃p�^�[�� 14�^7�^7�i804���j •�o�ϐ����̒莮�i���f���j ���T�́A���߂Čo�ϐ����̃��J�j�Y���ɂ��ďq�ׂ�B���̃e�[�}�͂���܂ʼn������グ�Ă����B�܂�
08�^9�^15�i��541���j�u�o�ϐ����̒莮�i���f���j�v
http://www.adpweb.com/eco/eco541.html
�Ő��������悤�ɁA�o�ϊw�̋��ȏ��ɂ́A
g�i�o�ϐ������j��s�i���~���j�^v�i���{�W���j�{n�i�J���l���������j �Ŏ������o�ϐ����̒莮������B
���������̒莮���K�肵�Ă���̂͋����T�C�h�ł���B
�܂肱�̒莮�͈Öق̂����ɐ��Y�������̂��S�ď����邱�Ƃ�z�肵�Ă���B �܂��ɂ���͌ÓT�h�o�ϊw�i�V�ÓT�h���܂߁j�́u�Z�C�̖@���v�̐��E�ł���B
�������P�C���Y�́u�Z�C�̖@���v����������͓̂���ȏɂ����Ă݂̂Ɛ�������B�ނ͌ÓT�h�o�ϊw�����̂悤�ȓ��ꗝ�_�ł��邱�Ƃ��ؖ����邽�߁u��ʗ��_�v�����̂ł���B
�M�҂��A�u�Z�C�̖@���v���ʗp����̂́A���Y�͂̋ɂ߂ĖR����������̂�傫�Ȑ푈�Ő��Y�ݔ����O��I�ɔj���Ƃ���������ȃP�[�X�Ɍ�����ƔF�����Ă���B
���ȏ��Ŋw�Ԍo�ϐ������_�́A������A�ÓT�h�o�ϊw�̐��E�ł���B
��L�̒莮�ɏ]���A�o�ϐ�������傫������ɂ͒��~����傫�����A���{�W��������������K�v������B���{�W��������������ɂ́A�Z�p�i���ɂ�鐶�Y���̌����Љ�̍\�����v�Ƃ������ƂɂȂ�B�܂��J���l���𑝂₷���Ƃ��L���Ƃ������ƂɂȂ�B �����������͑S�ċ����T�C�h�̘b�ł���A�܂�����g�i�o�ϐ������j�͐��ݓI�Ȑ������ɉ߂��Ȃ��B���������ăP�C���Y�̎w�E�����悤�Ȏ��v�s�����N��A����͑S���������Ȃ��莮�ɂȂ�B �Ƃ��낪�قƂ�ǂ̌o�ϊw�҂�G�R�m�~�X�g�i����ɂ͑����̐����Ƃ�}�X�R�~�l�܂Łj�́A�����ł��𗧂����̂��̒莮�ɂ����݂��Ă���B ����ǂ��납�����B�����̒莮�ɂ����݂��Ă���Ƃ����������������Ă��Ȃ��̂ł���B
�M�҂́A�P���Ɏ��v������Όo�ς͐������A���Ɏ��v����������Όo�ς͒���A�ꍇ�ɂ���Ă̓}�C�i�X�����ɂȂ�Ƃ����Ǝ咣���Ă����B�܂菭�Ȃ��Ƃ������̓��{�ɂƂ��āA�����T�C�h�̌o�ϐ����̒莮�Ȃ܂�ŊW���Ȃ��B�܂����Ԃɗ��z���Ă���o�ϐ����ւ̏���Ⳃ͂قƂ�ǂ��R�ł���B
�V������r�㍑�������o�ϐ����𑱂��Ă���̂͑傫�Ȏ��v�����邩��ł���B�����Ȃ��r�㍑�̐l�X�ɂ́A����T�[�r�X�ɑ��ċQ�슴�Ɏ����傫�Ȏ��v������B�������ɂ��̂悤�ȍ��ɂ͌o�ϐ����̒莮���K�p�ł��邩������Ȃ��B ���ہA������x�̏����i��̓I�ɂ͐����̈�����b�I�ȍ�������Ȃǁj�������A�����A���X�\���Ȏ��v������V������r�㍑�͌o�ϐ����𑱂��邱�Ƃ��ł���B���Ɏ������s�����Ă��Ă��A�����@��R�����Ȃ�����i�����珁��ȗ]�莑��������Ă���B�܂蒙�~�̕K�v���͏������B�܂��Z�p���Ȃ��Ƃ���i������Z�p�����ŐV�ݔ������邱�Ƃ��ł���B �܂��o�ϔ��W�ɕK�v�ȃC���t�����A�Ⴆ�Όg�ѓd�b�Ȃǂ̓o��ɂ���ăn�[�h�����Ⴍ�Ȃ��Ă���i�ȑO�͓d�b���Ԃ̐ݒu�H������n�߂�K�v���������j�B�v����ɉ����Ȏ��v��������A�ǂ̂悤�ȍ��ł��o�ϐ����͉\�Ȃ̂ł���B������ɂ��Ă��K���ɘa��\�����v�Ȃ�Čo�ϐ����ɂقƂ�NJW���Ȃ��B
��i���̒��ŁA�č��͔�r�I�����o�ϐ����𑱂��Ă����B����ɂ��ĕM�҂�
01�^6�^18�i��212���j�u���v�������Ă̌o�ϐ����v
http://www.adpweb.com/eco/eco212.html
�ŕč��̒��~�����ቺ���Ă��邱�Ƃɒ��ڂ������͂��s�����B���������ɂȂ��Ďv������͕s�\���Ȑ����������Ɗ�����B�M�҂́A�č��ɗ��������c��Ȉږ��i���@�E��@���킸�j�̉e���������ƍl����ׂ��������ƍ����v���Ă���B
�č��͐�i���̒��ł��߂��炵���l�����������傫�ȍ��ł���B����͈ږ��̉e�����傫���B���Ɉږ��̏o�����͑傫���A�ږ��̑�\�ł���q�X�p�j�b�N�n�Z�������ł�����5,000���l�i�S�l����17���j���z���Ă���B���疜���̈ږ��̗����́A�č��ɐV�����E�r�㍑�̈ꍑ�����܂ꂽ�悤�Ȃ��̂ł���B�����������ɕč��ւ���Ă����̂�����ږ��ɂ͉����Ȏ��v������B����ɂ���� 07�^11�^5�i��503���j�u�č��̃T�u�v���C�����v
http://www.adpweb.com/eco/eco503.html
���ŏq�ׂ��悤�ɁA����܂ŕč��̌o�ϐ�������������x�����グ����Ă����ƕM�҂͍l����B
•���_�I�ɕ�����
��T���Ńt�����X�o�ϊw�҂̃g�}�E�s�P�e�B���A1930�N�ォ��1980�N�܂ŏ����������č��̌o�ϊi�����A1980�N�i���[�K���哝�̎���A�܂�V�ێ��`�䓪���j�ȍ~�傫���Ȃ����Ǝw�E�����b�������B�����Čo�ϊi�����傫���Ȃ�ƁA���S�̂ł͒��~�������o�ϐ����ɂ̓}�C�i�X�ɓ����ƃg�}�E�s�P�e�B�͎咣���Ă���B���Ȃ킿�č��ł͓��Ƀq�X�p�j�b�N�n�̈ږ��������邱�Ƃɂ����v�����A���̃}�C�i�X��ł������Ă����Ƃ�������B �Ƃ��낪�č��̔�r�I�����o�ϐ������́A���[�K���哝�̈ȍ~�̋K���ɘa��\�����v�̂��A�ƐV�ÓT�h�̃G�R�m�~�X�g�͊Ԕ��������Ƃ����������Ă���B �ޓ��́A�o�ϐ��������v�Ō��܂�Ƃ������Ƃ��ǂ����Ă��F�߂����Ȃ��̂ł���B �����Čo�ϐ����̒莮���瓱����闝�_�Ɓu�o�ϐ����͎��v�����߂�v�Ƃ����o�ϗ��_�i�M�҂Ȃǂ��咣����j�Ƃ̊Ԃɂ͑傫�ȍa������B �������͂����肳�����B���Ȃ܂ܓ��{�Ōo�Ϙ_�c���i�߂��Ă����B���ꂪ�����œ��{�̌o�ϊw�҂�G�R�m�~�X�g�������Ă��邱�Ƃ�������ɂ����������Ă���B �o�ϊw�҂́A�w�Z�ŋ����T�C�h�̐V�ÓT�h�̌o�ϐ������_�̒莮��������B �Ƃ��낪�ޓ��́A���ۂ̌o�ϐ����̎��т�\�z�̕��͂ɂ́A���t�{���쐬����o�ϐ����̐��l�i����l�A����l�Ȃǁj���g���B ���̓��t�{�̐��l�́A�����T�C�h�ł͂Ȃ����v�T�C�h��Ϗグ�����̂ł���B��̓I�ɂ́A�l����A�ݔ������A���������A�Z����A���{����A�ɓ����A�����ď��A�o�i�A�o�|�A���j�����v�������̂ł���B
�܂�ޓ��́A�o�ϗ��_�͋����T�C�h�ł��邪�A�����̌o�ϕ��͎͂��v�T�C�h�ōs���Ƃ��������_�I�ɕ����Ԃł���B
������떂�������߂ɁA�ޓ��͋ɂ߂Ĉ����ȍH���g���B �Ⴆ�Ύ��v�Ƌ����̃M���b�v�ł���f�t���M���b�v���ُ�ɏ������Z�o����̂ł���B
�o�ϐ������_���\�z�����̂́A�n���b�h��T�~���G���\���Ƃ������P�C���Y�̒�q�B�ł���B�������ޓ���������o�ϐ����̒莮�́A�����T�C�h�����ɒ��ڂ������̂ł���A������A���v�T�C�h�����Ă���B
�B����v�T�C�h���l�������̂��n���b�h�ł���B�n���b�h�́A�����B��������o�ϐ������_�ł́A�����̕s�ύt�Ɋׂ�댯�������邱�Ƃ�F�����Ă����i�ύt�_�̓i�C�t�̐n�̏������悤�ɕs����Ɛ������j�B�����̓��{�Ȃǂ̐�i���̌o�ς�����A�n���b�h�̔F���������������ƌ�����B�����Ƃ��T�~���G���\����\���[�ȂǓ����V�ÓT�h�ƌĂꂽ�o�ϊw�҂���ɍl����ς��Ă���B����ɂ��Ă͗��T���ŐG���B
�M�҂́A�o�ϔ��W�i�K�ɂ���ēK�p�ł���o�ϐ����̃��J�j�Y���͈قȂ�ƍl����B�����M�҂͎O�̃p�^�[���ɕ����ė������Ă���B
��͐V������r�㍑�̂悤�ȏ\���Ȏ��v�̂��鍑�̂��̂ł���A ������͓��{�≢�B�̐�i���̂悤�ɖ����I�Ȏ��v�s���Ɋׂ鍑�̌o�ϐ������J�j�Y���ł���B �����������Ȃ�A�č��̂悤�ȐV�����E�r�㍑�̗v�f�������̐����p�^�[��������B �܂苟���T�C�h�̌o�ϐ����̒莮��������x���Ă͂܂鍑�ƑS���K�p�ł��Ȃ����A�����ĕč��̂悤�Ȃ����̒��Ԃ̍��Ƃ������ƂɂȂ�i�������č��͍�����{�Ȃǂ̃O���[�v�ɋߕt���ƍl����E�E�܂�T�}�[�Y�̌����Ă��钷����j�B ���̂悤�Ȃ��̍����u����Ă�������Čo�ϐ���������i�߂邩��A��̕�����Ȃ����ƂɂȂ�B�Ⴆ�����ɏ\���Ȏ��v���Ȃ���ԂŐݔ��������h�����Ă��A���Ԋ�Ƃ��ݔ��������s���͂����Ȃ��i�ݔ����������v�̂���V�����E�r�㍑�ɗ����͓̂�����O�j�B�܂�NISA�i���z������ېŐ��x�j���g�[����A�܂��܂��l����������邱�ƂɂȂ�B�܂��Ă����ő��łȂ�Ă����Ă̑��ł���B
http://www.adpweb.com/eco/eco804.html
�|���R�c�o�ϗ��_�̐M��ҒB 14�^7�^14�i805���j
�u�Z�C�̖@���v���Ӗ��������������������
��T���ŁA g�i�o�ϐ������j��s�i���~���j�^v�i���{�W���j�{n�i�J���l���������j �Ŏ������o�ϐ����̒莮�͌ÓT�h�i�V�ÓT�h���܂ށj�̌o�ϗ��_�̖{�����������̂Ɛ��������B ����͋����T�C�h�������K�肵�����̂ł���B����A���v�T�C�h�ł͍�������̂͑S�ď�����Ƃ����u�Z�C�̖@���v���Öق̂����ɑz�肳��Ă���B���������Č����̌o�ςŎ��v�s����������O�ɂȂ�Ή��̉��l���Ȃ��莮�ɂȂ�B
�܂薝���I�Ɏ��v���s�����Ă��鍡���̓��{�Ȃǐ�i���ɂƂ��ẮA�قƂ�NJW�̂Ȃ��莮�ł���B�����̂悤�Ȓᐬ���ɂȂ�A���v�T�C�h���������Ă���Ώ\���ł���A�����T�C�h�͂قƂ�ǖ������ėǂ��B
�Ƃ��낪�𗧂����̌o�ϊw�҂�G�R�m�~�X�g�́A���ς�炸���Ƀ|���R�c�ƂȂ������̒莮�ɂ����݂��Čo�ϐ����헪�Ƃ������Ă���̂���������B
���̗�����e�Ղɂ��邽�߁As�i���~���j��v�i���{�W���j�ɂ��Ă̐������s���i���������ϒl�ƌ��E�l�ւ̌��y�͂�₱�����Ȃ�̂Ŋ�������j�B
v�i���{�W���j�͎��{�iK�j�^�����Y�z�iY�j�ŎZ�o�����B ���{�iK�j�͑����{�X�g�b�N�ł���A�����Y�z�iY�j��GDP�i���������Y�j����������Ɠǂݑւ��Ă��ǂ��B v�i���{�W���j�͂�菬���Ȏ��{�iK�j�ł��傫��GDP���Y�ݏo�����ł͏������Ȃ�B�܂肱�̐��l���������قǐ��Y�����̗ǂ����ł���B
�܂��ÓT�h�o�ϊw�ł�
S�i���~�j��I�i�����j�� s�i���~���j��i�i�������j ���������Ă��邱�ƂɂȂ��Ă���B����������I�i�����j��s�i���~���j���傫��v�i���{�W���j���������i���Y�����̗ǂ��j���ق�g�i�o�ϐ������j�͑傫���Ȃ�B �܂蒙�~�i�܂蓊���j���傫�����Y�����̍������قnjo�ϐ����������Ƃ����A������₷���b�ł���i���������ǂ����͕ʁj�B
�܂����Y���iGDP�ƌ��Ȃ��ėǂ��j��������Ǝ��{���ɕ����A���̋c�_��⑫����B
���Y���̑S�Ă�������Ŏ��{�����[���̍��́A�����{�X�g�b�N�������Ȃ��̂Ő��Y�͂������Ȃ��B���������ČÓT�h�o�ϊw�̐��E�ł͌o�ϐ������ł��Ȃ��ƂɂȂ�B���ɏ�����l�߁i���~�𑝂₷���ƂƓ����Ӗ��j�A����𓊎��ɉ��͍����o�ϐ����������ł���Ƃ������ƂɂȂ�B
����E���Ő��Y�ݔ�����œI�ȑŌ����������{�́A���A��������ݔ������Ɏ��������B���~�����コ��A�a�����̗����ւ̉ېł�Ə�����}���D���x�܂œ��������B�܂���Ƃ͑��z�̋�s�ؓ�����s���A�ŐV�s�̐��Y�ݔ��������i�Â��Đ��Y�����̈����ݔ����푈�Ŕj�ꂽ���Ƃ��K�������j�B���̂��ߓ��{�̊�Ƃ̎��Ȏ��{�䗦�͂����Ə����������B
�l�X���V�Z�p���w�ѓ��{�S�̂̐��Y���͔���I�Ɍ��サ���B����ɂ���ē��{��v�i���{�W���j�͉��Đ�i����菬�����܂ܐ��ڂ��Ă���i�X���Ƃ��Ă͋ߔN�傫���Ȃ��Ă��邪�j�B���̌��ʁA���{���i�͋��ٓI�ȋ����͂������ƂɂȂ����B���������Y�͂��傫���Ȃ�߂������ߓ��{�����ł͐��Y�����S������ꂸ�A�]�������Y���͗A�o�����悤�ɂȂ����B���A���{�̖f�Վ��x�͖����I�ɐԎ��ł��������A1964�N�̓����I�����s�b�N�̔N�����ɖf�Վ��x�������ɓ]�������B���̗l�q�� 11�^3�^7�i��653���j�u���{���f�����Ƃ�������v
http://www.adpweb.com/eco/eco653.html
�ŏЉ���B
���Ȃ��Ƃ�1973�N�̃I�C���V���b�N�܂œ��{�͍������x���̐ݔ��������������i����ȍ~�����{�̐ݔ�������GDP�䗦�͉��Ăɔ�ב傫���j�B���ꂪ�����œ��{�͉ߏ萶�Y�͂���ɕ����邱�ƂɂȂ����B���������ē��{�o�ς͌i�C��ނō������v���k������ƁA���ɗA�o�h���C�u���|����Ƃ�����ԂɂȂ����B
���������{�̖f�Վ��x�ƌo����x�̍��������g�傷��ɂ�A���Ă���̔��傫���Ȃ����B���̖f�Ղ̃C���o�����X�����̂��߉~�����v������A�]���ɓ��{�͂���ɏ]���Ă����i���̓_�������Ƒ傫���Ⴄ�j�B�������ǂꂾ���~���ɂȂ��Ă��A���{�͂��̃n�[�h�������z���f�Ս������ێ����Ă����B���̌��ʁA�Ƃ��Ƃ�1�h��76�~�ƌ��������炩�ɍs���߂������~���ɓ������B ���̂悤�Ɍ��Ă����1973�N�܂ł̍��x�o�ϐ������́A���{�o�ς͌ÓT�h�i�V�ÓT�h�j�o�ϊw�̌o�ϐ����̒莮���قړ��ěƂ܂��Ă����ƍl���ėǂ��B�푈�Œ��̐g���̂܂܂ɂȂ������{�����̎��v�i�e���r��①�ɂ��A���͎Ԃ�Z��������Ƃ���������j�͉����ł������i�l���\�����W���邪���̘b�͌���Ɂj�B�܂��ꎞ�I�ɐ��Y�ߏ�ɂȂ��Ă��]�萶�Y���͗A�o����Ηǂ������B���ɓ��{���i�͈��|�I�ȍ��ۋ����͂������Ă����B�܂��������̂͑S�ď���i�A�o���܂߁j�����Ƃ������u�Z�C�̖@���v��������x�Ӗ�������������͂������ɂ������B
•�����������
�����̕��ϓI�ȓ��{�l�́A�ꉞ�̑ϋv������ƏZ������L���Ă���B���������Ă��ꂩ����{�Ŕ���I�ɏ���L�т邱�Ƃ͍l�����Ȃ��B��������s�����Ă���Ƃ����Ȃ�A����͎Ⴂ�N��w�A���ɒ�����̔K�J���҂ł��낤�B������������ޓ��̐e���Z���Ԃ����L���Ă���A�������w������ӗ~�͎キ�Ȃ�B �������w���ӗ~���ア�ƌ����Ă��A�̂̓��{�i���x�o�ϐ������j�⍡���̐V�����E�r�㍑�Ɣ�ׂ��b�ł���B���ۂ̂Ƃ��덡�ł����{�̑ϋv�������Z��̍w���͂��������������x���ɂ���B�Ⴆ�Γ��{�ł͎����Ԃ��N��500������x����Ă���B�����͎����ԃu�[���ƌ����Ă��邪�A�N�Ԃ̔̔��䐔��2,500������x�ł���B�����̐l���͓��{��10�{�ł��邩��A�܂��l����̕��ςł͓��{�͒����̔{�̎Ԃ��w�����Ă���v�Z�ɂȂ�B �Z������{�͔N��100���ˌ��z����Ă��āA�l����2.5�{�̕č��Ƃقړ��������ł���i�������č��̕����Z��̑ϗp�N���͒����j�B�܂����Y�Ƃ⊔���㏸�̉��b�����ҒB�́A���z���i��ɔ����Ă���B���������S�̂̏���̐L�тƂ����_�ł͋ɂ߂Ďキ�A���������ł���A���̂܂܂ł͂ƂĂ��f�t���E�p�Ȃ�Ė����ƌ��������B
���{�Ȃǔ�r�I���������������������ɂ����ẮA�����͊��Ɉꑵ�̑ϋv�������Z������L���Ă���ƍl���ėǂ��B���������Ď��v�ƌ����Ă������ւ����v�����S�ɂȂ�B�܂蔚���I�Ȏ��v���Ƃ������̂͐��܂�ɂ����Ȃ��Ă���B
�܂����{�̂悤�ɍ�������x���������Ă��鍑�ł́A����ȏ�̏���͂ǂ����Ă��I��I�ɂȂ�B����l�̍l�����ɍ��E�����̂ł���B�����̐l�X�������悤�ȓd�����i��Ԃ����߂����ۂ͉ߋ��̂��̂ƂȂ����B�܂�̂̂悤�ȑ�q�b�g���i�Ƃ������̂�����ɂ����B�v����ɍ����̓��{�̕��ϓI�ȏ���x�����Ⴂ�킯�ł͂Ȃ��̂ŁA��������I�ɐL�����Ƃ�����̂ł���B
����܂Ōo�ϐ����������������V�����̌o�ς������������Ȃ��Ă���B���̂悤�Ȍ��ۂ��u����������㩁v�ƌĂԃP�[�X������B�u���������v�ɂȂ�O�Ɋ��ɂ������Ă���̂ł���B
�������u����������㩁v�����݂���Ȃ�u����������㩁v�������ėǂ��ƍl����B�M�҂́A�O����l�X�ɏ���ӗ~�Ɍ��E�݂����Ȃ��̂�����̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă����B����Ɋ֘A�� 98�^4�^20�i��62���j�u����̌��E���l����[�[����1�v
http://www.adpweb.com/eco/eco62.html �� 99�^8�^30�i��128���j�u���{�o�ςƗ~���̌��E�i����1�j�v
http://www.adpweb.com/eco/eco128.html �ȂǂŁA����҂̗~���ɂ����E������Ƃ��������������Ă����B
����������ɂ͏������v�͖����Ƃ����o�Ϙ_��������҂�����B
��������̂͑S�ď�����Ƃ����A��̊Ԕ����ȁu�Z�C�̖@���v�̐M��ҒB�ł���B �܂����ɂ͋K���ɘa�Ŏ��v��������Ƃ�������Ȍo�Ϙ_�C�Ő����҂܂ł���B����ɂ��� 04�^3�^29�i��338���j�u�K���ɘa�ɔ�т��l�X�v
http://www.adpweb.com/eco/eco338.html
���ŕM�҂́A�����Ɏ��v��������̂́A����A�e�A���t�A�q���Ƃ����������Ǒ��ɔ�������̂̋K���ɘa�����Əq�ׂ��i�K���ɘa�̉e���͂قڒ����Ɛ����j�B
�������M�҂́A���{�̏������v���m���̐L�����@�͂���Ǝ咣���Ă����B ����͍����̏����𑝂₷���Ƃł���B �����������̈�芄���͏���Ɍ������B���������𑝂₷�ɂ͍����x�o�傳����Ηǂ��B �ꎞ�I�ɍ��̍����Ԏ��������Ă��A�����A�Ŏ����ƂȂ��ĕԂ��ė���i���{�����̔��s��i�v�̓��┃����Ƃ�����i������j�B�܂������̒���������0.5���ƁA�s��͍��̑������Ñ����Ă���̂ł���B ���̎�̊̐S�Ȑ�����l�����A�u����v�Ƃ��u��ՋK���̊ɘa�v�ɂ�鐬���헪�Ƃ������Ă��邩�炨�������̂ł���B ����������Ă���l�X�́A���Ƀ|���R�c�Ŕp�������ɂ��ׂ��o�ϐ����̒莮�i���f���j�̐M��҂Ȃ̂ł���B
http://www.adpweb.com/eco/
��ƂɈ�䂪���v�̓V�� 14�^7�^21�i806���j
•���v�T�C�h�d���Ƃ�������
��T�܂ŏq�ׂ��悤�ɁA���ȏ��̌o�ϐ������_�͋����T�C�h�������K�肵�����̂ł���i���v�͏�ɏ\������Ƃ����������Öق̑O����j�B���R�A����͓��{�Ȃǐ��n�������̌����̌o�ςɂ͑S�����ěƂ܂�Ȃ��B�Ƃ��낪���ȏ��̂��̊Ԉ�����L�q��{���̂��ƂƐM���Ă���҂��ɂ߂đ����B���Ɋw�Z�ŁA�ꐶ�����A�o�ϊw���w�G�˃^�C�v�i���ȏ��ɏ����Ă��邱�Ƃ͐^���Ǝv�����݁A�_��ɕ��������邱�Ƃ��ł��Ȃ��^�C�v�j������ł���B�܂������������Ȃǂ̊e�펎���̌o�ϊw�̏o������̋��ȏ�����Ȃ̂Ŗ��͑傫���B ���̃^�C�v�͌o�ϊw�҂�G�R�m�~�X�g�����łȂ��A�����Ƃ⊯���A�����ă}�X�R�~�l�Ȃǂɂ悭������B�ޓ��́u�����͋��ȏ��ł悭�����Ԉ���Ă��Ȃ��B�Ԉ���Ă���̂͌����̕��v�ƌ����M���Ă���B���̂��߂����̃^�C�v���D�ނ̂��u�\�����v�v�ł���B�u�\�����v�v�ɂ���āA�����̌o�ς��������M���Ă���o�ϗ��_���@�\����`�ɕς��悤�Ƃ����̂ł���B�Ƃ��낪���̊Ԉ�����F�����������l�X���A�����̌o�ϐ���ɉe���͂������Ă���̂ł���ɖ���傫�����Ă���B���ہA�����̌o�ϐ����헪�̂قƂ�ǂ́A���̋��ȏ��̋L�q�ɉ��������̂ł���B
���ȏ��̌ÓT�h�o�ϊw�̒��S����́A���{�̒~�ςƐ��Y���̌���ł���B����Ɋ֘A�����Ⴆ�b������B���鋙�t��������C���ނ��Ă���Ƃ���B����������ł͎������H�ׂ镪�̋������ނ�Ȃ��i�܂萶�Y�����S�ď����鎩����������̌o�ςł���j�B�����ŋ���ނ鎞�Ԃ������āA���t�͖ԂƂ������{�����쐻����B���̖ԂƂ������{���ɂ���ĈȑO��葽���̋����l�邱�Ƃ��ł���B
���̌��ʁA���l�i���Y���j�ɗ]�肪���܂�A����ɂ���ċ��t�͂���ɕʂ̖Ԃ���ɓ���邱�Ƃ��ł���B�ԂƂ������{��������ɑ�����̂ŁA���l�ʂ������Ƒ����A�]��͂���ɑ傫���Ȃ�B�����ŋ��t�����{�ƂƓǂݑւ��A�o�ς̊T�O����l�̋��t����ꍑ�S�̂ɍL����ƐV�ÓT�h�̌o�ϐ������_�ɂȂ�B
�V�ÓT�h��
g�i�o�ϐ������j��s�i���~���j�^v�i���{�W���j�{n�i�J���l���������j �Ŏ������o�ϐ����̒莮����������A���{��`�o�ς͎����I�ɐ������郁�J�j�Y������݂��Ă��邱�ƂɂȂ�B���������Čo�ς͂���ɂ���Ăǂ��܂ł������I�Ȑ������\�Ƃ����b�ɂȂ�B ���̌o�ϐ������_�̐M��҂́A���{�o�ς����̒莮�ʂ�ɐ������Ȃ��̂́A���{�̌o�ςւ̗]���ȉ����J���g���̑��݂������Ƒi����B�ޓ��́A�Ⴆ�ΐ��{�����{�Ƃ���ŋ�����邱�Ƃɂ���Ď��{�~�ς̎ז������A����ʂȌ������ƂɎg���Ă���Ƃ����Ǝ咣���Ă����B�܂��ޓ��͊e��̋K���ɂ���Ď��{�~�ρi�����j�̋@���D���A����ɂ��̋K�������̌o�ς̐��Y����ቺ�������ƌ����Ă���B�܂��ɋ����T�C�h���������Ă���҂̌������ł���B
���̌ÓT�h�o�ϊw�ɉ������o�ϐ����̃��J�j�Y���͒P���ł���B���������Ă��Ƃ��@�������w��ł��Ȃ����������Ƃ⊯���ł��ȒP�ɗ����ł���B���ہA���x�o�ϐ������̓��{���v�������ׂ���A����܂ł̒����Ȃǂ̌o�ϐ�����ڂ̓�����ɂ���ƁA���̒莮�������Ƃ��炵��������B
��w�̋��t�͂��̒P���Ȍo�ϐ����_���w���ɋ����Đ��������Ă���B�������o�ϗ��_���̂��̂͒P���ł��邪�A�������Ƃ������̂��Ƃɕ��G�Ȑ����ʼn��ς��Ă���̂Ŋw�Ԏ҂ɂƂ��ē��������B�ޓ���������o�ϗ��_�́A�Ȃɂ��V���@���̋��`�▧���̉��`�ƒʂ��鏊������B���������Ċw�Ԏ҂͋�J���Đ�����������ƁA�����̃X�e�[�W���オ���Čo�ς��������悤�ȋC�ɂȂ�B �������̒P���ł��邪�c�t�Ȍo�ϗ��_�������Ă������{�̌o�ϊw�҂��ŋ߂ł͏����s���ɂȂ��Ă���i�قڃm�C���[�[��ԂɂȂ��Ă���ƌ����ėǂ��E�E����ɂ��Ă͗��T��グ��j�B����܂Ŕޓ��͒ᐬ���ɂȂ����͓̂��{�̐��{�̑Ή�����{�̎Љ�݂̍���ɖ�肪�������ƕЕt���Ă����B�܂���{�ŗL�̏�Q�œ��{�o�ς͒ᐬ���Ɋׂ����ƌ떂�����Ă����Ηǂ������̂ł���B
�Ƃ��낪���{�ɂ�����o�ϔF�����傫���ς�钛�����o�Ă����B
14�^6�^30�i��803���j�u�T�}�[�Y�ƃg�}�E�s�P�e�B�v
http://www.adpweb.com/eco/eco803.html
�Ŏ�グ���悤�ɁA���Ă̌o�ϐ����̘_�c�ɂ����āA�����T�C�h�ł͂Ȃ����v�T�C�h���d������Ƃ����l�������ڂ����悤�ɂȂ��Ă���i�M�҂Ɍ��킹��Γ�����O�̘b�j�B�M�҂́A���̂������̗��ꂪ���{�ɂ��y��ł���̂ł͂ƍl����B
�܂��g�}�E�s�P�e�B�̒���̓��{��Ŗ|���̂����o�ł���A�������o��Ɨ\�z�����B�܂��č��o�ς�������Ɋׂ����Ɛ����T�}�[�Y�́A���̑�Ƃ��ĕč��̘V���������C���t���̑���C���咣���Ă���i�܂��ɔ��𗁂тȂ�����̂�����{�ł���Ă������Ɓj�B���{�ł����̎��v�T�C�h�d���Ƃ����������y��ł���A����܂Łu�^���ԂȉR�v�����Ă����o�ϊw�W�҂̗��ꂪ�Ȃ��Ȃ�̂ł���B
•���E�āE���̔N�ԐV�Ԕ̔��䐔
�ÓT�h�i�V�ÓT�h���܂߁j�̌o�ϐ������_�������������Ƃ́A�̂��瑊���̐l�X���C�t���Ă���B�������Ɏ��v�������ō��ΑS�Ă�����鎞��̊�ƌo�c�҂́A�ǂꂾ�����Y�͂����グ�邩���o�c�̍ŏd�v�ۑ�ł������B���{�̍��x�o�ϐ������̊�ƌo�c���v�������ׂ�Ηǂ��B��s����̎ؓ����łǂ�ǂ�ݔ����������{���A�l���ق�����A���Y�H�������P���Đ��Y�����グ�邱�Ƃ��o�c�̗v���ł������B�܂��ɐV�ÓT�h�� g�i�o�ϐ������j��s�i���~���j�^v�i���{�W���j�{n�i�J���l���������j �Ŏ����o�ϐ����̒莮���K�p�ł��鐢�E�ł������B �Ƃ��낪�i�X�Ɣ��オ�L�тȂ�����ɂȂ�B�o�c�҂́A�V���i�̊J����̔����i���s�������łȂ��A�]�ƈ��̃��X�g���������Ȃ��č�������i�߂�悤�ɂȂ����B�����č��S�̂Ŕ���i���v�j���L�тȂ����ԂɊׂ����̂�����20�N���炢�i�M�҂́A����40�N���O���炱�̒���͏o�Ă����ƌ����Ă����j�̓��{�o�ςł���B ���{��`�o�ςł͎��v�s�����N��Ƃ����P�C���Y���_�́A���ꎞ�I�ɂ��Ă͂₳�ꂽ�B�������č��Y�Ƃ̋����͂��キ�Ȃ���������A�P�C���Y���_�ɑ��镗�����肪���܂����B�����P�C���Y���_��ے肵����̖����Ɏg��ꂽ�̂��A�Ȃ�ƃ|���R�c���R�̌ÓT�h�o�ϊw�ł������B
�o�ϐ������������Y�͂������A���̂������v�s�����N�邱�Ƃ͒N�ł�������B�Ƃ��낪���{�̌o�ϊw�҂́A���̓�����O�̂��Ƃ��ɔF�߂悤�Ƃ͂��Ȃ��i�������|�����Ă���̂ł��낤�j�B���̂���������������̕��@�Ƃ��āA�e���̐V�Ԕ̔��䐔�̐��ڂ���グ�A����͂��Ă݂�B
���̕\�͓��{�A�č��A�����̔N�ԐV�Ԕ̔��䐔�̐��ڂ������Ă���B���������{�����́A�x�[�X���N�x�ł���A�܂�98�N�x����01�N�x�܂ł͏�p�Ԃ݂̂̏W�v�ł���B
���E�āE���̔N�ԐV�Ԕ̔��䐔�i����j
�N�@�@���{ �@��@�@�����@
98
�i414�j 1,544 167 99
�i419�j 1,677 208 00
�i426�j 1,724 215 01
�i430�j 1,702 237 02
587 1,681 325 03
589 1,664 456 04
582 1,686 520 05
586 1,694 587 06
562 1,650 722 07
532 1,608 879 08
470 1,319 963 09
488 1,040 1,365 10
460 1,155 1,806 11
475 1,273 1,851 12
521 1,444 1,930 13
569 1,549 2,198
�܂��ڂ������̂������̕������L�ї��ł���B����10�N�Ԃ͖��N10�`30�����x�̑����������Ă���B�����̍��������̐L�т͂������A�����Ԃɑ���j�[�Y���ɂ߂č������Ƃ͕������Ă����B�����������Y�ƐU���Ƃ����������{�̐����莩���Ԃɑ���A���ł͋ɂ߂č����B�܂��l�������Ⴍ���삳��Ă��邱�Ƃ�����A�����ւ̎����ԗA�o�͂قڕs�\�ł������B
���������Ē����ŎԂ낤�Ƃ����O����Ƃ͒������{�̕��j�ɏ]���A���n��ƂƂ̍��قŒ��������ɐ��Y���_��݂��鑼�͂Ȃ������B�������Ԃɑ��ĉ����Ȏ��v������������A�O���͑勓���Ē����ɐi�o�����B�܂蒆���ɂ͏\���Ȏ��v���������̂ŁA�ނ�����͋����T�C�h�ł������B�܂��ɒ����̎����ԎY�Ƃ����V�ÓT�h�� g�i�o�ϐ������j��s�i���~���j�^v�i���{�W���j�{n�i�J���l���������j �̌o�ϐ����̒莮���K�p�ł��鐢�E�ł������B �͂����ĊO���́A�ݔ������̒ɉ����A���Y���̍����ŐV�̐��Y�ݔ��𒆍��ɓ��������B�܂� s(���~���j�^v�i���{�W���j �͊O�������ɂ���đ傫�����邱�Ƃ��ł����̂ł���B�܂������ɂ̓^�_���R�i�l�������ɂ߂ĒႭ�}�����Ă��邽�߁j�̗]��J���͂�����n�i�J���l���������j�͊m�ۂ���Ă����B���̂悤�ɒ����̎����ԎY�Ƃ͂قڌÓT�h�o�ϊw�̗��_�ʂ�̌o�ϐ����𐬂������Ă���̂ł���B
����̓��E�Ă�08�N�̃��[�}���V���b�N��̃X�����v�������A�N�Ԃɔ����Ԃ̑䐔�͂قڈ��ł���B�܂��ɓ��Ă͔����������v���S�Ăƌ����ėǂ��B�܂萶�Y�͑����̓����͂قڕK�v���Ȃ��B�������s����Ƃ����Ȃ�ݔ��̌��Ղ�₤���x���������ɔ��������ł���A���̑��ł͎ԂɐV�������{�����́i�Ⴆ�n�C�u���b�h�j�Ɍ�����B���ہA���Ȃ��Ƃ����{�����ł͂���10�N���炢�́A�V�H��̌��݂͑S���Ȃ��i�č��́A�V�H��̌��݂����ꍇ�A�ǂ����̍H�ꂪ������Ă���P�[�X�������j�B
�܂���Ă͂Ƃ��Ɏ��v�̓V��ɂԂ����Ă���̂ŁA�V�ÓT�h�� g�i�o�ϐ������j��s�i���~���j�^v�i���{�W���j�{n�i�J���l���������j �̌o�ϐ����̒莮�͖��W�ł���B���������{���č����A���̒����Ɠ����悤�ȍ��x���������ߋ��ɂ������B�Ƃ��낪������x�܂ŗ���ƁA�S���L�тȂ��Ȃ����̂ł���B
�����܂ł̘b�͎����ԎY�Ƃ������ɍ̂����B����͎����ԎY�Ƃ̋K�͂��傫���A�܂��֘A�Y�Ƃ��L���i�K�\�����̔��A�ی��Ȃǁj�A�K���Ǝv��ꂽ����ł���B���ہA�����ł͎ԈȊO�̎Y�Ƃł������悤�ȍ��x�����������Ă����B���ꂩ��̊S�́A�����̍����������܂ő������Ƃ������ƂɂȂ�B
���������̒����Ő����ɉA�肪���ɏo�Ă���B��͉ߏ�ɂ�������Z��Y�Ƃł���B���ɂ������ԎY�Ƃɐ�s���Đ������Ă����d�@�Y�Ƃ����Ɏ��v�̓V��ɂԂ������ƌ�����B���N�̃e���r�̔̔��������ɓ]����Ɨ\�z����Ă���B�����炭�G�A�R���A�①�ɁA����@�Ƃ��������̉Ɠd���i���߁X�����ɓ]������̂ƍl������B������Ɠd���i�͊��Ɉ�ƂɈ��ȏ㕁�y���Ă��āA���������������v�������Ă��邩��ł���B ��͂�ϋv������́A��ƂɈ��Ƃ������̂��ꉞ�̎��v�̓V��ɂȂ�悤�ł���B�B�ꒆ���ň�ƂɈ�䕁�y���Ă��Ȃ��͎̂����Ԃ����Ƃ������ƂɂȂ�B�܂蒆���ł����A�V�ÓT�h�̌o�ϐ������_���K�p�ł��Ȃ��Ȃ鎞�オ�ߕt���Ă���̂ł���B����ɂ��Ă����{�ł��̃|���R�c�o�ϊw�������Ă���l�X�́A��̉����l���Ă���̂ł��낤���B
http://www.adpweb.com/eco/ ���J�[�h�̔�r�D�ʐ� 2011�N11��18��
�w�̐A���n������ƁA��r�D�ʁx
�����������P �V���R��`�̐��i�Ғr�c�M�v�Ȃǂ��^����s�o�o�^���_�̒��ł́A���J�[�h�́w��r�D�ʐ��x�Ȃ長������Ȃ����t���ˑR�����o����Ă���B
�f���B�b�h�E���J�[�h�iDavid Ricardo�A1772�N�`1823�N�j�́A�e������r�D�ʂɗ��Y�i���d�_�I�ɗA�o���鎖�Ōo�ό����͍��܂�A�Ƃ���w��r���Y����x���咣�����C�M���X�̌o�ϊw�ҁB �w��r�D�ʁx�Ƃ͔�r���Y����Ƃ������P�W���I�̖c������C�M���X�̒鍑��`���o�ϊw�̗���ō������E�������Ă���B ��r�D�ʘ_�́A�w���ە��Ƃ̗��v�x��������_�ł��邪�A�_�[�E�B���̐i���_�̈��������q�ł���Љ�_�[�E�B�j�Y����D���w�Ƃ̋��ʓ_���l���邱�Ƃ��o�������ł��B ���́w��r�D�ʘ_�x�Ƃ͂P�W�`�P�X���I�����S���������ߍ��Ȓ鍑��`(�A���n��`)�I�ȁA���R�f�Ղ𐄐i����l�����Ń��J�[�h���f���̊�{�ł���B �����čl����A���́w��r�D�ʘ_�x�̈Ӗ��Ƃ́A1813�N���C�M���X�̑C���h�f�Ղ����R��(�Ŏ��匠�̔��D�j����A�Y�Ɗv���̃C�M���X����@�B���ȐD�����C���h�֗����A�C���h�̓`���I�ȖȐD���Y�Ƃ����S�ɔj��A���n�����ꂽ���A�w���R�f�Ղ̊m���x�������ɂ����A�w���푈�i1839�N�`1842�N)�ŃC�M���X�����A���n�������A�����̐��������̖����߂ʼnߍ��ȐA���n��������o�ϗ��_�I�ɐ���������ׂ̕���ł��������B �������ƍp��͉����ɂł����Ƃ͌������A���w�����������P�x�̐V���R��`�Ƃ͌����A�Q�O�O�N���O�̂���Ȍ��܂݂�̉ЁX�����ߋ��̖S��w��r�D�ʁx�������h��Ƃ͒n���̃f���B�b�h�E���J�[�h��������Ă��邾�낤�B
�w�����F��r�D�ʂƂs�o�o�x���c���v�@�����V���@2011�N11��16��
���鏗���ٌ�m�����̒��łP�Ԃ̃^�C�s�X�g�ł�����ꍇ�A�ޏ������v���ő�ɂ���ɂ́A�^�C�s�X�g���ق킸�����ŏ��ނ��^�C�v����̂��悢���낤���B �����͋������Ăł��^�C�s�X�g���ق��A�����ٌ͕�m�Ɩ��ɐ�O���ׂ����A�Ƃ������̂��B ���ɂP�O���~�������Ă��A���̎��Ԃ�ٌ�ɂ��Ă�P�T���~�̕�V����B�ӂ���Ƃ��g�N����B �^�C�s�X�g�̓^�C�v�̔\�͂ŕٌ�m�ɗ��̂ɁA�Q�l�̊W�ɂ����Ă̓^�C�s���O�Łw��r�D�ʁx��L����B ���́w����Ă��Ă��D�ʁx�Ƃ����̂��~�\�ł���B �o�ϊw�҃��J�[�h�����R�f�Ղ̐�����������̂ɏ��߂Ďg�����o�ϊw��̑匴�����B���ł�����ł������Ő��Y������A�e������r�D�ʂ�L������̂Ƃ��A�f�Ղ���������v�ɂȂ�B �����ٌ�m�̂��Ƃ��b�͂��̃T�~���G���\�����A���ȏ��j���O�̃x�X�g�Z���[�u�o�ϊw�v�̂Ȃ��ŁA��r�D�ʂ̉��p���Ƃ��ďq�ׂĂ��邱�Ƃł���B������₷���B ���x�̊����m�p�[�g�i�[�V�b�v����i�s�o�o�j�ɂ��āA�o�ϊw�҂͂قƂ�ǂ��^���ɉ�����B��r�D�ʂ̊ϓ_����͎��R�f�Ղ𐄐i���邱�Ƃ��ǂ̍��ɂƂ��Ă����v�ɂȂ�͖̂����ŁA�o�ϊw�̋����ɒ����ł���Ύ^������̂����R�����炾�B
�ŁA�s�o�o���i�_���q�ׂ�ɓ������āA�����̌o�ϊw�҂́w��r�D�ʁx������A �w�ł��邩��s�o�o�Q���͓��R�ł���x �Ƌ����͂����̂ł��邪�A�����̏ꍇ�A�l�X��[���������Ȃ������B����搶�� �w�^�C�s�X�g�Ƃ����Ⴆ���Â��������ȁB���������E��͂������݂��Ȃ��ƒ��ӂ��ꂽ�x �Ɣ��Ȃ��Ă����B�܁A����͌y���Ƃ��āA�o�ϊw�҂��s�o�o���Ől�X�����܂������ł��Ȃ������͎̂����ŁA�܂��߂ȕ��X�͂�����ƃV���b�N���Ă���悤���B �i�o�����K���،��̖k��ꎁ�ɂ��A�P�X�T�O�N��A�w�@�c�x�Ə̂��ꂽ�ꖜ�c���o����ق▯�Г}�ψ����ɂȂ鐼�����L�O�@�c����́A���{�͏�p�Ԑ��Y�𒆎~���A�������ق����悢�A�Ǝ咣�����������B
�w��r�D�ʂ��炷��Ɨ��҂͐��������Ƃ������Ă����̂�������Ȃ��B�����A���Ď��R�f�Ջ���i�e�s�`�j�ō��ӂ��Ă���A���܂̓��{�Ƀg���^���z���_���Ȃ��������낤�x
�ƌ����B�Ȃ�قǁB �Ƃ�����A���R�f�_�����R�f�Ր_�b�_���A�s�o�o���@�Ƀ{�����������Ă���Ε�����Ƃ����i�K���߂��A������Ɋw�K�������Ă���B�����A���炢���ƂɂȂ��Ă����Ȃ��B
�i���ҏW�ψ��j �w�Ȋw�ƋU�Ȋw�x �����V���ȂǑ��}�X���f�B�A�͑S�����s�o�o���i�̕��j�ň�v���Ă���̂ŁA���̏�L�̃R�����w�����F��r�D�ʂƂs�o�o�x���c���v���ҏW�ψ����A�ܘ_���i�ׂ̈̋L���������Ă���B�E�E�E�͂��A�Ȃ̂ł���B
�m���ɁA�R�����̑O���̂S���̂R�̓��J�[�h�̔�r�D�ʂ��g���Ăs�o�o�̌��p(�����j������Ă���B�Ƃ��낪�����U�s�́A���́w��r�D�ʁx�_���N�ɂ��x������Ȃ������������q�ׂ��Ă���B
�Ō�̂W�s�Ɏ����ẮA�����ɑO������(���J�[�h�̔�r�D�ʐ��j���^���ԂȉR(�U�Ȋw)�ł��閾�m�Ȏ���������Ă���B���c���̓R�����ʼn�����������(�ړI�j�̂��낤���B
�����I�O�ɂ͓��{�̎����ԎY�ƂȂǁA�A�����J�̑����ɂ��y�Ȃ��قǕn��ȁA���J�[�h�̔�r�D�ʐ��ł͐�ɖ�����(�Y�ƂƂ��Ė��ʂȁj�㕨�������̂ł��B�����̃g���^�N���E���̓A�����J�̍������s�ɂ͑ς���ꂸ�G���W�����Ă��t���������Y�G�R�[�͂X�W�L���ȏゾ�ƃv���y���V���t�g���E�����Ďd�����厖�̂��N�����Ă���B
�ߋ��̃C�M���X�ƃC���h��̗��j���ؖ����Ă���l�ɁA�����Y�ƕی�̊ł��Ȃ����(���R�f�ՂȂ�j���̓��{�̎����ԎY�Ƃ̗����͂��蓾�Ȃ��B���{���{�̎�����ی쐭��(�łƏ���ł̖߂��ňȊO�ɂ��Ɛł�e��̗D����)�̌��ʁA���{�̎����ԎY�Ƃ́A���ł͐�ΓI�Ȕ�r�D�ʂ��l�������B �����ԂɌ���w��r�D�ʁx�́A���ł͓��Ă̗��ꂪ�t�]���Ă���̂ł��B�g�b�v���[�J�[�f�l�܂ł��|�Y�̊�@�ɕm���A�A�M���{�̑S�ʎx���ő��𐁂��Ԃ����A�����J�̎����ԎY�Ƃ́A���{�̃}�X�R�~�ł͕���Ă��Ȃ������͂s�o�o�ɔ����Ă���B
�Ȋw�̉����Ƃ́A�N����������Ă��ǂ����K����O�҂̌��؍�Ƃɑς��ď��߂Ē���ƂȂ鐫���������Ă���B�w�����x�Ƃ͈Ⴂ������A�Ԉ���Ă��������͎̂ċ�����B
���ɂ̐V���R��`�ł���s�o�o�̎^���_���A�����P�W�`�P�X���I�̒鍑��`�̌o�Ϙ_��(�ԈႢ���ؖ�����Ă���U�Ȋw�j���o���܂łɗ����Ԃ�ʂĂ��Ƃ͋�����ŁA���͒��c���v���́A�����V�����ҏW�ψ��̗���Ȃ̂Ō��X�s�o�o���i�������Ă��邪�A�{�S�łs�o�o���i�������s�ׂł��鎖�����A�N�����ǂ��m���Ă���̂ł��B �����璪�c���́A�I舂Ɉꌩ���邾���Ȃ�s�o�o���i�Ɍ����邪�Ō�܂œǂ߂ΐ����ɂȂ�x���ŗ�ňӖ��s���̃R�����w�����F��r�D�ʂƂs�o�o�x���������̂ł��傤�B �w�u�[�h�D�[���o�ϊw�r�c�M�v�̔�r�D�ʘ_�x
�w�������̋K���ɘa�x���i���g���[�L���O�v�A�̑�ʔ����ȂNJԈႢ�ł��邱�Ƃ��ؖ�����Ă���V���R��`�̃~���g���E�t���[�h�}�����A�����Ɂw�ŋ��̌o�ϊw�ҁx�Ƃ��ĐM��ڂ̑O�̎����������Ȃ����̃}�N���o�ϊw�҂̒r�c�M�v���A����͔�r�D�ʘ_���Ύ����āw���J�[�h�̔�r�D�ʂ��m��Ȃ��̂��x�ƁA�s�o�o�ɔ�����l�X���������l���Ă���B
��r�D�ʂƂ́A����ȑΏۂ������}�N���o�ϊw�ł͂Ȃ��āA���̐����̔��ׂȌo�ϒP�ʂ��Ώۂ̌o�c�w�̌�e���Ȍ�p�ł��鎖���ɋC���t���Ȃ��ӂ���B ���J�[�h�̔�r�D�ʂ���������ׂɂ́A���S�ٗp�Ƃ��בւ̊��S�ȌŒ葊�ꐧ�Ƃ��l�����������[���ł���Ȃnj`����w�I�Ȑ�ɂ��肦�Ȃ��o�σ��f�����̗p��������������I�ɐ��藧���A���ʂ͂��̋t�Ő������Ȃ��B �f�Ղňꍑ���傫�Ȗf�Ս�����ꍇ�A���̑��荑�͗A�����߂ƂȂ��Ėf�ՐԎ��Ȃ�B�f�Ղł́i�O���[�o���X�g�̍D���ȁjWin-Win �͂Ȃ��B�Ј���������Ȃ�A�Ј���͕K�R�Ƃ��Đ�ɐԎ��ɂȂ�B ���o�̔����̐��ƍ����̐����K���w�����x�ł���悤�ɍ��ƊԂ̖f�Ղł������͓����ŁA����ȏ�ł�����ȉ��ł��Ȃ��B��O�͈�����܂�Ȃ��B ���̎����͒��w���ł��C���t�����A�r�c���� �w���J�[�h�̔�r�D�ʂ̌�����m��Ȃ��o�J�x �Ɣl�����ŁA���̎q���ł�����_���ɂ͐�ɓ����Ȃ��B���������Ƃ��������Ȃ��̂ł���B�r�c�M�v�́A
�w���{�̂悤�Ȑ����Ƃɔ�r�D�ʂ��������_�Y���ɍ����̊ł������Ĕ_�Ƃ�ی삷��̂́A�����Ƃ��]���ɂ��Đ��E�o�ς����k�����Ă���̂��B
���̂Ƃ��f�Ս����ɂȂ邩�Ԏ��ɂȂ邩�͂ǂ��ł��悢�B�x
�ƁA�����ꒃ�ł���B
�o�ϊw�ł́A�o����x�́w�Ԏ��x�͑���ł���B���{���������E�e���̕��ʂ̐��{�������ŁA�r�c�M�v�I�ɂ́w�ǂ��ł��ǂ��f�ՂȂǂ̌o����x�̑�Ԏ��x����Ƃ���̂ł���B �����č����E�o�ς̑���̃A�����J�̃f�t�H���g��@�≢�B�̂o�h�h�f�r�����̃\�u�������X�N�������ŁA�e���̕������Ԏ����S�Ă̌����ł���B �ܘ_�I�o�}�A�����J�哝�̂̂s�o�o���i�̖ژ_�݂��S���w�����x�ł���B���Ă̔{�߂��f�Օs�ύt�̐���(�A�����J�̑�Ԏ��̉����j�ł��邱�Ƃ͘_��҂��Ȃ��B
�w�f�Ս�����ړI�ɂ���̂͂P�V���I�̏d����`�ő�ԈႢ�ł���x
�Ǝ咣����r�c�M�v�̔�Ȋw���ɂ͕�������ŁA�Ȋw�I�ɐ��������͎̂��Ԃɂ͖��W�ŗႦ�P�V���I�ł���I���O�ł��ꐳ�����B �܂Ƃ��ȍ���(���{)�Ȃ�f�ՐԎ���������������ڎw���̂́A�͎m��������ړI�ɓy�U�ɏオ��̂Ɠ����ŁA(���S���������j����ɊW�Ȃ���ΓI�Ȑ^���ł���B �Q�P���I�̍��ł��A���L���f�X�̌����͖�萳�����āA�ۉ��Ȃ��N���t�炦�Ȃ��̂ł����A���Ƃ͑�Ⴂ�̃A�����J����ΓI�Ȕ�r�D�ʂ�ێ����Ă�������̃|�[���E�T���G���\���́w�o�ϊw�x�ȂǁA���ł͒N���M�p���Ă��Ȃ��B �T�~���G���\���w�o�ϊw�x�̖��m�ȊԈႢ���A�����I�̎��Ԃ̌��ɂ���ďؖ�����Ă���̂ł��B http://blog.goo.ne.jp/syokunin-2008/e/ec52d4bbc8ecd0e74524b831157f3363
�o�ϐ����̒莮�i���f���j08�^9�^15�i541���j
�\�����v�̒莮��
�����}�̑��ّI�Ōo�Ϙ_�����s���Ă���B���̒��Őϋɍ����h�ƍ����Č��h�̎咣�́A���������ǂ�����ʂɂ��ĕ���₷���B�������グ���h�i�\�����v�h�j�̌��������B���ł���B�����ō��T����M�҂Ȃ�ɏグ���h�̎咣�̔w�i�ɂ���o�ϗ��_���𖾂��Ă݂�B
�܂��ŏ��ɗ��_�o�ςɂ�����o�ϐ����̒莮�i���f���j�������Ǝ��̂悤�ɂȂ�B
g�i�o�ϐ������j��s�i���~���j�^v�i���{�W���j
v�i���{�W���j�Ƃ�Y�i���Y�E�����j1�P�ʂ𑝂₷�̂ɕK�v��K�i���{�E�E���Y�ݔ��Ȃǁj�ł���B�܂�
v�i���{�W���j��K�i���{�j�^Y�i���Y�E�����j
�ƂȂ�B������v�i���{�W���j�����Ȃ�i�Z�p�i�����Ȃ����Y�ݔ��̌������s�ςȂ�j�As�i���~���j���傫�����ق�g�i�o�ϐ������j���傫���Ȃ�B
�܂萶�Y���ꂽ���́i�����j���A�Ȃ�ׂ�����ꂸ���~����A���ꂪ�����ɉ�鍑�قnjo�ϐ������͑傫���Ȃ�B�ɒ[�ȃP�[�X�Ő��Y���ꂽ���̂��S�ď�����悤�ȍ��́A�o�ϐ������̓[���ɂȂ�i�O���̓����͂Ȃ����̂Ƃ���j�B�܂�s�i���~���j�������傫���ł����Ă��A���{�W���i���Y�i�����j1�P�ʂ𑝂₷�̂ɕK�v�Ȏ��{�ʁj���������A���������Đ��Y�����̍������{�����Ă��鍑�̕����o�ϐ������͑傫���Ȃ�B ���ɂ��̒莮��n�i�J���l���������j�̗v�f����������Ǝ��̂悤�ɂȂ�B
g�i�o�ϐ������j��s�i���~���j�^v�i���{�W���j�{n�i�J���l���������j
���̎���
s�i���~���j�^v�i���{�W���j�����Ȃ�An�i�J���l���������j���傫�����قnjo�ϐ��������傫���Ȃ�B
�悭�グ���h�̐����Ƃ�G�R�m�~�X�g��
�u�l�������ꂩ�猸��̂�����A���{�͌o�ϐ����̂��ߐϋɓI�Ɉږ���������K�v������v �Ǝ咣����̂����̂悤�Ȓ莮�����̒��ɂ���̂ł��낤�B
����ɂ�����t�i�Z�p�i�����邢�͐��Y���̌���j�̗v�f����������Ǝ��̒ʂ�ɂȂ�B
g�i�o�ϐ������j��s�i���~���j�^v�i���{�W���j�{n�i�J���l���������j�{t�i�Z�p�i���j
����������t�i�Z�p�i�����邢�͐��Y���̌���j�́A���{�i���Y�ݔ��Ȃǁj�ƘJ���̑o���̌������̐��ʂ��O�ɏo���Ĉ�ɂ܂Ƃ߂����̂ł���B
��̓I�ɂ́A���Y�H���̉��ǂ�V�����Z�p��̌������ݔ��̓����ł���A�J���҂̋���E�P���ɂ�鐶�Y���̌���ł���B
�܂�t�i�Z�p�i�����邢�͐��Y���̌���j���O�ɏo���Ȃ��\�����l������B
���̏ꍇ�u�Z�p�i�����邢�͐��Y���̌���v�́Av�i���{�W���j������������Ƃ��An�i�J���l���������j��傫��������̂Ƃ��ė��������B
�グ���h�i�\�����v�h�j��
�u�\�����v�Ȃ����Čo�ϐ����Ȃ��v �Ǝ咣����B���������́u�\�����v�v�Ƃ������t���͂����肵�Ȃ��i�����Ƃ��\�����v�h�̐l�X�������{���ɗ������Ă��邩�^�킵�����j�B�����ŕM�҂̎������o�ϐ����̒莮�i���f���j�ł�����l���Ă݂�B �\�����v�Ƃ͒[�I�Ɍ�����t�i�Z�p�i�����邢�͐��Y���̌���j��傫�����邱�Ƃł���B���̕��@�͂� v�i���{�W���j�����������An�i�J���l���������j��傫�����邱�Ƃł���B �������ɂ���ɂ����g�i�o�ϐ������j�͑傫���Ȃ�B
���������ɋ�̓I�ɐ�������B
v�i���{�W���j��K�i���{�j�^Y�i���Y�E�����j
�ł���Bv�i���{�W���j������������ɂ́AK�i���{�j�����Ȃ炻�ꂩ��Y�܂��Y�i���Y�E�����j��傫������悤�ȁu�Z�p�i�����邢�͐��Y���̌���v���s�����ƂɂȂ�B
�܂�Y�i���Y�E�����j�����Ȃ�A��P�ʂ�Y�i���Y�E�����j���Y�o���邽�߂�K�i���{�j������������悤�ȁu�Z�p�i�����邢�͐��Y���̌���v���s�����ƂɂȂ�B ����ɋ���E�P���ɂ��J���̐��Y�������コ���邱�Ƃ�n�i�J���l���������j��傫������B
��������̊�Ƃōl�����ꍇ�A����O�̘b�ł���B������������ꍑ�̌o�ςōl�����ꍇ�͑������G�ɂȂ�B
�ꍑ�̎��{�iK�j�ƌ������ꍇ�A���Ԃ̐��Y�ݔ���̔��ݔ��Ȃǂ����ł͂Ȃ��A���H��`�p�ƌ������������{��Љ�{���܂܂��B �܂��ꍑ��Y�i���Y�E�����j��GDP�Ƃ������ƂɂȂ�B ����������Y�i���Y�E������GDP�j�̑����Ɍ��ѕt���Ȃ��悤�Ȍ����������\�����v�h�́u���ʂȌ��������v�Ɣᔻ����B
�܂��グ���h�i�\�����v�h�j�́u���v���u���v��������ƍl���A���{����̏k����i����B
�u�u���v�ɂł��邱�Ƃ́u���v�v �Ƃ������ƂɂȂ�B�����ĎЉ�S�̂́u�Z�p�i�����邢�͐��Y���̌���v�̂��߂ɍs���{�A�K���ɘa�Ȃǂ̋������i����ł���B���̂悤�ɍ\�����v�ɕK�v�ȋ�̓I�Ȏ{��́A�K���ɘa�����Ƃ̔p�~�▯�c���Ƃ������ƂɂȂ�B �X�b�|�������Ă������
�Ƃ��낪�グ���h�i�\�����v�h�j���O���ɒu���Ă���Ǝv����o�ϐ����̒莮�i���f���j�ɂ́A�厖�Ȃ��̂��X�b�|�������Ă���B
�����Ă���̂́u���v�v�ł���B �ޓ����i����{��͑S�āu�����T�C�h�v�Ɋւ�����̂Ɍ�����B �������ǂꂾ����Ƃ⍑������������葽���̐��Y���Y���Ă��A���v���Ȃ���ΐ��Y���͗]��B���Y�������c��A���̎��ɂ͎��{��J�����]��ƂȂ�A���{��J���̗V�x��������B �������グ���h�i�\�����v�h�j�̍l���ɂ́A ��������͑S�Ĕ�������� �Ƃ����т����肷��悤�ȑO��������A�Öق̂����ɐݒ肳��Ă���B�Ƃ��낪�グ���h�i�\�����v�h�j�̐l�X�́A���̂��ƂɋC�t���Ă��Ȃ����A�������͋C�t���Ă��Ă��떂�����B�����̏ꍇ�A�P�Ɏ��v�s���������ŗV�x�ݔ��⎸�Ə�ԂɂȂ��Ă��邱�Ƃ��A�グ���h�i�\�����v�h�j�͔F�߂Ȃ��B
�ޓ��͗V�x�ݔ��⎸�ƂƂ���������˂��t�����Ă��A�V�x��Ԃ̐ݔ��͊��ɒ������Ďg�����ɂȂ�Ȃ��ƌ��߂���B�܂����Ǝ҂́A���Y���̌���ɒǂ����Ȃ��l�X�ł���A�V���ȋ���E�P�����K�v�ł���Ǝ咣����B���������Ĉꎞ�I�ɗ]�������{��J���Ƃ��������Y�����́A�����Ɛ��Y���̍�����������ɃV�t�g������悤�ȍ\�����v���K�v������Ɛ����B���̂悤�ɏグ���h�i�\�����v�h�j�͋����T�C�h�̂��Ƃ�������Ȃ��B
�������M�҂͗V�x�ݔ��̑S�Ă��������Ă���Ƃ͍l���Ȃ��B�܂��E�ɏA���Ă���l�Ǝ��Ƃ��Ă���l�̊ԂɁA�Z�p��m���ɑ傫�ȍ��͔F�߂��Ȃ��B�����������ł͂Ȃ��A�����̏ꍇ���v�̕s���ɂ���ėV�x�ݔ��⎸�Ƃ��������Ă���ƍl����ׂ��ł���B���ɓ��{�͖����I�Ɏ��v�s���i�����s���j�Ɋׂ�̎��ɂ���i���̂��Ƃ�{���͉������グ�Ă����j�A�ނ���\�����v��ڎw��������Ȃ���v�s���𑣐i���Ă���B
�グ���h�i�\�����v�h�j�̍l���̔w�i�ɂ́A
�u��������̂͑S�Ĕ����v�Ƃ����ÓT�h�o�ϊw�́u�Z�C�̖@���v������B
�����������̌o�ς�m���Ă���҂́u����Ȃ��Ȃ��Ƃ͂Ȃ��v�Ƃ�������B�Ƃ��낪�������������\�����v�h�́A���̒P���Ȍo�ϗ��_�̐M��҂Ȃ̂ł���B
�u�Z�C�̖@���v�������̂͋ɂ߂ē���Ȏ������Ǝw�E�����̂̓P�C���Y�ł���B �������Ɂu��������̂͑S�Ĕ����v�̂́A�Ⴆ�ΐ푈�ő唼�̐��Y�ݔ����j��ɒ[�ȕ��s���Ɋׂ�������A�V�����ɂ�����o�ς̍��x���������炢�̂��̂ł���B�ÓT�h�̓��ꗝ�_�ɑ��āA�ނ͈�ʓI�Ȉꍑ�̌o�Ϗ�Ԃł̗��_�W�J���s�����B�P�C���Y�͒����u��ʗ��_�v�ŁA�������ʂɎ��v�s�����N���A�V�x�ݔ��⎸�Ƃ��������郁�J�j�Y�����𖾂����B�܂��P�C���Y�̒�q�̃n���b�h�́A�o�ϐ������_��W�J�������A�����Ǝ��v�̑���̉ߒ��ł̗��҂̊W�̕s���肳���w�E�����B �P�C���Y�͎��v�s���ɂ��s�����N�邱�Ƃ𗝘_�I�ɉ𖾂����B�ނ͂��̏ꍇ�ɂ͋����������邾���łȂ��A���{�������x�o�𑝂₷���Ƃɂ���Ď��v��n�o���邱�Ƃ��L���Ƃ����B�������̂悤�Ȑ���͐��E���̍��ō̂��Ă���B����������Ă�����E����A��i���{��`���Ƃ͐[���ȕs���Ɋׂ��Ă��Ȃ��B
�܂��グ���h�i�\�����v�h�j���ӖړI�ɐM��u�����T�C�h�d���v�̍l���́A�f�Վ��x�������I�ɐԎ��̕č��Ő��܂ꂽ�B�������ɕč��̂悤�ɋ����T�C�h�ɖ��̂��鍑�ŁA���̂悤�ȍl�������̎x����͉̂���B�����������I�ɒ��~���ߏ�œ������s�����A�ߏ萶�Y�̂͂������O���ɗ����Ă�����{�Ɂu�����T�C�h�d���v�̍l����K�p���悤�Ƃ��邩�炨�������Ȃ�̂ł���B
�������������T�C�h�ɖ��̂���č��ł����A�����T�u�v���C�����ŕs���ɂȂ������߁A���łȂǂɂ����v�n�o����A�܂�P�C���Y������s���Ă���̂ł���B���v�n�o������u�I�[���h�P�C���Y����v�Ɣے�I�Ȍ��߂�������G�R�m�~�X�g��A�����}�̑��ٌ��̒��ō����Ɂu���͍\�����v�h�v�ƌ����Ă���l�X�́A���̒��̍\���̉��v���K�v���B http://www.adpweb.com/eco/eco541.html
�Z�p�i���̉��b 11�^11�^28�i688���j
�Ӗ��̂Ȃ��o�ϐ����̒莮�i���f���j �l�X�̏����������A��l��l�̍������L�ɂȂ�̂����Ƃ̗��z�ƕM�҂͎v���B ���̂��߂ɂ͌o�ς���������K�v������B�{���͂��̌o�ϐ����̒莮�i���f���j��08�^9�^15�i��541���j�u�o�ϐ����̒莮�i���f���j�v�Ŏ�グ���B�����������
g�i�o�ϐ������j��s�i���~���j�^v�i���{�W���j�{n�i�J���l���������j�{t�i�Z�p�i���j
�ƂȂ�B�܂����̌o�ϗ��_�ł́A
s�i���~���j��v�i���{�W���j�����Ȃ�A�J���l���������Z�p�i�����Ȃ����Όo�ς͐������邱�ƂɂȂ�B ���ɊȒP�Șb�ł���B���������̗��_�̍ő�̎�_�́A���ꂪ�����T�C�h�݂̂ɒ��ڂ��Ă��邱�Ƃł���B���������Ă��̒莮�i���f���j���L���Ȃ̂͐��Y�͂��R�������������A��قǎY�Ƃ̔��W���x��Ă��鍑�����ł���B �����A���Ȃ��Ƃ���i���ł��̌o�ϗ��_�����Ă͂܂鍑�͂Ȃ��B�ǂ̍����]��̐��Y�ݔ��ƘJ���͂�����Ă���B�Ƃ��낪���܂��ɍ\�����v�h�́u���v�v���K�v�ƐQ�ڂ������Ƃ������Ă���B
�����A���̌o�ϐ��������߂�̂͋����ł͂Ȃ��ԈႢ�����u���v�v�ł���B���N�A10���O��̌o�ϐ����𑱂��Ă��钆���́A�����T�C�h�ɗl�X�ȑ傫�Ȗ�������Ă���B�Ⴆ�Ζ����I�ȓd�͕s���Ƃ������v���I�Ȗ��������ƕ����ė��Ă���A�����A����͉�������錩�ʂ����Ȃ��B�����������Ȗ��ԂƐ��{�̓����A����ɗA�o�̐L���Ƃ��������v��������܂ő����ė����̂Łi����̌��ʂ��͕s�����j�A�����o�ϐ����������ł����̂ł���B
�܂茻���̌o�ςɂ����ẮA�����̂悤�ɋ����T�C�h�ɖ�肪�����Ă����v��������Όo�ς͂ǂꂾ���ł���������B�܂�`���I�ȌÓT�h�̌o�ϗ��_�Ȃ�āA�����̌o�ςɂ����ĉ��̖��ɂ������Ȃ��B�������o�ϊw�҂́A���ꂵ���m�炸�܂������̌o�ςɋ������Ȃ��̂ŁA���ł��Ӗ��̂Ȃ��o�ϗ��_���w���ɋ����Đ��������Ă���B
�ޓ��́A�����̌����ƌ����̌o�ς̓����Ƃ̒�������킹�邽�߁A�����T�C�h�Ɛ��ݎ��v�Ƀ~�X�}�b�`������Ƃ�������Ȏ��������B�ޓ��̂������ݎ��v�Ƃ͗�̂��Ƃ���Â���Ƃ��������̂ł���B
�u���̕���̋K���ɘa���Ȃ���Ȃ�����A���ݎ��v�����݉����Ȃ��̂��v �Ǝ咣����B���������ɂ����̌����Ă��鎖�����������ꂪ���������Ƃ��Ă��債��GDP�͐L�тȂ��B�܂���Â���̎��v��L���L���ȕ��@�́A�M�҂͋K���ɘa�ł͂Ȃ��\�Z�̑��z�ɂ���Â���ɋΖ�����l�X�̑ҋ����P�ƍl����B�����ċK���ɘa��t�B���s����C���h�l�V�A����Ō�m��A��Ă��邱�Ƃł͂Ȃ��B
�ޓ��͉��\�N���O����
�u�K���ɘa���s�\���Ő��ݎ��v�����݉����Ȃ��v �Ƃ����Ԕ����Ȏ咣�𑱂��Ă���B�܂艽�ł������̃~�X�}�b�`�ƌ����Č떂�������Ƃ��Ă���B���������Ԃ́A�l�Z�����A�ǂ��ɐ��ݎ��v������̂��K���ɂȂ��ĒT������Ă���B�����͂����v���͂邩�ɃI�[�o�[���Ă�����{�ɂ����Ă͓���O�̘b�ł���B���ہA
09�^4�^13�i��565���j�u�M�҂̌o�ϑ�āv
http://www.adpweb.com/eco/eco565.html
�ŏq�ׂ��悤�ɁA���Ȃ��Ƃ����[�}���V���b�N�̑O�܂ł͓��{�̐��i�ɗ��w���͂�����100�O��Ő��ڂ��Ă����B�܂���{�ł́A����҂��K�v�Ƃ��鏤�i�̓s�^���Ƌ�������Ă����B�܂��T�[�r�X�ɂ��Ă������T�C�h�Ƀl�b�N�������Ă���Ƃ͎v���Ȃ��B�܂���{�o�ς̓R���r�j�݂����Ȃ��̂ł��苟���T�C�h�ɂ���������͂Ȃ��B
���Ȃ݂Ƀ��[�}���V���b�N��̐��E�I�Ȍo�ς̍����ȍ~�A���̐��l������n�߂��B������2010�N���瓌�k��k�Ђ̒��O�܂ł͂��̐��l������������߂��Ă����i100�`110���x�Ő��ځj�B�Ƃ��낪�k�Ќ�͍Ă�120���x�܂ŏ㏸���Ă���B�����炭�������Ƃ̒x��ɂ��A�֘A���i�̍ɑ����e�����Ă���ƕM�҂͌��Ă���B �L������^���Ȃ��Z�p�i�� �̂̌o�ϊw�̃��C���e�[�}�́A�����͂������ɂ��ďグ�邩�ł������B�����}���Ȃ��琶�Y�͂𑝂₷���߂̎��{�̒~�ρi�܂蓊���j���d�v�ł������B�܂����Y�����̓K���Ȕz�u���o�ϐ����ɗL���ƍl����ꂽ�B���̂��߂ɂ͉��i���J�j�Y�������邱�Ƃ���ƍl���A�K���ɘa�ɂ�鋣�����K�v�Ƃ��ꂽ�B ���̌o�ϗ��_�̔w�i�ɂ́A���v�͖����ɂ���i�Z�C�̖@���j�Ƃ������o������B�������O�i�ŏq�ׂ��悤�ɁA�����Ă��̐�i���͂ǂ������Y�ݔ��ƘJ���̗͂]�������Ă���B�K�v�Ȃ̂͋����͂̐����ł͂Ȃ��u���v�v�ł���B
�������ɃM���V���̂悤�ȗ�O�I�ȍ�������B���̃M���V���̂悤�ɖ����I�Ɍo����x���Ԏ��̍��́A�����T�C�h�̋������L���ł���B���̂��߂ɂ͈ꍏ���������[�����痣�E���A�����ʉ݂�啝�ɐ؉����邱�Ƃ��K�v�ƍl������B
����A���Ȃ��Ƃ����{�͎��v�s���̌o�ς���ԉ����Ă���B�K�v�Ȃ͎̂��v�n�o����ł���A�M���V���̂悤�ȍ��ɂƂ��ĕK�v�ȁu���v�v�ł͂Ȃ��B�������ʉ݂̐؉����i�~���j�͓��{�ɂƂ��Ă��L���ƍl����B�������o����x�̍�������ԉ����Ă�����{�̒ʉ݂̐؉����́A�Ȃ��Ȃ����ۓI�ɔF�߂�����̂ł͂Ȃ��B
�M�҂́A��i���ɂ�������v�s���̈�̌������A���炭���a�����������Ƃɂ���Đ��Y�ݔ��̔j�Ȃ��������Ƃƍl����i�傫�Ȑ푈���Ȃ�����������ЊQ�����������炢�j�B�����Ă�����d�v�Ȃ��Ƃ́A����E����A���Y�Z�p������I�Ɍ��サ�����Ƃł���B�܂萢�E�I�ȋ����̗͂]�肪�����Ă���B����ɐ��E�I�ȃo�u�������̉ߒ��œ���t�����}�l�[�T�v���C���ςݏオ�����iGDP�����Z���Y�̕����L�ї����傫���A����ɂ���đ傫�ȗL�����v�̕s���������Ă���j�B
�M�҂́A���Y�Z�p�̌���A�܂�Z�p�i���ɒ��ڂ��Ă���B�Z�p�i���ɂ���ď����Ȑ��Y�����i���Y�ݔ������ƘJ���́j�̓����ɂ���āA���傫�ȎY�o�����܂��悤�ɂȂ����B��������
���v�͖����ɂ���i�Z�C�̖@���j
�Ƃ��������v�h�̋Y���i���킲�Ɓj���{���Ȃ�A���i�ݔ��̗V�x�⎸�Ɓj�͐����Ȃ��B�Ƃ��낪���ꂪ��R�����獡����肪�N���Ă���̂ł���B
���N10���O��̍��x�o�ϐ����𑱂��Ă��钆���Ŏ��Ƃ��Ȃ��Ȃ�Ȃ��Ƃ�������Ȍ��ۂ��N���Ă���B�����悤�ȍ��x�o�ϐ������o���������{�ł́A�����A�l��s�����[���Ől����ǂ�ǂ�オ�������A�����̌���͑ΏƓI�ł���B����ɂ��Ė{����10�N�O
01�^11�^12�i��230���j�u�����ʏ����̕��́i����2�j�v
http://www.adpweb.com/eco/eco230.html
�ŁA���̌����𒆍�����i���̐i�Z�p��������Ȃ���o�ϔ��W��������Ǝw�E�����B
�����A�����ł��o�u�����N���ĕ����㏸���N���Ă��邪�A���{�̍��x�o�ϐ������Ɣ�ׂ�Α債�����Ƃ͂Ȃ��B�ނ��뒆���̌ٗp���͐[���ŁA�l�C�̂���������̕�W��1,000�{�̉��傪�������Ƃ����b��������B���ꂾ���̌o�ϐ�����B�����Ă����Ɩ�肪�������Ȃ��w�i�ɂ́A�J���͂����قǕK�v�Ƃ��Ȃ��i���Y�V�X�e���𒆍�������ꂽ����ƕM�҂͍l����B
�Z�p�i���͐l�ނɂƂ��đ厖�ł���A�l�X�ɖL������^������̂Ǝv���Ă����B�M�҂��Z�p�i���͐�ɕK�v�Ȃ��̂ƍl���Ă���B�Z�p�i���́A�ߍ��Œ����Ԃ̘J������l�X��������Ă������̂ƍl�������B���ہA�Z�p�i���ɂ���ē��{�ł͘J���҂̒P����Ƃ��y������A�J�����Ԃ��Z�k����Ă����B�Ⴆ�ΏT�x��������Z�p�i���Ȃ����Ď������Ȃ������ƍl����B�܂���{�����鎞���܂ł͗ǂ������ɐi��ł����̂ł���B
�Ƃ��낪�����A���{�ł͂ނ���J�������̕����Ɍ������Ă��āA�ٗp�������ǂ�ǂ��Ȃ��Ă���B���{�ł������Ɠ����悤�ɋZ�p�i���̉��b���l�X�ɍs���n�炸�A�ނ���l�X��s�K�ɂ��Ă��邩�̂悤���B�������炱�̂悤�Ȏ��Ԃ��ڗ��悤�ɂȂ����̂��M�҂��l����B��G�c�Ȋ��z�Ő\����Ȃ����A�M�҂͓��{�ō����Č��^���ƍ\�����v�^��������ɂȂ��Ă���Ǝv���Ă���B
http://www.adpweb.com/eco/
�s�o�o�𐄏����悤�Ƃ���l�B�̔w�i�ɂ���̂́A��r�D�ʐ��Ȃǂ̎��R�����P�ł���Ƃ���Ԉ�����o�ϗ��_�P���Ă��邱�Ƃł���B
���̂悤�Ȏ��R�����_�́A���Ă��A���n����̐��i��A�A�W�A�ւ̐i�o�ɓ������Ẵv���p�K���_�ł��������Ƃ��������Ă��Ȃ��̂ł���B���̃v���p�K���_�ɂ�薾�������̓��{��A�W�A�A�����ăA�t���J�������ǂ�قǂ̔�Q�������Ƃ��B����ɂ�胈�[���b�p���ǂꂾ�����v�����ł��낤���B
���̂��Ƃ𗝉����������ɔ�r�D�ʐ��Ȃǂ������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�݂�Ȃ̓}�Ȃǂ̎^���h�́A���̐^�ӂ𗝉������A�����𗝉������A�����������̂Ɠ����悤�ɂ��̉��b������Ǝv���Ă���̂��B
���̗��_�́A�P�Ȃ镽�ϒl�̖��ł���A���ꂼ��̍��������L���ɂȂ�Ƃ����ۏ͂��Ă��Ȃ��B���z���L�ѕ��ϒl�͏オ��Ƃ������_�ɉ߂��Ȃ��̂ł���B
��r�D�ʐ��́A���������̏ꍇ�ŁA�����悤�Ȍo�Ϗ�Ԃɂ��鍑���m�Ő��藧���ꗝ�_�ł���A�ݕ��o�ς����B���A�O���[�o���������s��ł́A���ׂĂ����藧���̂ł͂Ȃ��B ���Ƀo�u������f�t�����Ƃ̌��Ղł͐��藧���Ȃ��B �o�u�����ƃf�t�����̌��Ղ́A����I�ɃC���t�������A���v�A�f�t�����͑����邱�ƂɂȂ邩��ł���B���݂��̗��v�ɂȂ�Ȃ��̂ł���B �����ł̓f�t�����ƃC���t�����Ƃ̌��Ղ���ɐ������悤�B������������Δ�r�D�ʐ����ǂ�Ȃ��̂������邩��ł���B
���Y�ʂƎ����ʂ̊Ԃɑ傫�ȍ��z�������Ă���f�t�����ƃC���t�����̏������̊p�x���A�C���t�������U�O�x�A�f�t�������R�O�x�Ƃ��悤�B�C���t�����́A���Y�ʂɔ�����ʂ������������Ȃ��Ă���B�f�t�����͋t�ɐ��Y�ʂɔ�����ʂ����������Ȃ��Ȃ��Ă���B����䂦�������̊p�x������Ă���B
�i�f�t���̌����Ə���ŎQ��
http://www.eonet.ne.jp/~hitokotonusi/teraxBLG/blg-hiduke.html�j �������ȍ��͂S�T�x�ł���B
�f�t���̍��́A���ݏo�����t�����l�ɑ���ݕ��I�]�����{������ׂ����̂��Ⴍ�]������邽�߁A��ɖׂ��̈�����Ԃɂ���B�W���Ԃ̘J���łU���Ԃ��炢�ׂ̖����������Ȃ��B�i�W���ԘJ���Ő��ݏo�����t�����l���A�����ʂ����Ȃ����߉ݕ��I�]�������Ȃ��Ȃ����B�j
�t�ɃC���t���̍��͕t�����l�ɑ���ݕ��I�]���������]������邽�ߏ�ɖׂ����ǂ���Ԃł��B�W���Ԃ̘J���łP�O���Ԃ��炢�ׂ̖����������Ԃł��B ����ȍ��͓��R�̂W���Ԃ̘J���łW���Ԃׂ̖��ɂȂ�܂��B ���̂悤�Ȏ��f�t�����ƃC���t�������ʏ����s�����Ƃ��悤�B�S�̂ŕ����Ɍ����s���A�K�ޓK���Ő��Y���s��ꂷ�ׂĂ��Z���������A�����ʂƐ��Y�ʂ̍����Ȃ��Ȃ菊�����̊p�x���S�T�x�ɂȂ����B�߂ł����߂ł����B���l�I�ɂ͐������ł��傤�B ���������̓��e���ᖡ����ƁA�f�t�����͂��f�t�����������Ȃ�A�������̊p�x������ɉ�����Q�O�x�ɂȂ��Ă���A�C���t�����͏��������V�O�x�ɂȂ��āA���o�u�����������Ȃ�̂ł��B��𑫂��ĂX�O�x������Q�Ŋ���S�T�x�ɂȂ�B �f�t���̍��͏��������R�O�x��艺�����Ă���B�C���t���̍��͂U�O�x���オ���Ă���B�f�t���̍��͎����ʂ�����ɏ��Ȃ��Ȃ�A�C���t���̍��͎����ʂ�����ɑ����Ȃ�B �����J�����Ԃł��A�҂������ʂ��Ⴄ���߁A�f�t�����͏�ɃC���t�����ɂ��������A�f�t�����͂������Ȃ��������ƂɂȂ�A�������ǂ�ǂo���Ă����B �f�t�����͕��ł��T�[�r�X�ł����Y�ł��A�����ł��ǂ̂悤�ȕ��ł��l�����肵�Ă��邽�߁A���荑���ɗL���ɔ�����̂ł���B �C���t�����͔��ɕ��ł��T�[�r�X�ł����Y�ł���Ɋ����ɂȂ��Ă���B���荑����������̂ł���B �������f�t�����́A�n�[�g�����h�i�Y�ƌo�ϊ�Ձj����N�o���鎑�����قƂ�ǖ����t�Ɍ͊����Ă����Ԃł���B����䂦�������Y�̊������肪�����A�C�O���Y�̍w���ȂǂقƂ�ǂł��Ȃ��B �t�ɃC���t�����͉����ȃn�[�g�����h�̊����ɂ��A�������ǂ�ǂ�N�o���A�������Y��C�O���Y�̍w���������ɂȂ�B ���̂悤�Ȃ��Ƃ����E�I�ɋN����ƁA�f�t���̍��͐��E�S�̂ł�����p�C�������悤�Ƃ��A���̉��b���邱�Ƃ��ł�������ɐH��������邾���Ȃ̂��B
��r�D�ʐ��ł����_�͓����ł��B���̗��_�́A����Ȍo�ϓ��m�̊Ԃ����Ő��藧���̂ł��邪�A����ł��K�ޓK���̐��Y���s���A�S�̂̃p�C���傫���Ȃ��Ă��A���̉��b�͕��ϒl�ȏ�̍��������Ă����̂ł���A���ϒl�ȉ��̍��͑���������̂ł��B
���̂��ߎ��R�f�Ղɂ�鑹����h�����߁A���邢�͎����̐������x�����ێ����邽�߁A�����͂̂Ȃ����͂��܂��܂ȏ�ǂ�ׂ��邱�ƂɂȂ�B����͖����`���ƂƂ��ē��R�̂��ƂȂ̂ł��B ���R�f�Ղ�P�Ƃ���l�����́A������H�̍l�����ł���A�������͂�苭���A�ア���͂��キ�Ȃ�B���R�f�Ղ͖��\�ł͂Ȃ��B�K�x�ɊǗ����Ȃ���S�̂̍��x���グ�čs���̂��ǂ��̂ł��B����ɂ͂ǂ̍����f�t���łȂ����Ƃ��O��ɂȂ�܂��B ���݃f�t���ɂ��������{�́A���R�����������ɕs�����͕̂K��ł��B���̂Q�O�N�ԓ��{�͂ڂ땉���ł���A����I�ɕ��������Ă���̂ł��B ����͎��Ԃ��o�ɂꂻ�̍����ǂ�ǂ�傫���Ȃ��Ă����܂��B
�Ⴆ�o�u���̎��A�����̐l�B�̎��Y���i���Q�Ă���Ԃɏオ��A���̑��̒n��̐l�B�͐Q�Ă���ԂɎ��Y�����ꂽ�̓����悤�Ȃ��̂Ȃ̂ł��B �����s���ɂ������̒�͑����̊�Ƃ�l�Ɏ؋��������炵�A���̕ԍς̂��߂̊������肪���������߁A���i���i�⎑�Y���i�A�����������ɂȂ��Ă���B���ꂪ�O���̉a�H�ɂȂ��Ă���B �ŋ߂ɂȂ�悤�₭���Ă��f�t���Ɋׂ�n�߂����߁A�ȑO�̂悤�Ȃڂ땉����Ԃł͂Ȃ����A�����ɃJ�i�_��L�V�R�Ȃǂ̐���Ȍo�ύ����Q������A�m���ɔނ�ɓ��{�͐H����ł��낤�B�܂�������A����A�W�A�̍��������Ă������������܂����l�����Ƃ炷���낤�B �s�o�o�̕|���̓A�����J�����ɂ���̂ł͂Ȃ��B�o�u���̐V�����̕����|���̂ł���B���Ƀo�u���̒����┭�W���铌��A�W�A�����{�̕x��H���r�炷�̂ł���B
�A�W�A�̔��W����荞�ނ��ȏ�ɔނ�ɐH���Ă��܂��̂��B
�f�t���̍��͂����ł͂Ȃ����ɐH���Ă��܂��̂ł��B�s�o�o�̍L����́A�f�t���̓��{�ɂƂ��Ĕ��Ɉ������Ƃł��B���̂悤�Ȕ�펯�Ȃ��Ƃ����{�ōs���悤�Ƃ��Ă���̂ł��B ���{�̎R�т�y�n�̑������O���l�ɔ����A�����s��͊O���l�o�C���[�����Ȃ���ΊՎU�Ƃ��Ă��܂��̂����B����Ƃ̑������O�����{�ɕς���Ă���B �O���̓����ȂǂƂ����Â����t�ɂ��܂���A���{�̑����̊�Ƃ������A���O��ς��A���{���H���Ă���̂ł��B �O���������瑝���Ă��A�f�t���̉����ɂ͂Ȃ�܂���B����͊F����悭�������ł��傤�B�f�t���͏���s���ŋN�����Ă��܂��B�O���͏�������܂���B��Ƃ����邾���Ȃ̂ł��B (�f�t���̐����헪�Ƃ͉����Q�Ɓj
���̂��Ƃ��o�ϐ��Ƃ͔@���ɍl���Ă���̂��낤���B�����Ƃ͂ǂ������Ă���̂��낤���B�����ς�炸�Ԉ�������ȏ��R�����āA�f�t���𑣐i�������Ă���̂ł���B
��Q�����E�푈��̐��E�o�ς̊g����A���Ă���{�����̊g��̉��b�̑唼�����A��k�Ԋi���͂���ɍL�܂����̂ł��B����͔��W�r�㍑�̑������A�f�t���o�ςł���A����������A�`���I�Y�Ƃ��p��A�A�o�i�����������@����A��ʂɊO���ɗ���A�A���i�ɍ����Y�Ƃ����|����A�������ǂ�ǂo�����̂ł��B�����đ����̎��Y���O�����{�ɔ���ꂽ�̂ł��B ���̓��{�Ɛ����ς��܂���B ���̂悤�Ȃ��Ƃ������ɓ��{�ł��̂Q�O�N�ԋN�������̂ł��B���{�͎��R�f�Ղ̔s�҂Ȃ̂ł��B���̍��{�I�F�����Ȃ����߁A�s�o�o�𐄐i���悤�Ƃ���̂ł��B ���{�Ŕ����Ă���̂́A�_�Ƃ������ł����A�����̒n���o�ς��敾���Ă���n��ł��B�ނ�͐g�������Ă��̌��������Ă��܂��B���{�͔s�҂ł��邱�ƁB����ȏ�̎��R���͒n��Y�Ƃ��Ȃ��Ȃ邱�ƁA�n��o�ς����邱�Ƃ��悭�m���Ă���̂ł��B ���������Ȃ����{�̒����A�����g�D�A�������w�A�����ƒB�A�V���̉���ҒB�͏��҂��Ǝv���Ă���̂ł��B ���{�̔s�ނ̎�Ȍ����̓f�t��������ł��B���ꂪ���������ނ����A�A�o�𑣐i���Ă���̂ł��B�����̌��ނ͒ቿ�i������]�V���������A�A���i�̊g��������炵�Ă��܂��B ���{�l�͑ӂ��Ă���̂ł͂Ȃ��A�`�������Ȃ��̂ł��Ȃ��B���������������Ȃ̂ł��B �D������
http://blog.so-net.ne.jp/siawaseninarou/�Q�ƁA ���{�̃E�C�j���O�V���b�g
http://www.eonet.ne.jp/~hitokotonusi/winningshot.html
���̓��{�͏����ł��悢���玑���𑝂₵����𑝂₵�����̂ł��B�s�o�o�͂����^��������ׂ����̂ł��B��̉������o�ς��A������ē����邱�Ƃ͂Ȃɂ��Ȃ��̂ł��B
�s�o�o�Q���̒��ŁA�f�t�������������͎̂���̋Ƃ��B�Q��T�N���̓��{�ɂƂ��ėL���ȗA�o�ł��A����Ɏ؋���Ԃ����Ƃ��ł��Ȃ������̂�����B ���{�́A�f�t�����瓦��A�g��Đ��Y���Ȃ���鎞�܂łs�o�o�Ȃǂ̖������Ȏ��R���ɉ����Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł��B
http://www.asyura2.com/11/hasan74/msg/275.html ��p�w�҂����̐^�� 2016/10/24 �����Ȃ́A�������x�ɂ��ċc�_����u�������x���R�c��v��A ���Ǘ�����ɂ��āu�L���ҁv����ӌ����u���̍��Ǘ��݂̍���Ɋւ��鍧�k��v�Ƃ�������c���J���A �ُk�����𐄐i���悤�Ƃ��܂��B �e��c�̃����o�[�́A��{�I�ɂ͍����Ȃ̊������I�肵�܂��B ���̎�̉�c�̖���Ɂu�ψ��v�Ƃ��Čf�ڂ���邱�Ƃ́A ���Ɂu�w�ҁv�ɂƂ��Ă̓X�e�[�^�X�ɂȂ�܂��B ���R�Ȃ���A�ُk�����𐄐i����w�҈ȊO�������ȂɑI��邱�Ƃ͂���܂���B ������u��p�w�ҁv�����ł����A �R�c��⍧�k��̈ψ��ɑI�o�����A���o�V���Ȃǂ́u��p�V���v�Ɋ�e����@��Ȃǂ������܂��B ��p�w�҂������A�����Ȃ̎������Ƃ��Č�p�V���ɋُk�������i�_���f�ڂ��A���_�������Ƃ���킯�ł��B �����Ȃ́A�R�c��Ȃǂ̃����o�[�ȊO�ɂ��A�u�����v�u���v�ȂǁA �l�X�Ȏ�i�Ŋw�҂������蒆�Ɏ��߁A ��p�w�҂Ƃ��Đ��������悤�Ƃ��܂��B �����Ȋ̂���̌�p�w�҂����͑�w�̒��ŋ����Ƃ��Ẵp���[�����߁A���̉��ɏA�����y�����A�u�t�A�w���������A�g�b�v�i�����j�Ɠ����H����i�݂܂��B ������A��p�w�҂̉��ŁA���ُk�����_�̘_�����������Ƃ��Ă��A�̗p����܂���B �Ƃ����킯�ŁA��p�w�҂̒�q�������A�ُk�����h�Ƃ��Ē����A�����ȂɎ������Ƃ��ĔF�߂��A�R�c��⍧�k��̃����o�[�ɂȂ�B �ނ�̒�q�������܂��A�ُk���h�Ƃ��ċ����ւ̊K�i�����B �ƁA��p�w�ҍĐ��Y�̍\�����K�b�`���Ƒg�ݏグ���Ă��܂��Ă���̂��A�䂪���Ȃ̂ł������܂��B ���āA�Љ�ۏ�팸��ُk�������u�������_�|�v�Ɋ�Â��ᔻ���Ă����g��m�����A���͗��h�Ȍ�p�w�҂Ƃ��āu�������x���R�c��@�������x���ȉ�v�̉�Ƃ��Ă�����Ă��܂��B �ȑO�́A���̎�́u�����v����ʂ̍����ɒm���邱�Ƃ͂���܂���ł����B �Ƃ͂����A�ŋ߂̓C���^�[�l�b�g���A �V���ȏ�f�B�A�̏o���ɂ��A ��p�w�҂����̐^�������ԂɍL�܂����܂��B
http://www.mitsuhashitakaaki.net/2016/10/24/mitsuhashi-484/
�������́u��r�D�ʂ̌����v���L�ۂ݂ɂ��Ă��鎩�̌o�ϊw�� �r�c�M�v
���c�����̒m��Ȃ���r�D�ʁ@�i�r�c�M�vblog�j
http://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51752213.html
���R�f�ՂŌ��Ղ������ɂȂ邱�Ƃɂ���āA�o�ς���������Ǝv���Ă���l�������B���̗��_�I�����̈�����J�[�h�́u��r�D�ʂ̌����v�ł���B
���̃��J�[�h�̗��_�͋����T�C�h�����Ōo�ς̐����𑨂��Ă���i���v�͖����Ő��Y�������̂͑S�ď�����Ƃ������O��j�B���Ղɂ���ė]�������Y�v�f�����̕��̐��Y�ɐU��������A�o�ς���������Ƃ����������ł���B�܂�f�t���o�ς̍����̓��{�ɂ͑S�����Ă͂܂�Ȃ��c�t�Ȍo�ϗ��_�ł���B ���������ȏ��ł��̃��J�[�h�́u��r�D�ʂ̌����v���w�w�Z�G�˂́A�����Ȃ鎞�ɂ����̗��_���K���ł���Ǝv������ł���B�����Ă��̎��R�f�Ղ̏�Q���A�łł�������A�܂���ŏ�ǂƌĂ�Ă���⏕����e���̋K���ƍl���Ă���B ���ł��ő�̌��Ղ̏�ǂ��łƂ����F���ł���B���������ĊœP�p��ڎw��TPP�́A���R�f�Ղ̐M��҂ɔM��Ɋ��}����Ă���B���������J�[�h�́u��r�D�ʂ̌����v��������ꂽ�̂́A18�A19���I�̖q�̓I�o�σV�X�e���̎����O��ɂ��Ă���B�܂���قǏq�ׂ邪�A�����ł͊ňȊO�̑傫�Ȗf�Ղ̏�ǂ����邱�Ƃ��펯�ɂȂ��Ă���B http://adpweb.com/eco/eco651.html
�@�r�c���́A�w���c�����̒m��Ȃ���r�D�ʁx�̂Ȃ��ŁA�u�u�A�����J�����d�ɓ��{�̂s�o�o�Q����v���v���Ă���Ƃ����̂́A���������Ɍ����Ă���̂��낤���B���Ƃ���NY�^�C���Y��"TPP"����������ƁA2�������o�Ă��Ȃ��B���̈��Bergsten�́u�哝�̂����a�}��TPP�ɊS�������Ă��Ȃ��v�ƒQ���Ă���B�A�����J�ɂƂ���TPP�́A������ɂ������[�J���Ȓʏ�����ɂ����Ȃ��B�����Ɏ�v�ȗA�o��ł��Ȃ����{�������ė��Ă����Ȃ��Ă��A�ǂ��ł������̂��v�Ə����Ă���B
�@�č����������{���{�ɂs�o�o�Q����v�����Ă���킯�ł͂Ȃ��Ƃ��������̍ŏ��ɁA�m�x�s�̋L�������������o���̂ɂ͋������B�@����́A�s�o�o�i��Γ��ʏ����j���č�������f�B�A�ɂƂ��Ă���قǑ傫�ȊS���ł͂Ȃ����Ƃ��Ӗ����Ă���Ƃ��Ă��A�č����������{���{�ɂs�o�o�Q����v�����Ă��Ȃ��Ƃ����T�ɂ���Ȃ�Ȃ��B�@�s�o�o�̃L�[���[�h�łm�x�s�̋L�������������Ƃ��A�č����������{���{�ɂs�o�o�Q���������]��ł��邱�Ƃ́A���{�ŕ���Ă���č������̌�������\���ɂ킩�邱�Ƃł���B �@���Ă̖f�ՊW�́A�u�������Ɓv�Ő��ݕ��������܂������Ă���\���ɂȂ��Ă���ƍl���Ă���B �@�؍���ƂƂ̊W�Ƃ͈Ⴂ�A����قnj��������荇���������邱�Ƃ͂Ȃ��A�i�ڂ�Ώےn��i�s��j�Ő��ݕ����Ă���B�i�؍���ƂƂ́A�s��ƕi�ځi�����i�j�̗����Ő[���Ȋp���ɂ���j �@�r�c���́A�č��ɂƂ��ē��{����v�ȗA�o��ł͂Ȃ��Ƃ���������ے肹�����̂܂g���Ă��邪�A������ƒ��ׂ�킩��悤�ɁA�J�i�_�E���L�V�R�E�����Ɏ�����S�ʂ̈ʒu�ɂ���A�p����h�C�c������ʂȂ̂ł���B�i�Γ��A�o�T�P�Q���h���F�A�o�S�̂̂S�D�W���j �@�r�c���́A����ɁA�uTPP���Δh�́A���Z�̐����o�σ��x���̌o�ϊw���������Ă��Ȃ����Ƃ������v�Ǝw�e���A���̍����Ƃ��āA�w��r�D�ʂ̌����x�������o���Ă���B �@�r�c���́A�N���[�O�}�����̋��ȏ�������������p���A �u�e���Ő��Y��قȂ�Ƃ��́A���ΓI�ɃR�X�g�̈������ɓ������ėA�o���邱�Ƃɂ���Đ��E�S�̂̐��Y�ʂ������A�o���̍������v��Win-Win����������̂��B���ꂪ���J�[�h�ȗ��m���Ă���i�����ē��c���̒m��Ȃ��j��r�D�ʂ̌����ł���v �Ƌ������Ă���B �N���[�O�}�����̋��ȏ�����̈��p�����F �w�A�����J�ł�1000���{�̃o�����͔|���Ă��邪�A����Ɏg��������10����̃R���s���[�^�Y�ł���Ƃ��悤�B�����A��Ăł͓���������3����̃R���s���[�^�������Y�ł��Ȃ��Ƃ���B�A�����J�Ńo���̐��Y����߂đS�ʂ��Ă���A��������A��Ẵo���̐��Y��1000���{�����ăR���s���[�^�̐��Y��3���䌸�邪�A�A�����J�ł̓o���̐��Y���[���ɂȂ��ăR���s���[�^�̐��Y��10���䑝����B�܂萢�E�S�̂ł́A�o���̐��Y�ʂ͕ς��Ȃ����A�R���s���[�^�̐��Y�ʂ�7���䑝����x �@���̘_���ŁA��ĂɃR���s���[�^��������߂����o���͔|�ɌX����������ƍl���Ă���̂Ȃ炨����ݔq���ł���B �@�܂��A�ߑ�o�ϊw�͕����I�ʂł͂Ȃ����z�I�ʂ���{�̍l�@�x�[�X�ł���B �@�o���P�O�O�O���{�̕t�����l�ƃR���s���[�^�R����̕t�����l���r���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ꂪ�����Ȃ�A�Ƃ肠�����͔�r�D�ʂ̘_������悤�B�@�������A�o���̕t�����l���P�O�O���f�ŃR���s���[�^�̕t�����l���P�R�O���f�Ȃ�A��Ă͂���k�ł���ƃo���͔|�ւ̓��������ۂ��邾�낤�B �@�t�����l�͓������Ƃ��Ă��A���i�̐������ւ���Ă���B
���@�o���̐���͒Z���A���莞�ɔ���Ȃ���A���点�Ă��܂��������傫����������B�A���ɂ��C������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�@�R���s���[�^�́A�R�X�g�_�E���y�[�X��Z�p�v�V���������N�H�i�Ƃ���������邪�A�o���قǂł͂Ȃ��B������������肷��o���قǂ̑呹�͐H��Ȃ��B�o�ϓI���s�͂��邪�A�����I���s�͂قڂȂ��B ���@�o���͔̍|�����s���͐[���Ǝv���Ă��邪�A�ߑ㎑�{���Y�ƂW�����铮���͂��܂�Ȃ��B�R���s���[�^�̕��́A�����́E�f���\�����u�E�\�t�g�E�F�A�E�������u�ȂNjߑ㎑�{���Y�ƂW������v�f���l�܂��Ă���B �@�@�ߑ㍑�ƂƂ��č���������𐋂������Ǝv���Ă��鍑�ł���A���i�K�̐��Y���͒Ⴍ�Ƃ��A�R���s���[�^�̐��������������͂��Ȃ����낤�B
�@�r�c���́A�u��r�D�ʂ̌����v���g���āA�u���{�̂悤�Ȑ����Ƃɔ�r�D�ʂ��������_�Y���ɍ����̊ł������Ĕ_�Ƃ�ی삷��̂́A�����Ƃ��]���ɂ��Đ��E�o�ς����k�����Ă���̂��v�Ƃ������_���Ă��邪�A�����Ə]���҂����̂R�N�Ԃ����łP�O�O���l���������i�����X�O�O���l�j�A��N�J���ґw�̂W���ȏ�i�Q�O�O���l�j�����Ƃ��Ă��邱�̓��{�ŁA�u�����Ƃ��]���ɂ��āv�Ƃ������W�b�N�͒ʗp���Ȃ��B
�@���E�ō����x���̋����͂������䂦�ɁA���{�̐����Ƃ́A���{�����ŘJ���͂��g�����Ȃ��Ȃ��Ȃ����̂ł���B���{�̐����ƂɂƂ��ē��{�̘J���͐l���͉ߏ�Ȃ̂ł���A�_�Ƃ�ی삵�悤�����܂����A����͕ς��Ȃ��̂ł���B �u��r�D�ʂ̌����v�́A���̂悤�ȏł͂܂������ʗp���Ȃ��̂ł���B �@�r�c�����ᔻ���Ă�����c���̃u���O�͐\����Ȃ������ǂȂ̂ŁA�r�c�������p���Ă���
�w�f�Ղɂ����Ĉꍑ���A�o�ɂ���đ傫�Ȗf�Ս�����ꍇ�A���̑��荑�͗A�����߂ƂȂ��Ėf�ՐԎ��������邱�ƂɂȂ��Ă���B�ӂ��͂����ł���B�f�Ղł́i�O���[�o���X�g�̍D���ȁjWin-Win �͂Ȃ��B�Ј���������Ȃ�A�Ј���͐Ԏ��ɂȂ�B�x
�Ƃ��������݂̂ɂ��Ċ��z���q�ׂ����B �@�f�Վ��x�̕s�ύt����Win-Win �͂Ȃ��Ƃ������Ƃ炵�����A�f�Ս����̑��ǂ��v�h�m�̎w�W���Ƃ����̂Ȃ�ʂ����A�o�ϐ����⍑�������̌�����w�W�ɂ���̂Ȃ�AWin-Win �͂��肦��B
�@�r�c���̌��́A���c���̎咣���u��r�D�ʂ̌����v�ōْf���Ă��邱�Ƃ��B��r�D�ʂ́A�ÑԓI�ꎞ�I�Șb�Ƃ��Ă͒ʗp���Ă��A�����I��Win-Win ���_�ł��Ă���킯�ł͂Ȃ��B �@�����I��Win-Win�̏����́A
���@��́A�č��̂悤�ɁA�c��Ȗf�ՐԎ��ɂ��\���Ȃ��ŁA�����ȍ��݂̗A�����ł��鍑�����邱�ƁB
�@��㐢�E�̌o�ϔ��W�́A���ۊ�ʉ݃h���̔��s���ŌR���I�ɂ��j�i�̗͂����č����A�~���n�H�Ƃ�������A�����ߍ\�����p�����Ă������ƂɎx�����Ă���B
���@������́A�č��̗A�����ߍ\���𗊂�ɁA�ߑ�I�����Ƃ̈ړ]��ʂ��ēr�㍑�̍����������A�b�v������悤�Ȗf�ՊW�B
��r�D�ʂł͂Ȃ��A�R�X�g�̔�r�ǂ��납�������������Ȃ����ɐ�i�����������_��z���A�����ɐ��Y���╔�i��A�o���A��������č��⎩���ȂǂɊ����i��A�o����Ƃ����\�����B����ɂ��A�ٗp���ꂽ�l�X�̏������������A���̏����������ʂ��Ă��̍��̌o�ώЉ�S�̂ɉ��B�i�o��̍��̏����������オ�邱�ƂŁA�������_�̐��Y�ʂ���������A��������̐��i�A�o��������B �@�Ƃ����悤�Ȃ��̂ŁA�u��r�D�ʂ̌����v�́AWin-Win�̏����ł��Ȃ���A���̘_�ɂ��Ȃ��Ă��Ȃ��B
�ȉ��̃����N��̔�r�͎Q�l�ɂȂ�܂��B
��c�I�o�}����k�\�e���͉����������������Ȃ������� http://d.hatena.ne.jp/oguogu/20110923/1316769113 �I�o�}�哝��
�w�哝�̂͏��獇�킹�ɂ�������炸�A��̓I�Ȍ��ʂm�ɋ��߂Ă����x(�����V��)�A�w�I�o�}�哝�̂��������r�W�l�X���C�N�ȗv���x(�����V��)�A
�w��ς����哝�̂̎����I�Ȍ��Ԃ�ɁA���Ȃ̕č�������������Ƃ����x(�Y�o�V��)�A�w���獇�킹�ŁA�đ哝�̂����Ă�����A�����܂ŒP�������ɑP���𔗂�͈̂ٗ�Ƃ�����x(���{�o�ϐV��)�B
�I�o�}�哝�̂̌������A����܂ōs��ꂽ���Ď�]��k�Ƃ͈���Ă��������e�����`���Ă��܂��B�������A�ǂ����ăI�o�}�哝�̂��A�������������Řb���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��Ƃ������܂ŐG�ꂽ�V���Ђ͈�Ђ�����܂���ł����B���́A�e�Ђ̘_���ψ��������̎����������l���Ă��Ȃ����炾�Ǝv�킴��܂���B�I�o�}�哝�̂����{�Ƃ̊O���Ō��ʂ����߂��̂́A���ꂾ���A�����J�����Œǂ��l�߂��Ă��邩��ł��B���ۂɐ��_�����ł͍đI���낤���ƌ����Ă��܂�����B
���ǁA�I�o�}�哝�̂́A��c�����ɓ��_�ɂȂ�悤�ȕ�����z���ƌ����Ă���킯�ł��B http://www.asyura2.com/11/senkyo121/msg/582.html
�y�o�ϊw���_�̋��ρz�@�u��r�D�ʁv�Ƃ������J�[�h�́g���\�I���_�h�����Ȃ��������тĂ���s�v�c�@
�|�@�u���R�f�Վ�`�v�́u�ی�f�Վ�`�v�ł���@
�u���Ɣj�Y�P�T�v�{�[�h�ɂ��u��r�D�ʁv�w�����U�����ꂽ�̂ŁA������ɏ悹�����B
�܂��A�u���R�f�Վ�`�v�́A���ꂪ�L�����ƍl���鍑�Ƃ��咣����u�ی�f�Վ�`�v���ƍl���Ă���B ���R�f�Ղ����݂��̍����o�ςɂƂ��ă����b�g������Ƃ������_�I�����Ƃ��ẮA�u��r�D�ʁv�Ƃ����l������������Ă���B �u��r�D�ʁv�͌o�ϊw�ŕ��L��������Ă���i���z����Ă���j���_�ł��邪�A�����Ɨ��j���ƂĂ��Ȃ��̏ۂ������f���ɂ����ł݂̂��낤���Đ���������̂ł����Ȃ��B �����Ŏ��グ��u��r�D�ʁv�̗��_�́A���J�[�h�́u��r���Y����v�Ɓu�w�N�V���[���I���[���̒藝�v�Ƃ��A���̑R���_�i����j�Ƃ��ă��X�g�́u�c�t�Y�ƕی�_�v�����グ��B �o�ϊw���班������A�o�ς������o�ςł���A�����o�ς��ߑ㍑�Ƃ̊�Ղł��邱�Ƃ��l����A�u��r�D�ʁv���ǂ�قǁg��������h�������̂ł��邩�킩��B
�u��r�D�ʁv�������Ƃ��āA�S�|�Y�Ƃ�@�B�Y�Ƃ��m�������A�������O���Ɉˑ������ߑ㍑�Ƃ��A���ې����̍r�g�����z���邱�Ƃ��ł���̂��H �u��r�D�ʁv�������Ƃ��āA�H�Ƃ��O���Ɉˑ��������Ƃ��A�_�Ƃ̎��R�K�萫�Ǝ��R�ϓ��⍑�ې����̕ϓ����l�����Ƃ��A����Œ����I�ȍ��������̈�����ێ��ł���̂��H ���O���ƑΓ��Ɍ��ł��鎩���������Ƃ��߂��������҂��u��r�D�ʁv������邱�Ƃ͂Ȃ����낤���A�����̈���I�Ȑ�������`�Ƃ��铝���҂��A�u��r�D�ʁv������邱�Ƃ͂Ȃ����낤�B �܂��A�O���[�o�������i��㐢�E�ł��A���{��������i�����́u��r�D�ʁv��x�O�����ĐH�Ǝ������P�O�O�����߂����A���R��`�̌����ƌ����Ă���č��ł����A�@�ہE�S�|�E�Ɠd�E�����ԁE�����̂Ǝ��X�ɑΓ��f�ՋK�������v���Ă������ƂȂǂ��v�������ׂ�A�u��r�D�ʁv���A���O�◝�_�͕ʂƂ��āA�����Ƃ��Ă͎���Ă��Ȃ����Ƃ��킩��B �u��r�D�ʁv�����_�Ƃ��Ă͎�����Ă��Ă��A�����̋ߑ㐢�E�j�Łu��r�D�ʁv�Ɋ�Â��Č��Ղ��s��ꂽ���Ƃ͂Ȃ��Ƃ����̂����Ԃł���B �i�ߑ�Y�Ɩu�����̉p�����A���荑�i�C���h�Ȃǁj�ɋ������邩�����ŗA�o������B�������̂�����A���݂��[������u��r�D�ʁv�Ō��Ղ��s���Ă����킯�ł͂Ȃ��j �������A���̂悤�Ȑ����_�I���ꂩ��u��r�D�ʁv��ᔻ���邱�Ƃ��ړI�ł͂Ȃ��̂ŁA�o�Ϙ_���Ɍ��肵�Ă��̌����l�@���������A��Ƀ��X�g�́u�c�t�Y�ƕی�_�v�����邱�Ƃɂ���B ���@���X�g�́u�c�t�Y�ƕی�_�v
���J�[�h�́u��r���Y����v��ᔻ�����h�C�c�̃��X�g�́A���R�f�Ղ������鍑�ɗ��v�������炷���Ƃ��Ă��A�Y�ƍ\�����s�ςŁA�Z���ÑԓI�ȏ����ł̂ݓK�p�ł���Ƃ����B
�Ⴆ�A�h�C�c���ߑ�I�Ȗa�эH���Ȏ��Ƃ̔�r���Y���艺���Ă����A�����̗A�o������Ȏ��Ƃ����H�Ɛ��i��A�o����H�ƍ��ɕϐg���A���Y���傫���g�債�A�o�ό����������傫�����シ��Ɛ������A���Ƃ̐���ŁA�p�����i�̗A����}���A�Ȏ��̍������i�������グ�邱�ƂŖȎ��H�Ƃ̊g����������ׂ����Ǝ咣�����B�����āA���X�g�̍l���͂��̎���P�W�V�X�N�Ƀr�X�}���N�ɂ���č̗p����A���ꂪ�A�h�C�c�̍H�Ɖ��𑣐i���A�d���w�H�Ƃʼnp���𗽉킷��܂łɂȂ����B ����́A�P�X���I���̃h�C�c�܂ők��Ȃ��Ƃ��A���̓��{���l����Η����ł��邱�Ƃł���B �č��̎Y�ƂɊr�ׂė���Ă������{�̎Y�Ƃ����ɂ͕č��𗽉킷��܂łɂȂ����ߒ����l����A�u�c�t�Y�ƕی�_�v�ǂ��납�u�c�t���ƕی�_�v�Ɋ�Â�����ɂ���Ă��ꂪ�������ꂽ���Ƃ��킩��B �����{�̍��x�������́A�ی�ł݂̂Ȃ炸�g�����i���ґ�h�Ƃ������l�ς܂ō����ɐZ�������邱�ƂŗA����}�����A�O���̒��ړ����������֎~�Ƃ��A�A�o�̑��i������Ƃ��Ď��g���ʂł���B �P�X�U�O�N�O���܂łɁu���R�f�Ձv��u�O������v�𐭍�Ƃ��Ď��s���Ă���A���ł͖�������A�o�D�NJ�Ƃ̂قƂ�ǂ��Ȃ��A���������̐����������̗��j�ߒ���肸���Ɖ������̂ɂȂ����͂��ł���B �i�����ȍ��̗A���ɂ�荑���������ꎞ�I�ɏ㏸���邱�Ƃ͔ے肵�Ȃ��j ���@���̔��W�r�㍑
�u���R�f�Ձv��`�҂���㐢�E�����グ��Ƃ��́A�u�c�t�Y�ƕی�_�v�Ő����������{�ł͂Ȃ��A���Ɨ����ʂ��������W�r�㍑��ΏۂƂ��邾�낤�B
���W�r�㍑�͂��̑������ߑ㉻���߂����A�u�c�t�Y�ƕی�_�v�ɑ�������u�A����֍H�Ɖ�����v���̂����B
���̋�̓I�Ȑ���́A�ی�ŁE�A�����ʊ��蓖�āE�����בփ��[�g���x�[�X�ɁA�琬�Ώۂ̎Y�Ƃ����Y������̍������i�������グ�A���̎Y�Ƃ��K�v�Ƃ��鎑�{���̗A���ɕK�v�ȊO�݂�D��I�Ɋ��蓖�Ă�Ƃ���������̂����B �������A���̂悤�Ȑ����ʂ��グ�邱�Ƃ͋H�ł������B �����{�₩�Ẵh�C�c�����������߂����ŁA���ގ��I�Ȑ�����̂������W�r�㍑�����܂������Ȃ������v�����������l����B �Z�p�́E�o�c�E�����͂Ƃ������j�I�~�ς̍��ق��I�v���Ƃ��ďグ�邱�Ƃ��ł��邪�A
���@���{�ɂ�����L�@�I�\���̍��x�����Ȃ킿�Œ莑�{�䗦�ƋK�͂̊g��
���Ƃ��Ă��u�Y�Ɗv���v������ɂP�O�O�N�ȏオ�o�߂��A��̐��E�����o�Ă��邱�Ƃ���A�Y�Ƃ̋@�B�������Y���u�ƌ�����܂ō��x�����Ă���A���ۋ����͂��m�ۂ��邽�߂ɂ́A�����D�ʂ̋K�͂��������邽�߂ɂ͙ˑ�Ȏ��{������K�v�Ƃ���B ����Y�Ƃ�D���I�Ɉ琬���邽�߂ɂ́A���̎Y�Ƃɋ]���������邱�Ƃł���B
�����i�O�݁j���s�����Ă���̂��r�㍑������A���ێ������s���A���Y��������A�o���邱�Ƃŕԍς��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �r�㍑�͂f�c�o�̐�ΓI�K�͂��������̂�����A�ΊO���̕ԍϕ��S���ߑ�Ȃ��̂ƂȂ�B �ΊO���̉ߑ�ȕ��S�̓C�R�[�����������̑ϖR���Ӗ����邩��A���ۋ����͂��m�ۂł���قǂ̋K�͂ŎY�Ƃ��m������͖̂��d�Ȏ��݂ƂȂ�B �����������u�A����ցv�Ƃ����K�͂ɐ���A�����s������ɔ̔�����邱�ƂɂȂ�B �������A�Y�ƈ琬�̎����͍��ێ���ꂾ����A���̍����s�������́A�����o�ς̎��v����������B ���z�̐��Y�������ێ����ŗA�����Ȃ���A����ɂ���Đ��Y�������������s�ꂾ���Ŕ̔�����Ă���A���̎Y�Ƃ̈ێ���������ȍ����o�ϏɂȂ�B ���@�����ʉ݂����߂ɐݒ肵���בփ��[�g �בփ��[�g���g���́h�ȏ�ɍ�����A���ێ��������ΓI�Ɍy���ł��A���̗A�����L���ɂȂ�B �Ƃ��낪�A���̂��߂ɍ��̗A�o���������͌��������̂ɂȂ�B �u�A����֍H�Ɖ�����v�Ƃ��������s��Ɍ��肵���l���ł��������̂ɁA�r�㍑�̎Y�Ƃ͈琬�͂��܂������Ȃ������ƌ�����B ���ێ����̕ԍς̂��߂ɍ������v�͌�������̂�����A�Œ�ł��A�����s�ɕK�v�ȊO�݂�A�o�ʼn҂��o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B ���@���A�W�A�̌o�ϐ���
���A�W�A�n��́A���e���A�����J�E��A�W�A�E�����E�A�t���J�ƈ���Čo�ϐ�����B�������B
���A�W�A���o�ϐ����𐋂����̂́A�u��r�D�ʁv�ɏ]�������ʂł��Ȃ��A�u�A����֍H�Ɖ�����v���̂������ʂł��Ȃ��B �����̗v���́A���{�𒆐S�Ƃ����O����ϋɓI�ɗU�v���A�A�o�g��ƍ������v�g��𐬂����������Ƃɂ���B ���O�̎Y�ƈ琬�ł�����ێ���ꂪ�K�v�ɂȂ邪�A�O���ł���A���Y�ݔ��̓����͊O�����g���s���A�����œ����l�X�̋��炾���ʓ|����������B �ɒ[�ȗ��������ƁA�O���̍H��Ő��Y���������S�ʗA�o�����̂ł���A���������ɋ�������邱�ƂȂ��A�����̋ΘJ�҂�����������܂�܂鍑����ƂɂƂ��Ă̎��v�Ƃ��đ������邱�ƂɂȂ�B ���̗A�o�Ńf�t�����͂������邱�ƂȂ��A���v�̏������ɂ��Y�Ɗ���������������C���t���X���ݏo�����ƂɂȂ�B ���̂悤�Ȍo�Ϗł���A���v�g���h�����q�ɍ�����Ƃ̗͂����X�ɍ��߂Ă������Ƃ��ł���B �����āA�Y�ƈ琬�ɍ��ێ������s�����荂���Ȑ��Y����A������K�v���Ȃ��̂�����A�בփ��[�g�͈�����Ԃł����Ƃ������A�O���U�v�̂��߂ɂ������ق����L���ł���B
������Ƃ̗͂��t���ėA�o���ł���悤�ɂȂ�A�����בփ��[�g�����ۋ����͂̎x���Ƃ��čv�����邱�ƂɂȂ�B
���̂悤�Ȕ��W�r�㍑�̌o�ϐ����_���́A�����P�O�N�̒����o�ς��ڂ݂�Η����ł���͂��ł���B ���@���J�[�h�́u��r���Y����v
�u��r�D�ʁv�̐�엝�_�ł��郊�J�[�h�́u��r���Y����v����܂����Ă������Ƃɂ���B �ȒP�Ɂu��r���Y����v���������ƁA
�u���E�ɉp���ƃ|���g�K���̂Q�����������݂����A���Y���Ă�������ѐD���ƃ��C���̂Q��ނ����Ȃ��Ɖ��肷��B�p���͖ѐD���P�P�ʂY����̂ɂP�O�O�l�A���C���P�P�ʂY����̂ɂP�Q�O�l��K�v���Ă���B
�|���g�K���͖ѐD���P�P�ʂY����̂ɂX�O�l�A�Ԃǂ����P�P�ʂY����̂ɂW�O�l�K�v���Ƃ���B�����āA�p���̑S�J���ʂ��Q�Q�O�l�A�|���g�K���̑S�J���ʂ��P�V�O�l�Ƃ���A�f�Ղ��s�Ȃ��Ȃ��Ƃ��̂Q�����̖ѐD���̑����Y�ʂ́A�p���P�P�ʁA�|���g�K���P�P�ʂ̍��v�Q�P�ʂł���B���l�ɁA���C���̂Q�����̑����Y�ʂ��Q�P�ʂƂȂ�B �@�@�@�@�@�@ �@�@�p���@ �@�@�@�|���g�K�� �@�@�Q�����̑����Y�� �@
�@�ѐD�� �@�@�@�P�O�O�l�@ �@�@�@�X�O�l �@�@�@�@�Q�P��
�@���C�� �@�@�@�P�Q�O�l�@ �@�@�@�W�O�l�@ �@�@�@�Q�P��
�@���J���͗� �@�Q�Q�O�l �@�@�@�P�V�O�l
���Y���Ƃ������_�Ō���A�ѐD���ƃ��C���Ƃ��|���g�K���̂ق����D�ʂɂ���B
�����I�ɍl����A�|���g�K���������̍����p���ɗA�o��������Ƃ������ƂɂȂ�̂����A���J�[�h�́A�g��萶�Y�����D��Ă�����ɓ������Đ��Y�����������݂��ɂ�藘�v�邱�Ƃ��ł���h�Ə�����B
���C������ɂ���ƁA �@ �i�P�O�O�^�P�Q�O�j�O�D�W�R�@���@�i�X�O�^�W�O�j�P�D�P�R ������A�p���͖ѐD���̐��Y�����ΓI�ɓ��ӂƂ������ƂɂȂ�B
�ѐD������ɂ���ƁA �@
�i�P�Q�O�^�P�O�O�j�P�D�Q�T�@���@�i�W�O�^�X�O�j�O�D�W�X ������A�|���g�K���̓��C���̐��Y�����ΓI�ɓ��ӂƂ������ƂɂȂ�B
������A�p���͔�r�D�ʂ̖ѐD���ɓ������A�|���g�K���͔�r�D�ʂ̃��C���ɓ��������ق��������Ƃ���B
��������A
�@�@�@�@ �@�@�@�p���@�@ �@�@�|���g�K�� �@�Q�����̑����Y�ʁ@
�@�ѐD���@ �@�@�Q�Q�O�l�@ �@�@�@�@�O�l �@�@�Q�D�Q�@�@�P��
�@���C�� �@�@�@�@�@�O�l �@�@�@�P�V�O�l �@�@�Q�D�P�Q�T�P��
�@���J���� �@ �i�Q�Q�O�l�j�@�i�P�V�O�l�j �@
�@�Q�����̑����Y�ʂ�����킩��悤�ɁA�f�Ղ��Ȃ��ꍇ�ɔ�ׂāA���J���ʂɕω����Ȃ��ɂ�������炸�A���ꂼ��̍��̐��Y�ʂ���������B�v
���̂悤�ȁg���\�h�I�����Ń��J�[�h�́A���R�f�Ղ����݂��̍����o�ςɂƂ��ėL���Ȃ��̂��Ǝ咣�����B
���̓����ɂӂ�邱�Ƃ��Ȃ���̍��������r���邾���ŁA�����o�ς̗��Q��_����Ƃ͂Ȃ�Ƃ��G�ς��b�ł���B ��Ƃ��ďグ��ꂽ�|���g�K���́A�����p���̑������R���������甽�_�����Ȃ�������������Ȃ����A�܂��Ƃ��ȓ����҂����������Ɣ��_���Ă����ł��낤�B
���z�̃|���g�K�������҂ɂ�锽�_�����݂�B ���@�|���g�K���̉��z���_
�u���ǂ��̐��Y���̂ق����ѐD���ł����C���ł������Ƃ������Ƃ��悭�킩��܂����B�������A���ǂ��̍��ł͖ѐD���ƃ��C���̐��Y�ʂƎ��v�͂҂����荇���Ă��āA����Ă̓��e�ɂ���Ē������z�������邱�Ƃ͂���܂���A���Y�ʂ������Ă������̎��v�͑������܂���B�]�������͂ǂ��Ȃ���̂ł����H�S�������ɑウ��Ƃ�����A�������邵���Ȃ���Ȃ��ł����H�v
�u���J�[�h����A�ł͂������܂��傤�B�p���̖ѐD���ƃ��C���̎��v�ʂ͂ǂ�قǂł����H���ǂ��ł��̕��Y���ċM���ɗA�o���č����グ�܂��B�������A����̘J���͗ʂł͐��Y�ʂ������邱�Ƃ͂ł��܂���A�������̍�����J���҂ɗ��Ă�����Č��\�ł���B�ق�r�ׂČ��Ă��������B
�@�@�@�@ �@�@�@�p���@�@�@�|���g�K�� �@�Q�����̑����Y�ʁ@
�@�ѐD���@ �@�@�@�O�l�@ �@�@�Q�Q�O�l �@�@�Q�D�S�S�@�@�P��
�@���C�� �@�@�@�@�O�l �@�@�@�P�V�O�l �@�@�Q�D�P�Q�T�P��
�@���J���� �@�i�@�O�l�j�@�i�P�V�O�l�j
�@�@�@�@ �@�@�@�p���@�@ �@�@�|���g�K�� �@�Q�����̑����Y�ʁ@
�@�ѐD���@ �@�@�Q�Q�O�l�@ �@�@�@�@�O�l �@�@�Q�D�Q�@�@�P��
�@���C�� �@�@�@�@�@�O�l �@�@�@�P�V�O�l �@�@�Q�D�P�Q�T�P��
�@���J���� �@ �i�Q�Q�O�l�j�@�i�P�V�O�l�j
���C���̐��Y�ʂ͕ς��܂��A�ѐD���͂Q�D�Q�P�ʂ��Q�D�S�S�P�ʂɑ������܂��B�����őS�����Y�����ق����ѐD�������Y�ʂ������܂���v
�u���ꂪ������ł�����A�p���̓��C�����A�|���g�K���͖ѐD�����Ƃ������S�͔@���ł��傤�B�ѐD���͋@�B�Y�Ƃ��K�v�ł����A�ѐD����@�B�Y�Ƃ�ʂ̐D���Ƃ̔��W�ɂ��v�����܂��B���C���̐��Y�ʂ����邱�Ƃɂ��ẮA����}�����Ăъ|���ĉ��Ƃ����܂�������v�ł��v
����̃��J�[�h�́A�|���g�K���̔��_�ɂǂ�������̂��낤�B
�����o�ς̔��W���A�_�ƏA�Ɛl���̌����Ƃ���ɑ���H�ƏA�Ɛl���Ə��ƁE�T�[�r�X�ƏA�Ɛl���̑����Ƃ������ۂ������ƁA���z�ł���f�c�o�ł��������ۂ������A���݂̓��{�̔_�ѐ��Y�Ƃ��f�c�o�ɐ�߂銄���͂P�D�S�������Ȃ����Ƃ��l����A�|���g�K�������C���ɓ�������A���̌�ǂ������g���W�h�𐋂��Ȃ���Ȃ�Ȃ����𐄑�����̂͂���قǓ�����Ƃł͂Ȃ��B ���@�w�N�V���[���I���[���̒藝
�@��r�D�ʂ�������闝�_�Ƃ��ẮA���J�[�h�́u��r���Y����v�̑��ɁA�w�N�V���[���I���[���̒藝������B
�w�N�V���[���I���[���̒藝�́A�f�Ղ���Q���ԂŐ��Y���Ə����������ł������Ƃ��Ă��A�Q���Ԃɗv�f�����䗦�̈Ⴂ������Η����ňقȂ���ɔ�r�D�ʂ��������Ėf�Ղ��L���ɂȂ�Əؖ������Ƃ������̂ł���B �w�N�V���[���I���[���̒藝��������������́A
�i�P�j�Q���Q���Q�v�f���f��
�i�Q�j���Y���Ə�����͂Q���œ���
�i�R�j�s��͊��S����
�i�S�j��̍��͈�������{�L�x���ł���������J���L�x��
�i�T�j��̍��͈�������{�W����ł���������J���W���
�i�U�j��̗v�f�͎��{�ƘJ���ł��邱�ƁB
�i�V�j���Y�v�f�͍����ł͎��R�Ɉړ��ł��邪�A�������z���Ĉړ��ł��Ȃ�
�ł���B�����āA�v�f�����̈Ⴂ�������̍��̑��Ή��i�ɔ��f�����Ƃ���B
���{�L�x���ł́A����̐��Y���̉��ł͘J���L�x���������{�W����̑��Ή��i���Ⴍ�A�J���W����̉��i�������Ȃ�B
������A�e���́A�����ɑ��ΓI�ɖL�x�ɂ��鐶�Y�v�f���W��I�ɗp������ɔ�r�D�ʂ������ƂɂȂ�ƌ��_����B �܂��A���̒藝�ł́A�ގ��I�ȗv�f�����䗦�ł����i�����Ԃ�r�㏔���Ԃ̎��R�f�Ղ̐�������������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B ��i���Ɣ��W�r�㍑�̂������̎��R�f�Ղ𐳓�����������Ƃ��āg����I�Ɂh�L�����������Ă��邱�Ƃ͔F�߂��邪�A���R�f�Ղł͂Ȃ��A�O�q�����O�������ɂ�铌�A�W�A�����̌o�ϐ����_���Ɋr�ׂ�Η�����g�o�ϗ��v�h�ł���B �܂��A���W�r�㍑�̈ʒu�Â����Œ艻������̂ł���A�ʉݓI�ړx�ő����鎑�{���B�ł͂Ȃ��A�����Y�ʂ̍ő剻������i�̍ŏ������o�ϗ��v�ɒ�������ƍl�����Ƃ��̂ݒʗp������̂ł���B ���{�o�ς␢�E�o�ς�����킩��悤�ɁA�u�ߑ�o�σV�X�e���v�ł́A�����i�̋ɏ����͌o�ϗ��v�������炷�ǂ��납�A�u�f�t���s���v�Ƃ����o�ϓI��Ж�������炷���Ƃ��킩���Ă���B �u���R�f�Վ�`�v�́A���E���x���Ŏ��v�K�͂��傫���t�����l���傫�����̐��Y����ō��ۋ����͂��ւ��Ă��鍑���o�ς̍��Ƃ��咣����u�ی�f�Վ�`�v�Ȃ̂ł���B �����āA��������炩�ɏ��������邽�߂ɂ́A�����Ŋ��S�ٗp�ɋ߂��o�Ϗ��ێ�����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B http://www.asyura2.com/2002/dispute3/msg/570.html �f�ՂƃO���[�o���Y�� 05�^3�^7
���J�[�h�́u��r�D�ʂ̌����v
���C�u�h�A�̃j�b�|�������������́A�F�X�ȋ��P��^���Ă��ꂽ�B�����O���[�o���Y���������Ă�����{�̃}�X�R�~�����ɂ��č��Ǝ�`�҂ɕϐg�����B�Ⴆ�e���r�����̍L���В��́A���{���O���n��Ƃɂ������ǂւ̏o���K�������֓d�g�@������@�̉������������Ă��邱�Ƃɂ��āu���}�������v�Ǝ^������ӌ��������Ă���B
�����A���{�̃}�X�R�~�͍\�����v�h��j���[�N���V�J���o�ϊw�h�ɐȊ�����Ă���A�{���Ȃ�A�s�ꎊ���`�������A������K���ɔ����闧��̂͂��ł���B�Ƃ��낪�����B�ɍ~��|�������Г�ɑ��Ă����́A�K�������Ď��Ƃ͂������������ł���B�܂�Ő�T���Ŏ�グ���̂̎Љ�}�̐����Ƃ̂悤�ɁA���{�̃}�X�R�~�̓_�u���X�^���_�[�h�ł���B
�Ƃ���ŕM�҂́A�O���K���Ɏ^���ł���B�����������ƊE�����ɊO���K����K�p����Ƃ����l���ɂ͔��ł���i�O���ł����f�B�A�ɑ��ĊO���K�������邱�Ƃ������ɂ��Ă���炵�����j�B�S�Ă̊�Ƃɂ��Ă��O���̋K�����������ׂ��ƍl����B���������M�҂́A�o�ς̃O���[�o���Y�����̂��̂ɋ^��������Ă���B�M�҂́A���ꂼ��̍��������b�g�̂���͈͂ō��ۓI�ȋK���ɘa���s���Ηǂ��Ƃ����l���ł���B���ł��K�����ɘa����A�������K���ɂȂ�Ƃ����b�͌��z�ƍl����B
�O���ƌ��Ղ��邱�Ƃ́A���Ƃ��ėǂ����Ƃ��Ƃ����ӌ��������B���̍l���̉����ŁA�f�Ղ��ǂ�ǂR��������A�O�������ʂ̘J���҂̎����邱�Ƃ��ǂ����Ƃƍl����l�X������B���{�ɂ�FTA��ϋɓI�ɐi�߂邱�Ƃ��K�v�Ə����鐭���Ƃ�������A�o�c�A�͒P���J���҂���{��������ׂ��ƍl���Ă���B ��ʂ̐l�X�̊Ԃɂ́A�f�p�ɓ��{�l�͍����ɎY�o���Ȃ��Ζ����g���A���{�̐��i���e���ɗA�o���ł��ٗp�@����m�ۂł���Ƃ����ӌ�������B�������f�ՂƂ������̂͑o���Ƀ����b�g�����邩��s����̂ł���B�Y�����́A���̕ӂ��@������Ζ����o�Ă����̂ł���A����Ȃ��̂��Ă����҂����邱�ƂɊ��ӂ��Ă���Ƃ��l������B���Ղ�����I�ɓ��{�����Ƀ����b�g������ƍl����̂͂��������B
�M�҂́A�o�ς̃O���[�o���Y���ɂ͌��Ɖe������A�����A���̕����������₯�ɋ�������Ă���ƍl����B�����Ŗ{���͂��炭�o�ς̃O���[�o���Y������グ��B�������o�ς̃O���[�o���Y���ƌ����ƁA�e�[�}�Ƃ��đ傫���B�����Ōo�ς̃O���[�o���Y�����u���̌��ՁA�܂�f�Ձv�u���{�̈ړ��A�܂�O���̐i�o�v�u�l�̈ړ��A�܂�O���l�J���ҁv�̎O�̑��ʂ���_�������B
�܂��u�f�Ձv����グ��B�f�Ղ������ɂȂ邱�Ƃ��A�ǂ̍��ɂƂ��Ă��ǂ��Ƃ����ӌ��͒N�����咣�������邪�A�������Ƃɂ��̍����͂ƂĂ�����ł���B���̂悤�ȍl���̍��{��H���čs���ƁA�ǂ����Ă����J�[�h�́u��r�D�ʂ̌����v�ɓ���B����ɂ��Ă͒����Ƃ̌��Ղ̊W�ŁA�{��02�^7�^22�i��261���j�u�����̕s���Ȉב���v�Ŏ�グ���B �u��r�D�ʂ̌����v���K�ɓ����ɂ́A�בփ��[�g���K�Ȑ����ɂ���K�v������B���������{�̂悤�ɍw���͕�����荂���ב����Ő��ڂ��Ă��鍑���������A������C���h�̂悤�ɍw���͕�����蒘�����Ⴂ�ב����̍�������B����ɒ����́A�s�K�Ȉבփ��[�g��ăh���ɂb�O���邱�Ƃɂ���Ă����Ƃ��̕s�K�Ȉבփ��[�g���ێ����Ă���B���̂悤�Ȃ��Ƃ��������Ȃ�u��r�D�ʂ̌����v�������̂ł͂Ȃ��A�S�Ă̐��Y���͒����Ő��Y���邱�Ƃ��L���ɂȂ�B �����������J�[�h��18���I�㔼�̌o�ϊw�҂ł���A�����͋��{�ʐ��̎���ł���B�܂�s�K�Ȉבփ��[�g�Ȃ�čl����K�v���Ȃ������̂ł���B����Ƀ��J�[�h�̏�����ÓT�h�̌o�ϊw�ł́u���Y�������͑S�Ĕ����Ƃ����Z�C�̖@���v���������Ă���B�܂�u��r��ʁv�ƂȂ��ċ����ɔj��Ă��A���Y�҂͑��̕��Y���铹������Ƃ�����������������l�������{�ɂ���B ��͂���{�͓����g���
�u��r�D�ʂ̌����v�͈ב֕ϓ����K�łȂ���ΓK�ɓ����Ȃ������łȂ��A�ÓT�h�o�ϊw�̑O��ɂȂ��Ă��銮�S�������łȂ���Ό����ɓ����Ȃ��B�Ƃ��낪�����̌o�ςł͎Y�Ƃɂ���ĎQ����ǂ̍������܂��܂��ł���B�Q����ǂ������Y�Ƃ́A���{�̕ی쐭�Ȃ��Ƃ����R�f�Ղő������邱�Ƃ��Ȃ��B����A�Q����ǂ̒Ⴂ�Y�Ƃ́A�f�Ղ̎��R���̈��e��������Ɏ�B
�o�ς̃O���[�o���Y���ƎQ����ǂ̊W�́A�{���ł� 00�^5�^15�i��162���j�u�o�ς̃O���[�o������NGO�v
http://www.adpweb.com/eco/eco162.html �ŏq�ׂ��B�Q����ǂ̍������܂��܂��̏�Ԃ̂܂܂ŁA�P���ɖf�Ղ̎��R����i�߂�A�f�Ղ̎��R���ʼn��b����l�X�ƁA���Q����l�X�ɕʂ��B�������ɓ��{�ɂ����ď����i���̍L�����Ă��邪�A������f�Ղ̎��R���̐i�W�ƊW���Ă���B�܂��Q����ǂ��Ⴂ�Y�Ɓi�_�ƂȂǂ��T�^�j�͎�ɒn���ɔz�u����Ă���A�f�Ղ̎��R���̐i�W�͍����̒n���o�ς̔敾�Ɩ��ڂȊW������B �܂����i�H�Ƃ����グ��A�Q����ǂ��Ⴂ�ėp�i�Y���Ă���Ƃ���͖f�Ղ̎��R���ő��Q���A����ȕ��i���Ă���Ƃ���͉e�������Ȃ��B�������ɔėp���i�Ȃ���Ă��鎞��ł͂Ȃ��Ƃ����ӌ�������B�������S�Ă̕��i���[�J�����ꕔ�i�̐������[�J�ɊȒP�Ɉڍs�ł���킯�ł͂Ȃ��B�܂��Ă⒆���̂悤�ȕs���Ȉב�����s���Ă��鍑�̑䓪��e�F���邱�Ƃ͖��ł���B �_�Ƃɂ��Ă��A�k�C���̂悤�ȍH��ʐύL���Ăɗ��邱�Ƃ̂Ȃ��_�Ƃ�����Ă��鏊�ƁA�{�B�̂悤�ɔ_�Ƃ��ˑR�č�ɂ����������n��Ƃł͗��Q���Η�����B�k�C���͖f�Ղ̎��R����e�F���邩������Ȃ����A�{�B�̔_�Ƃ͊ȒP�ɂ͔_�Y���̎��R����e�F�ł��Ȃ�����ł���B���̂悤�ɖf�Ղ̎��R���ƌ����Ă��A�����̗��Q�͈�l�ł͂Ȃ��̂ł���B
������C���h�̈ב���͕s���ł���Ƃ��A���{�����̎Y�ƍ\�������Ă������������ɍs����͂����Ȃ��ƌ����Ă��A�f�Ղ̎��R���͊m���ɐi��ł���A�����i���͑傫���Ȃ��Ă���B������������C���h���ȒP�ɐ����ς���͂����Ȃ��B�����̓��{�̕�����O��ɂ���Ȃ�A�c�O�Ȃ��狣���ɂ��炳��₷���Y�Ƃ̐l�X�́A����ɑR����K�v������B������[���l���鐭���Ƃ��}�X�R�~�l�����Ȃ������A�����̎Y�ƂɌg���l�X�͎����Ŗh�q��i���l���鑼�͂Ȃ��Ƃ�������ɒǂ����܂�Ă���B
���{�̋��ȏ��ɂ́A���{�͖f�����ł���A�f�Ղʼn��b���Ă���ƋL�q����Ă���B�������P���ɂ��̂悤�Ȃ��Ƃ������Ȃ�����ɂȂ��Ă���B�f�Ս��������܂�A�~���ɂȂ�B�~����j�~���邽�ߎ��{�̊C�O���o�𑱂���ƁA���x�͊C�O�Ɏ����Y�������A���ꂩ��̗�����z�������������A���ꂪ�܂����̉~���v���ɂȂ�B�~���ɂȂ�Ί�Ƃ͍������ɔ����A���X�g�����s�������͂����邱�ƂɂȂ�B ���{�������g������Ȃ������ł́A��Ƃ͗A�o�ɗ��邱�ƂɂȂ�B���������ꂪ�����A�����B�̎���i�߂�̂ł���B�܂�f�Ղ��A�N�ɂƂ��ă����b�g������̂�������Ȃ��Ȃ��Ă���B��Ƃ̃����b�g�ƌ����Ă��A��Ƃ̌o�c�҂Ȃ̂��]�ƈ��Ȃ̂��A�͂��܂�����Ȃ̂��A�����b�g����҂�������Ȃ��B
�����A�ō��v���L�^���������Ƃł͒����̈��������v�悵�Ă���B��Ђ̗��v�͐L�тĂ��邪�A����͍����̔̔��̕s�U���C�O���Ƃ��J�o�[��������ł���B�܂荑���]�ƈ��̋������グ�闝�R���Ȃ��̂ł���B�����]�ƈ��͉�Ђ̊C�O�i�o�ɋ��͂��A�Z�p�̊C�O�ړ]�ɋ��͂����B�������C�O���Ɣ��W�̐��ʂ́A�����̏]�ƈ��ɂ͊Ҍ�����Ȃ��̂ł���B���ɂ��̉�Ђ͊O���̎������䗦�������A���Ղȍ����]�ƈ��̒��グ�͂ł����A�ނ���������ɓ����Ă���̂ł���B
���̂悤�ɓ��{�͖f�Ղɗ���f�����ŁA�f�Ղɂ���č����͍K���ɂȂ�Ƃ����P���ȊT�O�͍����ł͒ʗp���Ȃ��B�A�o���L�т�A�~�����i�݁A����ɗA�o��̍��ł̐ݔ��������v�������B��Ђ͐����������c�邪�A�����̏]�ƈ��≺�����Ǝ҂͂��̂����]���ɂȂ�̂ł���B �G�˂̃}�X�R�~�l����Ƃ́A���ȏ��̋L�q�ʂ�A�f�Ղ�����ɂȂ�����͖L���ɂȂ�ƐM���Ă���B���{���AFTA�𐄐i����Γ��{�̌o�ϐ������������グ��ƌ����Ă��邪�A������ꎞ�I�Ȃ��̂ł���i������ق�̂킸���Ȑ����j�B�ނ��돫���A���̔����̕����傫���B �����ł͊�Ƃ̗��v���A�����⍑�Ƃ̗��v�Ƃ͂Ȃ�Ȃ�����ɂȂ��Ă���B�M�҂́A�f�Ս����́A���{��ODA�̊z�Ɍ����������ŏ\���ł���ƍl����B�����ƌ����Ώ������x�������ł��邩��A����ɖf�Ս������������ėǂ��B�ނ�����{�́A�����g����s���āA�C�O�Ɉˑ�����x������Ⴍ���Ă������悤�Ȍo�ςɓ]�����ׂ��ł���B �@ ���T�́u���{�̈ړ��A�܂�O���̐i�o�v����グ��B��O�Ȏ��{�̘_�����������A����ɋt�炤�͎̂��{�s��̓�����c�߂�ƌ����Ă���B���Ƃ��u���C�u�h�A�̍s���́A���s�̖@���̏�ŋ�����Ă���̂ł���A�����ے肷�邱�Ƃ͎s���ے肷�邱�ƂɂȂ�v�Ƃ����ӌ��͂���ɉ����Ă���B�܂����ꂪ�O���[�o���X�^���_�[�h�Ƃ��A�����J���X�^���_�[�h�ƌ����Ă���B ����������̂悤�Ȃ��܂������̂悤�ȃ��C�u�h�A�w�c�̍s���́A�A�����J�ł��ڋ��ȍs���Ɣے肳���\���������B���[�}���u���U�[�X�����āA�č��Ȃ獡��̂悤�ȏ������s���Ă������^��ł���B�n�Q�^�J�t�@���h�����āA�č��ł͂ƂĂ����Ȃ����Ƃ���{�ł���Ă���\���������B�������{�̂��Ŏv�l�͂̂Ȃ������Ƃ�}�X�R�~���A���ꂪ�O���[�o���X�^���_�[�h�ƌ�����Ă���̂ł���B http://adpweb.com/eco/eco380.html
�����̕s���Ȉב��� 02�^7�^22
��r�D�ʂ̌���
�ŏ��ɁA���Ղ̗L�v���̗��_�I�Ȕw�i���q�ׂ邱�Ƃɂ���B���̂��߂ɕ���₷���Ⴆ��p����B�܂��k�C���Ǝ������̌��Ղł���B
�Ⴆ�Ζk�C���ł́A�u���Ⴊ�����v���ɂ߂Ĉ������邪�A�u�T�c�}���v�̐��Y�R�X�g�������������Ƃ���B���Ɏ������ł́u�T�c�}���v���������邪�A�u���Ⴊ�����v�̐��Y��������Ƃ���B���̂悤�ȏꍇ�A�k�C���͗]�v�Ɂu���Ⴊ�����v�����A������������ɔ��邱�Ƃɂ��A���Ɏ������́u�T�c�}���v�Y���A���Y����k�C���ɔ��邱�Ƃɂ���B�����Ėk�C���́u�T�c�}���v�A�������́u���Ⴊ�����v�͔̍|�����ꂼ����~�߂�B ���̂悤�Ȍ��Ղ��s�����Ƃɂ���āA�k�C���Ǝ������̑o���Ƀ����b�g�����܂��B�k�C���͍��R�X�g�́u�T�c�}���v�͔̍|���~�߂邱�Ƃɂ���āA���Y�����𑼂̍앨�ɐU�����邱�Ƃ��ł��A���������u���Ⴊ�����v�̐��Y�����𑼂̗L�v�ȍ앨�ɐU��������B�܂�k�C���Ǝ������́A�݂��ɒ�R�X�g�̐��Y�����������邱�ƂɁA���Y�]�͂����܂�B����ɂ��̂��Ƃɂ���ď����̑������\�ɂȂ�B���̂悤�Ɍ��Ղ́A�o���̏��������ƌ��������b�g��^���邱�ƂɂȂ�B�����Ă����Ń|�C���g�ƂȂ邱�Ƃ́A���Ղ��u�o���v�Ƀ����b�g��^����ƌ����_�ł���B �����Ă��̌��Ղɂ�郁���b�g�́A�����Ɏ~�܂炸�A�C�O�Ƃ̌��Ղɂ��L���邱�Ƃ��ł���B���̂悤�Ɍ݂ɐ��Y�R�X�g������������������A�܂�O���ƌ��Ղ��邱�Ƃɂ���đo���̍��ɏ����̑����������炳��邱�Ƃ��n�߂ė��_�I�ɐ��������̂����J�[�h�ł���B�����Ă���́u��r�D�ʂ̌����v�ƌĂ�A���ە��Ƃ𐄐i���闝�_�I�����ƂȂ��Ă���B��̗�̏ꍇ�A�k�C���́u���Ⴊ�����v���A�����Ď������́u�T�c�}���v���v�X�u��r�D�ʁv�ƌ������ƂɂȂ�B �l�X���悭���ɂ��� �u���R�f�Ղ𐄐i���A���Ղ��L�߂邱�Ƃ́A�o���Ƀ����b�g������A�����j�Q�����ǂ��������邱�Ƃ���v �ƌ����Z���t�̔w�i�ɂ��A���̃��J�[�h�̗��_������BWTO�́A���̐��_�ɏ���Ƃ��āA�ł�⏕���ƌ������f�Ղ̏�ǂ��Ȃ�ׂ��Ⴍ���邱�Ƃɂ���āA�f�Ղ̎��R���𐄐i���邱�Ƃ�ړI�ɂ����@�ւł���B
�������ɐ�i���̊Ԃł́A���ꂼ��̍��ɓ��ӂȐ��Y��������A��������Ղƌ����`�Ō�������A�݂Ƀ����b�g�������悤�ȋC������B���������ۊԂ̌��Ղɂ́A�����̌��ՂƂ͌���I�ɈႢ���Ƃ����݂���B�f�Ղɂ͈בւ���݂���̂ł���B�������בփ��[�g���K���Ȕ͈͂Ɏ��܂��Ă���̂Ȃ���͂Ȃ��B�Ƃ��낪���{�̂悤�ɍw���͕�����蒘�����������ۂ̈בփ��[�g�����ڂ��Ă���ꍇ�ɂ͖�肪������B
�����Ƃ������̉~���[�g�ɂ��ẮA�w���͕�����荂�����ڂ��Ă��錴���̑啔���͓��{�ɐӔC������B�܂��������v�������I�ɕs�����Ă���A�Y�Ƃ��A�o�w���^�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ���������B����Ɏ��{���o�i�ב։���ɂ��O�ݏ������̑�����܂܂��j�ɂ��c��ȊC�O���Y�̗ݐς�����A����炩�甭�����闘����z�����~�����͂ƂȂ��Ă���B�{���Ȃ�A�����g����s���Ă��Ȃ�������Ȃ������̂ł��邪�A���ꂪ�\���s���Ă��Ȃ������c�P�������̉~���ƂȂ��Ē��˕Ԃ��Ă��Ă���̂ł���B
���̂悤�ɉ~���[�g�͂��тȐ����Ő��ڂ��Ă���B����������ɂ́A�t�ɍw���͕�����蒘�������������Ő��ڂ��Ă���בւ�����B�����́u���v��C���h�́u���s�A�v�Ȃǂł���B���ɖf�ʂ����債�Ă��钆���́u���v������ł���B
01�^5�^28�i��209���j�u�����Ƃ̒ʏ����v
http://www.adpweb.com/eco/eco209.html
�Ŏ�グ���悤�ɁA����̒����ɂ��A���̍w���͎͂��ۂ̈בփ��[�g�̂Ȃ��4.55�{������B���Ȃ݂ɓ��{�̉~�͋t��0.78�{�̍w���͂ł���B�����̐��l�����ɁA�~�ƌ��̍w���͂��r����ƁA�����̌��͓��{�̉~�́A����6�{�̍w���͂����邱�ƂɂȂ�B
�����A���背�[�g�ł�1����15�~�ł���B���������Č��̖{���̍w���͂́A6�{��90�~�ƌ������ƂɂȂ�B�܂������̌��͕ăh���Ƀ����N�i�x�b�O�j���Ă���A���ɍ����̂悤�ȉ~���������A1����100�~�A110�~�ɂȂ�\��������B�������ɐ���̎��Z�͂�����ƌÂ����A�����́u���v���ɂ߂Ă��тȊǗ����s���Ă���͂������ł���B �����̍H�Ƃ̔��W���߂��܂������Ƃ͔F�߂邪�A�����̗A�o�̋}���́A�i���̌���ł͂Ȃ��A���̂悤�ȂƂ�ł��Ȃ��בփ��[�g�̈ێ�����ɂ����̂ł���B�����̍H��J���҂̒����́A���{��20����1�Ƃ��A30����1�ƌ����Ă��邪�A����͂����܂ł����背�[�g�̊��Z�ɂ����̂ł���B���̍w���͕����Ŋ��Z����A3����1����5����1�ƌ����̂����Ԃł���B ����͖{���ňȑO����q�ׂĂ��邱�Ƃł��邪�A���ƒ����̕����́A6�{�Ōv�Z����Ǝ��Ԃɍ����B�Ⴆ�A������GDP��1���h�����z���Ă���B������w���͕����Ŋ��Z�����6���h�����ƌ������ƂɂȂ�A���{��GDP���͂邩�ɉz���邱�ƂɂȂ�B�����Ƃ�����ł���l�����GDP�́A���{��8����1����7����1���x�ł���B�R��������\����Ă���z��200���h���ł��邪�A�č��̍��h�Ȃ́A����3�{�ȏ��650���h���ƌ��Ă���B�������h�Ȃ̌������������Ȃ�A�w���͕����Ŋ��Z���������̌R�����45���~�ƂȂ�A�����50���~�̕č��ɕC�G����z�ł���B�������ɒ����͔N��50����̃~�T�C����n�݂�����B�ƂĂ��z�ʂ�200���h���̌R����ł͂ƂĂ��d���Ȃ��悤�ȌR���̑������s���Ă���̂ł���B
�ŏ��̌��Ղ̘b�ɖ߂��B
�u��r�D�ʂ̌����v�������ɂ́A���Ղ��s�������̈בւ��K���Ȕ͈͂Ɏ��܂��Ă���K�v������B ���{�̏ꍇ�A�ΐ�i���ł��������~�����������Ă���B����������͓��{�������Ɉˑ�����o�ς��������邱�Ƃ�ӂ��Ă������ʂł�����A�Îׂ��ʂ�����B�������Β����͎���傫���قȂ�B���܂�ɂ������ُ͈�Ȉב����i�펯���킵�������j���ێ����Ă���B����ł͓��{�ƒ����̊Ԃł͂ƂĂ��u��r�D�ʂ̌����v�������Ȃ����ƂɂȂ�B����͂قƂ�ǑS�Ă̐��Y�����𒆍��ōs�����Ƃ������I�ƂȂ�B �Ƃ���Ŗ{���ꎞ�I�Ɉב������ُ�Ȑ����ł��A���炭����A�p�����[�^�ł���בւ��K���Ȓl�ɓ����͂��ł���B�����́A�Γ��{�����ł͂Ȃ��A�č����n�ߊe���Ƃ̖f�Վ��x�͑傫�ȍ����ł���B�܂肱�̂悤�ȏ�Ԃ������A���������Ȃ�A�~���n�ߊe���̒ʉ݂������Ȃ�悤�����͂��ł���B�����������͕ăh���ɂ������胊���N�����邱�Ƃɂ���āA���������ێ����Ă���̂ł���B���ɒ����̌��͍��O�Ɏ��o�����֎~����Ă���A�e�����������邱�Ƃɂ���Č��̈ב����ɉe����^���邱�Ƃ��ł��Ȃ��d�g�ɂȂ��Ă���B �ב֑���̌���
�h�C�c�̃t�H�[�N�X���[�Q���́A��N�`�F�R�Ɏ����ԍH��邱�Ƃ������������A�ŏI�I�ɂ�������~�߁A�h�C�c�����ɍH��邱�Ƃɂ����B�`�F�R�̐l����́A�h�C�c��5����1�ł���A����̓t�H�[�N�X���[�Q���ɂƂ��Ă͖��͓I�ł���B�������`�F�R�̃C���t���̏Ȃǂ����Ă���ƁA��͂�h�C�c�����̐��Y�ݔ������������ǂ��ƌ������_�ɂȂ����̂ł���B
�Ƃ��낪�����̐l����́A���{��20��1�A30����1�ł���B����ł͂����璆���̃C���t��������Ă��Ă��A���{�̐����Ƃ͑S�Ē����Ɉړ]���������ǂ��ƌ������_�ɂȂ�B ���̂悤�ɑS���u��r�D�ʂ̌����v�������Ȃ���Ԃł���B�܂��ɒ����̈ב���́A���{���n�߂Ƃ��āA�e���ɑ���Y�Ƃ̔j���ł���B ���ہA���{�����łȂ����E�I�ɒ����̈ב���̋]���҂��ǂ�ǂ�o�Ă��Ă���B���`�͒��s���Ŏ��Ɨ���7.7���ƂȂ��Ă���A����A�W�A���p�̐��Y���_���ǂ�ǂ��Ɉړ]���Ă���B���L�V�R�̕ېōH����A�������i�̑ΕėA�o�̋}���ŁA�m���̏�Ԃł���B �������s�K���Ȉבւ�����A�l����̓`�F�R���i���V�A���������炢�j�ɂȂ�͂��ł���B�����Ȃ�A�t�H�[�N�X���[�Q���̗�悤�ɁA�����Ɉړ]���������ǂ��H�������A��͂���{�ɒu���Ă��������ǂ��ƌ������Z�ݕ������N��͂��ł���B���Ȃ݂Ƀt�H�[�N�X���[�Q���́A�����ɐ��Y���_������A�u�T���^�i�v�Ȃǂ����Ă���A������4���ȏ�̃g�b�v�V�F�A�[���߂Ă���B
�M�҂��A�뜜����̂́A�����̂��̂ނ��Ⴍ����Ȉב����܂����莋����Ă��Ȃ����Ƃł���B�{�����ُ�Ȓ����̈ב������グ���̂�1�N�ȏ���O�ł���B����ȍ~�A�����̌o�ς⒆���Ƃ̒ʏ����́A�F�X�ȃ��f�B�A�Ŏ�グ���Ă���B�������قƂ�ǑS�Ă��A���̕s�K���Ȉב֑���ɂ͑S���ƌ����ėǂ��قǐG��Ȃ��B�����̌o�ς��l����ꍇ�ɂ́A�בւ���ɂ��Ȃ���A�S���Ӗ����Ȃ��B���������Ē����̎����`����e���r�ԑg���S�ăs���g���傫���Â�Ă���B
��ʂ̐l�X�������̈ב������C�����܂܁A�u��r�D�ʂ̌����v�������Ȃ���Ԃ������A��ςȂ��ƂɂȂ�ƌ������ƂɋC�����Ă��Ȃ��B
�����l�X�͉��̂����{�̐����Ƃ��ǂ�ǂ�ړ]���Ă����l�q��s�����Ɍ��߂Ă��邾���ł���B���̂������̗�����ς��Ɗy�ϓI�ɍl���悤�Ɠw�߂Ă���B�����������̈ב��ς��Ȃ�����A���̗���͎~�܂�Ȃ��B5�N��A10�N��ɂ͑�ςȎ��ԂɂȂ��Ă���͂��ł���B
���ۓI�ɒ����̈ב���ɖ��ڒ��Ȃ̂́A���ۋ@�ւ̎嗬�h�ƂȂ��Ă���l�X���قƂ�lj��Đl�ƌ������ƂƊW������ƕM�҂͍l����B�܂����B�e���́A���O�Ƃ̌o�ό𗬂͑傫�����A�唼�����[�������ł���A�P��ʉ݃��[�������ŁA�o�ς͈ב֕ϓ��ɂ��܂�e������Ȃ��B����A�č��́A���XGDP�ɐ�߂�f�Պz�̔䗦���������B����ɕăh���͐��E�̊�ʉ݂ł���A����Ƀ����N���Ă���ʉ݂������B�܂�č����בւ̕ϓ������܂�C�ɂ��Ȃ��Ă��o�ϊ������s����̂ł���B
�č��������C�ɂ���Ƃ����Ȃ玟�̂悤�ȃP�[�X�����ł���B�ăh���������Ȃ������̍����Y�ƁA���Ɏ����ԃ��[�J�[����̕s�����o��ꍇ�ł���B�܂����ɕăh���������Ȃ����ꍇ�̎Y��������̃N���[�����N��P�[�X�Ȃǂł���B�����������ĕĐ��{�́A�I���̎��ł��Ȃ�����A���܂�בւ��C�ɂ��Ă��Ȃ��B���̂悤�ɉ��Ă̌o�ς́A���{�قǂɂ͈ב����̓����ɉe�����Ȃ��̂ł���B ���ہAWTO�͊e���̈בւ̐�����ב�����قƂ�NjC�ɂ��Ă��Ȃ��B�����͏d�v�ȃ|�C���g�ł���BWTO�́A���Ղ������������邽�߂ɏ�Q�ƂȂ�̂́A�łƕ⏕���A�����Ċe���̏����s�⍑���Y�Ƃ̕ی��ړI�Ƃ����@���Ȃǂ̔�Q����ǂ����ƍl���Ă���B�Ƃ��낪�������s���Ă��邢��ב���́A�łƕ⏕���ȂǂƔ�ׂ��Ȃ����炢�傫�ȎQ����ǂł���B�������ǂ������A�ǂ����Ă�WTO�͂��̎��������ɂ͔F�߂�����Ȃ��̂ł���B���낤���Ē�����WTO�̉����Ɠ����ɁA�����ɑ�����ʂ̃Z�[�t�K�[�h �i01�^9�^17�i��222���j�u�Β����AWTO�̓���ی�[�u�v
http://www.adpweb.com/eco/eco222.html
���Q�Ɓj��F�߂����ƂɎ~�܂��Ă���B�ǂ����č���WTO�̔F���͂܂��܂��Â��悤�ł���B
�܂������Ƃ����łȂ��A�o�ϊw�҂�G�R�m�~�X�g���בւɊւ���S���Ⴂ�i�ăh���̑啝�����ɂ���ĕč��̐����Ƃ͎��������ƕM�҂͍l���Ă��邪�j�B�j���[�N���V�J���h�̑�\�I�ȑ��݁i���c�̈�l�j�ł��郍�o�[�g�E���[�J�X�Ȃǂ� �u�č��ɋ��Ȃ���t�����X�̃��C���Ɠ��{�̃X�V�����킦��v �u�������Y���_���ڂ�̂��A�����l�̐l���������ɐ��i�̎������サ�Ă��邩��ł���A����͎��R�̗���ł���v �Ƌɂ߂ĒP���Ɍo�ς̃O���[�o�������]���Ă���B���������̒��x�̔����Ȃ珬�w���̈ӌ��ƂقƂ�Ǖς��Ȃ��B����������Ƃ��āA�Ƃ�ł��Ȃ��ב������ێ����A���E���̌o�ς��h�����Ă��邱�Ƃɂ́A�S���l�����y�Ȃ��̂ł���B ���c�����c�Ȃ�A�ނ̓��{�̐M�҂��M�҂ł���B���{���_�Y���ɑ��ăZ�[�t�K�[�h������Ɠr�[�ɔ������A �u���R�f�Ղɔ�����v�Ƃ� �u���{�͋����͂�����ׂ��i�����̈ב֑���ɂ���Đl���20����1��30����1�ɂȂ��Ă��ẮA�����͂��ւ���������Ȃ��ł��낤�j�v �Ƃ��Ȕ��������Ă���B���ɂ́uWTO�̌��̐i�W�̂��߂ɂ́A���{�͂����Ɣ_�ƕ���̊J���������Ȃ��ׂ��v�ƌ����Ă���l�X������B���{�̐H���̎������͂�������40���ł���A���̐��l�͂قڐ��E�Œ�ł���B���������ɉ�����Ƃ܂��߂Ɍ����Ă���̂ł��邩��A�{���ɂ������B ���{���s�����Ƃ́A�܂�WTO�Ɉב������������ُ�Ȑ����ɂ��鍑�ɑ��Đ��������߂�悤�v�����邱�Ƃł���B�������ꂪ�F�߂��Ȃ��ꍇ�ɂ́A���{�Ǝ��ŁA�ב֕s�K�����ɑ�����ʊł�݂��鑼�͂Ȃ��B���������{�Ɠ�����Q�����Ă��鍑�Ɠ���������Ƃ邱�Ƃ��l������B�����Œ��������̂悤�ȓ����ɃN���[��������悤�Ȃ�A�����Ƃ̖f�Ղ�啝�ɐ������邩�A�ň��̏ꍇ�͎��~�߂邱�Ƃ��l����ׂ��ł���B�����Ƃ̌��Ղ��~�߂Ă��A���Ȃ���{�ɂ͂قƂ�ǔ�Q���Ȃ��͂��ł���B�ނ��덡���̏������A���ꂱ��������������ʏɒǍ��܂�邾���ł���B
�Ō�ɁA�����̈ב���̕ϑJ�ɂ��ďq�ׂ�B������1��15�~�ƌ����בփ��[�g���A���������I�Ȍo�܂Ō��܂��Ă���ƌ�����Ă���l�X�������͂��ł���B����������ɂ͍������͑S���Ȃ��B���ہA1,980�N�ɂ�1���͎���151�~�ł���A1,990�N�ɂ�30�~�ł������B�܂蒆���͎��ɊȒP�i�K���j�Ɂu���v�̐M�����Ȃ��قǑ啝�Ȑ؉������s���Ă���B���������̒����o�ς������̂悤�ɑ傫���Ȃ���������N�����ڂ��Ȃ����������̘b�ł���B�����ĈȑO�̈ב����Ȃ�A�����̐l�����1,980�N��2����1����3����1�ł���A1,990�N��10����1����15����1�ƌ������ƂɂȂ�B
���̂悤�ɐ̂��璆���͋ɂ߂Ă��������i�K���j�Ɉבւ𑀍삵�Ă���B�Ƃ��낪�����m��Ȃ��o�ϊw�҂�G�R�m�~�X�g�́A�̂��璆���̐l�����20����1�A30����1�������ƌ�����Ă���̂ł���B�����͂����炭����A�W�A�����Ƃ̋����ŏ��Ă鐅����T��Ȃ���A�בւ������܂ő��삵�Ă����Ǝv����i�������ɂ����܂Ō��������Ȃ�A���{�̊�Ƃ�����A�W�A���璆���ɐ��Y���_���ڂ��悤�ɂȂ����j�B �u���������Ƃ��납��Ⴂ�Ƃ���ɗ����悤�ɃR�X�g�̒Ⴂ�����ɐ��Y���_���ړ]����͓̂��R�v �Ɣ������悤�Ȃ��Ƃ������Ă��鎯�҂ƌ�����l�X�����ɑ����B���������̒�R�X�g�́A�������{���K���Ɍ��߂Ă���ƌ������ƂɋC�Â��ׂ��ł���B���������Ė�����ł����{�����̂������w�͂����āA�����Ƃ̃R�X�g�����ɏ��悤�Ȃ��Ă��A�����ɂƂ��Ă͈בւ̐艺����������x�s���ςޘb�Ȃ̂ł���B
���̂悤�Ȃ߂��Ⴍ����̒����̈ב���ɂ���āA��Ɠ|�Y��H��̈ړ]�ɂ���Ď��Ƃ�����A�s�K�Ȗڂɂ����Ă���l�X����������B�������}�X�R�~��f�B�A�ɂ́A�s�v�c�ƒ����̈ב���̕s�������w�E���鐺���Ȃ��B�O���Ȃ̃`���C�i�[�X�N�[�����b��ƂȂ������A�ǂ������{�̃}�X�R�~���`���C�i�[�X�N�[�������Ă���悤�ł���B���T�͂��̃`���C�i�[�X�N�[��������グ��B
����́A�����̐[���ȓ��{�̃f�t���o�ςɂ�������炸�A���������̍팸�␔�X�̌��I�x�o�̍팸��i�߂���j�ł���B���悻�o�ό����ɔ����鐭��̃I���p���[�h�ł���B�������ǂ����}�X�R�~�͂������������Ƃ͌��Ȃ��Ă��Ȃ��悤�ł���i�������Ɉ��e���������܂łɂ͎��Ԃ�������A����ƌ��ʂ̈��ʊW��������ɂ����Ȃ�j�B �܂����������⑼�̎x�o���팸�����ꍇ�A�ǂ������o�ό��ʂ����҂����̂������ׂ��ł���B���������Ԏ�������A�������ቺ����Ƃ��A��������������ƌ����ڎZ������Ȃ�A���̂悤�Ȑ��������ׂ��ł���B������N�̂悤�Ȃ����Ȃ��\�Z�����肷��ƌ������݂��Ƃ��Ȃ����Ƃ͎~�߂Ă��炢�����B����������Ɍi�C������߂邱�Ƃ��~�߂�ׂ��ł���B�{�l�̊�]�ʂ�ɂ�����B���̂����A���ʂɂ��Ă͂�������ӔC���Ƃ��Ă��炤���Ƃ���ł���B ����܂ł̏���̍s�������Ă��āA�M�҂̒m�l�� �u���{�͉̎��ł���ꂻ�����v �ƌ����Ă����B���ʂ����悤�Ƃ��Ȃ��̂Ȃ�i���Ƃ������Ă��~�X�}�b�`�ŁA�������������Ă��č��̂����ɂ���j�A�ǂ̂悤�Ȑ���ł��ǂ����A�N�ł��͋܂�B�ނ��i�߂鐭��̌��ʁA���{�̌o�ςƎЉ�K�^�K�^�ɂȂ��Ă��A�����炭�ނ́u���߂�Ηǂ��̂��v�̈ꌾ�ł��낤�B�ނ���{�̎ɑI�l�X�́A�^���ɐӔC��������ׂ��ł���B �|�����ꎁ���A�v���Ԃ�ɂ܂Ƃ��̂��Ƃ������Ă����B �u���{�́A�l�����łȂ���Ƃ����~���n�߂��B�܂苐�z�̂��̒��~�͐��{���g�킴��Ȃ��B���������ꂾ�������Ȃ����̂ł��邩��A���{�͌������������炷�̂ł͂Ȃ��A���������₷�ׂ��ł���B�v �ƌ����Ă����B�܂��ɐ��_�ł���B
���������A���Ղɑ�ʂ̍������邱�Ƃ͓���B�������ɍ�����肪3���i����ł����ۓI�ɂ͈�ԒႢ�����j�ɂȂ�܂ō��s����A���\���~����100���~���x�̎����͒��B�ł���Ǝv����B����������s�����ł�70���~����80���~�̍������ɕۗL���Ă���A����肪3���i����1.26���j�ƌ������ƂɂȂ�A�����傫�ȕ]����������邱�ƂɂȂ�B�n����s����ʂ̍��Ŏ����^�p���Ă���B�a�ݗ���55���ƌ�����s������B�c���45���߂��͍��ƒn���̉^�p�ł���B�����܂Ŗ���}�ɋ����ቺ����u���Ă������{�̐ӔC�͑傫���B
���������č����A���������Ȃǂ̐ϋɓI�ȍ�������ŁA�o�ς������������A��s�̕s�Ǎ������������A����ɍ����Č�����������ɂ́A��X���咣���Ă���Z�C�j�A���b�W����A�܂萭�{�̎������s�����i����̍������܂ށj���g�����͂Ȃ��̂ł���B�Ƃ���Œ|�����̂��́u���������𑝂₷�v�ƌ����ӌ��ɑ��ă}�l�b�N�X�،��̎Ⴂ�В����A�v�킸���_���悤�Ƃ��Ă����B�����A���������̎^���҂̓e���r�ɂ͏o���Ă��炦�Ȃ��̂ł��낤�B�����A�u�����̈ב���v�Ɓu���������v�̓^�u�[�ł���B���̂悤�ȃ��f�B�A�̌��_�����ɏ��Ă�̂́A��قǂ̗L�͎҂Ɍ�����̂ł���B http://adpweb.com/eco/eco261.html
�ňȊO�̖f�Տ�� 11�^2�^21
WTO�̎�̉�
�����̌o�ς𗝘_�I�ɘ_���邱�Ƃ͓���B�܂��Ă�b�����E�ɋy�ԂƁA�������������Čo�ς���邱�Ƃ���i�ƍ���ɂȂ�B���̂悤�Ȏ��������Ă��A���ɂ͋c�_�̍��������z���A�����B�ɂƂ��ėL���Ȑ�������������������߂ɁA�Ƃ�ł��Ȃ������E�ό�����l�X���o�Ă���B
TPP�̋c�_�Ɋւ��Ă��A����������Ȉӌ����܂���ʂ��Ă���B�Ⴆ�Ύ��R�f�Ղ������A���{�ɂƂ��āi���{�����łȂ����E�̂ǂ̍��ɂƂ��Ă��j�ɂ߂čD�܂����Ǝ咣����l�X������B�ޓ���TPP�Q�������B�ꐳ�����I���Ƃ܂Ō��`����B �܂����{�̃}�X�R�~�l�ɂ́u���{�͖f�������v�Ƃ��������v�����݂�����B�ޓ��͌o�ς���������ɂ͗A�o��L�����Ƃ����Ȃ��Ƃ����v���Ă���B���������{�����x�o�ϐ������Ă�������́A��ɓ����������Ă����B�ނ���ᐬ���ɂȂ��Ă���A���{�o�ς͊O���Ɉˑ�����x�����傫���Ȃ����̂ł���B����ɂ��Ă͗��T��グ��\��ł���B
���̂悤�Ɏ��R�f�ՂŌ��Ղ������ɂȂ邱�Ƃɂ���āA�o�ς���������Ǝv���Ă���l�������B���̗��_�I�����̈�����J�[�h�́u��r�D�ʂ̌����v�ł���A�{����02�^7�^22�i��261���j�u�����̕s���Ȉב���v�ł������グ���B
���������̃��J�[�h�̗��_�͋����T�C�h�����Ōo�ς̐����𑨂��Ă���i���v�͖����Ő��Y�������̂͑S�ď�����Ƃ������O��j�B���Ղɂ���ė]�������Y�v�f�����̕��̐��Y�ɐU��������A�o�ς���������Ƃ����������ł���B�܂�f�t���o�ς̍����̓��{�ɂ͑S�����Ă͂܂�Ȃ��c�t�Ȍo�ϗ��_�ł���B ���������ȏ��ł��̃��J�[�h�́u��r�D�ʂ̌����v���w�w�Z�G�˂́A�����Ȃ鎞�ɂ����̗��_���K���ł���Ǝv������ł���B�����Ă��̎��R�f�Ղ̏�Q���A�łł�������A�܂���ŏ�ǂƌĂ�Ă���⏕����e���̋K���ƍl���Ă���B ���ł��ő�̌��Ղ̏�ǂ��łƂ����F���ł���B���������ĊœP�p��ڎw��TPP�́A���R�f�Ղ̐M��҂ɔM��Ɋ��}����Ă���B���������J�[�h�́u��r�D�ʂ̌����v��������ꂽ�̂́A18�A19���I�̖q�̓I�o�σV�X�e���̎����O��ɂ��Ă���B�܂���قǏq�ׂ邪�A�����ł͊ňȊO�̑傫�Ȗf�Ղ̏�ǂ����邱�Ƃ��펯�ɂȂ��Ă���B
�����������A���R�f�Ղ𐄐i����l�X����ɖ��ɂ����̂��A���̊łł������BGATT�i�łƖf�ՂɊւ����ʋ���FWTO�̑O�g�j��WTO�̃��C���e�[�}���łł������B�ł͒P���ł���ڂɌ����₷�����߂��A����܂ł̌��ł�����x�܂ň����������{����Ă����B�������⏕����K���Ȃǂ̂��̑��̕ی쐭��ɘb���y�ԂƊe���̗��Q������ɂԂ���A�b���i�W���Ȃ��Ȃ����B
���̂��ߊe���́A�Ë��������߂鍑�Ƃ�FTA�i���R�f�Ջ���j��EPA�i�o�ϘA�g����j�̒����ɑ���o���Ă���B����������͈��̔����삯�ł���A���E���̍��̈�Ă̖f�Վ��R����ڎw��WTO�̐��_�ɔ����Ă���BFTA��EPA������閈�ɁA�����AWTO�͎�̉����Ă���B
�M�҂́A����̐��E�̖f�Ց̐��́ATPP�Ɍ�����悤�ȃO���[�v���ɂ��ی�f�Ղƌ��Ă���B�Ƃ��낪���R�f�ՐM��҂́AWTO�̎�̉��ɂ��Ă͉����R�����g���Ȃ��Ȃ����B�����炭������A�ޓ��̓��̒����������Ă��邩��ł��낤�B
���s�A���{�̍H�ƕi�̗A���ŗ��͂قƂ�ǃ[���ɋ߂��B�܂�TPP�ɉ��������ꍇ�A���荑�̊ł���{�I�Ƀ[���ɂȂ�̂�����A�A�o��ƂɂƂ��ċɂ߂ėL���ɂȂ�B���������ėA�o��ƂɌg����Ă���l�X��TPP�Ɏ^���Ȃ̂͗����ł���B
�Ƃ���ł���܂ŋK���ɘa��X�����v�Ȃǂ̉��v�^���ł́A�c�t�ȊϔO�_�҂Ƌ��~�Ɏ����̗��v�����߂�҂����ѕt���Ă����B�M�҂͍����TPP���i�h�ɂ�����������������i���J�[�h�́u��r�D�ʂ̌����v�Ȃǂ�M����悤�ȊϔO�_�҂ƗA�o�ŗ��v�悤����ҁj�B����������͔ޓ����Ƃ�ł��Ȃ���������������ł���B �V�[�E�V�F�p�[�h�̂悤�Ȑ����s�\�ȍ� �f�Ղ̏�ǂ��ł����łȂ����Ƃ͎��m�̎����ł���BWTO�ł��m�I���L���Ƃ��������̂����ɂȂ��Ă���B�������m�I���L���͖@�������Ŕ������̂ł͂Ȃ��B���̍��̍������Ƃ������̂��W���Ă���B ��T���Ŏ�グ���������A�����A�傫�ȏ�ǂɂȂ��Ă���B�����̂悤�Ɋ������鍑�́A�����C�ɂ�����R�X�g�Ő��i�����A�o���邱�Ƃ��ł���B���������R�f�Ղ̐M��҂͂��̂悤�Ȗ�肩�瓦���Ă���B ���������x���J�Ԃ����A�M�҂́A�����A���E�f�Ղōő�̖��͈ב֑���ƍl���Ă���B�����͑傫�Ȗf�Ս����𑱂��Ȃ���A���܂��ɍw���͕�����4����1�A5����1�̈בփ��[�g���ێ����Ă���B���ہA�f�Ղ̏�ǂ̘b�Ȃ�A�ב֑���ɔ�ׂ�ΊłȂ�ĉ���ł��܂��B�������ב֑����WTO�Ŗ��ɂȂ�Ȃ����A���R�f�Վ�`�҂��G��悤�Ƃ��Ȃ��B
�{���́A�́A1�l������1�h�����������Ƃ��w�E�����B�܂�1�l������360�~������������������ł���B�����̐l�������[�g�́A�Ή~��30����1�Ɍ������Ă���̂ł���B���E�ő�̖f�Ս������̒ʉ݂��A�w���͕�����4����1�A5����1�ł����]������Ă��Ȃ��ُ�Ȏ��Ԃ��N���Ă���B
��̕���Ȃ��]�_�Ƃ� �u�����̒����l�̃A���o�C�g�͂悭�����v�A ����u���{�̎�҂̓j�[�g�ƂȂ��Ĉ����������Ă���v
�Ɣ������Ă���B�ޓ��̍l���ł́A���ꂪ���{�o�ς̒���̌����炵���B�����������l�̃A���o�C�g�Ƃ��ẮA�����̏����������Ⴂ���Ƃɉ����A�l�������w���͕����̉�����1�Ɉێ�����Ă��邱�Ƃ��傫���B
���ɓ��{�̉~���w���͕�����荂�����ڂ��Ă��邱�Ƃ��l������A�����ł̃A���o�C�g�̎����́A�����l�ɂƂ���6,000�`7,000�~���x�Ɋ�������̂ł���B������6,000�`7,000�~�Ƃ������ƂɂȂ�A���{�̎�҂��ڂ̐F��ς��ē����͂��ł���B�j�[�g����������ł��낤�B �؍����A�ߔN�A�ב֑��삪�ڗ����̈�ł���BK�[POP�^�����g�̖{���ł̒�������b��ɂȂ��Ă��邪�A������ޓ������{�ɐi�o�������Ƃɂ���ċC�t�������ƂƎv����B�M�҂́A��������Ȃ��炸�؍��̈ב֑��삪�e�����Ă���ƍl����B
�����A��Ԃ�TPP�̐��i�҂͑��̗A�o��Ƃł���B�A�o��Ƃ�CM�X�|���T�[�ƂȂ��Ă��邽�߁A���f�B�A���T��TPP�Ɏ^�����Ă���B������TPP�͂Ƃ���s��ł���B
����͐�T���ł��q�ׂ��悤�ɁATPP�������r�����ӎ��������̂ƌ����邩��ł���B���ɒ����ɐ��Y�ݔ����ڂ�����ƂɂƂ��āA���̂��Ƃ������Ɏ�ɂȂ�\��������B�������������𐢊E�̗A�o��n�ɂ��悤�Ǝv���Ă�����ƂɂƂ��āA����܂ł̒����ł̐ݔ����������ʂɂȂ�̂ł���B
TPP���i�̕�̂ł�����E�ɂ��A�����Ƃ̐e���ȊW��]�ގ҂������B�������A����A�ޓ���TPP����邩�A��������邩�̑I���ɔ�����\��������BTPP�̓��e������A�������Ɏ��i��̓I�ɂ͒�����TPP�����j�Ƃ������Ƃ͂قڕs�\�ł���B
�M�҂́A���{��TPP�Q���̐���ɂ��āA���f�ɐ��������Ă���B�����_�ƂȂǂւ̈��e�����ŏ����ɗ}������̂Ȃ�ATPP���������傤���Ȃ��Ǝv���������̍��ł���B�f�Ղ��܂߁A�����m�̕t�����́A�ŏI�I�ɂ́A�������m�̉��l�ς̑���Ƃ������ƂɂȂ�ƕM�҂͍l����B �����̉��l�ς̈Ⴂ�����͈̔͂ɂ��鍑������TPP�ɎQ������̂Ȃ�A�M�҂͓��{������ɉ������Ă��ǂ��ƍl����悤�ɂȂ��Ă���B����ɂ��Ă����{�̎���́A�̓y���Ɍ�����悤�Ƀf���J�V�[�̂Ȃ�������ł���B���{�͂܂�ŃV�[�E�V�F�p�[�h�̂悤�Ȑ����s�\�ȍ��Ɏ��͂܂�Ă���̂��BTPP�Ɋ��H�������o���̂������Ȃ���������Ȃ��B�������TPP�����̖ړI�́A���R�f�ՐM��҂̂���Ƒ傫���قȂ�B
http://adpweb.com/eco/eco651.html
���R�f���_�̖��_�`���J�[�h�̃E�\
�n���Ɗ��j����������R�f�Ղ̖��_��������
���̃y�[�W�ł́A�t�F�A�g���[�h�i�����f�Ձj�̑ɂɂ���ƍl�����Ă���A ���R�f�Ղ̖��_�ɂ��Đ����������Ǝv���܂��B
���A���R�f�Ղ͐��E���Ŏ��Ƃ�n���A���j��������N�����Ă��܂��B�ɂ��ւ�炸���R�f�Ղ𐢊E����߂Ȃ��̂́A �u��r�D�ʁv�Ƃ����o�ϊw�̍l������M���Ă��邽�߂ł��B18���I�̃C�M���X�̌o�ϊw�҃��J�[�h�ɂ���Ē��ꂽ���_�ł��B ��r�D�ʂƂ́A���̂������ȒP�Ɍ����ƁA ���ꂼ��̍��ł��ꂼ�꓾�ӂȂ��̂��������B�H�������Ȃ��Ă����̓y�n�ō̂ꂽ���̂ʼn҂��ŁA�A����������v�ƌ����l�����ł��B���̍l�������u�M���Ă���v�Ƃ������A���R�f�Ղɂ��������ׂ���l���������āA ���������l�����ɂ���āA���E�Ɍo�ς���������Ă��邩��A �݂�ȂŐM���Ă���ӂ�����Ă���ƌ����������K�����m��܂���B ���̐��E�ŁA�r�㍑�ɕn���Ȃǂ̖��������N�����Ă���傫�Ȍ����̈�ɁA ���Đ�i�����ɂ�鍒���̉ߏ萶�Y���������܂��B��i���ł́A��^�@�B���g����K�͂Ȕ_�Ƃ��s���A���Y�����グ�Ă��܂��B�@�B���A���������i�ނƂƂ��ɁA���Y�ʂ����債�A�����̎��v�ȏ�ɍ��������Y�����悤�ɂȂ�܂����B �ߏ萶�Y������Ă����ƁA�_�Y�����i���ቺ���A �_�������Ƃ��ēs�s�ɗ�������Ȃǂ��ĎЉ�s���������N�������˂܂���B�����ŁA�����̂����i���ł́A�⏕�������ėA�o������悤�ɂȂ�܂��B�⏕���ɂ͂��낢�날��܂����A�����̔_���ɏ�����ۏ��������ŁA������A�o���荑�̍������i���A ����ȉ��̉��i�Ƀ_���s���O���Ĕ���̂��ړI�ɂȂĂ��܂��B����ɂ��A��i���̔_���͋~���܂��B ���A�A�o��ɂ��_���͂���킯�ł��B��i���̕⏕���t���̈��������������ė���悤�ɂȂ��āA �A�W�A��A�t���J�̓r�㍑�ł̎�v�Y�Ƃł������_�Ƃ������s���Ȃ��Ȃ�܂����B�����̕n���������ɂł́A�����̔_���ɕ⏕�����o�����Ƃ͂ł��܂���B���ʁA�_�������͗A���_�Y���ɑR���邽�߁A���Y�����グ�悤�Ƃ��܂��B ��i���̂悤�ɋ@�B������̂ł͂���܂���B��荂�����Y������y�n��T�����ƂɂȂ�܂��B���Ȃ킿�X�т��Ă��Ĕ������A��i���̍����ɑR�ł��鉿�i�ł̐��Y���\�ɂȂ�܂��B���A�����͑����܂���B�������������̔_�Ƃ́A�y�n������D����_�Ƃł��B�R�`�T�N�Œn�͂������ė{�����Ȃ��Ȃ�A�앨�����Ȃ��Ȃ�܂��B�����čk�삪��������A�܂��ʂ̏ꏊ��T�����ƂɂȂ�܂��B�̂Ă�ꂽ�y�n�́A���łɎ���̐X�т��Ȃ��Ȃ��Ă��đ�����{������������邱�Ƃ��Ȃ��A�r��ʂĂ܂��B ���{�ł������ł����A�k��������ꂽ�c���͍r��ʂĂĂ��܂��A������͍̂���ł��B�M�тł͋C�����������߂ɓy�n�̗L�@���̕����������A �y�n���Ă����X�т��Ȃ��Ȃ�ƉJ�╗�ɂ���Ĕ����\�y������Ă��܂��܂��B�ꏊ�ɂ���ẮA���������i�ނ��ƂɂȂ�܂��B����Ȃ��Ƃ̌J��Ԃ��ŁA�r�㍑�ł͐V���ɔ��ɂł���ꏊ�͂ǂ�ǂȂ��Ȃ�܂��B �s������Ȃ������_���́A�s�s�ɏo�ăX�����ɏW�܂�܂��B���邢�́A��n��̂��Ƃŏ���l�ɂȂ邵������܂���B�ł��A�n������̂����_�Ƃ��@�B������悤�ɂȂ�A�l������Ȃ��Ȃ�܂��B���ǔ_���͎��Ƃ��āA�s�s�̃X�����ɗ��ꂱ�ނ��ƂɂȂ�܂��B �X�����ł́A��i���̐H�Ɖ��������邽�߂ɁA�n�����Ă��Ƃ肠�����Q���邱�Ƃ͂���܂���B���A���̉����̂��߂̐H���́A��i���̗]��_�Y���̂͂����ɂȂ��Ă���Ƃ������ʂ�����܂��B ��i���̕⏕���t���̔_�Y���̗A�o�́A�����_���̕ی�̂��߂ł����B���A����̓A�W�A��A�t���J�̐��Y���̒Ⴂ��ה_�������Ƃ����A�n���Ɋׂ点�錴���ƂȂ�܂����B ���Y�����Ⴂ�Ƃ����̂́A���ꂾ����������̐l�ɐE���^������Ƃ������Ƃł��������̂ɁB ��i���ōL���s���Ă��鉻�w�엿��_����ʂɎg���A�n���������ݏグ��^�@�B�ōk�삷��_�Ƃ́A ���R������D����_�Ƃł��B����Ȃ��ƂŐ��Y�����グ�Ă��������͂��܂���B�ُ�C�ۂɂł��Ȃ�����܂����n���������āA�H���̕s�����������ƂɂȂ�ł��傤�B��i���������ɉ邾���̐H�����Ȃ��Ȃ�A���E�I�ȐH���s���A�Q�삪�����N������܂��B ���ēr�㍑�ōs���Ă����_�Ƃ́A ���K�͂ł͂����Ă�����I�ɓy�n���x�܂��čs�������\�Ȕ_�Ƃł����B�Ƃ肠�����͋Q�����肷�邱�Ƃ͂Ȃ��A���������I�Ȑ����𑗂��Ă��܂����B�����ɓ����Ă����̂����̐�i���ɂ��A���n�x�z�ł��B����Ƃ�������Ɨ������Ǝv������A ���x�͐�i����������Ă�������_�Y���̂��߂ɕn���Ǝ��ƁA���j�����炳��邱�ƂɂȂ�܂����B �r�㍑�̔_�������Ƃ�����A�n���Ɋׂ����肷�錴���ɂ́A���Ă̐A���n�x�z�̉e��������܂��B�A���n�x�z�⍡�̕⏕���t���앨�̗A�o�Ƃ������A �r�㍑�̐l�����ɂƂ��Ă͉����ǂ����Ƃ̂Ȃ��o�ς̗L����́A���R�f�Ղ̍l���Ɋ�Â����̂ł��B�t�F�A�g���[�h���s���c�̂́A�����Ɓu���R�f�Ղ������f�Ձi�t�F�A�g���[�h�j���v�Ƒi���A ���������Ă��܂��B
�ł͎��R�f�Ղ̉������Ȃ̂��H���̂�����̂��Ƃ����ɂ��b���܂��B
���R�f�Ղ̖��_�`��r�D�ʂ̃E�\
���R�f�Ղ̍l������������̂́A�Q�O�O�N�قǑO�̃C�M���X�̌o�ϊw�҂ŏ��l�̃��J�[�h�ł��B���J�[�h�́A�u��r�D�ʁv�Ƃ������t���g���āA ���ە��Ƃ����邱�Ƃ����ׂĂ̍��ɂƂ��ė��v�ɂȂ�Ɛ����܂����B
�Ɠc�֒��u�G�R���W�[�_�b�̌��߁@�T���Ƃ��Ċ����A�l�Ƃ��ĕ��߁v
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%BC%E7%A5%9E%E8%A9%B1%E3%81%AE%E5%8A%9F%E7%BD%AA%E2%80%95%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E6%84%9F%E3%81%98%E3%80%81%E4%BA%BA%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E6%AD%A9%E3%82%81-%E6%A7%8C%E7%94%B0-%E6%95%A6/dp/4795238529
�Ƃ����{�ɁA���J�[�h���_�̖��_�� �킩��₷���������Ă���̂ŁA���̖{�Ŏ�����Ă���l�������g���āA ���R�f�Ղ̖��_��T���Ă��������Ǝv���܂��B
���J�[�h�́u�f�_�v�Ƃ����{�̒��ŁA�C�M���X�ƃ|���g�K���̖ѐD���ƁA ���C���̐��Y���̔�r�����܂����B���̒��ŃC�M���X�́A�ѐD���������Ő��Y����郏�C���������Y���������A �|���g�K���́A���C���̐��Y���������Ő��Y�����ѐD���������Y���������Ɛ������܂����B�܂�A�C�M���X�ł͔_�Ƃɔ�ׂčH�Ƃ̐��Y���������A �|���g�K���͍H�Ƃɔ�ׂĔ_�Ƃ����Y���������Ƃ������Ƃł��B�����ŁA���ꂼ��̍��Ő��Y���̍������i����������A �����̍��ɂƂ��ē��ɂȂ�Ǝ咣�����̂ł��B�C�M���X�͍H�ƍ��ɂȂ�A�|���g�K���͔_�ƍ��ɂȂ�A�����Ƃ��ɗ��v�邱�ƂɂȂ�B���ꂪ��r�D�ʂƂ������R�f�ՁA���ە��Ƃ̗��_�I�����ƂȂ��Ă���l�����ł��B
�ł��A�{���ɂ����ł��傤���H �����A���J�[�h����������A���̐��E�͂����ƈ�����`�ɂȂ��Ă����͂��ł��B���ꂼ��̍�����r�D�ʂȂ��́A���ӂȕ��̐��Y�ɓ������A�A�o�����Ă�����ׂ��āA ���̂����ŕK�v�ȕ���A����������B����������ׂĂ̍������v�ĖL���ɂȂ��̂Ȃ�A �Ȃ����E�ɂ͕n���ɋꂵ�ލ����ɂ�l�тƂ�����Ȃɂ��������݂���̂ł��傤���H �J�J�I�̐��Y����r�D�ʂȍ��́A�J�J�I�̐��Y�ɗ͂��W�����āA�A�o���Ėׂ��āA �K�v�ȕ��͂��ׂĖׂ��������ŗA����������B�������Ă���ΖL���ɂȂ��̂Ȃ�A�R�[�q�[�̐��Y����r�D�ʂȍ��̓R�[�q�[�̐��Y�ɓ������āA �����A�o���ĕK�v�Ȃ��̂��O�����甃�������Ƃ������Ƃł���A �Ȃ������������i�앨�̐��Y�_�Ƃ̑������A�n���ɋꂵ��ł���̂ł��傤�H
�R�[�q�[�_�Ƃ̐����ɂ��ẮA �u���̃X�^�[�o�b�N�X�ɂ��A�t�F�A�g���[�h�R�[�q�[���I�v
http://www.fair-t.info/ft-coffee/index.html
�����ǂ݂��������B
�n���ɋꂵ�ރJ�J�I�̐��Y�n�̒��ł��Ƃ�킯���������̂́A �R�[�g�W�{�A�[���Ȃǐ��A�t���J�̍����ɂł��B���̒n�ł́A�̃J�J�I�_���傽���͕n���ɋꂵ��ł���̂ł��傤���H �Ȃ��q��������z��ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��傤���H 21���I�̍��ł��z����g�������Y���s���Ă��܂��B�z����g���Ă���̂Ȃ�A�������K�v���Ȃ�����A �_����ׂ͖��Ă���͂��Ǝv�������m��܂��A�_������܂��n�����̂ł��B �Ȃ��A���_�ǂ��肤�܂������Ȃ��̂ł��傤���H
���J�[�h���_�ɂ́A���܂��������邩��ł��B
��قǂ̃C�M���X�ƃ|���g�K���̗�Ō����A�������ł̖ѐD����C���̉��i�͊W�Ȃ��Ƃ����̂��A ���̗��_�̓����ł��B�C�M���X�̖ѐD�����A�|���g�K���̖ѐD����荂���Ă����܂�Ȃ��̂ł��B
�C�M���X���l�́A�|���g�K���ɍs���Ď����̖ѐD�����|���g�K�����i�Ƀ_���s���O���Ĕ���܂��B �C�M���X���l��������悤�Ɍ����܂����A�ނ�͖ѐD���邱�ƂŁA �|���g�K���̂�������ɓ���邱�Ƃ��ł��܂��B ���̂����ň����|���g�K���̃��C�����ăC�M���X�Ŕ�����������킯�ŁA ���l�͗��v�邱�Ƃ��ł��܂��B �����悤�Ƀ|���g�K���̏��l���A�����̃��C�����C�M���X�Ŕ����������āA ���ꂾ�������̃C�M���X�̂����邱�Ƃ��ł��܂��B�����ă|���g�K���Ŕ�����葽���̖ѐD�����C�M���X�Ŕ������Ƃ��ł��܂��B ��r�D�ʂ̍l�������g���A���݂��̏��l���ׂ���Ƃ����̂��A���J�[�h�̗��_�ł��B �����Ƃ��A���l�ȂǂƂ������t�͎g�킸�A�����Ɗw��I�Ȍ��t���g���Đ������A �����̌o�ϊw�҂�����������܂������B ��r�D�ʂ̗��_�́A�o�ϊw�҂������{��w��̐��E�����ŏ���ɋc�_���Ă��Ă���Ă��邾���Ȃ�Q�͂Ȃ��̂ł����A���E�������̗��_��M���Ă��܂��A���s���Ă��܂������߂ɁA�l���܂Ȗ�肪�N���邱�ƂɂȂ�܂����B �����̐��E�ɂ̓C�M���X�ƃ|���g�K�������łȂ��A�����Ƃ�������̍����ɂ����݂��܂��B�ѐD���ƃ��C�������łȂ��A�����Ƃ�������̐��Y�������݂��A�f�Ղ��s���Ă��܂��B����ɁA���J�[�h�̗��_�ł͂��݂��̍����ׂ��邱�ƂɂȂ��Ă���̂ł����A ���ۂɖf�Ղ��s���͍̂��ł͂Ȃ��A�f�Տ��ł��B ����ł��C�M���X��|���g�K���̏��l�����āA���v���グ��A �ŋ��ƌ����`�ō��Ƃ͗��v�邱�Ƃ��ł��܂��B���A�����ɑ�O���̏��l�����������ǂ��ł��傤���H ��r�D�ʂ̃E�\�`���l�������ׂ��邵����
�����ŁA���Ƌ�̖f�Ղ��Ƃ��āA���ۖf�Ղɂ��čl���Ă݂����Ǝv���܂��B
�`���Ƃa���������āA�`���ł͋��P�L������T�L���Ɠ����l�i���Ƃ��܂��B �����Ăa���ł́A���P�L���Ƌ�100�L���������l�i���Ƃ��܂��B
�`���F���P�L���@���@��T�L��
�a���F���P�L���@���@��10�L��
�����`���̏��l��������A���P�L���������Ăa���֍s���܂��B
�����Ă��̋����ċ��10�L�������܂��B �����Ă`���ɖ߂��ċ��Q�L�����܂��B�`���Ƃa���������������邾���ŁA �莝���̋����Q�{�ɂ��邱�Ƃ��ł��܂��B �a���̏��l���A�����ŋ�10�L�����Ă`���ɍs���A���Q�L�������ƂŁA �莝���̋����Q�{�ɂ��邱�Ƃ��ł��܂��B ���Â�ɂ��Ă������Ƃ��ɗ��v�Ėׂ���悤�Ɍ����܂��B���A�����ɑ�O���A �b���������Ƙb������Ă��܂��B �b���̏��l10�L������ɓ���܂��B ���̋���`���Ɏ����čs���A�����Q�L����ɓ���܂��B �莝���̋����Q�{�ɂ��邱�Ƃ��ł���̂ł��B�������A�`���Ƃa���͂ǂ��ł��傤���H �܂��a���́A�b�����l�������Ă������P�L���ƁA��10�L�����������������Ȃ̂ŁA�����̓[���ł��B �`������10�L���Ƌ��P�L�����������������Ȃ̂ŁA���l�ɑ����[���ł��B �����Ƃ��ɉ��̗��v������܂���B �b�����l����������I�ɖׂ���̂ł��B
���ꂪ���R�f�Ղɂ���ď��l�����v����ɓ����d�g�݂ł��B���ۂɂ͊W���ł���`�a�����́A���̗��v�����Ă��Ȃ��̂ɁA�I���ȃg���b�N�ɂ���āA ���J�[�h�͗������ׂ���Ǝ咣���A���E�͂��܂��ꂽ�̂ł��B
���J�[�h�́A�����ׂ������܂��f�Տ��l�ł����B�����玩���ɓs���̗ǂ����_�����o�����̂ł��B�����̗��_�̖����͏��m�̏�ŁA��l��ׂ������Ăق�������ł������Ƃł��傤�B
�b�����l���A�����Њ�ƂƂ��܂��B�`�A�a���̓A�����J�Ɠ��{�B
�b�����l�́A���{�Ŕ�r�D�ʂ̎����Ԃ��t���ăA�����J�Ɏ����Ă����܂��B
�����Ď����Ԃ������ŃA�����J�̔�r�D�ʂ̈����Ă��ʂɔ����t���ē��{�Ŕ�������D�D�D�B
�����l����Ǝ��Ƃ�n���ɋꂵ�ސl���o�邱�ƂȂǁA��r�D�ʂ̗��_�ŗl���܂Ȗ����A ��肪�������邱�Ƃ��ǂ��킩��Ǝv���܂��B ���ɂ��ЁA���Ȃ��ɒm���Ă������������̂́A��\�I�ȏ��i�앨�ł���A�J�J�I�ɂ��Ăł��B ���������`���R���[�g�̌����ɂȂ�J�J�I�ł����A���̐��Y�ɁA �u�z��v���g���Ă��邱�Ƃ�m���Ă��܂������H �z��Ƃ����Ă�10��O�����炢�̏��N�̓z��ł��B���E�ő�̃J�J�I�Y�n�A ���A�t���J�̃R�[�g�W�{�A�[���̓z����g�����J�J�I�����Y�ɂ��āA ���ꂩ�玩�R�f�Ղ������炵���P��͔|�����_�ɂ��Ă��������������B �J�J�I�_���̏��N�z����@
http://www.fair-t.info/ft-cocoa/index.html http://www.fair-t.info/economy-society/freetrade-ricardo.html
�s�o�o�⎩�R�f�Ղ͖����Ƀ��J�[�h�̔�r�D�ʘ_�������ɂ��Ă���A�����Ĕ�r�D�ʘ_�͈ȉ��̎O�����藧���Ȃ��ƍI�������Ȃ����߂ł��B
���Z�C�̖@���F���������v���Y�ݏo���i�t����Ȃ��ł��j
�����S�ٗp
�����{�ړ��̎��R���Ȃ�
�@�Ō�̎��{�ړ��̕����ł����A�H��Ȃǂ̎��{�ړ������R���݂ɂȂ��Ă��܂��ƁA���J�[�h�̔�r�D�ʘ_���������������̂ł͂Ȃ��Ƃ����b�ł��B���ہA�A�����J�͓��ƂȂǂ̐����Ƃ̖ҍU���������i'70�`'80�j�ɁA�{���ł���u�Z�p�J�������v�ɂ����������ނׂ��������̂ł����A���{���O���Ɉڂ��Ƃ�������I�сA�����Ƃ̈ꕔ���u�Y�Ƃ��Ɓv�����Ă��܂��܂����B
�@�c���������Ɓi�����ԁ[���[�J�[�Ȃ�)���A��͂�Z�p�J���������y�����A������e���̐��x�V�X�e����ς��邱�ƂŐ����c���}��܂��B���Ȃ킿�A�s��ɂ��킹�����i�J��������̂ł͂Ȃ��A�s��������ɍ��킹�悤�Ƃ����̂ł��B �@���x�V�X�e����ύX����̂͐��{�ɂ����ł��܂���̂ŁA�A�����J�̎����ԃ��[�J�[�Ȃǂ̓��r�C�X�g�⌣����ʂ��Đ��{�ɉe���͂����n�߂܂��B�������A�A�����J�̎����ԃ��[�J�[�͎����̃V�X�e���Ȃ�Ƃ������A�O���i���{�Ȃǁj�̐��x�V�X�e�����ڂ̓G�ɂ��A�u��ŏ�ǂ��I�v�Ƌ��сA�����͂��g���A�u�s��������ɍ��킹�悤�Ɓv�����킯�ł��B���ʁA���݂̂s�o�o�Ɍq������č\�����c���n�܂�܂����B �@���E�o�ς͂��܁A��L���J�[�h�̔�r�D�ʘ_�̑O��������O�Ƃ��������Ă��܂���B����ȏłs�o�o�𐄐i������A���{�͕������܂��܂��������A���Ɨ����㏸���邱�ƂɂȂ�܂��B���낵�����ƂɁA�A�����J�̕��������Ȃ�\��������܂��B �@�؉��h���搶�́A�f�t���ɓ˂�����ł��鍑���m�̎��R�f�Ջ���́u���X�|���X�v�ɂȂ�ƌx�����Ă�������Ⴂ�܂��B���{�ƃA�����J���s�o�o�Łu���X�|���X�v�ɂȂ������ɂ́A��k�����Ő��E�͑勰�Q�ڊ|���Ă܂�������Ƃ������ƂɂȂ肩�˂��A����Ȗ����͐S����肢�������Ǝv���킯�ł��B 22 ���^�ɛƂ߂�����K���̑��ʓI�l�@ ����r�D�ʘ_�͈ȉ��̎O�����藧���Ȃ��ƍI�������Ȃ� �@���J�[�h���f���Ɍ��炸�A�����鎩�R�f�Վ^���_�ɂ́A �u�����̋��߂�i���̍��E�T�[�r�X�荑������v �Ƃ����O��������g�ݍ��܂�Ă��܂��B���{�l�Ȃ�u�����A�����A������Ƒ҂��Ă�v�ƁA���̑O������������Ɍ������ꂵ�Ă��邩�����ɋC�Â��ł���B �͂����茾���āA�u���f���v���Ė��t����̂��n���炵���u���J�����n�E�X�v�Ȃ�ł��A����Ȃ��́B
�@���������o�ϊw�́A�u�i���v�Ȃ�Ď�舵���܂���B
�Ⴆ�APS3��Xbox�́u�i���v���|�C���g�v�Z�ł���u�q�ϓI�v��Ȃ�đ��݂��Ȃ��B�ߑ�ȍ~�̌o�ϊw�́A������������q�ϓI�v�f��r�����A�s�ꔄ�����i����b�ɐ����邱�Ƃɂ���Đ��w�����݂Ɏ�荞�݁A�Ȋw�̑����i�����܂ő����ł���j��g�ɓZ�����Ƃ��ł�����ł��B �@�����ɋC�Â��ĂȂ��w�ҘA�����ق�Ƃ��ɑ�����ł��B�o�ϊw�ɂ��������o���邱�ƂƏo���Ȃ����ƁA����������l�������Ƃ��Ȃ��B�o�ώY�ƏȂ́u�M�ҁv��������炭�����Ȃ�ł��傤�B�A�����̂���Ă�w����O�����Âɒ��߂����Ƃ��Ȃ��B���������Ђ�����u�o�����v�����B�����Ӗ��Łu�V�v�o�����Ȃ��A�Ⴆ�u�����Ԃ̔r�C���̕����I���l�v�Ȃ�Ă��̂����������Ƃ��Ȃ��B�����A�u�i���v�ȂC�ɂȂ�܂����B�w���͂����Ă��A�����l�E�����l����Ȃ���ł��B
http://ameblo.jp/takaakimitsuhashi/entry-11049519345.html �O���[�o���X�g��M�����
Again�̒��o�c��c�Ŕ������{�ɏW�܂�A���삭��A�Z�����A�ΐ삭��Ɠ��{�̍s�����ɂ��Ęb���������B
EU�̐�s���A���{�̃f�t�H���g�̉\������A�s�o�o���u�������A�����J�Y�Ƃ̍Ō�̒�R�v�Ƃ����b�ɂȂ�B ���������A�����J�͎��R�f�Ղɂ���ē��{�ɉ���A�o���āA�ǂ����������b�g�����Ȃ̂��H ���̒��S�I�Ș_�_�ɂ��āA���f�B�A�͎��͂قƂ�nj��y���Ă��Ȃ��B
�u�s�o�o�ɎQ�����Ȃ��ƁA�w���E�̌ǎ��x�ɂȂ�v�Ƃ��u�o�X�ɏ��x���ȁv
�Ƃ����悤�ȁA�u���ȗ��v�i�Ƃ������́u���ȗ��v�̑r���j�v�Ƀt�H�[�J�X�������t����ь��������ŁA �u�Ȃ��A�����J������قNj��d�ɓ��{�̂s�o�o�Q����v������̂��H�v �Ƃ����A�A�����J�̍s���̓��ݓI�ȃ��W�b�N���Âɉ�͂����L�������f�B�A�Ō���@��͂قƂ�ǂȂ��B �܂����A�A�����J�������̍��v�͂��Ă������{�̍��v����邽�߂Ɋ��S�Ȏs��J������{�ɋ��߂Ă���̂��Ǝv���Ă��鍑���͂��Ȃ��Ǝv�����A���f�B�A�̎А��������A�_���ψ������͂��̐����Ȃ���O�炵���B �s�o�o�Q���͓��{�̍��v�̂��߂��A�Ɛ��i�h�̐l�X�͌����B�����A����ł̓A�����J�����{�Ɏs��J�������ߗ��R������������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B�A�����J�������Ɏs��J�������߂�̂́A�����̍��v������ɂ���đ��傷��Ƃ������ʂ���������ł���B�����āA�f�Ղɂ����āA�ꍑ���A�o�ɂ���đ傫�Ȗf�Ս�����ꍇ�A���̑��荑�͗A�����߂ƂȂ��Ėf�ՐԎ��������邱�ƂɂȂ��Ă���B�ӂ��͂����ł���B �f�Ղł́i�O���[�o���X�g�̍D���ȁjWin-Win �͂Ȃ��B�Ј���������Ȃ�A�Ј���͐Ԏ��ɂȂ�B �A�����J�͎����̖f�Վ��x�������ɂȂ邱�Ƃ��߂����đ����Ɏs��J�������߂Ă���B����́u���肽�����́v�����邩��ŁA�u�����������́v�����邩��ł͂Ȃ��B�A�����J�������̖f�Ս�����B������A���荑�͖f�ՐԎ���������ނ��ƂɂȂ�B ������A�u�A�����J�̋��߂ɉ����āA���{���s��J�����邱�Ƃ́A���{�̍��v�傷�邱�ƂɂȂ�v�Ƃ��������L�Ӗ��Ȃ��̂ɂ��邽�߂ɂ́A �u�A�����J�̍��v���ő���ɔz�����邱�Ƃ��A���ʓI�ɂ́A���{�̍��v���ő剻���邱�ƂɂȂ�v �Ƃ�������������ɔ}���Ƃ��Ă͂ߍ��ނ����Ȃ��B�����A�u�A�����J�̍��v���ő���ɔz�����邱�Ƃ��A���ʓI�ɂ́A���{�̍��v���ő剻���邱�ƂɂȂ�v�Ƃ�������͔ĒʓI�ɐ^�ł���킯�ł͂Ȃ��B �����v���Ă���l�͏��Ȃ��炸���邪�A����͂����܂Ōl�I�ȁu�M�O�v�ł����āA��ʓI�^���ł͂Ȃ��B������͂��̂悤�ȁu���������Ή������ׂ���v���̐��_�ɂ܂�ō������Ȃ��ƌ����Ă���킯�ł͂Ȃ��B�o���I�Ɂu�����������Ɓv���J��Ԃ����������炱���A�ނ�(�������o�m�n�����ƂƂ����E�l�Ƃ������Ƃ����f�B�A�m���l�̂�������)�͂��̂悤�Ȑ��_�ɂȂ���ł���̂ł���B ���ƂČo�����̗L������ے肷����̂ł͂Ȃ��B�ł��A���̏ꍇ�ɂ́A�u���̐����I�I���͌����I�ɂ͍��������Ȃ����A�o���I�ɂ͂��ƍ�����������܂ł͂������̂ŁA���ꂩ����Ó����邩���E�E�E�v�Ƃ������炢�́A�ߓx����������̗p���ׂ����Ǝv���B�u�o�X�ɉ]�X�v�̂悤�ȁA�l����I�ɕs���ɂ��Ă����āA���̋����Ղ��ăK�Z�l�^�����܂��邠���ǂ��Z�[���X�}���̂悤�Ȉ���̌����͍̂�ׂ��ł͂Ȃ��Ǝ��͎v���B ������ė~�����Ȃ��̂����A���͎s��J���⎩�R�f�ՂɁu�����I�Ɂv�����Ă���̂ł͂Ȃ��B���̓_�ɂ��ẮA���Ђ������������B�����A�s��J���⎩�R�f�Ղ́u��`�v�Ƃ��č̗p���ׂ����̂ł͂Ȃ��A�����o�ςɎ�����͈͂Łu�z�v���ׂ����̂��Ƃ����������̗���ɗ^����̂ł���B�f�Ր���̓����ɂ��ẮA�u����ł����̂��v�ƕ�I�ɒf�肵���肵�Ȃ��ŁA�ʓI�ɋᖡ�������������Ɛ\���グ�Ă��邾���ł���B �Ƃ肠�������������m���Ă���̂́u�A�����J�͕K�����v�Ƃ������Ƃł���B�����łs�o�o�ɓ��{���������ނ��Ƃ��ł��邩�ǂ������u�A�����J�o�ς̐������v�ł��邩�̂悤�Ȕߑs�Ȋo��ŃA�����J�͓��{�ɔ����Ă���B�ʂɁA���{�̍��^���Ă��ĔߜƂɂȂ��Ă���킯�ł͂Ȃ��B�A�����J�̍s�������Ă��ĔߜƂɂȂ��Ă���̂ł���B �A�����J�̖f�Ղɂ��čl����ꍇ�ɁA���������܂��O��Ƃ��ė������ׂ����Ƃ́A�u�A�����J�ɂ́A���{�ɔ���H�Ɛ��i���Ȃ��v�Ƃ������Ƃł���B�A�����J�̐����Ƃ͉�ł��Ă��܂�������ł���B�u���̂���v�Ƃ����_�ɂ��Č����A�����A�����J�ɂ͐��E�̂ǂ�ȍ��ɑ��Ă����ۋ����͂̂���u���́v��A�o����͂��Ȃ��B�����Ԃ��Ɠd���ߗ��i���A�Ȃɂ��Ȃ��B
�ꉞ����Ă͂��邯��ǁA�N�I���e�B�ɂ��Ă̐M�������Ⴍ�A�����Ȃ̂ŁA�����肪���Ȃ��̂ł���B�u���́v�ł܂����ۋ����͂�����̂́A�_�Y�������ł���B �c��́u�m�E�n�E�v�A�܂�u���̂Ȃ��݁v�ł���BGoogle��Apple�̂悤�ȏ��Y�ƂƎi�@�A��ÁA����Ƃ��������x���{���u���ɂ���m�E�n�E�v�����͂܂��u���蕨�v�ɂȂ�B�ł��A�����Ɍ����ƁAGoogle��Apple���A�u�Ȃ��Ă�����Ȃ��v���̂ł���B����ƕ֗��Ȃ̂Ŏ������p���Ă��邪�A�ق�Ƃ��ɕK�v�Ȃ̂��A�Ɖ��߂čl����Ƃ킩��Ȃ��Ȃ�B �u��������ĉ���h�ɂ܂�iPhone��iPad���������ނ��ƂŁA�L�~�����̐l���͖L���ɂȂ��Ă���ƌ�����̂��ˁB����Ȃ��̂����邹���ŁA�L�~�����͂܂��܂��Z�����Ȃ�A�܂��܂��s�K�ɂȂ��Ă���悤�ɂ����A�I���ɂ͌����Ȃ��̂����v �ƌZ�����Ɍ����āA�������삭����Ԃ����t���������̂ł���B�������ɁA���̂Ƃ���ŁA���̂悤�ȍ��x�Ƀ��t�@�C�����ꂽ���������������������̂��A�Ȃ��Ă������̂��A�l����Ƃ悭�킩��Ȃ��B���N���ăp�\�R�����N�����āA���[����ǂ�ŕԎ��������Ă��邤���ɁA�ӂƋC�Â��Ƃ��������n�߂Ă������ƂɋC�Â��Ĝ��R�Ƃ���Ƃ��A �u���������I���͉������Ă���̂��v �ƍl������ł��܂��B�����@�B���g���Ă���̂��A����Ƃ��@�B�������g���Ă���̂��B�w���_���^�C���X�x�I�s�𗝊��ɑ�������B �Z�����̘b�ł́A�ŋ߂̃T�����[�}�������̓I�t�B�X�Œ�����ӂ܂Ńv���[���p�̎������p���[�|�C���g�ƃG�N�Z���ō���Ă��邻���ł���B �u�d���̎��Ԃ̔������v���[���̎������Ɏg���Ă���̂��w�����Ă���x�ƌ����Ă悢�̂��낤���H�v �ƌZ�����͖₤�B�����́u���P�v�ɂ���āA�������̘J���͌y���������͂ނ��닭�����ꂽ�B����͎����Ƃ��Ď����ł���B�Ƃɂ��Ȃ���d�����ł���悤�ɂȂ��������ŁA�������͊O�œ����Ă���Ƃ����Ƃɂ���Ƃ��������悤�ɂȂ�A��������đ��傷���Ƃ����Ȃ����߂ɂ܂��܂����x���E�����������[�������߂�悤�ɂȂ�A���̍��x�������[���̂����Ŏ������̂��Ȃ�������Ȃ��d���͂܂��܂����債�E�E�E �G���h���X�ł���B�A�����J�͂��̃G���h���X�̏���T�C�N���Ɏ������u�K�W�F�b�g��D���l�ԁv���������ނ��Ƃɂ���āA����Ȏs���n�݂��邱�Ƃɐ��������B�����A�����J���u���邱�Ƃ̂ł�����́v�́A���ꂭ�炢�����Ȃ��B ������A�A�����J�̑�w�ƌ����J���@�ւ͐��E������u�e�N�j�J���ȃC�m�x�[�V�������ł������ȍ˔\�v��K���ŋ��ł����W�߂悤�Ƃ��Ă���B�A�����J�̐�[�����̑�w�@�ɐ�߂钆���l�A�C���h�l�A�؍��l�̔䗦�͑��������Ă��邪�A����͔ނ�ɃA�����J�Ŕ����������āA������Ɍ̍��Ɏ����A�点���A�A�����J�̃h���X�e�B�b�N�ȃr�W�l�X�ɂ��邽�߂ł���B���܂ő������킩��Ȃ����A���炭�͂���ő��p���ł���͂��ł���B �u�A�����J�̑�w�͊O���l�ɊJ���I�őf���炵���v �Ƃق߂�������l���悭���邪�A����͂��܂�Ƀi�C�[�u�Ȕ����ƌ���˂Ȃ�ʁB��������Đ����c��������ĕK���Ȃ̂ł���B�O���l�����āA���x�傳���Ă����\��������Ȃ�A���z�̈���炢�U��܂��͓̂�����O�ł���B���ꂪ�u����������ɂ�����@�v�ł���B �A�����J�̊w�Z����ɂ́u�q�������̎s���I���n�𑣂��v�Ƃ������z�͂����قƂ�ǂȂ��B �w�Z�̓r�W�l�X�`�����X�ݏo���\���̂���˔\���Z���N�g����@��ł���A�s���I���n�̂��߂̂��̂ł͂Ȃ��B �A�����J�ł́A���t�����l�Y�Ƃ����������c��A���Y�����Ⴂ����ɑ傫�Ȍٗp��n�o���Ă����Y�ƃZ�N�^�[�͊C�O�Ɉړ]���邩�A���ł����B������A�u�˔\�̂����ҁv�ȊO�ɂ͌ٗp�̃`�����X�������Ă���i���Ɨ���2010�N���X�E�U�������A��\��̎�҂Ɍ�����̔{���炢�ɂȂ邾�낤�j�B�E�H�[���X�Ńf�������Ă����҂����́u�܂��ٗp�v�����߂Ă���B����܂ŃA�����J���{�͔ނ�Ɂu�䖝����v�ƌ����Ă����B �܂��A���ۋ����͂̂��镪��Ɏ����Ɛl�ނ��W���I�ɓ�������B���ꂪ��������A�A�����J�o�ς͊���������B�����������B�ٗp��������B�n�R�l�ɂ��u�]��ɗ�����v�`�����X���K���B������A�������u���Ă����Ȃ��v�ɏW������A�ƁB �u�I���ƏW���v�ł���B �ł��A�����30�N�قǂ���Ă킩�������Ƃ́A
�u�I������āA�������W������āA���������N�v�́A��������Ď�ɓ��ꂽ����n�R�ȓ��E�ɊҌ����āA�ނ�̐������x�������コ���邽�߂ɂ͌��ǎg��Ȃ������A�Ƃ������Ƃł���B
������͎��Ɨp�W�F�b�g�@��������A�P�C�}�������̋�s�ɗa��������A�J���u�C�̓�������A�t�F���[���ɏ������A�h���y����������A�A���}�[�j������i���Ƃ����Â��Ă��݂܂���E�E�E�j���Ďg���Ă��܂����̂ł���B
�I��-�W��-����-�x�̓Ɛ�Ƃ����X�p�C�����̒��ŁA
�u�I������R��A�W������r�����ꂽ�A���̑��吨�̊F����v ����ΓI�ȕn�����ɂ��炳��A���E�H�[���X��苒���Ă���B�ނ�̉^���� �u�����I�Ȏ咣���Ȃ�����A�����I�ɂ͖��͂��낤�v �Ɨ₽�������̂Ă�l�X�����Ăɑ������A����͊ԈႢ���Ǝv���B�ނ炪���{�ɉ���v�����Ă������킩��Ȃ��̂́A
�u���S�ٗp�͌o�ϐ����ɗD�悷��v
�Ƃ���(���{�̍��x�����𗝘_�Â���)�������̂悤�ȁu�펯�����l�v���A�����J�ł͐��{�����ɂ��A�c��ɂ��A���f�B�A�ɂ����Ȃ�����ł���B�E�H�[���X��苒���Ă����҂������g
�u�����ȂA���Ȃ��Ă������B�����荑���S�����т�H����悤�ɂ��邱�Ƃ������o�ς̗D��ۑ�ł���v �Ƃ����咣���Ȃ����邾���̗��_�������ʂ����Ă��Ȃ��̂ł���B �u���Y���̒Ⴂ�Y�ƕ���͓�������ē��R���i���Y���̒Ⴂ�l�Ԃ͓�������ē��R���j�v �Ƃ����O���[�o���X�g�̃��W�b�N�͕n���w�̒��ɂ����[�����t���Ă���B������A�ނ�͂��̊i���̔������u�����������̋��~(greed)�v�Ƃ������l�I�ȗ��R�Ő������邱�Ƃɖ������Ă���B�u���l�I�ȗ��R�Ő������邱�Ƃɖ������Ă���v�Ƃ����̂́A������Љ�\���̖��Ƃ��Ă͘_���Ȃ��Ƃ������Ƃł���B�u���~�ł���v�Ƃ����̂́u�\�͂ɔ䂵�ĕs���ɑ����̕x�Ă���v�Ƃ����Ӗ��ł���B ���͌l�̗ϗ����̃��x���ɂ���A���Ɛ��x�̃��x���ɂ͂Ȃ��B�u�A�����J�͂���ł����v�̂ł���B�����A�ꕔ�Ɂu�������m�v�����āA�����ɊҌ������ׂ��x��Ɛ肵�Ă���̂ŁA����́u�ϗ��I�ɐ������Ȃ��v�ƌ����Ă���̂ł���B ���̂悤�Ȉꕔ�̕x�҂����𗘂���o�σV�X�e���́u�A�����J�̌������O����̗ϗ��I�Ȉ�E�v�ł����āA�\���I�Ȗ��ł͂Ȃ��B������A�����̕��������v���`�����u����ׂ��A�����J�̎p�v�ɗ����߂�Ζ��͉�������B �ނ�̑����͂܂������v���Ă���B �A�����J�̂��������͂���������Ɓu�����̗��O�̃R�������[�v�ł͂Ȃ��̂��E�E�E �Ƃ��������������悤�ȕs���͂܂��A�����J�l�̂����ɍL�܂��Ă��Ȃ��B���ꂪ�ő�̊�@�ł���悤�Ɏ��ɂ͎v����B
�b�𑱂���B���Ƌ���̑��A���ƁA�A�����J�������ɂ��悤�Ƃ��Ă���͎̂i�@�ƈ�Âł���B����ɂ��ẮA���Ƃ��I�m�Ɋ댯�����w�E���Ă��邩��A���̕�����͓��ɕt�������邱�Ƃ͂Ȃ��B��Âɂ��ẮA�O�ɂ��Љ���x�����搶�́w�u���v�v�̂��߂̈�Ìo�ϊw�x������ǂ����������낵�����Ǝv���B
�����āA�A�����J�̍ő�̔��蕨�͔_�Y���ł���B
�����ׂ����ƂɁA�A�����J���u�������̂�����́v�Ƃ��Ĕ����̂͂��͂�_�Y�������Ȃ̂ł���i���ƕ��킪���邪�A���̘b�͑�l�^�Ȃ̂ŁA�܂����x�j�B �_�Y���͂���́u���̋������~�܂�ƁA�H���Ȃ��Ȃ�v���̂ł���BGoogle�̃T�[�r�X����~������AApple�̃K�W�F�b�g�̗A�����~�܂�Ɣ߂��ސl�͑������낤���i�����߂����j�A�u����Ŏ��ʁv�Ƃ����l�͂��Ȃ�(�Ǝv���j�B���{����A�����J�ٌ̕�m�����Ȃ��Ȃ��Ă��A�A�����J�I��ÃV�X�e�����g���Ȃ��Ȃ��Ă��A�N������Ȃ��B�ł��A�s�o�o�œ��{�̔_�Ƃ���ł������ƂɁA�A�����J�Y�̕Ă⏬�����`�q�g�݊����앨�̗A�����~�܂�����A���{�l�͂����Ȃ�Q����B���ۉ��i���オ������A�ǂ�قǖ@�O�Ȓl�ł��A����������Ȃ��B�����āA�������{�����s���s�Ɋׂ����肵���ꍇ�ɂ́A�����u�������v���Ȃ��Ȃ�B �m�`�e�s�`(North America Free Trade Agreement)������A���L�V�R�ɃA�����J�Y�́u�����g�E�����R�V�v���������āA���L�V�R�̃g�E�����R�V�_�Ƃ͉�ł����B���̂��ƁA�o�C�I�}�X�R���̌��ޗ��ƂȂ��ăg�E�����R�V�̍��ۉ��i�������������߁A���L�V�R�l�͎�H���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B��I�ȐH�����u�O�����甃���čς܂���v�Ƃ����̂̓��X�N�̍����I���ł���B �A�����J�̔_�Y�������R�f�Ղœ����Ă���A���{�̔_�Ƃ͉�ł���B �u���Y�����グ��w�͂����Ă��Ȃ���������A���R�̕��v �Ƃ����Ԃ��G�R�m�~�X�g�́A�����C�ەϓ��ŃJ���t�H���j�A�Ă�����ɂȂ��āA�����o���Ă��H�����A���ł��Ȃ��Ƃ����ɂȂ����Ƃ��ɂ͂ǂ��������Ȃ̂ł��낤�B�������W�b�N�� �u�����������X�N���w�b�W����w�͂����Ă��Ȃ������̂�����A���R�̕��v �ƌ�������ł��낤���B�����ƁA�����������낤�B��������Ȃ���A�b�̋ؖڂ��ʂ�Ȃ��B
�ł��A�����������Ƃ������l�Ԃ͂����������{���H����@�ɂȂ����Ƃ��ɂ́A�������ƃJ�i�_�Ƃ��I�[�X�g�����A�Ƃ��ɓ����o���āA�s�U��p�X�^�Ȃ����Ղ�H���Ă�̂ł���B
�s�o�o�ɂ��Ď����\���グ�������Ƃ͂��ƊȒP�ł���B
�u���Y���̒Ⴂ�Y�ƃZ�N�^�[�͓�������ē��R�v�Ƃ�
�u�I���ƏW���v�Ƃ� �u���ۋ����͂̂��镪�삪�������v�Ƃ� �u���ʓI�Ɍٗp���n�o����v�Ƃ� �u������������_���Ȃv
�Ƃ������Ă���l�Ԃ͐M�p���Ȃ����������A�Ƃ������Ƃł���B�����������Ƃ�������炪�A���{�o�ς�����Ƃ��ɂ͂܂������ɓ����o������ł���B�ނ�͎����̂��Ƃ��u���ۋ����ɏ���������v�u���Y���̍����l�ԁv���Ǝv���Ă���̂ŁA
�u��������A�I���ɋ��ƌ��͂Ə����W�߂�B�I���������c���āA���O��̌ٗp�����Ƃ����Ă�邩��v �ƌ����Ă���킯�ł���B�����p�S�������������B���������荇���͐������Ă��A��ɂ������݂�N�ɂ����z���Ȃ����A���s������A��n����S���u���{����o���Ȃ��l�X�v�ɉ������āA�������ƊO���ɓ����o���Ɍ��܂��Ă��邩��ł��� �u������w�������̓_�����x���đO���猾���Ă�����B�I���Ȃ��C�L�L�ƃo���ɕʑ����邵�A�n�m�C�ƃW���J���^�ɍH������Ă�����A���������Ƃ��ɋ����킯��B�o�J����A���O��B���{�Ȃɂ����݂��₪���Ă�v�B �����������Ƃ������ꌾ�������Ȃ�i����킩��Ǝv�����ǂˁj�͐M�p���Ȃ������ǂ��ł��B������̐S�����߂����ł���B http://blog.tatsuru.com/2011/10/25_1624.php �r�c�M�vVS���c��
TPP �� ��TPP�A�r�c�M�v�Z���Z�C���k�ق�M��2011.11.04 Friday
�S�̘̂_�|�����āA�������������グ�Ĕᔻ���āA����ɁA����������Ƃ��đS���̓��e��ے肷��B���������r�c�M�v�̗l�Ȕᔻ�̂������A���͈�Ԍ����ł���B �ڋ������炾�B
���c�������ATPP�ɔ�����w�O���[�o���X�g��M����ȁx�Ƃ����L�����u���O�ɏ������B���̔ᔻ��r�c�����u���O�ɏ������B�������A���̒r�c�M�v�ƌ����l���́A�_���I�������Ƃ������Ƃ�m��Ȃ��̂��낤���H
����l�����������A���镶�͂ƁA����Ƃ͈Ⴄ�ʂ̂Ƃ���ɏ��������͂Ƃ̘_���I�������������Ƃ������Ƃ͂悭����܂��B����́A���Ώۂ̐l�����Ⴄ�ȏ�A������x�d���������̂ł����A���̒r�c�M�v�Ƃ����l���́A�Z����̕��͂̒��ł��A�_�����j�]���Ă��܂��B �_���Ƃ������A�����Ă邱�Ƃ��^�t�������肵�ċ����܂��B�Ⴆ����B �� �w�O���[�o�����̍ő�̎�v�҂͌����Ȃ��x
http://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51751717.html �Ƃ������͂̍ŏ��̕��ł́A
>������700�~�ŃW�[���Y�������Ƃ��A���{��7000�~�ł���Ӗ��͂Ȃ��B
>�����ɔ�r�D�ʂ�������̂͗A������A���Ȃ��̎���������10�{�ɂȂ�̂��B
�Ə����A��̕��ł́A
>���_�I�ɂ́A���E���œ���J���̒���������ɂȂ�܂Ői�ށB
>�J���ړ����Ȃ��Ă��A������J���̐��i��A�����邱�Ƃɂ���ĘJ����A������̂Ɠ������ʂ����邩�炾�B �� �O���[�o�����ŁA���Ȃ��̒�����10�{�ɂȂ�ƌ����Ă����Ȃ���A�������͂̒��ŁA��i�����{�ɏZ�ނ��Ȃ��̒����́A���W�r�㍑���ɂȂ�ƌ����B�i���W�r�㍑���ɂȂ�A�ł͂Ȃ��A���ω�����āA���W�r�㍑�ƕς��Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ƃł��ˁB�ǂ����ɂ���A�O���[�o�����ŁA�L���̑O���ł͒�����������ƌ����A�㔼�Œ���������ƌ����Ă��܂��B�j (�r�c�M�v��) ���͑��v���H �Ƃ������ƂŁA�r�c�M�v���́w���c�������m��Ȃ���r�D�ʁx�Ƃ������͂ł����A�܂��A���͂̈�Ԃ̗v�_�����Ĕᔻ���Ă���B�����̌o�ϊw�I�ϓ_�ł̊ԈႢ���w�E���Ă���i���ǓI�O��j�����ŁA�̐S�v�̓��c���̌��_�A��Ԃ̃L�������Ă���B ���c���́A�A�����J�����X�ɓ��{��TPP�Q���𔗂��Ă���Ƃ������A�A�����J�̐��_�A�}�X�R�~��TPP�ɊS�������ƒr�c���͎w�E����B �A�����J���A���{��TPP�Q���𔗂��Ă��Ȃ��Ƃ����Ȃ�A�N�������Ă���̂��H�`�����u���l�C���V���K�|�[�����H �i�r�c�M�v�́j�A�z���B ���c���������ŃA�����J�ƌ����Ă���̂́A�A�����J�̐��_��}�X�R�~����Ȃ����Ƃ��炢������͂��ł��B �A�����J�̋��Z�A�Y�Ǝ��{�A���E�A�����Њ�ƁA���̎��ł���A�����J�̐����ƁA�������ATPP�����ɗ^���҂ł��傤�B���{��TPP�����𔗂�̂ɁA�A�����J�̐��_��}�X�R�~�����K�v���ǂ��ɂ���H
�t�ɃA�����J�̃}�X�R�~�␢�_�����{��TPP�Q��������������A�t���ʂł��傤�B���������S���{�ł��B
>�e���Ő��Y��قȂ�Ƃ��́A���ΓI�ɃR�X�g�̈������ɓ������ėA�o���邱�Ƃɂ���Đ��E�S�̂̐��Y�ʂ������A�o���̍������v��Win-Win����������̂��B
�Ƃ����̂���r�D�ʂ̌����ł���A���c���͂��̔�r�D�ʂ̌�����m��Ȃ��ƒr�c���͔ᔻ����B
�������A�w�O���[�o���X�g��M����ȁx��ǂ�ł݂�ƁA���̂��Ƃɂ��ẮA���c���ǂ��������Ă���悤�ɓǂ߂�B >�����A�u�A�����J�̍��v���ő���ɔz�����邱�Ƃ��A���ʓI�ɂ́A���{�̍��v���ő剻���邱�ƂɂȂ�v�Ƃ�������͔ĒʓI�ɐ^�ł���킯�ł͂Ȃ��B �i�����j >�o���I�Ɂu�����������Ɓv���J��Ԃ����������炱���A�ނ�(�������o�m�n�����ƂƂ����E�l�Ƃ������Ƃ����f�B�A�m���l�̂�������)�͂��̂悤�Ȑ��_�ɂȂ���ł���̂ł���B >���ƂČo�����̗L������ے肷����̂ł͂Ȃ��B �Ƃ����悤�ɁA���c���́A���Ă̊W�ɂ����āAWin-Win�̊W�͐����������Ƃ��������ł��낤�Əq�ׂĂ��āA��r�D�ʂ̌�����m��Ȃ��Ƃ����ᔻ�͓I�O��ł���B�Ƃ������A�ڋ��ł��蕠���������B �S�̘̂_�|�����āA�������������グ�Ĕᔻ���āA����ɁA����������Ƃ��đS���̓��e��ے肷��B���������ᔻ�̂������A���͈�Ԍ����ł���B�ڋ������炾�B
���āA���̒r�c����������r�D�ʂ̌����ł����A��ςɖ��ł��B
>�e���Ő��Y��قȂ�Ƃ��́A���ΓI�ɃR�X�g�̈������ɓ������ėA�o���邱�Ƃɂ���Đ��E�S�̂̐��Y�ʂ������A�o���̍������v��Win-Win����������̂��B �܂��A���Y�ʂ���������ꂾ���Ől�ނ͍K���ɂȂ邩�H �Ȃ�܂���B���Y�ʂ������Ă��A����z����V�X�e������������A�i���ƕn�����L���邾���̉\���������B���ɂ����Ȃ��Ă邶��Ȃ��ł����B�w�o���̍������v��x�Ƃ������A�o���̍��̒N���H�Ƃ������ł��B �O���[�o�����ŗ��v��̂́A�����Њ�ƁA���Y�Ɨ��ʁA���z�́w�V�X�e�������L����ҁx�ł��B�V�X�e�������L���Ȃ����́A�V�X�e���̎x�z������́A��ʂ̏���ҁA�J���҂͍����ڂɍ��킳���\���������B�R�[�q�[�A�R�R�A�A�V�R�S���A�p�[�����q���A���i�앨������Ă���r�㍑�̔_���́A�O���[�o�����ŖL���ȕ�炵�����Ă��܂����H �Ȃ��A���������̐H�ׂ�H�ו������Ȃ��ŁA�n���ɚb���Ȃ���A��i���̊�Ƃɒ������@����āA��i���̊�Ƃ̔��鍂���H�ו��킳��Ă���̂��H �O���[�o�����ŗ��v��̂͒N���H ���ɃO���[�o�����Ő��Y�ʂ͑����Ă��A���ʂ̐l�����ʂɕ�炵�₷�����̒��ɂȂ�Ƃ͓���v���܂���B _________ �R�����g �r�c�Z���Z�C�̕������ɂ͐r���s�������Â��̂ł����A�܂�����͂����̎��Ƃ��ĥ���B >����������10�{�ɂȂ�̂��B ����́h�����h����Ȃ��A�h�����I�h�Ȃ̂ł��傤�ˁB�O���[�o����(�����̌�傪���������}���J�V���ۂ��ł�)=�ψꉻ�Ȃ�A�����������́h�����h�����͌���܂���ˁB�h���������h���������Ă��A�h�����h���������̊�����艺����A�h�����I�����h�������茋�ǁh�L���h�ɂ͂Ȃ�܂���B �Z���Z�C�̗����ł́A���ӂȕ��ӂȎ҂������悭���Y��]�����鎖�Ń��m��T�[�r�X�̃R�X�g�������A���Ȃ킿���́h���l�h�������鎖���h�L���h�ւ̓����ƌ������Ȃ̂ł��傤���H�B �����̌��E�����`���E���K�E�n�搫�E�����������A�����݂̂�D�悵�Ď��{��`�̓s���őS�Ăɋψꉻ���v�邱�Ƃ��A�F�̍K���ł��錾�������ɂ͔[���ł��܂���B �b�艮 2011/11/04 6:24 PM
____
>���Y�ʂ������Ă��A����z����V�X�e������������A�i���ƕn�����L���邾���̉\���������B
>�ؑo���̍������v��x�Ƃ������A�o���̍��̒N���H�Ƃ������ł��B
>�O���[�o�����ŗ��v��̂́A�����Њ�ƁA���Y�Ɨ��ʁA���z�́w�V�X�e�������L����ҁx�ł��B
���Y�������オ��A���Y�ʂ������Ă��A���̐��Y�V�X�e���A���z�V�X�e�������L����҂��삦���邾���ŁA�J���ҁA�܂�A�J���ȊO�Ɍ�����i�i�����j�邱�Ƃ��o���Ȃ����̂́A�O��I�ɔ����@�����Ƃ������Ƃł��B��i�����낤�ƁA���W�r�㍑���낤�Ɠ������Ƃł��B�܂������A�r�c�M�v���̌����͕�������������ł��B �N�� 2011/11/04 6:38 PM _______
���͂悤�������܂��B���߂Ă��ז��������܂��B��ʂd�w�`�X���b�h�ňӌ����������Ă������������[�Y�ł��B�N����Ƃ͂d�w�`�𗬂̐e��������R�����ꂵ�����Ȃ�܂����̂ŁA��낵�����t�������̂قǂ��肢�\���グ�܂��B
���Ăs�o�o�ł����AISD�����ʂ��^�m���r�W�l�X�ʂ��A�ŁA�ł̂ݓP�p�^���m��̂Ƃ����t���[���łȂ�A�Q�����ׂ��ƍl���Ă��܂��B"����"��"�J��"�̉��l�̑���́A�����ېV�ł��ؖ�����Ă��܂��̂ŁB�������A�č��̌o�ωA�d�ɑ��ẮA���{�Ƃ��č���100�{���炢�x�����A���؎�̗̂��_�����̑��������{���ׂ��Ǝv���܂��B
�Ƃ����Ӗ��ŁA�O�q�́A�����t���Q���A�_�҂ł����́B �}���N�X�̎��{�_���o�ϊw�̕\���䂩������đ�30�N�o�߂��܂��B������ɁA�ނ̊g��Đ��Y�z�_�́A��ƉƂɂƂ��ẮA�K�̗͂��v�̒Nj��A�ȂǂŃo�b�N�{�[���ɂ͂Ȃ��Ă���悤�ł��B���P�C���Y�̃s�O�[�Ȃǂ��[���ƂȂ�A�����̃m�[�x���o�ϊw��܊w�҂����́A���{��`�o�ϊw�ł͂Ȃ����R��`�o�ϊw�ɃJ�W�������ċv�����ł��B �N��������̂悤�ɁA�ۑ�́A�ĕ��z�V�X�e���^���ׂĂ̌������v�͏���҂ɉ�A����V�X�e���̎����A�ł��B�א��҂���ƉƂ��A�}�N���̗D�ʂ��ɂ��蒍�͂��Ă���̂ŁA�Ȃ��Ȃ������������ɂȂ������ł��B �l�ԁi�~�N���Љ�j��^�ɍK���ɂ���o�ϊw��o�ϊ����́A�܂��܂����n�Ȓn�����E�̂悤�ł��B ���������̎��_�T�C�g�́A���N�O�ɔ`�����L��������܂��B���̂Ƃ��́A���I�ŁA���Â����_���R�����A����Ӗ��A�t�c�[�̐l���ȁA�Ɗ����A�킽���AROM���Ȃ��Ȃ�܂����B�N����u���O�̂������ŁA�v���Ԃ�ɔނ̘_�ɐG��邱�Ƃ��ł��܂����B���I�Ȃ̂͑��ς�炸�ł��ˁB ���Â����_�̒̂ق��́A�ȑO�ɂ����Ԓ@����Ă������Ƃ���A���ʂ͉��P����Ă���悤�ɁA���͊����܂����B
�������A�i�����h������l��q�����A�c�Ȃ��Ȃ���ے肵�Ă���̂Łj�A�S�̓����C�ł����i�j�B ���ƁA�G�z��������������������������̂ł����A ���������Ɋւ���N���� ���O���[�o�����ŁA���Ȃ��̒�����10�{�ɂȂ�ƌ����Ă����Ȃ���A�������͂̒��ŁA��i�����{�ɏZ�ނ��Ȃ��̒����́A���W�r�㍑���ɂȂ�ƌ����B
����͏����Ⴂ�܂��ˁB�ނ̌����́A
�E����������10�{�A�ł�����A������10�{�ɂȂ�A�Ƃ͌����ĂȂ��A����B �E���_�I�ɂ͐��E���œ���J���̒���������ɂȂ�܂Ői�ށA�ł�����A���W�r�㍑���ɂȂ�A�Ƃ͌����ĂȂ��A����B
���Ȃ݂Ɏ��́A���E���œ���J���̒���������ɂȂ�܂Ői�ށA���ꓯ���Ȃ�ł��B
���E�ōŒ�l����̍Ō�̍��i���A�t���J�j�̐B�Y���Ƃɍs����������A�ō��l����̏����i����i���j�ƍŒ�l����̏����i����ā��A�t���J�j�́A�l������̉��d���ϒl������ɗ��������̂ł́A�Ɛ������Ă��܂��B
�Ȃ��Ȃ�A�ō������̂���͒������A�ŒᏔ���̂���͒������Ă����A�����͂�������B
���Ƃ������A�ڋ��ł��蕠���������B
���S�̘̂_�|�����āA�������������グ�Ĕᔻ���āA����ɁA����������Ƃ��đS���̓��e��ے肷��B
�����������ᔻ�̂������A���͈�Ԍ����ł���B�ڋ������炾�B
�����ł��B�������������W���[�F�m�̈����O�Œ���Ă��錴���ł��B
�����āA���̒r�c����������r�D�ʂ̌����ł����A��ςɖ��ł��B
>>�ʊe���Ő��Y��قȂ�Ƃ��́A���ΓI�ɃR�X�g�̈������ɓ������ėA�o���邱�Ƃɂ���Đ��E�S�̂̐��Y�ʂ������A�o���̍������v��Win-Win����������̂��B�j
���܂��A���Y�ʂ���������ꂾ���Ől�ނ͍K���ɂȂ邩�H
���������̌����ɂ́A���Y�ʂ���������ꂾ���Ől�ނ͍K���ɂȂ�A�Ƃ͏����Ă��Ȃ��̂ŁA����ɂ��Ă͗N����̗E�ݑ�����Ȃ��ł��傤���H
�Ȃ��A���������̌���Win-Win�̊��������̂́A���エ���ނ�50�N�͂�����Ǝv���܂��B �킽���O�q�́A���E�ōŒ�l����̍Ō�̍��i���A�t���J�j�̐B�Y���Ƃɍs����������A����ȍ~�́AWin-Win�����̉\��������I�ɍ��܂�Ǝv���܂����A����܂ł́A������H�^�l����ɂ�鉿�i�j��̎��オ�����̂ŁA�^��Win-Win�͐�������킯����������ł��B
���O���[�o�����ŗ��v��̂́A�����Њ�ƁA���Y�Ɨ��ʁA���z�́w�V�X�e�������L����ҁx�ł��B
�����ł��B��������ɋL�q�́A���̎����A����������܂ł́B
���[�Y 2011/11/06 9:58 AM _____
���[�Y����A�R�����g���肪�Ƃ��������܂��B
�����͔��W�r�㍑���ɂȂ�A�Ƃ������́A���ω�����āA���W�r�㍑�ƕς��Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ƃł��ˁB�͂��B ���[�Y����́A���E���x���ŁA����J����������ɂȂ�Ƃ��l���̂悤�ł����A�����Ԃ�Ɗy�ϓI�Ȃ��l���̂悤�Ɏv���܂��B���̍l���ł́A �w������J���͂��ׂāA�قƂ�Ǔ�������ɂȂ�x �ł��B�܂�A�z�ꐧ�x�ł��ˁB�ǂ�ȐE�ƂɏA�����ƁA�J���҂́A�����Ă����邾���̍Œ�̒������������Ȃ��Ȃ�Ƃ������ƁB�Ȃ��A���F��v�m��ٌ�m���A�E��ŁA���Ȉオ���[�L���O�v�A�ȂɂȂ��Ă��܂����̂��H ����́A���F�͘J���Œ�����E�Ƃ�����ł��B�x�z�K���A�܂�A���Y���ʕ��z�́w�V�X�e���̏��L�ҁx�A������������̂��������|�I�ȕx�ƌ��͂���ɓ����B���ꂪ�A�O���[�o�����̍s�����������ł��B�������܂�
�V���R��`�A���~���{��`�A���R�������ȐӔC��`�A�l�I���x�����Y���A������H�̎E�C�̍r�쎑�{��`��O��I�ɐ����i�߂�Ɖ����N���邩�H
�����Ƃ������A�����Ƃ����{�͂̂����Ɓi�O���[�v�j���S�Ă̎Y�Ƃ�Ɛ肷��悤�ɂȂ�B�i���͂��ƊԂ̋����������Љ���Y��`�Љ�����j ������O�ł��B���{�͂𗘗p���āA�����̓V���������A���������Ő����Ƃ�������݁A�}�X�R�~�ɐ�`��𐂂ꗬ���Ď�Ȃ�����B�����āA�@����P���Ȃ��A���邢�́A���������ɗL���Ȗ@���ɉ���A�V�@�𐧒肵�ĉ��ł�����ł���肽������ɂȂ邩��ł��B �p�`���R�͓q���Ȃ̂ɁA�Ȃ��A�����̑ΏۂɂȂ�Ȃ��̂��H�x�@������V����Ŏ���A�������������āA�e���r�Ő�`�����T������ł��B�@���Ȃ�Ă���������Ȃ��B���ꂪ�A���E���x���ŋN����킯�ł��B ���{��`�����ɉ������Ƃ������Ƃ́A��莑�{�͂̂�����̂��������ɏ����ƂɂȂ邩�� ��������̍ŋ��̎��{�O���[�v���S�Ă̎Y�Ƃ������鐢�E�i���E�̋��Y��`���j�ł́A�ǂ�ȐE�Ƃł��낤�ƘJ���҂̒����͓O��I�ɔ����@����܂��B �V���R��`�ƃO���[�o�����𐄂��i�߂�ƁA���E�̋��Y��`�����������A�ǂ�ȐE�Ƃł��낤�Ƃ��A�����J���҂͂��ׂă��[�L���O�v�A�A�z��ɂȂ�Ƃ������Ƃł��B
���⑫
>���E�S�̂̐��Y�ʂ������A�o���̍������v��Win-Win����������̂��B �Ƃ����r�c���̈ӌ��ɑ��āA���́A�^�`��悵�Ă���킯�ł��B�w�������v�邱�Ɓ��l�ނ��K���ɂ���x�̂��H�������v�Ă��A�����ɂ��̗��v�z����V�X�e����������A�i���ƕn�����L���邾���ł���ƁB �N�� 2011/11/06 10:51 AM ____
�������͔��W�r�㍑���ɂȂ�A�Ƃ������́A���ω�����āA���W�r�㍑�ƕς��Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ƃł��ˁB�͂��B
�����A�Ⴂ�܂��B �����������̂́A�ō��l����̏����i����i���j�ƍŒ�l����̏����i����ā��A�t���J�j�̐l������̉��d���ϒl������ɗ��������̂ł͂Ɛ�������A�ł����B�قڒ����]�[���Ɏ����A�Ƃ����Ӗ��ł����B����ƁA���ω�����Ĕ��W�r�㍑�ƕς��Ȃ��Ȃ�A�͕��͂Ƃ��ĊԈ���Ă��܂��H
�����[�Y����́A���E���x���ŁA����J����������ɂȂ�Ƃ��l���̂悤�ł����A�����Ԃ�Ɗy�ϓI�Ȃ��l���̂悤�Ɏv���܂��B
�����A���̋t�ł��B���������o������Ă���A�Ƃ����Ӗ��ł��B �Ȃ��Ȃ�A�����Ă����Ă��A����50�N���炢�̂������ɁA�n���S�̂��A�����悤�̖����������J�j�Y���ɂ���āA���Ȃ킿�A�K�R�I�ɁA�����Ȃ��Ă��܂��ƍl���邩��ł��B�����G���A�ŒZ���I�Ɍ��Ă��A���łɁA���{�ƒ����́A�����������ƂɂȂ��Ă��܂��B�i���{�̐l����͒������A�����̐l����͒������Ă����Ă���j�B
�����̍l���ł́A�w������J���͂��ׂāA�قƂ�Ǔ�������ɂȂ�x�ł��B�܂�A�z�ꐧ�x�ł��ˁB
���ǂ�ȐE�ƂɏA�����ƁA�J���҂́A�����Ă����邾���̍Œ�̒������������Ȃ��Ȃ�Ƃ������ƁB
��������A�Ⴂ�܂��B
��L�́A���������̍���\���̌��_�����{�I�Ɂi���Ԉ���Ă���j�̂ŁA�����O��ɂ��Ă������̎����́A�ʕ����ɍs���Ă��܂��Ă���ƍl���܂��B
���Ȃ��A���F��v�m��ٌ�m���A�E��ŁA���Ȉオ���[�L���O�v�A�ȂɂȂ��Ă��܂����̂��H
���v�̑��ʂ������A�����̉ߏ�A����ɂ��A���R�̌��ʂł��B���̏؋��ɁA���v�Ƌ������o�����X���Ă�������̔ނ�̕��ϔN���́A���ɔ䂵�ēˏo���č��������ł��B
������́A���F�͘J���Œ�����E�Ƃ�����ł��B
�͂āH�C�~�t�ł��B
�p�v�i�T�[�r�X�j�����h�ɉ��l������E�Ƃ��Ǝv���܂����B�䂦�ɁA���̂悤�ȏA�E���[�L���O�v�A�̔��������ɂ́A�Ȃ肦�Ȃ��ƍl���܂��B
���x�z�K���A�܂�A���Y���ʕ��z�́w�V�X�e���̏��L�ҁx�A������������̂��������|�I�ȕx�ƌ��͂���ɓ����B
�����ꂪ�A�O���[�o�����̍s�����������ł��B�������܂�
���V���R��`�A���~���{��`�A���R�������ȐӔC��`�A�l�I���x�����Y���A������H�̎E�C�̍r�쎑�{��`��O��I�ɐ����i�߂�Ɖ����N���邩�H
�������Ƃ������A�����Ƃ����{�͂̂����Ɓi�O���[�v�j���S�Ă̎Y�Ƃ�Ɛ肷��悤�ɂȂ�B�i���͂��ƊԂ̋����������Љ���Y��`�Љ�����j
��������O�ł��B���{�͂𗘗p���āA�����̓V���������A���������Ő����Ƃ�������݁A�}�X�R�~�ɐ�`��𐂂ꗬ���Ď�Ȃ�����B
�������āA�@����P���Ȃ��A���邢�́A���������ɗL���Ȗ@���ɉ���A�V�@�𐧒肵�ĉ��ł�����ł���肽������ɂȂ邩��ł��B
���p�`���R�͓q���Ȃ̂ɁA�Ȃ��A�����̑ΏۂɂȂ�Ȃ��̂��H�x�@������V����Ŏ���A�������������āA�e���r�Ő�`�����T������ł��B
�ʕ����Ƀu�b���ł��܂����A�������̂��Ƃ��̂��̂́A���̂Ƃ���ł��B�ł��A��̎����̐����Ƃ��ẮA�ア�ł��B�Ƃ������ʕ����B
���@���Ȃ�Ă���������Ȃ��B���ꂪ�A���E���x���ŋN����킯�ł��B
�l�Ԑ��E�͔ڂ����ł�����A���z�ւ̉ߓn���ȂƎv���܂��B�V������p�`���R���������コ��ɋK������A���ӁA�Ȃ��Ȃ邾�낤�ƍl���܂��B
�����{��`�����ɉ������Ƃ������Ƃ́A��莑�{�͂̂�����̂��������ɏ����ƂɂȂ邩��
��������1980�N��܂ł́A���̖ʂ����������ł����A����ȍ~�́A���Ă͂܂�Ȃ��Ȃ��Ă��Ă��܂��B�J���̖͂R���������Ƃ́A���v�I�ɂ����Y�I�ɂ��Ǝ㉻���Ă��Ă��܂��B���l���������̂��J�������Ă����Ƃ́A�ǂ�ǂ�L�тĂ��Ă��܂��B
����������̍ŋ��̎��{�O���[�v���S�Ă̎Y�Ƃ������鐢�E�i���E�̋��Y��`���j�ł́A�ǂ�ȐE�Ƃł��낤�ƘJ���҂̒����͓O��I�ɔ����@����܂��B
���V���R��`�ƃO���[�o�����𐄂��i�߂�ƁA���E�̋��Y��`�����������A�ǂ�ȐE�Ƃł��낤�Ƃ��A�����J���҂͂��ׂă��[�L���O�v�A�A�z��ɂȂ�Ƃ������Ƃł��B
����������̍ŋ��̎��{�O���[�v���S�Ă̎Y�Ƃ������鐢�E�i���E�̋��Y��`���j�ł́A�ǂ�ȐE�Ƃł��낤�ƘJ���҂̒����͓O��I�ɔ����@����܂��B
���V���R��`�ƃO���[�o�����𐄂��i�߂�ƁA���E�̋��Y��`�����������A�ǂ�ȐE�Ƃł��낤�Ƃ��A�����J���҂͂��ׂă��[�L���O�v�A�A�z��ɂȂ�Ƃ������Ƃł��B
�Ⴂ�܂��B���Y��`���̐^�t�ł��B�����̔����@�����������Ă��܂���B�n�����E���ЂƂ̘J���s��ɂ������ł́A���ɂ��Ȃ��������A����ɋ߂Â��Ă����Ă���̂ł��B�����́A200�N�O�����݂��A�N�̂��߂ɂ��Ȃ�Ȃ��̂ł��B
�����⑫
>>�����E�S�̂̐��Y�ʂ������A�o���̍������v��Win-Win����������̂��B
���Ƃ����r�c���̈ӌ��ɑ��āA���́A�^�`��悵�Ă���킯�ł��B
���w�������v�邱�Ɓ��l�ނ��K���ɂ���x�̂��H�������v�Ă��A�����ɂ��̗��v�z����V�X�e����������A�i���ƕn�����L���邾���ł���ƁB
����ɂ��ẮA��Ɋ��q�̂悤��
�E���z�V�X�e���s���Ȃ܂܂ł́A���̂Ƃ���ł��B
�E�l�ԁi�~�N���Љ�j��^�ɍK���ɂ���o�ϊw��o�ϊ����A���ꂪ�i�ق̉ۑ�ł���A���̊�]�ł�����܂��B ���[�Y 2011/11/06 12:06 PM
_______
���[�Y����A�R�����g���肪�Ƃ��������܂��B
>����ƁA���ω�����Ĕ��W�r�㍑�ƕς��Ȃ��Ȃ�A�͕��͂Ƃ��ĊԈ���Ă��܂��H ���[���ƁA����́A���{��̖��ŁA�c�_���Ă����傤���Ȃ��悤�ȋC������̂ł����c�B �O���[�o�����ŕ��ω�����āA�����̍�����i�����A�����̒Ⴂ���W�r�㍑������J����������ɂȂ�Ƃ������ƂŁA�����Ă邱�Ƃ͓����ł͂Ȃ��ł����H ��i�������W�r�㍑���A���������ɂȂ�Ƃ����Ӗ��ŁB����Ȃ��Ƃŋc�_���Ă����傤���Ȃ��Ǝv���܂����B �� >�͂āH�C�~�t�ł��B
>�p�v�i�T�[�r�X�j�����h�ɉ��l������E�Ƃ��Ǝv���܂����B
>�䂦�ɁA���̂悤�ȏA�E���[�L���O�v�A�̔��������ɂ́A�Ȃ肦�Ȃ��ƍl���܂��B ����A���̂ł��ˁA���������Ă���̂́A �w�J���Ŏ������ VS ����������ҁx �Ƃ������Ƃł��B�T�[�r�X����悤���A�������낤���A���h�m���낤���A�x�@�����낤���A�ٌ�m���t���낤���A���F�J�������Ȃ��Ǝ����������Ȃ��҂ɂ����߂��܂���B�����Ō������������̌����Ƃ����̂́A�w�V�X�e�������L���錠���x�ŁA�V�X�e���Ƃ́A���Y���ʕ��z�̃V�X�e���̂��Ƃł��B �������A�ʂ̊�ƂŌ����A���Ƃ�GM��\�j�[�����ނ�����͂��Ă��܂��B�A�b�v����A�O�[�O���ADeNA�̑䓪�Ƃ������Ƃ�����ł��傤�B�������A���������ʂ̊�Ƃ̘b�ł͂Ȃ��̂ł���B�����Ƒ傫�Ȏ��{�̗��������A����Ȏ��{��������̂��x��c��܂������Ă��܂��B�����܂��ˁH �����Ȃ���I�ƌ��������܂łł����i�j�B �V���R��`�A�K���������~���{��`�ƃO���[�o�����̍s�������ŏI�`�Ԃ̘b�ł��B�����ԃ��[�J�[���A�o�c�����⎑�{��g�ȂǂŁA�e�������[�J�[��������A�傫�ȃO���[�v�ɓ�������Ă����B������Ƃ��ア��Ƃ����ݍ���ł����B
>�ʕ����Ƀu�b���ł��܂����A�������̂��Ƃ��̂��̂́A���̂Ƃ���ł��B
>�ł��A��̎����̐����Ƃ��ẮA�ア�ł��B�Ƃ������ʕ����B
�ʕ����ł͂Ȃ��Ăł��ˁB�����i���{�́j��������A���ł����肾�Ƃ������Ƃł��B�@�����A���_���A�������A���ׂď��z���Ă䂯��B ���Ƀp�`���R�Y�Ƃ����ނ��Ă��A���{�͔삦����Ȃ���A���D���J��Ԃ��A�y�X�ƕʂ̎Y�Ƃɏ�芷���Ă����i�������@�������z���āj�B�s�s��s���R�僁�K�o���N�ɓ�������Ă����܂����B��苐��Ȋ�Ɓi���{�j�Ɉ��ݍ��܂�A���邢�͎ア���̓��m���������Ă�苭���Ȃ�A�������J��Ԃ��Ă����B ���̐��ɂ�������̋��Z�@�ւ����Ȃ����E�i�����̖����Љ�B���邢�͕\�����͐��Ђ����Ă��A���ŗ��Q�����ɂ���W�j�B��̎Y�Ƃɂ��A��̊�Ɓi�O���[�v�j�����Ȃ��Љ�B����ɁA�ŋ��̊�Ɓi���{�j�O���[�v���A�S�Ă̎Y�Ƃ��x�z����Љ�B�������̎�����H���{��`�ŁA�ア��Ƃ͋�����ƂɈ��ݍ��܂�A��������Ă����i�����ڂŌ���j�B �z���C�g�J���[�G�O�[���v�V�����Ƃ����̂�����܂������A�����Ȃ�A�z���C�g�J���[�J���҂̒����������@����܂��B��ƊԂ̋��������������̓R�X�g������B
>�Ⴂ�܂��B���Y��`���̐^�t�ł��B�����̔����@�����������Ă��܂���B
>�n�����E���ЂƂ̘J���s��ɂ������ł́A���ɂ��Ȃ��������A����ɋ߂Â��Ă����Ă���A�̂ł��B
�V���R��`�ƃO���[�o���������ꂩ�炳��ɐ����i�߂�A�S�Ă̘J���ɑ�������A��V�͓O��I�ɔ����@����܂��B���ꂩ��A�N���邱�Ƃł��B
>���v�̑��ʂ������A�����̉ߏ�A����ɂ��A���R�̌��ʂł��B
�Ȃ������ߏ�ɂȂ����̂��H
�Ȃ��A�K���ɘa�A���x���v���ꂽ�̂��H
�Ȃ���R�ł��Ȃ������̂��H
�i���i�̋K���ɘa����ʍ����ɂƂ��Ăǂ����͕ʖ��j �ٌ�m����F��v�m�����厑�{�̏��L�҂ł͂Ȃ���������ł��i�����������͂����������j�B�V�X�e���̏��L�҂ł��Ȃ��̂ɁA�������Ȃ͖̂ڏ�肾�����B�l���l�̂܂ܗ͂������Ă����̂��ז��������̂ł��傤�B�ٌ�m����F��v�m�́A���F�͎��{�̎g��������ł����Ȃ������B�V���R��`�ƃO���[�o���������ꂩ�炳��ɐ����i�߂�A�S�Ă̘J���ɑ�������A��V�͓O��I�ɔ����@����܂��B����A�K������������H�𐄂��i�߂�A�����Ȃ�܂��B����������t��������A�Q�������Ă����肷�鏊������܂����A�傫�ȗ���͂����������Ƃł��B �K����P�p����������H���{��`�ɂ����ẮA���Ƃ�@���z���Ď��{�i��Ɓj�̘_�����܂���ʂ�܂��B���命���Њ�Ƃ̌o�ϊ������A�S�ĂɗD�悷��BISD������A�Ċ�FTA��NAFTA���ǂ���ł��B �₪�čŋ��̎��{�i��Ɓj�O���[�v�����܂�A�ƍّ̐����������i��Ɗ����͖@���ɗD�悷�邩��j�A���E�̋��Y��`���A�J���҂̓z�ꉻ���������܂��B����́A
>�ō��l����̏����i����i���j�ƍŒ�l����̏����i����ā��A�t���J�j�̐l������̉��d���ϒl������ɗ�������
�̂悤�Ȃ��Ƃ��N�����A���̂���Ɍ�ɋN���邱�Ƃł��B
>�����́A200�N�O�����݂��A�N�̂��߂ɂ��Ȃ�Ȃ��̂ł��B
�A�����J�嗤�ɏZ��ł����l�C�e�B�u�A�����J���́A���[���b�p�l�̐N���ʼn����ǂ����Ƃ��������̂ł��傤���H �s�T��������Ă�����ẮH �I�[�X�g�����A�嗤�̃A�{���W�j�́H �A�C�k�����́H ��R�̐l�X��z��Ƃ��ĝf�v����A���n�����ꂽ�A�t���J�́H �R�[�q�[�A�R�R�A�A�V�R�S���A�p�[�����q���A���i�앨������Ă���r�㍑�̔_���́A�O���[�o�����ŖL���ȕ�炵�����Ă��܂����H ���Ƃ��Ƃ́A���������̐H�ׂ�H�ו������������Œ��B���Ď����������Ă����l�����ł���H �Ȃ��A���������̐H�ׂ�H�ו������Ȃ��ŁA�n���ɚb���Ȃ���A��i���̊�Ƃɒ������@����āA��i���̊�Ƃ̔��鍂���H�ו��킳��Ă���̂ł����H ���Y���ʕ��z�A�����ĘJ���̋@�����Ƃ��Ɛ肵�Ă��邩��ł���B���ꂪ�O���[�o�����̍s�����������}�ł��B �� ���E�����Y��`���Ȃǂ���O�ɁA���[���b�p�o�ϊ�@��č��f�t�H���g�⒆���o�u�����ɂ���āA���E�̌o�σV�X�e���́A�V�X�e���N���b�V�����N������Ȃ��ł��傤���j
���̌�̂��Ƃ͎��ɂ͂킩��܂���B�j �N�� 2011/11/06 3:08 PM _____
�N�����O�̃u���O�L���̖`��
��������́A�O���[�o���������ۂ��Ċɖ��ɐ��ނ��Ď��Ɏ���ق����A�ɂ݂����Ȃ���������܂���B
���ǂ݂̂��A�l�͎��ʂ��A�l�ނ͐�ł��邵�A�n���͏��ł���i45���N���o�Ăj����A���{�ŗL�̕����Ȃǂǂ��ł��悢�̂����m��܂��c�B
�����邢�́A�������āA�A�[�~�b�V���̂悤�Ȑ���������̂���̑I���������m��܂���B
�N����̎v�z�|���V�[���W��Ă��܂��B
���C�Â��̂悤�Ɏ��́A�V�X�e�����X�̕s���ȓ_�͐l�ނ̉p�m�őŊJ���Đl�ލK���̍œK������߂��ɒNj�����A�Ƃ����v�z�|���V�[�ł��̂ŁA���̕ӂ́A�i���Ƀ}�b�`���O���Ȃ��Ǝv���Ă��܂������A100�l������100�l�Ƃ������������̂ł��̂ŁA����ł����Ǝv���Ă��܂��B
���i��̂��ԐM�j�����Ԃ�Ɗy�ϓI�Ȃ��l���̂悤�Ɏv���܂��B
�����[���ƁA����́A���{��̖��ŁA�c�_���Ă����傤���Ȃ��悤�ȋC������̂ł����c�B
����i�������W�r�㍑���A���������ɂȂ�Ƃ����Ӗ��ŁB����Ȃ��Ƃŋc�_���Ă����傤���Ȃ��Ǝv���܂����B
�������܂��ˁH�����Ȃ���I�ƌ��������܂łł����i�j�B
�����ق��������挊���@���Ă��邱�ƂɂȂ�̂ŁA������̓V�����܂��i�j���A�݂��̋c�_�̃m�������Ȃ��܂��̂ŁA���܂艿�l�͖����Ǝv���܂��B
���i��̂��ԐM�j�����͔��W�r�㍑���ɂȂ�A�Ƃ������́A���ω�����āA���W�r�㍑�ƕς��Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ƃł��ˁB�͂��B
����ɂ��ẮA���łɁA���͓I�ȊԈႢ�w�E���ς܂��A���̎v�����������A�����āA�����قǁA��t���k�ق̂悤�ȕԐM�Ղ��Ă��܂����A ���d���ϒl������ɂقڎ�������_�ŁA���Ƃ��Ƃ̔��W�r�㍑�̐�������͍����ق��Ɉړ����Ă���킯�ł�����A���W�r�㍑�ƕς��Ȃ��Ȃ�A�Ƃ������_�Â��͊Ԉ���Ă���A�Ǝv���܂��B
�������Ō������������̌����Ƃ����̂́A�w�V�X�e�������L���錠���x�ŁA�V�X�e���Ƃ́A���Y���ʕ��z�̃V�X�e���̂��Ƃł��B
�N����u���O�ŕp�ɂɏo�Ă���t���[�Y�ł����A��̓I�ȈӖ��̋L�q�͖����܂܁A�̂悤�Ɏv���܂��̂ŁA
�����@��H�ł��̂ŁA���肷���̂Ƃ��A��̓I�ȁA�V�X�e���`�Ԗ��^�܂��͑����ЏW�c���^���邢�͊��������̃O���[�v���^�Ƃ������������������B
���������A�ʂ̊�ƂŌ����A���Ƃ�GM��\�j�[�����ނ�����͂��Ă��܂��B
���A�b�v����A�O�[�O���ADeNA�̑䓪�Ƃ������Ƃ�����ł��傤�B
���������A���������ʂ̊�Ƃ̘b�ł͂Ȃ��̂ł���B
�����惌�X�ŏ��������Ƃ��ܘ_�X�̊�Ƃ̒f�ГI�Ȏ���ł͂���܂���B���ՓI�ȃE�l���i���l��`�ł̗D����s�j�ł��B
�������Ƒ傫�Ȏ��{�̗��������A����Ȏ��{��������̂��x��c��܂������Ă��܂��B�����܂��ˁH
�������Ȃ���I�ƌ��������܂łł����i�j�B
������A�����@��ł��̂ŁA���肷���̂Ƃ��A��̓I�ȁA���{�`�Ԗ��^�܂��͑����Њ�Ɩ��^�Ƃ������������������B
�����̐��ɂ�������̋��Z�@�ւ����Ȃ����E�i�����̖����Љ�B���邢�͕\�����͐��Ђ����Ă��A���ŗ��Q�����ɂ���W�j�B
����̎Y�Ƃɂ��A��̊�Ɓi�O���[�v�j�����Ȃ��Љ�B����ɁA�ŋ��̊�Ɓi���{�j�O���[�v���A�S�Ă̎Y�Ƃ��x�z����Љ�B
���������̎�����H���{��`�ŁA�ア��Ƃ͋�����ƂɈ��ݍ��܂�A��������Ă����i�����ڂŌ���j�B
����ł����A�ߋ��̐��X�̑ŊJ������������Ȃ��̂ł��傤���H
�l�ނ͋����Ȗʂ͑��X����܂������s���F�����������ł����A�قڂǂ�������Ă����ƍl���܂��B
�Ȃ��A���ʋ��t�̋��P�Ƃ��Đ������Ă������H�Ƃ����ƁA�������j�ł͂���܂����B
���ٌ�m����F��v�m�����厑�{�̏��L�҂ł͂Ȃ���������ł��i�����������͂����������j�B
���V�X�e���̏��L�҂ł��Ȃ��̂ɁA�������Ȃ͖̂ڏ�肾�����B
���l���l�̂܂ܗ͂������Ă����̂��ז��������̂ł��傤�B
�����܂ł���ƁA�����A���c�I���x���ł��̂ŁA�Ȃɂ���������A�ł��B �����E�����Y��`���Ȃǂ���O�ɁA���[���b�p�o�ϊ�@��č��f�t�H���g�⒆���o�u�����ɂ���āA
�����E�̌o�σV�X�e���́A�V�X�e���N���b�V�����N������Ȃ��ł��傤�� ���E�͋��Y��`���̔��Ε�����͋�������ł��܂��̂őO��Ƃ��Ă̓i���Z���X�ł����A�������Ɍo�σV�X�e���̃N���b�V���͑��Ӗu������Ǝv���܂��B�N����ɓ��ӂł��B �ł��������A���́A�N����̂悤�ɁA�ߊϓI�ł͂Ȃ����A�}���I�ł���������̂ŁA�N�����_�̏I���C���[�W�Ƃ͐^�t�̗\�������Ă��܂��B���E�̃r�W�l�X�l�Ԃ͔ڗ�Ȗʂ͎����Ă��܂����A���炭�����爫�͑P�ɒ@����A���l���郂�m��ǂ����m�����������c��Ƃ����A�������䂪�@�\���܂��B�����܂ł̃��[�h�^�C���͒����ł����A�Ō�̍Ō�́A���s�͐��ނ��A���`�̃V�X�e���������c��̂ł��B�ߋ��̏�����������ƂɁA�l�Ԃ̉p�m��M���܂��H
�l�Ԃ��āA����قǂ̔n���ł͂Ȃ��Ǝv����ł��B ���[�Y 2011/11/06 5:05 PM
_______
���[�Y����A�R�����g���肪�Ƃ��������܂��B
>���O���[�o�����ŗ��v��̂́A�����Њ�ƁA���Y�Ɨ��ʁA���z�́w�V�X�e�������L����ҁx�ł��B
>�����ł��B��������ɋL�q�́A���̎����A����������܂ł́B
�͂��B�������������Ă���Ƃ̂��ƂŁw�V�X�e�������L����ҁx�̐����͕s�v���Ǝv���܂����H
�W�F�C�E���b�N�t�F���[���I�Ƃ��A�W�F�C�R�u�E���X�`���C���h���I�Ƃ��A���ۋ��Z���{���I�Ƃ��������Ƃ���Ŏd���������ł��傤�B�N������̌l��c�̂ł͂Ȃ��T�O�ł�����B���������T�O�i����j���g���āA���ۂ�������悤�Ƃ��Ă��邾���ł��B
��
�c�_���A���t�ׂ̍�����`��A���t�����A�����A�l�i�ɂ��Ă̍U���ɂȂ��Ă���ƁA���͂��܂�y��������܂���B�s�т�����ł��B���܂茚�ݓI�ȋc�_�ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��傤�B �r�c�����A���͂̑O���ł̓O���[�o�����Œ�����������ƌ����Ă����Ȃ���A�㔼�ł͒�����������ƌ����Ă���Ƃ����������w�E�����܂łł��B �Ȃ�����Ȍ����ׂ̍����Ⴂ�ɂ������̂������ł��܂���B�w���ω�����āx�Ƃ������Ƃ̒�`�̖��ɂ����߂��Ȃ��̂��Ⴀ��܂��H �ꉭ�l�̐l���N���P�疜�~�ŁA�\���l�̐l���N���S���~�B���ω�����ƁA550���~�Ă��Ƃ͂Ȃ��ł��傤�H �i�ꉭ�l�~��疜�~�{�\���l�~�S���~�j���\�ꉭ�l�ł��B�Z�������Ȃ̂Ōv�Z���܂��B��疜�~�̔N���̐l�̎����͌������܂��ˁB �� >�����܂ł���ƁA�����A���c�I���x���ł��̂ŁA�Ȃɂ���������A�ł��B �l�Ԃ����E�⌻�ۂɂ��ė������悤�Ƃ���Ƃ��ɂ́A���郂�f�����g���ė��������葼����܂���B�����͂���̂܂܂ɐl�ԑ��݂ɓ͂�����̂ł͂Ȃ��A�����͊T�O�ɂ���ċ���A�Ӗ��t�����Đl�Ԃ̈ӎ��ɓ͂����܂��B�Ⴆ�A���E�� �w�J���Ŏ����邵���Ȃ���VS�V�X�e�������L���A����������҂Ƃ̑Η��x �Ƃ������f���Ō���Ɖ���������̂��H�Ƃ������Ƃ��l��������ł��B �؋���������I�ƌ����Ă�����܂��B�����������f���ōl����Ƃ����������Ƃ������܂���Ƃ����b�ł��B
��
���́A�c�_�ɏ��������Ƃ��A�����_�j�������Ƃ������~�]�͗]�薳���̂ł��B���̗~�]�́A���̌������Ƃ𐳂����������ė~�����Ƃ������Ƃł��B�c�_�̂��߂̋c�_�ɂ͋�������܂���B �N�� 2011/11/06 7:13 PM
______
�����X���炵�܂��B�@ �ŏ��͂悢�c�_�̕����֘b�����������Ɗ��҂��Ă����̂ł����A�r������͂�͂艽�����̂悤�ȗ���ɂȂ��Ă��܂��c�O�ł��B >>���[�Y�����
�c�_�̑Ώۂ́A�r�c���̋L���ɑ���ӌ����q�������ł͂���܂��H�B �N����̉��߂┭���A�v�l�������ł��Ȃ��܂��͔[���ł��Ȃ��A�����g�̂��l�����ƈႤ����Ƃ����āA���̌��_�Ɏ���؋���������̓I�ɒ���ƌ����̂͂����������\������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�r�c���̔����ɑ����[�Y����Ȃ�̉��߁E�����������A����������ؖ��������̂ł���A������q�ׂ��邾���ł�낵���̂ł͂���܂���H �b�艮 2011/11/06 8:32 PM
_______
�N����� ���������̌��� �@������700�~�ŃW�[���Y�������Ƃ��A���{��7000�~�ł���Ӗ��͂Ȃ��B�����ɔ�r�D�ʂ�������̂͗A������A���Ȃ��̎���������10�{�ɂȂ�̂��B �A���_�I�ɂ͐��E���œ���J���̒���������ɂȂ�܂Ői�ށB�J���ړ����Ȃ��Ă�������J���̐��i��A�����邱�Ƃɂ���ĘJ����A������̂Ɠ������ʂ����邩�炾�B
�N����̌�T���X���J�G
�@�r�c�����A���͂̑O���ł̓O���[�o�����Œ�����������ƌ����Ă����Ȃ���A �A�㔼�ł͒�����������ƌ����Ă���Ƃ����������w�E�����܂łł��B
�N����̌�T�ɂ��Ă͊��Ɏw�E�������ς݂Ȃ̂Ŋ������܂����A��L�́A�����ƗN�����ق́A���炩�ɐH������Ă��܂��B���������̂́A�t�F�A����Ȃ��A�ƌ����������������ł��B
���ٌ�m����F��v�m�����厑�{�̏��L�҂ł͂Ȃ���������ł��i�����������͂����������j�B
���V�X�e���̏��L�҂ł��Ȃ��̂ɁA�������Ȃ͖̂ڏ�肾�����B
���l���l�̂܂ܗ͂������Ă����̂��ז��������̂ł��傤�B ��t���ŁA�T�O�ɂ��_�q���ƍR�قȂ����Ă��܂������A����ɂ��Ă̓��A���Ȏ��ۂ�Ꭶ���āA�����Ƃ��Ă͒N���M�p���Ȃ������ł����ˁB���͉��ւɃI�u���[�g�ɕ��ŁA���c�I����ʂ�Ə����܂������A�͂����茾���ƁA�Ԉ���Ă����ł���ˁB �͂��A������̋����ߏ���A�������ȃO���[�o����Ƃ⋐�厑�{�ƃR���c�F�������W���Ă���̂ł͂Ȃ��A �E���̎i�@�������i�҂̌��������ďA�E��́A�@�ȑ�w�@�̗�������̔h���B�����ߏ�B �E���̌��F��v�m�����̍��i�҂̌��������ďA�E��́A��v�m���w�Z�̗�������̔h���B�����ߏ�B �E���̎��Ȉ�t�����̍��i�҂̌��������ă��[�L���O�v�A���́A�������ȑ�w�̗�������̔h���B�����ߏ�B
��������A�ʎ���Ǝ��v���Ƃ��ẮA�w�Z�̗����ł�����A���̂悤�ȃO���[�o������V�X�e���W�c�Ƃ��̎d�Ƃł͖����̂ł��B
���Ȃ݂Ɏ����A���������ɑ��ẮA�D���͂����Ă��܂���̂ŁA�ٌ삷�����͊F���ł��B�������A�ǂ�ȕ]�_�Ƃł��A���̐l�Ȃ�ɃA�b�v���Ă���_�q�Ȃ̂ŁA�ᔻ����Ȃ�A�����ƃt�F�A�ɔᔻ���܂��H�������̂ł��B ���Ԃ�N������������ȁA�c�Ȃ����O��̏�ɁA�ᔻ���_��ςݏd�˂�A���������A���E�t�F�A�Ȃ��Ƃ��A�N�����g������肾�����̂ŁA�V�k�S�Ȃ���w�E�Ɛ������������ł��B ��p�w�҂Ȃ�ʌ�p�R�����g�������A�������z��܂��͊��҂���Ă�����Ȃ�ܘ_��������R�ł����A����ɂ��ĉ������l�͂���܂����H ���[�Y 2011/11/07 2:36 AM
______
���[�Y����A�R�����g���肪�Ƃ��������܂��B
���́A�����������f���ŎЉ�ۂ����Ă݂�Ƃ����������Ƃ������܂���Ƃ����A�C�f�A����Ă��邾���ŁA����Ɏ^������Ƃ�������Ƃ������Ă���킯�ł͂���܂���B�����������f�����g��Ȃ���A�����͌����Ȃ��Ƃ������Ƃ͓�����O�ł��B����ɂ��āA�������Ƃ��Ԉ���Ă�Ƃ��������������Ă��s�тł��B�����������f���͍̗p���Ȃ��Ƃ������Ƃł���A�͂������ł����ƌ�����葼����܂���B
>�͂��A������̋����ߏ���A�������ȃO���[�o����Ƃ⋐�厑�{�ƃR���c�F�������W���Ă���̂ł͂Ȃ��A
�i�����j
>��������A�ʎ���Ǝ��v���Ƃ��ẮA�w�Z�̗����ł�����A���̂悤�ȃO���[�o������V�X�e���W�c�Ƃ��̎d�Ƃł͖����̂ł��B
�����̓I�ȎЉ�ۂɁA�ǂ������͊w�������Ă��邩�Ƃ������Ƃɂ��āA����T�O�A���f����p���Đ��������ƌ����Ă邶��Ȃ��ł����B����̌��͎҂�A��Ƃ̎d�Ƃ��Ȃǂƌ����Ă���̂ł͂���܂���B �W�O�����g�E�t���C�g���A�G�X�i�C�h�j�E����E������̃��f���ŋ�̓I�Ȑl�Ԃ̍s������������悤�ɁA���f�����g���Č��ۂ����߂�����A�Ƃ������Ƃł��B�t���C�g�Ɍ������āA�G�X�⎩��⒴����Ȃǎ��݂��Ă��Ȃ��I�ƌ������Ƃ���ʼn��ɂȂ��ł��H �T�O��f���͓���Ȃ̂ŁA�g�����g��Ȃ����͎��R�ł���B�Ƃ���ŁA���l�ɑ��āA�������킩��Ȃ����Ƃ����₷��Ƃ��ɁA�Ȃ����̂悤�ɍ����I�ŋ��䍂�ȕ������������̂ł��傤�B �� ���ꏬ���ɓ�������l�A���ǂ���炵�Ă���܂����B �����ցA�D������Ă��āA�D�����������F�E���ɂ��ē��ɏZ�ݒ����܂����B �₪�āA�D�ł���Ă����V���������͔_�k�Ƌ��J�̋Z�p�ɒ����Ă����̂ŁA���Y�����オ��A�l���͓��l�ɑ����܂����B �����I�������A��l������l�ɑ������I���Ƃ��_�Ƃ����W�����I���̓��́A���W�����̂ŗǂ������I �H �������̗��ꂩ�猩�邩�A�V�����̗��ꂩ�猩�邩�ŁA�����݂̍�l�́A�܂������قȂ�܂��B �N�� 2011/11/07 7:37 PM _______
�܂��܂��k�ق������Ă��܂��ˁB
�������̓I�ȎЉ�ۂɁA�ǂ������͊w�������Ă��邩�Ƃ������Ƃɂ��āA����T�O�A���f����p���Đ��������ƌ����Ă邶��Ȃ��ł����B
���T�O��f���͓���Ȃ̂ŁA�g�����g��Ȃ����͎��R�ł���B
���Ȃ��͊w�҂ł͂Ȃ��݂����Ȃ̂Ŏd�����Ȃ��̂����m��܂��A��ʐl�ł����l�Ȃ�A���ۓI���f�����g���Ę_�y����ꍇ�́A���ۓI�Ȏ��ۂɑ��Ę_����̂��A����Ȓ�ł��B�������A���ۓI���f�����g���āA��̓I�Ȏ��ۂ�_����̂Ȃ�A�����Ɛ^�t�Ȍ��_�Â��́A�����̓[���ł��B�ł�����A�{���̒m���l�́A�͂Ȃ���A�����������́A�������Ȃ��̂ł��B
��́A�ٌ�m�E��v�m�E���Ȉ�t�̎���Ȃ́A��̓I�Ɍ����w�i���ؖ�����Ă���̂ł�����A�������A���f���Ƃ��Ȃ�Ƃ��Ō��y����ƁA���₲���g���{���͂��C�Â��̂悤�ɁA���̂悤�ɁA�Ƃ�ł��Ȃ��ڒ����Ș_�y�ɂȂ�܂��B
���������̗��ꂩ�猩�邩�A�V�����̗��ꂩ�猩�邩�ŁA�����݂̍�l�́A�܂������قȂ�܂��B
������A�����ӂ̗U���k�قł��ˁB���́A�����܂ł̃R������ŁA�M���̂悤�ȁA�Е����炾�������A���������_�y�͂��Ă��܂���B�S�̑o���̍œK�����A���Ȃ��ɑ��āA�����Ă��܂����B ���Ȃ��́y�_�@�z�����Ȃ�A����ȕЕ����炾���̃��m�̌������Ă��y�d���Ȃ��ł��傤�z�A�ł��B ���Ȃ݂ɁA���Ȃ��́A��́A�Z�[�t�e�B�l�b�g�K���_���܂߂āA�Ƃɂ�����ҕی�̃X�^���X�̂悤�ł����A����ɂ��ẮA�l�̎��R�v�z�ł��̂ŁA���Ȃ��Ƃ����d�͒v���܂��B�������A�^�����邩�ǂ����́A�W�Ȃ��B
��������A�u���O�L���̕������������Ă����܂����ˁB����͕]���ł��܂��B
������ɁA�c�O�Ȃ���A���Ȃ��̊�����i�܂��͓��Y�m�����̂��̂̍���j�ɂ��A�قƂ�Ǖς��f�����Ă��Ȃ��ł��ˁB�c�O�ł��B
>>��������700�~�ŃW�[���Y�������Ƃ��A���{��7000�~�ł���Ӗ��͂Ȃ��B
>>�������ɔ�r�D�ʂ�������̂͗A������A���Ȃ��̎���������10�{�ɂȂ�̂��B ���Ə����A��̕��ł́A >>�����_�I�ɂ́A���E���œ���J���̒���������ɂȂ�܂Ői�ށB
>>���J���ړ����Ȃ��Ă��A������J���̐��i��A�����邱�Ƃɂ���ĘJ����A������̂Ɠ������ʂ����邩�炾�B ���O���[�o�����ŁA���Ȃ��̒�����10�{�ɂȂ�ƌ����Ă����Ȃ���A�������͂̒��ŁA��i�����{�ɏZ�ނ��Ȃ��̒����́A���W�r�㍑���ɂȂ�ƌ����B
���i�R�����g���Œ��ӂ��܂����̂ŁA���������ꂳ���Ă��������܂��B���W�r�㍑���ɂȂ�A�ł͂Ȃ��A���ω�����āA���W�r�㍑�ƕς��Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ƃł��ˁB
���ǂ����ɂ���A�O���[�o�����ŁA�L���̑O���ł͒�����������ƌ����A�㔼�Œ���������ƌ����Ă��܂��B�j
�n�n�n�i����I�j�A
�ǂ����ɂ���O���[�o�����ŋL���̑O���ł͒�����������ƌ����㔼�Œ���������ƌ����Ă��܂��A
�ł����B�܂�����܂����B
����킽�����R���ȗ��A���łɂQ�x���A���Ȃ��̒m�������A���E�t�F�A�ȑ��Ҕᔻ�̋��������w�E���Ă��܂������A�u���O���������Ɏ����Ă��A�����I�ɂ́A�Ȃ����P����Ă��Ȃ��͉̂��̂��H ���́i�߂����j�����A�i�荞�ނ��Ƃ��o���܂����B ����ł����A���Ȃ��A�����܂��͉��������̗]�T�]��̑����A�ƁA�����̑����A���A���ꎋ���Ă�����悤�ł��ˁB�����Ă�邢�ł����A�����Ӗ��ŁA���Ȃ��A�ƂĂ���������m�ł��B �����̓ǎ҂ɁA���ȏ�̃��x���̒m���l������������Ȃ�A����Ă�����Ǝv���܂��B _____
���[�Y 2011/11/08 12:56 AM
���́A���Â��A���Ȃ��̂��Ƃ�s�v�c�Ș_�q�҂Ɗ������̂ŁA��V��A�ߋ����O���ȑO�����A����Ƀ\�R�\�R�����̂ڂ��āA�����Ɣq�ǂ��Ă݂܂����B�������ŁA�قځA�𖾂ł��܂����i�j�B �ȉ��ɁA���ʂ������납�����ӂ��A�Ꭶ���܂��B �N����u���O2011.02.02
http://miruton.jugem.jp/?eid=480#comments �����{��`�Ƃ����̂́A�g��Đ��Y���g��ď��� ���̋L�����A���̖w�ǂ��A�g��Đ��Y�^�V�X�e�����L�҂���ʂ�A�قځA�����ӓ|�ł��ˁB
30�N���O�ɔp�ꂽ�}���N�X�o�ϊw�ł̎��{��`�_�ł����H
����́A�Ƃ����̐̂���A���R��`�o�ϊw�̎���ł���B �g��Đ��Y�_�^�V�X�e�����L�҂���ʂ�A�����ł́A�N��������́A����ǂ��̂ł́H
�����Ƃ����ƌ���w��A�����Ԃ��A�����܂��H ����ƁA�V�X�e�����L�҂���ʂ�A�z���g�p�ɂɏo�Ă��܂����A�s�v�c�ɁA�ǂ̋L���ɂ��A���̒�`�͊F���ł��ˁB
�܂��A�����ӂ̘_�@�ł���A���f��������C�C����A�ł��ˁH�i�j�B
���m�Ȓm���A���Â��f�[�^�A�������Ȃ�ł���ˁH
�܂����H
�i�j �����オ�㏸���Ȃ��Ƃ��A��Ƃ͌o��팸�̕����Ɍ������܂��B
���������X�g���Ƃ������c�ł��B�l���팸�A�����J�b�g�A���Ј�����h���Ј��ւ̈ڍs�B
�������Ċ�Ƃ͓������ۂ𑝂₵�A����z���Ɩ�����V���g�傷��B �n�n�n�i����j�A�܂�ŕs���ȍ��Z���̐��o�̓��Ă݂����Ȃ̂ŁA���B �}�[�P�e�B���O������A�u�d�^�s�n�b�ɂ��R�X�g�E���_�N�V���������A�j�[�Y�ƃV�[�Y�̃}�b�`���O�A�V�K�J���͂̑����A�b�r���㊈���Ȃǂ��A���v��v��ł���B
�������ۂ́A�ݔ������̌��������A���v���C�I���e�B�A�ł���B �܂�ŁA��̂̋��Y�}���Љ�}�݂����ł��ˁB ���������A���܂��琢�E�����Y��`������Ƃ͎v���Ă��܂��A
������ȏ�o�σV�X�e�����\�����A�l�Ԃݒׂ��悤�Ȃ�A���O�͖ق��Ă��Ȃ��ł��傤�B ���ꂠ��A��L2011.02.02�N����u���O�ł́A���܂��琢�E�����Y��`������Ƃ͎v���Ă��܂���A�Ȃ̂ɁA �i���g�i�j�A����2011/11/06�N����R�����g�ł́A���E�����Y��`���Ȃǂ���O�ɁA�ƁA�����Ă�����A
* �N�� 2011/11/06 3:08 PM�����E�����Y��`���Ȃǂ���O�Ƀ��[���b�p�o�ϊ�@��č��f�t�H���g�⒆���o�u�����ɂ���Đ��E�̌o�σV�X�e���̓V�X�e���N���b�V�����N������Ȃ��ł��傤���B ����ł����A�g��Đ��Y�^�V�X�e�����L�҂���ʂ�A��ӓ|�����łȂ��A�N���������鋤�Y��`������ʂ���A��ʂɂ���Ă͐����ɂȂ��ł��ˁB
���v�ł����H
�����܂��ɁA
��͂�A�����[�Y���q�̒����̓r���S�I�ł����B
�͂��A���Ȃ��́A��͂�A���c���܁A�ł��B�i�j �Ȃ��Ȃ�A���Ȃ��̃u���O�L���ɑ��āA�ق�̂��܂ɂ���R�����g�����Ă���A���̏؋�������܂��B �R�����g���ʂ���f����A �E�f�p�Ȉ�ʐl����́A�u���O�L���ւ̎^���������āA �E���L���m�����������̂�������́A�����}����Ă����邩��B
�ł͂ł́B�i�j�B
���[�Y 2011/11/08 6:19 AM �R�����g����
http://miruton.jugem.jp/?eid=539 ���[�Y����̂͗B�̌����|����ɂ��������Ȃ��ł��ˁB ����͌o�ςł͂Ȃ������w�I�ȓK���Ɠ����̖��ł�����B���ϗ͂��[���̃��[�Y���o�ς̒m���Ƙ_�������ł�����l���Ă��{���ɂ͓��B�ł��Ȃ��̂ł��ˁB �l�ނ͓V�G�����Ȃ��̂Ō݂��ɎE�������Đl�������炷�����Ȃ��̂ł��ˁB������A���ɓK�������������K���ł��Ȃ�����������łڂ������i���̓��͖����̂ł��ˁB
�g���E�̃r�W�l�X�l�Ԃ͔ڗ�Ȗʂ͎����Ă��܂����A���炭�����爫�͑P�ɒ@����A���l���郂�m��ǂ����m�����������c��Ƃ����A�������䂪�@�\���܂��B�����܂ł̃��[�h�^�C���͒����ł����A�Ō�̍Ō�́A���s�͐��ނ��A���`�̃V�X�e���������c��̂ł��B�ߋ��̏�����������ƂɁA�l�Ԃ̉p�m��M���܂��H
�l�Ԃ��āA����قǂ̔n���ł͂Ȃ��Ǝv����ł��B�g
�g����ł����A�ߋ��̐��X�̑ŊJ������������Ȃ��̂ł��傤���H
�l�ނ͋����Ȗʂ͑��X����܂������s���F�����������ł����A�قڂǂ�������Ă����ƍl���܂��B�g
���[�Y����̂��̌��t�ɂ͏��Ă��܂��܂��ˁB
�ꕶ�l��łڂ��Ȃ���Ζ퐶�l�͓��{��D���Ȃ������̂ł��ˁB
�A�����J�C���f�B�A����łڂ��Ȃ���A���O���T�N�\���̓A�����J��D���Ȃ������̂ł��ˁB �l�A���f���^�[����łڂ��Ȃ���z���E�T�s�G���X�͐����c��Ȃ������̂ł��ˁB �S�������l�ɍ��A�����l�͗L�F�l���łڂ����Ƃ��Ă���̂ł��ˁB�n����68���l�͑��߂��܂�����B ���X�`���C���h�͒n���̐��E�l��68���l�̂����A40���l���팸����v��݂����ł��ˁB�����́u�َ��^�v�ł͐l�ނ�2�^3���łԂ��ƂɂȂ��Ă���̂ŁB
�܂��A�����̗D�G���ł͐����l�����E��ł����A�����ł��邩�ǂ����͗D�G���ł͂Ȃ����ւ̓K���͂Ō��܂�܂�����A�����l���ŏI���҂ɂȂ鎖�͐�ɗL��Ȃ���ł����ǂˁB
���[�Y����͖ڐ��10�N�E20�N�P�ʂł��������l�����Ȃ��l�Ȃ�ł��傤�B�����҂ɂ͈�Ԍ����Ȃ����i�ł��ˁB
�N����̍l�����̖{���͂����������ł��傤�F
�O���[�o���Y���́A�鍑��`�B August 25, 2007
�������A�������Ȃ��Ă����B�A�����J�̌o�ςɂ��H���������Ă���B���̂܂܂��ƁA�߂������h���̖\���Ƃ������Ԃ��l������B
�����I�ȃA�����J�̈АM�́A�C���N�푈�̎��s�ł��ł��Ȃ�������Ă����B�K�R�I�ɃA�����J�̓��j���e�����Y�����̗p������Ȃ������Ƃ������Ƃ��낤�B��j�D����˂��݂������o���悤�ɁA�u�b�V����������͉��l���̊W�҂��ގU���Ă���B�����āA�����I�ȈАM���Ă̒������A���x�͌o�ϓI�ȐM�p����ւƐڑ����ꂻ���ȋC�z�ł���B�N���W�b�g�N�����`�ł���B ���{�̌o�ϊw�҂́A�y�Ϙ_�������悤�ł��邪���̓x�̏Z��[���̔j�]�Ɏn�܂�č��o�ς̍����ƁA�A�����鐢�E�����s���͗\�f�������Ȃ��ɂȂ��Ă���B�A�����J�̎��ԂɊւ��Ă͔ߊϓI�Ȋϑ����q�ׂĂ���G�R�m�~�X�g�̈�l�A����a�v�́w�l�X�͂Ȃ��O���[�o���o�ς̖{���������̂��x
http://www.amazon.co.jp/%E4%BA%BA%E3%80%85%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%9C%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%AB%E7%B5%8C%E6%B8%88%E3%81%AE%E6%9C%AC%E8%B3%AA%E3%82%92%E8%A6%8B%E8%AA%A4%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B-%E6%B0%B4%E9%87%8E-%E5%92%8C%E5%A4%AB/dp/4532352452 ��ǂB �@����́A�P�X�X�T�N�����ɂ��āA��オ�I�����A���{�����E������܂ł̌o�ϓI�ȏ펯�͂��͂�g�����ɂȂ�Ȃ��Ƃ������Ƃ��A���ؓI�ɗ��t���Ă䂭�B �ނ̓V���N�^���N�ۗ̕L���Ă��邠����f�[�^�͂��邱�ƂŁA�X�T�N������̓]�H�_�ł��邱�Ƃ�����B�����܂łȂ�A�����̌o�ϊw�ҁA�G�R�m�~�X�g���\�����邱�Ƃ͂ł���B����̑n���́A���ꂪ�o�ς̐��E�ɂ�����ߑ�̏I���ł���A�����Ɏ��{�ɂ�锽�v���̎n�܂�ł���Ƃ����A�o�σV�X�e���̕ϊ���ǂݍ����Ƃł���B �@��ςɖʔ����A�X�������O�ȗ��_�ł���B �������āA�X�S�N�Ƃ����N������̓]���_�ł���Ə��������Ƃ��������B �u�ڂ��̓r�W�l�X�̐��E�ŁA�P�X�X�S�N�����Ɍ��I�ȕω��A���l�ϓ������������ƍl���Ă��܂��B�����Ă��̕ω��͓��{�����G�Ȃ������s�����ĕ�����l�X�̌��t�Â����܂ŕς��Ă����قǂ̔ɐB�͂������Ă��܂����B���m�Ɍ����A�����J���E�X�^���_�[�h�Ƃ������̂��J�o�[����n��A�l��A�E�Ƃ��ׂẲ��l�ςɑ傫�ȏC���������炷���̂ƂȂ����v�i�w�����t�@�C�e�B���O�L�b�Y�x�j ���́A�r�W�l�X�̌���ɂ�����l�X�̌��t�Â������傫���ς�������Ƃ���A���̃A�C�f�A���v�������̂ł��邪�A����͐��Ƃ炵���o�ϓI�Ȏw�W��ǂ݉������Ƃ̒�����A���̓]���������I�ȃV�X�e���̓]���ł��邱�Ƃ��u�����v����B�����āA�|�X�g�ߑ�Ƃ́A�C���^�[�l�b�g����Z�Z�p���������钴�ߑ�Ȃǂł͂Ȃ��A�鍑�̍ė�,���{���A����ւ̕��z���m�ۂ��邽�߂̔��v���ł���ƌ����̂ł���B�@����́A���ɖڂ���̎w�E�ł������B �Ȃ�قǁA�O���[�o���Y���Ƃ́A���R��`�̊g��ł͂Ȃ��o�ϒ鍑��`�ł������̂��B �����l������낢��Ȃ��Ƃ��D�ɗ�����B�����l���Ȃ���A�O���[�o����Ƃ̖O���Ȃ��c����A�o�ϐ������Ȃ�����g�傷��i��������̔敾�Ƃ�������肪���܂������ł��Ȃ��B�c�����Ă���̂́A���{�����ł���A�����o�ςł͂Ȃ��̂ł���B �鍑��`�Ƃ͉����B ���[�j���͂��̒鍑��`�_�ł����q�ׂĂ���B �u�鍑��`�Ƃ́A�Ɛ�̂Ƌ��Z���{�̎x�z���������Ă��āA���{�A�o���������d�v���𑝂��A���ۓI�ȃg���X�g�ɂ�鐢�E�̕������n�܂�A�ŋ��̎��{��`�����ɂ�鐢�E�̑S�̓y�̕��������������Ƃ������B�i�K�ɒB�������{��`�̂��Ƃł���B�v �ȒP�Ɍ����A�鍑��`�Ƃ́A���v�g��̂��߂̍ی��̂Ȃ��������̐A�����ł������B �鍑��`�͂ǂ̂悤�ɂ��ďI�������̂��B ����́A�L���Ȑ��E�̒��ŁA�e�����m���Ԃ��荇���A�o�ϓI�ȃu���b�N�����i�s���A���ɂ͐푈�ɂ��ȊO�A�܂�͔e���̓��s�Ƃ������@�ł������������邱�Ƃ��ł��Ȃ��������炾�B �@���܋N�����Ă���O���[�o���Y���Ƃ́A���̒鍑��`�̎���ɂ�����R�ɑ����āA��Ƃ��A���E�o�ς��ĕ������Ă䂭�����ł���Ƃ����邩������Ȃ��B������̘J���́A�Q�����}�[�P�b�g���Œ艻�A�A��������Ƃ����`�ŁA��Ƃ��������Ă����B
�@
�@�u�O���[�o���[�[�V�����͒N�̎�ɂ������Ȃ��R���g���[���s�\�Ȍo�ό��ۂŁA�ւ��҂��ׂĂ͂���ɉe�����A�����āA���܂��ܓK�ȏ������ł��Ă����҂��������̉��b���邱�Ƃ��ł���̂��ƍl����l������v �i�w�E�H���}�[�g�ɓۂ݂��܂�鐢�E�x�j
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AB%E5%91%91%E3%81%BF%E3%81%93%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%82%8B%E4%B8%96%E7%95%8C-%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%9E%E3%83%B3/dp/4478000905
���傤�ǂ����]�������Ă���{�̒��ŁA���̒��҃`���[���Y�E�t�B�b�V���}���������Ă���B�s���`�Ƃ����A�O���[�o���Y���Ƃ����A���̉Q���ɂ�����̂ɂƂ��ẮA���ꂪ����̒��̉ߒ��I�ȃV�X�e���ł���ƍl������́A���ɂ̎p�ł���ƍl���₷���B�r�W�l�X���������A����I�Ȏ��Ԃ̒��ł̑������肵���ł��Ȃ�����ł���B
�u���v�Ȃ����Đ����Ȃ��v��
�u���������ׂẲ�����Ȃ����v �Ƃ����@�����A����I�Ȏ��Ԃ̒��ł����Ӗ����������Ȃ��B�����������X���[�K���́A�����̐^������������킷�Ƃ������́A���݂̃V�X�e�����A�����ٌ�Ȃ����͋������邽�߂Ɍ��킹�Ă���̂��Ǝv�����ق����悢�̂ł��� http://plaza.rakuten.co.jp/hirakawadesu/diary/200708250000/
�鍑��`�E�����`�E�O���[�o���Y��
�@�鍑��`�͈��ŁA�����`�͑P�A�����ď����O�܂ŃO���[�o���Y���͐����������ƌ����̂��A�ǎ��h�̐l�̔F���ł���B�����āA�鍑��` vs �����`�̐킢���A����E���ŁA���`���������̂��ƌ����̂��펯�ƂȂ��Ă���B�������A���̐}���̒��ɂ͖Y����Ă���ƌ������A�B������Ă���d�v�Ȏ������B����Ă���B
�@�鍑��`�������`���O���[�o���Y�����v���C���[���Ⴄ���߂Ɉꌩ�Ⴄ�ړI�������̂��ƍl����ꂪ�������A���ҁi�Əo�����j���Ⴄ�����ŁA�ړI��15���I��������Ă��Ȃ��Ƃ������Ȃ̂��B���҂�o�����͑����Ă��������s�傪�|���Ă���ŋ��i���[���b�p�̋��s�傪���X�`���C���h�ŁA�A�����J�̓��b�N�t�F���[�j�ɉ߂��Ȃ��ƕ�������ۋ��Z���{�Ƃ������̂��ǂ��������̂��͎����Ɩ��炩�ɂȂ��Ă���̂��B�X�I�Ƀ��_���ƌ������t���g���������邪�l��Ƃ��Ẵ��_���ł��A�C�X���G���ɏZ��ł���l�B���w�����̂ł������B���������A�����ȃ��_���l�Ȃǖ{���͑��݂��Ȃ��ƍl����ׂ��Ȃ̂��B ���s�j�ςɎ���ꂽ�l�B���猩��Β鍑��`�ƌ����ΐ������i���ƈɁj�̎��ɂȂ�̂��낤���A���풆�̍ő�̒鍑�͊ԈႢ�Ȃ���p�鍑���������A���{����̂����n��̑����͑���{�鍑�ł͖������[���b�p�̗̐A���n�������B�A���n�������Ă���ƌ������́A�t�����X��I�����_�����R�鍑��`���ƂŁA�鍑��`��ᔻ���Ă����A�����J�����ăt�B���s�����i���B��ᔻ�����A�����J�����Ę��S�������g���ăt�B���s����A���n�����Ă����̂��j���Ă������h�Ȓ鍑��`���������̂��B �@�v����ɐ폟�����P���Ƃ���Β鍑��`�͈��ł͖��������������͌���I�Ɉ����鍑��`�������ƍl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ł́A���̒鍑��`�͈��ƂȂ����̂��낤���B����E���ň��̒鍑��`���Ƃ��ӎU�������������ł͖����A�����̐A���n���Ɨ����A���[���b�p���鍑��`�𑱂����Ȃ��Ȃ�鍑��`�ł͋��ׂ����o���Ȃ��Ȃ������爫�ɂȂ��Ă��܂��������̘b�Ȃ̂��B����͖����`�ƒ鍑��`�̐킢�ƌ����Ă��邪�A�Â��鍑��`�ƐV���̒鍑��`�̐킢�ɉ߂��Ȃ������̂ł���B���̗����̒鍑����Ă��X�|���T�[�͓��C���h��Ђ̃I�[�i�[�������A���i���X�`���C���h�j�������̂��B �@�����`�i���{��`�j�̕��͂ǂ����낤�B�鍑��`�������Ȃ������ƂɓG�����̂͋��Y��`�������B�h�C�c����{�ƌ����r�b�O�v���C���[�i�����͂Ȃ�����肠���������Ԑ푈�̑�����o����ƌ����Ӗ��j�����Ȃ��Ȃ������ɂ́A���Y��`�ƌ����킪�傫������Ă����B �@�G���鑊�肪���Ȃ����ɂ͐��̒��͕��a�łȂ�������Ȃ����A���a�ł͋��ׂ��͏o���Ȃ��B���I�푈�œ��{�ɉ��S�i�V�t��ʂ��ă��X�`���C���h���x���j���A�����ɋ��Y��`�҂����i���͘J���҂ł͖������X�`���C���h�Ɏ�������ꂽ�M���K�����j�̓\�r�G�g�ƌ������������A�����`���ƂƓn�荇����悤�ɂȂ����B���ƌ��������킢�i�j������������������A�j����̌����͒N���x�z���Ă�������Y��Ă͂����Ȃ��j��������ꂽ���A�A�t�K�j�X�^���ƌ����Ύ���c���\�r�G�g�͕������A����͉Ύ킪�o��������ł����āA�����`����������������ł͂Ȃ������̂��B �@�A�t�K�j�X�^���N�U�ƌR�g�����Ŕ敾�����\�r�G�g�͏����ĂȂ��Ȃ�A���E�͕��a�ɂȂ锤���������A�C���N�ɂ��N�F�[�g�N�U�ƌ����o���߂��̃V�i���I�Œ��ߓ����Ζ�ɂ̖�ڂ��ʂ����Ă��ꂽ�B�����A���u�Ɨǂ��A���u�A�A���u�ƃC�X���G���A�p���X�`�i�ƃC�X���G���Ƒ����̎�͂�����ł����邪�A���b�N�t�F���[�́A911�������ɃC���N�ƃA�t�K�j�X�^���i�ǂ�������b�N�t�F���[�̃e���g���[�j�ɐ킢���d�|���ċ��ׂ��̎�ɂ��A�I�C���}�l�[���i���邽�߂Ƀh�o�C�Ȃǂ̑����Ɏ������W�߂邽�߂ɋ��Z�o�u�����d�|���Ă����̂��A�����̑O�܂ł̘b�������B���ǁA���E�̋��Z�����ۂɋ������Ă��郍�X�`���C���h�ɂ͓G��Ȃ������̂����Ȃ̂ł���B�O���[�o���Y�����A�v�͋��ׂ��̂��߂̈ꎞ�I�ȓ�������̂��B ���_�F���̒��ɐ��������`�咣��C�f�I���M�[�ɐ����������������B����ׂ����i�Ƃ��ċ@�\���Ă�����͑P�ŁA�����łȂ��Ȃ�Έ��ɂȂ邾���̘b�Ȃ̂��B�_�����[�}�鍑�̌�p��s�Ƃ����[�c�̃��X�`���C���h�́A�p�������ł͖������[���V�A����A�t���J�S�̂��x�z������Z���{�̑������߁B�k�Ă���̂̃��b�N�t�F���[���o��ɉ߂��Ȃ��i�\�ʓI�ɐ��60�N�ȏ�ŋ��Ɍ��������j�͎̂d�����Ȃ��B�C�f�I���M�[�ȂǂƂ����F�ዾ���O���A���̗��������ΐ��̒��̎d�g�݂͔��ɒP���Ȃ̂ł���B http://maimaikaburi.blogspot.com/2009/01/blog-post_1042.html �}���N�X�͎��{��`�ɂ��Ă͐��������� 2011/11/05 (Sat) 22:40:26
�@�J�[���E�}���N�X�͋��Y��`�ɂ��Ă͊Ԉ���Ă������A���{��`�̑啔���ɂ��Ă͐����������A�ƃW�����E�O���C�͏����Ă���B
�@���Z��@�̕���p�Ƃ��āA�܂��܂������̐l�X���J�[���E�}���N�X�͐����������ƍl���n�߂Ă���B19���I�̈̑�ȃh�C�c�l�N�w�ҁA�o�ϊw�҂ł���v���Ƃ́A���{��`�͍��{�I�ɕs����ł���ƐM�����B�@���{��`�ɂ́A���傫�ȃu�[���Ɣj�ł����o���X�����r���g�C������Ă���A�����I�ɂ͎������g��j��ɂ������Ȃ��Ƃ����̂��B �@�}���N�X�́A���{��`�̎��ł����}�����B�ނ́A��O�I�Ȋv�����N����A��萶�Y�I�ł͂邩�ɐl�ԓI�ȋ��Y��`�V�X�e������������Ɗm�M���Ă����B �@�}���N�X�́A���Y��`�ɂ��Ă͊Ԉ���Ă����B�ނ��\���I�ɐ����������̂́A���{��`�̊v���̂Ƃ炦���ɂ����Ă������B�ނ́A���{��`�ŗL�̕s���萫�𗝉����������ł͂Ȃ��\�\�������A���̓_�Ŕނ́A�����́A�܂����݂̑命���̌o�ϊw�҂����s�������̂����B �@�����Ɛ[���}���N�X�����������̂́A�ǂ̂悤�ɂ��Ď��{��`���������g�̎Љ�I��Ձ\�\���Y�K�� the middle-class �̐����l���\�\��j�邩�A�Ƃ������Ƃ������B�u���W���A�W�[�ƃv�����^���A�Ƃ����}���N�X��`�҂̗p��͌Â������������Ă���B �@�������A���{��`�͒��Y�K�����̌������}�����ꂽ�J���҂̕s����ȑ��݂Ɏ�����Ԃɂ��Ƃ������ƃ}���N�X���咣����Ƃ��A�ނ́A�����̐����̕ω���\�����Ă����B����́A���܂���ꂪ�����������Ă�����̂��B �@�ނ́A���{��`���A���j������Ƃ��v���I�Ȍo�σV�X�e���Ƃ��ĕ`���o�����B���{��`������ȑO�̌o�σV�X�e���ƍ��{�I�Ɉ���Ă��邱�Ƃ͋^�����Ȃ��B �@��E�̎斯�́A����N�����̐�������葱���A�z��͒����ɂ킽���čk���A�����Љ�͉����I���������B���ɁA���{��`�́A���ꂪ�G�����̂��ׂĂ�ω�������B �@���{��`�́A�₦���ω����邾���ł͂Ȃ��B��ƂƎY�Ƃ́A�v�V�̐₦���闬��̂Ȃ��őn������j��A���̈���ŁA�l�ԊW�͉�̂���V�����`�ԂōČ�����B �@���{��`�́A�n���I�j��̃v���Z�X�Ƃ��ĕ`����Ă����B���{��`�������قǐ��Y�I�ł��������Ƃ͒N���ے�ł��Ȃ��B���ہA���݂̃C�M���X�ɕ�炷�N�����A���{��`�����݂��Ȃ������ꍇ�Ɏ���Ă����ł��낤�������������̎����Ă���B
�ے�I�ȋA��
�@���́A�v���Z�X�̒��Ŕj��Ă������܂��܂Ȃ��̂̂Ȃ��ŁA���{��`���ߋ��ɂ����Ĉˋ����������l����j�Ă������Ƃ��B �@���{��`�̗i��҂����́A���̂悤�Ɏ咣����B���{��`�͂�����l�ɗ��v����邪�A����́A�}���N�X�̎���ɂ̓u���W���A�W�[�\�\���{�����L���A�����ɂ����ēK�Ȑ����̈��S�Ǝ��R���������肵�����Y�K���\�\�������������̂��A�ƁB �@19���I���{��`�ɂ����ẮA�命���̐l�X�͉��������Ȃ������B�ނ�́A�����̘J�����Đ��������B�s�ꂪ�������ƁA�ނ�͌����������ɒ��ʂ����B�������A���{��`�����W����ɂ�āA�܂��܂������̐l�X���������痘�v����ɂ��邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ邾�낤�\�\���{��`�i��҂����͂��������B �@�ւ�ׂ��L�����A�́A���͂�A�����̓����ł͂Ȃ��Ȃ邾�낤�B���͂�l�X�́A���������A�s����Ȓ����ŋ�J���Đ������邱�Ƃ͂Ȃ����낤�B���~�A���g�����L����Ɖ�����ё����ȔN���ɂ���ĕی삳��A�ނ�́A���O�Ȃ��ɐ����v���邱�Ƃ��ł��邾�낤�B�����`����ѕx�̊g���ƂƂ��ɁA�N�����u���W���A�I����������ߏo�����K�v�͂Ȃ��Ȃ�B�N�������Y�K���ɂȂ��̂��B �@���ۂɂ́A�C�M���X��A�����J�A���̑��̐�i���ł́A�ߋ��Q�A�R�O�N�Ԃɂ킽���āA���̂��Ƃ��N�����Ă���B�d���̈���͑��݂��Ȃ��B�ߋ��̐E�Ƃ���́A�قƂ�Ǐ��������āA���U�ɂ킽��L�����A�Ƃ������̂͂قƂ�NjL���ł����Ȃ��B �@�����l�X���Ȃ�炩�̕x�������Ă���Ƃ���A����͉Ƃ̒��ɂ��邪�A�Z��i�͂˂ɏ㏸����킯�ł͂Ȃ��B���܂̂悤�ɐM�p���^�C�g�ȂƂ��ɂ́A�ނ�͐��N�Ԃɂ킽���Ē���邾�낤�B���K�ɕ�炷���Ƃ̂ł���N�������Ăɂł���l�͂܂��܂������h�ɂȂ��Ă���A�����͏\���Ȓ��~�������Ă͂��Ȃ��B �@�܂��܂������̐l�X���A�����̂��Ƃ��قƂ�Ǎl���邱�Ƃ��Ȃ��A���̓��邵�����Ă���B���Y�K���̐l�X�́A�ނ�̐����������������W�J����ƍl�������̂������B�������A�l�����A�Ōォ���������Ă����X�e�[�W�̘A���Ƃ݂Ȃ����Ƃ́A���͂�s�\���B �@�n���I�j��̃v���Z�X�̂Ȃ��ŁA��q�͊O����Ă��܂��A�܂��܂������̐l�����ɂƂ��āA���Y�K���ł��邱�Ƃ́A���͂�l���̖ڕW�ɂ����Ȃ�Ȃ��Ȃ��Ă���B
���X�N�킳���l
�@���{��`�����W����̂ɂ�āA����͑命���̐l�X���A�}���N�X�̌����v�����^���A�K���̕s����ȑ��݂̐V�o�[�W�����ւƒǂ��Ԃ����B���݂̎����͂͂邩�ɍ������A������x�́A���̕������Ƃ̖��c�ɂ���ďՌ��������Ă�����B
�@�������A�����͎����̐l���R�[�X���قƂ�nj��ʓI�ɃR���g���[�����Ă͂��Ȃ��B�����͕s���肳�̂Ȃ��Ő������Ȃ���Ȃ炸�A���̕s���肳�́A���Z��@�ɑΏ����邽�߂ɂƂ�ꂽ����ɂ���Ĉ����������Ă���B�����㏸�̂��Ƃł̃[�������́A���Ȃ��̃J�l�Ƀ}�C�i�X�̕�V�������炵�A�₪�Ă��Ȃ��̎��Y�点��Ƃ������Ƃ��B �@�����̎�҂̏͂����ƈ����B�K�v�ȃX�L����g�ɂ��邽�߂ɂ́A���Ȃ��́A�؋���w����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������̓_����A���Ȃ��͒��~�ɓw�߂�悤�ɍČP������Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B�������A�����o���_����؋���w�����Ă�����A���~�́A���Ȃ��ɂł���Ō�̂��Ƃ��B���ł���A�����A�命���̐l�X�����ʂ��Ă���\���́A�s����Ȑ����ł���B �@���{��`�́A�l�X����u���W���A�I�����̈��S��D�����̂Ɠ����ɁA�u���W���A�I�����𑗂��Ă����悤�ȃ^�C�v�̐l�X���ł����Ă����B�P�X�W�O�N��ɂ́A�r�N�g���A���I���l�ς̂��Ƃ�������Ɍ���ꂽ�B�����āA���R�s��̑��i�҂����́A���ꂪ�������ߋ��̌��S�Ȕ����ɘA��߂����낤�Ǝ咣�������̂������B �@�����̐l�X�ɂƂ��āA���Ƃ��Ώ�����n���҂ɂƂ��āA�����r�N�g���A���I���l�ς́A�ނ�̌��ʂɂ����ĂقƂ�ǖ��Ӗ��Ȃ��̂ɂȂ������낤�B�������A���傫�Ȏ����́A���R�s�ꂪ�u���W���A�I�������x�����������@��������������邱�Ƃ��B �@���~���Z���ĂȂ��Ȃ��Ă䂭�Ƃ��A���f����́A�j�łւ̓��ɂȂ邩������Ȃ��B��������؋������āA�j�Y�鍐���邱�Ƃ�����Ȃ��l�����������c��A�����ւނ����̂��B �@�s��̗͂ɂ���Ď����I�ɕω���������Љ�ł́A�`���I���l�ς͏�肭�@�\�����A����ɂ���Đ������悤�Ƃ���l�͒N�����K���N�^�̎R�ɂ��ǂ蒅�����ꂪ����B ����ȕx �@�s�ꂪ�l���̂��ׂĂ̋Ȃ���p�ɐZ������������W�]���āA�}���N�X�́A�u���Y�}�錾�v�ŁA�u���ׂĂ̌Œ肵�����̂͏�������v�Ə������B�r�N�g���A�������\�\�u�錾�v��1848�N�ɏo�ł��ꂽ�\�\�̃C���O�����h�ɐ�������҂ɂƂ��ẮA����́A�����قlj����܂Ō��ʂ����ώ@�������B �@�����A�}���N�X�����������Љ�̎������ȏ�ɌŒ�I�Ɍ��������̂͂Ȃ������B�ꐢ�I���̂̂��A�����́A����ꎩ�g���A�ނ��\���������E�ɂ��邱�Ƃ�����B�����́A������l�̐������b��I�ňꎞ�I�ł���A���ł��ˑR�̔j�ł��N���肤�鐢�E���B �@�����킸���Ȑl�X����������ȕx��~�ς��Ă������A����͂͂��Ȃ��A�����Ă��͗H��̂悤�Ȑ����������Ă���B�r�N�g���A������ɂ́A�ƂĂ��Ȃ��x�҂́A���������̂��J�l���ǂ��������邩�Ƃ����_�ŕێ�I�ł��肽����A���낢�ł������邱�Ƃ��ł����B�f�B�P���Y�̏����̎�l�������́A�ŏI�I�ɂ́A��Y����ɓ���A���̌�͉i�v�ɉ������Ȃ��B �@�����A�����n�͂ǂ��ɂ����݂��Ȃ��B�s��̋}���ȕϓ��́A�킸�����N��ł���A�������l�������Ă��邩�m�邱�Ƃ��ł��Ȃ��قǂ��B �@���̂悤�ȉi�v�ɋx�����邱�Ƃ̂Ȃ���Ԃ́A���{��`�̉i���v���ł���A���{��`�́A�����I�ɍl���������̂ǂ�Ȗ����ɂ�����A��Ă䂱���Ƃ��Ă���̂��ƍl����B �@�ʉ݂Ɛ��{�́A����ꂪ�����ƈ��S���Ǝv���Ă������Z�V�X�e���̂��܂��܂ȕ����ƈꏏ�ɁA�قƂ�ǔj�ł��������Ă���B������3�N�O�ɐ��E�o�ς𓀂�����鋰��̂��������X�N�́A������̂܂܂��B���X�N�͍��Ƃɂ�����ꂽ�������B �@�����Ƃ������A�Ԏ���}������K�v�ɂ��ĉ��������Ă��A���͕ԍςł��Ȃ��قǂ̃X�P�[���Ŗc��オ���Ă���B ����炪�c��オ��v���Z�X�́A�����̐l�X�ɂƂ��Ēɂ݂��Ƃ��Ȃ��A�����̐l�X���n�����Ȃ�v���Z�X�ƌ��т��Ă���B �@���ʂ́A���ɑ傫�ȃX�P�[���Ō������N����Ƃ����ȏ�̂��̂ł������肦�Ȃ��B�������A ����͐��E�̏I���ł͂Ȃ����낤�B���邢�͎��{��`�̏I���ł����Ȃ����낤�B�����N���낤�ƁA�����́A�ˑR�Ƃ��āA�s�ꂪ�Ƃ��͂Ȃ��Ă��� �}�[�L�����[�i���Ƃ̐_�l�j�̃G�l���M�[�ƂƂ��� �����Ă䂭�����Ȃ����낤�B �@���{��`�́A�v���ɓ����Ă������A����̓}���N�X�����҂����悤�Ȋv���ł͂Ȃ��B�R����悤�ȃh�C�c�l�v�z�Ƃ̓u���W���A�I�����������A���Y��`�������j�邱�Ƃ����҂����B�����āA�ނ��\�������Ƃ���A�u���W���A�I���E�͔j�ꂽ�B�@�������A���Y��`�ɐȂ��������̂ł͂Ȃ��B���{��`���u���W���A�W�[���E���Ă��܂����̂��B
http://www.asyura2.com/11/senkyo121/msg/726.html �y�ؑ��z�u�o�ϊw���w�ԗ��R�́A�o�ϊw�҂��x����Ȃ����߂ł��v
�u�o�ϊw���w�ԗ��R�́A�o�ϊw�҂��x����Ȃ����߂ł��v�ƌo�ϊw�҃W���[���E���r���\���͌x������ƌ����Ă��܂��B
�o�Ϙ_���́A����ȑO������̉��Ő��藧�����ɂ����܂���B ����u�����y�U�̒��v�ł̘b�ł��邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł��i�w�����Ƃɓy�U�̍L���͈قȂ�܂����j�B �������A���Ԃɂ͌o�ϊw�̌��������������o�ς̕��͂ɒ��ړK�p���悤�Ƃ���o�ϊw�҂�G�R�m�~�X�g�����₿�܂���B �ޓ��́A�o�ϊw�Ƃ����y�U�̒��̗����ŁA�����o�ςƂ����y�U�̊O�̘b��_����Ƃ����߂���Ƃ��Ă��܂��B �����܂ł��Ȃ��A�����o�ς͌o�ϊw�̗v������O����������Ă���܂���B
����䂦�����o�ς�_����i�y�U�̒��ɓ����j���߂ɂ́A�O��������ɂ߂�i�y�U���g����j���Ƃ��K�v�ł��B �������ߎ��̎w������o�ώЉ�w�͂���ɂ�����܂��B �������A���݂̎嗬�h�o�ϊw�i�V�ÓT�h�o�ϊw�̌�p�̏��w���j�́A�y�U���������邱�Ƃɐ�S���Ă����܂����B ���̌��ʁA�o�ϊw�ƌ����o�ς̋����͂܂��܂��J���Ă������̂ł��B �o�ϊw�҂̌o�ϔF���ƌ����o�ς̃Y�����g�債�Ă���ȏ�A���͂�o�ϊw�҂̌������̂܂ܐM���Ă͌����o�ς̓���������邱�ƂɂȂ�܂��B �ޓ��̒ʂ�Ɍo�ϐ����{���ꂽ��A�����o�ς͂����ւ�ȍЖ�i�l�Ёj���邱�ƂɂȂ��Ă��܂��̂ł��B �{���́A�o�ϊw�̌����������Ύ����邱�ƁA�������͂���Ɋ�Â������o�ς�F�����邱�Ƃ̊댯���ɂ��ċ�̓I�ɂ��b���������Ǝv���܂��i���ʂ̊W�œ��ɕ����܂��j�B �o�ϊw�̌��������̋�̓I�ȑ�ނƂ��āA�����ȃj���[�E�P�C���W�A���̊w�҂ł���O���S���[�E�}���L���[�̒���u�o�ϊw�̂P�O�匴���v�̂����}�N���o�ςɒ��ڊւ���̌��������グ�܂��B ���Ȃ݂ɂP�O�匴���́A�}���L���[�̐��E�I�ȃx�X�g�Z���[�ł��钘���w�o�ϊw�����x�Ɏ�����Ă�����̂ŁA���̖M�w�}���L���[�o�ϊw�x�͌o�ϊw�̋��ȏ��Ƃ��ėL���ł��̂ŁA�����m�̕��������Ǝv���܂��B ������グ��̂́A�u���{�������s��������ƕ����͏オ��v�Ƃ����ݕ��Ɋւ��錴���ŁA����́u�Љ�̓C���t���Ǝ��Ƃ̊Ԃ̒Z���g���[�h�I�t�W�ɒ��ʂ��Ă���v�Ƃ��������Ńt�B���b�v�X�Ȑ��Ɋւ��錴���ł��B ����������t���h�̌o�ϊw�҂̈ˋ����闝�_�I��Ղł��ˁB �����̌����i����Όo�ϊw�҂̌o�ϊρj�Ō����o�ς�F������͕̂s�K�ł��邱�Ƃ�������܂��B �ȑO�A���̃R�����ŎO�����ݕ��̒�`�ɂ��Ă̘b������Ă��܂����B
http://www.mitsuhashitakaaki.net/2015/09/28/ ���̋L���̒��ŋ����[�������̂́A�ݕ��i���̏ꍇ�͒ʉ݁j�̒�`���߂����c�K�v�j���i�����╛���فj�ƎO������̂����ł��B ��c���́u�ݕ��̓}�l�^���[�x�[�X�i�����j�v�ƍl���A�O������́u�ݕ��̓}�l�[�X�g�b�N�i�����v���X�a���j�v�ƍl���Ă���܂����B ���́A���̂����̒��Ɂu�o�ϊw�ɂ�����ݕ��̒�`�v�Ɓu�����o�ςɂ�����ݕ��̒�`�v�̑��Ⴊ����ł���̂ł��B �������A��c���͑O�҂̗���A�O������͌�҂̗���ł��B ���̉ݕ��̒�`�̈Ⴂ�𗝉����邽�߂ɂ́A�����o�ς̊�{�\����m��K�v������܂��̂ŁA�ȒP�ȃC���[�W�������Ă����܂��B �����o�ς́u���{�����v�Ɓu���ԁi�o�ρj�����v���琬�藧���Ă���A���ꂼ��̃����ɂ͂Q���̉Ƃ������Ă���ƍl���Ă��������B ���{�����̂Q���́A�u�e�i���{�j�v�̉ƂƁA�u�q�i����j�v�̉Ƃł��B ���ԃ����̂Q���́A�u��s�v�̉Ƃƌl�Ɗ�Ƃ���炷�u���̌o�ρi���Ԕ���Z����j�v�̉Ƃł��B �o�ϊw�̎x�z�I�ȉݕ��ς́A�u�ݕ��͖��Ԍo�ς̊O�ő�����v�ƍl����O���I�ݕ������_�ł��B ���̓_�Ɋւ��Ă̓P�C���Y�o�ϊw���}�l�^���Y���i�V�ݕ����ʐ��j�������ł��B
���Ȃ킿�A�ݕ��͐��{�����̑��錻���i�}�l�^���[�x�[�X�������̓x�[�X�}�l�[�j�ƒ�`����܂��B ���ԃ����Ō�����ۗL���Ă���̂́A��s�Ǝ��̌o�ςɏZ�ތl�Ɗ�Ƃł�����A���̍��v�z���ݕ��ʂƍl���Ă���̂ł��B
���Ȃ݂ɋ�s�͕ۗL���錻�����u�����v�Ƃ��ē���ɗa���Ă���܂��i���ⓖ���a���j�B �����A�}�l�[�X�g�b�N�́u���̌o�ϓ��ŕۗL����Ă��錻���Ɨa���̍��v�z�v�Ƃ��Ē�`����܂��B �����ɂ͌����ɉ����āA���ԓ����ŋ�s�ɂ���đ�����u�a���ʉ݁v���܂܂�Ă��܂��B �����܂ł��Ȃ��A�}�l�[�X�g�b�N�̓����A���ɍ����̍��T�[�r�X�̍w���Ɏg����J�l�̗ʁi�A�N�e�B�u�}�l�[�j�̓������i�C�����i���̌o�ς̋K�͂̕ϓ��j�ɒ��ڊW���Ă��܂��B �t�ɁA��s�̌����ۗL�ʂ̕ϓ��͌i�C�ɒ��ڊW������̂ł͂���܂���B ���ߏ������������悤�ƁA�Z���������邩�ۂ��͌i�C�Ɉˑ����邩��ł��B ����䂦�A���̌o�ς̓���������w�W�Ƃ��ăx�[�X�}�l�[���}�l�[�X�g�b�N���d������͎̂��R�Ȃ��Ƃł��B ����ł͂Ȃ��x�z�I�Ȍo�ϊw�̉ݕ��̒�`�ɂ́A�a���ʉ݂��܂܂�Ă��Ȃ��̂ł��傤�B ��Ɏ����������o�ς̊ȗ��C���[�W���v���o���Ă��������B �l���Ɓi���̌o�ρj�ۗ̕L����a���Ƃ́A�u�a������v�Ƃ������̂����Ă���܂����A���ۂ͋�s�ւ́u�݂��t���v�̂��Ƃł��B ���Ȃ킿���̌o�ς̗a���i���Y�j�́A��s�ɂƂ��Ă̓��z�̕��ł���A���Ԍo�ϓ��ō��v����Ə��z�Ƃ��ă[���ɂȂ��Ă��܂��̂ł��B ���̏ꍇ�A���ԃ����Ŏ��Y�i�w���́j�Ƃ��Ďc��̂͌��������ƂȂ�܂��B ���̂悤�Ɍo�ϊw�̊�{�I�ȍl�����́A�P���Ɂu���{�v�Ɓu���ԁv��Λ������邾���ŁA�e����̓����i�Q���̉Ƃ̑��݁j�ɂ܂œ��@�������Ȃ����߂ɁA�ǂ����Ă������o�ς��l����ꍇ���ꗂ��o�Ă��܂��̂ł��B �������A�o�ϊw�̉ݕ��̒�`�ƌ����̂��ꂪ�قȂ��Ă��悤�ƁA���҂��֘A�Â���T�O������܂��B ���ꂪ�}�l�[�X�g�b�N�i�l�j�ƃx�[�X�}�l�[�i�g�j�̔䗦�Ƃ��Ē�`�����u�ݕ��搔�i�l�^�g�j�v�ł��B ���̉ݕ��搔�̒l�����̒l�Ƃ��Ĉ��肵�Ă���Ȃ�A�u�ݕ��Ƃ͌����̂��Ƃ��v�Ƃ���o�ϊw�̒�`�������ɓK�p���Ă����͂Ȃ��Ȃ�܂��B ���̏ꍇ�A�x�[�X�}�l�[�ƃ}�l�[�X�g�b�N�̊ԂɈ��̔��W����Ɉێ�����܂��i�ݕ��搔�̒�`�������ʎ��Ɖ��߂���j�B �Ⴆ�A�ݕ��搔���V�ň��肵�Ă���A�x�[�X�}�l�[���P���~���₵�����A�}�l�[�X�g�b�N�͂V���~�����邱�ƂɂȂ�A���{�̓x�[�X�}�l�[�̗ʂ𑀍삷�邱�ƂŃ}�l�[�X�g�b�N�𐧌䂷�邱�Ƃ��\�ɂȂ邩��ł��B ���ہA��c���́A���˂Ă���x�[�X�}�l�[�ɂ��}�l�[�X�g�b�N�̐���͉\�Ƃ���w��I���������Ă���܂����i�o�ϊw�̋��ȏ��̗���j�B �x�[�X�}�l�[�ɂ�鐧�䂪�\���ۂ��Ɋւ��āA�ȑO�A�ނ͓�������ɏ������Ă������M�Y���Ɓu��c�E���_���v���N���������炢�ł��B ����䂦�A��c�����A�O������ɖ��ꂽ���A�u�ݕ��̒�`�̓}�l�^���[�x�[�X�v�Ɠ������̂́A���R�ł��傤�B �������A��c���̋��ق́A�����o�ς�O��Ƃ���ΐ��藧���܂���B �ݕ��搔�́A�i���Z����̌��ʂƂ��āj�u����I�ɎZ�o�����g�Ƃl�̔䗦�v�ɉ߂��Ȃ��̂ł��B ���O�Ɍ��܂��Ă��鐔�l�i�p�����[�^�[�j�ł͂���܂���B ���̂��Ƃ́A���{���疯�Ԃ����𒍓�����o�H���l����Ηe�Ղɂ킩��܂��B ����̗ʓI�ɘa����l���Ă݂܂��傤�B ����͖��ԃ����̋�s�ۗ̕L���鍑�����A������n���܂��B �������A���̌o�ςɌ�����n���Ă���킯�ł͂���܂���A�}�l�[�X�g�b�N�͑����܂���B �Ȃ��Ȃ�A�u�x�[�X�}�l�[�Ƃ��Ē�`����錻���i���ԕۗL�̌����j�v�Ɓu�}�l�[�X�g�b�N���\�����錻���i���̌o�ϕۗL�̌����j�v�́A����ł͂Ȃ�����ł��B ��q�����悤�ɁA�}�l�[�X�g�b�N�̒�`�̒��̌����ɋ�s�ۗL���͊܂܂�Ȃ��̂ł��B ���̂��Ƃ����F�������A�����M���b�v���������Q���C���t����ڎw���Ƃ���ʓI�ɘa��̌��E�͂��̂����疾�炩�ł��傤�B �m���Ƀx�[�X�}�l�[�𑝂₷���Ƃ͏o���܂��i�ʓI�ɘa��Ƃ́A��s�ۗL�̌����𑝂₷����ł�����j�B �������A�}�l�[�X�g�b�N�𑝂₷�ɂ͋�s�ɂ����̌o�ςւ̗Z�����K�v�Ȃ̂ł��B�������A�Z���̑O��͎��̌o�ς̎������v�ł��B ������s���Y����������l���`���������ł͂Ȃ��A�i�i�C���g�̂��߂ɂ́j�����̎��������ւ̗Z���̑������K�v�Ȃ̂ł��B ������ʓI�ɘa�͌p������܂�����A�ݕ��搔�͉����葱���邱�ƂɂȂ�܂��B
����̓x�[�X�}�l�[�ɂ��}�l�[�X�g�b�N�̐��䂪�s�\�Ȃ��Ƃ̒[�I�ȏi�������j�Ȃ̂ł��B ���{���疯�Ԃ���������錻���I�o�H���l�����Ȃ��ǂ��납�A�Z�����̂�����̂��}�l�^���Y���ł��B ���́A��s�Z�����l������ƁA �u�ݕ��I�v���͎����I�v���ɉe�����Ȃ��v�A �ȒP�Ɍ����A �u���i���ω����Ă�����ʂ͕ω����Ȃ��v �Ƃ���}�l�^���Y���̗����i�u�ݕ��̒������v�j���j�]����̂ł��B �Z�����������Ƃ́A�����̕K�v�Ȃ��̂��������܂���B ����ɂ���Ēlj����v�̐���������̍��̉��i�͏㏸���܂�����A���Ή��i�̌n�i�����̌����䗦�j�͕ω����Ă��܂��̂ł��B ���̌��ʁA����ʂ��ω����܂��i�ݕ������I�ƂȂ�j�B �}�l�^���Y���́A�Z���̑���ɁA���̌o�ς֒��ڌ�����n���r�����m�Ȍo�H���l���܂����B ���ꂪ�u�w���R�v�^�[�E�}�l�[�v�ł��B �w���R�v�^�[�Ō��������̌o�ςւ�܂��̂ł��B ����͗Ⴆ�b�ƌ����Ă��܂����A���Ԃւ̉ݕ��̒����o�H�������Ȃ��}�l�^���Y���ɂƂ��Ă͋ɂ߂ďd�v�ȑO��Ȃ̂ł��B ����Ɍ������E�����ɂ��������������ۂ���܂��B �Ⴆ�A�P�O���̕����㏸��ڎw�����{�����Y�z�̌����Ԃɂ�܂��Ƃ��܂��B ���̂Ƃ��E�����́A���ݕۗL���Ă��錻���̂P�O�������E��Ȃ���Ȃ�܂���i����ȏ�ł��ȉ��ł������܂���j�B �����ďE�����l�B���A�E���O�Ɠ����n�D�i����p�^�[���j���ێ����Ă����Ƃ���ƁA���̎����߂āA�������P�O���オ��A������ʂ͕s�ςƂ����������̂ł��B �@���ł����B �o�ϊw�̗����́A�������O��������e���ΐ�������^���ł��邱�Ƃɋ^���͂���܂���B �������A���̏����������ɂǂ̒��x�Ó����邩���l�����ɁA���_�����̂܂e��Ă͂Ȃ�܂���B ���{�������s�������Ă��A������g��Ȃ���Ε����͏オ��܂���B ��s�ւ�������������n���Ă��A���̌o�ς̐l�X���������Ďg��Ȃ���Ε����͏オ��܂���B ���Ԃ��g��Ȃ��ł���Ȃ�A���{���g���i���������j���������͏オ��悤���Ȃ��̂ł��B ���r���\�����j�́A�u�o�ϊw���w�Ԃ��Ƃ́A�����Ɍo�ϊw�̌��E�i�K�p�͈́j��m�邱�Ƃł�����B����𗝉�������ŁA�o�ϊw�̌��������ɖӏ]����̂ł͂Ȃ��A�����o�ς̕��͂ɓK�������@��I�����˂Ȃ�Ȃ��v�ƌ������������̂�������܂���B
http://www.mitsuhashitakaaki.net/2015/11/07/aoki-20/ ���Y������K������鐢�E
http://www.mitsuhashitakaaki.net/2015/11/23/mitsuhashi-320/ ���E�T�[�r�X�͐��Y����A�K�������B �a���͕K���������A�����ɉ��B �@�l�ł�����������A�K����Ƃ̐ݔ�������������B �ٗp���͏�Ɋ��S�ٗp���������Ă���B ����������������A�K����Ƃ̓�����������B �בփ��[�g��������A�K���A�o��������B ���s����ƁA�������オ��A��Ƃ̐ݔ�����������A��������������B �f�t���E�p�̂��߂ɕK�v�Ȃ̂́A�}�l�^���[�x�[�X�̊g��ł���B �ʉ��i���ቺ���Ă��A�]�������J�l���K�����̍��E�T�[�r�X�̍w���ɉ�邽�߁A��ʕ����͏オ��Ȃ��B ���ݐ����������߂�A��������B ���Y������͏�ɐ������B ����łł��Ă��A�\���ȋ��Z�ɘa�i��`�s���j�����{����A�f�t���ɂ͂Ȃ�Ȃ��B
�ȂǂȂǁE�E�E�E�B
��L�A���݂̓��{�őS���������Ă��Ȃ��u�펯�v�́A�S�āu���鉼�݁v��O��ɂ��Ă��܂��B���Ȃ킿�A�Z�C�̖@���Ȃ�ʁu�Z�C�̉����v�ł��B
�Z�C�̉����B�u���������v�ݏo���v�Ƃ����o�ϊw�̊�{�ƂȂ�l�����Ɋ�Â��ƁA�o�ϐ����̂��߂ɂ͐��݂f�c�o�i�����\�́j�����߂�����Ƃ����b�ɂȂ�܂��B ���̂��߂ɂ́A�K���ɘa�A���R�f�Ղ𐄐i���A������������������B���{�̍����o���́A�s�v�Ȏ��v��n�o���邾���Ȃ̂ŁA�m�f�B �Ƃ����b�Ȃ̂ł����A��L�́u�f�t���[�V�����v�Ƃ������ۂ�z�肵�Ă��܂���B����ɁA�����̈��S�ۏ���������܂��B �����āA����I�Șb�Ȃ̂ł����A�Ȃ����f�t����́u�����v��L���ɂ��鐭��ł���A�t�ɋُk�����E�\�����v�i�K���ɘa�E���R�f�Ձj�Ƃ����C���t����́A�����ł͂Ȃ��ꕔ�̃O���[�o�������Ƃ���������ɂȂ��Ă��܂��̂ł��B �����Ō����O���[�o�������Ƃɂ́A�������ꕔ�̓��{�l���܂܂�Ă��܂��B ���݂̐��E�́A�f�t�����ɂ��ւ�炸�u�C���t����v�Ɋe��������ɂȂ�A�����������Ă��܂��Ă��܂��B���̍������ɂ́A���������A �u�ُk������\�����v�Ƃ����C���t���A�O���[�o�������Ƃ𗘂��鐭��ł���v �Ƃ�������������킯�ł��B
http://www.mitsuhashitakaaki.net/2015/11/23/mitsuhashi-320/ �鏑�̎d�����烊�J�[�h�̔�r�D�ʘ_���l���Ă݂�
�T���A�T�q�|�\�̘A�ڂŁA���R�f�_�҂����Ƃ��邲�ƂɎ����o���u���J�[�h�̔�r�D�ʘ_�v�ɂ��āA
�w�Ⴆ�A�M�҂̉�ЂɁu���M�v�Ɓu�M�҂̃X�P�W���[�����O�v�Ƃ����A���ނ̎d�����������Ƃ���i���ۂɂ���j�B�M�҂����M�A�X�P�W���[�����O�Ƃ�����̎d���ɂ����āA���ɔ鏑�������Y���������A������₷�������Ɓu���Ӂv�������Ƃ��悤�B ���̏ꍇ�A�M�҂͔鏑���ق킸�A���M�ƃX�P�W���[�����O�̓�̎d���������ł��Ȃ��ׂ����낤���B�����͂Ȃ�Ȃ��B�ق�ꂽ�鏑�́A�X�P�W���[�����O�Ɩ��͂��Ȃ��邪�A���M�Ɩ��͑S���ł��Ȃ��B���̏ꍇ�A���M�Ƃ����d������ɂ���ƁA�鏑�̓X�P�W���[�����O�Ɩ��ɂ����āA�M�҂����u��r�D�ʂɂ���v�Ƃ����b�ɂȂ�̂��B �Ƃ����킯�ŁA�M�҂͎��M�Ɩ��ɐ�O���A�X�P�W���[�����O�͔鏑�ɔC���������A�S�̂Ƃ��Ắu�d���̏����ʁv��������B�܂�́A�M�ҋy�є鏑�̘J�����Y�������܂邱�ƂɂȂ�B�x �ƁA������܂����B���J�[�h�̔�r�D�ʘ_���u���ƊԂ̖f�Ձv�ɓ��Ă͂߁A���u�o���ϖ��v���u�������ꍇ�A���ۂɂ͗l�X�ȏ����E������̂ł����A�����ɂ��Ă͏T���A�T�q�|�\�̘A�ڂ�����ǒ����Ƃ��āA��L�́u�M�҂Ɣ鏑�̗�v�ɂ��āA���������[���l���Ă݂܂��傤�B ���ہA���Ђł͎O�������M��u�����ɐ�O���A�X�P�W���[�����O�͔鏑���S�����Ă��܂��B���݁A�O���̃X�P�W���[���͕��G����ɂȂ��Ă��Ă���A�e�C�x���g�ɂ��ė������A���{�̌�ʃC���t����c�����A�h���{�݂��ǂ�����̂��A�n���u�����A�������ۂɂ͂ǂ����ړ�����ׂ����A��ʔ�̕��S�͂ǂ�����̂��A���n�ł̌�ʎ�i�͂ǂ�����̂��ȂǂȂǁA�l�X�ȃp�����[�^�𗝉����Ȃ���A�u���Y���̍����X�P�W���[�����O�Ɩ��v�͂ł��܂���B ���āA���݂̎O���̔鏑�����Ђ������_�ł́A�m���ɃX�P�W���[�����O�Ɩ��ɂ��Ă��A�O���̕������Y�������������̂ł��B�O�������Ђ̋Ɩ��ɂ��ďn�m���Ă���ȏ�A������O�Ȃ̂ł����B ���̌�A�鏑�͗l�X�Ȏd���̌o����ς݁A���݂̓X�P�W���[�����O�Ɩ��ɂ��āA�O�������u��ΗD�ʁi��r�D�ʁj�v�ȏɎ����Ă��܂��B������A�����A�����A���X�ɕ������ވ˗������A�X�P�W���[����g�ދƖ��𑱂��A�l�X�Ȍo����m�E�n�E���u�~�ρv�����킯�ł�����A����Ӗ��œ��R�ł��B ���̊ԁA�O���̓X�P�W���[�����O�Ɩ���S�����Ă��Ȃ��킯�ŁA�u�O���̃X�P�W���[�����O�Ɩ��Ɋւ��鐶�Y���v�́A�ԈႢ�Ȃ������Ă��܂��B �������������̂��Ƃ����A���Y���́u�d���̌o���̒~�ρv�Ƃ����l�ޓ����ɂ����サ�܂����A�t�Ɏd�������Ȃ��ƒቺ���Ă�������Ƃ����b�ł��B �O���̃X�P�W���[�����O�ɘb���i��A���܂�債���b�ł͂���܂���B�Ƃ͂����u���Ɓv�Ƃ������_�Ō����ꍇ�A�b�͂܂�ŕς���Ă��܂��B �Ⴆ�A���{�����u���퐶�Y�i���q���́u�����i�v�ƌĂт܂����j�v�u���R�ЊQ���̓y�E���݃T�[�r�X�v�u��ÃT�[�r�X�v���A�����̈��S�ۏ�Ɋ֘A���鐶�Y�ɂ��āu��r�D�ʂɂ��鑼���v�ɔC�����ꍇ�A�䂪���̈��S�ۏ�͂P�O�O���̊m���Ŏ�̉�����A�Ƃ����b�ɊԈႢ�Ȃ��Ȃ�܂��B ���m��T�[�r�X�̐��Y�̗́i�������\�́j�́A�d���̒~�ςɂ����シ��B�����ɁA�d���̒~�ς��S���s���Ȃ��ꍇ�A���Ƃ���u���Łv����B �Ƃ����A������O�̎�����F������A�u���R�f�Ղ͎��R��������i�|���������j�v�Ƃ������u�l�����v���A�����Ƀi�C�[�u�ł��邩��������͂��ł��B�����Ō����i�C�[�u�Ƃ́u�����v�ł͂Ȃ��A�u�c�t�v�Ƃ����Ӗ��������܂��B ���̎�̗c�t�Ȏ咣���A���������^���ł��邩�̂��Ƃ�������Ă���䂪���̌��_��ԂɁA�O���͊�@�����o����킯�ł��B
http://www.mitsuhashitakaaki.net/ 2016�N07��04��
�K���O���l2000���l���o�ς̓}�C�i�X�@�O���l�ό��͌o�ςɍv�����Ȃ� �O���l�����疜�l���Ă��A����Ōo�ϐ������邱�Ƃ͐�ɖ����B
http://livedoor.blogimg.jp/aps5232/imgs/a/5/a5a20193.png
�O���l�ό��q��2016�N�����������Ă��āA���̒��q�Ȃ�2000���l�B�����\���ƌ����Ă��܂��B
�����O���l�������瑝���Ă����{�̌i�C�͗ǂ��Ȃ炸�A�ނ���}�C�i�X�����ɂȂ��Ă���͉̂��̂ł��傤���B
����̃c�P��N�������H
���{�͖K���O���l��1000���l�����Ƃ��āA����2000���l�A���邢��3000���l���ƌ����Ă��܂��B 2011�N�̌������̂̌�A�����������K���q�͓��Ɉ����������n�܂���2013�N����A�ڂ����đ������܂����B ���{�́u�K���O���l���������͎̂����̎蕿���v�ƌ����Ă��āA����͕ʂɍ\��Ȃ��B
�����s�v�c�Ȃ̂͊O���l��2�{�ɐ����Ă����{�̂f�c�o���}�C�i�X�����Ȏ��ŁA�ނ���O���l��������قnjo�ς��������Ă���B
�K���O���l�������鎖�ƁA���{�̌o�ϐ����ɊW������̂��Ȃ��̂��A�c�_����܂���ł����B �F������O�̂悤�Ɂu�K���q��������Όo�ό��ʂ�����v�ƌ����Ă��邪�A�킽���͂����v���܂���B
�K���O���l���������g���̂́A�����̗��������ƗA�o�Ɠ����ŁA�Ⴆ�Ύ�����1��A�o�����200���~�̃h���������܂��B
���ۂ͌��ޗ���Ȃǂ�A�����Ă���̂�1��100���~�Ƃ��āA�O���l��5�l���炢�K������ƁA��ʔ�݂ł��̂��炢�g���܂��B �O���l���������g���̂�������{�ׂ͖����Ă���A�ƗA�o�_�҂͌����̂����A����͐�O����1980�N���܂ł̘b�ł��B
���̍��܂ł͒ʉ݂͎�����Œ葊�ꐧ�ŁA���{�����䎩���Ԃ�A�o���Ă��A1�h����360�~��200�~�ŌŒ肳��Ă��܂����B
�Ƃ��낪���{�̗A�o�ő呹�������A�����J�͂Ԃ���Ă��܂��A��������{�̑呠��b���m�x�ɌĂ�Łu��������ϓ����ꐧ�ɂ��邩��v�ƒʍ����܂����B ���ꂪ1985�N�̃v���U���ӂŁA�ȗ�30�N�ԓ��{�͂����Ɖ~���s���ŋꂵ��ł��܂��B
�����ꏊ�ŃN���N����邾���̃n���X�^�[�o��
f0189122_15113970
���p�Fhttp://pds.exblog.jp/pds/1/201209/15/22/f0189122_15113970.jpg
���{�̓n���X�^�[�o�ρH
�ϓ����ꐧ�ł͗A�o�������قlj~���ɂȂ�̂ŁA�A�o�Ŗׂ��鎩�̕s�\�ŁA�ނ���A�o����قǑ������܂��B �A�����J�̂悤�ȗA�����ߍ��̂ق����ׂ���悤�ɏo���Ă��āA���ׂ̈ɃA�����J�̓��[����ύX�����̂ł����B �ό��q���h�T�h�T����Ă��Ă������g���̂��������ŁA�ނ�̔������̂����ʼn~���ɂȂ�A�]�v�A�o��Ƃ��ꂵ�ނ����ł��B
�Œ葊�ꐧ�ł́u�A�o����قǖׂ������v���A�ϓ����ꐧ�ł́u�A�o����قǔ�����v�̂ł��B
2016�N�ɓ����Ē����V���b�N��C�M���X�V���b�N�ʼn~���ɂȂ�A�ꎞ99�~�ɒB���Ă܂��߂��Ă��܂��B �]�_�Ƃ̓C�M���X�̂d�t���E�̉e���ƌ����Ă��܂����A�������������ėA�o�Ɗό��q�̂����ʼn~���ɂȂ�̂ł��B
���{�̌o�ϐ�����݂�ƁA�~���ɗU�����ėA�o��ό��q�𑝂₵�Ă��邪�A�A�o����������K���~���ɂȂ�܂��B
�A�o�Ƃ̓h�����~�Ɍ�������ŁA�ό��q���h����l�������~�Ɍ������A�ی��Ȃ��~���ɂȂ�܂��B �Ȃ��n���X�^�[���ԗւ��Ă��邪�A�����ꏊ�Ŏ����������Ă��邾���A�Ƃ����̂�A�z���Ă��܂��܂��B
�A�o��ό��q�ł������W�߂悤�Ƃ��ĕK���ɓ����Ă���̂����A����Ȏ���������撣���Ă��[�������̂܂܂ł��B
�ό��ƗA�o�ɂ͂�����傫�Ȗ�肪����A���{�l�����������ʂ����O�ɗ��o���A�~�ς���Ȃ����ł��B ���{�Ŏ����ԂY���A�����J�ɗA�o������A���{�ɂ͉����Ȃ��Ȃ�A�A�����J�ɂ͎����Ԃ�1�䑝���܂��B
�A�o��ό��Ōo�ϐ����͂��Ȃ�
�����Ƃ��������������ɁA���x�ȍH�Ɛ��i�ł��鎩���Ԃ�n���̂́A���܂�L���Ȏ������ł͂���܂���B �A�����J�͎���������Ԃ����N���L���Ɏg���܂����A���{�̎����ԃ��[�J�[������������͗L���Ɏg���Ă���ł��傤���B ���͒�����C�O�ɕʂȍH������Ă��肵�āA���{�l�ɂ͉��̉��b�������炵�͂��܂���B
���邢�͊�Ƃ̓������ۂɂȂ�����A������n����݂�グ����A���N�Ȏ��Ɏg���Ȃ��̂������ł��B
�A�o��ό��œ��{��������O�݂́A��ʍ����̂��߂Ɏg���鎖�́A�܂�����܂���B �O���l���s�҂�荑�����s�҂𑝂₵�������o�ό��ʂ��傫���̂ɁA�O���l�𔑂߂邽�߂ɓ��{�l���z�e������ǂ��o���Ă���̂ł��B
���̐���𑱂������A���N���ė��N���A���{�̓[�������ł��傤�B
�ł͂ǂ�����Όo�ς��������邩�ƌ����ƁA���܂ŏ������t�A�܂�A���𑝂₵�Ėf�Ղ�ό���Ԏ��ɂ���A���̕��~���ŗA�o���Ղ��Ȃ�܂��B �f�Ս����̓��{���f�ՐԎ��̃A�����J��Ƃ̕����A�����͂�����ׂ����Ă���̂͂��ׂ̈ł��B
http://thutmose.blog.jp/archives/62830797.html
2016�N10��25��
���R�f�Վ���̏I���@���E�̖f�Պz���k��
���R�f�Ղ��l�X��L���ɂ����Ǝ咣����IMF�����́A��������d�G��������ē��v�����܂����ĕs���~�����Ă����B
���p�Fhttp://e.noticias.americadigital.pe/ima/0/0/2/1/4/214319.jpg
���E�̖f�Պz������
�����E�̖f�Պz���k�����Ă��āA2015�N�̐��E�̖f�Պz�́A�O��12.7������16��4,467���h���ɒ��݁A2016�N���}�C�i�X�Ő��ڂ��Ă���B ����ɍ��܂ł͐��E�o�ς̐L�ї����A���E�f�Ղ̐L�т������Ă������A���݂ł͖f�Ղ̐L�т�������Ă��܂��B �u�X���[�E�g���[�h�v���ۂƌ����A2016�N�̐��E�o�ϐ�������3.1���\�z�����A�f�ՐL�ї���2.8���\�z�ł��B
�@�@�@�@�@
2016�N4������6���̐��E�f�ʂ̓}�C�i�X0.8���A1������3�����}�C�i�X�������̂ŒʔN�ł��}�C�i�X�̉\���������B
2014�N�̐��E�f�Ղ��A�O�N��0.8������18��7,461���h���ɗ��܂��Ă��āA�Z���I�Ȍi�C�z�ł͂Ȃ������I�ȑ傫�ȗ���ɂȂ�\���������B IMF�␢�E��s�A���Ă̌o�ϐӔC�҂́u���O���[�o���Y���v�ƌĂьo�ς̓G���Ǝ咣���Ă��邪�A�ʂ����Ă����Ȃ̂��낤���B
IMF�̃��K���h�ꖱ�����͎��R�f�Ղ����E�𐬒������A�l�X�̕��������コ���Ă����Ƙb���Ă��邪�A���{�ł͂���Ȍ��ۂ͋N���Ă��Ȃ��B
�ނ��뎩�R�f�Ղ�����قǎd���𒆍��l�Ɏ���ĕn�����Ȃ�A�����������ď�����ł��Ȃ��Ȃ�A�O���l�ό��q����ɕ�������ɗ��ł���B ���͉��Ăɂ����Ă������ł���A�A�����J�ł���20�N�Ԃɂ������������̂́u�x�T�w�v�����ŁA���̑S�����f�Ղɂ���ĕn�����Ȃ�܂����B
�A�����J�l��50���͎��Y��10���~�ȉ����������Ă��Ȃ������ł����A����ŃA�����J�l�̕��ώ����͓��{�l��肸���Ƒ����B
�N�����S���~�␔�牭�~�̐l���u���Ϗ����v���グ�Ă������ŁA�A�����J�l��9���͐̂��n�R�ɂȂ��Ă���B ���B�ł����l�ŃM���V���͎��R�f�ՂŌo�ϔj�]���A�C�^���A�Ⓦ���������E�֕킦�A�ׂ����Ă���̂̓h�C�c�����ɂȂ��Ă���B
���R�f�Ղ͂���������
���̃h�C�c�ł��L���ɂȂ����͕̂x�T�w�Ɓu���c��Ɓv�̃t�H���N�X���[�Q���J���҂ȂǂŁA���c��Ƃƌ������ȊO�̘J���҂͓�̂��߂ɉƂ�ǂ��o����Ă���B ���R�f�ՂȂʖڂ��Ƃ����ے�_�҂��o�Ă��邪�A�̂��l�����͔ނ��ی��`�҂ƌĂуq�g���[�Ɠ���ɔᔻ���Ă���B �ނ�̗��_�ł͑���E���͕ی�f�Ղɂ���Ď��R�f�Ղ��~�߂��̂������ŁA�ی��`�̓q�g���[��^�Ɠ����߂������ł��B
���ۂɂ͎��R�f�ՂȂ��E�̐l�X��L���ɂ����A������������L���ɂ��āA�n���҂����o���V�X�e���Ȃ̂��������Ă����B
�d�t�̓C�M���X���E�ŕ��悤�Ƃ��Ă��邪�A�v����ɂd�t�̎��R�f�ՂȂC�M���X�l��n�R�ɂ����������Ƃ����̂����E�̗��R�ł����B �k�Ď��R�f�Ռ��m�`�e�s�`�ɂ��Ă��A���ꂪ�A�����J��L�V�R�̐l�X��L���ɂ����Ƃ������v�͂Ȃ��B
���������ŋ������͍����b�g�𑝂₵�A�n�R�l�̓V�[�g�ŘH��Ƀe���g�����Ă������̂��Ƃł����B
�O���[�o���Y�����咣����l�����͗Ⴆ�Γ��{���{�������̎Y�Ƃ�_�Ƃ𑣐i���邱�Ƃ��u�ی�f�ՂŐ��E�o�ς̓G���v�Ƃ��Ĕᔻ���Ă���B ���{�̔_�Ƃ���ł���Ζf�Պz�������Đ��E�o�ς͊g�傷��Ƃ����̂����A���{�l�ɂ͉��̃����b�g�������B
�������Ƃ�V���ȎY�Ƃւ̐��{�̓������S�āu�ی�f�Ձv�Ŗf�Ղ�j�Q���Đ��E�o�ςɑŌ���^���邻�����B
���E�o�ςȂ����H�炦�ƍl����l�����E���ɑ����Ă���̂���������ʎ��ŁA�����̌ٗp���̂ĂĎ�������n�R�ɂ���悤�ɂh�l�e�␢�E��s�͎d�����Ă���B 1991�N�Ƀ\�A�������E�f�Ղ͊g�債���������A���{�̂f�c�o�͏k���������A���{�l�͕n�����Ȃ葱�����B
�����̎Y�Ƃ�_�Ƃ��]���ɂ��Ď��R�f�Ղ𐄂��i�߂����炱���Ȃ����̂ł���A�f�Ղ͍����ɉ��̖��ɂ������Ȃ��̂������������������B
http://thutmose.blog.jp/archives/66835420.html
�w�x���Ƌ��� �n���o�ϊw�����x– 2016/12/9 ���� ���u (��)
https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4492444386/asyuracom-22?p=TK �g�����v������Brexit�O�𐭎���ł͂Ȃ�
�G�X�^�u���b�V�������g�̌�肪�ؖ����ꂽ ���� ���u 2016�N12��09��
http://toyokeizai.net/articles/-/145294
�u�O���[�o���[�[�V�����͗ǂ����Ƃ��v�Ƃ����G�X�^�u���b�V�������g�́u�펯�v�́A�{���ɐ����������̂ł��傤���i�ʐ^�FSK Photo / PIXTA�j
���ޒ������e�����A�����J�A�������钆���A�N���~�A�������ɒD�悷�郍�V�A�A���V�i�C�E��V�i�C�Œ����s�ׂ���߂Ȃ������c�c�B �p���[�E�o�����X����ϓ����鍡�A�u�n���w�v�Ƃ����A�Â߂������A�ЁX�����j���A���X���町�������t������ɂ�݂������Ă��Ă���B����A����܂ł̒n���w�I�v�l�����ŁA���E�͂��A�����������Ƃ͔��ɍ���ł͂Ȃ����낤���H �wTPP�S���_�x�ɂ����āA���ĊW�̂䂪�݂��s�����@�͂ł�����o�������썄�u���ɂ��w�x���Ƌ��� �n���o�ϊw�����x���A���̂قǏ㈲���ꂽ�B �{�e�ł́A�u�x���v�Ɓu�����v���L�[���[�h�ɁA�g�����v���ۂ�p����EU���E�̔w�i�ɂ���u�C�f�I���M�[�v��������o���B
���Ȃ��悤�Ƃ��Ȃ��G�X�^�u���b�V�������g
2016�N6���̉p����EU�i���B�A���j����̗��E�̐����₤�������[�A������11���̕đ哝�̑I���߂��鐢�E�̔����́A�����قǍ������Ă����B
�܂��A����������O�̗\�������ʂƂȂ����B�����āA������̌��ʂɑ��Ă��A���E�̐����w���҂�o�ϊE�A�L���҂��邢�̓}�X���f�B�A�̎嗬�h�A������u�G�X�^�u���b�V�������g�v�͋������A���|���A���邢�͕��̂̎����𓊂��������B�H���A�u�������v�u�ی��`�v�u�r�O��`�v�u�|�s�����Y���v���X�B �����A���́A�p����EU���E��h�i���h�E�g�����v�̏����Ƃ������ʂ��ꎩ�̂ɂ���̂ł͂Ȃ��B���̂悤�Ȍ��ʂ������������̍��{�́A�G�X�^�u���b�V�������g�������C�f�I���M�[�̌��ɂ���B����ɃG�X�^�u���b�V�������g���C�Â��Ă��Ȃ����ƁA�����Ĕ��Ȃ��悤�Ƃ��Ă��Ȃ����ƁA���̂��Ƃ��ő�̖��Ȃ̂ł���B �G�X�^�u���b�V�������g�����L����C�f�I���M�[�Ƃ́A�v����A�����ނˎ��̂悤�Ȃ��̂ł���B
���E�́A�O���[�o���[�[�V�����Ƃ����s���E�s�t�̒����̒��ɂ���A���Ǝ匠�͂܂��܂����������B���m�A�J�l�����ăq�g�͂₷�₷�ƍ������z���Ĉړ�����悤�ɂȂ�B���Ƃ͂��͂₻�����Ǘ��ł��Ȃ����A���ׂ��ł��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�O���[�o���[�[�V�����́A�e���Ɍo�ϓI�Ȕɉh�������炷�őP�̓��ł���݂̂Ȃ炸�A��蕽�a�Ȑ��E�������炷���炾�B�܂�A�o�ϓI�ȑ��݈ˑ������܂邱�Ƃɂ��A���ƊԂ̐푈�͂��͂⊄�ɍ���Ȃ����̂ƂȂ�̂ł���B�u�x���v��O�ꂷ��u�����v�͕s�v�ƂȂ�̂��B
���̂悤�ȃC�f�I���M�[�́A���ɗ��I���ȍ~�A�L�����z�������̂ł���B
���Ƃ��A1996�N�A�����Ȑ����o�ϊw�҂̃��`���[�h�E���[�Y�N�����X�́A���{�A�J���A�Z�p�A��������z���Ď��R�Ɉړ�����悤�ɂȂ������E�ɂ����ẮA���Ƃɂ��̓y�ւ̎����͉ߋ��̂��̂ƂȂ�A���ێЉ�͂�蕽�a�ɂȂ邾�낤�Ƙ_���Ă����B ���ꂩ��20�N���߂������A���̂悤�Ȑ��E�ς́A�G�X�^�u���b�V�������g�̊Ԃł͂Ȃ�����������B�u���͂⍑���⍑�Ђɂ�����鎞��͉߂�����܂����v�Ƃ����킯�ł���B �����A2016�N�̉p���̍������[�ƕč��̑哝�̑I�́A�G�X�^�u���b�V�������g�̊��҂𗠐�A�����⍑�Ђɂ������҂����̏����ɏI������̂ł������B EU�̓����g�傪�p�����E�̈������� �Ȃ��A�p����EU���E��g�����v�̏����́A�G�X�^�u���b�V�������g�̃C�f�I���M�[�����������ʂ��ƌ�����̂��B����́A���ꂼ��̌o�܂�U��Ԃ�Ε�����B �܂��A�p���̍������[���猩�Ă݂悤�B �p���ł́A2008�N����5�N�ԂŎ���������8�����ቺ���Ă����B�܂��A��ɓ����̒�����J���҂��ږ��Ƃ��ė����������A���̏�������2015�N��33���l����Ɏ������B���E�h�́A���̈ږ��̋}�����������������̈��������̗v�����Ǝ咣�����̂����A���̎咣�͊m���ɐ������B ������J���͂ł���ږ��̑�ʗ����Ƃ�����肪�����ɂȂ����̂́A2004�N�ȍ~��EU�̓����g�傩��ł���B2004�N�A���\�A����8�J���ƃ}���^�A�L�v���X��EU�ɉ��������B2007�N�ɂ̓��[�}�j�A�ƃu���K���A���A2013�N�ɂ̓N���A�`�A�����������B EU�̓����g��́A�o�ϓ����ɂ���č����̕ǂ����Ⴍ���邱�Ƃ��A�ɉh�ƕ��a�ւ̓��ł���Ƃ������B�̃G�X�^�u���b�V�������g�̗��O��̌�������̂������B�����A���̓����g�傪�p����EU���E�̈��������������̂ł���B
��������EU�̑O�g�ł���EEC�i���[���b�p�o�ϋ����́j��n�݂���6�J���̊Ԃɂ́A1�l�������GDP�̑傫�Ȋi���͑��݂����A1973�N�ɉ��������p����1�l������GDP�ƌ��������Ƃ̊Ԃɂ��A���قǂ̊J���͂Ȃ������B
�������A2004�N�̓����g��ɂ��A�ł��n�����V�K��������1�l������GDP�͍ł��L���ȍ��̂��悻3����1�����Ȃ��Ȃ�A2007�N�̃��[�}�j�A�ƃu���K���A�̉����ɂ�肻�̐��l�͂���ɉ��������B���̂悤�Ȓ��ŁAEU����̘J���ړ������R�ɂ���A�����̒�����J���҂��L���Ȑ��������ɎE�����A��҂̎������������������邱�ƂɂȂ�B�p�����{���������Ǘ��ł��Ȃ���A���������̉������~�߂邱�Ƃ͕s�\�Ȃ̂��B�p���̘J���ґw��EU���E�ɕ[�𓊂����̂���������ʐ���s���ł������B �O���[�o���[�[�V�������i�����g�����v���� �č��ł����l�̌��ۂ��N���Ă����B 1990�N��ȍ~�A�č��̐헪�ڕW�́A�O���[�o���[�[�V�����̐��i�ł������B1994�N�ɕč��A�J�i�_�A���L�V�R�̊ԂŔ�������NAFTA�i�k�Ď��R�f�Ջ���j���A���̈�ł���B ���L�V�R�ł́ANAFTA�ɉ����������ʁA�č���������ȃg�E�����R�V���������A�_�Ƃ���ł���ɂ��������B�����āA���������n���̃��L�V�R�l�����͕s�@�ږ��Ƃ��đ�ʂɕč��ɗ������A�č��̘J���ґw�̓��L�V�R�̕s�@�ږ��ɂ���ĐE��D��ꂽ�Ƌ����s����������B������ANAFTA���������A���L�V�R�Ƃ̍����ɕǂ�z���Ƃ����g�����v�̎咣�́A�J���ґw�̋����x�����̂ł���B 1990�N��̕č��́A�����ɑ��Ă��A�O���[�o���o�ςւ̓������x������Ƃ����헪��i�߂Ă����B�������o�ϓI�ȑ��݈ˑ��W�̒��ɗ��߂Ƃ�A�O���[�o���ȃ��[���̉��ɕ�������A�č��哱�̃A�W�A�����m�̒�����F�߂����邱�Ƃ��ł���ƍl�����̂ł���B���̐헪�Ɋ�Â��A�č��́A�����̐��E�f�Ջ@�ցiWTO�j�ւ̉������㉟�������B �����A���̌��ʁA��������̈����Ȑ��i�̗A���⒆���ւ̊�Ƃ̐i�o���g�債�A�č��l�̌ٗp�������邱�ƂƂȂ����B1999�N����2011�N�̊Ԃ̒�������̗A���ɂ���āA�č��̌ٗp��200���l����240���l�قǎ���ꂽ�Ɛ��v���錤��������B ���́ANAFTA��WTO�Ɍ���Ȃ��B����20�N�ԁA�O���[�o���[�[�V�������i�߂�ꂽ���ƂŁA�p�Ă��͂��߂Ƃ����i�����̎��������͐L�тȂ��Ȃ�A�J�����z���͒ቺ���A�i���͒������g�債���B�č����̑�����TPP�i�����m�o�ϘA�g����j���x�����Ȃ��Ȃ����Ƃ����̂��A��������ɒl���Ȃ��̂��B ����ɋ��Z�̃O���[�o���[�[�V�������i���Ƃɂ��A���Z�s��̓o�u���Ƃ��̕�����J��Ԃ��悤�ɂȂ�A���܂��ɂ�2008�N�̃��[�}���E�V���b�N�������N�������B����ȍ~�A���E�o�ς́u������v�ƌĂ��s���Ɋׂ��Ă���B 2008�N�ȍ~�A���E�̍��������Y�iGDP�j�ɐ�߂鐢�E�f�Ղ̔䗦�͉����Ő��ڂ��Ă���B����́A���Œ��̒�ł���BGDP��ł݂��C�O���ړ����̃t���[���A2007�N�ȍ~�A�������ቺ�������Ă���B���E�o�ς̌i�C�����������o���`�b�N�C�^�w���́A2016�N�ɁA1985�N�̎Z�o�J�n�ȗ��̍Œ�l���X�V�����B
������̎w�W���A�O���[�o���[�[�V�������I���������Ƃ������Ă���̂ł���B
�ɂ�������炸�A�G�X�^�u���b�V�������g�́A�Ȃ��O���[�o���[�[�V�������^�킸�A���܂����A���������ɐ��i���悤�Ƃ��Ă���B����ł́A�[���NJ��Ɋׂ����č������g�����v�̂悤�Ȑl���ɋ~�������߂邵���Ȃ��Ȃ��Ă����R�ł͂Ȃ����B �Ȃ��ATPP�̍��܂������Ď��R�f�Ց̐��̕��Ƒ������Ă�̂͑��v�ł���BTPP���������Ȃ��Ƃ��A�����m�͂��łɏ\���Ɏ��R�f�Ց̐����B�č��̖��ӂ����ۂ����̂́A���R�f�Ց̐����̂��̂ł͂Ȃ��A�G�X�^�u���b�V�������g���ߏ�ɐi�߂��O���[�o���[�[�V�����iTPP�͂��̏ے��j�Ȃ̂��B �������Ȃ���x������邱�Ƃ��ł�������͏I����� �O���[�o���[�[�V�����͌o�ϓI�ɉh����Ȃ��Ƃ��������ł͂Ȃ��B���ꂪ��蕽�a�Ȑ��E�������炷�Ƃ����̂��ԈႢ�ł���B �哝�̑I�̍Œ��̃g�����v�́A�č��͂��͂�u���E�̌x�@���v���蓾�Ȃ��Ƒi���A���ē����̌������ɂ����y���āA�킪����k���������B�����A������O���[�o���[�[�V���������������ʂȂ̂ł���B ���łɏq�ׂ��悤�ɁA�O���[�o���[�[�V�����͕č��̌o�ϗ͂���̉���������̂ł���B�����A�R���͂��x����̂͌o�ϗ͂��B�o�ϗ͂�������Ȃ�A�č��̌R���͂���܂�A�u���E�̌x�@���v���蓾�Ȃ��Ȃ�B �������A�O���[�o���[�[�V�����͕č����̖L���Ȑ�������Ȃ��̂ł���B�Ȃ�A�č���������ȃR�X�g�S���Ăł��O���[�o���Ȓ�������낤�Ƃ������@�������ē��R�ł��낤�B �O���[�o���[�[�V�������u�x���v�������炵�A�u�����v��s�v�Ƃ���͂����Ƃ����G�X�^�u���b�V�������g�̃R���Z���T�X�́A�������Ĕj�]��I�悵���̂ł���B ����Ɉ������ƂɁA2000�N��̒����́A�č��̎x���ɂ���ăO���[�o���o�ςɓ������ꂽ�̂𗘗p���āA�܂�܂ƗA�o�哱�̍��x�o�ϐ�����B������ƂƂ��ɁA�N��2�P�^��̃y�[�X�ŌR������g�債���B�����́u�x�������v�����H�����̂ł���B ���̌��ʁA�A�W�A�ɂ�����Ē��Ԃ̃p���[�E�o�����X������n�߂��B���ꂪ�܂��ɁA�����ɂ�铌�V�i�C���V�i�C�ւ̍U���I�Ȑi�o�Ƃ��Č���Ă���̂ł���B���̃A�W�A�ɂ�����댯�Ȓn���w�I�ϓ��̑����ɁA�킪���͒u����Ă���̂��B �u�����v�Ȃ��u�x���v���邱�Ƃ��ł�������͉ߋ��̂��̂ƂȂ����B�����́A�Ăсu�x�������v�ɔۂ����ł����g�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B
http://toyokeizai.net/articles/-/145294
2016.12.07
���c���̌����� �w�Ԋ��x�C���^�r���[�����O���@�[�W����
�w�Ԋ��x��12��4�����ɃC���^�r���[���ڂ����B
�L���ɂ͏�����Ȃ��������Ƃ��������̂ŁA�ȉ��Ƀ����O�E���@�[�W�������f���Ă����B �\�g�����v�����Ɨ\�z���Ă��܂������B �܂����B�������������Ƃ���܂ł䂭���낤�Ǝv���Ă��܂�������ǁA�͍��Ńq�����[�����Ǝv���Ă��܂����B���ہA�Q�O�O�����q�����[�̓��[�̕������������킯�ł�����u�A�����J�l�̓q�����[��I�ԁv�Ƃ����\���͊Ԉ���Ă͂��Ȃ������킯�ł��B�I�����x�̂����ŁA���[���̏��Ȃ������哝�̂ɂȂ��Ă��܂����B�l�̓q�����[���ʂɍD������Ȃ����ǁA�g�����v�͉������ł������킩��Ȃ�����|���ł��B���i�K�ł̓A�����J�̍��ۓI�ȈАM���n�ɗ����邾�낤�Ƃ������Ƃ����킩��Ȃ��B
�\�g�����v�����̔w�i�ɉ����������̂��B���{���Y�}�́A���j����c�ĂŁA�A�����J�Љ�̓O���[�o�����{��`�̂��ƂŊi���ƕn�����L����A�[���ȍs���l�܂�Ɩ����ɒ��ʂ��Ă���A�g�����v�����͂��̂ЂƂ̔��f�ɂق��Ȃ�Ȃ��Ǝw�E���܂����B
�������̐����Ƃœ����l�����������ł��ăg�����v�ɓ��[�����B���Y�K���̖v���Ɗi���̊g�傪�A����̓��[�s���Ɋ֗^�����ő�̗v���������Ǝv���܂��B�ꈬ��̋��命���Њ�Ƃ�ŕx�T�w�ɕx���W�����A�K�w�������Ɍ������Ă����O���[�o�����{��`�����Ɍ��E�ɒB�����B�g�����v�o��͂��̒f�������z���݂����Ȃ��̂���Ȃ��ł����ˁB �������A�O���[�o�����{��`�̌��ׂ��ł���藧�Ă��g�����v�������Ă���킯����Ȃ��B���Ԃ�g�����v�������ŁA�i���͂���Ɋg�債�A�g�����v���x�������u���[�J���[�̐����͂���ɋꂵ���Ȃ�Ǝv���܂��B �ł��A�g�����v�͂��́u�����̍����v�����{��`�V�X�e���ł͂Ȃ��A�q�X�p�j�b�N��C�X�������k�ɓ]�ł��邱�ƂŖ{���I�Ȗ����B�������B�r�O��`�I�ȃC�f�I���M�[����藧�āA�����O�Ɂu�A�����J���_���ɂ����v������������悤�Ɏd������A�����������Ă��A�x���w�̕s�������炭�̊Ԃ͂��炷���Ƃ��ł���ł��傤�B
�\���{�ł����A�����E�ېV�̎�@����҂Ɏ��Ă��܂��ˁB
��������ł��B��邱�Ƃ͗m�̓�����₢�܂���B�̐��́u�s���Ȏ�v�҂Ȃ���́v����肵�āA���ꂪ�u�����̍����v�Ȃ̂ŁA�����r��������ׂĂ̖��͉�������Ƃ����f�}�S�M�[�ł��B�U������Ώۂ����_���l�Ȃ甽���_����`�ɂȂ�A�Ώۂ��ږ��Ȃ�r�O��`�ɂȂ�B���̏ꍇ�́A�������E�����E�����ی�҂Ȃǂ��u��v�ҁv�Ɏd���ĂāA������U�����Ďs�������̕s�������炵���B
�\���[���b�p�ł������悤�ȓ��������܂�Ă��܂��B
���[���b�p�����ł��A���X�ƋɉE�����Ƃ��o�ꂵ�Ă��Ă��܂��B���̑O��ɂȂ��Ă�����j�I�����́u�O���[�o�����{��`�̏I���v�Ƃ������Ƃł��B
�O���[�o�����{��`�ɂ���āA���E�̓t���b�g�����A���{�E���i�E���E�l�Ԃ��������z���č����ړ�����悤�ɂȂ����B�O���[�o�����ɓK���ł��Ȃ��l�����A�����ړ��ł���悤�ȎЉ�I�@�����������Ă��Ȃ��l�����͉��w�ɒE�������B �����Ƃ̍H��J���҂��T�^�I�ł�����ǁA����̋Ǝ�ɓ��������Z�p��m���Ő��v�𗧂āA���܂�̋��̒n��Љ�ŕ邵�Ă����l�́A�O���[�o�����������E�ł́A���ꂾ���̗��R�ʼn��w�ɐU�蕪������B���e��c����̑�܂ł�������u�܂��Ƃ��Ȑ������v�����Ă����̂ɁA�܂��Ɂu�܂��Ƃ��Ȑ������x�����Ă����Ƃ������̗��R�ʼn��w�Ɋi�t������邱�ƂɂȂ����B�s�𗝂Șb�ł��B�ł�����A�ނ炪�u�A���`�E�O���[�o�����v�ɐU���͓̂��R�Ȃ�ł��B �ł��A�ނ炪�I�������u�A���`�E�O���[�o�����v�͂��܂��܂Ȑl���@���≿�l�ς����݂Ɍh�ӂ������ċ�����u���A���₩�ɋ�������Ƃ��������ɂ͌�����Ȃ������B�����ł͂Ȃ��āA�u�������������悯��ΊO�̐��E�Ȃǂ��Ȃ��Ă��\��Ȃ��v�Ƃ������Ȏ�������`�Ɍ������Ă���B
�\�A�����J�ł̓T���_�[�X���ۂ��N���A���E���Ŋi���ƕn�����Ȃ����^�����L����A���{�ł͎s���v���I�ȓ������N���Ă��܂��B
���܂����邱�Ƃ�����܂��A�P�X���I�܂ł̃A�����J�͎Љ��`�^���̐�i���̈�ł����B�������V�A����̎Љ��`�҂��P�X���I������A�����J�ɌQ����Ȃ��Ĉږ����Ă�������ł����瓖�R�ł��B�J�[���E�}���N�X�ł����N���ɂ̓e�L�T�X�ւ̈ڏZ���Ă����B���ꂭ�炢�ɓ����̃A�����J�̓��[���b�p�ɔ�ׂ�Ǝ��R�ŊJ���I�ȎЉ�Ɍ������B����ǂ��A�W�����E�G�h�K�[�E�t�[���@�[�̂e�a�h�̕Ύ��I�Ȕ��������ƁA�P�X�T�O�N����T�S�N�܂Ŗ҈Ђ��ӂ�����}�b�J�[�V�Y���ɂ���āA�A�����J�����̍����^���͂قڍ��₳��Ă��܂����B ���́u�����A�����M�[�v���\�A����A�����́u���{��`���v�ɂ��u���ۋ��Y��`�^���̏I���v�ɂ���āu�G�v���������B�T���_�[�X�̓o��̓A�����J�Љ�V�O�N�ɋy�ԁu�����v�̃t�@���^�W�[����o�����āA����������悤�ɂȂ������낤�Ǝv���܂��B ������ɂ���A�g�����v�̓o��ɂ���āA���������ǂ̂悤�ȗ��j�I�]���_�ɂ���̂��͂������������܂����B�O���[�o�����{��`�̏I�肪�n�܂����Ƃ������Ƃł��B �E�O���[�o�����͐����ߒ��ł��A�o�ϊ����̉ߒ��ł����ꂩ��K�R�I�ȗ���ƂȂ�ł��傤�B���̗���͎s��̖O�a�Ɛl�����Ƃ����ꍑ�̐��x���ł͂ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��l�ގj�I�����̏��Y�ł�����A��R���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�������ɂł���̂́A�u�O���[�o�����{��`�̏I���v���\�t�g�����f�B���O�����邽�߂̋�̓I�Ȏ藧�Ă��l���邾���ł��B���E���̐l�X���O�m���W�߂Ēm�b���i�邵���Ȃ��B ���̂悤�ȗ��j�I�ǖʂɂ����āA���{�̔������j�I�Ȗ\���������ُ�ɍۗ����Ă��܂��B���E�͒E�O���[�o�����ǖʂɂǂ��Ώ����邩�l���n�߂��Ƃ��ɁA������ɂȂ��ăO���[�o�����ɍœK�����ׂ����ׂĂ̎Љ�x��ς��悤�Ƃ��Ă���B�����������ǂ��������E�j�I�����̒��ɂ���̂��A���{�̎w���w�͂܂������킩���Ă��Ȃ��B�����N���Ă���̂��������Ȃ��܂܂Ɂu�A�N�Z�����ӂ����āv�˂�����ł䂭�B ���ۖ@���A�����A�����ĉғ��A�s�o�o�A��X�[�_���h���A�J�W�m���@���A�ǂ���Ƃ��Ă��u�Ȃ�������Ȃ��Ƃ��Q�ĂĂ��Ȃ�������Ȃ��̂��v���R���킩��Ȃ����Ƃ���ł��B ���{���g�͎�ϓI�ɂ́u�ō����ŃO���[�o�����ɍœK�����Ă���v����Ȃ̂ł��傤�B���Ԃ�u�Q�Ă�v�Ƃ������Ƃ��u�O���[�o�����v���Ǝv���Ă���B�s�o�o���悢��ł�����ǁA��s���̌��ʂ��Ȃ����ۏ�̒��Łu�Q�ĂĂ݂����v���Ƃł����Ȃ鍑�v���m�ۂł����̂��B ���ꂩ���̐����I�ȑΗ����͂����ɒu�����ׂ����Ǝv���܂��B �\�����鐭�����~�߂āA�Ƃɂ������������~�܂�B�����E�ł͉����N���Ă��邩�A���E�͂ǂ��Ɍ������Ă��邩�����߂�B��s�������ʂ��Ȃ����ɁA�A�N�Z�����ӂ����Ė\������Ύ��̂��N�����Ɍ��܂��Ă��܂��B����Ȑ��������܂ł�������Ύ��Ԃ��̂��Ȃ����ƂɂȂ�B�u�\���v���u�X���[�_�E���v���B�����̑R���͂������Ǝ��͎v���܂��B ���ۏ�̕ω��Ɓu�E�O���[�o�����v�ɐU��Ă���s�������K�ɂƂ炦����A��}���������̑I���ň��{������ǂ����Ƃ��\���͏\���ɂ���Ǝv���܂��B
http://blog.tatsuru.com/ �ǂ������{�ɂ́A�u�ی��`�v���������p�u���t�̌�����������悤�ł��B
2017/01/24 FROM�@���䑏�����t���[�Q�^(���s��w��w�@����) �g�����v�哝�̂̏A�C�����ɂ�����ő�̃G�|�b�N�́u�ی��`�v�̎p����哝�̂Ƃ��đN���ɂ����_�ɂ���܂��B ���ہA�A�����J�̑��j���[�X���f�B�A�b�m�a�b�́A���̗l�ȃw�b�h���C���Ńg�����v�A�C������Ă��܂��B �uTrump inauguration speech:
�@�@�@�fProtection will lead to great prosperity and strength�f�v
�g�����v�A�C�����F
�e�ی��`�������̑�Ȕɉh�Ƌ����ɂȂ���f�@�v http://www.cnbc.com/2017/01/20/donald-trump-were-transferring-power-from-washington-back-to-the-people.html ���́u�ی��`�v�i���@�m�g�j�̑S������j���咣������������̃Z���t���w�b�h���C�������������̔w�i�ɂ́A����̃A�����J�͂��������A�i���Ȃ��Ƃ��^�e�}�G�̏�ł́j���R�f�Վ�`���f���ی�f�Ղ���噂̂��Ƃ��������������A�Ƃ������j�I����������܂��B ���̃A�����J�哝�̂��A�A�C�����ɂĕی��`��O�ʍm�肵���킯�ł�����A�������ꂾ���ő傫�ȃj���[�X�ɂȂ�A�Ƃ�������ł��B
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170121/k10010847631000.html�j �Ƃ��낪�A���{�ł́A���̃Z���t�͑S�����グ���܂���ł����B �V���e�Ђ͂������āA�u�A�����J���v�iAmerica First�j�����o���Ɍf��������ŁA�u�ی��`�v�Ƃ������t���قƂ�Ǘp���Ȃ������̂ł��B ����ǂ��납�A���̓V���̂m�g�j���ŏ��Ɍ��\�����u�����S����v�ł́A�uProtection will lead to great prosperity and strength�v�Ƃ����Z���t�������ۂ肻�̂܂ܔ���������قǁA�y������Ă����قǂł����B ���Ȃ݂ɂ���́A�u�y���v�Ƃ��������u�B���v�ƌ����ɑ��������قǂ̑Ή��B�ڂ����́A���L�����Q�Ƃ��������B
https://www.facebook.com/Prof.Satoshi.FUJII/posts/959135840854026?pnref=story�j �Ȃ��A���{�̃��f�B�A�́u�ی��`�v�Ƃ������t���A�������������̂ł��傤���H ���̔w�i�ɂ́A�u�|���R���v�̉e��������܂��B �܂�A�u�ی��`�v�Ƃ������t�́u���v���Ӗ�������̂ŁA������g���̂́A�����I�Ɂi�܂�|���R���̎��_����j�]�܂����Ȃ��\�\�Ƃ�����C���A���_��Ԃ��x�z���Ă������̂ɁA����������C�ɕq���ȃ��f�B�A�E�́u�C���e���v�B�́A�ӎ��I�����ӎ��I���͂��Ă����u�ی��`�v�Ƃ������t���g�����Ƃ�������Ă��܂��Ă����A�Ƃ�������ł��B ����Łu�A�����J���v�́A�|���R���_�ɂ͂Ђ�������Ȃ����t�B���������u�A�����J���v�Ȃ�ăA�����J�哝�̂ł���Γ�����O�̎咣�ŁA����Ȃ��͉̂��������ɒl���܂���B���������A���{�����Ę@�u�̓�d���Ђ����ꂾ������ƂȂ����̂��A�����Ƃ���ҁu���{���v�̎p������ΓI�ɋ��߂��Ă��邩��ɑ��Ȃ�܂���B �������āA���{�̃��f�B�A�ł́A�������̂Ȃ��u�A�����J���v�����o�����������A������肠��u�ی��`�v�Ƃ������t�́A�S���|�炷��폜�������Ɋ�������A�B�����ꂽ�Ƃ�������ł��B �\�\�������A�悭�悭�l����A���́u�ی��`�v�́A�����ĖŒ��ꒃ�ȃG�L�Z���g���b�N�ȉߌ��Ȃ��̂ł��Ȃ�ł�����܂���B ���������f�Ր���̕��j�� �@�@�ی�f�Ձ@���@�|�@�|�@�|�@�|�@�|�@�|���@���R�f�� �̓_�ōl����Ƃ���Ȃ�A���S�ȁu�ی�f�Ձv�̍����A���S�ȁu���R�f�Ձv�̍����A���̐��ɂ͑��݂��锤�͂���܂���B �ی�ɂ����R�ɂ����ꂼ�ꃁ���b�g�f�����b�g������̂ł�����A�u���ɒ[���Ɓv�́A�̂ċ���������̍l�����̃����b�g���邱�Ƃ��ł����A���ǂ́A�傫�����ނ�����Ȃ��Ȃ邩��ł��B ���R�f�Ղ̃����b�g�́A���R�Ȍ�����ʂ��āA�e���̒����Z����₢�Ȃ���A���������E���̍���T�[�r�X�����L�ł��A��苭�����̂�苭���Y�Ƃ�����ɔ��W���Ă����Ƃ���A�ɂ���܂��B���̃f�����b�g�́A���ꂪ�ߏ�ɂȂ�A������H�����s���A���ア���̂��ア�Y�Ƃ��琬�ł��Ȃ��Ȃ�Ɠ����ɁA�ٗp�������A������Ɏ��v���k�����ăf�t�������Ă����Ƃ���\�\�ɂ���܂��B ����ŁA�ی�̃����b�g�ƃf�����b�g�́A���傤�ǂ��́u�t�v�ɂȂ�܂��B ���Ƃ���A���ꂼ��̍��̔ɉh�A����Ɍ����Ȃ�A���E�̔ɉh�̂��߂ɂ́A�ɉ������ی�Ǝ��R�́u�o�����X�v���K�v���A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B �i���@�܂肵���A���E�I�Ȏ��v�s�����w�E���ꑱ���Ă��鍡���A�f�t�����͂����߂�u���R�v�ɏC���������A�����u�ی�v���d����������ɑǂ��̂́A�ɂ߂ė����I�ȓ�����O�̑Ή����ƌ������Ƃ���ł��܂��j ������ɂ���A�ی삪���Ŏ��R���P�ł���킯�ł��Ȃ��A�ی삪�P�Ŏ��R�f�Ղ����A�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��̂ł��B �������u�P�v������Ƃ���Ȃ�A�u�ی�Ǝ��R�̃o�����X�v�������u�P�v�Ȃ̂ł���A�u�ی�Ǝ��R�̃A���o�����X�v�u�ی�̉ߏ�v�u���R�̉ߏ�v�������u���v���A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B ���̗l�ɍl����A����̃g�����v�́u�ی��`�v�̐錾�́A�u�ی�Ǝ��R�̃o�����X�v�ɂ����āA�u�ߏ�v�Ȏ��R�f�ՂɁu�C���v�������āu�ی�f�Ձv�������d�����鑤�Ƀ��o�����X��}�낤�Ƃ���錾���A�Ƃ������̂ł���Ƃ������Ԃ������яオ��܂��B ���������A�g�����v�ƂĊ��S�ȍ���������Ƃ͈ꌾ�������Ă͂��܂���B�m�`�e�s�`���͂��߂Ƃ����l�X�Ȗf�Ջ�����A����u�������v�ƌ����Ă���ɉ߂��Ȃ��̂ł�����B �E�E�E�E�ɂ��S��炸�A���������e���r�����Ă���ƁA�䂪���̑����̃R�����e�[�^�[���A �@�@�u�g�����v�̕ی��`�͊댯���v �Ƃ����_�������ɂ������Ă��܂��B ����Ȓʂ��Ղ̃R�����e�[�^�[�B�̑ԓx�Ɂu焈Ձv���Ă��܂��̂́A�M�҂����ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B�ǂ����A�ނ�ɂ��Ă݂�A �i�P�j�g�����v�̃}�X�R�~��_�G�ɑ��āA�c�C�b�^�[����p���Ĉ��Ԃ����s�V�̈����ԓx�A ��ᔻ����̂Ƃ܂������������q�ŁA �i�Q�j�g�����v�̕ی��`�Ƃ����s�V�̈������i�Ȏ咣 ��ᔻ����A�Ƃ����̂��A�u�C���e���Ƃ��Ė]�܂����ӂ�܂��Ǝv����̂��v�Ǝv���Ă���߂�����܂��B �����͂������A�i�P�j�ɂ��Ă͑傢�ɔᔻ���ׂ����ƍl���Ă��܂��B �i�P�j�̃c�C�b�^�[�����́A������u�m��v����_�����i���Ă����U��Ă���������j�ꕔ�咣����Ă͂���悤�ł����A
https://twitter.com/t_ishin/status/822380771247669250
���������c�C�b�^�[�������u���u�v���Ă����A�������͎҂̉��\�ɂȂ���͕̂K���ł��B �������A���������c�C�b�^�[�������܂���ʂ�悤�ɂȂ�A�u�אS�v���������l�X���c�C�b�^�[�����Ƃɂ�����A�c���@������������Ă��̐����Ƃ��g���āA���̒������́u�אS�v�Ɋ�Â��ē������悤�ɂȂ�̂��܂��A�K��ł��B������A�x���z�����i�P�j�̑ԓx�ɂ́A��ɔᔻ�����������A���̖\����H���~�߂邱�Ƃ��K�v�Ȃ̂ł����\�\�܂��A����͏펯�͈̔́B ���������āA���́i�P�j��ے肷�镗�����ꎩ�g�ɂ́A�i���̓��@�͂��Ă����j�����͂ł���̂ł����A������Ƃ����āi�Q�j�̕ی�f�Ղ̘_�������łɔ���̂́A���܂�ɂ��Z���I�B �J��Ԃ��܂����A�u�ی�f�Ղ����v�Ȃ̂ł͂Ȃ��A�u�ی�Ǝ��R�̃A���o�����X�v��u�ߏ�ȕی�v�u�ߏ�Ȏ��R�����v�Ȃ̂ł��B������A�g�����v�́u�ی�f�Ձv�̎咣��ᔻ����Ȃ�A�u����ɉߏ�ȕی�f�Ղ����݂��A����ɂ���āA���v��傢�Ɋ������Ă���v���Ƃ��������`��������̂ł��B �ł����A�ނ�͐�ɂ��������ᔻ�����邱�Ƃ͂���܂���B�ނ�͂����P�ɁA�������˓I�ɁA�܂�A �@�@�u�p�u���t�̌��v �̗l�Ɂu�ی�f�Ձ����v�̐}���Ŕ������Ă���ɉ߂��܂���B ���̂܂܂ł́A���{�Ɠ��āA���E��L���ɂ���u�f�Ր���v���c�_���邱�Ƃ��s�\�ƂȂ��Ă��܂��܂��B ���R�f�Ղɐ��`������悤�ɁA�ی�f�Ղɂ����`������̂ł��B
�����ɁA�ی�f�Ղɕs���`������悤�ɁA���R�f�Ղɂ��s���`������̂ł��B �g�����v�����Ƃ������ۂ��A���ʓI�ɉ��߂��Ȃ�����A���{�̔ɉh��A���Ă̔ɉh�A�����Đ��E�̔ɉh����ޖf�Ր�����c�_���Ă������Ƃ��ꎩ�g���s�\�ƂȂ�ł��傤�B �������͔@���Ȃ鐭���I�ۑ�ɂ��Ă��A�u�p�u���t�̌��v�ɂȂ邱�Ƃ����͔����˂Ȃ�Ȃ�Ȃ��̂ł��B
http://www.mitsuhashitakaaki.net/2017/01/24/fujii-233/
�u���{����`�v����̖��J���B�Ȃ��O���[�o���Y���͎��̂��H�������N�F 2017�N1��26��
http://www.mag2.com/p/money/31930
�č��ɂ�����g�����v�̏����́A���Ɍ��킹��u�����̐��������������炵�����R�̌��ʁv�ł��B�O���[�o�����͂Ȃ����s�������H�J�̕]�_�Ƃ������Ƃ��Ă���_��������܂��B ����ȓ��{�͍������u�W���p���t�@�[�X�g�v�ɑǂ��ׂ��ł���
�������̕ی�ɏ��o�����p���ƕč�
�p���ƕč��Ƃ��ɁA�O���[�o���������u�������̕ی삪���v�Ƃ������f�ł��B��i���̏͂Ƃ����ƁA���{�͕n�������AEU�Ƃ�������O���[�o������i�߂����B�͓����̗��z����傫������đ卬���B�g�����v�哝�̂ɂ��u�ٗp�d���v�ւ̐����]���́A�����������ŋN���܂����B ���_��́A�������悤�ɂ݂���u�O���[�o�����v�B�R���T���^���g��]�_�Ƃ̓o���F�́u�O���[�o�����v���咣���܂����A����͊ԈႢ�ł������̂ł��B���͂ǂ��ɂ������̂ł��傤���B
�J�̕]�_�Ƃ́u�ٗp�v���l�����Ă��Ȃ�����
�O���[�o�����̐��i�_�҂́A�e�������ӕ���ɏW�����邱�ƂŐ��Y�����オ��A���E�͗ǂ��Ȃ�Ǝ咣���܂��B��ԗǂ����̂��A��Ԉ������i�Ŕ�����Љ�ł��B�܂��Ɂu���̂Ƃ���I�v�ƒZ���I�Ɏv�������ł��ˁB �������A����ɂ͑傫�Ȍ�肪����܂��B�O���[�o�����́A�e���̍����̎��������̂܂܁i���邢�͂���ȏ�j�ŁA�ٗp�����̂܂܂Ƃ������Ƃ��O��ɂȂ��Ă���̂ł��B �Ȃ��A����܂ő����̐l�����̌��ɋC���t���Ȃ������̂ł��傤���H ����́A�����������R�ł��B ����u���v�̒l�i���A���鍑����A������邱�ƂŁA100�~���������̂�80�~�ɂȂ����Ƃ��܂��傤�B 100����80���i20���̃f�B�X�J�E���g�j �H���i�ł��G�݂ł��A�����������Ƃ͓���I�ɋN���Ă��܂��ˁB����������ƁA�叕����ł��ˁB ����A�ٗp�́A�f�t���ŋ�����8���ɂȂ����Ƃ��A�����������Ƃł͂���܂���B�ٗp�������u�����[���v�ł��B 100����0�� ����ɂƂ��Ȃ��āA�Ⴆ���ׂĂ̔������̉��i�����l�Ƀ[���ɂȂ�Ζ��Ȃ��̂ł����A�����������Ƃ͂��蓾�܂���B�܂�A���̉��i��2�����Ƃ��ɂȂ����ŁA�����̓[���i10�����j�Ƃ��A�ďA�E��h���J���Ŏ�����3���i7�����j�Ƃ������Ƃ��A����I�ɋN�����킯�ł��B ������݂܂��ƁA�O���[�o�����ŕ��̒l�i�������Ȃ��������b�g�����A�ٗp�̑����̂ق����͂邩�ɑ傫�����Ƃ��킩��܂��B ���̉��i�́u�����d�����v�������āA2�����Ƃ�3�����ɂ͂Ȃ���̂́A�[���ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�X�[�p�[�ŁA���i���[���~�Ŕ̔����Ă��邱�Ƃ͂���܂���B����A�ٗp�̓[���ɂȂ�A�ďA�E��7�����Ƃ�8�����ɂȂ�Ƃ������Ƃł��B�ٗp�Ɋւ��ẮA�����d�������Ȃ��̂ł��B ���ꂪ�A�R���T���^���g��]�_�Ƃ������A�O���[�o�����i���f�t���X���j�Ō����Ƃ��Ă���_�ł��B�Ȃ̂ŁA�č������g�����v�哝�̂ɓ��[�������Ƃ��A��ʍ����̐����������炷��Γ��R�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B �����ɂ͉����d�������Ȃ� ���Ȃ݂ɁA���̉��i�̉������ƁA�ٗp�r�����i�l����팸���j�̍��́A�ǂ��ɏ������̂ł��傤���H ����́A�O���[�o����Ƃ̓������ۂƁA�r�㍑�̒����A�b�v�ɗ��ꂽ�킯�ł��B ��i���ł́A�ٗp���Ȃ��Ȃ�A�i�C�����Ɛ��{�̎Љ�ۏ������N����܂��B����ɁA�O���[�o����ƂƓr�㍑�̒����A�b�v���i�݂܂��B �r�㍑�̐����R�X�g�͈����A�܂���i�����݂̕����ɂȂ�ɂ͎��Ԃ�������܂��B����A��i���ł́A�ٗp�������Ă��A�r�㍑�̂悤�ȕ����ɂ܂ł͂Ȃ�܂���B �����̉����d�����B���ꂪ�O���[�o�������߂���c�_�̃J���N���ł��B������_�����A���ۂ̐��������̕����������킯�ł��B�̂̌o�σA�i���X�g�Ȃǂł��A�����̉����d������M���Ă���l�����܂��B�����������́A�����̕��ɉ����d����������A�����ɂ͉����d�����͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�Ȃ��A�g�����v�����́u�A�����J����`�v�����s�ł���̂�
�g�����v�������{�i�n�����A�ٗp�����̎{��E�s���葱���̊ȑf���Ȃǂ�i�߂Ă��܂��B���́A���{���A�o�ϕ���ł́u���{����`�v��i�߂邱�Ƃ��\�ȃ|�W�V�����ɂ��܂��B�u���{����`�v�Ƃ����ƌR���ʂ�z���������ł����A�����ł́u�o�ϕ���v�̘b�ł��B �Ƃ���ŁA�g�����v�����́u�A�����J����`�v�́A�Ȃ��\�Ȃ̂ł��傤���B���̗��R�́A�傫�ȏ���s����A�����J���g�������Ă��邽�߂ł��B����A����Ȕ�����ł���킯�ł��B �ŋ߂̃A�����J�́A�O���[�o�����Ƃ����R�f�ՂƂ������ڂ�����A�傫�Ȕ�����̗͂����܂����������Ƃ��ł��Ă��܂���ł����B���������Ă���̂ɁA���g�̌ٗp�͎����A���ԑw�����ƕn�������N�����Ă����̂ł��B�u����͂��������v�Ƃ������ƂŁA�����]���������킯�ł��B ���́u���{�v�͗L���ȃ|�W�V�����ɂ��� �ł́A���{�̗���͂ǂ��Ȃ̂ł��傤�B����܂ł͖f�Ֆ��C�Ƃ��A���̈�ӓ|�ł��ˁB GDP�����Ă݂܂��傤�B���{��GDP�́A1990�N��ɂ́A�A�����J�ɒǂ��������ł����B�������A���̌�͐��E�̌o�ϐ����̐����i���������j�Ɏ��c����A�����Ƃ����ԂɃ|�W�V�������ቺ���܂����B 1995�N��2000�N��2005�N��2010�N��2014�N
�i����GDP�A�ăh���A�P��100���h���A������HP���j ���{�F534��473��457��551��460 �A�����J�F766��1028��1309��1496��1734 �����F73��120��229��600��1043 �A�����J��4����1�A�����̔����Ƃ����̂��A�ŋ߂̓��{�̎p�ł��B �������A���E�̌o�ϐ����ɗ������ڂꂽ�Ƃ͂����A��Ίz�ł͉��B�̃h�C�c��t�����X�Ȃǂ���ł����A�p��������ł��B 1995�N��2000�N��2005�N��2010�N��2014�N
�i����GDP�A�ăh���A�P��100���h���A������HP���j ���{�F534��473��457��551��460 �C�M���X�F123��155��241��240��298 �h�C�c�F259��194��286��341��386 �t�����X�F160��136��220��264��282 �C�^���A�F117��114��185��212��214 ������������́A�o�ς́u���{����`�v�ɔ��Ɍ����Ă���̂ł��B���́u���{����`�v�́A�ٗp�n�o�ł��B�܂�A����܂œ��{����肾������l�������Ȃ��������ƁA���{�̋���ȏ���s������p����Ƃ������Ƃł��B �葱���̊ȑf���ȂǁA�O����Ƃ̊����ɕX���͂������ŁA�g�����v�����̂悤�ɁA���������悢�̂ł��B
◾�u���ꂾ�����{�s��Ŗׂ��Ă܂��ˁv
◾�u���Y���_�̈ꕔ�ł��A���{�Ɉڂ��Ă��炦�܂��v
◾�u���p�b�P�[�W�����ł��A���\�ł��v
◾�u�ǂꂾ���A���{�l���ٗp���Ă��܂����H�v
◾�u���{�̋Ǝ҂ɔ������Ă��܂����H�v ����ȓ��{�̏���s��Ŗׂ��Ă���O����ƂɁA���̂悤�ɐ��������Ă����Ηǂ��Ƃ������Ƃł��B ������̗͂͋����ł��B���z�����]������A���̂悤�ɂ��đ�ʂ̌ٗp�ݏo�����Ƃ͉\�ł��B���{�l�I�ɂ́A�u����Ȃ���炵�����Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ƃ������o�ł��傤�B�������A�O���͂����������ƂC�ł��܂��B���ē��{���f�Ֆ��C�ŋ�J�����̂Ƃ́A�S���t�̘b�ł��B
���{�́u���{�̋���ȏ���s��v�̗͂����p����
����́A���{���A�O���l�ό��q�̏W�q����肾�����̂Ǝ��Ă��܂��B���ł����ϋɓI�ɊO���l�ό��q���W�q���Ă��܂����A���Ă̓��{�́A�C�O���s�ɂ͍s���Ă��A�O���l�����{�ɗ��邱�Ƃ͍l�������܂���ł����B ����Ɠ��l�ɁA���{�̋���ȏ���s��̗͂����p���邱�Ƃ͂قƂ�Ǎl�����܂���B����ȏ���s������p���āA���{�ł̌ٗp�ݏo���B����͔�����̃p���[������܂��̂ŁA�ɂ߂ėL���ł��B����́A�����Ԃꂽ�Ƃ͂����A���܂��ɐ��E�L����GDP�E����s������u���{�v�����炱���ł���A�����Ă�����@�ł��B �u������A�����J�ɍH���߂��Ă��v�_�̌�� ��胁�f�B�A�ł́A�����琻���Ƃ̋��_���A�����J�ɖ߂��Ă��d�����Ȃ��A�R�X�g�������������Ƃ����_���������ł��ˁB�������ď���҂��������i�����ƂɂȂ邾���A�Ƃ��B�ł��A���i���i�̉������̉��������A�ٗp�̉��l�̕����傫���Ƃ����b�͐�ɏq�ׂ��ʂ�ł��B �u�����琻���Ƃ��A�����J�ɖ߂��Ă��v�_�́A�R���h���`�F�t�T�C�N���Łu�Z�p�v�V�̎���v�ɓ�����邱�Ƃ��֘A���Ă��܂��B IT�EAI����Ő��E��Ƒ�����A�����J�ɁA�����Ƃ̋��_���ڂ��Ɖ����N����̂��B�z�������Ȃ��AIT�EAI�Ɛ����Ƃ̗Z���A�V���i�Ȃǂ��o�Ă���\��������̂ł��B �Ⴆ�Ύ����ԋƊE�ł́A�d�C�����Ԃ�����܂ł̎����ԎY�Ƃ�傫���ς���\�����o�Ă��Ă��܂��B�d�C�œ����d�g�݂ɕς��܂��ƁA����܂ŏd�v���������i������Ȃ��Ȃ�����A�ȒP�Ȃ���ł悭�Ȃ�����A�傫���ς��܂��B�����Ԃ́u�Ɠd���v�����蓾��킯�ł��B�����ɁAIT��AI�����т��Ɓc�B����܂œr�㍑�Œ�R�X�g�ŏ]���ʂ�ɐ������Ă������@���A�ꋓ�ɕς�邩������Ȃ��̂ł��B �u������_�v�́A����̉������オ�O�� �u������_�v�́A����܂łƓ��������Ԃ����@�ł���Ƃ������Ƃ��O��ɂȂ��Ă��܂��B���̂܂܉����ς��Ȃ��̂ŁA������������ǂ��Ɍ��܂��Ă���Ƃ������z�ł��B �������A����������̉�������ɂ���Ƃ͌��炸�A�z���ȏ�̋Z�p�v�V���N���鎞��ւƈڂ��Ă��Ă��܂��B�������čl����ƁA�A�����J�ɐ����Ƃ̋��_��u�����Ƃ́A�}�C�i�X�ł͂Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B����Ȃ�̃����b�g���o�Ă���͂��ł��B ���Z�ɗႦ�܂��ƁANY�̓I�t�B�X�����������ł����A���E�̋��Z�n��Ƃ�NY�ɏW�܂��Ă��܂��B�R�X�g�����l����A�c�ɂɉ�Ђ��������ق��������ł���ˁB�������A�����͂Ȃ��Ă��܂���B�s��̕��������b�g������̂ŁANY�ɏW�܂�̂ł��B �ł����琻���Ƃ��AIT��AI�̋Z�p�v�V���ڊo�܂����A�����J�ɋ��_��u�����ƂŁA�z���O�̃����b�g���o�Ă���\���������̂ł��B
|
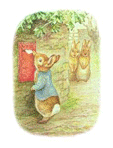
 �X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B