•؟’JچsگlپuŒ›–@9ڈً‚جچ،“ْ“Iˆس‹`پv(2016”N1Œژ23“ْچu‰‰‚جƒeƒLƒXƒg‹N‚±‚µ)
•؟’Jچsگl پuŒ›–@9ڈً‚جچ،“ْ“Iˆس‹`پv ژs–¯کAچ‡ ٹî’²چu‰‰ 2016.1.23پiPlaceUniversityپj
پm0:35پn چ،“ْ‚حŒ›–@9ڈً‚ة‚آ‚¢‚ؤکb‚µ‚ـ‚·‚ھپA‚»‚ج‘O‚ةˆê‚آ‚¢‚ء‚ؤ‚¨‚«‚½‚¢‚±‚ئ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پBچً”N‚ج‹مŒژپAƒ\ƒEƒ‹‚ج‰„گ¢پiƒˆƒ“ƒZپj‘هٹw‚إ‚ ‚ء‚½پu•½کa‚ةٹض‚·‚éچ‘چغ‰ï‹cپv‚إچu‰‰‚µ‚ـ‚µ‚½پB‚»‚ج‚ئ‚«‚ة‚¶‚آ‚حŒ›–@9ڈً‚ة‚آ‚¢‚ؤکb‚µ‚½‚ٌ‚إ‚·‚ھپAچ،“ْکb‚µ‚½‚¢‚ج‚ح‚»‚ج‰ï‹c‚إ•·‚¢‚½‚±‚ئ‚ھ‚ç‚إ‚·پB‚»‚ج‰ï‹c‚إ‚حپAژ„‚ھکb‚·‘O‚ة‰„گ¢‘هٹw‚جچ‘چغگژ،ٹw‚ج•¶پiƒ€ƒ“پj‹³ژِ‚ھچu‰‰‚µ‚ـ‚µ‚ؤپA‚»‚جچإŒم‚ة‚±‚¤‚¢‚¤‚±‚ئ‚ً‚¢‚ء‚½پB“ْ–{‚إ‚حچإ‹كژل‚¢گl‚½‚؟‚ھگ·‚ٌ‚ةƒfƒ‚‚ً‚â‚ء‚ؤ‚¢‚ؤ‚·‚خ‚炵‚¢پB‚»‚ê‚ةˆّ‚«‚©‚¦ٹطچ‘‚إ‚حژلژز‚حگژ،ٹˆ“®‚ً‚µ‚ب‚¢پBڈ«—ˆ‚ًچl‚¦‚é‚ئˆأàW‚½‚é‹Cژ‚؟‚ھ‚·‚é‚ئپB‚»‚¤‚¢‚ء‚ؤچu‰‰‚ً’÷‚ك‚‚‚ء‚½‚ي‚¯‚إ‚·پB‹ژ”N‚ج‹مŒژ”¼‚خ‚إ‚·‚©‚ç‚ـ‚¾“ْ–{‚جƒfƒ‚‚ج—]‰C‚ھژc‚ء‚ؤ‚¢‚½‚±‚ë‚إ‚·پBژ„‚ح”ق‚ج”Œ¾‚ً•·‚¢‚ؤ‹ء‚«‚ـ‚µ‚½پB‚»‚ê‚ـ‚إژ„‚حپA“ْ–{‚ة‚ح‚ب‚¢‚¯‚اٹطچ‘‚ة‚حƒfƒ‚‚ھ‚ ‚éپA‚ئ‚‚ةٹwگ¶‚جƒfƒ‚‚ھ‚ ‚é‚ئ‚¸‚ء‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚½پB‚و‚è‚ة‚à‚و‚ء‚ؤٹطچ‘گl‚©‚ç“ْ–{‚جƒfƒ‚‚ج‚±‚ئ‚إپAچ،Œم‚ةٹَ–]‚ھ‚ ‚é‚ئڈـژ^‚³‚ꂽپBپu‚¨‘O‚ة‚»‚ê‚ً‚¢‚ي‚ꂽ‚‚ب‚¢‚وپv‚ئ‚¢‚¤‚¢‚¢•û‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·‚¯‚اپAˆ«‚¢‚ئ‚«‚ةژg‚¤‚à‚ج‚ب‚ٌ‚إ‚·‚¯‚اپA—_‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ة‚»‚¤‚¢‚¢‚½‚‚ب‚ء‚½پB
پm2:30پn ‚ة‚ي‚©‚ةگM‚¶‚ç‚ê‚ب‚¢‚ج‚إپA‚»‚جŒم‚¢‚ë‚ٌ‚بگl‚ةˆسŒ©‚ً•·‚«‚ـ‚µ‚½پB‚·‚é‚ئ‚±‚¤‚¢‚¤‚±‚ئ‚ھ‚ي‚©‚è‚ـ‚µ‚½پB‚ق‚ë‚ٌٹطچ‘‚ة‚حƒfƒ‚‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB‘ه‚¢‚ة‚ ‚éپB‚ـ‚¾‰خ‰ٹ•r‚ً“ٹ‚°‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚¢‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚ ‚ـ‚è•ٌ“¹‚³‚ê‚ب‚¢‚¯‚اپB‚µ‚©‚µ‚»‚ê‚حژه‚ئ‚µ‚ؤکJ“ژز‚جƒfƒ‚‚إ‚ ‚ء‚ؤپAٹwگ¶‚ھƒfƒ‚‚ً‚µ‚ب‚‚ب‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حژ–ژہ‚ج‚و‚¤‚إ‚·پB——R‚حڈAگE‚ھ‘ه•د‚¾‚©‚ç‚إ‚·پB‚»‚جˆê•û‚إپAژ„‚حˆêگl‚جٹwگ¶‚©‚çگ[چڈ‚ب‘ٹ’k‚ًژَ‚¯‚ـ‚µ‚½پB”ق‚حپAŒR‘à‚ةچs‚«‚½‚‚ب‚¢پB‚µ‚©‚µپA‚»‚ج‚½‚ك‚ة‚ح–S–½‚·‚é‚ظ‚©‚ب‚¢‚ئŒ¾‚¤‚ٌ‚إ‚·پB“ْ–{‚إ‚àپA’¥•؛ٹُ”ً‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إٹطچ‘‚ة‹A‚ê‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤ٹطچ‘گl‚جژلژز‚ة‰ï‚ء‚½‚±‚ئ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB”ق‚ç‚ح“ْ–{‚جژلژز‚ئ‚حچھ–{“I‚ةˆل‚ء‚½ڈًŒڈ‚ة’u‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚»‚ج‚و‚¤‚بکb‚ً•·‚‚ئپA“ْ–{‚ةŒ›–@9ڈً‚ھ‚ ‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ًژہٹ´‚µ‚ـ‚·پB‚ئ‚à‚ ‚êپA“ْ–{‚ةژلژز‚جƒfƒ‚‚ھ‹N‚±‚ء‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ةٹ´–ء‚ًژَ‚¯‚½گl‚ھٹOچ‘‚ة‚¢‚½پBژ„‚ح‚»‚ê‚ً‚و‚낱‚خ‚µ‚ژv‚¢‚ـ‚µ‚½پB
پm4:10پn ژ„‚ح2002”NƒCƒ‰ƒNگي‘ˆ‚ج‚±‚ë‚©‚ç“ْ–{‚ة‚ب‚؛ƒfƒ‚‚ھ‚ب‚¢‚ج‚©‚ًچl‚¦‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پBƒfƒ‚‚ھ•K—v‚¾‚ئپB‚¾‚©‚ç2011”N•ں“‡‚جŒ´”ژ–Œج‚ئ‚ئ‚à‚ة‘ه‚«‚بƒfƒ‚‚ھ‹N‚±‚ء‚½‚ئ‚«پA‚±‚¤‚¢‚¢‚ـ‚µ‚½پBƒfƒ‚‚ب‚ا‚إژذ‰ï‚ھ•د‚ي‚é‚©‚ئ‚¢‚¤گl‚½‚؟‚ھ‚¢‚éپB‚µ‚©‚µƒfƒ‚‚إژذ‰ï‚حٹmژہ‚ة•د‚ي‚éپB‚ب‚؛‚ب‚çƒfƒ‚‚ً‚·‚ê‚خپA“ْ–{‚حگl‚ھƒfƒ‚‚ً‚·‚éژذ‰ï‚ة•د‚ي‚é‚©‚炾‚ئپBٹm‚©‚ةٹطچ‘‚ج‹³ژِ‚ح“ْ–{‚ھƒfƒ‚‚ً‚·‚éژذ‰ï‚ة‚ب‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ً”F‚ك‚½‚ي‚¯‚إ‚·پBژ„‚ج‚ف‚é‚ئ‚±‚ë‚»‚ê‚ـ‚إ“ْ–{‚إ‚حپAƒfƒ‚‚حژè’i‚إ‚ ‚é‚ئŒ©‚ب‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پBˆê‚آ‚ة‚حٹv–½‚ج‚½‚ك‚جژè’i‚إ‚·پB‚»‚ج‚½‚ك‚ة‰كŒƒ‚بƒfƒ‚‚ھ’ا‹پ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½پB‚à‚¤ˆê‚آ‚ح‘I‹“‚ج‚½‚ك‚جژè’i‚¾‚ئ‚¢‚¤چl‚¦‚إ‚·پBƒfƒ‚‚ة‚و‚ء‚ؤگlپX‚ةˆسŒ©‚ً‘i‚¦‚éپA‘I‹“‚إ‚»‚ê‚ًژہŒ»‚·‚é‚ئپB‚±‚ج“ٌ‚آ‚جچl‚¦‚ھپA“ْ–{‚إƒfƒ‚‚ً‚¾‚ك‚ة‚µ‚ؤ‚«‚½‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB‘O‚ج•û‚ج‚ح‚ح‚ء‚«‚肵‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‰كŒƒ‚بƒfƒ‚‚ھ‚ ‚ء‚½‚½‚ك‚ة•پ’ت‚جگl‚حƒfƒ‚‚ةچs‚©‚ب‚‚ب‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤—ًژj“I‚بژ–ژہ‚ھ‚ ‚é‚©‚ç‚إ‚·پB‚½‚¾پAŒمژز‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حچl‚¦‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ئژv‚¤‚ٌ‚إ‚·پB‚µ‚©‚µپA‚¶‚آ‚حچ،‹N‚±‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ح‚»‚ê‚ئŒq‚ھ‚é–â‘è‚إ‚·پBچً”N‚ج‰ؤ‚ة‚ ‚ء‚½ƒfƒ‚‚ً‚آ‚¬‚ج‘I‹“‚ة—LŒّ‚ةگ¶‚©‚»‚¤‚ئ‚·‚éپB‚»‚ê‚ح‚و‚¢‚إ‚·پB‚µ‚©‚µپA‚±‚±‚إ–Y‚ê‚ؤ‚à‚ç‚¢‚½‚‚ب‚¢–â‘è‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB‚»‚ê‚حپAƒfƒ‚‚ح‚¯‚ء‚µ‚ؤ‘I‹“‚ج‚½‚ك‚جژè’i‚إ‚ح‚ب‚¢پA‘I‹“‚ ‚é‚¢‚حگ“}گژ،‚ةڈ]‘®‚·‚é‚و‚¤‚ب‚à‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚·پB
پm6:28پn ژ„‚حˆب‘Oƒfƒ‚‚ة‚آ‚¢‚ؤچl‚¦‚½ژپA‚آ‚¬‚ج‚و‚¤‚ب‚±‚ئ‚ة‹C‚أ‚«‚ـ‚µ‚½پB“ْ–{Œê‚إ‚حƒfƒ‚‚حڈW‰ï‚ئ‹و•ت‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚µ‚©‚µ‰pŒê‚إ‚¢‚¤‚ئپAƒfƒ‚‚ً•\‚·‚¢‚¢•û‚ح‚¢‚ë‚¢‚ë‚ ‚è‚ـ‚·‚ھپAگ³ژ®‚ة‚حassembly‚إ‚·پB‚»‚ê‚ح“ْ–{Œê‚إپuڈW‰ïپv‚ئ–َ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚¾‚©‚çƒfƒ‚‚àڈW‰ï‚àassembly‚ب‚ٌ‚إ‚·‚ثپB“ْ–{‚جŒ›–@21ڈً‚ة‚حپuڈW‰ïپAŒ‹ژذپA•\Œ»‚جژ©—Rپv‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·‚¯‚ê‚ا‚àپAپuƒfƒ‚‚جژ©—Rپv‚ھ‚ب‚¢پB‚¾‚©‚ç‚©‚آ‚ؤ‚حپuƒfƒ‚‚جژ©—Rپv‚ًپu•\Œ»‚جژ©—Rپv‚©‚çچھ‹’‚أ‚¯‚é‚و‚¤‚بک_‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½‚¯‚اپA’Pڈƒ‚بŒë‰ً‚إ‚·پBƒfƒ‚‚حassembly‚إ‚ ‚éپB‚¾‚©‚çپuڈW‰ï‚جژ©—Rپv‚ھپuƒfƒ‚‚جژ©—Rپv‚ًˆس–،‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ي‚¯‚إ‚·پB‚؟‚ب‚ف‚ةŒ›–@21ڈً‚ة‚ ‚éپuŒ‹ژذ‚جژ©—Rپv‚ئ‚¢‚¤•\Œ»پA‚±‚ê‚ح‚ي‚©‚ç‚ب‚¢‚à‚ج‚إ‚·پB‚±‚ê‚ح‰pŒê‚إ‚¢‚¤‚ئassociation‚جژ©—R‚ب‚ٌ‚إ‚·پBپuŒ‹ژذپv‚ئ‚¢‚¤‚ئ‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‚جگl‚ح”é–§Œ‹ژذ‚®‚ç‚¢‚µ‚©ژv‚¢•‚‚©‚خ‚ب‚¢‚ٌ‚إ‚·پBassociation‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ح‚ا‚±‚ة‚إ‚à‚ ‚é‚à‚ج‚إ‚·پBڈ¬ٹwچZ‚ةچs‚¯‚خ‚ ‚è‚ـ‚·پBPTA‚جA‚¾‚©‚çپBگe‚ئ‹³ژt‚جassociation‚ب‚ٌ‚إ‚·‚وپB‚آ‚ـ‚è”ٌڈي‚ة‚ ‚è‚س‚ꂽŒ¾—t‚إ‚·پB“ْ–{Œê‚إ‚¢‚¦‚خassembly‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حٹٌچ‡‚إ‚·پB‚ا‚ج‘؛‚â’¬‚ة‚àٹٌچ‡‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پBچ،‚à‚ ‚é‚ئژv‚¢‚ـ‚·پAڈٹ‚ة‚و‚ء‚ؤ‚حپB‚»‚ê‚ھŒ³‚ة‚ب‚é‚ي‚¯‚إ‚·پBگ¼—m‚إ‚ح‚»‚¤‚¢‚¤ٹٌچ‡‚ھ‹c‰ï‚ة‚à‚ب‚ء‚½‚ي‚¯‚إ‚·پB‚¾‚©‚ç‹c‰ï‚حassembly‚ئ‚¢‚¤‚ٌ‚إ‚·پBٹٌچ‡‚إ‚·پB‚آ‚ـ‚è‹c‰ï‚ئƒfƒ‚‚حگeگت‚ج‚و‚¤‚ب‚à‚ج‚إ‚·‚ثپB‚½‚ئ‚¦‚خپAƒ‹ƒ\پ[‚ھپwژذ‰ïŒ_–ٌک_پx‚إپuŒ —ح‚ح–¯ڈO‚جassembly‚ًŒ™‚¤پv‚ئڈ‘‚¢‚ؤ‚¢‚éپB‚»‚جڈêچ‡پAassembly‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ح‹c‰ï‚ئ‚¢‚¤‚و‚è‚àڈW‰ïپEƒfƒ‚‚ئ‚¢‚¤ˆس–،‚¾‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB—ًژj“I‚ة‚حگâ‘خ‰¤گ‚ة‘خ‚·‚éassembly‚إ‚·‚ثپBڈW‰ïپEƒfƒ‚‚ھ‚¾‚ٌ‚¾‚ٌ‚ئ‘ه‚«‚‚ب‚ء‚ؤ‹c‰ï‚ئ‚µ‚ؤڈ³”F‚³‚ê‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½‚ي‚¯‚إ‚·پB‚»‚جˆس–،‚إ‹c‰ï‚ج‹NŒ¹‚حƒfƒ‚پEڈW‰ï‚ب‚ٌ‚إ‚·‚ثپB‚ـ‚½ƒ‹ƒ\پ[‚ح‚±‚¤‚¢‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBگl–¯‚حڈW‰ï‚ة—ˆ‚½‚ئ‚«‚ة‚¾‚¯ژهŒ ژز‚ئ‚µ‚ؤچs“®‚µ‚¤‚é‚ئپBگl–¯‚ئ‚¢‚¤ژهŒ ژز‚حŒآپXگl‚إ‚ح‚ب‚¢‚ٌ‚إ‚·پBŒآپXگl‚ھڈW‰ï‚ً‚µ‚½‚ئ‚«‚ة“oڈê‚·‚é‚à‚ج‚إ‚·پB‚»‚±‚ةƒ‹ƒ\پ[‚ھ‚¢‚¤پuˆê”تˆسژvپv‚à‘¶چف‚µ‚ؤ‚é‚ي‚¯‚إ‚·پBŒآپXگl‚ًڈW‚ك‚½‘چکa‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB‚»‚جڈW‰ï‚ة‚¨‚¢‚ؤپuˆê”تˆسژvپv‚ھ‘¶چف‚·‚éپB‚¾‚©‚烋ƒ\پ[‚ح“¯ژ‘م‚ج‹c‰ïگ§‚ھ”’B‚µ‚½ƒCƒMƒٹƒX‚ة‚©‚ٌ‚µ‚ؤ‚±‚¤‚¢‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBƒCƒMƒٹƒX‚جگl–¯‚حژ©—R‚¾‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ھپA‚»‚ê‚ح‘ه‚ـ‚؟‚ھ‚¢‚¾پB”ق‚ç‚ھژ©—R‚ب‚ج‚ح‹cˆُ‚ً‘I‹“‚·‚é‚ ‚¢‚¾‚¾‚¯‚ج‚±‚ئ‚إپA‹cˆُ‚ھ‘I‚خ‚ê‚é‚â‚¢‚ب‚âپAƒCƒMƒٹƒXگl‚ح“z—ê‚ئ‚ب‚èپA–³‚ة‹A‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚ئپB‚ـ‚½ƒ‹ƒ\پ[‚ح‚±‚¤‚à‚¢‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‘م•\ژز‚ئ‚¢‚¤چl‚¦‚ح‹كگ¢‚ج‚à‚ج‚إ‚ ‚éپB‚»‚ê‚ح••Œڑگژ،‚ة—R—ˆ‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئپB‚آ‚ـ‚èپA‘م•\گ§‹c‰ï‚ة‚حژهŒ ژز‚ئ‚µ‚ؤ‚جگl–¯‚ح‚¢‚ـ‚¹‚ٌپB‘م•\ژز‚ح••Œڑگ§‚ة‚¨‚¯‚é—جژه‚ج‚و‚¤‚ب‚à‚ج‚إ‚·پB‚»‚ج‚±‚ئ‚حŒ»چف‚ج“ْ–{‚ج‘م‹cژm‚ً‚ف‚é‚ئ‚و‚‚ي‚©‚è‚ـ‚·پBˆہ”{ژٌ‘ٹ‚ًڈ‰‚كپA”ق‚ç‚ج‘½‚‚ح‰½‘م‚ة‚à‚ي‚½‚éگ¢ڈP‚إ‚·پB“؟گىژ‘م‚ج•û‚ھ—{ژqگ§‚ھ‚ ‚ء‚½‚©‚çچ،‚و‚è‚ح‚ـ‚µ‚إ‚·پB‚±‚ٌ‚ب‹c‰ï‚ةژهŒ ژز‚ئ‚µ‚ؤگl–¯‚ھ‘¶چف‚·‚é‚ح‚¸‚ھ‚ب‚¢پB‚»‚ê‚ھ‘¶چف‚·‚é‚ج‚ح‚à‚¤ˆê‚آ‚جassembly‚·‚ب‚ي‚؟ƒfƒ‚پEڈW‰ï‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚إ‚·پB
پm11:25پn ‹c‰ï‚ھ‚ـ‚ء‚½‚گl–¯ژهŒ ‚ة”½‚·‚é‚©‚ئ‚¢‚¤‚ئپA‚»‚¤‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB‹c‰ï‚àƒfƒ‚پEڈW‰ï‚ئ‚¢‚¤assembly‚ً”½‰f‚·‚é‚©‚¬‚èپA‚»‚ج‚©‚¬‚è‚إگl–¯ژهŒ “I‚إ‚ ‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ـ‚·پB‚½‚ئ‚¦‚خپA‘I‹“‚ة‚و‚ء‚ؤŒˆ‚ـ‚ء‚½‚±‚ئ‚ًƒfƒ‚‚إ•د‚¦‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚ج‚ح–¯ژهژه‹`‚ة”½‚·‚é‚ئ‚¢‚¤—ق‚ج”Œ¾‚ً‚µ‚½گژ،‰ئ‚ھ‚¢‚ـ‚µ‚½پB‚±‚ê‚ح–¯ژهژه‹`‚ھ‰½‚إ‚ ‚é‚©‚ًچl‚¦‚½‚±‚ئ‚ھ‚ب‚¢‚ٌ‚¾‚ئژv‚¤‚ٌ‚إ‚·پB‘I‹“‚إŒˆ‚ك‚½‚±‚ئ‚ًƒfƒ‚‚إڈCگ³‚·‚邱‚ئ‚ھ‚ ‚肤‚é‚ئ‚«‚ةگl–¯ژهŒ ‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ھ‚إ‚«‚é‚ٌ‚إ‚·پB”½Œ´”‚جچ‘‰ï‘Oƒfƒ‚پEڈW‰ïپA‚ـ‚½‚»‚êˆبŒم‚جچ‘‰ï‘Oƒfƒ‚پEڈW‰ï‚إ‚حپA‚¨‚à‚µ‚ë‚¢Œ»ڈغ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB‚»‚ê‚حچ‘‰ï‚ج‘O‚¾‚ء‚½‚©‚ç‚¢‚¦‚é‚ٌ‚إ‚·‚¯‚اپA“ٌ‚آ‚جassembly‚ھ’¼–ت‚µ‚½‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚·پBƒfƒ‚‚ئ‹c‰ïپBƒfƒ‚‚ج‘¤‚©‚çچ‘‰ï‚ةچs‚‚±‚ئ‚ح‚ب‚¢‚إ‚·‚ھپAچ‘‰ï‚ج‘¤‚©‚çƒfƒ‚‚ةˆ¥ژA‚ة—ˆ‚ؤ‚¢‚éپBگژ،‰ئ‚ھ—ˆ‚ـ‚µ‚½پB‚ب‚؛‚ب‚ç‚خپAƒfƒ‚‚ھ–{“–‚جassembly‚¾‚©‚ç‚إ‚·پBˆê•ûپAˆêچً”N‘نکp‚ج‚ذ‚ـ‚ي‚èٹv–½‚إ‚حپAƒfƒ‚‚ج•û‚ھچ‘‰ï‚ةچs‚«‚ـ‚µ‚½پB‚»‚ê‚ة‚و‚ء‚ؤ‚ق‚µ‚ëƒfƒ‚‚±‚»–{—ˆ‚جassembly‚إ‚ ‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ًژ¦‚µ‚½‚ي‚¯‚إ‚·پBگو“ْ”ق‚ç‚ح‘I‹“‚إڈں‚؟‚ـ‚µ‚½پB‚µ‚©‚µپA‚ ‚ê‚حƒfƒ‚‚ج‰„’·‚¾‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB‚ـ‚½‚»‚¤‚إ‚ب‚¢‚ئچ،Œم‚¾‚ك‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB‚µ‚½‚ھ‚ء‚ؤپA‚ي‚ê‚ي‚ê‚حƒfƒ‚پEڈW‰ï‚ً‚½‚ٌ‚ب‚éژè’i‚ئŒ©‚ب‚µ‚ؤ‚ح‚¢‚¯‚ب‚¢پB‚»‚±‚ةژهŒ ژز‚ئ‚µ‚ؤ‚جگl–¯‚ھ‚¢‚é‚ئ‚¢‚¤‚ي‚¯‚إ‚·‚©‚çپB‚»‚ê‚حگ”‚ج–â‘è‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپBƒfƒ‚پEڈW‰ï‚ھŒ´“_‚إ‚ ‚éپB‚»‚ج‚±‚ئ‚ًژ„‚حچؤٹm”F‚µ‚ؤ‚¨‚«‚½‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB
پm13:47پn ژ„‚جچ،“ْ‚جچu‰‰‚حپuŒ›–@9ڈً‚جچ،“ْ“Iˆس‹`پv‚ئ‚¢‚¤‘è‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپA‚±‚ê‚حژ„‚ھŒˆ‚ك‚½‚à‚ج‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB‹C‚ھ‚آ‚‚ئ‚»‚¤‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½پB‚à‚؟‚ë‚ٌŒ›–@9ڈً‚ة•پ•ص“I‚بˆس‹`‚ھ‚ ‚邱‚ئ‚ح‚ـ‚؟‚ھ‚¢‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB‚½‚ئ‚¦‚خŒ›–@9ڈً‚حپAƒJƒ“ƒg‚جپw‰i‰“•½کa‚ج‚½‚ك‚ةپxپA‚ ‚é‚¢‚حپwگ¢ٹEژj“Iژs–¯“I—§ڈê‚©‚ç‚ف‚½گl—ق‚ج•پ•صژj‚جچ\‘zپx‚ئ‚¢‚¤‚à‚ج‚©‚ç—ˆ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBƒJƒ“ƒg‚ج—”O‚ح‘وˆêژں‘هگيŒمپA1920”N‚جچ‘چغکA–؟‚ئ‚µ‚ؤŒ‹ژہ‚µ‚ـ‚µ‚½پB1928”N‚ة‚حگي‘ˆ‚ًˆل–@‰»‚·‚éپuƒpƒٹ•sگيڈً–ٌپv‚ھچى‚ç‚ꂽپBŒ›–@9ڈً‚ح‚»‚ê‚ًژَ‚¯‚آ‚®‚à‚ج‚إ‚·پBژ–ژہ‰pŒê”إ‚إ‚ف‚é‚ئŒ›–@9ڈً‚ة‚ح‚»‚ج’†‚©‚çژو‚ç‚ꂽ•\Œ»‚ھژc‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚µ‚©‚µپAژ„‚حچ،“ْ‚»‚ج‚±‚ئ‚ة‚آ‚¢‚ؤŒê‚邱‚ئ‚ح‚µ‚ـ‚¹‚ٌپB‚ف‚ب‚³‚ٌ‚حŒ›–@9ڈً‚ج•پ•ص“Iˆس‹`‚ًچؤٹm”F‚µ‚ؤپA‚»‚ê‚ة‚و‚ء‚ؤ‰üŒ›‚ً‘jژ~‚·‚é—ح‚ئ‚µ‚و‚¤‚ئچl‚¦‚ؤ‚¨‚ç‚ê‚é‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپA‚¶‚آ‚حژ„‚ح‚»‚ج•K—v‚ح‚ب‚¢‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ٌ‚إ‚·پB‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حپA‰üŒ›‚ھ‚ب‚³‚ê‚邱‚ئ‚ح‚ب‚¢‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚é‚©‚ç‚إ‚·پBچ،“ْ‚ح‚»‚جکb‚ً‚µ‚½‚¢پB‚ق‚µ‚ë‚»‚±‚ة•پ•ص“I‚بˆس‹`‚ھ‚ ‚é‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB
پm15:16پn “ْ–{‚جگيŒمŒ›–@‚حپA9ڈً‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚¢‚‚آ‚à‚ج“ن‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB‘وˆê‚ةپAگ¢ٹEژj“I‚ةˆظ—ل‚ج‚±‚ج‚و‚¤‚بڈًچ€‚ھگيŒم“ْ–{‚جŒ›–@‚ة‚ ‚é‚ج‚ح‚ب‚؛‚©‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚·پB‘و“ٌ‚ةپA‚»‚ê‚ھ‚ ‚é‚ة‚à‚©‚©‚ي‚炸ژہچs‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ج‚ح‚ب‚؛‚©‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚·پB‚½‚ئ‚¦‚خژ©‰q‘à‚ھ‚ ‚èپA•ؤŒRٹî’n‚à‘½گ”‘¶چف‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‘وژO‚ةپA‚à‚µژہچs‚µ‚ب‚¢‚ج‚إ‚ ‚ê‚خ‚س‚آ‚¤‚ح–@‚ً•د‚¦‚é‚ح‚¸‚إ‚·‚ھپA9ڈً‚ح‚ـ‚¾ژc‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ح‚ب‚؛‚©‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚·پB‚ـ‚¸‘وژO‚ج“ن‚©‚çچl‚¦‚ؤ‚ف‚ـ‚µ‚ه‚¤پB‚»‚¤‚·‚ê‚خ‘و“ٌپA‘وˆê‚ج“ن‚à‰ً‚¯‚é‚ئژv‚¤‚©‚ç‚إ‚·پBژ©‰q‘à‚â•ؤŒRٹî’n‚ب‚ا‚حپAŒ›–@9ڈً‚ج‰ًژك‚ة‚و‚ء‚ؤچm’肳‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚ـ‚½پAڈW’c“Iژ©‰qŒ پA‚±‚ê‚حŒRژ–“¯–؟‚ج•ت–¼‚إ‚·پB‚»‚¤‚¢‚¤‚à‚ج‚à‰آ”\‚¾‚ئ‚¢‚¤‰ًژك‰üŒ›‚à‚ب‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚µ‚©‚µپAŒ›–@9ڈً‚ً•د‚¦‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ح‚¯‚ء‚µ‚ؤ‚ب‚³‚ê‚ب‚¢‚ج‚إ‚·پB‚ب‚؛‚»‚¤‚µ‚ب‚¢‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB‚ق‚ë‚ٌپA‚»‚ê‚ًŒِ‘R‚ئ’ٌ‹N‚·‚ê‚خ‘I‹“‚إ•‰‚¯‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚©‚ç‚إ‚·پB‚إ‚حپA‚ب‚؛•‰‚¯‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚ج‚©پBگlپX‚ھŒ›–@9ڈً‚ًژxژ‚·‚é‚ج‚حگي‘ˆ‚ض‚جگ[‚¢”½ڈب‚ھ‚ ‚é‚©‚炾‚ئ‚¢‚¤Œ©•û‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·‚ھپAژ„‚ح‚»‚ê‚ً‹^‚¢‚ـ‚·پB‚½‚ئ‚¦”sگيŒم‚ة‚»‚ج‚و‚¤‚ب‹Cژ‚؟‚ھ‚ ‚ء‚½‚ئ‚µ‚ؤ‚àپA‚»‚ê‚إŒ›–@9ڈً‚ج‚و‚¤‚ب‚à‚ج‚ھ‚إ‚«‚é‚ي‚¯‚ھ‚ب‚¢پBژ–ژہپA‚»‚ê‚ھ‚إ‚«‚½‚ج‚حگè—جŒR‚ھ–½‚¶‚½‚©‚ç‚إ‚·پB‚ـ‚½پAŒ›–@9ڈً‚ھگlپX‚جگي‘ˆ‘جŒ±‚ة‚à‚ئ‚أ‚¢‚ؤ‚¢‚é‚ج‚¾‚ئ‚µ‚½‚çپA‚»‚ê‚ًژ‚½‚ب‚¢گl‚ھ‘ه‘½گ”‚ة‚ب‚ê‚خڈء‚¦‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚إ‚µ‚ه‚¤پBژہچغپA‚»‚¤‚ب‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئŒىŒ›ک_ژز‚حŒœ”O‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚إ‚ح‚ب‚؛9ڈً‚ھچ،‚àژc‚èپA‚ـ‚½گlپX‚ح‚»‚ê‚ًژç‚낤‚ئ‚·‚é‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پBŒىŒ›ک_ژز‚حپA‚»‚ê‚حژ©•ھ‚ç‚ھگي‘ˆ‚جŒoŒ±‚ً“`‚¦پA‚ـ‚½Œ›–@9ڈً‚جڈd—v‚³‚ً‘i‚¦‚ؤ‚«‚½‚©‚炾‚ئ‚¢‚¤‚إ‚µ‚ه‚¤پB‚ھپA‚»‚ê‚ح‹^‚ي‚µ‚¢پB
پm17:35پn ‚±‚±‚إ–â‘è‚ً‚»‚ج”½‘خ‚ج‘¤‚©‚çپA‚آ‚ـ‚茛–@9ڈً‚ً”pٹü‚µ‚½‚¢‚ئچl‚¦‚ؤ‚¢‚鑤‚©‚ç‚ف‚ؤ‚ف‚½‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB”ق‚ç‚ح60”N‚ة‚ي‚½‚ء‚ؤ‚±‚ê‚ً”pٹü‚µ‚و‚¤‚ئ‚µ‚ؤ‚«‚½‚ھ‚إ‚«‚ب‚©‚ء‚½پB‚ب‚؛‚ب‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB”ق‚ç‚حپA‚»‚ê‚حچ‘–¯‚ج‘½‚‚ھچ¶—ƒ’mژ¯گl‚ةگô”]‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚©‚炾‚ئچl‚¦‚ـ‚·پB‚µ‚©‚µ‚±‚ê‚ح’[“I‚ة‚ـ‚؟‚ھ‚¢‚إ‚·پBچ¶—ƒ‚حŒ³—ˆŒ›–@9ڈً‚ةژ^گ¬‚إ‚ح‚ب‚©‚ء‚½‚©‚ç‚إ‚·پB‚½‚ئ‚¦‚خ1946”N6Œژ26“ْگVŒ›–@‚ًگR‹c‚·‚é’éچ‘‹c‰ïپA–ىچâژQژO‹¤ژY“}‹cˆُ‚حپAگي‘ˆ‚ة‚حگ³‚µ‚¢گي‘ˆ‚ئ‚»‚¤‚إ‚ب‚¢گي‘ˆ‚ھ‚ ‚éپBگN—ھ‚³‚ꂽچ‘‚ھ‘cچ‘‚ًژç‚邽‚ك‚جگي‘ˆ‚حگ³‚µ‚¢‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئڈq‚ׂـ‚µ‚½پB‚±‚ê‚حچ¶—ƒ‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚ح‚س‚آ‚¤‚جŒ©•û‚إ‚ ‚ء‚ؤپAŒم‚جگVچ¶—ƒ‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚à“¯‚¶‚إ‚·پB‚»‚ج’†‚ة‚حگشŒR”h‚ھ‚¢‚½‚©‚ç‚إ‚·‚©پAگVچ¶—ƒ‚ج‘½‚‚حŒم‚ةŒىŒ›”h‚ة“]‚¶‚ـ‚µ‚½پB‚µ‚©‚µپA”ق‚ç‚ھˆسŒ©‚ً•د‚¦‚½‚±‚ئ‚ً”ٌ“ï‚·‚éژ‘ٹi‚ح•غژç”h‚ة‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB‚½‚ئ‚¦‚خژٌ”ا‚ج‹g“c–خژٌ‘ٹ‚حپA–ىچâژQژO‚جژ؟–â‚ة‘خ‚µ‚ؤ‚±‚¤“ڑ‚¦‚½‚ٌ‚إ‚·پB‹ك”N‚جگي‘ˆ‚ج‘½‚‚حچ‘‰ئ–h‰qŒ ‚ج–¼‚ة‚¨‚¢‚ؤچs‚ب‚ي‚ꂽ‚邱‚ئ‚حŒ°’ک‚ب‚éژ–ژہ‚إ‚ ‚è‚ـ‚·پBŒج‚ةگ³“––h‰qŒ ‚ً”F‚ك‚邱‚ئ‚ھگي‘ˆ‚ً—U”‚·‚é‚ن‚¦‚ٌ‚إ‚ ‚é‚ئژv‚¤‚ج‚إ‚ ‚è‚ـ‚·‚ئپB‚³‚ç‚ة’©‘Nگي‘ˆ‚إƒAƒپƒٹƒJ‚©‚çچؤŒR”ُ‚ً”—‚ç‚ꂽ‚ئ‚«پA”ق‚ح‚»‚ê‚ً‹‘گ₵‚ؤ‚¢‚ء‚½پBچؤŒR”ُ‚ب‚ا‹ً‚جچœ’¸‚إ‚ ‚èپA’sگl‚ج–²‚إ‚ ‚é‚ئڈ‘‚¢‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚±‚ٌ‚ب‚±‚ئ‚ً‚¢‚¤•غژç”h‚ھچ،پcپc‚¢‚ب‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پBچ،‚â”ق‚ç‚حŒ›–@9ڈً‚ج‰ًژك‚إڈW’c“Iژ©‰qŒ پAŒRژ–“¯–؟‚ًگ³“––h‰qŒ ‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB—v‚·‚é‚ة•غژç”h‚ھˆسŒ©‚ً•د‚¦‚½‚ي‚¯‚إ‚·پB‚ئ‚±‚ë‚ھ”ق‚ç‚حŒ›–@9ڈً‚ً”pٹü‚µ‚و‚¤‚ئ‚ح‚µ‚ب‚¢پB‚ب‚؛‚©پB‚½‚ٌ‚ة‚»‚¤‚·‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ب‚¢‚©‚ç‚إ‚·پB‚à‚µ‚»‚ê‚ھ‘I‹“‚إ‘ˆ“_‚ئ‚ب‚é‚ب‚ç‚خپA‘ه”s‚·‚é‚ج‚حٹmژہ‚إ‚·پB‚µ‚½‚ھ‚ء‚ؤپA”ق‚ç‚ح‚²‚ـ‚©‚µ‚ب‚ھ‚ç‚â‚ء‚ؤ‚¢‚‚ظ‚©‚ب‚¢پB‰üŒ›‚ً–عک_‚ٌ‚إ60”N—]‚肽‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ة‚ـ‚¾‚إ‚«‚ب‚¢‚ٌ‚إ‚·‚ثپB‚»‚ê‚ح‚ب‚؛‚©پB”ق‚çژ©گg‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚à“ن‚ج‚ح‚¸‚إ‚·پB‚»‚ج“ن‚ً‰ً–¾‚µ‚و‚¤‚ئ‚¹‚¸‚ةپAچ¶—ƒگ“}پAگi•à“I•¶‰»گlپA’mژ¯گl‚ج‚¹‚¢‚ة‚·‚éپB‚»‚ê‚حژ©•ھ‚ج–³—حپA–³—‰ً‚ً’Iڈم‚°‚·‚邱‚ئ‚إ‚·پBŒ›–@9ڈً‚ھژ·X‚ةژc‚ء‚ؤ‚«‚½‚ج‚حپA‚»‚ê‚ًگlپX‚ھˆسژ¯“I‚ةژç‚ء‚ؤ‚«‚½‚©‚ç‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB‚à‚µ‚»‚¤‚إ‚ ‚ê‚خ‚ئ‚¤‚ةڈء‚¦‚ؤ‚¢‚½‚إ‚µ‚ه‚¤پBگlٹش‚جˆسژu‚ب‚ا‚ح‹C•´‚ê‚إگئژم‚ب‚à‚ج‚إ‚·پB9ڈً‚ح‚ن‚¦‚ة–³ˆسژ¯‚ج–â‘è‚ب‚ج‚إ‚·پB
پm21:06پn –³ˆسژ¯‚ئ‚¢‚¤‚ئˆê”ت‚ةپAˆسژ¯‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤’ِ“x‚جˆس–،‚إ—‰ً‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚ ‚é‚¢‚حگِچفˆسژ¯‚ئ“¯ˆêژ‹‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚½‚ئ‚¦‚خگé“`‚ب‚ا‚إ–³ˆسژ¯پAگِچفˆسژ¯‚ة“‚«‚©‚¯‚éƒTƒuƒٹƒ~ƒiƒ‹Œّ‰ت‚ً‘_‚¤‚±‚ئ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پBگو‚ظ‚ا‚à‚¢‚ي‚ꂽ‚و‚¤‚ة‰½‚ׂٌ‚àŒJ‚è•ش‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئگl‚ح‚¾‚ٌ‚¾‚ٌ‚ئژَ‚¯‚ئ‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚é‚ٌ‚¾‚ئ‚©‚»‚¤‚¢‚¤ˆس–،‚إ‚·پB‚µ‚©‚µپAƒtƒچƒCƒg‚ح‚»‚ج‚و‚¤‚ب‚à‚ج‚ً‘Oˆسژ¯‚ئŒؤ‚ٌ‚إپA–³ˆسژ¯‚ئ‚ح‹و•ت‚µ‚½‚ٌ‚إ‚·پB‚½‚¾ƒtƒچƒCƒg‚ھ‚¢‚¤–³ˆسژ¯‚ة‚à“ٌ‚آ‚جژي—ق‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پBˆê‚آ‚حƒGƒX‚ئ‚¢‚¤‚à‚ج‚إپAپu‚»‚êپv‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إپA–¼‚أ‚¯‚و‚¤‚ج‚ب‚¢‚à‚ج‚ًژw‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ي‚¯‚إ‚·پB‚à‚¤ˆê‚آ‚ح’´ژ©‰ن‚إ‚·پBژ„‚جچl‚¦‚إ‚حپAŒ›–@9ڈً‚ح’´ژ©‰ن‚ج‚و‚¤‚ب‚à‚ج‚إ‚·پB‚±‚ج‚و‚¤‚ب–³ˆسژ¯‚ج’´ژ©‰ن‚حپAˆسژ¯‚ئ‚حˆظ‚ب‚ء‚ؤپAگà“¾‚âگé“`‚ة‚و‚ء‚ؤ‘€چى‚·‚邱‚ئ‚ھ‚إ‚«‚ب‚¢‚à‚ج‚إ‚·پBŒ»‚ة•غژç”h‚ج60”Nˆبڈم‚ة‚ي‚½‚é“w—ح‚ح“kکJ‚ةڈI‚ي‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚¢‚‚ç”ق‚ç‚ھ9ڈً‚ح”ٌŒ»ژہ“I‚ب—‘zژه‹`‚إ‚ ‚é‚ئ‘i‚¦‚½‚ئ‚±‚ë‚إ–³‘ت‚إ‚·پB9ڈً‚ح–³ˆسژ¯‚جژںŒ³‚ةچھ‚´‚·‚à‚ج‚¾‚©‚çپAگà“¾•s‰آ”\‚ب‚ٌ‚إ‚·پBˆسژ¯“I‚بژںŒ³‚إ‚ ‚ê‚خگà“¾‚ح‚إ‚«‚ـ‚·‚¯‚اپB‚½‚¾‚µپA‚±‚ج‚±‚ئ‚ً—‰ً‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ج‚حŒىŒ›”h‚à“¯—l‚إ‚·پBŒ›–@9ڈً‚حپAŒىŒ›”h‚ھŒ[–ض‚·‚邱‚ئ‚ة‚و‚ء‚ؤ‘±‚¢‚ؤ‚«‚½‚ج‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB9ڈً‚حŒىŒ›”h‚ة‚و‚ء‚ؤژç‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢پB‚»‚ج‹t‚ةŒىŒ›”h‚±‚»Œ›–@9ڈً‚ة‚و‚ء‚ؤژç‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚éپBژ„‚ح‚»‚ê‚ً”ç“÷‚إ‚¢‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ي‚¯‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB‚½‚¾‚½‚ٌ‚ةˆہگS‚µ‚ؤ‚و‚¢‚ئ‚¢‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ٌ‚إ‚·پB‚»‚µ‚ؤ‚»‚جڈم‚إ‰½‚ً‚·‚ׂ«‚©پA‰½‚ً‚ب‚µ‚¤‚é‚©‚ًچl‚¦’¼‚µ‚ؤ‚ظ‚µ‚¢‚ج‚إ‚·پB
پm23:34پn ژ„‚حگيŒم“ْ–{‚ةگ¶‚ـ‚ꂽŒ›–@‚ة‚©‚ٌ‚µ‚ؤپAƒtƒچƒCƒg‚ج‚¢‚¤’´ژ©‰ن‚ئ‚¢‚¤ٹT”O‚ً“±“ü‚µ‚ؤچl‚¦‚و‚¤‚ئ‚µ‚ـ‚µ‚½پB‚±‚ê‚ح‚½‚ٌ‚ةگS—ٹw‚ج‰—p‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپBƒtƒچƒCƒg‚ھ’´ژ©‰ن‚ة‚آ‚¢‚ؤچl‚¦‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½‚±‚ئ‚حپAگ[‚گي‘ˆ‚ج–â‘è‚ئٹضکA‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚·پB‚»‚ê‚ة‚آ‚¢‚ؤڈ‚µڈq‚ׂؤ‚¨‚«‚½‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پBƒtƒچƒCƒg‚ح‘وˆêژں‘هگيŒم‚ةپA‚ ‚邱‚ئ‚ھ‚«‚ء‚©‚¯‚إ–³ˆسژ¯‚ة‚©‚ٌ‚·‚éچl‚¦‚ًچھ–{“I‚ة•د‚¦‚½‚ٌ‚إ‚·پB‚»‚ê‚ً‹«‚ة‚µ‚ؤ‘OٹْƒtƒچƒCƒg‚ئŒمٹْƒtƒچƒCƒg‚ة‹و•ت‚إ‚«‚é‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB‘Oٹْ‚جƒtƒچƒCƒg‚جچl‚¦‚إ‚حپA–³ˆسژ¯‚ھ—~–]‚ً–‚½‚»‚¤‚ئ‚·‚é‰ُٹ´Œ´‘¥‚ئپA‚»‚ê‚ً–‚½‚·‚±‚ئ‚ھ‚à‚½‚ç‚·ٹ댯‚ً”ً‚¯‚邽‚ك‚ة—}گ§‚µ‚و‚¤‚ئ‚·‚錻ژہŒ´‘¥‚ھ‚ ‚éپBŒ»ژہŒ´‘¥‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حپA‚¢‚¤‚ب‚ç‚خژذ‰ï‚ج‹K”ح‚إ‚·پBگe‚ً’ت‚µ‚ؤژq‚ا‚à‚ةچü‚èچ‚ـ‚ê‚éپB‚»‚ê‚ھ–³ˆسژ¯‚ة‚¨‚¢‚ؤگl‚ً‹Kگ§‚·‚éپA‚ ‚é‚¢‚حŒں‰{‚·‚é‚ي‚¯‚إ‚·پBƒtƒچƒCƒg‚جپw–²”»’fپx‚ح‚»‚ج‚و‚¤‚بچl‚¦‚ة‚à‚ئ‚أ‚¢‚ؤڈ‘‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚µ‚©‚µپA‚±‚جچl‚¦‚حگV‚µ‚¢‚à‚ج‚إ‚ح‚ ‚é‚ج‚إ‚·‚ھپA‚ ‚éˆس–،‚إ‚حڈيژ¯“I‚ب‚à‚ج‚إ‚·پB‚½‚ئ‚¦‚خپAگlٹش‚حژv‚¤‚ـ‚ـ‚ة—~–]‚ً–‚½‚·‚ي‚¯‚ة‚ح‚¢‚©‚ب‚¢پB‚¾‚©‚ç‚»‚ê‚ًŒ»ژہŒ´‘¥‚ة‚و‚ء‚ؤ—}گ§‚µ‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¯‚ب‚¢پB‚µ‚½‚ھ‚ء‚ؤژذ‰ï“I•¶‰»“I‚ب‹K”ح‚ةڈ]‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚éپB‚»‚ê‚ھگ¬ڈn‚·‚邱‚ئ‚إ‚ ‚éپB‚¾‚¯‚اپA“¯ژ‚ة‚ئ‚«‚ة‚ح‚»‚ê‚©‚ç‰ً•ْ‚³‚ê‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¯‚ب‚¢پB‚½‚ئ‚¦‚خچص‚è‚âگي‘ˆ‚ة‚ب‚é‚ئپA‚»‚ê‚ھ‰ً•ْ‚³‚ê‚é‚ئ‚¢‚¤‚ي‚¯‚إ‚·پBژہچغپAƒtƒچƒCƒg‚ح‘وˆêژں‘هگي‚ج’†‚إگي‘ˆ‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚ح‚ق‚µ‚ëچm’è“I‚إ‚µ‚½پB‚»‚µ‚ؤ‚ـ‚½گي‘ˆ‚ھڈI‚ي‚ê‚خژ©‘R‚ةŒ³‚ة–ك‚é‚ئچl‚¦‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB”ق‚جچl‚¦‚ھ•د‚ي‚ء‚½‚ج‚حگيŒم‚إ‚·پB‚µ‚©‚µپA‚»‚ê‚ح”قژ©گg‚ھگي‘ˆ‚ًŒoŒ±‚µ‚½‚±‚ئ‚ة‚و‚é‚ج‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB
پm26:09پn ”ق‚جچl‚¦‚ً•د‚¦‚½‚ج‚حپAگيŒم‚ةگي‘ˆگ_Œoڈا‚ة‹ê‚µ‚قٹ³ژز‚ةڈo‰ï‚ء‚½‚±‚ئ‚إ‚·پB”ق‚ç‚ة‚ئ‚ء‚ؤپAگي‘ˆ‚ح‚µ‚¾‚¢‚ةڈء‚¦‹ژ‚é‚ا‚±‚ë‚إ‚ح‚ب‚©‚ء‚½‚ي‚¯‚إ‚·‚ثپB–ˆ”سگي‘ˆ‚ج–²‚ًŒ©‚ؤ”ٍ‚ر‹N‚«‚ؤ‚¢‚½‚ج‚¾‚©‚çپB‚±‚ج‚و‚¤‚ب”½•œ‹”—‚ح‰½‚ب‚ج‚©پA‰½‚ة‚و‚é‚ج‚©پBƒtƒچƒCƒg‚ح‚»‚ê‚ًچl‚¦‚½پB‚»‚µ‚ؤ”ق‚حپA‰ُٹ´Œ´‘¥‚ئŒ»ژہŒ´‘¥‚ئ‚¢‚¤‚و‚¤‚ب“ٌŒ³گ«‚ج’ê‚ةژ€‚ج—~“®پA‚ ‚é‚¢‚ح‚»‚ج”hگ¶•¨‚إ‚ ‚éچUŒ‚—~“®‚ًŒ©ڈo‚µ‚½پBƒtƒچƒCƒg‚ح‚±‚¤چl‚¦‚ـ‚µ‚½پBٹ³ژز‚ç‚ج”½•œ‹”—‚حپAگي‘ˆٹْ‚ةٹO‚ةŒü‚¯‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚½چUŒ‚—~“®‚ھگيŒم‚ة“à‚ةŒü‚¯‚ç‚ê‚邱‚ئ‚ة‚و‚ء‚ؤگ¶‚¶‚½‚ج‚¾‚ئپBƒtƒچƒCƒg‚ھ’´ژ©‰ن‚ئ‚¢‚¤ٹT”O‚ً’ٌ‹N‚µ‚½‚ج‚ح‚»‚جŒم‚إ‚·پB‚»‚ê‚ةژ—‚½‚à‚ج‚حˆب‘O‚©‚ç‚ ‚è‚ـ‚·پB‚»‚ê‚حŒ»ژہŒ´‘¥‚ً’S‚¤–³ˆسژ¯‚جŒں‰{ٹ¯‚ب‚é‚à‚ج‚إ‚·پB‚ھپA‚»‚ê‚حژذ‰ï“I‹K”ح‚ھگe‚ً’ت‚µ‚ؤژq‚ا‚à‚ة“à–ت‰»‚³‚ê‚ؤگ¶‚¶‚½‚à‚ج‚إ‚·پB‚آ‚ـ‚è‚»‚ê‚حٹO‚©‚ç—ˆ‚é‚à‚ج‚إ‚·پB‚»‚ê‚ة‘خ‚µ‚ؤ’´ژ©‰ن‚ح‚¢‚ي‚خ“à•”‚©‚ç—ˆ‚éپB‚ب‚؛‚ب‚ç‚خ“–گl‚جژ€‚ج—~“®پAچUŒ‚—~“®‚ةچھ‚´‚µ‚ؤ‚¢‚é‚©‚ç‚إ‚·پBƒtƒچƒCƒg‚ج‚±‚ج‚و‚¤‚بچl‚¦‚ج“WٹJ‚حپA‹·‹`‚جگ¸گ_•ھگح‚و‚è‚à‚ق‚µ‚ë”ق‚ج•¶‰»ک_‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚و‚è–¾‰ُ‚ةژ¦‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ئژv‚¢‚ـ‚·پBŒمٹْƒtƒچƒCƒg‚جچl‚¦‚ً“TŒ^“I‚ةژ¦‚·‚ج‚حپA1930”N‚ةڈ‘‚¢‚½پw•¶‰»‚ج’†‚ج‹ڈگS’nˆ«‚³پx‚ئ‚¢‚¤ک_•¶‚إ‚·پB‚±‚±‚إƒtƒچƒCƒg‚حپA’´ژ©‰ن‚حŒآگl‚¾‚¯‚إ‚ح‚ب‚ڈW’c‚ة‚à‚ ‚é‚ئ‚¢‚¢‚ـ‚·پB‚ئ‚¢‚¤‚و‚è‚à‚ق‚µ‚ëپA’´ژ©‰ن‚حڈW’c‚ج•û‚ة‚و‚茰’ک‚ة‚ ‚ç‚ي‚ê‚é‚ئڈ‘‚¢‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚»‚µ‚ؤ‚±‚ج’´ژ©‰ن‚جڈW’c“IŒ»‚ê‚جˆêŒ`‘ش‚ھ•¶‰»‚¾‚ئ‚¢‚¤‚ي‚¯‚إ‚·پB‚»‚جˆس–،‚إپAژ„‚حگيŒم‚ج“ْ–{‚ةگ¶‚ـ‚ꂽŒ›–@9ڈً‚ً’´ژ©‰ن‚ئ‚µ‚ؤ‚ف‚é‚ج‚ھ‚س‚³‚ي‚µ‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB‚¢‚¢ٹ·‚¦‚ê‚خپAˆسژ¯‚إ‚ح‚ب‚–³ˆسژ¯‚ج–â‘è‚ئ‚µ‚ؤپB‚½‚ئ‚¦‚خƒtƒچƒCƒg‚حپA‹”—گ_Œoڈا‚جٹ³ژز‚حٹO‚©‚ç‚ف‚é‚ئچكگسٹ´‚ة‹ê‚µ‚ٌ‚إ‚¢‚é‚و‚¤‚ة‚ف‚¦‚邯‚ê‚ا‚àپA“–‚ج–{گl‚ح‚»‚ê‚ة‚آ‚¢‚ؤ‰½‚àˆسژ¯‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¢پA‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ًژw“E‚µ‚ـ‚µ‚½پB‚»‚ê‚إƒtƒچƒCƒg‚ح‚»‚ê‚ًپu–³ˆسژ¯“Iچكˆ«ٹ´پv‚ئŒؤ‚ر‚ـ‚µ‚½پB
پm29:19پn “ْ–{گl‚ھŒ›–@9ڈً‚ةچS‚é‚ج‚ح‚»‚ê‚ئژ—‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚»‚ê‚حˆêژي‚ج‹”—گ_Œoڈا‚إ‚ ‚èپAپu–³ˆسژ¯“Iچكˆ«ٹ´پv‚ًژ¦‚·‚à‚ج‚إ‚·پB‚‚è•ش‚·‚ئپA“ْ–{گl‚ةگي‘ˆ‚ة‘خ‚·‚éچكˆ«ٹ´‚ھ‚ ‚é‚ئ‚µ‚ؤ‚àپA‚»‚ê‚حˆسژ¯“I‚ب‚à‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚·پBŒ›–@9ڈً‚حگlپX‚ھچكˆ«ٹ´‚ً•ّ‚¢‚½‚©‚çچى‚ç‚ꂽ‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚µپA‰ك‹ژ‚جچs“®‚ض‚ج”½ڈبˆسژ¯‚ً‹‚ك‚邱‚ئ‚ة‚و‚ء‚ؤˆغژ‚³‚ê‚ؤ‚«‚½‚à‚ج‚إ‚à‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB‚à‚µ‚»‚ê‚ھˆسژ¯“I‚ب”½ڈب‚ة‚و‚é‚à‚ج‚إ‚ ‚ء‚½‚ب‚çپA9ڈً‚ح‚ئ‚¤‚جگج‚ة”pٹü‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½‚إ‚µ‚ه‚¤پB‚ب‚؛‚ب‚çˆسژ¯‚ً•د‚¦‚é‚ج‚ح‚½‚â‚·‚¢‚±‚ئ‚¾‚©‚ç‚إ‚·پB‹³ˆçپAگé“`‚»‚ج‘¼‚إگ¢ک_‚ً•د‚¦‚邱‚ئ‚ح‚إ‚«‚ـ‚·پB‚»‚ê‚ب‚ج‚ة9ڈً‚ھ•د‚¦‚ç‚ê‚ب‚¢‚ج‚ح‚ب‚؛‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB‚»‚±‚إ‰üŒ›”h‚حپA‹³ˆçپAگé“`‚ھ•s‘«‚µ‚ؤ‚¢‚é‚©‚炾‚ئژv‚ء‚½‚èپAŒىŒ›”h‚ج‹³ˆçپAگé“`‚ھ‹‚¢‚©‚炾‚ئچl‚¦‚éپB‹t‚ةŒىŒ›”h‚حپA‰üŒ›”h‚جگé“`چHچى‚ة‚¢‚آ‚à‹¯‚¦‚ؤ‚¢‚éپB‚»‚¤‚¢‚¤ŒُŒi‚ھ‚¸‚ء‚ئ‘±‚¢‚ؤ‚«‚½‚ي‚¯‚إ‚·پBŒ›–@9ڈً‚ة‚حگي‘ˆ‚ًٹُ”ً‚·‚é‹‚¢—د—“I‚بˆسژu‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB‚µ‚©‚µپA‚»‚ê‚حˆسژ¯“I‚ ‚é‚¢‚حژ©”“I‚ةڈo‚ؤ‚«‚½‚à‚ج‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB9ڈً‚ح–¾‚ç‚©‚ةگè—جŒR‚ج‹گ§‚ة‚و‚é‚à‚ج‚ب‚ج‚إ‚·پB‚¾‚©‚çگ^‚ةژ©ژه“I‚بŒ›–@‚ًگV‚½‚ةچى‚낤‚ئ‚¢‚¤گl‚½‚؟‚ھگيŒم‚ة‚ح‚¸‚ء‚ئ‚¢‚½‚µپAچ،‚à‚¢‚ـ‚·پB‚µ‚©‚µپAŒ›–@9ڈً‚ھ‹گ§‚³‚ꂽ‚à‚ج‚¾‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ئپA“ْ–{گl‚ھ‚»‚ê‚ًژ©ژه“I‚ةژَ‚¯“ü‚ꂽ‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ئ‚ح–µڈ‚‚µ‚ب‚¢‚ج‚إ‚·پBژ„‚ج‚ف‚é‚ئ‚±‚ëپAƒtƒچƒCƒg‚جŒ¾—t‚ح‚»‚ج‹^–â‚ة“ڑ‚¦‚ؤ‚¢‚é‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB
پm31:20پn پuگl‚ح’تڈيپA—د—“I‚ب—v‹پ‚ھچإڈ‰‚ة‚ ‚èپA—~“®‚ج’f”O‚ھ‚»‚جŒ‹‰ت‚ئ‚µ‚ؤگ¶‚ـ‚ê‚é‚ئچl‚¦‚ھ‚؟‚إ‚ ‚éپB‚µ‚©‚µ‚»‚ê‚إ‚حپA—د—گ«‚ج—R—ˆ‚ھ•s–¾‚ب‚ـ‚ـ‚إ‚ ‚éپBژہچغ‚ة‚ح‚»‚ج”½‘خ‚ةگiچs‚·‚é‚و‚¤‚ةژv‚ي‚ê‚éپBچإڈ‰‚ج—~“®‚ج’f”O‚حپAٹO•”‚ج—ح‚ة‚و‚ء‚ؤ‹گ§‚³‚ꂽ‚à‚ج‚إ‚ ‚èپA—~“®‚ج’f”O‚ھڈ‰‚ك‚ؤ—د—گ«‚ًگ¶‚فڈo‚µپA‚±‚ê‚ھ—اگS‚ئ‚¢‚¤‚©‚½‚؟‚إ•\Œ»‚³‚êپA—~“®‚ج’f”O‚ً‚³‚ç‚ة‹پ‚ك‚é‚ج‚إ‚ ‚éپBپv
پm31:58پn ƒtƒچƒCƒg‚ج‚±‚جچl‚¦‚ح‚ׂآ‚ةŒ›–@‚ة‚آ‚¢‚ؤڈ‘‚¢‚½‚à‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚ٌ‚إ‚·‚ھ Œ›–@9ڈً‚ھگ¶‚¶‚½‰ك’ِ‚ً‚¶‚آ‚ة‚¤‚ـ‚ژ¦‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حپAŒ›–@9ڈً‚حٹO•”‚ج—حپA‚آ‚ـ‚èگè—جŒR‚جژw—ك‚ة‚و‚ء‚ؤگ¶‚ـ‚ꂽ‚ي‚¯‚إ‚·پB‚ة‚à‚©‚©‚ي‚炸پA‚»‚ê‚ح“ْ–{گl‚ج–³ˆسژ¯‚ةگ[‚’è’…‚µ‚½پB‚ب‚؛‚©پB‚ـ‚¸ٹO•”‚ج—ح‚ة‚و‚éگي‘ˆپiچUŒ‚گ«پj‚ج’f”O‚ھ‚ ‚éپB‚»‚ê‚ھ—اگS‚ًگ¶‚فڈo‚µ‚ؤپA‚»‚ê‚ھگي‘ˆ‚ج’f”O‚ً‚¢‚ء‚»‚¤‹پ‚ك‚邱‚ئ‚ة‚ب‚ء‚½‚ي‚¯‚إ‚·پB‚¾‚©‚猛–@9ڈً‚حژ©”“I‚بˆسژu‚ة‚و‚ء‚ؤ‚إ‚«‚½‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢پBٹO•”‚©‚ç‚ج‰ں‚µ‚آ‚¯‚ة‚و‚é‚à‚ج‚إ‚·‚ھپA‚¾‚©‚炱‚»‚»‚ê‚ح‚»‚جŒم‚ةگ[‚’è’…‚µ‚½‚ج‚إ‚·پB‚»‚ê‚ح‚à‚µگlپX‚جˆسژu‚ة‚و‚é‚à‚ج‚إ‚ ‚ê‚خگ¬—§‚µ‚ب‚©‚ء‚½‚µپA‚½‚ئ‚¦گ¬—§‚µ‚ؤ‚à‚ئ‚¤‚ة”pٹü‚³‚ê‚ؤ‚¢‚½‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB
پm32:56پn ‚ئ‚±‚ë‚إپAŒآگl‚ج–³ˆسژ¯‚جڈêچ‡‚حگ¸گ_•ھگحˆم‚ھ‘خکb‚ً’ت‚µ‚ؤƒAƒNƒZƒX‚إ‚«‚é‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپAڈW’c‚جڈêچ‡‚ح‚»‚¤‚ح‚¢‚«‚ـ‚¹‚ٌپB‚µ‚©‚µپA‘I‹“پAچ‘–¯“ٹ•[‚ة‚ب‚é‚ئپA‚»‚ê‚ح‚ ‚é’ِ“xڈo‚ؤ‚«‚ـ‚·پB‚à‚؟‚ë‚ٌ‚»‚ج‚و‚¤‚ب”Fژ¯‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپAŒoŒ±“I‚ة‚»‚ê‚ھ‚ي‚©‚ء‚ؤ‚¢‚éپB‚¾‚©‚ç‰üŒ›‚ً‚ث‚炤گ“}پAگژ،‰ئ‚ح‚¢‚´‚ئ‚ب‚é‚ئŒ›–@9ڈً‚ً‘ˆ“_‚©‚ç‚ذ‚ء‚±‚ك‚ـ‚·پB‚»‚µ‚ؤ‘I‹“‚جŒم‚إ‚ـ‚½‰üŒ›‚ًڈ¥‚¦‚éپB‚»‚ê‚ً‚‚è•ش‚µ‚ؤ‚«‚½‚ي‚¯‚إ‚·پB‚±‚ج‚و‚¤‚بڈW’c“I–³ˆسژ¯‚ح‘چ‘I‹“‚âچ‘–¯“ٹ•[‚ً’ت‚·ˆبٹO‚ةژ@’m‚µ‚¦‚ب‚¢‚ج‚©‚ئ‚¢‚¦‚خپA‚»‚¤‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپBژ„‚ح‚»‚ê‚ً’m‚é•û–@‚ھ‚ ‚é‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB–³چىˆ×’ٹڈoپiƒ‰ƒ“ƒ_ƒ€ƒTƒ“ƒvƒٹƒ“ƒOپj‚ة‚و‚éگ¢ک_’²چ¸‚ھ‚»‚¤‚إ‚·پB‚±‚ج‚â‚è•û‚حپAگيŒمƒAƒپƒٹƒJ‚جگè—جگچô‚جˆêٹآ‚ئ‚µ‚ؤ“±“ü‚µ‚½‚à‚ج‚ب‚ٌ‚إ‚·پB”ق‚ç‚ح“ْ–{‚ج–¯ژه‰»‚ة‚حگ¢ک_’²چ¸‚ھ•K—v‚¾‚ئچl‚¦‚½پB‚µ‚©‚à”ق‚ç‚ھ“±“ü‚µ‚½‚ج‚ھ“Œvٹw‚ج—ک_‚ة‚à‚ئ‚أ‚¢‚½ƒ‰ƒ“ƒ_ƒ€ƒTƒ“ƒvƒٹƒ“ƒO‚ة‚و‚é’²چ¸‚إ‚·پB‚»‚ê‚حƒAƒپƒٹƒJ‚إ‚à‚ـ‚¾ژہچs‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚©‚ء‚½‚à‚ج‚ب‚ٌ‚إ‚·پB‚»‚ê‚ھ“ْ–{‚إژہچs‚³‚ꂽپB1948”N’©“ْگV•·‚ھچs‚ب‚ء‚½گ¢ک_’²چ¸‚ھچإڈ‰‚ج‚à‚ج‚¾‚ئ‚¢‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚ ‚éˆس–،‚إ‚±‚ج‚و‚¤‚بگ¢ک_’²چ¸‚حپAŒ›–@9ڈً‚ئ—قژ—‚·‚é“_‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB‚»‚ê‚ح‚ا‚؟‚ç‚àگè—جŒR‚ھƒAƒپƒٹƒJ‚إ‚à‚â‚ء‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚±‚ئ‚ً“ْ–{‚إ‚â‚낤‚ئ‚µ‚½‚©‚çپB‚³‚ç‚ة‚à‚¤ˆê‚آ‚ج—قژ—“_‚حپAگè—جŒR‚ھ“ْ–{‚ج“ژ،‚ج‚½‚ك‚ةژ‚؟چ‚ٌ‚¾‚»‚ê‚ç‚ج‚à‚ج‚ھپAگè—جŒR‚ة‚ئ‚ء‚ؤ— –ع‚ةڈo‚½‚±‚ئ‚إ‚·پB‚½‚ئ‚¦‚خپA’©‘Nگي‘ˆ‚ھژn‚ـ‚ء‚½‚ئ‚«‚ةƒ}ƒbƒJپ[ƒTپ[‚حŒ›–@9ڈً‚ًچى‚ء‚½‚±‚ئ‚ًŒم‰÷‚µ‚½‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB”ق‚ح‚»‚±‚إ‹g“c–خ‚ةچؤŒR”ُپA‚µ‚½‚ھ‚ء‚ؤŒ›–@‚ج‰üگ³‚ً—vگ؟‚µ‚½‚ي‚¯‚إ‚·پB‹g“c‚ح‚»‚ê‚ً‚·‚°‚ب‚’f‚ء‚½پB‚»‚ê‚ة‚آ‚¢‚ؤ‹g“c‚ح‰ٌ‘zک^‚إ‚±‚¤ڈ‘‚¢‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚ـ‚¸پA“ْ–{‚حچؤŒR”ُ‚ج‚½‚ك‚جژ‘‹à‚ًژ‚½‚ب‚¢پB‚»‚ê‚ھ‘وˆê‚ج——R‚إ‚ ‚éپB‘و“ٌ‚ةپAچ‘–¯ژv‘z‚جژہڈî‚©‚猾‚ء‚ؤپAچؤŒR”ُ‚ج”wŒi‚½‚é‚ׂ«گS—“Iٹî”ص‚ھ‘S‚ژ¸‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚éپB‘وژO‚ةپA——R‚ب‚«گي‘ˆ‚ة‹ى‚è—§‚ؤ‚ç‚ꂽچ‘–¯‚ة‚ئ‚ء‚ؤپA”sگي‚جڈگص‚ھٹô‚آ‚àژc‚ء‚ؤ‚¨‚ء‚ؤپA‚»‚جڈˆ—‚ج–¢‚¾ڈI‚ç‚´‚é‚à‚ج‚ھ‘½‚¢‚ئپB‚±‚ج‚¢‚¢•û‚ً‚ف‚ـ‚·‚ئ‹g“c‚ھ–‚ةپuگS—“Iٹî”صپv‚¾‚ئ‚©پu”sگي‚جڈگصپv‚¾‚ئ‚©‚¢‚¤‚ج‚ح‚ب‚؛‚©پB‚¨‚»‚ç‚”ق‚حگ¢ک_’²چ¸‚جŒ‹‰ت‚ً’m‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB”ق‚ح‚±‚¤چl‚¦‚½پB‚à‚µ‚±‚±‚إچؤŒR”ُ‚ً‚µ‚½‚炽‚¢‚ض‚ٌ‚ب”½‘خ‰^“®‚ھ‹N‚±‚èپA“àٹt‚ھ‰َ‚ê‚é‚ا‚±‚ë‚©ٹv–½‘›‚¬‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤پB‚¨‚»‚ç‚”ق‚ح‚»‚ê‚ًƒ}ƒbƒJپ[ƒTپ[‚ة‚¢‚ء‚½‚ة‚؟‚ھ‚¢‚ب‚¢پB‚½‚¾پA‹g“c–خ‚حƒ}ƒbƒJپ[ƒTپ[‚ج—v‹پ‚ةڈ]‚ء‚ؤŒxژ@—\”ُ‘à‚ًچى‚è‚ـ‚µ‚½پB•ؤŒR‚ھ’©‘N”¼“‡‚ةŒü‚©‚ء‚½Œم‚جˆہ‘S•غڈل‚ج‚½‚ك‚ئ‚¢‚¤–¼–ع‚إ‚·پB‚ئ‚ح‚¢‚¦پA‹g“c‚ح‚ ‚‚ـ‚إŒ›–@‰üگ³‚ح‘ق‚¯‚½پBŒxژ@—\”ُ‘à‚ھ•غˆہ‘àپAژ©‰q‘à‚ئ”“W‚µ‚ؤ‚¢‚ء‚½’iٹK‚إ‚àپA‚»‚ê‚ç‚حپuگي—حپv‚إ‚ح‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¢’£‚ء‚ؤپAŒ›–@9ڈً‚ج‰üگ³‚ج•K—v‚ً”غ’肵‚½‚ٌ‚إ‚·پB‚±‚ê‚ح‚ ‚éˆس–،‚إ9ڈً‚ج‰ًژك‰üŒ›‚ج‚و‚¤‚ب‚à‚ج‚إ‚·پBˆب—ˆپA9ڈً‚ج•¶–ت‚ً•د‚¦‚ب‚¢‚ـ‚ـ‚ةپA‚»‚ê‚ة‘ٹ”½‚·‚é‚و‚¤‚بŒR”ُٹg‘ه‚ھ‚ب‚³‚ꑱ‚¯‚ؤ‚«‚½‚ي‚¯‚إ‚·پB
پm37:17پn ‚±‚±‚إگ¢ک_‚ئ‘I‹“‚جٹضŒW‚ة‚آ‚¢‚ؤˆêŒ¾ڈq‚ׂؤ‚¨‚«‚ـ‚·پBŒ‹ک_‚©‚ç‚¢‚¤‚ئپA‘I‹“‚حڈW’c“I–³ˆسژ¯‚ئ‚µ‚ؤ‚جگ¢ک_‚ً•\‚·‚à‚ج‚ة‚ح‚ب‚肦‚ـ‚¹‚ٌپB‚ب‚؛‚ب‚ç‚خ‘ˆ“_‚ھB–†‚ب‚¤‚¦پA“ٹ•[—¦‚àٹT‚µ‚ؤ’ل‚پA“ٹ•[ژز‚ج’nˆو‚â”N—î‚ب‚ا‚جٹ„چ‡‚ة‚à•خ‚è‚ھ‚ ‚é‚©‚ç‚إ‚·پB‚½‚¾‘I‹“‚ً’ت‚µ‚ؤŒ›–@9ڈً‚ً‰üگ³‚µ‚و‚¤‚ئ‚·‚éڈêچ‡پAچإŒم‚ةچ‘–¯“ٹ•[‚ًچs‚¤•K—v‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پBچ‘–¯“ٹ•[‚à‰½‚ç‚©‚ج‘€چى‚âچô“®‚ح‰آ”\‚¾‚©‚çپAگ¢ک_‚ًڈ\•ھ‚ة”½‰f‚·‚é‚à‚ج‚ئ‚ح‚¢‚¦‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپA‘ˆ“_‚ھ‚ح‚ء‚«‚肵‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إپA“ٹ•[—¦‚àچ‚‚پA–³ˆسژ¯‚ھ‘O–ت‚ةڈo‚ؤ‚«‚ـ‚·پB‚ن‚¦‚ةچ‘–¯“ٹ•[‚إ‚ح•‰‚¯‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚·پB‘I‹“‚إڈں‚ء‚ؤ‚àچ‘–¯“ٹ•[‚إ”s–k‚·‚ê‚خپAگŒ ‚ح’v–½“I‚بƒ_ƒپپ[ƒW‚ًژَ‚¯‚ـ‚·پB‰ًژك‰üŒ›‚·‚çˆغژ‚إ‚«‚ب‚‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‰آ”\گ«‚ھ‚ ‚éپB‚ق‚ë‚ٌ‘I‹“‚إ‚à9ڈً‰ü’è‚ً—Bˆê‚ج‘ˆ“_‚ئ‚µ‚½‚ب‚ç‘ه”s‚·‚é‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB‚¾‚©‚çگ•{ژ©–¯“}‚ح•پ’i‚ح9ڈً‚ج‰ü’è‚ًڈ¥‚¦‚ؤ‚¢‚é‚ة‚à‚©‚©‚ي‚炸پA‘I‹“‚ئ‚ب‚é‚ئ‚¯‚ء‚µ‚ؤŒ›–@9ڈً‚ً‘ˆ“_‚ة‚ح‚µ‚ب‚¢‚ٌ‚إ‚·پBچ،Œم‚à“¯‚¶‚إ‚·پB
پm38:47پn ‚ب‚¨پAگ¢ک_‚ً’m‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚حپAƒ‰ƒ“ƒ_ƒ€ƒTƒ“ƒvƒٹƒ“ƒO‚ة‚و‚éگ¢ک_’²چ¸‚ج•û‚ھ‚à‚ء‚ئ“Iٹm‚¾‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB‚µ‚©‚µپA‚»‚جڈêچ‡‚حژ؟–â‚ج‚µ•û‚ة’چˆس‚µ‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¯‚ب‚¢‚ٌ‚إ‚·پB‚½‚ئ‚¦‚خپuŒ›–@9ڈً‚ً‚ا‚¤ژv‚¤‚©پv‚ئ‚¢‚¤‚و‚¤‚بژ؟–â‚ح‚¾‚ك‚ب‚ٌ‚إ‚·‚وپA”™‘R‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚é‚©‚çپBپuŒ›–@9ڈً‚ً”pٹü‚·‚é‚©‚ا‚¤‚©پv‚ئٹm’肵‚ؤ–â‚ي‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¯‚ب‚¢پB‚ئ‚ة‚©‚ژ؟–â‚ً“Kگط‚ة‚·‚邱‚ئ‚ھٹجگS‚إ‚·پB‚ب‚ة‚µ‚ë–₤‚ؤ‚¢‚é‘ٹژè‚حŒآپXگl‚جˆسژ¯‚²‚ئ‚«‚إ‚ح‚ب‚‚ؤپA–³ˆسژ¯‚³‚ـ‚ب‚ٌ‚إ‚·‚©‚çپB‚آ‚¢‚إ‚ة‚¢‚¤‚ئپAŒ»چف‚â‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚ب“dکb‚ة‚و‚é‚â‚è•û‚حƒ‰ƒ“ƒ_ƒ€ƒTƒ“ƒvƒٹƒ“ƒO‚ة‚ب‚ç‚ب‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB“dکb‚ًژ‚ء‚ؤ‚¢‚ب‚¢گl‚حڈœٹO‚³‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚·پB‚ئ‚‚ةچإ‹ك‚جژلژز‚حŒg‘ر‚µ‚©ژ‚ء‚ؤ‚ب‚¢‚©‚ç‚إ‚«‚ب‚¢‚ٌ‚إ‚·پB‚±‚ê‚إ‚حƒ‰ƒ“ƒ_ƒ€‚ب’ٹڈo‚ة‚ح‚ب‚è‚ـ‚¹‚ٌپB‚¾‚©‚ç–تگع‚µ‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¯‚ب‚¢‚ٌ‚إ‚·‚ھپA‹à‚ھ‚©‚©‚é‚ج‚إ‚â‚ç‚ب‚¢پB—v‚·‚é‚ةژ„‚ھ‚¢‚¢‚½‚¢‚ج‚حپAŒ›–@9ڈً‚ھ–³ˆسژ¯‚ج’´ژ©‰ن‚إ‚ ‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚حپAگS—“I‚ب‰¯‘ھ‚إ‚ح‚ب‚‚ؤپA“Œvٹw“I‚ة— ‚أ‚¯‚ç‚ê‚é‚à‚ج‚¾‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚·پB
پm40:20پn چإŒم‚ةˆêŒ¾پBŒ»چفگ¢ٹE’†‚إگي‘ˆ‚جٹë‹@‚ھ”—‚ء‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ح‚ـ‚؟‚ھ‚¢‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB‚ا‚جچ‘‚à‚±‚جٹë‹@‚ج‚à‚ئ‚ة‚ ‚èپA‚»‚ꂼ‚ê‚ة‘خچô‚ًچu‚¶‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚»‚µ‚ؤ‚»‚ê‚ھ‘¼چ‘‚ة‰e‹؟‚µپA‘ٹŒف“I‚ة“G‘خگS‚ھ‘•‚³‚ê‚éپB‚»‚ج’†‚إ“ْ–{‚إ—Dگ¨‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚«‚½‚ج‚حپA•ؤچ‘‚ئ‚جŒRژ–“¯–؟پiڈW’c“Iژ©‰qŒ پj‚ًٹm—§‚·‚é‚ئ‚¢‚¤ˆؤ‚إ‚·پB‚»‚ê‚حگي‘ˆ‚ھگط”—‚µ‚½Œ»ڈَ‚ج‚à‚ئ‚إ‚حƒٹƒAƒٹƒXƒeƒBƒbƒN‚ب‘خ‰‚إ‚ ‚é‚و‚¤‚ة‚ف‚¦‚ـ‚·پB‚µ‚©‚µپA‹t‚ةٹeچ‘‚جƒٹƒAƒٹƒXƒeƒBƒbƒN‚ب‘خ‰‚ج‚¹‚¢‚إپAژv‚¢‚ھ‚¯‚ب‚¢‚©‚½‚؟‚إگ¢ٹEگي‘ˆ‚ةٹھ‚«چ‚ـ‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚¤ٹW‘Rگ«‚ھچ‚‚¢
‚ج‚إ‚·پB‘وˆêژں‘هگي‚ح‚ـ‚³‚ة‚»‚¤‚¢‚¤‚à‚ج‚إ‚µ‚½پBƒˆپ[ƒچƒbƒp‚ج’nˆو“I‚ب•´‘ˆپAƒIپ[ƒXƒgƒٹƒA‚ئƒZƒ‹ƒrƒA‚ج•´‘ˆ‚ھپAŒRژ–“¯–؟‚جچ‘چغ“Iƒlƒbƒgƒڈپ[ƒN‚ة‚و‚ء‚ؤ“ْ–{‚àژQ‰ء‚·‚é‚و‚¤‚بگ¢ٹEگي‘ˆ‚ة“WٹJ‚µ‚ؤ‚¢‚ء‚½‚ي‚¯‚إ‚·پB“ْ–{‚جڈêچ‡‚ح“ْ‰p“¯–؟‚ھ‚ ‚ء‚½‚©‚ç‚إ‚·پB‚ـ‚½‚»‚ج‘وˆêژں‘هگي‚جŒ‹‰ت‚ئ‚µ‚ؤچ‘چغکA–؟‚ھگ¶‚ـ‚êپAگي‘ˆ‚ًˆل–@‚ئ‚·‚éپu•sگيڈً–ٌپv‚ھگ¬—§‚µ‚ـ‚µ‚½پB“ْ–{‚جŒ›–@9ڈً‚ھ‚»‚جپu•sگيڈً–ٌپv‚ة•‰‚¤‚±‚ئ‚حگو‚ة‚àŒ¾‚¢‚ـ‚µ‚½‚¯‚اپAچ‘چغکA–؟‚©‚ç’E‘ق‚µپA‚©‚آپu•sگيڈً–ٌپv‚ً“¥‚ف‚ة‚¶‚ء‚½‚ج‚حژہ‚حƒhƒCƒc‚ئ“ْ–{‚ب‚ج‚إ‚·پB‚ا‚؟‚ç‚à‚»‚ج‚و‚¤‚بƒJƒ“ƒg“I—”O‚ًڑ}ڈخ‚µ‚ؤپAژ©چ‘‚جˆہ‘S‚ًƒٹƒAƒٹƒXƒeƒBƒbƒN‚ةٹm•غ‚µ‚و‚¤‚ئ‚µ‚½‚ي‚¯‚إ‚·پB‚»‚جŒ‹‰ت‚ھ‘و“ٌژں‘هگي‚إ‚·پB‚µ‚½‚ھ‚ء‚ؤپA–h‰q‚ج‚½‚ك‚جڈW’c“IŒRژ–“¯–؟‚ح‰½‚畽کa‚ً•غڈل‚·‚é‚à‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢پB
پm42:27پn ‚µ‚©‚µپAچ،‚à‚»‚ê‚ھƒٹƒAƒٹƒXƒeƒBƒbƒN‚ب‚â‚è•û‚¾‚ئچl‚¦‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚»‚µ‚ؤ“ْ–{گl‚ھ‚»‚ê‚ًژہŒ»‚·‚邽‚ك‚ة‚ح‰½‚ئ‚µ‚ؤ‚à”ٌŒ»ژہ“I‚بŒ›–@9ڈً‚ً”pٹü‚µ‚ب‚¯‚ê‚خ‚ب‚ç‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB‚µ‚©‚µپA”ق‚ç‚ح‚»‚¤–]‚ٌ‚إ‚à‚إ‚«‚ـ‚¹‚ٌپB60”Nˆبڈم‚ة‚ي‚½‚ء‚ؤŒ›–@9ڈً‚ً”pٹü‚µ‚و‚¤‚ئ‚µ‚ؤ‚«‚½‚ج‚ةپA‚»‚ê‚ًژہŒ»‚إ‚«‚ب‚©‚ء‚½‚ج‚إ‚·پBچ،•غژç”h‚ج’†گ••”‚حپA‚ب‚؛‰üŒ›‚إ‚«‚ب‚¢‚ج‚©‚ي‚©‚ç‚ب‚¢‚ب‚ھ‚çپA‚½‚ش‚ٌ‰üŒ›‚ً‚ ‚«‚ç‚ك‚ؤ‚¢‚é‚ج‚¾‚ئژv‚¢‚ـ‚·پB‚à‚؟‚ë‚ٌ‚¢‚آ‚à‰üŒ›‚ًŒû‚ة‚µ‚ـ‚·پB‚µ‚©‚µپA‚»‚ê‚ًژہŒ»‚إ‚«‚é‚ئ‚حچl‚¦‚ؤ‚¢‚ب‚¢پB‚»‚ج‚©‚ي‚è‚ة‹c‰ï‚إ‘½گ””h‚ئ‚ب‚ء‚ؤˆہ•غ–@ˆؤ‚ج‚و‚¤‚ب–@—¥‚ًچى‚邱‚ئ‚âپA‚ـ‚½چ،Œم‚ةŒ›–@‚ة‹ظ‹}ژ–‘شڈًچ€‚ً‰ء‚¦‚é‚ب‚ا‚إپA9ڈً‚ً–³—ح‰»‚·‚é•û–@‚ً‚ئ‚낤‚ئ‰وچô‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚±‚ê‚حچ‘‰ï‚إ‚ح’ت‚ء‚ؤ‚àچ‘–¯“ٹ•[‚إ‚حٹmژہ‚ة‹p‰؛‚³‚ê‚ـ‚·‚©‚çپA‚â‚ç‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤پB—v‚·‚é‚ةˆہ”{گŒ ‚حپA9ڈً‚ھ‚ ‚ء‚ؤ‚àگي‘ˆ‚ھ‚إ‚«‚é‚و‚¤‚ب‘جگ§‚ًچى‚낤‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ي‚¯‚إ‚·پB
پm43:40پn ‚ن‚¦‚ةŒىŒ›”h‚ح9ڈً‚ھ‚ب‚‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ً‹°‚ê‚é•K—v‚ح‚ـ‚ء‚½‚‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB–â‘è‚ح‚ق‚µ‚ëŒىŒ›”h‚ج‚ ‚¢‚¾‚ة‰üŒ›‚ً‹°‚ê‚é‚ ‚ـ‚è9ڈً‚جڈً•¶‚³‚¦•غژ‚إ‚«‚ê‚خ‚و‚¢‚ئچl‚¦‚é‚س‚µ‚ھ‚ ‚邱‚ئ‚إ‚·پB‚©‚½‚؟‚جڈم‚إ‚ج‚ف9ڈً‚ًژç‚邾‚¯‚ب‚çپA9ڈً‚ھ‚ ‚ء‚ؤ‚à‰½‚إ‚à‚إ‚«‚é‚و‚¤‚ب‘جگ§‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚·پB‚»‚ê‚ھچ،Œم‚ة‹N‚±‚肤‚邱‚ئ‚إ‚·پB‚»‚جˆس–،‚إژ„‚حŒ›–@9ڈً‚ج‰ü’è‚ً‹°‚ê‚ؤ‚ح‚¢‚¯‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¢‚½‚¢پB”ق‚ç‚ة‚حگ³پX“°پX‚ئŒ›–@9ڈً‚ً•د‚¦‚½‚ç‚ا‚¤‚©‚ئ‚¢‚¦‚خ‚¢‚¢‚ٌ‚إ‚·پB‚؛‚ذچ‘–¯“ٹ•[‚ً‚â‚è‚ـ‚µ‚ه‚¤پB‚ׂآ‚ة3•ھ‚ج2‚ج‹cگب‚ًژو‚ç‚ب‚‚ؤ‚àپAˆêڈڈ‚ة‚â‚è‚ـ‚µ‚ه‚¤‚ئ‚¢‚ء‚ؤپA‘Sˆُژ^گ¬‚ة‰ٌ‚ء‚ؤ‚à‚¢‚¢‚ٌ‚إ‚·‚وپAچ‘–¯“ٹ•[‚ة‚µ‚و‚¤‚ئپB‚±‚ê‚حڈç’kپB
پm44:44پn ‚¾‚©‚ç’چˆس‚·‚ׂ«‚±‚ئ‚حپA”ق‚ç‚ھŒ›–@9ڈً‚ً•د‚¦‚邱‚ئ‚ب‚‚³‚ـ‚´‚ـ‚بژèŒû‚إگي‘ˆ‚ًچs‚¦‚é‘جگ§‚ًچى‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚±‚ئ‚إ‚·پBچ،Œم‚ة“ْ–{‚ھگي‘ˆ‚ةٹھ‚«چ‚ـ‚ê‚邱‚ئ‚ح‘ه‚¢‚ة‚ ‚肦‚ـ‚·پB‚ ‚é‚¢‚ح‚»‚ج‚و‚¤‚بٹë‹@‚ً‚ ‚¦‚ؤچى‚èڈo‚µ‚ؤŒ›–@‰üگ³‚ً‚ح‚©‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚à‚ ‚肦‚é‚إ‚µ‚ه‚¤پB‚µ‚©‚µپA‚»‚ج‚ ‚°‚‚ة‚ا‚¤‚ب‚é‚©‚ئ‚¢‚¦‚خپA‚¢‚¸‚êچ‚‚·‚¬‚é‘مڈ‚ً•¥‚ء‚ؤŒ›–@9ڈً‚ًچؤ‚رژو‚è–ك‚·‚±‚ئ‚ة‚ب‚邾‚¯‚إ‚·پB‚»‚ٌ‚ب‚±‚ئ‚حŒ»چف‚©‚ç‚ف‚ؤ‚à–¾”’‚إ‚·پB‚µ‚½‚ھ‚ء‚ؤپAگي‘ˆ‚جٹë‹@‚ھگg‹ك‚ة”—‚éژٹْ‚ة‚¨‚¢‚ؤ‚à‚ء‚ئ‚àƒٹƒAƒٹƒXƒeƒBƒbƒN‚ب‚â‚è•û‚حپAˆê”ت‚ة”ٌŒ»ژہ“I‚ئ–ع‚³‚ê‚ؤ‚¢‚錛–@9ڈً‚ًŒf‚°پA‚»‚ê‚ً•¶ژڑ’ت‚èژہچs‚·‚邱‚ئ‚إ‚·پB9ڈً‚ًژہچs‚·‚邱‚ئ‚حپA‚¨‚»‚ç‚“ْ–{گl‚ھ‚إ‚«‚é—Bˆê‚ج•پ•ص“I‚©‚آ‹—ح‚بچsˆ×‚إ‚·پB‚»‚ê‚ھچ،“ْ‚ج‰‰‘è‚ة‚ ‚é‚و‚¤‚ةپuŒ›–@9ڈً‚جچ،“ْ“Iˆس‹`پv‚إ‚·پB
پm“ٹچeژزƒRƒپƒ“ƒgپn
‚±‚ج•¶ڈح‚حپA2016”N1Œژ23“ْ‚ة“Œ‹“s–k‹و‚إچs‚ي‚ꂽژs–¯کAچ‡ژهچأ‚جƒVƒ“ƒ|ƒWƒEƒ€پu2016”N‚ً‚ا‚¤گي‚¢”²‚‚©پv‚ة‚¨‚¯‚é•؟’Jچsگl‚جٹî’²چu‰‰‚ًپA“ٹچeژز‚ھƒeƒLƒXƒg‚ة‹N‚±‚µ‚½‚à‚ج‚إ‚·پBƒVƒ“ƒ|ƒWƒEƒ€‚ًٹé‰وژہچs‚µ‚ؤ‚‚ꂽژs–¯کAچ‡‚¨‚و‚رژQ‰ءژزپAYouTube“®‰و‚ً‚ ‚°‚ؤ‚‚ꂽPlaceUniversity‚ةٹ´ژس‚µ‚ـ‚·پB
’i—ژ“ھ‚ة•t‚µ‚½گ”ژڑ‚حپA“®‰و‚جچؤگ¶ژٹش‚إ‚·پB•·‚«ژو‚è‚âƒ^ƒCƒv‚ب‚ا‚إٹشˆل‚¢‚ھ‚ ‚ء‚½‚炲—eژح‚‚¾‚³‚¢پB
‚ب‚¨پAپwگ¢ٹE 2015”N9Œژچ†پxپiٹâ”gڈ‘“Xپj‚ة‚حپu”½•œ‹”—‚ئ‚µ‚ؤ‚ج•½کaپv‚ئ‚¢‚¤‘è‚إ‚ظ‚ع“¯ژïژ|‚ج•¶ڈح‚ھŒfچع‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
http://www.asyura2.com/14/test31/msg/428.html


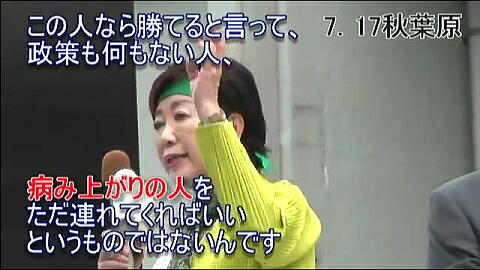
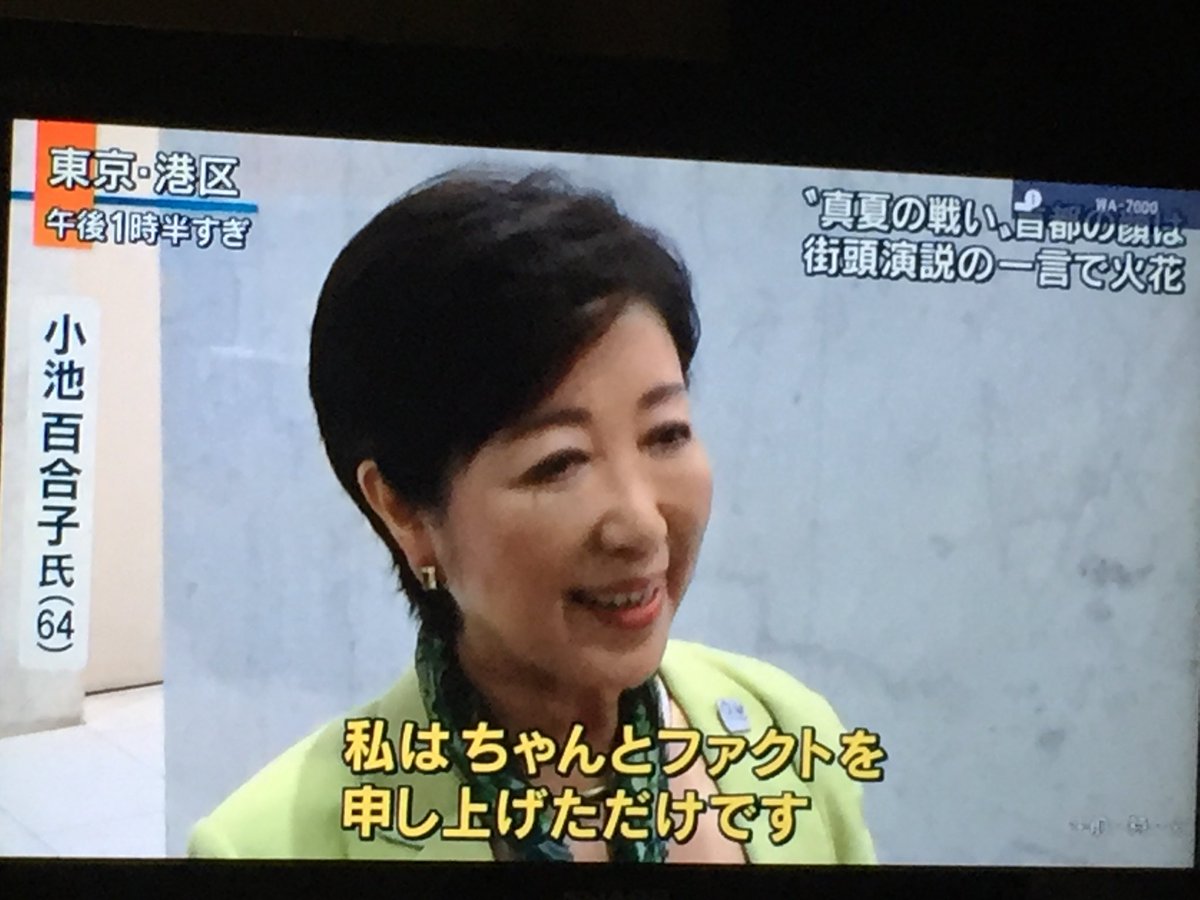
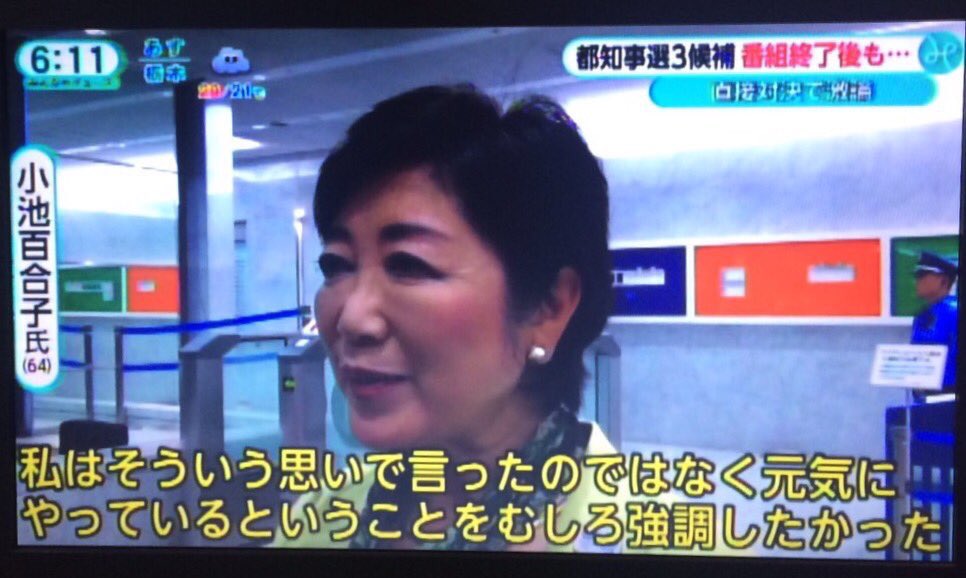
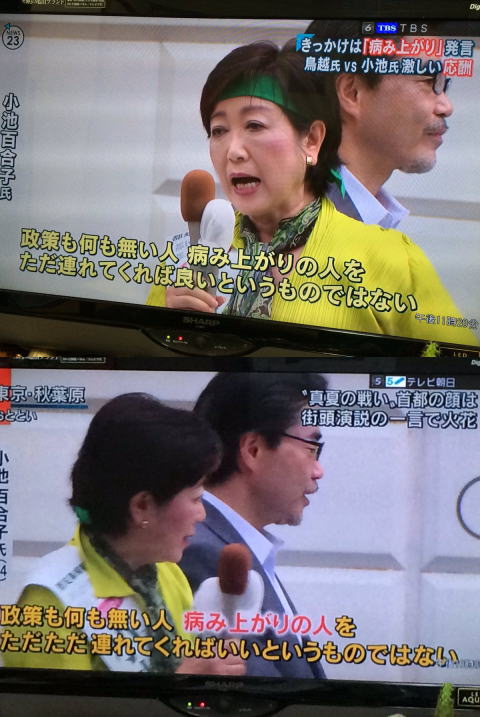
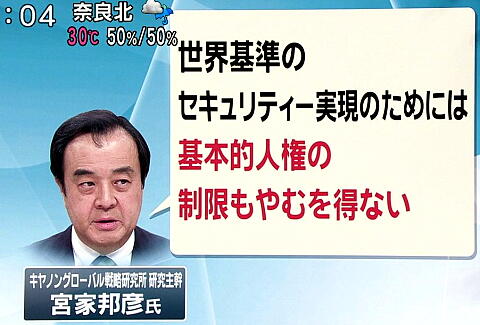


 پ@‘è–¼‚ة‚ح•K‚¸پuˆ¢ڈC—…‚³‚ٌ‚ضپv‚ئ‹Lڈq‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB
پ@‘è–¼‚ة‚ح•K‚¸پuˆ¢ڈC—…‚³‚ٌ‚ضپv‚ئ‹Lڈq‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢پB