�o�u�������Ă�������Ă͂����Ȃ����R�\�����鎞�͂����܂Łh�\���h�ł����āA����͈�C�ɋ}������A�M�p������d�|�����Ȃ��قǂ̖\���Ȃ�ł��B �����Ă݂�A�}���z�̍������l�Ȍl���M�p����ŃR���g���[���o����l�ȑ㕨�ł͂Ȃ��A�����ɓˑR�傫�Ȑ[�������J���āA�^���ɐ^���t���܂Ɍ��̒��ɗ�������l�ȁh�\���h�Ȃ�ł��B ������A�\�����ɐM�p������d�|���Ă��A������l���S�R�t���Ȃ��̂ł�����M�p�������肷�鎖�͂��蓾�܂���B����قǂ̋��낵�����̂Ȃ�ł��B �\���̕|���Ƃ���́A�����邾���ł͂Ȃ��A���̗����͋t�ɒl���늴�������������Ƃ��ꋓ�ɔ����ɎE�����Ĕ��]�\�����āA���x�͔��������Ă��l���t�����A���������o���Ȃ��E�E�E ����ȏ𑍂��āh�\���h�Ƃ����̂ł��B
���ɖ\�����ɐM�p������d�|���āh�^�ǂ��h��肵�Ă��A���̗����́A�t�Ɉ�C�ɑS���S�ʖ\�����A���o���ςʼn���~�����ݏグ����̂ł��B
����ȏł��M�p������d�|����̂́A�]���́h�E�ҁh���]���́h���Y�Ɓh���]���́h�f�l�h�Ȃ�ł��傤�B �u���b�N�}���f�[�̗l�ȁA�����o�R�X�O�O�O�~����̃o�u������̗l�ȁ@�h�\���h�͂���Έ�������̖\���Ȃ�Ă����㕨�ł͂Ȃ��A�\���Ɩ\������ւ��ŌJ��Ԃ��Ȃ��犔�����}�����čs���A�h�_�b�`���[���h�̒ė��̗l�ȁh�\���h�ł��鎖�����Ă����ĉ������B
�l�b�g�n�̌l�����Ƃ́@�t�ɍs���s���h���h���́@�����ё̎�������܂��̂ŁA��]�\�����N��������A�ߋ��̖\���ȏ�ɔ��肪������Ă�ŁA�T�[�o�[�_�E���������܂��āA�ߋ��̖\���ȏ�̐��܂����z���ȏ�̖\���ɂȂ�Ǝ��͎v���Ă܂��B
_________________
S���̑���ρ@���Ĕ�Ȃ���́@2017�N11��14���@ ����S�̂ɓ��ɕς�������Ƃ͗L��܂���ˁB ���o���ς͂���ƒ����ɓ����Ă��ꂽ�悤�ŁA��͂��̒����̏I�������ɂ߂�Ηǂ������ł��B ���̊Ԃɍޗ��������키�ł��낤���͊��ɗ\�z�ς݂ŁA�d���݂����S�ł��B
����������Łu��������̂ł́H�v�u��͂ǂ��ł����H�v�Ƃ������̂�����܂������A�������肽���nj�Q�������������Ă���̂����{�̊����s��ł��낤�Ǝv���Ƃ���ł����A���͔��鎖�͍l���Ȃ������ǂ��ł��B
������͔��邵���Ȃ����ꂪ���邩�Ǝv���܂����A���邵���Ȃ��Ƃ���܂ʼn����Ă��甄���Ă��Ԃɍ����܂��B ����́A���ꂪ���S�ɉ��Ă���ł��Ԃɍ����̂ł��B �X�P�x�������o���Ă������l���甄�肽���Ƃ��l���邩���₯�ǂ�����̂ł��B �m���ɓ��o���ς́A�������甃���ƌ����Ă��|�������m��܂��A�ʂł͔����Ă��Ȃ��������R�قǂ���܂����A�����������̂�����Δ����C���N����̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł����ǂˁE�E�E�B ���S�Ғ��A���o���ς����őS�̂�c�����悤�Ǝv���̂����m��܂��A�傫�ȊԈႢ���Ǝv���܂��B �����̓��o�V����ʂł́u�}�l�[�c���A�x��ʌo�ρv�Ƃ������ŁA�|�����Șb�����W�őg�܂�Ă���܂������A���S�Ȕ������L���ł���A�l�����Ƃ̋��U�����Ƃ��Ă���̂����������ł��B ����̎哱���͊O���������Ă���A�����܂�5���~�ȏ㔃���z�����Ă����ԂŁA�ǂ����đ��ꂪ�����ɓ]����̂��H �����ڂ͋��U������㩂ł����Ȃ��A����㩂ɖ��x������̂��l�����ƂȂ̂ł��B �̂͋�͕ۏ؋���500���~�ȏ�ς܂Ȃ��Əo���Ȃ����A����o����������x�ς�ł��Ȃ��ƌ��������Ȃ������̂ł����A����30���~��������A�N�ł����������܂�����ˁE�E�E�B ���悤�ɂ���Ă͗L�v�ȋ�ł����A�{���ɓ�����̂ł���A�����ȒP�ɗ��v���o����̂ł͂Ȃ��ƒm���ė~�����ł��B ���Ȃ݂ɁA��́A�����̋t������悢�ƍl���Ă��鎞�_��OUT�ł��B
�E�����͏㏸�Ŗ����̗��v�ɂȂ��邪�A�����ł̑����͌���I
�E����͏㏸�Ŗ����̑����ނ��A�����ł̗��v�͌���I
�u�����͉Ƃ܂Ŕ���͖��܂Łv�Ȃ�đ���i��������܂����A���ꂾ�����Ă��A�P���ɔ��̂��̂ł͂Ȃ�����������Ǝv���܂��B
�����Ƃ��ẮA���Ȃ�ǂ��炩����ɓ������ė~�����ł��B ����͎��Ĕ�Ȃ���̂ł���A�l�������Ⴄ�̂ŁA��������肭��낤�Ǝv���Ă���肭�s�����̂ł͂Ȃ��̂ł��B
�ł�����A����Ȃ甄��A�����Ȃ甃���B
����ȕ��ɂ��ď㋉�҂ƂȂ�A�㋉�҂̎�������Ă�����ɁA�ǂ����Ă����������ł͎��Ȃ��Ɗ������ʂ�A���肾���ł͎��Ȃ��Ɗ������ʂ��������ɁA���߂Ĕ��̎������Č���B ���ꂪ�������������Ǝv���܂��B ���E�̃}�l�[���c�����A�����㏸����Ƃ������̓��[�}���V���b�N�̒���ɐ��E���Ŏn�܂������Z�ɘa�番�����Ă������Ƃł��B �����A���̔������v��������ɂȂ��ďo�ė��������̎��ł���A���̕s�v�c���Ȃ����Ȃ̂ł��B ����͊��ɖ��m�̗̈�ł���A�����܂ōs�����Ȃ�ė\�z���t���܂��A���Ȃ��Ƃ�����ɉ��ׂ��ɂ͂Ȃ��ł��B �����͔����ŗ��v�����߂čs����ʁB �����l���Ē����ėǂ��Ǝv���Ƃ���ł��B �܂��A���o���ςɊւ��܂��ẮA�������x�݂��낤�Ǝv���܂��B �������Ă��x�݂��Ȃ��甄���U���A�G�l���M�[�����߂čď㏸�B ����܂ł̊Ԃ͍ޗ������������鑊��ł���A���̍ŏd�v�ۑ�͂����@���ɂ��đ����邩�B
http://ssoubakan.com/blog-entry-2668.html
2017�N11��06�� S���̑���ρ@����͉���܂ł͔����
���������{���͍������ł��B
�č������Ɏx�����A�ǂ�ǂ�l�オ�肵�Ă���܂��ˁB ���ς�炸�l�����Ƃ͔���p���ł���A���̂܂ܔ��葱����A�����͏��Ǝv���܂����A���O�Ɏ���ł��܂��̂ł͂Ȃ����Ɗ뜜���Ă���Ƃ���ł��B �ߋ��ɒm�荇���́A���������̑�������Ƃ����܂��āu���̑���ُ͈킾�I�K��������I�v�ƌ����Ĕ����Ă����̂ł����A�J�l�����Ă�����Ă��Ǐɒǂ��A1�N��ɂ͑S���Y���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B ���ǍŌ�͓��܂�ďI������̂ł����A���ꂩ�炵�炭���đ���͉����ɓ]���A���̓����Ƃ��������l�i�����啝�ɉ����܂����B ���̓����Ƃ̍l���͐����������ƌ�����̂ł����A�������ǂ߂Ȃ��������߂ɔs�ނ��Ă��܂����Ƃ�����ł��B ���̑�������Ă���ƁA���̎��̎����悭�v���o���Ă��܂��̂ł����A����Ȃ��Ƃ����Ă��Ă��鎖������u����͉���܂ł͔���ȁv�Ƃ����i��������ɍ���āA�S�ɂ��܂��Ă���̂����ł���܂��B ���x�������Ă��Ă��鎖�ł����A����͉��Ă��甄��̂����������̂ł��B �����̐M�p���������܂��āA��]�������Ȃ��Ȃ��āA�����̓����Ƃ��܂ݑ�������A�ɂ��������������s���Ȃ��Ȃ��āA�����ɔ��藁�т����ē������U����B �I���ɂ͒Ǐœ�������Ȃ��Ȃ�B ���̒i�K�܂ŗ���ƁA���肪���������̂ł��B �̏o��������艮�̓����Ƃ́A�����{���ɂǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ����ɉ������Ă��甄��ƌ����Ă��܂����B �������l�������Ĕ����ɍs�������Ƃ̋t�����̂ł����A�����܂ōs���Ɩ쐶�̊����K�v�ȋC�����܂����A�����ƈ���Ĕ���̏ꍇ�͋����I�ȕ���������܂��̂ŁA�M���Ŕ����ɍs���Ă���̂Ƃ͂܂��Ⴄ���̂ł���̂ł��B �ł�����A�ɂ킩�����Ƃ��A�グ�͔����Ŏ���āA�����͔���Ŏ�낤�ƈ��Ղɍl����̂ł����A�w�i�ɂ�����̂͑S���Ⴄ�̂ł��B ���ꂪ������Ȃ��ŁA���Ղɉ����Ŏ�낤�Ȃ�čl����̂ł�����A����͂�������ē��R�ƌ����Ă��ǂ��ł��B ���ɂ͏�肭��铊���Ƃ�����̂ł��傤����ǂ��A�����͎��s���܂��B ����Ɣ����̈Ⴂ�̐^����T��ΒT��قǁA���������s���͏o���Ȃ��Ȃ�Ǝv���̂ł����ǂˁB �ł�����A�����Ȃ甃���A����Ȃ甄��Ƃ��Ĉ꓁�ōs�����čs�������ǂ��̂ł��B �܂��A��������̑���͖{���ɖ��m�̗̈�ł���A�����N���邩������Ȃ����ꂾ�Ǝv���܂��B �����I���ƌ����A�����I���ł���A�������炾�ƌ�����������ɂ��Ȃ鑊��Ȃ̂ł��B �܂��A�l�������Ă��Ȃ��̂ŁA��������̑���ɂȂ�\���̕����������ȋC�͂���̂ł����ǂˁE�E�E�B
http://ssoubakan.com/blog-entry-2662.html
50/50�@�@2017�N10��05���@
�����͘A�x�O�̏T���ł��ˁB
�N�ɕ����Ă������͊���������ƌ����܂����A���������邾�낤�Ƃ͎v���Ă��܂��B �A�x���ɖk���N���\�ꂽ���ς��Ƃ��A�グ�����ė�������Ƃ��A���R�͗����Ď̂Ă���ɂ���܂��B �Ƃ�����ł���܂��̂ŁA������Ȃ甄���Ă����Ηǂ��B �Ƃ����̂��f�l�̍l���ł��B ����9��������Ǝv���Ă��܂����A1���͉�����Ȃ��\�����c���Ă��܂��B ���R�͊ȒP�ŁA�����̐l��������Ǝv���Ă��邩��ł��B �ǂ����������ƌ����܂��ƁA��ɏq�ׂ��u������Ȃ甄���Ă����Ηǂ��v�ł����A����͎�������������������Ȃ�A��������͂Ȃ��̂ł��B �Ƃ��낪�A�̂ɔ�ׂčŋ߂͐M�p������e�Ղɍs����悤�ɂȂ����̂ŁA�l�����Ƃ͈��ՂɁu��v���d�|���ė���̂ł��B ��Ƃ́A�������l�i�������Ƃ���Ŕ����߂����Ƃɂ���ė���̂ł�����A���R������Η��H���̔��߂�������܂��B �ł�����A�F��������Ǝv���ċ肪��ʂɓ����Ă��܂��ƁA���ۂɉ����Ă������߂��Ńu���[�L�������邽�߂ɁA�]�������̍����ƂȂ鈫�ޗ��ł��lj�����Ă��Ȃ�����A�啝�ɂ͉�����̂ł��B �u�����ł����v����낤�B�v ���̍l�����A�����Ƀu���[�L��������̂ł����A�t�ɍD�ޗ�����������A�������̐��͂����܂����肵�܂��ƁA��͑��������ď�l�Ŕ����߂��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ȃ�̂ł��B �܂��A�����܂ł̎������T���ɋN����Ƃ͎v���Ă��Ȃ��̂ł����A�\���͔r�����Ă���܂���B �ł�����A�����o�[�ɂ�������\�z���Ƃ��Ă���܂����A�ꕔ���H���������߂��Ă�����x�ł��B �܂��A�S�̂��ǂ��ł��낤�Ƃ��A�ʂŋ}����������͂���Ǝv���܂��̂ŁA�ꕔ���H���ƌ����Ă����ׂĂ̎������ɓ��Ă͂܂�b�ł͂���܂��ǂˁB ���v���o�Ă�����́A������ƎQ�l�ɂ��Ē�����Ǝv���Ƃ���ł��B �Ƃɂ����A����̐��E�Ƃ����̂́u100/0�v�ł͂Ȃ��̂ł��B �����́u50/50�v�̐킢�ŁA�����́u60/40�v�ŏゾ�ȁE�E�E�Ƃ��A�����ȁE�E�E�Ƃ��A�����������̂ł���̂ł��B �ł�����A���̏�Ԃŏゾ�A�����Ƃ��������ǂ������Ă���̂ł��B �����āA�������d�|����^�C�~���O�ł����A����͂����u90/10�v�̑卷�Ŕ����Ŏ���Ɣ��f�ł������ł��B ����225�͂��������^�C�~���O�ł̂ݐ������Ă���܂��̂ŁA���N�̕�����1�x�����ł��B ���������90���ŁA10�����9��͏��Ă邩�ȁH�ƌ������Ƃ���ł��B �����������ċ�����A�����u50/50�v�ʂ̏��s�ɂȂ�ł��傤�B ����Ȃ��͖̂������ׂ��ł͂Ȃ��A���Ă�\���������Ǝv�������ɂ����������̂ł��B ��X�͋x�߂Ȃ��@�֓����Ƃł͂Ȃ��̂ł�����A�x�߂鋭�݂����ė��v�čs���Ē�����Ǝv���Ă��܂��B ���������A�x�߂Ȃ��@�֓����Ƃł���܂����A3������9������3���Ԃ����͋����I�ɋx�܂���邱�Ƃ������ł��B ���R�͌��Z�̂��߂ł����A�����3������9������3���Ԃ͏o�������������鎖�������̂ł��B
http://ssoubakan.com/blog-entry-2642.html
�����}�����{����ő��Ł����������H�@�@10��04���@
�̐S�ȑ���̗\���ł����A�Ȃ������Ă������}�����͊������ӎ����Ă��邵�A����������グ�悤�Ƃ��܂��B
�ł�����u�����}�����{����ő��Ł����������v�Ƃ܂ł͈��Ղɍl���Ȃ����ł��B ���炭�͊����͏㏸�������ł��傤�B
���܂�����͓��܂���čs���ł��傤���A�����̌l�������l�ɂȂ�܂ł͓V���������͂��Ȃ��ł��傤�B
����������ƁA���łɂ�鉺���������肪������A�t�ɓ��ݏグ�鎖�����邩���m��܂���B �F���������Ǝv���Α���͓�����Ȃ��Ȃ�̂ƈꏏ�ŁA�F�����肾�Ǝv���A����͉����炭�Ȃ�̂ł��B �ǂ݂₷���ޗ��ł͂���܂����A�P���ɂ͍l���Ȃ����ł��B ������f�[�^�𑍍��I�ɔ��f���čs�����čs���̂��厖���Ǝv���Ƃ���ł��B
http://ssoubakan.com/blog-entry-2641.html
�ߋ��̋L�^�Ɩ����\�z�}�@�@10��03���@
�����͎j��ō��l�ŁA���{������⍂���Ȃ��Ă���܂��B ���{�̌l�����Ƃ͋�ɐ����o���Ă���̂�����A���܂芔�͓����Ȃ��Œ��������Ǝv���Ă���Ƃ���ł����A�����͖≮�������Ȃ��ł��傤�B �l���ǂ�ǂ���Ă�H��������ǂ�ǂ��Ă�낤����Ȃ����I���ꂪ�O���̍l���ł��B
�u20000�~���V��v
�`���[�g�����Ă���ƁA����������Ƃ���ȕ��ɂ��������̂����m��܂��A�`���[�g�ł���ȓ������o�����Ȃ�Α�ԈႢ�ł��鎖�ɋC�t���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł��B
�`���[�g�Ȃ�Ă��̂́A�ߋ��̋L�^�ł���A�����\�z�}�ł͂Ȃ��̂ł��B ����Ȃ��̂Ŗ����͐肦�Ȃ��B �܂��A�����Q�l�ɂ��鎖�͂���܂����ǂˁE�E�E�B ����225��20000�~�œV��Ȃ�Ĕ��f�́A��ɏo�Ă��܂���B �����͏d�������ȁE�E�E�ʂł���A����̍����܂ł͍s���܂���B ���ʁA225�͌y��20000�~��˔j���A�����㏸�𑱂�20500�~��������Ƃ���܂ŗ��܂����B
http://ssoubakan.com/blog-entry-2640.html
����ɂ�������Ə��@�@10��02���@
���{�̖����͂�������邭�͂Ȃ������ł��B �����Ȃ�܂��ƁA�������S�z�ɂȂ��ł����A�ڐ�͂܂��ǂ��ł��傤�B �Ă͗��グ�𑱂��čs���ł��傤���A���{�͗��グ�����邱�Ƃ������͖���������ł��B ���Ȃ��Ƃ����N�͖����ł��傤�B �k���N�Ɛ푈�ɂȂ�Ƃ��A�]���傫�ȃC�x���g���Ȃ�����́A10�N�ȏ㑱���Ă����������Ȃ��Ǝv���Ă���ʂł��B ���Ɉ��{�������p������u����ő��Łv���҂��Ă��܂�����A���{�o�ς͗�������Ȃ����A�C���t���ɂȂ�Ȃ��̂ł��B �ł�����A���グ�͓����ł��Ȃ��̂ł��B ���ł𓀌����A�X�ɂ͌��łȂǂ̏���N������s�o����Ȃ�A��͕ς��܂����ǂˁE�E�E�B �܂��A�����͖����ł��傤���A�l���Ȃ��Ă��ǂ��悤�ȋC�͂��܂��B �����A�Ƃɂ����Ă͗��グ�Ȃ̂ŁA�������g��ʼn~���ɂ͂Ȃ�܂��B �_�Y�i�f�Վ��R���Ƃ��A�����Y�Ƃ�ɂ߂��鐭�����Ȃ̂ŁA�~���ɂł��Ȃ�Ȃ��ƁA���{�̔_�Ƃ͉�ł��Ă��܂��\��������܂��̂ŁA�~���͔_�ƂɂƂ��ėB��̋~���ƂȂ�̂��낤�Ǝv���̂ł����A�Ƃɂ��������̏���҂͋ꂵ���Ȃ����ł��B �܂��Ƃɂ����A�����͉~���X���ł���܂��̂ŁA�����͊����Ƃ������ŗǂ��Ǝv���܂��B �܂��A���E��EV���̗���͂��͂���ʂ�z���ĊC�̈�ł���܂��B �ł�����A���̗���ɂ͋t��킸�A��������Ə���čs���ׂ����ƍl���Ă���Ƃ���ł��B
�C���̗���ɏ���đD��i�߂�A��葽���̗��v����ɂ��邱�Ƃ��o����ł��傤�B
���D���̓��{�̌l�����Ƃ́A���ς�炸������d�|���Ă���܂����A����͗���ɋt����đD��i�߂Ă����Ԃł��̂ŁA���Ɍ����������ł��B ����ł����v���o������̂ł����A���炭�͔s�ނ��čs�����ɂȂ낤���Ǝv���Ƃ���ł��B ����z���������O���������z���ɓ]���Ă���܂����A�{���ɖڂ����Ă��Ȃ��l�ȔߎS�Ȍ��ʂɂȂ肩�˂Ȃ��Ɗ뜜���Ă���Ƃ���ł��B
http://ssoubakan.com/blog-entry-2639.html
���ɕK�v�ȗv�f�@�@09��29���@
FX����ɂ�����M�p�{���̋K�����������ꂻ���ł��ˁB ����܂ł̔{����25�{�ł���܂������A�����10�{�Ƃ������ŁA�啪���ʂɂȂ肻���ł��B �܂��A����3�{�ł��̂ŁA����ɔ�ׂ�܂��܂������Ƃ������܂����A�בւ̒l�������l���܂��ƁA���͂�FX�ɖ��͂͂Ȃ����낤�ȂƎv���Ƃ���ł����A�����FX�s��͊��S�ɐ��ގY�ƂƂ������ɂȂ�ł��傤�B ���܂ł͖��d�Ȍl�̎�����ב֎s��ɉe����^�����肵�Ă���܂������A����͂����������������Ȃ��Ȃ�̂��낤�Ǝv���Ă���Ƃ���ł��B �������܂��A���N�O�܂�200�{�Ƃ��A���̐�������ł���A�悭������Ȏ���������Ă����ȂƎv���܂��ˁB ����ɖ������ꂽ�M�����u���[�������A���X�ƎU�����čs�������̂ł����A����Ȍ��i�������Ȃ��Ȃ�Ƃ������ł��傤�B ������FX�̏��Ђ����܂蔄��Ȃ��Ȃ�ł��傤���A���U�T�C�g���I���A����Ǝ҂����ނł��傤�ˁE�E�E�B �����āA���̋����ǂ��֗����̂��H �M�����u���������߂�r�b�g�R�C���ł��傤����ǂ��A�Ō�͋K���ł����߂Ő��ނ���Ǝv���܂����A����܂ł̊Ԃɖׂ��悤�Ɗ����Ȃ�A����Ȃ̂����m��܂���ˁB �܂Ƃ��ɉ^�p�������Ɩ]�l�̑����͊����s��ɗ���ƌ��Ă���܂����A���������M�����u���D�������Ƃ́A�����炭����ւ������ŁA���ꂪ�V��ƌ���╽�C�ŋ���d�|���ė��邱�Ƃł��傤�B FX�Ŕ|��������̃e�N�j�J���^�p�ŏ��Ă�Ǝv���Ă��邩���m��܂��A�����܂Ŋ��͊Â��Ȃ����A�����͔�������̂ł͂Ȃ����ȂƎv���Ƃ���ł��B ���ʂɖׂ��铊�������čs���Ηǂ��Ǝv���̂ł����A���炭�͖����ł͂Ȃ����ȂƎv���Ƃ���ł��B �����ݎc���Ă���l�����Ƃ̑�������łǂ�ǂ���c��܂��Ă���l�ł�����ˁE�E�E�B �e�N�j�J�����͂Ȃ�Ă��̂́A�ڈ��ɉ߂��Ȃ��̂ł�����A�����������̂�ӐM���Ď������l�̋C���m��܂���B �ǂ������̖ڂɌ�����`���[�g��������\�����Ă���l�Ɋ����Ă��܂��̂��낤�Ǝv���̂ł����A�`���[�g�Ƃ͂���܂ł̋L�^�ł���A���ꂩ��̎��ł͂Ȃ��̂ł��B ����͂܂��A�v���v���ɌX���̗l�Ȃ��̂��������肵�܂�����A�����鎖������܂����A�����Q�l�ɂ��邱�Ƃ͂���܂����A�����ĐM������͂��܂���B �����܂ł��A�⏕�I�c�[���ɉ߂��Ȃ��̂��A�`���[�g���͂ł���A�_�Ђ̂��݂������x�̑��݂ł�������܂���B ���ɕK�v�ȗv�f�͂���������܂����A�ł��厖�Ȃ̂͐M�O���Ǝv���܂��B �܂��ÏL�����t�������Ă����ȂƎv���邩���m��܂��A�M�O���Ȃ���Ί��ł̏����͗L��܂���B
�܂��A�����ɂ���Ă͐M�O�����厖�Ȏ����������肵�܂����A�{���ɑ傫�ȗ��v�������炷�̂́A�ԈႢ�Ȃ����̐M�O�ł��B
�㏸����Ƃ���1000�~�O��Ŏd���ݑ�����6723���l�T�X���ǂ��Ȃ������H EV�̎���ɂȂ�Ƃ��ĉ����ڔ����������߂���6674GS���A�T���ǂ��Ȃ������H �Z�F���w�̎P���ɂȂ��āA�傫���l�ς�肷��Ƃ��āA�O��I�Ȕ���������ƁA�ۗL�������߂���4080�c�����w���ǂ��Ȃ������H �C�ꎑ���͂��ꂩ��d�v�ɂȂ�Ƃ��āA�O�ꂵ�Ĕ�����������6269�O��C�m�J�����ǂ��Ȃ������H ����炪���̌����Ƃ���̐M�O�̗��v�ł���A���ꂱ����������ň�Ԗʔ����������Ǝv���̂ł��B ������������������Ȃ��ƁA�����͉���������H�����͉���������H�����͂��ꂽ���A���������́I�ƁA�Z���I�Ȏv�l�ɂ����Ȃ�Ȃ��̂ł��B �����āA���ꂪ���ތ��ʂȂ�Ă��̂͑z������K�v����Ȃ����ł���̂ł��B
http://ssoubakan.com/blog-entry-2638.html
���̖������o���Ă��܂����H�@�@09��22���@
�}���������o���ςł���܂������A���̌�������Ȓl�����𑱂��Ă���܂��ˁB �Ă͔N�����グ�m���Ƃ̌����ʼn~���ɂȂ��Ă���܂����A�ǂ����ƌ����Βǂ����ł����A�P�ɔ����Ă����Ƃ��낪�����߂��Ă��������Ƃ̊ϑ�������܂����A�����͒Z���ł���Ƃ������Ă���܂��ˁB �Z���̔�������������A�ڐ�͂ǂ��Ȃ邩������Ȃ��ȂƎv���Ƃ���ł����A�����̓����Ƃ͂ǂ����ƌ����A�E���������邱�ƂȂ��p�����Ă���Ƃ��낪�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B ���̑�\�́A���ƌ����Ă�����ł���܂����A����̔������j���ς��Ȃ�����A���͂ǂ�ǂ�z���グ����̂ł�����A���̊Ԃɂ�狏�����ς��Ă���Ƃ������ɂȂ�ƍl����ׂ����Ǝv���̂ł��B �ڐ�Ƃ��ẮA�m���ɒZ���̔��������ɍ��E����銔���s��ł���܂����A���������傫�Ȏ��_�ł����čs���K�v������Ǝv���Ƃ���ł��B �����A�ڐ���厖�ł���܂����A�����ł��Ȃ������F�X����܂��̂ŁA�����̓u���[�L��A�A�N�Z���肵�Ȃ���A��肭�R���𑖍s���čs���C���[�W�ŏ��z���čs���Ē�����Ǝv���܂��B �Ƃ��낪�A�ŋ߂̌l�����Ƃ́A�ȒP�ɋ肪�o������̂ł�����A�����ŃM�A���o�b�N�ɓ���Ă��܂��̂ł��B �R���͐T�d�ɃA�N�Z���ƃu���[�L���g�������čs�������ł���ςȂ̂ɁA�o�b�N�ő���n�߂Ă��܂��̂ł��B ���܂ɂ͏�肭�s���l������ł��傤����ǂ��A���邵��Ȃ����A�����͎��̂ɑ����Ă��܂��ł��傤�B �Ȍ|�Ȃǖڎw���Ȃ��Ƃ��A���v�͎�ɂł��邵�A�T�d�ɉ^�]���������A���ʓI�ȕ�V�͑傫���Ǝv���Ƃ���ł��B ���Ƃ��Ă��A�ڐ�͂�����ƍr���\���͍l���Ă���܂��B ���T�͗X���̔���o��������܂����A����ɋz���グ���鎑����1���~����l�ł�����ˁE�E�E�B �����̎����͊����s��̑��̖������Ē��B�����̂ŁA���̊����s��ɖ�1���~�̔��舳�͂�������̂ƈꏏ�ł��B �ł�����A��X�͖��Ȃ��Ƃ��Ă��A�ڐ�Ɋւ��Ă͒��ӂ��K�v�Ƃ������ɂȂ�܂����A�m���ɉ�����Ƃ������ł͂���܂���B ���ɍ���̔���o���ɍ��킹�ĂȂ̂��A���{�͉��U���I���̕��j��ł��o���Ă���A���̐���オ��ʼn�����������������Ă����Ԃł��B ���̂܂܉������Ȃ��������̔@���ŗǂ��̂��ǂ����͕�����܂��A���ɂ߂��ԈႤ�Ƃ�����ƒɂ��ȂƎv���Ƃ���ł͂���܂��B �����A������Ȃ���A������Ȃ��ŁA����ėl�q���f�������̂ł��B �����Ŗ��������ƂƂ����̂́A������ėǂ����ǂ����ŔY��ł��邾���ł��傤�B ���ׂ����Ƃ́u�����܂Őςݏグ�����v�̈ꕔ���m�肵�A�����䗦�����߂ɂ��ėl�q���f���v���ł��B ������Δ����Ηǂ����A������Ȃ��Ȃ�A��������㏸����Ǝv����������čs���Ηǂ��̂ł��B ����������͂Ȃ��̂ł��B �����Ŏ���āA����ł�����āE�E�E�ƁA�X�P�x�S�ۏo���Ŏ�����悤�Ƃ��邩�����Ȃ邾���Ȃ̂ł��B ���ׂ����Ƃ́A�����ł�����ǂ��炩�̈꓁�����𐽎��Ɏ��s���čs�������Ǝv���Ƃ���ł��B ��������A�K�����v�Ƃ����`�Ŋ��͉����Ă���邱�Ƃł��傤�B
http://ssoubakan.com/blog-entry-2633.html
����̋�C��ǂ߂�́@�@09��21���@
�X���̔���o���̉e���́A�m���ɏo��ƌ��Ă���܂������A���U���I���̍D�ޗ��őł������ɂȂ��Ă���i�D�ł��ˁB �m���ɗX���ɋz���グ����̂ŁA���ꂩ��e�����o�ė���\���͂��낤���Ǝv���Ă���Ƃ���ł����A�x�����߂��Ă������܂��A�����ł̃o�����X���o�͔��ɓ���ƌ����܂��B �����A����ƌ����܂��̂́A�����u���^���̏�ԁv�ł���A�Ƃ��������t���ł��B ����ɉו����R��������ԂŒ݂苴��n��A�����̓O���O�����邵�A���������Γ]�����܂����A�K�x�ȉו��ł���A�h��Ă������~�܂�Ηǂ������ł��B �v�͌y�����Ă����ƁA���ꂾ���̎��Ȃ̂ł����A�l�����Ƃ́A�ӊO�Ƃ��ꂪ�o���Ȃ��̂ł���ˁE�E�E�B �ǂ����ɒ[�Ȑl�������āu����Ȃ̂��H�����Ȃ̂��H�v�����l���Ȃ��̂ł��B ���������̔���Ƃ����̂��肾�Ƃ����̂ł�����A�����ڂ����Ă��Ȃ��̂ł��B �����𗘐H��������A�����Œu���Ă������Ԃ������Ă���������Ȃ����Ǝv���܂��B �����ł��鎞�͖��ʂ��Ƃ������܂����A���Ԃ��߂����Ă�����Ƀ`�����X�͓ˑR�K�ꂽ�肷��̂ł��B �u�����ǂ������o���̂ɁA���������]�͂��Ȃ��E�E�E�B�v ������₵�����͖����Ǝv���̂ł����A�ǂ������̕ӂ̃o�����X����肭�o���Ă��Ȃ��̂��l�����Ƃ��Ǝv���̂ł��B ���̋�͂܂���1���~���܂������A�������㏸����A�X�ɑ����鎖�ł��傤����ǂ��A���ꂪ�ǂ��܂Ŗc���̂��E�E�E�B ���Ƃ����͖̂{���Ɏc���Ȃ��̂ŁA�����A���������ł͔��f���o���Ȃ��̂ł��B �u����ȂƂ���܂Ŕ����Ĕn������Ȃ��̂��I���肦��I�v ���Ă��Ƃŋ������̂��Ǝv���܂����A�オ���čs�����������āA�u��Ɋ�������ˁH�v�Ƙb������A���Ҏ��v���傫�����Ƃ��A�F�X�ʂ̘b������̂����̐��E�ł��B �܂��A�����肾�������Ɂu���Ҏ��v��������ˁH�v�ƕ����A�u����Ȋ����Ȏ��ɉ������ĂI�v�ƌ����鐢�E�ł����ǂˁB �v����ɁA������ɂȂ���̂Ȃ�āA���͑��݂��Ȃ��̂ł��B �����܂ł��A���̎��̋�C�B ���̐��E�́A�������ꂾ���ł��B �ł�����A����̋�C��ǂ߂�́A�u����ρv�������ł��厖�Ȏ��ł���Ǝv���̂ł��B
�����̓����ɖ@�������_���Ȃ��̂ł��B
http://ssoubakan.com/blog-entry-2632.html
�Â��l���͉��߂�@�@09��20���@
����͓��o���ς��}�����܂����ˁB �������̃��|�[�g�ŁA�l���h����������Ă���Ƃ��A20000�~���V�ゾ�ƍl���Ă��邾�Ƃ��A��Ȃ��������s�������Ă���Ƃ������b�����Ă��܂����B �����āA�����������S�͕����ɂȂ���Ƃ����`���������܂����B �����Č��ꂽ�̂�����̋}���ł��B �܂��A���������������̂͐��{�ŁA���U���ő�̍ޗ��ł͂������̂ł����ǂˁB �u�グ�^���ŁA��͂���ȁv�ƁA���x�����x�����������ė����̂ł����A����Ă��܂��Ă������͖{���Ɏc�O�ł��ˁB ���{�͊������グ�����̂ł����A�Ƃɂ����}�C�i�X�ɂȂ�悤�Ȏ��͂��Ȃ��̂ł��B �}�C�i�X�ɂ��Ă��܂����͂����Ă��A���Ȃ��l�ɐS�����Ă���͂��ł�����ˁB �ł�����A������I�Ɍ���A���̉��U�͓��R�ł���A�ǂ߂Ă��ē�����O�Ȃ̂ł��B �ł����A�������͂����܂œǂ�ł��܂���ł����B ����͒P���ɁA������傫��������l�ȍޗ��ɂ͕q���ɔ�������K�v�����邪�A�グ��b�ɂ͂��������ŗǂ�����ł��B ���������グ�^���ŁA�グ��Ζׂ���|�W�V�����������߂��Ă���̂ŁA�D�ޗ��͏o�Ă���Ή����Ă��Ԃɍ����̂ł��B �ł�����A�グ��ޗ��͌���ɂȂ��ĒT���K�v���Ȃ��̂ł��B ��Ԓ��ӂ�������ׂ��́A�����o�[���v��D���\���̂���u�����ޗ��v�ł���A���ꂾ���͐�Ɍ������Ȃ�����őS�_�o���X���Ă���Ƃ���ł��B ���ɔ���Ŏ�낤�Ƃ����蓊���Ƃ́A���ƑS���t���s���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł��B �����������グ��ޗ����ǂ����炩�o�Ă��Ȃ����E�E�E�B �u�グ�ޗ��v�ɑS�_�o���X����K�v������̂ł��B �����A�����蓊���������߂��Ă���Ȃ�A�ԈႢ�Ȃ����U�͌x���v�f�ɓ����Ă����͂��ł����A�����o���Ď�d��������Ȃ�A�x�������߂�Ȃ肵�Ă����ł��傤�B ��Ŗׂ��悤�Ǝv���Ȃ�A���̈ʂ��Ȃ��Ă͂��߂��Ǝv���̂ł��B �u20000�~�͊ȒP�ɂ͒����Ȃ����낤���甄��v ���̒��x�̍l���ŋ�Ȃ�āA�͂����茾���ĊÂ��ł��B ����u���O�ł������܂������A�����Ȃ甃���A����Ȃ甄��ƁA�����̃X�^���X�m�Ɍ��߂�ׂ��ł��B �u�����ł��A����ł��ׂ������I�v����Ȏ��v�������ږ�ɂ���͕̂S�����m�ł����A���͔������Ȃ̂ŋ�̐����͖w�ǂ��܂���B �オ�肻���Ȃ甃���A�����肻���Ȃ��B ���̂悤�ȁA�Â��l������������̂ł��B
����ł��A�����ł��ǂ���ł���������A�Ƃɂ����^���ɂ�����l���Ȃ��ẮA���ŗ��v�͓����Ȃ��B
�����S�ɍ���ň꓁���ɂ߂邱�Ƃ������߂������ł��B �i�u�꓁���ɂ߂�v�@�ˁ@http://ssoubakan.com/blog-entry-2623.html�j ����̏㏸�ŁA�����̌l�����Ƃ����܂�Ă���ł��傤���A����őޏ�łȂ��Ȃ�A���̍l�������߂āA�܂����̏����ɒ���ōs���Ē�����A�����߂Â���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
http://ssoubakan.com/blog-entry-2631.html
�꓁���ɂ߂�@�@09��07���@
�k���N�̖��̉A�ɉB��Ă��܂������A�Ă̍���������グ���́A����Ȃ�ɏd�v�ȍޗ��ł���܂����B ���͍ŏ�������Ȃ��Ƃ��Ă��܂������A����ɂ͊m���ɉe�����y�ڂ��Ă���܂������A���f�B�A�ɐ����ĕs���ɋ���Ă��铊���Ƃ͊m���ɋ���܂����B ���Ȃ��Ƃ��������́A�ߋ��ɂ����x�������悤�Ȏ��������Ă��A�S�ĉ������ė������u�����ł��Ȃ����ł͂Ȃ��v�Ƃ��������ő�̍����ł��B ������̈����グ�ō��ӂł��Ȃ���A�Ă͊m���Ƀf�t�H���g���܂����A�v�͓�吭�}�̊Ԃ̋삯�����ł���A�����u�����̋�v�Ńf�t�H���g��I������͂����Ȃ��̂ŁA���ӂ���͓̂�����O�ƍl����ׂ��Ȃ̂ł��B ������q����A�}���ق�������邾�Ƃ��A���R�̏��_��������邾�Ƃ��A�����@�ւ̂�����Ƃ���ɉe���͏o�ė���̂ł����A���ꂪ�Čo�ς�h�邪���O�ɉ�������Ȃ���A�ԈႢ�Ȃ��������狭��Ȕᔻ�𗁂т�̂ł��B �����Ƃ�����Ȕn���Ȏ�������͂����Ȃ��ł����A�N���肦�Ȃ����ł���̂ł��B �����A�Ӓn�Ƃ��͂��邩���m��܂��A���ǂ͗��Ƃ��ǂ����T�荇���������Ǝv���̂ł��B �����āA�������ꂽ�̂����Q�������炵���n���P�[���u�n�[�r�[�v�ł���܂����B ���̔�Q�����āu�����A����ō�������͉������ȁv�Ɣ��f���A����͂��������ł��ƃ��|�[�g��������ł���܂��B �����āA����́u����������グ�ō��Ӂv�Ƃ̃j���[�X����э���ł��܂����B ���̂ɍ��ӂ��ƌ����A���ꂾ���r��Ȕ�Q���o�Ă��钆�ł�����Ȃ����������Ă���ꍇ�ł͂Ȃ����A�����ɐS���𒍂��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ���Ԃł��邩��ł��B ���ʁA�h���͏㏸���ĉ~���ƂȂ�A���o���ϐ敨�͔����E�E�E�Ƃ̗���ł��B ���̗���͊��S�Ɏ��̃V�i���I�ʂ�ł���A�����o�[�e�ʂ��������f�ɐ����������낤�Ǝv���Ă���Ƃ���ł��B �܂��A����̓��������s��ł���܂����A�k���N�ɋ��|�������Ă���l�����Ƃ�������������������A�����甄��C�z�̖������ڗ����܂������A���̔���C�z�͒�l�ɓ͂�����������Ɣ��f���A9�����O�ɔ���C�z�ƂȂ��Ă���4080�c�����w�Ȃǂɑ��Ĕ��������čs�����������߂������܂����B �˂����݂�����������͔����čs�������Ƃ̃��|�[�g�ł���܂������A1490�~�Ŋ�������1480�~�܂Ŕ����܂������A1679�~�܂ł����Ă�1657�~�����ƁA200�~�߂��㏸�������܂����B �����������C�z�X�^�[�g�ł���܂����A���S�ɓǂݒʂ�̓W�J�ɖ������Ă���Ƃ���ł��B ���������V����������ł͂���܂��A����ȑ���ł���������_�����߂ē����A���v�͏o�ė�����̂ł��B ���̑��ɂ����҂ł�������͂���܂����A�����瑽���̌l�����Ƃ���C�ł��낤�Ƃ��A���������ŗǂ��Ɣ��f���Ă�����́A�����Ŏ���čs���Ηǂ����낤�ƍl���Ă���Ƃ���ł��B �܂��A�����ꔃ���łׂ͖���Ȃ��Ǝv�����͗���ł��傤���A���̎��͋�̐��������܂����ǂˁE�E�E�B �����ő厖�Ȏ��́A�オ��Ȃ甃���A������Ȃ��ƁA���傱�܂������čő���̗��v����낤�Ǝv��Ȃ����ł��B �u�����ł��A����ł��ׂ������I�v����Ȏ��v������͕̂S�����m�ł����A���͋�̐����͖w�ǂ��܂���B �m���ɉ�����Ȃ�肪�ǂ��Ƃ͎v���̂ł����A���͐l�Ԃ���ȂɊ�p�ɂ͏o���Ȃ����̂ł��B �{���ɑ���Ő����������Ȃ�A�����g���ɂȂ�����A�꓁���ɂ߂�����ǂ��̂ł��B ����́A��������ȂƂ������ł͂Ȃ��u����Ȃ甄�肾�����l���A�����Ȃ甃���������l����v�Ƃ������ł��B �����̎��g�݂₷�������傽�铁�Ƃ��A���g�ݓ����e���ɂ��Ă��������̂ł��B �����܂ꂽ���ɁA�d�����Ȃ��e���Ő키�ƍl����Ηǂ����Ǝv���Ƃ���ł��B �ł�����A���ł��肪�o���鏀���͕K�v�ł����A���i�͊ώ@�����ōs���͂��Ȃ��B �����܂ł����������ōl���A����āA����āA�킢�����āA�����܂�Đ킦�Ȃ��Ȃ�����A����Ƃ�������̂ł��B
�́A�������̍��̘b���������Ƃ�����܂����A�������Ĉ���̎��ɐS���𒍂��ōs���A�����ꔄ��ł������Ȃ���ʂ��������ɁA�f���炵�����肪�o������̂ƍl���Ă���Ƃ���ł��B
�i�W�N�O�̋L���ł��u���艮�̍��Ɣ������̍��v�j�@���@http://ssoubakan.com/blog-entry-455.html
�u�ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��Ȃ�܂ł́A�����������l����B�v
���ꂪ�A�Ԃ�邱�Ƃ̂Ȃ����̏����̊�{�ł��B
http://ssoubakan.com/blog-entry-2623.html
�_������_������@�@09��08���@
�����͐敨�ƃI�v�V�����̐��Z���ł��郁�W���[SQ�iMSQ�j�ł��ˁB MSQ��3�����Ɉ�x3�C6�C9�C12���̑����j���̊��t���ōs���鐴�Z�ł���܂����A���̑��̌��ɍs���Ă���I�v�V����������SQ�ɔ�ׂ�ƁA�啪�l�������r���Ȃ邱�Ƃ������̂ł��B MSQ�����Ă̈�T�Ԃ�1000�~���������Ƃ�����ł����A�Ƃɂ����r���̂�����MSQ�ł���܂����A���͂�����Ƃ����|�C���g������܂��B ���Z�͋��j���̊��t���Ȃ̂ł����A�ŏI�������͖ؗj�̑�����ƂȂ�܂��̂ŁA���j���̒��͐��Z��҂����́u�܂Ȕ̌�v��ԂȂ̂ł��B �ł�����A��������Ƃ̑����͐��j���ɂ͏��������߂Ă��܂��̂ŁA����d�|���̃s�[�N�����j���ɂȂ�P�[�X�͔��ɑ����ƍl���ėǂ��̂ł��B �����A�����ŊԈ���ė~�����Ȃ��̂́A�u�����v�Ƃ��������̎��ł���A�K�������Ȃ��ł͂Ȃ��_�ł��B �ł�����A����܂ł̓��������Ȃ���A����̃s�[�N�͐��j���Ȃ̂��A�ؗj���Ȃ̂��A���j���̊��t���Ȃ̂��E�E�E�ƁA�l���Ȃ��画�f���čs���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ŁA���̓_�͌������Ȃ��l�ɂ��肢�������Ƃ���ł��B �����āA�����MSQ�̘b�ɖ߂�܂����A�s�[�N�͐��j���̊��t���Ɣ��f���A����@����Ďn�܂肻���������L�]�Ȗ������A�����ɍs���ׂ��ƃ����o�[�l�ɂ̓��|�[�g��������ŁA���ɗǂ��d���݂��o�������̂Ɣ��f���Ă���Ƃ���ł��B ����̐��E�͊m���̐��E�ł�����̂ł����A�ǂ�ȂɊm�����オ���Ă�100���ɓ��B���鎖�͂Ȃ��Ǝv���܂��B ��ɂ������������ӎ����Ĕ�������̂���{�ƂȂ��ŁA�����炱�����͐M�p����͋ɗ͂��Ȃ��l�ɂƂ����߂��Ă���̂ł��B �M�p��������ȂƂ܂ł͌����܂��A���߂��Ă���Ɩ{���Ƀ`�����X���Ǝv���鎞�ɓ����Ȃ����������̂ł��B �`�����X�Ƃ́A�T�ˉ��������Ɍ������̂ł���܂����A�M�p��������߂��Ă���ƁA�`�����X�̎��ɔ����ǂ��납�ꏏ�ɔ��炳��Ă��܂��̂ł��B �����߂ɂ́A�M�p����ō����Ă���l��_�������ɂ���̂���Ԃł���ƍl���Ă���A�����o�[�ɂ͑_���闧��ł͂Ȃ��A��ɑ_������ɂ��ė~�����Ɗ���Ă���Ƃ���ł��B
http://ssoubakan.com/blog-entry-2624.html
S���̑���ρ@�u�����v�Ƃ������́@10��06���@
�č������ُ�Ȃ܂łɋ����Ƃ�����������܂����A225�����̐����ɏ悹���āA�A�x�m�~�N�X����̍��l�ɔ����Ă��܂����ˁB
�A�x�m�~�N�X�͍����ɂƂ��ăv���X�̍ޗ��͂Ȃ��A�P�Ɋ������邾���̋����Ȑ���ł���܂������A���̒l�i���悤�Ƃ����Ƃ���܂ŗ��Ă���̂́A�����ƌ��������ł��B �����A���{���ς�����̂ł͂Ȃ��A�Ă��ς���������ł��邵�A���{�ɂ͏���ő��łƂ����V���Ȓn�����҂��Ă���̂ŁA������͊��������邾�낤�Ǝv���Ă���Ƃ���ł��B �������A����͖�����̎��ł���A�����炻������z��������͎��������Ƃ������ɂȂ�܂��B ���������ɂ��Ă��A����܂ł͔����Ŏ���čs���̂�����ł���A�S�\���Ƃ��ẮA�܂����Ȃ������m��Ȃ����ȁE�E�E�ʂŗǂ��Ǝv���܂��B �Ⴆ�A����̓u���O�ł� �u�����܂߂āA�F��������Ǝv���Ă��邱�̘A�x�O�́A�t�ɉ����Ȃ��\��������B�v �u������A�ꕔ���H�����̗]�T���������镪�ɂ͗ǂ����A��܂ł���̂͂��߂����B�v �Ƃ��܂����B �����̑���͍��̂Ƃ���A���ɂ��̂悤�Ȋ����ŁA�N����������Ǝv���Ă���Ƃ���ŁA�ӊO�Ƃ������ďグ�ė����ł��B �グ�ė���ƁA�����Ɋ������Ƃ��A�ߔM���Ă��邾�Ƃ��A�F�X�ƌx�����錾�t���o�ė���̂ł����A����̐��E�ɂ́u�����v�Ƃ������̂�����A���ꂪ���ɏd�v�Ȃ̂ł��B ���ɋߔN�́u�ǂ��܂Ŕ���I�v�Ƃ����Ƃ���܂Ŕ��邱�Ƃ����������Ǝv���܂����A����Ɠ��������āu�����܂Ŕ����I�v�Ƃ����Ƃ���܂Ŕ������������Ȃ�܂����B �����͂����炭AI�ɂ��CTA����ł���A�l�Ԃ̊��o�ł͕�����Ȃ����̂Ȃ̂ł����A�������悤�Ƃ����A���o�Ŏ���čs���������ǂ��̂��낤�Ǝv���Ă���Ƃ���ł��B ���āA�����̂Ƃ���F�X�Ɖ����Ă�����������������̂ł����A���炳�ꂽ�肵�Ă���܂��H ������O�Ɉꕔ���H���Ȃǂ��ė]�T���������Ă���ΐ����ł����A�������Ƃ���ŕ|���Ȃ��đ��肵�Ă����Ȃ�A����͔��Ɏc�O�ł����A�X�ɉ�����Ǝv���ċ肵�Ă�����ň��ł��ˁB ���x����͂��Ă͂����Ȃ��Ə����Ă��Ă���܂����A�����������ꂪ�o��\�������鎖��\�z���Ă̎��ł��B ��Ȃ�Ă��̂́A���S�ɑ��ꂪ���Ă���ł��Ԃɍ����̂ł��B �Ⴆ�A����225�ōl����Ȃ��19000�~���ꂩ��ł��x���͂���܂���B ����ȂɈ����Ȃ�Ȃ��I�����v���Ƃ���������āA��������Ȃ��ߎS�ȏ�ԂɂȂ��Ă���̕����ǂ��̂ł��B �ł�����A���̗l�ȏ�ԂɎ���܂ł́A�Ƃɂ��������ōl���čs���̂ł��B ���͔����Ŗׂ��鑊��ł����A�V��낤�Ȃ�Ďׂȍl�����N�����Ȃ����ł��B �グ�^���ŏオ�镪�ɂ͉����܂ōs���Ă��ǂ��B ���̈ʂ̊����ő�������čs�����������߂������܂��B
http://ssoubakan.com/blog-entry-2643.html
S���̑���ρ@�����̌l�����Ƃ��������Ă��Ȃ����Ɓ@�@10��11���@
�A�i���X�g�̑���\�z�����C��F�ɂȂ��Ă��܂����ˁB
��T�܂ł�19500�~�\�z�������̂ł����A���T�ɂȂ�����21000�~�\�z�ł��B �܂��A����20800�~�ł�����A���C�ƌ����Ă��債�����C�ł͂Ȃ��̂ŁA���Ɍx������قǂł͂Ȃ��̂ł����A��T�܂ł̎�C�\�z����`���āA�l�����Ƃ͋�𑝂₵�ė����̂��Ǝv���ƁA�{���Ɏc�O�ł��B ���̕��j�͉��x���\���グ�Ă��Ă���܂����A�����܂ł����C�Łu�������甃���v���������ڔ����X�^���X�ł���܂����B �|����Ύ�����Ă��ǂ����A�肾���͂��Ă͂����Ȃ����ꂾ�ƁA���x�������Ă��܂����B �u�k���N���E�E�E�v�Ƃ��u���������ł͂Ȃ��v�Ƃ��A���闝�R��T��������������ƌ����܂����u�|����Ύ���Ă����H�v�Ƃ������x�ł���A��ŗ��v�悤�Ȃǂƍl����̂́A���炩�ɍs���߂����Ǝv���̂ł��B ���̒��x�̋��|�ŁA���������̑���Ŕ���Ŏ�낤�Ƃ����̂́A�ǂ��l���Ă����ՂȔ��z�ł���Ǝv���̂ł��B ���x�������Ă��Ă���܂����A�����ƁA��́A�P���ɐ^�t�̍s���ł͂Ȃ��̂ł��B ��������ƒ����Ȃ�܂����A���܂ł����x�������Ă��Ă����ނł��̂ŁA�����͐��_�ʂɍi���čl���Ă݂܂��傤�B
�����Ƃ́A�㏸�ɓq�����ł����A���̌���������u���W�v�ɓq���Ă����ł��B
�������́A�����ɓq�����ł����A���̌���������u�v���v�ɓq���Ă����ł��B
���Ђ̈Ⴂ�͏q�ׂ�܂ł�����܂��u�|�W�e�B�u�v�l�v�Ɓu�l�K�e�B�u�v�l�v�ł��B
����͗ǂ��Ƃ����T���A����͈����Ƃ����T����ł��B
����͓����l�Ԃ̐S�ŊȒP�ɏo������̂ł͂���܂���B
�قȂ鐸�_��Ԃ̔������ɂ��Ȃ��Ƃ����̂́A���͔��ɓ�����̂ł���̂ł����A����𑽂��̌l�����Ƃ��������Ă��Ȃ��̂ł��B
�����������Ƃ����̂́A���X�u��������̂͂Ȃ����H�v�ƒT�������邩�u���X������̂͂Ȃ����H�v�ƒT�������鎖�Ȃ̂ł��B �����A���͋肪�_�����ƌ����Ă���̂ł͂Ȃ��u�}�C���h�͂ǂ��炩�ɂ��Ȃ�����v�ƌ����Ă���̂ł��B �����炭�A�����_�ł���Ŏ���Ǝv���܂��B �����A�����͑�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł���ˁB ����łقڊm���Ɏ��鎞�́A�����}���������A����ő��ł����s����鎞�ł��傤�B �������̎��ł����A���̎�����͔�����l���邩���m��܂���B ���łŁA�ԈႢ�Ȃ��l�����œI�_���[�W���܂��̂ŁA���ɂ����Ŏ��Ȃ���͂���܂���ˁB �܂��A���̐���肭�s���āA�l����_���[�W���Ȃ��Ƃ��A�������ς��Εʂł����ǂˁE�E�E�B ���āA�Ƃɂ��������͍������A�l�����Ƃ̔����������Ǝv���̂ł����A�l���𐳂������Ƃ���čs����Ǝv���̂ł��B
http://ssoubakan.com/blog-entry-2645.html
|
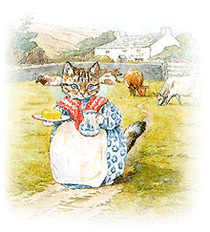
 �X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B �X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B