�p�b�V�u�v���A���v�̖��
�Z���N�^�[�ƌŒ��R���A�b�e�l�[�^�[�𓋍ڂ����p�b�V�u�v���A���v
�v���A���v/�R���g���[���A���v�Ɠ���ւ��āA���͐ؑւƉ��ʒ��߂������s���܂��B
CD����̏��ʂ����̂܂܃p���[�A���v�ɓ����������ɍœK�ȃp�b�V�u�v���A���v�ł��B
�p�b�V�u�v���A���v�̓A�b�e�l�[�^�[�݂̂ɂ�艹�ʒ��߂��s���܂��B ���������ėǎ��̃A�b�e�l�[�^�[��p�����ꍇ���������ɂ����̂������ł��B ���ۂɒʏ�̃v���A���v���p�b�V�u�A���v�Ɍ������Ă݂�ƁA�𑜓x�����������A�������X�����Ȃ����A�����O�ɏo�Ă���悤�ɂȂ����Ƃ������𑽂������܂��B �ʏ�̃v���A���v�ł́i���ꂪ���\���~�̐��i�ł��j���������Ă����Ƃ����ɂȂ��Ă��鎖�������Ƃ�����ł��傤�B
�p�b�V�u�v���̌��_�͏o�̓C���s�[�_���X���������Ƃł��B
�����ʂɂ���ĈقȂ�܂����A���Ђ�10K���̃A�b�e�l�[�^�[�̏ꍇ�o�̓C���s�[�_���X��0�`2.5K���ɂȂ�܂��B �v�̌Â� Tr�p���[�A���v�A�n���OP�A���v����͒i�ɗp���Ă���p���[�A���v�Ȃǂł͓��͒i�̃L���p�V�^���X�̔����ɂ���č���̘c�����������邱�Ƃ�����܂��B���̏ꍇ��������łɂ��₩�ɒ���������A�������ɂ������������肷��Ǝv���܂��B
�܂����̗��R�Œ�R�l��100K���ȏ�̃{�����[����A�b�e�l�[�^�[�� Tr���A���v�Ɏg�p���邱�Ƃ͂����߂ł��܂���B ���̓C���s�[�_���X���傫�����̂̓p���[�A���v�̘c�������������܂� �p�b�V�u�v���̏ꍇ�A���̌�����A�o�̓C���s�[�_���X���傫���Ȃ�܂��B ���Ƃ���10K���̓��̓C���s�[�_���X�̃A�e�j���G�[�^�[�i���̓{�����[���j��p�����ꍇ�A�o�̓C���s�[�_���X�� 0-2.5K�I�[���̊Ԃŕω����܂��B �ő�ƍŏ��̎��ɂO�A-6dB�̎���2.5K���ɂȂ�܂��B �����Ŗ��ɂȂ�̂͏o�̓C���s�[�_���X�傫���ƍ���Ŗ����ł��Ȃ��c������A���v���������Ƃł��B �A���v�̓��͒i�͍���������H�ł����A���̓��͒i�̗e�ʂ̔��I�ȓd���ˑ����̂��߂ɁA����̘c�����Ă��܂��̂ł��B �o�̓C���s�[�_���X��2.5K���ʂȂ炻��قǂł��Ȃ��̂ł����A���ꂪ50K���ƂȂ�ƃI�[�f�B�I�p��OP�A���v�ł�10KHz��0.1%����c���������܂��B ���̕ӂ��\���ӎ������v���A���v�ɂȂ���Ă���Ζ��͏��Ȃ��̂ł����A�l������ĂȂ��A���v�̕��������Ǝv���܂��B���Ƃ����ē��̓C���s�[�_���X�����܂菬�������́i���Ƃ���600���j���g�p����ƃv���A���v�̕��ׂƂ��ďd�����āA�v���A���v�̂ق��Řc�����܂��B���Ђ̃p�b�V�u�v���A���v�͔����̃A���v�Ƃ��čœK��10K�����̗p���Ă��܂��B
http://www.audiodesign.co.jp/PPA.htm
�@�o�̓C���s�[�_���X�̖��Ɖe��
��ʂɋ@�킩��@��ւ̉��y�M���̎n���́A�u���[�o���A�n�C�v�������Ƃ���Ă���B �u���[�o���A�n�C�v�Ƃ́A �M�����o�����̏o�̓C���s�[�_���X��Ⴍ���A
�M������鑤�̓��̓C���s�[�_���X���������鎖�ł���B ��ʂɏo�̓C���s�[�_���X��10���`600���A���̓C���s�[�_���X��20k���`50k���ɐݒ肳��Ă���ꍇ�������B ���ʂƂ��āA�Ⴂ�d���Ŏn�����߃P�[�u����ʉ߂���Ƃ��Ƀm�C�Y�ɋ����B�P�[�u���ɂ�錸�����N������g���̒l�������B�d�����Ⴍ�Ȃ�A����o�����@��̕��S���������B �Z���Ƃ��āA�`�����X���傫���Ȃ邪�A�ߔN�̋@��ł͂��܂���ɂȂ�Ȃ��B �A�N�e�B�u�^�v���A���v�́A�����œd���������Ă���d���d�����ł��邽�߁A���o�͂̃C���s�[�_���X�͎��R�ɐݒ�ł���B �p�b�V�u�^�v���A���v�́A�\����{�����[���̒��߈ʒu�ɂ��ω����A�����o�̓C���s�[�_���X�����ꍇ������B50k���̃A�b�e�l�[�^�ł���A�ŏ�0k���A�ő�12.5k���̏o�̓C���s�[�_���X�����B �p�b�V�u�^�v���A���v���g�p�����Ŗ��ƂȂ�̂́A�u�����o�̓C���s�[�_���X���A�����ɂǂ̒��x�e������̂��v�ł���B ��ʂɌ����Ă��鍂���o�̓C���s�[�_���X�ɂ�����������ƁA
�������̑�����������B
�o�̓C���s�[�_���X���傫���ꍇ�A�P�[�u�����������Ȃ�ƁA�����̈�̑�����������B �Ⴆ�A�o�̓C���s�[�_���X 12.5k���ł���A�P�[�u����1.9����100kHz�̉��悪�����ɂȂ�B
�ǂ̒��x�̍�����L���ɂ����邩�ŁA�����ɉe���̂Ȃ��P�[�u���̌��E�������قȂ�A��������P�[�u�����g�p����Ɖe�����o�Ă���B
�����̓C���s�[�_���X���o�̓C���s�[�_���X���������Ȃ�A�c�݂�������ꍇ������B
�p���[�A���v�̓��̓C���s�[�_���X���Ⴂ�o�̓C���s�[�_���X�̃p�b�V�u�^�v���A���v��I�ׂA���Ȃ��B
���o�̓C���s�[�_���������Ɠd�����傫������A���葤�̋@��̕��S���傫���Ȃ�B
�d�����傫���Ȃ邱�Ƃ͑傫���Ȃ邪�A�@�킪�ǂ̒��x�ς�����̂�������Ȃ����߁A�e���͕s���B
http://www015.upp.so-net.ne.jp/yoneharu/etc/passive.html 3�̏����Ńv����荂�����H �p�b�V�u�A�b�e�l�[�^�[ ���W�J��2��̃p�b�V�u�A�b�e�l�[�^�[ att30
http://www.musika.jp/30.html iris-att
http://www.musika.jp/iris.html �����C���i�b�v���Ă��܂��B���ꂪ�ӊO�ɉB�ꂽ�q�b�g���i�Ȃ̂ł��B ���Ă͐��Ђ���o�Ă��܂��������݂ł͂قƂ�ǖڂɂ��邱�Ƃ͂���܂���B
�Ȃ��ł��傤�H ����͕s�K�Ȏg�p���@�ɂ���āw�p�b�V�u�A�b�e�l�[�^�[�͉��������x�Ƃ����Ԉ��������ꂽ���炩������܂���B �����炭�A�p�b�V�u�A�b�e�l�[�^�[�͎g�p�����ɂ���Ĉ�ԑ傫���������ς��I�[�f�B�I�@��ł��B �ǂ����̂��߂̏����͂R�B A.�ݒu�ꏊ
B.�o�̓P�[�u���Ƃ̑���
C.�p���[�A���v�Ƃ̑��� ���̂R�̏������������Ƃ��A�d���m�C�Y�Ɩ����̃p�b�V�u�A�b�e�l�[�^�[�� �ƂĂ��N���A�[�ȉ����o���Ă���܂��B ���������A�p�b�V�u�A�b�e�l�[�^�[�Ƃ͉��ł��傤�H �@�\�͓��͑I���Ɖ��ʒ��߁B����̓v���A���v�Ɠ����B ���\�Ȍ�����������A �v���A���v����o�b�t�@��H���O���ƃp�b�V�u�A�b�e�l�[�^�[�ɂȂ�܂��B �w�A�N�e�B�u�x�ȃo�b�t�@��H���Ȃ��Ȃ�܂����̂ŁA�w�p�b�V�u�x�Ȃ̂ł��B �ł́A�o�b�t�@��H�Ƃ͉��Ȃ̂ł��傤�H �o�b�t�@��H�͊ɏՑ�����Ƃ������A �O�̉�H�ƌ�̉�H�����݂��ɉe�����邱�Ƃ��Ȃ����ړI�Ŏg�p����܂��B �p���[�A���v�ɂ���ăv���A���v�Ɉ��e�����o�Ȃ��悤�ɂ���̂��o�b�t�@��H�B �Ȃ�A���e�����łȂ��p���[�A���v���v���A���v�ɐڑ�����A�o�b�t�@��H�͕K�v�Ȃ��̂ł��B �]���ȉ�H���Ȃ��Ȃ�A�m�C�Y�������āA�N���A�ȉ��ɁB ���̂����肪�p�b�V�u�A�b�e�l�[�^�[�̎g�����Ȃ��ɂȂ�܂��B
�@ �ǂ����̂��߂̏����A���̂P�@�ݒu�ꏊ�B
�����ł́A�v���A���v�i���̓p�b�V�u�A�b�e�l�[�^�[�j�ƃp���[�A���v�̊W�ɂ��čl���Ă݂܂��B �p�b�V�u�A�b�e�l�[�^�[�ƃv���A���v�̑傫�ȈႢ�͏o�̓C���s�[�_���X�B �o�̓C���s�[�_���X�͍����قǁA���̋@��̈��e�����₷���Ȃ�܂��B
����ł���O���m�C�Y�̉e�������l�ł��B ��ʓI�ȃv���A���v�̏o�̓C���s�[�_���X�� 1K���ȉ��B
�p�b�V�u�A�b�e�l�[�^�[�� 2.5K���B �p�b�V�u�A�b�e�l�[�^�[��2.5�{�m�C�Y�̉e�����₷���Ȃ�ƍl�����܂��B �m�C�Y�̉e�����ɂ���������@�͂Ȃ��̂ł��傤���H �o�̓C���s�[�_���X�ɋN������O���m�C�Y�͎�Ƀp�b�V�u�A�b�e�l�[�^�[�ƃp���[�A���v�Ԃ̃s���P�[�u�����獬�����܂��B �Ȃ�A�s���P�[�u���̒����� 1/2.5 �ɂ���ΊO���m�C�Y�̉e���͓����B �ʏ�s���P�[�u����1.5m���̂��̂��悭�g���܂��̂ŁA����Ɠ����ɂ���ɂ́A60cm�ȉ��̃s���P�[�u�����g�p����Ηǂ����Ƃ��킩��܂��B �����Ȃ�ƁA�p�b�V�u�A�b�e�l�[�^�[�̐ݒu�ꏊ�̓p���[�A���v�ׂ̗���{�B ���̂��߃A�C���X�ł́A����300mm�̃p���[�A���v�ɑ��āA�p�b�V�u�A�b�e�l�[�^�[�̉�����100mm�B
2����ׂĂ��I�[�f�B�I���b�N1�i�Ɏ��܂鐡�@�ɐv����Ă��܂��B �A �ǂ����̂��߂̏����A���̂Q�@�o�̓P�[�u���Ƃ̑����B �p�b�V�u�A�b�e�l�[�^�[�ƃp���[�A���v��ڑ�����s���P�[�u����60cm�ȉ����]�܂����Ƃ������b�����܂������A���̃P�[�u���͎����d�v�ł��B �m�C�Y�����肱�܂Ȃ����߂ɂ́A�V�[���h�����i�Ԃ̕����j�̖ڂ��ׂ����K�v������܂��B ���g���������m�C�Y�قǁA���̖Ԃ̌��Ԃ�����荞��ł��܂��B �ʐ^���������������B
http://blog.goo.ne.jp/musica-corporation/e/dd3ab2b0f48887dfcb1630e7badaed87
�V�[�X�i�O���̃r�j�[���̕����j�͓����悤�ȃP�[�u���ł����A�P�[�u��A�̓V�[���h�̖ڂ��r���A�P�[�u��B�̓V�[���h�̖ڂ��ׂ����A������2�d�ɂȂ��Ă��܂��B
�p�b�V�u�A�b�e�l�[�^�[�Ɏg�p����ꍇ�͉����̃P�[�u�����K���Ă��܂��B �I�[�f�B�I�ł͈�ʓI�ɍd���P�[�u�����D�܂�܂����A����̓V�[���h���������肵�Ă���Ƃ�����ʂ�����܂��B �B �ǂ����̂��߂̏����A���̂R�@�p���[�A���v�Ƃ̑����B �p�b�V�u�A�b�e�l�[�^�[�ƃp���[�A���v�̊W�͋@�֎ԂƋq�Ԃ̊W�Ɏ��Ă��܂��B �v���A���v�͋쓮�͂̂����^�@�֎�
�p�b�V�u�A�b�e�l�[�^�[�͏��^�@�֎�
�p���[�A���v�͋q�Ԃł��B �@�֎Ԃ��q�Ԃ������đ���ꍇ�A ��^�@�֎Ԃł�������ő��邱�Ƃ͊ȒP�ł��傤�B �����q�Ԃ��������Ƃ��A���^�@�֎Ԃł̓X�s�[�h���オ��Ȃ���������܂���B �ł́A�X�s�[�h���グ��ɂ́H �P�̕��@�Ƃ��āA�y�ʂȋq�ԂɕύX���邱�Ƃ��l�����܂��B �p���[�A���v�̓��̓C���s�[�_���X��������p�b�V�u�A�b�e�l�[�^�[�ł��v���A���v�Ɠ����쓮�͂Ńp���[�A���v���h���C�u�ł���̂ł��B ��ʓI�ȃp���[�A���v�̓��̓C���s�[�_���X��47K���ł����A
���W�J�̃A�C���X�ł͓��̓C���s�[�_���X100K���Ƃ��A
�p�b�V�u�A�b�e�l�[�^�[�Ƒ������ǂ��p���[�A���v�ɂȂ��Ă��܂��B �o�̓C���s�[�_���X�Ɠ��̓C���s�[�_���X�̊W�͑��ΓI�Ȕ�̖��ł��肻�̐�Βl�͏d�v�ł͂���܂���B
http://blog.goo.ne.jp/musica-corporation/e/06b9ade4e2573a2e5010c23cbef5367b
���ʒ����{�����[���ɂ��čl����
http://www2s.biglobe.ne.jp/~yapsys/vrsystem.html
��H�\������l���� �p�b�V�u��H�̃{�����[���Ƀs���R�[�h�X�Ɛڑ����邱�Ƃ͂������߂ł��܂���B
�s���R�[�h��ς���ƁA�����ς��Ƃ����܂����A�p�b�V�u�^�C�v�Œ��X�ƈ����܂킵�Ă͈��e�����o�Ă��邾���ł��B �����ōl���Ă݂����̂��A�g������Ɖ������ǂ̂悤�Ƀo�����X���邩�ł��B
�ǎ��ȃ{�����[��������ł��Ȃ��Ȃ��Ă��������A����ł͂ǂ����邩�l���Ă݂܂����B �d�����R�[�h�@�d㜁��P�[�u���@�R�[�h�̏�ɔ핞������P�[�u���ł��傤���H�R�[�h�������A�P�[�u���������i�̂悤�Ɏv���Ă���悤�ł����A�d�������炷���Ƃ͉��������サ�܂������₷���Ƃ͒ቺ���܂�
���蕶��ɏ��Ȃ��悤�ɂ��������̂ł��B
�Ԉ�����p�b�V�u�v���̎g����
�ŋ߃o�C�A���v�쓮�Ńp�b�V�u�v�������ɂ��ăp���[�A���v���쓮���邱�Ƃ��ꕔ�ōs���Ă��܂��B ����ɂ��邱�ƂŁA�ڑ������ CD�Ȃǂ̕��ׂ��d���Ȃ�ꍇ�ɂ���ẮA�ቹ��̓����ቺ�������܂��B �����ďo�̓s���R�[�h�̊e�ʂō�����B
����ł͉����₹�Ă��܂��܂��B ��̐}�Ő������Ă���悤�ɒ��ɂ���ׂ���H���O�Ɏ����Ă��������̕��Q�ł��B
�v���A���v�s�v�_�̓A���v���Ƀ{�����[��������ꍇ�̘b�ŊO���Ɏ����Ă����ꍇ�͕K�����������ł͂���܂���B �p�b�V�u�v���̌��ɊɏՃA���v�����邾���ŃP�[�u���̉e����}���邱�Ƃ��o���܂��B
�P�[�u���͈Ӑ}�I�ɉ����ς��悤�ɍ���Ă��镨�����Ȃ�����܂���B �v���ł͂��܂�̏�܂Ŕ��W����悤�ȃP�[�u���͂���܂��A��ւ̂悤�ȃP�[�u���̗e�ʕ��ׂŌ̏Ⴗ��p���[�A���v��������̂ł��B
�����ς��Ή��ł��ǂ��ƌ����̂͂������Ȃ��̂ł��傤�H�B
�{�����[���̗�
�ړ_�𑽂�������s�v�Ȕz�������܂킵�A�]�v�ȃV�[���h������M�I�ȓd�����A�܂��́��~�������A����ł́A�킴�킴�p�b�V�u�R���g���[���[������Ă��A���ʂ͖]�߂Ȃ��B 70�N��v�����C���A���v�̃{�����[�����O���Ɉ����o�����̂Ɠ����悤�Ȃ��́B
�����ቺ�������]�v�ȃR�[�h�������������ɉ߂��Ȃ��B ���ʐ^�̓��[�^���[�X�C�b�`�Ő��삵���Œ��R�̃A�b�e�l�b�^�[�A���̗͏��Ȃ��B
�ꉞ���́A���t�@�����X�p�Ƃ��āA�c���Ă����䂾�B ���i���[�^���[�X�C�b�`�Ŏg������́A�����Ԃ鈫�����̂́B
�@��g���Ŏg�p���đ����̕�����D�]�����������Ă���B �@��g���́A�I���g�p���@���B
100�{���̒�R�������X�C�b�`�ɔ��c����킯�����瑊���A��V�Ȃ��̂��B
�����ŗD�悾�ƁA���쐫���]���ɂȂ�B ���ʒ��������Ȃ�{�����[���P�i�A�t�F�[�_�[���͒�R���A�b�e�l��^�[�ŁA�p�͑����̂Ńv���A���v�͕s�v�_���[���̎����B �����ň�ʂɍ����v�����C���A���v�ɗp������{�����[�� RK27 �Ȃ�܂������A����ȉ��̂��̂ŁA�p�b�V�u�R���g���[���{�����[�����\�����Ă��A���ʂ͏��Ȃ��B
���ƌ�����23�i���x�̃A�b�e�l�b�^�[�ł͎g��������l����ƁA�S�Ă̐l�������ł�����̂ł͂Ȃ��B �A���ς͎g�����肪�ƂĂ��ǂ��BRK27 �͍����v���A���v�ɂ����̗p����Ă���̂ŁA�����Ĉ����{�����[���ł͂Ȃ��B��i�ɂ�����ׂ��v���A���v��H���g���āA���\�����Ă���ꍇ�����Ȃ��Ȃ��B�@
�@
�ʐ^�㍶�[ �A���v�X�q�j27�i�e�ՂɏH�t�Ŏs�̕i�w���o���閔�͓d���[�Œ��́j
�ʐ^��E �A���v�X�q�j40�i�@����O���i�j
�ʐ^���� �s�̂S��H�Q�R�ړ_���[�^���[�X�C�b�`�Ŏ��삵���A�b�e�l��^�[
�ʐ^���E �A���v�X�j�t�F�[�_�[�Ő��쒆�̂��́A�F�X�ȕ�������Ĕ�r���Ă݂邽�B �A�b�e�l�b�^�[�͉����ǂ��]��������A�����i�̃v�����C���A���v�ɂ����{�����[���ɃN���b�N���t�������オ�������B�{�����[���̌��ɍa�t���̔��lj����ꂻ���ɔ˂��������ėǍD�ȃN���b�N���o�������o�����̂ł������B ���[�J�[�������A���v����O�����A�b�e�l�b�^�[�i���j�A
�Œ��R�A�b�e�l�b�^�[�i���j�A
�t�F�[�_�[�a�n�w�����B ���̌��ɒZ���V�[���h�R�[�h�Ńp���[�A���v�ƂȂ��D���ʂ������邩���m��܂��A����ɂ́A�{�����[���̒�R�l�A�R�[�h�̗e�ʁA�Ȃǂ��܂��܂ȉe�����o�܂��B
���������܂킷�ɂ́A�o�̓A���v���K�v�ƍl���܂��B �R�[�h�ʼn����ς��Ǝv���Ă���l�����܂����A�����ς�鎖���͂��̒ʂ�ł��A���̉e����}����̂��o�̓A���v�ł��B �J�t�^�C�v�Ő��삵���t�F�[�_�[�͎��Ɏg���₷���B
���ʼn��ʂ����R�ɒ����ł���B���̂悤�ȃ����R���������Ȑl�ɂ͗ǂ��B �莝���̃s���R�[�h�� 1���Ŏ����� 100PF�ʂ̊e�ʂ�����܂����B
�����Ȃ��̂ł���e�ʂȖ�ł͂���܂���B����ɃA���v���̓��͂ɂ�C�͂���B
�P�[�u���ɗe�ʂ͕t���܂Ƃ����̂ł��B �����̂Ƃ���͌��\�B���Ă��镔���ł��傤�B
�p�b�V�u�^�C�v�̉��ʒ�����͎g��������ł��B
�f�ނɑ���O�ɗǂ��l���Ă݂܂��傤�B
�P�[�u���i�V�[���h���j�̂��b
�f70�N��ɂ͖O���O������ė������ƂȂ̂ł����A�ŋ߂͌���܂���B
�f�ޏd���Ƃ������A�����̌��t���x����Ă���悤�ɂ����v���܂��B
���ނ͒Z���A�o����Ζ��������ǂ��̂ł��B �Z����ΒZ���قǗǂ����A�s���W���b�N�iRCA�j�͍\���I�ɂǂ��v���܂��H
�����̂Ŏg���ق��́A�ǂ��̂ł����AXLR�ɔ�ׂ���ǂ��ł��傤�H
�����͂������łǂ����I ���āA�{��ł��B �V�[���h���͍\������Ód�e�ʂ������Ă��܂��B
�e�ʂƌ�����悤�ɖ��p�̂��̂ł��B
���������̂� 1���Ő�100PF�͂���ł��B �����傫�����̂�1000PF�������Ƃ��܂��B2����2000PF
����Ōv�Z���Ă݂܂��傤�B ����1/�i2��CoRo�jHz �ŋ��߂邱�Ƃ��o���܂��B �����-3��B��������g���ł�������6��B�i*�P�j�I�N�^�[�u�Ō������܂��B �i*�P�j�I�N�^�[�u�F���̊���g����2�{���I�N�^�[�u��ƌ����܂��B
�P�OKHz�̃I�N�^�[�u���20KHz�ɂȂ�܂��B�I�N�^�[�u���͔�����5KHz�ł��B ���̃I�N�^�[�u���̎��g���܂ł��t���b�g�Ƃ������Ƃƍl����ƁA�e�Ղ����ɉe�����o��̂ł͂ƍl���Ă��܂��܂��B ����������������ė������������̃P�[�u���ƌ����Ă���̂����m��܂���B
�v�Z���ʂ͉��Ɩ�32KH���i-3��B�j�ɂȂ�܂��B
���̑��ɃA���v�̓��͂�1000PF�̗e�ʂ��������Ƃ��܂��傤�B
3000PF��21KHz�ƂȂ�܂��B ��ʓI��25K�I�[���̏o�̓C���s�[�_���X�Ƃ��Ă̌v�Z�ł��B ������p�b�V�u�Ŏg���ꍇ�͒Z�������K�v�Ȃ̂ł��B
�����p�b�V�u�v���A���v����A���x�̓P�[�u������邻��ȏ��@�Ƃ͂�������܂��傤�B �����ƌ����ȕ��͏o�̓A���v�ŁA�o�̓R�[�h�̉e����}���邱�Ƃ��l���܂��ˁB
�Â��d�����ŃV�[���h�\���Ȃ��Ńs���R�[�h������ĉ����ǂ��Ȃ����̂́A�d�����ɂ����̂����ł��傤���H ������������ł��ˁB ���c�t�����o���Ď����Ŏ�������̂���Ԃł��B
�s�̂̍����P�[�u��1�{�ɂ������Ȃ�������p�Ŏ����o���܂��B ����ʼn��ʒ�����Ƃ��Ă��镪�ɂ́A�����\���܂��A�f�����b�g���B���p�b�V�u�̗ǂ����Ƃ����������̂͂������Ȃ��̂ł��傤�B�d���̉e���͉B���܂���B
�P�A�^�������Ȃ����A���������Ȃ̂ʼn��ʒ������ł���悢�ꍇ
�@�p���[�A���v�̓��͂Ƀ{�����[����t���Ďg���i�^��ǃA���v�ɑ�����j�B
���̏�A�s�x�p���[�A���v�̃{�����[�����̂ŁA���ɏ��ɒu���Ă���p���[�A���v�̏ꍇ�����Ԃ鑀�쐫�������B
�A�b�c�ƃp���[�A���v�̊ԂɌ�����i�{�����[�����̓A�b�e�l��^�[�j������
�s�̂̃{�����[����A�b�e�l��^�[�i�p�b�V�u�v���A���v�Ƃ����������Ȃ��A���v�H�H�H���w������j�����삷��B 600���₻��ȉ��̒���C���s�[�_���X�̃A�b�e�l��^�[�ł̓��̓A���v�Ȃ��Ŏg���Ă̓_���B
����ł́A�ߕ��ׂȂ̂ɒP���ɂ���������B
�Q�A�^�����A�������������̋@��������Ă���̂Ő֑ؑ�����A�����������쐫�d���Œ��������ꍇ
�@�s�̂̃R���g���[���A���v���w���i���ł͂�����n�C�G���h�@�����Ȃ��j �A�ؑ@�\��A�������l�������p�b�V�u�R���g���[���[���w�����͎��삷�� �B�܂Ƃ��ɁA�����@�\�̕t�����v���A���v���w�����͎��삷��B
�R�A������t���f�W�^���̏����Ɋ�]���đ҂�
�{�����[���ʉ߂ʼn��̗��C�ɂȂ�o������A�Œ��R���A�b�e�l�b�^�[���l���Ă݂܂��傤
���āA�{���Ƀ{�����[��������Ɖ��������Ȃ�̂ł��傤���H
�����̓C�G�X�ƌ����܂��B ����͌Â����猾���ė������Ƃł����A�����̕����͂�����Ƃ����Ⴂ�������Ă��炦�镔���ł��B �������g�p�̂b�c�v���[���[�ɏo�͂���������@�\�i��ʼn{�����[���̓_���j�d�q�A�b�e�l�b�^�[���t���Ă�����o�͂��i��R���g���[���A���v�̃{�����[�����ő�ɂ��܂��傤�B�����ω����킩��܂��B �{�����[�����ő�ɂ���Ɠ��͏o�͂��قڃ_�C���N�g�ɂȂ���\���ł��B
���}�P�iB)�̏o�̖͂���͂ɂȂ���킯�ł��B
�P�}�i�`�j�͌Œ��R�ɂ��ؑ֕����̉�H�ł��B
���̑g�ݍ��킹�����[�^���[�X�C�b�`�Ő�ւ��čs���Ηǂ��B
�L���ȓ_
�P�j���̕ω������Ȃ��B�ŏ����̂Q�{�����̒�R�g�p
�Q) ��R�����Ȃ����Ƃ͒�R�̐��̈����o���L���b�v�i�S�j�ɂ�鉹���ቺ���͏��ɗ}������i���̃L���b�v�͉����p��R�ō����j
�s���ȓ_
�P�j���i���[�^���[�X�C�b�`���A�g�p����̂ŁA�d���đ��쐫�������B
�Q�j���[�^���[�X�C�b�`�̐ړ_�s�ǂ��������ł͋N���₷���B
�R�j�z�����ʓ|�ł��x�ݏ�Ԃ̒�R�������̂ő��ȋC������B
�P�}�i�a�j�͒���^�̃A�b�e�l�b�^�[��ŁA�����̌Œ��R���P�̐ړ_�����Ő؊�������́A
�L���ȓ_
�P�j�ړ_�͂P�Œ���ŗ��̔z�������₷���B
�s���ȓ_
�P�j��R�����������Ƃ́A��R�̃L���b�v�i�S�j�ɂ�鉹���ቺ���C�ɂȂ�Ƃ��덂�i�ʒ�R�́A�S�̓I�ȃR�X�g�A�b�v�ɂȂ���B
�Q�j�P�{�̒�R�̉����͂킩��Ȃ��������Ȃ�킩��B
���̐����ŁA�킩���Ă����������Ǝv���܂����A�����特�̗ǂ��ƈ�ʂɌ�����Œ��R�ł�����ɑ�ʂɎg���P�{�ɕt���Q��������ɂ͂̐ڍ����Q�������v�S�����ɂ��Ȃ�̂ł��B
����̂��{�̐ړ_�ʉ߁A���ꂪ�����܂����H �{�����[���ł͈����R�𐠓��q���ړ����A���I�ɒ�R�䂪�ς��B
���ꂪ�X�e�b�v�ɕς�邾���ő���I�ȓ���͓����ł���B ��R�Q�{�̕����������A�����ɗD��Ă��邩�����킩�肢��������Ǝv���܂��B
���������̒���^���{���������Ȃ��悤�ɍl��������H������܂��B
�{�����[�����ƈ��������R�ʂ��u���V����������킯�ł����炠�܂�ǂ����Ƃ͂���܂���B ���Ă̓Z���~�b�N��������A������R�Ƀg���~���O���Đ��m�ȃA�b�e�l�b�^�[�\���ő����^�b�v���o���āA���̃^�b�v��������b�L�ړ_����������}�P�iB)�̂悤�ȃ^�C�v�ł���Ȃ��� RK40�̊O�ρA���쐫�̐^�̃N���b�N�t���{�����[��������܂����B���{���{���ɉ�����Njy���Ă�������ł����B
�p�b�V�u�h�ł͂���܂���B
���܂ŏq�ׂĂ������ƂŎ��̓p�b�V�u�h�Ǝv���邩���m��܂���B
�p�b�V�u�^�C�v�͉e�����₷�����̂ł��B
�o�͂Ƀo�b�t�@�A���v�����邱�Ƃɂ��A�s���R�[�h�̉e����}���邱�Ƃ��ł���ƍl���Ă��܂��B ���̓x�����ƃp�b�V�u�^�C�v�ɂ��ĉ�����}���邩�̑I���ɂȂ�܂��B �������A�b�e�l�b�^�[�a�n�w��t�F�[�_�[�a�n�w�삵�Ď����������߁A�p�b�V�u�^�C�v�̂��̂��o���オ���������ł��B�P�̂̉�����r�p�ł��B
���ۂɂ͂����̂a�n�w�̌�ɃA���v��H��t���Ď����p�Ƃ��Ă��܂��B ���̑��Ɏg��������d�v�ȗv�f�ƍl���Ă��܂��B
���t�K���Ƃ炦�Ă��邾���́A�A���`�p�b�V�u�h�Ƃ͎v��Ȃ��ł��������B
�v���A���v�łȂ����Ƃ����Ă��炦�邱�Ƃɉz�������Ƃ͂���܂���B
����䂦�ɕ��Q�����邱�Ƃ𗝉����ăP�[�u�������Ƃ����D�����甲���o���Ă��������B
�p�b�V�u�֘A�́A�l�b�g��ő�R�����ł���܂����A�����������ŗ����Ă���y�[�W�́A���ɏ��Ȃ��ł��B
���LURL�͑S�Čv�Z���Č����āA���̕����𗝉����Ă���Ă�����ł��B
����������v���ł��B
http://www.vlsi.iis.u-tokyo.ac.jp/~majima/html/e/component/preamp.html
�{�����[���̓��肪����Ȃ��Ă������ł̈�
�{�����[���Ƃ����g������̗ǂ��ɏd�_��u���������̂��߂ɁI �ŋ߂́A�~�j�f�e���g�q�j 27�^�͓���ł��Ă��f�e���g�q�j 40�^�͓���o���܂���B
�܂������̏�� RK50 �^�J���o���P�[�X�ɓ��������̂� 3���ȏ�o���Ĕ����̂ɂ��S�O���܂��B �����Ŕ�r�I�������̂ŁA�A���v�X�̂j�t�F�[�_�[�Ƃ������̂�����܂��B
����̓X�g���[�N���P�O�O�o�������ώg���₷�����̂ł��B �Q�{���ׂ邱�Ƃɂ��o�����X�����I�Ȏg�������o����{�����[���ƂȂ�܂��B
�P�A�̉�]�{�����[���ł́A���ׂĂ��Q�ꏏ�ɉ܂��A�X���C�h�^�C�v�ł͉\�ł��B �@�B�I�ȃo�����X�@�\���\�Ƒ��܂��Ă������āA�o�����X�{�����[���r���܂��Ɉ�Γł��B ���������̈����R�ƍ\���Ɉ��萫������܂��B�d���[�œ���\�Ȃ̂����ꂵ���ł��B
�j�t�F�[�_�[�����B��p�r�Ȃ̂ō\�����f���炵���B
�X�g���[�N100�o�ׂ͍������ʒ����ł��܂��B
���N�O�Ɏv�����ď������Ă������A���������H���ʓ|�ŕ��u���Ă����B
�V�i�̕ۊǕi�Ȃ̂őS�����茸���Ă��Ȃ��B������K���ƌĂ�鐠���G�����Ȃ��B
RK501 ������A
4�A�^�C�v�A�p�b�V�u�^�C�v�Ɏg���C�͑S���Ȃ��o�����X�i���t�j�v���A���v����Ɏg�p����\��B
������ʓI��6�~���������̂Ńm�u�ŔY�ޕK�v�͂Ȃ��B ���ꂪ�ō���̃{�����[���ƌ����Ă���B RK501�Ŏ��@���삵�܂������Q�Ƃ��������B
http://www2s.biglobe.ne.jp/~yapsys/hifipri.html
���܂��A����\���̃A�b�e�l�b�^�[�̓�����H�i��R����{���̑������}�����Ă����H�j
http://www2s.biglobe.ne.jp/~yapsys/vrsystem.html
��C���s�[�_���X�^�A�b�e�l�[�^�[ �V���v���C�Y�x�X�g�ȁA�A�b�e�l�[�^�[�B
�ؑւ��Ƀ����[���g���̂œd�����K�v�ł����A�����@�\�͈����܂���B
��C���s�[�_���X�^�A�b�e�l�[�^�[������������Ă݂�B
�I�[�f�B�I�A���v�ɂ͉��ʂ�����Ƃ����@�\���K�v�ł��B
���̋@�\������������@�Ƃ��ẮA��܂��A �E�A���v���̂��̂̑��������ςɂ������
�E�A���v�̑������͈��̂܂܁A���͂���M���̑傫����ς������ �ɕ������܂��B ��ʓI�ɂ͌�҂̂��̂��命�����߂Ă���A�䂪�Ƃ̌����A���v���S�Ă��̉ϓ��͌Œ�Q�C���^�̉��ʒ����@�\�������Ă��܂��B �X�ɁA���̓��͐M���̑傫����ς��邽�߂ɁA��ʂɂ̓{�����[���ƌĂ��ϒ�R����g���̂ł����A��ɂ���ĉ����M�������ɗ���܂��̂ŁA�{�����[���̕i���͉��ɑ傫���e������B�ƌ����Ă��܂��B ���Ȃ݂ɁA�䂪�Ƃ̃o�b�e���[�h���C�u�A���v�̓A���v�X�̃~�j�f�e���g�iRK27�j�{�����[�����g���Ă��܂��B
���[�J�[�������A���v�ł��̗p��̑����A����Β�ԕi�ł��B �X�ɒ������i����I�t�i�A���x���Y���������v���p�A�������̎���i�Ȃǂł́A�Œ�̌������x����i�K�I�ɐؑւ��Ďg���u�A�b�e�l�[�^�[�v���g�p�������̂�����܂��B �ƌ������ƂŁA����͌Œ��R���g�����A�b�e�l�[�^�[������Ă݂����b�ł��B �A�b�e�l�[�^�[�ƌ����܂��Ă����낢�날��܂��āA���͌l�I�ɂ̓g�����X�����~���������肷��̂ł����A�ڃ��ʔ�яo����~�B�\�Z�̓s����A�Œ��R���ł����܂��B �܂��A�����͊O���Ȃ��ƌ����Œ�X�y�b�N�����߂܂��B �E�g�����������\�Ȃ̂悤�ɓ��͒[�q�Əo�͒[�q�����P�̂̃A�b�e�l�[�^�[�ɂ���B
�E���o�̓o�����X20k���A�A���o�����X10k���̒�C���s�[�_���X�^�Ƃ���B�i�^�[�Q�b�g�A���v�̓��̓C���s�[�_���X�ɍ��킹�܂��B�j �E�o�����X�A�A���o�����X���p
�E��������0〜-60dB�ȏ�
�E20�X�e�b�v�ȏ�̐ؑ�
�E���E�A�� ���Ƃ́A�����z�Ƒ��k���Ȃ��獂�i���Ȃ��̂�ڎw���܂��B ����́A���Ɂu���o�̓C���s�[�_���X���̃A�b�e�l�[�^�[�v�Ƃ����̂��������|�C���g�ł��B �P���ɃR�X�g�����ōl������_�[��R��p�b�h�����I�����ɂȂ�܂����A����ł͘A���ς̃~�j�f�e���g���Œ��R�ɒu�������Đؑւ����ɂ��������ŁA�d�C�I�ɂ͂قƂ�Ǖς�肪�Ȃ��̂ŁA�ǂ������Ȃ�B�Ƃ����`�������W�ł�����܂��B �C���s�[�_���X�́A�A���v�̓��̓C���s�[�_���X�ɍ��킹�ăA���o�����X10k��/�o�����X20k���Ƃ����̂́A�A�b�e�l�[�^�[�L���⌸���ʂɊւ�炸�A�\�[�X���猩���p���[�A���v�̓��̓C���s�[�_���X�i���׃C���s�[�_���X�j�����ɂȂ�A�{�����[���g�p���ɔ�������C���s�[�_���X�ϓ��ɔ������F�ω���}������_��������܂��B
�Ȃ��A���̒��ɂ́u�p�b�V�u�v���v�ƌĂ��A�A�N�e�B�u�ȑ����@�\�i�v���A���v�A�o�b�t�@�A���v�j�������Ȃ��A�����Ă��܂��u���͐ؑւ��@�\�t���A�b�e�l�[�^�[�v���A�Ɉꕔ�ŔM���x���Ă���悤�ł��B
������̂͒P�̂̃A�b�e�l�[�^�[�ł�����A�@�\�I�ɂ́u���͐ؑ@�\�̂Ȃ��p�b�V�u�v���v�Ȗ�ł����A
��R���g�����P�̃A�b�e�l�[�^�[�i�p�b�V�u�v���j�ɂ́A�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ�ł��Ȃ����_������ �ɂ��ւ�炸�A�p�b�V�u�v����M�����X�̑����͂��̂��Ƃ����܂�C�ɂ��ĂȂ��l�Ɍ����邽�߁u�p�b�V�u�v���v�͏��X�~�X���[�h��U�������Ȍ��t�Ɗ������̂ŁA�������u�A�b�e�l�[�^�[�v�ƌĂԂ��Ƃɂ��܂��B ���̌��_�Ƃ͏o�̓C���s�[�_���X���������ƂɋN�����Ă���A �E�m�C�Y���E���₷���B
�E�o�͑��P�[�u���̕��V�e�ʁi���Ԃ̐Ód�e�ʁj�ɂ���āA����̎��g�������ɕω���������B
�Ƃ������̂ł��B
��̓I�ɁA���̃o�����X�ڑ��A���v���ɍ��挸�����v�Z���Ă݂܂��傤�B
�����Ƃ��āA
�E�A�b�e�l�[�^�[��HOT-COLD�ԏo�̓C���s�[�_���X20k��
�E�A���v��HOT-COLD�ԓ��̓C���s�[�_���X20k�� �E�@������z����R�l�N�^�̍��v���V�e�ʂ�50pF �E�ڑ��P�[�u���̕��V�e�ʂ�150pF/m
�Ƃ��܂��B
���v���V�e�ʂ�20kHz�̌����ʂ��Z�b�g�ŕ\���ƁA
�E150pF�i�P�[�u��60�p�j��20kHz�̌����ʂ͖�0.15dB
�E200pF�i�P�[�u��1m�j��20kHz�̌����ʂ͖�0.25dB
�E350pF�i�P�[�u��2m�j��20kHz�̌����ʂ͖�0.8dB
�E800pF�i�P�[�u��5m�j��20kHz�̌����ʂ͖�3dB �ɂȂ�܂��B �����傫���Ƃ݂邩�A�������Ƃ݂邩�́A��H�Ɛl���ꂼ��̃|���V�[�����낤���Ǝv���܂����A���I�ɂ͂����͐L���Ă� 1m �ɗ}�������Ƃ���ł��B ���Ȃ݂ɁA �o�̓C���s�[�_���X600���̂�����ʓI�ȃv���A���v�̏ꍇ�A
200pF�i�P�[�u��1m�j��20kHz�̌�����0.001dB�B 20kHz��3dB����������ɂ́A100m�ȏ�P�[�u������������܂킷�K�v������܂��B �O���t�ł��������r����Ƃ���Ȋ����ł��B
���̕��̋Ȑ����o��20k���A��̕���1200���i���͋���20k���j�̓����ł��B �P�[�u���������Ȃ�قǍ���������������邱�Ƃ�A�����P�[�u���ł��o�̓C���s�[�_���X���ς��Ƒ傫���������ς�邱�Ƃ��������肢��������Ǝv���܂��B ���̎�����A���g�������̗�P�[�u�����L���Ȃ����_��������ׂ��A�u���o��600���̃p�b�V�u�v���v������Ă��������������Ⴂ�܂����A�}�C�N�p�Ȃ炢���m�炸�A���C�����x���̓��̓C���s�[�_���X�� 20k���ȏ�Ƃ����̂���ƂȂ��Ă���̂�600���Ŏ邱�ƂɂȂ�A�\�[�X���@��ɂƂ��Ă͑����d�����ׂƂȂ�܂��B �܂��A�\�[�X���o�͂ɃJ�b�v�����O�R���f���T�[���g���Ă���ꍇ�A���̃��x���ቺ�������N�����܂��B �����I��600���� OK�ȃ\�[�X�i�قڃv���p�j���q���ꍇ�������o�b�t�@�A���v���K�v�ŁA������p�b�V�u�f�q�����ō\������̂͏��X����������܂��B �]�k�ł����A�����悤�ȒP�̃A�b�e�l�[�^�[�i�p�b�V�u�v���j�ł��A���ʒ����@�\���g�����X���̏ꍇ�́A �\�[�X�����猩���Ƃ��̕��׃C���s�[�_���X�����ב��A���v�̓��̓C���s�[�_���X�ȏ�ɕۂ���A�t�ɃA���v�����猩���\�[�X���C���s�[�_���X�͐ڑ�����\�[�X�̏o�̓C���s�[�_���X�ȉ��ɂȂ�A�����Ē�x�����قǂ��̌X���������ɏo��̂ŁA�����P�[�u�������p�\�Ƃ����t�̓����������Ă��܂��B �����B�B�����~�����Ȃ��B�B�i�j ���āA�b��߂��ĉ�H�̌����ł��B �o�����X�A�A���o�����X���Ή��̒�C���s�[�_���X�^�A�b�e�l�[�^�[�ƂȂ�ƁA��H�̌`���͕��tO�^�����tH�^�����t�u���b�W H�^������܂����A�u���b�W�^�C�v�͎�ɉϒ�R���g���ꍇ�̉�H�Ȃ̂ŁA�Œ��R���g���ꍇ�̑I�����͕��t O�^�����t H�^�ɂȂ�܂��B �����̐��E�ł͍����g�i�d�g�̎��g���j�̈�ł̃C���s�[�_���X�������ǂ� O�^���嗬�ł����A�������o�̓C���s�[�_���X�Ɠ��������ʂȂ�ʉ߂����R�̒�R�l���傫���Ȃ�Ƃ����̂�����������܂��B �Ƃ������ƂŁA����͕��tH�^������Ƃ������Ǝv���܂��B �����Đؑ֕������ǂ����邩�B ���ʂɍl����A���i����H��23�ړ_���[�^���[�X�C�b�`���g���܂��B ���̏ꍇ�AH�^�ł�O�^�ł��A1ch ������ 4��H���K�v�ł����A����ō��E�A���i�����j����������ɂ́A8�i8��H23�ړ_�Ƃ����������̂悤�ȃX�C�b�`���K�v�ł��B �����łȂ��Ƃ����������i���[�^���[�X�C�b�`�B
8�i�̕��Ȃ�ē�����������܂��A��̂�����ɂȂ�̂��z�������܂���B�B
����Ȃ�ƁA1�i1��H�X�C�b�`�Ń����[���쓮���Đؑւ���Ƃ������@���g���Ă�������������������܂����B ���ꂾ�ƃX�C�b�`�̔�p��}���邱�Ƃ��o���܂����A��ʓI��2��H6�ړ_�����[���g�����ꍇ1ch1�X�e�b�v������2�K�v�ł��̂ŁA2ch23�X�e�b�v����92�K�v�ƂȂ�A�p���Ĕ�p���|���肩�˂܂��A�������ꏊ��H���܂��B �܂��A��R��23�X�e�b�v���̃A�b�e�l�[�^�[��H�����̂����ł����\�ȏo��ƂȂ�܂��B
�Ƃ������ƂŁA��������H�v�̐��E�B �����X�e�b�v�͏������i�o����ŏ�1dB���݁j�A�������͑傫���A��H�̐��͏��Ȃ��������B ���������ꍇ�A�����������X�e�b�v�̃A�b�e�l�[�^�[�Ƒ傫�Ȍ����X�e�b�v�̃A�b�e�l�[�^�[��g�ݍ��킹��A���Ȃ���H�ŕK�v�Ȍ����ʂ̃Z�b�g��g�ނ��Ƃ��o���܂��B
�������A����g����H�͓��o�̓C���s�[�_���X���Ȃ̂ŁA���i�d�˂Ă��C���s�[�_���X�������������ω����܂���B
�����ł͂悭�g����ł��B ���āA�����Ŗ��ł��B 1dB ���݂� 0�`-60dB�̌����ʂ���ԏ��Ȃ���H���ō\������ɂ͂ǂ�����悢�ł��傤���H ���W�b�N��H�����������l�Ȃ�s���Ƃ��邩������܂���ˁB
�����́B�B -1dB, -2dB, -4dB, -8dB, -16dB, -32dB ��6��H��ɂȂ��A���ꂼ��X���[(0dB)�Ɛؑ֏o����悤�ɂ��邱�ƂŎ����o���܂��B
���킹�Ă�����i�A-���i�J�b�g�I�t�j��������A0�`-63dB�i1dB�X�e�b�v�j�{�S�~���[�g�̃X�e�b�v�A�b�e�l�[�^�[���\���ł��܂��B
23�X�e�b�v��S����ւ����ɂ�����A�����[����R��7���ȏ�팸�ł��A���ׂ������݂Ő��䂪�\�ł��B 23�ӏ��̃X�C�b�`�ړ_����6bit�o�C�i���ɕϊ�����f�R�[�_�[���v��܂����A100�{������̃_�C�I�[�h������ΊȒP�ɍ\���ł��܂��B �������A�X�C�b�`�̂ǂ̈ʒu����dB�ɂ���̂��͂��̃f�R�[�_�[�Ō��߂�̂ŁA�����ʂ�ς���̂ɃA�b�e�l�[�^�[���̂���蒼���K�v������܂���B�܂��A�����ʂ��o�C�i���ŕ\���o����Ƃ������Ƃ́A������d�q����ɂ����p�\�ł��B �ŁA������̂�����ȃA�b�e�l�[�^�[�{�b�N�X�B
��R��1������A�����[�͏H����100�~�A���[�^���[�X�C�b�`��2�i2��H23�ړ_�̌����i�ł��B
�X�C�b�`1�i��d���ƃ~���[�g�����Ɏg���A����1�i��-62dB�`0dB��22�X�e�b�v�Őؑւ��܂��B �V�[���h���ւ���������Ȃ��o���b�N�g�݂Ȃ��Ƃƃo�����X20k���Ƃ����C���s�[�_���X����A�Ă̒�m�C�Y���E���₷���A�����M���Ɠd���͒��ڊW�Ȃ��ɂ�������炸�A����m�F��AC�A�_�v�^�[���g������c�O�Ȃ��ƂɂȂ��Ă��܂��܂����B ��ɂ���ăo�b�e���[���d�ŃX�b�L�������B�i�j
�c�}�~���i�肫���OFF�ɂȂ�̂����C�ɕ֗��ł��B ������_������܂��B ��̕��ɂ��������ʂ�A�o�̓C���s�[�_���X�������̂ŁA�O���m�C�Y���E���₷���A�P�[�u���̕��V�e�ʂɂ���Ď��g���������ς���Ă��܂�������A�p���[�A���v���߂ł����g���܂���B �܂��A�e�i�A�b�e�l�[�^�[�ƃX���[�������[�Őؑւ��Ă���A�ؑփ^�C�~���O��OFF(�ǂ��ɂ��q�����Ă��Ȃ�)��Ԃ����݂��鎖����A�ؑւ�莞�Ƀv�`���Ƃ����m�C�Y�����₷���ł��B �X�ɁA����g����23�ړ_�X�C�b�`�̊��G���C�}�C�`�Ȏ��ƁA���Ń����[���K�`���K�`�������̂ƂŁA����t�B�[�����O���G�ŁA�����ɂ������ۂ��B
�܂��A���蕨�ɂ͂Ȃ肻���ɂ���܂���B�i��j �T�E���h�́i�Œ��R�炵���H�j�\���b�h�Ȋ����ł��B
�~�j�f�e���g�������ڂ₯�Ċ�����قǁA�X�b�L�����Ă��āA�����ƌ��ʂ����ǂ��ł��B
��J�����b�オ������̂ŁA����A�䂪�Ƃł͈�Ԃ��������̃T�E���h����Ă��܂��B������DAC�Ŏg���Ă��܂������A���̓t�H�m�C�R���C�U�[�Ɏg���Ă��܂��B
http://ezto.info/ezhome/blog/entori/2015/5/15_dinginpidansu_xingattenetawoo_anku_zuottemiru.html �f�W�^���n�Ƀv���A���v�͕K�v�H�@�A�b�e�l�[�^�[�H�@�t�F�[�_�[�H�@�}�b�`���O�g�����X�͂����� ����CD�łTV���̏o�͂�������悤�ɂȂ��āA���{���g�Ń}�L�V�}���̃p���[�A���v�Ƀv���A���v�͕K�v�Ȃ̂��H����X�I�ɋc�_���ꂽ�B ���ǁA�D�݂ŏI������悤�ɋL�����Ă���B �����ŁA�}�����c��}�b�L���̃��B���e�[�W�^��ǃv���A���v�ƁA����g�����W�X�^�[�p���[�A���v�̑����̈����B
�v���A���v�Ȃ��ACD��@�A�b�e�l�[�^�[�@�p���[�A���v�ł͉��������ĕ�������A�ቹ�������Ȃ�Ȃǂ̃N���[�����N�����B
����ّ͐�ł��o�����Ă���B ����I�[�f�B�I��y�����Ԃ̒��N�̎�������͂����͂���Ӗ��^���̂悤�B �Ȃ�v���A���v���K�v���Ƃ����Ƃ����ł͂Ȃ��B �t�H�m�͂Ƃ��������C���͂��̕��@�ʼn������邱�Ƃ��������ꂽ�B
�Ȃ��A���� CD�ƃA���v�̊ԂɃ��C���g�����X�����邱�Ƃ����s�������Ƃ�����B
�Ƃ��Ƃ����� CD�̉����a�炢�ŕ����₷���Ȃ�etc
������A�b�e�l�[�^�[�ƃp���[�A���v�̊Ԃɓ����̂���l�����A�C���s�[�_���X�}�b�`���O�̈����͉����ł��Ȃ��B �Ȃ��Ȃ�
�ꎟ�U�O�O���F�U�O�O�� �̂P�F�P�g�����X�����炾�B �v���A���v�̌��\�́A�n�C�̃��[���肾���ƌ�����悤�ɁA�n�C�C���s�[�_���X�̏㗬����̋@��̐M�����āA���[�C���s�[�_���X�ő���o���A�C���s�[�_���X�����@�Ƃ��Ẵ����b�g�Ƃ����B ������g�����X�ɂ�����ɂ́A���\k���̏o�̓C���s�[�_���X������ CD�v���[���[�@DAC��̃��C���A�E�g���A �}�b�`���O�g�����X�i���C���g�����X�@���C���A�E�g�g�����X�j
�ꎟ�@�������`���\����
�Ŏā@
�@600���O��
�ő���o���A�n�C�@���[���肾�������������B 600������o���͋Ɩ��p�̏o�̓C���s�[�_���X�̖��ł���ˁB
�ّ�� Western Electric�� WE49�A���v�̃��C���A�E�g�g�����X��
WE127C�g�����X�� �ꎟ�Q�R�����F�T�O�O��
�������������̂�����
���͒P���ł��B
����UTC��LS-55�g�����X�́A�Z���^�[�^�b�v�������āA�ꎟ�R�D�T����������WE300B�v�b�V���v���A���v��̏o�̓g�����X�Ɏg����B ���̎���̏o�̓g�����X�͋Ɩ��p�g�p���ӎ����āA�ɂ͕��ʂ̃X�s�[�J�[�p�̂S���@�W���@�P�U���̂ق��ɂT�O�O�����o�Ă���B ���̌�ɋƖ��p�@�킪�ڑ������p�^�[�����ӎ�����Ă���g�����X�̂T�O�O����������p�����B UTC�g�����X�̃^�b�v�ɒ�R�������Ă���̂́A����ɒ����Ȃ��炱�̒l�ŃC���s�[�_���X���������ĉ������œK���������̂��B
���̒�R�̃N�I���e�B�[�����̋@��̉��������E����̂ō��i���Ȃ��̂�p�������B �����ł͍��͂Ȃ��A�����JIRC�Ђ̃J�[�{����R��p���Ă���B ��r�������ł��B Western Electric �� WE127C ��UTC�ɔ�ׂ�Αш�͋������̂́A��������������Ȃ����Ƃ������Ȃ����y���������Ă��炽�߂Ă��̗ǂ���F�������B
���� UTC�͌���g�����X������ 20Hz�`2���gz �܂ł͕ۏ���Ă���Ƃ���A������ł����C�h�����W�����ו\�����悭����I���B
�ǂ��炪��Ƃ������Ƃ��Ȃ��A��������g�����X�Ȃ�̉����͊m�ۂ���Ă���B �D�݂Ȃ�ŁA�p���[�A���v�ȉ��̑����@�\�[�X�Ƃ̑����@���̓��̋C���Ŏg�������Ă������Ǝv���Ă���B ���{���̃g�����X�ɂ͂��܂�n�C�@���[���肾���̃��C���A�E�g�g�����X�͏��Ȃ��������炩�A���̕��@���G����Ō����������Ƃ͒m�����Ȃ��B ����v���[���[�ƁA�p���[�A���v�͂��̕��@�Ń}�b�`���O���邱�Ƃ����L������������K���ł��B
�R�����g
mixi���[�U�[2013�N11��27�� 08:27
���͎ʐ^�����ċC�Â��ꂽ�������Ȃ��Ȃ��Ǝv���܂����A����Ƀm�E�n�E������܂��B
�Q�A�̃X�e���I�{�����[�����p�����āA���m�����{�����[���Ŏg����@�ł��B
��������Ԃ̎�������҂ݏo���ꂽ���������@�ŁA�����_�[�o��������� VOL��荂�����ł��B����VOL�̐�����Ђ������Ă��܂��܂����B
mixi���[�U�[2013�N11��27�� 12:21
���c����̓p�b�V�u�v���͉���������ƌ����p�b�V�u�v���ے�h�ł����A���c����̌�����������ԈႢ�Ȃ����낤�ƁA���c���c�b���C���A���v�̏o�����������܂����B
�����ă_���������ƁA�����p�b�V�u�v���ɖ߂��܂����B
���C���P�[�u���̃h���C�u�͂������ƌ����܂����A�����f�q��ʂ��Ɖ��̑@�ׂ��������Ȃ�B
�܂��A���u�Ɋ��܂����A�l���ꂼ��ł��B
�p�b�V�u�v���͒�悪������ƌ����܂����A���ꂪ�{���̐M�������m��Ȃ��B
������͖̂c��܂������ɒ����ł��܂����A�@�ׂ�����������߂����@�������B
mixi���[�U�[2013�N11��27�� 12:22
�����ł̓v���A���v���g���ƁA����Ƃ͈Ⴄ fat �ȕt�щ��݂����ɂȂ�܂��B
�]�v�ȑ����i���������ɁA�{�����[���ł��̕��̃Q�C�����i��Ƃ����i���Z���X������I�T���o�ł��܂��B
mixi���[�U�[2013�N11��27�� 12:48
���̓Z�C�f�����[�^���[�r�v�ɍ��͎�ɓ���Ȃ���R�킪��R�����t�����^�C�v�����̃p�b�V�u�v���ł����A�g�����X+�u�q�� �ɂ͂��Ȃ�Ȃ��ł��B
���g�����X�^�b�v��ւ����̂k�t�w�̐��i����Ă��āA�߁X��r���Ă݂܂��B
mixi���[�U�[2013�N11��27�� 12:56
LUX �̂Ȃ�t�B�[�X�g���b�N�X����̂Ƃ���̃t�@�C�����b�g���ǂ������ł����A
�g�����X�� ATT�ł� impedance �̐������͍���ł��B
��x���ƒ�ŏ㗬�Ƃ� impedance �}�b�`���O����ꂽ�����Ă��������������̂ł��B
mixi���[�U�[2013�N11��27�� 23:14
�ق��Ƀ��t�I�N�� STC4212 ��̃A���v�������Ƃ�����n�b�g�I�[�f�B�I���{������t�@�C�����b�g�R�A�̂��̂��o����Ă��܂��ˁB�@
�g�����X���@�悢�]���͕����܂��A�ǎ����|�肢�܂��B
mixi���[�U�[2013�N11��27�� 23:52
���݂܂���A�����Ă��������B
�A�b�e�l�[�^�̓g�����X��1�����ł����H
�܂��A�A�b�e�l�[�^�̃C���s�[�_���X�͂ǂ̂��炢���ǂ��̂ł��傤���B
mixi���[�U�[2013�N11��27�� 23:56
��������o���ɉϒ�R���ł����A�A�b�e�l�[�^�[�̓��j���Ŋ���������Ă݂Ă��������B������ɓ���܂����B
�g�����X�� ��K�����琔�\�����A�ɂR�O�O���`�U�O�O�����炢���o�Ă���Ό�͖{���̂Ƃ���A�Œ��R�Œ����ł��܂��B
mixi���[�U�[2013�N11��28�� 00:25
�A�b�e�l�[�^�͒�C���s�[�_���X�^���ǂ��̂ł��傤���H
mixi���[�U�[2013�N11��28�� 00:27
�������B���ʂ̓���VOL�^�ő���܂��B
�P�OK����2�A�ɂ��ĂT�����ł��B�@
�����T�O����2�A���p�������łQ�T������肱���炪�悩�����ł��B
mixi���[�U�[2013�N11��28�� 06:36
��������12�����炢����p���ʂƂȂ�Ǝg���₷�����A�����ǂ��悤�Ɏv���܂��B
http://open.mixi.jp/user/8290003/diary/1916790097
14 �F�����������������ς��B�F2012/12/30(��) 16:52:01.54 ID:C+faVvPO �v���ȂR���̃p�b�V�u�ŏ[��
�p���[������ȂɈ���
���� �� ������ �ɒ��͂��ׂ�
15 �F�����������������ς��B�F2012/12/30(��) 18:00:10.08 ID:HyxhwMiM
�p�b�V�u�v���́A�����������A���v�X�̍����� ATT�Ƃ��A�Œ��R��ւ����̓z���A���͂��ꂢ�����A��͂艹���������
�v���A���v���g���Ɖ��������Ȃ��L���ȉ����łĂ��Ĉ��S����
64 �F�����������������ς��B�F2013/01/15(��) 08:28:57.11 ID:1Mv41vsQ
�������ł͖����t�щ��������N���A�T�E���h�ɋ߂Â������ł��B
65 �F�����������������ς��B�F2013/01/15(��) 13:07:07.73 ID:GhKte38k
�o�̓C���s�[�_���X�������Ȃ邩�獂��͌������邵
�p���[�A���v���̕��ׂ�������̂ɁH
143 �F�����������������ς��B�F2013/03/15(��) 12:46:25.45 ID:pTMip3zl
�p�b�V�u�̓v���@�p���[�Ԃ��o���邾���Z�����Ȃ��Ɨ��_�I�ɂ��������Ȃ�B
�i�A���v���_�̊�b�̊�b�@�C���s�[�_���X�̖��j
436 �F�����������������ς��B�F2014/05/26(��) 23:38:23.96 ID:p+xEZDtp
�X�s�[�J�[�̔\���������ƃv���A���v�̃{�����[�����i��鐡�O�Ŏg��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�����Ȃ�ƁA�v���A���v�ɃQ�C��(����)�͕K�v�Ȃ��B
�p�b�V�u�v�����Ƒ������Ȃ��̂�0dB(1�{)�ƂȂ邪�A�o�̓C���s�[�_���X��Ⴍ�ł��Ȃ��̂Ńp���[�A���v�Ƃ̐ڑ��Ŗ�肪������B
439 �F1�F2014/05/27(��) 11:10:29.66 ID:zPt+HCCg
>>436
�p�b�V�u+�o�b�t�@�ɂ���Ȃ�
�ŏ����畁�ʂ̃v���ł悳���������B
144 �F�����������������ς��B�F2013/03/15(��) 12:59:31.01 ID:EdSHSb4b
��������C���s�[�_���X�̖��́A�v�̌Â�Tr�p���[�A���v��n���OP�A���v�̓��͒i�̃p���[�A���v�Ŗ�肪�N����B
�����́A���͒i�̃L���p�V�^���X�̔����ɂ���č���̘c�ݗ��̈���������B
145 �F�����������������ς��B�F2013/03/15(��) 14:14:06.68 ID:FsaSRnla
���������Ă��A�����Ƀp�b�V�u�v���ʼn��������鎖���͂�����
�Œ��R��ւ���ATT�Ƀo�b�t�@�A���v�������悤�ȃv����������ǂ�
422 �F�����������������ς��B�F2014/05/24(�y) 18:41:58.42 ID:APM1ar4T
�v���́A���ʒ����ƃC���s�[�_���X�ϊ��̂��߂ɓ����B
����ɁA�s���A�I�[�f�B�I�ł͐ϋɓI�Ƀv���������F�̕ω��𗘗p����B ���ʒ��������Ȃ�p�b�V�u�v���ŗǂ��B
�Z���N�^�[�ƃ{�����[���ō\������V���v���ʼn��̑N�x���������������C���s�[�_���X�̖�肪����B
�C���s�[�_���X�́A�����ĒႭ�o���������ŁA�ڑ��R�[�h�̗e��(�L���p�V�^���X)�̉e���Ŏ��g���������ω�����B
�܂��A������������ƌ�����ꍇ�������B �v���Ƀg�[���R���g���[���̕K�v��������{�����[���{�o�b�t�@�[�A���v�̍\�����V���v���ʼn����ǂ��B
�ŋ߂́A�����@�ł��I�y�A���v���g���Ă��ăA�}�`���A�ł�����v�����ȒP�ɑg�߂�B
http://jisaku.155cm.com/src/1400956625_82ddd1bf766d38133687b7f090f49cefc6c58405.jpg �Z���N�^�[���{�����[�����o�b�t�@�[�A���v�̍\���ŃV���v���ɍ�����B
�I�[�f�B�I�p�I�y�A���v�������ւ��ĉ��F�̕ω����y���ނ��Ƃ��ł���B
524 �F�����������������ς��B�F2014/12/14(��) 21:29:22.13 ID:GL0wW6zM
�����̌J��Ԃ��ɂȂ邪�A�p�b�V�u���Ⴂ����t���������Ă�
�C���s�[�_���X�ϊ��ł��Ȃ�����Ȃ��B
���j�e�B�Q�C���̌��͂͂�͂�ł����B
525 �F�����������������ς��B�F2014/12/18(��) 18:17:12.56 ID:r1YXykwO
�p�b�V�u�́A������������P�[�u���̐Ód�e�ʂŎ��g���������s����ɂȂ�B
�����ŁA>>524���̌����悤�ɃC���s�[�_���X�ϊ��̌��ʂ͑傫���B
�i�C���s�[�_���X�́A�����ĒႭ�o���B�j �Q�C��(����)�͕K�v�Ȃ��̂ő����x1�{�ň���ȃo�b�t�@�[�A���v���\������B
�i���j�e�B�E�Q�C���E�X�e�[�u���j
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/pav/1356822460/
92 �F�����������������ς��B�F2014/06/22(��) 21:02:11.11 ID:2bDBJ3qP
���͂� digital �����Ȃ�C���ʒ��߂��ł��� DAC �Ńv���s�v�D
�v�����킸�� DAC �ɉD���낻��D-70�ւ������D
93 �F�����������������ς��B�F2014/06/23(��) 19:35:19.58 ID:0Vt26Dvp
��H�����点�Ή����ǂ��Ȃ�(�Ǝ�����������)�Ǝv���Ă邤���͉����������ĂȂ���
137 �F�����������������ς��B�F2014/08/12(��) 02:48:50.32 ID:TJkWH0HS
���ɂ�����ˁH
���͂قڑf�l�����A�v���Ȃ��̒����͉������ꂢ�������݂������Ǝv��
�v�������ƃt�B���^�[�������悤�ȉ��ɂȂ邪�ʔ��݂͏o��
�h�g�Ǝϕt���݂����Ȃ����
18 �F�����������������ς��B�F2013/10/26(�y) 19:10:04.63 ID:0aovYKIy
���̓v�������h�B
�{�����[���t����DA/C�A���e���[�v�E�]�f�B�A�b�N�S�[���h���g���Ă邪�A�i�O���̃v����ʂ��ăp���[�ɓ���Ă��B
�P���ɂ��̕����������Ȃ�ˁB
�𑜓x�͎������C��������ǁA�܂��A�قƂ�lj���Ȃ����x���B
�����ǒ��̐L�тƂ��L��̔������̓v��������Ɩ����Ƃ���i�Ⴂ�B
�v����ɁA���y�������܂銴���B
�F�Â����Č������Ⴆ����܂ł����A���ꌾ���o���ƃz�[���̉��ƃI�[�f�B�I�̉��͑S���Ⴄ���ȁB
�v���͌����Đ��@�ł͂Ȃ��A�I�[�f�B�I�Ƃ��Ă��������o������B
���ꂪ�v���̉��l�Ȃ�Ȃ����ȁB
101 �F�����������������ς��B�F2014/07/15(��) 18:03:29.87 ID:AkdS9SDp
�v������Ȃ��Ƃ܂�ɂȂ�
DAC�̌��-12dB�̃A�b�e�l�[�^�����ƃv������DAC�{�����[���ł������o���鉹�ɂȂ邩�玎���Ă� 20 �F�����������������ς��B�F2013/10/27(��) 11:26:35.89 ID:vR+kkjxq ��F�߂���ʼn��̕ω���ǂ��Ƃ����͓��R�����Ă�������B ���̐L�тƂ��ɍ����L��Ȃ� DAC�̑���̃C���s�[�_���X�ƃp���[�A���v�̓��̓C���s�[�_���X�Ƀ~�X�}�b�`���L�邩�ADAC�̃{�����[�����i�O���̕������������낤�ˁB
�i��ƃn�C�����Ƃ����ʌ�������{�����[�����Ă����ς��L�邩��B
22 �F�����������������ς��B�F2013/10/27(��) 18:26:08.19 ID:wusfLoz3
���ە����Ċ������鉹�ɂȂ��Ă��Ă��u�v�Ȃ낤����
���������A�����̃I�[�f�B�I�̍����@�͗l�X�ȉ�H����g���� �������ɂȂ�悤�Ɂu�����v���Ă���
��������������Ƃ����l�́A�I�[�f�B�I�ɉ������߂Ă���̂�
�ǂ�ȉ��Ɋ�������l�Ȃ̂������Ă݂�����
23 �F�����������������ς��B�F2013/10/27(��) 20:23:39.97 ID:iXNkJYT0
�ǂ�ȉ��Ɋ������Č���ꂽ��
�\�[�X�ɓ����Ă�C�z�̂悤�ȕ��܂ŃX�|�C�����鎖�����A�C�����̈������炢�̃��A�����������čĐ����ꂽ���ɐG�ꂽ���ł��傤�ˁB
���t�ҁA�A�[�e�B�X�g�̑��݁A�C���܂ł�������ꂽ���ł��傤�ˁB
�l�̐��Ȃ���̒��̑��̉��Ƃ����̓r���u�Ԃ̐��т̐k���܂Œ����������ł��傤�ˁB
��肢�̎���Ă����̂͐��̎~�ߕ�����肢�B ���������o������Ƃ������Ă邤���͉�S�̂��V�тł��B
�������̓\�[�X�ɓ����Ă��ł��B
���ꂪ�ǂꂾ���Č��o���邩���I�[�f�B�I�̉��l�B
26 �F�����������������ς��B�F2013/10/28(��) 19:31:29.95 ID:ULDNt83s
>>23
���̌o�������ƁA
�����܂Ń��A���ȉ������߂Ȃ�A�S��ׂ��͋@�ނł͂Ȃ��������낤�ˁB
���Ƃ��ƁA���^���Ă͔̂����̋�Ԃōs���邩��^�����̂������ȉ��Ȃ�B
����ʂ̃��r���O�ōĐ����ē����҂��o��������B
�����A�o�����Ƃ������́A�����Đ������̂ł͂Ȃ��@�킪�u������ۂ��v����������Ƃ������B
27 �F�����������������ς��B�F2013/10/28(��) 19:41:13.92 ID:ULDNt83s
���̓N���h�Ȃ̂ŁA�T���g���[�z�[���ƐV���͂�������イ�s���B
�ŁA���̂Ƃ���A�𑜓x���Ƃ�S/N�Ȃ�Č������Ⴀ�蓾�Ȃ��B
�ǂ̐Ȃŕ����Ă����͑S���������Ⴞ���A�g�D�b�e�B�Ȃ�Ă����A�����̉��̔×��ɂȂ�B
����������ĂȂ��l�قǁA�������ǂ��Ȃ��ˁ`�Ƃ��A�����Đ��Ƃ����ɂ���X��������B �����ˁA�ق�ƂɃ��A���ɂ������Ȃ�@��̐��\�͂���ȏア��Ȃ��̂�B
�ނ��댻��@�͂ǂ���I�[�o�[�X�y�b�N�ŁA���ꂽ���B �����牴�͂���������āA�R���T�[�g�͕��͋C�Ɖ��̔g��̂Ŋy���ށB
�I�[�f�B�I�̓I�[�f�B�I�̉������Ŋy���ށB
28 �F�����������������ς��B�F2013/10/28(��) 19:51:13.07 ID:ULDNt83s
�z�[�����ƁA��ɔ����m�C�Y���Ă̂������B
����`������L���L����������A�z�[����Ȃ̈ʒu�őS���Ⴄ�B
�ׂ̐ȂɈړ����������Ō��y�킪�ٗl�Ɋ��ɕ���������ˁB
�ł����ꂪ���ʂŁA���ꂪ�����B
�s�̂���Ă鉹���́A�S�������ҏW�Ŏ��������Ă�B
54 �F�����������������ς��B�F2014/05/16(��) 22:52:14.06 ID:L2D0s/2V
�v�����K�v�Ȃ����ċ���������Ȃ��čK���Ȏ����������ł���
���̓v���Ō��܂�A�p���A���v�͒����͑N�x�͍������������ �������肵�����@���ȉ��ł���
���̉���L����A�g���݁A���y�����͓����ɂ����ł���
88 �F�����������������ς��B�F2014/06/22(��) 15:29:46.71 ID:8jMy4r89
LP����CD�ւ̈ڍs���A���͐ؑփX�C�b�`�ƃ{�����[�������̃p�b�V�u�^�C�v���J��̒|�̎q�̂悤�ɑ������܂ꂽ�B
���ǐ��N�őS�ď������B
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/pav/1379603306/
3 �F�����������������ς��B�F2012/12/30(��) 08:44:21.74 ID:EqSaj9ER
���܂܂Ńp���[�A���v�̕]�������Ă������ł��������̓v���A���v�̉����Ă��������ł����Ƃ����̌������܂����B
�v���ŗ������̓p���[�A���v�ƃX�s�[�J�[���ǂ�Ȃ� ������Ă����܂���B
7 �F�����������������ς��B�F2012/12/30(��) 14:01:45.40 ID:
�����A�u���A���v�̃V�X�e���x�z�͂́A���Ȃ荂���Ɗ����Ă��܂��B
���̋@��������ւ����A�v������ւ��������ŃV�X�e���̕\�����鐢�E���ς���Ă��܂����ł��ˁB
16 �F�����������������ς��B�F2012/12/30(��) 18:44:18.95 ID:PKSnLDaw
�̂���k�m�o-�Q�� marantz 7 �݂����Ȗ��i���g���̂��A���̎�̉����� ���������Ƒz���܂��B
������COHERENCE�𒆐S�ɁA�p���[�ɐƋ����g�������Ă��邩�ł��B
No32�̕�������ł��傤�����ɂ��ǂ��v���͂���̂ł��傤�B����ɂ��Ă��ǂ��v����SP�𒆐S�ɐ����āA���߂�\���̃j���A���X���A���̊��̌q���ւ��œW�J���Ă����̂��ǂ����낤�A�Ƃ����̂����̎����̌��_�ł��B
539 �F�����������������ς��B�F2015/01/13(��) 13:23:37.91 ID:KAyV0g5P
�v����ς���Ɖ��͌��ς����B
�P�[�u�����C���V����薾�m�ɕω�������B
���̓v�����O���[�h�A�b�v���đ吳�����Ǝv�����B
514 �F�����������������ς��B�F2014/09/07(��) 21:06:00.02 ID:DMka7Op+
50�����x�̃v���͉�������Ȃ������݂�
��͂�100���ʂ��炾��
���Y
QUALIA INDIGO Line Amplifier 510���~
http://qualia-highend.com/jp/index.php/products/line-amplifier/
TAD-C600 300���~
http://tad-labs.com/jp/consumer/c600/ TECHNICAL BRAIN TBC-Zero/EX 298���~
http://www.technicalbrain.co.jp/products_tbc_zero_ex.html �G�\�e���b�N Grandioso C1 250���~
http://www.esoteric.jp/products/esoteric/c1/ �A�L���t�F�[�Y C-3800 170���~
https://www.accuphase.co.jp/model/c-3800.html ���b�N�X�}�� C-900u 110���~
http://www.luxman.co.jp/product/c-900u
�C�O��
FM Acoustics FM 268C
http://www.fmacoustics.com/products/line-stages/fm-268c/
Constellation Audio ALTAIR II plus 980���~
http://www.stella-inc.com/001constellation/page/AltairIIplus.html GOLDMUND Mimesis 22 History 970���~
http://www.goldmund.com/jp/products/mimesis_22h VIOLA SPIRITO II 890���~
http://www.zephyrn.com/products/viola/01_spirito2.html TIDAL Presencio
http://www.tidal-audio.de/english/startprodukteverstaerker1.htm Burmester 808 MK5 500���~
http://www.noahcorporation.com/burmester/pre808.html PASS Xs-Preamp 480���~
http://www.electori.co.jp/PASS/Xspreamp.pdf CH Precision L1
http://www.theabsolutesound.com/articles/ch-precision-releases-l1-dual-monaural-line-preamplifier/ soulution 725
http://www.soulution-audio.com/en/serie7/725/index.php OCTAVE Audio Jubilee Preamp 400���~
http://www.fuhlen.jp/octave/products/jubileepreamp.html Ayre KX-R Twenty 390���~
http://www.axiss.co.jp/brand/ayre/ayre-reference/kx-r-twenty/ darTZeel NHB-18NS 380���~
http://naspecaudio.com/dartzeel/nhb-18-ns/ Mark Levinson No.52 330���~
http://marklev.harman-japan.co.jp/product.php?id=no52 Jeff Rowland Corus 212���~
http://www.taiyo-international.com/products/jrdg/corus/ mbl 6010 D 210���~
http://www.mbl-japan.com/6010D.htm Spectral Audio DMC-30SS series2 188���~
http://spectralaudio.com/dmc-30ss.htm
572 �F�����������������ς��B�F2015/07/30(��) 03:04:22.29 ID:jfrinoir
�h�C�c���v���A���v TIDAL Presencio
http://www.tidal-audio.de/english/presencio.htm Burmester 808 MK5
http://www.noahcorporation.com/burmester/pre808.html mbl 6010 D
http://www.mbl-japan.com/6010D.htm 577 �F�����������������ς��B�F2015/07/30(��) 20:04:50.30 ID:jfrinoir �X�C�X���v���A���v FM Acoustics FM 268C
http://www.fmacoustics.com/products/line-stages/fm-268c/ Goldmund Mimesis 22 History
http://www.goldmund.com/jp/products/mimesis_22h CH Precision L1
http://www.zephyrn.com/chprecision/page/L1.html soulution 725 preamplifier
http://www.soulution-audio.com/en/serie7/725/index.php darTZeel NHB-18NS
http://naspecaudio.com/dartzeel/nhb-18-ns/
578 �F�����������������ς��B�F2015/08/11(��) 01:26:09.96 ID:CI12d15c
�܂������c�u�����v�Ƃ����疜�~�Ƃ��c���S�ɋ����Ă邾�낗
580 �F�����������������ς��B�F2015/08/23(��) 12:41:47.90 ID:oZo3Vk2p
�t�H�m�C�R���g���R���������{�����[���ƃZ���N�^�[�����̂��w�ǂȂ̂ɉ��̂ɂ���Ȃɔn�������̂��B�������Ƀ��[�J�[���x������Ȃ��ƌ�����̂� ��������20���ǂ܂�̃p�b�V�u�v�����o�ė��Ă�B 17 �F�����������������ς��B�F2012/12/30(��) 19:07:52.12 ID:HyxhwMiM ���g���Ă�v���A���v�̕����́A �E�ϒ�R
�@������嗬�ȕ������������A�n�C�G���h���d�q�{�����[�������Ă����ď��Ȃ��Ȃ��Ă��� �E�Œ��R��ւ���
�@�����[�J�[�E�K���[�W���[�J�[���悭�̗p�A�L�b�g�Ƃ��ł����� �E�d�q�{�����[��
�@�n�C�G���h�v���̑����͓d�q�{�����[���ɂȂ��� �ECDS�Z�����g����ATT
�@�����ꕔ�̃n�C�G���h��K���[�W���[�J�[�Ɏg���Ă�
599 �F�����������������ς��B�F2015/10/28(��) 14:23:20.41 ID:6OFSdJKE
�v�������͋쓮�d���̉e�����傫��
�I���́{�|30V�ȉ��ʼnғ����Ă�v���͎g��Ȃ�
���������Ӗ��ł�OP�A���v�g���Ă���@��͑S�ċp��
���d���ŗ���1����������1�D5�{���x�̃v���ɓ��̓A�e�l�[�^�Ȃ��̃p���[AMP
SP�l�b�g���[�N�̈����{�����[�����P���@�g�����X�����Œ��R�ɒu������
����ʼn����X�s�[�J�ɂւ���Ȃ��@�ڂ̊o�߂�悤�ȉ��ꂪ�o������
526 �F�����������������ς��B�F2014/12/18(��) 19:16:52.88 ID:QobAx8Oh
�S�̓I�Ɉ������܂����n�C�X�s�[�h�ȃv���A���v��������
527 �F�����������������ς��B�F2014/12/18(��) 19:54:05.40 ID:r1YXykwO
>>526
�\�E���m�[�g�̃t�@���_�����^��LA-10(100���~)���ȁB�l�I�ɂ́B
100���~���o���Ȃ��Ă��I�y�A���v�g���Ď��삷��ΐ����~�ŏo����Ǝv���B
�����{�����[����A�b�e�l�[�^�[�ɍŐV�I�y�A���v�g���ΊȒP�ɏo����B
�{�����[��1��1���~�`5���~���炢�ŁA�P�[�X��1���~���炢���������B
���Ȃ݂ɁA��\�I�ȃI�y�A���v�̃X�y�b�N LME49710 High-Performance, High-Fidelity Audio Operational Amplifier
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lme49710.pdf �c�ݗ�0.00003%���g������55MHz���o����Έ������܂����n�C�X�s�[�h�ȃv���A���v�Ȃ�ăA�}�`���A�ŊȒP�ɍ����B
�D�݂Ƃ��ẮA ��H���I�[�f�B�I�p�g���e���I�y�A���v�@�n�o�`�Q�P�R�S�o�`
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-03743/
�����̃I�y�A���v�͍����\�ł���Ȃ��烆�j�e�B�E�Q�C���E�X�e�[�u�������甭�U�����Ɉ��蓮�삪�\�B
�n�C�X�s�[�h�Ȃ�Č��z����B�������b��340m��葬���Ȃ�̂��H
�I�y�A���v�̕����y���Ƀn�C�X�s�[�h������ˁB
528 �F�����������������ς��B�F2014/12/20(�y) 11:56:52.23 ID:XtC8BAgM
�A���v�̎��g�������ɖ\�ꂪ����ƃn�C�X�s�[�h�Ɋ�����B
�g�`�Ō���Ƌ�`�g�̊p���I�[�o�[�V���[�g����у����M���O�ŃM�U�M�U���Ă���B
�{���̃n�C�X�s�[�h�Ƃ́A�Â��ɂ���C�Ȃ������オ��̂Ńn�C�X�s�[�h�ȂǂƊ�����O�ɗ����オ���Ă���B �A�L���t�F�[�Y�̍ō��@��C-3800�� NJM4580DD �� NJM5532DD �Ȃǂ� JRC��1��50�~���x�̃I�y�A���v�ō���Ă���B
�傫�ȃg�����X��ėp�R���f���T�[���R�g���Ē��g���l�܂��Ă���悤�Ɍ����Ă���B
���~��`�̃I�[�f�B�I�}�j�A�͒��g���l�܂��Ă��Ȃ��Ɣ���Ȃ��B �A�}�`���A�́A�Ɍ��܂Ő��\�������o�������g�K���K���Ŕ��蕨�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B
�������A���\�͕��i�_�������Ȃ��������\�B
531 �F�����������������ς��B�F2014/12/21(��) 09:58:23.80 ID:GZwJ9o+o
����Ńv���A���v������ăI�y�A���v������ւ������ւ����Ă݂�Ɣ����ɉ����ω�����B
�͂����S�~�̃I�y�A���v��ւ��邾���Ńv���A���v���ւ��邮�炢�̕ω�������킯�Ŗʔ����B
�}�[�N���r���\����}�b�L���g�b�V�������ăI�y�A���v���g���Ă���ƌ����L���Șb������B �I�y�A���v�ƃI�[�f�B�I�̂͂Ȃ�
http://www.wisetech.co.jp/opampdou/story/04/ �K���[�W���[�J�[�����グ�Ă����S���~�͋����Ȃ����A �����ɂ�鎩���̂��߂̎���v���A���v�́A�ō��ł��ȁB
532 �F�����������������ς��B�F2014/12/21(��) 10:19:08.36 ID:Cp+MgQJ
CD�Œ����Ă��킩��Ǝv�����ǁA�����ȔN��̘^�������ƕK�������V�������̂������ǂ��Ƃ͌���Ȃ��A����ǂ��납�Â����̂ɋ����悤�Ș^���̕�������
���R�I�y�A���v�ǂ��납�g�����W�X�^����g���Ă��Ȃ�
�F�X�����Ă邤���ɁA����Ȃ��Ƃ����R�ɋ^��Ɏv���悤�ɂȂ�
�����ă��B���e�[�W�ɑ���悤�ɂȂ�낤�Ȃ�
533 �F�����������������ς��B�F2014/12/21(��) 11:40:12.49 ID:GZwJ9o+o
���B���e�[�W�̓Ɠ��̉��F�͔ے肵�Ȃ����ǁA���I�����I�y�A���v���g�����X�g���[�g�ȉ������͓I�B �I�y�A���v�A�g�����W�X�^�[���g��Ȃ��Ƃ����Ɛ^��ǂ��낤���ǐ^��ǃA���v�͒ʐM�@�ɂ��g����L�ш�̑f�q�Ȃ�ˁB
�I�y�A���v��g�����W�X�^�[���y���ɍL�ш�Ȃ̂����͐^��ǂȂ�ˁB
�ǂ��ł����^��ǃA���v�́A�g�����X�ɋ����|����̂ō����Ȃ�ˁB
�K���ɉ��F�����o���Č떂�����Ĕ����Ă��邾���ȂȁB 20 �F�����������������ς��B�F2012/12/31(��) 07:54:46.10 ID:oEm+kF8j �^��ǃo�b�t�@�̌Œ��R��ւ����ŋ�
�v���͐^��ǂ��ǂ���
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/pav/1356822460/
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q
|
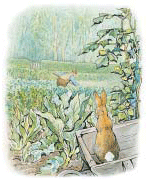
 �X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B
�X�p�����[���̒����猩���o�����߂Ƀ��[���̃^�C�g���ɂ͕K���u���C������ցv�ƋL�q���Ă��������B